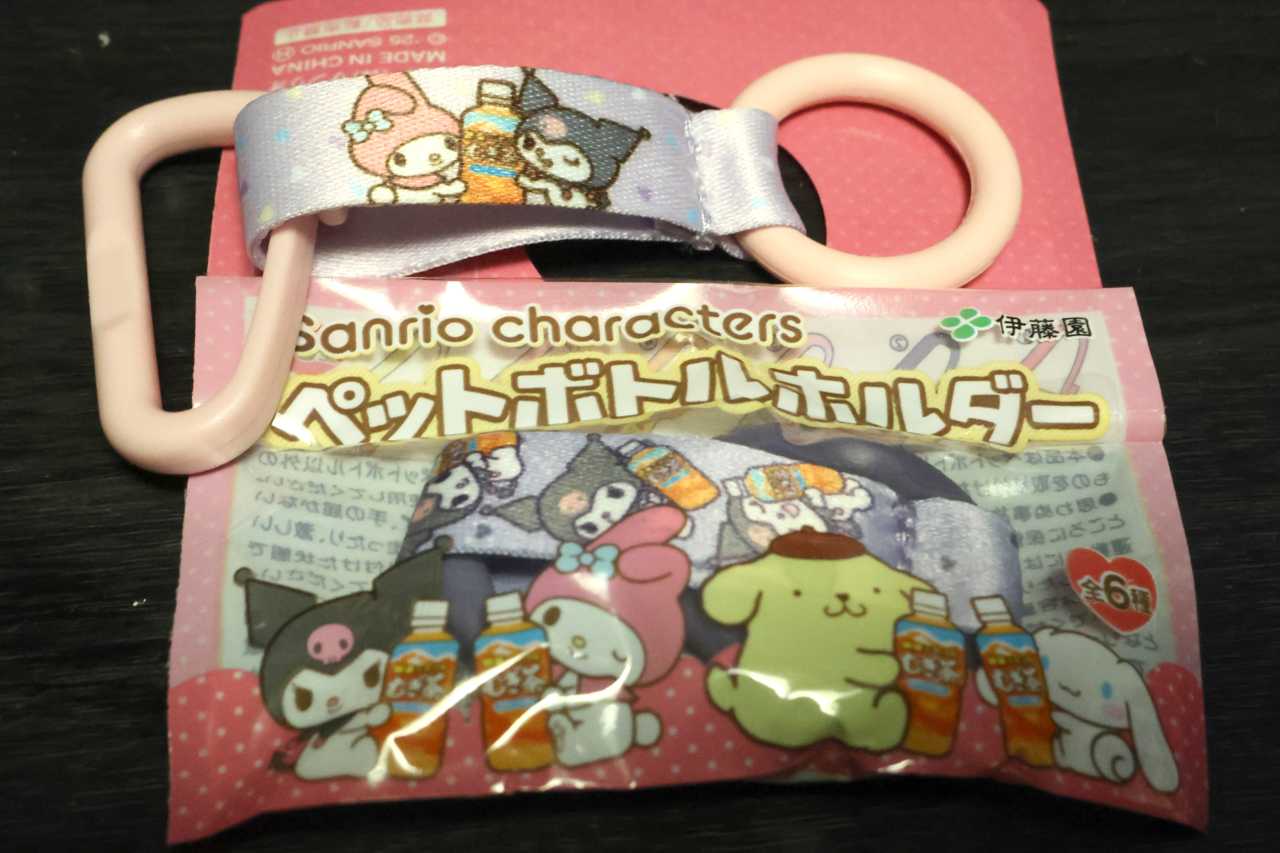2006年08月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

グレンファークラス: 多彩なシェリー樽由来が生む奥深さ/8月31日(木)
グレンファークラス(Glenfarclas=写真左は、オフィシャルの12年物)。日本でもモルトBARならまず、置いていない店はないスコッチモルトだろう。シェリー樽熟成モルトが好きな僕だが、この「グレンファークラス」を飲み始めたのは約6年半ほど前で、比較的最近だ。 その特徴は、シェリー樽由来による赤みがかった琥珀色と上品な甘さ、そしてピートを効かせたスモーキー香。同じシェリー樽熟成のモルトには、マッカラン、グレンドロナック、エドラダワーなど他にも有名な銘柄がある。 しかし、グレンファークラスの味わいは、他のどの銘柄とも微妙に違う。シェリー樽も、オロロソだけしか使わないマッカランとは違い、各種のシェリー樽で巧みに造り分けをしているという。 1836年の創業。ハイランドのスペイサイド地方にある蒸留所(写真右 ( C ) オフィシャルHPから)を興したグラント家は、元々は農家だったという。銘柄の名は、「緑の草原の谷間」を意味するゲール語に由来するとか。 買収に次ぐ買収で、次々と大手製造業者の傘下に再編されていく蒸留所が多いスコットランドで、このグレンファークラスは数少ない独立系業者である。しかも、創業者一族が今なお経営を続ける数少ない蒸留所でも知られる。 スコットランドでは元々人気があった銘柄だった。サッチャー元・英首相が大好きな銘柄としても有名だった。そして80年代以降、英国外へ数多く輸出されるようになってからは、欧米各国やアジア、とくに日本でもモルト愛好家に好んで飲まれるようになった。 オフィシャルも10年物から30年物(写真左)、さらには樽からほとんど加水せず瓶詰めした「105」(アルコール度数は60度!)まで多彩な商品を揃えているが、ボトラーズ(独立系販売業者)で扱うところが多いことでも知られる。 僕がBARでよく頼むのは、オフィシャルの「12年物」。オフィシャルの中でも「12年物が一番完成度が高い」という評判は、 バーテンダーからもよく聞くけれど、確かに安心して飲めるシェリー系モルトの一つだと思う。 もちろん、ボトラーズの「グレンファークラス」でも、面白いものがあれば、頼むこともあるが、時々期待を裏切られることも(写真右=3月の「テイスティングの集い」で飲んだ「105」のオールド・ボトル。旨かった!)。 オフィシャルの「25年物」でも、日本の酒屋さんでは1万円を切る値段で売っているところもある。良質のモルトを手頃な価格で提供したいという創業者の心意気の現れか?(18年物に2万円以上の小売り価格を付けている会社は、反省してほしいなぁ…)。 グレンファークラス。シェリー系モルトでマッカランしか味わったことのない方は、ぜひ一度、BARで頼んでみてください。また新たな「モルト観」が生まれるに違いない。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2006/08/31
コメント(6)
-

デジカメ買い換えて3カ月/8月28日(月)
デジカメを買い換えて3カ月(キヤノンIXY800です)。 相変わらず、オンでもオフでもデジカメをよく活用しております。 そこで、ここ1カ月くらいの間に撮った中で、 印象に残ったショットを何枚かご紹介--。 会社帰りの中之島、夕立ちが上がった後、 西の空を見ると、息を呑むほどの夕景でした。 沈む夕陽をバックにシルエットになる高層ビルと高速道路…。 都会ならではの構図。そして、おそらくこれほど綺麗な夕景は、 1年に数度あるかないか…。思わず、カメラを取り出し1枚。 久々に見に行った甲子園での阪神・巨人戦。ただしこれは7月19日の試合です。 阪神ファン恒例の7回の風船飛ばしの光景。 資源を無駄遣いし、ゴミをまき散らすだけという気も少しするけれど、 5万人が一度にやるとさすがに壮観です。 この日は勝ったので、ゲームセットの瞬間にもう一度風船を飛ばしができました。 毎度毎度の「バラネタ」ですみません。 8月初めに撮った「芳純」です。 今年のバラは、「3番花」までが終わって、 次は、秋の「4番花」まで、しばしのお休み。 「4番花」がシーズン最後の開花と聞いています。 花の種類はたくさんありますが、 バラはやはり花の女王です。 サクラやアジサイとともに、僕にとっての「3大美花」です。 被写体としても、この3つに勝る花はそうないでしょう。 来年もしっかり咲かせたいです。 階段で気持ちよく熟睡している「うらん」です。寝ている姿も、愛らしくアピール。 人間はこんな格好で寝られませんが、ネコはよくこういう寝姿をします。 うらんは今年11月が来ると、11歳。お母さんは阪神大震災の被災ネコでした。 3匹のきょうだいは、それぞれ別の家にもらわれていきました。 今も元気なのはそのうち、うらんも含めて2匹です。 うらんは、大震災がなければ、我が家にやってきませんでした。ほかの震災で被災したイヌ、ネコたちはどうしてるんでしょうか…。大震災は人間だけでなく、動物たちの運命も変えてしまいました。 これも会社帰りの1枚。お盆のさなかの14日。 冷た~いハイボールでも飲みたいなぁと、 馴染みのBARへ足を向けました。 嫌な予感が的中。やはりお休みでした。 店の前でさて、これからどこへ向かおうかと、 思案しながら、ふと上を見上げると、 以前はなかったお店の看板が。 「オイシイ オサケ」。何というわかりやすいキャッチ・コピー! レトロなデザインの看板もいいけれど、このコピーのセンスに脱帽です。 また来たくなりました。マスター、また寄るからねー。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2006/08/28
コメント(22)
-

明治屋:歴史と風格あふれる空間/8月25日(金)
BARというものがあまり街場になかった時代は、日本人にとって、居酒屋がBAR代わりだったと思う。居酒屋とBARの違いは、一言で言えば、食いもんがメインか、酒がメインかの違いだろう。 BARはあくまで酒がメインで、酒そのものを飲み、楽しむ場所。それに対して、居酒屋はどちらかと言えば、食いもんがメインで、酒は食をすすめるための引き立て役か、あるいは単に酔うためのものだろう。 僕は、空き腹の胃にアルコールを入れるのは嫌いな人間である。しばしば、BARでアテも食べずにひたすら、ただ飲み続ける人と出会うが、あれは僕の一番嫌いな酒呑みのスタイルである。 フードもリーズナブルなお値段で食べられるBARならいいが、普通BARで食べると結構高くつく。だから普段は、どこかで腹ごしらえをしてから、BAR巡りに出かけることが多い。そんな腹ごしらえの場として、最近は、居酒屋がお気に入りだ。 とくにレトロな雰囲気が漂う、昔ながらの居酒屋が好きである。そんな僕のお気に入りの居酒屋を、何回かに分けて紹介していきたい。まずは大阪から--。「食い倒れの街」「居酒屋天国」とも言われる大阪でも、僕の知る限り、天王寺の「明治屋」(写真左上)ほど居心地、雰囲気ともに素晴らしい店は他には知らない。 JR(または地下鉄)天王寺駅から阿倍野筋に沿って5、6分歩くと、年代物の大きな看板が目に入る。元々酒屋さんだった店が居酒屋に変わったのが昭和13年(1938)。以来、約70年もの歳月、なにわの酒呑みに愛されてきた。 店内は開業当時の雰囲気をそのまま残し、まるで昭和20~30年代にタイムスリップしたかのよう。大きな銅の燗器で出される熱燗(夏はちょっと大変だが)が名物だが、これがまた旨い。これまた名物の湯豆腐との相性は抜群だ。湯豆腐以外の居酒屋メニューも豊富だ。 昼間から(午後1時~)開いているのも嬉しい。そして、2時、3時から常連客が集う(写真右)。一人客が多いが、客は概して行儀がいい。酒グセが悪い客や、飲んで騒ぐ客には僕はほとんどお目にかかったことがない。みんな静かに淡々と、新聞でも読みながら、飲んで食べて、過ごしている。 値段は普通の居酒屋よりは少し高めだが、それでも2000円もあれば、僕はいつも満足できる。最近は、若い女性の間でも、静かな居酒屋ブームだといい、女性のグループ客も結構見える(写真左=メニューの内容はこんな感じです)。 残念なのは、風格あるこの店の周辺が、再開発(大阪市の道路拡幅計画とか)のため次々と更地になっていくことだ。この明治屋もいずれ、移転せざるを得なくなるのだろう。 大阪市には、歴的な文化財とも言えるこの素晴らしい建物をそのまま移転・保存させて、明治屋の営業継続を支援してほしいと心から願う。スキャンダルばかりで、評判の悪い市政のイメージアップにもつながると思うのだが…。関市長の英断を願いたい。【明治屋】大阪市阿倍野区阿倍野筋2-5-4 電話06-6641-5280 午後1時~10時 日曜休こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2006/08/25
コメント(10)
-

小西さんの「日本一」を祝う会/8月22日(火)
20日の日曜の午後、大阪キタのホテルで、今年の日本バーテンダー協会(NBA)の全国コンペティションで見事日本一(総合優勝)に輝いた小西広高さん(Bar Blossom)のお祝いの会=写真左=があり、不肖うらんかんろも参加してきた。 実は、このような業界の内輪が中心のお祝いの会に同席するのは、なんとなく場違いな感じもして、最初、僕はあまり気は進まなかった。 しかし今回は、関西から30年ぶりの優勝者誕生というめでたい祝宴(もう当分はないかも?)で、あるバーテンダーさんからも強く誘われたこともあって、末席にお邪魔させてもらった。 小西さんは以前のブログでも書いたが、まだ30歳の若さ。バーテンダーになって約7年。最初、大阪キタの「Harbor Inn」というBARで約5年間修業。2年前独立して、キタのお初天神の近くに念願の店を持った。 年齢的には若手に違いない小西さんなのだが、数年前からは、さまざまなコンペで上位入賞するなど、とても注目される存在だった(おまけに、大阪のバーテンダーの中でも3本の指に入る「イケメン」!で、女性ファンも多い)。 だから、今回の全国コンペで、彼も含め関西代表からの総合優勝を予想する業界関係者がいなかったとしても、小西さんの「日本一」は決してまぐれではない。 彼が全国コンペで上位入賞するに値する実力を持っていることは、関西のバーテンダーなら誰もが認めていることだろう。 もっとも、上位入賞者に実力差なんてほとんどない。さらに言えば、全国大会に勝ち上がってくる各地区代表の実力差なんて、微々たるもの。後は、運と巡り合わせが左右するのがバーテンダーのコンペの世界だ。 いずれにしても、前のブログでも触れた「今年からよりフェアに改善された審査方法」が、小西さんに良い方向へ働いたのは間違いないという。来年以降も、このようなフェアな審査が続いていってほしいと願うのは僕だけではないだろう。 それはともかく、お祝いの会には業界内外から200人近くが集まった。まず、関西のNBA各支部の代表らの祝辞が続いた後、小西さんが舞台上で、全国コンペ同様、フルーツ・カッティングや創作カクテルのパフォーマンスを披露(写真右上)。 カクテルのパフォーマンスはNBAのコンペ等で見飽きている僕だけれど、普段は一般には公開されないフルーツ・カッティングの演技(制限時間10分以内に、4種のフルーツをカッティングし、大皿に飾り、盛り付ける)は、プロのペティナイフのつかい方がとても興味深くて、面白かった。 おしゃべり上手の司会担当のSさん(Bar Beso)は、演技中に冷やかしやからかいのツッコミを入れるが、さすがの小西さんは余裕の笑顔で、次々とフルーツを飾り付けていく。これも全国優勝からくる自信だろうなぁ…拍手! この後、同じ全国コンペの創作カクテル部門で1位になった鴻野良和さん(徳島のBar 鴻)が駆け付けてくれてスピーチ。「小西君とは同じ組で演技させられ、顔や背丈では勝てないので、僕は絶対総合優勝できないと思った」と話し、会場を笑わせた(写真左上)。 師匠である藤田敏章さん(「Harbor Inn」マスター)は、「彼は5年間無遅刻、無欠勤。とにかく真面目で、努力家でした。それが今回報われたのだと思う」と絶賛した。 この後さらに、若手バーテンダーたちによる仮装パフォーマンス=写真右=(Bar「P」のマスターNさんの「長州小力」には、体型といい、あまりにハマリ役なので笑ってしまった)、奥さんからのねぎらいの言葉、息子さんからの花束贈呈、お楽しみ抽選会などと続き、賑やかに、そして和気あいあいの内に会は終わった。 バーテンダーにとって、全国コンペでの総合優勝(日本一)は究極の夢であり、目標だろう。「しかし、その後のバーテンダー人生の方が長いんですよね」と、ある先輩バーテンダーが僕に語った言葉が印象的だった。だから、まだ30歳の小西さんにとっては、まだ半分にも達していない。 お祝いの会にこれだけたくさんの人たちが集まったのは、関西にとっては30年ぶりの祝宴ということもあるが、小西さんの素朴で、丁寧で、飾らない人柄に負うところも大きいだろう(写真左=奥さん、息子さん、そして師匠の藤田さん=左端=も舞台に上がって、フィナーレ)。 コンペ(競技生活)からは退くことになるが、どうかいつまでも客に愛されるバーテンダーでいてほしい。全国大会で上位入賞したせいなのか、その後「天狗」になって、昔の客が離れていった人も僕は知っているが、小西さんにはそんな心配は杞憂だろう。 日本一という栄誉を得ても、彼はきっとこれからも変わぬ接客につとめて、末永く愛されるバーテンダーであり続けてくれると信じて疑わない。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2006/08/22
コメント(6)
-

念願の「伝・源頼朝像」と出会う/8月19日(土)
前回に続き、酒やBAR巡りや音楽とは違う話題だけれど、お許しあれ。お盆の休日、京都国立博物館(京都・東山七条、以下、「京博」と略す)に行ってきた。 「美のかけはし-名品が語る京博の歴史 開館110年記念特別展」(7月15日~)。 なぜ暑いこの時期、京都まで出かけたかと言えば、子どもの頃からずっと見たかったけれど、その機会が一度もなかった素晴らしい絵画の本物が出展されるから。 中学や高校の歴史(日本史)教科書には必ずと言っていいほど登場していて、おそらく日本人なら一度は目にしたことがあるその絵画とは国宝「源頼朝像」(京都・神護寺蔵、伝・藤原隆信筆)=写真左下。 日本絵画史上の肖像画の中でも、「最も完成度の高い傑作」と誰もが認める逸品。この国宝は神護寺から寄託された京博が収蔵しているが、貴重な絵画なので普段は一般公開されていない。 今回の特別展は、明治30年(1897)に開館した京博の110周年を記念し、所蔵する(または寄託された)貴重な名品を集めたもの。 展示されてるのは、国宝26点、重要文化財37点を含む約120点。国宝の中には有名だけれど普段は見られないものも多い。 僕のお目当ての「源頼朝像」は13世紀の作で、最近の学術研究で実は源頼朝ではなく、足利尊氏の弟、直義であるという説も有力になっている。 だから、最近の教科書などでは「伝・源頼朝像」という表記をしているものも多いが、京博は、鎌倉時代の絵画技法などから、あくまでこの絵画は「頼朝」だという立場のようで、特別展でも「伝」の文字はなかった。 ただ、僕自身は、この肖像の主が頼朝であろうとなかろうと、この絵画の価値を下げるものは一切ないと思っている。 実物の「頼朝像」は保存状態も良く、顔や髪の部分の筆遣いまでもはっきりと分かる。写真で見ると黒一色にしか見えない衣装も、実物では生地の文様も細かく、丁寧に描かれている。 冷徹・沈着な「頼朝」の表情。その鋭い眼光は心の内までも映すようで、見る者に迫る(大きさは縦約1.5m、横約1.2mと、想像してたよりでかい)。 作者の藤原隆信という絵師はどういう人かはよく知らないが、海外で言えば、レンブラントやルーベンスにも負けない、我が国が誇る肖像画家と言っていいだろう。 会場では、同じ隆信作という国宝「平重盛像」(これも神護寺所蔵。なぜかこちらは左向き)と共に一対で展示されているが、完成度は「頼朝像」が圧倒的に上。 重盛像には、頼朝像にはある「足」が描かれていない。手抜きなのか意図的に描かなかったのかは知る由もないが、隆信がいかに頼朝像に力を入れたかが分かる。 この特別展には、他にもこれまた教科書によく出てきた如拙の「瓢鮎図(ひょうねんず)」=写真右=など素晴らしい国宝の数々が出展されている。 個人的には、豊臣秀吉関係の書状や遺品の数々、鴨長明直筆という「方丈記」、空海直筆の書が記された菩薩図に、感銘を受けた(詳しくは京博のHPをご覧あれ)。 残念ながら会期は今月27日(日)まで。京博はJR京都駅からバスで7分ほど(徒歩でも20分ほど)。近くには三十三間堂、智積院、方広寺、豊国廟などの名所旧跡も多い。天気が良ければ京都駅から散歩がてら行くのも楽しい。ご興味のある方はぜひ足をお運び下さい。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2006/08/19
コメント(6)
-

大空襲と大震災に耐えた階段/8月16日(水)
昨日15日は62回目の「終戦の日」だった。戦後生まれの僕には、当然戦争体験はない。小学校低学年時代、給食に牛乳が出ることはなく、(美味しいとは思えぬ)脱脂粉乳だったが、今思えば終戦後の食糧難の名残りだったのかもしれない。 母からは昔、戦時中や終戦直後の苦労話をよく聞かされた。滋賀県の農家に野菜を分けてもらうため、反物を背負って買い出しに行ったこと…等々。 そう言えば、60年代初め頃はまだ、大阪の街のターミナルでは、傷痍軍人の姿をした人たちが物乞いをしていた。亡き父も陸軍兵士としてフィリピン戦線へ送られたが、幸い無事に帰還した。僕がこの世に在るのはそのおかげである。その意味では、亡き父には本当に感謝しなければならない。 あの戦争に対する思いはいろいろある。靖国問題やA級戦犯問題に対しても個人的意見はあるけれど。そういうことは、このブログでは書かない。僕のブログは、あくまでお酒とBAR巡りと音楽をメイン・テーマにした趣味のページ。だから、「政治」と「宗教」と「ブログを利用した個人的ビジネス」の話題はNGにしている。訪れる皆さんも、この点はどうかよろしくご理解ください。 ただ、終戦記念日には直接関係はないけれど、今回、一つだけ紹介したい場所がある。 関西以外の方はごめんなさいという話題(場所)だけれど…。 三宮駅前にある「神戸そごう」。1933年(昭和8年)に開業。神戸では大丸・神戸店と並ぶ老舗デパートである。しかし、95年、あの阪神大震災でともに全半壊に近い大きな被害を受けた。現在の両デパートは震災後建て替えられたものである。 そんな神戸そごうに、一つだけ「秘密の場所」がある。阪神・三宮駅改札口を南側から出て、そごう地下玄関方面へ向かう。玄関には入らず、もう10数m南へ歩くと、地上に出る階段がある。そこはそごうの建物の一部なのだが、近代的な建物の一部には似つかわしくないレトロな、意匠を凝らした階段。 実はこの階段は、創業当時の神戸そごうの姿を伝える唯一の場所。そこに来ると、まるでここだけ違う時間が流れているような不思議な気分になる。この階段は、米軍のあの神戸大空襲にも、阪神大震災にも耐え、今も普通に人々に利用されている。三宮には月に2度ほど行く僕だが、山側へ足を向けることの方が多いので、この階段は滅多に通らない。 しかし、時々思い出したようにこの階段を訪れる。そして、あの空襲時におそらくここに逃げ込んだ神戸の人たちのことに思いを馳せる。B29から次々落とされる焼夷弾で燃えさかる地上の焦熱地獄から逃げ込み、恐怖に耐えた人たちのことを…。 大震災後、神戸そごうを建て替えた際、この階段を残したのは経営者の素晴らしい英断だった(個人的には称賛を贈りたい)。阪神大震災で徹底的に破壊された神戸の街に、戦前の面影をしのぶ場所を探すのは難しい(それどころか震災そのものの爪痕も日々風化している)。 そんな神戸にあって、太平洋戦争と阪神大震災という2つの大きな惨禍に耐え抜いた、貴重な「証人」がここにはある。もし関西以外にお住まい皆さんで、神戸を訪れる機会があれば、ぜひ「神戸そごう」の地下から地上に出るこの階段を登ってみてほしい(関西在住の方でも、この「場所」をまだ知らない方はぜひ!) そして、あの神戸大空襲の恐怖に震えていた人たちのことや、阪神大震災で無念にも倒れた人たちのことに、わずかな時間でも思いを馳せてもらえたら、とても嬉しい。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2006/08/16
コメント(14)
-
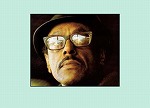
悲しい知らせ…デューク・ジョーダン氏死去/8月13日(日)
8月9日の日記で書いた米国の偉大なジャズ・ピアニスト、デューク・ジョーダン氏(写真)が、なんと8月8日にデンマークのコペンハーゲン(ジョーダン氏は1978年以来コペンハーゲン在住)で亡くなっていたという事実を知りました。享年84歳。死因は分かりません。 ブログの友人B・Gさんが、別のブログからの情報として、取り急ぎ教えてくれました。日本の一般紙はまだキャッチしていないのか、きょう(8月13日)現在、私の知る限りまだどこも報じていないようです(その後、A紙の14日付夕刊に死去の知らせが載りました。Y紙は15日の朝刊で報じました)。 しかし、ジョーダンの死を伝える海外の報道(HPなど)を読む限り、間違いないようです。デンマークの米国大使館も確認しているとか…。GoogleやYahooで、「Duke Jordan」「Died」と入れて検索すれば、さらに多くの情報に接することができます。 9日の日記でジョーダン氏のことを取り上げたのはまったくの偶然ですが、今となってみれば「虫の知らせ」と言うか、とても不思議な気がしてなりません。こんなことって、あるんですね…。 敬愛するジョーダン氏の訃報に、ただただショックで、僕は言葉もありません。元気だと聞いていたので、またもう一度日本にやってきてライブをしてくれると信じていたのですが、その夢はもう叶わなくなってしまいました。 今はただ、ジャズの歴史に残る偉大なピアニストをしのぶとともに、きょうは「Flight To Demmark」を聴きながら、冥福をお祈りしたいと思います。合掌。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2006/08/13
コメント(6)
-

さよなら、そして有難う 「セカンド・ラジオ(Second Radio)」/8月12日(土)
いささか旧聞になって恐縮だが、尾崎浩司さんのBar、「Second Radio(セカンド・ラジオ)」が6月末で、店を閉じたのだという。閉店の事実は一般紙に載るはずもなく、Bar業界と常連客だけが知り、僕の耳にはしばらく入ってこなかった。 尾崎さんが1972年、初めて世に送り出したBar「Radio」、そして「Second Radio」、さらに「Third Radio」については、以前、僕のブログ(05年1月15日の日記)でも触れた(写真左=Bar「Second Radio」の入り口のサイン=看板)。 神宮前にあったBar「Radio」は、僕が20代後半にお邪魔した伝説的なBar。おそらく、僕の東京BAR巡りの歴史でも、きわめて初期に出合った酒場だ。JR原宿駅で降りて、地図を頼りにたどり着くのに非常に苦労した思い出が、今もよみがえる。 そして、南青山の「Second Radio」もオープン当初に、連れ合いとともにお邪魔して、たまたま店がすいていたため、尾崎さん本人からアンティ-ク・グラスにまつわる様々なお話をじっくり聞けるという幸運に恵まれた。 「Radio」も「Second Radio」もどちらかと言えば、1杯のお値段が張るBARだった。チャージも確か前者が1500円、後者は2000円と、普通のBARに比べて格段に高かった(チャージを1500円以上取るようなBARには、僕は基本的には、店やマスターがどんなに有名でもまず行かない)。 だが、お通しで出される料理(3種盛り)の芸術性の高さ、見事なアンティークグラスを使ってつくられるオリジナル・カクテルの完成度、そして店内のライティング、生け花などの雰囲気など、高いチャージに見合うだけのものを客に提供してくれていると、僕は感じた(写真右=「Second Radio」の店内)。 僕はその後徳島へ転勤した。そして、徳島で尾崎さんのお姉さんと、あるジャズBARで出逢うという奇遇を得た。尾崎さんが徳島出身という話は知っていたが、まさかお姉さんと出逢うとは思わず、何か不思議な縁を感じた。 素晴らしいカクテル・アーチストでもある尾崎さんだが、Bar業界ではどちらかと言えば、あまり群れない「孤高の人」というイメージだ。そして、酒好きの友人の間でも、「尾崎評」や「Radio」系列のBarに対する評価は人さまざまだ。 僕も最初は、「寡黙で、とっつきにくい人」という先入観を持っていた。だが、「Second Radio」で会ってから、尾崎さんに対する印象は変わった。 BARで大人の振るまいができ、酒を愛する人間に対しては、きちんと接してくれて、結構おしゃべり好きな人なんだと分かった(写真左=伝説のBar「Radio」の店内。光ファイバーを使った天井の美しさは絶品だった (C) 「バー・ラジオのカクテルブック」から)。 そんな「Second Radio」閉店のニュースは、ショック以外の何ものでもない。店を閉じた理由について、尾崎さんは「粋なお客さんが少なくなったから…」とあまり多くを語らない(尾崎さんは現在、「Third Radio」のカウンターに立っているという)。 でも、嬉しいニュースも一つ。02年に閉店したままだった「Radio」が8月21日にリニューアル・オープンするという話を、あるサイトで知った。本当なのだろうか? あの伝説のBARがよみがえるとしたら、小躍りしてしまうようなニュースだ。 尾崎さんは「Third Radio」から「Radio」に戻るのだろうか? いずれにしても再開「Radio」にぜひお邪魔して、新たな「尾崎ワールド」の展開を見てみたい。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2006/08/12
コメント(6)
-
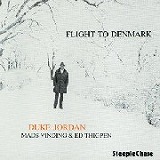
デューク・ジョーダン: 歌心あふれる哀愁のピアノ/8月9日(水)
ジャズを聴き始めた頃、ビル・エヴァンス、オスカー・ピーターソンと並んで、針が擦りきれるくらいよく聴いたピアニストのレコードがある。とくに、深夜に聴くのが好きだった。A面からB面、終わればまたひっくり返し、A面に戻るということを何度も繰り返した。 その人の名は、デューク・ジョーダン(Duke Jordan)。そして、アルバムのタイトルは「フライト・トゥ・デンマーク(Flight To Denmark)」(1973年発表=写真左)と言った。 このレコード、誰が私に教えてくれたかは忘れた。しかし、初めて聴いた時の感激は今も忘れられない。テクニックを駆使するタイプでもない。一音、一音がゆったりと心に沁み入るという感じ。聴き終わった後も、心地よい余韻がしばらく漂う。 デューク・ジョーダンは、1922年米ニューヨーク生まれ。高校生の頃からバンドを組み、高卒後、すぐプロとして活動を始めた。そして、1946年、弱冠24歳の時に、あのチャーリー・パーカーのグループに参加。その後自らのトリオで1955年、初のアルバム「Trio And Quintet」(写真右)を発売する。 その後50年代末、ジョーダンは米国を離れ、フランスへ向かう。故郷を離れた理由は定かでない。新たな音楽スタイルを欧州に求めたと説や、米国内の人種偏見に嫌気をさしたという説もあるが、いずれにしろ、ジョーダンが渡欧しなければ生まれなかったアルバムが「フライト・トゥ・デンマーク」である。 マッツ・ヴィンディング(ベース)、エド・シグペン(ドラムス)という最高のメンバーにサポートされた、ジョーダンはこのアルバムで、哀調を帯びた、実に味わい深い曲を次々と聴かせてくれる。名曲「No Problem(邦題「危険な関係のブルース」)をはじめ、「Glad I Met Pat」「How Deep Is Ocean」のほか、「Green Dolphin Street」などスタンダードの名曲も織り交ぜて。 ジョーダンは1970~80年代、たびたび来日し、コンサートを開いた。当時地方都市で仕事をしていた僕は、残念ながら生演奏に接することはできなかったが、先日ブログの友人、B・Gさんから、「88年頃、徳島のライブハウスで演奏をした」という凄い話を聞いて驚いた(地方都市も結構まめにまわってくれてたんだ!)。 しかも、この時のジョーダンは凄く機嫌が良くて、なんと自ら歌まで歌ったとか。ジョーダンの歌なんて、ほとんど誰も聴いたことはないだろう。小さなライブハウスならではの幸運。その場にいなかった僕は、ただただ悔しい(写真左=1960年発表のアルバム「Flight To Jordan」も名盤です)。 「エヴァンスやキースが目標」の素人ピアノ弾きとしては、ジョーダンは少し理想のスタイルとは違うが、それでも、美しいメロディーを紡ぎ出す技はとても参考になる。唯一、演奏する曲はあの「No Problem」だが、シンプルがゆえに、歌うように、リズムに乗って弾くのは結構難しい曲だ(写真右=1983年発表のアルバム「Plays Standards」)。夢は「Glad I Met Pat」のような素敵なワルツを弾きこなすこと。 今年84歳になるジョーダンだが、これまでに生み出したアルバムはそう多くない。おそらく20枚もないだろう。それでも、「Flight To Denmark」を生みだしたことで、ジョーダンはピアニストとして、そして作曲家としても、永遠に輝き続ける。 ジョーダンは今も一応、現役ピアニストとして、欧州を中心に演奏活動を続けているという。往年の輝きはもうないかもしれないが、機会があれば、あの歌心あふれる、枯れたピアノタッチに触れてみたいという気持ちは今も募っている。【追記】デューク・ジョーダン氏はこの日記をつづっていた日(欧州の現地時間では8月8日)、デンマーク・コペンハーゲン郊外の自宅で亡くなられました。享年84歳。なんという偶然にただ驚くばかりです。心からご冥福をお祈りいたします。8月13日の日記で続報を記しています。 ※CD画像はTower Record HPから引用・転載しました。感謝いたします。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2006/08/09
コメント(4)
-

クロ・ドゥ・タール: 極上のマールを味わう/8月6日(日)
いろんなお酒を日常的に飲んでいるから、たまには変わったお酒が飲みたくなる。今夜はビールも、ウイスキーも、ワインも、日本酒も、焼酎も、ホワイトスピリッツも飲みたくなーい。 そんな時は、行きつけのBarで、「こんな夜に何かいい飲み物はないかなぁ?」と我が儘を言う。すると、マスターはしばらく考えて、「じゃぁ、こんなお酒はどうです?」とバックバーの棚から1本のボトルを取りだした。 それはマール(Marc)。マールとはワインを造る際に絞った葡萄の絞りカスを、再発酵させて蒸留したブランデー。マールとはフランスでの呼び名で、イタリアだとグラッパと呼ぶので、名前を聞いた方もいるだろう。 マールは様々な銘柄が出ているし、僕も何種類かは味わったことがある。ワインでもないし、ブランデーでもない。だからと言って、二つを足して2で割ったお酒でもない、複雑な味わいのお酒。 「えっ、マール? 飲んだことあるけれど…」と言う僕に、マスターは「いや、普通のマールとはちょっと違う、面白い、特別なマールなんですよ」と応えた。そう言われるとちょっと好奇心がそそられる。 そのマールの名前は「クロ・ドゥ・タール(Clos de Tart)」(写真左)。普通、僕らがBARで出合うマールには、そんな名前の銘柄はない。「見たことないボトルやなぁ…」と僕。でもボトルの形は、ブルゴーニュっぽい。 それもそのはず、「クロ・ドゥ・タール」は、ブルゴーニュ地方のモレサンドニという村を代表する最高の畑が生むワインの銘柄で、13世紀から続く「グランクリュ(特級)」畑でもある。 特級の単独畑が産み出し、市場に出ているマールというのは、「たぶんこのクロ・ドゥ・タールだけでしょう」とマスターは語った(写真右=ワインとしての「クロ・ドゥ・タール」のラベルはこんな感じです)。 それならば、是が非でも味わってみなくてはならない。で、味わった僕の感想はと言えば、さすが「グランクリュ」畑から生まれたマール。熟成感たっぷりで、果実味も豊かな味わい、そして余韻のある上品な後味。 日本には輸入量は少ないかもしれないが、ネットでは取り扱っている業者もいるようだ。お値段はボトルで16000円~18000円と結構お高めだが、もし、置いているBARで出合ったら、ぜひ、一度味わってみてほしい。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2006/08/06
コメント(8)
-
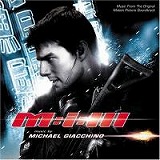
ミッション・インポシブル3: 期待が大きすぎたのが…/8月3日(木)
遅ればせながら、話題の映画「M:I:3(ミッション・インポシブル3)」を見てきた。最初は、まだ観ていない「ダ・ビンチ・コード」をと考えていたのだが、訳あって「M:I:3」にした。 さて、この映画、前評判はとてもいい。観た人の中では、「3部作では一番面白い」という意見が多い。1も2も観た僕としては、期待が高まる。 主演はもちろんトム・クルーズ。監督は1、2とは違って、J.J.エイブラムスという人。「フェリシティの青春」など人気TVシリーズの監督で知られるそうだが、ハリウッドの大作を手がけるのは初めてという。 脇を固める俳優で大物は、ローレンス・フィッシュバーン、フィリップ・シーモア・ホフマン(「カポーティ」で今年のアカデミー主演男優賞を取った人)くらいかな(トムのギャラに使い過ぎたんだろうね)。 あらすじは以下の通り。元IMFエージェントのイーサン・ハントは、現場を引退し、後輩の育成に取り組んで、平穏な日々を送っていた。私生活では、看護師のジュリアとの将来を誓い合い、結婚を間近に控えていた。そのハントに、緊急のミッションがやって来る。 ミッション中にベルリンで拘束された教え子のリンジーを救出せよと言う。チームと共に現地入りしたハントは、リンジーの身柄を確保するが、彼女は頭蓋の中に埋め込まれた爆弾により死亡。結果的にミッションは失敗に終わる。 教え子を殺した敵は、デビィアンという武器商人。しかし、その存在は謎につつまれ、IMFの全組織が躍起になって行方を探している。 デビィアンがバチカンに現れるという情報を掴むと、ハントは網の目を潜り抜けるような作戦で一気に身柄を確保するが、同時に、デビィアンと身内のIMFの人間が内通していることも分かる。 帰国後、護送中に謎の敵が現れ、ハントはデビィアンを奪われる。一方、妻のジュリアは誘拐され、逆に窮地に追いやられる。デビィアンはジュリアの命と引き換えに、「『ラビットフット』と呼ばれる正体不明の兵器を48時間以内に盗み出せ」とハントらに命じる。 ハントらチームのメンバーは、無事に「ラビットフット」を手に入れられるのか? そして、デビィアンの黒幕は誰か? 結末は明かせないけれど、最後のどんでん返しは、意外とオーソドックスで、意外性はなかった。 また、1や2にあったような知能をこらした面白い仕掛けも少なく、どちらかと言えばアクション重視の演出(トム・クルーズはとにかく走る、走る。走るシーン満載! カーチェイスもやや多すぎるかなぁ)。 1や2を観ていない人なら十分楽しめる映画だろうが、1&2を知る僕自身としては「期待以上ではなかった」という評価(割引料金=千円=で見たから、まぁ元は取ったかと思うけれど…)。10点満点だと、8点くらいかな。 ベルリン、バチカン、上海…と舞台は次々と変わり、異国情緒もたっぷりに作っていて、飽きさせない工夫も随所に。夏休み、オヒマなら観ても損はないよという映画でしょう。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2006/08/03
コメント(12)
全11件 (11件中 1-11件目)
1