2006年02月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-

秋が楽しみ、バラづくりに挑戦!/2月28日(火)
家の外構(外回り)にある小さな箱庭のコニファーやシーダー・クレスト(常緑の針葉樹)が成長しすぎて、剪定などの手入れが大変になってきた。 高さが2m以上に育ってしまうと、6段くらいの脚立に乗らなければ剪定できない。それも樹勢がとてもいいために、枝葉が多く、手作業だと時間がかかるので電動バリカンでやるが、これが結構疲れるし、危ない作業になる。 そんな訳で、約10年ぶりにこの箱庭を、思い切って模様替えすることにした。余り高く伸びる樹種はもうこりごりなので、あれこれ考えてバラを植えようということになった。 造園もやってる近所のガーデン・ショップ(植木屋さん)に相談して、一切合切をお願いすることにしたが、天気がいまいちの日が続き、植え替えは2度延期になった。 そして、ようやく植え替え当日。高さ約2.5m、直径が20cm近くに育った樹を引き抜くのはそう簡単ではない。根が相当しっかり張っているので、無理にクレーンで引き抜くと、外構のレンガ積みが壊れる恐れがあるという。 結局、電動ノコギリで枝葉を切って、切って、切って、高さが30cmくらいになるまで短くして、後は職人さんが2人がかりで、手作業で引き抜いていた。大きく育った樹を切るのは若干しのびなかったが、きっと新たな苗木(挿し木)の母木にでも活用されて、第二の「人生」を歩んでくれると信じたい。 さて、1日目。コニファーとシーダー・クレストを抜いた職人さんは、土をバラ用のものにすべて入れ替えて、苗木を10本(種類)置いて帰った。「明日、このなかから6本を植えますから、それまでに選んでおいてください」と言い残して…。 そして、翌日我が家が選んだ品種は、写真(左上から時計回りに、アプリコット・ネクター、芳純、アイスバーグ、金閣、テキーラ、ブルームーン)の6つ。まだ高さ20cmほどの、花も葉もまったくない、ただの苗木だが、晩秋には1.5mくらいに育ち、この写真のように花が咲くという。ホントかなぁ? 植木屋さんは、「バラは結構マニアがいて、植えたばかり苗木は根こそぎ盗まれることが多いから、(大きくなるまでは)苗木をチェーンにつないでカギをかけておいた方がいいですよ」と言って、帰って行った。 箱庭は公道に面している。見た目に無粋なことはあまりしたくないのだが、そう言われたからには心配になる。近所のホームセンターでチェーン(土に合うようにカラーは茶色に)と鍵を買ってきて、6本の苗木を結んだ(チェーンはもちろん、ある程度の大きさに育てば、外せるのだが…) 「花泥棒」なんて、あまり聞きたくない嫌な言葉だが、比較的治安がいいとされる我が家周辺でも、現実には花泥棒はいる。そして一度盗んだ家には、またやって来るという。他人の花を盗んで育てるなんて、そんなあさましい心の人間には、花を育てる資格はないと思うのだが…。 植木屋さんは、台風シーズン前の支柱立てや、来年1月頃にする剪定の仕方も指導してくれるという。近所にこういう親切な植木屋さんを持っていると、素人にはほんとに頼りになる。 バラはとてもデリケートな花。害虫も付きやすく、育てるのは結構大変だという。それは覚悟している。でも、難しいからこそ挑戦してみたい(僕のジャズピアノと同じかも…)。花がいっぱい咲く日が、今から楽しみだ。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】
2006/02/28
コメント(18)
-

ミュンヘン:スピルバーグの勇気/2月25日(土)
スティーブン・スピルバーグ監督の話題作「ミュンヘン」(写真左上=映画のポスター)を観た。ご存じのように、1972年のミュンヘン五輪の際起こった、あの悲劇的なイスラエルの選手・コーチ殺害事件をテーマに作られた話題の映画。 ミュンヘン五輪と言えば、男子バレーボールの金メダル、競泳平泳ぎの田口信教とバタフライの青木まゆみの金メダルが、僕にとっての鮮烈な思い出。 もちろん、あの選手村での占拠事件やイスラエルの選手、コーチら11人が殺害されたことも記憶にあるけれど、事件の詳細やその後の報復等には今までほとんど無知だった。だから、この映画はまず史実を知るという意味でも、とてもいい材料になる。 映画の冒頭で、まず、あの選手村占拠&選手・コーチ殺害事件が事実として、伝えられる(ただし、アナウンサーやレポーターの声だけで。実際の場面再現=空港での銃撃戦=は映画の最後に、「フラッシュバック」のように描かれる)。 イスラエル政府は、モサド(機密情報機関)に命じて、事件を企てた黒幕らへの報復を決断する。秘密裏に5人からなる暗殺チームが組織され、そのリーダーに任命されたのが主人公のアヴナー(エリック・バナ)だ。 アヴナーには身重の妻がいる。しかもこれまで人を殺したことなどない。だが、愛国心はある。悩んだ末に、今回の報復には「大義」があると信じて、彼はこの難しい任務を引き受ける(写真右=映画の1シーン。右が主演のエリック・バナ)。 そして、他の4人のメンバーとともに報復のターゲットであるテロ指導部の11人を追って、ヨーロッパ各地や中東に赴く。ジュネーヴ、ロンドン、パリ、ローマ、アテネ、ベイルート…。さながらヨーロッパ旅行を体感しているような気分にもなるが、内容は重くて、暗い。 国際法すら無視した報復(他国内での違法行為)に果たして「大義」はあるのか。国の生存を守るためなら何をやっても許されるのか。任務を終えて、一日でも早く、愛する家族(妻と生まれたばかりの娘)の元へ帰りたい(写真左=アヴナーは娘が生まれ、国家より家族の大切さをより自覚していく)。 アヴナーは日々自問自答しながら、任務を遂行し続けるが、テロリスト側もその都度、報復する。果てしない報復の連鎖。やがて自身も狙われるように。そして自分の行為に疑問を感じ始めたアヴナーは…。 ユダヤ系のスピルバーグだから、おそらくはイスラエル寄りに作られている映画だろうと、観る前は想像していた。だが、「一方だけの正義なんてあり得ない。報復して抹殺しても、またそれを超えるテロリストが後釜に座るだけ」(主にアヴナーに語らせているが…)というメッセージに、僕の想像は見事に裏切られた。 米政府はもちろんのこと、イスラエル支持者の多い米国民の間でも、スピルバーグ批判が起きているという。当のイスラエル政府も「親パレスチナの映画だ」と批判しているという。批判を覚悟でこの映画をつくったスピルバーグを素直に評価したいと思う。 映画にはとくにオチも意外な結末もない。映画の演出として若干の設定変更はあったようだが、ほぼ事実に忠実につくられているという。3時間はやや長いのかもしれないが、場面転換のテンポがいいので、退屈することはない(写真右=報復には爆破という手段も用いられ、アヴナーらが望まなかった一般市民の巻き添えも出る)。 サスペンス・アクションとしても、政治・軍事ドラマとしても、家族愛をめぐる人間ドラマとしても、見事に描ききったスピルバーグの手腕は、たださすがと言うほかない。「シンドラーのリスト」「プライベート・ライアン」など歴史ドラマを作らせたら、かなう人はいないだろう。 映画は、ニューヨークに移り住んだアヴナーが、中南米での新たなミッションを打診され、任務を断るシーンで終わる。そのバックに、当時はまだあった世界貿易センタービルがそびえ立っているのが、その後の世界の現実を暗示しているかのように…。 スピルバーグが言いたかったのは、「結局のところ、復讐は復讐しか生まない」ということだろう。ユダヤ系であるスピルバーグがそんなメッセージを発信したことに、僕は大きな意味を見ている。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】
2006/02/25
コメント(6)
-

東京BAR巡り(下)+α /2月22日(水)
上京2日目。快晴の土曜日。昨晩の酔いも消えて、気持ちよく目覚める。とは言っても、BARが朝から開いている訳がない。そこで、いつものように夕方まで東京散歩としゃれ込む。 前回は、青山墓地(霊園)の著名人のお墓巡りに興じた僕だったが、今回はうって変わって、11日にオープンしたばかりの「表参道ヒルズ」(写真左)にお邪魔した。「表参道ヒルズ」と言えば、あの歴史的な同潤館青山アパートの跡地に建った表参道の新しいランドマーク。設計は、今をときめく安藤忠雄氏とあれば、注目されない訳がない。開館15分前に着いた僕だったが、すでに300人近い列が…。さすが話題のスポットだけに、凄い人気。 入館した僕は、とりあえず最上階を目指す。「表参道ヒルズ」は地上6階、地下6階(店舗は地上3階~地下3階)と、とんでもなく底が深い。安藤氏曰く「建物は表参道のケヤキ並木とあまり違わない高さに、しかし容積率はしっかり確保したい」という相反する願いを両立させるために生まれた設計だという。 外観はガラスとコンクリートの打ちっ放しというモダンな造りで、細長い形はなんとなく、豪華客船を連想する。内部の造りも面白い。地下3階から地上4階くらいまで、中央部分が吹き抜けになっていて、内部の周囲に緩やかなスロープが、最上階から最下階までスパイラル状につながっている(写真右)。そして各階のスロープに面してショップが並ぶ。 安藤氏の建築は時に、その奇抜さが故に賛否両論を呼ぶ。しかし独学で建築を学び、今日の名声を築き上げたことは、誰しも認めるところ(同じ関西人としてその活躍は嬉しい限り)。この「表参道ヒルズ」については、知る限り評判はいいようだし、個人的にもユニークな発想がとても気に入っている。今回も、建物の一角に同潤館アパートの一部を再生させるなど、安藤流のこだわりも。 さて、内部をざっと見て回った僕の印象。日本にまだあまりお目見えしていないブランドを、よくぞこれだけ集めたなぁと感心する(ショップの詳細は「表参道ヒルズ」のHPを見てね!)。酒飲みの僕が一番気に入ったのは、名だたる蔵元から集めた日本酒や珍味がBARスペースで楽しめる「はせがわ酒店」(地上3階)と、常時80種のワインがテイスティングできる「BISTY’S」(地下2階)=写真左。今回は時間がなくて味わえなかったが…。 さて、「表参道ヒルズ」を後にした僕は、夕刻までの時間を映画鑑賞にあてた。当初は、「有頂天ホテル」か「フライトプラン」を見ようという心づもりだったが、有楽町の映画館まで来て気が変わり、S・スピルバーグ監督の「ミュンヘン」に変更した(まぁ、こっちも前から見たいと思っていたし…)。 この映画「ミュンヘン」については後日の日記で詳しく触れることとして、映画の後、いよいよ陽も落ち始めて、BAR巡りタイムの始まり始まり! 2日目のスタートも、やはり銀座から。 まず、7丁目の「Rockfish」にお邪魔。大阪・北浜でBARを開いていたMさんが4年前、上京して開いた支店。老舗のサンボアで修業したMさんは、格式と伝統で知られる銀座に、サンボア・スタイルのハイボールを紹介。フード類などは、サンボア以上に充実させた。安い、旨い、早いがモットーの「Rockfish」は東京でもBAR好きに支持され、根強いファンがついている。 この日飲んだのは、もちろん定番のハイボール(美味しくて胃にしみるー!)=写真右。ちなみに現在休業中の北浜の本店も、4月に再オープンするとのこと。順調な発展を祈りたい。 さて2軒目は、久々に5丁目のBar「ルパン」(写真左)へ。ここは言わずと知れた、銀座のBARの歴史そのものという老舗。とくに太宰治、坂口安吾、織田作之助ら数多くの作家に愛され、店内のインテリアや、太宰らが座ったスツールなどは昔のまま現役。 カウンターの隅にはいつも、太宰らが来店した際の有名な写真が飾られている。昭和のヒトケタ時代のBARにタイムスリップしてみたい方は、ぜひ一度お越しを。 さて、今回の最大のお目当ては6丁目にある、シェリーがウリの「しぇりークラブ」。ここは、大阪で僕が最近よくお邪魔しているBar「Artemis」出身のMさんが店長をつとめている。5年前(確か…)、「しぇりークラブ」の店長にならないかという話をもらい、「何の縁もゆかりもない東京へ出てきた」というMさん。(写真右=味わったシェリーのうち2種。きりっとして旨かった!) しかし持ち前の努力と、紳士的で、上品、気さくなキャラクターで、東京でもお客さんの心をつかむ。そして数年前には、スペインで念願のヴェネンシアドールの資格も得るまでに。お店の壁には、なんと「世界で一番たくさん227種類のシェリーを置いているBAR」とのギネスブックの認定証が! 本国スペインを差し置いて、す、すごーい! さすがに最近は、「接客時の関西弁もあまり出なくなった」と言うMさんだが、この日は関西人の僕が訪れたとあって、「関西人同士やから、関西弁でやりましょか」と楽しそうに応対してくれた。迷うほどあるシェリー・メニューの中からお勧めを4種ほどを味わい、前菜&生ハムの盛り合わせ、エリアなどもいただき、至福の時間を貰った。 さて、「しぇりークラブ」に長居した僕は、同じ6丁目にあるBar「保志」に移動したが、あいにくオーナー・バーテンダーのHさんはまだ店に来ておらず、「出直して来まーす」と言い残して、いったん店を辞す。そして西麻布へ転戦。以前から一度行ってみたかった住宅街の中にあるBAR「霞町・嵐」(写真左)へ。 ここは、実は有名な女優さんKさんの元邸宅の地下を利用して開いたBAR。邸宅のオーナーは今もKさんで、この地下室はその元夫だったUさんの音楽スタジオだったとか。いわゆるオーセンティックBARではないが、照明やインテリアがとてもおしゃれ。とても落ち着けてリラックスできる。 店には僕と同行者のほか、外国人の家族連れが1組、個室のようなスペースでくつろいでいる(場所柄、外国人客が多いのだろう)。7歳くらいの女の子が一緒にいる。na_geanna_mさんが見たら、顔をしかめるかなぁ…? 「霞町・嵐」にはバーテンダーとバーテンドレスがいたけれど、福井県出身のバーテンドレスの方とは、共通の知り合いである大阪のバーテンダーの話で盛り上がる(ちなみにバーテンダーは石川県出身で、北陸コンビです)。家主のKさんも月に一度くらい、ここに飲みに来られるとか。 さて、「霞町・嵐」を別れを告げた僕。まだ10時すぎ。まだ銀座に戻るのは早いので神楽坂へさらに転戦。ここでも以前から気になっていた「Kansui」というBAR(写真右)へ。華道家というマスターが和風の趣を上手く生かした、隠れ家的な、素敵なお店だったが、マスターはちょっと寡黙すぎたかなぁ…。 さて気を取り直して、地下鉄で再び銀座へ戻る。そしてBar「保志」(写真左)へ。マスターのHさんとは、昔(たぶん8年ほど前)、友人に連れて行ってもらった銀座の「Little Smith」というBARで初めてお会いした。Hさんは、そのときすでにバーテンダー世界大会での優勝経験を持つという凄い方だった。 しかしHさんには、そんな栄光をひけらかすようなことは微塵もなく、初対面からとても気さくで、温かい接客をしていただいた。その後もたまに、「Little Smith」にはお邪魔したが、Hさんが別のBARの店長に移られてからは少し疎遠になっていた。そして昨年、念願かなって独立したと聞いて、ようやく実現した訪問。久しぶりに見るHさんはやはり、明るく気さくな人だった。 さて、初訪問の「保志」で味わうのは、やはりマスター自慢のカクテルしかあるまい。フルーツが何があるか尋ねた後、僕は「ストロベリー・マティーニ(写真右下)をお願いします」と頼む。 普通の関東のバーテンダーならここで、「かしこまりました!」とだけ言うだろうが、Hさんは「ストロベリー・マティーニ、いっちゃいますかー?!」と少しおどけたような声で、コミカルに受け返す。関東のというより、大阪のバーテンダーのノリに近い。それも、僕が親しみを感じる理由かなぁとも思う。 従業員のバーテンダーさんとあれこれ話し込んでいるうちに、気が付けば午前0時半頃に。そろそろ今夜の締めにかからなければと、「レッド・アイ」(ビール&トマトジュースのカクテル)を注文する。「レッド・アイ」もHさんが作ると普通のレッド・アイではなくなる。 Hさんは、ボストン・シェーカーを取り出し、グラスの方に生トマトを8つくらいに切って入れ、ペストル(すりこぎ)で潰し始めた。そしてスパイス類を加え、シェーカーに移して一気に振る。それを別の大型ビア・グラスに半分ほど移し、冷えた生ビールをゆっくり注ぎ、優しく混ぜる。 7割ほど満たした後、さらに残りの3割ほどを同じ動作で作り、完成させるという手の込んだやり方。出来上がりはクリーミーで、美味しいったらない。さすがHさんの「レッド・アイ」は絶品。どんな客にも手抜きしないサービス精神が嬉しい。だからこそ、今夜も「保志」は、銀座という激戦区で客が絶え間ないのだろう。 という訳で、東京BAR巡りもめでたく終了(計6軒はちょっとハードだったかな?)今回お邪魔したくて実現しなかった店もいくつかあるけれど、それは次回の楽しみにとっておこう。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】
2006/02/22
コメント(14)
-

東京BAR巡り(上)/2月19日(日)
久々に週末の東京出張。本来は1泊2日だったのだが、1日目の仕事が夜遅くまでかかってBAR巡りには少々時間不足ということもあり、身銭を切って2泊してきた(長くなるので、上下2回に分けて記します。今回はまず1日目のご報告)。 今回の出張の最大のお仕事は、会社の06年度の予算調整。東京以外に、札幌、名古屋、大阪、九州(小倉)の予算担当者が集まった。景気がいまいちのため社の財政事情もパッとしない。だから、経理当局から数%くらいの予算削減指令が来るぞと覚悟はして行ったが、意外や意外、削減要請額は0.5%ほどで、拍子抜け。逆に、「これっぽっちの削減で大丈夫なのかなぁ」と心配してしまう。 でもまぁそういう訳で、会議は紛糾もせずにすんなり終わり。夕食は会社近くのこじゃれた居酒屋さんで。僕は、9時半くらいで皆と別れて、早速銀座へ。1日目の夜は、とりあえず3軒がノルマ。 まず以前から行きたかった「幻の桜」という8丁目のBARへ(写真左=何も書いてない超重~い木の引き戸。あまりに重いのでお休みかと思った)。ここはブレンディドでもモルトでもとくかく超マニアックなものばかり置いていることで、通の間では知る人ぞ知るBAR。 最初は都内・三軒茶屋で出店したが、5年ほど前に銀座に移転。おかげで僕も行きやすくなって嬉しい。店内は大きな1枚板のカウンター(白木で、ブナだったかな?)があり、バック・バーの棚も同質の白木。いわゆるオーセンティックBARの造りではないんだけれど、それはそれで心地よい。 セーター姿で、想像してたより若い(ような)マスターのIさん。一見気むずかしそうな印象を感じたが、喋ってみるととても気さく。料金はノー・チャージなのだが、超マニアックな酒が故に、基本的にショットで4000円未満のものは置いていない。しかし、すべての酒がハーフ・ショットで味わえるので、ただ、マニアックな世界を体験してみたい僕のような者にとっては、2杯飲んでも4千~5千円だから、それはそれで、良心的かもしれない。 「幻の桜」で味わったのは、「Old Mull」という1900年頃(今から100年以上前!)のブレンディド(写真右=見よ、この凄いラベル)。相当アルコール分がへたっているかぁと思ったが、意外としっかりしたボディで、麦の香りもよく出ていた。 もう1杯は、1960年代の陶器ボトルの「Spring Bank」(写真左=グラスもすべてアンティークもの。そのこだわりが嬉しい)。こちらはシェリー樽熟成。昔のバンクの良さがにじみ出ている。 2杯飲んで4500円をお支払いして、2軒目の老舗BAR「Brick」(写真右)へ。場所は「幻の桜」からもすぐそば。ここは20年くらい前から何度かお邪魔しているのだが、ここ6、7年はご無沙汰していたので、ドアを押すのはほんとに久しぶりだ。 ところが金曜の夜とあって、超満員。「これはちょっと、だめかななぁ…」と思ったたら、従業員の方が「地下の方へご案内いたします」と優しく声をかけてくれた。 何度も来ているのに、地下もあるとは知らなかった。あぁ不覚。地下の方も、8~9割の入り。良心的な価格設定や、1人でもグループでも来やすい雰囲気、キャパの広さ、ロケーション等が支持されているようだ。僕は、ここでジン・リッキーとフェイマスの水割りを頂いて、次なる店へ。 ところが3軒目に考えていた7丁目のBARは満席(それもほとんどが女性!)。やむなく、久しぶりに彼の顔を見てみようか、と同じ7丁目にある「Talisker」というBARへ(写真左=目印はビル1階の店の看板灯)。「Talisker」はオープンした98年に、友人に連れられて来て以来、すっかり気に入ってしまって、たびたびお邪魔している。 気さくなオーナー・バーテンダーのUさんは、今年40歳。僕が大阪でよく行くBARのバーテンダーたちとも懇意であるという不思議な縁もあって、最初から意気投合してしまった。 「Talisker」の自慢は2000本はあるかというモルト、そして、「若きモルト博士」の異名を持つUさんの博識ぶり。博識だが、決して自分からあれこれウンチクを垂れるようなタイプではなく、話術はあくまで控えめでスマートだ。 この夜「Talisker」で頂いたのは、いずれもボトラーズものの「Ardmore」(写真右=写真映り悪くてすみません)と「Tamnavulin」(写真左)。前者はピートがよく効いたアイラ・タイプ。ガツンとくる旨さ。 後者はシェリー樽熟成の22年もの(確か70年代だったかな)、嫌な苦みもほとんどなく、とても奥行きのある味わい。チョイスはすべてUさんに任せたが、さすが、僕の好みをよく知ってくれている。 ウイスキーマガジン・ライブの話やパブデ・ピカソさんの絵の話(「僕もあんな絵、描いてみようかなと思ってるんです」とUさんも言ってましたぞー)などで盛り上がっているうちに、スタートが遅かったこともあり、時間も午前1時ごろに。明日もハードな日程の予定なので、「では、この辺で」とUさんに別れを告げる。 ホテルまでの徒歩での帰り道、小腹がすいた身に、ところどころにあるラーメン屋のにおいで腹がきゅんと鳴る。でも、ダイエット中の身としては「いかん、いかん」とぐっと我慢(腹が減って寝付きは少々悪くなったけれど…)。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】
2006/02/19
コメント(12)
-

チック・コリア:陽気に、自由に、軽やかに/2月16日(木)
久々にジャズの話題に戻る。ジャズ・ピアニストとしては、以前、ビル・エバンス、 キース・ジャレット、 オスカー・ピーターソンを取り上げた。この3人は今も僕の憧れの人であり、永遠の目標。 そして、エバンスやキースとくれば、次はやはりチック・コリア(写真左)を取り上げざるを得ない。1941年生まれのチックは、キース(1945年生まれ)やハービー・ハンコック(1940年生まれ)らとほぼ同世代。同じ頃デビューして、3人とも今日まで、第一線で精力的に活躍し続ける。 僕がチックを聴き始めたのは遅かった。初めて聴いたレコードは、ご多分に漏れず、名盤「リターン・トゥ・フォーエバー」(写真左中=1972発売)。それも、聴いたのは発売から数年経ってからだった。 「クロスオーバー」という言葉を生むきっかけとなったこのアルバムは、センセーションを巻き起こし、驚異的なセールスを記録した。その華麗な指さばき、斬新な音づかいは、今も新鮮だ。 出会いがこのアルバムだったから、ジャズと言うより、どちらかと言えば、フュージョンのキーボーディストのような印象が強かった。そして、ジャズに詳しい友人から、実はジャズ・ピアニストとしても凄い人なんだということを教わる。 彼から教えてもらい、当時聴いたアルバムは、例えば、「ナウ・ヒー・シングス、ナウ・ヒー・ソブズ」(写真右上=1968年)や「ピアノ・インプロヴァイゼーション」(1971年)、 「マッド・ハッター」(1978年)。「ナウ・ヒー…」はリーダー・アルバムとしては2枚目だが、実質的にチックの出世作と言っていいアルバム。今もジャズの名盤の1枚として、必ず名前が挙がる。 チックのピアニズムは素晴らしいし、有名なスタンダードを弾いても実に自由奔放。シンプルなように見せて、実は結構お遊びもする。原曲のフレーズはどこへいったのかと思うくらい、大胆なアレンジ。一時はフリー・ジャズにもはまっていた。 その後、チックは「エレクトリック・バンド」を結成し、ピアノよりもキーボードを弾くことの方が多くなった。時代の一歩先を行くようなサウンド、アレンジには、僕は正直言って、あまり付いていけなかった。 だがチックはやはり、ジャズ・ピアニスト。その後も、キーボードに戻りつつ、ピアノから完全に離れることはなかった。1989年発売の「スタンダーズ・アンド・モア」(写真右)で、アコースティック回帰したチックは、「自分の原点はアコースティック・ピアノだよ」と言うかのように、2000年にはソロでのスタンダード・アルバムもリリース。 チックの素晴らしさは、その音楽性の幅広さ。モーツアルトのコンチェルトを弾くかと思ったら、フュージョンやソウル、ロック分野のミュージシャンとの共演も欠かさない。昨年のグラミー賞授賞式のパフォーマンスでは、ラッパーのEMINEMと共演し、度肝を抜かせた。 チックはその自由奔放な演奏が故に、僕にはほとんど手が届かないピアニスト。エバンスや、キースの一部の曲は、まだ僕でも頑張れば手が届くものはある。しかし、チックの真似は無理だと僕はあきらめている(写真左下=2003年に発売されたチックの音楽活動40周年記念コンサートのライブCD。豪華ゲストとの共演が話題に)。 チックはことしで音楽活動45周年。誕生日(6月12日)が来れば65歳だが、願わくは、これからも素晴らしいフレーズを紡いでいってほしい。次回、ブルーノートのような小さなライブハウスにやってきたら、生チックを一度見て(聴いて)みたいとも思っている。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】【追記】出張で2日ほど留守をします。コメントへのお返事は遅くなるかもしれませんが、お許しください。
2006/02/16
コメント(6)
-

歴史に残る、人々に愛される建物をつくりたい/2月13日(月)
BARの内外装ではないけれど、前回に続き、少し建築の話。僕はウィリアム・メレル・ヴォーリズ(1880~1964)という建築家が好きだ。明治38年(1905)に来日し、大正から昭和にかけて、日本各地に素晴らしい建築を数多く残した偉大な人。 彼の設計した温かみのある建物は、今も人々に愛され、歴史的にも高い評価を得ている。その代表作でもある大丸百貨店・心斎橋店(写真左=1922~33年にかけての建築)など、僕は日本の百貨店建築の最高傑作だと思っている。 高度成長&バブル経済が日本人に残した愚は、古い物はなんでも壊して建て替えればいいと思うようになったことだ。最近は、古い建物を生かしながら建て替える手法も増えたが、完成した建物をみると、建築家のセンスを疑うミスマッチも目立つ(例えば、その最悪の例が神戸地方裁判所=写真右下。「何考えとんねん!」という見本)。 実は昨年の9月から、社内で変わった職場は予算の策定・執行・管理がメインの仕事だが、社の出先の建物を定期的に建て替える際、建築業者を選定し、設計者らとともに相談しながら改築を進め、そして什器備品も選定・購入していくのも重要な業務になっている。 そして現在は、兵庫県内で鉄筋コンクリート3階建ての出先拠点の建て替えプロジェクトが進行中。施工業者さん(Z社)、設計者さん(N設計)、CMさん(設計監理=U社)らと、月に1~2度は現場見学をし、現場近くの会議室で、工事進行に合わせて細かい部分を協議している。 着工は昨年の8月。完成は3月末。現在工事は追い込み段階に入っている。施工業者の方や建築士の方とこれほど密接に相談しながら、一つの建物をつくりあげていくのは初めての経験。建築士の方もまだ30歳前後の若い方だが、センスのいい、歴史に残るいいものをつくろうという意気込みにあふれている。 外壁のレンガ(茶色系)は特注なのだが、色や焼き具合について、我々の要望を取り入れて複数の業者に何度も試作させ、作り直してくれた。「質感イメージが近いレンガだからぜひ見てほしい」と彼の会社が手がけた兵庫県立芸術文化センター(西宮北口)にまで我々を連れて行った(写真左)。 時には、広島にあるレンガ工場まで行って、焼き上がったばかりの重いレンガ見本をリュックにかついで持って来てくれたり。その情熱にはほんとに頭が下がった。 建物内部の展示物のステージ(台)についても、当方は既製品の安物でいいと考えていたが、彼は特注の自家製にこだわった。材料や色、塗装などを何度もやり直し、細かく変えられた。「(展示物に)隠れてほとんど見えない部分だから、そんなにこだわらなくてもいいじゃないか」と素人は思うのだが、建築家には建築家のこだわりがあるのだろう(予算は限られているのでヒヤヒヤだが…)。 バーテンダーも、建築家もそうだが、そんなこだわりがある人が好きだ。今回の建物は、とくに理由(わけ)があって、「50年後、100年後でも評価に耐えられるものにしよう」という共通認識で一致している。そして、きっとそんな夢が実現できそうな気がする。 ヴォーリズとまではいかないが、僕も、自分の手がけた建物が地域の人々に愛され、可能な限り末長く活用されていってほしいと心から願う。そのためにも今は、後世の人々に恥ずかしくないよう、完成まで全力を尽くしたいとと思っている。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】
2006/02/13
コメント(11)
-

「酒朱」生みの親と嬉しい出逢い/2月10日(金)
「このBARを訪ねてみたい」と思うきっかけは何だろうと考える。雑誌や本、インターネットやブログでの情報、友人や同僚の口コミ、バーテンダーからの紹介、その店の前をよく通っていて気になっていた(ごくまれだけれど…)等々。 情報はいろんな形で僕に届く。そして与えられた情報の中から、どこかひっかかるところはないかを、探す。探すというより、そんな「ひっかかり」は探さなくても、向こうの方から僕にひっかかってくれる。 「ひっかかり」はいろいろある。オーナーやバーテンダーその人(技術的なことも含めて)、お店が積み重ねてきた歴史、お酒の品揃え、お店の雰囲気、お店のポリシー、客層、料金体系、ロケーション…等々。 バーテンダーのプロフィールやお店の歴史、品揃え、料金体系、ロケーションなどは、文章から与えられる情報からある程度は分かる。ただし、バーテンダーの人柄は行間から読み取るしかないし、お店の雰囲気は掲載された写真から想像力をめぐらせるしかない。 情報誌に紹介されるお店の写真は、ほとんどが上手く、温かい感じに雰囲気良く撮ってある。だから昔は、写真だけみて感じがいいなぁと思って、行ってみたらがっかりということも少なくなかった。 しかし、長年そういう経験をしていると、1枚の店内の写真の細かい部分から、かなりいい確率で雰囲気のいい店かどうかが読み取れるようになる。読み取るポイント(基準)が何かは、言葉ではうまく表現できないのだけれど、最近では、写真にインスピレーションを得て訪ねたBARで、失敗だったという経験はほとんどなくなった。 バーテンダーあってのBAR。だから、もちろんバーテンダーがBAR選びの最初の基準であるべきだ。しかし時々、写真で見たお店の第一印象にすごく惹かれて、行ってみたいと思うことだってある。 「写真先行」で出合ったBARの一つで、僕が今も愛してやまない店として、大阪キタの「酒朱」というBAR(写真左上= (C )May Company )がある。「酒朱」は先般、「Peat」とその名を変えて再出発(5月30日付の日記でも触れた)したから、正確には「あった」というべきなのだろう。幸い、内装やインテリアはほとんど「酒朱」時代のまま。「酒朱」が大好きだった僕には、とても嬉しい。 そんな「酒朱」の内外装設計に携わった建築家のMさんが先日、偶然、僕のブログを訪れてくださった。BARでお酒を飲む際、そこを設計した建築家のことを考えることはまず、ない。しかし、この「酒朱」は例外の1軒だった(かつてミナミにあった伝説のBAR「be-in」=杉本貴志氏の内装設計=も然り)。 BAR造りに「和」を取り入れるブームなどまだなかった時代。阪神大震災の年(1995年)に、「酒朱」はオープンした。看板も何もない高さ1.5mほどの木戸を初めて開けたとき、どんなに勇気が要ったことか。 店内は昨今の薄っぺらな和風BARとは一線を画している。しっとりとした落ち着きにあふれて、重厚なバー・カウンターには温かいぬくもりがあった(写真右=店内奥のコーナーには素敵なテーブル席が一つ (C )May Company )。 関西の人なら分かるが、「酒朱」のある大阪・梅田の東通り商店街のはずれは、東京で言えば、歌舞伎町のような一角。猥雑で、怪しげな雰囲気が満ちた街。そんな界隈にまるでエアポケットのように「酒朱」はあった。 そんな場違いな「違和感」も僕は好きだった。店で、会社関係の人間に出会うことなどまずなかった。文字通り、隠れ家として僕は使った。そんな「酒朱」が大好きで、「Peat」と名を変えた後も、僕は時々お邪魔する。 「酒朱」の生みの親のMさんと「出逢える」とは、夢にも思わなかった。何かのご縁すら感じる。きっと、あの酒朱の内装(インテリア)のように温かい方なんだろうなぁと想像する。ブログがなければあり得なかった出逢いが、また一つ生まれた。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】
2006/02/10
コメント(16)
-
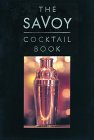
元祖・ギムレットを飲んでみた/2月7日(火)
ギムレット(Gimlet)と言えば、昔からBARで人気の高いカクテルの一つ。そのレシピは、ジン45ml、生ライム・ジュース15ml、シロップ少々というのが一応の定番。 すなわち、ジン3にライム1という辛口の比率が現代では好まれている。さらに辛口が好きな人には、4:1とか5:1とかいうレシピもある。僕もどちらかと言えば、辛口が好きなので、ジンの割合は多めがいい。 しかしある日、ふらっと立ち寄ったBARで、「ギムレットが最初できた時のレシピ、今とは違ったんは知ってますかー?」とバーテンダーから言われた。当初考え出されたギムレットは、現在のような辛口のものではなく、甘口だったというのだ。 1930年に出版された有名な「SAVOY COCKTAIL BOOK(サヴォイ・カクテル・ブック)」(写真左上)には、もちろんギムレットが紹介されている。 だが、そのレシピをよく読むと、プリマス・ジン2分の1、ローズ社のライムジュース・コーディアル2分の1とある(写真右=左がプリマス・ジン、右がローズ社のライムジュース・コーディアル)。 コーディアルとは、甘みを付けたジュースのこと。フレッシュ・ライムが手に入りにくかった時代につくられたという(なめてみると、ジュースと言うよりもシロップに近いような感じ)。 「へーっ、知らんかったよ」と言うと、そのバーテンダー氏、「うちに今ちょうど、プリマス・ジンもローズ社のライム・コーディアルもあるんで、作ってみましょか?」と。こちらも二つ返事で「ぜひお願い」と頼んだ。 出来上がったギムレット(写真左)は、バーテンダー氏は「ややライムは抑えめにつくった」と言うものの、正直言って甘~い! 日頃、辛口のギムレットに慣れた僕には、まったく別のカクテルに思える。食中、食後の酒というより、食前酒の趣。 でも、あの「長いお別れ」で、探偵フィッリプ・マーロウが飲んだギムレットは実はこのレシピだったとか。こんな甘いカクテルを味わいながら、「ギムレットには早すぎる」なんて、ハードボイルドなセリフがよく言えたものだなぁと感心してしまう。 「元祖・ギムレット」。甘口のカクテルが好きな女性なら、気に入るかもしれません。ローズ社のライム・コーディアルはあまり輸入されていないが、もし、材料が揃っているBARがあったら、皆さんも話のネタにぜひ一度味わってみてください。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】
2006/02/07
コメント(14)
-

最高のミステリー「容疑者Xの献身」/2月4日(土)
久々にミステリーの話題。と言っても、もうお読みになった方も多いと思うので申し訳ないけれど、先に直木賞を受賞した東野圭吾氏の「容疑者Xの献身」(写真)。 直木賞を取る前に、「このミステリーがすごい!2005年版」の国内部門で第1位にも選ばれた。この時から、久々に凄い作品が誕生したと注目してきた。直木賞でさらに注目が集まり、書店での売れ行きもとてもいいらしい(あるサイトの文芸書売れ筋ランキングでは、今週第1位)。 物語は、一見さえない高校の数学教師にして、天才数学者の石神を中心に展開する。ある日、マンションの隣に住む花岡靖子とその娘が、訪ねてきた前夫を殺してしまう。靖子に密かに思いを寄せてきた石神は、完全犯罪を目論んで、靖子らを警察の追及から守ろうとする。 靖子に対する思いはとても純粋。そして、天才的な才能を駆使して、完全犯罪のプログラムを組み立てていく。そんな石神の前に立ちはだかるのが、東野氏の探偵ガリレオ・シリーズでおなじみの物理学者・湯川、そして警視庁の刑事・草薙。 この4人による駆け引き、心理戦も面白いが、次々と予想を裏切る展開に、寝不足になること間違いなし。東野氏は「僕がこれまで考え出した最高のトリック」と言うが、決して奇をてらったトリックではなく、「言われてみればそうか」という理詰めのトリック。 ネタばらしになるので詳しくは書けないが、物語途中の一見、事件と関係ないような描写(場面)も手を抜かずきちんと読めば、最後に明かされる真相も納得できるだろう。読み終わった後は、ただ「やられたー!」のひと言。はっきり言って、最近読んだミステリーの中でもナンバー1かな。 そして、最高の推理小説なんだけど、ミステリーに名を借りた石神と靖子の恋愛小説としても、素晴らしい作品に仕上がっているのがにくい。「こんなピュアな純愛なんていまどきあるかな…」と思うほど。だから結末には、ほんとに泣かされます。 東野氏は大阪府生まれで、今年48歳。大阪府立大で電気工学を学んだ後、エンジニアとして勤務しながら推理小説を書き始め、1985年に「秘密」で江戸川乱歩賞を受賞。その後も「探偵ガリレオ」「白夜行」などの話題作を次々と発表している。だからキャリアはもう20年とベテランの域。直木賞は候補に挙がること6回目での念願の受賞だった(同じ関西人としても嬉しいなー)。 さて、この「容疑者Xの献身」。おそらくは映画化(またはドラマ化)されるだろうが、主役の石神は誰が演じるのがいいか。僕と連れ合いの意見は奇しくも一致して、オダギリ・ジョー。そして、靖子役は鈴木京香。湯川役は藤木直人。皆さんなら誰を推す? ※本の表紙画像はAmazon上のものを引用しました。Amazon.Japanに感謝いたします。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】
2006/02/04
コメント(8)
-

今年も行ったぞ 「太陽酒造」蔵開き/2月1日(水)
今年も行って参りました。明石の「太陽酒造」(写真左上)の蔵開き。好天の日曜。明石市中心部から山陽電車と徒歩で30分ほど。江井ヶ島(海に浮かぶ島ではありません。念のため)という、のどかな所にある蔵元を訪れた酒好きは、100人近くはいたかなー。昨年の日記はこちらに。 友人が主宰している同好会の新年恒例イベントとして、もう10年近く参加しているだろうか。太陽酒造は江戸末期の創業。家族経営で月産約800本という、おそらく日本で一番小さい酒造メーカー(公称「百石」)。 蔵開きでは、純米吟醸の生原酒2種、透明なタイプの「たれくち」(写真右上)と、にごりタイプの「おり酒」(写真左下)がほぼ飲み放題。「たれくち」は酒船搾りという手間のかかる手法で丁寧につくられた辛口。「おり酒」は普通のにごりのように極甘口ではなく、ほのかに甘いという程度のすっきりした味わい。 出来たての新酒が味わえるのも嬉しいが、酒の肴には寿司や、イイダコの煮付け、漬け物の盛り合わせ、粕汁、湯豆腐、かわきもの等が人数分出て、お土産に酒粕まで付く。これで2千円はホンマに安い! 蔵開きの宴は醸造所前の広場のような、屋外のスペースで開かれる(写真右下)。この時期、当たり前だけれど結構寒い。寒い中で、新酒を冷やで飲むもんだから、これはよほどの酒好きでないとちと辛い。体を温めようとピッチを上げるから、酔うのも早い。 去年あまりにも寒かったので僕と連れ合いは、毛糸の帽子&携帯用カイロ(体用&靴用)、それに熱いお茶入りの水筒持参という、ほぼ完璧な防寒準備のうえで参加した。おかげで今年は寒さなど平気で、お酒を存分に味わえたぞー。 蔵開きの帰り、一部のメンバーはさらに明石駅前の、日曜も営業している居酒屋へ「転戦」したようだが、僕らは相当出来上がってしまって、まっすぐ帰宅。お土産にはもちろん「たれくち」と「おり酒」、そして、自家製の奈良漬も購入。 夜は、お土産(おまけ)でもらった酒粕をふきんに包んで、お風呂に入れて、即席の「酒粕風呂」。これが、お酒のいい香りが漂い、体も温まって、肌もつるつるになって、とても幸せな気分になれる。 どうですか、皆さんも、一度太陽酒造の見学へぜひお越しください。蔵開きのようなイベントの時以外でも、製造直売はしています(ネットでの通信販売をしている酒屋さんもあります→YahooかGoogleで検索してみてネ!)。【太陽酒造】兵庫県明石市大久保町江井ヶ島789 電話078-946-1153人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】
2006/02/01
コメント(10)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-

- やっぱりブルゴーニュ&シャンパーニ…
- ジャッキー・トルショー・マルタン /…
- (2025-11-16 15:33:26)
-
-
-

- ビールを語ろう
- サントリー生ビール 名前・似顔絵入…
- (2025-11-16 17:50:20)
-
-
-

- 焼酎は美味い
- だいやめはお湯割りの時季ですなぁ~
- (2025-10-31 08:55:40)
-







