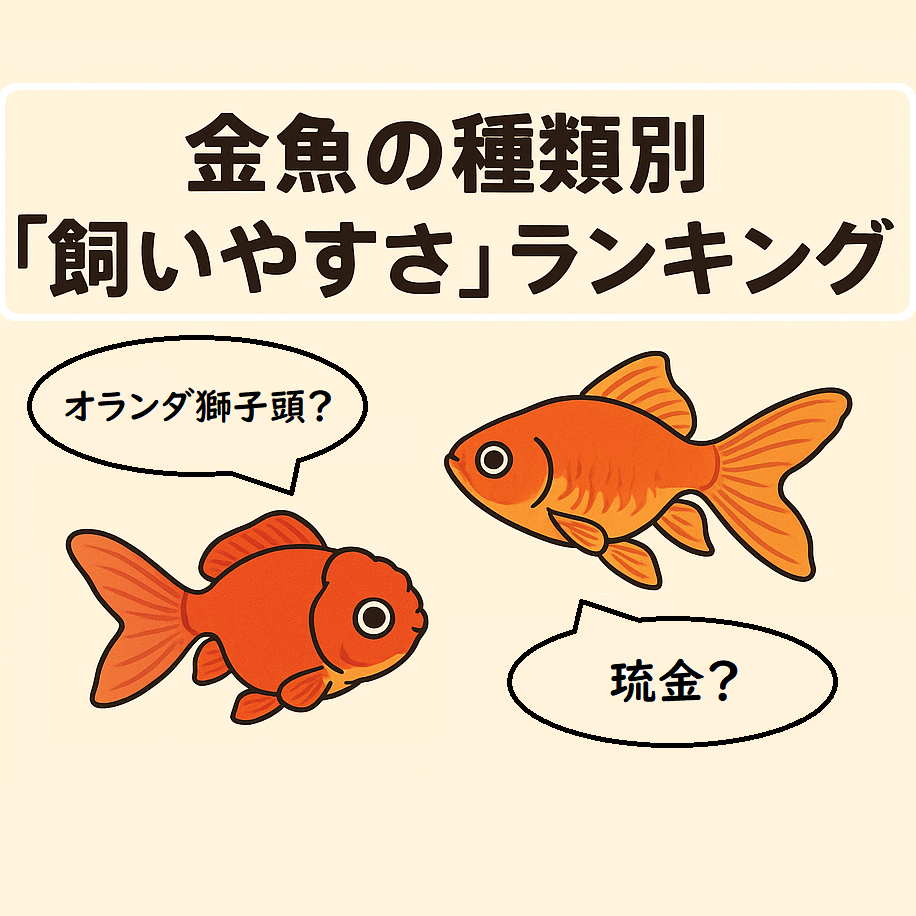2016年12月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

貧血
いよいよ大晦日。やってきてしまいました。このプログに足を運んでくださる皆さま、今年1年有難うございました。こんなチンケなブログでも沢山の方のご訪問をいただき、とても感謝しています。また来年もヨロシクお願いします。たぶん、まだ死なないと思いますので(笑)私は健康診断の度に貧血の気があると指摘されます。特別に薬を飲むほどぢゃないけれど、血の量が足りないみたいです。大事な式典中に貧血で倒れてしまった兵隊さん達、この人たちだって人の子ですものね。そりゃあ、ずぅ~っと同じ場所で立ちっぱなしでは、いくら鍛えている兵隊さんたちでも貧血で倒れてしまうのしょ~がない。そんな画像を集めてみました。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 31, 2016
コメント(7)
-

ペンタックスの天体望遠鏡
口径150mm、集光力459×。ペンタックスが誇る4群4枚構成SDP光学系の最高峰。圧倒的な光学性能。これは2008年に生産を開始し、翌年に生産終了したペンタックスが作った天体望遠鏡「PENTAX 150SDP」のカタログに記載されているうたい文句です。さらに続けて...6×7判をカバーする広いイメージサークル。追尾誤差±3.5以内の高性能MS-55z赤道儀。同架重量40kg の高剛性仕様。両軸500倍速のステッピングモーター制御。暗視野照明付の9~18倍正立ズーム付の極軸望遠鏡は南北両半球に対応。六角レンチ1本で組み立て可能。優れた機動性を発揮。インテリジェントコントローラーで高度なパソコン制御を実現。 興味のない方にはチンプンカンプンですが、この圧倒的な、まるでバズーカ砲みたいな個体を見せられると...これはペンタックスが本気で作った天体望遠鏡と云うふれこみの商品で、価格がなんと511万円!日本国内にはこれを所有している人が4人居るそうです。しかしこのクラスの望遠鏡だと揺れると観測できないため、コンクリートでこの望遠鏡専用の土台を建設して設置したり、自室のパソコンと望遠鏡を接続してリモートコントロールで星を追っかけたりと追加費用もハンパありません。もはや何が何だかわからないほどの巨大さ。スケール感がおかしい。デジカメの超望遠レンズぢゃないですよ~これは「PENTAX 150SDP」のファインダーです!ファインダーだけでもそこらの望遠鏡サイズ。こっちが本体の接眼部。肉眼では詳細が全くわからないほど遠くのものがらくらく見えます。逆方向から除くと見ている人の目がはっきり見えます。左側のファインダーで大ざっぱな位置を決めてから本体の鏡筒で見ると云う仕組みになってます。複雑そうに見えますが、なんと六角レンチ1本で組み立て可能。もちろんデジカメの装着もワンアクション。東京ビッグサイトのはるかかなたにいるコンパニオンさんを撮影してみると...当然ながら相手からこちらを感知することはこの距離だと不可能。現在、ペンタックスは全天体望遠鏡事業から撤退しています。海外ではまだ売っているかも知れませんが、国内ではシェアーが伸びないようです。技術はスゴイけど、売り込みがヘタなのか?はたまたもともと需要の薄い業界なのか?しかし日本の一流企業がちゃんとしたものを作ると、やっぱりちゃんとしていると云う証拠ですね。中国や韓国製品では絶対見れない。こう云う製品は儲けを度外視して、企業の顔として創り出すのでしょうね。最後にこの望遠鏡が"動いている"動画を。今の望遠鏡はリモコンで動かすのですね。結構なめらかに動作し、しかも思っていたよりもすばやく動くのでびっくりです。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 30, 2016
コメント(5)
-

アイヌの文化
現在、「日本の」アイヌの人口は全く不明です。長年にわたって迫害を受けてきたため、血筋を明かすのをためらったのと、一般の日本人との婚姻が多くなって紛れ込んでしまったからです。2006年、北海道内で調査に応じた者のみで23,782人でした。ここで「日本の」とあえて断わったのは、アイヌは北海道を中心とした日本にだけ住んでいるワケではないからです。1855年に取り交わされた日露和親条約での国境線決定により、一部がロシア国民となったからです。驚くべきことに、近年の遺伝子調査では、アイヌとDNA的にもっとも近いのは琉球民族なんです。次いで大和民族で、大和民族とアイヌ人の共通性は約30%程度です。同じ日本人でありながら、私はアイヌの文化と云うものを全く知りません。アイヌの人々はひどい差別の中で生きてきたので、ことさらにアイヌ文化を隠そうとしたのですね。あるアイヌの人の言葉「民族としてのアイヌはすでに滅びたと言ってよく、厳密にいうならば彼らはもはやアイヌではなく、せいぜいアイヌ系日本人とでも称すべきもの」なんか悲しいですね。しかし都会に住んでいるアイヌの人たちは独自文化こそ廃れてしまいましたが差別なんて無いと云ってるし、どっちが幸せなのか...アイヌの文化の紹介がひろく行き渡らないのは、アイヌ語には文字がないからかもしれません。アイヌ語はかつて北海道、樺太、千島列島で暮らしていたアイヌ民族の言語であり、口承で受け継がれていた言語のため文書として残っている記録がほとんどないのです。2007年の調査・推定では、当時生存していたアイヌの中で、アイヌ語を流暢に話せる母語話者は10人しかいなかったそうです。アイヌ語を母語とする人は、千島列島では既に消滅し、樺太でもおそらく消滅していて、残る北海道の母語話者も平均年齢が既に80歳を越えているそうです。このためアイヌ語は、2009年、ユネスコにより「危機に瀕する言語」として、最高ランクの「極めて深刻」の区分に分類され、数年後には母語話者が消滅すると推察されているのです。下の画像にある「古釜布(ふるかまっぷ)」はアイヌ語で「丘の上にあるもの」を指します。国立国語研究所のアンナ・ブガエワ特任准教授と千葉大の中川裕教授らのグループが、ネット上でアイヌ語で民話を読み上げてくれるサイト「アイヌ語口承文芸コーパス」をオープンさせました。「アイヌ語口承文芸コーパス」のサイトメニューから作品名(全10編)を選択。センテンスごとに番号が振られているので、番号の下のスピーカーのマークをクリックすることでその音声を聞くことができます。この音声は、かつて北海道でアイヌ民話を語り継いでいた沙流川流域出身の木村きみさん(1900年~1988年)のアイヌ語沙流方言だそうです。アイヌ語には文字がないため、聞き取ったことばはカタカナとローマ字で表記され、そこに日本語と英語の訳と単語ごとの詳細な解説がつけられています。アイヌの風俗を描いた図版は18世紀~19世紀にかけて多く出されています。残念ながら、その多くは散逸して多くはアメリカのウィスコンシン大学が所蔵している約40冊の本のコレクションに見られます。日本人によるアイヌ民族の18世紀~19世紀の最も初期の描写を描いています。先ずはカラフト探検で有名な間宮林蔵の「北蝦夷図説」から。なんかアイヌと云うより、中国文化の影が色濃く出ていますね。お次は新井白石の「蝦夷志(えぞし)」から。蝦夷志は、日本最初の本格的な蝦夷地の地誌で、後の蝦夷地研究の先駆をなしたものです。新井白石が 享保5年(1720年)に松前藩の情報や内外の諸書を参考にして作成しました。この写本の巻末には十余枚の貴重な彩色アイヌ風俗画が付けられています。画家は不明ですが、アイヌの衣服など絵画が細密に描かれており、当時のアイヌの風俗を知るうえで重要な文献になっています。次は松浦武四郎の「石狩日誌」からです。松浦武四郎は幕末から明治にかけての探検家で浮世絵師です。「北海道」という名前を考案したのはこの人です。次に近藤重蔵の著した作品から。近藤重蔵は間宮林蔵、平山行蔵と共に“文政の三蔵”と呼ばれていました。最後に村上島之丞の「蝦夷島奇観」から。村上島之丞は江戸幕府の役人で寛政10年(1798年)から数回にわたり蝦夷地探索の一員として、北海道、国後、択捉を踏査しました。間宮林蔵は村上島之丞の門弟の一人です。こちらの本は東京国立博物館に現存しています(非公開)。アイヌの酋長を描いた図。「夷名イコリカヤニ肖像ナリ。酋長(ヲトナ)トキイ三男」と明記され、有名なクナシリアイヌの酋長イコリカヤニの肖像であるとしています。酒造りの様子を描いた図です。シントコ(行器)に満たされた酒を女が手桶に入れようとしているところです。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 29, 2016
コメント(6)
-

素晴らしいデザインのオーディオ機器
25日にジョージ・マイケルが亡くなりましたね。大好きな歌手。まだ53歳の若さでした。死因は心不全だったそうです。ジョージ・マイケルと云えばポップデュオ「ワム!」の時代に発表した「ラスト・クリスマス」が世界的なヒットになりましたが、1984年の作品だったのですね。この年に1度だけ、私は「ワム!」の仕事をしたことがありました。大阪公演。このときは私もまだ若かった(笑)しかしクリスマスソングで一躍世界のトップスターになった歌手がクリスマスの夜に息を引き取ると云うのは何と云う偶然でしょう。私はどちらか云うと、ソロシンガーになってからのジョージ・マイケルの方が好きでした。同性愛者であることを公表したり、大麻を吸って運転して事故を起こし実刑判決を受けたりと何かとお騒がせな人でしたな。しかし歌は素晴らしい。1996年に発表した「Jesus to a Child」でもど~ぞ。さて今日は素晴らしいデザインのオーディオ機器でもご紹介しましょうかね。どれも日本には輸入されてないので、欲しいと思った方は直接輸入しか方法がありません。先ずはYakir Buaron と云うデザイナーが製作したターンテーブル(レコードプレーヤー)もうこれ以上シンプルにしようがないほど削ぎ落とされたデザイン。カートリッジはリニアトラッキングアームで直線的に動くみたいです。ターンテーブル部分は"糸かけ"式でモーターからの不要な振動が伝わりにくい構造になってます。なんだかまな板に乗っかってるように見えますね。デザイナーのYakir Buaronはイスラエルの人です。お次もターンテーブルですが、Gramovox と云うメーカーの驚くデザインのターンテーブル。なんとレコードを垂直に立てて操作するのです。しかもスピーカーまで内蔵してます。Gramovox からはこんなスピーカーも発売されていました。なんと古典的なグラモフォン・ホーンのスピーカーです。1920年代のR3 Magnavoxホーンを3:4の比率でスケールダウンして再現したものらしい。しかもUSB入力も備えているので、例えばPCからの音楽再生も可能です。またBluetooth も備えているので、音楽プレーヤーやスマホとの接続も可能。リチウムイオン電池を内蔵しているので、まったくコードなしで使えます。ネット検索してたら、日本のネット販売業者で1社だけこのスピーカーを扱っていました。お値段は83,390円でした。お次もこれまた渋いデザイン。Symbol Audio と云うメーカーの音楽コンソールですが、ひと昔前のステレオセットのコンセプトを受け継ぎながら、もっとモダンでデザインコンシャスな造りになっています。アメリカンウォールナットのケースが綺麗ですね。次は先ず画像をご覧になってください。これ何だと思われます?実はワイヤレス・スピーカーなんです。しかも...浮揚する!量子浮揚スピーカーと呼ばれるもので、リチャード・クラークソンと云う人がデザインしました。「雲」の内部にはスピーカーの他に、LEDライトが仕込まれてて、音楽に同期した照明が点滅するそうです。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 28, 2016
コメント(8)
-

世界最古のアニメ
世界最古のアニメと云うものはイランで発見されました。1970年代にイタリアの考古学者によって発見された5200年前のボウルに描かれたヤギの絵です。と云っても、実際に動くのではなく、ヤギの動きを表した5枚の絵がパラパラマンガを1コマずつ横に並べたような感じで動きの想像できる絵ということで世界最古のアニメと云われているのです。このアニメでは木の葉をジャンプして食べるヤギの動作が5枚の絵で表されています。しかし考古学チームが発見した当初は、それぞれの絵に関連性があるとは認識されていませんでした。発見されてから数年後にイラン人の考古学者が研究して、初めてそれぞれの絵が連続していると云うことが分かったのです。その一連の画像を連続表示してアニメーション化されたものがこれです。1902年にジョルジュ・メリエスが製作した有名な映画「月世界旅行」では、ロケットが港に戻るシーンで、すでに切り絵アニメーション(静止した背景画の前で、船の切り絵を少しずつずらしてコマ撮りする)が用いられ、これが映画のコマ撮り(ストップモーション)によるアニメーションの最初とされています。アニメ作品としては、ジョルジュ・メリエスよりずっと以前、1892年にフランスで作られたエミール・レイノーの「哀れなピエロ」が本格アニメの最初の作品とされています。しかしレイノーの作品は純粋な意味での映画ではなく、テアトル・オプティークと呼ばれるゼラチンフィルムに別々に描かれた手書きの人物と背景をプロジェクターで同時にスクリーンに投影する装置によって上映されていました。1906年製作でアメリカのジェームズ・スチュアート・ブラックトン監督による「愉快な百面相」と云うものがあります。これは黒板に白チョークで描く実写と、そのコマ撮りを組み合わせた線画アニメで、この最後のピエロの部分では白い枠線の切り絵がチョークアニメーションと組み合わされて用いられているのです。世界最初の実写部分を含まない、純粋な"短編"アニメーション映画は、フランスの風刺画家エミール・コールによる「ファンタスマゴリ」で1908年に製作されました。世界初の純粋"長編"アニメーション映画は1917年にアルゼンチンのキリーノ・クリスティアーニによって製作されました。1914年、今日のアニメーション製作技法の元となるセル画によるアニメーション技術がアール・ハードによって開発されました。しかし当時、一般には背景を印刷した紙にペン描き、というのがほとんどでした。「クレイジー・カット」シリーズ(1916年)や「フェリックスの初恋」(1919年)など。またアルゼンチンやドイツなどでは、切り紙や人形アニメが盛んに創られていましたた。アジアでは1941年に中国において万籟鳴と万古蟾の万氏兄弟監督で公開された「西遊記 鉄扇公主の巻」がアジア初の長編アニメーション映画とされています。1942年には戦時下の日本にも輸出され、当時16歳の手塚治虫に影響を与えると共に、海軍省に長編アニメーション映画「桃太郎 海の神兵」(1945年)を制作させる動機となったのです。日本では大正期にかけて外国から輸入されたアニメーション映画の人気を受けて、天活(天然色活動写真株式会社)で下川凹天が、小林商会で幸内純一が、日活で北山清太郎が独自にアニメーション制作を開始しました。1917年(大正6年)下川凹天が手がけた短篇アニメーション映画「芋川椋三玄関番の巻」が公開された国産アニメーション映画の第1号となりましたが、他の2人の作家との差は数ヶ月程度でそれぞれ独自の方法で製作しているため、3人とも日本アニメーションの創始者として扱われています。3作品はいずれも1917年に公開されましたが、現存するのは幸内純一の「なまくら刀」のみです。日本でも諸外国と同じく当初作られていたアニメは数分程度の短編映画が多かったし、作り手も個人もしくは少人数の工房での家庭内手工業に準ずる製作体制で、生産の効率化を可能とするセル画の導入も遅れていました。太平洋戦争を迎えると、戦意高揚を目的とする作品が制作され、日本初の長編アニメーション「桃太郎の海鷲」(19422年)や前述の「桃太郎 海の神兵」などが製作されました。他には戦時中にも関わらず叙情性が豊かなミュージカル仕立ての作品「くもとちゅうりっぷ」(1943年)がありましが、この作品は日本最初のフルセル(全セル画)アニメーションとなったのです。戦後、東映は1956年にアニメスタジオ「東映動画」を発足し劇場用アニメーション映画の製作を開始しました。そして製作されたのが日本初のカラー長編アニメ映画「白蛇伝」(1958年)で、この作品は海外にも輸出されましたし、ご覧になった方も多いと思います。1961年には手塚治虫が「虫プロダクション」を発足させました。そして虫プロダクションは日本で最初の本格的連続テレビアニメ「鉄腕アトム」(1963年)を製作したのです。最後に現代のCMですが、丸紅新電力 鳥獣戯画「出会い」篇をご紹介しましよう。なかなかによくできた作品です。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 27, 2016
コメント(6)
-

世界で最初の持ち運べるコンピュータ
タイトルから読み解くとノート・パソコン?いえいえこの機械がでてきたときは、まだノート・パソコンはできていませんでした。それどころかディスプレイは今みたいに液晶ではなく、ブラウン管!名前を「Osborne 1」と云います。「Osborne 1」の製造は1981年。アメリカではラップトップ・コンピュータの部類に属しています。1981年と云うと、レーガンがジミー・カーターの後継として第40代アメリカの大統領に就任した年で、中国の毛沢東のヨメ、江青に対し死刑判決が出た年です。そして ダイアナ妃がチャールズ皇太子と結婚した年でもあります。NECの初代PC-9801が出てきたのが1982年。マイクロソフトのWindows 1.0(10ではありません)が1985年です。これが「Osborne 1」です。Osborne 1の「オズボーン」は作った人の名前がオズボーン。そのまま使われています。価格は1,795$(約20万円)。重さは約11kg あります。日本では有名でありませんが、米州では極めて有名なPCで、国立アメリカ歴史博物館にも展示されてます。なんかやたらと画面が小さいでしょ。このマシンの一番の問題点は、この5インチの小さなディスプレイと容量が小さすぎて実際のビジネス用途では使い物にならないフロッピーディスク(片面単密度)にあったのです。宣伝ではミシンほどの大きさと重さで、旅客機の座席の下に納まる唯一のコンピュータとされていました。しかし重量はとても可搬型とは呼べない代物で、実際に持ってみると「両腕が肩から抜けそうに」なります。それでも当時としては革新的なコンピュータだったため、発表後の8ヶ月で11,000台を売り上げ、ピーク時の売り上げは1ヶ月で1万台に達しています。このコンピュータのOSはWindows でもなければMS-DOSでもありません。当時人気のあったCP/M 2.2(初代の開発は1976年です)と云うOSが動作。OS以外のソフトウェアも多数バンドルしており、それらを別々に買うと総額がマシン本体と同程度になります。今だったらメーカー製のパソコンを買うと、オマケのソフトがこれでもかと云うほどついてきますが、その先駆けをいってたのですね。このような販売手法は他のCP/Mコンピュータ業者も追随することになったのです。Osborne 1にバンドルされているアプリケーションソフトウェアにはワードプロセッサのWordStar、表計算ソフトのSuperCalc、言語処理系の CBASIC(英語版) と MBASIC(英語版) という当時人気のあったアプリケーションがありました。これらソフトウェアだけで通常販売価格は1,500$にもなります。しかし勝者の常で、Osborne 1は他のコンピュータメーカーに真似をされ、より低価格のコピー商品が出回わり出しました。結局「Kaypro II」というよく似たマシンがOsborne 1の人気を奪うことになるのです。なぜならOsborne 1が5インチのディスプレイなのに対し、Kaypro IIは9インチディスプレイと倍密度フロッピーを装備していたからです。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 26, 2016
コメント(5)
-

電話線の塔
約100年前のスウェーデンの首都ストックホルムには5,000本もの電話線が繋がれた巨大な塔がありました。1913年に電話線の塔としての役割が終わった後もストックホルムのランドマークとして保存されていましたが、1953年の火事によって消失したため残念ながら現在は存在していません。この塔は1887年に作られたものです。その塔に繋がれた電話線の数5,000本。その姿は非常にカオスそのものです。お城の様な雰囲気もある塔ですが、電話線が繋がれていた電柱の巨大版です。白く見えてるのが全部電話線です。なんか現代のインドあたりで見かける電線のメチャメチャぶりに相通ずるとこがありますね。これだけの電話線、どうやって維持していたのか不思議ですね。塔の内部はこんな感じになっていました。水平に取り付けられたアームにいっぱい"つぶつぶ"が見えるのは碍子のようです。クラッシクな車が並ぶ大通りから撮影した塔。記念撮影してたら、ちょっと強面の守衛さんがこっちを見ていました。塔のすぐ隣で火災が発生したこともありましたが、このときは塔はセーフでした。塔を上空から見るとこんな感じです。なんとも不思議な光景。塔と云うよりお城のような雰囲気を漂わしています。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 25, 2016
コメント(9)
-

映画の舞台裏写真
ほんとうは映画の舞台裏なんて気にせずに、映画そのものを楽しむのがイチバンですが、そこはそれ、ついDVDなんかでもメイキング映像を観てしまいます。でも最近の映画はSFXやCGのオンパレードで、俳優さんたちは何もない"グリーンスクリーン"の前で演技していることが多いのですよね。これは有名な「マトリックス」で30数台のデジカメを俳優を囲むように並べて同時撮影する装置。これによりストップモーションのようなシーンが360度の角度から写せるわけです。古いところでは「ジョーズ」。この頃はCGが未熟だったので、ほとんど実写ですね。いきおい実際の大きさのサメになってしまいます。「エイリアン」なんかは被り物が定番。エイリアンの手の部分はロボットの応用ですな。これはエイリアンの第1作目でラストシーンに登場するにゃんこと撮影の合間にたわむれるシガニー・ウィーバー。彼女もまだ若かったですな。「スター・ウォーズ」だと、やはりR2-D2役の今は亡きケニー・ベイカーが忘れられない。身長112cm でロボット役やったのですものね。しかしCG全盛と云っても、こんな困難な撮影が今でも行われていることもあります。「(バットマン)ダークナイト ライジング」の冒頭シーン。飛行機に別の飛行機で追いかけてきた悪党一味がワイヤーで飛行機に飛び移り、さらには標的の飛行機をワイヤーで宙づりにして最後に落下させるという迫力満点のこのシーンは実写のみで作られています。本物のC-130輸送機から飛び降りるスタントマン。ワイヤーを使ってスタントマンが別の飛行機に飛び移るところも実写です。宙づりにされた飛行機は、ヘリコプターでつられています。スタントマン顔負けの俳優さんと云ったら、この人をおいて語れないでしょう。トム・クルーズ。これは「ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル」でスタントマンを使わずにドバイにある世界一高い超高層ビル、ブルジュ・ハリファの頂上に登ったトム・クルーズです。このときの撮影のドキュメント映像はこちら。こっちは同じくミッション:インポッシブルの「ローグ・ネイション」で飛行中のエアバスA400Mの外壁にしがみつく有名なシーンのドキュメントです。いくら命綱つけてるからって、実際に飛行している機にしがみつくって、しかもこの時の撮影は3回も行われているのです。よ~やります。最後にあまり紹介されることない珍しい画像を。ホラー映画の古典(公開は1980年)にして傑作「シャイニング」の裏舞台を捉えた写真いろいろ。先ずは主人公が吹雪により外界と隔離されたオーバールック・ホテルで、家族3人だけの生活をしているハズなのに、狂気に蝕まれて、居るハズの無いホテルの宿泊客に混じってバーで酒を飲むシーン。カメラ近くに立つスタンリー・キューブリック監督とジャック・ニコルソンです。お次は「シャイニング」の中でも最も恐ろしいシーン。誰も居るハズのないホテルの廊下に突然すがたを現す「グレイディの双子」です。この姉妹はリサ・バーンズとルイーズ・バーンズと云う双子の子役。今は...こんなになってしまいました。こっちは存在そのものがホラー?(笑)中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 24, 2016
コメント(6)
-

現実ではありえない映画の世界
よくスパイ映画などで、サイレンサーを付けた拳銃を撃つと「プシュ」とほとんど聞き取れない音がして銃弾が打ち出されるシーンがありますが、あれってホントウなんでしょうか?実は銃口から火薬の燃焼ガスが噴出す以上、音は消せません。サイレンサーはただ音を"下げる"効果があるだけです。要するに火薬が爆発するときの衝撃波、サイレンサーはこの衝撃波を一旦受け止めてゆっくり外に出すことで、音を下げているのです。なので横から火薬ガスが漏れるリボルバーでは、サイレンサーはあまり意味がないわけです。効果としてはおよそ160デシベルの銃声を、120デシベル程度まで下げることが可能です。特に耳に鳴り響く高音域を除去することができ、体感的には元の音よりはかなり低く感じることでしょう。実際に拳銃にサイレンサーをつけて撃ってる動画がありますのでご参考までに。ことさらさように、映画でおなじみのシーンが、実は現実にはありえないことが結構あるのです。例えば高い滝などから飛び降りるシーン。目もくらむような高いとこから落下して着水したあと泳いで岸へ。って、現実には時速約128km 以上で落下すると致命的な事故につながります。60m の高さから落下すると、時速約193km 。確実に死ぬか、骨がバラバラ。漏れたガソリンに火のついたタバコを投げると引火する。よくギャング映画なんかで見かけるシーン。実際はタバコ自体が燃えていない限り、タバコの火だけではガソリンを引火させるには不十分なんです。静電気の火花はガソリンの蒸気に引火するが、煙草では容易に引火しないことが確認されています。また、煙草では容易に引火しないとしても、煙草に火を着けるためのライターの炎なら確実に引火することから、給油取扱所において喫煙することは危険です(消防庁)。アクション映画や戦争映画でよく出てくるシーンのひとつに「銃弾で車の燃料タンクが大爆発!」。現実にはガソリンに引火する可能性があるのは、空気の摩擦で弾丸自体が発火する特殊な銃弾だけです。ぢゃあ銃で鍵を壊すってのは?直射距離で撃っても銃弾では錠を壊せません。ショットガンならまだ可能性はあるけれど、銃弾の破片で自分が死ぬ公算の方が高いです。映画では犯人逆探知のために会話を引き延ばすってシーンも多いですよね。「あと10秒会話が続いていれば逆探知できたのに!」現代の強化された警察システムでは秒速で電話をかけた場所が割り出せるそうです。そんな何十秒もかからないらしい。停まった心臓をAED(除細動器)使ったら奇跡的にまた動きだした!なぁんてことは絶対に有りえません。AEDは心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態(つまりまだ動いている)になった心臓に対して使うもので、止まった心臓に使っても全く意味はないのです。AEDがあれば、心停止した人を救えるというのは誤解です。脈がふれない時に、電気的に異常な心臓を元に戻すことは可能でも、停止した心臓を再度動かすことはできません。SF映画となると映画と現実の違いはもっといっぱい。例えばスタートレックなんかで、宇宙船が宇宙空間で大爆発!大きな爆発音とともに巨大な火の球ができる。って、真空状態の宇宙では音は伝わりません。また酸素がないので火は燃えず、閃光がきらめくだけです。ワープ航法のような科学的に立証されていない場面だったらまだしも、こんな単純な物理的法則でさえ無視されているのですね。これも見る人(映画の創り手)の誤解が映像になっている事例「命がけで小惑星帯の間を駆け抜ける」。「小惑星帯を通り抜けるのは決死的行為!衝突せずに密集している惑星間を突っ切るのは至難の業だ!」って、実際には惑星の間には何km も距離があります。惑星に衝突する可能性なんてほぼ皆無と云っても過言ではないのです。宇宙空間に投げ出された人間は破裂する?現実には皮膚はゆるやかに膨張はしますが、瞬時に破裂することはありません。ただし10秒後に皮膚とその下の組織が焼けたようにただれて減圧症となり、酸素不足から意識を失うのです。その1~2分後に死ぬとされていますが、これはあくまでも理論上で正確にはわかっていません。まぁそんなことばかり詮索していると、映画がちっとも面白くないので、難しいことは考えず単純に受け入れるのがイチバンなんですけどね。宇宙人もドラキュラも居たっていいぢゃない。その方が夢があって楽しいってのが結論です。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 23, 2016
コメント(5)
-

珍発明
いつの時代も珍"発明"は後をたたないですよね。やっかいなのは発明してるご本人はちっとも"珍"とは思っていない。近年は中国が温床かな?それも安物でチンケなのが多いですね。中国の道路清掃作業員が開発した「道路掃除機」この道路掃除機は竹ぼうき16本を回転させることで道路上のごみを掃く仕組みです。車の速度に応じて竹ぼうきが回転するようになっており、毎日20km の道路清掃が可能になったそうです。これにより清掃作業の効率は大幅に向上したと云う。この道路掃除機の存在が英紙デイリー・メールで報じられると、英国のネットユーザーからは「こんなものできれいになどならない。ごみを飛ばして他所を汚しているだけじゃないか」「100年以上昔ならいざしらず、時代遅れもはなはだしい」などと、嘲笑を込めた厳しいコメントが相次いだそうです。 と云っても一昔前の日本でもこんな珍発明が。「なんでも収納ネクタイ」一見すると普通のネクタイがひっくり返すとあらびっくり、こんなに収納スペースが!手帳、はさみ、クリップ、通帳、クレジットカードまでなんでもござれの万能ネクタイです。「寝過ごし防止ヘルメット」このヘルメットはとってもエコなことに一切電源を必要としません。額の部分に降りる駅名を書いておき周囲の人に寝過ごしそうになったら起こしてもらおうという、助け合いの精神満載のアイデアなのです。しかも寝過ごし防止機能だけではありません。電車内で居眠りをしているとつい後頭部を窓にぶつけて「ゴッン!」。しかしこのヘルメットは窓に吸盤を取り付けることで頭を支えてくれるため、大変楽に居眠りすることができるのです。「目薬失敗いらず眼鏡」うまく目薬をさせない人に朗報!先についた漏斗に目薬を垂らせば失敗などあり得ません。現行商品でも「うそ~」と思うようなのが。「USB花粉ブロッカー」花粉を物理的にシャットアウト!USBファン付きで息苦しさも解消の花粉対策用マスクです。首から上をすっぽり覆うマスクを被り、胸元の紐を調整すれば外気をシャットアウト。もう花粉はあなたに近寄れません。お値段は4,230円(税込)しかし有用そうなモノも掲出されています。「ストーブ用循環ファン」石油ストーブなどの上に置くだけで自動的に回転し、暖かい空気を循環させてくれるストーブ用ファンなんです。製品の底面部分(ストーブとの接触面)が熱を感知し、そのストーブからの熱をエネルギーに変換する仕組みなんです。ヤカンのお湯が沸かせるような昔ながらの石油ストーブや薪ストーブなどストーブ上部が高熱になるタイプのものに使用できるのですね。お値段は6980円(税込)pico5404さん、ご自宅の薪ストーブ用にいかが?(笑)興味があれば「サンコーレアモノショップ」で検索してください。他にもいろいろヘンチクリンなものがいっぱい。20世紀も初めごろともなると珍発明のオンパレードです。例えば「バキュームクリーナー付きピアノ」これは1917年の発明です。ピアノ演奏の時のペダルの動きでポンプを動かし、床のゴミを吸い取ると云う仕組み。ペダルの少ない曲だとろくにゴミが吸えないことと、そもそも移動できない掃除機に価値がないことから普及はしなかったようです。「アラレ避けキャノン砲」1900年ごろ、西ヨーロッパを中心になんと1万本以上も設置されたという「アラレ避けキャノン砲」。キャノン砲といっても弾を撃ち出すわけではなく、アセチレンガスを爆発させてできた衝撃波をラッパ状の管で上空に打ち出し、大気の状態を変化させるというコンセプトでした。オーストリア、イタリアの学者の調査によって「まったく効果なし」と判断されボツになりました。「電気式キノコ育成装置」A.G. ハプフェルと云う発明家の作品。ボイラーからの蒸気、雷によって発生するオゾン、そして「ジャズのドラム音」によってキノコの成長を早めることができる...という脅威の理論に基づく装置でした。特にドラム音が大切だったそうですが、そのメカニズムは現在に至るも不明です。「飛行船病院」船体の一番上の部分を日光浴し放題のサナトリウムにするというアイディア。常時飛行していて、補給は飛行機とドッキングすることで行います。しかし上空では地上よりも宇宙からの放射線が強くなるため、あまり長時間の滞在はできないという長期療養施設としては致命的な欠陥があったのです。「風力を利用した水上スキー」誰かが「ボートに引っ張ってもらえばいいじゃないか」と思いついたため、歴史の闇に消えました。「ミシンつき自転車」考案した本人は実用にする気満点だったと思われますが、現代の目からすると芸術作品としか思えない代物です。しかし現代でもこの発想が生きていて、こんな物を作った人が居ます。インドやインドネシアでは普通にミシンつき自転車は実用化されてます。ぢゃこれはどうだ!「ワンワンモービル」ワンちゃんが前に走ろうとするエネルギーを利用し、移動しながら散歩も兼ねられる素敵な発明になる...予定でした。人間がワンちゃんの代わりに自前で漕ぐってのは...想像の世界だけでした。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 22, 2016
コメント(5)
-

外国の学校給食
きのうは日本の学校給食を時系列に眺めましたが、諸外国ではど~なんでしょう?もともと給食のない国も多いハズです。だいたい給食のなりたちは日本でもそうですが、貧困などでちゃんとご飯が食べれない子供たちへの支援が契機です。国連がおこなっている「学校給食プログラム(WFP)」もアフリカなどの貧困家庭に対する食糧支援と云うかたちでおこなっています。国連の学校給食プログラムには栄養をとると同時に、虫下し薬を投与したり、ビタミン・ミネラルなどの栄養素を給食に含めたりすることも目的の中に含んでいます。また子どもがきちんと学校に通えば、その子どもの家族全員分の食糧を受け取れるという「持ち帰り食糧」と云うシステムもあって、とくに伝統的に女の子が教育を受けてこなかった地域での支援に活用されています。国連のこうした取り組みはほとんど世界中の個人や企業からの支援でなりたってます。たとえば日清食品のチキンラーメン1袋から0.2円、カップ麺なら0.34円寄付される仕組みになってます。これで1年間におよそ3,100万円を寄付することができるのです。低開発国の給食費は1食分が平均約30円なので単純換算で100万人分の食糧支援をやっていることになります。この活動は「国連WFPレッドカップキャンペーン」と呼ばれています。もちろん国連の支援に頼らず、国が給食プログラムを展開しているところは多くあります。たとえば「ソマリア沖の海賊」で有名なジプチ(アフリカ北東部に位置する共和制の国)ではご飯と豆にソースを絡めた給食が提供されています。もちろん栄養価から云うと充分ではありませんが、非常に貧しい国ですので、これでも子供たちにとってはご馳走なんです。ガーナの給食。ライスがメインですが、おかずが寂しいですね。ケニアの給食にいたっては...これはアボカドです。こちらもケニアです。豆料理のようですね。先進国でも給食を実施している国はたくさんあります。先ずは今なにかと話題のアメリカ。さぞや素晴らしい給食と思われるでしょ?ところがアメリカくらい栄養バランスを無視した、しかも美味しくない給食を出している国はないのです。ネットでは刑務所の食事より劣ってると云われています。アメリカの小学校の昼の給食の値段は2.5$(約300円)に設定されています。所得の低い人達用にはもっと安い値段設定になっていますが、なんとしても食べたくなくなるような内容です。そこへ行くとヨーロッパの給食の方がずっとマシです。料理が不味いので有名なイギリスでもこの程度。フランスはやはりフランスパン。どの給食もデザートに気合が入っています。こっちはイタリア。こうなると給食とは云えない。そうとうに美味しそうです。ギリシャの給食も美味しそう。スペインの給食なんて、先ほどのアメリカのと見比べてください。北欧や東欧も負けていません。これはスウェーデンの給食。こっちはチェコの給食。スロベキアの給食はビタミン重視!エストニアはじゃがいもと肉。男らしい給食。中南米もなかなかのものです。これはブラジルの給食。こっちはチリ。やっぱ東南アジアから東は絢爛豪華ですね。先ずはシンガポール。フィリピンはフィリピン料理のレチョン・カワリ(豚バラ肉のカリカリ揚げ)。台湾の給食はおかずもお代わりOKです。これは韓国の給食。基本的にワンプレート方式です。中国は...ご飯、盛り過ぎ!(笑)中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 21, 2016
コメント(8)
-

学校給食
昭和レトロ感を満喫できる学校給食が食べられるレストランってのが意外に流行ってますなぁ。出してる学校給食は昭和50年代とか60年代がほとんど。コッペパンは私らの世代には普通だったけど、ソフト麺なんてあったかしら?もっと世代が後のような。私らのそれも小学校低学年のときの学校給食と云ったら、そりゃあヒドイものでした。脱脂粉乳!戦後間もないころの日本の食糧事情を知ったアメリカの市民団体が中心となって、日本の子供たちの為にユニセフを通じて供与された代物です。私はこれが原因で牛乳そのものが飲めなくなりました。これが美味しかったという人はほぼ皆無に近いです。特に臭いが酷かったのですが、その原因は学校給食に供されたのがバターを作った残りの廃棄物だからです。欧米では家畜の飼料用として供されてた代物です。今売られているスキムミルクも脱脂粉乳ですが、これとは全く違うものです。記録では1950年代なかばに、普通の牛乳に切り替わったとされていますが、とにかく私が低学年のときはまぎれもなく脱脂粉乳でした。そして金属製の食器!これがセットになって出てくるのが私の世代の学校給食です。おかずも好き嫌いの多かった私には食べられないものが多かった。1週間に1度の割合で大豆の煮たのが出たのですが、これの味ったら!もちろん牛肉なんて絶対に出なかったですよ。私のヨメは「鯨の竜田揚げ」だけは好きだったと云うのですが、大阪の小学校に通ってた私には揚げ物の類が出た記憶がない。ヨメは東京の小学校だったので、やはり地方とは予算が違っていたのか?と云っても、今と違って「鯨」はお肉の中でイチバン安物だった時代ですからね。私の家は貧乏だったので、鯨を牛肉の代わりにカレーに入れたりしてました。コッペパンも今のレトロ食堂が出しているような美味しいパンではないです。残して持って帰ると、翌日には岩みたいにガチガチに固まって。そしてそのパンについてくるのが、お世辞にも美味しいとは云えないマーガリン。かつて日本ではマーガリのことを「人造バター」と呼んでいたそうですが、1952年に「マーガリン」と呼称が変更されました。しかし私の世代のマーガリンはまさに"人造バター"の味そのものです。ところが当時の学校給食はどこでも構内に調理場があってそこで全部手作りしてた。そこのオバチャンに頼んで釜土の火でコッペパンを炙らしてもらうのですな。そうするとパンが香ばしくなって、これに件のマーガリンつけても食べられるようになる。日本の給食の始まりは意外と古く、明治22年に山形県鶴岡町で僧侶たちがつくった私立忠愛小学校で貧困児童のためにおにぎり、焼き魚、漬物の昼食が無料で配布されたのが最初らしいです。東京麹町小学校でわが国最初の牛乳給食が行われたのが大正9年。このときは牛乳ビンからコップにあけてストローで飲んでいたと記録されてます。私の記憶では給食で牛乳ビンがついてきたのは高学年になってからですから、この時代の方が裕福でんがな!しかし大正から昭和にかけての給食は、おにぎりと漬物がほとんどで、貧困・虚弱児童を対象に行われていたと云うから、全員に供与されてたものでは無かったのか?それも第二次世界大戦の勃発とともに食糧不足のため中断されたのですね。そして戦後の私らの世代。つまり脱脂粉乳の時代です。脱脂粉乳を溶いたミルクは、給食当番によって大きなアルミのバケツで教室に運ばれ、杓子で1人分ずつアルミのお椀に注がれ飲んでいたのです。小麦粉の半額国庫補助が開始され、全国の小学校で完全給食が始まったのが昭和27年と云いますから、終戦後7年かけてやっと「全国」の学校に給食が提供されるようになったのですね。学校給食法が施行されたのはなんと昭和29年になってからです。ちゃんとした牛乳が供されたのは昭和30年代後半になってからと思います。最初は180ml のビン容器だったものが、昭和45年からは200ml のビンになりました。コッペパンから揚げパンなど調理したパンが給食で使われるようになったのも昭和30年代の終わりごろです。ソフト麺が給食に取り入れられたのは昭和40年頃からのようです。しかし大阪の私は一度も口にしたことがありません。ど~も関東地方を中心に供給されてたようです。昭和45年頃から瓶牛乳とともに紙容器の流通も始まり、とりわけ低学年へのビン牛乳の重量も考慮して、三角形のテトラクラシックタイプの紙容器に移行する学校が増えはじめました。その後、四角のブリックタイプ、ゲーブルトップ(屋根型)などが利用され今日にいたっています。最近では食堂やランチルームでバイキング式の給食を楽しむ学校も増えてきたそうです。和食・洋食・中華などメニューも豊富になりました。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 20, 2016
コメント(6)
-

大火星戦争(Great Martian War)
きのうのサッカー、クラブワールドカップ(W杯)決勝戦、鹿島はよく戦いましたね。PKがなければ大番狂わせも。それにしてもゴールキーパーの曽ケ端はいいですね。あのレアル・マドリードの怒涛の攻めに、よく持ちこたえました。昔の画像や映像と現在の画像を組み合わせると意外にオモシロイものができあがります。私もよくテンプレで使ってる手法です。この場合、モノクロ画像の方が加工しやすいですね。かえってモノクロ写真に彩色したものは、特に肌の色をあわせるのに苦労します。きょうご紹介するのはそんな白黒映像に後から付け足した白黒映像を組み合わせて1本のムービーに仕立てたもの。時代は機関銃や戦車、塹壕や飛行機といった兵器が初めて本格的に運用され、近代戦の幕開けとなった第1次世界大戦。もしあの戦いが人間同士ではなく、突如現れた火星人との戦いであったらと云うストーリーです。こう云う作品の場合、第1次世界大戦の方がテーマにしやすいです。なにしろ兵器そのものがレトロ感満載。それに第2次世界大戦ではあまりに生々しすぎてシャレになりません。皿形のヘルメットをかぶったイギリス兵達が塹壕から飛び出していくところなどは実に当時の映像っぽいですね。実際はアーカイブに残されていた映像と、新たに撮影し編集を加えた映像を合わせたもののようです。この「大火星戦争(Great Martian War)」はヒストリーチャンネル・ジャパンが運営する衛星放送チャンネル"ヒストリーチャンネル"が企画・制作したものです。第1次世界大戦の様々なモチーフを使い、欧州戦線における人類の死闘を振り返るという体のSFドラマ仕立てになっています。第1次世界大戦の欧州戦線で人類と火星人が戦うSFショートムービー「大火星戦争(Great Martian War)」中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 19, 2016
コメント(7)
-

50年代
私は1950年生まれなので、50年代の世代と云うことになります。「もはや戦後ではない」と言われ大流行したのが1956年ですから、生まれた頃はまだ終戦(玉音放送により日本の降伏が国民に公表されたのが1945年です)の面影がいっぱい残ってたんですね。ちょうど太平洋戦争から立ち直って高度経済成長へと突入する矢先です。もちろん幼いころですから、そんな記憶は全く残っていませんが。そして、その裏には1950年から始まった「朝鮮戦争」抜きには語れません。この戦争によって、特需を得た日本はどんどん経済成長していったのですから。朝鮮戦争が休戦になったのは1953年のことです。朝鮮戦争のミッションへ向けて待機しているアメリカ空軍の爆撃機「B-26」。1950年。戦犯のため外地で投獄中に亡くなった戦友の遺灰を手に持つ帰還兵士を出迎える女性たち。1950年。舞鶴港の中国北部からの引揚船。親が下船準備をしている間にデッキで寄付された三輪車に乗って遊ぶ子どもたち。1953年。大阪の児童養護施設(孤児院)の食堂の様子。部隊のニックネームから「やさしいオオカミ」と呼ばれた米陸軍第27歩兵連隊から寄付された食料で作られた食事でランチ中の160人の孤児たち。1951年。原爆が投下された6年後(1951年)の広島 原爆ドーム前。アメリカ人記者に背中のケロイドを見せたことで原爆第1号と呼ばれた「吉川清」さんのお店。警察官に石を投げている暴徒と化したプロ・コミュニスト(容共主義者)のデモ集団。警察が催涙ガス、警棒を使用し暴徒を抑えたため両者に負傷者が出ました。1952年のメーデー。総理官邸で公開された第1次鳩山一郎(孫があの鳩山由紀夫です)内閣を45人のカメラマンが撮影している瞬間。1954年。アメリカ・ロングアイランドにかつて存在していたミッチェル空軍基地で、アメリカの記者や写真家に取材されている10年前に広島で被曝した女性2人。原弾で被曝した25人の日本人女性が、遠く離れたニューヨークへ顔の整形手術を受けるために渡米したのです。1955年。イギリスによるクリスマス島での水素爆弾実験計画に反対するため、水素爆弾のキノコ雲のレプリカを運ぶデモ隊。1957年、東京。日本を守るため新しく設立された「自衛隊」の北海道演習に参加する女性看護師たち。1955年。硫黄島の砂浜に埋まってしまった旧日本軍 軍艦を掘り起こす人々。1954年。東京のデパートで新作の水着を披露している女性モデル。雨模様にも関わらず多くの人の関心を惹きつけています。1950年。戦艦大和の最後の一日を描くドキュメンタリ映画「戦艦大和」で使用する模型を制作中の映画マンと撮影中の戦艦大和のシーン。「戦艦大和」は新東宝製作の映画で日本映画で初めて戦艦大和を題材とした作品です。大和の造形物は製作費200万円をかけたセットや、1/44と1/70の2種類のミニチュアが用意され、新東宝発足以来初めて大規模な特撮となりました。1953年。大リーグのオールスター・チームと読売巨人軍のエキシビションゲーム。ボストン・レッドソックのドム・ディマジオが打席に立っている瞬間。1951年。当時はどちらも非常に珍しかった「アメリカ」の「プロレス」を放送する「街頭テレビ」を見る群衆。1954年、東京。ラジオ東京が4月1日に開始するテレビ放送(現TBS)のために建てられた157m のテレビアンテナ塔に飾り付けれた1万個のフラッシュバルブ。当時世界最大の数のフラシュが取り付けられていたため、多くの人の関心を引いていました。1955年、東京・赤坂。かつて浅草に存在した国際劇場で「夏の踊り」を踊る松竹歌劇団(SKD)のダンサーたち。1958年。かつて有楽町に存在した日本劇場(日劇)の舞台で活躍するミッキー・カーチス。1958年。アメリカのTV番組「スーパーマン」で主役のジョージ・リーヴスの吹き替えをする大平透。当時日本のショー番組の99%はアメリカ製で、スーパーマンは昭和天皇もお気に入りの番組だったと伝えられています。1959年。当時流行していたフラフープに興じる浴衣姿の女性。1958年。東京・大阪間の長距離列車(特急「はと」の東京-大阪間の所要時間8時間)が5分間だけ停車する浜松駅での1コマ。長距離旅行をしている乗客の筋肉をほぐすため、プラットフォームに音楽を流して3分間柔軟体操をしているドリルマスター率いる体操軍団。1952年。東京の満員電車で人を押し込む係「プッシャー」に雇われた大学生たち。ソニーが開発した8インチのポータブルテレビを車の助手席に乗せる女性。ソニーが開発した高性能トランジスタによりテレビの小型化が可能となりました。また屋外では約3時間駆動するバッテリー、屋内では200Vの電源で動作します。1960年。50年代の映画雑誌。昭和30年代(1958年ごろ)の居酒屋。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 18, 2016
コメント(6)
-

こんなの覚えていますか?
もうどんなに古びた喫茶店でも置いてないのでは?「ルーレット式おみくじ器」昔はどこの喫茶店やラーメン屋さんなどでも置いていましたなぁ。「ルーレット式おみくじ器」と云うのは一時期、日本一人口が多い村と云われた(今は市制施行で村でなくなりました)岩手県の滝沢市と云う所にある有限会社北多摩製作所の特産品です。ここは本来、金属加工業者なんですが、今現在、日本で「ルーレット式おみくじ器」の製造、保守をおこなっているのはここだけなんです。このルーレット式おみくじ器と云うのは「卓上小型自動販売機」と云う部類らしい。1970年代の星占いブームに乗じて流行ったらしいです。当時は、複数のメーカーがいろんなタイプを出していて、上に灰皿が乗っていた卓上おみくじ機がよく見かけられました。北多摩製作所では最初、灰皿の代わりに上をドライフラワーにした製品を出したのですね。ところがあんまり売れなかった。で、3年の試行錯誤の末にルーレット版を出したのが1983年のことです。で、北多摩製作所のルーレット式おみくじ器は最近では数々のTVでも取り上げられており、NHKの朝ドラ「あまちゃん」でも、駅前の喫茶&スナック「リアス」のカウンターにこれが乗っています。現在では滝沢市のふるさと納税の返礼品として市から認められています。しかし、そもそもなぜ金属加工業者がおみくじ器を作っているのか?北多摩製作所と云うのはマシニングセンタ・タッピングセンタによる高精度な金属加工をメインとしているのですが、電池とか電源の類はなくて、コインの重みとレバーだけで稼働するおみくじ器はお金の識別からルーレットをまわしておみくじの排出など幾つもの動作を同時に行わなければならない複雑な機構なので、こう云う加工工場でないと逆にできないのです。例えば10円玉は入らないよう穴のサイズを調整して、5円玉や50円玉を入れた場合は、くじが出てこない構造なんですね。今でこそ外側はプラスチックで作っていますが、元々は全金属製品だったのです。で、この機械の調整と云うのが職人技で、部品の僅かな曲げ方によって硬貨の識別をするため、自社で調節しながら製作しているらしいです。このおみくじ器に使われている部品は60個あまり。で、何人の人で作ってるかと云うと...たった1人なんです。生産ラインなどというものはなく、工場の1室でひっそりと作られているのです。それも女性の従業員さん。ユニットごとに組み立てておいて最終的に彼女が最後まで組み立てるという作業を繰り返すらしいです。それより驚きなのが紙に巻かれた「おみくじ」。これは150種類あるそうですが、それも彼女がひとつひとつ手で巻き上げているのです。おみくじの内容の中には30年前のものがそのまま使われているのもあるとか。このルーレット式おみくじ器、全盛期は北海道から沖縄まで、何十万台も卸したそうです。基本的にはリース契約で設置費用はかからず、売上金の30%が店舗側に配分される仕組みなんです。お店としては、ただ置いておくだけで100円につき、30円が黙って入ってきたんですね。1996年(平成8年)がピークで、北多摩製作所では1年で4,000万円の売り上げになったそうです。本体は1台約8,000円で販売していますが、概述のように基本的にはリース契約です。しかし最近は個人で購入希望される方が多く、2010年になってから個人向けにも販売するようになったら、全国から注文が殺到してるらしいです。今では売り上げの約50%が個人向けの販売が占めています。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 17, 2016
コメント(5)
-

モロッコと衛星アンテナ
モロッコと云うと北アフリカの地中海に面したエキゾチックな印象のある国ですね。もう私の年齢では一生行くことがないでしょうが、なんか魅力的なのはやはり映画「カサブランカ」の舞台になったからか?と云っても「カサブランカ」は1942年の映画で、私が生まれる前なのでDVDで観ただけですけどね(笑)そんなモロッコの旧市街と云うのは、これまた異国情緒が満点。なんとも魅力的な町並みです。と、思っているでしょう。ところがこの市街をロングで引いて見てみると...ん!なんか建て物の屋上に白いものが...ゲ、ゲ、ゲ~ゲェ!パラボラアンテナが林立!そうなんですね、モロッコと云うのは、TV局が国営の2局だけしかないんです。1つはアラビア語で、もう1つはフランス語放送です。で、世の常として"国営"TVだから放送内容がつまんない。と云うワケで彼らのほとんどは衛星放送を観ているのです。モロッコの衛星放送は中東、ヨーロッパの放送がほとんどカバーされてて、中国のチャンネルまであるんです。その数1,000局以上。DVDデッキ買うより、先ずはパラボラアンテナとチューナーと云う国なんです。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 16, 2016
コメント(4)
-

リング
英語でリング(RING)と云うと「輪」のことですね。なのにボクシングやプロレスみたいに四角い試合場も「リング」。これってなぜ?ボクシングの起源は古く、今から1万年前のエチオピアで行われていた兵士の訓練がルーツと云われています。やがてボクシングは見世物や賭けの対象として広場などで行われるようになり、闘う選手を観客が輪になって囲んで観戦してたのです。その取り囲む形から「リング」と名付けられました。つまり、ボクシングやプロレスの舞台は、最初は「輪」だったのです。剣の携帯が一般的でなくなりだした16世紀前半ごろから、賞金をかけたベアナックル・ボクシングの形で徐々にイギリスで浮上の兆しを見せ始めます。ジャック・ブロートンと云うチャンピオンがタイトル防衛戦の時、相手を殺してしまったために「ボクシングを普及させるには、このような危険は廃さねばならない」と考え、1743年に近代ボクシング初となる7章のルールブック「ブロートン・コード」を発表しました。その中ではリングについて直径25フィートの円形、硬い土の上と決められていました。やがて観客が見やすいように、地面に直接4本の杭を立ててロープを張るようになりましたが、形は四角くなってもこれをそのままリングと呼び習わしたのです。1865年成立の「クインズベリー・ルール」ではリングの1辺が24フィート(7m32cm)の四角形と規定されました。現代では、主に鉄製の柱4本の間に3~4本のロープを張り、鉄骨製の土台の上に丈夫な板を並べ、その上にクッションを敷いてキャンバスで覆い、リングとしています。形は正方形でなくてはならない。プロレスにおいては1901年にサンフラシンスコでプロモーターが1辺18フィート(5.48m)四方のキャンバスマットを考案しました。かつてボクシングの前座として興行が行われていたことから、ボクシング同様のリングが使用されているのです。しかしプロレスのリングでは、ロープの本数は3本が主流です。プロレスではタッグマッチや場外乱闘があるために、選手が試合中もリングを出入りすることが頻繁にあり、出入りしやすい方がむしろ好ましいのですな。またジャイアント馬場の「16文キック」のようにロープの反動を利用した技が多数あり、ロープの本数が増えると間隔が狭くなって使いにくくなるからです。こうして選手の試合場は四角くなったのですが、「リング」と云う名前はそのまま残ったと云うワケです。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 15, 2016
コメント(5)
-

グローマーエクスプローラー
「グローマーエクスプローラー」とは何か?かつてアメリカとソ連によって繰り広げられた冷戦の時代1968年に、ソ連の弾道ミサイル潜水艦「K-129」が爆発事故を起こして太平洋に沈没するという事故が起こりました。アメリカはソ連の機密情報を入手するために、沈没したK-129を秘密裏に引き上げることに決定。ソ連の監視の目をくぐりぬけながら極秘任務を遂行すべく、巨大なサルベージ船「ヒューズ・グローマーエクスプローラー」が開発されたのです。まるでスパイ映画の世界そのものが現実に起こっていたのですね。「K-129」と云うのは当時のソ連における最新鋭の潜水艦(ゴルフ型潜水艦)です。まだ原子炉を積んでいないために長期間潜航できない(航続距離70日)し、弾道ミサイルの搭載数はI型ではわずか3発(II型では6発、III型では4発)に留まっています。全長約98m 、全幅8.2m 、搭乗人員は80名。ゴルフ型潜水艦はソ連では1990年までに全艦退役しましたが、1993年に10隻が北朝鮮に解体するために売却されています。北朝鮮はこの潜水艦を運用したことはありませんが、艦の弾道ミサイル発射システムなどを学習した可能性があり、今日の北朝鮮のミサイル技術はここから発生していると考えられます。また中国人民解放軍海軍に4隻と設計図及び核弾頭無しのミサイルが供与され、これを改造して水中発射能力を付与し、弾道ミサイル発射実験に使用して弾道ミサイルと弾道ミサイル潜水艦のノウハウを得たとみられてます。この弾道ミサイル発射試験艦「長城200号」は40年以上の艦齢ですが、現在でも使用され続けているとみられています。さてアメリカが沈没したK-129を秘密裏に引き上げる作戦をプロジェクト・ジェニファーと呼びます。作戦を決行したのはアメリカ中央情報局(CIA)です。まさにスパイ映画の世界。1968年にK-129がミサイル発射可能な状態で作戦海域を大きく逸脱し、ハワイ近海を航行するという不可解な事態のなか沈没しました。周辺海域が放射線によって汚染される事態が発生したのです。アメリカのシースパイダーソナーネットワークは即座にこの爆発を探知。衛星や海兵隊の調査船によって事故の状況を探るなど、K-129の沈没事故について追跡調査が行われました。アメリカがK-129に強い関心を寄せた理由は、K-129が弾道ミサイルを搭載する潜水艦であること。沈没船から冷戦の相手国であるソ連の軍事技術や暗号技術を入手できると期待したからです。アメリカがK-129に関する情報を入手したがっていることはもちろんソ連も把握しており、ソ連は海軍を派遣してK-129の探索に乗り出しました。しかし沈没した潜水艦を発見することはできず、逆にアメリカ海軍の原子力潜水艦ハリバット(SSN-587)が太平洋の水深5km の海底に沈むK-129を発見することに成功したのです。CIAは秘密裏にK-129のサルベージを断行することを決め「Project Azorian(アゾレス諸島プロジェクト)」と呼ばれる極秘任務がスタート。しかしソ連の監視の目をかいくぐるために、表だって沈没潜水艦を引き上げることはできません。そこでCIAは当時、アメリカ海軍と武器や航空機に関する製造契約を結ぶなど実業家として成功を収め「地球上の富の半分を持つ男」と呼ばれていた大富豪ハワード・ヒューズと結託して、架空のマンガン掘削事業を隠れ蓑に利用したのです。CIAはヒューズの運営するヒューズ・ツールカンパニーにK-129を引き上げられる巨大なサルベージ船の建造を依頼。1972年11月に、排水量6万3,000トン、高さ189m で、すべての付帯設備を含めるとパナマ運河にも収まらないという全長を持つ「ヒューズ・グローマーエクスプローラー」の建造がスタートしたのです。グローマーエクスプローラーは沈没船を海底の土ごと持ち上げるための巨大な機械式のかぎ爪を搭載。かぎ爪はロッキードが開発を担当しました。さらにかぎ爪で引き上げたK-129をソ連の衛星に探知されないように格納する巨大施設「ヒューズ・マイニングバージ」も併設されました。こうして完成したグローマーエクスプローラーはマンガン団塊掘削船という表向きの顔を与えられた上で、1974年7月にリカバリーポイントに配置され、約1ヶ月にわたる諜報作戦を開始。ソ連の監視の目をそらせるために億万長者のヒューズがマンガン採掘プロジェクトに大金を投じたというプレスリリースまで打ち、海洋採掘事業が大々的に発表されたそうです。グローマーエクスプローラーはサルベージ開始から数週間後にK-129を引き上げましたが、水深約2.7km の地点で機体が分裂。結果的に潜水艦の前方部分だけが回収されました。引き上げに成功したK-129からは6人の乗組員の遺体が発見され、アメリカ軍によってひっそりと葬儀が行われています。こうしてK-129の機体半分の引き上げに成功しましたが、肝心の軍事技術や暗号技術などは見つからなかったとされています。しかし核魚雷や暗号表など有益な諜報情報を入手したとする説もあり、1997年に発刊されたクライド・W・ブルーソン著「The Jennifer Project」では、そもそも機体が半分しか回収できなかったというのも偽の情報であると記述されるなど、アメリカが有益な情報を獲得していた事実をCIAが隠蔽しているとする陰謀論も根強く残っています。冷戦時代に最も複雑で極秘裏に行われた諜報作戦の一つに数えられるプロジェクトを成功させたグローマーエクスプローラーは、2006年にはアメリカ機械学会から「前例のない挑戦を敢行し成功した歴史的建造物」に認定されましたが、スクラップ現場に搬出され、ついに解体されることになったそうです。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 14, 2016
コメント(4)
-

映画館とポップコーンの関係
今はシート内で飲食禁止の映画館も多いですが、相変わらず映画館ではポップコーンが売られていますね。なぜ映画館でポップコーンを食べるようになったのか?今では切っても切れない仲になっているポップコーンと映画館の関係はどのように作られたのか?トウモロコシの起源は8,000年前で、現在のトウモロコシとは見た目の異なる、ブタモロコシと呼ばれる雑草が起源だとされています。ちなみに私が北海道に赴任してたとき、細川たかしで有名な真狩村(まっかりむら)を通ると、地平線までトウモロコシ畑でした。ある日、誰も見ていないのをいいことに、そのトウモロコシを盗んだのですな。幾本か盗んだところで、お百姓さんが笑いながら見ているのに気づきました。バツが悪いなぁ~そしたら、そのお百姓さんが「これは牛のエサのトウモロコシだから、人間が食べてもちっとも美味しくないよ~」だってさ(笑)ポップコーンという名前は穀粒がポンッとはじけることに由来しますが、これは熱を加えた時に内側にでんぷん質とともに蓄えられた水分が蒸気となり膨張し、内側からの圧力に固い外側の組織が耐えられなくなって爆発するためです。そしてチリに向かった北アメリカの捕鯨船員がさまざまなポップコーンを発見し、ニューイングランドに持ち帰ったのが北アメリカにポップコーンが伝わった経緯だと考えられています。一度北アメリカに持ち込まれたポップコーンはまたたく間に広がりました。人々はみなポンポン跳ねるコーンをエンターテイメントだと見なし、1848年までにポップコーンは辞書に載るほど一般的なお菓子となりました。そして文字通り爆発的に広まったポップコーンはサーカスや縁日といったエンターテイメントの場で食べられるようになったのです。しかしエンターテイメントの場でポップコーンの姿が見えないたった1箇所がありました。それが映画館です。当時の映画館は教養のある人に向けて映画をアピールしており、館内には美しいカーペットやラグが敷いてあったため、ゴミとなるものの持ち込みを許しませんでした。当時は無声映画だったので、映画が上映されている時にポップコーンを食べる音に気をそらせたくなかったのも1つの理由です。そんな映画館の状況とは裏腹に、ポップコーン人気に拍車をかけたのは1885年にチャールズ・クリエイター氏が発明した蒸気によってポップコーンを作る移動可能な機械でした。ポテトチップスなどのお菓子は調理場なしでは作れませんが、移動可能な機械で作れるようにすることで、サーカスや縁日といった場で利用される商業的なお菓子になったのです。さらに他のお菓子にはない魅力としてはじけた時の香りも挙げられます。1927年に初めて映画に音声が加えられることで映画館の門戸は大きく開かれます。無声映画では文字を使っていたのですが、音声が加えられることによって読み書きの能力は問われなくなりました。1930年には映画の観客は週に9,000万人となり、それに伴ってお菓子の販売などから収益を得られる可能性も増加しました。しかし映画館のオーナーたちは観客席にお菓子を持ち込むことにまだためらいがあったとのこと。1929年の世界恐慌が起こると、人々の群れは気晴らしとして映画館に押し入り、そんな時に道端で5~10セントで売られるポップコーンは人々にとっては手に取れる贅沢品だったのです。それに目をつけた商人たちは映画館へと続く道でポップコーンを販売しだし、人々は映画館の外でポップコーンを購入してから映画館に向かうようになったため、初期の映画館にはコートを預ける場所が設けられるようになりました。コートの下にポップコーンを持っていないかチェックするためです。ポップコーンは秘密のお菓子だったのです。もう一つオーナーたちがポップコーンの販売に踏み切れない理由として、映画館に適切な換気場所がないということがありました。しかし観客たちは次々にポップコーンを持って現れ、お菓子を販売するという金銭的な魅力にあらがえなくなったオーナーたちはついに「映画館のロビーでお菓子を販売する権利」を手数料を払った商人たちに与えます。しかし道で売ると映画に向かう人と通行人の両方にポップコーンが販売できるため、商人たちはこの権利を気に掛けませんでした。最終的に映画館のオーナーたちは仲介人を打ち負かせば自分たちの利益がうなぎ上りであることに気づきました。多くの映画館ではお菓子の力を借りて不況中でも利益を得ることができましたが、1930年の中頃から、街の映画館は傾きはじめます。映画館チェーンのダラスでは、80の映画館でポップコーンマシンを導入しましたが、最も収益のよい映画館5つはポップコーンマシンを導入するにはハイクラスすぎるとして、マシンを置きませんでした。すると2年もしないうちにそれら5つの映画館の収益が赤字に転じたのです。映画館のオーナーたちはポップコーンが利益へのカギだとついに認めました。第二次世界大戦はさらにポップコーンと映画館の繋がりを強固にしました。キャンディーやソーダのようなお菓子は砂糖不足に悩まされ、1945年にはアメリカで消費されるポップコーンのうち半分は映画館で食べられるほど、ポップコーンは映画館になくてはならないお菓子となったのです。また、このころ映画が上映される前にコマーシャルが流されるようになりました。最も有名なコマーシャルは1957年に流された40秒の「みんなロビーに行こう」というというもの。コマーシャルによって人々はさらにお菓子を食べるようになりました。しかし1960年にテレビが普及することで、映画館の、そしてポップコーンの売上は減少します。道ばたやイベントで簡単に食べられるポップコーンですが、作るのが難しいという理由で家庭では普及していませんでした。この問題を解決したのがEZ PopやJiffy Popと呼ばれるキットで、ポップコーン作りに必要な専用の用具、バター、塩といった材料をすべて含んでおり、容器を火に掛けるだけで家庭でも簡単にポップコーンが作られるようになりました。1970年代には電子レンジの助けを借りて第二のポップコーンブームがやってきます。レンジのボタンを押すだけで簡単にポップコーンが作れるようになり、家庭で再び食べられるようになったポップコーンはエンターテイメントとポップコーン、映画とポップコーンの伝統的な繋がりを存続させました。ドイツの電子機器メーカーであるNordMendeは「水曜日の映画のスポンサー」という趣旨で電子レンジの広告にポップコーンを使用したほどです。一方で、ポップコーンと映画の繋がりが映画館の匂い以上に変えたものがあります。それがポップコーン産業自身です。コーンにはホワイトコーンとイエローコーンの2種あり、ホワイトコーンの2倍もコストがかかるイエローコーンは世界恐慌前は普及していませんでした。しかし、映画の観客たちはイエローコーンを好み、バターでほんのり色づけられたポップコーンに慣れきってしまったため、ホワイトコーンは受け入れられないようになったのです。現在市場で使われているホワイトコーンは約10%、残りの多くはイエローコーンで、青や黒のコーンはごく少量となっています。古い映画館であるほどポップコーンは重要で、材料費がかからないため、売店の利益率は85%ほどとなっており、これは映画館の収益全体の46%を構成します。近年アメリカでは高級志向の映画館ができはじめ、サンドイッチやパンを扱っているところも増えていますが、iPic TheatersのCEO Hamid Hashemi氏は「永遠にポップコーンはなくならないだろう」としており「ポップコーンは人々が作ることができる最も安い食べ物であり、なにより多くの人にとって儀式的な体験なのです」と語っています。と、ここまで映画館とポップコーンの関係を語ってきましたが、ここでポップコーンには罪はないけれど、かなりヤバイ動画を...「スマホの電磁波でポップコーンができるかどうか」徹底検証してみたと云うもの。iPhoneを置いた周囲にポップコーンの元になる爆裂種のトウモロコシを置き、iPhoneに着信させるとちょっとした電子レンジ状態になり、中央に置いてあるトウモロコシがはじけてポップコーンになります。これはiPhoneだけでなく、Androidのスマホでも、ガラケーでも同じ現象がおこります。電波が弱い時は、同時に2~4台のスマホをポップコーンを取り囲むようにみごとにはじけます。ドコモのページの「医用電気機器を使っている方へ」という項目を見てみましょう。ドコモのFOMAの出力は最大0.25ワット、movaは最大0.8ワット、デジタルカーホンの出力は最大2.0ワットです。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 13, 2016
コメント(5)
-

アポロ月面着陸誘導コンピューター
1966年のアポロ月面着陸誘導コンピューターなんて、どこかの博物館に後生大事に所蔵されていると思うでしょ。ところがそうではなかったのですね。なんとこのコンピューター、つい最近まで誰にもかえりみられることなく、アメリカ、テキサス州ヒューストンにある倉庫のスクラップの山の中にひっそりと放置されていたのです。それが今回、南アフリカの自称ハッカー、フランソワ・ローテンバッハによって見つけ出され、復活をとげたのです。しかし、そもそもこんな貴重な遺産がなぜスクラップの中に紛れていたのか?コンピュータの回路やモジュールなどの部品はヒューストン在住の匿名希望の男性がオークションで競り落としたのですが、なぜかゴミの山に放置してしまってたのです。この男性は、手持ちのガラクタをeBayで売りさばこうとしていたらしい。すると、ある日突然FBIがやってきて、彼がどこでこれを手に入れたかを知りたがったと云います。男性が当時の納品書を彼らに見せると、そのまま立ち去ったそうです。男性は怖くなって、自分がなにを持っているか、誰にももらさないよう秘密にして、スクラップの中に捨ててしまったのですね。アポロ誘導コンピューターは通称AGCと呼びます。月面着陸の道を切り開いた立役者です。アポロAS-202ミッションで、初めて宇宙へ打ち上げられたコンピューターで、周回軌道内外でロケットを誘導して、月へのミッションを見事に成功させた代物です。ローテンバッハはAGCのことを知って興味をもち、世界中のAGC専門家の助けをかり始めました。まもなく持っているスクラップの山の中から歴史的な宝を見つけ出したという件の男性から連絡をもらったのです。男性はローテンバッハの作業場にメモリーモジュールを送ってくれました。AGCのソフトウェアのほとんどは、磁気コアを介してワイヤを織ることによって作られるコアロープメモリとして知られている特殊な読み出し専用メモリに記憶されていました。「これは集積回路やマイクロチップを使った世界初のコンピューターです」ローテンバッハは、厚みのある黒い棒状のモジュールをひとつを持ってくると、カメラの前に近づけて云う。NASAのシリアルナンバーが入っているのがはっきりわかります。「宇宙で初めて使われたコンピュータのまさに現物なんですよ」ローテンバッハのおかげで、この偉大な歴史的コンピュータは、現在カリフォルニア州アラミダにある航空母艦ホーネット船舶博物館に展示されています。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 12, 2016
コメント(7)
-

ペストリーシェフの見事な作品
ウクライナの女性ペストリーシェフ、ディナラ・カスコさんと云う人が居ます。この人の作り出すスイーツと云うのが、もう近代建造物や工業規格品のように精巧な形状なんです。彼女は幾何学的な形と洗練された質感を伴いつつ、革新的なデザートやペストリーを目指し、つねに新しい技術を試してるそうです。その緻密さゆえ、崩して食べるのがためらわれるほどシャープでモダンな造形美をもつスイーツの数々を見てみよう。もうひとりご紹介しましょう。ロシアの菓子職人、オルガさんは、大理石の鏡のように見えるお菓子を作り上げています。この輝きの秘密はゼラチンとブドウ糖(グルコース)を使用することにあるそうです。ブドウ糖と砂糖に水を入れたものを沸騰させ、そこに水で溶いたゼラチンをくわえます。更にコンデンスミルクをくわえ着色をします。チョコレート味にしたいのなら、更に気泡が入らないよう35度に熱したバターとチョコレート(ホワイトチョコレート)を混ぜたものをくわえるそうです。でも、私ではとても自分で作れ無さそう。やっぱこの人の作品を買うしかないですね。で、勿体なくて...飾っておく(笑)。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 11, 2016
コメント(7)
-

なぜ地図は「北」を上にして描かれるのか?
なぜ地図は「北」を上にして描かれるのか?一般的には「ヨーロッパ人が地図を作り、彼らは上にいたかったから」と云うもの。しかし世界中の地域や、さまざまな時代の古い地図を調査すると、地図の上が「北」を向いていることにはそれ以外の理由があることが分かるそうです。古い地図をたどることでこの謎の答えを導き出しています。現在では地図を作成する際に、地図の上を「北」にすることが決めごとのようになっています。それが常識なのでしょうか?これは1979年にオーストラリア人のスチュアート・マッカーサー氏により発表された「マッカーサーの世界地図」です。上が北が常識の時代に書かれたこの地図は「上下逆さまの地図」と呼ばれていることからも明らか。現代の地図を使う人たちからすると、地図の上方向が「北」でないものというのはとても珍しいものです。しかし地図の上が「北」であることに地理学的な必然性はまったくなく、むしろ地図を作る方法や人間の方にこの理由があるとのこと。古代エジプトの地図は「南」が上になっていました。これはナイル川が重力に従って北に流れていく様子を表すためだと思われます。また、中世にはほとんどのヨーロッパの地図が「東」を地図の上に持ってきていました。同時期、アラビア人の地図作製者は「南」を地図の上に持ってきていたそうです。これらの理由は、それぞれがそれぞれの信仰の対象(エルサレム)と自分たちの国を地図の見やすい位置に配置したためとのこと。しかし、時代と共にこれらは変化していきます。14世紀~15世紀には地中海やその周辺に点在する多くの港町を示すための正確な地図が現れます。これらの地図はコンパスと一緒に使うことで水夫が通商路を航海できるようにと作られたものであったため、地図には上や下という概念がなかったそうです。しかし、これらの地図には方角が分かるように羅針盤と「北」が描かれていました。また、イタリアの地図製作法を学ぶ学校では、地図の方位記号の「北」を帽子や矢印で表すことが流行った時期もあるそうです。似たようなことはスペインのマジョルカでも行われており、ここでは地図の「北」を北極星で表していました。このマジョルカ出身の地図製作者は「地図上では紅海を赤く塗る」や「アルプスを大きな鶏の足のように描く」といった多くのとりきめを作りました。地図とは切っても切れない関係にあるコンパスですが、最初に使われたのは中国だと言われていて、何かを教えるときに使う「指南」という言葉は常に一定の方角を指し示す「指南車」という車から来ています。指南車は、乗っている仙人の人形が常に一定の方向を指し示す車のことです。中国の伝説の皇帝である黄帝が戦のために指南車を作らせたと史書に記載があります。磁石は使われず、左右の車輪の回転の差から機械的機構により方位を特定する仕組みであったとされているのです。その仕組みは、現代の自動車などにおける差動歯車の原理に類似するものです。羅針盤とはことなり「自ら南の方角を探し当て示し続ける」機能はなく、指南車の示す方向はあくまで操作者が最初に設定した方角です。台車を床に置き、あらゆる方角に台車をころがし差し向けても、台上の仙人人形は同一の方角を指し示すのですな。中国古来の思想に「天子は南に面する」というのがあり、それに基づくとされています。その後ヨーロッパ人がコンパスを使用するようになった際、ヨーロッパの水夫たちは既に常に北の空に輝く「北極星」を使って航海する術を会得していました。なのでコンパスは曇りで星が見えない夜に、北極星の代わりに「北」を確認するために使われたようです。最初は北極星の代替品として使われていたコンパスですが、時代の流れとともに需要が増していき、15世紀には航海に必要不可欠なものとなります。そして次第にヨーロッパやアラブの一部の地図以外は、コンパスの針が示す「北」を地図の上に持ってくるようになっていきました。「地図は北を上にする」ということが既成事実になっていったのは16世紀ぐらいのこと。これには2世紀頃に活躍したギリシャ人地図製作者で、地図製作に経度と緯度を加えるというアプローチを考案した人物、プトレマイオスが深く関わっています。16世紀に活躍した、ゲラルドゥス・メルカトルやマルティーン・ヴァルトゼーミュラーなどの地理学者たちは、こぞってプトレマイオスの作成した地理学書を印刷機で複製して出版したそうです。この地理学書と地図は多くの地理学者や地図製作者に広まったわけですが、プトレマイオスが描いた地図の上は「北」を指していたので、これが現在まで続く慣習となったのですね。プトレマイオスが地図の上が「北」を指すように地図を作成した理由は歴然としていませんが、アレキサンドリアで座っているときに「自分は天体の北側に座っていることをふと理解したから」なのかもしれない。もしくはプトレマイオスがいたアレキサンドリアを地図の底に配置したかったからなのかもしれないとのことです。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 10, 2016
コメント(4)
-

世界で唯一"天然原子炉"のある国
世界中旅行したいけど、北朝鮮とアフリカだけは嫌やなぁ。アフリカでちょっと見てみたいのは北アフリカのモロッコとチュニジアぐらい。なんと云ってもアフリカは食べる楽しみが無さそう。アンゴラ、ガボン、カメルーン、コンゴ、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、赤道ギニア、チャド、中央アフリカ、ブルンジ、ルワンダ赤道アフリカの国々は少なくとも私にとっては最も縁の無い国々です。そんな無知の赤道アフリカでも、とりわけ"ガボン共和国"と云うのはほとんど名前さえ聞いたことがあるかないか。北西に赤道ギニア、北にカメルーン、南と東にコンゴ共和国と国境を接し、西は大西洋のギニア湾に面している国です。アルベルト・シュヴァイツァーが医療・伝道活動を行っていたのは、この国のランバレネと云う土地です。この国は長い間、奴隷貿易に苦しめられてきました。15世紀末にポルトガル人が渡来し、奴隷貿易を行ったのをかわきりに、オランダ、イギリス、フランスが進出してきました。この地は奴隷貿易と象牙の集散地として栄えたのです。1885年にフランスが占領しました。1910年にフランス領赤道アフリカの一部となり、この状態は1959年まで続いたのです。ガボンは国土の80%以上が森林で、近隣諸国と比べ人口密度が低いため、手付かずの豊かな自然が多く残されています。アフリカ森林には、ゾウ、ゴリラ、チンパンジーなどの大型哺乳類が多数生息しているのです。ガボンには多様な自然環境をふくむ、13の国立公園があります。ガボン政府は、自然環境の保全に力を入れており、中部のロペ国立公園や、大西洋岸のロアンゴ国立公園ではエコツーリズムが導入されています。また南西部ニャンガ州に位置するムカラバ-ドゥドゥ国立公園では、日本人研究グループによる大型類人猿の長期野外研究プロジェクトが進められています。2007年にロペ=オカンダ生態系と残存文化的景観が複合遺産として世界遺産に登録されました。気候は熱帯モンスーンで、首都リーブルヴィルの降雨量は雨季の9~5月が毎月約300mmですが、乾季の6~8月は3ヶ月で35mmと極端に少ないのが特徴です。1日の最高気温は平均29~30度Cですから、比較的過ごしやすい部類ですね。とは云ってもスコールが来ないので、午後はかなり暑いそうです。旅行者は毎日、ペットボトル2~3本の水を飲んでいるもよう。コカコーラやファンタは750ml という特大のビンで売られています。これだけ水を飲んでいても、ほとんど汗になって出てしまうので意外なほどトイレに行かないそうです。トイレシャワー共同の部屋は5,000セーファーフラン(CFA、日本円で約850円)Lalala(ラララ)の集落に1件しかない宿。このLalalaは地図にも名前がありますが、村などというものはなく、三つ又のジャンクションを中心に十数軒の家が並ぶだけの何もない所でした。主要道路の分岐にある小さな村の一軒宿。電気、水道は無し。ベッドがあるだけの宿です。こちらは市場と典型的なガボン料理。ヌジョレと云う町で、トマトと玉ねぎと赤唐辛子醤油で鶏肉と牛肉のソテー。こちらはヌジョレの美容師。ガボンランバレネ魚の燻製ストリートガボンの魅力的な民族お面。このガボンには天然原子炉と云う珍しい土地があります。「オクロの天然原子炉」天然原子炉とは、過去に自律的な核分裂反応が起こっていたことが同位体比からわかるウラン鉱床のことです。天然原子炉の知られている地球上唯一の場所がオクロにある3つの鉱床で、自律的な核分裂反応のあった場所が16箇所見つかっています。20億年ほど前、数十万年にわたって、平均で100kW 相当の出力の反応が起きていたもようです。オクロ以外では天然原子炉は見つかっていません。ほかのウラン鉱床も核分裂反応を起こすのに十分なウランが含まれていたものの、ウランと水と、核反応を起こすための物理的な条件とがそろっていたのはオクロ以外にはなかったのです。天然原子炉では、ウランに富んだ鉱床に地下水が染み込んで、水が中性子減速材として機能することで核分裂反応が起こります。核分裂反応による熱で地下水が沸騰して無くなると反応が減速して停止する。鉱床の温度が冷えて、短命の核分裂生成物が崩壊したあと、地下水が染み込むと、また同じサイクルを繰り返すと云う仕組みです。このような核分裂反応は、連鎖反応ができなくなるまで数十万年にわたって続いたそうです。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 9, 2016
コメント(6)
-

おもちゃ映画ミュージアム
TVで京都の「おもちゃ映画ミュージアム」なるものが放映されてました。これがなかなかオモシロイ。ちょっと見ることのできない映画機材が展示されてます。ここには映画誕生以前より映画の原理でもある残像現象を利用した動画装置やアニメーションの玩具がありました。静止した絵がどうして動いて見えるのかという原理...ここにはソーマトロープやフェナキスティコープ、ゾーイトロープ、プラキシノスコープなどの光学玩具がいっぱい。ソーマトロープは1825年に、イギリスのジョン・エアトン・パリスによって考案されました。これはオモチャの一種です。円板やカードの両面に絵を描き、2本の紐を取り付けたものです。両面の絵は例えば1方に鳥、反対側に鳥かごを描きます。表に鳥、裏に鳥かごが描かれた円盤の両側にある紐を指で引っ張ると円盤やカードが回転し、鳥かごの中に鳥がいるように見えると云うものです。最初に登場したアニメーション機器は1831年にベルギーのジョゼフ・プラトーが発明したフェナキストスコープです。日本では「おどろき盤」とも呼びますが、これは1970年代にフェナキストスコープを復元した古川タクが命名したものです。フェナキストスコープの最大の弱点は1度に1人しか楽しめないことです。軸に垂直に取り付けられた回転する円板があって、その円板にアニメーションのコマに相当する絵が順に描かれており、コマとコマの間にスリットがあります。この円板を回転させ、絵を鏡に映し、動くスリットから透かして見るのですな。そうすると残像現象で静止した絵が動いて見えると云う仕掛けです。フェナキスティスコープの円盤と鏡の代わりにドラムを使ったものがゾーイトロープです。1834年にギリスの数学者ウィリアム・ジョージ・ホーナーによって発明されました。スリットのあけてある円筒の内側に、アニメーションの元になる絵の帯を丸めてセットし、円筒を回転させながら、円筒の外側からスリットごしに眺めると、動く絵が楽しめるという仕掛けです。ゾーイトロープの原理を応用したものにドイツで開発された「エレクトロタキスコープ」があります。馬の走る様子の連続写真14枚~20枚を大きな円盤に貼り、円盤を回転させつつ小窓を通して映像として見せました。これはドイツで写真学を学び、プロシア軍の写真技師でもあったオットマール・アンシュッツが1886年に開発したものです。ゾーイトロープを改良しプリズムを使ったプラクシノスコープを開発したのはエミール・レイノーです。1877年のこと。ゾートロープが円筒に開けられたスリットから反対側の内側をのぞく形式だったのに対して、プラキシノスコープは回転軸を鏡で囲い、その鏡に反射して写る絵を見る形態です。ゾートロープに比較すると像が明るく歪みが小さいのが特徴です。プラクシノスコープは改良が続けられついにスクリーンに投影されるようになります。テアトル・オプティークという投射式のプラキシノスコープが開発されたのです。レイノーはこの映写式のテアトル・オプティークを使って、多くの人にアニメーションを見せています。ミュートスコープと云うのは亜流がたくさん有ります。要するにパラパラ・マンガの原理で映画やアニメーションを見せる機器です。キャスラーが1894年に発明し、1895年から商品として製造を開始しました。無数の紙を軸に綴じ込んだもので、1枚ごとにフレームの絵が描かれています。これをモータで回転させてビデオとして再生して見せるようになっていました。日本にもミュートスコープの会社が有りました。「阿機商事」と云う会社が1974年~75年ごろに発売した「TOPIC」という機種で、立体カラー写真のステレオトーキー。マンガ、童話などがありますと説明があります。「日本娯楽機」と云うメーカーが1977年に発売した「子供テレビ劇場」もミュートスコープです。前面のパネル、フィルム、音楽テープの交換がワンタッチでできるのが大きな特徴。画面と音楽は迫力満点。定価28万円。と説明があります。「日本娯楽機」というメーカーは、1931年に日本で初めてデパートの屋上に遊園コーナーを設けた会社で、戦前の1936年ころには既にミュートスコープを製造販売していました。「日本娯楽機」はその後「ニチゴ」に社名を変え、今も百貨店の娯楽施設の運営を行っていますが、娯楽機の製造からは手を引いています。これは1930年代に作られた小さなブリキ製のミュートスコープ・マシーン「ニュースペーパー・ムービー・マシン」です。今でも海外の骨とう品サイトではよく見かけます。こちらは1956年に製造された「sensorama」と云う機器です。これのスゴイとこは3D映像のみならず、360度のステレオサウンド、振動、匂い、風を用いて人間のあらゆる感覚器官に刺激を与えることができることです。モーターサイクル・ライド・シミュレータとして作られ、お客さまは時折、一酸化炭素の嫌な臭いさえかがされて加速しました。現在のVR機器も真っ青ですね。ミュートスコープとよく似た技術にエジソンのキネトスコープがあります。ミュートスコープとキネトスコープとは全く同じ時期に発表されたので、たがいに競合する関係にありました。キネトスコープは媒体として35mmフィルムを使い、ビュアの内部のスクリーンに映写した像を見せるようになっていました。そのため時間の長い映像を見せることができたのです。1893年のシカゴ万博に出品されて話題となり、翌年4月には史上初の映画館(キネトスコープ・パーラー)がブロードウェイに開設されました。上映されたのは1分程度の短編で、人が踊ったり汽車が走ったりするだけの他愛ないものだったようです。客もボードビルを見る金がない貧しい移民労働者ばかりだったと云います。「おもちゃ映画ミュージアム」の住所は京都市中京区壬生馬場町29-1JR・地下鉄「二条」駅から徒歩約8分。阪急「大宮」駅から徒歩約7分です。祝日含め月曜、火曜は休館。開館は10:30~17:00まで。入場料は大人500円で、小学生以下は無料になってます。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 8, 2016
コメント(6)
-

ベル研究所
「ベル研究所」と云うのは電話を発明したグラハム・ベルが、電池を発明したボルタを記念したボルタ賞の賞金で設立したボルタ研究所が起源です。このボルタ研究所は元々「聾唖教育」のために作られたものなのです。その後「ベル研究所」と名前を変え電話交換機から電話線のカバー、トランジスタまであらゆるものの開発を行いました。その関係会社として古典的なオーディオで有名なウェスタン・エレクトリックもあり、その母体はアメリカ最大手の電話会社AT&Tでした。現在は携帯電話で有名なノキアの子会社として存在しています。ベル研究所で開発されたものにはコンピューターに関するものも多く、ミニコンに搭載された最も重要で、今日のMac OSの元となった「UNIX」や開発言語として今日でも大手の「C言語」などがあります。世界初の太陽光発電もベル研究所で開発されました。アポロ計画にも深く関わっています。同社の研究員でノーベル賞受賞者も何人か輩出しました。そんな叡智の塊とも云えるベル研究所の60年代に撮影された写真が公開されています。これがまた実にレトロフューチャーな雰囲気を漂わせていていいんですな。まさに古いSF映画に登場しそうなコンピュータやオフィスが登場します。60年代にはテレビ電話として知られているビデオ・コーリングプラットフォームを開発しました。これにはインターネットの開発もついてきます。まだ今日のような高速の通信網が完備していないときに、カリフォルニアのディズニーランドでゲストに大陸横断のビデオ通話を行うデモンストレーションをおこなったのです。冷蔵庫ではありません。Honeywell社のコンピュータDDP-516です。端末をメインフレームに接続する、今で云うスイッチングハブとして使われていたのです。現在ほとんど見ることが難しくなっているオープンリール磁気テープです。コンピュータの記憶装置として使われていました。ベル研究所では女性スタッフが豊富に居ました。1964年、ニュージャージー州のベル研究所の研究者ペアが世界最大の電波望遠鏡を駆使して、無意識のうちに20世紀の最も偉大な発見の1つをしました。宇宙背景放射。このようにベル研究所の研究はありとあらゆるものを網羅していたのです。こうして見ると、ベル研究所が活躍していた時代と云うのは、アメリカが世界のトップリーダーとして生き生きとしていた時代とリンクしますね。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 7, 2016
コメント(4)
-

いまだ科学で解明でききっていない不思議な物品
ナスカの地上絵、ストーンヘンジなどまだまだ解明されていないものや場所がありますね。アメリカの動物学者で超常現象研究家のアイヴァン・サンダーソンと云う人が造った言葉で「OOPARTS(オーパーツ)」と云うのがあります。「out-of-place artifacts」を略して「OOPARTS」。「場違いな工芸品」という意味です。オーパーツは、それらが発見された場所や時代にはまったくそぐわないと考えられる物品を指すのです。例えばこんなのがあります。コロンビアのシヌー地方の古代遺跡から発掘された「黄金スペースシャトル」。古代遺跡ってどれくらい古いかと云うとシヌー文化(紀元500年~800年)時代のものという説と、更に古いプレ・インカ文明のものという説があるのです。そんな時代に飛行機や宇宙往還機を思わせる黄金細工が作られていた...これを鑑定した動物学者のアイヴァン・T・サンダーソン博士は、他のどの生物とも似ておらず、三角翼と垂直尾翼がありジェット機やスペースシャトルにも見えるといったことから「ベル・ヘリコプター」の設計者として知られるアーサー・ヤングに検証を依頼しました。ヤングの検証結果は、航空力学の理にかなった形状をしているというものだったのです。発掘地のコロンビアと、ナスカの地上絵のあるペルーが場所的に近いことや、黄金スペースシャトルとナスカの地上絵の造られた年代が一致することから、なんらかの関わりがあるのではないかとも云われているのですが、定かではありません。この「黄金スペースシャトル」は現在、コロンビアの首都ボゴタにある、国立銀行付属黄金博物館に展示されています。大きさは幅5cm 高さ1cm ほどの、手に乗る大きさで、ペンダントなどの装飾品の類であったと思われています。これ以外にも、垂直尾翼のないもの、翼の大きく湾曲しているもの、目のあるもの、ヒレや羽などの模様のついているものなどがあり、一般には魚や鳥などを模したものという説明がなされているのです。当然、魚や鳥がモデルであれば流体力学的に「理にかなった」形状をしていても不思議ではないですからね。これはどうでしょう「ピーリー・レイースの地図」。この地図はコロンブスがアメリカ大陸を発見し、アメリゴ・ヴェスプッチが南アメリカを調査してから間もない時期に描かれているにもかかわらず、アメリカ大陸を非常に詳細に描いており、コロンブスやヴェスプッチの原図が失われた現在では、アメリカ大陸を描いた史上最古の地図といわれています。それより不可解なのは当時未発見であった、南極大陸の海岸線が書き込まれているのです。地図が描かれた時代よりもかなり後の19世紀に発見された南極大陸の北岸と思われる海岸線が描かれていることから、歴史史料としてよりも、むしろオーパーツとして世界的に有名になっています。この地図は1929年にイスタンブルのトプカプ宮殿博物館に収蔵された写本類の中から発見されました。現在もトプカプ宮殿に保管されていますが、一般公開はされていません。錆びない鉄柱ってのもあります。紀元415年にインド・デリー市郊外の世界遺産クトゥブ・ミナールに建てられた「デリーの鉄柱」です。およそ1,500年の間、屋外で風雨に晒されていたにもかかわらず、ほとんど錆びていないのです。この鉄柱は使われた鉄鉱石や製法の関係からリンの含有量が多く、そのおかげで表面がコーティングされ錆を防いでいると考えられています。こんどは有名な「アンティキティラ島の機械」。ギリシャのアンティキティラ島近海で発見された青銅製の歯車の組み合わせによる天体運行を計算するために作られた古代ギリシアの差動歯車式機械なんです。紀元前150年~100年に製作されたと考えられているのですが、問題は、これが地動説に基づいて制作された装置である点なんです。地動説は16世紀のニコラウス・コペルニクスより遥か前、古代ギリシャのアリスタルコスが唱えており、当時既に存在していたことが確認されています。実物はアテネ国立考古学博物館の青銅器時代区画にデレク・デ・ソーラ・プライスによる復元品と共に展示されています。その他の復元品は米国モンタナ州ボーズマンのアメリカ計算機博物館、マンハッタン子供博物館に収められています。イラク、バグダードで製造されたとされる土器の壺で「バグダッド電池」と呼ばれるものがあります。製造はパルティア時代(紀元前247年頃~228年)と推定されていますが、中央に層状の炭素が巻かれた金属棒が入っており、葡萄果汁を満たすと電池になるのですな。発掘当時は用途が不明だったのですが、電池メーカーのボッシュによる復元実験で電解液として酢やワインを用いた結果、電圧0.9~2V程度の発電がなされたのです。「ネブラ・ディスク 」は、2002年に保護されたドイツ中央部、ザーレラント地方の街ネブラ近くのミッテルベルク先史時代保護区で、1999年に発見された青銅とその上に大小幾つかの金が張られた円盤です。これが人類最古の天文盤。青銅器時代に太陽太陰暦が成立したことを表すものと考えられてます。この天文盤は、初期の青銅器時代ウーニェチツェ文化(紀元前2,300年~紀元前1,600年にかけての中央ヨーロッパの青銅器時代考古文化)とかかわる天文盤と考えられてます。直径約32cm、重さおよそ2,050g の青銅製。円盤の厚さは、中央から外側へとおよそ4.5mm ~1.5mm と減少している。現在の状況は緑色の緑青をふいているが、元の色は茶色を帯びたナス紺色であったようです。この盤の上には金の装飾(インレー)で、太陽(または満月)と月、32個の星が模られ、太陽暦と太陰暦を組み合わせた天文時計であると考えられています。もともとの天文盤には、37個の金のインレーがありました。1つのインレーは、古代に既に取り除かれていたが、その前の位置は、まだ見える溝により決めることができます。円盤の縁は、前面から38個の穴が開けられ、その穴の直径は、およそ2.5mm です。オリジナル品は、ザクセン=アンハルト州立のハレ先史博物館で見ることができます。またネブラの発見場所近くにはビジターセンターが設置され、そのレプリカが常設されています。2005年の愛知万博(愛・地球博)で展示されたことがあります。「20世紀の最も重要な考古学上の発見の1つ」としてユネスコ記憶遺産に登録されましたし、ドイツでは10ユーロ記念銀貨のデザインや55セント記念切手の絵柄にも用いられました。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 6, 2016
コメント(6)
-

ナイロビ・スラム街の個人商店
「ナイロビの蜂」と云う映画をご覧になりました?ケニア最大の都市でもあり首都のナイロビで起こった事件。妻が殺害された真相をあばくため奮闘するイギリス外務省一等書記官。そこには政府高官と製薬会社の陰謀があったのです。この映画で妻は国際難民救済協会の活動の一環として慈善活動のためにナイロビの巨大なスラム街に通います。映画では実際にナイロビの巨大スラム「キベラ」で撮影がおこなわれました。ケニア政府が映画撮影を許可したのは、もし拒否しても別のところで映画は作られるだろうから、それだったら真実の姿を見てほしいと云う理由だったのです。「キベラ」は、アフリカで2番目の規模のスラム街です。「ナイロビの蜂」の監督は初めてキベラを訪れた時のことを「酔いも覚めるほどの貧困で、リオのスラムのファベーラよりもひどいところだ」と述べています。妻を演じたレイチェル・ワイズは撮影関連のインタビューで「何百万人もが水道も電気も公衆衛生もない小屋の町に住んでいます。これほどの貧困は見たことがありません」と語っています。ケニアの首都ナイロビ自体が治安の悪さでは世界第2位。そこのスラムなんですから押して知るべしです。この「キベラ」の推定人口はナイロビ人口の過半数である約100万人と云われています。大阪の「あいりん地区」東京の「山谷」横浜の「寿町」が日本の三大スラムと呼ばれています。この三大スラムの生活者を全部足しても2万人にも満たない訳で、キベラスラムはその50倍。「キベラ」の人口はほぼ仙台の人口に匹敵します。この「キベラ」に行く"ツアー"が現地で主催されてます。それはナイロビのいくつものツアー会社が催行しているのです。日本人に有名なのは、キベラスラム内にある恵まれない子供達の為の学校、マゴソスクールを運営する早川千晶さんのスタディツアーでしょう。このツアーは千晶さんはもちろんの事、銃を持った警官が3名同行するらしい。ただ物見遊山にスラムをブラつくのではなく「なぜスラムは出来るのか?」「スラムの人々はどこから来るのか?」「日々の生活はどういうものなのか?」などの疑問を解きスラム訪問を意義のあるものにしようと云う趣旨のツアーです。だいたいどのツアーもキベラスラム入口近くの現地集合です。そこまではタクシーを使って自分で。警官が同行しないツアー会社もあります。集合場所から徒歩でスラムの中へ。しばらくは露店が建ち並ぶ道を歩いていくと「チョコレートタウン」と云う道にでくわします。「チョコレートタウン」とは足元がグチャグチャになった泥濘んだ道なんです。ここからが本格的なスラムの始まりなんですな。奥の方に赤い屋根の住宅が見えます。この建て物はスラムに住む人に少しでもまともな生活をさせようと政府が建てたものですが、家賃が高くてみんな手前の方のボロ小屋に安住。政府の用意した建て物に住む人はほとんど居ません。ところでケニア料理ってどんなだと思います?これはマツンボシチュー。キベラ周辺だとチャパティ、コーラつきで130シリング(159円)マツンボとは羊の胃や腸などをトマトで煮込んだものです。ケニア版モツ煮といったところ。臭みがエグくて、食べきるのがやっとって感じの代物です。マツンボの隣に写っているワケの分からん葉っぱは何か分かりませんが、日本人には一口でお手上げらしい。そんなキベラスラムにもお店はあります。かなり強烈な個性に溢れた個人商店ばかり。先ずは映画館。もちろんスクリーンがある訳でなくテレビが1台あるだけ。薬草屋さん。ホテル「SMALL JOINT HOTEL」。こっちもホテルって書いてあります。ホテルです。これらのホテルは住居すら持たない人のための簡易宿泊所なのか?灯油屋さん。テレビ屋さん。洗車屋さん。なぜかアダルト・オンリーと書いてある。バー「BORA-BORA」。ヘアーサロン。こちらは散髪屋さん。もしかするとスポーツバー?食料品店。家政婦斡旋所。電化製品の修理屋さん。ブラウン管テレビはバリバリ現役です。ミュージックストア。格闘技ジム。靴屋さん。炭売り。これらの写真はキベラでは極めて状態の良いお店ばかりです。実態は以下の通りのありさま。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 5, 2016
コメント(5)
-

クトウ蓄音器
蓄音器と云う言葉の響きには懐かしさが溢れていますな。私が子供の頃には、今風のステレオではなく、モノラールの蓄音器をまだ置いてるお宅もありました。レコードはLPレコードではなく、それより昔のSPレコードが幅をきかせていました。SPレコードは落とすと木っ端みじんにみごとに砕け散るので、俗称「瓦盤」。実はSPレコードの素材は酸化アルミニウムや硫酸バリウムなどの粉末なんですが、それを固めるのにカイガラムシの分泌する天然樹脂を使っていたのです。カイガラムシって見ただけで鳥肌立つくらい群生している細かい虫です。ところで蓄音器は「器」であって、「機」ぢゃないんですね。ビクター、コロムビア、テイチク、ポリドール、名だたるレコードメーカーは「○○蓄音"器"株式会社」と社名を名付けています。「器」を使うのは音を盛るからという説からきているらしい。この蓄音器と云うのは、アンプがついてるし、モーターもついてるから、と~ぜん電気を使いますよね。ところが昔は電気を全く使わない蓄音器もあったのです。この蓄音器に電源プラグなんて存在しません。ぢゃあどうしてレコード盤を回転させるのでしょう?「ぜんまい」なんです。ビクターなんかでも、最初の頃はぜんまい式でした。で、初期の蓄音器はレコードをトレースする「針」に「竹」のレコード針を使ってたのですな。普通はダイアモンド、ルビー、サファイアなどの硬い宝石をレコード針の先端に使います。時代が下がって、私が子供の頃には「鉄針」も使われていました。「竹針」は最初期のものです。ところが、この"ぜんまい"すら使っていない蓄音器が日本には存在したのです。「クトウ蓄音器」ぜんまいすら使ってなくて、どのようにしてレコードを回転させるのでしょうか?それが笑ってしまうんですね。レコードを回転させるのは「手」です!つまりレコードを聴いている間、ずっとハンドルを回していなければいけない代物。しかし手で回転させていては、回転が一定でなくて音が高くなったり低くなったり...そう云うことは詮索しないんですね、この手の蓄音器は。とにかく音が出れば儲けものって代物です。「クトウ蓄音器」は仙台市の工藤豊治郎と云う人が大正3年に特許登録した発明品なんです。この「クトウ蓄音器」は蓄音器のターンテーブルの脇のハンドルを回すとターンテーブルが回り、テーブルの両サイドに付いた大きな錘が一緒に廻ります。その弾み車の遠心力で、ターンテーブルの下に繋がっている革ひもを回転軸に絡めて回転を調節するユニークな仕組みなんです。なんでこんな蓄音器が登場したかと云うと、当時の蓄音機は国産でも数十円から百円近くした贅沢な高級品でした。それでこのような普及品が考えられたのです。「クトウ蓄音器」の当時の売値は9円。それなりに売れたらしいです。「クトウ蓄音器」の銘板。「歯車ゼンマイナシ」(笑)全国で約2万台ぐらい売れましたが、高級品ではなかったため、大事に残されることもなく今では全国に数台しか残存していないそうです。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 4, 2016
コメント(5)
-

カフカの「変身」
フランツ・カフカの「変身」と云う小説を読まれたことありますか?カフカと云うのはチェコ出身のドイツ語作家で、ユダヤ人です。「変身」は「ある朝目覚めると巨大な虫になっていた」で始まる男の物語で、家族からはキモチ悪がられ疎んじられて、父親に投げつけられたリンゴによって深い傷を負った男は次第にやせ衰え息を引き取ります。そんな物語です。人間の不条理を描いた小説として実存主義の金字塔と評価されてる小説です。フランツ・カフカは小説家専業ではありませんでした。本業は労働者傷害保険協会の職員です。当時のハプスブルク家の官僚体制で、勤務時間が朝8時から14時まで昼食を取らずに働くというシステムだったため、残りの午後の時間を小説を書く時間に使えたのですな。やがて結核を患ったカフカは勤務が不可能となり、年金生活者となりますが、困窮する生活の中で病状が悪化し、40歳と11ヶ月でこの世を去っていきます。1924年のことです。カフカの「変身」はその解釈をめぐってさまざまな研究がなされており、また「変身」に触発された映画や「変身」そのものを描いた映画も作られてます。「変身」と云うタイトルの映画だけでも、1975年にヤン・ニェメツが監督したTV映画「変身」を始めとし、1977年のキャロライン・リーフ監督によるアニメーション「ザムザ氏の変身」、1987年にはジム・ゴダード監督でTV映画「変身」、2002年には有名なワレーリイ・フォーキン監督による「変身」が上映されています。これらの映画に描かれている主人公は虫と云うだけで、ゴキブリのようなナンキンムシのような、いっこうに形体がハッキリしませんね。実はカフカが「変身」を発表したとき、彼は出版社に対して「昆虫そのものを描いてはいけない」「遠くからでも姿を見せてはいけない」と注文をつけていたのです。これはドイツ語の原文が「Ungeziefer」なっており、古高ドイツ語では「生け贄にできない不浄な動物」を意味する単語なんです。つまりカフカはどんな虫に変身したのか、読む人の想像にまかせていたのですね。先に上げた「変身」の映画画像を観て、どっかで見たような?と思いません。そう、テレポットと云う転送装置にハエが紛れ込んでたため、人間がハエに変身してしまう映画「ザ・フライ」。この作品は1986年の映画ですが、1958年に公開された映画「ハエ男の恐怖」のリメイク版です。このザ・フライの監督をしたデヴィッド・クローネンバーグは、カフカの「変身」に触発されて映画を作ったと述べています。「変身」はまた舞台化もされてます。それもバレエやオペラに。有名なのが1969年に初演されたイギリス人演出家スティーブン・バーコフのバージョンで、バーコフ自身のほか、ロマン・ポランスキー、ミハイル・バリシニコフ、ティム・ロス、また日本では宮本亜門や森山未來が主人公役に挑戦しています。私にはデビッド・リンチが監督した有名だけど、とても難解な映画「イレーザーヘッド」もカフカの影響が大きくのしかかっているように思えてなりません。「変身」は虫に変身した男の悲劇と捉えられがちですが、どっかユーモラスな部分が見え隠れしています。だいたい虫に、それも突然変身するって発想自体が奇想天外。実はカフカはこの作品の原稿を朗読する際、絶えず笑いを漏らし、時には吹き出しながら読んでいたと云います。学者先生が深刻な物語と受け止めて、研究に余念がないのを尻目に、カフカは出版物が文字の大きさや版面のせいで作品が暗く、切迫して見えることに不満を抱いていたと云います。最後にカフカ自身を描いた映画をご紹介しておきましよう。「KAFUKA/迷宮の悪夢」1991年に上映された私の大好きな映画です。ここでも現実と非現実が入り乱れたストーリーで、非常に興味深い映像美を見せています。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 3, 2016
コメント(7)
-

お年玉
なんだかあれよあれよと云う間に年末になってしまいましたな。来月はもう新年。歳を取ると、とりわけ時間が目覚しく流れていきます。新年と云えば、お年玉。お年玉と云えば、お金を包むものですが、お年玉の「玉」=「お金」?実は「玉」はお金ぢゃなくて、もともとは「お餅」だったのですな。それも「魂」が宿ったお餅のことです。そもそも正月は、年の初めに「年神」さまを家族そろって迎えて祝う行事でした。そこで年神さまをお迎えするため、古くから供え物として丸い鏡餅を重ねて供えてきたのです。年神さまは家に来ると鏡餅に依りつくので、鏡餅に年神さまの魂が宿ると考えられてました。この年神さまの魂が宿った丸い餠の玉を、その年の魂となる「年魂」といいます。そしてこの鏡餅玉を家長である父親が家族みんなに「お年魂」として分け与えて食べるのがしきたりでした。それが雑煮で、餠を食べることによって、年神さまの魂を体内に取り込むと云う意味があったのです。このように昔は年の初めに年神さまから、その年の魂を分けていただいて、新しい1年をはじめる習慣がありました。そのため元旦を迎えると、みながいっせいに年をとる「数え年」だったのです。つまり「お年玉」の「玉」はお金ではなく、神さまの魂だったのですね。かつては餠を分けてたのが、室町時代からは目上の者が「刀」「扇」「茶道具」などを目下の者に与えるようになり、いつからかそれがお金に変わったのです。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 2, 2016
コメント(6)
-

"世界初のウェブサーバ"と"日本最初のホームページ"
世界で最初のウェブサーバ(ウェブブラウザに対してHTMLや画像などの表示を提供するソフトとコンピュータ)はなんとNeXTで作られていました。NeXTと云うコンピュータはアップルのスティーブ・ジョブズが一時アップルを辞め、1985年に創業した会社の製品で、革新的なシステムだったのですが、とにかくべらぼうに高価でほとんど売れませんでした。日本ではキャノン販売が代理店をしてました。しかしその遺産は現在のアップルのMac OS Xの基盤として生き続けています。NeXTのOSはミニコンピュータ用OSのUNIXを使っています。これが"世界初のウェブサーバ"です。ウェブサーバとして稼働し始めたのは1991年のこと。スタンフォード大学でのことですこの1台のサーバーマシンから私たちが利用しているWWWの歴史が始まったのです。キーボードの上にあるのはWWW(ワールド ワイド ウェブ)の起案で、NeXTマシンに貼ってある紙には「この機械はサーバである。電源を落とすな!」と書いてあります。このサーバを作ったのは物理学者ポール・クンツです。画像背後にNeXTマシンが写っています。これに先立つ1989年、欧州の物理学者ティム・バーナーズ=リーとロバート・カイリューがWWWを提案します。これがあったから今日のネット社会が出来上がったのです。ティム・バーナーズ=リーは世界初のウエブブラウザとHTMLエディタも作っています。このティム・バーナーズ=リーからサーバ設置を要請されて作った日本最初のウェブサーバがこれです。文部省高エネルギー加速器研究機構(KEK)で1992年にセッティングされました。ディスプレイの下にあるのがコンピュータで、いちばん下は外付けのハードディスクです。なんとディジタル・イクイップメント(DEC)製のマシン!DECはかつてアメリカを代表するミニコンピュータの企業だったとこです。安価なPCに侵食されて、コンパックに買収されましたが、そのコンパックはヒューレット・パッカード(HP)に買収されているので、現在でもDECの製品群の一部はHPで販売され続けています。DECはミニコン・メーカーなので、使ってるOSはUNIX。と云うことで、黎明期のインターネットはUNIXと切っても切れない関係だったのです。ちなみにこの時表示されたホームページはこれです。なんとも味も素っ気もないページですが、昔のホームページはみなこんなだったです。このシステムを作ったのは高エネルギー加速器研究機構、計算科学センターの森田洋平博士です。博士の回顧を見ると、当時のコンピュータのスペックの低さと、回線速度の遅さで数十行程度のファイルを転送するのに転送の様子を目で追いかけることができるぐらいだったらしいです。ところでホームページを閲覧するのにウェブブラウザが必要ですよね。皆さんは何を使ってらっしゃるのでしょう?私は「Firefox」一辺倒です。「Opera」は勝手に自宅PCの情報を収集するので使っていません。「IE」は...(笑)世界初のブラウザは「Mosaic」と信じている人が多いですが、実はMosaic以前に最初のブラウザが登場してました。名前は「WorldWideWeb」ってそのままですがな(笑)リリースされたのは1991年。これを作ったのが先ほど出てきたティム・バーナーズ=リーで、これが稼働してたのは世界初のウェブサーバと同じ「NeXT」だったのです。1993年に「Mosaic」が登場しました。Mosaicは画像が扱える最初のウェブブラウザで、これによってウェブの利用者が激増するきっかけとなったのです。これを作ったのは米国立スーパーコンピュータ応用研究所(NCSA)の Mosaic チーム。チームリーダーのマーク・アンドリーセンはその後まもなくネットスケープを設立し、Mosaicを汲む Netscape Navigator を1994年にリリースしました。このブラウザは瞬く間に世界中のもっとも主流なウェブブラウザとなり、最盛期には全てのウェブにおいて9割もの利用率を占めたのです。これにマイクロソフトが反応し、米国立スーパーコンピュータ応用研究所から1995年にMosaicのライセンスを引き継ぎ、Internet Explorer を開発するのですな。マイクロソフトはIEをWindows に同梱させることでIEに力を持たせることができたのです。これによって2002年にはIEの利用率は95%を超えることができたのですが、現在では20%程度です。2015年時点で世界シェアのトップをいってるのは「Chrome」です。ところが日本国内に限ると、依然としてIEのシェアは高く過半数を占めているのですな。Windows 10のリリースに合わせて新たに「Edge」が登場しましたが、まだまだシェアはとても低いです。中之島公園の猫たち-SAVE THE CATS IN NAKANOSHIMA PARK-」整備工事で閉鎖になった大阪の中之島公園。そこに暮らしてた約70匹の子供たち。心あるボランティアのご尽力で「猫の部屋」と呼ばれる仮住まいを得ることができました。すこしずつ里親さまも決まってきてますが、まだまだ多くの子供たちが良いご縁を心待ちにしています。なを「中之島公園の猫たち」では恐縮ですが現金によるご支援は一切お断りしております。「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」が実施されています。そちらのリンクもありますので、大阪市在住の方はぜひ見てください。
Dec 1, 2016
コメント(6)
全31件 (31件中 1-31件目)
1