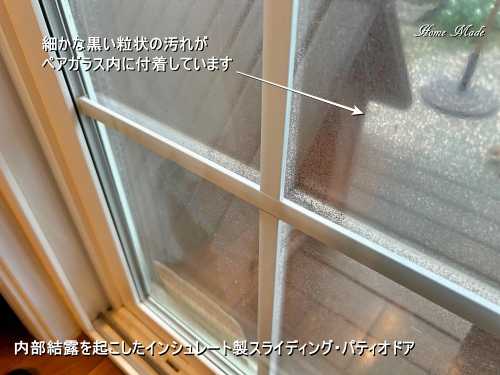2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2010年11月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-

七年目の連獅子
この日は、ブルーグレーの色無地と組紐織りの袋帯という、私物ランキングではかなり格上の部類に入るコーディネートでお出かけ。mayさんと特急に乗り合わせて、名古屋に降り立ち、目指すはJRタカシマヤのタカノフルーツパーラー。フミさん、おーこさんにご一緒させていただいて、美味しいパフェを堪能しました。フミさんとおーこさんは、素敵にお似合いなヅラウィッグを着用。私はいちごのパフェ、mayさん達は洋ナシのパフェ。大粒いちごの下には、カスタード系のクリームが入っていて美味しかった!次にmayさんと向かったのは御園座。にっぽんちゃんと合流し、三人で「十七代中村勘三郎 二十三回忌追善舞踊会」を鑑賞してきました。満員御礼の札がかかる御園座。大阪での「平成中村座」を終えたばかりでお疲れなのでは…と思いきや、この日の舞台が先代の追善公演ということもあってか、どの演目も気迫と集中力が漲り、感動的な見ごたえでした。七之助さんの「藤娘」、きれいだったね良かったね~…と余韻に浸りつつ。幕間に名物の最中アイスをいただきました。皮がパリパリで美味しい!最後の演目は、勘三郎、勘太郎、七之助父子による「連獅子」。この三人の連獅子を、私は歌舞伎座でも観ました。2003年3月のことです。日付をはっきり覚えているのは、その日、アメリカがついにイラク空爆を開始した、というニュースが駆け巡っていたから。幕見席のチケットを買う行列に、ざわざわとその話題が広まっていった時のイヤな胸騒ぎは、忘れられません。…あれから七年を経て、再び観る連獅子。それはそれは、お見事でした!躍動感に満ちた仔獅子たちを、親獅子の貫禄ががっちりと受け止めていて、歳月を重ねて芸が練り上げられて来たことがひしひしと伝わってきました。本来、二人で踊る振付を三人で舞って、それで破綻しないためには、計算された動きを完璧にこなし、狂いのない同調性を保たなければいけない訳で…その点、もうまったくお見事、というほかなく。クライマックスの毛振りでは、たてがみが描く軌跡までがキレイに揃って見えるのです。その回数が30回、50回と続いていくにつれ、場内で鳴り止まない拍手にどよめきが加わり、舞台と客席が一つになって大盛り上がり!私も興奮し、圧倒されてしまい、目頭が熱くなりました。その後、お約束(?)のカーテンコールの後、最年長のお弟子さんである小山三さんが舞台袖から呼ばれて、満場の拍手を浴びながら感無量のご様子…こちらももう、涙腺が決壊してしまいました。二日間だけの特別公演で、こんなにエキサイティングな思いをさせてもらって、お誘いいただいたmayさんにっぽんちゃんに感謝です。この日のおしゃれのワンポイントは、カメリアの帯留です。アクリル樹脂のパーツと帯留パーツを購入して手作りしました。材料費約300円(笑)
2010.11.29
コメント(4)
-

晩秋の海へ
今週末、義父母から「伊勢志摩旅行の通りがかり(?)に訪問したい」という申し出があり、一緒にご馳走を食べて、旅先までお送りしましょう、という話になりました。駅でお出迎えの後、雲ひとつない秋晴れの下、海辺を目指すドライヴの始まり!インターの入り口。山の木々は様々な色あいに染まっていました。伊勢市から志摩市へ向かう山あいの道。紅葉見物を満喫できました。到着したのは的矢湾。名産の養殖牡蠣のイカダが凪いだ海に浮かんでいます。見学用(?)のデッキに下りて、興味津々のお母さんと夫。私達がお二人をお連れしたのは、養殖場のすぐそばにある、秋~冬しか開店しない小さな牡蠣料理の専門店。的矢の牡蠣は、高級ホテルの指定銘柄になるくらいの品質を誇るブランド品だそうですが、産地でいただく分にはかなりリーズナブル。何より美味しい!ここの牡蠣の味を知ってからは、お高いオイスターバーで輸入物の牡蠣を食べる気がしなくなってしまいました。加熱しても縮まない見事な牡蠣。アツアツジューシーな焼き牡蠣が最高!今回の義父母の旅行は、母方の五人きょうだいとその伴侶が集まっての親睦会。お腹いっぱい冬の味覚を先取りした後、無事に集合地点までお二人を送り届け、結婚式以来ご無沙汰していた叔父さん、叔母さんとも再会を果たして、解散しました。
2010.11.27
コメント(0)
-

reunion
今年の秋は、不思議と「再会」の機運に恵まれていました。これまでも帰省の都度、友達と連絡を取って会っていましたが、今回は「偶然が偶然を呼ぶ」といった巡り合わせがいろいろと重なり、かつての同僚、中~高校の同級生、お世話になった先生…といった具合に、懐かしい顔ぶれと久しぶりに集まることが続いたのです。それぞれ、5年ぶりとか6年ぶりとか、中には9年ぶりの再会(!)という人もいました。興奮気味の挨拶の後、おしゃべりが始まれば、年賀状だけのやり取りでご無沙汰していた年月もあっという間に飛び越えてしまい…一緒に過ごした頃の感覚が、すぐに甦ってくるのには驚かされました。それだけ、共有している思い出が輝いているという証なのかも…そんな風に考えれば、熱い心で真剣に物事に打ち込む経験というのは、なんて豊かな贈り物を与えてくれることか。と、改めて気づかされたのでした。日曜日は、高校の同級生が出演するピアノリサイタルを聴いてきました。主宰は彼女の恩師に当たる方。最後の演奏が終わった後の挨拶で、この日の準備に奔走された別のお弟子さんが、二ヶ月前に突然の病で急逝されたことを、声を詰まらせながらお話になりました。そして、その方の霊が安らかであるように、感謝をこめて…と、チェリストの方とサン・サーンスの「白鳥」を合奏されました。亡くなられた方を直接には存じ上げない私でも、つい目頭が熱くなるほど想いのこもった、気高く美しい「白鳥」でした。忙しさに取り紛れて疎遠になっていても、元気でいれば、いつかは会える。会いたいと思える人がいること、会って話が出来ること。その有難さをたくさん実感したこの秋の、忘れられない出来事です。銀座資生堂ビルのクリスマスツリー。なんだか紅葉の盛りにも見えます。向かいのビルの緑のツリーが左側の窓に映って、クリスマスカラーの彩り。
2010.11.25
コメント(2)
-

UTAU
溜まった有給休暇の消化を兼ねて、一週間の予定で横浜に帰省中です。APEC開催時の厳重警備が解かれて、街はすっかりクリスマスの装いですね。発売前から楽しみだった、坂本龍一×大貫妙子のコラボレーションアルバム「UTAU」。ツアーもぜひ聴きに行きたい、と思っていたのに、最寄の会場に来る日は日程が合わず、泣く泣く断念。ところが偶然が重なり、詰まったスケジュールの合間を縫って東京公演の初日に行くことが出来ました。ピアノ1台とヴォーカルだけの、簡潔なステージから届く音の美しさ、奥深さ。教授のエモーショナルなピアノも、大貫さんのヴェルヴェットのような歌声も、年齢を重ねても変わらぬ魅力を放っていて、堪能しました。夫婦とも恋人同士とも異なる、「信頼しあう仕事仲間」の絆にも魅力を感じます。四半世紀という時間が熟成させた、素敵な関係性がそこにはあるのだと思います。二人の音楽を一番聴いていたのは、十代の終わりからの約10年でしょうか…鼻歌で諳んじるほど好きだった曲が演奏されると、何とも言い表しようのない感慨が胸にこみあげてきて、涙がこらえきれなかったです。そういえば、レコードでしか持っていないアルバムもあるなぁ、CDで買い直そう!と思った次第(笑)音楽が、普段は意識しない心の深い場所にどれほど根付いているものか。その力を再確認させられた、至福の2時間でした。今夜、一番泣いてしまった曲。この曲が収められた「Cliche」は名盤です。(それにしても残念だったのは、客席のあちこちからひどい咳の音が聞こえていたこと。それも演奏中…場内の乾燥がすごかった上に、途中から空調が効いてきたせいもあるのでしょうが、風邪気味ならそれなりの対応をするのがマナーでは?とも思うのです。自分の持っていたのど飴をばら撒きたくなりました・苦笑)大貫妙子 & 坂本龍一 / UTAU 【CD】価格:1,890円(税込、送料別)
2010.11.22
コメント(2)
-

大人の文化祭
諸事情により半年間お休みしていたお茶のお稽古を、先月から再開しました。…ところが、長いブランクが明けて間もないというのに、これまた諸事情により、今日はお茶席でお点前をすることに(泣)そのことが決まって以来、アメリカの中間選挙を伝える新聞の「茶会旋風」という見出しの文字にもドキっとする始末。私が茶道を習っているのは市民講座のクラスなので、講座全体の発表会に毎年お茶席で参加しているのです。本格的な社中のお茶会と比べれば、学校の茶道部の文化祭のようなもの。とはいっても、お客様に粗相のないよう気をつけなければいけないことには変わりなく…責任重大。自分なりに努力はしましたが、大先輩のお姉様方には居残り特訓を命じられ、先生からは「…とにかく、姿勢だけはシャーンとしてなさい。ちょっとでも上手に見えるから」という、あきらめの境地のようなアドバイスをされる始末(笑)その上秋の花粉症で体調も急降下!でも、「転ばない」「こぼさない」「落とさない」という、自分で掲げた三つの目標(低すぎ?)は達成できたからよかった。無我夢中で終わった一日、帰宅して着物を脱いだら、腰から下の関節すべてがギクシャクするほど疲れていました。遊び歩いている時は苦しさなど感じない着物も、畳で立ったり座ったりを一日くり返すには、私の場合まだまだ大変…修業が足りませぬ。先生がいつもおっしゃるのは、「お茶一杯をいただくのでも、その裏でどれだけの大変な準備がされているかを思い起こさないといけない」ということ。一度でもそういう立場を経験すると、本当にそのことが実感できます。お稽古ごとには多少のわずらわしさもつきもの。でも、自分に甘くてすぐに現状に満足する私のような人間には、出来ない自分を叱咤激励してもらう機会がつくづく必要なのだと思う次第です。 床の間の軸は「開門落葉多」あとむちゃんが用事の合間に来てくれました。感謝!
2010.11.14
コメント(6)
-

フィギュアスケートは愉し
週末を心待ちにしながら平日を乗り切る、というパターンはいつものこと。ただ、特にこの時期、フィギュアスケートが大好きな私には、毎週のようにグランプリシリーズの試合が予定されている…という楽しみがあります。過日、生まれて初めて生で見るアイスショーを体感して、一層その魅力に引き込まれたばかり。オリンピック翌年のシーズンは、引退・休養する有力選手もいて"ちょっと一休み"な感もありますが、有望な若手の台頭や、ベテランが挑む新境地…などなど、見所はたくさん。今年も、テレビの前で熱く楽しませていただいております。しかし、ほんの数年前までは、フィギュアスケートをテレビで観戦すること自体、今ほど機会に恵まれていませんでした。荒川さんが世界選手権で優勝した頃など、ニュースの扱いはとても小さかった記憶があります。私が好きな男子シングルも、完全に女子の「添え物」という感じで、ペアやアイスダンス同様、放映時間は大幅カット(涙)それを思えば、日本人選手の層がこれだけ厚くなって、公式戦の多くがテレビで見られるようになったのは大変ありがたいこと。そればかりか、YouTubeにTwitterにストリーミング中継…と、ネットを駆使すれば選手や試合の情報から過去の名場面まで、手軽に見られる今の状況は夢のようです。こちらは長洲未来選手がツイートで紹介して有名になった動画。名作です。何度見ても笑える!これを見てしまうと、佐藤コーチと小塚くんの2ショットを見るたび、つい脳裏に妙なメロディが…(ごめんなさい)。「夢のよう」と言えば、一昨年は怪我で不在、昨年は「五輪までにコンディションが戻るのかな」とドキドキして見ていた高橋大ちゃん。今シーズン、いきいきと氷上で踊りまくってくれているのが、本当にうれしい!はじける火花のように激しいショートプログラムのマンボも最高ですが、フリーのピアソラのタンゴもくり返し見たくなってしまいます。音楽と一体化して、メロディやリズムに細かくこまかくエッジワークを同調させていく、前半のステップシークエンスが大好き。プログラムの構成も衣裳もヘアスタイルも、シーズンの大詰めに向けて修正が重ねられていくことでしょう。他の選手たちも含め、ワクワクしながら最終形の完成(と、それについてくる結果)を待ちたいです。夢中になれるものがあれば、寒い冬もまた楽しい!
2010.11.12
コメント(2)
-

柳家三三 ひとり会
日曜日のキモラク(着物で落語)、行く先は名古屋の「柳家三三ひとり会」。落語に造詣の深い知人から、ずっとお奨めされていた噺家さんの一人。今回初めてその高座を聴けるということで、この日を楽しみにしていました。落語会の前に、1月の「りらっくご」のチケットを受け取るため、ことりさんと待ち合わせ。にっぽんちゃん、トモさんともご一緒させていただいて、会場のガスビル地下にて、ひつまぶしのランチを楽しみました。食べながら、フィギュアスケートのこと、歌舞伎のこと、その他おしゃべりの話題は尽きず…好きな分野が同じでも、ご贔屓や趣味が違ったりすると、かえって興味のない人と話しているより余計に気を使ったり、険悪なことになったりするものですが(苦笑)逆に「そうよね、そうなの!そう思うでしょ??」と、「我が意を得たり」な会話が続くと、これほど楽しいことはなく。私、相当テンションが高くなっていたと思います…失礼いたしました(汗)ことりさん、私、にっぽんちゃん、トモさん。会場で合流した夫に撮ってもらいました。この日の客席は、シックな着物姿の女性がたくさんいらして素敵だった。 出演者と演目。 柳家歌る美 「堀の内」 柳家 三三 「鮑のし」 -仲入り- 日向ひまわり 「出世馬喰」(講談) 柳家 三三 「笠碁」前座の歌る美さんと、ゲストの講談師ひまわりさん、「両手に花」の三三さん。10分間のお仲入りをはさんで、たっぷり2時間半、話芸に浸りました!三三さんの、師匠譲り(?)の長くて濃密なマクラも楽しかったです。落語に時折差し挟まれる時事ネタも、ピリっと効いていて。街で声をかけられる時に「いつもテレビで見てます」と言われたら、その相手はウソつき…と、笑いを取っておられました。確かに、これまで小三治師匠の映画や、チラシの写真等でしかお姿を拝見したことがなかった私。妙なことを言うようですが、実は未だに、三三さんのお顔の印象が安定しない。三三さんってどんな顔してたっけ?と、首をかしげてしまうような。高座の様々な場面を捉えた写真などは、角度や表情によってまったく違う人みたいで、これはある意味「変幻自在」ということ?落語の登場人物の中に、三三さんという個人のキャラクターはすっかり溶け込んで見えなくなっているのに、高座を通して聴けば、そこにははっきりと個性や独自の味がある…落語って不思議で面白いものだな、と思います。本当に楽しい一日でした。
2010.11.08
コメント(4)
-

水玉蝶々
週末ごとに遊び歩いている割には、着物に袖を通す機会が少ない今年の秋。今日は、久しぶりのキモラクでした。先月は、まだ袷では暑さを感じる気温でしたが、さすがに空気はヒンヤリ。外に出た瞬間、手袋とショールが要ったかな…と後悔しましたが、人混みや屋内ではやっぱり暑い!つくづく、温度調整って難しいです。麻の葉つなぎの江戸小紋に、大好きな水玉の帯。 そして、ココロヤさんのイベントで購入した、すずめのトランクさんの帯留をデビューさせました。(当日の日記…「伊勢木綿を買いに」)一緒に購入した伊勢木綿は、お仕立てに出したばかりでまだまだお預けですが、この帯留を見た瞬間、実は真っ先に手持ちの水玉帯が頭に浮かんだのです。写真では今ひとつ、帯留の可愛らしさが上手に撮れなくて残念ですが(涙)ポンポンと散った刺繍の水玉の中で、蝶々が羽根を休めているようで…鏡を見てうれしくなってしまいました。
2010.11.07
コメント(8)
-

「アルゼンチンタンゴ 伝説のマエストロたち」を観た。
今から約半世紀前の、タンゴ黄金時代に活躍していた名演奏家たち。彼らが集結して行われたレコーディングと、一夜限りのコンサートの模様を通して、往年のスターの姿を追ったドキュメンタリー映画です。ちなみに、上の写真の場面でバンドネオンを演奏している方、当時の年齢なんと96歳(!!)。カフェや競馬場へ行ったり、サッカー観戦を楽しんだりする彼らの日常生活も紹介されていて、その様子は一見、穏やかに余生を楽しむ老人としか映りません。(ちなみに、サッカースタジアムの熱狂ぶりはハンパない!さすがはマラドーナを生んだ国です)それが、ひとたびマイクの前に立ち、楽器を手にすると…私はそもそもタンゴの黄金期を知らない年齢ですし、コンチネンタルタンゴと黒猫のタンゴの区別もつかない門外漢。当然、登場するミュージシャンの名前もすべて初耳だったのですが、90分余のあいだ、優雅でノスタルジックな音楽の美しさに存分に酔いしれました。レコーディングスタジオで、自分の演奏を聴いて満足気な表情を浮かべる姿や、オペラハウスで行われたコンサートで満場の拍手に包まれている様子…それぞれの、人生が報われる瞬間。その輝きが、観ているこちらの胸を打ちます。(いい年齢を重ねた顔って、本当にかっこいいなぁ!予告編でその片鱗をご覧ください)映画の撮影期間から現在に至るまでに、出演者のうち8名がすでにお亡くなりになったのだとか…そう考えると、より一層、CDや映画として残った記録の価値を感じます。惜しいのは、映画の後半、壮麗なコロン劇場(世界三大オペラの一つだとか)で行われたコンサートの場面が、かなり端折った内容だったこと。せっかくなら、細切れのダイジェストではなく、もっとそれぞれの演奏をたっぷりと聴きたかった…それだけは残念でした。往年のスターを勢揃いさせた、このオムニバスCDの企画がすべてのスタートだったとか。2006年ラテン・グラミー最優秀アルバム賞受賞。【送料無料】Cafe De Los Maestros: アルゼンチンタンゴ伝説のマエストロたち 輸入盤 【CD】価格:2,940円(税込、送料込)
2010.11.03
コメント(2)
-

錦秋文楽公演
日付が前後しますが、土曜日のこと。季節はずれの台風の動向を気にしながら、半年ぶりの国立文楽劇場へ行ってきました。この日初日を迎えた、錦秋文楽公演。夜の部の演目は「一谷嫩軍記」(いちのたにふたばぐんき)と「伊達娘恋緋鹿子」(だてむすめこいのひがのこ)です。 お人形の細部をしっかりと見たくて、今回もつい、前から三列目の席を取ってしまいました。大夫さんと三味線の様子を見る時は真横を向かねばならず、ぐるぐると頭を動かして、すっかり首が痛くなりました…ちょっと反省。それにしても文楽は、演者と観客の垣根が本当に低い。文字通り「手の届きそうな」近くに名人が、人間国宝がいる!という状況に、未だにドキドキしてしまう私です。「一谷嫩軍記」は、源平の合戦の一幕を描いたもので、熊谷直実一家の悲劇を描いた「熊谷陣屋」の場面は、歌舞伎でも人気の演目です。…が、私はこのお芝居のあらすじが、あまりにも理不尽に思えてどうしても受け入れられず、どちらかというと嫌いでした。封建制の、武家社会ならではの悲劇を描いたものだと頭ではわかっていても、主人公の行動に感情移入できなくて、涙より先に怒りが…(だって奥さん可哀想すぎるよ~)正直、文楽で見てもその感想は変わらなかったのですが(ごめんなさい)、終盤、登場人物たちの感情のボルテージが最高潮に達する場面での、義太夫と三味線の迫力は凄まじかった。聴いているこちらの心拍数がどんどん上がっていくような…人間の情念を表現するのに、太棹三味線の音色はかくも適しているのか、と感じ入りました。「伊達娘恋緋鹿子」は、いわゆる"八百屋お七"のお話。クライマックス、お七が火の見櫓へ登る場面で、びっくりする出来事!人形遣いが姿を消して、お七だけがするすると梯子を上がっていくのです。文楽では、一瞬で人形の首が落ちたり、早変わりしたりと、イリュージョンのような手法が時折出てきて目を見張るのですが、こんな手法もあるのかあ、とアイディアに感心しきり。仕掛けは単純なのですが、遣い手の技量で、人形に命が宿ったように見せてしまうのだからすごいものです。さて、どこでもmyアイドルを発見してしまう私には、実はお気に入りの人形遣いさんがいまして、今回もお七の仇役を熱演しておられました。(4月の公演では、お三輪をいじめる官女役の一人でした。いつか善人の役を見てみたい…)心配されていた台風もまったく気配を見せず、大満足のうちに劇場を出たら、品の良いジャケットをお召しの、小柄なおじいさんとすれ違いました。その面影に見覚えが…なんと、つい先程まで舞台上で、見台にのしかかるようにして熱演されていた、豊竹嶋大夫さんではありませんか!太夫の中でも四人しかいない、切場語りの地位にありながら、お付きの人もなく飄々と帰っていかれる姿…まったく文楽って、演者と観客の垣根が低いなぁ、と再度驚かされたのでした。*おまけ*劇場内の展示室には、実際に触って動かせる「文ちゃん」「楽ちゃん」というお人形がいます。今回、三度目の正直でやっと手に取ることが出来ました! 熱いまなざしを交す夫と楽ちゃん。…あやしい雰囲気???
2010.11.02
コメント(4)
全10件 (10件中 1-10件目)
1