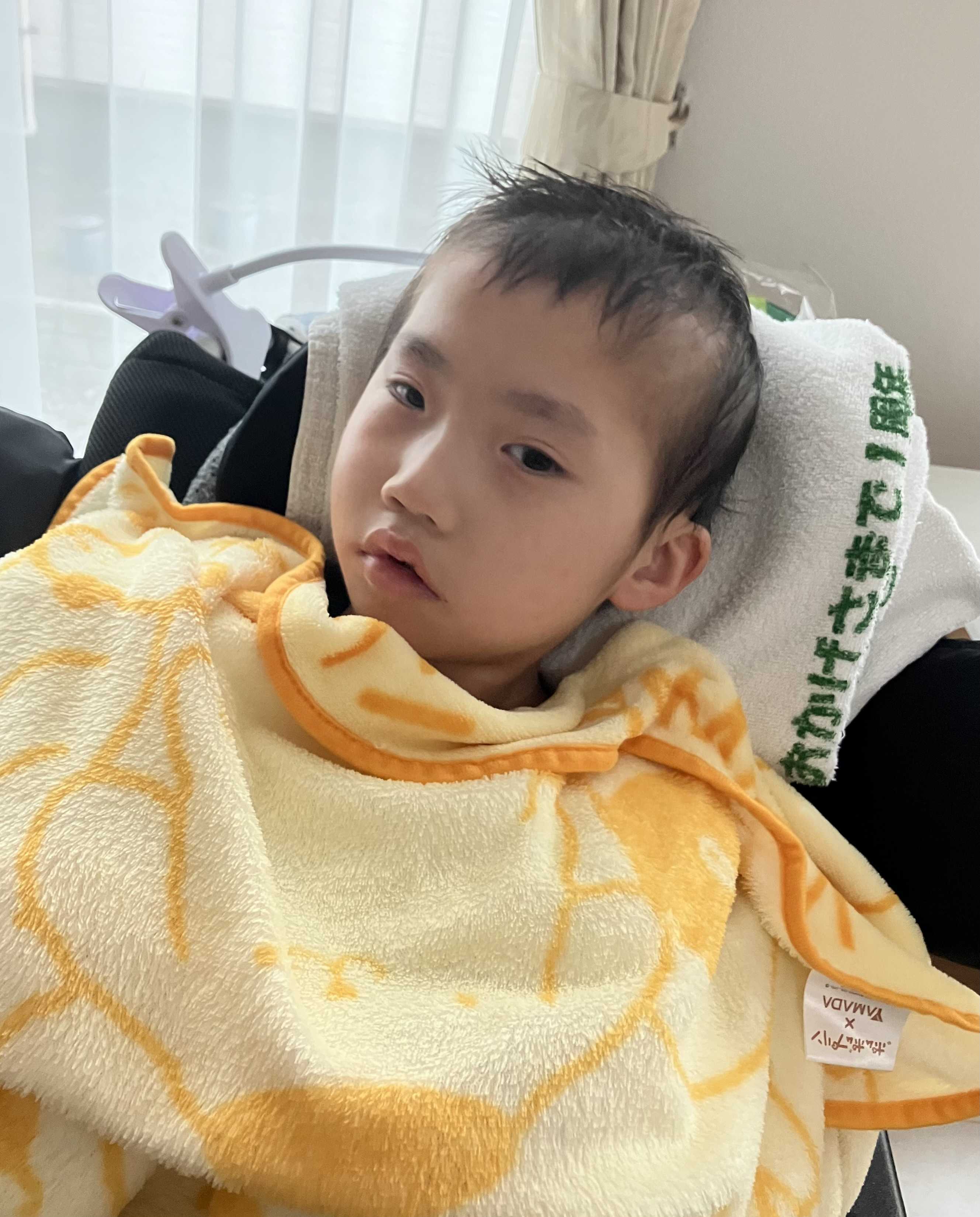全161件 (161件中 1-50件目)
-
タンパク質の反乱(5)
『タンパク質の反乱』石浦章一著 講談社ブルーバックス●四次構造の異常と病気「タンパク質の中にたとえ1個でも違うアミノ酸が挟まれば、フォールデングが十分にいかず、働きのないタンパク質が作られることがある。これが病気に結びつくことがある。… ヘモグロビンは、私たちの赤血球の中にあるタンパク質で、鉄を含んでおり、血が赤いのもこのためである。鉄分が不足すると疲れやすくなり、頑張りが利かなくなる。これが貧血である。からだに酸素が有効に運ばれなくなる病気なのだ。… このヘモグロビンは、4つの分子が1つに固まってはじめて活性をもつ四量体である。しかも、2種類のタンパク質αとβがα2β2という形で厳密に4分子まとまっていて、LDHのようにα3β1という形にはならない。 このうち「β」タンパク質の6番目のアミノ酸が、グルタミン酸からバリンへ変換している突然変異が見つかった。これが鎌形赤血球貧血患者であった。この病気では、溶けているはずのヘモグロビンが赤血球内でからまり合ってフュラメントを形成し、その結果、赤血球が鎌のような形に変形してしまう。この赤血球は酸素と結合する能力が低く、貧血が強くなる。(satom) タンパク質の変異と病気とは本当に深く関わっているんだと思いました。
2006.05.04
コメント(74)
-
タンパク質の反乱(4)
『タンパク質の反乱』石浦章一著 講談社ブルーバックスより●タンパク質の4次構造「タンパク質にはもっとおもしろいことがある。それは、タンパク質同士が会合(定められた形で結合すること)して機能をもつことが多いということである。…LDH(乳酸脱水素酵素)を例にとってみよう。 LDHは、生体内のどこにもあるタンパク質で、ピルピン酸を乳酸に変える酵素である。みなさんが「疲れた」といって風呂に入るとき、筋肉の中には乳酸が蓄積している。乳酸は疲労物質として有名で、栄養源のブドウ糖が酸素なしで分解するときに蓄積する。十分に酸素が与えられれば、途中のピルピン酸が乳酸にならずに、ミトコンドリアで燃やされ、多大なエネルギー産生とともに二酸化炭素と水まで分解される。 このLDHは、タンパク質としては四個が会合してはじめて活性をもつようになる。一個だけでは不十分なのである。このように、いくつかのタンパク質が会合して新しい構造をとることを四次構造という。ところが、LDHには骨格筋で作られるM型と心筋で作られるH型の二種類がある。筋肉内はM4であり、心臓ではH4となっているのだ。 血液の中では、筋肉から出たM型と心臓から出たH型が混ざり合って。混合型になっている。 …MもHも十分に存在すると仮定すると、四次構造を作る過程でM3H1とかM2H2ができる。高校時代に数学で習った「パスカルの三角形」より、M4:M3H1:M2H2:M1H3:H4=1:4:6:4:1になる。 ところが、心臓病で心臓の筋肉が壊れやすい場合には、血液中のHの割合がMに比べて高くなる(もちろん、骨格筋が壊れた場合には逆のことが起きる)。そうなると、比率は理論値より高くなるのである。 このように、血液中のタンパク質の性質を調べることによって、どの臓器が障害されているかをたちどころに知ることができる。GOTという酵素は肝臓に多いので、血液中にGOTが基準以上に出ていれば肝臓疾患が疑われることになる。(satom) なんとタンパク質がいくつか結合してはじめて活性が出るものがあるようです。タンパク質はアミノ酸の種類での違い(一次構造)、短い単位での構造(二次構造)、短い単位の構造が集まり一定の分子構造が完了(三次構造)、そしてそれらがいくつか結合して活性型になる(四次構造)というふうになっているようです。この複雑な構造の中でちょっとでも異変が起こると、活性を持たなくなる。ようするに体にとって重要な働きができなくなる。つまり病気になるということでしょうか。 それにしても健康診断の時の血液検査に出てくるGOT値って、つまり肝臓から漏れ出てしまうってことだったんですね。何か肝臓が悪くなるとGOTという物質ができるんじゃなくて、そもそも体にある酵素が雨漏れではないですが、肝臓の機能が悪くて漏れ出てくるということでしょうか。
2006.04.19
コメント(0)
-
タンパク質の反乱(3)
『タンパク質の反乱』石浦章一著 講談社ブルーバックスより●タンパク質は折りたたまれている「体内で合成されたタンパク質は、一本の長い鎖になっている。そしてこの鎖の中でアミノ酸の並ぶ順序が違えば異なるタンパク質になってしまう。… どんなタンパク質でも、機能を発揮するためには構造をもたなければならない。もちろん、小さなタンパク質は構造を持つことはないが、アミノ酸が十数個以上つながれば、自分自身で自然に一定の構造をとることが知られている。これをモジュール(ドメインとも呼ばれ、現在1000個ほどあることが構造解析の結果わかってきた)といい、長いペプチド(アミノ酸が数十個以下のものは、タンパク質と呼ばずにペプチドという)が構造をとるために巻き戻ることをフォールディングという。 一般に、どのような生物のタンパク質も、ドメインのつなぎ合わせでできている。ドメイン自体の大きさは変わらない。ところが…高等動物になればなるほど長いタンパク質をもっていることが知られている。 これは、進化の過程でドメインが次々につなぎ合わされて新しいタンパク質ができあがったことを示している。タンパク質の種類が増えるだけでなく、新しい機能をもったタンパク質ができあがるのである。 どうしてそんなことが可能になるかというと、遺伝子内である単位の長さ(これがドメインを決めている)が重複したり、遺伝子シャッフリングという遺伝子同士のつなぎ合わせが起こるためなのである。 これらのドメインは、アミノ酸がらせん状に巻くαヘリックス構造や、折り返しが続く平面状のβシート構造、まったく構造をもたないランダムコイルなど、短い単位での構造(二次構造)から成り立っている。また、一分子のタンパク質としてフョールディングが完了し、一定の分子の形を取るが、これを三次構造という。(satom) タンパク質はアミノ酸の配列の仕方だけではなく、その折りたたみの具合などの構造からも違いが出てくるようです。しかし、進化とはまさにタンパク質合成の歴史だったのでしょうか?
2006.04.08
コメント(0)
-
タンパク質の反乱(2)
『タンパク質の反乱』石浦章一著 講談社ブルーバックスより●タンパク質の分解とアポトーシス「…タンパク質は、生体内で常に合成されつつ、同時に分解を受けている。 …細胞は、不要なタンパク質や不適切に折り畳まれたタンパク質を細胞内から除去しなければならない。このためにも、タンパク質の分解は不可欠である。これに加えて、タンパク質の分解はもう一つ重要な機能をもっている。 ある大きな前駆体タンパク質から、限定分解という特別な分解によって新たな機能をもつタンパク質が作られることも生体の特徴である。この場合を特にプロセシングという。これらのタンパク質分解を適切におこなうには、細胞内に厳密な基質特異性(切断する相手がすでに決まっている)をもったタンパク質分解機構が存在するはずである。つまり何でも分解されればいいというものでなく、必要なものだけが必要な分だけ分解されることが必要なのだ。このタンパク質の分解が、「プロテオリシス」である。」「アポトーシスとは、あらかじめプログラムされた細胞死のことである。 …この死にゆく細胞には、ced-3という遺伝子が特別に多く発現していることがわかったのである。そこでced-3があれば必ず細胞が死ぬかどうか確認するため、ふつう生きている細胞にced-3遺伝子を導入してみると、死なないはずの細胞でもアポトーシスしてしまう。この他に、ced-4という遺伝子も細胞死に必須であることがわかってきた。 また、ced-3による細胞死を防ぐレスキュー遺伝子としてced-9も見つかってきた。ced-9があれば、いくらced-3が働いてもアポトーシスが生じない。そうなると死ぬべき細胞が死なないために、正常に線虫が発生しなくなってしまう。 線虫ではなくてヒトで細胞死を起こさせたり、逆にそれを防ぐことができるならば、病気を治療できるのではないかと考えるのは当然のなりゆきである。 …研究者たちは、キラー遺伝子ced-3、補助キラー遺伝子ced-4、レスキュー遺伝子ced-9に対応する遺伝子を探しはじめた。その結果見つかったのが、ced-3に相当するカスパーゼ群、ced-9に相当するbcl-2であった。ced-3から作られるCED-3タンパク質は、実はタンパク質分解酵素(プロアテーゼ)で、よく似たものが10種類もあることが判明したのである。私たちはこれらを総称して「カスパーゼ」と呼んでいる。 …この線虫のアポトーシスの研究により、高等動物と一見下等な動物の間に、かなり似かよった生理機能が保存されていることがわかり、ヒトを研究する前に、扱いやすいハエ、線虫、酵母などでやってみるという風潮がいきわたった。 …細胞を殺すガスパーゼという酵素タンパク質は、細胞がアポトーシスするときにしか働かないと考えられている。ガスパーゼの一つの働きは、細胞の形を保つ構造タンパク質である細胞骨格を切断することである。 …個々のガスパーゼの機能差を調べたところ、意外な事実が浮かび上がってきた。あるガスパーゼは、特別なガスパーゼを活性化することがわかってきたのである。 たとえば、細胞膜上にあるガスパーゼ-8は、細胞外からの刺激によって細胞質にあるガスパーゼ-3を活性型に変える働きがあり、このガスパーゼ-3が強いタンパク質分解能力を備えているために、細胞骨格タンパク質が切断されるのである。決して。ガスパーゼ-8が直接タンパク質基質を分解するのではないのだ。このような連鎖反応がおこなわれているために、10種類ものガスパーゼが必要になるのである。」(satom) タンパク質の分解には、やはりタンパク質である分解酵素が関わっているとのことです。それにしても不必要な細胞は速やかに分解して、排除しないと生体機能の妨げになってしまうようです。細胞のすさまじい数の「生と死」から私たちの体は成り立っているようです。
2006.04.04
コメント(0)
-
タンパク質の反乱(1)
『タンパク質の反乱』病気の陰にタンパク質の異常あり! 石浦章一著 講談社ブルーバックスより●からだはタンパク質からできている「生物のからだは、タンパク質で作られている。元素で書くと、C、H、O、N、Sの5元素から成る。炭水化物はC、H、Oだから、N(窒素)とS(イオウ)が余分に含まれていることになる。 肉の主成分がタンパク質であることはよく知られていて、肉の腐った匂いやおならの匂いは、含まれているイオウ化合物が変化したものである。肉食の割合が高い欧米人のおならや体臭が強いのも、そのためである。 また窒素化合物が分解して生ずるアンモニアも困り者で、この処理のために肝臓が存在するといっても過言ではない。肝臓を摘出したイヌは、数時間で血液中にたまったアンモニアのために昏睡状態に陥ってしまう。…」●タンパク質のパーツ「…実はタンパク質は、アミノ酸の重合物なのである。細菌の代表である大腸菌は、平均317個のアミノ酸で作られている。真核生物である酵母は平均484アミノ酸、同じ真核生物で動物の線虫は442アミノ酸、と高等になればタンパク質も長くなることがわかっている。… アミノ酸には、グリシン、アラニンなど20種類があることがわかっており、それぞれに大切な働きを持っている。※真核生物…真核細胞を持つ生物のこと。真核細胞の最も際立った特徴は、細胞内に細胞核(核)と呼ばれる構造を持っていることである。つまりDNAを持っていること。(satom) これはちょっと前に読んだ本なんですが、内容はほとんど忘れていました。今狂牛病や様々な病気の原因にタンパク質の変質(異常)があるということがよく言われるようになりました。改めてタンパク質についてちょっと知識を深めてみたいと思います。 それにしても欧米人の体臭が強いのは、タンパク質に含まれるS(イオウ)化合物が原因とのことです。では菜食主義の欧米人は体臭は強くないののでしょうか?。しかしイオウが含まれているアミノ酸は20種類のうち2種類(システイン、メチオニン)しかありません。この2種類のアミノ酸のためにあんなに匂うということでしょうか。 またたった5元素で20種類のアミノ酸だけで構成されているタンパク質が、数限りない種類を持ち、多様な機能をしているというのは何か不思議でしょうがありません。
2006.03.30
コメント(0)
-
抗癌剤(10)
『抗癌剤 知らずに亡くなる年間30万人』平岩正樹著 祥伝社より●肝臓癌の治療法「肝臓癌でわかりにくいのは、二種類の癌があることだ。 癌の「本籍」も「現住所」も肝臓というものと、「本籍」は他にあってそこから転移して「現住所」が肝臓癌という二つである。この二つは、性質も治療法もまったく異なる。本籍も現住所も肝臓、という本来の肝臓癌の中の肝細胞癌の治療法はたくさんある。1.切除。第一選択の治療法 肝機能が落ちている場合は、切り取る肝臓を小さくしたい。しかし、大きく取るより小さく取る手術は難しいのである。2.移植 癌を含めて肝硬変の肝臓をそっくり取り替える。新たな肝臓癌もできにくい。日本では、脳死臓器移植により生体肝移植が行われる。3.アルコール注入 飲酒は肝臓に悪いのに、肝臓癌には効く。ただしアルコールを飲んでもだめで、酒飲みの口実にならない。外から針で注射する。かつては手術に勝るとも噂されたが、治療成績は手術に劣る。手術できないケースが対象になる。4.ラジオ波焼灼は3にとって替わろうとしている。 針を刺して癌だけを焼く。手術できないケースで、小さな癌に有効。5.放射線 大きな癌にも有効。肝機能が放射線に耐えられるかの評価が大切になる。第三の放射線・陽子線が注目されている。6.肝動脈塞栓術 肝臓癌は動脈だけから栄養を受けているが、正常組織は動脈と門脈の両方から栄養を受けている。この差を利用する。癌を養っている動脈を閉塞させる。7.抗癌剤 10年前に「夢の抗癌剤」として世間を騒がしたインターフェロンは、夢で終わった。ただ肝臓癌や腎癌では効果があることが海外や日本の研究で報告されている。8.免疫療法 日大外科の高山忠利教授は、手術後に特殊な処理をしたリンパ球の投与が再発予防に有効と医学誌「ランセット」にも報告している。 これほど治療法の多い癌も珍しい。肝機能と癌の状態で絞り込むことになる。(satom) 一口に治療法と言っても、様々な方法があるものだなと思いました。多くの試行錯誤により少しでも癌に効く治療方法がだんだん分かってきたのかと思われます。切除が一番。切除できない場合、つまり様々に転移して収拾できなくなってしまった癌でしょうか、針で焼いたり、放射線を照射したりして局部に対処する。それでもだめなら抗癌剤でということでしょうか。
2006.03.16
コメント(0)
-
麻薬、脳内麻薬様物質(オピオイド)
●麻薬とは…精神に作用し、酩酊・多幸感・幻想などをもたらす薬物のうち、依存性や毒性が強く健康を害する恐れがあるために、あるいは社会に悪影響を及ぼすため、国家によって指定され、取締りの対象になるもの。→アヘン、モルヒネ、ヘロイン、コカイン、覚せい剤、大麻、LSD、MDMA、THCなど。○アヘン→アヘンに含まれるアルカロイドをモルヒネという→モルヒネからつくる依存性のきわめて強い麻薬塩酸ジアセチル-モルヒネのことをヘロインという。 つまりアヘン、モルヒネ、ヘロインとはその純度をどんんどん増すにつれて呼び名が変わるようです。○コカイン…コカノキに含まれるアルカロイド○覚せい剤…覚せい剤取締法で規制されている。中枢神経刺激剤である。アンフェタミン、メタンフェタミンなど。脳内で快楽神経系を興奮させるドーパミンに構造が似ている。○LSD…D-リゼルギン酸ジエチルアミドは、主にアシッドやLSDと呼ばれる。脳内のセロトニンの働きを抑制し強い幻覚作用を持つ。●脳内麻薬様物質(オピオイド) オピオイド受容体に作用する薬物の総称。オピオイド受容体とは、モルヒネなどの麻薬性鎮痛薬などが作用する受容体。歴史的には、まずモルヒネが関わる脳内の受容体が発見されて、そもそもそこに本来体内で作られる物質が働くはずだと探していたところ、エンケファリン、β-エンドルフィンなどが次々と発見されました。 そしてモルヒネ・アヘンアルカノイドやエンケファリン・β-エンドルフィンというオピオイドの大量放出は、一方で精神活動の鈍麻、鎮痛作用などがありますが、他方徐々に受容体の感受性が上昇して、禁断症状(依存性)のような状態に陥り、また危険なものなど避けなくなるようになるとのことです。またオピオイドの放出を受けるとGABA神経のドーパミン抑制が弱められてしまい、快楽神経系(A-10神経)のスイッチを入れるドーパミンが活性化したままになり、ハイな感じが続き、過剰になると幻覚・幻聴・妄想などが生じます。 ちょっとうまく説明できませんが(上記のオピオイドの説明はsatomがところどころ付け加えて書きました)、とにかく脳内の神経伝達物質と神経系とのやり取りは結構難解です。 でもごく簡単に言うと、麻薬も含めてオピオイドは、体の現実の信号、例えば炎症を起こして「痛い」という信号を、脳には伝達させないようにして、つまり騙して、さらに多幸感になるように脳内幻覚、つまり誤魔化しを起こさせるというような感じでしょうか。 しかし薬物の種類により、その騙し方と誤魔化し方の程度が違うようです。誤魔化しを何度もしていると、本当に現実感覚から乖離してしまうようです。ということでなるべく副作用というか依存性・毒性がない薬物が開発されているようです。 さて商品名デュロテップもフェンタニルというオピオイドとのことです。●フェンタニル フェンタニルの鎮痛効果はモルヒネの100~150倍(50~70倍といする報告もあり)とされており、100倍ですと塩酸モルヒネ注射液10mg1Aとフェンタネスト注射液0.1mg1Aが同等ということになります。副作用はモルヒネに比べて、便秘をはじめとする消化管の副作用や眠気、せん妄が少ないとされています。フェンタニルは肝で代謝されますが、代謝産物は活性を持たないので、腎機能低下による影響をモルヒネより受けにくくなっています。日本におけるフェンタニル製剤には経皮吸収剤のデュロテップと注射剤のフェンタニスト注射液があります。 またオキシドコンもオピオイドの1つとのことです。
2006.03.02
コメント(0)
-
抗癌剤(9)
『抗癌剤』平岩正樹著 祥伝社より●「痛い痛い」は昔の話「がんの種類はおよそ200もあり、性質や適切な治療法は、同じがんかと思うほど異なる。それでも相談にくる患者さんには共通する症状がある。「痛み」「体重減少」「抗癌剤の治療に伴う嘔吐」の三つである。 幸い、「痛み」の相談は最近少し減ってきている。きっと、新しい麻薬「デュロテップ」と無関係ではない。膏薬に似ている。三日に一回貼り替えるだけで、どんなに強い痛みでも消える。痛い部位に貼るのでない、からだのどこに貼っても効くから便利だ。 デュロテップは、日本人の麻薬アレルギーを解消してくれたのかもしれない。なにしろモルヒネだけに頼っていた時代、日本人の癌の患者一人当たりの麻薬使用量は欧米の患者の十分の一だった。長い間、日本の患者は痛みを我慢し、痛いままに放置されてきた。「癌は痛い痛い」神話の由縁である。 麻薬で痛みをとれば、患者の寿命が延びることは、欧米のいくつもの論文で明らかになっている。当然だ、痛いままでは、眠ることもできない。食事も満足に取れない。痛みを放置して、長生きなどできるわけがない。「人間やめますか」のコピーは、癌でない人だけに限って使わなければならない。(satom) 麻薬というとなんかダーティなイメージだけ先行して、薬としての意味合いは薄いですが、癌など重度な病気には必要なものらしいです。 さてなぜ、麻薬により「痛み」が抑えられるのでしょうか。またデュロテップとは何でしょうか。ちょっとブログで調べてみました。
2006.03.01
コメント(0)
-
抗癌剤(8)
『抗癌剤 知らずに亡くなる年間30万人』●分子標的治療薬?「…イレッサに下痢や発疹といった副作用は避けられない。でも、イレッサには他の抗癌剤のような副作用死が少ない。 なぜか?癌細胞表面にある上皮成長因子受容体(EGFR)のタイロシキナーゼを阻害する、という今までにない「理屈」がある。でもこの理屈も仮説にずぎないから、鵜呑みにしないほうがよい。 肺癌以外にも、多くの種類の癌細胞の表面にEGFRはある(それどころか正常細胞にもEGFRはあるのだ)。それなのになぜ、肺癌に有効なのか?数ある肺癌の中でも、なぜ肺腺癌に良く効くのか?どうして他の癌にはそれほど効かないのか?EGFRという理屈だけでは説明できない。… 『ニューイングランド医学誌』2004年5月20日号に、面白い論文が出た。…謎に挑んだのが、マサチューセッツ・セントラル病院のリンク医師だ。以下のことが明らかになった。(1)ある癌では、EGFRが癌細胞の細胞膜を貫いた部分に突然変異(ミュータント)がある。(2)ミュータントをもつ癌は、ミュータントが癌の成長を促進している。(3)イレッサはミュータントの部位と結合しやすい。(4)ミュータントは、肺腺癌に比較的多い。(5)非ミュータント癌では、イレッサを増量すると効果がでるかもしれない。」 『フリー百科事典 ウィキペディアより』「上皮成長因子(Epidermal Growth Factor)は53アミノ酸残其及び3つの分子内ジスルフィド結合から成る6045Da(ドルトン=単位)のタンパク質で、細胞の成長と増殖の調整に重要な役割をする。 EGFは高い親和力で細胞表面の特異的な受容体に結合することで、受容体に備わるタンパク質チロシンキナーゼ活性を刺激する。受容体のチロシンキナーゼ活性はシグナル伝達カスケードを開始して、最終的にはDNA合成と細胞増殖に導く。 多様な生化学的変化がシグナルカスケードの反応で細胞内で起き、それらの変化は細胞内カルシウム水準の上昇、糖分解及びタンパク質合成の増加、そして上皮成長因子受容体(EGFR)の遺伝子を含む明らかな遺伝子発現の増加となどがあり、全てが有糸分裂の準備である。 EGFRの変異はその直接の活性化を起こして、制御不可能な細胞分裂を引き起こし、ガンの始まりうる。結果EGFRの変異はいくつかのタイプのガンと同定され、抗がん剤治療の標的として注目されつつある。」『医者にまけない知識塾より(フリーページにリンク貼りました)』EGFR(上皮成長因子レセプター)「細胞の表面に存在する蛋白質で、EGF(上皮成長因子)が結合するレセプターである。 EGFがこのレセプターに結合すると、酵素の一種であるチロシンキナーゼを活性化させ(正確に言えば、EGFR自体がチロシンキナーゼで、EGFの結合によりEGFR自体が活性化する)、このことにより、その細胞の成長・増殖が開始される。 RGFRは、多くのガン細胞の表面に異常に高密度で存在することが知られており、従って、EGFがやって来ると、ガン細胞上のEGFRに多量に結合し、ガン細胞が異常に増殖することになる。 イレッサは、EGFRに予め結合してしまい、ERFが後から来ても結合できなくさせる。これによってガン細胞の増殖を抑制する。 EGFRを詳しく見ると、3つの部分に分けることができる。細胞外に突き出た部分(ここにEGFが結合する)、細胞膜中の部分、細胞膜の中にある部分、の3つである。 尚、上記のチロシンキナーゼというのは、蛋白質を構成するアミノ酸のうち、チロシンをリン酸化する酵素で、このことが細胞増殖の引き金になるのである。」(satom) 細胞を成長・増殖させるシステムの一部が変異によりおかしくなるとガンになってしまうようです。タンパク質の変異が、タンパク質合成の変異を呼び起こし、ガンになる。ガンはタンパク質変異のよるものらしいです。狂牛病もタンパク質の変異が原因のようです。 それにしてもちょっと難しいです。
2006.02.18
コメント(0)
-
抗癌剤(7)
『抗癌剤 知らずに亡くなる年間30万人』平岩正樹著 祥伝社より●わずかな副作用死を問題にする社会「日本の新薬承認は慎重である。「欧米で使われていて、日本では使えない抗癌剤のことについて、話を伺いたいのですが」とマスメディアから取材を受けることが多い。慎重な承認作業の間に、患者は命を失っている。 最近、製薬会社アストラゼネカから発売された、肺癌の新薬イレッサが承認された。せっかく日本が世界で初めて承認された薬だったのに、水を差す出来事があった。副作用死である。 2002年10月15日、アストラゼネカのAさんが、血相を変えて私のところにやってきた。その日の新聞で、アストラゼネカの非小細胞肺癌の内服薬イレッサによる、副作用死が13人出たと報道され、Aさんの用件もその報告だった。原因は間質性肺炎という。 私はその1ヶ月前、「イレッサは、致命的な副作用がない新しいタイプの薬と思われている。でもそれは世界の1000単位の患者への投与結果に過ぎない。今後もっと多くの患者に使われれば、何が起こるかわからない。稀な副作用死がどのくらい出るのか、世界の誰にも予想できない」と週刊誌で警告し、… 私だけでなく「癌細胞だけを標的にする分子標的治療薬」を鵜呑みにする医者なんて、ほとんどいなかったはずだ。「で、副作用死の分母は?」と聞くと、Aさんは、「7000人に投与した結果です」と答えた・0.2パーセントの副作用死なら、抗癌剤としては低い(その後、数字は1パーセントを越えたが、抗癌剤としては標準的である)。 …新聞はイレッサの稀な副作用死を大々的に報じた。多くの人がイレッサで命拾いしていることなどは、ほとんど書かないで不公平である。歴史的狂気といっても良い。 世界で抗癌剤が使われているのは、癌で100パーセント命を失うことがわかっている人にとって、抗癌剤は損な選択肢ではないからだ。」(satom) 癌医療の現場は激しい戦闘の前線なんだとつくづく思いました。戦争でどんどん負傷して倒れる中、起死回生の特効薬が使用されるのは仕様がない。使わなければ、バタバタと死んでしまうからだ。そんな修羅場に少々似ているのでしょうか。 それにしてもマスコミの芸能化は目を覆うばかりに見えます。人の関心を引こうと、ドラマばりの演出を凝らして、事件を面白おかしく報道している。なんにもその事件の本質に迫らないで、人々の感情を高揚するような瑣末な演出ばかりに終始しているように思えます。 ライブドア問題でも、少なくともマスコミであれば、薄々ホリエモンがやっているダーティな部分が分かっていたはずです。それを面白おかしく煽てておいて、急に手のひらを返したように中傷している。ドラマ化としか思えません。 健康関連についても、ひどくドラマ化してセンセーショナルな報道が多いようです。面白くないと視聴率が取れないということは分かりますが、情報発信という点では、メディアの死を意味するのではないでしょうか。様々なブログでの情報交換の方がずっとメディアとしては健全なんではないかと思います。
2006.02.10
コメント(0)
-
抗癌剤(6)
『抗癌剤 知らずに亡くなる年間30万人』平岩正樹著 祥伝社より●人がいない、お金がない、薬がない 「医学を東洋医学と西洋医学に分けるやり方は、良い分類ではない。たとえば抗癌剤のイリノカテンやカペシタビン、オキサプラチンなどは東洋人である日本人が発明した薬である。東洋医学の優れた産物と誇っても良い。 ところがイリノテカンは、日本より欧米で重用されいる。カペシタビン(03年発売)やオキサリプラチン(05年発売)に至っては、今でも日本では販売されていない。…日本人が使いたい場合は、わざわざ逆輸入しないといけないのである。 …手術治療の、高い成績レベルに比べると、「日本に抗癌剤治療はない」といっても言い過ぎではない。私はそれを「人がいない、お金がない、薬がない」と総括している。 アメリカには抗癌剤治療の専門家の医者が4000人以上もいるのだが、日本に何人いるだろうか。白血病を治療する血液内科を除けば、数えるほどしかない。数人ではないにしても、全国にせいぜい数十人である。大半は新薬の治験に追われている。」●抗癌剤治療の技術料はタダ「それでも、専門を越えて熱心に抗癌剤治療と取り組んでいる医者がいる。 あちこちの病院で、人目を忍ぶようにひっそりと治療にあたっている。ひっそりと影を薄くしているのには、以下のような理由がある。 ある病院の事務長に訊ねてみた。「患者が支払っている抗癌剤の治療費の内訳は、どうなっているのですか」「ほとんどが薬代ですね」…「手術や検査のような、医者の技術料はいくらですか」「技術料は、ないんです」…医療経済上、日本に抗癌剤治療は存在しない。…自分が手術した患者には充分なアフターサービスもできるが、よその病院で手術を受けた人の無料治療はやりずらい。これこそ癌難民発生の理由である。病院は「無料サービスだけ」の患者には、治療法はないと言う場面も多くなる。(satom) 日本には抗癌剤治療は存在できないようになっているらしいです。年間30万人もの人が亡くなる癌という病気の治療制度がこんなので良いのでしょうか。なぜ技術料はなしになっているのでしょうか。抗癌剤はあまり使うなということでしょうか。 NHKの番組で、医者の方が国は他の先進国の何倍もの公共事業をやってきて、先進国に比べて少ない予算で頑張っている医療関係費を財政赤字のための削減の槍玉に挙げるのか。こんな公共事業をやってきて赤字垂れ流しの責任は政治家に責任があると言っていました。しかし東北地方の建築関係の方は、でも東北地方ではまだ半分下水道が整備してないのですよ。つまりくみ取り式ですよ。そしてNPOの方は、とにかく国民の勉強が足りないんです。情報が行渡っていないから、そういう政治家を選んでしまうんです。もっと地道に勉強会をして、情報を集めるべきです。 つまり国は先進国の何倍もの公共事業をやってきた。それも下水道整備など基本的だが目立たない事業はあまりやらないで、誰も使わないような道路や橋や箱物をいっぱい作ってきた。それもある人に言わせると約30%は政治家やさまざまな利害関係者のリベートとなっているとのこと。→国の財政は大赤字になり。→医療関係費など国民の必要とする経費を削減しようとしている。 しかしそんな政治家を選んだのは国民だ。国民は何を考え、そんな政治家や行政を選んだのか。国民はバカなのか。情報が足らないのか。現在インターネットの普及により、様々な情報が政府や圧力団体の検閲から漏れて流れてくるようになってきました。情報を得ることで、賢い国民になり、ちゃんとした政治家を選び、ちゃんとした予算を組んでもらい、国民のためになる行政を行ってもらいたいと思います。
2006.02.08
コメント(0)
-
抗癌剤(5)
『抗癌剤』平岩正樹著 祥伝新書より●学会を支配する「癌の縮小至上主義」「世間で行われている抗癌剤治療は「癌の縮小至上主義」をめざしている。「癌が縮小しなければ、抗癌剤治療の意味はない」と考えているのだ。 たしかに、縮小しないより縮小したほうがいいに決まっているが、私はこの「縮小至上主義」に賛同しない。癌の「休眠」という方法もある。「休眠」には世間に大きな誤解がある。 休眠療法は特別な抗癌剤治療ではなく、行うことは通常の抗癌剤治療だが、治療の目標を「癌の縮小」に置くのではなく、「癌の成長の横ばい」に置くという概念的なものである。 …休眠療法とは、癌細胞の消滅と生成のバランスがとれている「結果」を言っているのであって、休眠させる特別な治療があるわけではない。副作用が容認できる範囲なら、縮小しないより縮小するほうが良いに決まっている。 …手術受けたが1年後に癌が再発した。いったん再発した胆道癌を治すなんて難しいから、最初から治療を諦める医者は珍しくない。都内某医大病院の主治医は「もう治療法はない」とNさんに最後通牒を出した。 Nさんの腹部CTでみると、癌性腹膜炎で溜まった腹水で灰色になっている。画面中央に胆道癌の再発がある。… それから約2年後に撮ったCT写真では、腹水は無くなっているものの、癌の大きさはほとんど変わらない。 癌を知らない人は、NさんのCTを見て、「2年も治療を続けて、癌は何も変わらないのか」と不満に思うかもしれない。「縮小至上主義」の抗癌剤研究者なら、抗癌剤は効いていないとNさんの治療をとっくに打ち切った違いない。 でも、Nさんは治療に満足している。Nさんの癌が縮小しないからといって、別に私はNさんの治療を手抜きしているわけではない。都内某医大病院を訪れれば、元気なNさんは幽霊と間違えられるに違いない。腫瘍マーカーのCEAは2年間で、15→8とゆっくり減少している。成長の速い胆道癌なのに、治療が元気な日常生活をもたらしている。(satom) 癌との「共生」ということもあるのかと思いました。癌というのは高速増殖炉のように、いったん増大すると加速度的に拡大するように思っていましたが、抗癌剤をうまく使うことによって現状維持の状態に抑えることができるようです。しかしそのためには、多種類の抗癌剤とその量の微妙なさじ加減が必要のようです。このような職人にような抗癌剤治療を専門に行う医師はごく少数のようです。なにしろ技術料はゼロと決まっているようです。何かおかしいなと思います。
2006.02.04
コメント(0)
-
抗癌剤(4)
『抗癌剤』平岩正樹著 祥伝新書より●「適量」は患者によって、まったく違う「薬の治療は、手術の「やるか、やらないか」の二者択一とちがって、間に無数の選択肢がある。たとえば「半分の薬量を試す」こともそうである。 通常、抗癌剤の量は患者の体表面積で決める医者が多い。だから電卓を叩いて薬の量を決め、「基準量」の治療をしようとする。そのほうが科学的治療の薫りもする。でも抗癌剤の適量には「体重面積に比例」以上の要因がある。 そもそも抗癌剤の適量には「個人差」があり、患者によって約十倍もの開きがあると思ってよい。抗癌剤の「基準量」は、多数の患者の平均値に過ぎない。計算した薬量に、絶対的根拠があるわけではないのだ。半量を投与してみることは、日和見主義ではないのだ。 胆嚢癌が再発したSさんがは、地元の病院から、もう治療法がないと告げられた。2001年7月から私が抗癌剤治療を続けているが、治療内容は、その後の1年間に以下のように変わった。(1)5FU+LV、(2)ジェムザール、(3)ジェムザール+イリノカテン、(4)ジェムザール+イリノカテン+シスプラチン、(5)TS-1+シスプラチン、(6)イリノカテン Sさんに使う薬が次々と変わるのは、治療の効果が長く続かないからだ。 どんな抗癌剤も、永久に効き続けるということはまずない。「薬剤耐性」という抗癌剤のやっかいな性質が大きな課題である。… Sさんの場合も、効果が減ればすぐに薬を変える。薬の種類だけでなく、毎回のように薬の量を変えている。Sさん個人の「適量」を探すためだ。 1年間の治療で一貫しているのは、Sさんの抗癌剤の適量が一般よりも常に少ないことである。(6)イリノカテンの治療も、「基準量」の5分の1で、これで癌の成長は止まっているのだ。もしSさんに「規準量」を使えば、強い骨髄抑制が出て、白血球が減少し、副作用死する可能性もある。」(satom) 癌と抗癌剤との戦いは「心理戦」のような細心で奇抜な戦術が必要なようです。いったい「癌」とは何者なのかと思ってしまいます。少しウイルスと免疫系との戦いを連想してしまいます。「急速に増殖」するということに関しては「癌」も「ウイルス」も同じ特性を持っています。 癌についてはまだ私の頭でよく理解できないのですが、「ウイルス」が他の細胞のDNAを書き換えて自己複製をするのと違い、「癌細胞」はそれ自身が増殖して様々な臓器に転移して、他の細胞の栄養を吸い取ってしまい死滅させてしまうようです。そして癌の発動する遺伝子が人間のDNAに格納されてあるようです。
2006.02.02
コメント(0)
-
抗癌剤(3)
『抗癌剤 知らずに亡くなる年間30万人』平岩正樹著 祥伝社新書より●200種類もある「がん」の種類「癌と肉腫を合わせて「がん」と呼ぶ。がんは200種類もあり、その中には珍しいがんもあれば、患者数の多いがんもある。ひじょうにタチの悪いがんから、良性腫瘍に近い比較的タチの良いがんもあり、治しやすいがんから治りにくいがんまである」●早期治療の鉄則は変わらない「胃癌を例にとると、ひじょうに早期ならば胃カメラで胃粘膜を切除するだけでよく、おなかを開いて胃を切らなくても治癒してしまう。進んだ早期胃癌では手術が必要になる。抗癌剤は使わない。たいていは手術だけで治癒する。 進行胃癌になると、手術だけでは不充分になってくる。いくら執刀した外科医が、「目に見える癌は、すべて取りました」と慰めてくれても、目に見えない癌の転移までは取りきれない。0.01ミリの癌にも1000個のがん細胞がある。こんな癌が肺や肝臓に転移していたら、どんな検査でも発見できない。 だから外科医は手術のあとに、「念のために、抗癌剤治療を追加しましょう」と勧めるのだ。外科医の「すべて取った」と「念とため」が、一見矛盾するので患者は混乱する。」●治療の目的のどれを選択するのか「抗癌剤治療の種類は二つある。 一つ目は、3センチ、5センチなど、目で確かめることができる大きさの癌へ、抗癌剤によって小さくする治療法で、目に見える大きさなので、効果が目で確かめられる。 二つ目は、再発を抑えるための重要な療法で補助的抗癌剤治療という。…私は、癌治療の目的として 1.癌の治癒(完治のこと) 2.広い意味での延命、つまり一日でも長く元気な日常生活を送る 3.症状の緩和 の三つを挙げ、どれをめざすのかは、癌の種類、進行度、患者の価値観、その他の状況で選択する。(satom) 抗癌剤というと、末期治療でほとんど助からない患者に使用するといったようなイメージがありました。高額で、副作用が強いなどとういうな印象もありました。 しかし、抗癌剤の使用方法も画一的なものではなく、多種類の「がん」に対して、その進行度合、また患者の価値観まで含めて使われるとのことです。 それにしても一口に「がん」といっても、本当に多種多様な面があるようです。発症した部位で肺癌とか胃癌とか乳癌とか言いますが、そもそもガン遺伝子が発動したのが「がん」だと思いますが、どうして部位によって進行の度合いなどが違うのか、まだまだ神秘性に包まれているようです。
2006.02.01
コメント(0)
-
抗癌剤(2)
それでは『抗癌剤 知らずに亡くなる年間30万人』平岩正樹著 祥伝社新書から引用してみます。●抗癌剤はなぜ効くのか?「抗癌剤がどうして効くのかということは、ほんどわからない。なぜなら、薬は「トライ・アンド・エラー」で開発されるもので、近年の分子標的治療薬を除けば何かの理論にしたがって作られるのではないからだ。分子標的治療薬にしても理論は仮説にすぎない。 たとえば、イリノテカンはインドや中国にある樹木の葉の成分である。また、1997年に承認されたタキサンテールも木の皮から作られる。人間に投与して、癌治療に効果があるとわかったあとで、なぜ効いたのかの理由を調べ、その仕組み、すなわち機序の仮説を立てるからで、まずはじめに実験ありきなのだ。」「抗癌剤がなぜ効くのかも解明されるまでには、あと100年はかかるだろう。人体は常にブラックボックスで、医学は「結果」の塊であるからだ。」●抗癌剤がもつ二つの働き「細胞を障害する抗癌剤の働きには二つの働きがある1.癌の遺伝子に異常を起こさせる2.癌細胞の細胞分裂の邪魔をする 1の働きは、癌に入り込んでDNAに異常を起こさせたり、DNAに付着してコブのようになって邪魔したり、DNAの構造の特徴である二重螺旋を切り開いたり、逆に二重螺旋を離れないようにする。 2の働きは、癌細胞が増殖して増えていくときに、分裂に必要な部品と思わせて細胞の中に取り込ませて癌細胞を壊すのである。癌細胞の分裂は非常に活発で、その性質を利用したのだ」(satom) 抗癌剤と言っても、木の皮から抽出した成分などもあり、どんなものが効くかは試してみないと分からないようです。
2006.01.27
コメント(0)
-
抗癌剤
1月7、8日にNHKで『日本のがん医療を問う 2』というスペシャル番組が放映されてました。すべて観たわけではないのですが、「ガン」は基本的には不治の病で、罹ったときから死に対する恐怖・生への願望という激しい葛藤が始まるとのことです。それに関わる社会・行政・医療・精神的な問題についていろいろ議論されていました。 欧米ではガンの薬の開発、手術・放射線などの治療、また心のケアなどのために、膨大な情報を共有するシステムと専門の相談員などが充実しているとのことです。日本では、医療制度などの問題もあり、医師に「もう治療法はありません」と告げられるケースが多いそうです。患者自身が「ガン」の情報を集めようとすると非常に困難なようです。そして海外で実績がある抗癌剤なども日本ではなかなか承認が下りない(保険の対象にならない)とのことです。「抗癌剤」というと「副作用」ということがすぐに連想され、あまり良い印象がなかったのですが、ここ10年ぐらいの進歩はめざましいものがあり、延命率も上がっているようです。ただ安全第一の日本では承認が海外に比べ相当遅れるようです。「最後の希望」を求めて、ひたすら縋るような気持ちで新しい治療法を探し求める患者に対して、副作用の危険はあるとしても、あまりにも国の政策には柔軟性がないのではないかといういうことが話題になっています。 そんなことが頭の片隅にあったのか、『抗癌剤 知らずに亡くなる年間30万人』平岩正樹著 祥伝社新書という本を読んでみました。いままで予防医学の重視ということで、薬とくに抗癌剤などに対する偏見がありましたが、癌など不治の病に対してはやはり「薬」の効果は絶大だと思いました。私見ですが、糖尿病などの生活習慣病には重症でない限り食事(健康食品含む)及び運動療法が効果的でないかと思います。癌など不治の病はやはり手術・放射線・抗癌剤の療法が中心になると思います。 ガンとういのは200種類以上あり、またその進行状況も含めると千差万別とのことです。患者の抗癌剤への耐性の程度も様々のようです。また抗癌剤も数十種類の組み合わせにより、効き方が違うとのことです。ですから抗癌剤の種類、投与量を様々に調整することで、副作用を最小限に抑えて治療することができるとのことです。その治療も、完全治癒を目指すものでなく(完全治癒は望ましいが、それは本当に稀である)、ガンの進行を遅らせる、現状維持に留めるようにして、日常の生活を行えるようにするとのことです。「あと1年の命です」と宣告されてから2年、3年いやもっと長く延命できる(日常生活を送れる)ということが、患者にとって、家族にとってどれほど貴重な時間になるのかと思います。 ただびっくりしましたが、抗癌剤による治療については医師の技術料はまったくない(0円)のだそうです。つまり薬代はすべて製薬会社に流れて行き、病院には何も残らないとのことです。そのため「もう治療法がない」と言うしかなくなってしまうのでしょうか。著者の平岩先生は嘆いていました。
2006.01.26
コメント(0)
-
お久しぶりです
何かずいぶんご無沙汰してしまいました。「カニ・エビはなぜ赤い」の本が行方不明になってしまいました。どこに行ってしまったんでしょう?(杜撰!)ということでカロチンの連載はストップします(て言うか、実質半年近くブランクです、怠惰です)。 さて健康ブームはますます盛んになってきていますね。チョコレートなんかもポリフェノールが多いやつじゃないと売れないみたいですね。テレビ・雑誌では、もうこれでもかぁーって感じですね。ただ何か「商品」が先行して、予防医学の基礎みたいなことを地道に啓蒙する努力が欠けているんじゃないかとも思います。それに中立的な第三者機関で本当に評価できる「商品」を発表したらどうでしょうか。まあいろいろな圧力でダメなんでしょうが。 また今新型インフルエンザの脅威についてマスコミや政府が騒いでいますが、はっきり言って遅すぎるんじゃないでしょうか。詳しくはフリーページの「インフエンザ」のところをクリックしてください。あれだけ専門家が警鐘を鳴らしていたのに、アメリカが数千億円のカネを新型インフルエンザの対策に使うと発表したとたんに、そんなに重大事なのって感じですから。 「ウイルス」についての研究にもっと本腰を入れるべきじゃないかと思います。それと「インフルエンザ」の啓蒙活動もっとした方がいいんじゃないでしょうか。学校で何時間か教えるとか。「かぜ」と「インフルエンザ」の違いが、本当に分かっている人少ないんじゃないでしょうか。 とまあ長い間サボっている割には言いたい放題の、一番いい加減な私でした。
2005.11.29
コメント(0)
-
カロテノイド(2)
●生体色素(続き)(4)ヘム鉄-マグロの赤身- マグロの赤色は、ミオグロビンという色素による。 ヘム色素はタンパク質クロビンと結合して血色素となる。血色素は赤血球の中に存在してヘモグロビンとも言う。ヘモグロビンは肺からの酸素を全身に運ぶ働きをする。 また、ミオグロビンはヘモグロビンと同じように酸素と結びつく力が高く、動物の筋肉組織に見られるので、筋肉ヘモグロビンともいわれる。(5)クロロフィル(葉緑素)-猫に食わすなアワビの緑の肝- 「アワビの肝をネコにやるとネコの耳が落ちる」と古くから漁民の間で伝えられてきた。これは特異な食中毒の症状のことである。 …この特殊な食中毒は光過敏症の一種であること、その原因がクロロフィルaの分解産物のピオフェオフォルバイトaである… クロロフィル(葉緑素)は植物の葉に含まれている緑色の色素で水に溶けない。太陽エネルギーを利用して炭酸ガスと水からデンプンその他の有機化合物と酸素をつくる光合成の中心的役割を演ずるものである。 中毒の原因となるピオフェオフォルバイトaは、アワビが食べる海藻のクロロフィルaに由来すると考えられる… この中毒症状は有毒な肝を食べた後、日光にあたると発症する。重症の場合には、浮腫、やけどのような水泡などができて、全治に20日間も要すことになる。…この光過敏症は、皮膚にあるピオフェオフォルバイトaが光増感剤となり、日光によって励起されて皮膚内の酸素にエネルギーを移し、活性酸素を作り出すために起こると考えられる。 1977年には東京を中心にクロレラの不良品による同様の中毒が発生し、光過敏症に対する関心が高まった。(satom) 光化敏捷とは、びっくりしました。体内で光合したようになり、酸素を発生する??。春先のアワビの濃緑黒色の肝は気を付けましょう。
2005.04.24
コメント(0)
-
カロテノイド(1)
『エビ・カニはなぜ赤い -機能性色素カロテノイド-』松野隆男著 成山堂書店 2004年8月より引用します。●水生生物の色-生体色素-(1)メラニン-養殖マダイの日焼け- メラニンという色素は褐色から黒色をしている。アミノ酸の一種チロシンから生成される非常に安定した高分子で、色素胞の中でも生物界に最も広く分布している。単独か、またはタンパク質と結合したメラニンタンパク複合体として存在し、アルカリには徐々に溶解するが、水、酸(濃硫酸を除く)、有機溶剤には溶けない。 よく知られているように、動物の毛髪、皮膚、黒眼の色は主としてメラニンによる。北欧人はメラニンが少ないため肌は白く、金髪で青い目をしている。海や山に出かけたときに、太陽に焼けると肌が黒くなるのは、メラニン色素が皮膚に沈着して広がったためである。養殖マダイは天然のマダイが棲んでいるところよりも、はるかに浅いところで飼われている。そのため日焼けを起こし、多量のメラニン色素が沈着して天然魚よりも黒ずんでしまう。メラニンには太陽光線、特に紫外線を吸収して皮膚を防護する作用がある。(2)プリン類-タチウオの銀白色- タチウオは魚体全面が銀白色をしている。秋の味覚サンマも体の半分は白く輝いて見える。これは皮膚の表面に、プリン類という色素のグアニンや尿酸が多量に沈着しているからである。このように、プリン類のグアニン、ヒポキサチン、アデニン、尿酸などは赤や青などの色ではなく、光沢に関わっている。皮膚の細胞中に多量に沈着すると、紫外線を強く吸収し、皮膚は白く輝いて見える。(3)オモクロム-ゆでタコが赤くなるわけ- タコやイカは黄色素胞、赤色素胞と黒紫色素胞の3種類の色素胞をもっている。タコはそれらを収縮、拡張して体の色を頻繁に、急激に変化させているのである。休息しているときには白色、活動時には茶褐色、興奮したときには暗赤色に体色が変わる。 オモクロムは黒紫色素胞に含まれているが、タコをゆでると筋肉組織中の黒紫色素胞から紅紫色のオモクロムが溶け出し、それがタンパク質と結合して赤くなるのである。 オモクロムはアミノ酸の一種トリプトファンが酸化して生成される色素で、無脊椎動物のみに見られる。節足動物、特に昆虫の複眼に含まれているオモクロムはよく研究されている。(satom) カロテノイド(英語風)又はカロチノイド(ドイツ語風)は緑黄色野菜に多く含まれていますが、何と魚類にもたくさん含まれているとのことです。カロテノイドといえば抗酸化作用の面で最近注目を集めてきています。いったいカロテノイドとは何か、魚類の色素を通して少し見てみることにしましょう。
2005.04.22
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(27)ビタミンC(3)
●コラーゲン合成のかなめ ビタミンCの生理機能は抗酸化ネットワークの作用以外にも多くある。たとえば、ビタミンCは結合組織のタンパク質であるコラーゲンの合成構築に不可欠である。このコラーゲンは骨や血管を作るのにも必要である。 コラーゲンは、文字どおり人体を維持するために細胞どおしを接着する分子である。もし、壊血病などでコラーゲンが合成できなくなれば、皮膚はたるんで軟弱になり崩れてしまう。コラーゲンは外傷の治療にも重要であり、外科手術後にビタミンCをすすめているほどである。 コラーゲンは軟骨や骨の必須要素でもあるため、関節炎の患者に多量のビタミンCを処方する医者もいる。ビタミンCが傷害された靭帯を修復するという証拠はないが、ビタミンCの投与により回復が促進される兆候がみられるからである。 最近まで、年とともにコラーゲンの合成が低下することは仕方がないと考えられていた。しかし今日では、抗酸化能力を高く維持することによりしわやたるみを防止することが可能になりつつある。 たとえば、新生児の皮膚(3~7日齢)と老齢者(73~93歳)の皮膚で細胞内のコラーゲン合成に対するビタミンCの効果を比較した結果、いずれの場合もビタミンCを摂ったほうが早く細胞が増殖し、ビタミンCがコラーゲンを合成を増強することが明らかになった。この研究は、ビタミンCを含む新しいスキンケア製品を作る際の基本的概念として広がっていった。(satom) 現在美容にかかせないコラーゲンとビタミンC、肌などの皮膚の健康も予防医学の重要な課題だと思います。一昨日のNHKの「試してガッテン」ではカレイとヒラメの話が出てきました。体ごと使って動き回るカレイやウナギは全身にわたってコラーゲンが網の目のように筋肉を繋ぎ合わせているとのことです。料理するときは、最初に湯通しするなどして、コラーゲンを逃がさないようにすることがやわらかく煮るときの極意だとか言ってました。
2005.04.21
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(26)ビタミンC(2)
●ビタミンCの必要量 ビタミンCの一日あたりの摂取量を実際に決定したのはL・ポーリング博士だった。彼の著書である「風邪よさらば」により、ビタミンCに対する人々の考えが変わった。 ポーリング博士らは分子矯正医学という新しい分野を開拓した。それは適正量の栄養分やビタミンがその欠損症を予防するだけでなく、健康維持と疾患治療にも有効であるという考え方を基盤とする学問である。 それでは、ビタミンCをどれだけ摂取すればよいのだろうか。まず、ビタミンCの推奨1日所要量(RDA)はかなり低いので、その量では十分な抗酸化作用を期待できないと考えられる(第六次改定日本人の栄養所要量では、成人のビタミンC所要量は1日100ミリグラムとされている。 最近の研究では、1日のビタミンC摂取量が200ミリグラムならば精子中のDNAを酸化的攻撃から十分護ることができないことが判明している。人の精液には血液の8倍ものビタミンCがあり、遺伝情報を保護する重要な役割を担っている。壊血病を防ぐだけならビタミンCのRDAは1日60ミリグラムで十分であるが、子孫を残すうえで遺伝子の欠損を防ぐには不十分である。●ビタミンCと癌 ビタミンCは口腔内や胃腸の癌などを抑制する作用がある。ビタミンCは発癌性のニトロソアミンから生体を保護する。ミトロソアミンは食物中に含まれ、口腔内や胃腸の原因となる物質である。 ビタミンCに関するポーリング博士の説は健康管理に対する人々の考え方を大きく変えただけでなく、医学における栄養学的コンセプトをも大きく変えた。今日、医者は栄養管理と食事療法の重要性を深く意識しているが、それはポーリング博士の貢献によるところが大きい。 酸化ストレスを強く受けている病気がちの人々はより多くのビタミンCを服用するのがよいかもしれない。…動物が種々のストレスにさらされるとビタミンCの合成量が2~3倍に増加することから、ビタミンCの大量投与が提案されている。ある外科医は、心臓病、関節炎、癌などで治療を受けている患者には毎日数グラムものビタミンCを処方している。(satom) ビタミンCは水溶性なので、大量摂取しても尿中に排出されてしまうとのこと。1日2回に分けてビタミンCを摂取したほうがいいようです。
2005.04.13
コメント(2)
-
アンチオキシダントミラクル(25)ビタミンC
●抗酸化物の女王ビタミンC ビタミンCは脂溶性抗酸化物質と水溶性抗酸化物質の作用を助けるが、この作用は抗酸化ネットワークと呼ばれている。このネットワークでは、脂溶性のビタミンEラジカルからビタミンEを再合成するためにビタミンCが重要な役割を担っている。リポ酸もビタミンEを再生できるが、ビタミンCはその作用も促進する。 ビタミンCの構造はグルコースに似ている。グルコースは体を動かすのに必要なエネルギーを作る単糖である。このエネルギー源は体の抗酸化ネットワークを機能させるうえで非常に重要であり、グルコースは細胞に速やかに取り込まれる。 ネットワークを形成して働く抗酸化物は、フリーラジカルを消去することにより反応性の弱いフリーラジカルになり、これが再び抗酸化機能を有するもとの形に再生される必要がある。酸化されたビタミンCの構造はグルコースに類似しているため、グルコース輸送体によりすばやく細胞内に取り込まれる。 酸化されたビタミンCは細胞内で抗酸化作用を有するビタミンCに還元産生され、再びリポタンパク質などを守るために血中に分泌される。 驚いたことに、人はビタミンCを合成できない数少ない動物である。これはグルコースをビタミンCに変える酵素が欠損しているからである。そのために食事を通して十分な量のビタミンCを摂取しなければならない。たとえば、山羊は1日に13グラムのビタミンCを合成し、大きな動物では1日に20グラムも合成するものもいる。 今日、私たちは先祖たちが摂取していたような多量のビタミンCは摂取していない。実際、アメリカ人の約25%は1日に必要とされる60ミリグラムのビタミンCさえとっていない。喫煙者は肺や血漿中のビタミンCを低下させて酸化ストレスを増強するため、多くの抗酸化物を摂取する必要がある。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P102から103より(satom) まあくどいようですがビタミンCも詳細に書かれていますので、引用させてもらいます。 今日テレビで、米国の大手薬品会社ファイザーの薬の副作用による企業業績の悪化懸念のニュースが流れていました。メルクに次ぐ失態です。薬の万能性や安全性も神話も崩れつつあるのかもしれません。 また私の勤めているビルの本屋さんで「アンチオキシダントミラクル」が山積になっていました。結構堅い本なんですが、今のコエンザイムやリポ酸の大流行の種本的な面もあると思います。 ほんの数年前まで「コエンザイム」や「リポ酸」などと言っても胡散臭い話のように思われていましたが、今はなんだか常識的ようになってしまいました。今後は「質」の面をよく考えてみたほうがいいと思います。
2005.04.08
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(24)ビタミンE(4)
●ビタミンEと運動 研究者は25年以上も前に、身体活動によってフリーラジカルが産生されること、およびビタミンEが運動による傷害を抑制することを観察していた。持久力運動を負荷した動物では、運動中に血中のフリーラジカルと過酸化脂質が増加し、グルタチオンが減少することが判明している。とくにビタミンEの低下が著しく、筋肉細胞膜の傷害やフリーラジカル傷害がみられた。ビタミンEを投与すると酸化ストレスが少なくなり、長時間運動することができた。 スポーツを行う際にビタミンEを補給すれば、酸化ストレスを抑制するだけでなく、スタミナや体力の向上を促進する。登山者の調査によると、ビタミン400単位を摂取した人では持久力がアップしただけでなく、過酸化脂質も減少していた。しかし熟練した水泳選手ではビタミンEを補給しても持久力の変化はみられなかった。●ビタミンEと寿命 ヒトの細胞を用いた研究において、ビタミンEが細胞の老化を抑制することが判明している。細胞の老化は、しわや白髪などのように明らかに見える現象よりもはるかに早い段階でおこる。脳や心臓などにリポフスチン色素が蓄積してくるのが老化のサインである。 リポフスチンは脂質やタンパク質の酸化や過酸化によって生じる。カルフォルニア大学のディーマー博士は、細胞レベルで老化に対するビタミンEの効果を実験した。10%の血清を添加した培養液中で幼若な細胞を培養すると、細胞の成熟過程でリポフスチンは生じなかった。しかし、低濃度の血清中で培養すると、細胞分裂が起こらず、修復機能も働かなかった。このような培養条件では老化色素が蓄積し、蛍光顕微鏡下で黄色のリポフスチンがはっきりと見られた。この際、培養細胞にビタミンEを添加しておくとリポフスチンは蓄積されなかった。これは細胞の老化が抑制されたことを意味する。 通常、細胞の寿命は生まれながらに決められている。細胞の中に、自分の分裂回数を調節する時計のようなものが組み込まれている。細胞の寿命は自己の分裂回数や病気など、さまざまな原因により決定される。体外で50回分裂することが可能な肺細胞にビタミンEを添加して培養したところ、なんと100回以上も分裂して増殖できた。このことから、酸化ストレスから身を守ることが細胞や個体の寿命を延ばすキーとなるらしいことがわかった。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P89から92より(satom) ビタミンEの働きは広範囲に細胞レベルの健康維持に大切なようです。
2005.04.06
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(23)ビタミンE(3)
●生体のボディガード トコトリエノール トコトリエノールは、小麦、オート麦、稲などに含まれるビタミンEの一種である。基本的にはトコフェロールと同じ機能であるが、分子構造が異なる。この分子構造の違いが抗酸化物以外の特別な能力を発揮する。ビタミンEにはいろいろな種類があるが、それぞれ高コレステロール血症、アテローム性動脈硬化症、癌の予防などに固有の役割を果たしている。 脳卒中は生命を脅かす疾患であるが、トコトリエノールによって予防しうる。脳卒中は頚動脈にプラークが蓄積し、脳血流を遮断することによって発病する。頚動脈狭窄と診断された患者では脳卒中を起こす可能性が高い。これまでは、大掛かりで危険な手術を行っていた頚動脈手術患者にも治療薬を選択できる余地がでてきた。 重症の頚動脈狭窄患者にトコトリエノール、もしくはブラセボを約4年間与え、超音波で経過をみた実験で、トコトリエノール投与群では94%の患者で経過が良好もしくは安定していたが、非投与群では一例も改善されず、半数以上が増悪していた。この実験では、トコトリエノールを摂取した人では6ヶ月後によい兆候が見られたのに比べ、摂取しなかった人では増悪する一方であった。α-トコフェロールはLDLの酸化を抑制し、トコトリエノールは動脈壁をきれいにする。 他の研究によれば、トコトリエノールは血中のグルコース濃度を下げ、肝臓病を予防し、脳卒中や心臓病の原因となるトロンボキサンA2を低下させることがわかった。 最近、乳癌にも効果があることがわかった。乳癌にはエストロゲン感受性(+)と非感受性(-)の二種がある。(+)型はエストロゲンによって腫瘍が増大して癌になるタイプであり、(-)型はエストロゲンによって影響を受けない。これらの患者には抗癌剤のタモキシフェンが使われるが、若い女性には(-)型が多く、効果がよくない。タモキシフェンは子宮癌などの強い副作用を示す。エストロゲン感受性の癌に対してタモキシフェンとトコトリエノールの効果を調べた結果、トコトリエノールは両方の癌に対して効果を示すことが判明した。 トコトリエノールの有効性の秘密は、細胞膜内を有効に移動する特性と抗酸化ネットワークにおける有効性にあると考えられる。トコトリエノールは細胞膜の中を移動しやすく、そこに局在していることが判明している。トコフェロールが入り込めない膜内の狭い場所にも入り込めるのである。この固有の能力に加え、トコフェロールより40倍~60倍も再生能力が強く、作用を持続させることができる。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P85から87より(satom) ビタミンEにもいろいろ種類があるようです。トコフェロールがLDLなどのリポタンパク質の酸化を予防し、トコトリエノールは動脈壁などの膜内の酸化を予防するようです。
2005.04.03
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(22)ビタミンE(2)
●アルツハイマー病患者への福音 …アルツハイマー病は脳のある領域が、時には緩慢に、時には迅速に蝕まれて起こる痴呆症であり、記憶、会話、情報整理能などが傷害される。病気が悪化すると自己管理ができなくなり、四六時中介護が必要となる。 アルツハイマー病にかかると神経細胞が死んで脳組織が傷害されるが、その原因は分かっていない。この病気ではβアミロイドと呼ばれるタンパク質が脳内に蓄積している。酸化傷害のマーカーである脂質過酸化物の脳内濃度が高いこと、および神経細胞の膜が酸化されやすいことから、その進行にフリーラジカルが関与していると思われている。多くの研究者は、思考に必要な神経細胞の情報伝達物質の産生がフリーラジカルにより傷害されると考えられている。 341人のアルツハイマー病患者を4つのグループに分け、1群には10グラムのセレグリン(モノアミンオキシダーゼ阻害剤)、2群には2000単位のビタミンEを、3群にはセレグリンとビタミンE、4群にはプラセボ(偽薬)を投与して、2年後にその効果が評価された。その結果、ブラセボ投与群に比べてビタミンE投与群では重度のアルツハイマー病に至る率が53%も低く、セレグリン単独群では43%、両者併用群では31%も低かった。このことからビタミンEはもっとも有効な治療薬であることがわかる。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P83から85より(satom) 脳がフルーラジカルに傷付けられると、記憶や認知など高等な人間の意識に影響がでるとのこと。抗酸化物をよく摂取して予防に気をつけましょう。
2005.04.02
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(21)ビタミンE(1)
●抗酸化ネットワークの王者ビタミンE ビタミンEは1922年に発見された。レタスに含まれる未知の物質がラットの流産を防ぎ、レタスを食べないラットは流産した。1936年、小麦の胚芽オイルから有効成分が取り出され、ギリシャ語でトコフェロール(tocopherol)と名付けられた。Tokosは誕生、Pherinは妊娠を意味し、olという接尾語はアルコールを意味する。 ビタミンEには4種のトコフェロール異性体と4種のトコトリエール異性体があるが、その中でα-トコフェロールが一番よく知られている。 これまでは、ビタミンEが流産を防ぐこと以外の作用はわかっていなかった。しかし、ビタミンE不足が筋肉の衰えと体力の消耗をひきおこすことが明らかになってきた。 1954年にカリフォルニア大学の科学者が、ビタミンEが食物中の脂質のみならず血中の脂質の酸化も防御することを明らかにした。脂肪の過酸化反応は心臓病の原因となる。タッペル博士は、ビタミンEが心臓病の原因となる脂質過酸化を抑制することを示した。 ビタミンEは脂溶性なので細胞膜の脂質層で作用し、フリーラジカルの発生を抑える。ビタミンEはリポプロテインというタンパク質粒子に結合して血中を運ばれる。リポプロテインは肝臓でつくられ、血液を介して脂肪やコレステロールを各組織に運ぶ。運ぶ脂質の種類によってさまざまなリポプロテインがある。LDL(低密度リポプロテイン)はコレステロールを組織に運び、HDL(高密度リポプロテイン)はコレステロールを肝臓に運ぶと考えられている。 細胞膜の脂質の量と比較して、ビタミンEの量は1/1000~2000と低く、少量でも強く作用しうる。ビタミンEはラジカルや酸化傷害からリポプロテインを守る。ビタミンEはラジカル連鎖反応を断ち切る抗酸化物であり、フリーラジカル障害を抑制する。高コレステロール血症とはリポプロテインの血中濃度が高い状況であり、フリーラジカル傷害の危険性を増強し、心臓病の発症の危険因子である。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P79から81より(satom) ビタミンEはよく食品の酸化防止剤として入っていますが、体内でも抗酸化物として働くようです。リポプロテイン(リポ蛋白質)の酸化は動脈硬化の原因となりますので気をつけないといけません。(フリーページ(左上)の中の「コレステロールと中性脂肪、動脈硬化」のところを参照下さい)
2005.04.01
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(20)グルタチオン(3)
●免疫能の若返り T細胞の働きをはじめ免疫機能は加齢とともに低下する。動物ではグルタチオンが減少すると免疫機能も著名に低下する。病気になったり年をとっても、グルタチオンのレベルが低下する。 最近、米国の加齢栄養研究センターでは若者と老人に与えるグルタチオンの影響を調べた。35~45歳および65~84歳の人から採取した免疫細胞を使用し、血液濃度以上のグルタチオンを含む試験管内で培養した結果、若年者の免疫細胞には影響しなかったグルタチオンが、高齢者の免疫細胞には大きな影響を与えることが判明した。 グルタチオンはインターロイキン1(IL-1)と2(IL-2)の産生を刺激する。IL-1は炎症反応に関与し、IL-2は免疫細胞の分化成熟に関与している。実際、グルタチオンはリンパ球を増殖させ、免疫細胞の急速な再生を可能としている。このため、グルタチオンを補給することは、免疫細胞を武装することになる。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P143から144より(satom) 免疫機能の低下というのは、以前インフルエンザウイルスのところで触れましたが、非常に危険な状況に陥ることになります。 老化によるリスクには、細胞レベルの変性などによる各臓器の機能低下による内因性のリスクと、ウイルスや細菌などに対する免疫機能の低下による外因性のリスクといものがあるように思えます。 この両リスクをうまくコントロールできれば、老化に対して大きな防御方法になると思います。
2005.03.31
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(19)グルタチオン(2)
●グルタチオンは炎症の処理屋 寒くなると気管支炎や肺炎を起こしやすい人は、グルタチオンの濃度を維持するように注意しなければならない。グルタチオンとその関連酵素は肺にも多いが、これは呼吸に伴い、肺組織の多量の空気中の酸素と汚染物質にさらされるためである。外界からのストレスにより酸化的障害が生じないように、グルタチオンはここでも他の抗酸化物とともに防御作用を発揮している。喘息などの慢性炎症に苦しむ患者の肺では、還元型グルタチオンが少なく、酸化型グルタチオンが増加している。●グルタチオンは解毒薬 …肝細胞内でのグルタチオン濃度はきわめて高い。 …肝臓の機能でもっとも重要なのは、食物や薬物の代謝と内因性有毒物の解毒である。飲料水や食物中の薬物、家庭や工場で使われる洗剤など、私たちはいつも有毒の物質にさらされている。医者に処方してもらった薬の中にも危険な成分が含まれている。 幸いなことに、肝臓に高濃度のグルタチオンがあるおかげで、このような危険から救われているのである。 グルタチオンは解毒作用にとって重要である。肝臓のグルタチオンが毒物と出会うと、それらと結合し、いろいろな過程を経て水溶性の代謝産物となり、おもに腎臓から尿中に排出される。 健康の維持には肝臓の働きが大切である。これがうまく働かないと、病気になったり死亡してしまう。たとえば、肝のグルタチオン低下と肝硬変は密接な関係がある。リポ酸はグルタチオンの量を激増させるので、肝臓におけるリポ酸の役割も需要である。エストロゲンやテストステロンなどのステロイドホルモンやプロスタグランジンなどのホルモン様物質も肝臓で分解される。体を正常に機能させるには、ホルモンの量を適切に保つことが必要である。ステロイドホルモンの量が正常値を超えると、乳癌のようにホルモン感受性の癌になる危険性が増加する。グルタチオンにはホルモンやプロスタグランジンのレベルを調整する役割もある。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P141から143より(satom) コンザイムQ10は特にミトコンドリアのエネルギー産出に関して重要な働きをしているようですが、グルタチオンは肺や肝臓などで解毒作用などに働いているようです。そしてどちらの場合もリポ酸によって増強されるようです。
2005.03.27
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(18)グルタチオン(1)
●グルタチオンは体内で作られるもっとも重要な水溶性抗酸化物である。●体内のグルタチオン濃度が下がると病気になったり死亡しやすくなるので、そのレベルを高くしておくことが必要である。●抗酸化ネットワークを介して酸化型ビタミンCを還元再生し、その抗酸化力を回復する。●グルタチオンは薬剤や汚染物質を解毒し、肝機能を正常に維持するのに重要である。●グルタチオンは免疫能の強化に重要であり、その濃度が増加すると、加齢に伴う免疫能低下を防ぐことができる。●グルタチオンは、アミノ酸の貯蔵、輸送、およびタンパク質合成にも深く関与している。その体内濃度を高めるもっともよい方法は、毎日100ミリグラムのリポ酸を摂取することである。●グルタチオンは、果物、野菜、肉などに豊富に含まれているが、消化される間にアミノ酸に分解されてしまう。 グルタチオンは、3種類のアミノ酸であるシステイン、グルタミン酸、およびグリシンから細胞内で合成される。これら3種類のアミノ酸は、すべて食べ物から摂取できる。 酸化的ストレスにさらされると、体内ではグルタチオン合成酵素を始めとする一連の酵素がが産生される。体調が悪いときは多量のグルタチオンが必要とされるが、体内で産生できるグルタチオン量はその必要性を十分満たすことができない。 …グルタチオンを必要としている組織では、リポ酸がその濃度を急速に上昇させることができる。 ところで、システインの前駆物質であるN-アセチル-L-システイン(NAC)というアミノ酸を摂取するとグルタチオンの体内レベルが上昇する。しかし、その作用はリポ酸ほど顕著ではない。 グルタチオンの作用を低下させるものを避けることも賢明な策である。このようなものとしては、タバコや添加物過剰食品などがある。後者の例としては亜硝酸塩や硝酸塩を多く含んでいるかん詰めの肉などがあげられる。酒を飲みすぎても体内のグルタチオンは減少するため、酒の飲みすぎは抗酸化機能の点でも体に悪い。 多くの場合、薬を飲めば体内のグルタチオンは減少する。その顕著な例は、よく使われている鎮痛剤アセトアミノフェンである。このため、アセトアミノフェンを投与されているときには酒を飲んではいけない。両者はいずれもフリーラジカルを産生するので、両者が混ざると、肝臓のグルタチオンが極端に減少し、肝障害を起こす。グルタチオンがなければ、肝臓は解毒をはじめ多くの重要な働きをすることができず、肝臓自体も悪くなる。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P136から139より(satom) ビタミンやミネラル、植物栄養素・ハーブなど摂取する前に、やはりアミノ酸も十分広範囲に摂取することが必要のようです。タンパク質の構成要素となるのはもとより、いろいろな役割をもっているようです。
2005.03.24
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(17)コエンザイム(3)
●コエンザイムQ10と癌予防 私は(L・パッカー/C・コールマン)、抗酸化物が癌の予防に有効であり、他の治療法とともに治療にも役立つと信じている。抗酸化物はフリーラジカルを制御するだけでなく、細胞増殖をコントロールしている遺伝子の活性を調節している。もちろん、体内の抗酸化物を正しい量に維持することにより、癌の発生制御することができる。 …フォルカーズ博士は1991年に、癌患者の血中コエンザイムQ10濃度が健康人よりも低いことを報告した。癌細胞を殺す免疫細胞であるT細胞の働きをコエンザイムQ10が助けるとの研究もある。フォルカーズ博士は、癌患者はコエンザイムQ10を効率よく産生できないので病気の回復が低下していると考えている。 …私は(L・パッカー/C・コールマン)、癌患者全員が抗酸化物を使うべきとはいっていないが、治療中の患者は使用を考えるべきだと考えている。多くの癌化学療法剤は、癌細胞を殺すためにフリーラジカルの産生を増加させるようにデザインされている。もし、化学療法を受けるなら、薬を服用する前に抗酸化物の使用を専門医に相談すべきであろう。●コエンザイムQ10と脳の若返り …脳細胞が正常に機能するうえでエネルギー産生は不可欠である。コエンザイムQ10はミトコンドリアのエネルギー産生を助けるので、加齢性脳疾患の進行を遅らせたり、回復させるのに役立つ可能性がある。●コエンザイムQ10と歯ぐきの健康 …フッ化物の入った水や口腔内の衛生に注意したおかげで、アメリカでは虫歯が少なくなった。しかし、歯がなくなる歯ぐきの病気は依然としてなくならない。 1985年から1986年における国民成人病歯科健康調査によると、アメリカでは成人の約半数が炎症徴候(歯ぐきの出血)を経験し、成人の24%と高齢者の68%が義歯などを使っている。 歯ぐきの病気は歯垢の蓄積によって起こる炎症がおもなものである。歯ぐきの炎症が進行すると、結合組織や歯を支えている骨が破壊され、最終的にはひどい感染症にかかり、歯を失ってしまう。 …歯ぐきの組織を支えるコラーゲンはフリーラジカルによって破壊されるので、高齢になるほど影響が出てくる。 日本の研究者は1971年に、歯ぐきの病気の患者の組織にはコエンザイムQ10の濃度が低いことを発見し、コエンザイムQ10が歯ぐきの治療薬になるかもしれないと考えてきた。実際、コエンザイムQ10を直接歯ぐきに塗布したり服用すると、症状が著しく改善して治りが早くなった。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P128から134より(satom) この頃いろいろと忙しい(&少々塞ぎ込んでいる)こともあり、日記が書けないことも多いです。どうにか頑張らないと… さて、いろいろな病気になると、どうも抗酸化物の濃度が減少するようです。たぶん何らかの細胞の不具合から、フリーラジカルの量が増大して、通常の抗酸化物の量では対応できなくなり、細胞を傷つけてしまうのではないでしょうか。 そういえば、花粉症でこの頃はひどい症状になっています。こんなに免疫が活発になってはフリーラジカルの量が増えているんじゃないか不安です。
2005.03.23
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(16)コエンザイム(2)
●心臓に不可欠な抗酸化物コエンザイムQ10(続き) コエンザイムQ10は、1957年にウィスコンシン大学のF・クレイン教授によって発見された。彼は、牛の心臓のミトコンドリアからオレンジ色の物質を分離した。次いで、ビタミンB6とB12の構造を決定した医学者K・フォルカーズは、1958年に牛の心臓からコエンザイムQ10を分離し、これが治療薬して大きな可能性を秘めていることを直感したが、研究は中止されてしまった。 1965年、心不全のために十分量の血液を拍出できないうっ血性心不全患者の治療に、日本人医師が初めてコエンザイムQ10を試験的に使用した。それはたいへんよく効き、今日では約600万人もの日本人がコエンザイムQ10を摂取しており、心臓病や歯ぐきの病気など、多くの病気の治療に使われている。 その後、フォルカーズ博士はテキサス大学でコエンザイムQ10の研究を続けることができ、多くの人々の命を救う薬剤の開発に成功した。この業績により、フォルカーズ博士はあらゆる化学賞を受賞し、1990年には科学勲章も受章した。 年齢が進むにつれてコエンザイムQ10の体内濃度が低下し、それが老化、心臓病、癌、アルツハイマー病などの原因になることを最初に述べたのもフォルカーズ博士であった。 エネルギーは体内のあらゆるシステムを機能させる不可欠であり、十分なエネルギーがなければ体は効率的に機能できない。コエンザイムQ10はATP産生にも関与しているので、この抗酸化物の合成低下はエネルギー産生能も低下させることになり、その影響は、心血管系や免疫能などあらゆるシステムに現れる。 …心臓病患者はしばしば、コエンザイムQ10が不足して危険な状態になる。…実際、さまざまな心臓病患者の心筋では、50%から75%の確率でコエンザイムQ10が不足していることが生体組織検査により判明している。 心臓病の原因の一つしてコエンザイムQ10不足が考えられるの、これを補充することによりよい結果が得られると考えられる。多くの研究より、コエンザイムQ10は心臓病患者に有効との結果が出ている。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P123から125より(satom) いまから40年も前に日本人医師が初めてコエンザイムQ10を試験的に使用したとのことです。それにしても医薬品として使用されているんでしょうか。コエンザイムの名前が広まったのはごく最近のように思います。
2005.03.16
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(15)コエンザイムQ10
●心臓に不可欠な抗酸化物コエンザイムQ10 …コエンザイムQ10は、ある特定の反応を触媒するために酵素タンパク質とともに働く補酵素である。 コエンザイムQ(補酵素Q)は炭素数の異なるいくつかの類似体が存在する。この補酵素の基本骨格はキノンである。キノンの構造は、ビタミンEに似ている。注目すべきことに、細菌、昆虫、マウス、ラットなど、短命の生物は短い炭素鎖のコエンザイムQを有し、長命のヒトや大動物などはコエンザイムQ10をもっている。 コエンザイムQ10は、ATPを産出するクエン酸回路に関与している。自動車のプラグがエンジンをかけるのに必要なように、コエンザイムQ10は「細胞内発火プラグ」と呼ばれている。コエンザイムQ10は、生命維持に必要なエネルギーの産生に必要不可欠である。十分な量のコエンザイムQ10がなければ疲れて活動できなくなる。 コエンザイムQはすべての細胞膜に高濃度に存在するので、ユビキノンという名前(いたるところにあるという意味)でも知られている。コエンザイムQ10は、細胞のエネルギー合成装置であるミトコンドリアに局在し、とくに心臓、脳、腎臓、肝臓など、活発に働く臓器のミトコンドリアに多い。 コエンザイムQ10はミトコンドリアで二つの重要な機能をはたしている。その一つはATP産生に不可欠な役割であり、もう一つは脂溶性抗酸化物としての機能である。 さらに重要なことは、コエンザイムQ10は強力な脂溶性抗酸化物であるビタミンEを再生していることである。コエンザイムQ10はビタミンEとともに血中のリポタンパク質内に含まれる抗酸化物であり、フリーラジカルによる脂質酸化を制御している。試験管内の研究によって、コエンザイムQ10がビタミンEを再生できることがわかっている。 これらの結果から、コエンザイムQ10とビタミンEとともに、皮膚の老化や癌化の原因となる紫外線の毒性を軽減していることがうかがわれる。 体内で作られるじほかの多くの物質と同様に、コエンザイムQ10の生体内濃度は年齢とともに減少していく。コエンザイムQ10は鮭やレバー、その他の内臓などに含まれているが、食事だけでは十分な量を得ることは難しい。高齢者ではこれが顕著なため、50歳以上の人たちは、毎日50ミリグラムのコエンザイムQ10を摂取することをおすすめする。心臓病の人は、通常の人よりコエンザイムQ10が少ないので、食事療法の一部としてさらに50ミリグラム多く摂取するとよいであろう。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P120から122よりまたリポタンパクについては左側フリーページの「中性脂肪とコレステロールの3と4」を、補酵素については上の「酵素」を参考にしてください。(satom) いま流行のコエンザイムQ10、エネルギー産生の発火プラグ(触媒)と脂溶性抗酸化物として働いているようです。ミトコンドリアという工場で、猛毒にもなる酸素を使って、毎日毎日エネルギーを作っている。その中にあって、大働きというところでしょうか。 とくにリポタンパク質は脂肪を運ぶ船でもあるので、それが酸化してしまい変性してしまうと、動脈硬化の要因にもなりかねません(左側のフリーページの「動脈硬化を参考にしてください)。 それにしてもこの本が出版される頃には、日本でもコエンザイムなどという言葉はどこにも見当たりませんでした。それが今では薬局などに山と積まれて、飛ぶように売れているようです。まあどういう具合にいいのかということを理解して買っている人は少数でしょうが、○○○○○Cなんかよりはいいような気がします。
2005.03.13
コメント(3)
-
アンチオキシダントミラクル(14)リポ酸(7)
●リポ酸と記憶力増強 中年以降、年をとると脳の機能が衰え始める。とくに、共通の徴候として短期記憶の衰えが著しい。たとえば名前をど忘れしたり、約束の日時を忘れるなどである。これらの一時的な症状はアルツハイマー病の徴候ではなく、通常の単なる老化現象の一部分である。抗酸化物は脳のこのような機能を保つのに有効と思われる。 …小さな脳が全身の神経細胞を調節し、意識、記憶、衝動、判断、そして知性などを司っている。その結果、脳は莫大な量のエネルギーを消費することになる。 このエネルギーを作るために、脳組織にはATPを産出する多量のミトコンドリアがある。多量の酸素をエネルギー産出に利用するために脳もフリーラジカルを産出する。脳は酸化ストレスに弱いために、フリーラジカルによっても傷害される。 加齢とともにフリーラジカルによる脳障害が強くなると記憶力が低下するので、抗酸化物によってこの障害を抑制することが試みられてきた。最近、老化マウスの記憶低下に対するリポ酸の影響が研究されている。老化したマウスにリポ酸を含む飲水を14日間投与した後に迷路試験を行ったところ、リポ酸投与群では成績が著しくよかった。このことからリポ酸が脳内の酸化ストレスを軽減し、脳細胞障害を抑制したと考えられている。 リポ酸がヒトの脳機能を高めるか否かは不明である。しかし、ビタミンEをはじめ、イチョウの葉や松の皮から抽出した抗酸化成分ピクニゲノールが加齢による記憶力低下を抑制するとの報告もある。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P73から74より なおピクノゲノールやイチョウ葉については左側のフリーページの「ハーブ」の中に説明がありますので参考にしてください。(satom) そういえば脳はものすごく働くところですよね。神経細胞が一斉に伝達し合っているんですから、エネルギーも消費するわけですね。酸化ストレスというと、やはり脳が一番ダメージ受けるような気がします。 この頃物忘れ多いんですが、私の脳細胞もガタがきだしたかもしれません。
2005.03.11
コメント(2)
-
アンチオキシダントミラクル(13)リポ酸(6)
●有毒遺伝子の抑制 リポ酸などの抗酸化物は、フリーラジカルを抑制するだけでなく、不都合な遺伝子の活性化を阻止して病気の発病を抑制することができる。このことは種々の病気の治療に応用できるだけでなく、それらの根本的な予防治療法にもなりうる。 遺伝子の発現にはその活性化が必要であり、体内ではそれらを制御する多くのシステムがある。…DNAがフリーラジカルにより傷害されると、有毒な遺伝子が活性化される。このことが、フリーラジカルを多く産出する人で特定の病気が悪化する理由である。 タバコにより産出されるフリーラジカルは、さまざまな癌や心臓病など、多種多様な疾患を誘発する遺伝子を活性化させるが、タバコを吸わない人ではこれらの遺伝子は眠ったままである。 何百もの遺伝子がNF-kBといわれる転写因子によって活性化されて発現する。正常に制御されているNF-kBは、病気に対する抵抗力を強化するが、それが過剰発現すると免疫能を低下させ、心臓病や皮膚老化を促進する。このように、NF-kBの過剰発現を制御することは、健康維持に重要である。 一般的に、リポ酸などの抗酸化物はNF-kBを制御し、逆にフリーラジカルはこれを活性化するので、病気が発症する前にフリーラジカルを制御することが非常に重要である。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P66から67より(satom) 病気の発症には遺伝子の発現によるものも多いようです。通常は眠っている遺伝子もいくつもの要因によって発現するようです。(フリーページの「活性酸素とガン」も参照してください)
2005.03.09
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(12)リポ酸(5)
●リポ酸と心臓病の予防 脳卒中後の脳障害は心臓発作後の心筋障害と類似している。心臓の虚血性発作は心臓へ血液を送る動脈の閉塞により起こる。虚血時の酸素欠乏が回復する際にフリーラジカルが大量に発生して心筋組織を傷害する。 …拍動する心臓を無酸素溶液で40分灌流後、酸素を含む溶液を灌流すると深刻な障害が起こり、20~25%の心臓しか回復できない。しかし、再灌流液中にリポ酸を添加しておくと、回復率は60%にまで上昇した。リポ酸投与ラットの心臓にフリーラジカルを作用させて解析した結果、投与群でもフリーラジカル傷害は抑制されていた。これらの結果は、抗酸化ネットワークやリポ酸が、心臓病、脳卒中、白内障などの老化病態の予防と健康維持に重要であることを示唆する。 …細胞内の脂肪酸はカルチニンと反応してミトコンドリア内に輸送されるが、リポ酸は老化した動物のミトコンドリアの機能を強化することを示した。 ミトコンドリアは細胞の「発電所」であり、エネルギー産生の場である。人間と同様に、このミトコンドリアも年とともに老化し、エネルギー産生が低下する。リポ酸を投与した動物では、ミトコンドリアの機能が増強するのみでなく、より若い動物のミトコンドリアの活性を示す。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P63から64より(satom) フリーラジカルに対してリポ酸は重要な予防薬になる可能性があるようです。
2005.03.06
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(11)リポ酸(4)
●脳卒中とリポ酸 脳卒中では、脳への血液や酸素の供給が途絶する。アメリカでは脳卒中が死因第3位であり、毎年約70万人が罹患し、約15万人がこれで死亡している。 筆者(L・パッカー、C・コールマン)らの研究により、リポ酸が脳卒中の予防薬となる可能性が示唆されている。脳に血液と酸素を運ぶ頚動脈を30分遮断したのちに血流を再開通させると、フリーラジカルが爆発的に産出されて脳の抗酸化防御能を致命的に破壊する。約80%のラットは24時間以内に死んでしまう。一方、脳の血流再開直前にリポ酸を注射すると、24時間後の死亡率が25%に低下し、生き残ったラットの状態もきわめて良好であった。 …ルポ酸を与えなかったコントロール群では脳内でフリーラジカルが多量に発生して酸化的傷害を起こしたが、リポ酸投与群の脳は正常に保たれていた。 脳には血液脳関門と呼ばれる関所があり、血中から脳内に入り込む物質を遮断しているので、多くの治療薬は脳に到達しにくい。 解析の結果、リポ酸が確かに血液脳関門を通り、目標の脳細胞に到達して抗酸化的保護作用を示すことが判明した。重要なネットワーク系抗酸化物グルタチオンの脳内レベルは再開通後に急落するが、リポ酸投与群では著名に上昇していた。リポ酸によるグルタチオンの脳内濃度が高く保たれると、フリーラジカルによる傷害は有効に抑制させる。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P61から62より(satom) 細かい実験を繰り返すことにより、細胞レベルの抗酸化機能を実証しているようです。くどいようですが、リポ酸などの抗酸化物の機能をもう少し引用してみようと思います。
2005.03.04
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(10)リポ酸(3)
●白内障とリポ酸 白内障は老化により起こる病気の一つである。白内障では、レンズのタンパク質をフリーラジカルが傷害することによって不透明になる。白内障は老人に共通した病気であり、加齢により発症の可能性が高くなる。白内障では、多量のフリーラジカルによりレンズの抗酸化物が激減する。 食物などからビタミンCを摂取しなくてはならないヒトと異なり、ほとんどの動物は体内でビタミンCを合成することができる。しかし、かれらも生後1ヶ月間はビタミンCを合成できず、新生児は生後数週間は抗酸化防御反応をおもにグルタチオンに頼る必要がある。したがって、グルタチオン合成能が未発達な新生児ラットは抗酸化力が低く、さまざまな酸化ストレスにさらされることになる。 抗酸化物欠乏状態の幼弱ラットは、同様の代謝状態を有する老齢ラットと同じ問題を抱えている。グルタチオン合成阻害剤ブチオニンスルフォキシミン(BSO)を新生ラットに単独投与、あるいはリポ酸と併用投与して6週間後の開眼時に比較したところ、BSO投与群はすべて白内障になったが、リポ酸併用群では白内障はほとんど見られなかった。●ビタミンEのピンチヒッター リポ酸が抗酸化ネットワークを増強することは以下の実験からもうなずける。 生後12週のマウスを3群に分け、1群には普通食、2群にはビタミンE欠乏症、3群にはリポ酸を添加したビタミンE欠乏食を与えた。6週間後に比較したところ、普通食に比べ、ビタミンE欠乏症群では体重減少と筋力低下が見られ、病気にかかった老化マウスの様相を呈していた。 高度のビタミンE欠乏では、ヒトも動物も同じような徴候を見せることが知られている。驚いたことに、リポ酸を添加したビタミンE欠乏症群では、まったく欠乏症状がみられず、普通食群と同様に元気であった。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P59から62より(satom) あたりまえですが、ビタミン欠乏はやはり病気の主要な原因になるようです。しかしビタミンが欠乏してもそれを補うシステムも体には備わっているようです。リポ酸やグルタチオンなどがその役割を担っているようです。
2005.03.02
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(9)リポ酸(2)
●リポ酸はビタミンか 最近まで、リポ酸の多彩な機能はほとんど知られていなかった。リポ酸は1937年に発見されたが、当時は細菌の増殖にジャガイモ抽出物中のある成分が必要であることが観察され、この未知の栄養物を「ジャガイモ成長因子」と呼んでいた。しかし、それが何であり、どのような作用をするか、また人間にも重要なのかどうかもわからなかった。 1951年、生化学者のレスター・リードがリポ酸を分離し、その分子構造を決定した。これは大変な仕事であり、わずか30ミリグラムのリポ酸を抽出するのに10トンもの牛の肝臓が必要であった。 今では、リポ酸が成長に重要な栄養物であり、ビタミンの一種と考えるべきであると思う研究者もいる。ビタミンは、生体の機能に必要な微量成分だが、ヒトの体内では作られず食物からしか得られない栄養成分である。 リポ酸は、動物、ヒト、および植物で合成されるが、その量はほんわずかであり、生体が必要とする量にはほど遠いものである。 しかし、ヒトにおいてリポ酸はビタミンと同様に摂取される必要がある。その第一の理由は、年を追うごとにリポ酸の体内生産量が減少するからである。中年期までは生体内で必要とする十分な量が作られるが、それはリポ酸のもつすべての利点を利用するには十分でない。 リポ酸の機能は何十年もかけてゆっくりと明らかにされてきたが、1989年に抗酸化物であることが認められ、しかももっとも強力なネットワーク系抗酸化物であることが判明した。 最近まで、各抗酸化物は他の抗酸化物とは独立的に作用するものと思われてきた… グルタチオンは、複雑な一連の酵素的反応を介して他の抗酸化物を再生しているが、既知のネットワーク系抗酸化物はいずれも効率よく直接利用することができない。 グルタチオンの濃度を高く保っておくことは、生きるためにきわめて重要なことである。事実、どの年齢をとってみても、グルタチオン濃度の低下は致死性病変におけるリスクの増大のパラメータとなる。 たとえば、エイズ、癌、自己免疫疾患、リウマチ性関節炎などの慢性疾患では、全身組織のグルタチオンが激減する。この際、グルタチオンを経口投与してもそれが細胞に届く前に、分解酵素でほとんど壊されてしまうので体内レベルを上げることはできない。 …ヒトおよび動物のさまざまな培養組織にリポ酸を添加して実験を行った。その結果、細胞のグルタチオン濃度が30%も増加した。つまり、他の抗酸化物や抗酸化剤と異なり、リポ酸はグルタチオンの細胞内レベルを増加させることが判明した。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P55から58より(satom) それにしても細胞レベルの分子生物学は1990年前後から急速に研究が進んできたようです。今読んでいるカロテノイドについても、1960年頃には150種類ほどしかわかっていなかったものが、今は約650種類にも及んでいるそうです。まだまだ今後の研究で発見されることでしょう。 今日、コンピューターなど科学技術がこれほどまでに進歩しているのに、体の内部の細胞のことについては、まだまだ未知のことが多いということでしょうか。
2005.02.27
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(8)リポ酸(1)
万能の抗酸化物リポ酸●リポ酸は、抗酸化防御ネットワークを活性化し、体内のビタミンEとC、グルタチオン、およびコエンザイムQ10などを維持する。その結果、老化に伴う脳卒中、心臓病、白内障などの予防や、脳老化抑制、記憶力強化などに重要な役割を果たす。●ヨーロッパで20年以上も前から糖尿病合併症予防の有効な治療薬として使われてきたリポ酸は、遺伝子制御機構を介して老化や癌を予防し、肝臓の解毒作用を強化することから、C型肝炎のと治療にも使われてきた。●リポ酸は、体内で合成され、ジャガイモ、ホウレンソウ、肉などにも少量含まれているが、1日当たりの推奨栄養所要量(RDA)は決められていない。●最近の十年間ほどの研究により、抗酸化物としてのリポ酸の概念は大きく変化した。とくに生体内で生じるフリーラジカルに対する抗酸化防御機構における重要性が深く理解されるようになった。●リポ酸は、抗酸化物としては例外的な作用を有し、スーパーアンチオキシダントであるといえる。実際、理想的な抗酸化物を開発しようとすれば、多機能抗酸化物であるリポ酸に類似した化合物になるであろう。 リポ酸の特異な作用●融通がきくリポ酸のかたち すべての細胞は、細胞内外の水溶性成分が混じり合わないように、細胞膜脂肪質によりバリアを形成している。生体内のネットワーク系抗酸化物は脂溶性か水溶性のいずれがであり、それぞれ細胞内区画での分布が異なっている。一方、特有の両親媒性構造を有するリポ酸は細胞内の水溶性および脂溶性の区画に分布することが可能であり、両部位でフリーラジカルを有効に捕捉することができる。●抗酸化物再生作用 フリーラジカルと反応すると抗酸化物もフリーラジカルに変わるので、それが再生されなければ抗酸化能は失われる。リポ酸は、ビタミンE、コエンザイムQ10、グルタチオン、ビタミンCなど、すべてのネットワーク系抗酸化物を再生しうる抗酸化物である。●エネルギー産生機能 肉体を動かすためのATPを作るのに、細胞内で糖が分解する反応が必要である。リポ酸はこの糖の分解を助けている。事実、リポ酸がなければ細胞はエネルギーの産生利用ができず、動けなくなる。●リポ酸は自身を還元再生する リポ酸は、細胞のエネルギー産生と類似の機構を利用し、酸化型から還元型の分子に自己再生する。リポ酸のこの自己再生能力が他の抗酸化物の機能を回復させ、抗酸化物全体の生物学的重要性のカギとなっている。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P53から55より(satom) リポ酸の化学構造は COOH | (CH2)4 | / \ | S \S/ということになるそうです。このどこが効くのか?私には化学的に細かくわかりませんが、それにしても不思議だと思います。 今巷ではリポ酸が相当流行しているようです。世は本当に予防医学の時代に突入したようですが、知識がどうも私も含めてイマイチとうことが言えると思えます。
2005.02.25
コメント(2)
-
アンチオキシダントミラクル(7)
●フリーラジカルと脳梗塞 脳梗塞は、フリーラジカルが生体を傷害して病態を増悪させる一例である。脳梗塞は脳への血流低下や停止によって起こる。血栓や動脈硬化病巣からはがれおちた断片などにより、脳に血液や酸素を運搬している動脈がふさがれてしまうと、たいへん重篤な病態となる。 脳への血液供給停止よりも血流が復活した直後のほうが強い傷害が起こり、虚血再還流傷害と呼ばれている。血流が回復すると多量の酸素が活性化されてスーパーオキシドラジカルが爆発的に発生し、組織を攻撃するため、脳では不可逆的な傷害が起こる。 平時はしっかりとタンパク質に結合してコントロールされている鉄イオンが遊離して放出されると、脳組織の損傷が増悪する。鉄イオンは体内にもっとも豊富に存在するミネラルであり、生命維持に不可欠なものであるが、これが体内でフリーな状態で移動することはなく、さまざまなタンパク質に結合し、細胞内では安全な場所に貯蔵されている。 フリーな状態の鉄はフリーラジカル反応を誘起しうるので非常に危険であり、このため生体は鉄イオンをタンパク質に結合して保持している。多量の遊離鉄が脳内に蓄積するれば、アルツハイマー病やパーキンソン病などの変性疾患の原因にもなりうる。事実、フリーな鉄の血中濃度と心臓病や脳梗塞のリスク増加が相関することを示唆する研究結果が報告されている。●フリーラジカルと心臓病 心臓病は、悪玉コレステロールとして知られているリポタンパク質LDLの酸化とともに、症状が出る何年も前から始まっている。この酸化は、心臓に血液を運ぶ動脈に病巣を作る一連の反応の最初のステップであり、この過程には何年もかかることが多い。動脈が詰まれば、心臓への血流と酸素の供給が突然止まることになり、心臓発作が起こる。 脳梗塞の場合と同様に、心筋梗塞で心筋がダメージの多くは、血流再開時に生じる大量のフリーラジカルによるものである。 最近、フリーラジカルがアテローム性動脈硬化症を悪化させるもう一つの機序が明らかになった。フリーラジカルの一種であるNOは、正常な血液循環には不可欠であるが、過剰に産出されると危険であり、心臓病や脳梗塞の増悪因子にもなりえると考えられる。循環系を健康に維持するには、体内でNOのバランスを適切に調節しなければならない。この調節は抗酸化物のバランスを制御することによりなされる。●フリーラジカルと慢性炎症 炎症は生体内で過剰のフリーラジカルが産出されることにより増悪する。癌の原因の約30%は持続的な炎症に起因する。フリーラジカルはさまざまな疾患の直接的ではないにしても、多くの病態の増悪因子となっている。 アスベスト(石綿)が中皮種という肺癌の原因になることはよく知られている。しかし、アスベストが肺組織に慢性炎症を起こし、それによりフリーラジカルが産出されていることはあまり知られていない。 肺でフリーラジカルが増加すると、呼吸困難を伴う肺繊維症が起こる。アスベストは辺縁がギザギザで不規則な構造をしており、気道内に吸い込まれると免疫細胞により感知され、その局所に多量の白血球が動員される。白血球は火災現場に急行する小さな消防自動車と考えることができる。しかし、アスベストによる火災は決しておさまらず、白血球はそれをうまく処理できないまま多量のフリーラジカルを産出し続ける。白血球により放出されたフリーラジカルは、肺組織を傷害して病態を増悪させ、難治病の慢性炎症状態を誘起する。このような状態が何年も続く結果として、肺癌が生じる。 また、炎症反応は関節炎の主要な要因であり、関節の結合組織や関節軟骨を変性させる。 関節炎では炎症により浮腫が起こり、血流が傷害される。脳梗塞の場合と同様に、血流が停止すると、血流再開時にフリーラジカルが爆発的に発生する。このような反応が膝でも起こり、生じたフリーラジカルにより炎症が増悪して関節の機能を低下させ、関節の浮腫と変形が生じた。 フリーラジカルをうまく制御する秘訣は、抗酸化物の濃度を維持してフリーラジカルとのバランスを最適な状態に保っておくことである。食事やサプリメントによって適量の抗酸化物を摂取し、有毒酸化物との接触を少なくすることにより、抗酸化物の生体制御機能を維持しておくことができる。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P47から50より(satom) 3大病の心臓・脳疾患、癌の原因もフリーラジカルによると思われるものが多くあるようです。体が錆びにより腐食してしまわないように、抗酸化物を摂取して防衛しましょう。
2005.02.24
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(6)
●フリーラジカルの功罪 …しかし、ヒトは生きているかぎりフリーラジカルとは無縁でいられないように設計されており、フリーラジカルなしでは生きていくこともできない。 たとえば、血流の流れを調節したり、感染を防いだり、頭脳を明晰にしたり、性的興奮や寒さを耐え忍ぶときなど、フリーラジカルは有効に利用されている。 抗酸化物と同様に、フリーラジカルはシグナル伝達を担う分子としても働き、遺伝子発現のスイッチを入れたり切ったりしている。 NO(一酸化窒素)やスパーオキサイドのようなフリーラジカルは、ウイルスや細菌を殺すために、体内の免疫細胞によって多量に作られている。癌細胞を殺すフリーラジカルもあり、多くの抗癌剤は体内でフリーラジカルを産生することにより薬効を発揮している。 生きていくためにはフリーラジカルは不可欠であるが、同時にその一部は生体の重要な成分をも傷害し、病気を起こしたり、老化を促進したりしている。●フリーラジカルがいっぱい …細胞内ではフリーラジカルと抗酸化物の白熱した戦いが休むことなく繰り広げられている。 この世に存在するすべてのものは微小な原子からできており、各原子は電子と原子核からなっている。2個以上の原子が電子を共有することにより原子間の結合が起こる。生体のエネルギー代謝過程で起こる酸化反応では、ときとして不対電子と呼ばれる自由電子が生じ、この状態をフリーラジカルと呼ぶ。 フリーラジカルは、体内の至るところで発生し、驚くほどの速さで消滅しているので、それを捕まえることは困難である。 フリーラジカルは、細胞の増殖や分化を制御する遺伝物質DNAを攻撃し酸化するため、癌の発生や増殖の原因となる。これらの不安定な分子が血中の脂質を酸化変性させれば、動脈硬化を基盤とする心臓病や脳梗塞がおこる。このようにフリーラジカルはさまざまな加齢性疾患の原因となり、老化を促進する。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P43から45より(satom) フリーラジカルと抗酸化物の拮抗が崩れたときに、急速に老化が進むようです。40歳ぐらいから急速に抗酸化物の産出が減少傾向になるとのことです。 フリーラジカルにより遺伝子が乱され、変性したタンパク質が生じ、それらが様々な老化現象を引き起こすようです。
2005.02.22
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(5)
●エネルギー代謝とフリーラジカル 人間の体はエネルギー代謝のため十分な量の酸素を要求するが、この酸素は同時に危害をも加えうる。代謝によって、さまざまな生命活動のために必要なエネルギーを栄養素から作り出している。エネルギーは、呼吸、心臓の拍動、思考、あるいは生殖活動など、すべての生命活動になくてはならないものであり、酸素はもっとも重要な成分である。 ヒトは酸素がなければエネルギーを作ることはできない。しかし、エネルギー産生の過程でフリーラジカルが生じ、これが生命に有害な作用を及ぼす。 フリーラジカルは細胞を傷害し、癌、心臓病、その他多くの病気をひきおこす不安定な分子である。…老化と関連した多くの疾患がフリーラジカルによって誘起されたり憎悪するこが知られている。●抗酸化物とフリーラジカルの攻防 抗酸化物とフリーラジカルが出会うと、両者が速やかに反応して抗酸化物はフリーラジカルを包み込み、フリーラジカルは消去される。この際、抗酸化物自体がフリーラジカルになることもある。新しく生じた抗酸化物質フリーラジカルの作用は比較的弱く、他の成分と反応してそれ以上障害を与えることはない。このようにして、フリーラジカルの破壊的な作用から細胞や組織を守ることができる。 ヒトの体内には、ビタミンC、ビタミンE、コエンザイムQ10、リポ酸、およびグルタチオンという5種類の主要な抗酸化物が存在し、この間にダイナミックな相互作用が起こる。これらの抗酸化物質は抗酸化システムを強化するために共同して働いている。 以下に、ネットワーク系抗酸化物質がどのようにして働くか紹介する。 ビタミンEがフリーラジカルと反応してその毒性を失わせると、自身はフリーラジカル(ビタミンEラジカル)になる。しかし、新たに生じたこのフリーラジカルは有毒でなく、ビタミンCやコエンザイムQ10によって抗酸化能を有するビタミンEに再生される。すなわち、これらのネットワーク系抗酸化物質はビタミンEラジカルに電子を与えてビタミンEを還元する。 同様にビタミンCやグルタチオンもフリーラジカルと反応してその毒性を弱め、自身は反応性の低いフリーラジカルになる。これらの抗酸化物質もリポ酸やビタミンCによって、もとの抗酸化能を取り戻す。 このように、あるネットワーク系抗酸化物質の低下を抑制する反応がサイクルとして繰り返されることにより、生体は適切な抗酸化物質のバランスを保つことができる。 ヒトでは各細胞のDNAが毎日およそ1万回も酸化的に傷害されることが知られている。この傷害反応が何兆個もの細胞で同様に起こっていることを考えると、いかに多いかがわかる。食物などから抗酸化物質を補給しなければ、組織や細胞がフリーラジカルにより傷害されやすくなるのはこのためである。 ネットワーク系抗酸化物質は互いに相乗効果を示すが、各抗酸化物質が細胞内でフリーラジカルの毒性を消去するには、それぞれに適した特有の部位がある。 たとえば、細胞膜はおもに脂質でできているが、細胞質内水で満たされている。このため脂溶性のビタミンEやコエンザイムQ10は細胞膜の脂質をフリーラジカルから保護するが、水溶性である細胞内や血漿中では保護できない。このような水溶性区画ではおもにビタミンCやグルタチオンなどの水溶性抗酸化物質が防御作用を示す。 水溶性区画でも脂溶性区画でも作用できる抗酸化物質としてはリポ酸がある。したがって、水溶性抗酸化物質(ビタミンCとグルタチオン)と脂溶性抗酸化物質(ビタミンE)の両者を再生できる特徴を有する。 重要な点は、ネットワーク系抗酸化物質は個々の抗酸化物質の総和より大きな力を持ち、それらが共同して作用すれば、生命を脅かす酸化的ストレスに対して非常に大きな防衛能力を発揮することである。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P33から37より(satom) フリーラジカルについては左上のフリーページの「活性酸素」のところを参考にしてください。 またビタミンについては上の自由欄を、グルタチオンはフリーページの栄養素の中を参考にしてください(後ほど詳しくこの本の中で説明されていますが)。 ネットワーク系抗酸化物質ということで、5つの物質が挙げられていました。コエンザイムQ10は売れに売れているようです。またこの頃リポ酸もよく見かけるようになりました。しかしネットワークということなので、5つ一緒に摂取するようにしたほうがいいようです。またその他のビタミン・ミネラル・植物栄養素なども満遍なく摂取するように心がけたほうがいいようです。
2005.02.21
コメント(2)
-
アンチオキシダントミラクル(4)
●抗酸化ネットワークの生理機能 これまで医学生物学は、おもに個体レベルで生物の生理機能や病理変化を研究してきた。細胞生物学の発達により、生命の基本単位である細胞レベルでの詳しい解析が可能となった。… ヒトをはじめ、多くの動物も何兆もの細胞集団からできている。お互いによく似た細胞どうしが集まって組織を作り、お互いにうよく似た組織が集まって器官を作っている。1940年代の後半には、食事により十分な量のビタミンCをとらなければ壊血病となることを科学者たちは知っていたし、ビタミンEの存在も知られていたが、それがどのような働きをしているのかわかっていなかった。 食品化学者たちは、ビタミンCやビタミンEが食物の酸化を抑制することを突き止め、そのような作用を有する物質を抗酸化物質と呼ぶようになった。当時の細胞生物学者は、食品化学者たちの仕事が自分たちの研究と関係するとは考えていなかったので、彼らの仕事に興味を示さなかった。ヒトの体内でも同様な反応が起こっているとは、誰一人考えなかった。そのため、重要な事実を発見するまでに長い時間がかかったのである。 1957年、ソビエト連邦が世界初の人工衛星スプートニクを打ち上げた。アメリカ政府は科学の分野でロシアにおくれることをおそれ、一夜にして基礎科学研究と教育に多くの予算をつぎ込むことが決まり、その結果、目を見張る技術革新がおこった。 電子顕微鏡の開発はもっとも重要な事柄の一つだった。旧式の光学顕微鏡よりも数千倍も強力な電子顕微鏡が細胞生物学を新世界に駆り立てた。電子顕微鏡がなければ、抗酸化物質に関する重要な発見も大きく遅れたと思われる。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P30から32より(satom) 米ソの軍拡時代も、その基礎には科学技術の競争があったようです。そんな中から電子顕微鏡が発明され、細胞レベルの研究に大いに役立ったようです。
2005.02.17
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル
●抗酸化ネットワークのなかまたち ネットワーク(リポ酸、コエンザイムQ10、ビタミンC・E、グルタチオン)以外の抗酸化物や非抗酸化物にも、複数のネットワーク系抗酸化物の作用を高める効果があることが知られている。それには植物に由来する無数のフラボノイドが含まれており、そのうち15種類んフラボノイドが果物、野菜、緑茶、赤ワインなどに多量に含まれている。 また、ネットワーク系抗酸化物の作用を増強するセレンは、非項酸化物のミラクルメーカーである。 抗酸化ネットワークとは直接相互作用しないが、体内でフリーラジカルを減少させることにより抗酸化作用を示す多くの抗酸化物がある。ヘルパー抗酸化物とも呼ぶことができるこれらの物質としては、緑黄色野菜や橙黄色の果物などの色素カロテノイドがる。●食事だけで抗酸化物摂取は十分か? 食事中にはすべてのネットワーク系抗酸化物が検出されるのに、なぜさらに補給物を摂取する必要があるのだろうか。抗酸化物を多く含んだ食物をとることはもっとも重要なことであるが、実際には食物のみで最適な量の抗酸化物を摂取することは困難である。 たとえば、パッカープランでは毎日500単位のビタモンEを摂取することを推奨している。この量はビタミンEを食事のみで摂るには、45キログラム以上のレバーや、スプーン125杯分のピーナッツオイルを摂取しなくてはならない。しかしわずかなビタミンE補給剤(サプリメント)を飲むことにより同じ効果を得ることができる。 70%以上のアメリカ人は、抗酸化ネットワークの欠如に起因するさまざまな病気によって本来の寿命より早く死んでいると思われる。このような状態を抗酸化物によりコントロールし、場合によっては病気を予防治療することが可能である。 一種類の抗酸化物を毎日補給するだけで、心臓病や前立腺癌のリスクを大幅に減らすことができる。したがって、抗酸化ネットワークに関与するすべての抗酸化物を補給すれば、大きな効果があることが予想できる。『アンチオキシダントミラクル』Lパッカー・C・コールマン著 講談社サイエンティフィィク P25から28より(satom) どうもサプリメントというと日本では胡散臭いイメージがまだありますが、細胞レベルの分子研究の成果を基盤にしてアメリカではある程度の信頼性を持たれているようです。 運動療法や食事療法などの健康法も大切だと思いますが、「老化」に対抗するために積極的に抗酸化物を補給剤(サプリメント)として摂取することも選択肢の一つだと思います。 また今、環境関連の本を読んでいるのですが、「情報の非対称性」という言葉が出てきます。一方で技術や経営などの十分な知識があるものと、まったくの素人の人が何らかの交渉及び取引をする場合、知識の十分ある者がない者に対して特別に有利な立場になる、また時には詐欺的な内容になるとのことです。また十分知識がない消費者は、環境に悪い・質が割るいが格安なサービスを提供する会社を受け容れて、環境に配慮し・質が良いが割高なサービスを提供する誠実な会社を排除してしまうことがあるようです。 環境問題も健康食品についても草の根的な啓蒙運動が必要だと思います。
2005.02.16
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル(2)
●抗酸化物の奇跡的効果 抗酸化物は体内で作られる一連の化合物であり、多くの食物に含まれている。複数の抗酸化物が共同して働くことが、健康や活力の維持に重要である。抗酸化物は、細胞や組織を傷つけるフリーラジカラから私たちを守っている。 フリーラジカルは正常時にもエネルギー産生の過程で発生しているが、私たちのまわりにはその発生を増加させる化学物質、ガス、汚染物質、紫外線などが満ち溢れている。フリーラジカルが健康に与える影響を過小評価してはならない。フリーラジカルは心臓病、関節炎、癌、白内障など、ほとんどすべての病気の重要な因子であり、老化の主因である。 抗酸化物は、フリーラジカルをうまく制御することにより健康な状態を保ち、老化を抑制し、時には生死も左右することもある。人体における抗酸化物の役割はまさに奇跡的ともいえ、健康で幸せな生活を維持するにはその作用機構を知ることが不可欠である。●健康維持の主役、抗酸化ネットワーク 科学者たちは、」いろいろな抗酸化物が生体内で独立に働いていると考えていた。しかし、今ではこの考えが誤りであることがわかっている。いくつかの重要な抗酸化物が強く相互作用しいる。この相互作用は「抗酸化ネットワーク」、これに関与する物質は「ネットワーク系抗酸化物」と呼ばれている。これらの「ネットワーク系抗酸化物」は共同して健康維持と疾患予防のために働いている。 自然界には何百種類もの抗酸化物があるが、その中でビタミンC、ビタミンE、グルタチオン、リポ酸、および補酵素Q10(コエンザイムQ10)など、わずか5種類が生体内でネットワークとして働いている。 ビタミンCとビタミンEは人の体では合成できないので、必ず食物から摂取しなけれならない。グルタチオン、リポ酸、およびコエンザイムQ10は体内で生合成できるが、これらの生体濃度は加齢とともに低下してくる。そのため、生理代謝を維持するためには、これらの抗酸化物を補給する必要がある。※フリーラジカルについてフリーページの活性酸素のところを参照してください。(satom) それにしても健康食品(サプリメント)の売上げは急増しているようです。ある経済誌には薬品会社も大衆薬の売上げが伸び悩んでいる中、健康食品市場が急拡大しているので、何らかの対応策を取らなければいけないようになっているとのことです。それにしても○○○Cとか○○カップ××とか今まで本当に効いていたのでしょうか。テレビCMでは何かと連呼しているので、つい口をついて出てしまいますが…。 昨年からの健康食品の市場の拡大はまだ第一派だと思います。とにかくサプリメントが効くんだということが普通に認識され始めているのだと思います。次にはその品質や成分の吟味に向かうと思われます。アメリカでは第三者機関がサプリメントの評価を行っているようですが、日本では今のところそういった機関はないようです。ラベルにコンザイムとさえ貼ってあれば飛ぶように売れているようです。天然・化学合成物の違い、製造工程や原料の品質などのチェックが必要になってくると思います。
2005.02.12
コメント(0)
-
アンチオキシダントミラクル
抗酸化物(アンチオキシダント)の研究の第一人者であるレスター・パッカー南カリフォルニア大学教授の書かれた『アンチオキシダント ミラクル』米国では1999年出版、日本では講談社サイエンティフィクより2002年に出版の中から引用してみたいと思います。 コエンザイムやαリポ酸などこのごろ喧伝され急に人気が高まってきましたが、抗酸化物のネットワークとしてパッカー博士らは以前より注目してきた。今のサプリメントなど健康(予防医学)ブームを巻き起こす根源的な要因に、この本はなったのではないでしょうか。 なおL・パッカー教授はファーマネクス社の科学諮問委員会にもなられています。●序文より このわずか半世紀における科学の進歩は実に驚異的である。私(パッカー教授)はカリフォルニア大学バークレー校で細胞分子生物学を教え、抗酸化物の生理機能を研究してきた。私の研究所には世界中から優秀な研究者が集まり、健康や病気に対するさまざまな物質の影響を研究し、毎日のように奇跡的な生命現象を目の当たりすることができた。食物やビタミン、ミネラル、およびさまざまな抗酸化物は私たちの健康維持に不可欠である。 多くの研究により、抗酸化物が病気を予防治療するのみならず、寿命を延長させうることが確認されている。(satom) 今のコエンザイムブームもこういった科学者の地味で真摯な研究の成果によってもたらされたということでしょう。
2005.02.09
コメント(0)
-
タンパク質(3)プリオン病
タンパク質がいかに健康にとって重要なものか、プリオン病というタンパク質だけからなる感染因子のことを少し引用してみたいと思います。 『微生物vs人類』加藤延夫著 講談社現代新書より●プリオン病(伝達性海綿状脳症) ヒトのクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)、ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病(GSS)、致死性家族性不眠症(FFI)、ヒツジのスクレイピー、ウシ海綿状脳症(BSE)、ミンク伝達性脳症とよばれる病気は、プリオンと名づけられている感染因子が発病の原因であり、長い年月を経て脳がスポンジ(海綿)状に変性し、痴呆や運動失調などの中枢神経の異常に基づく病状を呈し、発病後は、比較的短期間のうちに死亡するという特徴を示します。 …スクレイピーを発病したヒツジの脳を乳剤にして霊長類の動物やハムスター、マウスなどの小動物に注射すると、数年の潜伏期のあと発病し、スクレイピーと同様の脳病変が発症しました。脳乳剤中の感染をもつ因子は、核酸を含まず、蛋白質だけから成ることが明らかにされ、蛋白質性感染性粒子の意味でプリオンと名づけられました。 病原性があり、宿主生物に感染したり増殖したりするものが、核酸を含まないということは、たいへん驚くべきことでした。 生物の遺伝情報はDNAの塩基配列に刻印され、それがRNAに伝えられ、その遺伝暗号に基づいて蛋白質が合成されるというのが、生物界の中心教義といわれる基本的な考え方です。 …ところが、プリオンにはDNAもRNAも含まれず、他の細菌やウイルスとまったく異なり、その病原性は蛋白質に担われるとみなされます。 プリオンが宿主動物の脳細胞に感染し、増殖する機構については次のように説明されます。動物の種を問わず、正常細胞の染色体にはプリオン類似蛋白質をつくる遺伝子があり、プリオン類似蛋白質(PrPc cは細胞性を意味する)を常に生産しています。病原性のあるプリオン(PrPsc scはスクレイピー)に感染した細胞では、細胞自身がもっているPrPcがPrPscの触媒作用により、その立体構造が変化してPrPscに変わってしまいます。 プリオンの増殖は、このようにおきます。(satom) なんとタンパク質の酵素の役割が、あるタンパク質を正常なものから病性のものへと変位させてしまうとのことです。正常なタンパク質も何らかの影響で変性されてしまうと、とんでもない酵素作用(触媒作用)により、正常タンパク質を病性のものへと変えてしまうようです。 年齢と共にタンパク質の変性が進み、ヒトの体のなかの正常タンパク質を悪性のものに変えてしまうのかもしれません。
2005.02.07
コメント(2)
-
タンパク質(2)
ちょっと難しいですが、タンパク質の引用を少し続けます。様々なタンパク質の状態を良好に保つということが、「健康」に繋がるということだと思います。普通タンパク質というと「体を形造る」などという簡単な言葉で済まされがちですが、これがまた複雑極まりない代物のようです。●単純なユニットで無限の構造 タンパク質は20種類のアミノ酸をつなげた高分子であって、ユニットから見るとじつに単純である。ユニットという言葉では、タンパク質の部分構造である二次構造も一般的な構造のユニットであり、その種類はごくわずかである。それにもかかわらず、タンパク質がひじょうに多様な機能を持つことは驚きである。そこには単純なユニットからほとんど無限の構造を生成することができる高分子の特徴がよくあらわれている。 まず、タンパク質のアミノ酸配列は、可能な配列のなかでひじょうに特殊なものが選ばれていることは確かである。100個のアミノ酸からなるタンパク質を考えてみると、20種類のアミノ酸をランダムに配列すれば、潜在的には20の100乗種類のタンパク質が可能である。この天文学的な数に対して、ヒトゲノムの中に含まれる遺伝子はせいぜい数万であり、選択的スプライシンングを考えたとしてもタンパク質の種類は数十万くらいだろう。そのちがいはまさに桁はずれである。そういう意味では、実際のタンパク質は高度な機能をもつことができた特殊な配列なのかもしれない。 タンパク質の立体構造についても同様の計算ができる。タンパク質はアミノ酸がペプチド結合(CO-NHの結合)で一次元的につながったものである。一般的に高分子には、結合部位のところで回転の自由度がある。タンパク質の場合は、っ各アミノ酸が2種類の回転の自由度を持っている。側鎖がある程度の大きさを持っているために、高分子の回転の自由度には制限がある。一般的に各自由度は3つの可能な方向を持っているので、ひとつのアミノ酸は9つの可能な構造をもつと考えていい。 典型的なタンパク質は、100~500個のアミノ酸を含んでいるので、タンパク質の構造の自由度は、原理的には10の100乗を超えることになる。ひとつの生体高分子は一般の高分子と同じように、潜在的に膨大な数の構造をとりうるのである。しかし、実際のタンパク質はひとつのまたはかぎられた数の安定な立体構造をとる。つまり、タンパク質は天文学的な数の立体構造のなかから、機能に適切なごくかぎられた数の立体構造をとるように、天文学的な数のアミノ酸配列から特定の配列が選ばれたのである。(satom) タンパク質は20種類のアミノ酸から作られているのですが、そのいくつかのアミノ酸の配列により、特定の立体構造ができるようです。タンパク質では、例えばその中のアミノ酸のひとつが似たようなアミノ酸に入れ替えられても、その立体構造に変位がなければ、機能的に問題ないようです。 私たちの体の様々なタンパク質も特定な立体構造を持っているために、役に立って機能しているようです。何らかの影響でこの立体構造が変化してしまうようなことになりますと、機能不全→病的症状の顕現ということになるようです。
2005.02.02
コメント(0)
-
タンパク質
長かったウイルスものも終わりにします。それにしてもウイルスって面白い、いや怖いですね。 『分子生物学入門』美宅成樹著 岩波新書にたんぱく質のことが細かく出てましたので引用します。●多様なタンパク質のはたらき ヒトのゲノムには3万~4万種類の遺伝子が含まれている。選択的スプライシングという現象があって、ひとつの遺伝子から多種類のタンパク質ができることがある。したがって、数万から数十万というタンパク質が、わたしたちの体を構成していることになる。そして、それぞれのタンパク質は異なる機能をもっているが、ゲノムの情報から得られるタンパク質のアミノ酸配列のなかで、機能が知られているものはせいぜい半分くらいである。しかし、おおざっぱにタンパク質を分類することはできる。思いがけない機能をもったタンパク質もあるが、代表的なものをしめすと、以下のとおりである。(1)酵素は、生体内の化学反応を促進するはたらきをもつタンパク質である。一般に化学反応を促進する物質を触媒というが、酵素は化学反応の触媒ということになる。たとえば、タンパク質を分解する酵素やDNA分解酵素、脂質分解酵素ばどの一群の化学結合を切る反応を触媒する酵素がある一方、トリプトファンというアミノ酸を合成する酵素、ATP合成酵素、DNA合成酵素などの化学結合を形成する酵素があり、その他さまざまな化学反応の触媒をする酵素がある。(2)モータータンパク質は、文字どおり動くことを機能しているタンパク質である。代表的なモータータンパク質には、筋肉の繊維を構成しているミオシンがある。ATPをADPに分解して得られる化学エネルギーを利用して、分子の構造を変えて動くことがわかっている。細胞の中には微小管などの繊維状のタンパク質の構造が発達しているが、その上を歩くように動くキネシンやダイニンというタンパク質もモータータンパク質である。直線的に動くモーターだけではなく、回転モーターもある。バクテリアのべん毛の根元にあるべん毛モーターは、多くのタンパク質が複合体をつくっていて、水素イオンの移動をエネルギー源として回転運動をおこなう。(3)受容体は、細胞膜に埋め込まれたタイプのタンパク質で、細胞外からの情報をつかまえて細胞内に伝える役割をはたしている。受容体の多くは、化学物質(ホルモンや神経伝達物質、におい物質など)を結合して、その情報を細胞内に伝達する。さらに、それ以外のさまざまな刺激に対しても受容体が発達している。たとえば、ロドプシンは光を吸収して、その情報を細胞に伝えている。(4)輸送タンパク質は、特定の分子をある場所から別の場所に移動させるものである。ヘモグロビン(酸素を輸送する)や血清アルブミン(脂肪を輸送する)のように体の循環器系を利用して輸送させるものと、細胞内外の輸送をおこなう膜輸送タンパク質がある。後者では、細胞に必要な栄養の分子やイオンを取り込んだり、細胞に不要あるいは毒性のある分子を排出する。(5)遺伝子調節のための転写因子タンパク質は、DNAに結合してRNAへの転写を制御するはたらきをもっている。多細胞生物でひじょうに重要な役割をはたす転写因子タンパク質にホメオドメインタンパク質がある。ホメオドメインタンパク質は体の形成スイッチとしてはたらいていて、頭、胸、腹などの体全体の形を決めている。頭、胸、腹があったり、背中とおなかがあったりするという意味では、昆虫もヒトも同じであり、同じようなモメオドメインタンパク質によって決められている。(6)コラーゲン、ケラチンなどの構造タンパク質、フェリチン(鉄を貯蔵する)やカゼイン(アミノ酸の貯蔵庫)などの栄養の貯蔵に使われるタンパク質、神経成長因子、上皮成長因子、インシュリンなどのシグナルとしてはたらくタンパク質も生体の維持に不可欠である。変わったところでは、時間を記憶するようなタンパク質も見つかっている。凍結防止のタンパク質がある一方で、積極的に氷の核になるタンパク質もある。とにかく生体内でなんらかの機能が見つかったら、その機能のためのタンパク質があることをまず疑ってみるべきである。(satom) 一口にタンパク質といってもいろんな機能を持ったものがあります。生体機能のすべてはタンパク質が担っていると言っても過言ではないでしょう。何しろDNAやRNAも転写因子タンパク質がなければ何にも仕事ができないようになっています。 ヒトのDNAはすべて解析されたとのことですが、なんとタンパク質はその半分ぐらいが構造を決定できていないとのことです。いままだ謎のベールに包まれているのがタンパク質です。 また様々な酵素が生体の代謝機能に不可欠ですが、この酵素にはビタミン・ミネラルなどの補酵素が必要とされます。つまり酵素がちゃんと働くためにビタミン・ミネラルを十分摂取しないといけないということです。今話題のコエンザイムも補酵素です。年齢と共にビタミン・ミネラルなどの補酵素が減少することで、酵素が十分働かなくなると、様々な体の不調に繋がっていくことになります。 また受容体や輸送タンパク、コラーゲンなどの構造タンパクが変性してしまうとまた体のトラブルに繋がっていくことになります。また転写因子タンパク質がうまく働かないと、ガン化の原因にもなるようです。すべての病気はタンパク質の変性・不調にあるといってもよいでしょう。
2005.01.27
コメント(0)
-
SARS(2)
●症状・感染力に個人差が WHOによると、SARSの死亡率は24歳以下では1%未満、25~44歳が6%、45歳~65歳では15%であるのに対して、65歳以上の高齢者では50%以上と推定される。全体では14~15%の高い致死率を示すと推測されているが、2003年10月現在では9.6%である。心臓や肝臓、糖尿病などの慢性基礎疾患を持つ人では重症化傾向が見られる。患者の2割程度が重症化するが、微熱程度の症状で回復する人もおり、SARSの症例定義がかならずしもあてはまらないことを示している。インフルエンザと同様に、高齢者における予後は悪いが、小児では軽症で済む傾向が強く、幼稚園や小学校でのSARSの報告はほとんど見られない。この年齢による差の理由は解明されていない。 ほとんどの患者では、1人の患者から1~3人への小規模な感染の伝播である。しかし、感染力のきわめて強い「スーパースプレッダー」の存在が感染拡大を招いた事実が明らかにされており、1人の患者が30人以上にも感染をひろげた事例も報告されている。スーパースプレッダーの本体は不明であるが、糖尿病などの基礎疾患を持っている場合が多く、生体防御機能の低下によって体内でのウイルス増殖を抑えきれず、大量のウイルスを長期間排泄し続けるのでないかと推定される。今回の流行は、広東省から香港にウイルスを持ち込んだ第一例患者がスーパースプレッダーであり、しかも国際的なホテルに宿泊したことが、SARSが急速に世界各地へ伝播された原因であったと考えられる。(satom) SARSもインフルエンザと同じように高齢者に対する感染→致死率が高いようです。通常の「かぜ」もそうですが、免疫の低下した人にとっては非常に危険なことになります。 高齢者医療では、中心となる「生活習慣病」とともに、弱毒型でもウイルス感染に対する予防策が重要なファクターになるように思われます。 なお糖尿病など栄養過多な人は、前に連載した「半断食法」に書いてあったように、ウイルス増殖に豊富な栄養を供給してしまうことになるのでしょうか。
2005.01.25
コメント(0)
全161件 (161件中 1-50件目)