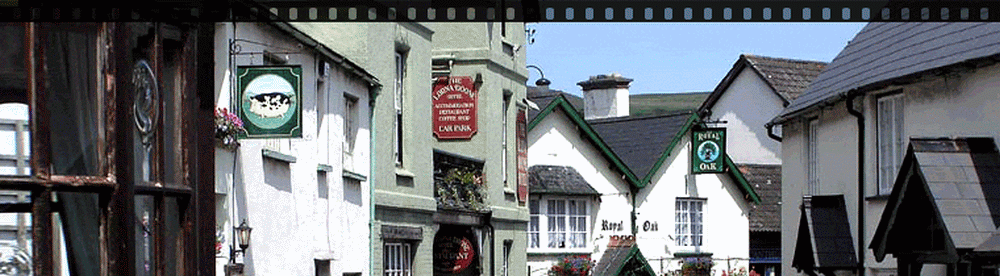2014年05月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
シモン・ボッカネグラ ローマ歌劇場来日公演
なんだかんだ言われても、ムーティのヴェルディはいいですね。飽くことなく時間が過ぎてしまいました。そして、ときには海のさざ波、ときには海をわたる風のように、静かに奏でられる弦が、ジェノバの雰囲気を醸し出し、単に復讐や憎悪のどろどろにはしていません。フリットリの急遽の代役、エレオノーラ・ブラットは、最初は堅さが出てましたが、徐々にこなれて、紅一点の重要ポイントこなしてました。若さあふれてイイ。フランチェスコ・メーリも、こういった直情的かつ繊細な役どころも表現豊かでイイですね~なんといっても低音陣が皆充実。タイトルロールのジョルジョ・ペテアンは本当に歌いっぱなしで、最後まで全然疲れ感じないのですから、素晴らしい歌いっぷりです。なんといっても品があります。低音メイン三人、甲乙つけがたし!なかなかこういう機会ないですよね!! しかし、日本人のムーティびいきを差し引いても、カーテンコールは、ひさびさの大盛況、はっきり言って前回スカラ座より盛り上がってました。イタリアに求める「らしさ」を指揮も歌手も超良質に仕上げてくれればイイんです!! 指揮:リッカルド・ムーティ演出:エイドリアン・ノーブル美術:ダンテ・フェレッティ衣裳:マウリツィオ・ミレノッティ合唱指揮:ロベルト・ガッビアーニシモン・ボッカネグラ:ジョルジョ・ペテアンマリア・ボッカネグラ(アメーリア):エレオノーラ・ブラットガブリエーレ・アドルノ:フランチェスコ・メーリヤーコポ・フィエスコ:ドミトリー・ベロセルスキーパオロ・アルビアーニ:マルコ・カリアピエトロ:ルーカ・ダッラミーコ伝令:サヴェリオ・フィオーレ侍女:スィムゲ・ビュユックエデス ローマ歌劇場管弦楽団ローマ歌劇場合唱団プロローグ、第1幕 15:00 - 16:40 休憩 第2幕、第3幕 17:10 - 18:102014(平成26)年5月25日(日)東京文化会館大ホールにて
2014年05月25日
コメント(0)
-
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2014 5月5日
最終日、大好きなアンヌ・ケフェレックをメインに据えられました。 まずは昨日と同じトリオから。昨日に続く、ひたすら軽快なハイドンが心地よい。そしてラヴェルのピアノ三重奏曲の描く夢幻の幻想に圧倒されました。ピチカートから入っていき、ヴァイオリンとチェロとピアノがそれぞれ織り成す曲想は、フルオーケストラのように華やかで、かつエキゾチックな雰囲気。私はオリエンタルをイメージしました。こんな幻想的かつ壮大な三重奏曲があるんですね、たいへんすばらしかった! 361ハイドン:ピアノ三重奏曲第28番 ホ長調Hob.XV-28 第1楽章 アレグロ・モデラート 第2楽章 アレグレット 第3楽章 フィナーレ:アレグロラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調 第1楽章 モデレ 第2楽章 パントゥム:アッセ・ヴィフ 第3楽章 パッサカイユ:トレ・ラルジュ 第4楽章 フィナーレ:アニメトリオ・カレニーヌ マリー=カトリーヌ・ジローのピアノソロ、ショパンとモシェレスを堪能しました。彼女はは本当にピアノが大好きなんだなぁという気持ちが溢れて伝わってきます。それを感じ取れたら、他に何も言うことなし、大満足です。362ショパン:ボレロ ハ長調 op.19モシェレス:スペイン・ロンドショパン:3つの新しい練習曲 KK II b-3 第1番 へ短調 第2番 変イ長調 第3番 変二長調モシェレス:性格的練習曲第1番 op.95-1「怒り」ショパン:即興曲第4番 嬰ハ短調 op.66「幻想即興曲」モシェレス:メランコリックなソナタ op.49ショパン:タランテラ 変イ長調 op.43ピアノ マリー=カトリーヌ・ジロー アンヌ・ケフェレックのピアノというのは、本当に不思議。音を奏でているのに(ピアノ・ソロ・リサイタルを聞いたときもそうでしたが)絵のようで、色彩をふんだんに感じます。凛としている感じもいいですよね。今回モーツァルトを知的かつ表情豊かに奏でてくれました、言うことなしです。しかし「ジュノム」の第3楽章、ロンド・フィナーレなのに、合間にメヌエットが出てきて、しかもまったく違和感ない。モーツァルトはまさに天才です。343モーツァルト:ディヴェルティメント 二長調 K.136 第1楽章 アレグロ 第2楽章 アンダンテ 第3楽章 プレストモーツァルト:ピアノ協奏曲第9番 変ホ長調 K.271「ジュノム」 第1楽章 アレグロ 第2楽章 アンダンティーノ 第3楽章 ロンド:プレストアンコールヘンデル:メヌエット ト短調(W.ケンプ編曲)ピアノ アンヌ・ケフェレック横浜シンフォニエッタ指揮 ジョシュア・タン
2014年05月05日
コメント(0)
-
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2014 5月4日
本日は前半はサロン雰囲気の小粋な演奏。後半はフィリップ・カサール、フィリップ・ジュジアーノという、知的に感情抑えてるのに、かえって情感伝わるという、大変私好みのプログラム堪能の1日でした。 朝一は、いかにもハイドンらしい、ひたすら明るいピアノ三重奏曲と、いかにもモーツァルトらしいオシャレで華やかなピアノ三重奏曲。曲調に、遥か昔のソナチネ練習を思い出してしまいました(笑)モーツァルトの第3楽章の変奏は、ピアノ・ヴァイオリン・チェロの組み合わせだとこんなに多様になるんですね~、よかった!261ハイドン:ピアノ三重奏曲第27番 ハ長調Hob.XV-27 第1楽章 アレグロ 第2楽章 アンダンテ 第3楽章 フィナーレ:プレストモーツァルト:ピアノ三重奏曲第2番 ト長調K.496 第1楽章 アレグロ 第2楽章 アンダンテ 第3楽章 主題と変奏:アレグレットトリオ・カレニーヌ モーツァルトの子供時代から晩年へかけて、順に手紙を朗読して、そのイメージに合ったモーツァルト歌曲を天羽明惠さんが歌う、ユニークな企画。オペラ「マティルデ・ディ・シャブラン」タイトルロール役のCDでしか聞いたことのないので、ぜひ生で聞きたかった天羽さんは、ベルベットのようなやわらかさのなかに力強さとやわらかさを感じます。モーツァルトのオペラがたいへんよく合いそう、今度聞いてみたいです。天羽さんの澄んだ声は、たいへん素敵でした! 262手紙からひも解くモーツァルト歌曲の世界モーツァルト:春への憧れ鳥たちよ、年毎に寂しい森の中ですみれ喜びは胸に躍りクローエに魔術師静けさはほほ笑みにルィーゼが不実な恋人の手紙を焼いたとき夕べへの想いアンコール春への憧れ 1番のみソプラノ 天羽明惠ピアノ 仲田淳也朗読 村上信夫 フランスの音楽教育家ナディア・ブーランジェが指導したアメリカ人作曲家の企画。ガーシュインのジャズと、コープランドのリズム&ブルースがよかった。ルネ・マルタンが企画しなきゃたぶん聞く機会ない楽曲を体験できました。263ナディア・ブーランジェ・トリビュートグラス:メタモルフォーシス ガーシュイン:3つの前奏曲 第1曲 変ロ長調 第2曲 嬰ハ短調 第3曲 変ホ短調 コープランド:4つのピアノ・ブルース 第1曲 きままなポエム 第2曲 甘さと物憂げ 第3曲 黙りと感覚 第4曲 はずみをつけてグラス:ウィチタ・ヴォルテックス・スートラ フィリップ・カサールでシューベルトの遺作ピアノ・ソナタを聞きました、いやぁすばらしかったです!病に冒された死の間際の遺作なのに、なぜか後半行くほど明るい曲調になる。でも希望の光には感じません。第3楽章スケルツォから第4楽章の凄まじさ!第3楽章スケルツォでいったん死の直前の覚醒を得ますが、第4楽章では、繰り返されるモチーフの明るさと合間の深刻さの交代が、死を目前ということを如実に感じます。モチーフはやがて半音づつさがって弱くなり、最後の力を振り絞った蘇生後に力尽きる。カサールの表現は大変知的で感情に流されないが、映像を見るようなイメージを感じる。強弱と緩急のバランス見事です。わたしが今まで感じていた、オーストリア人のシューベルトとまったく違う色彩と映像で表現されるイメージに大感動です。アンコールの即興曲はひたすら優しくて和みました。シューベルトを大得意とするピアニスト堪能です。よみうり大手町ホールという新しいホールも、音響効果よく、これから色々開催されて馴染むとかなりよくなりそうです。 284音楽の捧げもの〈最期の音楽〉シューベルト:ピアノ・ソナタ第21番 変ロ長調D960(遺作) 第1楽章 モルト・モデラート 第2楽章 アンダンテ・ソステヌート 第3楽章 スケルツォ:アレグロ・ヴィヴァーチェ・コン・デリカッツァ 第4楽章 アレグロ・マ・ノン・トロッポアンコールシューベルト:即興曲 変ト長調D899-3ピアノ フィリップ・カサール シューベルトの余韻冷めやらぬまま、よみうり大手町ホールから有楽町国際フォーラムへもどり、今日のラスト、フィリップ・ジュジアーノのショパンに。1995年のショパンコンクール最高位者(1位なしの2位)は、知的でした。前奏曲24曲全曲を休みなしに一気に聞けるというのは、マニアックでふつうの演奏会だとなかなかないんですよね~ヴァリエーションに富む曲を感情に流されることなく、しかし杓子定規ではなく、余韻聞かせながらの表情に魅入られました。266ショパン:ノクターン 嬰ハ短調 KK IV a-16(遺作)ショパン:24の前奏曲 op.28ピアノ フィリップ・ジュジアーノ
2014年05月04日
コメント(0)
-
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2014 5月3日
今年はまずは、フォーレのレクイエムから。フォーレも初めて、そしてミシェル・コルボもわたしは初めてです、いつもタイミング悪くてチケット取れなくて。フォーレは鎮魂の中でも、荘厳で讃えるというより、美しい楽園への誘(いざな)いというイメージをもちました。しかもコルボの指揮するローザンヌ声楽アンサンブル、ピアニシモがまたいい!冒頭、合唱のピアニシモは弦楽器かと思ってしまいました。ほんとうに美しく、聞き終わったあと、心が浄化(ピューリファイ)されるってこういうことかと体感できる、至上の音楽でした。143 フォーレ:レクイエムop.48アンコール グノー:「十字架上のキリストの最後の7つの言葉」より終曲指揮 ミシェル・コルボソプラノ シルヴィ・ヴェルメイユバリトン ファブリス・エヨーズオルガン マルチェロ・ジャンニーニローザンヌ声楽アンサンブルシンフォニア・ヴァルソヴィア 次は、いろいろ珍しい曲目を積極的に紹介しているという、マリー=カトリーヌ・ジロー。今回はチェコの作曲家モシェレスの作品をいろいろ選んでいるようで、興味深いです。ショパンは異なった2曲を組み合わせた大変ユニークなもの。それにしても彼女のテクニックすごいです!モシェレスは七重奏曲というめずらしさに興味持ったのですが、仲間内で楽しむミニピアノ・コンチェルトという感じでした。まあしかし、ピアノが圧倒的存在感で、他は伴奏みたいというのはしかたないのかな。大変希有な演奏楽しみました。やっぱこういうの聞く機会って、ここじゃなきゃないですものね~。 134ショパン:アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 変ホ長調op.22モシェレス: 七重奏曲二長調op.88 第1楽章アレグロ・コン・スピリート 第2楽章スケルツォ:プレスト 第3楽章アダージョ・コン・モート 第4楽章フィナーレ:アレグロ・コン・ブリオピアノ マリー=カトリーヌ・ジロークラリネット 山根孝司コントラバス 赤池光治フォル・ジュルネ・カメラータ ヴァイオリン アナ・ゲッケル ヴィオラ コランタン・アパレイー ホルン ニコラ・ラメズ チェロ ルイ・ロッドゥ 2002年リストコンクール満場一致で優勝のジャン・デュベのオール・リスト・プログラムラストの自身で編曲した、「19のハンガリー狂詩曲 第19番」に尽きます。超絶テクニックはもちろん、彼のピアノは大変情熱的で、甘さを感じます。リストはテクニックにハマりがちな一般ピアニストと大違い、まさに「現代のリスト」ですね!イングリット・フジコ・ヘミングの「癒し」音色(これはこれで衝撃でハマりました)のリストばかり聞いてきた私には、まさに当時のリストはこれで御婦人方を引き付けたんだろうなぁと想像する、大変カッコイイ音色でした。(見た目はかなりのオッサン体型ですが)途中のオリジナルのハンガリー狂詩曲は楽譜見ながら弾いてました。譜面見ながら弾くレベルのテクじゃないですから、たぶん編曲の方を弾きすぎて、オリジナル弾くには慎重になっているんだろうなあと理解してます。リストの神髄に触れた気分です、すごかった。155リスト ペトラルカのソネット第47番、第123番(巡礼の年 第2年「イタリア」より)リスト 19のハンガリー狂詩曲より 第1番、第4番、第18番リスト(デュベ編) 19のハンガリー狂詩曲より 第19番ピアノ ジャン・デュベ 今日の最後、シューマンのピアノ五重奏曲。名曲というのはピアノと弦楽奏団のバランスが大変よくて心地いいですね。第4楽章は、民族的なフレーズで、ドヴォルザークかと思ってしまいました。ピアノソロ以外の室内楽奏というのを聞く機会がほとんどないので、大変楽しめました。若手のカメラータの、特に第4楽章の掛け合いのコンビネーションがたいへんよかったです。 126シューマン:ヴァイオリン・ソナタ第1番 イ短調op.105 第1楽章 ミット・ライデンシャフトリッヒェン・アウスドリュック(情熱的な表情をもって) 第2楽章 アレグレット 第3楽章 レブハフト(生き生きと)シューマン:ピアノ五重奏曲 変ホ長調op.44 第1楽章 アレグロ・ブリランテ 第2楽章 イン・モード・ドゥナ・マルチア ウン・ポコ・ラルガメンテ 第3楽章 スケルツォ:モルト・ヴィヴァーチェ 第4楽章 アレグロ・マ・ノン・トロッポピアノ クレール・デゼールフォル・ジュルネ・カメラータ ヴァイオリン 正戸里佳 ヴァイオリン クレモンス・ドゥ・フォルスヴィル ヴィオラ コランタン・アパレイー チェロ オーレリアン・パスカル
2014年05月03日
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-
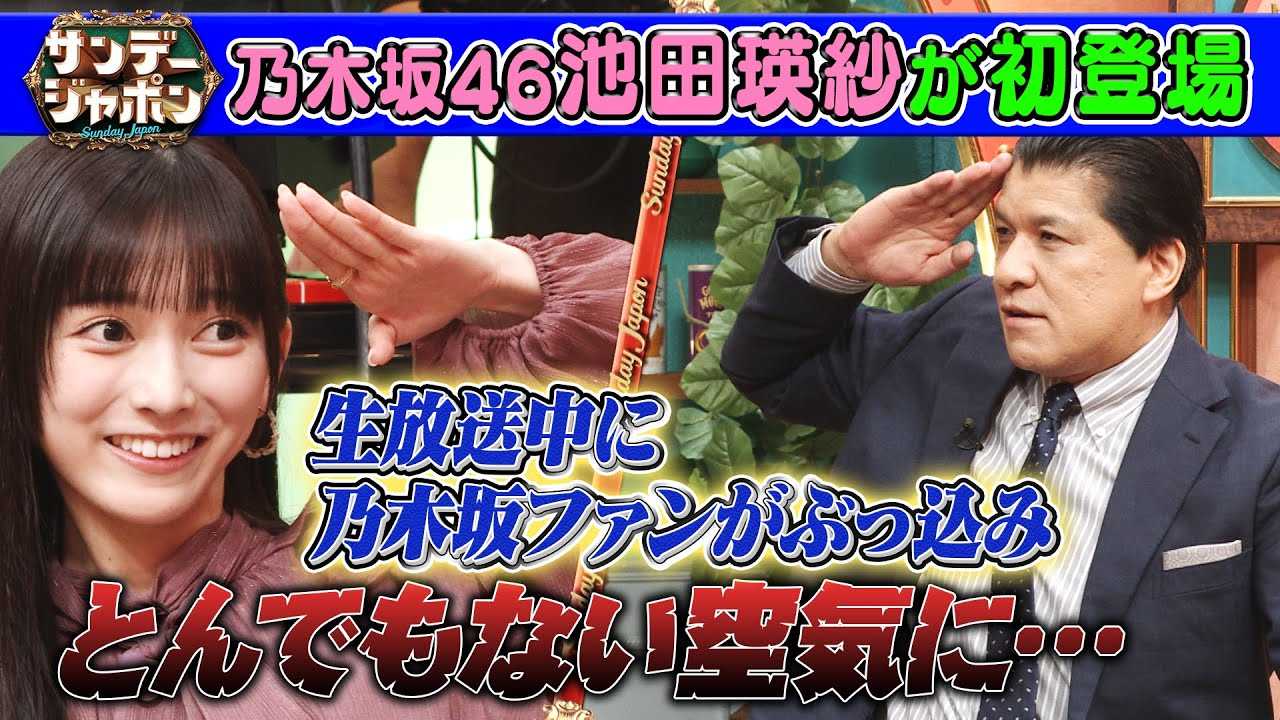
- ☆AKB48についてあれこれ☆
- ☆乃木坂46♪【アイドル界の二刀流】池…
- (2025-11-27 06:58:00)
-
-
-

- いま嵐を語ろう♪
- 嵐ライブ2026生配信を見逃さないため…
- (2025-11-23 20:15:02)
-
-
-

- X JAPAN!我ら運命共同体!
- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…
- (2024-07-25 18:16:12)
-