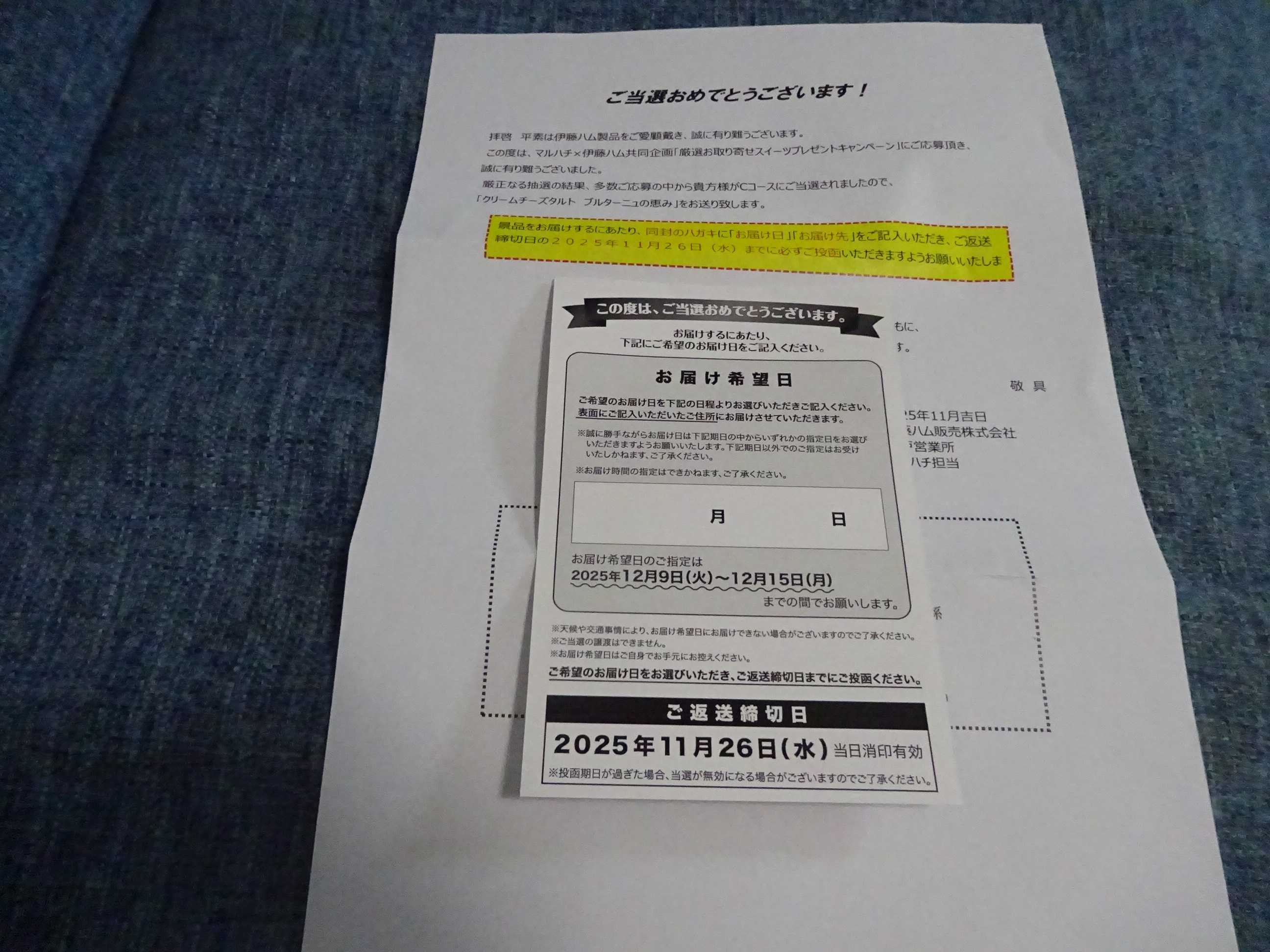2007年05月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
どうする!?今後の「日田観光」
日田市観光協会の総会が開催されましたが、それに先立ち、当協会の新しい事務局長の佐藤真一氏の講演会が行われました。佐藤事務局長は(株)リクルートを退社し起業、旅行誌「じゃらん九州発」の元編集長という経歴の持ち主です。 また、佐藤氏は「バリュークリエイター」とも言われています。「バリュー・クリエーター」とは、「地域、企業、個人に対して、潜在価値を発掘して、消費者価値に転換させる達人」という意味だそうです。 講演会では「自ら機会を作り、機会をもって変えよ」「観光資源が眠っているというが、人が眠っている」「情報のストーリー化」「そんなことはできる(「そんなことはできない」の反対)という発想」など示唆に富んだ言葉を話されました。 新しい事務局長を迎えた日田市観光協会をみんなで盛り立てて、日田市の観光資源を大いに生かし、「観光・日田」を全国にアピールしていきましょう。
2007年05月31日
-
これからもがんばろう!大鶴防犯パトロール隊
私が会長を務める大鶴防犯防災協議会では、平成16年の11月から青色防犯等装着車による、大鶴地区内の防犯パトロールを週に一回行っています。 29日には総会があり、19年度は95名が「大鶴防犯パトロール隊」に登録して、今後も活動を続けていくことを確認しました。 パトロール車は、隊員のひとりが寄付してくれたもので、車の維持費・ガソリン代・保険代などパトロールに関わる経費は大鶴地区民が手出ししたお金でまかなわれています。 私は昨年9月議会の一般質問で「このような自助努力の活動に関しては行政が後押しすることを考えてもいいのではないか」という質問をしましたが、その時の市の答弁は「今後ボランティア団体の支援体制について協議していく」ということでした。 会長の私が言うのもおかしいのですが、「パトロール隊」に登録した皆さんのまじめな活動ぶりには頭が下がります。
2007年05月29日
-
思い出のカメルーン・キャンプ地で少年サッカーフェスティバル
(坂本休・地球財団理事長にむかって「選手宣誓!」)「第2回カメルーン杯中津江村ジュニアサッカーフェスティバル」(主催・中津江村地球財団)が今日から明日にかけて開催されています。私は日田市サッカー協会会長として開会式で来賓挨拶を行いました。 会場は2002年サッカーW杯でカメルーン代表がキャンプ地とした鯛生スポーツセンターのグラウンドです。この大会はその時の感動を次の時代へ受け継いでいこうと、昨年から始まりました。 対象はUー11のチームで今年は大分県と熊本県から12チームが参加しました。小学生達はカメルーン代表が使った芝の感触を楽しみながら、懸命にボールを追いかけていました。
2007年05月26日
-
「川開き観光祭」で旧日田郡内の芸能隊もがんばる!
26,27日の両日「第60回日田川開き観光祭」が開催されています。 26日には屋形船上で「水神祭」が厳かに執り行われ、神事の後、日田観光キャンペーンレディーのみなさんにより、鮎の稚魚が三隈川に放流されました。 この2日間、市内でいろいろなイベントが行われますが、「芸能隊」の活躍も呼びもののひとつです。 昼ごろ、サッカー大会の開会式のために中津江村に向かっている途中で、前津江町の芸能隊「シャカダケッツ」が「水辺の郷おおやま」で踊っているところに遭遇しました。 こういう場面を見ると、あらためて、日田市郡が合併した実感がわきます。
2007年05月26日
-
静修小の校区内鼓笛パレード
今週末は日田市の川開き観光祭が開催されますが、それにそなえて静修小学校では連日鼓笛パレードの練習にはげんでいます。 昭和60年からつづけていて、4~6年生が参加しています。最初の頃は3学年で100人以上いましたが、最近は児童数も減ってここ数年は35人程度です。それでも楽器を充実させて児童数の減少をおぎなっています。 「静修小学校校歌」「オリバーのマーチ」「島唄」を演奏しますが、中でも3年位前からレパートリーに加わった「島唄」はすばらしいアレンジです。26日に市内中心部で開催される「鼓笛大パレード」での活躍が楽しみです。 この日は好天にめぐまれ、子供たちもバテ気味でしたが、地区内の皆さんに励まされながらがんばっていました。
2007年05月22日
-
天女が来たりて笛を吹く
雅楽の2人組ユニット「むすびひめ」のコンサートが「井上家滴翠園・穀倉ホール」で開催されました。といっても、今回の主催は私たちではなく、市内大肥本町の吉田忠司氏が中心となっている、お茶の研究グループである「My Tea茶,s 倶楽部」の主催でした。 吉田さんたちは、10時から3時までは大肥本町で「釜炒り茶づくり体験」のイベントを行い、4時から「滴翠園」での雅楽のコンサートを企画しました。 コンサートではできたての釜炒り茶とお菓子もふるまわれ、倉の窓からおだやかな陽ざしがさしこむなか、日本古来の雅楽のしらべがながれ、聴衆はゆったりとした時間に身をゆだねていました。 「滴翠園コンサート」は一昨年秋に開催して以来、行っていませんが、今日は聴衆として参加し、「滴翠園コンサート」の感動がよみがえりました。「やっぱり、近々『滴翠園コンサート』を復活させなくては!」と思いました。
2007年05月20日
-
市内鶴河内町の梶原菜園で「第2回収穫祭」
市内鶴河内町で野菜作りをしている梶原昭彦さん・洋子さんご夫妻の経営する「梶原菜園」で昨年12月につづき第2回目の収穫祭が行われました。 お客さんに露地の畑やビニールハウスの中の野菜を自由に収穫してもらい、販売をするコーナーと、野菜のおいしい食べ方を体験する試食コーナーが今回も設定されていました。 今回のその場で収穫する野菜は「ダイコン・ニンジン・タマネギ・ジャガイモ・レタス・ホウレンソウ・ミブナ・シュンギク・ミニハクサイ」などで、みなさん収穫の喜びを味わっていました。また、大鶴産ヒノヒカリ5kg1,500円のお米も大人気でした。 試食コーナーでは、とれたての野菜をふんだんに使った、やきそば・おにぎり・サラダなどがずらりとならび、お客さんたちの食欲をそそっていました。 今回は「ももは工房」からも味噌や豆乳プリンなどを販売するコーナーを出店しました。 梶原さんによると「今後もつづけていきたい」とのことでしたので、将来は広く日田市内外からお客さんの来る収穫祭に育っていけると良いと思います。
2007年05月20日
-
豊かな国の森づくり大会
大分県や日田市などの主催で「第7回豊かな国の森づくり大会」が、市内の萩尾公園で開催されました。 大会のテーマは「水の郷 みんなで支える 森づくり」で、日田市内外の森林・林業関係者や「みどりの少年団」はもちろんのこと、下流域の福岡県の森林ボランティアグループ、漁業関係者、大分県や福岡県の大学の留学生のみなさんなど約1,200人が参加しました。 大会行事では広瀬知事の主催者あいさつ・「林業技術コンテスト」や「ふるさとおおいたの森写真コンクール」の表彰式・緑のメッセージの朗読等が行われました。 その後、隣接した会場で記念植樹が行われ、ヤマザクラ・モミジ・イチョウなど8種類2,000本の苗木が植樹されました。 森林の持つ「水源涵養」「二酸化炭素の吸収源」「治山治水」などの公益的機能が近年ますます重視されており、ここ数年は、この種の大会に森林・林業関係者以外の人たちが重要な役割で関わることが多くなりました。 このようなイベント的な大会と同時に「滞在型でしかも一過性ではない」森林ボランティア作業の取り組みも中津江村などで以前から行われています。地道に民間で行われている「森林づくりをつうじた上下流域の交流の取り組み」を行政がバックアップすることもこれからは必要です。 (写真は植樹会場で「広瀬知事を囲む井上明夫夫妻」)
2007年05月19日
-
今年も「釜炒り茶」ができました。
うちではずっと以前から「釜炒り茶」を作っています。と言っても、せいぜいうちで消費するくらいの量ですが、この「釜炒り茶」という製茶方法は現在では貴重なもののようです。 日本茶には抹茶・玉露・煎茶・番茶・茎茶など様々な種類があります。これらのほとんどが、摘んだばかりの茶の葉をすぐに蒸して作る蒸し製のお茶で、総称して緑茶といわれています。 その一方で、茶葉を蒸すのではなく、釜で炒ってお茶に仕上げていくのが釜炒り茶です。釜炒り茶の歴史は、蒸し製の煎茶よりも古く、15世紀前後に中国から日本に伝わったといわれ、長く親しまれてきました。今では佐賀県、熊本県、宮崎県など九州を中心に西日本の一部の地域のみで作られているようです。 うちでは、お茶の時期になると、近所の「釜炒り茶づくりのベテラン」のおばさんをやとってきて、毎年、昔ながらの製法で作ります。 聞くところによると、日本の「釜炒り茶」の生産は風前の灯になっているそうなので、この技術はしっかりと残さなければなりません。
2007年05月17日
-
日田市議会5月臨時議会を開催。
選挙後初の臨時議会が15日から16日未明にかけて行われました。この議会は2年に1度のいわゆる「ポスト決め」の議会であり、毎回紛糾しますが、今回はこれまで以上に紛糾し、結局、朝10時から翌日の3時半ごろまでかかる長丁場となりました。 私はこれから2年間、「議会運営委員会」と「建設委員会」と「交通体系整備促進特別委員会」に所属することになりました。また、土地開発公社理事等の役職も勤めることになりました。 議会の中での役割を果たしながら、これからも市民の立場に立って活動していきたいと思います。
2007年05月16日
-
岳滅鬼山の山開き式、盛大に開催
小野地区源栄町の北山神社(標高430m)で岳滅鬼山(標高1037m)の山開き式が開催されました。この山開き式は源栄町の壮年会の主催で行われ、今年で17回目とのことです。 式には振興協議会長や自治会長・壮年会長など小野地区のそうそうたるメンバーが出席しており、午前11時から神事が執り行われました。私は小野地区の皆さんになにかとお世話になっているので、飛び入りで参加させてもらいました。 神事の後、野田高巳先生より「北山神社と岳滅鬼山」と題する講話がありました。 お話によると「かつて北山神社は『日田の北の玄関口』であった。それというのも、昭和25年ごろに『シャカ岳トンネル』ができるまでは、日田の人が北部九州へ行くときは、北山神社の横の道を通って歩いて行っていたからだ。北山神社は、この道沿いの民家が途切れる場所にあるので、日田から北のほうへ抜ける時に最後に通過する建物であった。日露戦争の頃の出征兵士は、北九州に招集されることが多かったので、日田の中心部の人も北山神社まで見送りにきて、ここで『武運長久』を祈って万歳をして送り出されていた。また、英彦山神社へ多くの人が参拝するとき立ち寄るので、日田の中で一番賑わう神社である時期もあった」そうです。 現在は、山の中にひっそりと佇む感のある神社ですが、いろいろなことに思いをはせながら眺めると、感慨深いものがあります。ここに限らず、日田の中にあるいろいろな歴史を語り継いで、記録して残していくことは大切なことです。
2007年05月13日
-
「春の交通安全運動」初日から日田市で飲酒事故相次ぐ!
今夜、交通安全協会日田支部大鶴分会の総会があり、私も来賓として出席してご挨拶をしましたが、総会に先立ち「交通法令講話」がありました。講師は日田警察署の渡辺交通課長でしたが、大忙しで大変な状況でした。 というのも全国ニュースでも報じられているとおり、昨夜日田市天ケ瀬町で「飲酒運転の10トントラックが自分が無銭飲食した食堂に体当たりした後、パトカーに追跡されながら50キロ逃げながら、途中で21台の車に衝突した事故」(リンクした記事は大分合同新聞)があったために渡辺課長はゆうべから一睡もしていないそうです。(暴走した運転手は宮崎県の人です。) しかも「交通法令講話」の直前に、日田市内でまた飲酒運転の当て逃げ事件があったとのことで、「講話」もそこそこに日田警察署にUターンして行かれました。 飲酒運転がこれほど問題になっている時に、なぜこのような事件がつづくのか理解に苦しみますが、結局いくら厳罰化しても意識の変わらない人が必ずいると言うことです。 また、無銭飲食された上にトラックに突っ込まれた食堂が「飲酒運転すると知って酒を飲ませた」と判断されるのだろうかと言うことも気になります。 いろいろむつかしい問題がありますが、飲酒運転の根絶のためには、子供の時からの教育も含めた粘り強い啓蒙活動しかありません。(写真は大分合同新聞のサイトより拝借した「暴走トラックが捕獲された場面」)
2007年05月11日
-
杉と桧を使用した木の照明「ひた灯り」
私も所属している異業種交流会である「技術・市場交流プラザ日田」の「県産木材の有効利用と商品開発研究グループ(13人)」は、このほど「杉と桧を使用した木の照明『ひた灯り』」の試作品を開発し発表しました。 写真のとおりのものですが、台座はスギ製で直径45センチ、その上に広がるフロアスタンドはヒノキ製の丸棒で高さは1mです。 グループではこれまで日田の主要産物であるスギ・ヒノキを使った新しい発想の商品開発に試行錯誤していましたが、生産効率やコスト面でなかなか開発にはいたりませんでした。 この『ひた灯り』は杉桧という素材特有のあたたかみや、「エコ」な雰囲気が特徴の製品です。今後、いろいろな機会に展示して、消費者の皆さんの反応を見ながら、販売にむけて準備をすすめていきます。 開発メンバーには木材関係者以外の人もいましたが、ふるさと日田の誇りである杉や桧を生かそうという情熱には変わらないものを感じました。
2007年05月10日
-
今年もお米作りの準備のシーズン本格化。
毎年恒例の「苗代用の種まき作業」を4軒共同でやりました。われわれの使っている「みのる式」は少々時代遅れの感があるので、ここ数年は毎年のように「新しい方法に変えようか」という話しがでます。 しかし、種をまいて苗代にすえるまで、みんなで役割分担をして作業すれば半日くらいで終わり、その後、昼食をかねた「打ち上げ」を4軒が持ち回りで会場を提供して行います。 その頃には、作業方法の改善の話などぜんぜん話題にならず(笑)、当分は今の方法が続きそうです。今年の打ち上げでのもっぱらの話題は「選挙」のことでした。 うちは水田は一反五畝(0.15ha)しか作っておらず、共同所有の田植え機以外の機械も持たず、外注作業も多いので、合理的に考えれば「米を買ったほうが良い」のかもしれませんが、やはり自分で作った米を食べるのは格別のものです。
2007年05月05日
-
今日は憲法記念日です。
最近、憲法改正についての議論がさかんになってきていますし、先ごろ憲法改正に関わる国民投票法案が可決されました。このことについて、新聞紙上等でいろいろなことが言われていますが、基本的に憲法は「絶対的な普遍の摂理」というわけではありませんし、現行憲法の「戦力を保持しない」という部分をまともに受け取ると、自衛隊は明らかに憲法違反となります。 しかし、現在の日本の周辺諸国のなかに「日本を狙った核兵器を搭載した弾道ミサイル」を配備する国がある状況を見るにつけ、日本が国土防衛のために必要な軍備をそなえることは、国として当たり前のことです。 このような理由から、私は憲法9条の「国際紛争の解決策としての軍事力の行使を否定する」という部分は支持するものの、「陸・海・空のいっさいの戦力を保持しない」と言う部分については改正の必要性をつよく感じます。 「憲法9条」を改正すると「戦争になる」かのような「短絡的な理由」から「憲法改正反対」を主張する人たちがいますが、現在の日本の憲法は、「終戦直後にGHQの将校たちが主導し、『日本が2度とアメリカに逆らわない』ようにするために、一週間で作成されたものをアメリカが日本に押し付けた憲法」ということを、日本人がもっと認識したうえでの、広い視野にたった国民的な「憲法改正」の論議を今後求めたいと思います。
2007年05月03日
-
新緑のまぶしいなか、中学生サッカー少年がんばる!
第26回日田市会長杯中学生サッカー大会が市内の「崔本グランド」と「陸上競技場」で開催されました。日田市内外の中学校やクラブチーム合計12チームが参加しました。好天にめぐまれて、芝の緑がまぶしいほどでした。 日田市中心部でこのような大会が開催されるときは、どうしても離れた2箇所の会場での開催となります。中津江村まで行けば「鯛生スポーツセンター」の立派なサッカー場がありますが、どちらかというと滞在型の「合宿所」的な色合いの濃い同センターは、ゴールデンウィークは宿泊しての利用者で早くから予約でいっぱいになります。 市内中心部にも子供たちが身近に利用できて、2面並んだサッカー場(総合球技場)の建設がのぞまれます。
2007年05月03日
全16件 (16件中 1-16件目)
1