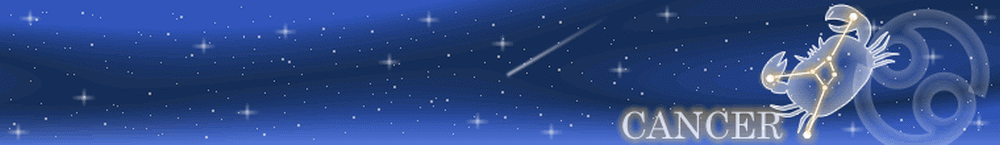2020年07月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-

至高の十大指揮者
本著はトスカニーニから、 21世紀初頭までに活躍した無数の指揮者のなかから10人を選び、 その略伝を記したものだ。 10人を選ぶのはかなり無謀で、誰もが納得する人選など不可能である。(p.6) これは、本著冒頭の「はじめに」で、著者の中川さんが述べた言葉。 そして、フルトヴェングラー、カラヤン、アバド、ラトル、トスカニーニ、ワルター、 バーンスタイン、ムラヴィンスキー、ミュンシュ、小澤の10人を選んだ経緯を、 中川さんは、これに続く文章で明らかにしている。 ***トスカニーニとワルターは、その指揮者人生に大戦が大きく影響を及ぼしている。これは、フルトヴェングラーやミュンシュも同様で、その最中の行動は、時の権力者や戦況により大きく左右された。20世紀になって生まれたムラヴィンスキーやカラヤンも、その中を生き抜いた。彼らに比べると、バーンスタインは、様々な点で趣きが異なる。デビューしたのは大戦中であったものの、彼の拠点はアメリカであり、ヨーロッパ・デビューと本格的な大活躍は戦後のこと。また、クラシックの枠を超えた作曲活動や教育者としての一面も際立っている。アバドやラトルは、私の中では印象が薄い。しかしながら、アバドが指揮者として大成していく様子は、それまでのパターンと違っていて、なかなか興味深いものだった。そして、この10人の中で、ラトルのものだけ、私はCDを1枚も所有していない。この10人の中で、私が実演に接したことがあるのは、小澤征爾ただ一人。ボストン響とのマーラーは、圧巻の演奏で、客席の熱気は凄まじかった。ラトルは、いつかその姿を直に見ることが出来るだろうか。演奏会に足を運べる日が戻ってくることを心から願っています。
2020.07.26
コメント(0)
-

使いみちのない風景
村上さんと写真家・稲越さんによるフォトエッセイ集。 1994年に出版された『使いみちのない風景』に、 「ドゥマゴ通信」No.13に掲載された「ギリシャの島の達人カフェ」と 「anan」1984年4月27日号に掲載された「猫との旅」を加え、 1998年に文庫化されたもの。 *** 一般的に言って、僕らは通り過ぎることを前提として旅行をしている。 あるいは僕らは通り過ぎることを目的として旅行をしている。 僕らは定着という静止的行為あるいは状況から 一時的にせよ離れるために旅行に出ると言ってもいいだろう。 でもそこには定着を打ち壊してしまうような崩壊はほとんどない。 もちろんまったくないというわけではないけれど、 その可能性はきわめて微小なものである。(p.28)村上さんは、自身の「略歴」に「趣味は旅行をすること」と書かれていたことに深く考え込んでしまい、「趣味は定期的な引っ越し」と書かれるべきだと思い至ります。「住み移り」とう行為と「旅行」という行為は、別物だと。 でも「住み移り」の場合、我々を囲んでいるあらゆる風景は、 我々の存在そのものにもっと直接的なコミットメントを持つようになる。 それは過ぎ去っていく束の間の風景ではない。 我々はそれらの風景と現実的に折り合いをつけなくてはならない。 それらの風景に対して、我々はそれなりの判断を下さなくてはならない。 我々は何を取り、何を捨てるか、何を受け入れ、何を受け入れないか、 というようなことをきちんと決断しなくてはならない。 好むと好まざるとにかかわらず、 そこにはある種の現実的責任のようなものが生じることになる。(p.37)なるほど、と思いました。今、コロナ禍の中で、こんなにも息苦しいのは、現実的責任を生じる場所に、ずっと留まり続けることを強いられ続け、静止的行為あるいは状況から、一時的に離れることすら許してはもらえない空気で、自分の身の回りが覆いつくされているからなのだと。
2020.07.26
コメント(0)
-

村上春樹、河合隼雄に会いにいく
村上さんと河合隼雄さんの対談集。 対談は1995年11月に2夜に渡り京都で行われましたが、 その様子は、村上さん自身が本著「前書き」に書いてくれています。 『ねじまき鳥クロニクル』を執筆している時期の対談です。 *** だから、学生運動のころに、ぼくがよく学生を冷かしていたのは、 きみたちは新しいことをしているように見えるけれども、体質がものすごく古い、 グループのつくり方がものすごく古い、ということですね。 あれはおもしろいですね、みんなが集まるというときに、 ちょっとサボっていると、おまえは付き合いが悪いとか。 つまり個人の自由を許さなくなるんですよ。 全体にベタベタにコミットしているやつが立派なやつで、 自分の個人のアイディアでなんかしようとするやつは、 それは異端になってしまうでしょう。 ところが、その点、欧米のコミットする人は、個人としてコミットしますからね。 来るときは来る、来ないときは来ないというふうにできるんですよ。(p.23)これは、河合さんの発言。25年も前の言葉なのですが、現在もあんまり変わってない…… 日本人の場合は、もう泣いて不満を言うばっかりの人がいるんです。 なぜわたしだけがこんな不幸なのか、と言っていてね。 結局自分で乗り越えるしかない、というふうになかなかならないのです。 だって、責任はみんなにあるわけだから。 「わたしの不幸をなんとかしてちょうだい」という格好になるから、 なかなか治りにくいのですね。(p.31)これも、河合さんの発言。欧米人の場合は、あくまでも個人のレスポンシビリティーなのに、日本は集団というか、場のレスポンシビリティーになってしまうという指摘。これも、あんまり変わってないように感じますね。
2020.07.26
コメント(0)
-

雨天炎天
1990年に刊行、そして翌年には文庫化された作品。 村上さん、写真家の村松さん、編集のO君の3人で訪れたギリシャと、 村上さんと写真家の村松さんの2人で訪れたトルコについて記されています。 30年の月日の流れ、社会の変化、そして異文化世界の在り様に圧倒されます。 ***まず最初はギリシア編。副題は「アトス-神様のリアル・ワールド」で、ウラノポリからアトス半島に入り、ギリシャ正教における修道の中心地・アトス山を、修道院に泊まりながら周回。全4泊5日の行程ですが、道も天候も食事もハードな状況の連続。 でも結局のところ、その臭さがギリシャ正教の良さである。持ち味である。 カソリックの寺院にも同じような仕掛けはあるけれど、これほどの凄まじさはない。 ヴェネチアのトルチェッロ島で見た受難の絵なんて、 イタリアでは残酷な地獄絵として有名だが、これにくらべたら準天国みたいに見える。 いずれにせよこういう絵を見ていると、 僕なんかまだ受難が足りないのかなという風にも思う。 文芸批評なんてものはとても受難とは呼べないだろうと思う。(p.76)ギリシャ編で、私が一番印象に残っているのがこの部分。ギリシャ正教の凄さ、激しさを感じると共に、当時、村上さんが日本の文壇において、色々と苦しい状況にあったのだと、改めて気付かされました。 そして続くトルコ編。副題は「チャイと兵隊と羊-21日間トルコ一周」で、イスタンブールから黒海沿岸、そしてシリア国境近くのディヤルバクルに至る、全21日間の行程。四駆車での旅は、兵隊と羊と埃でいっぱい、そして、常に危険と隣り合わせ。 とにかくそんな騒動のどまんなかに僕らは - よくわけがわからないままに - 入ってしまったわけである。 今になってみると「まったく何がノー・プロブレムだ、何が平和そのものだ!」 とあきれるわけだが……(p.177)この後に続くエピソードは、思わず背筋が寒くなるようなもの。まかり間違えば、本著はもちろん、それ以降の数々の名作が、この世に生み出されることが無くなってしまっていたのかもしれない……でも、今も世界のあちこちで、こういう状況が続いているのですね。
2020.07.19
コメント(0)
-

ギフト±(19)
加藤はリュウに、自分の腹の奥に仕込んだC4爆弾の起爆装置を取り出させる。 そして、リュウに船外へ出るよう促すと、自ら起爆装置のスイッチを押した。 秋光正が自分に近づいてきた真の目的を知らされ、激しく動揺した気持ちのまま。 一方、リュウは曹国良の元に向かい、炎上する船上から二人共海に放り出される。 しかし、そこで死亡したのは、国良ではなく弟の暁東だった。東京湾に入港していたコンテナ船が炎上したことは、広く世間の知るところとなる。ところが、曹や加藤の名前について報道されることは一切なかった。事件解明に向けて、廣瀬は桜田に、英琢磨を日本に呼び戻すと告げる。一方、崇のもとにやって来た愛怜は、解体すべき対象・クジラを自ら用意し、その男を解体する様子を、崇と環に披露する。それを見て、自ら行ってきた行為に、強く疑問を感じ始める環。そんな環に「お前はあいつとは違う」と、崇は声をかける。愛怜は、崇の子供を身籠った梨世に圧力をかけると共に、環に対しても強い言葉を投げかける。 ”もう解体がつらい” - そう思っているんじゃない…? だとしたら かなり危ないかもしれない 今度解体されるのは 環ちゃんかもしれないよ…? ***上記のお話のほか、少年・曹暁東が、兄の国良を救ったエピソードや愛怜に解体された佐川雄大のエピソードも、しっかりと描かれています。また、愛怜と崇の「解体」についての言葉のやり取りや、愛怜の解体中の独白シーンも、今巻の核をなす部分です。しばらく、愛怜がお話を動かしていく存在になりそうですね。
2020.07.12
コメント(0)
-

もし僕らのことばがウィスキーであったなら
村上さんご夫妻が2人で2週間ほどかけて旅行し、 夫が文章を、妻が写真を担当して出来上がったコンパクトな一冊。 今回のこのスコットランドとアイルランドの旅のテーマはウィスキーだった。 スコットランドのアイラ島に行って、 その名高いシングル・モルト・ウィスキーを心ゆくまで賞味し、 それからアイルランドに行って、あちこちの町や村をまわりながら アイリッシュ・ウィスキーを楽しもうと。(p.10)朝ドラ『マッサン』の主人公・政春がウイスキー作りのため留学したのがスコットランド。政春はそこでエリーと出会い、その後、結婚することになりました。そのモデルとなったリタさんの出身地が、アイルランドのグラスゴー。アイラ島は、その遥か西方にあります。そのアイラ島から南方に位置するのがアイルランド。北アイルランドはイギリス領ですが、それ以外の場所は、アイルランド共和国という別の独立国。そのあたりの様子については、本著では特に触れられていません。『やがて哀しき外国語』とは、全く趣の異なるエッセイ。あくまでも、主役はウィスキーです。
2020.07.05
コメント(0)
-

やがて哀しき外国語
村上さんが、1991年初めから約2年半、 アメリカのプリンストンに住んでいた時に書かれたエッセイ。 『本』の1992年8月号から1993年10月号に連載され、 1994年3月に単行本として発行、1997年2月に文庫化されたものです。 村上さん自身が、「文庫版のための前書き」に記されているように、 本著に描かれている日米双方の状況や関係、立ち位置と、 1997年時点でのそれとでは、大きな変化がありました。 その後、さらに20年余を経た現在のそれは、もう言わずもがなです。村上さんが記すアメリカでの生活からは、実に様々な人間模様が伝わってきます。それは、アメリカの持つ本質的なものもあれば、その当時の時代を強く反映したものもあります。日本とはもちろん、ヨーロッパとも異なるアメリカらしさが、そこからは感じられました。私が、本著の中で最も興味深かったのは、吉行淳之介さんの『樹々は緑か』についての記述。村上さんはセミナーのため、この作品を英訳版で初めて読むことになり、試しに、それを村上さんが、日本語に再翻訳したというエピソード。本著では、村上さんが再翻訳した文章と共に、吉行さんの原文が掲載されているのですが、その違いに愕然としました。翻訳のプロフェッショナルである村上さんの文章は、もちろん素晴らしかったのですが、その後目にした吉行さんの文章には、日本語の美しさというものが滲みだしていました。この部分を読むだけでも、本著を手にする価値があると思います。ぜひ、ご一読を。
2020.07.05
コメント(0)
-

やっぱり食べに行こう。
毎日新聞「日曜くらぶ」に、 2015年7月5日から2017年7月30日まで連載されたものを、 テーマ別に並び替え、一冊にまとめたもの。 その数80という、圧倒的満腹感を味わえます。 メニューは、「朝ごはん」が16、「麺」が10、「シーフード・肉」が16、 「デザート」は10で、「アートとグルメ」が14、「何度でも通いたい店」は12、 そして、「欠かせない一品」が28とバラエティ豊か。 よくぞこれだけ取り揃えられたものだと、感心させられます。『暗幕のゲルニカ』や『楽園のカンヴァス』といった作品を書くため、ヨーロッパやアメリカ各地を取材して回った際の出来事や、旅友・御八家千鈴さんとの「ぽよグル(ぽよよ~んとグルメを楽しむ旅)」で、47都道府県を制覇した際のエピソード等が、次から次へと出てきます。グルメの話題だけでなく、マハさんの文筆活動やアートに対する姿勢、これまで関わった人や場所、作家になるまでの経緯等も記されており、マハさん自身についての理解も深めることが出来ました。マハさんのファンにとっては、たまらない一冊ですね。
2020.07.04
コメント(0)
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- 悪役聖神官ですが、王太子と子育て恋…
- (2024-10-04 21:52:45)
-
-
-

- 今日どんな本をよみましたか?
- 『藍を継ぐ海』~伊与原 新
- (2024-11-27 12:00:13)
-
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- ちょっと気味の悪い話をしますが最近…
- (2024-11-25 12:21:24)
-