2009年03月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

4月からのサンク・オ・ピエ
4月は恒例となっているパルマの生ハム登場です。レギュラーメニューでもチョイスできますよ!本日入荷予定です。手切りの生ハムは美味いですよ! 魚料理は、イカ墨の焼きリゾット仕立て。イカ墨リゾットにチーズを振りかけ、バーナーで焼きつけます。白身魚のポワレをのせて仕上げます。今回は甘鯛。 仕上がりはこんな感じ。4月の魚料理は、イカ墨で行こうと思ってます。 それから、4月5月のフォアグラ・マッドネスのコースは、ハンガリー産のガチョウのフォアグラ料理です。詳しくはホームページをご覧ください。
Mar 31, 2009
-

さかもとこーひーとパウンドケーキ
うちの店の常連さんであり、私がリスペクトするこーひー屋さん“さかもとこーひー”のさかもとさんが最近始めた「さかもとこーひーの四季を味わう会」。先週の土曜日が、第二回目でした。さかもとさんには、いつもおいしいこーひーをいただいているので、何かお返しを、、、と考えていたので、、、さかもとこーひーに合わせて、フランボワーズとドライクランベリー風味のパウンドケーキを作って送り、召し上がっていただきました。詳しくは、さかもとさんのブログをご覧ください。 私のイメージ通りうまくさかもとこーひーに合ってくれたようで、良かったです。私にとってはさかもとさんのこーひーは、ワインと同じ感覚なんですね。普通のコーヒーなら、あまり深くは考えないんですが、上品なブルゴーニュワインを思わせるようなさかもとこーひーの独特なトーンに合わせるには、ある程度の酸味や果実系それも赤いフルーツ系のフレーバーをリッチにバターをきかせたパウンド生地と合わせれば、、、と思い作ったものです。 桜も咲いて、就職や入学進学の季節ですね。いろいろな道に進む方がいるんでしょうが、、、料理人の私、友人の音楽家クリヤマコト、それからさかもとこーひーのさかもとさん、共通点は独学でした。まあ、それぞれかなり特殊な職業と言えるのかもしれませんね。 私はよくお客さんにフランスのどこで修業したのか?とか師匠は誰ですか?などと訊かれることがありますが、、、「いやぁ、私は独学でフランスに食べに行ったことはありますが、フランス料理屋で修業したことはありません。」と答えると怪訝な顔をされることがあります。 私たちのような職人仕事は、仕事に対する誠意とある程度の自己分析能力があれば、一人でもやっていけると思っています。最も形になるにはなかなか時間がかかりますけどね、、、。 私が一番力を入れて取り組んでいるのが、素材への火の通し加減。つまり肉や魚の焼き加減ですね。さかもとさんはコーヒーの焙煎家ですから、豆の焼き加減が命。さかもとさんと話をするといつも“火の使い方”の話になります。お互い相手にする物が違うとはいえ、熱をコントロールして思い通りに仕事を進めるという点では共通することが多く、いつも普通の人にはわからないような専門的な話になってしまいます。 だから、ジャンルは違うといってもさかもとさんがあのようなこーひーを作るためにどれだけ神経を使っているかが私にはよくわかるし、さかもとさんも私の料理をかなり深く味わってくれると思っています。 クリヤマコトは、ピアニストとしてすごい技術を持っていますが、それは長年の練習に支えられていることは言うまでもありません。彼はたまに「どうやって練習したらクリヤさんみたいにうまく弾けるようになるんですか?」なんて訊かれることがあるようですが、そんな方法があったらおれが知りたいよと笑うそうですが、、、職人仕事とはそういったもので、やっていることは実にシンプルなんです。ピアノは上手に弾けばよいのだし、コーヒー豆は上手に焼けばよいのだし、肉も上手に焼くだけのことです。言葉にすれば本当にそれだけのことですよ。 どうすればそれらが上手にできるか?努力しかないわけです。ただ、無駄な努力はできればしたくないので、色々な知識が必要になりますね。音楽なら音楽理論がありますし、料理なら偉大な先人たちが残した、レシピや料理研究の本があり、私はよく知りませんがコーヒーの焙煎にもきっと専門書が色々あると思います。それと、自分のことも含めて冷静に観察して判断する能力も必要ですね。ミュージシャンなんかよくありがちですが、自分が気持よくなるためだけに音楽をやっている輩がいます。それではプロにはなれません。独りよがりの仕事では、職人とはいえないと思います。趣味としか呼べませんね。作って売れて何ぼの職人ですからね、、。 これは、独学だろうが誰かに付いて学ぼうが同じことです。自身が努力しなければ誰かが一人前にしてくれるなんてことはあり得ません。私は結構教え魔で、同業者にも包み隠さず何でも教えてしまうのですが、その裏にはレシピだけで料理は作れるものではないということがあるんです。たとえば、音楽の楽譜。楽器が弾ける人に楽譜を渡せば、何らかの演奏ができるでしょう。でも、それで人を感動させるような演奏ができる人はなかなかいないでしょう? 家庭料理のレシピなど、大匙小匙で何杯などというのをその通りに作ったところで、まず美味しい料理にはならないですね。下手をすると食べられないことすらあると思う。料理というのは、調味料を混ぜ合わせることではなく、味見をして感じて、足りない味を補うというのが味付けなんですね。そういった作業を真剣に日々繰り返していくと、だんだん熟練してあまり頻繁に味見をしなくても味が決められるようになるわけです。日々修業ですね。 それから大切なのが、イメージですね。たとえばきれいな風景や面白い映画、素敵な音楽などを体験してそういうイメージを自分が作る料理なり音楽なりコーヒー豆のブレンドなりにいかすんですね。たとえば雨上がりに東京湾から富士山が見えた時にその清々しさを音楽や料理やコーヒーで表現することは可能だと思うんです。またそういったイメージを具現化する能力がプロとして必要だと思います。それから科学的な知識も必要ですね。料理なら、肉のたんぱく質の凝固する温度とか、バターの融点とか、チョコレートの分子構造を安定させるための温度操作などですね。 文学的な部分と科学的な部分。両方のバランスが大切ですね。
Mar 30, 2009
-
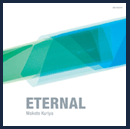
クリヤ・マコト公認!CD直売所は、サンク・オ・ピエ
少しさかのぼりますが、、、3月15日の日曜日に親友のミュージシャン、クリヤ・マコトが自らCDを持ってきてくれた。 友達の特権で、新しいアルバムができるといつも進呈してくれるのだが、貰うばかりで恐縮なので、お店でCDを売ることにしたのは、かなり前からのこと。プロモーションを兼ねて、うちの店のランチタイムのBGMはクリヤ・マコトと決めている。 特にETERNALというアルバムはクリヤ・マコトのホームページか彼のライヴ会場などでしか買えない特殊なアルバムな上に、数量限定プレス版なので残りわずからしい。そして、このアルバムが常時現物販売されているのは、サンク・オ・ピエだけなんです。 しかも、本人が直接持参する産直品!おまけにマコトの指紋も付いてます!(鑑識に回してみよう!?) クリヤ・マコトは、留学していたアメリカで腕を磨いてきたミュージシャンだが、彼がアメリカで学んでいたのは、言語学。アメリカで修業するジャズ系のミュージシャンの多くが、ボストンのバークリー音楽院(あの渡辺貞夫も通った学校)で学ぶ人が多いのだが、マコトはウエストヴァージニア大学で言語学を勉強しながら、隣町のピッツバーグの地元ジャズシーンで活動していたわけ。言語学だってきちっと修め、ちゃんとマスターの資格も取っているインテリミュージシャンなのだ。 しかも、ピッツバーグ大学では、ジャズの音楽史の講師を務めアメリカ人にジャズを教えていた!というくらいで英語もネィティヴだし、ジャズ史やジャズ音楽理論などにも精通しているという凄いやつなのだ。 最近気づいたことなのだが、私とマコトの共通点はお互い独学だということ。マコトも幼いころのピアノのレッスンを除けば、正式な音楽教育を受けたことはないし、私も調理師学校には行っていないし、フランス料理屋で誰かの下について修行したこともない。 彼は音楽を聴くことと演奏することで自分を高め、私は料理を食べることと作ることで自分を鍛えてきた。その他に大事なのが読むこと。マコトは音楽関係の文献は勿論、数多くの楽譜を読みこむことだったろうし、私の場合はフレンチだけでも2万種位はレシピを読んだことや、辻静雄氏の著書などを参考に料理の歴史なども研究した。 その裏には、技術や知識で同業者にバカにされたくないという気概もあったかもしれない。 マコトがまだあまり売れてないころ、家に籠って練習しているというので、様子を見に行ったことがあるが、「ドレミファソラシドやドミソがちゃんときれいに弾けるように練習しなおしているんだ。」と、言っていたのを思い出す。そんな彼も「近頃ゆっくり練習する暇がない」くらい忙しい! そんなわけで、産直のクリヤ・マコトのCD売ってますよ!!
Mar 27, 2009
-

アマダイのポワレ、イカ墨風味
私の作るイカ墨ソースは、主成分がほとんどトマトソース。イカ墨料理というとイタリアンというイメージだろうが、スペイン料理でもかなり使われる。 私が使っているイカ墨もスペイン産のスミイカの墨袋だけを集めて冷凍にしたもので、業務用に出回っているものだ。 ニンニクと鷹の爪にオリーヴオイルだけでシンプルなトマトソースを作る。この状態でソース・プロヴァンサルといいます。南仏風トマトソースですね。それに対して一割弱程度のイカ墨を入れてしばらく煮込みます。 色と旨味が出てきたら、ミキサーにかけて漉して仕上げ、最後のパプリカのパウダーをたっぷり加えます。このパプリカが結構ポイントで、イカ墨に色を消されて全く見えなくなってしまうが、味がとてもいい感じになる。 この味付けはスペインとフランス国境あたりのバスク地方あたりのやり方だ。イカ墨はアンチョビ並みに魚介系の旨味を持っているから、魚料理のソースにもぴったりだ。 もちろんこれで作るパスタやリゾットも脳天直撃的な旨さですよ!
Mar 25, 2009
-

クラシックフレンチを見直そう!3月4月は、プーレ・ロティ!
焼く準備が整ったPoulet(若鶏)。フランス西南部ランド地方の農家製のプーレ・ジョーヌ(黄色地鶏)のラベル・ルージュ(フランス国家指定の優良農産物)の鶏の丸焼きですね。 詳しくは、ホームページをご覧ください。 この鶏の丸焼きは、オーブンを使わずに鍋の上で焼いていきます。まずは、背中から、、 そのあとは、モモ肉を中心に火を入れていきます。 もう一度背中を焼いたり、、 モモを焼いたり、、 胸肉は短時間でさっと火を通します。最後の仕上げですね。 このようにお尻をあげて、胸を下にした状態で暖かいところで休ませます。最低でも焼いた時間くらいは休ませます。つまり、50分ほど焼いて、50分くらい休ませます。 さばきます。モモ肉が2枚と胸肉が2枚。しっとり焼けているでしょう! 切り分けて盛り付けます。 カマルグ産の塩を振り、上質なオリーヴオイルと焼き汁と胡椒を挽きかけて出来上がり! こんな鶏、まず食べられませんよ!詳しくは、ホームページをご覧ください。ご予約限定メニューです。
Mar 20, 2009
-

春色のポタージュと新作魚料理
Potage Saint German. ポタージュ・サン・ジェルマン、グリーンピースのポタージュです。 これが、下手に作るとまずいスープの代表格といえるほどで、煮込みすぎて色あせたようなやつは御免こうむりたいもの。新玉ねぎをバターで炒め、小麦粉を少し入れて馴染ませる。そこに生のグリーンピースを入れて薄いチキンブイヨンをひたひたに加えて強火で沸かす。 火が通ったら、すかさずミキサーにかけ、シノワで漉して、スープを器ごと氷水につけて冷やして色止めをする。とにかく早く冷やしてしまうのが肝心。ここでもたもたすると、色が悪くなるばかりか、せっかくの風味も飛んでしまうのだ。 うちのポタージュ・サンジェルマンは毎年大評判で、これができたら連絡くださいというお客様もいるくらいだ。 アマダイのヴァプール、グリーンタプナードとゆずオイル風味。 アマダイはは塩をして蒸し器で火を通す。グリーンオリーヴとアンチョビとケーパーにパセリを加えてペースト状にしたグリーンタプナードを添え、ゆずの皮を漬け込んだエクストラヴァージンオリーヴオイルを仕上げにかける。 今日的スタイルのソースらしいソースのない魚料理ですね。 アマダイは、白身で淡白ながら独特のしっかりした風味を持っている魚なので、このようなシンプルな味付けが生きてくる。さわやかな柑橘系の香りがするソービニヨン・ブランの白ワインと合わせたら楽しそうだ。
Mar 18, 2009
-

牛スネ肉のマルサラ酒煮込み
牛スネ肉のマルサラ酒煮込み。まあ、ビーフシチューの一種ですね。 マルサラ酒はイタリアの酒精強化ワインで、やや甘口。カラメル的な香ばしさや蜂蜜のような丸みがあり、茶色の肉系のソースにはとても合います。フランス料理では、たいていマデラ酒を使うのだが、マデラ酒よりはさっぱりしているので、軽く仕上げるにはマルサラ酒も捨てがたいものだ。 牛スネ肉は旨味とコラーゲンが豊富だから煮込み料理には良い部位。というか肉質が固いので、焼いて食べるのにはむかない部位だ。脂はないのだが、コラーゲンが多い分、煮込んでもパサパサしないのが良い。 ナイフを使わなくてもスプーンだけで肉がほぐれるほどに煮込むのだが、ばらばらにに崩れては元も子もない。その辺の加減がプロの腕の見せ所ですね。 後、10人前くらいあります。本日のスペシャルメインディッシュでやってます。
Mar 16, 2009
-

8周年記念コース
お米でつないである蕪のポタージュです。米でとろみをつけるという技法はとてもクラシックでもう忘れされている感があるが、うまく使うととても上品なポタージュができる。 さて、8周年コースが大好評です。 毎年のサンク・オ・ピエの二大メニューが、この開店記念のコースとクリスマスディナーなんです。クリスマスディナーの時期にはトリュフがあるので、クリスマスはトリュフの香りを中心にメニューを組みます。開店記念コースは、2月21の開店記念日から毎年3月末までのコースですが、クリスマスが終わったらもう考え始めます。 ここ数年の課題があって、まずはクラシックなメニューで普段なかなかできないものを一品入れること。それから、三ツ星シェフまたは有名店のコピー料理を一品入れることと、かなりユニークなデザートを考えるという3点。 まずはクラシックなメニューとして、オマールのビスク。 スープのために活のオマール海老を二人で一尾使ってしまうこのメニューは、原価がかかりすぎるのでそうそうできるものではない。オマール海老は高いので、もしこれをアラカルトで出したら、一杯¥3000は超えてしまうことになる。スープ一杯が¥3000ではなかなか売れないだろうから、今時こんなゴージャスなスープは作られることはほとんどないだろう。だが、やはりビスクというスープは、コンソメと並ぶフランス料理のスープの最高峰であることは間違いないのだから、こういう機会にぜひ味わってもらいたいものだ。 三ツ星のコピー料理。今回は20世紀最高のシェフと言われるジョエル・ロブション氏のレシピによるもの。レシピは彼の著書から頂いたものです。ロブション氏のレシピは、とても正確で嘘偽りなく、その料理のポイントやコツなども惜しげなく伝えてくれる大変ありがたいもの。 ただ、レシピというものは、当たり前だが料理そのものではない。音楽における楽譜のようなもので、レシピがあれば料理ができるというわけではないのだ。私の場合、他人のレシピで料理を作るときは、まず何回も読みこんでその料理の味わいのポイントや使われた調味料や食材の意味や役割などが、自分なりに完全に把握できたと感じるまでは絶対に作らない。 つまり作者がどこをどのように美味しく感じてもらいたくて作るのか?その焦点が見えなければ、作る意味がないと思っている。 この料理は、半分ピュレにしたレンズ豆と丸のままのレンズ豆をクリームで仕上げ、蒸して柔らかくなったフォアグラの滑らかな食感との渾然一体となる食感がポイントになる。さらにほんのりかおるスパイスのバランスもポイント。その香りが、アルザスのゲヴェルツトラミネールというワインと見事にマリアージュするのだ。 作る前に考え抜いて、味わいや合わせるワインまで思いつくくらいになったところで初めて試作する。たいていは、一発で決まることが多い。 デザートには、フォアグラのプリン!これならユニークでしょ?ただし、ユニークなだけで食べて美味くなければ意味がないのですが、自分で食べても美味しいと思うし、評判も良いですよ。 詳しくはホームページをご覧ください。
Mar 14, 2009
-

牛肉のブランケット
牛肉のブランケット。ブランケットといっても、毛布じゃないですよ。Blanc(白い)という言葉からきている料理で、クリーム仕立ての煮込みのことです。 まず、肉を水かブイヨンで煮込みます。柔らかくなるまで肉の種類や部位によりますが、まあ2~3時間くらいでしょうか、、、。 できた、煮汁と肉を分け、煮汁はリエします。リエというのはとろみをつけること。つまりルーとかコーンスターチなどでとろみをつけます。私の場合は、コーンスターチを使います。 煮汁を煮詰め、生クリームとバターで仕上げます。
Mar 8, 2009
-

Petit sale aux rentille verte du Puy塩豚&ピュイ産レンズ豆
携帯で撮ったので、画像がいまひとつですが、、、。フランスの家庭料理またはビストロの定番、Petit sale aux rentille 塩豚とレンズ豆の煮込み の私版。塩豚は煮込まずにグリエにしてあります。 フランスの肉屋さんには、塩豚が普通に売っています。demi selといってうす塩のものを買ってきて(うす塩といってもかなりしょっぱいのだが)2~3時間水で塩抜きをしてから、2~3時間水で煮込んで、肉が柔らかくなってきたらレンズ豆を加えて、30分ほど煮込んだら出来上がりというシンプルなもので、アツアツのところをハフハフ食べるわけ。まあ、フランス人なら誰でも知っている料理だ。 普通は山盛り作って、冷えた白ワインかビールでも片手にメインディッシュとしてたべるのだが、、、 私の場合は、レンズ豆を30分ほど茹で、バルサミコと鶏のブイヨンで味付けして、少し甘すっぱい温製の豆サラダ的に仕上げ、塩漬けにしたスペインのデュロック豚の肩ロースをグリエにして添え、仕上げに特上のオリーヴオイルを回しかけてある。 軽い味わいで前菜に使おうということで考えたもの。今週来週のお勧め前菜でやってます。
Mar 7, 2009
-

大好評!8周年記念コース
8周年記念コースが、おかげさまで大好評です。作るのに夢中で、なかなか写真が撮れなかったのですが、やっと全品画像がそろいました。 まずは、お楽しみアミューズ。この日は、魚のテリーヌとイノシシとフォアグラのリエットと自家製ピクルスを一口づつ。 前菜は、自家製の冷燻のサーモンとホタテ。冷燻というのは、30℃以下くらいの冷たい煙で燻製にすること。温度を上げないので、食感はしっとり。上質な生ハムを食べるような感じですね。 続く温前菜は、蒸しフォアグラのレンズ豆のクリーム添え。これは20世紀最高のシェフと言われたジョエル・ロブションのレシピによるもの。このレンズ豆は、AOCというフランスの食品(ワイン、チーズ、野菜、畜産品など)に関する最高ランクの法律で指定された唯一の豆で、おそらく値段も世界一だろう。とても複雑で独特の風味があり、肉類との相性が良い。そのレンズ豆を一部ピュレにしたものと、豆を合わせクリームで仕上げる。豆を下茹でする時にクローブやアニスなどを使っているので、一層甘い香りが加わって蒸した柔らかいフォアグラと渾然一体となってとても美味しい。さらにアルザスのゲヴェルツトラミネールを合わせれば、その甘い香りとまろやかな口当たりがフォアグラと溶け合って、、、。 次は、オマール海老のビスク。二人で一尾のオマールを尻尾の身以外を細かく砕いてだしをとり、海老味噌も溶かしこんで濃厚なクリームスープにしたもの。一尾のオマールを隅から隅まで味わっていただくというものだ。スープというよりソースに近い感じと言えるかもしれない。 そしてメインは、低温で時間をかけしっとりと焼き上げたイベリコ豚ベジョータの背肉のロースト。究極の焼きあがりを目指して、日々精進しています。さすがに世界最高の豚と言われるイベリコのベジョータ。きめ細かさ、上質な脂の旨さがとても豚肉とは思えないほど上品だ。 デザートその一は、イチゴのスープ仕立てリモンチェロ風味のレモンのソルべ添え。スープ本体は、南仏産の完熟イチゴのピュレを使い、千葉県産の生イチゴを散らし、イタリアはカプリ島産のレモンリキュール“リモンチェロ”で香りをつけた自宅の庭のレモンを使ったシャーベットを浮かべたもの。次のデザートのためにさっぱりとしていただく。 そして最後は、バニラとカラメル風味のフォアグラプリンと生チョコ。砂糖をカラメル化させ、マデラ酒を加えて煮詰めてカラメルソースを作りプリン型に流す、卵と牛乳と生クリームにフォアグラとバニラを合わせたプリン生地を入れてオーブンで蒸し焼きにする。フォアグラが一種生クリームのように働いて、プリンに独特のコクを与えるし、また思いのほかバニラとの相性も良く、かなりユニークなデザートに仕上がった。熟成したポルト酒やマデラ酒またはマラガ酒、あるいはバニュルスなども合うだろう。 今月いっぱいまでやっています。ご予約はホームページからお願いします。
Mar 6, 2009
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
-

- 簡単レシピ
- いつもの卵焼きに「ちょい足し」アレ…
- (2025-11-22 17:00:05)
-
-
-

- 楽天レシピ
- 豚ロース肉の低温ロースト ローズマ…
- (2025-11-25 23:50:04)
-
-
-

- 美味しいお店を教えて!
- 昔ながらの?焼き餃子とスープに浮か…
- (2025-11-25 15:00:07)
-







