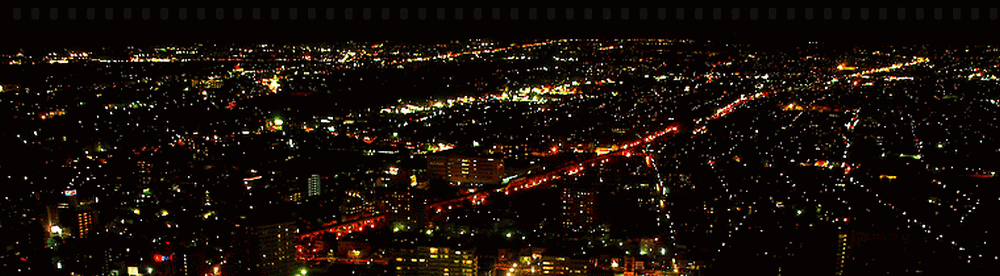2007年10月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-

西郷南洲翁生誕180年記(11) by 北洲
3日目(9月24日)はこれまでとは異なり幾分、緊張感を伴って起床しました。この日は西郷先生の命日なのです。毎年、墓参へ行く午前中は観光気分は吹き飛びます。本日も晴天に恵まれたようです。カ-テンを開けると明るい太陽光がまぶしい。前日はホテルへ戻った時間が遅かったため体はまだ起きてはいませんでした。そのため早速、“さつま乃湯”へ行くことにしました。浴衣を脱ぎ大浴場に浸かり体を温めました。数分間の入浴後、桜島と錦江湾が眼前に広がる露天風呂へ。太陽の角度が低いせいか、やや霞んだ桜島を眺めながらの入浴は格別です。とはいえすぐに130年前のこの時間帯を思い起こしました。つまりまさにこの時間は薩摩軍が政府軍により壊滅させられ多くの死骸がこの城山に横たわっており、悲惨な様相を呈していました。130年前の早朝は大雨が降ったそうです。その光景を想像しつつ私は露天風呂の中で手を合わせました。その後、前日よりも丁寧に体を洗い脱衣場で浴衣に着替え少し休憩しました。当日の新聞朝刊がテ-ブルに置かれていましたので手に取ると自民党の新総裁が決定したとの記事が一面に大きく掲載されていました。予想以上に麻生前幹事長に票が集まり少しは安堵しました。自民党にも少しだけ良心が残っていました。鹿児島県選出の国会議員は全て福田さんに投票していたのが心に引っかかりました。朝食は早めに済ませました。9時少し過ぎにホテルを出発しました。昨年は10時過ぎにホテルを出た上に途中、寄り道をしたため式典(法事?)に遅れてしまったのです。そのため今年はわき目を振らず目的地の南洲神社へ行く予定でした。写真は当日朝の城山観光ホテルです。しかし時間的な余裕があったせいか昨夜訪れた“西郷洞窟跡”横のお土産屋さんに立ち寄ってしまいました。こちらの店名は“せごどん”さんといいます。まさに“さいごうさん”という店名です。こちらには毎年必ず立ち寄っているので習性になっているのでしょう。時間も無いので店員さんとの会話もそこそこに買い物を早々に済ませました。店を出て、昨夜、暫くの時間たたずんでいた“西郷洞窟跡”に目をやりますと10名程の観光客らしき一行がおりました。“せごどん”さんの店員さんによりますと昨日(前日)の昼間は例年より遥かに多くの人が来ていたそうでTV局の取材も行われていたそうです。更に前方を見ましたら、初老の男性が笛を吹いておりました。興味を示した私はその男性の側まで接近しました。朝とはいえ既に暑さを感じる中で、この男性は洞窟に向かい、一心不乱に笛を吹いておりました。それは130年間前に亡くなった西郷先生を始めとする薩摩軍兵士に対する鎮魂歌ともいうべき物寂しい音色でした。本日の命日のためにわざわざ笛を吹かれていたのでしょう。この男性がどこから来たのか聞くことは出来ませんでしたが西郷先生を敬愛する私は嬉しく思いました。その笛の音色が終了するまでじっと聴いていた次第です。それから“せごどん”さん駐車場内の大きな西郷像を記念撮影。これまた毎年の行事?です。目的を達したのであとは南洲神社へ向け一直線です。私は昨年よりも1時間以上も早く到着するので駐車場は空いていると思っていましたが予想を裏切る多数の車に驚きました。私が鹿児島へ来るようになってこれほど多くの車があるのは始めてです。何とか車を停め西郷隆盛先生のお墓に向かいました。
2007.10.30
コメント(0)
-

西郷南洲翁生誕180年記(10) by 北洲
鹿児島ラ-メンで空腹を満たし天文館周辺を散歩していましたら冷たいモノを食べたくなりました。やはり南国・鹿児島は夜でも暑いのです。そうなりますと場所柄、 “氷白熊”しかないと確信し本店へ。こちらの正式名称は“(株)天文館・むじゃき”といいます。このアイスクリ-ムは類似品が多く全国のス-パ-でもカップ入りで販売されています。でも本家本元は鹿児島なのです。さっそく本店に向かいました。しかし時間は22時をはるかに過ぎており1階店舗は閉店でした。しかしこちらは4階の居酒屋さんでも“氷白熊”を注文することが出来るのです。(5階建てのビルには系列店が営業しているようです。)1階店舗では何と10種類以上もの“氷白熊”を注文することが出来るのですがこの居酒屋では限られた種類しか注文は出来ません。(当然ですが。)それゆえオ-ソドックスな“氷白熊”を注文しました。この“氷白熊”はいわゆるカキ氷とは異なり、氷のキワが細かく口に含んだ瞬間、すぐに溶けてしまいます。ですから冷たいモノを食べるとよくありがちな頭が痛くなることはありません。5年ぶりに食べた“氷白熊”は大変美味しく大満足です。あっという間に食べ終わりました。もう一つ追加注文したかったのですが体調を考え断念しました。何といっても翌日は西郷先生の命日で墓参りに行かなくてはいけません。時間は23時近くになっていました。車でホテルに戻りました。岩崎谷方面からホテルに向かう途中に“西郷洞窟跡”があります。この洞窟については「西南戦争編」で記しましたが西郷先生始め生き残った薩摩軍兵士が終戦末期に岩を削り立てこもった洞窟の跡です。もちろん私は車を停め見学することに。まさに、この瞬間から130年前には明日、戦死する覚悟の西郷先生を始めとする薩摩軍兵士が痛飲し、歌い、互いに最期の別れをしました。昨年のこの時間は人影を見ることが出来ませんでしたが今年は西郷先生没後130年のせいか若い男女が訪れておりました。130年前のこの時間は城山は政府軍によって幾重にも固く包囲されていました。人間一人でさえ出入りすることは不可能でした。当時から130年が過ぎた今は周囲には住宅・お土産屋さんが立ち並んでおります。しかし夜は静寂に包まれております。また誠に不思議なのですが天文館周辺とは異なり涼しさも感じます。そのなかで私は薩摩軍の連帯感の強さを感じました。薩摩軍の幹部・兵士のなかには互いに意の合わない者も存在したでしょう。しかし西郷先生という大人物の存在が最後の最後まで離反を防いだということでしょう。西郷先生も純粋な精神の持ち主でしたしその周辺の弟子達も同様な精神の持ち主であったのでしょう。今の世の中、義理人情は死語に近くなりました。自分が属する会社や近所付き合いも表面的な交わりでしかないのでしょう。その最後の砦は家族ですがその家族関係も最近は崩壊しております。寄って立つ存在が無い共同体は脆くその悪弊は今や日本全国を覆っております。私はそれゆえ、今こそ、西郷隆盛先生の志を見直し実行していくことが肝要と意を強くしているのです。(次回からは3日目の様子を記します。)
2007.10.28
コメント(4)
-

西郷南洲翁生誕180年記(9) by 北洲
札幌はこのところめっきり寒くなりました。札幌市の南側に藻岩山という有名な山があります。丁度今時分、紅葉が綺麗です。鹿児島から戻り1カ月が経過しました。あっという間の1カ月でした。鰻温泉のドアを開け入浴してから出てくるまで20分という短い入浴時間でした。何せ後がつかえておりますもので仕方ありません。本当はじっくり入浴したかったのですが・・・・・・。それでも自然に囲まれた静寂のなかで西郷隆盛先生ゆかりの湯に浸かることが出来たのは幸せでした。湯上りは“温泉ゆでタマゴ”で温泉気分(?)を味わいました。それもお湯でこしらえたタマゴではありません。このように自然の熱を利用して作られたゆでタマゴです。値段は確か5個で150円だったと記憶しています。(これまた安いです。)温泉で汗を流し心身ともにリフレッシュした後はいよいよ開聞岳に向かいました。実は私の大学同期に鹿児島出身者がおりまして「ぜひ長崎鼻に行ったら良いよ。そこから眺める開聞岳は最高だから。」との助言を得ておりましたので長崎鼻に向かいました。長崎鼻とは?という疑問が湧き出るでしょうが簡単に申しますと“岬”です。(と私は勝手に認識しております。)時間は17時近かったので少し日が落ち始めておりました。長崎鼻へは車を乗りつけることは不可です。途中までは可能なのですが行き止まりになっております。それゆえ眼前にそびえる開聞岳を眺めながら徒歩でゆっくりと先端まで進みました。さすが“薩摩富士”と呼ばれるだけあって絶景でした。日本最南端の山です。もう少し早い時間に到着していたらより美しい開聞岳を堪能出来たでしょう。この景色はTVのCMで見ることがあります。確か焼酎の“さつま白波”の宣伝に用いられていたかと記憶しています。それにしても鹿児島の山というのは不思議です。桜島にしてもこの開門岳にしても何故か海の中にそびえているのです。こういった山は日本でも珍しいのではないでしょうか。これからの人生において再び訪れるか否かわかりませんが、とにもかくにも満足しつつ車に戻り本日の最後の目的地である“指宿砂蒸し風呂”へ。こちらは余りにも有名な観光地です。私にとっては、4年前に訪れて以来、2度目の訪問です。砂浜の地熱を生かした“お風呂”です。札幌で営業されている岩盤浴の砂が無い状態です。(もちろん場所は海岸の砂浜ですが。)利用方法はいたって簡単です。まず全裸になり浴衣を着用します。後は砂浜に仰向けで寝そべり係の方がスコップで砂をかけてくれます。10分もすると身体全体が温かくなり15分が過ぎる頃には汗が出てきます。既に陽は沈み辺りは暗くなっております。かすかに波が打ち寄せる音色を聞いていましたらいつの間にか寝てしまいました。妻に起こされ目が覚めましたが汗で浴衣はびっしょり濡れていました。あやうく脱水症状になるところでした。寝ぼけた状態で砂を落とし服に着替え水分補給をしました。これで一日に3度の入浴を体験しました。湯治効果のせいか体調も良くなり咳も止まりました。やはり自然治癒は身体に効果的なのですね。すっかり暗くなったなか鹿児島へ向かい車を走らせました。所要時間は1時間以上になります。昼間なら右手に海が見えるのですが辺りは真っ暗です。何とか事故にも巻き込まれず鹿児島市内に到着しました。時刻は21時を過ぎていました。いくら温泉ゆでタマゴを3個も食べたとはいえお腹がすいてきました。もう遅い時間でしたので簡単に済ませることにしました。(郷土料理は翌日に控えていましたので断念しました。)そうなると鹿児島ラ-メンです。お目当てのくろいわさんは21時で閉店。こむらさきさんも同じく閉店。「最後の切り札のとんとろさんも閉店だろう。」と半ば諦めにも似た気持ちで足を伸ばすと何と営業していました。嬉しかったですねえ。しかし、人気店の宿命です。店内は満員。しかも既に待ちの行列が出来ていました。空腹は最高のソ-スという諺があります。20分待ちました。昨年同様、とんこつ風味ながらさっぱり感があり、かつ塩の効いた美味に幸福感を味わいました。札幌ラ-メンとは異なる味ですが歳を重ねるにつれてこちらの味を受け容れるようになります。それにしても鹿児島のラ-メン屋さんには何故、漬物が大量に置いているのでしょう?こちらは食べ放題です。(でもこの漬物がラ-メンに合うのですよねえ。)空腹を満たし混雑するとんとろさんを後にし少し繁華街を散歩しました。翌日が休日の日曜日の夜でしたがさほど混雑していませんでした。何でも鹿児島市内には性風俗店は4店しか存在しないそうです。道徳倫理を重んじる伝統なのかどうかは判りませんが確かにススキノのような雰囲気とは異なっておりました。(次回は2日目最後の紹介です。)
2007.10.25
コメント(0)
-

西郷南洲翁生誕180年記(8) by 北洲
知覧特攻平和会館で多くの特攻兵の遺品を眺めながら私は戦争に至る背景を日本国民が常に考察していかなくては再び過ちを繰り返すことになると痛切に感じました。今となっては一部の軍人(特に陸軍閥)が独裁体制を敷き、強引な手法で日本を戦争に突入されたとされています。しかし最も重大な事実はそこに至る過程で民衆の熱烈な支持が存在していたからこそ彼らは権力を掌握出来たのです。もちろん戦後は手のひらを返したかのような姿勢に終始したマスコミが軍部そして民衆を扇動したことはいうまでもありません。しかし最大の戦犯はマスコミが発する偏った情報を鵜呑みにし検証を怠った民衆であると私は強く主張したいのです。そしてその体質は今の世になっても程度の差こそあれ根本的には変わっていないのです。そんな切ない感情を引きずり知覧を後にしました。知覧から車で南下し続けて到着した地は池田湖です。ここは当初の訪問予定ではありませんでしたが大うなぎで有名な湖らしく休憩を兼ねて見学することにしました。上記のような大きなウナギが浴槽の中で泳いでいました。池田湖は大ウナギ見学のみでした。時計の針は13時30分を過ぎており、そろそろお腹が空いてきましたので次の目的地へ車を走らせました。池田湖から約15分位で指宿市の“唐船峡そうめん流し”に到着。こちらは市営の流しそうめん店です。ただ、流しそうめんといいましてもTVなどで紹介されている竹からそうめんが流れてくるシステムとは異なります。下記のように独特の円形機械に水とそうめんを入れぐるぐる回します。そして水の中で回り続けるそうめんを箸ですくい上げ、いただくのです。この市営そうめん店の歴史は古く昭和37年6月に営業を開始しています。私は生まれてからこんなに美味しいそうめんを食べたという実感を得たことは今回が初めてです。私はこういった作法でそうめんを食べたことはなく童心に帰って楽しみました。もちろん、お腹が空いていたこともありますが美味しい訳は空腹だけではありません。ここ指宿市唐船峡は自然の湧水を利用しているのです。加えてこの中は多くの草木に覆われているため外気の暑さが大幅に緩和されるのです。豊富なマイナスイオンの中にいることも食欲をそそる大きな要因なのでしょう。リラックスしながらの昼食でした。結局、2人前も食べてしまいました。(1人前は550円です。)ちなみに年間利用客は約30万人とのことです。空腹が満たされ、更に美味しい水で水分補給が出来ましたので休憩はせず次の目的地へ。(この時点で当初の予定時間を2時間もオ-バ-しているのです。)このまま開聞岳を見に行くことを考えましたが何せ朝から暑さ(熱気)の洗礼を浴びせられています。さっと湯に浸かり汗を流すことにしました。開聞岳からは少し離れますが東方面に向かいました。私が以前から訪問したかった“鰻温泉”が目的です。この“鰻温泉”は晩年の西郷隆盛先生が好んで利用された温泉です。名前の由来は判りませんがすぐ近くに“鰻湖”という湖がありますのでそこから命名されたのではないかと思います。硫黄の香りが漂うこの温泉はとても小さな施設です。温泉というより小さな銭湯という表現が相応しい当てはまります。この“鰻温泉”は現在でも街外れどころが民家も少なく相当な田舎(失礼!)に位置します。西郷先生が利用された時期は明治7年~10年でしょうから当時は山中に位置していたと思われます。明治6年の政変(いわゆる征韓論)に敗れて鹿児島に帰郷された西郷先生はこの大自然のなかの温泉で心身の疲れを癒されたのでしょう。入浴料・200円(安い!)を受付の女性に支払い早速、入浴しました。石鹸もシャンプ-も備え付けられていない温泉でしたが湯は最高でした。先客が3名いました。会話から地元の方と判断しました。それにしても鹿児島弁は全くもって理解不能です。鹿児島市内では多少、イントネ-ションに違和感をおぼえる程度なのですが地方に来ると標準語とは相当、かけ離れております。そもそも鹿児島弁は他藩の者に理解されないよう、わざと難しく編み出された性格の言語であると聞いたことがあります。彼らの会話を聞きつつ私は今から130年前の西郷先生もこのようにして湯に浸かり「私学校生徒の暴発をどう防ごうか。」であるとか「これからの日本の行く末がどうなっていくのか。」思案されたお姿を想像しました。実際、この“鰻温泉”で湯治中の西郷先生を江藤新平さんが密かに訪れています。江藤さんは佐賀の乱に巻き込まれ首謀者として明治政府に追われていました。追い詰められた江藤さんは佐賀からこの南端まで西郷先生に“決起”を促したのです。西郷先生は江藤さんと激論を交わし“決起”の意思が無いことを示しました。落胆する江藤さんでしたが西郷先生は数日間、江藤さんをこの“鰻温泉”の湯と郷土料理でで慰労されたそうです。西郷先生も内心、苦渋の思いだったのでしょう。身じろぎもせず、そんなことを思い浮かべていましたら少しのぼせてきました。(次回に続きます。)
2007.10.21
コメント(0)
-

西郷南洲翁生誕180年記(7) by 北洲
太平洋戦争時、知覧訓練所では少年飛行兵・学徒出陣の特別操縦見習士官たちが操縦訓練を行っていました。しかし、太平洋戦争末期に突入すると戦況悪化により“体当たり攻撃”が決行されることになったのです。それは説明するまでもなく“神風特攻隊”の編成です。敵の空母に対し操縦士の命と引き換えに突撃しダメ-ジを与えるこの作戦は歴史上、例のない戦術です。さすがのアメリカ軍人も驚くばかりであったそうです。この玉砕戦法により1,035人もの多数の若者が“犠牲”になりました。否、ここで私が簡単に“犠牲”という表現を用いて良いのかは自信がありません。というのは南海へ飛び立った若者は自分達を“犠牲者”であるとは思っていなかったかもしれないからです。むしろ「自分の尊い命を犠牲にすることで少しでも戦況を回復できたら。」という切なる願いであったのかもしれません。あるいは「既に亡くなった戦友に続きたい。」という感情も内包されていたのかもしれません。その本心は誰にも知りうることは出来ません。(こちらは特攻銅像です)特攻平和記念館へ入ると当時の写真が所狭しと飾られています。同じく亡くなった特攻兵士が飛び立つ前に書き残した手紙等も陳列されています。小泉純一郎元総理大臣が現職時にここを訪問しその手紙を読み涙した様子はマスコミにより報道されたことは記憶に新しいです。小泉氏ならずとも涙なくしては読むことが不可能である内容です。その一例を簡潔に紹介します。「私は明日、飛び立ちますが爽やかな心境です。とても明日に死んでしまうとは思えません。この心境で明日は祖国のために立派に死んできます。」「(故郷の家族に宛てた内容)私は明日、南海に消えます。短い人生でしたがお父上、お母上の子供として生まれ幸せでした。貴方達の子供としてお国のために死ぬことができ光栄です。どうか私がこの世から消えてもお体には留意されお過ごし下さい。」といった内容が大部分を占めていました。中には「武運長久」、「鬼畜米英」といった短い決意表明も存在しましたがこれから死を迎える人間が記したとは思えない爽やかで慈愛に満ちた内容でした。当時の教育及び時代背景が大きく影響しているのでしょうが私を含め現代人とは全くレベルが違います。特攻隊員の大部分は10代、20代でした。自分と比べ恥ずかしさを感じるのは私だけではないでしょう。(こちらは特攻平和観音です。)私はここで「戦争はいけない。」とわざわざ述べるつもりはありません。そんな当たり前の概念を述べることは無意味であるからです。私が声を大にして申し上げたいことは“南海に消えた特攻隊兵”が若き生命を“犠牲”にしてまで残したこの日本が本当に彼らの“遺志”の応えているのかということです。いささかヒステリックな表現を用いるならば「彼らはこんな堕落した国(今の日本)におとしめるため犠牲になったのか!」のであります。もちろん私は“今後の日本を当時のような軍事大国にすべき”と主張しているのではありません。わずか60年前の出来事において、残された身内を始め多くの日本国民が受けた心の傷は一生涯に渡り消え去るものではないということです。同時にそうであるならば、現在のように同朋が殺しあう(無差別殺人・イジメによる自殺)国を夢見て特攻隊兵が命を散らしていったのではないことを各人がしっかりと認識しなくてはいけないのです。彼らは恋愛も飽食をも享受せずまさに“禁欲”のなかで亡くなっていきました。私とて時代が時代であれば彼らと同様、南海の海に消え去っていたでしょう。そう考える度、 “犠牲”になった尊い命に応えるため“自覚を持った行動をしなくては”と反省させられる次第です。(こちらにも入館しました。偶然にも“西郷先生愛用の刀”が展示されていました。)余談になりますが私の祖母の末弟も先の大戦で亡くなっています。私はその詳細を祖母から聞いたことはありませんが、その末弟は南方の海に消えたそうです。今となっては祖母は故人となり、その方の人となりを聞くことは出来ませんが私の身内に日本のため立派に若き命を散らした人物が存在したことは誇りと思っております。(当時の日本には敵国のスパイとして卑劣な生き方をした売国奴が相当数、存在していたそうですから。)
2007.10.20
コメント(5)
-

西郷南洲翁生誕180年記(6) by 北洲
知覧町は見学すべき建物が町の規模に比べ多すぎるほど存在しています。また、静岡と並ぶお茶の産地で“知覧茶”はあまりにも有名です。そのなかで、私はまず“武家屋敷群”を見学することにしました。(入場料は500円でした。)この“武家屋敷群”は江戸時代から存在する住居です。昭和56年に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。合計7つの庭園(屋敷)が現在においてほぼ変わらぬ形で残されております。しかも驚くべきことはこの屋敷には今も子孫の方々が住んでおられるということです。ですから“立ち入り禁止”のお宅も存在します。と思えば、広い庭を生かして食堂や喫茶店として商売をされているお宅もあるのです。私は当時の武士の気分を味わうべくあるお宅で休憩することにしました。地元で古くから伝わる菓子と知覧茶のセットを注文しました。江戸時代から残る住居を単に残すだけではなく実際にそこで生活し商売に結び付けることは無駄のない意義あることであると認識して後にしました。それにしましても暑かったです。次の目的地は“知覧特攻会館”です。ここはあらためて説明する必要は無い位有名な施設です。時計の針は12時近かったですが我慢してこちらの見学に専念することにしました。この日は日曜日ということもあり大勢の方が来ておりました。(アバウトな目測で約300名くらい。)雰囲気としましては東京九段の靖国神社を似ておりました。こちらは零戦です。先ごろ公開された映画(題名は失念してしまいました。)で使用された零戦と同様のモノらしいです。次に“参拝所”がありましたので亡くなった若き日本兵を偲び手を合わせました。と、そのすぐ横にこのような石碑がありましたので写しておきました。小泉元総理の名が刻まれた大きな石碑でした。そういえば小泉元総理もこちらを訪問していた記憶があります。“特攻会館”の手前には当時の日本兵が寝起きしていた簡易宿舎を再現した施設がありました。敵にその存在を気付かれないようにする為か目立たない小さな造りでした。こんな狭く粗末な宿舎で熟睡することが出来たのでしょうか。せまり来る“死”を覚悟しつつ色々な想いを胸にしまい込んでいた日本兵士の姿が浮かぶようで沈痛な気持ちに苛まれました。本日は写真を多めに掲載致しました。(次回に続きます。)
2007.10.16
コメント(4)
-

西郷南洲翁生誕180年記(5) by 北洲
激しい咳に悩まされはしましたが7時30分には目覚め、何とかベッドから飛び出し大浴場(さつまの湯)に直行しました。まだ頭と身体は目覚めていませんがゆったりと湯に浸かりながら朝の桜島を眺めること10分。それから露天風呂に移動しました。この段階では身体はともかく頭は目覚め始め、至福のひと時を堪能しました。朝から眼前にそびえる桜島を眺めながらの露天風呂は最高の贅沢です。私は毎年この湯に浸かる度に感じるのですが桜島は眺める時間帯によってその色合いが変化するのです。そして色合いの変化によってその様相も変化する印象を与えてくれます。誠に不思議な“山”です。私は年に一度しか鹿児島を訪れませんのでそのように感じるのでしょう。普段から見慣れている地元の方はどのように思っているのでしょうか。それにしましても130年前のこの地、時間帯においては、まさに緊迫した状況なのでありました。西郷先生助命嘆願が成功するか否かといった段階なのです。そう考えるとゆったり湯に浸かっているうちに切ない感情と申し訳ないという多少、恥ずかしい複雑な心境になりました。温泉の効用なのか身体が元気を取り戻したようで大浴場を出た後は朝食会場へ向かいました。バイキング形式の会場に到着して驚いたことは人数の多さです。昨年とは全く異なる光景でした。私は席が空くまで待つことを余儀なくされました。待つこと約15分。その間私は会場向かいのテラスを散歩しました。ここから眺める桜島も風光明媚で昨日、磯庭園周辺で見た光景とは異なっておりました。やっと会場に入り朝食にありつけました。以前にも述べましたがこの城山観光ホテルの朝食は内容が充実しており今年も変わらぬ素晴らしい料理の提供に満足しました。朝から鯛の刺身にはじまりさつまあげ・きびなごまで用意されています。味噌汁は白・赤の2種類があり御飯に至っては10穀米までありました。ついつい食べ過ぎてしまいますが、これから薩摩半島南端まで足を伸ばすスケジュ-ルです。ゆっくりもしておれず大好物のパイナップルを食べてから朝食会場を後にしました。レンタカ-に乗り、目指すは知覧・指宿です。途中、焼酎工場(蔵元)の看板が目に入りましたので少しだけ寄り道することにしました。こちらは観光スポットに指定されているのか女性のガイドさんが常駐していました。慣れたガイドさんで芋焼酎の製造過程を丁寧に説明して下さいました。こちらは材料のさつまいもです。そしてこちらは麹の発酵中です。一通り説明をしていただいた後は隣接する販売店へ導かれました。いくら観光スポットとはいえ当然ながら商売もしなくては飯は食えません。(笑)こちらでは何十種類もの芋焼酎が販売されており眺めるだけでも楽しい気分になります。もちろん“試飲”もあります。“出来立て”というのか“絞りたて”というのか判りませんが美味しそうでした。もちろん私は運転がありますので断念です。(咳も完治していませんでしたし。)店員さんがしきりに薦めたの銘柄は“一縷”という焼酎。アルコ-ル度数が44度です。何でもこの焼酎を冷凍庫に入れた場合、瓶は凍っても中身の焼酎は凍らないとのこと。加えて限定品という宣伝文句に負けて高値にもかかわらず購入してしまいました。(300mlでこの値段です。)それにしても「焼酎ばかり何本も購入し誰が飲むのだろう?」と今となって考えこんでおります。(私は先の“荻窪の夜”を反省し暫くは強い酒を口にしないつもりですので。)この蔵元の隣にはさつまあげ工場もありますがその内容は省略します。(またの機会にご紹介させていただきます。)再び知覧方面に向けて車を走らせ、第一の目的地である“武家屋敷”まで休憩を取りませんでした。こちらは明治維新の遥か前からのさむらいの住居がそのままの形で残されているのです。(次回に続きます。)
2007.10.14
コメント(0)
-

西郷南洲翁生誕180年記(4) by 北洲
鹿児島市内にはお土産店は多数ありますが食品関係は山形屋さんが便利でしょう。私は毎年、こちらを利用しております。購入した品をまとめて宅急便で送りますので同一店舗が良いのです。購入の順序も慣れたものでまずは焼酎販売コ-ナ-に足を運びます。札幌の知人・友人・同僚へのプレゼントを大量に購入しますが70種類近い銘柄をあれこれと考えながら選ぶのは楽しいです。今年は下記のような珍しい銘柄を見つけました。今年が西郷隆盛先生の生誕180年にあたりますので造られたのでしょう。他の銘柄に比べ多少、値が張りましたが記念に購入しました。封はまだ切っておりません。次なる目的はやはりさつまあげコ-ナ-です。私が毎年利用している店舗は“有村屋”さんです。こちらは老舗で味も良く差し上げた方から好評をいただいております。その後は、かるかん・漬物などを購入し買い物は終了しました。山形屋さんを後にした時間は19時前でしたが土曜日というのに中心街は人影もまばらでした。天文館のア-ケ-ド街は行き交う人数も少なく札幌の狸小路以上に寂しさを感じました。維新の英雄を数多く輩出したここ鹿児島にも不況の波は押し寄せているのですね。散歩を兼ねて周辺を探索していましたら時計の針は20時を回っておりました。まだ夕食を済ませていませんでしたのでそろそろと思い辺りを見回しましたが居酒屋。郷土料理店以外は営業を終了していました。そこでホテルに戻る途中にある華蓮Jrに行くことにしました。こちらは天文館近くで営業している華蓮さんの姉妹店です。私は昨年、その暖簾をくぐっておりますので味は間違いないと確信していました。車を駐車場から出し華蓮Jrに向かいました。場所は歴史ある建物(元は公的な建物であったのかもしれません)の2階にありました。店内に入りますと何組かお客さんがおりました。しゃぶしゃぶもメニュ-に書かれてありましたが私は躊躇せず“黒ぶたのカツカレ-”にしました。私は肉体疲労時には何故かカレ-ライスを食べたくなるのです。さすが華蓮さんの姉妹店だけあり味はgoodでした。宿泊先の城山観光ホテルに到着したのは21時でした。空腹も満たしたことですしこのホテルの大浴場(温泉)を楽しむ予定でしたがかねてからの体調悪化に加え旅の疲労が重なり爆睡してしまいました。朝方はひどい咳で目が覚めました。出発前の札幌は寒い日があり気管支が炎症を起こしていたようです。翌日は薩摩南方面に行くので薬を飲み再び眠ることにしました。初日からさんざんな目に遭いました。
2007.10.13
コメント(2)
-
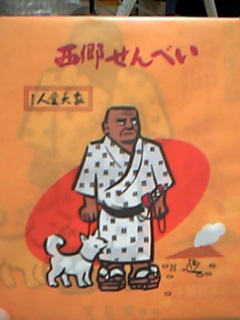
西郷南洲翁生誕180年記(3) by 北洲
北海道では決してお目に掛かることは出来ない両棒餅を口中に押し込み急いで平田屋さんを飛び出した私が向かう先は“西郷隆盛先生蘇生の家”でした。平田屋さんの女将さんに行き先を聞き車を飛ばしました。西郷先生と月照和尚が抱き合って冷たい錦江湾に沈みましたが天は西郷先生に休むことを許しませんでした。天は西郷先生に島津斉彬公そして月照和尚の遺志をしかと受け留め実行させんがため蘇生させたのでしょう。車を鹿児島空港方面に向けて飛ばすこと約5分。前方左手に藁葺きの“それらしき”古い屋敷が目に飛び込んできました。「よし!車を止めよう。」と思ったのですが車を駐車するスペ-スなど全くありません。車の往来が激しい細い国道脇に“西郷隆盛先生蘇生の家”は確かに見えるのですが車で近づくことは不可能です。仕方がありませんでしたが車中から眺めることで満足させました。時間はまだ16時前後です。近くにある磯庭園は過去に訪れておりますので今回はスル-です。私は市街に向かうことにしました。目的地は山形屋(やまかたや)さんです。こちらは鹿児島を代表する百貨店です。私は毎年、山形屋さんでお土産を購入することにしております。焼酎・さつまあげ・西郷せんべい・さつま大根の漬物・かるかんなど何でも揃うので時間を節約出来ます。観光客にとって時間の節約はとても重要なのです。下は鹿児島名物・西郷せんべいです。1袋に厚めのせんべい(西郷先生を模った)が2枚入っております。山形屋さん近くの駐車場に車を預け歩いていましたら何と月照和尚ゆかりの地跡に遭遇しました。写真は月照和尚が常宿とされていた建物の跡地でした。月照和尚終焉の地(海)からさほど離れてはいないこの地で和尚は維新実現に想いを馳せていたのでしょう。私も少し感慨に浸ってしまいました。僧侶という立場で時代に翻弄されつつも時の政(まつりごと)に対し重責を担われた月照和尚のような存在は現世において皆無かもしれません。生臭ボウズは腐るほど蔓延っていますが・・・・・・。
2007.10.10
コメント(0)
-
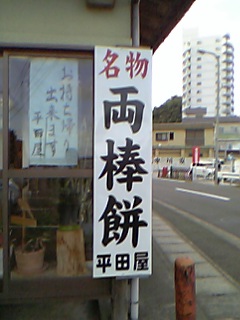
西郷南洲翁生誕180年記(2) by 北洲
錦江湾に浮かぶ桜島を眺めながらのんびりと両棒餅を頬張る私の脳裏にかすめた記憶が蘇りました。それは中川家さんの隣で営業している両棒餅のお店に西南戦争時に刀で斬りつけられた傷跡が残った柱があるという内容です。昨年は時間が無く入店は断念しました。今回は「何としてでも」と意を決しお邪魔することにしました。店名は平田屋さんです。既に中川家さんで12本の両棒餅を食べておりましたが以外と両棒餅はあっさりしておりまだ胸焼けするほどではない状態でしたのでチャレンジすることにしました。(さすがに両棒餅を注文せず“柱”だけ見せていただくことは申し訳ないと思った次第です。)平田屋さんの両棒餅も12本で500円です。ただ中川家さんの味と異なる点があります。それは中川家さんの両棒餅が“味噌ベ-ス”なのに対し平田屋さんの味は“醤油ベ-ス”なのです。こちらの方が味が薄めに感じました。お目当ての“柱”について女将さんに尋ねました。私はてっきりこちらの建物を支えている柱のどこかに刀傷が残っているのだと思っていました。しかし柱は1mにも満たない長さでお店の隅に立てかけられておりました。女将さんが仰るにはこの柱の傷は西南戦争最中につけられたものではないということです。この平田屋さんは昔は旅館業だったそうで多くの士族が宿泊していたそうです。確実な内容ではありませんが西南戦争勃発のきっかけとなった“私学校生徒による政府の武器弾薬庫襲撃”直前に斬りつけられた跡ではないかということです。当時の平田屋さんには多くの私学校生徒が密議のため終結していたそうです。そうなりますとあくまで想像とのことですがこれから武器弾薬庫を襲撃するか否かの白熱した議論のさなかにつけられたのかもしれません。つまり“西郷先生暗殺計画”を耳にした私学校生徒が激昂し刀を振り回した可能性があります。下部に刀傷を見ることが出来ます。当時の手に汗握る緊迫した様子を思い浮かべつつ両棒餅を頬張っておりましたらまたまたある光景が私の脳裏に浮かんできました。「そういえばこの近くに西郷先生蘇生の家跡があったはず。」そうなのです西郷先生は若き頃まさに私がのんびりとくつろいでいるこの地近くの錦江湾に入水自殺を試みているのです。自殺といいましてもその性質は失恋ですとか借金苦、リストラの類ではありません。いつか取り上げますが幕末の勤皇僧侶として高名な京都・清水寺の月照和尚と抱き合って冬の寒い錦江湾に飛び込んだのです。当時の徳川幕府から追われた月照和尚を匿おうと鹿児島へ連れてきた西郷先生に対し、時の実質的藩主・島津久光は幕府からの攻撃を恐れ西郷先生に“月照和尚殺害”を命じました。しかし情に厚く島津斉彬公死去に際し殉死しようとした西郷先生を説得し命を救った恩人を殺害するなど西郷先生は到底出来ることではありません。大久保利通であれば部下を使い殺害したかもしれません。そこが西郷先生の良さであり反面、弱さであるかもしれません。進むも地獄。退くも地獄。西郷先生は月照和尚と死ぬことを決意しました。結果、西郷先生のみが助かりました。西郷先生が息を吹き返した家の跡が近くにあるので私はいてもたまらず両棒餅を勢いよく口に含み勘定を済ませその地に向かいました。
2007.10.08
コメント(0)
-

荻窪の夜(2)。 by 北洲
昨日から三連休です。ゆっくり休養をとっておられる方、家族サ-ビスにお忙しい方、お仕事の方と様々でしょう。昨日の私は多少、多忙な時間を費やしました。私は毎年、本州の知人に“じゃがいも”を送らせていただいております。北海道の“じゃがいも”は本州産に比べ「質が良い。」と高評価を得ております。例年は鹿児島へ行く前に発送を済ませておりますが今年は諸事情のため10月に突入してからの発送になりました。昨日は知人の農家さんへ行き頼んでおいた“じゃがいも”を受け取りに行きました。農家さんのなかには生産のみの業務で発送業務をされていないところもありますので私が荷造りをします。今年は少雨のせいか例年に比べ生産が少なかったとのことです。しかし私が購入する“じゃがいも”は“無農薬・有機栽培”ですので味が良く体にも良いのです。1箱・10kg入りの“じゃがいも”を20箱運びましたが少し疲れました。そろそろトレ-ニングを再開しなくてはいけないと痛感しました。購入先である石狩・生振(おやふる)の農家さんの畑を観察しました。下記の写真は何の実だと思いますか?松の実?ナナカマドの実?これは“アスパラ”の実(種)なのです。私も数年前に初めて目にして驚きました。前置きが長くなりましたが「荻窪の夜」に移ります。暫くアルコ-ルを体内に注入していなかったせいか知らず知らず酔っていた私です。意識が朦朧とするなかトイレに駆け込みました。吐き気は無かったのですが一度しゃがみこむと起き上がることが出来ず長時間、トイレにいたと想像します。さすがに竹社長始め皆さんが心配になられ私の名前を呼んでおられるのですが声すら出ない始末です。学生なら“アルコ-ル中毒”とやらで救急車に運ばれるのでしょうが鹿児島帰りの私にはそんなみっともないことは出来ません。ましてや中村稔先生・Fさん の眼前でぶざまな姿を晒すことは武士の恥です。何とか立ち上がろうとするのですがそれもままなりません。いよいよ「様子がおかしい。」と察知された竹社長がトイレのドアを何度も叩き私の安否を気遣って下さいます。私は最後の気力を振り絞り開錠しました。竹社長に体を持ち上げられ私は何とかカウンタ-にもたれかかりました。お店のご主人が塩水を飲ませて下さった記憶はかろうじてあるのですが飲み干した後は再び意識が無くなりました。さすがに竹社長は「これは早くホテルに返した方が良い。」と思われたらしくタクシ-を呼んで下さり私の思い体を担がれタクシ-まで運んで下さいました。中村先生、Fさん、お店のご主人・女将さんに御礼も出来ませんでした。今こうしてパソコンに向かっていても赤面の限りです。中村先生は哀れに思われたのかこのような表情でかつての教え子を眺めておられました。恐らく先生の心中は「これしきの事で軟弱な教え子だ!」と憤慨されておられた 思います。無意識ななかでもホテルの住所は何とか口に出来たらしく人形町までは到達出来ました。しかし運転手さんはホテル名が判りません。運転席から何度か私に質問するのですが私も何を言っているのか理解出来ないでおります。しかし幸いにも私のシャツのポケットにホテルの住所等が明記された名刺が入っており運転手さんはナビに入力しました。かくして何とかホテルにたどり着くことが出来ました。竹社長が運転手さんに1万円を渡して下さったらしく運転手さんは私におつりをくれました。翌日は案の定、強烈な二日酔いに悩まされました。11時には日比谷の結婚式会場であるホテルに到着しなくてはいけないので8時30分にはベッドから這って出ました。その間、ポカリスエットを1リットルと味噌汁2杯そして水を500ml飲みました。今回の失態は私の反省材料として暫く脳裏に刻み込んでおかなくてはいけません。(泥酔のため怪しげなネオン街に繰り出さなかったことは天の配剤かもしれませんが。)
2007.10.07
コメント(0)
-

荻窪の夜。 by 北洲
伝説の名講師・中村稔先生(愛称・ミック)との20数年振りの再会に多少ずうずうしい私も緊張しておりました。もちろん中村先生にとって私は大多数の教え子の一人(one of them)でしかありません。しかし薩摩隼人の竹社長から事前に私のことを聞いておられた先生は私のために高価なブランデ-を用意して下さいました。店主さん、中村先生にご挨拶をさせていただいた後、ビ-ルでの乾杯となりました。私は竹社長と中村先生の間で“酔い過ぎないように”注意しつつ予備校時代の話題を語り始めました。実は私は暫くアルコ-ルを口にしておりませんでした。長い夏風邪に悩まされておりとてもアルコ-ルを口に出来る状態ではありませんでした。当然、鹿児島でも一滴の焼酎を口にせず大変寂しい思いをしました。しかしこの日は体調が良く気候も過ごし易かったせいか杯が自然と進んでしまいました。今から思いますと私はブランデ-をロックで飲んでいたようです。中村先生は“ゆうたろう”が物まねする際に使用するような大きなグラスでご自身のブランデ-をぐいぐい飲んでおられました。相当お酒がお強いと瞬時に判断することが出来ました。ちなみにそのブランデ-のラベルには“ミック”と書かれておりました。私は酔いも手伝い中村先生にかつて受講した講義の回想録を話し始めました。そのなかで私が今も覚えている言い回しがあります。それは“Please remember me to your mother." です。和訳しますと「お母様によろしくお伝え下さい。」なのですが中村先生は大声で(マイクを使用しているのにも拘らず)「皆さん、この言い回しは試験に出題されますよ!よ-く覚えておいて下さい。いいですか!意味はですね、 “お母ちゃんによろしく!”です。」と何故か奇妙な和訳をされるのです。中村先生はその話を聞かれ「君、よくそんな事覚えているね。」と笑っておられました。そんな昔話をしておりましたらある上品な男性が入店してこられました。その方も竹社長に呼ばれ(というよりこのお店の常連です。)わざわざ来て下さいました。Fさん というこの方は私の大学の先輩でしかも学部も同じです。大先輩を前にして一気に緊張状態に戻ってしまいました。Fさん は現在、文京区目白にあるw塾の理事をされていらっしゃいます。このW塾はあまりにも有名な塾です。東京都心の大学に通うまともな男子学生であれば必ずその名を耳にしたことがあるでしょう。もっとも塾といいましても受験向けのものではなく早い話、男子大学生の為の寮なのです。しかし単なる寮とは異なり“文武両道”をモット-にした教育機関に近い性質が内包されております。昭和30年創立のW塾は細川護立氏(細川元総理の父)が本宅として建てた建物を使用しております。私の後輩のなかにもW塾OBが何名かおりますのでその質実剛健な生活ぶりは聞いておりました。こうなりますと私達4名は薩摩の郷中教育の話題に始まり政治・経済にまで議論が進みます。しかし私は議論に熱中する余り中村先生が用意して下さったブランデ-がいつの間にか3分の1にまで減っていることに気付きませんでした。お店のご主人がこんなに美味しい鮪を出して下さいました。酔う前に味わうことが出来て良かったです。しかし私は段々と口が回らなくなっていく肉体の変化に気付いてはおりました。私はそんな状態で失礼にも中村先生に対しこう言っておりました。「先生は私達、迷える浪人生に大学に合格できる究極の英語を伝授して下さった。その我々の世代は今や小中学生の子供を持つ立場になりました。私には子供はいませんが皆、子育て、今後の人生について悩みを抱えています。そうであるならば先生は札幌に来てかつての教え子に今度は男としての生き様死に様を指導する義務があるのではありませんか?先生が育成された教え子に対し今一度、正しい道を歩いているのか否か検証されるお立場にあると思います。」と呂律が回らなくなるなか、最後の力を振り絞って半ば先生を詰問するように思いのたけを吐露しました。もっとも中村先生にとっては一方的な言いがかりでしかありません。中村先生にしてみれば「いい大人が何をほざいているのか!」と内心思われたことでしょう。しかし中村先生は「わかった。必ず札幌に行くよ。」と言って下さいました。私は胸が熱くなり思わず、中村先生と固い握手を交わしておりました。しかし精神の高揚が頂点に達したこの直後一気に酔いが私の全身を駆け巡りました。意識が無くなりました。私は意識がないままトイレに駆け込みました。(以下続きます)
2007.10.04
コメント(1)
-

私は代ゼミOBです。 by 北洲
本日は「西郷南洲翁生誕180年記」を休みます。そして、いきなり意味不明のタイトルですが、これにはきちんとした理由があります。私は先週土曜日(9月29日)大学時代の後輩の結婚披露宴に出席するため上京いたしました。9月は出張、西郷先生の墓参、そして今回の結婚式出席と都合3回も津軽海峡を渡りました。余り旅をすることが好きではない私にとっては誠に珍しい月でした。先週土曜日、東京の気温は11月並の寒さでした。私としましては大変救われました。何といいましても“礼服”を着用して結婚式会場まで移動することは暑さに弱い私にとりましては苦痛なのです。北海道においては結婚式に出席する男性は一般的には“平服(普通のス-ツ)”でOKなのですが東京はそうはいきません。披露宴は翌日でしたが私は余裕をみて前日に上京しました。披露宴会場は“日比谷”の某ホテルでしたが私の宿泊先は披露宴会場から決して近いとはいえない“日本橋人形町”でした。これにも訳がありました。“日本橋人形町”は西郷隆盛先生が明治6年の政変において敗れるまで何年か屋敷を構えていた土地なのです。現在はその面影はありませんが当時の雰囲気を少しだけでも味わうことが出来たらと思った次第です。 地元の小学校・幼稚園入口前に上記の看板が立てられておりました。周辺は伝統あるお店が軒を連ねておりました。明治初期は更に閑静で風情に溢れた街だったのでしょうね。実際の西郷邸は下記の建物のところに位置していたと仰る方もおられます。「西郷先生はこの土地で生活され明治新政府の礎を創られたのだなあ。」と感傷にふけった後はホテルにてチェックインを済ませました。その後は“荻窪”目指しホテルを出ました。北海道から来た私が何故に“銀座”・“赤坂”ではなく“荻窪”なのか?それは本日のタイトルと密接に関わっているのです。それは私が日ごろお世話になっている鹿児島出身の竹社長がごひいきにされている お鮨屋さん が荻窪にあり「ぜひ来るように。」とお誘いいただいたからです。じつはこのお店にはかつて代々木ゼミナ-ルにおいて“名講師”の誉れ高きお方も常連とされているのです。そのお方とは中村稔先生です。私は今から20年以上も前に代々木ゼミナ-ルで学んでおりました。私は「世の中に予備校という学校が存在する以上、高校卒業後は予備校で学ばなければ大学進学の意義を見出すことは出来ない。」という信念のもと“浪人生活”をエンジョイしていました。そこで私に受験英語の極意を叩き込んで下さったのが中村稔先生です。中村先生はミックジャガ-に似た風貌から当時の受験生は“ミック”と呼んでおりました。その授業はハ-ドかつアグレッシブで私は授業についていくのが精一杯でした。発音など一切無視。辞書を徹底的に駆使した授業はさながらミックジャガ-のコンサ-ト会場にいるのかと錯覚してしまう熱狂ぶりでした。今思い出してもあの躍動感が蘇ってきます。更に歩く早さは驚くべきでカバンの中には鉄アレイを入れ常に肉体を強化されているという超人でもありました。昨年、札幌に来られた竹社長から中村先生の近況を伺い私は「いつかお目にかかりたい。」と思っていましたがまさかこんなに早く実現するとは正直、驚きました。お引き合わせいただいた竹社長に感謝申し上げます。“荻窪駅”に到着した私を竹社長が迎えて下さいました。駅から徒歩数分のところにそのお鮨屋さんはありました。少し緊張しながら暖簾をくぐりますと中村先生は既にカウンタ-に座っていらっしゃいました。20年以上もお目に掛かっていないとはいえ私は中村先生をすぐに認識することが出来ました。あの苦しくも夢を持って過ごした私の浪人時代の支えであった“名講師”との邂逅に私の胸は高鳴っていました。しかしこの後、私の身に恐ろしい出来事が到来するとはこの時点において全く想定しておりませんでした。(以下次回です。)写真は中村先生です。往年の名講師のダミ声が今も耳に残っている大人(中年?)は多数、存在するのではないでしょうか?
2007.10.02
コメント(0)
全13件 (13件中 1-13件目)
1