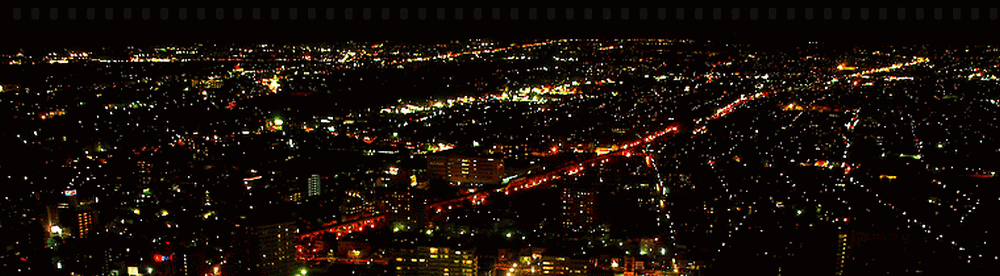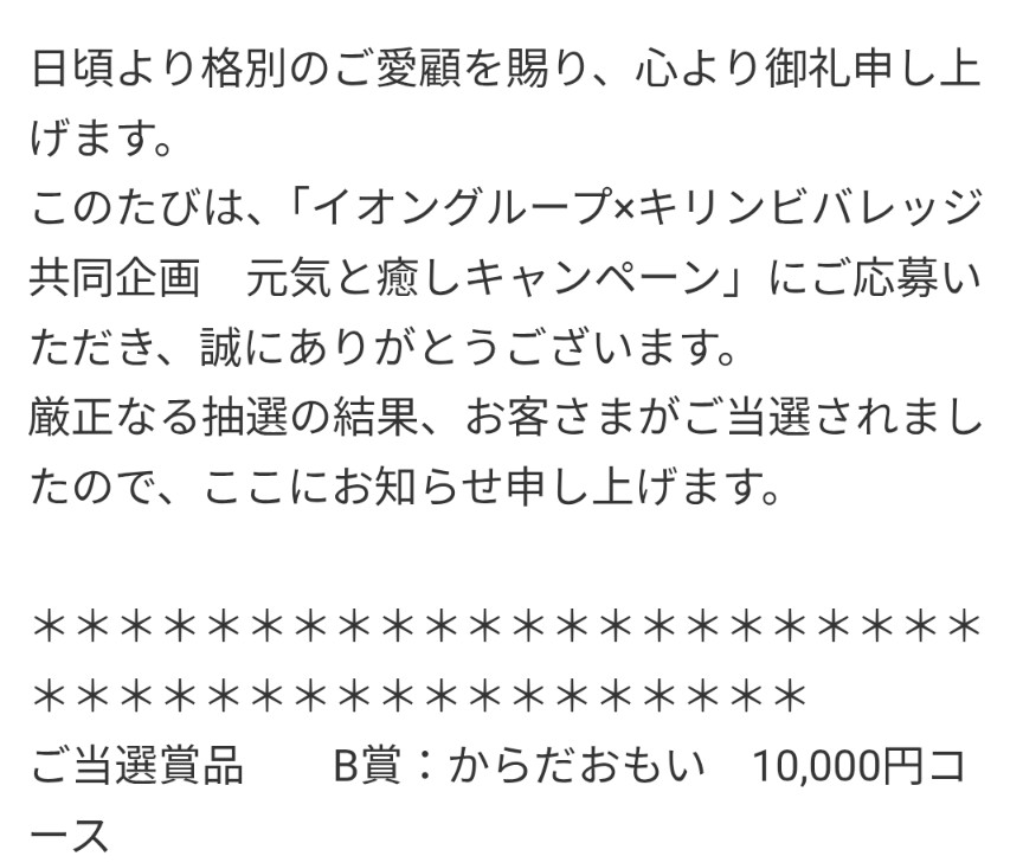2007年11月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

西郷南洲翁生誕180年記(19) by 北洲 (井上剛鹿児島市議会議員編)
邂逅-まさにこの言葉がピッタリな井上氏との会食でした。学生時代はサシで食事をしたことなどありませんでしたが年月が経過すると深い思慮などなく楽しい時間を過ごすことが出来るのです。私は井上氏による心のこもったおもてなしが嬉しかったのです。それはいくら大学の先輩後輩とはいえ政治家である彼にしてみれば鹿児島市民ではない私と費やした時間は票にはならないのです。政治家にとって一番大切なモノ(人物)は間違いなく選挙民なのです。逆の表現をすると地元の有権者以外の人間と会食をしても票にはつながらないのです。しかし井上氏はそんな損得抜きに札幌からきた私のために貴重な時間を割いてくれました。その心意気がたまらなく嬉しかったです。元来、私は お金や物品を貰ってもそんなに嬉しくは感じない性質の人間のようです。私はむしろ お金では買うことの出来ない対象に強い感情を向けるのです。そんな私に対して、3連休の最終日で込みあっていた「あぢもり」さんの個室を予約してくれた井上氏には感謝です。井上氏の心遣いはそれだけではありませんでした。「あぢもり」さんの社長さんに私の来店を話してくれたのです。その結果、社長さんから想像もしなかった“差し入れ”がありました。何と“薩摩焼酎”です。しかも西郷先生のお姿(模様)付きの器でした。更にこの非売品の器を私にプレゼントしてくれるとのことです。まさに“お金では買うことの出来ないモノ(器)”です。何でも「あぢもり」さんオリジナル製品らしく販売もしていないそうです。私が想像する限りでは社長さんと親しい井上氏が私が西郷先生の崇拝者であることを知って「プレゼントして下さい。」と頼んでくれたのでしょう。この器は私にとって一生の宝物になるでしょう。西郷先生の裏側は大久保利通です。因みにこの社長さんは札幌市のご出身だそうです。そのせいか社員旅行は常に北海道にいらっしゃるそうです。(ますます親近感が湧きました。)料理を運んで下さった店員さんによりますと「昨年は旭山動物園(旭川)に行きました。」とのことです。感激している私を横目に井上氏は西郷先生の器に入った焼酎を飲み続けます。さすが地元の人間です。強いです。しかも酔っている風でもありません。驚きのなか、いよいよ“黒豚しゃぶしゃぶ”に移ります。本当に見事な“黒豚”です。札幌ではお目にかかることは出来ない美しさです。「あぢもり」さんが提供する“黒豚”は赤身と脂身のバランスが良くどんなに煮込んでも硬くなったりパサパサすることはありません。更に驚いたことに(驚いてばかりですね)しゃぶしゃぶには必至の灰(あく)が出てこないのです。井上氏が言うには「あぢもりさんの肉は最高品質ですからあくは出ないのですよ。」とのこと。私が自宅でしゃぶしゃぶをする時、大量のあくが出るというのに・・・・・・。通常のしゃぶしゃぶは箸で肉・野菜などをつまんだ後、タレに漬けていただく作法が常識と思っていましたが「あぢもり」さんではタレなど存在しません。鍋に入っているお湯それ自体がカツオのダシが効いた味付きなのです。まさに食べ方はすき焼きと同じなのです。(好みによって溶いた卵に肉他を付けたりします。)この最高品質の“黒豚”を口に含むとそれはそれはやわらかく、それでいて歯ごたえのある感触を覚えました。鹿児島最後の夜を占めるに相応しい味でした。これで焼酎を口に出来たら「言うこと無し」だったのですが・・・・・・。感動・驚きの連続のなか井上氏との昔話も盛り上がった次第です。その内容は難易なものではなかったですが現在、鹿児島市は教育・環境・観光の3K対策に力点を置いているそうです。これら3点は鹿児島市においてだけではなく日本全体において取り組むべき重要課題です。かつて明治維新樹立の先鞭をつけた中心は鹿児島の人々でした。今の日本が抱える病巣を取り払う先駆者として鹿児島市には期待するところ大であります。同時に若き鹿児島市議会議員・井上剛氏には彼が敬愛する小松帯刀さんのような英知をもってしてまずは鹿児島市のリ-ダ-に成長することを遠く離れた札幌から祈っております。来年4月には井上氏にとって3度目の選挙があります。常に前向きで困難をものともしない井上氏ですから当選は確実と想像しますが油断だけは禁物です。彼にとっては迷惑でしょうが私は定期的に「くれぐれも油断無きよう!」とのメ-ルを送信する予定です。そして来年9月には少し遅れた彼の“当選祝い”を「あぢもり」さんで行いたいと今から考えております。爽やかな気持ちで城山観光ホテルに戻りました。鹿児島市内を一望することの出来るテラスに足を踏み入れると写真上のような魅惑的な“噴水”を楽しむことが出来ました。
2007.11.28
コメント(0)
-

西郷南洲翁生誕180年記(18) by 北洲 (井上剛鹿児島市議会議員編)
井上剛氏は現在、38歳の若さながら鹿児島市議会議員を2期務めている将来有望な若き政治家であります。井上氏は地元・鹿児島に生まれ名門・鶴丸高校を卒業しました。大学卒業後は地元のシンクタンクに就職し地域づくりの政策作成に携わりました。平成12年4月に、鹿児島市議会議員に初当選し現在に至っております。(下の写真)井上氏とは大学のサ-クルで知り合ったのですが当時、私は3年生で彼は1年生でした。このサ-クルは形式上は文科系に属しますが中身はまさに体育会系でした。しかし体育会系特有の“上級生に服従”という体質は薄く“あわよくば上級生を痛めつけてやろう(肉体的にではありません。)”的雰囲気がありました。私は、後で知りましたがこの体質は大昔からの伝統だそうです。何せ年号が平成に移ってからこのサ-クルから3名も総理大臣を輩出していますので門を叩く学生も一癖どころか十癖もある連中ばかりです。学生サ-クルにもかかわらず派閥があり確執、怨念渦巻くドロドロとした活動を送ることが出来ましてそれなりの緊張感を味わうことを余儀なくされました。私のような精神が純粋で小心者はその体質に馴染めず、何度も“退会”を申し入れましたがついに聞き入れてもらえず4年間、男性ばかりのサ-クルで過ごしてしまいました。今回、井上氏から聞いて初めて知ったのですが井上氏はこのサ-クルを途中退会していたそうです。正義感が強く純粋な井上氏なりの苦悩があったようです。実は私と井上氏は当時、異なった派閥に属しており、深い交流はありませんでした。それゆえ、私が大学卒業してからは全く交友は途絶えておりました。今回の井上氏との再会は私の同期の仲介によるものでした。この同期も鹿児島出身で井上氏の高校の先輩にあたります。仲介の労を取ってくれたこの同期にも感謝しております。鹿児島滞在最後の夜に井上氏が予約してくれたお店は鹿児島市内でも屈指の名店「あぢもり」さんです。(鹿児島市千日町13-21 電話番号:099-224-7634)「あぢもり」さんは“さつま黒しゃぶ”が売りのお店です。今でこそ、鹿児島の黒豚(肉)は全国でもその名を轟かせておりますが本来、豚肉は淡白な味ゆえ、しゃぶしゃぶにはなじまないとされてきたとのことです。しかし「あぢもり」さんでは、厳選された良質の黒豚を使用し独特のス-プをあみ出した結果、あっさりとしたなかにも濃厚な食感のしゃぶしゃぶを提供しております。因みにさつま黒豚が日本にやってきた時期は何と江戸時代初め とのことです。発祥はアジア東南部で中国、台湾、琉球(沖縄)を経て薩摩(鹿児島)に渡って来たそうです。私は5年前にこの「あぢもり」さんで食事をしたことがあります。しかし、その当時は黒豚料理の知識が乏しく「あぢもり」さん売りの料理が何なのか判りませんでした。確か札幌でも食することの出来るオ-ソドックスなしゃぶしゃぶコ-スを注文した記憶があります。井上氏との待ち合わせ時間少し前に到着した私と妻は2階の個室に案内されました。既に井上氏は到着しているとの事。店員さんが障子貼りの個室の戸を静かに開けると懐かしい顔が私の目に飛び込んできました。冒頭の写真のような明るい表情で「先輩、お久し振りです。」と井上氏。爽やかさは学生時代と変わっていませんでした。とかく議員になると横柄になる愚か者が多い中で井上氏は礼儀をわきまえておりました。私も「久し振りです。それにしても学生時代と変わっていないねえ。」と言いました。掘りごたつの席に腰を落ち着けてからまずは飲み物の注文へ。私は体調が回復してきたとはいえ用心のためウ-ロン茶を注文しました。井上氏と妻はビ-ルを注文。その後乾杯。井上氏と妻は初対面でしたが、政治家である井上氏は積極的に妻に話しかけてくれました。“とんかつ”に舌鼓を打ちました。脂身が少ないにもかかわらず柔らかな肉質に満足しながら井上氏と妻を見るとビ-ルに合う様で表情も豊かでした。ビ-ルを飲むことの出来ない私は羨ましく感じつつも“とんかつ”をじっくりと味わいました。それにしましても先付けに“とんかつ”というのも鹿児島らしいですね。(以下続きます。)
2007.11.25
コメント(4)
-

西郷南洲翁生誕180年記(17) by 北洲
確かに西郷先生は貧困の中に誕生し成長していきました。西郷先生は終生、贅沢を嫌い質素を旨とされていたようです。それは幼少時の貧しい生活が体にしみ込んでいたせいかもしれません。では一体、当時の西郷家がどれ位、厳しい生活を強いられていたか記します。西郷先生には自身を含め7人の兄弟姉妹がいます。両親を含めると合計9名の大家族です。しかし西郷先生の父親の年収は現在に換算すると約250万円だったそうです。9名の家族が約250万円でやりくりすることは想像を絶する節約を余儀なくされるでしょう。通常であれば貧困から逃避せんとして今で言う“アウトロ-”的行動に走っても不思議ではありません。しかし西郷先生は貧困を理由に道を誤ることはありませんでした。一貫して王道を正々堂々と歩まれたのです。それは何故でしょうか?第一に西郷先生の母親が偉かった と私は思います。西郷先生の母親は常日頃、西郷先生に「貧乏を恥じることはありません。貧乏に負けることが恥ずかしいのです。」と言い聞かせていました。西郷先生は母親の教えを胸に刻み成長されたのです。もちろん母親自身も立派な行いを実践していたのでしょう。いくらきれい事を口にしても行動が伴わなければいくら子供とはいえ瞬時に見抜いてしまいます。実際、西郷先生と兄弟達は冬の寒い日でも布団が1枚しか無く皆がが足だけを布団に突っ込み寒さを凌いでいたそうです。下の家で生活していた頃も決して裕福とはいえなかったようです。場所は生誕の家からそれ程離れてはいません。次に訪れたのは西郷先生が3回目の引越し をされた屋敷です。通称“西郷屋敷”と呼ばれているその家はJR鹿児島中央駅の裏側にあります。住所が武という関係上、武屋敷とも呼ばれています。この屋敷は西南戦争勃発まで住んでいたいわば終の棲家です。この屋敷は西郷先生がいわゆる“征韓論”に破れ明治新政府に辞表を提出し帰郷(明治6年)してから住みました。帰郷後の西郷先生は政治の世界から離れ毎日、畑を耕し肥溜の桶を担いで汗を流していました。ほんの少し前までは実質的な総理大臣の地位にあった西郷先生ですが、こうした自然のなかでの生活の充実間を味わっていました。その家族にとっても久し振りの水入らずで、やっと得られた家族との団欒を楽しんでいた西郷先生のお姿が目に浮かびました。この屋敷には西郷先生を慕う大勢の者が訪問しました。西郷先生の教えを乞いたいという意図なのでしょうが余りの数の多さに西郷先生は居留守を使うことも度々だったそうです。その中でも、山形・庄内藩からやってきた一行は手厚いおもてなしにあずかったようです。明治8年、庄内藩家老・菅臥牛さんもその一人で西郷先生をは肝胆あい照らす仲だったようです。意見交換する西郷先生と菅臥牛さんの像です。そもそも西郷先生と庄内藩の人間は先の戊辰戦争において敵と味方の関係でした。幕府側の立場にあった庄内藩は幕府敗北後、厳罰を覚悟していました。しかし意外な程、軽微な処罰で済まされました。驚く庄内藩関係者が怪訝に思いその理由を調べたところ敵の総大将である西郷隆盛先生が黒田清隆に「穏便な処置をとるよう。」指示をしていたのです。すっかり感激した庄内藩の人達はすっかり西郷先生の崇拝者へと変貌してしまいました。“勝てば官軍負ければ賊軍”とは世の中の常ではあります。しかし西郷先生は敗れた者に対し慈悲の念を抱いておりました。それは「敗北者が必ずしも悪というものでもない。全ては時の運。勝者も敗者も紙一重。」という西郷先生なりの哲学があったと思われます。西郷先生自身、常人には耐えることの出来ない辛酸を嫌と言うほど経験されております。そうであるからこそ、敗北者の心情は人一倍、理解できたのでしょう。こちらは井戸の跡です。西郷家で使用される水はこの井戸から汲み上げられておりました。自分の身の回りのことは自分で行う西郷先生のことですからきっと、水も自分で汲んでおられたでしょう。この“西郷屋敷”は現在、公園として利用されてもおります。5年ぶりの“西郷屋敷”訪問に西郷先生の生活臭を感じつつ一旦、ホテルに戻りました。夜は後輩との会食が控えております。この後輩は私が大学生の頃に所属していたサ-クルの後輩です。私が3年生の時、彼は1年生でしたのでそれ程深い関係ではありませんでした。しかし17年振りの再会に学生時代のノスタルジ-も手伝い、私の精神は高揚しておりました。その後輩は現在、鹿児島市議会議員の要職にある井上剛氏です。
2007.11.21
コメント(0)
-

西郷南洲翁生誕180年記(16) by 北洲
終焉の地石碑が建てられている場は完全な住宅地なのです。向かって左隣は大規模マンションがあります。今年は西郷先生の130回忌にあたるせいか、花が添えられており例年とは異なった雰囲気でした。更にボランティアの男性が待機され訪問された方に石碑等の説明をされておりました。暑い中本当にご苦労なことです。私が記念撮影をしたり石碑に手を合わせているのを見ていたこの男性が私に「鹿児島の方ですか?」と尋ねてきました。私が「いいえ、札幌から来ました。」と返答すると大変、驚いておりました。この男性が仰るには「現在の鹿児島市民の半数は本日(9月24日)が西郷先生の命日に該当することを知らないのではないか?」とのことです。それゆえ遠い北海道からはるばる命日に合わせやってくる人間の存在に驚かれたのでしょう。そういえば今から5年前、私が初めてこの地を訪れた際の出来事を思い出しました。この時は巡回観光バスで西郷先生ゆかりの場所を移動しておりました。終焉の地バス亭を下車後、地図を頼りに探していましたがなかなか見つけることが出来ずにおりました。その時、まだ20歳前と思われる女性が近くを歩いておりましたので道順を訊いてみました。するとこの女性は「わかりませんね。」との答えが返ってきました。そして、それから暫く考えた後「そういえばそういうものが私の自宅近くにあったかもしれません。」と仰ったのです。結局、この女性に案内してもらいようやく到着することが出来ました。それにしても近所の住民でさえも西郷先生にゆかりのある場所を意識していないことに意外な感想を持った記憶があります。しかしこのボランティアの男性のように猛暑の中待機されている方がいらっしゃるのですからまだまだ西郷先生を慕う市民も存在するのです。再び終焉の地石碑に手を合わせ「宝山ホ-ル」に向かいました。「宝山ホ-ル」は西郷隆盛像の向かいに位置しております。これから稲盛会長を初めとする方の講演等が行われます。会場に到着しますと長蛇の列に気付きました。当日入場の方達でしょう。私は事前に予約しており、しかも西郷南洲顕彰館会員ゆえ待たずに入館出来ました。しかも席は前列でした。開演までまだ少し時間がありましたので会場を出て入口近くを歩いていましたら小松帯刀像に遭遇しました。薩摩藩きっての切れ者老中でしたす。そういえば小松帯刀という銘柄の焼酎も存在しますね。そういえば先程、南洲神社で私にインタビュ-をされた女性に会いました。「先程は有難うございました。」との丁重な御礼をいただきこちらも恐縮した次第です。開演の時間になったので会場に入りました。講演前に西郷隆文氏(西郷先生の曾孫)のご挨拶。続いて島津義秀氏による薩摩琵琶「城山」の演奏。一日に二度も薩摩琵琶を聞くことが出来るとは幸せこの上ありませんでした。島津義秀氏はその名から判る通り鹿児島県加治木当主の末裔に該当するそうです。現在はNPOの代表として様々なご活動をされていらっしゃるようです。続いて、稲盛会長の講演が始まりました。その内容についてですが、私は以前から稲盛会長が書かれた著書を拝読しておりましたのでそれ程、新鮮味はありませんでした。(失礼)しかし崇高な理念を持った偉大なる経営者の講演を間近で拝聴出来たことは大変、良い思い出となったように思います。何と言っても西郷先生の影響を受けた方が日本を代表する経営者になられたことが嬉しくもあるのです。稲盛会長は“西郷南洲に学ぶ”とのサブタイトルを冠した新著を出版されたばかりです。私はまだ拝読していないのですが年内にはひもとくつもりです。本講演後にも講演等はありましたが時間の関係もあり中座することに。昼食をとっていませんでしたので徒歩で繁華街み向かいました。山形屋さん近くに有村屋さんと並ぶさつま揚げ の名店・揚立屋さんがあります。こちらは店内でさつま揚げ を食べることが出来るのです。今年も出来立てのさつま揚げをいただくことが出来ました。その味は格別です。更に、焼酎のロックがあれば言うこと無いのですが・・・・・・。因みに有村屋さんのさつま揚げは札幌市では東区のイト-ヨ-カド-(アリオ)さんで販売されています。(昨日、購入して来ました。)少し散策したのち本格的な昼食をとることにしました。山形屋さんに入り店内のレストランにてビ-フカレ-を注文しました。以前、TVで観たのですが、かの有名な山下清画伯がこちらのビ-フカレ-を好んで召し上がっていたそうです。桜島を眺めながら素朴な味に舌鼓を打った次第です。空腹を満たした後はまだ見学したことのなかった地へ行くことにしました。それは“西郷先生屋敷跡地”です。西郷先生生誕の地(加治屋町)は訪れたことはあるのですがこちらはノ-マ-クでした。この屋敷は西郷先生が明治維新前からその樹立後まで住んでいた屋敷だそうです。父親の代からの借金を返済するために生誕の屋敷を売却した後の屋敷です。西郷先生は想像も絶する貧困のなかに生まれ、貧困に負けずに成長された人物です。
2007.11.18
コメント(0)
-
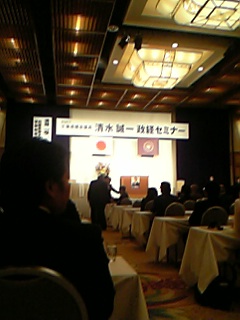
西郷南洲翁生誕180年記(15) by 北洲
昨夜は雪が降りました。気温が低くはなかったので湿った雪でした。とうとう本格的な冬の到来です。(12月生まれで冬が好きな私には過ごし易い季節ではあります。)昨日は札幌パ-クホテルで清水誠一道議会議員(帯広選挙区)のセミナ-が開催されました。講師は中川義雄参議院議員でした。中川参議は「今、私が思っていること。」と題しハゲタカファンド批判・地方軽視の政治を批判されました。更には真の保守政治による改革の必要性を訴えられました。突如、「平沼赳夫さんのような真の保守政治家とスクラムを組んで日本を誤った方向に進ませない!」とのご発言。一番主張されたかったことはこの点なのでしょうか。(笑)でも私も同感です。では前回の続きといたします。西郷南顕彰館は南洲神社に隣接しております。本館は昭和52年建設着工されました。その建設費用は西郷隆盛先生を敬愛する全国の方からの寄付でまかなわれたそうです。構造は二階建てですが決して大きな建物ではありません。余談ですが本館駐車場から眺める桜島も絶景です。城山頂上から眺める桜島の美しさはいうまでもありませんがこちらは城山よりも低位置にありますのでちょうど自分の目線で眺めることが出来ます。西郷先生達のお墓もこの高さに位置します。西郷先生たちは桜島をご自身と同じ目線で眺めておられるのです。特に“他人に対し偉ぶらず自身と同じ目線で接された”西郷先生にとっては格好の場所であるのかもしれません。こちらは西郷南顕彰館入口です。西郷南顕彰館の入場料は大人100円です。今のご時世で安い入場料であると私は考えます。せめて150円~200円が妥当かと勝手に思っております。因みに私はこちらの会員ですので入場料は無料です。私は毎年、こちらに入館しております。5回も入館していると、どこに何が展示されているかが頭の中に入っているのです。しかし何故か入館してしまいます。それは恐らく西郷先生の遺品を近くで眺めることにより、今は存在しない西郷先生に触れているかの錯覚を味わいたいからなのかもしれません。しかし今年は例年とは異なったイベントが開催されておりました。「西郷南洲生誕180年」を記念して秘蔵の刀の展示です。その内容は何と、西郷先生の首を刎ねた刀なのです。つまり西郷先生の介錯を務めた別府晋介さんが握り締めていた刀です。私はその刀を見るまでは「さぞや長い刀なのだろう。」と想像しておりました。しかし実際は刃渡り約60cm~65cmの決して長刀とは言えぬ代物でした。私はその刀を眺めながら考えました。“首を斬る際に痛みを感じさせず一瞬で事を終えるには仕損じは許されません。そうであるならば長刀は介錯には不向きでむしろ刃渡りが短い方が良いのかもしれない。”次に辺見十郎太さんが西南戦争時、戦地で使用されていた刀を見学することに。こちらは前記の刀とは全く異なり驚くべき長刀でした。その長刀に解説なされていました。内容は下記の通りです。「辺見十郎太の指揮刀。 新納武蔵守を祭った大口神社に奉納してあった刀を辺見が西南戦争の時、持って行った無銘・128cm」この解説から判断しますと、辺見さんは本長刀の使用目的を敵を斬るためではなく、部下の闘争心を鼓舞するために馬上から振り回すために使用していたのかもしれません。まさに闘将・辺見十郎太のための刀でしょう。この長刀に驚き前を離れずにいましたらすぐ側に館長の解説を真剣な眼差しで聞いていた初老の男性に気付きました。よく見ますと京セラ・稲盛会長でした。想像していたより背が高く歳をとられていました。そういえば今朝の風呂で似た方に会った気がしましたがメガネをかけていなかったので判りませんでしたが。午後からはこの稲盛会長の講演を聞くことになっています。何を語られるのか楽しみにしつつ西郷南洲顕彰館を後にしました。その講演まで時間がありませんでしたので昼食は後に延ばすとして“西郷南洲翁終焉の地”に向け車を走らせました。こちらは読んで字のごとく西郷先生が亡くなられた場所の跡地です。ということは別府晋介さんに首を刎ねられた場所です。城山の麓に位置するのですが西郷洞窟からそれ程離れていない場所です。西郷洞窟を発ってから弾丸の嵐のなかを下山しましたがさほど長い距離を歩いていないのです。いかに政府軍の攻撃が激しかったのかが理解できます。私はこちらも毎年、必ず訪問し石碑に手を合わせます。実はこの場所は西郷先生が亡くなった場所ではないのです。実際の場所は石碑が建っている場所より少し城山よりの位置だそうです。
2007.11.17
コメント(0)
-

西郷南洲翁生誕180年記(?) by 北洲
たった今、間違って文章を消してしまいました。どうも本仕組みを理解していないようです。機械に弱い人間はダメですね。というわけで本日はこの言い訳で失礼します。明日は帰宅が遅くなるかもしれませんので土曜日に雪辱戦を果たしたいと考えております。ただ言い訳で終了するというのも無粋ですので先々週、散歩ついでに携帯電話のカメラで写した北海道大学構内の色づいた木々を紹介致します。こちらは池で泳ぐカモです。新渡戸稲造先生像です。こちらは、イチョウの木でしょうか。
2007.11.15
コメント(0)
-

西郷南洲翁生誕180年記(14) by 北洲
昨日は久々の午前様(帰宅時間・1時30分)でした。確かにススキノからの帰宅であったことは間違いありませんが単に遊んでいたのではありません。昨夜、私の母校とそのライバル(友好)校の札幌支部交流会が催されたのです。場所は札幌プリンスホテルでした。実は、私にとってこの手の集まりへの出席は初めてでした。結局、3次会(ススキノ)まで参加しました。出席者の年齢は私よりも遥かに上の方が多かったですが先輩風を吹かすことも無く丁重に接して下さいました。中には北海道民であれば誰しもが知っている会社の経営者もおりその方から多岐に渡るお話を伺うことが出来たことは有意義でありました。また、北海道新聞の某役員もOBのようで月曜日にご馳走に与った私が私淑している方について共通の話題で花が咲きました。(世間は狭いものです。)何年か振りで校歌を2回も歌い少し喉が疲れましたが楽しい会でありました。では次回の続きを開始します。「私利私欲の無い指導者・西郷隆盛先生」との私の発言に対し女性レポ-タ-は更にこう質問をぶつけてきました。女性レポ-タ- 「私利私欲の無いリ-ダ-の台頭と言われましたが現在の政治は私利私欲無しに運営されているでしょうか?」さすがプロですね。私利私欲という表現から現在の政治状況を対比させるなどこの女性は相当、優秀です。私はこう返答しました。私 「今の政治家(国会議員)で私利私欲が無く、政治に携わっている人物はごく少数と思います。それは昨日、行われた自由民主党の総裁選を見れば判ります。」女性レポ-タ- 「それはどういうことですか?」私 「つまり派閥解消と口先だけは勇ましいですが実質的に一部の派閥の長の意向によって多くの国会議員は動いています。候補者の政策を聞いて支持の有無を判断するのでは無く寄らば大樹の陰になっています。」そして私は更にこう付け加えました。私 「今回の自由民主党の総裁選挙と130年前の昨日、鹿児島で起こった出来事があまりにも酷使しています。それは所属国会議員がわずか16人の少数派閥である麻生派に対しその他大勢の大派閥がぐるっと取り囲み勝負を決してしまいました。その光景は130年前の昨日、城山で新政府軍が薩摩軍に対し行った行為と何ら変わりはありません。現在も政界においてはその本質が変わっていないのです。」女性レポ-タ- 「それでは、もし今の世に西郷さんが存在していたらどのような行動を取ったと思いますか?」私 「難しい質問ですが、西郷先生は国民の待望論があれば命を投げ出す覚悟で戦っているでしょうね。」以上、内容の短いインタビュ-でありましたが私は特に黙考しつつ返答したのではありません。あくまでも無自覚のまま永田町から離れた立場で判断した感想をそのまま述べたに過ぎないのです。西郷先生の墓前でなされた上記のインタビュ-が、果たして放映されたのか否かは知る由もありません。ただ西郷先生がどのように感じられたのかは興味があります。それから私はお墓を正面にして右方向の式典会場に再び足を向けました。丁度、薩摩琵琶の演奏が開始されるところでした。私はこれまで琵琶の演奏すら聞いたことがありませんでした。静まり返った会場に琵琶の音色と詩が響き渡りました。もちろん前回紹介した「ぬれぎぬを果そうともせず~」の一節も詠まれました。心にグッとくるこの一節がまさに西郷先生の生涯を凝縮させているかのごとくです。同時に最後の幕臣・勝海舟の表現力にも感服した次第であります。こうして式典が終了した頃には暑さが増してきていた。薩摩軍兵士の墓の下にある階段を降りたところに広場があります。そこでは薩摩示現流の演武のが開催されておりました。あまりにも有名すぎる薩摩示現流であるが、私は初めての実演観戦(?)でした。成年、少年が入り混じった道場生(?)の演武はその技術もさることながら気合の激しさに度肝を抜きました。「チェスト-」 、 「キエ-」といった裂帛の気合です。私も武道を多少かじったので理解出来ますが、気合に満ちた相手と向き合った時は風圧ともいうべき力に圧倒されてしまいます。こちらが相手以上の気合を全身から発しなければ勝負の趨勢は決したも同然です。西南戦争時、にわか兵士が度々、薩摩軍の抜刀攻撃に恐れをなし逃げ去ったことはこの演武により納得出来ました。木刀、竹刀での組手。短刀(木製)による木材倒し。久々に武道の真髄に触れることが出来まして満足しました。演武終了後、満足感を抱えたまま私は会員になっている“西郷南洲顕彰館”に入場しました。南洲神社に隣接するこの“西郷南洲顕彰館”は文字通り西郷先生の偉業を称えんとして建立された西郷博物館とも呼べる建物です。
2007.11.10
コメント(0)
-

西郷南洲翁生誕180年記(13) by 北洲
札幌はすっかり冬の入口に入ったかのごとく気温が下がっております。私達を楽しませてくれた紅葉は少し茶色になってしまいました。そんな中、昨夜は私が私淑する北海道新聞社勤務の方との会食がございました。二人きりの会食でしたが、会話は多岐に渡る内容でしたので充実感で一杯です。この方も私のこのブログをご覧になられています。有難いことです。ついでに感想を伺いましたら「よく調べているね。」を連発されました。「文章が上手だね。」とは仰って下さいませんでした。 (笑)その方と別れた後、絶望感で一杯の私は“ウサ”を晴らそうとススキノに行こうと考えましたが余計に虚しくなると思いそのまま帰宅しました。まあ、私はアマチュアですから神経質になることもないのですが・・・・・・。それでは前回の続きと致します。私は相変わらず、私学校幹部のお墓を少し離れた所から凝視しておりました。お墓に近いところにいては他の墓参者に申し訳がないからです。こちらは“幻の初代総理大臣”である村田新八さんのお墓です。村田新八さんは、ただ単に西郷先生に対する“情”に殉じるために地位・名誉を捨てて明治新政府を去りました。「130年前の昨夜、村田さんは西郷洞窟でアコ-ディオンを奏でたのだなあ。」と感慨に浸っていたところ着物を着た精悍な若者が西郷先生のお墓に近づきました。若者はお参りをしようとしていました。とはいえ相変わらず多くの人が西郷先生の墓前に陣取り手を合わせたり写真を写しています。そのため若者は遠慮して彼らの後ろで手を合わせようとしました。すると一人の目つきが鋭い老人が若者に近づきこう叫んだのです。「おい、そんな後ろで手を合わせないでちゃんと墓の前で挨拶しろ!」若者は反論もせずに「はい、わかりました。」と言い西郷先生の墓前に向かい手を合わせました。私は少しホッとしました。しかし若者が西郷先生への挨拶を終えて踵を返した瞬間、またしてもこの老人が「そうだ、それが正しい挨拶の仕方だ。せっかく着物を着ているのだから、西郷から逃げるな!」と若者を一喝したのです。若者はまたしても「はい、すみません。」と頭を下げていました。目上の人間を立てる鹿児島の慣しとはいえ私は驚きでその場から離れることは出来ませんでした。しかし驚きの出来事はこれで終わりではありませんでした。呆然とする私の前に一人の女性が近寄り「失礼ですが少しお時間よろしいですか?」と話しかけて来ました。まさかこのような神聖な場所で逆ナンパでは無いと直感しましたがすぐにはこの状況を理解することは出来ませんでした。訝る私にこの女性は地元のTV局の名を告げ「インタビュ-をお願いします。」と依頼したのです。そういえば駐車場にTV局の車が数台、停まっていたことを思い出しました。通常であればお断りするのですが南洲神社において素っ気ない態度をとると先の恐い老人に恫喝される可能性もありますので応諾した次第です。以下相互のやり取りを列挙します。女性レポ-タ- 「今年はこんなに多くの方が西郷さんの130回忌にいらしていますが西郷さんのどういうところに魅かれて集まるのでしょう? 」私 「やはり何と言っても西郷先生の私利私欲のない生き方であると思います。人の上に立つ人物がわずかでも私心を持って事に当たるならばそれが行動に現れてしまいます。それでは下にいる人間の士気であるとか意欲は激減します。」女性レポ-タ- 「他にはありますか?」私 「極めつけは西郷先生の慈悲深さです。城山において弟子を敵に売ることなく共に戦死したことですね。人間は究極の場面において初めてその本性を表しますから。本日、集まった人は西郷先生の潔さにも敬服の念を抱いていると思います。」これでインタビュ-は終了かと思いましたが女性レポ-タ-は更にマイクを向けてきました。普段は冗談ばかり口にする私ですが西郷先生について論じる時だけは真剣になります。恐らくこの女性レポ-タ-に対し真剣さが伝わったのかもしれません。続きは次回に記します。上記の石碑はこの南洲神社にあります。西郷先生の友人であった勝海舟が西郷先生を偲んで読んだ詩を刻んでおります。私が上記で述べた西郷先生の弟子に対する慈愛を勝海舟は的確に表現しています。何か世間の批判にさらされた時に「秘書がやったこと。」と自己弁護に走る、政財界人にはこのような詩は詠まれないでしょうね。西郷先生は一切の弁解をせず、妻と小さい子供達を残して弟子達と心中しました。
2007.11.06
コメント(0)
-

西郷南洲翁生誕180年記(12) by 北洲
「一体この人間の多さは何だろう?」とさえ思ってしまう程、今年の南洲神社は賑わっていました。やはり西郷先生生誕180年(没後130年)という節目のせいであろうか昨年とは全く異なった様相をみせていた南洲神社でありました。その数ざっと300名(目測で)。地元TV局も数社取材に来ていました。喧騒のなかで私はまず西郷先生のお墓参りをしました。今回の鹿児島訪問の第一の目的はあくまでも西郷先生のお墓参りなのです。こちら(上)が西郷先生のお墓です。西南戦争で亡くなった多数の薩摩兵士を従えているかのごとく南洲神社の中央最前列に位置しております。正面は鹿児島のシンボル・桜島がそびえております。私は西郷先生の墓前で手を合わせ「混迷する日本国の光明を見出すきっかけをいただきたい。」ということと「皇室の繁栄が続きますように。」とお願いして参りました。例年ですと参拝客が少数のため西郷先生の墓前で更に多くのお願いを申し上げたり“会話”をさせていただくのですが上記で述べたように多くの人がみえております。西郷先生を独り占めするわけにもいかず早々に墓前から退きました。今年は献花が多く岩手県知事から立派な御花が届いておりました。達増知事は西郷先生の信奉者なのでしょうか?余談になりますが私は西郷先生のお墓に来る度にお供えとして北海道の菓子を持参します。甘いものが好物だった西郷先生が喜びそうな菓子を出発前の新千歳空港で選びます。今年は柳月(りゅうげつ)というメ-カ-の主力商品の“三方六”をお供えしました。 “三方六”は種類としてはバ-ムク-ヘンです。写真向かって右下に見ることが出来ます。神社の式典は10時に始まりました。この日は朝から気温が上昇し10時過ぎとはいえ北海道から来た私にとっては結構、きつかったです。式典は厳粛に進められ関係者の挨拶に始まり身内の方々の玉串奉てんが行われました。西郷先生の御身内からは3名の方が代表で奉てんされていました。その中のお一人は陶器家で有名な西郷隆文氏です。地元日置市で窯を持たれ薩摩焼を生業とされているようです。西郷隆文氏始め皆さん大柄で西郷先生の血を受け継がれていることが容易に理解できました。御身内の方以外では京セラ・稲盛会長、鹿児島市長、鹿児島選出の国会議員(代理)などが参列されていました。式典は大変長く私は途中で南洲神社に祀られているお墓全てをまわることにしました。私学校幹部以外の方の墓が多く私自身、お名前を存知申し上げないのですが「130年前は、おやっとさあでございました。(お疲れ様でした。)」と心の中でつぶやきました。その後、西郷先生のお墓に再び戻りました。西郷先生のお墓は先程と変わらず多くの方が手を合わされており人気の高さにあらためて敬服した次第です。そういえば西南戦争時、鹿児島県外から応援に来ていた若き武士達がいました。彼らは戦争末期に西郷先生から「あなた達は鹿児島の人間ではないのだからもう故郷に戻った方が良い。お命を大切にして下さい。」と申し渡されたそうです。ほとんどの者は西郷先生の言葉に従いました。しかしある増田宋太郎という中津出身の武士はこう言って最後まで残りました。「私は城山に入って初めて西郷先生に会い、景慕の情に堪えない。先生に一日接すれば一日離れられず。十日接すれば十日の愛を生じて離れることは出来ない。私は西郷先生と生死を共にする決心です。」今の日本ではあり得ない師弟愛が130年前の鹿児島には存在していたのです。そうした西郷先生への情愛は他の幹部は更に強固なものであったでしょう。その代表格である桐野利秋さんのお墓は正面向かって西郷先生のお墓の左に位置しています。薩摩藩屈指の剣豪として暗殺者から西郷先生の身を守った桐野さんは死してもすぐ横で西郷先生を守っているかのようです。こちらは城山で西郷先生の介錯をした別府晋介さんのお墓です。西郷先生が別府さんに発した最後の言葉は「晋どん、もうここらでよか。首を刎ねてくれ。」でした。毎年のことですが、私はつい西郷先生のお墓の周辺から動かなくなります。西郷先生に接したことのない私もお墓に接しただけで離れられなくなるのです。
2007.11.04
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1