2018年08月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

「8月31日 脱原発みやぎ金曜デモ」 リヤカーを曳いて放射性プルームから逃れられるか?
10年ほど前から「サラ・コフマン」という名前を知っている。正確に言えば、『サラ・コフマン讃』という本の背表紙を何度も何度も眺めていた、ということに過ぎないのだが。 定年退職してから図書館に通い始めた。仙台市立図書館の哲学のコーナーにその本は並んでいた。パラパラめくってみると、フランスの哲学者サラ・コフマンへの追悼文集のようで、知らない著者名のなかにジャン=リュック・ナンシーとジャック・デリダの名前が並んでいた。 ナンシーとデリダの名前に惹かれて借り出そうとも思ったのだが、私はコフマンの名前は初めてで、彼女の著作などまったく読んでいないのである。それで、コフマンの著作を検索したら市立図書館には一冊もないのだった。 小説は読まずにその書評だけを読むみたいなことはいやだな、そう思って書棚にそっと返した本で、それ以来図書館に行くたびに背表紙を眺めるだけの本だった。 ところが、最近、哲学のコーナーに読みたい本がほとんどなくなってしまった。哲学の本は山ほどあるのだが、わずかしかなかった読みたい本はほぼ読み終えたのである。読書の守備範囲が狭い人間の悲しさである。 それでつい『サラ・コフマン讃』を借り出してしまったのだ。小説も読まずにその書評を読もうというのである。借り出し手続きをしながら、妙にめげてしまった。 読み始めたら、ジャン=リュック・ナンシーの次のような一文が出てきた。サラはニーチェというすベての名を演じることに参加したかったのだ。彼女はこの柔軟性にぴったりと寄り添いながらも、これらすベての名が「女になる」ようにしくむ――すべての哲学者の真実であるかのように。あたかもすべての名がサラという唯一の女の名に戻っていくかのように。他のすべての柔軟性を名づけるのに女という名が使えるかのように。「サラというこの女を見よ」と送ってくれた『爆発I』に彼女は書きつけた。おそらくは他の人たちにもこう書いたにちがいない。 「哲学者」でも「女性哲学者」でもなく、むしろすベての哲学者の妻そして彼らの「競争相手」。しかしまた彼らの真理と彼らの論理の生命。つまりは彼らの母、姉妹、恋人、そしてそれ以上に哲学「それ自身」と言ってよかった。哲学をからかい、際限なく追い越し、ひいては哲学なしで済まし、結局は他のどんな言説の流れよりもほの暗い濁ったむき出しの生々しい流れに哲学を引きずりこんでいく。 [1] もちろん、この文章ではコフマンの哲学の気配、匂いすらほとんどわからないのだが、「哲学をからかい、際限なく追い越し、ひいては哲学なしで済まし、結局は他のどんな言説の流れよりもほの暗い濁ったむき出しの生々しい流れに哲学を引きずりこんでいく」という一文は、明らかに挑発的である。ナンシーにかコフマンにか判然としないが、たしかに私は挑発されているのである。 あらためてサラ・コフマンで検索すると、あいかわらず仙台市立図書館には『サラ・コフマン讃』しかなかったが、宮城県図書館では3冊見つかった。それでも、県の図書館まで借りに行くかどうか、微妙に躊躇っている。私にとって読むに値する本かどうか読んでみなければわからないに決まっているが、なにか微妙な感じで自信がないのだ。 それに、年々、県立図書館がどんどん遠くなってしまうような気がして億劫なのもあって、躊躇いから抜け出せないでいる。錦町公園から一番町へ(定禅寺通り)。(2018/8/31 18:39~19:10) 小雨が降り続いている。雨に濡れることを覚悟して、上から下まで夏山登山の格好で家を出た。登山靴ではなかったが、もらったばかりの息子からのお下がり(お上がり?)のトレランシューズがじつにぴったりとフィットして、足元も軽快である。 さすがに人は多くない。屋根付きテラスの下に集まっているのは20人ほどだ。こじんまりとした集会に拡声器は不要だと、マイクなしでスピーチをする人もいた。東海第二原発、県内で始まった放射能汚染ゴミの一般ゴミ混焼時の空間線量増加、トリチウム汚染水などがスピーチの話題になった。一番町(1)。(2018/8/31 19:20~19:22) 少し前、フェイスブックに一枚の地図が掲載された。原発の30km圏内に住む人口を地図表記した図である。東京新聞が自治体に問いあわせたうえで作成したものだという。 なかでも、もっとも人口が多いのがフリースピーチの話題にもなった東海第二原発で、96万人が30km圏内に暮らしている。東電1F事故の放射能汚染のことを考えれば、東海第二の事故による放射能汚染が東京を襲うのは確実で、そうなれば96万人などというレベルではなくなる。 次に人口の多いのが浜岡原発の84万人、さらに柏崎刈羽原発と島根原発の47万人と続いて、500万人近くが30km圏内に住んでいることになる。これだけの人々が東電1F事故で故郷を追われた福島の人たちと同じような運命の可能性を背負って生きているのである。もちろん放射能が30km圏内に止まってくれる科学的根拠はまったくないので、その可能性は1000万人程度まで広がっていると考えるべきである。 こうした過酷な運命の可能性を除去するのは、現在稼働している原発を止め、動いていない原発の再稼働を行わず、そしてすべての原発を廃炉にするしかないのは言うまでもない。たかだか蒸気タービンのためのお湯を沸かすだけの施設としては原発はあまりにも不合理である。一番町(2)。(2018/8/31 19:29~19:30) 8月21日付の東京新聞電子版に東海第二原発の事故時の避難に関する記事が掲載された。原発の30km圏内に自力で逃げられない高齢者や障害者ら「要支援者」が約六万人住んでいるが、避難時の移動手段はまったく確保されていないというニュースである。 自宅から一時集合場所へ移動させる手段もなく、集合場所から避難所まで移動する方法もまったくの白紙状態だという。避難計画が不十全なまま東海第二原発の再稼働が進められれば、「要支援者」は行政に見捨てられる可能性が極めて高くなってしまう。 行政とは異なり、同じ地域に住む隣人にとってそれは深刻な問題である。記事は町内会の話題に言及している。 原発から西へ約十五キロの那珂市の上宿第一自治会。後藤只男会長(71)は、もともと地震などの災害用に購入したリヤカーを前につぶやいた。「原発事故でも使えるのではないかと。リヤカーに人を乗せるのは申し訳ないが、使えるものを使うしかない。本来なら、福祉車両が迎えに来てくれればよいが」 放射性プルームが飛び交う下で、リヤカーでひとりひとりを運ぶのはきわめて危険で困難な仕事だ。町内会のみなさんの真剣で必死な思いに水を差すようなことは控えたいと思うものの、それでも私にはほとんど無理な望みのよう思える。みんなで一緒に高線量被曝という結果になってしまうのではないか。 何とか誰にとっても安全な避難方法がないかと思うのだが、せめてそのような避難手段が確保されないかぎり再稼働をしない、再稼働をさせないということが必須だろう。 そして、じつのところ、そのような全員の安全を担保する避難方法は存在しないというのが本当のところだろう。再稼働どころか、廃炉にして原発事故の確率をゼロにすることがもっとも最良な安全策なのだ。青葉通り。(2018/8/31 19:34~19:43) 一番町のアーケードから青葉通りに出ると、雨はほとんど降っていなかった。気温は高くなかったが、ここまで歩いてくるとやはりじっとりと汗ばんでいた。 小雨が降った後のデモだった先週も、まったく同じことを思ったのだが、街灯のある街を歩いているのに闇が深いという印象なのだ。さすがに一番町を歩いているときはさほど感じないのだが、定禅寺通りや青葉通りでは街灯の光もビルの窓明かりも車のヘッドライトですらどこか無駄に闇に吸い込まれていくように見えるのだ。どうしてだろう? [1] ジャン=リュック・ナンシー「クール、サラ!」F.コラン他(棚沢直子他訳)『サラ・コフマン讃』(未知谷、2005年)p. 54。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也) 小野寺秀也のホームページブリコラージュ@川内川前叢茅辺
2018.08.31
コメント(4)
-

「8月24日 脱原発みやぎ金曜デモ」 デモでかく汗にトリチウムが……なんて悪夢だ!
盆も過ぎればすっかりと秋になる、それが仙台人の常識のように思っていたが、今年はまるっきり違う。また暑さがぶり返し、それに降雨も混じる日もあって、湿度の高い不快な日が続いている。 今日も午後になって少し雨が降って、その雨が降りやんだ後は下がっていた気温がもとに戻って、急激に湿度が高くなった。じっとしていれば何とか汗は出ないが、デモに歩き出すとたくさん汗をかくだろうと、何もしないうちからがっかりしている。そう思うだけで汗がにじんでくるようだ。 湿度と明るさは関係がないだろうと思うものの、街を取り囲む闇はいつもよりずっと深い。そういえば、集会もデモも夕焼けなどと関係ない時間になってしまった。あまり暑さが続くので、季節は巡って、日が短くなっていることにようやく気付いた。 金デモといういわば定点観測の機会があって、やっと季節の微妙な変化に気づくのである。風流人とは真逆を行く暮らしぶりである。花鳥風月を詠う俳句が苦手なわけだ。勾当台公園から一番町へ。(2018/8/24 18:44~19:07) 勾当台公園に着き、野外音楽堂までの階段を上がると集会も間もなく終わるという時間になっていた。その時スピーチをしていた人の話から、東京電力福島第1原発が太平洋に捨てようと画策している放射性物質トリチウムを含んだ水に、他の放射性物質が残留しているというニュースが集会の話題として話されていたらしい。 トリチウムをめぐる話題には、くつかの問題が錯綜していて、問題を簡単にまとめるというのはなかなか難しい。 ひとつは、トリチウムは低エネルギーのβ線を出すだけの放射性核種で、生体内に濃縮もしないので比較的安全な放射性物質だと政府や東電が喧伝し、それが海洋放出の根拠になっていることがある(もちろん、これは間違っている)。 もう一つは、汚染水からトリチウムを除去できないのは当然だが、現状の技術ではほかの核種も十分には取り除けないという事態がはっきりしたことである。ここには原子力工学・技術の問題がある。 そして、トリチウム問題は、放射性物質を何らかの方法で薄めれば捨てることができるとする自然環境についての根本的に誤った考え方を前提としているという救いがたい問題もある。一番町(1)。(2018/8/24 19:11~19:14) トリチウムは水素(H)原子核の同位体で、陽子1個だけの水素原子核に2個の中性子が結合した原子核を持つ。「セシウム137」のような呼び方をすれば「水素3」と呼ぶべきだが、3個の核子(陽子と中性子)を持つという意味でトリチウム(三重水素)という名前が付けられている(ちなみに、同じ水素の同位体で陽子1個と中性子1個の「水素2」は核子2個という意味でデューテリウム(重水素)と呼ぶ)。 トリチウムは半減期12.32年の放射性核種で、18.6keVのβ(ベータ)線を放出して「ヘリウム3」という安定な原子核に核変換する。β線は原子核から放出される電子のことだが、この18.6keV(18,600eV)というエネルギーは、たとえばセシウム137が放出するβ線の0.512MeV(512,000eV)の3.6%にしかならない。 低エネルギーβ線であるということが「トリチウムが生体に及ばす影響は小さい」ということの一つの根拠になっている。そして、法は周辺監視区域外のトリチウムの水中濃度を1リットル当たり60,000ベクレルまで認めている。これはほかの核種の100倍に相当する量である。 たしかにトリチウム原子核1個の放射線の影響は小さいが、セシウム137の100倍の数が存在すれば、放射線エネルギーは3.6倍になってしまうので、何の前提もなしに「トリチウムが生体に及ばす影響は小さい」と主張することは許されない。 ちなみに、事故前の東電福島第1原発は、じつに年間1.4~2.0兆ベクレルものトリチウムを太平洋に垂れ流していた(「平成23年版(平成22年実績)原子力施設運転管理年報」)。 2013年12月時点で東電1Fがタンクにため込んでいたトリチウムは800兆ベクレルに達していると報告されているので、現在では1000兆ベクレルを越えているのではないかと推測される。つまり、かつての年間放出量の500年分に近いトリチウムを薄めて太平洋に垂れ流したいと原子力規制委員会は主張しているのである。 しかし、東電2Fのタンク群に貯められていた汚染水にはトリチウムばかりではなく、半減期1570万年のヨウ素129や28.79年のストロンチウム90などが含まれているというのが今回のニュースだったのである。汚染水はトリチウムだけを含むという海洋放出の議論の前提そのものが崩れてしまったのである。一番町(2)。(2018/8/24 19:14~19:23) トリチウムは生体内に蓄積(濃縮)されない、という主張も「トリチウムが生体に及ばす影響は小さい」という言説の根拠にされているが、これもきわめて疑わしい。 トリチウムの生物濃縮はないという主張は、私の知る限りでは高度情報科学技術研究機構(旧原子力データセンター)という政府機関がしているが、これは実験したわけでも実地観測したわけでもないただのシミュレーションということらしい(つまり、まったくあてにならないのだ)。 それに対して、イギリス食品基準庁が1997~2007年の調査から生物濃縮が起きていることを報告している。それによれば、 5~50Bq/Lのトリチウムを含む海水に生息するヒラメは4,000~50,000Bq/kg、二枚貝イガイは2,000~40,000Bq/kgのトリチウムを取り込んでいて、その濃縮率はじつに2,300~3,000倍に達しているというのである。 これはβ線エネルギーで比較すると72~1,800Bq/kgのセシウム137に相当する。これは、日本のきわめて緩い規制値をもってしてもヒラメやイガイのほとんどはアウトということである。トリチウムがとくに危険性が低いという根拠はないのである。 トリチウムの危険性に関してはもう一つ重要なことがある。トリチウムは化学的には水素原子とまったく同じ挙動をする。それは、生体の主要な構成物としての水分子として体内に入り、あるいは、生体を構成する有機化合物中の水素原子と置き換わって存在するということである。これは、ヒラメやイガイで起きている生物濃縮はほとんどすべての生物で起きている蓋然性が極めて高いことを意味している。 化学的には水素と同じであるということは、ヨウ素やセシウムやストロンチウムのように甲状腺や筋肉や骨に偏在するのではなく、トリチウムは生体内のあらゆる場所にあまねく分布してしまうのである。生体のありとあらゆる細胞や遺伝子を破壊することができる。一つ一つの晩発性障害の確率が低くても、ありとあらゆる障害の原因となりうるのである。 このことについては、原子力村の住人たちは、証拠がないとか、そういう観察事例はないなどと主張するに違いないのだが、彼らが頼りにしているのは「見えないものは存在しない」という思い込みだけである。人間は見えないものに対して合理的な科学的推論ができる能力を持つということを無視するのである。 人間が放射性物質を環境にばらまき始めてからまだ100年も経っていない。個々の観測データが不足しているのは当然で、だからこそ慎重な科学的推論が必須なのである。 彼らは「見えないものは存在しない」と強弁し、見えそうになると見ないようにしてしまうのである。その典型的な例が、福島の放射能汚染地から線量モニターを撤去しようとしている政策に顕われている。放射能汚染がモニターを通して見ることができなくなれば、放射能汚染をないことにできると思っているのである。そこまでやるということは、単なる科学的思考、推論の能力の問題ではなく、明らかに人倫の問題であり、もうすでにそれは犯罪であるとしか思えない行いだ。青葉通り。(2018/8/24 19:24~19:27) 青葉通りに出ると、30人のデモの周囲に闇がぐっと押し寄せてくるようだった。今日はできるだけゆるやかに動こうと思っていたが、もうすでに汗で下着がぐっしょりとしている。 ずっと昔、沖縄の暑さに閉口していたとき、地元の人とペースを合わせて歩くと意外に汗をかかないということに気づいて、仙台に戻ってからもそうしようと思っていた。じっさいには、ゆっくり歩くから汗をかかないのか、汗をかかない程度にゆっくりと歩くのか、その加減がよくわからなくてあまり実用的なアイデアではなかった。 そんなことを思い出したが、写真を撮るためにデモの列の前後を何度も移動する身であれば、ただ単に思い出したということだけで、汗はひたすらに流れるだけで終わってしまったのだった。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也) 小野寺秀也のホームページブリコラージュ@川内川前叢茅辺
2018.08.24
コメント(4)
-
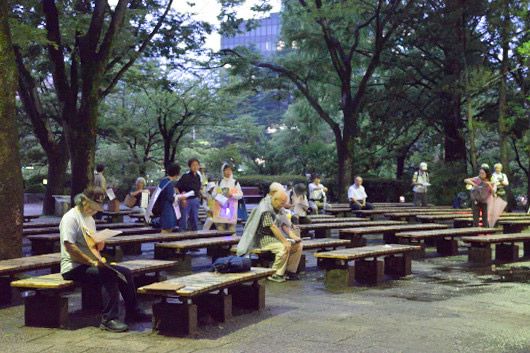
「8月10日 脱原発みやぎ金曜デモ」 沖縄に原発はないが……
2018年8月8日午後7時36分に沖縄タイムスのニュースメールが届いた。膵臓がんで入院中の沖縄県知事の翁長雄志さんが8日午後7時までに死去したことを報じる号外の記事だった。 7月27日に辺野古埋め立て承認を撤回するという重い政治的決断を表明してからわずか12日目の死である。その報の後、ネットには翁長知事の死を悼む言葉が溢れるように流れ出した。それぞれの追悼の言葉、哀惜する心情の一つ一つ激しく同意しながら、私は言葉がないのだった。 死の床にありながらも最後まで自らに課した政治的闘いを放棄しなかった死は鮮烈な政治的な死を死んだのだと受け止められているが、それはまた、夫であり父でもあった人間としての全的な死を死んだということでもある。 私は、数か月前から「体を使い切って死ぬ」ということをプチテーマにして日々の生活を見直し始めていた。しかし、67歳という私より若く苛烈な政治的死に突き進んだ翁長知事の死のニュースによって、そのような生のテーマは恥ずかしいほど不十分だと思い知らされた。 この年になるまで、私は一度も政治を志したことはないし、ましてや政治家という生き方を積極的に忌避してきた。だから、おそらくは政治的死とは無縁のまま死ぬだろうと思うが、せめて「身体と精神を使いきって死のう」とは思うのだ。それが翁長知事ばかりではなく、多くの政治的死者たちへのせめてもの礼儀だろうと思い直したのだ。政治をけっして志さなかった私にも、政治的意志はあるのだ。勾当台公園から一番町へ。(2018/8/10 18:39~19:13) 家を出る前に雨が降っていて、傘を片手に出たのだが、開くことなく公園に着いた。今日は珍しく遅刻をせず、私が勾当台公園に着いてから集会が始まったのだった。 言いにくいことだが、私が集会に遅刻するようになったのはもちろん意図的なことが始まりだった。論旨不明なスピーチと説教臭い演説がいつものことになってしまった集会をつまらないと思うようになったからである。もちろん、フリースピーチなので文句を言う筋合いではないし、大切な告知やとても良いスピーチもあるのだが、その抱き合わせで我慢できるほど私は忍耐強くもないのである。 来週はお盆のため、金デモは休みとなる。二週間後からの金デモも遅刻しそうな気配がしている。一番町(1)。(2018/8/10 19:13~19:19) かなり湿度は高いが、夕暮れになって気温が下がったので、まずまずのデモ日和(夜のデモに「日和」というのは変?)となった。 世間は夏休みということなのか、一番町はよく賑わっている。こう書いていて、どうも私はデモで一番町を通るときは、いつも「いつもより人出が多い」と思ってしまうようだ。何度も同じことを書いている気がする。 いずれにせよ、35人のデモは通行人が多いほど元気が出るので、一番町の賑わいはいいことには違いない。一番町(2)。(2018/8/10 19:20~19:25) 先日、仙台市図書館に行ったのだが、蔵書の整理期間の延長とかで臨時休館となっていて、暑いなかで街の本屋巡りとなった。その成果は、絓秀実さんの『革命的な、あまりに革命的な』という本だった。副題に「「1968年の革命」史論」とある。 めくってみると、〈1968年〉は世界革命だとするウォーラースティンが引用されていたり、日本の〈1968年〉を単なる挫折と評する史観は正しくないという趣旨のことなどが書いてあった。 私は、若いときのことを思い出すということにあまり気が向かないのだが、福島泰樹の短歌評のなかに吉本隆明が次のような文章を記していたことがずっと気になっていた。戦後はブルジョア的にもプロレタリア的にも錯誤されてきた。また現代的にも反現代的にも錯誤されてきた。わたしたちは切断すべきものに執着し、貌を背けるべきものに貌を向けることで、無限の喪失を唱いつづけたのである。 [1]戦後において現実の権力と深層の権力とを二重に透視できない闘争はすべて無効であったし、いまも無効であることは論ずるまでもないことだ。 [2] この大きな括りに異論はまったくないのだが、その実相の細部まではとても思い及ばない。吉本隆明の言葉はずっと以前に読んだものだが、『革命的な、あまりに革命的な』を手にしたときに思い出して、60年安保はまだ幼かったが、若い私が生きた〈1968年〉前後を思い出し、考えてみるのは悪くないと思ったのだ。 『革命的な、あまりに革命的な』を手にしてから10日余り、翁長知事の死去のニュースがあり、「身体と精神を使い切って死ぬ」というテーマに思い至ったとき、この本を通じて若いときの私の精神のありようを確認しつつ、使い切るべき老いの精神というものが見えてはこないかと期待もしたのである。青葉通り。(2018/8/10 19:26~19:29) この数か月、「体を使い切って死ぬ」というテーマに沿って暮らしてきたので、使い切るべき身体の整備は順調である。写真を撮るためにデモの前後を走り回っても疲れるということはなくなった。少しだけ結果が出ている気がする。 さて、それでは「精神を使い切る」ためにはどうするか、それはこれからだ。さしあたって、デモを終え、家に帰り、『革命的な、あまりに革命的な』の続きを読むことにする。 脱原発デモに参加したという内容のブログ記事なので、いつも原発関連の話題を書くことにしていたのだが、翁長知事の死去のニュースですべて飛んでしまった。[1] 吉本隆明「解説 風姿外伝」『現代歌人文庫25 福島泰樹歌集』(国文社 1980年)p.185。[2] 同上、p.175読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也) 小野寺秀也のホームページブリコラージュ@川内川前叢茅辺
2018.08.10
コメント(6)
-

「8月3日 脱原発みやぎ金曜デモ」 高速増殖炉を諦めずにプルトニウムを減らすというのか?
ウィキペディアに「長寿」という項目があって、その中の「存名中の世界の長寿者十傑」と「存名中の日本の長寿者十傑」という表をスマホで探し出して見せてくれたのは、奥さんの故郷の秋田に向かう途中でわが家に立ち寄ってくれた甥である。今日の午前中のことである。 世界一の長寿者は、田中力子さんという115歳の日本女性で、あたりまえだが日本一の長寿でもある。その世界のリストの5番目、日本の3番目に「松下しん 114歳」が掲載されていた。その松下しんは、長寿者リストを探して見せてくれた甥の祖母で、つまりは私たちと同居している妻の母親である。甥夫婦は、毎年「ばあちゃん」に会いに来てくれるのである。 義母が日本の長寿の5番目にリストされているということを誰かから聞いたのは、ほんの1ヶ月くらい前だったような気がする。リストを見せてくれた甥も、「日本で5番目、世界で9番目ですよ」といいながらスマホを差し出したくらいで、かなり短期間で順位が変わっていたということだ。 そのことに気づいて、どこかみんなの雰囲気が静かなものになってしまった。こうなると、見方次第では長寿者リストというものは、死神の持つ「○○リスト」というものに似ていなくもない。ぞっとするが、そういうことなのだった。もっともっと長生きしてもらおうと思って必死になって介護している身にはなおさらきついのである。 「いやーっ、すごい! すごい!」などと口々に言いながら、みんなでその場のムードを切り替えたのだったが、114歳の当人は、甥夫婦のために用意した白桃とずんだ餅をお相伴して、満足そうにうつらうつらしているのだった。 暑い日が続く。午後6時過ぎ、家を出るといくぶん暑気は和らいでいて、ゆっくり歩いて行けば、汗をかかないで勾当台公園まで行き着きそうだ。そんなことを考えながらゆっくり歩いて、結局は今日も遅刻である。勾当台公園から一番町へ。(2018/8/3 18:37~19:10) 集会でのスピーチでは、青森県からの参加者が大間での集会や青森県での脱原発候補の選挙戦の総括など詳細な報告を行ってくれた。また、何人かはプルトニウム問題に触れた。今日の市民への呼びかけにもプルトニウムのことが次のように取り上げられていた。 7月31日、原子力委員会は、プルトニウムの保有量を減少させるとの方針を初めて明記しました。現在、日本は47トンものプルトニウムを有しています。これは原爆6000発分に相当し、かねてアメリカなど海外から疑念の目が向けられてきました。 原子力委員会の岡委員長は、「プルトニウムを着実に減らしていくのは日本の責務だ」と強調しました。しかし、もんじゅが廃炉になった今、プルサーマルとして通常の原発でプルトニウムを消費することも限界があります。プルトニウムを増やさない唯一の方法は、原発を動かさないことです!国は一刻もはやく核燃サイクルを放棄し、六ヶ所再処理工場を本格稼働させる前に、閉鎖することを決断すべきです。すでに再処理工場の地下にはとてつもなく危険な高レベル放射能廃棄物が眠っています。 東北の大地が再び放射能に汚染させられる前に、全ての核施設を廃炉・閉鎖に追い込みましょう!一番町(1)。(2018/8/3 19:17~19:20) プルトニウムを増やさないように原発を動かすというのは不可能だ。誰かがスピーチで述べたように、保有するプルトニウムを何らかの口実を設けてアメリカに引き渡すか、国際管理に任せるしかないのではないか。そうなれば、日本はアメリカの同盟国だと信じて疑わない政府や官僚の思惑とは違って、まるでイランや北朝鮮の核に対する国際的(主としてアメリカ)の扱いと酷似してしまうのではないか。日本の国家主権などないに等しいということになる。今回のプルトニウム削減も、アメリカから言われて慌てて言明したということだろう。 プルトニウムの保有量を減らしたいという日本は、「もんじゅ」の破綻、廃炉へという結末にもかかわらず、高速増殖炉を諦めきれず、フランスの高速炉ASTRIDにしがみついている。高速増殖炉というのは、文字通り核燃料を増殖しつつ運転する炉ということで、大量にプルトニウムができてしまうのである。燃料を燃やしながら燃料を増やすという「夢の原子炉」がいまや日本の足枷になってしまったということですらある。この事ひとつとっても、日本の原子力政策というのは、将来への整合性も合理性もなく進められていることがわかる。 さっさと原発を捨て去ることが、もっとも合理的なエネルギー政策なのは今さら言うまでもない。一番町(2)。(2018/8/3 19:21~19:23)「原発ゼロをたどって」という朝日新聞の連載記事がある。その9回目に「民意、推進側を悩ます」(8月3日付け)と題して、自民党政権がどのようにインチキをしながら原発政策を決定している(あるいは、決定していない)かを描いている記事がある。そのまま引用しておく。 原発・エネルギー政策の議論から逃げようとするのが安倍政権の特徴でないか。端的なのは有識者会議の構成だ。 政権を奪還した2012年暮れの衆院選から約2カ月後の13年3月1日。当時の経済産業相・茂木敏充(もてぎとしみつ)(62)は第4次エネルギー基本計画をまとめる有識者会議の委員を発表した。それは民主党政権時代の25人を15人に縮小、「脱原発派」とみられた委員を8人から2人に減らすものだった。 会見でこの点を聞かれた茂木は「専門性を中心にして議論をしていただく」などとかわしたが、原発の是非の論議を封じ込もうとしたのは明白だった。こうしてつくられた14年の第4次計画で、原発は「重要なベースロード電源」という位置づけを獲得した。 さらに17年8月、第5次計画の議論を始めた有識者会議では、「脱原発派」委員は1人に。その「1人」が日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会常任顧問の辰巳菊子(たつみきくこ)(70)だった。 「あのメンバーで結果が見えていると思いました……私は国民の代表との立場で参加しましたが、マイナーというか、独りぼっちでした」 今年5月、「脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会(eシフト)」などが開いた集会で辰巳はそう語った。事実、7月に閣議決定された第5次計画は第4次に続き原発を維持するものになった。 が、それは民意の裏打ちを欠いていた。朝日新聞の今年2月の世論調査では、停止中の原発の運転再開について反対が61%、賛成が27%。「反対」が「賛成」のほぼ倍というのは、ほかの報道機関の調査でも大差ない。 eシフト運営幹事の桃井貴子はこう見る。「民意を聞けば、『原発ゼロ』になる。だから原発維持で行くには民意無視を決め込むしかない」 先の国会で「原発ゼロ基本法」を審議しなかったのも、原発をめぐる議論の拡大を恐れたからではなかったか。実は推進側は「原発ゼロ」の声が怖くてならない。 今年6月10日投開票の新潟県知事選。原発維持路線を取る政権与党の自民、公明が支持する陣営が開票日前日9日、地元紙に出した1ページの広告が話題になった。 「脱原発の社会をめざします。……再稼働の是非は、県民に信を問います!」――焦点の東京電力柏崎刈羽原発の再稼働について慎重姿勢をそうアピールした。 新潟県では前回16年10月の知事選で再稼働に慎重な野党系候補者が当選。そこで今回、与党系は再稼働の争点化回避に動いたと報じられた。 野党系の選対幹部の新潟国際情報大教授・佐々木寛(52)は話す。「新潟では『脱原発』の姿勢でないと勝ち目がない。だから向こうはそんな戦術を取るしかなかった」 重い原発のリアル(現実)。もはや7年前の事故をなかったことにできない。いまも使用済み燃料問題ひとつ解決できない。そして「原発ゼロを」という多くの人の思いが推進側を苦悩させる。 (太字は引用者による) 私たちの脱原発デモがどのような意味を持っているのか、とてもよく理解できるような記事だ。青葉通り。(2018/8/3 19:31~19:35) 今日のデモも30人である。言ってしまえば、ほんとうにコアだけの人数だが、仙台人にはあまり経験のない酷暑の中でこの人数を維持できているのは、私が思う以上にすごいことかもしれない。しかもコアのかなりの部分が高齢者だということ、その持つ意味をよく考えてみなければ……。 「金デモは、私の終活だ!」と語る人がいる。それは、原発を子や孫に残さないという意志なのか、それとも、原発廃炉の達成を自分自身の生きた証としたいのか。 そして、私はどうなのか。一つだけはっきりしていることがある。大学、大学院と原子力工学を学んだ責任のようなものを感じている。原発の危険性をもっともよく知り得た者の責任である。 もう一つ、18歳から23歳までの、人間がもっともよく学びうる時期に原子力工学を選んでいたという悔い、悔しさが私をかき立てている。その後の人生を物理学者として生きたので、その思いはなおさらである。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也) 小野寺秀也のホームページブリコラージュ@川内川前叢茅辺
2018.08.03
コメント(6)
全4件 (4件中 1-4件目)
1










