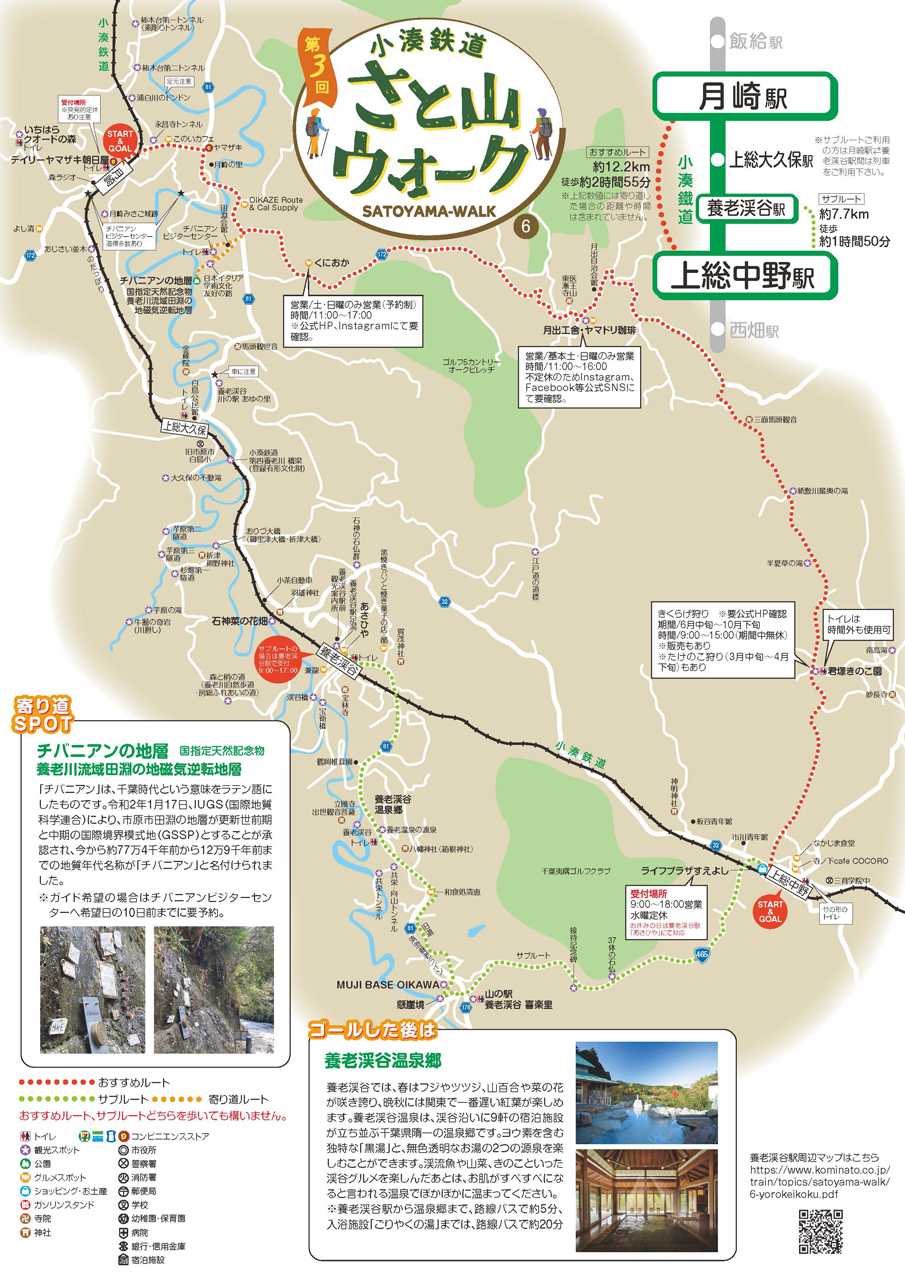2015年12月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-

「冬の星まつり」 立体造形展示会 終了
上の画像は、会場の出入り口を、場内から撮影したものだ。千秋楽の本日、会場を後にする雰囲気が出ている。そういえば展示会の初日だったと思うが、この撮影場所から出入り口を見ていると、その上部に見える小さな白い造形の連なりが、なぜか神社の鳥居にかけられた「注連縄(しめなわ)」に観えるのだった。そして、それに連動するかのように、出入り口の左右に配置した「月」と題した銀色の造形と「太陽」と題した金色の造形が、神社の参道で見かける左右一対の「狛犬(こまいぬ)」に観えてきたから不思議である。結果的にそのような印象を抱く飾り付けや配置になったのは、おそらく入口から真正面奥の壁面に展示した「八咫鏡(やたのかがみ)」と題する作品(⇒リンク)が、神社の本殿に置かれている「御鏡(みかがみ)」に相当するからではないか・・・などと想像を膨らませながら、来場された方々に展示作品を解説する際に、いつの間にか上記の「注連縄」・「狛犬」・「御鏡」は、キーワードとして定着していくのだった。今月の12月19日~27日の日程で開催してきた【 立体造形『冬の星まつり』展 】は、本日を以て終了。当展示会にご来場くださった皆さま、そして支えてくださった関係者の皆さま、ありがとうございました。
2015年12月27日
-

「冬の星まつり」・・・オリオン座の星々
今回の展示会場の中央には、冬の星座の筆頭たる「オリオン座」の星々を、各種の星型立体に準えて配置することにした。冒頭の画像は、そのオリオン座を代表する五つの星々、つまり画像の中央部に並ぶ三つの造形が「三ツ星」、左側奥の赤色の造形が「ベテルギウス」、そして右手前の青色の造形が「リゲル」の見立てである。実はこのオリオン座の五つの星々を、五柱の神々として祀られてきたと思われる神社が存在する。その神社とは、地元は山口市内の三ノ宮に鎮座する「仁壁(にかべ)神社」だ。★関連記事 2014年01月07日の日記・・・「初詣」に想う・・・⇒ リンク上にリンクした関連記事にあるように、同神社に祭祀される神々と星々の対応は以下となる。◎仁壁神社(周防国三の宮)の御祭神・・・五柱の神々と対応する五つの星々 〔 表筒男命 〕・・・オリオン座 三ツ星の「 ミンタカ 」 〔 中筒男命 〕・・・オリオン座 三ツ星の「アルニラム」 〔 底筒男命 〕・・・オリオン座 三ツ星の「アルニタク」 〔 味耜高彦根命 〕( アヂスキ タカヒコネ )・・・オリオン座「ベテルギウス」 〔 下 照 姫 命 〕( シ タ テ ル ヒ メ )・・・オリオン座「 リ ゲ ル 」 この「仁壁神社」は、現在の山口市と重なる椹野川流域の、古くは「吉敷郡(よしきぐん)」の総鎮守とされ、南北朝時代に大内氏が山口を本拠地にする以前から鎮座していた延喜式神名帳にも記載される古社である。同神社の真祭神たるオリオン座の星々を見立てた五つの星型立体を、宇宙を象徴する八角形を基本とした展示会場の中央に据えられたことに、展示会の最終日を迎えて有り難き幸せを噛みしめる今日この頃である。
2015年12月27日
-

「冬の星まつり」・・・クリスマス満月と太陽
この度の展示会(⇒リンク)の12月19日~27日の期間中において、22日は「冬至(北半球では太陽の南中高度が最も低く、一年の間で昼が最も短く夜が最も長くなる日)」、そして本日の25日は「満月(旧暦11月15日)」となっていた。特に本日の12月25日は、クリスマスと満月が重なる19年ぶりの・・・クリスマス満月・・・とのことで、上の画像は展示会場の出入り口に置いた「月」と題する造形を映したものだ。そして次の画像は、同じく展示会場の出入り口に置いた「太陽」(冬至の朝日をイメージ)と題する造形を映したものである。
2015年12月25日
-

「冬の星まつり」・・・南北の星座
ただいま開催中の展示会(⇒リンク)では、会場の南方の壁に「南十字星」として朱色の4つの形、そしてその上方に「うみへび座」として金色の9つの形を配置して映した画像が上である。次に下の画像は、北方の壁の中央に「北極星」として金と銀の和合した形、その左側に「カシオペア」として銀色の5つの形、そして右側に「北斗七星」として緑色の七つの形を配置したものである。なお、「北斗七星」の下から二番目には五色の形を、八番目の星(アルコル)として添えている。(古代において「北斗七星」は、アルコルを含めた「北斗八星」と唱えられていた。)
2015年12月24日
-

宇宙船 『 か ぐ や 』 完成!
12月23日(祝)、いよいよ一人乗りの宇宙船『かぐや』(上の画像に映った大きな造形)が、自分の考える理想的なかたちで完成した。これと同じ作品は、一週間以上の長期となる個展や合同展などで、広いスペースがある場合に設置してきた。この作品の設置は今回で4回目。会場の現場で綿密な構成法により組み上げていくので、理想の造形表現に至るまでに時間がかかるわけだが、この度は最短時間(といっても会期の4日目)で完成に漕ぎ着けた。この長さ約2mの細い竹竿(60本)で構成した造形の内部空間には、どうやら特別な「ひびき」が渦巻いているらしく、実際にこの中に入って体験された方は、その内部空間との「共振・活性(ひびきあい)」によって、その人が本来あるべき姿になるための《心身の変容》を体感されている模様である。実は、この大型の竹製造形は、展示会の終了とともに解体してしまい、また制作が困難なために今後も披露できるかどうかわからないので、この宇宙船『かぐや』に搭乗できるのは今回限りかもしれません。興味のある方は、この機会(詳しくはこちら⇒ リンク)に「体感」されてみてはいかがでしょう。もっと素敵な自分に出会えるかも・・・。(※下の画像は作品の解説とその雛形)
2015年12月23日
-

冬至の朝日
一陽来復の冬至(12月22日)の掲載画像(上・下)は、晴天に輝く清々しき今朝の朝日を撮影したものである。かつては年始とされた本日、現在開催中の展示会(⇒ リンク)の会場には、神々の采配により二人の美しき舞姫が現れて、「八咫鏡」の前で「ウズメの舞」が披露された。そのたおやかな「わざおぎ」により、どうやら本家本元の「天の岩戸」は開いた模様である。そしてこの度、その岩戸よりお出ましになられた「天照大神」とは、「 天照国照彦 天火明 櫛甕玉 饒速日命 (あまてるくにてるひこ あめのほあかり くしみかたま にぎはやひのみこと )」なのかもしれない。・・・ あはれ、あなおもしろ、あなたのし、あなさやけ、おけ ・・・
2015年12月22日
-

今年の「冬至」に向けて
明日の12月22日は、年間で日照時間が一番短い「冬至」で、言わば一陽来復の「太陽」が主人公である。しかし古代では、この冬至の「太陽」は、夜の太陽とも謳われる「シリウス」と濃密に関連付けられ、天体信仰として深く根付いていたことを知る人は、意外に少ないのではなかろうか・・・。かつて、以下のリンクように「冬至」に関する記事を書いたことがあるが、改めて読んでみて新鮮だった。☆2007年12月20日の日記・タイトル「冬至に向けて」⇒リンクさて現在、「聖母子像」ということで世界的に浸透している「キリスト(子)を抱くマリア(母)」の図像は、古代エジプト神話の「ホルス(子)を抱くイシス(母)」の図像が原型とされ、この母子関係を日本神話に置き換えると「応神天皇(子)」と「神功皇后(母)」と想定される旨は、以下のリンク等で取り上げたことがある。そして、その母子関係の本質とは、「母親=シリウス」・「息子=太陽」となり、「冬至」が年始とされていた時代においては、この二つの天体を抱き合わせた思想信仰が形成され、おそらく世界各地で語り継がれてきたのである・・・。※「春の旅」の締め括り(上)⇒ リンク※「春の旅」の締め括り(中)⇒ リンク※「春の旅」の締め括り(下)⇒ リンク今回の立体造形展「冬の星まつり」(⇒リンク)は、上記のリンク内容にもあるように、冬至(22日)からクリスマス(25日)までの3日間に焦点を絞るかたちで、「冬の星座」の天体運行を自作の造形群になぞらえて展示したものである。そこで本日の画像は、現在開催中の展示会にて、会場の入口から真正面に見える奥の壁面に展示した『八咫鏡(やたのかがみ)』と題する作品だ。神社にお参りすると御神前には「御鏡」が置かれているが、その本質は「太陽」である。明日の冬至より「よみがえる(日照時間が長くなる)」新生の太陽を寿ぎ、その形代たる八角形状の「御鏡」を象徴した作品を掲載させていただくことにした。
2015年12月21日
-

19日(土)より展示会!
★ 立体造形 『 冬の星まつり 』 展 ★ 山 本 裕 一 冬至の頃に輝く天空の星々を立体造形の作品群に見立てて展示します。 日本神話に基づく祭事「岩戸神楽」や 欧米の祭典「クリスマス」など、 世界各地で行われてきた「冬のまつり」に共通する原点を演出します。 会場には一緒に [ 星型(☆)立体 ] を作る《体験コーナー》を設けて、 小さいお子さんからお年寄りまで 皆様のご来場をお待ちしています。 〔 と き 〕 2015年 12月19日(土)~12月27日(日) 開館時間 9:00~17:00 (入館は16:30まで) 〔※21(月)は休館日・最終日の27(日)は15:00まで〕 〔ところ〕 山口市小郡文化資料館 2階ギャラリー 【 入場無料 】 山口市小郡下郷609番地3 TEL 083-973-7071 〔※JR新山口駅北口より徒歩15分・駐車場16台(無料)〕
2015年12月17日
-

悠久の大地 北海道ツアー(9)
大手旅行会社が企画した「北海道ツアー・三泊四日」の最終日は、オプショナルツアーにてロマンチック小樽観光(自由散策)だった。冒頭の画像は、緩やかに湾曲しているのが特徴の「小樽運河」を映したものである。かつての小樽の繁栄を現在に伝える建造物や街並みを散策しつつ、「海陽亭(旧魁陽亭 )」という(旧)料亭の玄関を撮影したものが上の画像で、明治初期に開業し、伊藤博文などの公人をはじめ多くの著名人が訪れた場所とのことだ。ちなみに、昭和の銀幕スター石原裕次郎も幼少の頃、この料亭には父親によく連れてきてもらっていたらしい。・・・ということからか、今回が二度目となる小樽散策では、この旧料亭の「海陽亭」が強く印象に残った。新千歳空港では・・・北海道の旅の終わりにリラックス&リフレッシュ・・・港内には温泉があり、出発までの待ち時間に入浴できたのは嬉しかった。そして、山口宇部空港へ向かう経由地の羽田空港へ・・・。上の画像は、羽田空港での待ち時間に撮影した「日本国政府専用機」のボーイング747-400である。実は新千歳空港でもターミナルの近くで、バスガイドの案内により同じ日の丸マークのあるボーイングを見たので、まさしく有り難いことに、約4時間の間に全部で2機の政府専用機の双方を見たことになる。ちなみに通常その2機は、千歳基地と誘導路で繋がっている新千歳空港の専用ハンガーに格納されているとのことだ。この上の画像は、ロビーでたまたま見かけた「スター☆にしきの」こと錦野旦の後ろ姿・・・。ミリオンセラー「空に太陽がある限り」のフレーズが自ずと浮かび、その余韻に浸った直後に遭遇した場面が下の画像である。同じ港内ロビーにて、西方に沈みゆく太陽と黄昏の夕日に輝く飛行機、さらに画像中央の遠方には「富士山」のシルエットが・・・。夕暮れ時の、ほんの一瞬しか見ることのできない素晴らしい景色に、しばしの感動であった。このシリーズの冒頭でも、機内から映した「富士山」の画像を掲載したが、今回の北海道ツアーは「富士山」で始まり「富士山」で終わるという、まさに「霊峰富士」に見守られた旅路だったともいえよう。この度の旅路を振り返ると、近年の私は言わば《「イザナミ」のよみがえり》をテーマに動いてきたところがあり、それは今回の北海道ツアーで垣間見たアイヌ文化にも深く関係する「縄文文化」に繋がり、それはまた…女ならでは世の開けぬ国…と謳われてきた、[縄文]を文化の柱とする日本の「母系社会」の復活を暗示しているのではないか・・・。現在の私の心中には、以上の「イザナミ」・「縄文文化」・「母系社会」という3つのキーワードが、三巴の渦を巻きながら浮上し、よみがえる(復活)時を迎えていると、そのような想いが沸々と湧いている。※シリーズ「悠久の大地 北海道ツアー」・・・(了)
2015年12月15日
-

悠久の大地 北海道ツアー(8)
冒頭の画像は、日勝峠のドライブインから、大きくて広い十勝平野を一望した図だ。やっぱり北海道は、デッカイど~ヽ(*´∀`)ノなのである。そしてツアー三日目となる最後の宿泊地は札幌。同市内にあるホテルに到着する直前に訪れたのは、1972(昭和47)年の札幌冬季オリンピックの舞台となった「札幌大倉山シャンツェ」だった。上の画像は、そのジャンプ台を撮影したものである。ホテルで夕食後は自由時間ということで、あの「すすきの」を少し散策した後は、「札幌雪まつり」で有名な大通公園まで歩き、そこで「さっぽろテレビ塔」を撮影した画像が上である。そして地下鉄に乗ってJR札幌駅へ行き、バスガイドから教えてもらった駅直結の「JRタワー展望室 タワー・スリーエイト」へ向かった。その展望室のある38階からは、札幌の夜景を街並とともに360度楽しむことができた。そこで上の画像は、私なりに最も映えると感じた一角の眺望である。最後の画像は、建造物としては北海道一の高さ(160m)を誇る展望室に存在する、噂の「男性用眺望化粧室」からの眺めを撮影したもので、私も札幌の素敵な夜景を望みながら圧倒的開放感を・・・。その「JRタワー展望室T38」で「ホッと一息」した後は、またてくてくと長い道のりを歩き、宿泊ホテルに近いラーメン店で美味い「味噌ラーメン」を食し、大満足で就寝したのであった。しかし、まあ・・・よく歩いたものである・・・。
2015年12月14日
-

悠久の大地 北海道ツアー(7)
前回の日記では「雄阿寒岳」を映した画像を掲載したが、本日の冒頭の画像は、言わばもう一つの「阿寒岳(雌阿寒岳・標高1,499m)」・・・画像の向かって左側の活火山・・・を、「オンネトー(北海道三大秘湖の一つ)」の湖畔より撮影したものだ。そして、向かって右の円錐状の山は、「阿寒富士(標高 1,476m)」である。ちなみに、この「オンネトー」という名称は、アイヌ語で「年老いた沼」あるいは「大きな沼」の意味とのこと。バスガイドの話では、一般的な北海道ツアーでは、なかなかこの「オンネトー」からの展望は、コースに組み込まれないそうである。以下、「五色沼」の別名もある幻想的な「オンネトー」の湖畔から展望する、美しき二峰をご堪能いただきたい。
2015年12月11日
-

悠久の大地 北海道ツアー(6)
ツアー三日目の早朝、阿寒湖畔の温泉宿にある露天風呂から、朝日に映える阿寒岳(雄阿寒岳・標高1,371m)を撮影した画像が上である。阿寒湖の淵より眺める阿寒岳・・・その風情は、なかなかの圧巻(´∀`)であった。そして以下の画像は、朝食後に阿寒湖に生息する「マリモ(毬藻・特別天然記念物)」を、遊覧船で見物に行く往復の過程で映した、印象に残る様々な景色を載せたものである。
2015年12月09日
-

悠久の大地 北海道ツアー(5)
今回の掲載画像は、宿泊したホテルに収蔵展示してあった「アイヌ文化」にまつわる衣類等を含む文化財の数々を映したものだ。ホテルに用意されたアイヌ文様のデザインされた御洒落な浴着を纏って、ひとつひとつの展示物をじっくりと拝見しつつ・・・この度の北海道旅行は、アイヌ文化に触れる旅路だったのだ・・・と、何度も反芻するのであった。
2015年12月04日
-

悠久の大地 北海道ツアー(4)
二日目のホテルは、阿寒湖の湖畔にある立派な温泉宿で、玄関口のロビーをはじめとして、ここかしこに手の込んだ木彫りの動物を模した彫刻が据えてあるのが印象的だった。その中でも「縞梟(シマフクロウ)」の彫刻が、特別に多く展示してあったことから・・・これほど多いのは何故だろう・・・と少し疑問に思っていたのだが、ある場所に掲げてあった解説(以下の内容)を読んで納得した次第である。「アイヌ民族と縞ふくろう」アイヌ民族は、カムイモシリ(神の国)とアイヌモシリ(人間の国)という二つの世界があると信じています。この二つの世界を結びつけ、村を守ってくれる神の使いとして、熊、狸、狐、鶴など、様々な動物がいます。そのなかで最も位の高い動物が「縞ふくろう(コタン コル カムイ)」です。今回の画像の数々は、展示された「シマフクロウ」の彫刻群から、私なりに選別して掲載したものである。
2015年12月01日
全14件 (14件中 1-14件目)
1