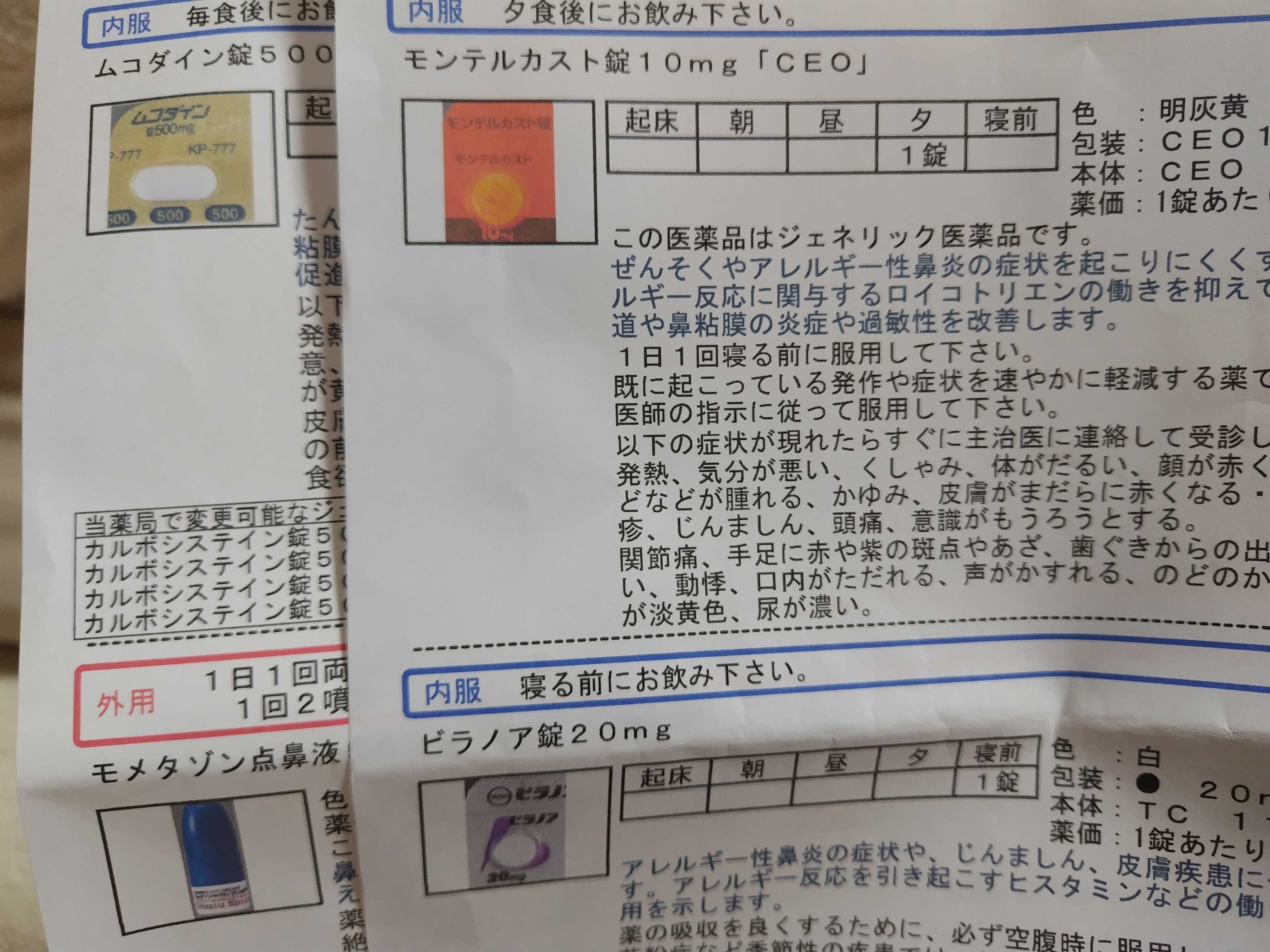2008年02月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
簡単で,難しいこと。
「これ、簡単なようだと思ったけれど やってみて、これは、 意外と難しいものなんだなと思いました。」去年この日記(11月27日)にも書いた『サラとソロモン』という本を読んだ子がそう教えてくれました。いい気分でいること。ただ、味わい愛でることをずっと練習し続けること。たったこれだけなんですが意識していないと、すぐに忘れてしまうしすぐに、目の前で起こっていること降りかかってくることに思考を奪われ『でも。。。』という言葉から続く吹き出しが出てきます。「ほんと、これは、面白い課題だ」と、そんなことを思っていたら先日、みさきよしのさんがジョー・ビタリーさんの『ザ・キー』という本を紹介してくださいました。いま必要なことがたくさん書かれてあったんですが読んで気づいたことは最初に書いた生徒さんの言葉。根っこは、同じなんだなと思いこれからは、広くではなく深く、透明度をあげていきたいなと思いました。勉強も心もほんと同じで意識すればするほどできていない自分に気づきそれをクリアにするほど望む現実になっていきますね(笑)
2008年02月28日
コメント(6)
-
偶然をつかむゾーンの力。
まだ始めていないのにする前に、これはできちゃうなって、思うことありませんか?ボーリングだと、投げる前にストライクが入る確信がある。野球だと、投げてくる前に次は、ホームランになりそうな気がする。勉強だと、する前になぜか解けてしまうような気がする。まだしていないのになぜだか解らないけれどできちゃう気がするそして、結果もその通りとなる。そんなことは、ありませんか。先週NHKを見ていたら東海大学の高妻先生と爆笑問題の二人がそんなテーマで話をしていました。 イチローや中田英寿さんが見せる高い集中力メンタルトレーニングでよく話題になるゾーンに入るような感覚を偶然ではなくいかにプログラム化するかそういうお話をされていました。いろいろ大切なことをお話されていたんですがサイキングアップといわれる方法で音楽やリズムで気持ちを高めていくことゾーンに入ったときを1回の偶然と捉えるのではなくイメージトレーニングで繰り返し強化することゾーンに入るひとつ前の段階を大切にしルーティンと呼ばれる準備段階を定式化して自動化した動きにしてしまうこと この3つは、最近考えていたこととつながり応用すれば、日常生活に活かせるなと思いました。子供たちと勉強しているときノッテいるときと、そうでないときのカラダの使い方の違いを見ていてそのリズム感、スピードに変化を加えられないかと思っていたので、また新たなヒントを頂いた気がします。プログラム化してきたらまた書かせていただきたいなと思います。
2008年02月25日
コメント(6)
-
ひとつ前へ。
「『怒ってはいけないと解っていても 言うことを聞いてくれなくて ついつい怒ってしまうんですよ。。。』というような相談を受けることがあるんです。そんなときは、同じお母さんとしてキモチわかるんだけど、先生は、どう答えますか?」先日、ベビームーンに行ったときにひろみ先生がぽんぽこ先生に聞いていました。「『子供に怒らないようにしましょう』 とか 『子供と視線を合わせて 子供の意見に耳を傾けてみましょう』 とよく言われるけれど でも、もう怒る段階になっているんだし いうことを聞いてくれない状態になっている 子供に言うことを聞いてほしい しっかり話し合いましょう と論理的にお話してもうまくいくわけないよな。」と話してくれたあとで「そのひとつ前の段階を考えてみると なぜそういう状態になったのか わかってくるものなんだよ。 子供は、勝手に言うことを 聞かなくなるような子になるのではなくて 子供に限らず人がある行動をするには 以前にそんな風にしている人を見たとか それに近いことをしていたとか そういうことがないと できないものなんだよ。 ということは、その子は親の姿を見たのか 大人や友達の姿を見たのかで それを知ったということなんだね。 だから、対処的に怒るのではなく その行動の少し前に焦点を合わせ うまくいくような循環・サイクルを 一緒にやっていた方が ずっといい解決になるんだよ」と話してくれました。家のネコを見ていても子供たちを見ていても何かことが起こる前にはちゃんと、サインが出ているものですよね。彼らと一緒に過ごしているとここから先にいくといつも負のパターンなるという現象にあたったりします。その分岐点みたいな場所で『なんで、こうなったんだ!!!!』って、怒るのではなくいい流れに切り替えることを一緒にやっていると自分でいい流れに切り変えることができる子の姿をたびたび見るようになりました。怒りがこみ上げてくるときってそのことにある意味、期待があるからなんですよね。その期待をうまくいく方向に持っていくにも何かのひとつ前の段階を思い出してみたいなと思いました。
2008年02月23日
コメント(8)
-
思い出し笑い。
最近どんなときに『思い出し笑い』しましたか?今日、右脳教室をきっかけに仲良くさせて頂いているお友達のともゆきさんとランチをはさんでお話しました。ともゆきさんが『思いだす訓練』をすることは脳をバージョンアップする上でとても大切だとお話してくれて自分がしていることとつながって思わずニコニコしてしまいました。自分がいつから習慣になったのかちょっとわからないのですが何かをしたり、見たりすると、その直後に左上を見上げて思い出すことをしています。今日あった出来事を思い浮かべたり昨日見たドラマを想い浮かべたりそんなことをしています。今日会った出来事であれば想い浮かべながらキーになることをメモしたりそんなことをしたりしているんです。さらに、もっといい方法があって時間の流れと逆にして考えてみると潜在意識を刺激することができるそうです。ビデオを巻き戻しするように後ろから思い出すことは潜在意識の時間の流れと同じ方向の流れなので刺激することができるんです。こうして、ブログを書くことも「思い出す訓練」のひとつですよね。
2008年02月22日
コメント(14)
-
ダイヤの煌めき。
「炭も、ダイヤモンドも同じ炭素Cだから 燃やそうと思ったら、燃えるんだよ。」中学の時、化学の先生からそう聞いて「ふ~ん。そうなんだ。」と思っていました。先日、テレビ番組を見ていたら「ダイヤモンドを使って 七輪でマツタケが焼けるのか ぜひとも実験してみたい(^v^)」と、ある小学生が番組に投稿していました。宝石屋さんから、古い貴金属を頂いたり工業用ダイヤを譲ってもらおうとしたり番組の力を借りてなんとかダイヤを集めていました。工業用ダイヤ、安いかと思ったら5カラットでベンツ1台買えるくらいの価格で番組内で、提供してくれた住友電工ハードメタルの宣伝をするということを条件に、50カラットも頂いていました。実際に、燃やすとなるとダイヤは硬く、燃えにくいので大学の先生に指導してもらいながら圧縮された酸素を送りバーナーで火をつけると見事に、ダイヤが赤く燃えマツタケがちりちりと焼けダイヤは、灰になっていました。「なぜって、問い続ける、想い続ける」って、素晴らしいなと思いました。しかし、ダイヤは、輝くからこそ価値があるものだなというのも実感したそんな実験でした。ダイヤは、お好きですか?
2008年02月21日
コメント(12)
-
偶然と必然のあわい関係(1)
なんだか時間が取れなくて日記の更新が滞っていました。ごめんなさい。ちょっと前から感じていたことがあって、それは少し抽象的な言い方なのですが何かを、一度体験するとあるものが見えてくる人と同じことを何度繰り返しても見えてこない人がいるということ。見えてきた人には次も同じようなものにうまく対応できるし見えていない人には同じようなことがあってもなかなか、できるようになりません。コツをつかむのがうまいとかセンスがあるというのは勉強以外の多くの事柄にも通じることですよね。この違いは、何に由来するんだろうと、ずっと思っていました。で、学習という現場にいて体験・経験のなかから法則性や規則性を見つけようとする心のクセなのではないかと思うようになりました。人間の脳には、もともと法則や規則性を見つけようとするクセがあるそうなんですがそれを積極的に活用しようとしている人とそれほど活用していない人には大きな違いがあるそう思うようになりました。子どもたちと学習しているときにはそういうものを意識したような語りかけ「どこから(何を根拠に) この答えを見つけてきたの?」とか「○○は、なんでだと思う?」とか「なんで、こうなるか先生に聞かせて」と聞くようにしています。いま放送中の「エジソンの母」とはちょっと違いますが「どうしてなんだろう? なぜなんだろう? 」こういう思考の子供たちがたくさん増えてくれたらいいなと思います。
2008年02月20日
コメント(10)
-
虫の知らせ。
先日、電車で和歌山から大阪に帰っていた時のことです。座席に座っているとりんくうタウン駅あたりから出先から戻りらしい男性と新人の女性がぼくの前に立ちました。そして、ここ最近考えていたことまさに知りたかったことについてまるで、僕に聞かせてくれるかのように二人が話し始めました。チラチラ見てるなんて思われたらなんだか怪しまれるよな。。。なんて思いながら『この時間、このタイミングで なんで、よくもまぁ 自分が考えていたことを 解るものだよな。。。。』と不思議な偶然にちょっと可笑しくなりました。子どもたちと話をしていても「2日前に、先生に質問したでしょ。 入試で、あれと同じ問題、出たんだよ。」とか「こないだ間違えてて 先生が『これは、お知らせだよ』 と言ってたのが、そのまま出たよ」とか「試験会場に行く電車のなかで ここは、気になると思って 最後に見たところが、そのままでて。。」とか「他の大学の過去問でしていたのと そっくりなのが出てきたんだよ。」というのをよく聞きます。そして、これは、感覚的な話ですがどうしたらいいかと周りばかりを見ているときにはなかなかそういう偶然に出会わないもののように思います。出会わないのではなくて出会っていても気付いていないだけかもしれません。ヒント、サインはさりげなく隠されていて探そうと思えば、見つかるところに隠れているものなんでしょうね。このお知らせに対してこの状況で何ができるかと客観的に自分を見ること自分を磨き続けることって大切だなと思いました。今日は、降りしきる雪のなか大阪の私立高校の入学試験でした。自分の持てる力を十分に発揮してくれたらなと思います。
2008年02月09日
コメント(12)
-
温かい想い。
「わざわざ塾に行っているなら、これくらいは」「少なくない費用を出しておられるから なんとかして、これくらいの状態には。。。」保護者の方が思っておられるであろう想いを想像して、せめて、このくらいの状態には。。。と思っていました。なんとか、そこまでするにはと方法を探り、多くの人と話もしました。もちろんいい感じで目覚ましい成果が出て学校で評判になるようなときもあります。でも、みんなが一瞬で効果てきめんとわかるくらいすぐにうまくいくかというとそうではないのでうまくいかないなとか今は問題になっていないけれどいずれ問題は表面化するだろうってことがあるときはそのことを目の前にするときだけではなくそのほかの時も、四六時中どうしたらいいんだろう。。。って、考えていました。いや、悩んでいました。問題を目の前にしてどうしたらいいんだろうと悩んでいるときってどうするべきなんだろうとか、何が問題なんだろうと原因を探っているんですよね。一見、自分に原因を探っているようで過去に問題を見つけようとしたり相手や対象物に問題を見つけたりして問題となるところ悪いところを原因を見つけて主体と客体を分離させて自分が変化しようとしていないのです(汗)そして、やっているこっちも相手の方も苦しいし楽しくないのです。あるとき、そのことに気づいてみんないい子、いい人でそのいいところをさらに伸ばすにはさて、ここで自分には何ができるんだろうと思い、接しているとなんでこんなにも壁に苦労していたんだろうと思うように問題が解決していきました。口に出さずに、その子のその人のいいところに光を当てようと思っていると口に出そうと思っていないのに「賢いね、嬉しいね、すごいね」という言葉が自然に口をついてくるようになってほんとに、どんどん賢くなってしだいに、問題は解決していきました。想いとか言葉ってすごい力をもっていますね。そんな変化に驚いていたある日小学校低学年のある女の子が「勉強楽しいから、ここに来てるの。 もっと勉強して、いろんなこと知って 賢くなりたいから、ここに来てるの。」と、ふいにお話してくれて心の内側の反映、鏡が現象となるほんと、その通りだなと小さな女の子の笑顔を見ながら思いました。
2008年02月08日
コメント(10)
-
発見力のある子(3)
線を一本引くだけで、一見脈絡がない複数の対象の間に関係が見えてくる。そんなことってありませんか?テレビドラマや映画を見ていたらそんなことは、よくありますが。。。日常、生活していてもそんなことがよくあります。「あぁ、こういうことだったのね。」って。そして、その感動を有機的につなげることを繰り返すとぱっと、ひらめきが訪れそれまで見えなかったものが見えてくるということが頻繁に起こるようになります。脳科学者の茂木健一郎さんによると、まったく関係ないように見えるものとの間に補助線を引くようなことができるのは今のところ、人間の脳に固有の能力なんだそうです。コンピュータには、局所的にロジックを積み重ねていくことが得意なので一見関係のないものを一本の線を手がかりに結びつける能力というのは、不得手なんだそうです。思考するとは、手を動かすことなんだって前回の日記で書きました。手を動かして繰り返しトレーニングしていると手を動かさなくてもキーワードが見えちゃったり補助線が見えてきちゃうんです。茂木さんのクオリア日記を読んでいてまったく関係ないように見えるものとの間に補助線を引くようなことこれをただの偶然とするのではなくてひとつの技にしてしまうのはとても面白いなと思いました。『思考の補助線』昨日書店で探したら発売日が2月5日でまだ並んでいなかったのですが読んでみたいなと思います。
2008年02月04日
コメント(8)
-
発見力のある子(2)
「これ、足し算?引き算?」「これ、割り算?掛け算?」こういう風に聞いてきたときまた、途中式を飛ばして答えを書くことに熱心なときこれは、まずいなって思います。なぜなら、文章題というのは問題文を読んで、自分のなかでいかに構造化して再現させるかというプロセスが一番大切なのにそこを避けてしまっているからです。だから、できるだけ早い時期に図や表やグラフを書いたり考えることとは同時に手を動かすことなんだ答えが合っているということより途中式をきちんと書くこと思考を積み上げていくことの方がすっと大切なんだということを体験として自らが発見するするような取り組みを繰り返ししています。 こういうものって教えられる子供にとってみれば「アタマがグッチャになる」とか「なんで、そこまでしつこいん?」とか「学校では、こんなことしないよ」とか先生は『大魔神』と言ったりすることで(笑)うまくいったりすることもうまくいかないときもありますが選択的に考えていく能力手を動かして考える能力は答えを発見していく上でとっても重要だなと感じています。 こうして、手を動かして考えていく延長線上に数学の図形の問題で補助線がずばっと引けたり現代文読解や英語の長文読解で答えのヒントのなるポイントに線がちゃんと引けるようになったり多くの情報の中から必要なものをピックアップする能力が育ったりのではないかと思います。手は、脳が身体として外にでてきたものといいますよね。手を使って動かすトレーニングって、その年齢により違いますがとても大切なことだなと感じています。
2008年02月02日
コメント(10)
全10件 (10件中 1-10件目)
1