2015年04月の記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-

4月のおしゃれ手紙:PC不調
パソコンが不調だ。大好きなニコ動を見る度に何度もフリーズする。故障のため、このPCを買ったのは、2009年だったか2010年だったか。2013年には、iPaddoを買い、2014年には、夫がPCを買った。そして今度は、私がまた買うことになるのだが、買い過ぎの感がある。でも、どれも必要として買ったのだから、贅沢とは思わない。いや、贅沢なのか・・・。それはともかく、今のPCの中で大切にしているものがある。それは、■亡くなった親友とのメールのやりとり■や■2009年~2011年までイギリスで暮らした娘■とのやりとりなどなど、プライスレスなものが残っている。こんな時、みんなどうしているのだろう?なんとかならんかな?老前整理を口癖のようにいう私だけれど、本当に大切なものは、残しておきたい。それに、場所をとらないしね。 ■4月に見た映画■*博士と彼女のセオリー■2015.4.14*イミテーション・ゲーム■4.14*リトル・ダンサー■4.15*ジヌよさらば~かむろば村へ~■4.15■書きのこしたネタ■*整理ネタ*琵琶湖ネタ*畳で洪水防止?*大阪市のレトロビル*古い針箱*植物の痛み*天才プルシェンコ*皇帝ダリア*四国ネタ*電気自動車*「ビッグイシュー」*ごんご*ダウントン・アビー*「大阪人の格言」*警察のポスター*小浜島・・・漂着ごみ*は行とぱ行の歴史*渡し舟*西行寺*娘の引っ越しの荷物が多いことと簡素な引っ越し*街で見つけたデザイン。*白虎隊の歌*「君をだいて」*「とっさの方言」*からほり御屋敷再生複合ショップ「練」*近つ飛鳥*近つ、遠つ*キラキラネーム*和泉市の美術館*もっと緑が欲しいのだ!(駐車場)*みどり学*あさぶら*小説「アーレンガート」*「北極星」*アルミ缶エコ*江戸時代、和歌山の防災意識*子供と春の花と桜・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
2015.04.30
コメント(0)
-

昔語り:甘茶
私が子どもの頃住んでいたのは、兵庫県に近い岡山の山の中の村だった。村には、お寺が一軒あった。それも、山の中腹だったので、めったに、お寺に行くことはなかった。しかし、卯月八日、4月8日は、子どもがそろって、山を登ってお寺に行く日だった。お寺で「甘茶」がもらえるからだ。みんな、自分用の金属製の水筒を持っていた。水筒に入れてもらった甘茶を飲みながら山を下った。あの頃は、おやつは■自分で調達するもので■、甘茶も、そのひとつだった。甘いものといえば、おはぎや■地蔵盆にもらう白砂糖■くらいだった。そういう時代だったので、あまちゃの飲める4月8日は、子どものとって楽しみな日だった。少し大きくなると時代は、砂糖が前よりも手軽に手に入るようになり、いつの間にか卯月八日に甘茶をもらいに行かなくなった。甘茶をもらっていたのは、今から60年近く前のこと。■2010年になくなった母の49日■のためにお寺に行った。あれから半世紀以上たっていたので、お寺は様変わりしていた。山腹のお寺には、もちろん、車で行った。あのお寺では、卯月八日には、今も甘茶の接待をしているのだろうか?・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
2015.04.26
コメント(0)
-

滋賀県・「江若鉄道(こうじゃくてつどう)の思い出」展
■2015年4月9日(木)江若鉄道(こうじゃくてつどう)は、今は無い鉄道。1921年(大正10年)に滋賀県の三井寺下-叡山間の6kmで開業。モータリゼーションに押される形で乗客は減少し、1969年に鉄道事業を廃止し、その鉄道用地を湖西線建設に当たる日本鉄道建設公団に売却した。琵琶湖東岸には、早くから鉄道があったが、西岸にはなかった。近江(おうみ)と若狭(若狭)、関西と北陸をつなぎたいという願いから、作られたこの鉄道は、北陸まで届かず、今津どまり。上の写真は、江若鉄道(こうじゃくてつどう)の駅でただ一つ残っている「今津駅」。しかし、夏は、京都や大阪から、水質のよい湖北に向かう湖水浴の客で臨時列車が出たそうだ。また、スキーも盛んだったようで、スキー客も多く、賑わっていた。たまたま、今回の福井、滋賀旅行の際、「江若鉄道(こうじゃくてつどう)の思い出」という展覧会を大津市歴史博物館でやっていたので見て来た。冬は一駅ごとに、雪の深さが違っていたそうだ。湖のすぐそばを走る列車の写真があった。その横で、子どもたちが泳いでいた。そんな当時の思い出が会場いっぱいに展示されていた。歳をとった地元の人が懐かしがって、車椅子に乗って見に来ていた。会場では、初対面の人が、お互いに思い出を語りあっていた。新幹線では、こうはいくまい。鉄道マニア(鉄ちゃん)の京都の学生が廃止の日とその前日を写真と文章で残していたが、哀惜の念を感じた。今回、名前をはじめて知った私だが江若鉄道(こうじゃくてつどう)の思い出は、なぜか私にも懐かしい。■江若鉄道(こうじゃくてつどう)の思い出■■江若鉄道(こうじゃくてつどう)の廃線跡■■江若鉄道(こうじゃくてつどう)■■桜三昧2泊3日:福井県と琵琶湖湖西地方■■2015年4月7日(火)■国内第三位の美:養浩館(ようこうかん)■■4月8日(水)■一筆啓上:丸岡城■■湖北の「かくれ里」菅浦(すがうら)■■4月9日(木)■■今津:ヴォーリーズ建築■■琵琶湖周航の歌■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
2015.04.23
コメント(0)
-

滋賀県・今津:琵琶湖周航の歌
われは湖(うみ)の子 さすらいの 旅にしあれば しみじみと 昇る狭霧(さぎり)や さざなみの 志賀の都よ いざさらば 琵琶湖の西岸の北に位置する今津は、■ヴォーリーズの建築■の他にもうひとつウリがある。この歌には、琵琶湖を中心とした滋賀県の風景が歌われている。第三高等学校(現在の京都大学)に入学した小口は、1917年(大正6年)の琵琶湖一周の漕艇中にこの歌詞を思いついたとされる。周航2日目の6月28日夜、今津(現滋賀県高島市今津)の宿で部員の中安治郎が「小口がこんな歌を作った」と紹介したのが初出である。吉田が作曲した『ひつじ草』のメロディに当てて歌われたのが定着し、三高の寮歌・学生歌として広まっていった。現在も京都大学ボート部の部員によって歌い継がれている。昔の大学生はエリートである。優秀な成績であることは、もちろん、家もそれなりに裕福だ。■博士と彼女のセオリー■でも見たが、そんなエリート学生の間では、ボートがはやっていたのだろうか。「琵琶湖周航の歌」を私は、琵琶湖周航中に亡くなった人の歌だと思っていた。私の勘違いだったのか?いや、琵琶湖でボートの練習中に亡くなった現金沢大学の学生11人を悼んで作られていた歌があった!!「琵琶湖哀歌」という歌だ。■琵琶湖哀歌■。1941年4月6日に琵琶湖でボート練習中に突風のため転覆し水死(琵琶湖遭難事故)した第四高等学校(現・金沢大学)漕艇部の部員11人を悼んで作られたとされている。歌詞には遭難事故には全く関係のない琵琶湖八景が詠み込まれており、またメロディの半分ほどは琵琶湖周航の歌の借用である。謎は解けた!!!それにしても、(現)金沢大学の学生が琵琶湖まで来て練習していたのには驚いた。■今津は金沢藩■だったというし、私の思っているより近い距離だったのかもしれない。「琵琶湖周航の歌」の曲名は「ひつじ草」というのだが、「ひつじ草」とは、スイレンのこと。名前の由来は、未(ひつじ)の刻に花が咲くからことらしいが、朝から夕方まで咲くそうだ。「琵琶湖周航の歌」の作詞をした小口太郎、作曲の吉田千秋も20代で亡くなった。2人は会ったことがあったのだろうか?「昨日は猛烈な順風で殆ど漕ぐことなしに雄松まで来てしまった。雄松は淋しい所で松林と砂原の中に一軒宿舎があるだけだ。羊草の生えた池の中へボートをつないで夜おそくまで砂原にねころんで月をながめ美人を天の一方に望んだ。今朝は網引きをやって面白かった。今夜はこの今津に宿る。 今津で 小口」■小口太郎が今津から友人に宛てたハガキ■ 消印 大正6年6月28日 午後9~12若くして亡くなった作詞者の小口だったが、この歌を作った時は青春真っただ中。そして、「ひつじ草」と書いてある偶然に、ビックリした。「琵琶湖周航の歌」作詞:小口太郎作曲:吉田千秋1.われは湖(うみ)の子 さすらいの 旅にしあれば しみじみと 昇る狭霧(さぎり)や さざなみの 志賀の都よ いざさらば2.松は緑に 砂白き 雄松(おまつ)が里の 乙女子は 赤い椿の 森陰に はかない恋に 泣くとかや3.波のまにまに 漂えば 赤い泊火(とまりび) 懐かしみ 行方定めぬ 波枕 今日は今津か 長浜か4.瑠璃(るり)の花園 珊瑚(さんご)の宮 古い伝えの 竹生島(ちくぶじま) 仏の御手(みて)に 抱(いだ)かれて 眠れ乙女子 やすらけく5.矢の根は深く 埋(うず)もれて 夏草しげき 堀のあと 古城にひとり 佇(たたず)めば 比良(ひら)も伊吹も 夢のごと6.西国十番 長命寺 汚(けが)れの現世(うつしよ) 遠く去りて 黄金(こがね)の波に いざ漕(こ)がん 語れ我が友 熱き心三高では明治26年に初めて琵琶湖周航が行われ、以後学生たちによる恒例行事になっていました。昭和15年ころまで行われていました。三保ケ崎から西岸を北上する時計回りのコースで、4泊5日、もしくは3泊4日の日程。■琵琶湖周航の歌:高島市■■琵琶湖周航の歌■■桜三昧2泊3日:福井県と琵琶湖湖西地方■■2015年4月7日(火)■国内第三位の美:養浩館(ようこうかん)■■4月8日(水)■一筆啓上:丸岡城■■湖北の「かくれ里」菅浦(すがうら)■■4月9日(木)■■今津:ヴォーリーズ建築■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
2015.04.22
コメント(0)
-

滋賀県・今津:ヴォーリーズ建築
■2015年4月9日(木)■湖北のかくれ里:菅浦■から、琵琶湖西岸沿いの桜のきれいな道路にそって今津に行った。今津市のウリ、ヴォーリーズの建物と「琵琶湖周航の歌」が出来た地ということ。まず、行ったのが「今津ヴォーリーズ資料館」。大正12年(1923)百三十三銀行今津支店として建築され、その後合併して滋賀銀行今津支店となりました。滋賀銀行の移転により、昭和54年(1979)今津町図書館として開館。図書館の移転により平成15年(2003)ウォーリズ資料館として開館しました。■今津ヴォーリズ資料館■この建物の場所は、江戸時代には、金沢藩今津役所が置かれていたという。水運しかなかった頃、琵琶湖は、今津は、大事な所だったのだろうなと思う。ヴォーリーズは、琵琶湖の対岸の近江八幡に住んでいたので、エンジン付きの船で今津にもよく来たらしい。■今津基督教会館同じ通りに可愛らしい、今津教会がある。幼稚園の建物とつながっていて、幼稚園児とよく似合う建物だ。その大きさ(小ささ)と屋根の形、植物の絡む門など、可愛い。今津の「今」が、ひっくりかえっているが、これは間違いではなく、中国の「てん書体」。 ■今津ヴォーリーズ資料館■所在地 : 高島市今津町今津175番地 TEL : 0740-22-0981 開館時間 : 午前10時~午後5時 休館日 : 月曜・12/28~1/4 ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
2015.04.21
コメント(0)
-

湖北の「かくれ里」菅浦(すがうら)
■2015年4月8日(水)「菅浦(すがうら)」をご存知ですか・・・。2014年10月6日、滋賀県長浜市西浅井(あざい)町の「菅浦の湖岸集落景観」が、国の重要文化的景観に選定されました。菅浦は琵琶湖北端に位置し、三方を山に囲まれた小さな集落ですが「陸の孤島」ではありません。毎日新聞2014.11.5■福井県にある丸岡城■の後は、滋賀県の琵琶湖北にある菅浦(すがうら)に行った。写真の車が止まっている所は、かつては琵琶湖。石垣があるところからが陸。つい数十年前まで、車の通る道がなく、島ではないのに、交通は船だったそうだ。ガイド氏に案内してもらったが、ここは、書きつくせないほど面白ところだった。■中世には外敵から民を守る強固な自治組織「惣(そう)」があった。室町時代、菅浦が武装集団の舟数万漕(そう)に囲まれ、村存亡の危機を迎えたと村の古文書「菅原文書」(国の重要文化財)にある。交通は、船だった。だから、船で敵が来たらすぐ分かる。しかし細い道があったのでその出口と入口に門を作った。四足門という。陸路、敵が来た場合、この門の下の方に置いてある石をどける。すると、門はすぐ倒れるようになっているという。そして、茅葺の屋根に火を放って敵の侵入を防ぐのだそうだ。門をささえる向かって右の柱が、真ん中に寄り過ぎている。それによって、門を倒し易いのだそうだ。■供御人(くごにん)平安期から菅浦の民は朝廷に食物を献上する「供御人(くごにん)」だった。京の帝に仕える民たちは湖の交通・漁業権も保証されていたのだろう。■淳仁天皇が隠れ住んだという伝説。政争で退位させられた淳仁天皇は「淡路(あわじ)国」に流され、若くして亡くなったというのが定説。しかし、流されたのは「淡路」ではなく「淡海(あわみ)」で、たどり着いた菅浦の地に隠れ住んだという伝説が今の地元で語り継がれている。私たちが泊まったのは「つづらお」という国民宿舎だったが、この「つづらお」は、淳仁天皇が逃げてくる時、つづらに入って尾根を越えたことに由来しているという。写真は、神社の参道から。■須賀神社淳仁天皇など三神を祭る須賀神社。「須賀」は菅浦の当字だと私は思っている。また、「菅(すが)」はヨシのような植物ではないかとも推測する。菅浦地区から少し行った所に「ヨシ群落保全地域」保全地区というのがあった。育てて、門の屋根を葺くのかもしれない。■白州正子■が書いた「かくれ里」という有名な本がある。白州正子は、全国各地のまわって、「かくれ里」を紹介したが、ここ菅浦も紹介している。写真のお堂に座って写真を撮ったのだそうだ。明治に至るまでの約800年間の村の自治に関する貴重な古文書が残っている菅浦集落。いつの時代の歌なのか次のような歌が残っていた。菅(すが)はよいとこ うしろは山で前はみずうみ竹生島(ちくぶしま)■桜三昧2泊3日:福井県と琵琶湖湖西地方■■2015年4月7日(火)■国内第三位の美:養浩館(ようこうかん)■■4月8日(水)■一筆啓上:丸岡城■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
2015.04.20
コメント(0)
-

ボタニカル・ライフ:ハーブ・すました雑草
(略)そのへんを歩いている普通のばばあがポリジだのキャラウェイ言ってるくらいで、俺は最初、やつらが息も絶え絶えで病院からもらってくる薬のことだろうと思っていた。まあ、ハーブは半ば薬だからまったく間違いというわけでもない。(略)どいつもこいつも生えたばかりの風体で生彩がなく、どう見ても雑草である。いや、ハーブなんて、実際雑草なのだが、売られ方でその正体がばれているところが悲しいのである。そして、その高級感のなさが俺の性に合うのだ。それを世の中の田舎者は、ハーブ育成があたかもヨーロッパ趣味のように扱いやがる。まさに言語道断である。あいつらは意地汚い雑草であり、放っておけば自らの首をしめるまでに育ってしまう大食らいなのだ。(略)あの強さがまずいい。(略)育ちかけのやつを植え替えてやればあとは適当に水でもやっておけばいいし、枯れたと思っても復活の可能性が高い。なんせ雑草である。ペンペン草を家の中やらベランダで後生大事に育てているような不条理がまたなんともいえず価値転倒的である。 娘2人と花屋に行った。下の娘、レイが植物を育てたいと言い始めたのだ。「ハーブは?」と長女のミナが言った。やはり、ミナも「ハーブ栽培」という流行に乗っているのだろうか。しかし、私は、ネギを進めた。「使う時、根っこを切って、植えていたら根付くよ」と私。それに、植木鉢にすーっと伸びたネギは、美しい。おしゃれな雑貨屋やカフェの前に、素焼きの鉢に植えたネギを見ることはよくある。ネギは日本のハーブだと思う。なぜ、ネギや紫蘇やニラではいけないのだろう?「それを世の中の田舎者は、ハーブ育成があたかもヨーロッパ趣味のように扱いやがる。」作者の言葉にそのとうりと思う。まぁ、うちにも、ハーブはあるけどね・・・。■ボタニカル・ライフ■庭のない都会暮らしを選び、ベランダで花を育てる「ベランダー」。そのとりあえずの掟は…隣のベランダに土を掃き出すなかれ、隙間家具より隙間鉢、水さえやっときゃなんとかなる、狭さは知恵の泉なり…。ある日ふと植物の暮らしにハマッた著者の、いい加減なような熱心なような、「ガーデナー」とはひと味違う、愛と屈折に満ちた「植物生活」の全記録。 第15回講談社エッセイ賞。■ベランダ:消え去るもの■■アラビカ種コーヒー■■胡蝶蘭:第二の人生■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
2015.04.19
コメント(0)
-

ジヌよさらば~かむろば村へ~★お金恐怖症
■ジヌよさらば~かむろば村へ~:あらすじ■♪音が出ます!さわれない、使えない、欲しくない銀行に勤めていながら現金に触るだけで失神してしまう金アレルギーになってしまったタケ(松田龍平)は、仕事を辞め、一銭も使わずに生活しようと東北地方のとある寒村に逃げるようにやってくる。田舎暮らしを甘く見るタケに、過疎の地だからこそ現金や携帯電話が必要なのにと村人たちはあきれ顔だった。面倒見のいい村長・与三郎(阿部サダヲ)は自分が経営するスーパーでタケを雇い、食料の現物支給という形で給料を払うことにする。村人たちから田畑の仕事を教わり、自作でまかなったり物々交換をしたりしながらなんとか暮らすタケ。ある日、村に怪しい男(松尾スズキ)が現れる……。 *田んぼを借りて米を作る。*移動は、もらいものの自転車。*日用品は、手伝いをしている店で物々交換。ケチだからではなく、お金がないからでもなく、ただ、お金が怖いから・・・。彼が生きていけるのは、田舎だから・・・。いや、田舎でも、こういうことは、ないだろう。そういう意味で、ユートピアを描いているのかもしれない。漫画見たいと思ったら、原作は、漫画だった、やっぱり・・・。映画に出てくる人も、片桐はいり、荒川良々、松尾スズキ・・・と個性的。監督、脚本、出演:松尾スズキ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015.04.17
コメント(0)
-

リトル・ダンサー★バレエ男子
■リトル・ダンサー:あらすじ■僕がバレエ・ダンサーを夢見てはいけないの?1984年、ストライキに揺れるイングランド北部の炭坑町。母親を亡くし、父(ゲアリー・ルイス)も兄のトニー(ジェイミー・ドラヴェン)も炭坑労働者のビリー(ジェイミー・ベル)は、ボクシング教室に通っているが、試合に負けてばかりの11歳。そんな時、偶然目にしたウィルキンソン夫人(ジュリー・ウォルターズ)のバレエ教室に強く惹かれ、女の子たちに混じって練習するうちに夢中になっていく。ウィルキンソン先生はどんどん上達するビリーに自分が果たせなかった夢を重ね合わせ、熱心に彼を教える。しかし、家族の金をバレエに使っていたことがバレてしまい、父は激怒。ビリーは悔しさをぶつけるように、一人で踊っていた。だが、ストライキが長引き町中が暗く沈んでいるクリスマスの夜、親友マイケル(ステュアート・ウェルズ)の前で踊るビリーの姿を見て、息子の素晴らしい才能に初めて気づいた父は、彼をロンドンの名門、ロイヤル・バレエ学校に入学させる費用を稼ぐため、スト破りを決意する。それは仲間たちへの裏切り行為であった。だがスト破りの労働者を乗せたバスの中に父を見つけたトニーが、バスを追いかけて必死に止め、父は泣き崩れる。その事情を知った仲間たちがカンパしてくれ、ビリーは学校に行くことができた。15年後。バレエ・ダンサーになったビリー(アダム・クーパー)は、父と兄とマイケルが客席にいるウエスト・エンドの劇場の舞台で、スポットライトに包まれながら堂々と踊るのであった。 10年以上前に映画館でみたような気がする。しかし、細かい所を忘れていたので、もう一度行って見てよかった。家族構成も、お婆ちゃんがいるのを忘れていた。最後に、バレエ・ダンサーとなったビリー役にアダム・クーパー。最後のシーンの素晴らしいこと。あの後、アダム・クーパーの日本公演があって、私も見に行った。(主役がダブルキャストで、アダムでないダンサーの日だったが)「白鳥の湖」といえば、女性のダンサーが華麗に舞う。また、主役ではないが女性の群舞(コールド)も美しい。しかし、アダムが踊ったのは、男性のみの「白鳥の湖」。この演目で初めて、男性の群舞を見た。上半身は、裸、足に羽根をつけて、舞う群舞は、今も、はっきりと覚えている。■マシュー・ボーンの白鳥の湖■■マシュー・ボーン■■アダム・クーパーの白鳥の湖■♪音が出ます!今回、ビリーの家の部屋を見てビックリした。引き戸だったのだ。日本では、引き戸は普通にあるが、イギリスでは、ドアが主流。しかし、ドアだと、狭くて開けられないから引き戸にしたのだろうが、ビリーの家の貧しさがあらわれている。そんな貧しい中、スト破りをしてまでも、息子の才能を伸ばそうとする父親の姿が胸を打つ。ビリーの兄が、必死でスト破りを止め、炭坑で働く仲間がカンパしてくれるというところも泣ける。■おまけ■熊川哲也はロイヤル・バレエ・スクールで、アダム・クーパーと兄の同期であった。兄とアダムは、同学年というのは、アダムが優秀で飛び級で上がったから。■第三回:新・午前十時の映画祭■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
2015.04.16
コメント(0)
-

イミテーション・ゲーム★暗号
■イミテーション・ゲーム:あらすじ■♪音に注意!!挑むのは、世界最強の暗号・・・。1939年、イギリスがヒトラー率いるドイツに宣戦布告し、第二次世界大戦が開幕。 天才数学者アラン・チューリング(ベネディクト・カンバーバッチ)は、英国政府の機密作戦に参加し、ドイツ軍の誇る暗号エニグマ解読に挑むことになる。エニグマが“世界最強”と言われる理由は、その組み合わせの数にあった。暗号のパターン数は、10人の人間が1日24時間働き続けても、全組合せを調べ終わるまでに2000万年かかるというのだ――! 暗号解読のために集められたのは、チェスの英国チャンピオンや言語学者など6人の天才たち。MI6のもと、チームは暗号文を分析するが、チューリングは一人勝手に奇妙なマシンを作り始める。子供の頃からずっと周囲から孤立してきたチューリングは、共同作業など、はなからするつもりもない。 両者の溝が深まっていく中、チューリングを救ったのは、クロスワードパズルの天才ジョーン(キーラ・ナイトレイ)だった。彼女はチューリングの純粋さを守りながら、固く閉ざされた心の扉を開いていく。そして初めて仲間と心が通い合ったチューリングは、遂にエニグマを解読する。 エニグマとは、ドイツの軍事用エニグマ暗号。その暗号を解く機械を考えたのが、チューリングだ。これを解読したのだからチューリングは、英雄と言われなければならない。しかし、このことは、英国政府が50年以上隠し続けた秘密にしてきた。イギリスの国難を救ったのであるのに、チューリングは自分が救った国によって裁かれ、自殺に追い込まれた。彼はゲイだったのだ。1940年代~50年代、イギリス(ほとんどの国)では、ゲイは神を冒涜するものとして罰せられた。ゲイへの偏見が彼を死に追いやった。■チューリングの功績■は、科学と歴史の2つに及ぶ。コンピュータの基礎を築いたのが科学的功績。そして暗号解読でドイツ軍を弱体化し、イギリスに、結果的には世界に平和をもたらしたのが歴史的功績だ。そんな重要なキーマンを42歳の若さで失ったことは、後世に大きく影響を及ぼしたに違いない。今回、映画を見てチューリングの事を知りたくなって色々調べた。★「スティーブ・ジョブズやビル・ゲイツからも崇拝されるコンピューターの初期の発明者」 天才は、天才を知る。★「リンゴ殺人事件」?チューリングは自殺したといわれているが、殺されたのかもしれないという推測もある。その現場には、かじりかけのリンゴが落ちていたそうだ。 ♪殺人現場にリンゴが落ちていた~ガブリとかじった歯形がついていた~「リンゴ殺人事件」という歌があったがなんか、ぴったり。 かじりかけの林檎といえば、アップル社のマーク。スティーブ・ジョブズは、彼のことを崇拝していたというから、ただのリンゴではなく「かじりかけのリンゴ」のマークをアップル社のマークに使ったことは、ただの偶然ではないのかも知れない。 「毒リンゴ」を使って白雪姫の死を演出することで、自分の死が他殺だと主張したかったのかもしれないという見方もあるという。暗号解読によって、ドイツとの戦争を2年早く終わらせたというチューリング。チューリング賞というコンピューターのサイエンスにチューリング賞というのがあるという。こんなスゴイ人がいたことをこの映画で、はじめて知った。彼の悲劇は、50年先を生きたことかもしれない。■アラン・チューリング■・・・・・・・・・・・・
2015.04.15
コメント(0)
-
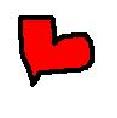
博士と彼女のセオリー★ホーキング博士
■博士と彼女のセオリー■♪音が出ます!生きる希望をつないだのは、無限の愛。天才物理学者として将来を嘱望されていたスティーヴン・ホーキング(エディ・レッドメイン)がケンブリッジ大学の大学院に在籍中、詩を学ぶジェーン(フェリシティ・ジョーンズ)と出会い、二人は恋に落ちる。だが直後にスティーヴンは難病ALS(筋萎縮性側索硬化症)を発症、余命2年の宣告を受ける。そんな彼と共に生きると覚悟を決めたジェーンは、一緒に病気と闘う道を選択し、やがて二人は結婚、そして出産……。 「車椅子の科学者」として名高い、ホーキング博士と妻のジェーンの愛の物語。ケンブリッジ大学時代から映画は始まる。いろんな見方が出来るが、私はいつものように、小さなことが気になった。■ファッション■■アナザー・カントリー■や■炎のランナー■などでも見たが、イギリスの大学生は、ハイソサエティの男子が行く所。特に、ケンブリッジやオックスフォードは、親がお金持ちで、なおかつ、成績優秀の学生が集まるとこのだ。学生たちは、スーツ(ブレザー)にネクタイ。ダンスパーティともなれば、学生でもタキシードで決める。決めるというより、それが当たり前という環境で育ったのだろう。ブイネックのネックに黒い線が入った白いセーターも制服のごとく、みんな着ている。■ミッドセンチュリー■1960年代前半を表すために、所々に、ミッどセンチュリーが見える。ジェーンの母親がいれていた紅茶のセットは、その代表。■環境■ケンブリッジ大学の環境は素晴らしい。川が流れていて、そこでボートをする。広い芝生もある。大学の建物が素晴らしい。吹き抜けの階段は下から見たら美しかった・・・。こんな所で学んだ人がイギリスを動かしているのだろう。 映画の内容は、出会いからまもなく、ホーキンスが発病。医者から、余命2年と言われる。それでも、なお一緒にいたいというジェーン。そして結婚する。子どもが次々と生まれる。もし、ジェーンが、彼と共に生きると言わなかったら、子どもが生まれなかったらホーキンス博士の命は、本当に2年だったのかもしれない。生きなければという気持ちが、彼を生かしたのだろう。余命2年と言われても、結婚し、出産をした2人。普通の人なら選ばない、セオリーを選んだ2人。しかし、その選択は、正しかったのだ。セオリー【theory】理論。学説。・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
2015.04.14
コメント(0)
-
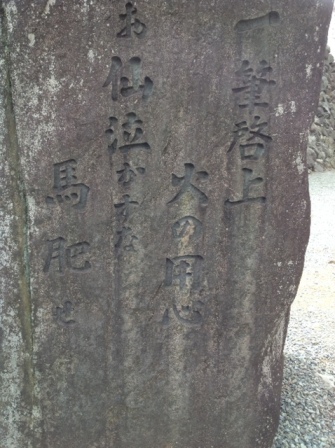
一筆啓上:丸岡城
■4月8日(水)■一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ越前丸岡城は福井地震で倒壊したが、その古材で復興し、現存する天守閣は日本最古とされている。大入母屋の上に廻り縁のある小さな望楼を載せた古式の外観から現存最古の天守とも呼ばれている。その城内には、徳川家の家臣で、この城ゆかりの本多重次の「一筆啓上碑」がある。手紙の内容自体は味も素っ気も無いが、無駄を省いて要件だけを明瞭に伝えているため、武士の文章の手本とされている。自らが留守中に家中を取り仕切る妻に「火事に気を付けるように、使用人への徹底を改めてするように、そして5人の子の内、男子は仙千代だけだから病気に気を付け、武士にとって戦場で命を預ける馬の世話を怠りなくせよ」と妻子を気遣う優しさが見え隠れしている。天守閣の下に、石のシャチが置いてある。このシャチも、もとは、木彫り、銅版貼りであったが、昭和15年~17年にかけての修理の際、に石製のシャチに替えた。当時は戦争のただ中で、銅版が入手出来なかったため、天守閣の石瓦と同じ石材で作った。この石のシャチも、昭和23年6月の福井大震災で屋根から落下。丸岡城の石垣は野面積み(のづらづみ)といわれるやり方。野面積み(のづらづみ)自然石をそのまま積み上げる方法である。加工せずに積み上げただけなので石の形に統一性がなく、石同士がかみ合っていない。そのため隙間や出っ張りができ、敵に登られやすいという欠点があったが排水性に優れており頑丈である。技術的に初期の石積法で、鎌倉時代末期に現れ、本格的に用いられたのは16世紀の戦国時代のことである。野面積みの一種として穴太積み(あのうづみ)があげられるが、穴太積みは穴太衆が手掛けた石垣であって、特に野面積みの一種をいうものではない。穴太衆の技術の高さを誇示する為に江戸後期以降用いられた呼称である。■日本さくら名所100選 ■にも選ばれた丸岡城。■一筆啓上賞■■丸岡城■■2015年4月7日(火)■桜三昧2泊3日:福井県と琵琶湖湖西地方■■国内第三位の美:養浩館(ようこうかん)■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
2015.04.11
コメント(0)
-

国内庭園、第3位の美:養浩館(ようこうかん)庭園
■4月7日(火)■■福井市足羽川の堤に咲く桜■はみごとだったけれど、あまりの寒さに、早々と、養浩館(ようこうかん)庭園に出かけた。日本庭園は大好きなので、期待していたが、期待以上に素晴らしい庭園だった。それもそのはず、米国の日本庭園専門雑誌『数寄屋リビング(ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング)』では、当庭園に日本国内の日本庭園の中で高い評価を与えており、2008年度ランキング以降第3位に選ばれている。「市民の憩いの場所として、また観光の名所として親しまれている名勝養浩館庭園は、江戸時代には「御泉水(おせんすい)屋敷」と呼ばれ、福井藩主松平家の別邸でありました。」という名前の通り、庭園内を水が流れる。明治時代、廃藩置県によって福井城は政府所有となりますが、御泉水屋敷の敷地は引き続き松平家の所有地として、その福井事務所や迎賓館としての機能を果たしました。明治17年には松平春嶽によって「養浩館」と名づけられ、その由緒については由利公正が明治24年に「養浩館記」を記しています。また養浩館は、その数寄屋造邸宅や回遊式林泉庭園が早くから学会で注目され、すでに戦前に建築史・庭園史の専門家による調査がなされています。庭園は、大きな池を中心とした回遊式林泉庭園<かいゆうしきりんせんていえん>です。広い水面に対して立体的な変化をもたせるさまざまな工夫がなされてます。岸辺の周遊や舟による鑑賞、また屋敷内からの眺望も考慮していると思われます。 かつては、このこの池にうつった月を愛でていたのだろう、「御月見ノ間」があった。今回は、さっと見てしまったが、もっとしっかり見ればよかったと思うくらいに、気にいった。新緑の頃は、どんなにか美しいだろう。 ■養浩館庭園:サイト■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
2015.04.10
コメント(0)
-

桜三昧2泊3日:福井県と琵琶湖湖西地方
4月7日~9日の2泊3日、福井県:福井市と滋賀県:湖西地方で桜を満喫してきた。*福井市足羽川の堤に咲く桜*のみごとなこと!!しかし、気温は真冬並み。{{ (>_
2015.04.09
コメント(0)
-

♪大阪環状線の発車メロディ
JR大阪環状線全19駅のホームで流れる発車メロディーが決まった。JR西日本が16日、未定だった15駅分を発表した。桃谷駅は故・河島英五さんの「酒と泪(なみだ)と男と女」、天王寺駅は和田アキ子さんの「あの鐘を鳴らすのはあなた」、天満駅はaikoさんの「花火」など、大阪ゆかりのアーティストの曲が目白押しだ。大阪環状線は昨年、大阪駅の「やっぱ好きやねん」(故・やしきたかじんさん)など4駅で発車メロディーを始めた。一つの路線の全駅で違う曲を流すのは全国的にも珍しいという。3月22日より使用。♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪先日、天王寺駅からJR環状線に乗ったら、聞き覚えのあるメロディが流れて来た。「あの鐘を鳴らすのはあなた」だ。そういえば、ニュースでそんなことをいってたなと思いだし、大阪駅に着くまで曲を聞きながら行った。★が分かった曲。■JR大阪環状線の発車メロディーと選曲理由★天王寺 あの鐘を鳴らすのはあなた(和田アキ子) 四天王寺の鐘にちなむ。 鐘の音を響かせたアレンジに♪寺田町 Life Goes On(韻シスト) 昨年書き下ろした大阪環状線イメージソング♪桃谷 酒と泪(なみだ)と男と女(河島英五) 駅近くでライブハウスを経営した、亡き河島の代表曲♪鶴橋 ヨーデル食べ放題(桂雀三郎withまんぷくブラザーズ) 焼き肉で有名な街。冒頭は「焼き肉バイキングで食べ放題」★玉造 メリーさんのひつじ(アメリカ民謡) 電車型ビル「ビエラ玉造」。窓の高さを音階に見立て、この曲を表現★森ノ宮 森のくまさん(アメリカ民謡)※ 「森」といえばこの曲だった★大阪城公園 法螺(ほら)貝(オリジナル) 戦国時代の戦を象徴する「大坂の陣」を思い起こす★京橋 大阪うまいもんの歌(アメリカ民謡『ゆかいな牧場』) 大阪のご当地ソング。駅周辺のにぎやかさをイメージ★桜ノ宮 さくらんぼ(大塚愛) 駅名や近くの大川の桜から。 数ある「桜」の曲から大阪出身者を選ぶ♪天満 花火(aiko) 天神祭の花火から。編曲でおはやしのリズムも加えた ★大阪 やっぱ好きやねん(やしきたかじん) 大阪を愛した故・やしきたかじんの代表曲♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪環状線は、内回りと外回りがあるので、今度は外回に乗ってたしかめてみよう。♪福島 夢想花(円広志) 「回って、回って…」の歌詞が環状線を思い起こす♪野田 一週間(ロシア民謡) 歌詞冒頭は「日曜日に市場へ出かけ…」。 大阪市中央卸売市場が近い♪西九条 アメリカン・パトロール(アメリカ民謡) ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの乗換駅♪弁天町 線路は続くよどこまでも(アメリカ民謡) 昨春閉館した「交通科学博物館」が高架下にあった♪大正 てぃんさぐぬ花(沖縄県民謡) 駅周辺は沖縄からの移住者が多い♪芦原橋 祭(芦原橋太鼓集団『怒』) 「太鼓の町」で知られる。 地元の太鼓集団のオリジナル曲♪今宮 大黒様(文部省唱歌) 駅に近い「大国町」や「大国主神社」にちなむ♪新今宮 交響曲第9番「新世界より」(ドボルザーク) 通天閣がある「新世界」の最寄り駅新世界は、大阪の色を濃く残す町。そこに、ドボールザークを持ってきた所が面白い。・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
2015.04.06
コメント(2)
-

播州の小京都:醤油(しょぉゆぅ)こと
■龍野の町屋カフェと老舗店■が見どころの、兵庫県・龍野市。龍野は、醤油の町でもある。醤油やもろみの自動販売機があるのは、 しょぉゆぅこと!全国的に有名な東丸醤油も龍野市にある。写真は、「うすくち龍野醤油資料館」。博物館の建物は、本館が菊一醤油本社社屋として建てられた後ヒガシマル醤油の先代本社として使用され、徒歩2分の場所にある別館は先々代ヒガシマル醤油本社として使用された後に龍野醤油協同組合本館として使用されていたという歴史を持つ近代建築である。本館と別館は共に平成19年度の県の景観形成重要建造物に指定された。■うすくち龍野醤油資料館■昭和50年代以降、東丸醤油は、川の向こう側に引っ越し。「うすくち龍野醤油資料館」の中にある、「麹室(こうじむろ)」 しょぉゆぅうこと!■播磨の小京都・龍野で花見■■私の城下町:龍野で花見■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
2015.04.05
コメント(0)
-

龍野の町屋カフェと老舗店
■播州の小京都:龍野■は、空襲にあわなかったことと、狭い地域で「開発」出来なかったことが幸いして、古い町並みが今に残っている。1979年創業の、このカフェ「エデンの東」も古い町屋カフェ。ここで、コーヒーを、いや珈琲(この字がピッタリ)を飲んで、ひと休み。■町屋喫茶 エデンの東■住 所:兵庫県たつの市龍野町上川原52 電 話:0791-63-1273定 休 日:毎月5・15・25日(5のつく日) 営業時間:AM8:00~PM8:00写真がダメよ、ダメダメ・・・。(ノД‘)次に向かったのは、明治創業当時のままのレトロな本屋「伏見屋」。二階は木造の回廊で吹き抜け天井の珍しい建物。私が中学、高校と毎日のように通った書店だ。その頃の伏見屋は、中学生、高校生で溢れていた。通っていた頃は気がつかなかったけれど、店の奥が深い。■写真参照■昔は、店の浦の揖保川(いぼがわ)の水運を使って本を仕入れていたからだとか。次に行ったのは、大正15年創業の井戸糀製造所龍野の産業が酒造りから醤油造りに転換した後も麹は必要とされ、特に薄口醤油の開発が麹の需要に拍車をかけた。いろんな所に行っているが、「麹」専門店があるのは、ここ以外知らない。■和歌山県:湯浅■で「麹店」の看板は見たが、営業はしていないようだった。ここで、使いこまれた「もろぶた」を見た。「もろぶた」は、「もろ味蓋」の変化したもので、昔、丸めた餅を入れて、重ねていた。まったく同じ形だが、ここのは、だいぶ小さい。名前も「もろぶた」ではなく「麹(こうじ)ぶた」と言っていた(うろ覚え)。この店は奥に細長く、作業場がある伏見屋書店と一緒で、かつては、水運を利用していたのか。龍野に住んでいた頃は、母が、この店で麹を買い、味噌を作っていたが、私は、出来あがりの味噌を購入。少し行くと、觜崎屋(はしさきや) 本店寛保2年(1742)の創業以来、十代にわたり伝統の味を守り続けている和菓子の老舗。龍野藩主脇坂侯のお国自慢の一つとされ、後に明治天皇お買い上げの栄にも浴した淡紅色の煉り羊羹をはじめ、名産うすくち龍野醤油を皮に練り込んだ醤油まんじゅう、四季折々の目にも鮮やかな生菓子等、小京都龍野ならではの味を楽しめる。店内には、昔から使い続けてきた木型など、和菓子の道具類も展示している。お土産に和菓子を買う。そして、その店の80代くらいと思われる女主人にかねてから気になっていたことを聞いた。「ここの創業者は『觜崎』のご出身なんですか?」と。その答えは、思っていた通りだった。龍野の近くに■觜崎(はしさき)■という地名がある。店の名前は、創業者の出身地からとったのだそうだ。この店で、お土産に、和菓子6個入りを買う。寛政10年(1798年)の城下町地図を包装紙に使われているという。武家屋敷は黒、町人の家は赤で示されており、このお店もちゃんと載っているそうだ。しかし、お土産は、もう渡してしまった。しまった・・・。_| ̄|○次は、うち用に買おう。カフェ「エデンの東」、本の「伏見屋」、「井戸麹店」、そして和菓子の「觜崎屋(はしさきや)」は、同じ通りに並んでいる。名所や名店がぎゅっと詰まっていて、歩きやすいところも、龍野の魅力だ。・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
2015.04.04
コメント(0)
-

播磨の小京都・龍野で花見
■播磨の小京都といわれる兵庫県・龍野市。■小さな動物園の近くにある、グランド、その一角にある駐車場から、龍野城の方に歩いて行く。登り下りのある細い道を通って行くと神社の桜がきれいだ。少し歩くと、龍野藩主脇坂氏の上屋敷跡にある歴史的建造物、聚遠亭(しゅうえんてい)という茶室がある。聚遠亭(しゅうえんてい)の名前の由来。老中松平定信が脇坂氏の上屋敷を訪問した際、庭園から龍野城城下町越しに淡路島や瀬戸内海の島々を望める眺めの素晴らしさから当地を「聚遠の門」と呼んだ。その故事から浮堂は「聚遠亭」と命名された。聚遠亭のとなりには、藩主の「別邸」がある。「ここ、側室さんの家でしてん」とここの管理の女性が教えてくれた。中は昔のままで、いざという時には、地下道からの逃げ道が今も残っている。小雨の中で、苔が美しい。そこから、龍野城までは、すぐ!実はこの道は、中学時代にいつも通っていた道だ。私の通っていた龍野中学は、今のお城の場所にあった。グランドを作る広さがないので、私たちは、体育の時間になると、学校(現在のお城)から、「聚遠亭」の横を通って、神社を通り小径を抜け、グランドへと通っていた。私たちが卒業すると、学校は平野部に移転され、残った跡地にお城が出来たというわけだ。今から半世紀以上前の「龍野昔話」。■聚遠亭■・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
2015.04.03
コメント(0)
-

私の城下町:兵庫県・龍野市で花見
♪格子戸を潜り抜け見上げる夕焼けの空に誰が歌うのか子守唄 私の城下町~13歳から24歳まで暮らした兵庫県・龍野市は、龍野藩5万3千石の城下町の面影から「播磨の小京都」と呼ばれ、また童謡「赤とんぼ」の作詞者、三木露風の生誕地として「童謡の里宣言」を行っている。そんな町に桜を求めて4月1日、行って来た。駐車場に植えてある桜も満開。お城の桜も満開。グランドの周りの桜も満開・・・。小径の桜も満開。神社の桜も満開。町を流れる揖保川(いぼがわ)の堤の桜も満開。町が桜の花で華やかだ。花見の観光客を迎える支度で、係の人たちは忙しそうだった。4月1日は、残念ながら小ぶりの雨。この雨で桜よ、散るなと願いながら見て回った。・ ■兵庫県竜野市(たつの市)■・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
2015.04.02
コメント(0)
-

娘の魅せる収納
■老前整理■をやっても、やっても追いつかない。なんでこんなに、モノが多いのだろう?心が折れそうになる時には、インテリアの本を買ってこうするぞ!と思うようにする。しかし、本が増えた。(ノД‘)そんな時、先日会った娘・ミナが、「流しの上に棚をつけた」と写真を見せてくれた。それが上の写真。棚にS字フックをかけ、キッチン用品をかけている。鍋敷、まな板、ザル、ブラシ・・・。どこにでもあるキッチン用品だが、シンプルで美しいと思う。見せる収納というが、「魅せる収納」だ。きっと、決して高いものではない、それらを選ぶ時でも、さっと買わないで、あれこれ考えたのだろう。「本当に必要な物、本当に美しい物以外持ってはいけない」と言ったのはウィリアム・モリスだったか・・・?「必要で美しい物以外持ってはいけない。それも少しだけ」というのがシンプルで美しく暮らすには、物を減らすしかないと改めて思った。そして、美しい物だけを残すのだ。身近な人が美しく暮らしているとやる気が出てくる。・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・
2015.04.01
コメント(0)
全20件 (20件中 1-20件目)
1









