2015年10月の記事
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-

10月のおしゃれ手紙:火山列島に暮らす。
▲阿蘇山は白い煙をはいていた。▼右の赤みを帯びた岩は、噴火の岩だと南島原市で友人が言った。▲別府では、いたる所から湯煙があがっていた。▼「火砕流」という言葉を知った、島原の雲仙普賢岳。他にも、桜島、口永良部島(くちのえらぶじま)・・・。九州は、活火山がいっぱいだ。火山は隙間のおお い溶岩でできているので降った雨は、地面に染み込む。染み込んだ水は地下水になって、湧き出す。火山は,天然の浄水装置として美しい水となり湧き出すのだ。島原の湧水は、雲仙普賢岳のおかげだし、富士山の麓の柿田川の湧水は有名だ。温泉や美しい水を売りにするなら、火山という負のものを背負っていることを忘れてはいけない。日本は火山列島だということを忘れて、原発を再開することは、愚かなことだ。何百年も噴火していないからといっても、何百年は、46億年という地球の歴史からいうと、瞬きするほどの時間なのだから。日本は地震列島で火山列島で、私たちは、その上に住んでいると■九州に行って実感した。■■10月に見た映画■*マイ・インターン*バクマン。*ヴェルサイユの宮廷庭師 ■書きのこしたネタ■*島原大変、肥後迷惑*ノーベル賞ネタ*大阪市のレトロビル、大丸心斎橋店が建て替えで取り壊しになる。*からほり御屋敷再生複合ショップ「練」*無くなった川を歩く*「あさが来た」・・・京都、大阪の交通*スエーデン・ストックホルムの市庁舎*北欧グループツアーに来ていた人たち*花に恨みはないけれどinノルウェイ*佐渡:地名*佐渡:金山*古いアルバム*新たに発見「は行」と「パ行」*琵琶湖ネタ*古い針箱*植物の痛み*天才プルシェンコ*皇帝ダリア*四国ネタ*電気自動車*「ビッグイシュー」*ダウントン・アビー*「大阪人の格言」*小浜島・・・漂着ごみ*は行とぱ行の歴史*渡し舟*西行寺*娘の引っ越しの荷物が多いことと簡素な引っ越し*街で見つけたデザイン。*白虎隊の歌*「君をだいて」*「とっさの方言」*近つ飛鳥*近つ、遠つ*キラキラネーム*和泉市の美術館*もっと緑が欲しいのだ!(駐車場)*みどり学*あさぶら*小説「アーレンガート」*「北極星」*アルミ缶エコ*江戸時代、和歌山の防災意識*子供と春の花と桜・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.31
コメント(0)
-

九州:さよなら九州
■10月10日(土)~11日(日)■福岡県・柳川■観光の後は、帰途につくために大分県・別府に向かった。フェリーで大阪から別府に着いたときは、別府の郊外を見たので、別府のウリの温泉にかかわる場所を見て回った。温泉の湯の花を作っている所があった。藁ぶき屋根の小屋が続く、景色は、重要無形民俗文化財に指定されている。■明礬温泉の湯の花小屋■大分県別府市の明礬温泉では、地熱地帯に「湯の花小屋」と呼ばれるわらぶき小屋を建て、小屋の中に青粘土を敷き詰め、粘土から析出し結晶化した湯の花やミョウバン(明礬)を収穫する方法が採られている。この方法により製造される湯の花は、生産量も多く全国に広く流通している。ここにも、沢山の中国からの観光客が来ていた。地熱を利用して 、卵や野菜を蒸していて、卵を食した。別府港からフェリーに乗り、大阪へと帰る。帰りは土曜日だったので、フェリーの中ではジャズのライブやテープ投げをやるといっていたので、さっそくテープ投げをやった。投げたテープで海が汚れるのではと思っていたが、きわどい所で船員さんが、引き揚げて行った。遠のいて行く別府の夜景。夜明けに、外に出ると、橋が見えた。時間からすると明石海峡大橋だろう。ああ、帰ってきた。こうして、10月1日から11日までの九州旅行は無事、終わった。 ■九州旅行2015.10.1~10.11■2015年10月1日(木)夜:大阪港出港■3009歩■10月2日(金)大分県:別府着■10377歩★内成(うちなり)の棚田★由布川渓谷★別府公園■10月3日(土):日田市と小鹿田(おんた)■11421歩★日田市内★バーナード・リーチ@小鹿田(おんた)★小鹿田(おんた)焼きの里にて■10月4日(日):阿蘇■6690歩■阿蘇山は大きい■■10月5日(月)■13419歩★高千穂峡★高千穂あまてらす鉄道の悲劇★南阿蘇鉄道・高森線に乗る。■10月6日(火)■5511歩★長崎県・島原の湧水を歩く。■10月7日(水)■13233歩★南島原を友人と歩く★島原のキリシタン墓を歩く。■10月8日(木)■5237歩★島原の失われた鉄道と島原の乱など■10月9日(金)■13658歩★映画「柳川掘割物語」と北原白秋記念館★柳川の掘割をたのしむ。■10月10日(土)■6869■10月11日(日)■695★さよなら九州・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.29
コメント(0)
-

九州:柳川の掘割をたのしむ
■10月9日(金)■柳川の川下りは「お堀めぐり」です。■柳川市は市全体に「堀」が大規模に巡る「水郷のまち」です。これはもともと海に近い低くじめじめした湿地帯に「堀」を掘り、掘り起こした泥を盛り上げて乾田をつくり、「堀」は貯水池として生活用水、農業用水、さらには地下水を涵養し地盤沈下を防ぐなど、他に代替できない機能で、柳川の人々の生活、柳川土地全体を支えてきました。柳川の光や緑をそのまま水面に映し、清らかなやさしい水の流れであっても、力強く私たちを支えてくれる 「堀割」を船頭さんのさす竿に任せてめぐっていく、ひとときの舟旅が柳川の川下りです。そんなお堀のやさしさに、身も心もゆだねてみませんか?■水の都として知られる福岡県柳川市■を縦横につらぬく水路網「堀割」。そこで、舟で掘めぐりをした。舟は上りと下りがあり、通常、川下りが行われる。流れに逆らう川上りは、結婚式に使われるのだそうだが、私たちが乗ったのは、川上りだった。東京から来た夫婦、沖縄のおばあの長寿を祝っての一家4人、それに私たち夫婦のオールジャパン。船頭さんは、歌はイマイチだが、シャベリが面白い人。舟がぶつかりそうになって私が「ぶつかる!」と言うと「大丈夫、会社の舟だから」と言って笑わせる。川下りの団体さんに「ニーハオ」声をかけ、返事がなければ「アンニョハセヨー」言って、笑わせる。何回もそんな時があったが、ある時は「この舟は、一緒に乗ってるんや」とすれ違いの船頭さんに言われていた。中国、韓国入り乱れて乗っているという。九州は、中国、韓国に近いからか、他の観光地でも多くの人に出会った。▲ここは、掘割沿いのお店で船頭さんいわく、「ドライブスルー」。10月とはいえ、暑かったので、アイスクリームを買った。沖縄の人が船頭さんに差し入れ。(気が利くわ!)▲大きな船着き場跡。こんな所は、大きな店があって、荷下ろしをしたのかもしれない。レンガ倉庫の並ぶ所は、「佐賀のがばいばあちゃん」の撮影場に使った所だそうだ。堀の水を使った庭園などもあり、あちらこちら、絵になる、柳川。この柳川の地名は、魚を捕る簗(やな)からきた簗川(やながわ)だったという説もある。北原白秋は「柳河」と書いている。柳川がふさわしいような所だ。一時は■埋め立てられて■しまいそうになった掘割だが今では、観光として、農業用水、防火用水、遊水地としてなくて、歴史的な遺産で、なくてはならないものと認識されているので、埋め立てられる心配はなさそうだ。■柳川のお堀■下船してから、市のボランティアガイドさんに案内されあちこりとよく歩いた。 ■九州旅行2015.10.1~10.11■10月1日(木)夜:大阪港出港■3009歩■10月2日(金)大分県:別府着■10377歩★内成(うちなり)の棚田★由布川渓谷★別府公園■10月3日(土):日田市と小鹿田(おんた)■11421歩★日田市内★バーナード・リーチ@小鹿田(おんた)★小鹿田(おんた)焼きの里にて■10月4日(日):阿蘇■6690■阿蘇山は大きい■■10月5日(月)■13419歩★高千穂峡★高千穂あまてらす鉄道の悲劇★南阿蘇鉄道・高森線に乗る。■10月6日(火)■5511★長崎県・島原の湧水を歩く。■10月7日(水)■13233★南島原を友人と歩く★島原のキリシタン墓を歩く。■10月8日(木)■5237★島原の失われた鉄道と島原の乱など■10月9日(金)■13658★映画「柳川掘割物語」と北原白秋記念館★柳川の掘割を楽しむ。・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.28
コメント(0)
-

火山国日本で、原発は危険だ!!
九州電力の川内原発2号機(鹿児島県薩摩川内市)が、8月の1号機に続いて再稼働した。東京電力福島第1原発事故後に策定された新規制基準に基づく原発の再稼働は、全国で2基目となる。菅義偉官房長官は「原子力規制委員会が、世界で最も厳しいといわれる新基準に適合すると認めたものは再稼働させていく政府方針に変わりはない」と強調する。■西日本新聞■2015年10月21日 1時37分政府は、本当に川内(せんだい)原発が安全と思っているのだろうか?「世界で最も厳しいといわれる新基準」というのは何を基準にしているのだろうか?日本は、地震や火山の噴火が多い国。今月、約10日間九州をまわったが、あちこりで火山活動の印を見た。大分県は温泉県というだけあって、町のあちこちから温泉の湯煙が立っていた。熊本県の阿蘇山は噴火を繰り返し、現在も白い煙を出している。長崎県では、島原半島の雲仙普賢岳の大噴火が記憶に新しい。「火砕流」という言葉を一般の私たちが知ったのも、ここが噴火したから。過去に起こった噴火で流れ出した溶岩で赤くなった岩も見た。鹿児島県にも桜島の噴火のニュースはよく聞く。■九州■は火山がしかも活火山が多いのだ。火山の噴火による原発への影響はないのだろうか?こんな危険と隣り合わせの所がなぜ安全なのかと思う。調べていたら、専門家も火山を問題視していた。■噴火で立ち上った巨大な黒い噴煙は■、数日後に広がった火口から、さらに太く噴き上がった。やがて、上の部分が崩れるように下降を始め、大地にたたきつけられると火砕流となり、すべるように地上を広がっていった。セ氏1千度近い火砕流は、すべてのものを焼き尽くしながら広がり続け、100キロ以上離れた原発をのみ込んだ――。まるでパニック映画のワンシーンのようだが、日本にあるいくつかの原発では、起こりえる場面だ。その原発とは、泊原発(北海道)、伊方原発(愛媛)、玄海原発(佐賀)、川内原発(鹿児島)の4つ。東京大学地震研究所火山噴火予知研究センターの中田節也教授がこう警告する。「4つとも、過去に超巨大噴火の影響を受けたと考えられる場所にあります。火砕流が過去に到達したと思われる場所に建っているのです」100歩譲って、火山噴火は関係ないとしても、使用済みの核燃料の処分が出来ていないのに、なんで再稼働をするのか!!川内原発の立地自治体である薩摩川内市と鹿児島県は再稼働に同意したが、薩摩川内市の周辺自治体であるいちき串木野市や姶良市は再稼働に反対の立場だ。薩摩川内市は、鹿児島県は、本当に責任をとれるのか?フクシマの惨事から何も学んでいない政府と国民!!!このことを一人でも多くの人に知らせなければならない。「今回、地元自治体からも要望として出された『国が責任を持つ』ことについて、デタラメだということが露呈されたと思う。たとえば原子力損害賠償法で定められている損害賠償措置額の上限は1200億円だ。震災による福島第一原発の事故発生前から変わっていない。まIAEAは過酷事故対策として5層の防御を定めているが、依然として日本は第3層まで。つまり福島の事故の反省が活かされておらず、本当に国が責任を持つ対策がなされていない状況で、再稼働へ進んでいます。今回の経緯から、こうしたデタラメさが多くの国民に知れ渡り、再稼働への疑問はさらに高まると思います」(ダイヤモンド・オンライン編集部 片田江康男)・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.27
コメント(0)
-

昔語り:祭のこづかい
今から60年くらい前の秋祭は大人も子どもも年間でも最大級の楽しみだった。御神楽が舞い、笛がなり神社は賑やかだった。普段は静かな小さな村にも、祭になるとお宮の参道に多くの出店がならんだ。綿菓子売りに、ヨーヨーつり・・・。おもちゃの刀や人形を売る店と狭い参道の両側に出店が並び、活気があった。普段は、私たちきょうだいは、親からこづかいをもらったことがなかったが祭の日は特別で、ひとり50円のこづかいをもらった。うちが貧しいということを知っていたので、それ以上を望まなかった。まだ小学校に行く前の妹と一緒に参道を歩くと、妹が「これを買う」と人形を指さした。その人形は50円だった。「それを買(こ)うたら、綿菓子やヨーヨーが出来んようになる」と私は止めた。それでも妹は買うというので、私は許可した。人形を手にして、妹は嬉しそうだった。私は、自分の50円の中から綿菓子を買って、妹と食べた。祭が賑やかではなくなったのは、いつからだっただろう。50円は今の貨幣価値でいくらぐらいだったのだろう?500円くらいなのかもしれないが、当時、私の家では、祭だけに許された贅沢だった。賑やかな祭が終わると待ち遠しかった分、さびしかった。母がよく■「待つが祭■と言っていたのを思い出す。・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.26
コメント(0)
-

映画「柳川掘割物語」と北原白秋記念館
■柳川掘割物語:あらすじ■掘割は残った。水の都として知られる福岡県柳川市を縦横につらぬく水路網「堀割」。市街と水路がへだてなく隣接し、人々の暮らしにとけこんでいる様子がある。本作は、その成り立ちから現代にいたる水辺の暮らしと知恵を紹介しながら、近代化の波におされて荒廃した堀割の再生をめざす住民のたたかいをあわせて描いている。 『風の谷のナウシカ』のヒット後、次回作のアニメーション映画のために柳川市を訪れた高畑氏。そこで水路再生の中心人物広松伝氏と出会い、活動に感銘を受け柳川をただの背景にするのではなく、その活動をドキュメンタリーで製作しようとなったと言われています。撮影期間は、一年の予定が延び、三年かかったと言われています。当時は、スッタフが住み込んだり作業したりするために、柳川市内に一戸建てを借りての撮影でした。監督は、高畑勲氏。映画柳川堀割物語/1987年監督 ・脚本:高畑勲、監修・脚本協力:広松伝(柳川市職員) ■10月9日(金)「柳川掘割物語」という映画を20年くらい前に見て、いつか行ってみたいと思っていた柳川。福岡県の水郷で名高い柳川市に行った。掘割の舟下りを楽しむために、多くの観光客が来る柳川。しかし、柳川のウリである、掘割は、駐車場になるはずだった。 ドブと化した水路を埋め立て、駐車場などにすれば利用価値が高まるという都市計画が実施されそうになった時、役所の一係長が、水路の歴史的な役割などを調べ上げ、むしろ浄化して生活に役立てることを逆提案、柳川の水が甦ったという事件です。この話に触発され、柳川を舞台にした記録映画という形で実現しました。「毎日のように水を使い、それを口にふくみながら、私たちは水の持つ心地よさやありがたさに、少し鈍感になりすぎてはいないだろうか―。」時代は変わっても、水と人間のかかわりあいは、大きな問題として私たちの前に存在しています。柳川は、また詩人、■北原白秋■の生まれた地でもある。白秋は、「水の構図」という詩で次のようにうたっている。「水郷柳河こそは、我が生れの里である。この水の柳河こそは、我が詩歌の母体である。この水の構図この地相にして、はじめて我が体は生じ、我が風はなった…」 白秋の記念館にも行ったが、カラタチの木があった。「からたちの花」 からたちの花が咲いたよ。 白い白い花が咲いたよ。からたちのとげはいたいよ。 青い青い針のとげだよ。■北原白秋・画像■柳川市議会では、掘割を埋めることに決定していた。しかし、それを県知事にまで直訴し、ひっくり返した市役所の一職員広松伝氏。この北原白秋の家も掘割の前にる。だから美しいのだが、その掘割は広松伝氏らの努力によって守られたことを知っていると柳川の風景は、また違った見方が出来る。 ■九州旅行2015.10.1~10.11■10月1日(木)夜:大阪港出港■3009歩■10月2日(金)大分県:別府着■10377歩★内成(うちなり)の棚田★由布川渓谷★別府公園■10月3日(土):日田市と小鹿田(おんた)■11421歩★日田市内★バーナード・リーチ@小鹿田(おんた)★小鹿田(おんた)焼きの里にて■10月4日(日):阿蘇■6690■阿蘇山は大きい■■10月5日(月)■13419歩★高千穂峡★高千穂あまてらす鉄道の悲劇★南阿蘇鉄道・高森線に乗る。■10月6日(火)■5511★長崎県・島原の湧水を歩く。■10月7日(水)■13233★南島原を友人と歩く★島原のキリシタン墓を歩く。■10月8日(木)■5237★移動日:島原の失われた鉄道と島原の乱など■10月9日(金)★映画「柳川掘割物語」と北原白秋記念館・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.25
コメント(0)
-

九州:島原の失われた鉄道と島原の乱など
■10月8日(木)■島原内■を観光した後、■南島原市に住む友人に会った■島原半島をフェリーで出て、天草経由で福岡県・柳川に向かう。その前に、昨日、友人の家の近くで見た廃止になった鉄道が気になって仕方がない私は、鉄子か!!■南阿蘇鉄道に乗る■■高千穂あまてらす鉄道の悲劇■口之津港は、フェリー乗り場の近くにバスのたまり場がある。そこで、運転手さんに、「鉄道跡はどこですか?」と聞くと、「そこです」と教えてくれた。なんと、バスが止まっているは、かつての駅のプラットホーム。今は、線路も枕木もなくなっている。電車が通っていた時には駅を降りたらすぐ、フェリー乗り場があって、便利だっただろうに・・・。かつては、昨日、バスで行った■小浜にも鉄道が■通っていたそうだ。■廃線探索 雲仙鉄道■■口之津駅■が無くなる前、雲仙普賢岳の噴火活動が1991年(平成3年)頃から活発となり、同年火砕流により南島原 - 布津間が約半年間不通となる。もともと赤字路線だったから、これを機に廃線になったのだろうか。島原に来て、知ったことがある。それは「島原の乱」。子どもの頃、■「南海の美少年」■という歌が流行った。1 銀の十字架(クルス)を 胸にかけ 踏絵おそれぬ 殉教の いくさ率いる 南国の 天草四郎 美少年 ああ はまなすの 花も泣く■歌・橋幸夫:音が出ます!■天草四郎は、天草の人。島原の乱になんで天草四郎?と思っていたが、キリシタン弾圧に立ち上がり、島原の貧しい百姓たちの一揆と一緒になって闘った、つまり島原、天草共同戦線ということだ。今度の旅行まで天草と島原のことをほとんど知らなかったので、やっと腑に落ちた。また、歌の二行目、「踏絵おそれぬ・・・」を「海へおそれぬ・・・」と覚えていて、おかしいな、この歌と思っていたが、おかしいのは私だった。(恥) もうひとつ、「島原の乱」は、島原城にたてこもったと思っていたが、「原城」という古い城だった。2 天の声聴く 島原の 原の古城址(しろあと) 此処こそは 神の砦ぞ 立て籠もり 怒濤に叫ぶ 美少年 ああ 前髪に 月も泣く「南海の美少年」の2番にちゃんと 原の古城址(しろあと) 此処こそはと歌ってある。 原城にたてこもった、百姓やキリシタンは、ほぼ全滅。あまりにも悲劇だ。だからこそ、語り継がれているのだろうが・・・。もうひとつ、今回、知ったことがある。それは、天草は、熊本県ということ。ずーーーーと長崎県と思っていた。くまモン、すまぬ。 _| ̄|○ ■九州旅行2015.10.1~10.11■10月1日(木)夜:大阪港出港■3009歩■10月2日(金)大分県:別府着■10377歩★内成(うちなり)の棚田★由布川渓谷★別府公園■10月3日(土):日田市と小鹿田(おんた)■11421歩★日田市内★バーナード・リーチ@小鹿田(おんた)★小鹿田(おんた)焼きの里にて■10月4日(日):阿蘇■6690■阿蘇山は大きい■■10月5日(月)■13419歩★高千穂峡★高千穂あまてらす鉄道の悲劇★南阿蘇鉄道・高森線に乗る。■10月6日(火)■5511★長崎県・島原の湧水を歩く。■10月7日(水)■13233★南島原を友人と歩く★島原のキリシタン墓を歩く。■10月8日(木)★島原の失われた鉄道と島原の乱など・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.24
コメント(0)
-

九州:島原のキリシタン墓を歩く
■10月7日(水)長崎県・島原は、「島原市」、「雲仙市」、「南島原市」からなる半島。泊まったのは雲仙市。■島原内■を観光した後、■南島原市に住む友人に会った。■口之津という古い港で会い、彼女の家のある「加津佐」まで歩く。私のために、日傘まで用意してくれていた。彼女の家の近くの松林で、彼女の作ってくれたお弁当を食べた。友人は、大阪時代と変わらず、優しい。彼女の家でお茶をしたり、お手製のパンを食べたりしたが、帰らなくてはならない。バスの本数が少ないのと、泊まっている宿舎の迎えの車の時間が決まっているからだ。その前に、友人の家のすぐそばにある、キリシタンのお墓を見に行った。私は、お墓が、それも古いお墓が大好きと言うと友人は笑った。 首のない像を見て、これは、キリシタンで、死んだ後のお墓さえもこういう形にされたのかもと二人で語り合った。丸い形が彫ってある石は、なんだろう・・・? なかにしれいの作品、「長崎ぶらぶら節」という本の中で、お墓の拓本をとっているシーンがあったが、調べれば面白いだろうな・・・。▲長崎県指定文化財のキリシタン墓もあった。▲石の墓で、十字の印のある西洋風の細長い形だ。友人と別れてひとりで「小浜」に行くためにバスに乗った。20~30分乗ったが、客は数人だった。バスの便数が少ないので、病院に行く人は、自家用の舟で行く人もいるそうだ。小浜に着いた! って、オバマか!!小浜は今では小さな港町だが、かつては、長崎・茂木港と行き来があった。当時、客が蒸気船を使って小浜温泉まで湯治に来ていたそうだ。長崎ちゃんぽんが、小浜に伝わり、「小浜ちゃんぽん」というご当地名物になっていた。一日中、ぶらぶらと歩き回ったが、久しぶりに友人と話して楽しかった。 ■九州旅行2015.10.1~10.11■10月1日(木)夜:大阪港出港■3009歩■10月2日(金)大分県:別府着■10377歩★内成(うちなり)の棚田★由布川渓谷★別府公園■10月3日(土):日田市と小鹿田(おんた)■11421歩★日田市内★バーナード・リーチ@小鹿田(おんた)★小鹿田(おんた)焼きの里にて■10月4日(日):阿蘇■6690■阿蘇山は大きい■■10月5日(月)■13419歩★高千穂峡★高千穂あまてらす鉄道の悲劇★南阿蘇鉄道・高森線に乗る。■10月6日(火)■5511★長崎県・島原の湧水を歩く。■10月7日(水)■13233★友人と歩く★島原のキリシタン墓を歩く。・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.23
コメント(0)
-

九州:南島原を友人と歩く
■10月7日(水)長崎県・島原は、「島原市」、「雲仙市」、「南島原市」からなる半島。長崎に住む友人と「口之津(くちのつ)」という所で9時半頃、会う約束をした。彼女はケイタイを持っていないので、果たして会えるのかと心配だったが会えた!!何年ぶりだろう。その日別行動する夫と別れ、友人と二人で相談して、歩いて向かったのが友人家。100mほどいくと彼女が空き地に止まり「昔は、ここまでが港だった」と説明してくれた。見れば「南蛮船来航の地」という碑があった。*永禄5年(1562):有馬義直、口之津港を貿易港として開港。*永禄10年(1567):司令官トウリスタン・ヴァスダウェイガの南蛮定期船の外、二隻の南蛮船が入港。*天正4年(1576):司令官シマンガルシーアのポルトガル船(ジャンク)が入港。*天正7年(1579):ポルトガル船入港、巡察師ヴァリニャーノが口之津に着く。 全国宣教師会議を口之津で開催した。*天正8年(1580):南蛮定期船(ジャンク)入港。*天正10年(1582):南蛮船入港。(これが最後の入港) フロイス、口之津に居住し、京都から届いた本能寺の変をこの地からヨーロッパに発信した。:::::::::こうして、開港以来、20年間、南蛮貿易商業地として栄えてた。この間、キリシタン布教の根拠地とし、また西洋文化の窓口としても栄えたのである。(以上、口之津町教育委員会) 坂道を越えて歩く。 道に咲く花を見たり、飼われているヤギを見たり、休んだり・・・。神社の鳥居には、「唐人町」の字があった。今は静かな所だけれど、戦国時代には、いろんな人が来ていたのかもしれない。ヨーロッパから宣教師も来たというこの地には翼のある仏さま、「有翼少年像=エンジェル」が祀られているのだそうだ。彼女の通ったという高校の側を通りを見たり・・・。 海に出た。この右半分の赤い岩は、噴火の時のものだそうだ。「加津佐駅」と書いてある建物があったが、廃止になった鉄道の駅跡だ。2008年3月31日限りで廃止になったが、それまでは、友人も、彼女の娘も使っていたそうだ。今は線路さえなく、この建物がなければ、ここに鉄道があったことも分からないところだった。素晴らしい松林が続く。友人がいつも猫を連れて散歩するコースだそうだ。松原越しに見えるのは、女島(めじま)。島といっても陸続きで女島はおよそ200万年前に玄武岩質の火山が水中で噴火してできたものだそうだ。白い砂と松林に女島がアクセントになって、昔から名所になっていたそうだ。・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.22
コメント(0)
-

九州:島原(長崎県)の湧水を歩く
■10月6日(火)■熊本県・阿蘇■に連泊した後、次の目的地、長崎県・島原に向かった。■熊本から長崎県島原へはフェリーで60分。■もし、陸路を行くなら何時間もかかる。■島原半島は■「島原市」、「雲仙市」、「南島原市」からなる半島。フェリーが着いたのは、島原市で主な観光地もここにあると言っても過言ではない。島原市に着いて、観光ガイドさんと待ち合わせの場所で会った。水が豊かだと聞いていたので、水に関することで町を案内してもらった。待ち合わせ場所には、鯉が泳いでいる水路があったが、あまり水がきれいなので、鯉が早死にするのだとか。この辺りは湧水が多く、家に湧水のあるうちを「水屋敷(みずやしき)」というそうだ。そんな水屋敷を代表する■湧水庭園「四明荘」■で、お茶をいただいた。室内から見る庭は、水が美しい。こんな家だったら、どこにも行きたくなくなるんだろうなと思うくらい。水屋敷のほかに、どうしてもみたい武家屋敷跡の水路に案内してもらった。藩政時代の武家屋敷跡には、当時、飲用、防火などのために道路中央に造営された水路が、現在も約400m遺されていて、縦横に整然と区画された町並みを流れる水は清冽である、昔ながらの石垣が当時の面影を偲ばせています。■湧水散策■明治維新まで、7つの町筋には総て街路の中央に湧水の水路が設けられていたが今ではここだけになっている。ガイドさん(無料)に1時間と伝えていたが、1時間では、水の名所だけでも回り切れない。島原市だけで1日は欲しい所だ。 ■九州旅行2015.10.1~10.11■10月1日(木)夜:大阪港出港■3009歩■10月2日(金)大分県:別府着■10377歩★内成(うちなり)の棚田★由布川渓谷★別府公園■10月3日(土):日田市と小鹿田(おんた)■11421歩★日田市内★バーナード・リーチ@小鹿田(おんた)★小鹿田(おんた)焼きの里にて■10月4日(日):阿蘇■6690■阿蘇山は大きい■■10月5日(月)■13419歩★高千穂峡★高千穂あまてらす鉄道の悲劇★南阿蘇鉄道・高森線に乗る。■10月6日(火)■5511★長崎県・島原市で湧水を歩く。・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.21
コメント(0)
-

ヴェルサイユの宮廷庭師★女性庭師
■ベルサイユの宮廷庭師:あらすじ■♪音が出ます!!世界一有名な宮殿の<秘密>がいま明かされる。17世紀のフランス。国王ルイ14世(アラン・リックマン)は、栄華のシンボルとしてヴェルサイユ宮殿の増改築を計画する。庭園を設計するのは、国王の庭園建築家アンドレ・ル・ノートル(マティアス・スーナールツ)。そして、彼と共に野外舞踏場“舞踏の間”を任されたのは、稀有な才能を持つ女性庭師サビーヌ(ケイト・ウィンスレット)だった。心に傷を負い、孤独に生きてきたサビーヌの人生に突然舞い降りた宮廷からの招待状。歴史と伝統の世界の中で、自分の人生の花を咲かせることができるのか?ヴェルサイユ庭園誕生の陰で、1人の名もなき女性が起こす愛と奇跡とは……。 人は誰も植物が好きで庭が好きだ。庭が持てないものは、鉢植えででも植物を身近に置きたがる。しかし、ヴェルサイユの庭は単に、庭が好きだからで生まれたのではない。■ヴェルサイユ宮殿■の建設よりも労力を費やされている噴水庭園には、宮殿建設の25,000人に対し、36,000人が投入されている。そして、その噴水にはルイ14世の三つの意図が込められている。★「水なき地に水を引く」ヴェルサイユには近くに水を引く高地がない。ルイ14世は10km離れたセーヌ川の川岸にマルリーの機械と呼ばれる巨大な揚水装置を設置し、堤の上に水を上げさせた。そして古代ローマに倣って水道橋を作って、水をヴェルサイユまで運び、巨大な貯水槽に溜め込んだ。こうして水なき地で常に水を噴き上げる噴水庭園を完成させ、自然をも変える力を周囲に示した。★「貴族を従わせる」ルイ14世は10歳の時にフロンドの乱で、貴族たちに命を脅かされたことがある。ルイ14世はこの体験を一生忘れず、彼は貴族をヴェルサイユに強制移住させた。 「ラトナの噴水」は、ギリシャ神話に登場するラトナ(レートー)が村人に泥を投げつけられながらも、息子の太陽神アポロンを守っている銅像と、その足元にある蛙やトカゲは神の怒りに触れて村人たちが変えられた像を、模った噴水である。ラトナとアポロンはフロンドの乱の時、彼を守ってくれた母と幼いルイ14世自身を示し、蛙やトカゲに変えられた村人は貴族たちをあらわしている。王に反抗をする者は許さないという宣言を示している。「太陽神アポロンの噴水」は、アポロンは天馬に引かれて海中から姿をあらわし、天に駆け上ろうとしているものを模った噴水である。アポロンはルイ14世自身をあらわし、彼が天空から地上の全てを従わせると示している。★「民衆の心をつかむ」ルイ14世は民衆の誰もがヴェルサイユに入るのを許し、民衆に庭園の見方を教える「王の庭園鑑賞法」というガイドブックを発行した。それには「ラトナの噴水の手前で一休みして、ラトナ、周りにある彫刻をみよ。王の散歩道、アポロンの噴水、その向こうの運河を見渡そう」と書かれている。民衆は、ガイドブックに従って庭園を鑑賞することで、貴族と自然を圧倒した王の偉大さを刷り込まれていった。夏、ヴェルサイユでは毎晩のように祭典が催され、訪れた民衆はバレーや舞劇に酔いしれた。 こうしてみると、単にガーデニングが好きな派手すぎな王様というだけではないのだなと思う。ヴェルサイユといえば■マリーアントワネット■を思うが太陽王と言われたルイ14世がパリ市内からヴェルサイユに宮殿を増改築する時の話で、アントワネットは登場しない。しかし、宮廷の中では、不倫や嫉妬心が渦巻いていて、面白い。主演のケイト・ウィンスレットは、こういう服装をさせたら一番かもしれない。しかし、あの恰好では、庭仕事ができない。大きく開いた胸など、虫に刺されるのでは・・・と心配だ。それにしても、フランスの宮廷の庭は、幾何学的で自然がない。庭園の中に自然風景の美しさを入れようとするイングリッシュ庭園の方が好きだ。・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.20
コメント(0)
-

九州:湧水公園と南阿蘇鉄道に乗る
■10月5日(月)■高千穂峡(たかちほきょう)■の絶景を見た後、■高千穂あまてらす鉄道■で30分の「鉄道の旅」をし、南阿蘇鉄道「高森線」に乗ることに・・・。私は、鉄子か!!高森駅で電車を待つ間に、高森湧水公園を見に行った。宮崎県・高千穂と熊本県の高森をつなごうとしてトンネルを掘っていたら、水脈に当たり、トンネルを断念したという所。鉄道の敷地後だけに、細長い公園だ。柳の緑と水が美しい公園。高千穂、高森間がつながらなくなったため、他の完成したトンネルも今は、酒蔵として利用している。南阿蘇鉄道株式会社(みなみあそてつどう)は、熊本県で旧国鉄特定地方交通線の鉄道路線高森線を運営している南阿蘇村・高森町など沿線自治体が出資する第三セクター方式の鉄道会社である。今は、高森から立野という区間しか走っていないけれど、国鉄時代は、熊本や博多に通じる電車だった。今は、駅前も閑散としていた。たった一両しかない小さな電車には私たち二人と数人の高校生。出発前に「途中の駅から、台湾の団体さんが乗りますが、ご協力ください」と運転手さんは、ボソボソとアナウンスした。阿蘇山という観光地だけに、運転手さんは、説明もしてくれたが、小声で聞き取りにくかった。途中の駅に近づくと、カメラの放列。台湾の団体さんが車両を写していた。そして乗り込んできて、急に車内がいっぱいになった。乗客の数が増えようが運転手さんは、相変わらず、ボソボソと外の景色を話す。30分かけて立野に着くと、30分ほど待ち時間があったので、うろうろして時間をつぶした。JRの車両が止まっていた。この立野という駅は、かつては乗り継ぎの駅だったが南阿蘇鉄道の終点となっている。同じ駅なのに、バラバラの車両が・・・・帰りは、高校生で満員だった。必要としている人はいるのに切り捨てられた高森線・・・。■立野(たての)駅■立野駅はJR九州の豊肥本線と、南阿蘇鉄道の高森線の2路線が乗り入れる。高森線は当駅が起点である。JR豊肥本線はスイッチバック構造となっており、ななつ星in九州を除く全ての特急・普通列車が停車する(ななつ星in九州は運転停車扱い)。 豊肥本線も以前は当駅発着の列車が設定されていた。写真は、立野駅を降りて陸橋より南阿蘇鉄道を俯瞰する。 ■九州旅行2015.10.1~10.11■10月1日(木)夜:大阪港出港■3009歩■10月2日(金)大分県:別府着■10377歩★内成(うちなり)の棚田★由布川渓谷★別府公園■10月3日(土):日田市と小鹿田(おんた)■11421歩★日田市内★バーナード・リーチ@小鹿田(おんた)★小鹿田(おんた)焼きの里にて■10月4日(日):阿蘇■6690■阿蘇山は大きい■■10月5日(月)■13419歩★高千穂峡★高千穂あまてらす鉄道の悲劇★湧水公園と南阿蘇鉄道・高森線に乗ったこと。・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.19
コメント(0)
-

九州:高千穂あまてらす鉄道の悲劇(宮崎県)
■10月5日(月)■高千穂峡(たかちほきょう)■の絶景を見た後、高千穂あまてらす鉄道の高千穂駅に行った。高千穂線(たかちほせん)は、かつて宮崎県延岡市の延岡駅から宮崎県西臼杵郡高千穂町をつないでいた。2005年9月の台風14号による被害で運行休止となり、2008年12月28日に全線が廃止された。廃線に追い込まれた、高千穂鉄道の跡地を保存、利用して公園化に向けて活動しているのが「高千穂あまてらす鉄道」。現在スーパーカートを使って天岩戸駅までの往復運行をしています。軽トラを新幹線と蒸気機関車という形をし、観光客を乗せている。「始発駅:高千穂」を出て運転手兼ガイドの軽妙な語りでスーパーカートは走っていく。次の駅は「天岩戸(あまのいわと)」だがもちろん、止まらない。鉄橋に出た。この鉄橋は105mの高さで、見晴らしは抜群。ここで、運転手さん2人がシャボン玉を吹いてくれた。100m以上のところから、ふわりふわりとシャボン玉が飛んだ。鉄橋を渡るとトンネルが見えたが、そこへは、行けないようにフェンスがしてあった。途中、トンネルに入ると、イルミネーションをトンネルの天井に写し、愉しませてくれる。往復30分の「列車」の旅は終わった。高千穂線の悲劇は台風の被害だけではなかった。高千穂鉄道がまだ国鉄だった頃、宮崎県・高千穂から、熊本県の国鉄高森線まで繋ぎ、そこから熊本駅に続くようにしようという計画があった。そこで、トンネルを掘っていると、水が、しかも大量の水が溢れ、計画は白紙になった。1975年(昭和50年)2月 建設中の高森トンネル坑内で異常出水事故。 水が出た所は今、親水公園になっている。 高森町内の井戸水が枯れ水道が断水するほどの大量の水だったそうだ。ガイド兼運転手さんの話だと、トンネルの水さえ出なければ、なんとか再建できたと思うと悔しそうだった。悲運だなと思う。地元民や観光客に無くてはならなかった交通手段も、なくなれば忘れられるのだろうか? ■九州旅行2015.10.1~10.11■10月1日(木)夜:大阪港出港■3009歩■10月2日(金)大分県:別府着■10377歩★内成(うちなり)の棚田★由布川渓谷★別府公園■10月3日(土):日田市と小鹿田(おんた)■11421歩★日田市内★バーナード・リーチ@小鹿田(おんた)★小鹿田(おんた)焼きの里にて■10月4日(日):阿蘇■6690■阿蘇山は大きい■■10月5日(月)■★高千穂峡★高千穂あまてらす鉄道・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.18
コメント(0)
-

九州:高千穂峡(宮崎県)
■10月5日(月)高千穂峡(たかちほきょう)は、宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井にある五ヶ瀬川にかかる峡谷である。国の名勝、天然記念物に指定されている(五箇瀬川峡谷(高千穂峡谷))。阿蘇カルデラをつくった火山活動によって、約12万年前と約9万年前の2回に噴出した高温の軽石流(火砕流の一種)が、当時の五ヶ瀬川の峡谷沿いに厚く流れ下った。この火砕流堆積物が冷却固結し溶結凝灰岩となり、柱状節理が生じた。その柱状節理が、グニャっっと曲げられているところがあるが、地球の力を感じて感動する。溶結凝灰岩は磨食を受けやすいため、五ヶ瀬川の侵食によって再びV字峡谷となったものが高千穂峡である。高さ80m~100mにも達する断崖が7kmにわたり続いており、これを総称して五ヶ瀬川峡谷(高千穂峡)と呼ぶ。また、峡谷は貸しボートで遊覧できるようになっており、峡谷に流れ落ちる日本の滝百選の一つである「真名井の滝」の至近まで近づくことが出来る。ボートに乗って下から見る景観は、上からとまた違って、迫力がある。狭い所をボートが行きかうので、ぶつかり合ったりする。時々、大きな穴のあいた岩を見た。滴り落ちる水が、何万年という時をかけて作った作品。▲ボート乗り場今回、ボートに乗ったのは、初めてということがあるが、体力的なことがある。数十メートル下のボート乗り場に行くには、急な階段の上り下りが必要。もし次に行くとしても体力があるかどうかだ。また、ツアーで来ると、絶対にボートには乗らないだろう。そういうわけで、ボートに乗れてよかったと思う。漕ぎ手は、しんどかっただろうが・・・。別府市で■温泉より由布川渓谷■を見たのも、体力のあるうちに階段を昇り降りする所に行った方がいいと思ったからだ。高千穂峡を上から見て歩いていた時途中で橋があった。石造りの年期の入った橋で周りの景色になじんでいた。ここで写真を撮るべしというピクチャーポイントがある。それが、三つの橋が見えるというところ。分かりにくいので、赤で線をひいてみたが、ここが高千穂峡の一番いい場所とは思わない。むしろ、自然の景色の中に、人口の構造物を置くということを私は好まない。「ニッポン景観論」私が日々ストレスに感じていることに日本の景観への意識の低さがあります。品のない色の看板があふれ混沌とし調和せず見苦しい景色が増えています。景観破壊にショックを受けた下関の門司港レトロハイマートについても写真入りで紹介されていました。歴史とかその土地の良さを無視した唐突なタワーを建設する愚かさに当時びっくりしました。景観関して寛容すぎると思います。見る人に不快感を与える場合もあります。周囲環境、歴史、文化、自然を無視した景観破壊は観光立国ニッポンやおもてなしなどに反すると思います。景観破壊は大きな損失です。それに早く気づいて欲しいと思います。美しい街並みや美しい自然は財産でです。 ■九州旅行2015.10.1~10.11■10月1日(木)夜:大阪港出港■3009歩■10月2日(金)大分県:別府着■10377歩★内成(うちなり)の棚田★由布川渓谷★別府公園■10月3日(土):日田市と小鹿田(おんた)■11421歩★日田市内★バーナード・リーチ@小鹿田(おんた)★小鹿田(おんた)焼きの里にて■10月4日(日):阿蘇■6690■阿蘇山は大きい■■10月5日(月)■★高千穂峡・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.18
コメント(0)
-

九州:阿蘇山は大きい
■10月4日(日)くまモンが迎える熊本県にキタ――(゚∀゚)――!!。熊本県と言えば阿蘇山。阿蘇山は、世界でも有数の大型カルデラと雄大な外輪山を持ち、「火の国」熊本県のシンボル的な存在として親しまれている。中でも9万年前の噴火 は最も規模が大きく噴出量は約600立方kmを越えており、火砕流は九州中央部を覆い一部は海を越え山口県秋吉台まで達し、火山灰は日本海海底、北海道まで達した。朝鮮半島でも確認されている。外輪山の中に何万人もの人が生活し、電車が走っているって、どんだけすごい規模やねん、阿蘇山!!今、噴火が話題になっているが、それは、外輪山の中に出来た山からの噴火だ。カルデラを見下ろす大観峰などは、カルデラ噴火前の火山活動による溶岩とカルデラ噴火による火砕流堆積物(溶結凝灰岩)で構成された山である。この「大観峰」という名前に「??」と思っていた。するとここは、かつて、「遠見ヶ鼻(とおみがはな)」とよばれていたという碑が立っていた。往昔阿蘇豪族が手野宮川の上流に居館を構えて阿蘇谷に君臨した。外敵防御の西の砦がここ遠見ヶ鼻であった。この由緒ある名前が大観峰と変わったのは凡そ次の理由がある。大正十一年(1922年)五月十七日 徳富蘇峰は初めて阿蘇山に登り次いで遠見ヶ鼻にも足を延ばした。その時同行の人に勧められて大観峰と命名した事情が紀行「煙霞勝遊記」に書かれている。(以下略)という碑が立っていた。徳富蘇峰、勝手に地名を変えるな!!同行の人、そそのかすな!!!遥か昔より使われてきた名前を勝手に変えるなんて、不遜ではないか!!!徳富蘇峰らが勝手に名前を変えてもそれに従うことはなかったのに、なんで大観峰なんて名前でよぶんだろう。プンプン!!「草千里」まで行くと近くに藁で作った「小屋」のようなものがあった。車が無かった頃、人々は草刈りに来て、このような「小屋」を建ててそこで泊まって翌日も働いたそうだ。秋が深くなると寒かっただろうな。秋の田のかりほのいおの とまをあらみ わが衣では露にぬれつつみたいな・・・。 ■九州旅行2015.10.1~10.11■10月1日(木)夜:大阪港出港■3009歩■10月2日(金)大分県:別府着■10377歩★内成(うちなり)の棚田★由布川渓谷★別府公園■10月3日(土):日田市と小鹿田(おんた)■11421歩★日田市内★バーナード・リーチ@小鹿田(おんた)★小鹿田(おんた)焼きの里にて■10月4日(日):阿蘇・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.17
コメント(0)
-
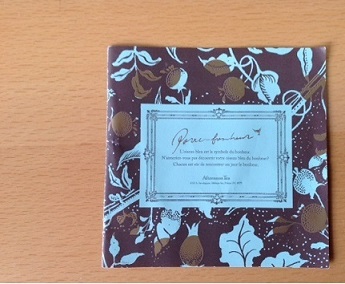
老前整理:捨てられない物を捨てる
二言目には■老前整理■と言って暮らす今日この頃。しかし、捨てられない物もある。それは、美しいもの。いくら美しいからといっても、使わなければ、ごみだ。捨てなければならない。これは、「アフタヌーン・ティー」というお店でもらった小さな冊子の表紙。中もきれいだったが、泣く泣く捨てた。無印良品で買った黒い表紙のA4のノート。これに、貼ってみた。このノートは、予定や切り抜きを貼って旅行に持って行く。旅行から帰ったら、使った頁をはがすから、ノートは、どんどん薄くなり、終わる。終わった頃には、貼り付けた紙も汚れて、捨てるのをためらわない。この他にも、小さなきれいなカードは、しおりの代わりに本に挟むなどして使っている。 *老前整理*老いる前に身辺を見直して、今後の生活にいらないものを整理すること=老前整理を提唱してきた著者による、老後に快適な生活を送るための生き方指南書。 高齢になればなるほど整理はおっくうになり、悪化すればごみ屋敷のような社会問題に発展する。 本書では、片付けられずモノに囲まれて暮らす人が、老前整理の考えを知り、思い切って整理に取り組み、生き生きとした暮らしを取り戻すさまが描かれる。 実用的で社会的使命もある新しい整理術の提案。 ■私の整理術■■一つにまとまるものは、まとめる。*シャンプーとリンス・・・ひとつにした。*化粧水、乳液、美容液、栄養クリームが合体したのがあったのでそれにした。■同じ用途のものを2つ置かない。*石鹸とボディソープは石鹸にする。■買い置きをしない。*衣類の洗剤など無くなってから買いに行っても充分間に合う。■使い切る。*旅行先から持って帰った(持って帰ってもらいたくない) 歯ブラシは、細かいところを磨く。■適量を考える。*タオルなど沢山あるが、私が使うのは■このタオル。■使い始めたら止められない柔らかさ。タオルくらい贅沢したい。■置き場所を決める。*これは、どんなものにでもいえるが、置き場所を決めてそこに置く。■化粧品。*これは、私が原因。ついつい買う、口紅やアイブロー、香水。 最近は買っていないが、積もり積もって、多いこと、多いこと。もう買わないが、その量を減らすためにも、お化粧をしなければ・・・。まだ道半ばだ。(ノД`)・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.16
コメント(0)
-

九州:小鹿田(おんた)焼きの里にて
■10月3日■大分県日田市■から車で30分ほど行ったところにある焼き物の里、小鹿田(おんた)。その村の中を小さいけれど豊かな川が流れている。それを利用して「唐臼(からうす)」が上がったり下がったりして山からとってきた土を砕く。かつては、小鹿田(おんた)では、米搗き用と土用の2つの唐臼を持っていたそうだ。数年前役人がやって来て、これではあまりにも原始的だというわけで、コンクリートの建物に新式の電気装置の機械を据え付けたが、村人たちにとって必要以上の陶土が出来るのと、慣れないベアリングに油をさすのを忘れたのとで・・・彼らが使っている木の杵には油なんかささなくともいい・・・この機械はやがてがたがたになり壊れてしまった。「日本絵日記」 ギーゴットン、ギーゴットンという音は今も小鹿田(おんた)で聞こえている。唐臼のみで土づくりをする集落は世界でも小鹿田(おんた)だけだそうだ。「残したい日本の音風景百選」に選ばれている。▲唐臼で搗かれた土は、水槽に入れられ、より細かくする。その後、土を乾かすのだが、山間部である小鹿田(おんた)は日当たりが悪く、窯の上に並べている。(写真右の上部)▲皿や茶わんなどを作って天日干しする。▲窯にいれる。村には10の窯があるがそのうち、5つは共同釜だそうだ。▲明治という字の入った古材があったがこれは窯を焚く材料だろうか。登り窯とギーゴットン、ギーゴットンという、唐臼(からうす)の音が、聞こえる小鹿田(おんた)。ここで写真を撮っている人に出会った。なんとなく話をして、お互いにブログ持ちと分かり自己紹介をした。■あとりえAYA■というブログを運営する彼女は、「写心」という写真集をくださった。 娘さんからもらったデジカメがきっかけで写真が趣味になったそうだ。(「写心」より)ゆっくりと読ませていただいたが、その中でも、私は、廃屋好きな私は、廃屋の写真にひかれた。思いもよらない嬉しい出会い。ギーゴットン、ギーゴットンという、唐臼(からうす)の音とともに忘れられない思い出になった。記念に直径15センチほどの小鉢を買った。小鹿田(おんた)焼きの代表的な技法の「飛びかんな」。バーナード・リーチがこの「飛びかんな」を知って大喜びしたそうだ。小鹿田(おんた)に滞在中、■さっそく取り入れて作っている■ 小さな壺も欲しかった・・・。 素朴な感丸出しの水差しも欲しかった・・・。そんなわけで、また行きたい小鹿田(おんた)の里。私が最も感銘するのは、しんそこ心をひとつにした自発的な村全体の行動であった。彼らの心が末永く脈打ち、また下の流れの唐臼がいつまでも地を叩いてくれるように。「バーナード・リーチ日本絵日記」 ■九州旅行2015.10.1~10.11■10月1日(木)夜:大阪港出港■3009歩■10月2日(金)大分県:別府着■10377歩★内成(うちなり)の棚田★由布川渓谷★別府公園■10月3日(土):日田市と小鹿田(おんた)■★日田市内★バーナード・リーチ@小鹿田(おんた)・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.15
コメント(0)
-

バーナード・リーチ@小鹿田(おんた)
♪いくつもの~山を越えて、たどり着いた場所がある。と歌いたいくらいに、小鹿田(おんた)は遠い。昭和28年2月から翌29年10月までの1年半の日記、「バーナード・リーチ日本絵日記」によれば、そんな小鹿田(おんた)に、バーナード・リーチがはるばるとやってきたのは、 *村の陶工たちの再三のたよりだった。村では、ベッドや特別の風呂も用意するから来てくれという。*柳宋悦や濱田庄司という当時の民芸をひっぱる人たちも勧めた。柳は、だいぶ前に、何時間か山道を歩いて小鹿田(おんた)をはじめて訪ねた時の話をしてくれたが、そこの人たちは簡素な、世俗に損なわれない生活を送っており、作っている焼き物もなかなかよいものだということだった。出かけることにしたが、ただし、特別な用意を思い止ませることができてからのことだった。 また、日田では、なぜ九州に来たのかという質問に(当時より)20年ばかり前、故秩父宮が柳の書いたものを読まれて、訪ねたいと言われたが、役人たちもどこにあるのか正しく知らなかったのだ。「バーナード・リーチ日本絵日記」要約。■4月5日それから私たちは車を駆って数マイル行き、長い渓谷に入った。 道はだんだん狭く悪くなり、坂も険しく迫ってきて、高い常緑の杉の木であたりも暗かった。そうして、曲り道に来たとき、木の皮で葺いた屋根と、立っている人々の姿が見えた。 「小鹿田(おんた)の皿山」だ。「バーナード・リーチ日本絵日記」(略)それに答えて私が、まごつきながら、ここに来たのは私自身が勉強するためだが、もしそのお返しに何か御助力できることがあるとすればこんな嬉しいことはない、と言った。「バーナード・リーチ日本絵日記」上の写真は「鹿文大皿」リーチ作 小鹿田(おんた)焼陶芸館にて展示。▲壺(昭和29年)リーチ作 小鹿田(おんた)焼陶芸館にて。リーチの性格を表すような、謙虚なこの挨拶は、きっと当時の人々も喜んだろうと思う。4月1日に東京をたち、その日の夜の船で別府に渡り、4月26日に九州を離れている。当時、バーナード・リーチの行く所は、新聞記者や政治家などが来て大騒ぎだったようだ。記録映画まで作られている。なによりも、「日本絵日記」を読むとよく分かる。小鹿田(おんた)に行く人におすすめだ。■バーナード・リーチ 日本絵日記:用の美■「バーナード・リーチ 日本絵日記」は、昭和28年2月から翌29年10月までの1年半の日記。 ■九州旅行2015.10.1~10.11■10月1日(木)夜:大阪港出港■3009歩■10月2日(金)大分県:別府着■10377歩★内成(うちなり)の棚田★由布川渓谷★■別府公園■10月3日(土):日田市と小鹿田(おんた)■★日田市内・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.15
コメント(0)
-

九州:日田(ひた)市
■10月3日(土)棚田が美しかった■別府■を後にして、日田に向かった。日田は「ひだ」ではなく「ひた」と読む。九州はなぜか濁らない場合が多い。知り合いに「中島」という九州出身の人がいたが「なかしま」と名乗っていた。 「バーナード・リーチ日本絵日記」によると、彼は1954年4月4日に日田に来ている。■1954年4月4日売るまで山を幾つか越えて奥地の日田におもむき、山陽館ホテルに入って・・・。とあるので、ボランティアガイドさんに、「山陽館ホテル」の場所を聞いた。ガイドさんは、「えっ!!バーナード・リーチが日田に来たんですか?」とビックリしていた。本を見せると「わー、どうしよう・・・」とまるで自宅に来たように感動していた。翌、4日、山陽館ホテルで、バーナード・リーチに関するものが残っていないかと聞いたが、ここでも「知らなかったです」と言われた。頼山陽は来たことがあるんですけどとも言っていたので、いいホテルなのだろう。玄関を入ると広いホールが見え、その向こうに川が流れ、屋形船があった。バーナード・リーチは、小鹿田(おんた)に行く途中にこの町に泊まり、小鹿田(おんた)に滞在中、息抜きに日田でとまっているので、たぶん何か残っているのではと思う。日田の豆田という地区では、電線を地中に埋めるなど、努力をしているが、日田の印象は、強くない。それは、日田で行きたかった所に行けなかったからだ。日田の行きたかった所とは、★亀山公園日田は水郷の町といわれるが、その一番美しさが見らる場所だ。そこを、見ないでは、日田に来た理由が分からないではないか・・・。■日田市 亀山公園■★日田リベルテ日田は10万に満たない小さな町だけれど映画館がある。この程度の人口で映画館を持っている市は、あまりないだろう。しかも、この映画館の上映作品は私が見たいものや、見たものが多い。つまり、私好みなのだ!!10月3日にも見たい映画■アドバンススタイル(音が出ます)!!■をやっていた。見たかったけど、却下され、涙。ニューヨークの60歳以上のファッショニスタの映像、見たかったなぁ~~~。ここまで来て、映画もないというかもしれないが、見逃した映画は、見るべし!!今もなお、心残りだ。■ブログ「アドバンススタイル」■ ■九州旅行2015.10.1~10.11■10月1日(木)夜:大阪港出港■3009歩■10月2日(金)大分県:別府着■10377歩★内成(うちなり)の棚田★由布川渓谷★■別府公園■10月3日(土):日田市 小鹿田(おんた)■★日田市内・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.15
コメント(1)
-

バクマン。★漫画の裏側
■バクマン。■友情、努力、勝利、そして恋。目指せ、ジャンプの頂点。“俺たち2人で漫画家になって、ジャンプで一番目指そうぜ!”2人の高校生が抱いた壮大な夢。優れた絵の才能を持つ“サイコー”こと真城最高(佐藤健)と、巧みな物語を書く“シュージン”こと高木秋人(神木隆之介)。クラスメイトの亜豆美保(小松菜奈)への恋心をきっかけにコンビを組んだ2人は、人気漫画雑誌、週刊少年ジャンプの頂を目指す。編集者・服部(山田孝之)に見出され、次々に漫画を生み出してゆくた最高と秋人。だがその前に、ジャンプ編集部と新進気鋭のライバルたちが立ちはだかる。そして、突如現れ、遥か先を走り始めた若き天才漫画家・新妻エイジ(染谷将太)。果たして2人は、ジャンプの頂点に立つことができるのか?! 漫画家としての成功を夢見て奮闘する2人の高校生の姿を描き、テレビアニメにもなった、「DEATH NOTE」のコンビによる人気漫画を佐藤健&神木隆之介の主演で実写映画化した青春ストーリー。画力に優れた最高と巧みな物語を生み出す秋人のコンビが週刊少年ジャンプのトップを目指す。監督は『モテキ』など話題作を数多く手がける大根仁。 漫画というより、漫画の裏側、漫画家の暮らしに興味がある。古くは、手塚治虫の住んでいた伝説のアパート「トキワ荘」。手塚治虫がいて、寺田ヒロオがいて、、藤子不二雄がいて、石森章太郎、赤塚不二夫・・・。沢山の漫画家が一緒に食事をし、話をし、議論をし、そして漫画を競い合った・・・。 そんな「トキワ荘」を思わせるような場面が出てきた。手塚賞の受賞の打ち上げでは、キャベツの炒め物を食べる。「法律で決まっている」と言う人がいた。貧乏だったトキワ荘の住人たちは、お金がない時には、キャベツの炒め物で過ごしたのだから・・・。 その人は、「トキワ荘」に憧れていたのだろう。「俺、一番、年上だから、『テラさん』」ともいう。「テラさん」とは手塚の次にトキワ荘に入った寺田ヒロオ。そんな風に漫画の裏を知っているとこの映画は楽しい。しかし、最近の漫画は知らないのでついていけない会話もあったが・・・。それにしても、漫画家とは、なんと不健康な職業だろう。座ったままの同じ姿勢で描き続けることや、アイデアが出ない時のストレス、締切のことなどを考えていたら、絶対に好きでなければ出来ない職業だ。でも、掃除したり電話の取次ぎや食事の世話、アイデアも一緒に考える・・・。そんな手伝いだったらしてみたいと妄想が膨らむ。この漫画の原作は、二人。そのうちのひとりを演じる、神木隆之介がキュート!!■「トキワ荘の時代」梶井純■■「トキワ荘青春日記」藤子不二雄A■■戦後少女漫画史:少女漫画バトン■・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.14
コメント(0)
-

マイ・インターン★老人力
■マイ・インターン:あらすじ■アドバイスひとつで、人生は輝く。家庭を持ちながら何百人もの社員を束ね、ファッションサイトを運営する会社のCEOであるジュールズ(アン・ハサウェイ)は、女性なら誰しもがあこがれる華やかな世界に身を置きながら、仕事と家庭を両立させ、まさに女性の理想像を絵にかいたような人生を送っているかに見えた。しかし、彼女に人生最大の試練が訪れる。そんな悩める彼女のアシスタントとして、会社の福祉事業として雇用することになった40歳年上のシニア・インターンのベン(ロバート・デ・ニーロ)がやってくる。人生経験豊富なベンは彼女に最高の助言を与え、2人は次第に心を通わせていく。やがて彼の言葉に救われたジュールズは、予期せぬ人生の変化を迎える……。 アン・ハサウェイが好きで■ワン・デイ23年のラブストーリー■や■レ・ミゼラブル■も見た。コゼットの母親、フォンティーヌ役のアン・ハサウィが歌うのを見聞きし、天は二物を与えたと思ったものだ。アン・ハサウェイを見たいと思っていったが今回は、ロバート・デ・ニーロがよかった。ロバート・デ・ニーロの役は、70歳の男性。妻が亡くなって、寂しい一人暮らし。仕事は、とっくに辞めていて、毎日、何をしていいか分からないような毎日。旅行に行ったりしているが、満足できない。そこに、仕事をしないかというチラシ。■応募は、履歴書ではなく動画!!■就職でき、出社したものの、メールで送られてくる社長の命令を待つ日々。命令が来ない間も、社員の手伝いをしたりして、喜ばれている。■やっと来た命令は、「服に付いたシミをとって」というもの。そんな時も、彼は嫌な顔ひとつしない。インターンのベンを見習いたいところは、いろいろあったが、その中で、常におしゃれをしているということ。ワイシャツにネクタイ、スーツが彼の仕事着。GパンにTシャツ姿の中にあって、凛として見える。それに、1970年代のカバンを持っている。彼が長年の会社務めに使っていたもので、いいものを大事に使うという彼の信念のようなものがうかがえる。 彼はまた、常に白いハンカチを欠かさない。「ハンカチって必要?」と若い男性に言われると「ハンカチは、人に使ってもらうために持つもの」と言う。彼は、年齢的にパソコンは苦手な方かもしれないが、フェイスブックに挑戦したりしている。いいね!!いつまでもお洒落で挑戦する気持ちと、人に対する優しさ・・・。仕事をしなくても、必要なものはそれだと思った。・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.13
コメント(0)
-

九州:温泉より公園
温泉県、大分・別府のいいところは、温泉だけにあらず。★内成(うちなり)の棚田★由布川渓谷と郊外にある自然の美しさは、案外知られていないのかもしれない。そして、もうひとつ、あった、公園だ!!別府駅から西に向かって徒歩10分足らずのところにある別府公園。広い!!!それもそのはず、元陸上自衛隊の駐屯地だったそうだ。芝生や樹木が生えており、自然豊か。私が特に気に入ったのは、松林!最近の公園は、桜、桜、桜・・・。どんな所にも桜が植えてある。そんな中で、この公園は、松が中心。この公園は、海に近い別府のそのまた、海に近い場所。海といえば、松でしょう。その植生にあった木を植えているのか、それとも、ここに生えていたのを使ったのか・・・。また、水辺も欲しいところだが、この公園には、小さな小川がある。こういう大きな公園が街の中にあるのは、別府市民の宝だと思う。■別府公園■もし今日の東京に果たして都会美なるものがあり得るとすれば、私はその第一の要素をば樹木と水流に俟(ま)つものと断言する。■「日和下駄」■永井荷風■パリのブローニュの森■が狩場から市民に公開されたことについて、フランスの作家*ジュール・ルナール*は、こう言ってる。 貧しい者にもこう言える。「彼は、500ヘクタール(*注*本当は800ヘクタール)の森を持っている。」■みどり学■ ■九州旅行2015.10.1~10.11■10月1日(木)夜:大阪港出港■3009歩■10月2日(金)大分県:別府着■ ★内成(うちなり)の棚田 ★由布川渓谷・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.12
コメント(0)
-

九州:温泉より由布川渓谷と「ニッポン景観論」
温泉県・大分の別府に行ったら温泉より■棚田■だ!と棚田を見た後は、別府に来たら、渓谷に行かなきゃあ!!!と由布川渓谷に向かった。※平成27年8月現在:「猿渡入り口」階段が通行止めのため、渓谷へ降りることができません。別府市「椿入り口」をご利用ください。 という記事を見て、「椿入口」から階段で降りる。苔むした階段を下りると、そこは由布渓谷だった。■由布川渓谷■由布岳と鶴見岳の間を流れる由布川の上流部に位置し、 深さ15m~60mの峡谷が約12km続いている。40数条の滝や長い年月をかけて自然の力で曲線美を作り出した岩肌など その美しい景観は、周囲を幻想的な雰囲気で包み込む。 四季折々の季節の装いも楽しめ別府の自然の豊かさと雄大さを表わす秘境である。■由布川渓谷■■所在地:別府市東山椿 ■電話:0977-21-1111 ■駐車場:無料・20台 ■市内アクセス車で JR別府駅*由布川峡谷*所要時間:約45分 「人にやさしく、環境にやさしく」と書かれた看板が設置されていました。山をつぶして、大地を削る行為の、どこが人と環境にやさしいのか、と考えてみました。【楽天ブックスならいつでも送料無料】ニッポン景観論 <ヴィジュアル版> [ アレックス・カー ] *巨大な駐車場駐車場は、必要かのしれないけれど、最小限に。また、コンクリートで覆ってしまわず、草地にして、留めるところだけレンガなどで囲うなど自然に溶け込むようにして欲しい。*駐車場の写真スポット・・・。_| ̄|○お金を使うためにこれを作ったのなら問題だ。風景にあった、あずまやなど、休憩できるスポットなら許せるが・・・。 *おまけに環境センターの車の中では職員が仰向けになってさぼっていた。あなたに払う給料を環境に使いたい!!! 以上、由布川渓谷の景色があまりに美しかったから、それを邪魔するものに、文句が言いたかった。■美しい北欧■と比べれば、その差が歴然。北欧には、「自然を大切に」などという文字はないのだ。 ■九州旅行2015.10.1~10.11■10月1日(木)夜:大阪港出港■10月2日(金)大分県:別府着 ★内成(うちなり)の棚田・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.12
コメント(0)
-

九州:温泉より棚田
■10月2日(金)夜、大阪の南港から船に乗り、別府に着いたのは、翌日の朝早く。かつては、温泉地の代名詞のように言われていた別府だが、最近では湯布院や黒川温泉に人気が集まっている。だから、別府の市街地にはいかないで、郊外に行った。車で少し行くと素晴らしい景色があった。▲コスモスが咲いていた。▲大きなイチョウが棚田と村を見守る。▲水を抜くための穴なのか?▲人間が手を加えないとすぐに荒れる棚田。田んぼは、稲を作るだけではない。大雨が降ったら、水をためるダムの役目をする。湿地として、鳥や昆虫の生きる場所だ。また、日本人の原風景でもある里山は、残して欲しい景色だ。今でも棚田の保存には大変なのに、海外から安い米が入ってくれば、農業はやっていけない。米だけでも日本で100%賄えないものか。■内成(うちなり)の棚田■■所在地:別府市大字内成 ■電話:0977-21-1111(別府市農林水産課) ■市内アクセス:車で JR別府駅*内成の棚田*所要時間:約20分 内成棚田は、農林水産省「日本の棚田百選」にも選ばれています。◎地球を救う127の方法・食◎穀物自給率32%の食料輸入大国で暮らしている私たちは、 自分の口に入る食べ物が、どのようにして生産されているか知ることが とても難しい状況にいます。 国内の農業は、環境を保全し、安全な食べ物を生産する、本来の姿から、ますますかけ離れつつあります。エネルギーを大量に投入し、薬づけにされて生産され、 長距離輸送される食べ物は、私たちの体を蝕むばかりか、 産地の生態系を破壊し、砂漠化をさらに進めているのです。このままでは肥沃な大地やそこを耕す人の技術すら失われてしまいます。生態系のなかで、行きつづけていくために、私たちは何を食べていけばいいのか、どう生産し手に入れてゆけばいいのか、できるところから考えてみましょう。 「地球を救う127の方法」より「地球を救う127の方法」は、1990年に作られたパンフレットです。 ■九州旅行2015.10.1~10.11■10月1日(木)夜:4大阪港出港■10月2日(金)大分県:別府着・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.11
コメント(0)
-

九州:別府へ船で行く。
■10月1日(木)フェリーで九州は別府に行き、そこから約10日間の九州旅行。船で泊まるのは、今年の7月の■北欧いらい。■▲北欧の船内は、ベッドと机、小さな洋服ダンス、それにトイレとシャワールームつき。▲今回のは、ベッドを置くといっぱいの部屋だった。もちろん、トイレは共同だった。なにより、窓がないのが気になったが、ファーストクラスにはついているのだろう。北欧での航海も窓のない部屋もあったのだろうと今回気が付いた。■1954年4月1日私たちが別府に着いたのは午前八時だった。別府は有名な温泉地で、日本旅館がたくさん並び建ち、保養客が「ユカタ」で街をぶらついている。静かな海を港に向かうと、数マイル沖合からもう山へと立ち昇っている湯の煙が望まれた。船が海の流れに乗ったり逆らったりして進む瀬戸内海の素晴らしい景観は、夜だったので見ることはできなかったが、それでも、昨日の朝見た透かし絵のようなさまざまの姿の無数の島々と小さな黒い漁舟は美しい夢のようだった。*バーナード・リーチ日本絵日記***バーナード・リーチ**東西の伝統を融合し、独自の美の世界を創造したイギリス人陶芸家リーチ。 昭和二十八年、十九年ぶりに訪れた第二の故郷日本で、浜田庄司・棟方志功・志賀直哉・鈴木大拙らと交遊を重ね、また、日本各地の名所や窯場を巡り、絵入りの日記を綴る。随所にひらめく鋭い洞察、真に美しいものを見つめる魂。リーチの日本観・美術観が迸る興趣溢れる心の旅日記。■九州へ■・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.11
コメント(0)
-

ボタニカルライフ:アボカド
(略)アボカドの種というやつは、実に頼もしい風体をしている。がっしりとしたアヒルの卵くらいで重さもあり、しかも黒光りしている。考えてみれば、時に質量において果肉より種の方が大きいわけで、俺たちは種に金を払っているといってもいいのである。(略)それならば、なぜその種を植えてみないのか。なにしろ、売っているのは種なのだ。決して果肉ではない。鉢植え好きなら誰でもそう考えることだろう。「ボタニカル・ライフ」 私もそう考えた。コップに水を少しはって、その中にアボカドの種を入れる。数日したら水を足す。そして待つ。そうすれば、種はパカリを割れ、根や芽が出てくる。 植木鉢に移す。今、家には3本のアボカドの木がある。もちろん、種から育てたもの。花屋で買ってきた植物より、種から自分で育てた植物は、愛着が違う。■ボタニカル・ライフ■庭のない都会暮らしを選び、ベランダで花を育てる「ベランダー」。そのとりあえずの掟は…隣のベランダに土を掃き出すなかれ、隙間家具より隙間鉢、水さえやっときゃなんとかなる、狭さは知恵の泉なり…。ある日ふと植物の暮らしにハマッた著者の、いい加減なような熱心なような、「ガーデナー」とはひと味違う、愛と屈折に満ちた「植物生活」の全記録。 第15回講談社エッセイ賞。■サボテン倒壊■■朝顔:ベランダーの矛盾■■朝顔■■おじぎ草・雑草の価値■■ベランダ:緑は萌える■■ハーブ:すました雑草■■ベランダ:消え去るもの■■アラビカ種コーヒー■■胡蝶蘭:第二の人生■・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・
2015.10.11
コメント(0)
-

九州へ:「バーナード・リーチ日本絵日記」
東西の伝統を融合し、独自の美の世界を創造したイギリス人陶芸家リーチ。和二十八年、十九年ぶりに訪れた第二の故郷日本で、浜田庄司・棟方志功・志賀直哉・鈴木大拙らと交遊を重ね、また、日本各地の名所や窯場を巡り、絵入りの日記を綴る。■「バーナード・リーチ日本絵日記」■。その中で、バーナード・リーチと河合寛次郎らが一緒に九州に行った記録がある。■1954年4月1日:東京から特急「つばめ」で京都に。河合寛次郎と甥といっしょに神戸に。神戸から22時の別府行きの船に乗る。四国の港で濱田が乗り込んで来た。■4月2日:別府着=午前八時。■4月4日車で山を幾つか越えて奥地の日田におもむき・・・。■4月5日それから私たちは車を駆って数マイル行き、長い渓谷に入った。道はだんだん狭く悪くなり、坂も険しく迫ってきて、高い常緑の杉の木であたりも暗かった。そうして、曲り道に来たとき、木の皮で葺いた屋根と、立っている人々の姿が見えた。「小鹿田(おんた)の皿山」だ。■4月26日九州にも、楽しい小鹿田(おんた)にも、真心あふれる陶工たち皆にもお別れである。■4月27日:京都■5月12日:東京着 今夜のフェリーで九州に行く。別府、日田、それに小鹿田(おんた)・・・。バーナード・リーチと全くおんなじコースだ!!今から60年以上前のバーナード・リーチの旅と同じところに行けるとは、ファンとしてうれしい。小鹿田(おんた)の後、長崎に行き、古くからの友人に会う!これも楽しみだ。・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・
2015.10.01
コメント(2)
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
-

- 楽天市場
- 49%OFF!楽天1位の極暖パンツで、こ…
- (2025-11-16 00:00:05)
-
-
-

- 楽天写真館
- Insta360 Ace Pro 2 ストリート撮影…
- (2025-11-15 23:26:26)
-
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-15 02:35:31)
-






