2024年02月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-

【歪みマニア】高崎晃モデル AT-222Fz GermaniumTransistor FUZZ レビュー
■AT-222Fz GermaniumTransistor FUZZ 【AKIRA TAKASAKI Signature Pedal】2024 Limited個人的に大好きなエフェクターは『クリーンブースター(もしくはトランスペアレント系OD)』『ファズ』『ワウ』 ファズに関してはボリュームを絞ったときの音や全開時の轟音がテンション爆上がりなわけです。ご覧の様にファズは大好きで厳選したファズは既に複数所有しております。そんな中、高崎 晃モデルのファズが27台限定で発売されるのを確認。製造元のキャッツファクトリーは高崎氏 御用達のエフェクトメーカーで高品質なペダルをハンドメイドで製作・発売している注目株です。ファズは持ってるし、どうしようかな・・・と悩んでいるうちに受注第1期の生産が終わり悩みは増すばかり。無くなってしまうのか・・・買った方が良いのか。。悩み過ぎて疲れ果て『買うしかない!』と色々と売り飛ばして資金を集めポチリ。大体は欲望を抑えきれずこのパターンで購入に至りますが、資金源に色々売るのでお陰様で部屋もスッキリしてきました。AT222P.D.W.に通ずるシンプルなミリタリーグリーン。メーカー直販のみでカスタムショップ名義です。ツマミは3つありゲイン/ボリュームに加え、キャラクターをコントロールするニュアンスとなっています。ファズに関しては作り手やメーカーによってクセがモロに出ることが多く、これまではファズを中心にペダルをラインナップしているメーカーを選択肢に選んでいましたが、理想のギタートーンを出しているギタリストの1人でもある高崎晃氏がこだわったファズとなれば話が変わってきます。ということで、早速、色々と試してみましたのでレビューしてみます。※あくまで個人的な感想です。 ファズの魅力の1つが “轟音” とも呼べる野太い音で『ノイズの美学』といっても過言ではない複雑な音を出します。それこそ一音一音が太く単音弾きでも存在感があります。 反面、暴れすぎて各弦の分離感というよりは単にノイズ気味になってしまったり、一定の周波数がカットされることでタッチレスポンスが遅くなってしまうモノも多くあります。とりわけ太い弦が張ってある5~6弦をピッキングした時にその傾向が強くなるわけですがこのAT-222Fzでは解像度が高く分離感があり、ニュアンスもしっかり出てくれます。轟音系でありながらピッキングニュアンスに忠実でレスポンスが速い。なおかつフル10状態で6弦でもピッキングハーモニクスが出せるので、“THE FUZZ” というファズフェイスやビッグマフ、ベンダー系等のコテコテな王道に寄せたと言うよりは いなたく芯のある太さの中に “レスポンス” “ヌケ” “レンジ” を持たせたディストーションの延長線上にある様な印象です。スピードプレイを多用する高崎氏にとってこの辺りは重要なポイントだったのではないかと。 詳細は不明ですが “ファズらしい太さとスピード感” という相反する特性を実現した絶妙な味付けが高崎氏のこだわりでもあり、エンジニアの苦労した部分だろうなと感じることが出来ました。“良いファズペダル” の特権とも言えるボリュームの追従性も良く、少し絞れば良質なディストーション、さらに絞り込めばオーバードライブまで実用的なサウンドを奏でます。アンプをあまり歪ませずに使用すれば美しい鈴なりサウンドもOK。ファズを通すことで倍音成分とバイト感が増すのでボリューム調整によって通常の歪みペダルとはまた違ったドライブサウンドも楽しむことが出来ます。ファズはペダル1つで表情の変化がつけられるので単純に弾いていて楽しいペダルです。特性上、オーバードライブやディストーションよりも難易度が高く、使い道に困る場合もありますがAT-222Fz はニュアンスの操作でキャラクターも変化するので、アンプとファズのセッティングを突き詰めれば理想的なサウンドに持っていくことができそうです。汎用性があって非常に素直なペダルでした。人の手で生み出すモノというのはビルダーの想いが入っているのが良いですね。“自分の存在意義” とでも言いましょうか、工場での大量生産とは違った『氣』を感じます。もう少し色々試したらまたレビューしてみようと思います。
February 29, 2024
コメント(0)
-

最強のピックアップ “PAF” 究極のレプリカが純正で登場!?
その名を『1959 Humbucker Collector's Edition Series 1, Exclusive』Gibsonから究極のPAFを再現したピックアップが1000SET限定で登場しました。価格999ドル。日本円にして16万円。ほうほう・・・まぁ。高いっすね(笑)とは言え、ここ最近の楽器業界の価格高騰は何も楽器本体に留まらずって感じなので何とも言えません。安くて良いのもありますが、高いのは高いだけ良いモノもある。戦略的な値付けやプラシーボも勿論ある。今回は1959年のPAFを再現したということで、個人的にはメチャメチャ気になっています。これでエイジング加工されて日本で売られていたら多分買っていたかもしれませんね。豪華にブラウンケース入り・・・まさにコレクター品ですね。ふと思ったんですが1959年製は何でそんなに値段が高いのか・・・最も熟した年というのは分かりますが1954年の方が安いとかヴィンテージは謎だらけ。そもそもピックアップまで1959年が最高なのかも試したことが無いので謎です。とはいえPAF系のピックアップの特徴としては非常に感度が高くて素直なイメージがあります。その中でも実際に試したのは下記・ジミーウォレス PAF・K&T WEEP・K&T Tetrad・ギブソン カスタムバッカー・ウィズ PAF・ダンカン ANTIQUITY ※各種レビューはコチラどれも良さがありますけど、何だかんだで個人的にはカスタムバッカーとK&Tは好きです。低域が枯れていて高域が出るので、ボリュームやトーンを使いやすいという理由です。PAF系はどれもスモーキーな感じで倍音が豊か。クリーンなのに歪んでいるような印象を持っています。昔は高出力なピックアップばかりつけていましたけど、今は低出力が本体の良さを出すので好きです。とは言え、高いピックアップを載せても、本体が良くないと良い音にはならないですね。本体が良くないなら高性能なものは載せず適度に誤魔化してくれるダンカンのJBあたりがベスト。どちらも高さやポールピース、ブリッジの高さやネック調整あり気での音作りは本当に重要。PAF系は素直が故に調整範囲が広いというか各部調整に対してシビアに音が変化するので素敵です。本物のPAFは今や100万円の時代。細いワイヤーを巻いたピックアップが数十年経っているとなると憧れる反面、経年劣化が心配過ぎて手が出せません。むしろ経年劣化でコイルが緩んだり磁力が落ちたりで音が育っているとなると綺麗に保存され過ぎていても良い音が出なそうですし。結局、バンドアンサンブルに混ぜてしまうと微細な違いなんて大して分からないんですけど気になるのが性です(笑)
February 17, 2024
コメント(0)
-

【濃厚駄話】ギターとバイクの共通点を熱く語る。
ふと思ったんですが、ギターやベースとか音楽を好きな人って意外とバイクやクルマといった乗り物好きな人が多い気がします。そして以外にも共通点は多いなとも感じています。そこで自分なりに『ギター』と『バイク』を勝手に想像して比較してみたシリーズです。■没頭と開放感バイクは不安定が故に強制的に集中力が必要な乗り物なので走りに没頭でき、大きく言えば何もかも忘れさせてくれる良さがあります。具体的には排気音や鼓動感、加速力、操る楽しさがあります。一方でギターに関しても演奏時の集中力は余儀なくされ、感情移入して没頭することが出来ると同時に、双方ともにストレスフリーの開放感があります。共に雑念が入ると楽しめないジャンル。感情の赴くままに操り、それを表現出来た時の充実感が半端ないですよね。■スキル追求型経験値と感性がものを言う世界というか『運転技術』『演奏技術』という意味では近いものがあります。微細なアクセル・ブレーキ・体重移動のコントロールや適格なライン取りでタイムを出すことのできるバイク(主にスポーツモデル)に対し、適切なピッキングと運指、リズム感で表現の幅を広げるギターの音色。それを極めたいという探求心も少し近い。加えてバイクは『視覚』『聴覚』『身体のコントロール』と頭を使います。ギターも『聴覚』『身体のコントロール』 頭を使うので似ていますね。■長く愛せる。旧車&ヴィンテージの価値観本当に気に入った相棒を見つければ長く大切にすることが出来る。時代は移り行き、新しい商品は出ますが、当時でしか出来なかった構造や製造工程、経年による貫禄等、古き良き時代にしかない味わい深さの魅力があります。 当時の良さは今には無くなってしまったものもあり、最新が最高というわけでもない。それこそバイクでは旧車、楽器ではヴィンテージの価値観にも近く、人気商品はプレミアムで取扱われる傾向も似ています。各メーカーの動きとしても古き良き時代の産物を復刻させて現在に蘇らせるという展開が似てますよね。ギブソンの復刻モデルなんかもそんな考え方でしょうし、バイクに関しても過渡期の人気商材をオマージュして今に蘇らせるという戦略をもつジャンルかなと感じています。まぁ普段は楽器のことばかりネタにしていますがバイクの分野に関しては仕事柄 専門なので間違い無いです。■個人表現が出来るバイクのカテゴリーで言えばオフロードやスーパースポーツ、クルーザー、ネイキッド等、乗り手が求める用途によって選択肢もあり、見た目も乗り味も違います。カスタム分野では求める走行性能にする為にマフラーやサスペンションを交換したり、見た目を格好良くするのに装飾したりします。これをギターで表せば音を良くする為にピックアップやブリッジを変えたり、見た目で言えば色味や杢目にこだわったり、カテゴリーで言ってもジャズやブルース、ロック、クラシックと弾き手が求めるジャンルによって見た目から弾き心地まで全て選択肢が違います。 そしてバイクもギターもカタにはまらず表現が自由。■インドアとアウトドア楽器に関してはインドアでも十分に楽しめることがありますがバイクはそうはいきません。この2つの趣味を持つことでバイクに乗れないときにはギターを楽しむ。このコラボはインドア&アウトドアの趣味として最高の組み合わせなのかもしれません。 バイクに乗った高揚感・開放感から生まれる感覚は音楽としても非常にネタになるというか、影響を与えてくれる何かがあるような気がします。例えば排気音の咆哮、ハーレーでいうアイドリングのリズム・ビートも何かロックなんですよね(笑) 共に感性に訴えかける何かがあるのは明白ですね。■楽器とバイクのコラボこんな感じで、実際にバイクと楽器業界は時折コラボしたりもしています。これはGibson の伝説の名機とも言われ、本物は数千万円までプレミアム価格となっている『1959年製 レスポールスタンダード』と同年にトライアンフで生まれた『ボンネビルT120』がコラボした作品。チャリティーで最高額だった人に商品として贈呈されたギター&バイクのようです。素晴らしいコラボ企画ですね。 近年のバイクは排気音や吸気音にこだわっています。ヤマハでは自社の楽器部門(管楽器)から技術提供をもらってマフラーの内部構造を考えたりとライダーが満足する排気音を演出するまでに至りました。写真にあるSR400はアコースティックギターのサンバーストカラーをSR400のフューエルタンクに模した限定モデル。美しい造形を持ち、職人塗装にこだわったSR400のフューエルタンクに非常に似合います。確かに楽器の持つノスタルジックで美しい雰囲気と楽器の持つ雰囲気はどことなく似ているような気もします。我ながら良い趣味を持った!
February 4, 2024
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
-

- 楽器について♪
- 2025年冬のハープコンサートのお知ら…
- (2025-11-13 00:50:21)
-
-
-
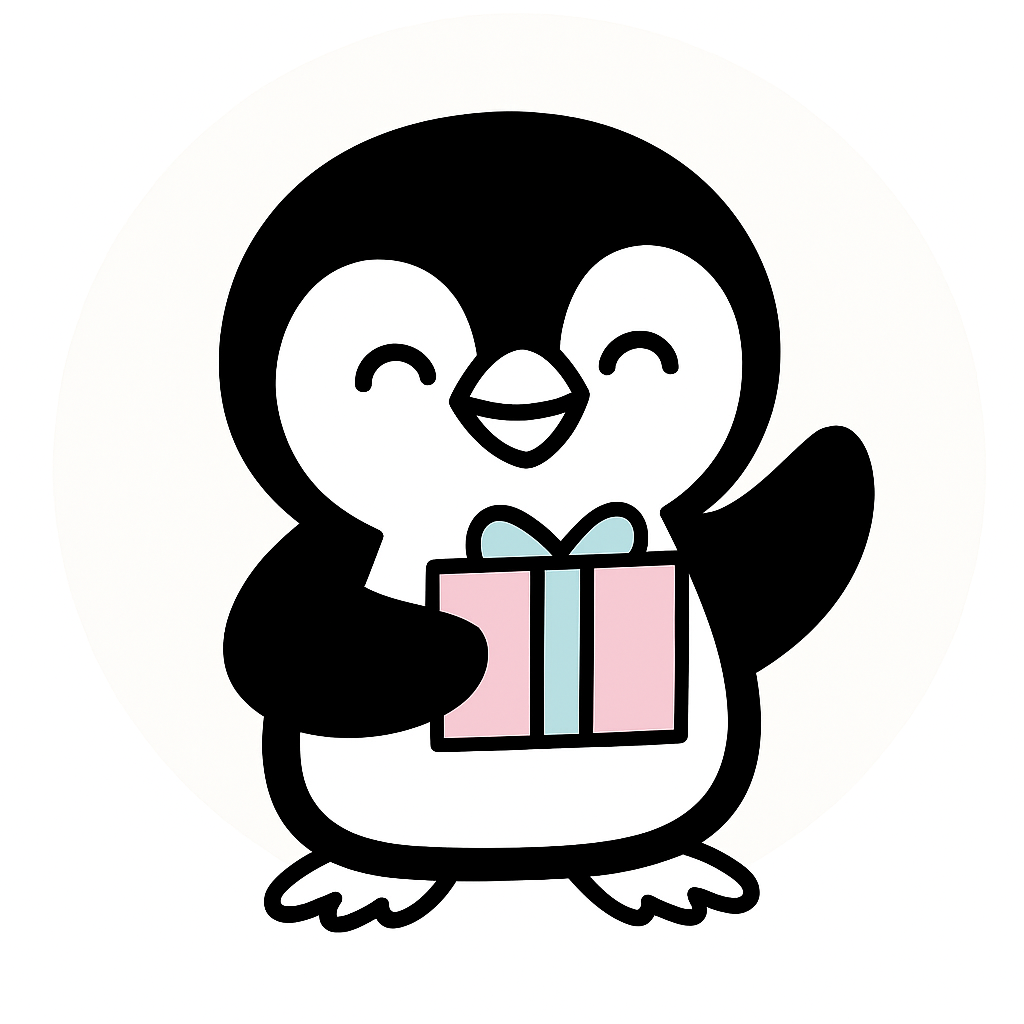
- いま嵐を語ろう♪
- 嵐コンサートツア決定! ARASHI LIVE…
- (2025-11-22 22:27:58)
-
-
-

- 田原俊彦さん・としちゃん・トシちゃ…
- KING of IDOL 踊るパワースポット!
- (2025-10-05 15:16:43)
-







