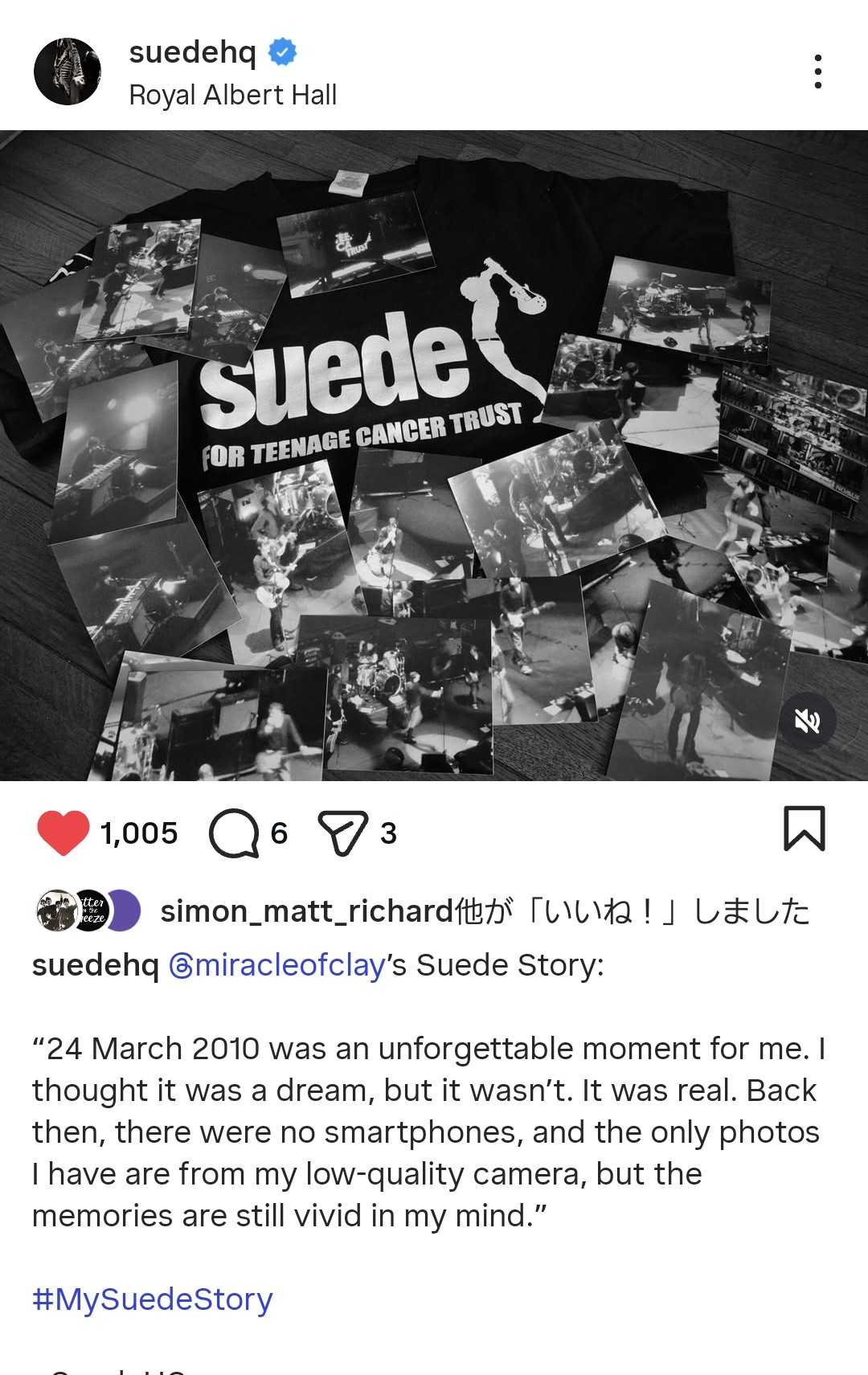2024年04月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-

親父になったギタリストの悩み ~ 親父としての自覚編 ~
最近の悩み。今、我が家には、それはそれは可愛い2人(一男一女)の子供達が暮らしております。 1人目が産まれたとき、自分にとって子供(赤ちゃん)は未知の存在で、親族周囲が “可愛い” としているのを見ても自覚することが出来ない自分自身に不安を持ち、“親” として失格なのではないか。そんな悩みが少なからずありました。子供たちが1日1日、日に日に大きくなると表情も豊かになり、私を親だと認識して呼ばれるようになると、その過程と共に自分自身の存在意義 “親” としての自覚と、“守らなければならない”という宿命の様な感覚・感情が芽生え、今では妻や子供達あってこそ自分があると感じております。そして最近になっての悩みが 『ちょっと俺、自分の物が多すぎない?』 ということ。ギターやエフェクター、インテリア雑貨も好きで色々と集めてしまっているわけですが、我が家の将来を考えると少しずつ自分の物は減らした方が良いのかなと考えるようになりました。さて、どうしたものか。。。つづく。
April 25, 2024
コメント(0)
-

【ワウ沼】Shin's Music Freeze Frame WAH
■Shin's Music Freeze Frame WAH知る人ぞ知るプロ御用達の高品質なエフェクターを生み出す “Shin's Music” の “Freeze Frame WAH” は下記の様な希少な部品をふんだんに用いたヴィンテージワウ。 単にヴィンテージを模しただけではなく、ヴィンテージパーツを使って現在のノウハウ、俺のエッセンスを入れるとこうなる!といったある種の到達点的なワウコンセプト。トゥルーバイパスやLED、電源ジャックなど実用的に進化した30台限定モデルです。一度、電源部分が壊れてしまい“Shin's Music”で修理しました。説明前ですが “Shin's Music” のエフェクターはどれも素晴らしいです。ヴィンテージ路線であれば個人的には群を抜いていると感じてしまいます。・60年代後期〜70年代初期のTelefunken BC109Bトランジスタ。・70年代後期のDucati Polystyrene コンデンサ。・60年代後期〜70年代初期のMullard Tropicalfish コンデンサ。・70年代後期のSprague Little Lytic 30D Redtop電解コンデンサ。・50年代後期〜70年代初期のカーボン抵抗。・50年代後期〜70年代初期の配線材。・60年代後期のイングランド製ハンダ。・Haloレプリカのインダクター・ヴィンテージピクチャーワウのポッドを再現したICAR Special POTもはや上記の希少部品だけでも満足度が高いですね。今は無きヴィンテージパーツをマッチングさせて作るが故に限られた台数しか作れない。それを手に入れて持っているという所有欲がまず満たされます。とりわけ音に関してはクリア。ワウを使わなくても踏んだだけで真空管アンプの様な艶が出るので基本ONにしちゃいます。踏み込んだ時の いなたく乾いた感じと適度な倍音が美しい。レスポールで使用して踏み込めば太いままカラっとしたサウンドにもなり、ワウ(常時ON)+ボリューム/トーンという使い方でも使えます。クリーン~クランチでのチャカポコの切れ味も抜群。ヴィンテージ路線ながら高解像度なワウペダルです。其々の好みはありますが “Shin's Music” の音は個人的に大好きで2台持ってます。出音が出音だけにコイツはガシガシ使ってボロくなった感じが似合いそうです。ちなみに気に入っているので無駄に2つ持ってます。
April 18, 2024
コメント(0)
-

【歪みマニア】圧倒的熱量で生み出す Richard Electric Sound の歪みペダル。
■Richard Electric Sound “Sound in Glory”Richard Electric Sound はHP等も無く、ビルダーの存在を口コミで知る人しかオーダーする手段が無いという知る人ぞ知る個人制作ブランドです。ビルダーが多忙を極めることと、エフェクトペダルの製作における情熱が半端ないらしく、取り扱っている石橋楽器でも年に数個単位でしか入ってこないらしいです。そんなRESの中でラインナップする“Sound in Glory”は、究極のウォームサウンドを追求したオーバードライブ系ペダルとのことで、シンプルなシングルノブで名前の通りウォームサウンドを体感することが出来るそうです(謎)大量生産ではないことから、同じ製品名でも1つ1つの内部基板やパーツ種類、点数、配列に至るまで全てが個体ごとに違います。こだわり抜いたパーツを使って丁寧にPOINT TO POINTで仕上げていることや、装飾の芸術性も高い。特に今回手に入れた個体はRESの中でも初期個体で配線処理や使っているパーツが後の仕様とも少し違い豪華。極々小さな抵抗まで装飾を施すなど手間暇がかかっていて仕上げが綺麗です。「ウォームサウンド」と聞くと「こもった甘いサウンド」とイメージしてしまいますが、実際のところBOSS OD-1を主体とした様な、いなたく太いサウンドのオーバードライブを主体として発展した印象を受けました。 “Vitamin-Qオイルコンデンサー(Black Candy)”を使っていることを謳っているように、Black Candyを積んだギターのトーン回路を絞ったときのウォームサウンドに近いんですが、削れてしまうヌケや金属的な倍音成分や高域、サスティンが別の領域からジュワッと出てきて何故か抜けてくる。とは言えエッジが立ちすぎておらず、あくまでウォーム。どういう回路なのかは詳しくないので分かりませんがトーンを絞った音質に対して、別のルートでブーストした原音をブレンドした様な独特な響きを持っています。トーン回路を用いた音・・・ありそうで無かった。そして使える音です。Black Candyを使っているのは癖なく万能型なので扱い易いことが目的だと思いますが、これをヴィンテージコンデンサ―に変えても面白そう。2wayのミニスイッチ(Warm Select Switch)では右上:Red Warm(レッドウォーム)出音に勢いのあるウォームサウンドが得らピッキングニュアンスによる繊細な演奏が可能です。右下:Blue Warm(ブルーウォーム)歪みの粒が非常に細かいウォームサウンド。歪んでいない歪みとして捉えられるような、非常に独特のサウンドを得ることができます。共に良いサウンド出してました。 Red Warm(レッドウォーム)ではソロ等で主張したい時に踏み込むと図太い音圧と共にリードサウンドを主張してくれます。Blue Warm(ブルーウォーム)はローゲインやクランチで弾いても追従性が良く音楽的で味のある飽和感が素敵です。タッチレスポンスは鋭いんですが柔らかくギャンギャン言わないので素敵に鳴ります。ワンノブのシンプル構造の中に複雑な音が混じり合った、ビルダーのセンスを感じるペダルだなと感じます。■Richard Electric Sound Custom “BAERHEIM”Richard Electric Sound “Sound in Glory” を体験して『正体不明だけど、こだわりが詰まっていて良いブランドだなぁ』なんて思っていたら、とあるSALEで“BAERHEIM(写真右)”なるものを偶然発見してしまったのでゲットしました。今回のは Richard Electric Sound Custom ということで、CustomShopのような上位グレード(?)のものらしく、『これまでの価格帯では表現できなかった音を極限まで詰め込んだ』という珠玉のペダルの模様。※説明書にそう書いてあった。BAERHEIM(ブラハム)は1ノブによるシンプルな使用が可能とするユーティリティに焦点を当てたモデル。かつて、歪みという概念が生まれたドライブサウンドの黎明期、そのサウンドを得るには「すべてのノブを最大にする」たったそれだけのシンプルさでした。しかし、そのシンプルさが多くの名サウンドを生み出し、それらのサウンドは今日に至るまで連綿と受け継がれています。ブラハムは1ノブ(ドライブ)の設定を済ますだけで、多くのシーンに適応したサウンドを作り出すことが出来ます。そして、そのサウンドクリエイトの領域をさらに押し広げているのが、"SAVAGE"スイッチの存在です。通常モードの状態では、クリーンサウンドに与えるバッファー的効果からクランチドライブに至るサウンドが得られます。そして、"SAVAGE"スイッチを踏むことで、アンプライクな豊かな歪みを得ることが出来ます。これがペダルの説明なのですが、歪みペダルである認識は出来ても音のイメージがまったくつかない(汗)体験することも出来ず、単に “RES” なら間違い無いだろうというギャンブル感覚で買ってみました。コチラが内部基板。何と神々しい・・・各個体ごとに選定された抵抗部品1つ1つ、数ミリしかない小さな部品に至るまで芸術的に装飾されています。良くあるパーツを隠すための筆でベタ塗りや、グルーで潰す等でもなく、部品個体単位でを熱伸縮ゴムで抵抗値を隠し 足にカバーをつけたりと、精密模型かの様に小さなパーツまで気配りされています。手間暇考えて ここまでのペダルはRES以外見たことがありません。これを見た時に “千手観音菩薩像” を思い浮かべてしまいました。“見た目に関しても1つの芸術作品として見て頂ければ幸いです” との説明書記載もあり、作品に対する鬼気迫る向き合い方が感じられます。長々と見た目の話ばかりになってしまいましたが、音のレビューを。。。 まず。はじめに述べると “凄く良い” です。ただ、相変わらず音が唯一無二過ぎて表現が難しい音です。 一般的にはOD系やTS系といった基盤になる歴史的名器があって、その要素が入りそうなもんですが、RESは何にも属していない複雑さがあります。シンプルなように見えて色んな出汁が入っているスープみたいで、奥深いというか単純ではないので表現が難しい。“通常ON” の場合、ナチュラルブースターの様な感覚で使うと良いです。 原音そのままに音色に太さと艶、倍音成分が加わることでレンジが広くなり存在感が増します。ミニスイッチによってキャラクターも変えられるので使用するギターやアンプ、好みによって調整すればダイナミクスのある明瞭なサウンドを簡単に作ることが出来ます。ここまで聞くと、一般的なブースターであれば同じ表現でも通ってしまうのですが、奥底に響く倍音の複雑さと歪みの飽和具合は他にない個性として感じることが出来ます。極めつけは "SAVAGE" スイッチ! ONにした刹那 “極楽浄土” の歪。 この世の全ての歪みが出てくる感じでした(謎) ファズやオーバードライブ等、違う周波数を持つペダルが複数同時に重なって鳴っているかの様な不思議な感覚で一気に空間が広がり後光がさします。 非常に複雑な音が鳴っているんですが出汁として上手に調律されているので1つの料理として完成されており、素晴らしいペダルでした。個人ビルダー恐るべし。
April 5, 2024
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1