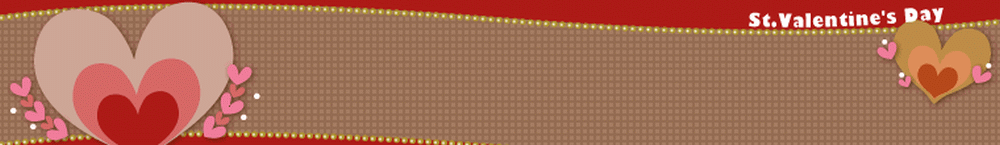全274件 (274件中 1-50件目)
-
利用停止
今後、このブログの利用を停止することにしました。理由は:迷惑メール、スパム、嫌がらせのコメントがいっぱいある更新する時間がないMIXIのブログを使っているこれからもよろしくお願いします
2008.10.13
-
詩は自分の心を映す鏡
毎日の暮らしの中で、一人一人がいろな刺激に取り巻かれている。マスコミのお陰で、遠くからの物事も身近なものになるようである。とはいえ、人造環境からの刺激ばかりそうである。自然環境と付き合わなくなると共に、季節の移り変わりなどの自然現象に対する感受性もますます鈍くなるようである。自然現象に淡白になるだけでわなく、一人と一人の感覚交流に情熱も失うことになる。感受性の豊かな人、或いはものの哀れを感じる人は、常に文学や音楽の中に自分の感覚や思想を具象化している。世の中がどのように見えるかは、自分の心の中が反映されているのである。詩を通して、自らの世の中への態度を表せるだけでなく、気持ちを切り替えることができるのではないでしょうか。いつも、人間や自然に関する感受性が持てるように、詩を書いていきたいと思います。
2007.12.07
-
恋の匂い
ともしびにゆれるこの夜のままにやぶれた恋とお酒を一息に飲みほしてもいい酔わせる匂いが心を燃える味に合うわ息切れできないほど胸いたく嘆きだけがあってもいい微かな思い出と絡めた逝き去ったあの日ああ唇に残る恋の匂いが夜の色に染まるまで
2007.12.06
-
寝るのは、馬鹿!?
最近、私がはまってるもの。それは、登山。 先週の水曜日と木曜日、二朝続けて、高雄人の後花園と呼ばれている柴山へ行った。 今朝、また柴山へ。 いつもより2時間早く起きた。 家族、皆がまだちゃんと眠っていたところを、家を出かけた。 私は、リーダとして、友達の3人と一緒に行くにした。 待ち合わせ先で、約束をしたとおり、皆が、遅刻もなく、柴山の登山歩道へ向かって行った。 昨夜、ちょっと少し雨が降っていたので、空気も綺麗だし、歩道ですれ違い人もいつものわりに少なかったので、気持ちがとてもよかったんです。登山にぴったり合う日だった。 歩道の入口は二つあるけど、普段、鼓山区の竜泉寺から入山することが多い。今回、「雅座亭」まで往復することにした。約一時間半の登山。 柴山は、山というより、丘と言ってもいい。登山道には、かなり険しい坂が多いので、私たちは、時々息を切らしたこともある。ただ10分程で、服は汗でびっしょりだった。心臓にも足力にもいい運動だと思う。 「雅座亭」までのんびり歩きながら、友達と雑談したりして、あっという間に、展望台の「雅座亭」に辿り着いた。ここで、少々息をついた。数人の熱心家は雨の日も変わらずに毎日、水やお茶を山上のここまで運んでくるそうだ。 だからここに来た皆は彼達のおかげで無料で水やお茶を飲める。 ここで大勢のサルが集まっているので、可愛いけど、やはりちょっと怖く感じた。今回は、リス、フクロウも出会っていた。うれしかった。 家に帰る途中で、大勇路にある有名なサンドイッチ店で朝食を取った。 大満足でした。家に着いたら、ただ9時近くだったので、まだまだ早いっ感じ。 私の場合は早起きが苦手なわけでなく、睡眠時間を短くして空いた時間を有効活用したいなと思ったわけだった。 でも単純に睡眠時間を短くすると起きてからが、まだ眠いだろう。 で、短くても寝不足にならない秘訣はないものかと。 たまに、山登りをしたりするのもいいかも。 エジソンは、「寝るのは、馬鹿だ」と言ったそうである。しかし、睡眠時間を短くする必要があってもなくても、「寝るより楽は無かりけり」と思っている人も、少なくないだろう。
2007.09.06
-
おかしい逸話
昨日、家庭教師Nさんは、冗談みたいな文章を教えてくれました。面白かったので、早速ノートをとりました。※※※レニングラードの国立銀行の入口に、警備兵がひとり立っているのを見たユダヤ人のウォルフ、不審な面持ちで、隣の男に聞いた。「大事な国の財産の番をするのに、警備兵一人で足りるのかね。」「もちろん、一人で十分さ。」「金庫に近付く奴もいないよ。」「それなら、あの警備兵もいらないだろうか。」「いやいや、あいつをあそこに立たしておけば、よそで盗みを働かないわけさ。」※※※この滑稽な話を聞いたら、ロシアの治安は、どれほど悪いのか、想像できます。ロシアの警備兵をからかうというより、ロシアという国を見下すと言ってもいいです。ロシアでの最大の難問題は治安の悪さである。まじめな一般ロシア国民にとってもまた、旅行者にとっても頭の痛いところです。わたしは、ずっとロシアへの旅行に憧れっていたが、治安が非常に悪いという点を考えてみれば、やっぱりあきらめるほか仕方がありません。あちこち、「マフィア」が横暴さを極めているそうです。現地の会社や企業、自分の身を守るには、彼らを頼りにしなければならないという話もあります。ロシアの人たち自体が、ロシアの警察を信頼する一面と、半ば公然と行われている不正も仕方がないとする一面を持っているのです。ロシア人のなかに、警察を信頼する人は、信頼できない人より、多いだろうかとしか思えません。今日のロシアを象徴しているのは、悪い治安と言えます。とうりで、こんなにおかしい逸話が生まれたわけです。台湾の治安なら、どうですか。「いま、住んでいるところの治安は、どうですか。」とわたしは日本人の家庭教師に聞きましたところ、彼は、「かなりいいですが、ただヘルメットを盗まれたことが二回あります」って言いました。やっぱり、台湾のほうが、安全ですよね。でも、昼間にドアが開けっ放しにしても大丈夫という30年前の光景と比べにはならないものです。
2007.09.05
-
大好きな【緑豆湯】
台湾で夏のドリンクと言えば、何と言っても、【緑豆湯】です。緑豆は日本では春雨の原料として知られている豆ですが、台湾ではデザートとして良く食べられます。あずきを餡としてのお菓子が多いですが、台湾にしたら、緑豆で餡を作ることが多いです。日本ではなかなか見かけない食材だとのことですが、台湾人にとっては、冷蔵庫に常備されている食材だと思っています。台湾の料理で「緑豆湯(りゅうとうたん)」というのがあります。緑豆湯は、台湾のコンビニにも普通に売られていて、スイーツ屋台でも定番メニューになっています。特に、カキ氷のトッピングとしてよく食べられています。豆の臭みがなくさっぱりした味なので、暑い夏のドリンクとしてもいいし、デザートとしもいいし、台湾人には、欠かせないものだと言えます。さらに、緑豆は、美容効果がありそうで、天然の化粧品という話しもあります。豊富なカリウムが含まれている緑豆は、熱体質な人に体内水分を調整できるので、足先や体が熱る人にはびったり合うのです。血行を活発にするので、浮腫みを解消でき、利尿に効くそうです。また、台湾女性たちには、皮膚にたまった角質を取り除くために、緑豆を粉にして、マスクとして顔に敷く人が多いです。夏バテを解消するには、緑豆湯に限りますね。緑豆を炊飯器で柔らかく煮込み、水と砂糖を入れると、緑豆湯となります。常温でもおいしいですが、冷やすと一層おいしくなります。豆のツブツブした食感とさっぱりした甘さはおいしいですね。わたしなら、夏のドリンクだけでなく、朝食としてよく食べています。ミルクを加えると、もっと美味しくなります。毎朝、「緑豆ミルク湯」を食べたりするのは、最高だと思います。美味しいし、値段も安いし、それに手間が掛からないので、朝食と言えば、「緑豆湯」に限りますね。シンプルの豆には、パワーがいっぱいです。機会があるなら、台湾人ならではのスイーツをぜひおためしください♪。
2007.09.05
-
破産の哲学
今週の聞き取り内容は、下記のように書いてあります。****************************頭が良くなる即効薬エダヤ人が列車の中で、塩付けのニシンを食べていた。食べ残した頭を新聞紙で包んでいると、向かいに座っていたポーランド人がユダヤ人に向かってたずねた。「あなた方は、頭がいいという評判だけど、いったいどうしたら、利口になるんですかね。」ユダヤ人は答えていた。「それは塩ニシンを常食としているからで、特に頭の部分を食べると効き目があるといわれていますよ。」「それじゃ、その頭を売ってくれませんか。」「これはうちに帰て、子供に食べさせようと思っていたんですが、ようござんす」「ひとつ1ドルなら、お分けします。」ポーランド人は5ドル払って、ニシンの頭を5個もらった。食べにくいのを我慢して飲み下した。ポーランド人はしばらく不快げにしていたが、やがて吐き出すようにいた。「あなたもひどい方だ。5ドル出したら、次の駅でニシン五匹買っても、お釣りがきいたはずじゃないか。」すると、ユダヤ人が言った。「それ、御覧なさい。もうそろそろ、頭がよくなってきたようですよな。」****************************破産の哲学チョウさんが息子たちに生活の哲学を教えていた。「いいかな。もし破産しかかったときは、朗らかな顔をして何事ともなかったようなふるをしているのだよ。例えば、ユダヤ人の女の人が鶏を一羽盗まれたとする。彼女は、黙って隣の鶏を一羽盗んでくればよい。すると、隣の女の人も、よその鶏を盗んでくる。結局、どこかで、鶏が一羽足りなくなるわけだが、ユダヤ人の女の人の鶏は、元通りというわけだ。ところが、盗まれたからといって、うろたえ、騒ぎ立てたら、どうなると思う。近所の鶏小屋は、皆、鍵がかかってしまい、損をしたのは、自分だけになってしまうだろう。」****************************「破産の哲学」の文について、感想がある。人間さまざま、価値観や人生観もそれぞれ。人間のひとりひとりが、自身ひとりの人生や世間について抱く態度、見方などが異なっている。また、何が大事で何が大事でないかという判断、物事の優先順位づけの価値観も多様である。価値観か、人生観が違ってからこそ、運命も別々になるはずだと思う。というと、正しい価値観を養成するのは、大事にしなければならないものである。しかし、価値観か人生観というものは、どう生まれたのか、それは、大きな問題である。親や学校から教えられること、あるいはや共同体に属することによって継承されることもある。また、個人的な体験をきっかけにしたり、思索の積み重ねによって、独自に新たな価値観が構築されることもある。なんといっても、もっとも決定的なのは、親からだと思う。親の生き様への反発が人生観を形成している場合もあるけど、幼いころから見て育った親の生き様や、親が語って聞かせた人生観が色濃く反映している場合が多い。正しい価値観を持つ親は、正しい価値観を持つ子供を育つ可能性が高いだろう。
2007.09.04
-
地名というものは、文化遺産のひとつ
先日、ある教授の講演で「大字(おおあざ)」という言葉を初めて聞いた。あまり詳しく説明してくれなかったので、すっぐWikipediaで大字について調べてみた。大字は、近世の村の名を、明治時代以降の市町村合併の際に残したものである。例えば、例えば、新宿市大字渋谷字池袋とあれば、その池袋とは明治初年には渋谷村の池袋集落といった具合になるつまり、日本の近世の村の区画単位の名である。台湾では、日本に殖民されていた頃、特に1909年から1920年にかけて、市町村合併が行われたので、和式の地名も多く生まれていた。元々「打狗(Tago)」と呼ばれた「高雄」はその一例である。そのとき、日本の「大字」のような区画単位も使われていた。「どこに住んでいますか」と聞かれると、「大字」を答える台湾人はいまだに少なくない。特に、お年寄りと話しかけると、正式的な地名を使わずに、「大字」ばかりを使うことが多い。しかし、「えー、そういうとこるがある?!」と戸惑う若者も沢山いる。高雄人たちによく使われている「哈瑪星」、「五塊」、「林徳官」、「凹仔底」などの古い地名は、地元の人にとって、特有の地方感を表している。大字の地名を聞くと、なんだか懐かしさを感じがする。残念ながら、数回の廃置分合によって消滅された「大字」と「小字」も沢山である。地名とは、文化的に象徴的な意味をしている。文化遺産のひとつだと思います。地域のゆかりと歴史を語るような地名を、ひとつひとつ、、大切にしなければならないと思う。いくつの時代がすぎても、なるべく従来の地名を守ることだと思う。
2007.09.03
-
狡賢い人vs素直な人
今週の日本語授業に、二つのおどけを聞いた。面白かったので、ノートをとりました。******************【逆手の勝利】ある男が弁護士にたずねた。「弁護士様、訴訟が始まるまえに、裁判官にアヒルの立派なやつを一羽、名刺をつけて送っておいたら、どうでしょうか。」「とんでもない、そんなことをしたら、贈賄となって、裁判は、絶対にあなたの負けになります。」この裁判は、結局、勝訴になったので、男は大喜びで弁護士に言った。「あのとき、先生には、反対されましたが、やっぱり、裁判官には、アヒルを一羽送っておりました。」弁護士は、びっくりしていった。「しかし、あの謹直で知られた。判事さんが黙っていたとは。とうしても、信じられない。いや、何、名刺のほうは、訴訟相手の名前にしておいだんで」****************************【してやられた】イワンが一杯飲みたくなって、隣の人に1ルーブルを借りようとした。条件として折り合ったが、返却は来年の春。ただし、利息付で2ルーブルとする。この担保として、イワンは斧を預けること。イワンが承知して帰ろうとすると、その人が呼び止めて、「イワン、ちょっと」思い当たったのだが、「お前さんが、春になって、2ルーブルも返すのは、難儀だろう。だから、今のうちに、半分返しておいたら、どうかね。」イワン、「なるほど」と思って、1ルーブルをその人に返した。しばらく経って、イワンは思案顔でづぶやいた。「少しおかしいぞ。せっかく借りた1ルーブルは、これでなくなったし、斧もとられたし、しかも、春になったら、もう1ルーブルを返さにゃならん」と言って、あの人のいうことはもっともだし。****************************この二つのおどけは、おかしかったのだが、読む側に「やっぱり、ずる賢い人のほうが、得をとる」、「素直な人のほうが、損をしやすい」と思い込ませるきらいがあるかもしれないでしょうか。確かに、人間には、狡賢い人もいれば、素直な人もいる。世の中に生きるのに、狡賢くなければいけないっていう話もよく耳にしていた。正直に言えば、我々は、勝ち負けに取り組んでいる日々を過ごしているではないだろうか。学生時代に、成績のために、競争したり、社会人になったら、業績を向上するように、頑張ったりしていて、まるで競争の中で生きているような生活だとも言えるかもしれない。いろんな現実に遭遇しているとともに、知らず知らずのうちに、多かれ少なかれ、童心を無くしてしまうのだ。年を重ねるとともに、狡賢くなってきた感じがする。周りに、素直なのは、動物と子供しかなさそうだ。現代人を慰める効き目があるものだ。ペットか、赤ちゃんに出会うと、笑顔で迎えない人はいないだろう。可愛くて可愛くて、目に入れても痛くないほど、可愛がっている人も少なくない。動物や赤ちゃんが純粋だからこそ、かわいがられるではないでしょうか。もしかして、素直さを失いつつある現代人にとって、人間に触れ合うより、動物に触れ合ったほうが楽かもしれないなぁ。やっぱり、童心に返る必要がある。童心を通して、素直な自分に出会えたら、もっと心が豊かに、そして優しくなれるんじゃないのかな。いったい、狡賢い人のほうが、賢いか、素直な人のほうが、賢いかという問題が考える価値がある。わたしなら、いつも「賢い童心を保つよう」自分に励まして、その気持ちをこめて成長して生きたいと思います。
2007.09.02
-
自己流のヨガ
最近、ヨガに夢中になっている。毎晩、寝る前に、1時間ほどヨガをして、一日中の疲れを全部吹き飛ばしてしまうような感じがする。実は、ヨガをしているといっても、ヨガ教室に通わずに、ただヨガの本やDVDを参考にしながら、独習している。自己流、或いはマイペースとも言えると思う。難し過ぎず易し過ぎず、危険なポーズが少ないので、初心者の私には、ぴったりあう運動である。ヨガは伝統的でありながら、現代人にとても受け入れられる運動である。最近、台湾にも、ヨガ教室が増えてきたようです。私の知り合いの中に、わたしのようにヨガに夢中になっている人が多い。ただ、自分の部屋でヨガをするのは、私しかないらしい。ヨガの見た目は、普通の体操に似ているけど、確かに、違いがあるものだ。ヨガの本質は、呼吸にある。ヨガでは、呼吸の方法が非常に大切である。他のエクササイズとの、決定的な違いと言ってもよいかもしれないそうだ。つまり、吸う息と吐く息に結ばれたものという意味である。エネルギーをコントロールすることで、身体の機能を整え、体の動きと深い呼吸を組み合わせた最初の行法である。ヨガは、腹式呼吸で行う。鼻から吸って、鼻から吐き出す。そのままにし続けると、1ヶ月に5キロを減らすという話もある。わたし、初めてヨガをしたとき、なかなか上手にできなかったけど、自分で「伸ばす時に吸う、ポーズで息を止める、戻す時にゆっくり吐く」という行法に従って、今、だんだんなれるようになったような感じがする。これから、少しずつもっと難しいポーズを挑戦しろうと思っている。たとえば、ホタルのポーズとか、魚のポーズとか。
2007.09.01
-
台湾の中元祭りと日本のお盆
先日、言語交換の相手とお盆について話しました。初めて聞いたので、お盆の由来について、ちょっと調べてみました。台湾の中元祭りとお盆とは、旧暦の七月15日を中心に日本で行われる祖先の霊を慰める行事です。台湾の中元祭りと似ているところが多いらしいです。台湾社会には、一年に一度、鬼の霊が地獄から人間を訪れるという説があるので、夏に祖先や鬼の霊を供養する風習となるわけです。今年のお盆と中元はそろそろですね。最近、デパートやスーパーからのチラシ、お目玉品は、ほとんどお菓子です。実は、供物としてのお菓子です。一般的に言えば、台湾人は、お菓子、果物、飲み物、鶏肉、豚肉、魚などを供えます。もともとは、祖先や鬼の霊を慰めるために供養しますが、どんどん自分の仕事、勉強、恋愛、家庭、人間関係などを祈るようになってきます。というわけで、台湾人は、中元祭りの間に、「旺」、「福」、「来」などの字が付けられた商品を好みますから、特に、パイナップル(台湾語の発音は、旺に近いので、盛んという意味をする)、粽(中国語の発音は、「中」に近いので、あたりという意味をする)、「旺旺」という米餅(名前が好運を表す)、「孔雀」というクッキー(赤っぽい包装が好運を表す)、コーラ(赤っぽい包装が好運を表す)は、人気が集まっています。一番高い売り上げは、この時期なのです。なぜかというと、台湾人は、それを供えると運が開くことを信じているからです。実は、それは、経営者が「弊社のお菓子を供物としてすれば、霊を喜ばせるに限らず、運も開ける」と人目を引き付けるコマーシャル手法ばかりだと思います。現代人は、五感を刺激されて、洗脳を受けつつ、しらずしらずのうちに、物欲に目がくらむようになるようです。昔から伝われてきた行事も、さまざまな商売の手法で変身し、ますます本来の意味を失っていくのです。行事を行っている人々も目がなくなっているようです。祖先を慰めるというよりも、自分を慰めようと思うと言ってもいいです。人間は、わがままな生き物だと思います。ふりまわされ易くて、騙されやすい人間は、やはり、感情的になされた決定をするときが多いのですね。
2007.08.25
-
乗馬の旅の思い出
夏の旅行を振り返って、一番印象的な思い出と言えば、何と言っても馬に乗って喀納斯に行った旅です。特に、図瓦族のガイドとカザフ人の一家と一緒にユルトで過ごした体験です。 喀納斯(カナス)ほど美しい場所は、ないという話しもあります。モンゴル、ロシア、カザフスタンと国境を接する喀納斯(カナス)という地域では、雪化粧した山々、生い茂ている森林、広く果てしない高原だけでなく、カザフ、図瓦族、モンゴル人という珍しい民族も昔ながら生活を送っているとよく知られています。その中に、わずか2000人が残っている図瓦族は、今中国政府に特別に保護されている民族だそうで、絶滅危機人種だといえます。 図瓦族は、主に、カザフスタンとの国境に近い禾木村、白哈巴村、喀納斯村の集落で住んでいます。主に、自給自足の放牧をしています。禾木村から喀納斯村へ観光バスがあります。道路の状況もいいし、それに楽に綺麗な景色も見えるし、とても便利です。しかし、バスに乗ったら、多くの観光客や車の音がうるさいということを我慢しなければならないし、ゆったり自然を楽しむことができないので、やっはり、馬での移動のほうがいいと思いました。というわけで、私たちは、二日間かけて、馬に乗って禾木村から喀納斯へ行くことにしました。でも、最も気になっていたのは、このルートを歩くなら、坂を登ったり、下がったりするのは、もちろん、急流を乗りこえたり、谷や湖を越えたりすることも多いので、本当に険しいルートということです。 私たちは、もう危険を冒す覚悟で現地のガイドと馬を雇って、翌日の朝5時に出発することにしました。二日間の旅を通して、フウという図瓦族の男性のガイドに、私たちと馬たちの世話と道を案内してもらいました。私たちは誰も馬に乗ったことがないと彼に言うと、出発の直前に、「怖がることはないよ。わたしに任せてください。気をつければ、大丈夫だよ。」と言われたが、私たちは、物事が期待通りにうまく行くかどうか心配でした。 朝、4時ごろ起きて、5時に村から出発しました。丸木橋を渡ったり、坂を登ったり、思っていた通りに、凸凹道や曲がりくねた道ばかりでした。 空が明るくなるとともに、高原の遠くから日の出が見えるようになりました。高い丘に近づいていくと次第に壮観な名前も知らない山々が迫ってきます。少し残っている雪が被っている峰が、湖に映っています。一面の花々が絨毯のように、広がっています。景色を楽しめながら、山の奥へ向かって行きます。私たちは、雪化粧した山々、森林、せせらぎ、そして、青空に囲まれ、ガイドの牧場に辿り着きました。四時間、休憩なしに馬に乗り続けたわたしたちは、やっと一時の休みが取りました。40歳ぐらいのガイドHさんは、牧畜をやっているかたわら、乗馬のガイドをしています。ここのあたりには、観光客があまりいないのですが、お小遣いを稼ぐため、予約も受けるそうです。 彼は、羊が百頭、馬が80頭、牛が60頭がいるといいました。 さすが、馬の背に生まれ、育てられてきた子だけあって、馬を手懐ける時の立派さは、言うまでもありません。 彼の家族の皆さんは、私たちを親切に歓待してくれました。親切だといえば、親切ですけど、人なつっこいウイグル人とちょっと違って、彼らは、照れ性です。でも、牧民の彼らは「客が幸運を運んでくる」ということを信じていて、大量のご馳走で私たちを招待しすることを喜びとしているようです。彼の家でミルク茶を飲み、揚げパンを食べながら、一休みをしました。一時間の休みが終わってたら、彼の家を離れて、また旅を続けました。 しかし、彼の家を出た途端、大粒の雨がばらばらと降り出しました。レインコートを持っていない私は、雨に濡れながら、馬に乗っていました。心配そうなガイドは、わたしのために、わざわざお隣の遊牧民から手作りのレインコートを借りってくれました。 ガイドが私にコートを手渡した瞬間に、私の馬がびっくりして、前足が飛び上げたので、私は背中から引き落とされてしまいました。 私は、馬から落ちてしまいました。地面にしりもちをついたとき、大きい衝撃で体が再び前に飛んでしまいました。一瞬のことですから、皆がびっくりしました。実は、わたしもショックでした。 ガイドがて私の側で「大丈夫?大丈夫?」と叫びましたが、わたしは、驚きと痛みのあまり、声も出せないまま10秒もじっとしていました。ガイドは、返事ができなかった私を見て驚いたに決まっています。 「私、大丈夫。でも、痛い」と言いました。 痛くても全力で立ち上げたら、顔だけでなく、全身も泥だらけになってしまいました。私は、その光景を見て泣いたらいいのか笑ったらいいのかわからなかったのです。幸いなことに、お尻を痛めても、大怪我をすることなく、体も、背負っていたカメラバッグも、大丈夫でした。 皆がほっとしました。 わたしは、お尻の痛めを我慢していて、宿泊のユルトに着くまで、また四時間も休憩なしに馬に乗り続けました。夜の7時に湖畔の遊牧民のユルトに着きました。ここに泊まりました。馬から降りると、お尻も足も膝も、全身が泣きたいほど痛かったのです。私だけでなく、皆もそうでした。のろのろテントに入りました。ちょっと移動することさえも死にたいほど辛いのです。 カザフ人の夫婦は、忙しそうに、木を刈ったり、絨毯を敷いたりしています。私たちの食事と宿泊を準備しているようです。手伝ってあげる元気もない私たちがテントのなかに横たわって休憩するしかなかったのです。 日が山の遠くに沈みつつ、白いユルトも夕焼けに染まてきます。牛、羊、馬などが牧場で草を食べています。穏やかに流れているせせらぎを聞きながら、気持ちが落ち着いてきました。 皆が、静かにユルトから景色を眺めています。 幻の景色を初め見た感激といったらありませんでした。 知らず知らずのうちに、皆は、眠りに落ちてしまいました。 私が仮眠をしようとする頃、ガイドが私の側にやってきました。彼も私の側に腰を掛けました。 「また、痛いですか。大丈夫ですか、どこか、怪我をしましたか」と心配そうな彼は、私の具合を確かめて聞きました。 「原っぱには、鋭い石がいっぱいがあるので、あのとき、あなたは、石にぶつかたかなと思って、心配でした。万一、大怪我をすると、わたしもひどい目にあうのよ」と彼が言い続けました。「今日は、心配をかけてすみませんでした」と私が言いました。 「あなたの目は赤っぽいですね。疲れたのでしょうか。ちゃんと、休んでください。あした、旅も長いですよ。」と彼が何度も念を押して言いました。 仮眠をしようと思ったわたしは、急に寝る気がなくなって、彼とおっしゃべりをしたくなりました。 わたしは、図瓦族のことについて聞きました。 彼も私の質問に対して詳しく教えてくれました。特に生活習慣とか、価値観とか、お互いに意見を交換していました。 彼らの収入は、わずか私の収入の30分の1しかないのです。 収入は十分とはいえないまでも、彼らは、自給自足の生活を満足そうに過ごしているようでした。素朴な彼らと比べたら、私たちは、無駄使いをしすぎて、本当に浪費家だと自分で考えさせられました。さらにいえば、我々は、さまざまな生活の快適さを手に入れたかわりに、我々は取り返しのつかないほど自然を破壊してしまったのではないでしょうか。、科学の発達は人間の生活を便利で豊かにする反面、環境を汚し、素朴な人間さを失わせることになるのではないかでしょうか。 言い換えれば、彼らの生活こそ、贅沢だと思います。欲が少ない彼らは、もっともありがたいものをもっています。それは、純粋そのものだと思います。空気、水、食べ物、そして人間の優しさが、全て純粋なのです。 彼らは、純粋なものを大自然からもらって、感謝の気持ちをこめて、そのまま大自然に返すというのは、我々が模範として目指さなければならないのではないでしょうか。 やっと夕食です。 「これ、ボーサク(揚げパンみたいな食べ物)なんです。お口に合うかどうかわからないんですが」と遊牧民のおばさんが夕食と朝食を作ってくれました。 翌日、馬に乗るとき、お尻が針の上に座っているように痛かったですが、わたしは、どんどん乗馬に慣れるようになって、馬を操縦するのも上手になりました。今回の旅のおかげで、わたしは、牧畜のことや乗馬のことなどよく勉強になりました。もし、私が再びカナスに行く機会があるなら、現地の少数民族にもっと馴染んで彼らの生き方や物の考え方などを詳しく記録してみたいと思います。馬に乗るのは、体力も時間もかかりますけど、身近に自然を親しむことができるというよさもあります。馬に乗りながら、そこの独特な雰囲気を身をもって味わったのは、忘れられない体験だと思います。今回の旅をきっかけとして、私と姉が乗馬のことに興味を持つようになります。来年、中国の四川省とチベットの間の高原へ行くつもりです。十五日間の乗馬とハイキングの旅を計画しています。
2007.08.24
-
新疆とは
新疆という名前を耳にしたことがなくても、シルクロードを知らない方は少ないのではないでしょうか。シルクロードと言う言葉を聞いて思い浮かべる地域、大雑把に言えば、その一部に新疆があります。新疆とは、日本語の読み方は、「しんきょう」、漢語では、「シンジャン」といいます。元々は清朝の乾隆帝が征服した領土で、新たな(平定した)疆域」という意味を表す漢語訳の名前です。中華人民共和国成立以後、新疆ウイグル自治区と名称が変わりましたが、現在も一般的には新疆と呼ばれ、中国最大の省区となっています。新疆の総面積は160万平方メートルで、中国の国土の約6分の1を占めます。その面積は実に日本の4.5倍に相当します。中国の西北に位置する新疆は、東北はモンゴル人民共和国、西北はロシア連邦、カザフスタン共和国、クルグズ共和国、タジキスタン共和国、そして南部はアフガニスタン、パキスタン及びインドと国境を接し、国境線は5400キロメートルにもわたります。新疆ウイグル自治区(新疆)は中国最大の省区だといっても、そこの民族、文化、宗教などが中国の多数派(漢族、ハン族)と大きく違っています。中国文化に育てられてきた私にとってさえも、新疆にいたときに、異国にいるような感じがしました。地味の町には、中国語ができない人が多くいます。言葉が通じない場合に、わたしは、身振り手振りをして意味を伝えていました。それは、旅の醍醐味の一つともなります。今回の旅は、区都のウルムチから、モンゴル人民共和国、ロシア連邦、カザフスタン共和国と国境を接する喀納斯(カナス)、天山山脈の野原、中部の伊犂(イリ)谷を歩いてきました。私たち(私、姉、台北からのIda、北京からのBessie、あわせて4人の女性)が17日間近くにわたって旅行しました。地図と情報に関しては、下記のサイトを参考しました。http://www.geocities.jp/vinira2126/ditu.htmhttp://home.m01.itscom.net/shimizu/yultuz/silkroad/history/index.htm
2007.08.23
-
夏特村
限られた時間に追われての、慌ただしい旅行でしたが、私にとって一番思い出深い出会いは、やはり初めて思い出深い出会いはを訪ねた時だったなあと思います。新疆の真ん中を貫く天山山脈の中に位置されている夏特村は、伊犂谷から南疆と呼ばれる天山以南の地域に入る門戸なので、ここから南に向かって、天山の木札爾特峠を超えるのが、久しいルートでした。木札爾特峠は5000すぎメートルの標高ですから、おっかない道でした。玄奘もこの道を歩いたときに、相当の苦労を食いましたという歴史が<大唐西域記>という本に書いてあります。昔ながら、馬に乗らないと歩けないこのルートには、死霊が居ついていたのでしょうか。馬でこの道を通って、南疆に行くなら、少なくとも三日間がかかるということで、私たちは、このルートを歩かずに、ただ町を巡って歩きました。残念ですが、夏特人の若い娘に出会って、彼女の家を見学したのは、思いがけない体験で嬉しかったです。わたしは特に古い民家に興味がありますから、夏特人の民家を尋ねた時の喜びを言うまでもありません。古い雰囲気が溢れてる夏特村の家並みは今では珍しいです。屋根は、草葺が主体ですが、壁や床が草と土の混じりの素材で建てられたのです。魅力的で独特な民家です。民家の内部を見せてくれればいいなぁと思った途端に、ある若い娘を見かけました。わたしは、勇気を持って挨拶しました。私が「あなたの家を見学させてくださいませんか」と大胆に彼女に伺っていました。「いいですよ」と彼女が私たちを案内して彼女の家に入りました。やっと珍しい夏特民家の内部を見ました。好奇心が深いわたしは、沢山の質問をしたり、写真を撮ったり、しました。彼女は、たどたどしい中国語で私の質問を答えました。彼女の家はとても広い!驚いたことに、ただ女性しか出会いませんでした。それは、当たり前のことですね。なぜかと言うと、昼間に、男は外で稼いでいるのからです。中国語が通じないお婆さんとおばたちが私たちの手を繋がって、親切で家のあちこちを案内してくれました。彼らの笑顔は、もっとも綺麗な風景だと思います。たどたどしい会話ながらも確かに心を通い合わせることができた時の嬉しさは、他ではなかなか味わえないものです。干されている牛の糞が庭の真ん中に並んでいます。菜園、部屋、露天の台所、家畜小屋、ナンを焼く用の土炉などを見学させていただきました。この地方は、冬が来ると、すごく寒いので、彼らのベッドは、高床で、床も壁もジュータンのような毛織物がかかっていました。日ごとに消えてゆく古い民家とその町の生き方を訪ね歩く旅なら、地域を違えることやそれぞれに違った特色をもつ風土にふれることができます。これが旅の楽しさだし、感動でもあると思うのだが、そこでそれらの消えてゆく姿に接するなら、愛惜を噛み締める旅もなるでしょう。外人に入らせたことはない彼女の家を部屋から庭まで見せてもらいました。でも、どのように、彼らの歓待に返したらいいのか、迷っていました。わたしは、彼女の家を離れたとき、台湾から持ってきたチョコレートをプレゼントとして彼女にあげました。彼女と夏特村の人々が幸せになるように、祈っています。
2007.08.22
-
トイレのこと
以上の写真は、私が用を足したところの三ヵ所です私、新疆に旅行したとき、便意あるいは尿意が起きたら、野外で用を足すことが多いです。下品ですが、ずばり言えば「野ぐそ」です。旅行したところは、殆ど砂漠、草原、高山ですから、トイレがないから仕方なく野外でしているにすぎません。運転手のHさんは、時々、合う場所を探すなんてなかなか気が利いている人です。たとえば、大きい石とか、雑草の生い茂った森林とか。困ったことに、草原には、石も木もない場合なら、どこでしたらいいのか、迷うことも多いですね。最初は、ちょっと恥ずかしかったが、今まで育ってきた文化なんか一切考えないようにしたら、かえて楽になりました。何だか慣れてきたような感じがしました。いつでもどこでも好きな時に用が足せるようになっていますから、知らず知らずのうちに、野外式のトイレが好きになりました。実は、便所があっても、野外ですることが多いです。なぜかというと、多くの公衆便所は、仕切りとドアがないので、順番待ちの人と目が合うこともあり、ひどく心理的プレッシャーを感じるのからです。人前で排泄するのは、なかなかできない私は、公衆便所より、一人静かに野外で用を足すほうがいいと思います。特に、綺麗な花畑や森林の中で世を足せるとということの何と幸せなことか!景色も綺麗し、空気も新鮮し、それに、ストレスがないので、最高です。しかし、偶には隣で羊やら牛やらがじっと見守っているので、何となく居心地が悪いということと、夜は夜で電灯がないためどこにいるのかわからないので、危ないということなど、気をつけなければいけないのです。わたしは、野原である毒草(地元の人が蠍子草と呼ぶ)に触れて、ひどい目に遭った経験もあります。お尻や足が毒草に刺されて、三時間も痛めてたまらなかったので、大変でした。それは、旅の刺激の一つなのではないでしょうか。
2007.08.21
-
哈密瓜(ハミ瓜)
新疆の人々は、スイカやメロンなどの果物を多く食べます。新疆のピチャンはシルクロードの果物として有名な哈密瓜(ハミ瓜)の原産地として知られています。ハミ瓜は細長い形をしており、50センチ以上の大きいものまであります。果肉は柔らかくジューシーで、美味しいです。今では新疆の各地で栽培されていますので、あちこちで美味しいメロンを食べられます。新疆に旅行した時、夏バテで食欲が無い日に、果物で自分を元気にしたい気持ちで、夕食の代わりに、メロンを食べていました。実は、新疆の伊犂谷には、哈密瓜だけでなく、西瓜、メロン、桃、りんごなど果物が最高だそうです。フルーツに目が無いわたしは、初めて伊犂谷に行った時、蜂が花に引かれるように道の側に並んでいたフルーツスタンドに魅せられた。美味しくて安いので、大満足でした。
2007.08.20
-
無事に帰国しました
18日間の旅が終わりました。シルクロードからから無事に帰国しました。しばらく記事を書いていなかったので、日本語が下手になってしまった気がしますね。今、旅の写真と資料の整理に忙しいです。これから一週間に、記事も書くことのもできません。正常の暮らしに戻らないと。
2007.08.19
-
いよいよシルクロードへ
いよいよシルクロードへ出発。今度の旅では、どんな風景に出会えるのか、どんな人に触れるのか、想像するだに胸がどきどきします。新疆ウイグル自治区の区都、ウルムチを台湾語で読むと、「おろもちぇ」に近いので、台湾語の「おろもちぇ」は、中国語に訳すと、「乱七八糟」と言う意味です。日本語で言えば、「滅茶苦茶」という意味に似ているのです。いつの間にか、台湾人は、「ウルムチは、滅茶苦茶の町だ」というイメージを持つようになります。冗談みたいですが、知らず知らずのうちに、その冗談は、当たり前のことになってしまって、皆がそう思うようになるのです。母も、「ウルムチ?あぁ、わかった。おろもちぇね。あの滅茶苦茶の町じゃないか。どうして、そんなところへ行くのか。」と口にしました。わたしが答えられるのは、苦笑しかありませんでした。確かに、私たちと遠く隔たっている新疆というところは、さすがに風変わりが湛えた遥か所だと思います。情報によると、新疆ウイグル自治区の区都、ウルムチは、世界で最も海から離れた内陸都市だそうです。大陸乾燥性気候に属し、寒暖の差が激しく、降水量が少ないという特徴を持ちます。過去、最高気温は1973年8月1日に42.1度、最低気温は1951年に-41.5度を記録しています。一日中の気温差は少なくとも30度以上を達するのは、普通だそうです。そこの331MMらいの平均降水量から見ると、3000MMぐらいの平均降水量に恵まれている台湾人にとっては、いかにも不毛なところなのでしょう。気候は、もちろん、文化や風景も独特の雰囲気が溢れている場所なんです。新疆(シンジャン)には、ウイグル、漢、回、カザク、満、モンゴル、シボ、オロスなど13の主体民族があるということです。中国の一部といっても、まるで異国のような地域といえます。あとは、二日間しかないので、旅の準備をしなければいけません。今回の旅の間によく日焼けする場合が多そうですから、黒くならないように、日焼け止め、帽子、マスクなどが欠かせないものを持たなければいけません。もっとも気になるのは、YURT(ユルト:遊牧民のテント式住居.)に泊まることなんです。わたしは、馬に乗ったことがないので、一日中6時間で馬に乗るなんて、わたしはできるかなと、ちょっと心配です。ユルトのあたりには、シャワーどころか、トイレもないのです。水のことも大事なことだと思います。そこには、水道水もなさそうです。とりあえず、タオルと寝袋を用意しておいたほうがいいと思います。楽しみにしています。
2007.08.01
-
こうもりの話(2)
こうもり(蝙蝠)の「蝠」の字が「福」に通ずることから、縁起物とされます。特に中国では、百年以上生きたネズミがコウモリになるという伝説もあり、長寿のシンボルとされているらしいです。多くの国では、蝙蝠は夜行性で奇妙な羽をもつ、不気味な動物と見られがちであるが、古来、中国では蝙蝠は吉祥紋として工芸品に盛んに用いられている。 しかし、西洋文化圏にとって、こうもりはバンパイアそのものだというイメージをもっているようです。あまり美しいとは言えない蝙蝠は、全く邪悪と善良の正反対なイメージです。 西洋であれ、中国にであれ、コウモリの擬人化をしているようです。忌み嫌われる西洋のこうもりと中国の蝙蝠の正反対なイメージに文化の違いの面白さを感じたものですね。 だが、こうもりが幸運なものだと思う中国人は少ないでしょうか。 西洋文化に影響されたからです。
2007.06.21
-
こうもりが訪ねてきた
毎朝、スズメが何羽うちのベランダに餌を食いに飛んでくるのは、普通だが、今朝、ベランダを訪れてきたゲストのは、こうもりだった。 実は、こうもりの赤ちゃんだった。 黒っぽくてちっぽけな体は恐れられたように、びくびくしていた。もしかして、道に迷ってしまったのかなと思っていた。迷子を捜しているお母さんは、いまきっと焦ているに決まっている。 都会でうまれ、都会で育ち、田舎で暮らす経験は少ない私は、目の前にいるこうもりを見たとき、驚かされて「何ですか、これ」と大声で母に聞いた。 母は、ちょっとびっくりもしないように、「こうもりだ」平気に答えた。 母は、そのこうもりの胸に手をあてて、そのこうもりが母の指を噛みそうに怒っていた。 母は、「実は、わたし、子供のとき、こうもりが怖かったのよ。大嫌いだった。子供のとき、こうもりが時々屋根に止まってきて、皆が困ったものだ。」と言った。 インドで旅行したとき、泊まった部屋の窓に止まっている大勢の大きいこうもりを見たことがあるが、怖かったので、窓を閉めてちゃんと観察できなかった。 私なら、そんなに近い距離にこうもりに触れるのは、初めてだ。見れば見るほど、怖いどころか、かなら可愛いと思った。 こうもりは本当は、害虫を食べてくれるいい動物だという話を聞いたことがある。主蚊、ハエ、蛾などを食べて生活しています。こうもりがいなくなってしまうと、害虫だらけになってしまうのだ。 おまけに、こうもりは退治・駆除してはいけない、つまり殺したり、捕まえたりしてはいけない動物だ。 面白い動物だね。
2007.06.20
-
シルクロードへ
夏休みは、目の前ですね。 前月から、夏休みの旅の準備に熱中しています。 今回は、シルクロード(SilkRoad)の旅を立つ予定です。 しかし、最も気になっているのは、アクセスのことです。 台湾から中国へ向かうの直行便がないので、香港か、あるいは、マカオで乗り換えることは、多いです。 だが、香港から烏魯木斉に向かう直行便は、ないので、ほかの主な都市で乗り換える必要があるのです。 三区間のフライトがスムーズに進むように、どんなスケジュールをしたらいいのか、旅行会社の係り者とよくブレーンストーミングをしていました。 最後のスケジュールを下記のように立てました。 6月29日に、高雄を出発し、香港で乗り換え、午後三時半ぐらい北京に着く。北京発の国内便でウルムチ(烏魯木斉)に向かう。烏魯木斉に着くのは、だいたい夜の12時。 21世紀の今日にすら面倒くさそうなアクセスは、昔々、長安から天竺を目指し、絹の道をひた歩いた玄奘三蔵にとって、きっと何倍以上に困難な道には違いないのです。朝に飛び立てば、夜には西域に降り立つことができる大変便利な時代になりました。 駱駝がないと移動できない時代は、もうなくなりました。今は、レンタカーで西域を旅行できるようになる時代です。 豊田の砂漠王というジップを借り、運転手とガードを雇い、自由自在の旅にしました。 期待でわくわくしていた私は、3分もじっとしていられないほど、興奮しています。 PS.ちょっと長い(18日間)の旅ですから、日本語はさっぱり忘れてしまうかな、また、強い日ざしを受けて黒人になるかな、心配ですね。
2007.06.19
-
日本人の夫婦関係について
先日、クラスの中で、高雄市政府で建築局長をしているH先生は、「日本人の夫婦関係は、中国人の夫婦関係となんだか違うんですね。日本人夫婦がパーティーに誘われて、夫婦なのにわざと席を離れて座ったりします。人前で、自分の女房のこと、あるいは、自分の旦那のことを話すなんか、珍しそうです。」 先生の感想を聞いたわたしは、周りにいる日本人の友達のことを思い浮かべてみると、確かにこれはよくあたっていると思うからです。 妻の仲間と夫の仲間は別々のようです。夫婦は、お互いに付き合っている仲間を紹介する傾向はなさそうです。夫は、自ら自分の知り合いを妻に紹介しなければ、妻も自ら自分の仲間を夫に知りあわせないのです。 夫婦の共有した友人は、ほとんどないといえます。 「日本では、夫婦の関係より親子の関係、とりわけ母と子の関係が中心になっている。父親は自分のもつ社会的職務を遂行する事に多くの時間を割き、家庭内のことに注意を向ける余裕のないことが多い。」というある話も聞いたことがあります。 日本人の夫婦関係には、繊細的なたてまえというものもあるはずだと思います。 好奇心がわくわくしたわたしは、日本人の夫婦関係について、もっと知りたいのです。
2007.06.13
-
What do I want to be remembered for?
昨夜、デパートでテレサ・テンのCDを購入しました。 収録してある作品は1984から1993までの日本曲です。テレサの歌は、殆ど持っていますが、今度買ってきたCDには、二三曲聴いたことはないのです。今回、それを手に入れるたのは、とてもうれしかったです。 新曲の中には、もっとも気に入るのは、夕凪とい歌なのです。詞も美しいし、曲調もロマンチックだし、素晴らしい作品だと思います。 夕凪 詞:松井五郎 曲:川口真 白い波が ささやくように 指先を 濡らしてゆく 涙だけが 拭い上手な 思い出を 覚まして 遠い海に 心が見える そっと胸に 手をあてて 夢にしまった いとしい名前 今は、優しく 響く 一人 漂うなら 夕凪に 恋も静かに 揺れるから 砂にねむる 貝殻ひろい 古い詩 たずねてみる 耳に残る 吐息でさえも なつかしくなるまで あてもなく 続く 足跡 迷わないで 振り返る 髪の毛のほつれ なおす間に きっと 優しく なれる 一人ただようなら 夕凪に 恋は まぼろし 物語 恋は まぼろし 物語 夜更けの静かさに、テレサの歌声が流れてきたとき、全身が粟立つような感覚にとらわれました。聞き耳を立てるかのように、テレサの声に集中して、感激して体が震えたりしました。 宝石を鏤めたみたいに、キラキラした空気まで送り込んでくるようない歌い方。澄み切った声は、もう、上手という次元を超越していました。感動の一言です。 聞き惚れたわたしは、彼女の透き通った声音を通じ、彼女の気持ちと深く共鳴するものがありました。 彼女の歌に彼女の波瀾に富んだ人生を重ねて思うと、感慨が出てくるようになりました。しかし、彼女は、自分のことは後回しにしても、他人のために一生懸命に歌うような人でした。音楽で幸せを与えたり、人の疲れや苦しみを癒したりした彼女は、いつまでも多くの人の心に残っていると信じています。 She left a legacy that everyone will remember and pass on from generation to generation. What about myself? 不意にわたしの頭に、 「What do I want to be remembered for?」 「What legacy do I want to leave when I one day make my own exit from the stage of life?」という質問が浮かんできました。 そうですね。 What a shame that I would say nothing but “Is this all there is to life? I always thought there was so much more to achieve and be when I arrive at the end of my life. 昨夜は、自分にそんな質問を聞いたわたしはなんだか眠れなくなりました。
2007.06.10
-
偏見は怖い凶器
最近、気になっているのは、高校三年生J君のことです。 非常に大人しくて、礼儀正しい青年です。わたしは、とても気に入りの子です。 ただし、いつも、明るい子ですが、最近、無口になって、憂鬱な顔をしています。 高校生時代は、大変不安定時期ですから、彼のことがとても心配です。 先日、彼とお喋りをする事によって、彼の悩みがわかりました。 思った通りです。学業の悩みです。 実は、それは台湾で高校教育を受けないとは、理解できない問題です。 根本的にいうと、その問題は台湾の高校教育制度にあると思います。 実は、二年生になる高校生たちは、学期の末に自然組と社会組のふたつの進路に、一つを選ぶことになっています。ここの「組」は一般的な**年**「組」ではなくて、教科によって別々の編制をとることを表すというのです。つまり、高校二年生を自然志向と社会志向の二つの集団に編制する制度ということです。 自然組というのは、自然科学や理工学部志向を持つ人向きで、社会組というのは、文学、法律、商業などの学部志向の人向きです。高校生たちをふたつのカテゴリーに分けた制度は、まるで人間自然と社会の二元性に分けるのだろうかとと思って、ぜんぜん人間性を考えずに作られた制度のではないでしょうか。 そういう制度は、元々は、「適切な人材を適切な位置で発展させる」という理想に基づいて設計しされたが、しかし、台湾社会は、殆ど「自然組の生徒は、将来性がかなり高い。就職が易しいし、給料もいいしというという意識をもっています。 「男なら、自然組を選ぶ!」か、「自然組を選ばないと男ではない」という偏見を持っている親や高校生が少なくないのです。多くの高校生は、親の指示に従って、無理に自分に合わないクラスに入ったそうです。 やっぱり、一度も親の意見を違反したことはないあの子は、大人しかったばかりに、高校の二年生のとき、親の指示に従って、自分のやりたい進路を諦めてしまいました。両親に対する遠慮から、自分のなりたいことを断った彼は、毎日、自分の勉強したくない科目に触れて、つらくてたまらなかったのです。 今、もう三年生の彼は、がっかりとした打ち明けました。今回の化学は、ゼロをとっただけでなく、物理も不合格そうだ。彼は、どうして男は社会組じゃいけないのと繰り返して言いました。 身のあたりの生徒たちを見ると、J君だけでなく、大体同じ悩みを持っている人は、多そうです。 台湾社会の偏見かもしれません。 親のなかでは、子供の進路はすでに決まっていました。 自分の子供の意見や気持ちを聞くまでもなかったのかもしれません。子供本人の気質に合うかどうか、一切考えに入れないようです。 いつも「いい子」と思われた彼は、幼いころから、ずっと親に気兼ねをして、親の意向を優先して、結局、何を自分が好むか、何が本当に自分に似合うか、もう見分けつかなくなりました。 やっぱり、彼にとって、これは、「遠慮」と「思い切り」の間の戦争ではないでしょうか。 彼の親の意見には、サンデーが口を挟む余地など、ありませんが、彼に「Choose what you love and then love what you chose」わたしが言いました。 社会の偏見は怖いものは一言です。親は、それを凶器として使って、自分の子供の自分らしさを殺してしまったかもしれません。
2007.05.31
-
人間は本来、自由人ではないか
先日、「団塊自由人」をテーマーにしての研究ペーパーを読みました。 団塊自由人はどのようなセカンドライフを送るのか、どんな生活意識を持っているのか、興味があります。 団塊自由人のセカンドライフというのは、主に、道楽的生き方、稼ぐ生き方、社会還元生き方の三つの生き方が絡み合う構造をなすということです。団塊自由人は、「自ら」を中心として、自分らしい生活を追求し、様々な選択肢を考えに入れ始める新しい人生段階へ進むのです。 文章の内容を目を通すと、自分、自由、自分らしい、自ら、自己、自在、自然、という言葉で、「自」をめぐって描かれたものです。 その研究ペーパーを通して、サンデーは、日本社会をよりよくわかるようになります。 いよいよ、団塊自由人が登場する時間ですね。 集団意識を強く持っている日本人は、リタイヤになったら、とうとう「自己」を意識し、かえって大胆になりたがるかのような気がします。現役時代の“大人しい会社人”というイメージでしたが、定年になるときには、“わがままな自由人”を意識しているようにも見えます。 その研究ペーパーは、主に団塊自由人登場以後の社会と市場をめぐって考えていますが、実は、わたしは、内容に関わらない疑問があります。 人間は本来、自由人ではないか。 この疑問の答えは、わたしだけでなく、だれもかも知りたいかもしれないと思います。 自由というものは、定年者ならではの特権ですか。 実は、自分らしさを抑える必要がないと思います。 今時のライフを楽しめれば、セカンドライフは、いらないと思います。 「わがまま」、「勝手」、「自由」、「個人」、「自分」という言葉は、東方社会にとって、あまりよくないと思われるそうです。日本にも中国にも。でも、いつまで自分らしい生活を待てばもういいのか、いつまで自分らしさを抑えれば、もういいのか、サンデーは、苦笑せざる得ないのです。 人生は、一度しかないのでしょうか。 人間は本来、自由人でしょうか。 なぜ、定年にならないと、自由を楽しむことができませんか。 確かに、この疑問の答えは、わたしだけでなく、だれもかも知りたいのです。 勿論、一度しかない人生には、いろいろな役を演じること。 いやな役もあれば、好きな役もあります。 女性なら、子どもから、青春時代の乙女、現役時代のレディー、熟年のおば、最後に痩せた老人になるまでの姿です。一生の道は、ぱっさりと決まったように、変えようにも変えられないようです。 しかし、人間は、そのままに、、決まった段階に決まった役を演じなくてもいいです。 いやな役を演じなくてもいいです。 この世で本当に演じたい役は、一生のうちにチャ決まっています。定年者ならではのものではないと思います。 実は、こんな生きがいは古代の先人たちが認めていることです。ギリシャ人も中国人もそう思っていました。 30代のサンデーもそう思います。 いつも、今のモーメントをしっかり掴んで、精一杯に自分らしさを発揮さえできれば、セカンドライフは、いらない、定年もいらないと思います。 第一人称の台詞を言ってみては、どうですか。 足の向くまま、気の向くまま、自己実現生活をしよう!
2007.05.27
-
ノスタルジアとは
先日、日本人のロングステーの意思決定について、調査をしました。自由記入の答えをまとめて、面白い結果を発見しました。アンケートの中に、日本人の回答者に「あなたは、ロングステイ地としての台湾に対してどのようなイメージを持っていますか。三つの形容詞をお答えください。」という質問を答えてもらいました。最も多く選ばれた形容詞は、下記の通りです。 一、親切(やさしい、暖かい、情熱的、親日的な、友好的) 21% 二、賑やか、活気的、刺激的、近代的 15% 三、美味しい 13% 四、楽しい、面白い 12% 五、暑い 11% 六、気楽、のんびり 8% 七、安い 7% 八、綺麗、美しい 6% 九、安全 5% 十、懐かしい 3% その中に、もっとも気になっているのは、「懐かしい」という形容詞です。 私は、なぜ日本人が台湾にくる、懐かしい気分になるのか、興味があります。 やはり、1895年(明治28年)から1945年(昭和20年)にかけて、台湾を殖民地として統治した歴史は、まだ日本人の心に残っているようです。すなわち、日本人は、台湾を殖民地として統治したという歴史を忘れられないでしょうか。 確かに、日本統治時代の名残は、今もなお台湾人の生活に色濃く息づいてるのです。 たとえば、駅弁とか、地名とか、日本式様の建築とか、いろいろな日本原風景が残ってきました。サンデーが住んでいる高雄近郊にある、旗山という山間の小さな町には、1920年前後に建てられたバロック風の町が今も残っています。旗山だけでなく、日本殖民時代の雰囲気が溢れている町は、多いです。日本人は、そういった町を見ると、何気なくノスタルジアを感じさせられるかもしれません。 ノスタルチックな雰囲気に包まれ、知らず知らずのうちに時空を超えるのでしょうか。 ノスタルジア(英語、nostalgia)とは、異郷から故郷、あるいは過ぎ去った時代を懐かしむという意味です。とはいえ、ノスタルジアは必ずしも過去への郷愁を意味しないのです。「元いた故郷」に対する郷愁は、実際にはその「元いた故郷」がどこかわからなくともノスタルジアが生じることがあります。もっというなら、最初から特定の場所にかかわりない場所に向かってそこをなんとなく元いた場所にいるような気がして、深く身に沁みることもあります。 よく考えてみれば、人間は、ノスタルジアを感じながら、未来を想定するのでしょうか。ノスタルジアというものを通して、自分の過去と未来の時空がお互いに対話できるようです。時には、ノスタルジアの感情に身を任せると、しばらく現実を逃避することもできると思います。 一度でいいから懐かしい場所に行ってみたいと思うだけなのだと思います。実は、ノスタルジアはありえないものへの憧れにもとづきながらも、そのありえないものからのはぐれた時点で世界を眺めている視線なのです。 人間は、失われた時を追憶したり、今を逃避したり、未来を創造していくものだと思います。 サンデーが「幼いころに戻れれば、いいな」と、「一日早く定年になりたいものだ。定年になったら、幼いころのような生活を取り戻すことができるだろう。」とつねづね冗談を言っていました。 幼いころに戻るなんて、それは、ありえないものだとわかっていますが、昔ながらの環境に優しいシンプルな生活を送ろうと思って、積極的に未来の生涯を設計しよう」といつも、自分に言っています。
2007.05.23
-
世界を変えるのは、一人一人の交流から
韓国と北朝鮮を結ぶ南北縦断鉄道、京義線と東海線で17日午前、休戦ラインを越える列車が57年ぶりに運行されたそうです。南北分断によって途絶した縦断鉄道を再運行させるのは、平和に向かって大きな一歩を踏み出すのではないか。 台湾から中国大陸までの直行便に乗れる日がくるように願っているサンデーは、民族和解の象徴としての鉄道再運行が羨ましいなぁと思う。 一日も早く第三地で乗り換えないで中国への直行便に乗りたいものだ。 実は、国と国の絡み合いは、一人一人の交流から始まるのだ。 小さな青い地球で争い、血を流し合っているのは、ほかでもない、人間一人一人である。つまり、自分たちだったのだろうかと思う。物事の考えの違いによる戦争や民族対立を起こすなんて本当にばかばかしい。 現代社会における人間関係は、かなり冷淡で、お隣の人すらあまり挨拶しなくなる社会である。今時の子供たちは、自分の部屋で引きこもってばかりいて、家族のメンバーたちにも無関心そうで、自分の親の職業も年齢も知らない人もいる。信じられないな。親を殺す人もいるとは。 人と人の間に、感性の交流も少なくなりそうである。ちょっとしたことのせいで、喧嘩したり、傷つけたりするなんか報道がしばしばでてくるようだ。人と人は、お互いに冷たく扱い続けたら最後、きっと民族と民族、国と国が、争いや疑いばかりを起こすに違いない。 教育関係の仕事をしているサンデーは、生徒たちに触れる毎日を送っているけれども、彼らの思いがわかりにくくなるような感じがする。彼らは、世界の未来を創造する主人公ではないか。サンデーの役割は、いかに大切なのか、わかるようになる。サンデーの一人の力はちっぽけというものの、世界の未来を変えられるパワーとなるかもしれないのだ。 だから、これから、サンデーは、力のかぎり、自分の生徒たちの学力を上達させるだけでなく、彼らに「感激、感謝、感動」という三つの態度を伝えろうと思う。 「感激、感謝、感動」という気持ちをこめて生きたがる次世代を育てれば、世界の未来には、争いや戦争などが少なくなるだろうと思う。 世界を変えるには、自分自身からやらないとね。
2007.05.19
-
Seven-year's itchとは
先日、ある女性の友人が訪ねてきました。 貿易関係の仕事をしている彼女は、とても優秀なキャリアーウーマンです。私と同じ年配で、子供が一人います。ご主人は、いま大陸で単身赴任中です。 「実は、サンデーさんに言いたいことがあるのですが、いいえ、聞きたいことがありますけど」そんなに悩みそうな顔をしている彼女を見るのは、初めてです。 「何ですか。」とわたしは聞きました。 「サンデーさんがそんなことを知ると、きっと怒る決まっているのです」「わたしは、叱責されるのだと覚悟を決めました」といった彼女は、なかなか「そんなこと」を口に出し難そうでした。 「わたしは、叱りませんよ。いったいどうしましたか。グレースさん。」私は、ふっと不安になりました。 彼女は「恥かしいですが、あの、最近、わたしは、男が気になっている」と言いました。 「正常ですよ。あなたは、女です。女は男が好きものです。それは、当たり前のことです。」とわたしはニコニコとして答えました。大したことはないと思ってほっとしましたが、次の言葉は、わたしを驚かせることでした。 「でも、あの人は、旦那ではないですが…」彼女は、ついに打ち明けました。 「それじゃ、大変ですね。どんな人ですか。」ちょっとびっくりしたわたしは、頭の中で、「あっ、もしかしたら、不倫の関係があったかしら」と思いました。 「彼は、仕事上での取引先なんです。先日、彼の会社に伺ったとき、彼は、そっとメモをわたしに渡した。ラブレターでした。ただし、彼は妻と子供がいるのに、」と彼女は、とても悩んでいるようです。「あなたも既婚の女ですよ」と私は、内心でそう言いました。 「あなたは、あの人のことを好きになりましたか、それとも、ちょっと一時の気持ちだけですか」わたしは、後者のほうが可能だと思って、聞いてみました。 「自分自身は、わからないんです。彼に会いたかったり、彼の声を聞いたかったり、します。彼の顔が時々頭で浮かんで、忘れようにも忘れることができないので、つらいです。」彼女は、「どうしよう、どうしよう」って繰り返して聞きました。 「それじゃ、困りますね。あなたは、もう妻と母でしたよね。」わたしがわざと伝えました。 「それがわかってますよ」と彼女が言った。 「もうデートをしましたか。」わたしは、心配なので、聞いてみました。 「そんなわけはないよ。わたしは、絶対不倫なんかしない。信じてください。」「でも、精神的に自分の旦那を裏切ったかのような気がします。つらいですから、誰かに聞いてほしくて、誰かにわかってほしいのです。サンデーさんは、私の仲良しですから、内緒をサンデーさんに言いたかったのです。」彼女は、正直に答えました。 実は、サンデーにとって、こんな難しい問題には、何とも答えようがなかったのです。サンデーは、結婚もしないし、子供もいないし、それに、男のひとを見る目がないのです。夫婦の関係について意見を与えるなんか、自信はありません。 どちらかと言えば、サンデーは浮気と不倫のことに反対です。 「じゃ、自分をよりよく忙ししては、どうですか。そうすると、彼のことを思う時間がなくなるのかもしれないんです」わたしは、名案を挙げました。 「たとえば、ヨガとか、語学とか、とにかくできるだけ自分を何かに打ち込ませるようにしよう。何かに熱中したら、あの人のことを忘れるようになるかもしれません。あなたは、理知の大人ですから、自分の判断は正確かどうか、分別できないわけがないのです。あなたはどちらのことを選ぼうとも、サンデーは、サポートしておりますよ。あなたのことを信じていますよ」とわたしが言いました。 仲良しが自分の内緒を聞かせてくれたのは、うれしかったのですが、本当に「それは、だめ!」と注意しようとと思っていたが、考えたあげく、やはりやめる事にしました。 「だめです」「いけないです」という言葉ばかりを出せば、彼女を失意の底に突き落とすのだろうかと思っていた。ですから、わたしは、非難するよりもユーモアで彼女の気持ちを解するほうが効果的だと思っていた。私は、彼女を励ましたり、慰めたり、しました。 それ以後、彼女が電話をかけてくれたのは、一週間が過ぎたころでした。「あしたから、週に三回、語学学校に通いますよ。英語を勉強するようにします。もっと有意義なゴールを目指すと、人生の道に迷わない」と彼女はもう元気を取り戻したようでした。 その話を聞いて、よかったとほっとしました。 英語には、「the seven year’s itch」という言葉を聞いたことがあります。日本語に訳すのは、結婚後7年目ごろの倦怠や浮気などという意味です。 単調な結婚生活には、だるさや疲れを感じることもありますね。 さらに、世の中にたくさんの誘惑が身を囲んでいるだけあって、一旦迷ったら、たいしたことになるのかもしれないんです。だからこそ、忠告をあげられる仲良しが大切ですね。迷っている友達をリーダーできれば、うれしいと思います。
2007.05.17
-
お茶を恋しています
昨日、姉、友達Yさんと、一緒に老家福というレストランへ食事にいきました。 実は、老家福の経営者も私の仲良しです。彼女はやる気がいっぱいで.、すごく精力的人です。 彼女は、看護婦の専門学校を卒業してから、看護婦をしているかたわら、家族のレストランとお茶の事業を手伝っています。彼女は、まだ若いですが、、もういろいろ経験があり、特にお茶のことに熟練しています。 お爺さんからレストランとお茶の事業を受け続いてから、かれこれ30年になるそうです。ご家族の皆が精一杯に頑張っています。ですから、地元の人には、大好評の店だけでなく。外国の観光客にも、人気高いだそうです。日本語のガードブックにもススメの文章も書いてあるということです。店のガラスに貼っている雑誌とガイドブックの報道が見られます。 去年、ある友達が中国雲南省のプーアル茶を送ってくれました。ただ外見から見ると、黒っぱくて丸い餅みたいなものです。しかし、鼻に寄せると、カビの臭みとお茶の香りの混じりの匂いがします。プーアル茶は、中国の有名なお茶の一種だと知っていますが、そんなに変なお茶を飲んだら、大丈夫かしらとちょっと心配でした。とりあえず、彼女にお茶のことを伺ったほうがいいと思いました。 彼女とお母さんは、非常に親切で、私たちをお茶を飲みに誘ってくれました。わたしたちは、いろいろな種類のお茶を味見させて頂いきました。まるで、お茶の味ききの会のようでした。勿論、お茶についていろいろを語っていました。その中に、もっとも印象深かったのは、やはりプーアル茶でした。 雲南茶(プーアル茶)は中国雲南省に自生している茶大木の茶葉を数年間貯蔵さあれ、古くから伝わる特殊の方法で発酵させたものです。麹菌を加えて永年熟成させた後発酵の黒茶なので、独特の芳醇な香りとさっぱりした味がしています。飲めば飲むほど、繊細的で柔らかい味が出ています。 天然サポニンとミネラル類を豊富に含み、肥満、脂肪の溶解、ダイエット効果、消化促進、整腸作用、二日酔い、胃のむかつき改善、血糖値の上昇を抑制、血行促進に効果がある。さらに、増強免疫力(免疫力を強める効果)、抗老化(老化予防)、癌予防、歯を強くする効果もあるそうです。プーアル茶は、美容にも良いだけでなく、脂っこい料理を食べた後に飲むのがよいといわています。 わたしみたいな中年の女性は、ぴったりではないか。(笑) 美味しいお茶を飲みながら、元気の生活を送れば、いいなとおもいます。
2007.05.14
-
好客(ハオク)って
食事中に、日本の友人が「台湾人は、外国人に親切です。特に日本人にやさしいです。」と言いました。それを聞いて、うれしかったのです。 しかし、「中国の人も、台湾の人に親切ですか」と友人がいきなり質問を投げかけたとき、サンデーはちょっと戸惑いました。 実は、サンデーは、小さい頃から、親友はもちろん、馴染みのない人たちも歓待してあげる父母の姿を見て、感心していました。それから、サンデーは、優しく人と接することは大事だと育てられていました。ですから、サンデーは客好きの気質を持つようになります。私の家族は、皆、好客(ハオク)です。 中国人や台湾人のみならず中華系の人々全般の文化的特性だといえるかもしれないのです。「朋あり遠方より着たる、また楽からずや」にもあるように、おもてなし好きな中国の人は客人を温かく迎え入れることになっています。 残念なことに、政治の違いのせいで、中国と台湾は、二つに分裂されているのです。政治への考え方が違っても、中国で歩いたサンデーは、優しい現地の人々に触れました。どこへ行っても、皆は優しく招待してくれました。 中国の人といい、台湾の人といい、皆親切です。 しかし、ほかの国の人たちは中国の人のようにおもてなし好きなのか、という質問は、体験しないと答えられないのです。 10年ほど前から、年に二三回海外へ旅に出ています。かれこれ27カ国を歩きました。知らない国で知らない人に出会って、日常生活に体験できない感覚をもらいました。現地の人たちとのおしゃべりを通して、いろいろなインスピレーションを受けるとともに、人間心根の優しさを感じ取りました。 もしかしたら、人間は、本来優しいものなのかもしれません。優しさは、国境を越え、政治や、思想や、人種をも超えます。 わたしは、新約聖書に書いてある言葉を信じています。 「兄弟愛を保ちなさい。 よそから来た人を親切にもてなすことを忘れてはいけません。そうすることにより,ある人たちはそれと知らずにみ使いたちをもてなしたのです。」 今、私は、その質問を答えるようになります。 はい、中国の人は、皆に優しいです。 わたしも、優しい人になりたいのです。 偉い人か、天使のような人をそれと知らずにもてなせるかもしれないのですよ。
2007.05.13
-
The Amish and I
高雄もすっかり夏らしくなってきました。日中もよく晴れて、日差しがたっぷりとありそうです。高雄も、ヒートアイランドで苦しんでいます。ヒートアイランドというのは、大都市において、都市の中心部が郊外より気温が高くなる現象ということです。ヒートアイランドを引き起こしている原因は、汚染物質がちりとなって浮遊して、熱が逃げにくくなったり、冷暖房機器や交通機関などの多量の熱源により暖まってしまうそうです。 地球の環境破壊は、非常な速さで進む一方です。いったい、私たちを取り巻く環境は、悪くなりつつある原因はなんでしょうか。 暑い日に何気なくクーラーをつけて、扇風機をつけっぱなしにしているわたしは、責任をとるべきだと思います。毎日の暮らしの中で、便利な電化製品に囲まれた私は、便利な生活を楽しむとともに、環境を破壊してしまいそうです。つまり、わたしは、地球の殺人者と言えますね。 これから、省エネとか節電ということばかりを意識して生活しなければならないのです。確かに、皆がアーミッシュ(Amish)のように、生活できれば、環境にちょっと一休みさせられるかもしれないと思います。 数年前に、アメリカへペンシルバニア州に住んでいる友達を訪ねていたとき、初めてアーミッシュ人に出会いました。外へ出かけると、すれ違いの馬車に乗るアーミッシュを見かけたら、といつでも「怪しい」と感じがした。 彼らは、原則として、現代の技術による機器を生活に導入することを拒み、昔と同様の生活様式を営むそうです。日常生活ではきわめて、古い時代の技術しか使わないようにするために、自動車は運転せずに、それに風車・水車によって蓄電池に充電した電気しか利用できないそうです。そのとき、電気も使用せず、現代の一般的な電話も持っていない生活にどうして我慢できるのだろうかと不思議でたまらなかったのです。 友達は、わたしを連れて隣のアーミッシュ人の家へ行った。 農場で走たり、遊んだり、自由自在に自然を楽しんでいるアーミッシュの子供たちの姿は、本当に印象的でした。素晴らしいライフスタイルだと感心していた。 自分の生活を反省してみたら、無駄の場合が多いです。これからも、少しずつ「電」に関するものを避けようにしました。 確かに、個人の力など地球環境を破壊してきた力とは、比べものにならないほどちっぽけなものかもしれません。しかし、一人一人の意識の変化や小さいな歩みは、地球を守るための大きな運動につながる確実な動きです。 人間一人一人が「地球に優しい」存在になり、「ふるさとは地球」ですと美しい地球を誇る日が来るかどうか、それは、ほかでもないそこに住む私たち次第のです。
2007.05.12
-
デスティネーションとイメージ
デスティネーションイメージについての課題を勉強してから、もう二月間になりました。ただ今、引き続き、観光地のイメージをめぐって、ロングステイ適地に関する意思決定やイメージについて研究したり、欧米や日本の既存の文献を読んだりしています。よく勉強になりましたけど、とても複雑な分野です。デスティネーションに関するイメージというのは、心理面の先入観そうですが、実は、心理面の先入観は、認知的要因と関連があります。人間は、自分の好みや志向に従って、ある特定の行き先に関するイメージを繋がることになっているといえます。ですから、行き先を選びときに、自分の好みや志向によって、いろんな情報を探して、合わないところを取り除いて、合うデスティネーションが選択肢として考えに入れることになっていると思います。自分の好みや志向は濾過装置器のように、特定の行き先を導き出すのではないでしょうか。人々の好き嫌いは情報に影響をうける一方で、人々の好き嫌いは、どんな情報を探すのを決めるのではないでしょうか。イメージは、人の好みとどんな関係があるのか、とても面白いですね。人間は、本来複雑なものですね。とりあえず、今の調査のこと、頑張ります!!!
2007.05.01
-
偉くなりたいか
今日、「日本の高校生は米中韓の高校生よりも「出世意欲」が低いという面白い報道を聞きました。米中韓に比べ、明確な目標を持てない日本の高校生の実情が浮かんだ。「偉くなりたいか」という問いに、「強くそう思う」と答えた高校生は中国34.4%、韓国22.9%、米国22.3%に対して、日本はわずか8.0%。卒業後の進路への考えを一つ選ぶ質問では、「国内の一流大学に進学したい」を選択した生徒は、他の3国が37.8~24.7%だったのに対し、日本は20.4%にとどまった。また、将来就きたい職業では、「分からない」を選んだ生徒が従来のより増えるとのことがわかった。なぜかというと、「食べることに困らなくなり、今の高校生は『偉くなりたい』という意欲がなくなってきている」と、また、「職業に魅力や権威がなくなっている」という話しがある。高校生の時代に、わたしは、「卒業さえすれば、出世できる」とずっと憧れていた仕事ができるよう期待していたので、優れた物になりたいという野心がいっぱいでした。現在の学生は明確な目標を持てないどころか、伝達力も無くなるようだ。いつも「わからない」と口にだす学生が多くいるのです。わたしは、旅行が好きだけでなく、自分の専門、経歴、年齢と違う人とお喋りをすることにもとても興味があります。MIXIや楽天を通じて、多くの素晴らしい人に知り合いました。日本語の勉強にためになるのは勿論、人生を指導して励ましてくれて、ありがたい仲間だと思っています。まだ日本語が下手なわたしとお喋りをすると、いらいらするに決まっているのでしょうか。幸いなことに、年上の友達は、皆、わたしの先生みたいのように、辛抱が強くて、優しく教えてくれました。ありがとう。ところで、日本の高校生だけでなく、台湾の高校生も出世意欲がなさそうです。未来、台湾の若者は世界の舞台で競争ができるものか。心配です。もっと頑張ってやらないといけないと思いますね。
2007.04.25
-
カラーのパワー
わたしの庭は色がいっぱいだ。まるでにじみたいだ。変化も色彩も富んだスペースでコーヒーを飲んだり、本を読んだするのは、満足がいっぱいだ。鳥たちの囀りに起こされて、庭に出て、朝焼きに染める浴びる毎朝、わたしにとって、とても楽しい一時なのだ。鳥たちとお花は、皆、お早うと言ってくれるようだ。庭に目を通すと、緑はもちろん、茶色、紫、ピンク、赤、白、オレンジ、淡黄色、暗赤、青、約十種以上がある。華やかで綺麗だ。偶には、小さいな自然に身を任せれば、心も体も癒されるね。
2007.04.21
-
ほっとしました
昨日、第1回の研究発表をしました。ほっとしました。 ただし、再来週には、2007年の地理学者大会でプレゼンを発表する予定ですから、休憩どころではなく、頑張っています。 ところで、昨日、建築士の友人から、素晴らしいプレゼントをいただきました。それは、Cities for a small planetという本です。面白そうだったので、夜更けまで読んでしまいました。都市というのは、複雑で不思議なものだと思います。いいえ、正しく言えば、都市を作る人間は複雑で不思議だと思います。
2007.04.19
-
鳳飛飛のコンサート
母、姉、わたしの大好きな女性歌手は、何といっても鳳飛飛です。 彼女は1981年に香港人と結婚し、香港へ移住しました。その後子供にも恵まれ、円満な家庭を築いています。2003年には高雄と台北で「鳳飛飛35週年演唱會」コンサートを開催しました。まだまだ根強い人気者ですから、2005年にも台北ほか各地でコンサートが行なわれました。 4月14日に高雄文化中心で彼女の二年ぶりのコンサートに行ってきました。わたしたちは、二ヵ月前に、チケットを買っておきました。広告がなかったのに、もう早く完売だそうです。大好きな歌手ですから近いほどいいと思っていたので、1枚約15000円の席を買いました。 多くのファンは、皆、彼女の姿と歌に感動して、興奮しました。お洒落な舞台服と照明やネオンなどがちかちかと輝き、幕が開くと、その瞬間、彼女が現れました。母、姉、わたしは、ほかのファンと一斉に席から跳びあがりそうにキャーと叫びました。 いつもお洒落な帽子をかぶりながら登場するので、「帽子歌后」とも呼ばれた彼女は、今回もやはりも五つの綺麗な帽子をかぶって出演しました。彼女の立派な演出を見たときの感激は何とも言えないのです。 彼女の歌はわたしたちを時空を越えた昔に回帰させ、幸せいっぱいの思い出を甦らせました。最後のモノローグでは、彼女は今まで芸一筋に生きてきたと感じて、涙までも出てしまいました。わたしは本当に感動して、涙が零れました。 コンサートというと、歌が主役でしたが、今回の演出は、最初から最後までダンスや熱唱でした。53歳の鳳飛飛はコンサートを開く資格のある歌手に違いないと思います。 わたしは、感心しました。彼女を模範として生きていきながら、有意義な夢をかなえようと決心しました。
2007.04.15
-
睡眠時無呼吸症候群とは
最近、気になっているのは、呼吸のことです。寝ているとき、呼吸が時々中止することです。人生の約3分の1は睡眠に費されており、睡眠の障害は健康に大きな影響を与えます。先日、最近では居眠りによる交通事故があったというNHKの報道を耳にしました。わたしは、睡眠障害のことに気がつくことになりました。実は、以前も睡眠中に窒息感があったことがあります。側に寝ていた姉から目覚まされたこともあります。「いびき」ではなく、ただ言葉を言うように怪しい声がでるだけでした。特に試験やプレゼンを準備している間に、睡眠中に呼吸が中止することが多くあります。特例だと思ったので、あまり気にしないでいました。しかし、そのうち、何となく深刻になるようになって、ちょっと心配しています。もしかしたら、論文のことを脳を使いすぎたせいかもしれません。今月の下旬のセミナーで論文を中間報告するために、研究に打ち込んでいました。寝ているときにも、いろいろな考えが頭の中に集まったりしていました。ちゃんと休むことができませんでした。ストレスが睡眠中の呼吸障害に繋がる可能性があるのか、分りません。これは病気の一種類かどうかも知らないんですから、ちょっとインターネットに、情報を調べて見ました。情報によって、これは、睡眠障害の一つで睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndromeを略してSASと呼びます。睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは10秒間以上続く無呼吸が、一晩の睡眠中(7時間)に30回以上、もしくは1時間に平均5回以上認められ、かつその一部は脳波上覚醒している睡眠時(ノンレム睡眠)にも認める場合を睡眠時無呼吸症候群といいます。無呼吸により脳波上も覚醒し、深い睡眠を得ることができなくなり(断眠)、日中の眠気を生じたり、集中力が低下します。また無呼吸により血液中の酸素の低下と炭酸ガスの蓄積や血液の酸性化をもたらし長期的には様々な臓器に悪影響を及ぼします。幸いなことに、わたしは、一晩の睡眠中2、3回ぐらいしかありませんから、睡眠無呼吸というより低呼吸だと思います。また、わたしは、深い睡眠を得ることができなくなるわりには、日中の眠気もなければ、頭痛もありません。逆になかなか張りがあります。さらに、睡眠時無呼吸症候群の患者さんは肥満、高血圧や糖尿病に伴っていることも多いですが、わたしには、いずれもないんです。この病気は、ストレスにかかわるかどうか、わからないんですが、ストレスがあるかぎり、この病気が治られないと思います。研究の世界には、苦しみも楽しみもあります。苦しみを感じてからこそ、楽しみを実感できるかなと思います。
2007.04.04
-
ロングステーとしての台湾のアンケートを募集
日本人の皆様、こんにちは:私は台湾高雄師範大学地理大学院生のサンデーと申します。現在、日本人の海外長期滞在(ロングステイ)希望者を対象に、ロングステイ適地に関する意思決定について研究しております。 台湾では、ロングステイを希望する日本人の方々を招致する事業が、昨年から本格化いたしました。台湾の学界にとって、ロングステイというマーケットは、まだまだ未知の分野であると私は考えています。地域活性化のために、日本人観光客、特にロングステイヤーを招致しようという研究はあります。またその中で、ロングステイヤーのために、どのような施設の改善や環境の整備が必要か、といった供給面から分析された研究も多くなされています。 しかし、日本人の好みとか、滞在先へのイメージなど、ニーズ面からのロングステイ適地分析の研究は未開拓であると言えます。日本人のロングステイヤーが、希望滞在先へどのようなご希望やお考えをお持ちなのか、もっと詳しく知りたいと思いました。 以上の観点から、今回、私はアンケートを作成いたしました。このアンケーはこのアンケートには老若男女を問わず、日本人である限り、誰でも答えられます個人情報保護のため、回答者の方々にご記入いただいた個人資料などは一切公開いたしません。どうぞご安心ください。また、調査報告書ができあがりましたなら、ご報告いたします。アンケートを添付いたしました。お手数ではございますが、ご回答を頂ければ幸いです。 ご質問、ご不明な点等ございましたら、私の楽天のメッセージボックス、あるいは掲示板までお気軽にお問い合わせください。 アンケートの答えは私のMixiのメッセージアドレスへお送りください。 サンデー ロングステイ先としての台湾に対するイメージのアンケート調査票 下記の質問に直観でお答えください。 ***************************ロングステイとは生活の源泉を日本に置きながら海外の1カ所に比較的長く滞在し、その国の文化や生活に触れ、現地社会への貢献を通じて国際親善に寄与する海外余暇を総称したもの。(LS財団、2007) *************************** 1.あなたは、ロングステイ候補地を考えたら、台湾を考えに入れますか。 答え:( )。 1-1:はいと答える方は、理由を教えてください。 1-2:いいえと答える方は、理由を教えてください。 2.あなたは、ロングステイ地としての台湾に対してどのようなイメージを持っていますか。三つ以上の形容詞を使ってお答えください。(例:面白い、つまらない、うるさい、静か、危ない、刺激的、汚い、綺麗、親切、懐かしい、冒険的、気楽、安い、賑やかなど) 3.あなたは台湾を思ったとき、何を連想しますか。頭に浮かんだ場所、人物、事件などを、三つ挙げてください。 4.あなたは、ロングステイ希望者に台湾をお勧めますか。答え:( )。 4-1:「はい」と答える方は、理由を教えてください。 4-2:「いいえ」と答える方は、理由を教えてください。 5.あなたの抱いている台湾のイメージに点数をつけてください。各項目とも7点満点です。数字を選んで右の答えの欄に記入してください。5-1:( )。醜い1-2-3-4-5-6-7 美しい 5-2:( )。つまらない1-2-3-4-5-6-7面白い 5-3:( )。不清潔1-2-3-4-5-6-7清潔 5-4:( )。うるさい1-2-3-4-5-6-7 静な 5-5:( )。物価が高い1-2-3-4-5-6-7 安い5-6:( )。不親切1-2-3-4-5-6-7親切な 5-7:( )。さびしい1-2-3-4-5-6-7 にぎやかな 5-8:( )。こせこせ1-2-3-4-5-6-7 のんびりした 5-9:( )。危険1-2-3-4-5-6-7安全5-10:( )。沈滞している1-2-3-4-5-6-7 活気がある6.あたたのプロフィールについて: 6-1:あなたの年代をお答えください。 1、20-29歳2、30-39歳3、40-49歳4、50-59歳5、60歳以上答え:( )。 6-2:あなたの性別をお答えください。 答え:( )。 6-3:あなたのご職業・お立場は、以下のどれにあてはまりますか。 1、現役 2、退職者 3、無職(退職者ではない) 4、主婦 5、その他(ご記入ください) 答え:( )。 6-4:あなたの同居形態・家族構成をお答えください。 1、一人暮らし(単身世帯) 2、配偶者(夫又は妻)、(夫婦二人世帯) 3、その他:(ご記入ください) 6-5:あなたは海外でロングステイをしたことがありますか 答え:( )。 6-6:あなたは台湾に行ったことがありますか 答え:( )。 アンケートはここで終わります。 ご協力いただき、ありがとうございました。 アンケートの回答は私の楽天のメッセージアドレスへお送りください。
2007.03.11
-
ロングステー先としての台湾のアンケートを募集
日本人の皆様、こんにちは:私は台湾高雄師範大学地理大学院生のサンデーと申します。現在、日本人の海外長期滞在(ロングステイ)希望者を対象に、ロングステイ適地に関する意思決定について研究しております。 台湾では、ロングステイを希望する日本人の方々を招致する事業が、昨年から本格化いたしました。台湾の学界にとって、ロングステイというマーケットは、まだまだ未知の分野であると私は考えています。地域活性化のために、日本人観光客、特にロングステイヤーを招致しようという研究はあります。またその中で、ロングステイヤーのために、どのような施設の改善や環境の整備が必要か、といった供給面から分析された研究も多くなされています。 しかし、日本人の好みとか、滞在先へのイメージなど、ニーズ面からのロングステイ適地分析の研究は未開拓であると言えます。日本人のロングステイヤーが、希望滞在先へどのようなご希望やお考えをお持ちなのか、もっと詳しく知りたいと思いました。 以上の観点から、今回、私はアンケートを作成いたしました。このアンケーはこのアンケートには老若男女を問わず、日本人である限り、誰でも答えられます個人情報保護のため、回答者の方々にご記入いただいた個人資料などは一切公開いたしません。どうぞご安心ください。また、調査報告書ができあがりましたなら、ご報告いたします。アンケートを添付いたしました。お手数ではございますが、ご回答を頂ければ幸いです。 ご質問、ご不明な点等ございましたら、私の楽天のメッセージボックス、あるいは掲示板までお気軽にお問い合わせください。 アンケートの答えは私のMixiのメッセージアドレスへお送りください。 サンデー ロングステイ先としての台湾に対するイメージのアンケート調査票 下記の質問に直観でお答えください。 ***************************ロングステイとは生活の源泉を日本に置きながら海外の1カ所に比較的長く滞在し、その国の文化や生活に触れ、現地社会への貢献を通じて国際親善に寄与する海外余暇を総称したもの。(LS財団、2007) *************************** 1.あなたは、ロングステイ候補地を考えたら、台湾を考えに入れますか。 答え:( )。 1-1:はいと答える方は、理由を教えてください。 1-2:いいえと答える方は、理由を教えてください。 2.あなたは、ロングステイ地としての台湾に対してどのようなイメージを持っていますか。三つ以上の形容詞を使ってお答えください。(例:面白い、つまらない、うるさい、静か、危ない、刺激的、汚い、綺麗、親切、懐かしい、冒険的、気楽、安い、賑やかなど) 3.あなたは台湾を思ったとき、何を連想しますか。頭に浮かんだ場所、人物、事件などを、三つ挙げてください。 4.あなたは、ロングステイ希望者に台湾をお勧めますか。答え:( )。 4-1:「はい」と答える方は、理由を教えてください。 4-2:「いいえ」と答える方は、理由を教えてください。 5.あなたの抱いている台湾のイメージに点数をつけてください。各項目とも7点満点です。数字を選んで右の答えの欄に記入してください。5-1:( )。醜い1-2-3-4-5-6-7 美しい 5-2:( )。つまらない1-2-3-4-5-6-7面白い 5-3:( )。不清潔1-2-3-4-5-6-7清潔 5-4:( )。うるさい1-2-3-4-5-6-7 静な 5-5:( )。物価が高い1-2-3-4-5-6-7 安い5-6:( )。不親切1-2-3-4-5-6-7親切な 5-7:( )。さびしい1-2-3-4-5-6-7 にぎやかな 5-8:( )。こせこせ1-2-3-4-5-6-7 のんびりした 5-9:( )。危険1-2-3-4-5-6-7安全5-10:( )。沈滞している1-2-3-4-5-6-7 活気がある6.あたたのプロフィールについて: 6-1:あなたの年代をお答えください。 1、20-29歳2、30-39歳3、40-49歳4、50-59歳5、60歳以上答え:( )。 6-2:あなたの性別をお答えください。 答え:( )。 6-3:あなたのご職業・お立場は、以下のどれにあてはまりますか。 1、現役 2、退職者 3、無職(退職者ではない) 4、主婦 5、その他(ご記入ください) 答え:( )。 6-4:あなたの同居形態・家族構成をお答えください。 1、一人暮らし(単身世帯) 2、配偶者(夫又は妻)、(夫婦二人世帯) 3、その他:(ご記入ください) 6-5:あなたは海外でロングステイをしたことがありますか 答え:( )。 6-6:あなたは台湾に行ったことがありますか 答え:( )。 アンケートはここで終わります。 ご協力いただき、ありがとうございました。 アンケートの回答は私の楽天のメッセージアドレスへお送りください。
2007.03.11
-
「台湾でロングステイ!」アンケートを募集中
日本人の皆様、こんにちは:私は台湾高雄師範大学地理大学院生のサンデーと申します。現在、日本人の海外長期滞在(ロングステイ)希望者を対象に、ロングステイ適地に関する意思決定について研究しております。 台湾では、ロングステイを希望する日本人の方々を招致する事業が、昨年から本格化いたしました。台湾の学界にとって、ロングステイというマーケットは、まだまだ未知の分野であると私は考えています。地域活性化のために、日本人観光客、特にロングステイヤーを招致しようという研究はあります。またその中で、ロングステイヤーのために、どのような施設の改善や環境の整備が必要か、といった供給面から分析された研究も多くなされています。 しかし、日本人の好みとか、滞在先へのイメージなど、ニーズ面からのロングステイ適地分析の研究は未開拓であると言えます。日本人のロングステイヤーが、希望滞在先へどのようなご希望やお考えをお持ちなのか、もっと詳しく知りたいと思いました。 以上の観点から、今回、私はアンケートを作成いたしました。このアンケーはこのアンケートには老若男女を問わず、日本人である限り、誰でも答えられます個人情報保護のため、回答者の方々にご記入いただいた個人資料などは一切公開いたしません。どうぞご安心ください。また、調査報告書ができあがりましたなら、ご報告いたします。アンケートを添付いたしました。お手数ではございますが、ご回答を頂ければ幸いです。 ご質問、ご不明な点等ございましたら、私の楽天のメッセージボックス、あるいは掲示板までお気軽にお問い合わせください。 アンケートの答えは私のMixiのメッセージアドレスへお送りください。 サンデー ロングステイ先としての台湾に対するイメージのアンケート調査票 下記の質問に直観でお答えください。 ***************************ロングステイとは生活の源泉を日本に置きながら海外の1カ所に比較的長く滞在し、その国の文化や生活に触れ、現地社会への貢献を通じて国際親善に寄与する海外余暇を総称したもの。(LS財団、2007) *************************** 1.あなたは、ロングステイ候補地を考えたら、台湾を考えに入れますか。 答え:( )。 1-1:はいと答える方は、理由を教えてください。 1-2:いいえと答える方は、理由を教えてください。 2.あなたは、ロングステイ地としての台湾に対してどのようなイメージを持っていますか。三つ以上の形容詞を使ってお答えください。(例:面白い、つまらない、うるさい、静か、危ない、刺激的、汚い、綺麗、親切、懐かしい、冒険的、気楽、安い、賑やかなど) 3.あなたは台湾を思ったとき、何を連想しますか。頭に浮かんだ場所、人物、事件などを、三つ挙げてください。 4.あなたは、ロングステイ希望者に台湾をお勧めますか。答え:( )。 4-1:「はい」と答える方は、理由を教えてください。 4-2:「いいえ」と答える方は、理由を教えてください。 5.あなたの抱いている台湾のイメージに点数をつけてください。各項目とも7点満点です。数字を選んで右の答えの欄に記入してください。5-1:( )。醜い1-2-3-4-5-6-7 美しい 5-2:( )。つまらない1-2-3-4-5-6-7面白い 5-3:( )。不清潔1-2-3-4-5-6-7清潔 5-4:( )。うるさい1-2-3-4-5-6-7 静な 5-5:( )。物価が高い1-2-3-4-5-6-7 安い5-6:( )。不親切1-2-3-4-5-6-7親切な 5-7:( )。さびしい1-2-3-4-5-6-7 にぎやかな 5-8:( )。こせこせ1-2-3-4-5-6-7 のんびりした 5-9:( )。危険1-2-3-4-5-6-7安全5-10:( )。沈滞している1-2-3-4-5-6-7 活気がある6.あたたのプロフィールについて: 6-1:あなたの年代をお答えください。 1、20-29歳2、30-39歳3、40-49歳4、50-59歳5、60歳以上答え:( )。 6-2:あなたの性別をお答えください。 答え:( )。 6-3:あなたのご職業・お立場は、以下のどれにあてはまりますか。 1、現役 2、退職者 3、無職(退職者ではない) 4、主婦 5、その他(ご記入ください) 答え:( )。 6-4:あなたの同居形態・家族構成をお答えください。 1、一人暮らし(単身世帯) 2、配偶者(夫又は妻)、(夫婦二人世帯) 3、その他:(ご記入ください) 6-5:あなたは海外でロングステイをしたことがありますか 答え:( )。 6-6:あなたは台湾に行ったことがありますか 答え:( )。 アンケートはここで終わります。 ご協力いただき、ありがとうございました。 アンケートの回答は私の楽天のメッセージアドレスへお送りください。
2007.03.05
-
お宅に閉じ込めているリタイヤ者
日本では、2007年から、大勢の団塊世代が退職し始めるそうです。退職する団塊世代が今後どのような生き方をするのかは、日本社会に大きな影響を与える問題だと思います。日本と同じように、台湾の人口構造もますます少子高齢化になっていく一方です。今後の台湾の行方はどのように進むのかということに関心があります。これから退職する団塊世代はどのように定年生活を送るつもりなのか、すでに退職した人たちはどのように暮らしているのか、知りたいと思います。定年生活というと、どういったことを連想しますか。人によって、さまざまですが、そのなかでも、どこへ行くこともなくただ家にいながら暮らしている人が大勢いるそうです。私の周りの高齢者たちは、ほとんどそのタイプです。高齢者と言っても、体が不自由というわけではないのです。彼らはまた労働力を持っている人たちですが、家に閉じ込もったまま日々を送るしかないんです。 お宅に閉じ込もている人を分けると、自分を缶詰にする人と自分を引篭もる人という二種類があります。まず、缶詰という意味を調べてみました。缶詰というのは:1 食品をブリキ缶やアルミ缶などの容器に詰め、空気を抜いて密封したあと、熱を加えて殺菌し、長期間保存できるようにしたもの。2 一定の場所に人を閉じ込めて、外部との交渉を断った状態に置くこと。たとえば、「小説家をホテルに―にする」「牛肉を缶詰にする」 狭い場所に多人数がとどめ置かれた状態。閉じ込めること。たとえば、「立ち往生の電車の中で―にされる」「子供たちを一室に缶詰にして勉強させた」また、引き籠というのは:1家に閉じこもる。たとえば、「風邪で1週間家に引きこもっていた」、「病気で引きこもりがちだ」2活動をやめて静かに暮らす。たとえば、「田舎に引きこもる」、「政界を辞して別荘に引きこもっている」ただ定義だけからみると、意味が似ているようですが、実は、微妙に違うところが見えると思います。自分で缶詰になる人と自分から引き篭もる人との間の、主な違いは、環境を感受する気持ちだと思います。家に自分から引き篭もる退職者は、外部との交渉や新しい人間関係を作るなんて興味がありません。社会というものは自分に関係ないと思うので、まったく世間に無関心で地域社会に参加しようともしないようです。自分の趣味を探すつもりもなければ、別に生きがいも自省するわけでもないのです。つまり、自分の生きている地域社会と結びつく気もなく、環境を感受するには、マイナスの気持ちを持っています。周囲にマイナスの印象を与える恐れがあります。自分から引き篭もる退職者に対して、缶詰になる退職者はそんなにマイナス印象を周囲に与えないようです。ほかの人から邪魔されないように、自分から閉じ込もって、自分の好きなことや趣味に夢中になれるのです。とういわけで、意欲的です。やる気のあることには、自分を磨こうという意欲があります。独学で技術や言語を身に着ける人もいるそうです。たまには、気の合う仲間と交流したり、同好会に参加したりします。自分の部屋に缶詰になったまま、趣味に打ち込むのです。周囲からは社会の中で肯定的な役割が生かせると思われます。私の周りのリタイヤした人たちの中では、前者のほうが多いようです。孫の世話を見ているじじばばがいっぱいですが、Couch potato人(ソファーに寝そべってテレビやビデオばかり見ている人.)も少なくないようです。定年生活はどうすごしたらいいのか、リタイヤした人にはもちろん、若い世代には考えるべき大切な問題ではないか。
2007.01.02
-
Happy New Year
新年快樂 Happy New Year! Bonne année 明けましておめでとうことしも よろしくお願い申しあげます。
2007.01.01
-
今年の自分にご褒美は
今年もいよいよ終わりですね。今年がすべてが終わると豪華なレストランで食事できれば、いいなぁと思っていたので、家族と一緒に王品ステークレストランで食事することにした!自分にもご褒美を送るのです。贅沢だが、幸せがいっぱいと感じができれば、価値があると思います。大事な家族と食事をしたり、一杯飲んだりして、そして一年の無事を喜びあい、新しい年が無事迎えられることを皆とお神さまに感謝するのは、大切だと思います。どうぞ良いお年が迎えられますように。
2006.12.29
-
本当の定年生活とは
今朝、NHKニュースを見たとき、定年についてのニュースを耳にした。早速、NHKのHPを訪ねた。下記のように書いてある:「発表によりますと「イオン」は、来年2月から、パートを含むすべての従業員、およそ12万人を対象に、定年を現在の60歳から65歳にまで延長し、延長後も賃金などの処遇は原則として変えないということです。企業の間では、法律の改正でことし4月から、原則として65歳までの雇用が義務づけられたのを受けて、定年退職した人を再雇用する動きが広がっていますが、人件費を抑えるため、現役時代よりも低い賃金で雇用し直すケースがほとんどで、厚生労働省では賃金などの処遇を変えずに65歳まで定年を延長するのは大手企業では珍しいとしています。「イオン」が定年の延長に踏み切るのは、景気の回復で企業の間に人手不足が広がっていることに加えて、来年の春からいわゆる「団塊の世代」の大量退職が始まり、人材の確保が大きな課題となっているためで、ほかの企業にも今後、影響を与えそうです。「イオン」人事企画部の公文節男部長は、「何十年も勤めてきた従業員が持っている能力、技術をそのまま生かしていけることが一番大きなメリットで、新たに人を雇って教育するよりも効果が見込める」と話しています。」報道によると、定年後でも、仕事に強い意欲を持っている人も大勢いるらしい。もしかして、忙しくて忙しくてたまらないと感じさえすれば、自分の生きがいが感じられるかなあ。定年になったら、これまでの仕事中心の生活から、いぎなり地域中心の生活に変えられないではないか。つまり、仕事がなくなることに不安を感じる方はたくさんいるでしょうか。定年になるそばから、現役時代からもう慣れてしまった生き方はなくすとともに、従来の自分の生きがいも消えるようになる。もともと会社を母体として依頼してきた「会社人間」は定年になったら新しい支点を見つけないと、自分の価値はないと思いがちだと思う。定年生活を始めようという気持ちにかわって、「でもあきらめなければ、しようがないか」、「失業生活」か、「浪人生活」を始めるところ」という気持ちを持っている退職者が増えているようだ。どうして、のんびりと定年生活を送れないのか。もしかして、定年後、失業生活にはやましいと感じられるのか。あるいは、仕事をしないと、周りの人にゴミと思われる恐れがあるのか。何かをしないと、生きがいがないと思われるので、定年になっても、何にかをしなければならないという労働感もどんどんでてくるではないか。どちらかというと、人間は労働感を持ちものではないか。人の目にまったく気にせず、自分の趣味を求めて、自分らしい生活を送れるのは、本当の定年でしょうか。
2006.12.26
-
私は負け犬なの
私は負け犬なの最近、Business Weeklyが「負け犬の遠吠え」という本の書評を掲載していた。負け犬は何を指すのか、早速、調べてみた。負け犬って、三十代の女性、未婚、子供なし、女の負け犬なのだ。というと、日本社会には、そういう女性は人間じゃないって思われる。私はこの本の分類上メスの負け犬だ。すると、私は人間じゃない。怖い。お金持ちでも「嫁がず、生まず、30歳以上」になるとこのカテゴリーに入り、一般的に「負け組」という。欧米人の女性にしたら、女性を簡単に勝ち組、負け組にカテゴライズするなんて、不思議極まりないと思うにちがいない。性別の差別をつける視点かも。Sex and the Cityというドラマでの主人公の四人は作者の定義する「負け犬」に当たる女性。だが、皆が経済的にも生活的にも自立できる女性。自分らしさを持って、独身の生活に大満足を感じる女性。私の周りの女性には、独身でいる女性もいれば、早婚をした人もいる。恋愛を経験して、ご主人に出会って、結婚して、子供を生んで、家庭を築くパターンに従っていた人がいっぱい。残念なことに、「独身生活に戻れるといいなあ」、「もう一度、人生をやり直せたらいいなあ」、「結婚しなかったらよかったのになあ」、「羨ましい、サンデーサンのこと」と言ったこともある既婚の女性友人が大勢いる。そういう話を聞くたびに、「今更言ってもしようがない」と思うが、既婚者でも独身者でも、尊い人生経験が得られると思う。人生はそんな単純ではない。独身のわたしは楽に生活できるが、きれいな花嫁のドレスを着てみたらいいなあと願うときもある。ただ着てみるだけでいい。旦那はいらない。笑納してください。
2006.12.24
-
義理チョコ
昨日、日本語の先生が新しい日本語の単語を教えてくれた。その中に、もっとも面白いのは、義理チョコなのだ。初めて聞いたので、とりあえず、義理とはどんな意味なのか、ちょっとインターネットの辞書を引いた。1 物事の正しい筋道。また、人として守るべき正しい道。道理。すじ。たとえば、「―を通す」「―にはずれた行為」。2 社会生活を営む上で、立場上、また道義として、他人に対して務めたり報いたりしなければならないこと。道義。たとえば、「―が悪い」「君に礼を言われる―はない」「―をわきまえる」3 つきあい上しかたなしにする行為。たとえば、「―で参加する」4 血族でない者が結ぶ血族と同じ関係。血のつながらない親族関係。たとえば、「―の母」5 わけ。意味。日本人は、バレンタイン&ホワイトデーに義理でチョコレートを贈ったり、もらったりする習慣があるようだ。学校、職場の恒例イベントと化したものなので、日本社会ならではのものだ。学生の場合、義理チョコというよりは「友チョコ」となっている。一方、職場となると一種の儀礼。「義理でももらえてうれしい」といった肯定派の人もいれば、「面倒なので」と気乗りしないタイプもいる。上司や取引先の年配男性には、チョコにこだわらず趣味のワインや本などを渡すのも好印象となり、ビジネスチャンスになる可能性もありそうだ。バレンタイン&ホワイトデーは本命の恋人の日のはずだが、集団意識を大切にしている日本人はピライペトに自分が好きな人(本命の人)にプレゼントを贈る一方で、公開に周りの人にプレゼントを上げる。義理チョコをもらって、恐縮を感じてお返しを送る人もたくさんいる。台湾社会には義理チョコを送る慣例がないけれども、友人や親戚が結婚する際にお祝儀袋を贈るとか、赤ちゃんが1月歳になったら、「満月」のケーキ、赤い卵を贈るとかすることになっている。「No man is an island」ということわざがある。地域文化もさまざまがあれば、決まりや義理もさまざまがある。自分たちの社会に受け入れられるように、その決まりや義理を身につけて、守っている。「もう疲れた!」、「面倒くさいなぁ」という嘆きもある。世間知らずの人が周りの人に嫌われる人といっても、ただ人間関係の義理を知らない人かもしれないのだ。物事の正しい筋道というのは必ずしも正しいわけではない。ただその社会にふさわしいだけだ。わたしにとって、義理ということは地域社会を作るのに欠かせないものだが、いつも世間の義理にこだわったりしたら、大変だと思う。義理社会は複雑なものだ。
2006.12.23
-
義理チョコ
昨日、日本語の先生が新しい日本語の単語を教えてくれた。その中に、もっとも面白いのは、義理チョコなのだ。初めて聞いたので、とりあえず、義理とはどんな意味なのか、ちょっとインターネットの辞書を引いた。1 物事の正しい筋道。また、人として守るべき正しい道。道理。すじ。たとえば、「―を通す」「―にはずれた行為」。2 社会生活を営む上で、立場上、また道義として、他人に対して務めたり報いたりしなければならないこと。道義。たとえば、「―が悪い」「君に礼を言われる―はない」「―をわきまえる」3 つきあい上しかたなしにする行為。たとえば、「―で参加する」4 血族でない者が結ぶ血族と同じ関係。血のつながらない親族関係。たとえば、「―の母」5 わけ。意味。日本人は、バレンタイン&ホワイトデーに義理でチョコレートを贈ったり、もらったりする習慣があるようだ。学校、職場の恒例イベントと化したものなので、日本社会ならではのものだ。学生の場合、義理チョコというよりは「友チョコ」となっている。一方、職場となると一種の儀礼。「義理でももらえてうれしい」といった肯定派の人もいれば、「面倒なので」と気乗りしないタイプもいる。上司や取引先の年配男性には、チョコにこだわらず趣味のワインや本などを渡すのも好印象となり、ビジネスチャンスになる可能性もありそうだ。バレンタイン&ホワイトデーは本命の恋人の日のはずだが、集団意識を大切にしている日本人はピライペトに自分が好きな人(本命の人)にプレゼントを贈る一方で、公開に周りの人にプレゼントを上げる。義理チョコをもらって、恐縮を感じてお返しを送る人もたくさんいる。台湾社会には義理チョコを送る慣例がないけれども、友人や親戚が結婚する際にお祝儀袋を贈るとか、赤ちゃんが1月歳になったら、「満月」のケーキ、赤い卵を贈るとかすることになっている。「No man is an island」ということわざがある。地域文化もさまざまがあれば、決まりや義理もさまざまがある。自分たちの社会に受け入れられるように、その決まりや義理を身につけて、守っている。「もう疲れた!」、「面倒くさいなぁ」という嘆きもある。世間知らずの人が周りの人に嫌われる人といっても、ただ人間関係の義理を知らない人かもしれないのだ。物事の正しい筋道というのは必ずしも正しいわけではない。ただその社会にふさわしいだけだ。わたしにとって、義理ということは地域社会を作るのに欠かせないものだが、いつも世間の義理にこだわったりしたら、大変だと思う。義理社会は複雑なものだ。
2006.12.22
-
個人と集団につて
先日、言語交換の相手に日本の地域社会という概念を紹介してもらった際に、町内会と村八分についても聞いた。特に、村八分のことを始めて聞いたとき、好奇心が強いわたしは宝くじが当たったようにうれしかった。大学院のゼミで台湾人の先生とクラスメートに紹介した。さらに詳しい内容を日本人の友人に聞いた方がいいと思った。いったい村八分とは、どんな意味なのか、わたしはWikipediaで調べてみたが、日本社会ならではのものなので、長く日本で生活し続けなくては、やはり理解できないと思ぅた。Wikipediaによると、村八分ということは、日本の村落で行われた村のおきてに従わない者に対し、村民全体が申し合わせて、その家と絶交すること。地域の生活における十の共同行為のうち、葬式の世話と火事の場合(二分)以外の一切の交流を絶つこと。また、「八分」は「はじく」(つまはじきにする)の訛ったものであるとの説もある。消極的制裁行為とはいえ、昔の日本社会では強い影響を及ぼしたということだ。村八分を課される人は事実上生活が出来なくなって、地域社会から外されてしまったと言える。地域社会に入っていないと、世間にわすれられたと感じ、生きがいを失ってしまう人もいた。昔の日本社会の現象だが、今も残っているようだ。仲間はずれにするような感じだ。現代社会の中に、人と人の距離は近くなったら、かえって疎遠感が深くなった。村八分は珍しくなっているようだが、現在でも田舎で、特に近所との連帯が必要とされる地域(農村、漁村など)では依然存在する現象で、生活不能な状態に追い込まれることもあると言われている。ちなみに、いわゆる若者言葉で一人を仲間はずれにすることを「ハブ」「ハブる」というが、これは村八分が語源といわれている。集団意識を強く持っている日本人は自分自身をグループの中に位置できるように、生きているうちにいろいろな「会」や「組織」に入ったり、作ったりしているようだ。例えば、町内会、自治会、連合会、懇親会、OB会、同好会、同窓会、日本人の会、親睦会、飲み会、二次会等、まるで、「会」の網に縛られながら、生きているようだ。その中には、気の合う仲間や同好と一緒に楽しめる会もあるが、嫌な会もある。嫌だが、付き合いのために、参加しなければいけないときもある。人間関係を和やかにするように、いろいろな予定に参加した結果はいろいろな雑事に追われることになるのかもしれない。例えば、町内会がもう廃止されているが、近隣住民のコミュニティー組織(地縁団体)として町内会の名称が使用されて、まだ残っている。加入しなければならないこともないが、実は参加しないわけにはいかないという話もある。加入を強制されたといったトラブルが発生する場合もある。現在、単身者、共働きが多いために、未加入の人も多くなる。家族で居住している場合、加入を勧誘すると応じる場合が多いが、単身者等の場合、町内会に勧誘しても加入を断る人が少なくないということだ。また、神社・仏閣の管理を行っている町会では、宗教上の理由により入会を拒否したり裁判を起こされるケースも発生している。もちろん、人間は地域社会との連帯がないと、生きられないには違いないが、いつも「グループ」のことを第一にしている人はちょっと可哀想ではないかと思う。退職した後、一時でもいいからちょっと今までの社会から解放されて、海外へのロングステイに行く日本人が増えて来たそうだ。もしかすると、我慢したまま集団社会の中にいさえすれば、自分の価値や生き甲斐を感じられるような生き方にもう疲れてしまったという退職者が多くなったのかもしれない。 現在の日本人は、個人意識が濃くなったのか集団意識が薄くなったのか私はよくわからないが、日本人の社会は複雑なものなのだろうと思う。
2006.12.18
-
師走の感想
今年も気がついたらクリスマスがもう直ぐやってきます。今年は、やはり、人生の転機を迎える年なんです。変わりがいっぱいでしたが、一応は順調でした。まず、五月に仕事をやめて、大学院に入って、地理学の研究を始めていた。さらに、夏休みに気の合う友人とオーストラリアを旅行して、楽しい思い出を作りました。九月に二軒目の家を買いました。自ら内装をデザイナーをして、居心地よい家を作りました。または、語学のパートナーを通じて、いろいろ勉強になりました。十二月にいとこの結婚披露宴をデザイナーをするだけでなく、会場の雰囲気を激高させるために、ブライズメイドとして舞台で歌ったり、ダンスをしたりしました。大変でしたが、皆の笑顔を見る瞬間、すべての疲れを忘れてしまいました。披露宴は無事に終わりました。大学院に入ってから、毎日研究のことに打ち込んでいますので、あまり暇がありません。日本語の勉強にはあまり心がけないんですから、下手になったことを気がしました。もともと練習しないといけないんですね。皆さんの一年はどうでしたか。うれしい思い出だけを心に抱いて、最高の笑顔で年越ししましょ!
2006.12.14
-
自分らしい色彩
自分らしい色彩マイホームを買ってから、とても気になっていたのは、デザインのことだ。デザイナーに頼まないで、今回は自分でデザインをして、内装業者に内装工事をしてもらった。デザインすることなんて、初めてだから、大丈夫かなぁ~てまったく自信がなかった。最初のチャレンジは壁だった。ペンキを塗るのか、壁紙を張るのか、どちらのほうがどのような部屋に似合うのかという問題だ。また、色の相性も視野に入れなければならないことだ。せっかくのマイホームだから、自分らしい色を大胆に使ってみよう!って思って、姉とわたしは変な色合い(いろあい)を決めた。リビングは抹茶のような緑で、天井はライム(lime)の薄い黄色。キチンは黄身のような色。また、開放感が広がるように、ひとつの部屋のリビングに向かう壁を取り除いて、細い木が格子に組まれていてそれに白いガラスを張ったもので、左右に引いて開けたり閉めたりできる引き戸を仕切りにした。この部屋の壁はオレンジにする。寝室のほうは、壁は明るいピンクの壁紙で、天井は紫のペンキだ。結果は親戚や友たちに「派手すぎじゃないか、やはり間違いないのは白!」と言われた。ペンキ業者も「けばけばしくすると、しつこく感じさせますよ。もう一度考えてください」と言っていた。「家を面白くできれば、いいじゃないか」とずっと思っていたわたしは、周りの人たちの意見を聞いた後、ちょっと不安になった。迷っていた。「白はきれいだけど、活気のある色をつけると、気持ちを生き生きとさせられるようになるじゃないか」と自分に言う。「部屋の色を変えると、そこに住んでいる人の様子や性格まですっかり変わってしまう」という話もある。台湾人の知人たちの家を欧米の友たちの家と比べると、面白い違いに気づいた。台湾人の知人たちのほとんどは薄い色を使い勝ちだが、外国人の友たちは、鮮やかな色づけが好きなようだ。ヨーロッパに住んでいた際に、常にヨーロッパ人の家や博物館を訪ねに行った。けばけばしい壁紙や鮮やかなペンキを使う人は少なくない。大胆だけど、和やかさや優しさを伝えるという印象も残っている。ヨーロッパ人はカラーにセンスがすばらしいなぁと感動させられたわたしは、「自分の家があったら、自分らしさを表現できる色をつけたい」と時々自分に言っていた。個性を大切にする雰囲気が溢れるフランスで暮らすうちに、芸術の鑑賞力も変わるようになる。さらに時々旅に出るから、知らず知らずのうちに、わたしはカラーセンスも変わるかも。何気なく色をつけると、何気なく自分らしさが描けるたどろうか。色彩そのものは人間に影響を与えるものだ。心地とか、情長とか、色によって、効果もそれぞれ。または、色彩も様々な感情が表現でき、物事を連想させることがあるという話もある。というわけで、色合いの選択を通して、人の人柄, 個性や本心が見抜けるかも。「きっと恐ろしい感じになるだろう」!と母に言われたのに、結果はやはり自分の望みどおりに、家を色づけた。やっと出来上がったね。胸がどきどきしていた。ドアを開けた瞬間に、びっくりした。鮮やかだけど、意外に柔かいバランスが作られた!一言でいうと、Sandyの味がいっぱい!Sandyの味とは?下記の色に対する一般的なイメージを参考すると、Sandyの味とはどんな味なのか分かるようになる。(笑)白 善(主にキリスト教圏)、雪、無、清潔、純粹、無罪 など 黒 悪(主にキリスト教圏)、死、男、武勇、汚濁、夜、有罪 など 褐(茶) 土、豊穣、糞 など 赤(赤) 血、生、火、力、女、情熱、危険、熱暑 など 橙 温暖、快活 など 黄 太陽、穀類、金、注意、臆病、色欲(中国) など 緑 植物、自然、安全、幼稚、嫉妬(アメリカ)など 青 水、冷静、知性、憂鬱、寒冷 など 紫 王位、高貴(中国)、貴重 など
2006.10.20
全274件 (274件中 1-50件目)
-
-

- 北海道の歩き方♪
- 「上川大雪酒造 緑丘蔵 蔵まつり」に…
- (2025-11-22 14:00:04)
-
-
-

- 海外旅行
- ●6th trip〜マレーシア・クアラルン…
- (2025-11-22 23:18:10)
-
-
-

- アメリカ ミシガン州の生活
- いよいよ日本へ本帰国
- (2025-01-11 13:13:28)
-