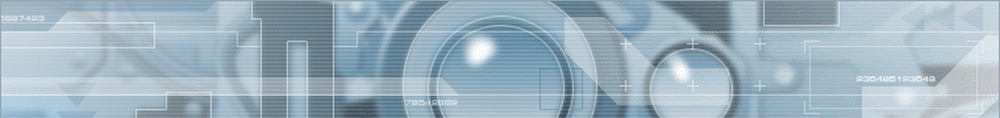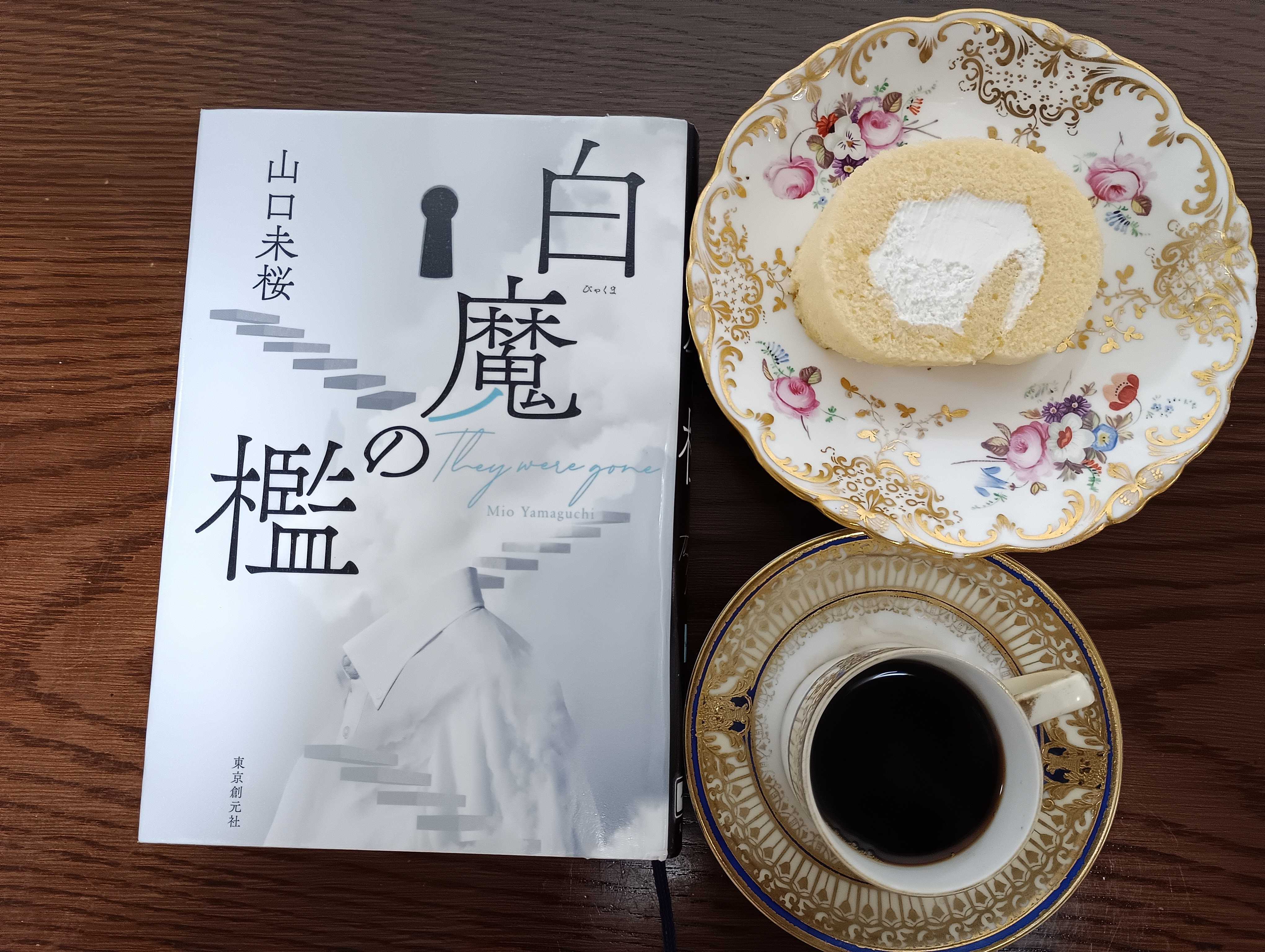2008年11月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
とても大変な目に遭った
今日家の前の自動販売機で某会社の商品である炭酸檸檬飲料水を買ったんだが、なんとホットで出てきたw通常、気体を液体に溶かす場合、その溶解度は水溶液の温度の低さと外圧に依存するので、炭酸飲料水をホットで飲むというのは、自殺行為である。ていうかフタを開ける時点でもすでに危険である。う~む、困ったorz結局、開けた。結果、 小爆発(゚Д゚|||)なぁ~んだ、期待してたのに損しちまったじゃないか!まったく、飲料水ホットで飲むのは不味かったし、腹が立つ。で、この事件とは全く関係の無い話だが、侍道3 悶絶!タイピング殺法というのをたまたま見つけたのでやってみた。フォトの女の子が可愛かった、ただそれだけだwタイピングして、プロポーズしたけど…。うん、まあ色々あった。詳しくはネタバレになるので言わないが、面白かったかな?最近この日記も更新が滞りがちだが、こんな調子で適当に更新はするのでよろしく☆
2008.11.30
コメント(4)
-
意外
意外にも知人の名前がWikipediaに載っていました。まさか、週1回会うあの知人が…。この間1対1で対談したあの知人が…。世間って案外狭いんだね。
2008.11.29
コメント(0)
-
解釈の仕方
多分高校生くらいのときにまず思うのが、1.微分係数は、その点での接線の傾きである。ということだろう。でも、これは微分の本質を捉えていない。むしろこう教えるべきだ。2.その曲線をルーペで拡大してみたとき、あたかも直線であるかのように見える。もともと微分とは局所的な概念であるのだから、狭い範囲を見るというニュアンスが出ているこの文面のほうが面白い。あるいは、3.曲線をその点でもっとも良く近似する線型近似を求める。という言い方もいい。で、その線形近似を式でかくと、f(a)+Df(a)(x-a)x-aをhと置いてみる。すると、f(a)+Df(a)・hつまりaから微小ベクトルhだけ離れた点でのfの値を、Df(a)という線型写像で近似している。これを微分の定義っぽくかくと、lim(h→0) |f(a+h)-f(a)-Df(a)・h|/|h|=0hを0に近づけたとき、分子、すなわち実際の値と線形近似による値の誤差が、hのノルムよりも早いスピードで0に収束することを意味している。ここまで書くと、かなり理解できた気になる。あと、基底の表現行列、変換行列に関する、素晴らしさもここに書きたいと思う、ていうか流布したい。ちなみにこれは俺の勝手な解釈なので一般的であるかどうかはわからない。基底の表現行列の定義をかくと、FをVからVへの線型変換とするとき、(F(x1),…F(xn))=(x1,…,xn)A なる行列Aを基底x1,…xnに関するFの表現行列という。ただしこの定義だけではありがたみがよく分からないと思う。実際俺もそうだった。表現行列の効能は、次の2つによって解釈されるべきである。1.Fという抽象的な変換を成分と行列の計算という、比較的解りやすい概念に落として考える。例えばxというVの元は、x=a1x1+…+anxnというx1からxnの線型結合で表されるわけだが、これをFで変換するというのは、Fを具体的に定めないとイメージが湧かないし、計算が大変である。だが、基底の表現行列Aがあるお陰で、Fによる行き先の成分は簡単に求めることができる。すなわち、Aにa1,…anを縦に並べたベクトルをかけたものがその成分である。実際、線型写像は基底の行き先を定めれば唯一つに定まってくれる。これは基底がVにおいてまさに"基底"としてはたらいている一つの例だ。基底はVを"ある意味"近似しているという表現もなかなか面白いのではないか。2.線型空間上の線型変換を、数空間における線型変換に落として考えている。一般に線型空間の元は数とは限らない。関数や数列が元となることもある。しかし、基底の存在によって、ある元x=a1x1+…+anxnはあたかもa1からanを縦に並べた数空間のベクトルであると同一視できる。数空間上の線型変換は行列を書けるという操作で得られるのだから、線型空間→数空間→線型空間、という同一視によって分かりやすくとらえることができる。続いて変換行列。一般に有限次元線型空間には基底が存在するが、これは普通一意的にはとれない。だから、A氏は(x1,…,xn)という基底をとるが、B氏は(y1,…,yn)という基底をとるかもしれない。つまり相対的なものである。いまA氏がある線型空間の元xを基底(x1,…,xn)を用いて、x=a1x1+…+anxnとかいたとする。あとでB氏は、同じく元xを基底(y1,…,yn)でかきたいと思った。このとき、またいちいち成分を計算するのは面倒である。できればA氏の用いた基底によって得られたxの成分を流用したいと考えるのが普通である。そこで変換行列Pを(y1,…,yn)=(x1,…,xn)P によって定める。すると、求めたい成分は、Pの逆行列をa1からanを縦に並べたベクトルを書けるだけで求まってしまう。これは嬉しい。よって、表現行列も変換行列も、作業を効率化する上で必要な概念であると俺は思う。
2008.11.22
コメント(3)
-

ついにやってしまった
とうとう「多様体の基礎」を買ってしまったw明日、テストなのに・・・。でも、この本の内容をマスターすれば、ついに距離が無い空間でも微分ができるようになるわけだ、多分。多様体強すぎです。
2008.11.19
コメント(0)
-
多様体
本屋に置かれている多様体の本を衝動買いしそうになること1週間。そろそろ始めようかとは思うんだが、さすがにテスト前に読むのはヤバいだろうなぁ。しかも3200円は結構な値段だ。多変数、線形、位相のレベルがある程度に達していないと読めないそうなので、もう少し位相の基本事項とコンパクト・連結性、あと多変数のほうでテンソル、微分形式をやってから入ろうと思う。少なくとも12月下旬には入れるようにしたい。多様体は位相空間において定義され、開集合とユークリッド空間の開集合を位相同型によって結び、局所的にユークリッド空間とみなせる。(局所座標)最終的に開集合を張り合わせて大域的な結果を生む。これをwikiで見たときの興奮が収まり切れなくて、数学に対するモチベーションが上がってきたのはよいことです。多様体始めると絶対ひきこもりそうだから、頑張って学校に行くようにしたいと思います。さて、最近、また色々なアニメに手を出している。今日の5の2とらドラ!かんなぎ今日の5の2は前に紹介したやつで、早い話が内三人は俺の嫁である。チカのツンデレが見所。とらドラ!は釘宮病患者推奨。かんなぎは、なんかこう、神秘的な感じがいい。でありながらかつ、萌え要素を取り込んでいるのは素晴らしい。みなさんも暇があったら見てください。私は暇が無くても見ますw
2008.11.17
コメント(0)
-
線形空間と再双対空間の同型性
最近情報をチェックしていなかったので、新鮮でないかもしれないが、みなみけの第三期の具体的な内容が明らかになったようだ。みなみけ おかえり製作はまたしてもアスリード。ただし、デザイン設定を見ると、二期で痛烈な批判を浴びたせいか、大分原作に近いものとなっている。といっても実際に動いているところを見ないと正確な判断はできないが、少なくとも二期に比べれば大分マシな気はする。やはり一期が神すぎたのか、千秋の目とホイップの表現が童夢製作の千秋に比べて劣って見える。ただ、原作にあわせればよいという訳でもなく、アニメはアニメらしく、躍動感、表情の連続的な変化を重視したほうが良いと思われる。話は変わるが、線形空間が有限次元の場合、再双対空間への標準同型が存在する。(すなわち線形空間によってのみ、同型が定まる)ただ、一般には同型ではなく、単射になる。ということは全射でない例がありそうだが、どうなんだろう。ヒルベルト空間から反例が挙がらないか。なんせ無限次元の場合を勉強していないのであまり思いつかない。余談だが、今日の昼に学食で食べたラーメンは、餅と、粘性を保存する同型であったと思われる。
2008.11.11
コメント(1)
全6件 (6件中 1-6件目)
1