2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2009年08月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
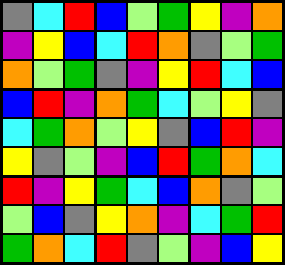
『カラープレイス』の解答
先日、「数独(ナンバープレイス)」の数字をカラー(色)に置き換えた「カラープレイス」の問題を掲載したが。その解答を掲載しておく。図を見てわかるように、全体として綺麗な模様になっているが、おそらく「数独」の解答パターンは、人に心地よいパターンとなっているのかも知れない。興味あるところだ。エッセイは、次のページでいろいろ掲載しています。遊邑エッセイ↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.31
コメント(0)
-

全国学力テスト、成果出た?/その2
(その1からの続き、引用記事は再掲)【文部科学省が27日に公表した全国学力テストで、3年連続で全教科、全国平均を下回った大阪府。教育改革を推し進めてきた府教育委員会は小学校について「全国平均に近づき、取り組んできたことが実を結び始めている」と評価。一方、中学校を「依然として全国との差は大きい」と認識し、原因の分析を急ぐ考えを示した。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/大阪日日新聞:2009年8月28日) 府教委は学校に責任を転嫁し、学校は教師に責任を転嫁し、そして最終的には、こどもたちにその責任を転嫁するのだろうか。府教委と同様の態度は、奇しくもかの知事の、今回の全国学力テストの結果をうけての談話に如実にもあらわれている。【知事は27日、滞在先のバンコクで「誰に責任があるのか総括する」と述べた。橋下知事は「自治体の長の責任なのか、市町村教委なのか、原因追究したい」と述べ、市町村長らも学力向上に責任を負うべきだと強調した。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/毎日新聞:2009年8月28日) まさに、序列(順位)に振りに振り回されている、知事と教委のお粗末な談話だ。少なくとも全国共通の傾向となっている、「活用力(応用力)」の低下や、経済格差による学力格差が、どのように改善されたのかを、自己反省を含めて報告する事こそ、真剣に府民に提示すべきだろう。そして、こんな低レベルの談話を知事や教育委員会が発表するような、全国学力テストは、もうお終いにすべきなのだ。それが、こどもたちへの思いやりのある、正しく確実な学力向上への第一歩となるだろう。エッセイは、次のページでいろいろ掲載しています。遊邑エッセイ↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.30
コメント(0)
-

全国学力テスト、成果出た?/その1
【文部科学省が27日に公表した全国学力テストで、3年連続で全教科、全国平均を下回った大阪府。教育改革を推し進めてきた府教育委員会は小学校について「全国平均に近づき、取り組んできたことが実を結び始めている」と評価。一方、中学校を「依然として全国との差は大きい」と認識し、原因の分析を急ぐ考えを示した。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/大阪日日新聞:2009年8月28日) こんな教育委員会に、こどもたちの教育を任せるのは、非常に先行きが心配となるだろう。全国学力テストの全国平均に近づいた事だけを根拠に、自らの取り組みを自賛するのは、教育者としては最低のレベルの認識だと言える。記事の引用部以外には、「正答率の全国比」についても指摘しているが、同じ事だ。 全国平均は、他の都道府県の取り組みが功を奏さなければ、大阪府が何もしなくても全国平均に近づく。また、他府県の取り組みの弱まり方が激しければ、大阪府の取り組みの効果が上がっていなくても、これまた全国平均に近付く。要するに、他府県の取り組みの詳細がわからなければ、大阪府の数値だけでは取り組みの効果(成果)を見極める事が不可能なのだ。こんな自明のイロハとも言える事が、ご理解できない府教委には、全国学力テスト結果を分析する能力や資格が無いのは明らかで、こどもたちをはじめとした府民にとっては、極めて憂うべき事となる。 さらに、同じ府教委の指導の下にある、小学校と中学校に差がある事を捉えて、府教委自らの取り組みの問題を分析もせず、記事の他のところにあるように、「小学校は確実に学校が動きだしたと感じているが、中学校は動いたと読み取ることができない」と、即断する姿勢では、大阪の教育は一向に改善されないだろう。(続き)エッセイは、次のページでいろいろ掲載しています。遊邑エッセイ↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.29
コメント(0)
-

『遊具』の特殊コーティング:ニュースに見るあそび
【高温で溶かした金属粒子を吹き付ける「溶射」の工事施工会社のプラズワイヤー(本社・福岡市)は、鳥栖市の若葉小学校にある遊具の補強工事を無償で行っている。(中略)同社はアルミニウムとマグネシウムの合金線を使ってプラズマ溶射し、金属皮膜を形成する工法を独自に開発。「特殊コーティングでさびない。遊具の耐用年数も3倍ほどのばせる」という。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/佐賀新聞:2009年8月25日) 鉄製遊具の耐用年数を3倍にのばせると言う事だが、これにより遊具事故が減少する事を期待したい。しかし、その一方で、遊具の材料や塗装の進歩が、遊具事故を必ずしも減らすとは言えない状況がある。昔に比べて、ステンレスやプラスティックなどの格段に進歩した材質、防錆加工や特殊塗装などの遊具の防護技術が進歩しているにも関らず、事故は減ってはいないだ。 それは、日常的な遊具の点検と、それにともなった適切な整備の、不十分さから起きる事故が増大してきているからだ。この人的原因を減らさない限り、遊具の耐用年数が3倍にのびたからと言って、事故は減らないだろう。耐用年数に過信しすぎると、日常の点検に緩みが起きかねない。 遊具の支柱部分などの耐用年数がのびても、ブランコの釣り金具のように、可動部分の磨耗は必ず起きる。その部分の点検と整備を怠れば、耐用年数内での遊具事故は起きる。ボルトなどの緩みや脱落を見逃しても遊具事故は起きる。肝心なのは、遊具であそぶこどもたちの顔を思い浮かべる、暖かい眼差しでの遊具点検が望まれるのだ。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.28
コメント(0)
-

寄せ木細工の『秘密箱』:ニュースに見るあそび
【寄せ木細工の幾何学模様が美しい木製小箱。手のひらに乗せた女性観光客の顔が、不思議そうな表情になった。箱の模様は切れ目がなく、開け方が皆目分からない。(中略)こうした木の仕掛けのからくり箱は「秘密箱」と言われ、明治時代から続く。観光地・箱根独自の木製品だ。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/東京新聞:2009年8月26日) 「数独」は数学的(論理的)に解けるが、どうしても論理的に解く事が不可能、もしくは極めて困難なパズルが、日本の伝統的工芸品とも言える寄せ木細工の「秘密箱」だ。私も、ごく簡単な小さな「秘密箱」を持っているが、10手数程度の仕掛けなのだが、およその開け方を知っていても開けるのに苦労する。もちろん、知らない人にはもっと難しい。 この「秘密箱」、論理的に解けないのは、からくりの仕掛けが、表からは完全に見えないからだ。仕掛けとその部分の動かし方が、全てわかれば論理的に解法が見つかるかもしれないが、見えない仕掛けを見つけ出す純粋な論理は無いに等しい。 「秘密箱」は、同じ立体的なパズルのルービックキューブが、完全に論理で解けるのとは、極めて対照的なパズルとなっている。日本の伝統技術の素晴らしい一面でもある。20手数以上の難解の「秘密箱」もあるが、それは万が一解答書を紛失してしまえば、二度と開けられない可能性もあるので、10手数以内がお手ごろで安全だ。箱根土産に一つくらいは買ってみてはいかがだろうか。 日本の伝統工芸によるパズルには、「秘密箱」の他には、「組木」(下図:商品リンク)が人気がある。この「組木」、考えれば古(いにしえ)の神社仏閣は、釘を一切使わずに建築されたものも多いので、まさに千年以上の歴史を背景として育ったパズルと言えよう。 「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.27
コメント(0)
-
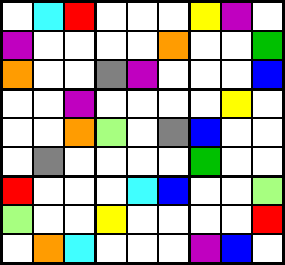
『数独』と『数学』/その2:ニュースに見るあそび
(その1からの続き、引用記事は再掲)【主人公の元恋人役を演じた貫地谷は妻夫木について「やさしいお兄さんという感じで、休み時間に(パズルの)数独を教えてもらいました」と共演の印象を明かし、タイトルにちなみ男の涙について聞かれると「たまらんですね」と即答。笑いを誘った。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/日テレNEWS24:2009年8月22日) 狭い意味では「数独」は、数学のパズルとは言えないし、もちろん「数独」を沢山しても、計算や数学の問題が得意になるわけではない。しかし、論理的な思考力を鍛える意味では、「数独」は数学に役立つとも言える。これを昨日のブログ記事に「広い意味では数学に役立つ」とした所以だ。 そして、この「数独」のような純粋の論理的パズルや、一定の論理に基づき解法が存在する「ルービックキューブ」、「ペントミノ」などの、一部の機械的パズルは、数学的方法で解けるということにもなる。特に「数独」は、ごく初歩的なプログラムによっても解法が見つかるので、その点で「数独」は簡単なパズルの範疇に入る。 しかし、「数独」はコツを知っていないと、初心者向けのものでも苦戦する方も多いし、難問になるとコツをしっていても解法に時間がかかるので、決して「数独」は侮(あなど)れない。このブログでも以前に紹介したが、数字を色に替えたパズルは、より難解なパズル(左図:問題編参照、解答編は後日、このブログに掲載。)になるのでお試しを。 このカラープレイスとでも定義できるパズル、数独のコツを知っておられる方には案外簡単に解けるが、そうで無い方には難しいパズルとなる。もちろん、カラー(色)をいちいち数字に置き換えてやれば、その限りではない。(元の数独をご存知で無い方のために、どんなパズルかを簡単に記しておきます。図の太線で囲まれた9(3×3)マス内、縦の一列内、横の一列内、このどれもが同じ色が重ならないように、残りの白マスを色で埋めると言う問題ですので、挑戦してみてください。)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.26
コメント(0)
-

『数独』と『数学』/その1:ニュースに見るあそび
【主人公の元恋人役を演じた貫地谷は妻夫木について「やさしいお兄さんという感じで、休み時間に(パズルの)数独を教えてもらいました」と共演の印象を明かし、タイトルにちなみ男の涙について聞かれると「たまらんですね」と即答。笑いを誘った。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/日テレNEWS24:2009年8月22日) 記事は、日韓合作映画「ノーボーイズ、ノークライ-泣かない男なんていない-」の紹介記事だが、俳優の妻夫木聡さんもやっているくらいに、パズル「数独」(「ナンバープレイス」)の愛好者は多い。最近では、高齢者の「脳トレ」としても人気がある。 ところで、この「数独」、数字を使っているので、あたかも数学に役立つと思われている方も多い。広い意味では、確かに数学に役立つのだが、狭い意味ではあまり役立たないのだ。何故なら、パズルに使うのは数字でなくても、カタカナでもアルファベットでも、あるいは色やマークでもいいのだ。基本的な1~9までの数字を使用する「数独」なら、9種類の違った文字やマークでも、同じ形式のパズルは成立する。(続く)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.25
コメント(0)
-
線路を敷く楽しさ:なつかしのあの風景
「鉄ちゃん」、最近では「鉄子」と呼ばれる、鉄道を趣味にする方々は多い。そして、男の子には、昔も今も鉄道おもちゃであそぶこどもたちも多い。その鉄道あそびにも色々あるが、線路を敷いて、その上を機関車や電車を走らせるあそびは、昔から多くのこどもたちが熱中してきた。そのまま、おとなになっても、その楽しみを発展させておられる方も少なくない。 私もこどもの頃、プラスティック(ベークライト)製のミニ電車(長さ2cm程度)を、紙の上に描いた線路の上を、走らせてよくあそんだものだ。もちろん、動力が付いていないので、手で持って電車を走らせるのだが、精巧な鉄道おもちゃを知っている、今のこどもたちから見れば、少しも面白く思わないかもしれない。 しかし、私は自分で描いた線路のレイアウト通りに、電車を走らせることを楽しんだ。正確には、電車を走らせるよりも、線路のレイアウトを設計する事がもっと楽しかったのだ。これは、鉄道模型ファンやプラレール好きのこどもたちも、多くが同様に楽しんでいる事だろう。そして、この線路を敷く楽しみは、パズルを解く楽しみと重なるのだ。 線路をどのように分岐させるか、そして分岐した線路をどのように合流させるのかなどなど、紙の上ならその紙の範囲内で、家に線路を敷くならその部屋の範囲で、思い描いたレイアウトを完成させる。紙に鉛筆で描くのなら自由自在だが、鉄道模型のレールパーツには制限があり、必ずしも上手く接続させられない時もある。だからこそ、完璧にピッタリと、線路が接続された時の、喜びは大きくなり、あるものはその魔力の虜になってしまうのだろう。 ただ、鉄道模型は基本セット程度でも高額となり、さらに取扱も難しく、こどもたちが楽しむには不向きかもしれない。その点プラレールは、こどもたちが「線路を敷く楽しさ」を味わう上ではお手軽だ。出来れば、狭い部屋でも大規模なレイアウトが組めるように、ミニ(マイクロ)のプラレールがあればいいと思っている。それは、おとなにも手軽な、卓上プラレールとなるかも知れない。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.24
コメント(0)
-

『トレカ』と『めんこ』:ニュースに見るあそび
【米サンディエゴで今月13~15日に開かれた「ポケモンワールドチャンピオンシップス2009」でのカードゲーム世界大会。日本からは、年齢別に分けられた3部門に計36人が出場し、1998年以降生まれのジュニア部門で東京都調布市の中村翼君(9)が、94~97年生まれのシニア部門で川崎市の板垣拓斗君(12)が、それぞれ優勝した。(中略)玩具業界誌「トイジャーナル」編集長の伊吹文昭さんは「かつてのメンコのように、戦う、集める、交換するという、男の子の遊びの要素がそろっている。人気は根強い」と解説する。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/大手小町:2009年8月22日) 記事のように、トレーディングカード(トレカ)を昔のメンコ(面子/めんこ)に例える意見は多い。そして、両者には記事の指摘通りに「戦う、集める、交換するという、男の子の遊びの要素」がそろってもいる。しかし、「トレカ」と「めんこ」は全く違ったあそびなのだ。先ず第一に、同じ「戦う」のでも、「トレカ」は頭を使い、「めんこ」は身体を使うという決定的な違いがある。 「めんこ」は身体を使うと書いたが、もちろん手・腕を主に使うのだが、足腰を使うのはもちろんのこと、しなやかな身体のねじりがなければ、「戦い」には勝てないのだ。さらに、目と手の連動が正確でなければならない。いわば、人が人たる所以の身体各部の使い方が必要となるのだ。 そして、「めんこ」が全く頭を使わないかと言うと、そうでもない。あまり気付かれない点だが、その場の「めんこ」の状況と相手の力量を、的確に判断する頭脳すら、「戦い」には重要になってくるのだ。この身体と頭を両方使う点では、少なくとも現在の「トレカ」のあそび方では難しい。 「トレカ」と「めんこ」の違いは、「集める」にもある。「トレカ」は基本的には、カードを買ったり・交換したりして集める。一方、「めんこ」は「トレカ」のように、買ったり・交換したりして集める事もあるが、基本的には「戦い」の戦利品を得て、「めんこ」を増やしていくのだ。腕前が上がれば、ほとんど新たな「めんこ」を買う必要無しに集める事が可能となる。 もちろん、「トレカ」でも「めんこ」と同じあそび方をしたり、「戦い」(ゲーム)での戦利品を承認すれば、いいのかも知れないが、それをするには一枚の「トレカ」の価格が高すぎるのだ。「めんこ」は、例え「戦い」に負けた結果、全てを無くしても、日々のお小遣い程度で十分に、次の「戦い」が出来うるくらいに安価なのだ。 ただ、「めんこ」が駄菓子屋さんの店頭から姿を消す直前は、「めんこ」は厚くて綺麗になり、その価格が上昇した。私は、この「めんこ」価格の高騰が、「めんこ」が廃れるひとつの理由とも、なったと考えている。昔のように、薄くて安い「めんこ」の再生を願ってはいるのだが・・・・・「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.23
コメント(0)
-

貼り紙だらけの住吉区複合庁舎:シリーズ自治体の愚策/29
迷う人が後を絶たない住吉区の新庁舎群については、先日もブログでその理由とともに紹介した。もう一つの理由は、施設名が見つけやすいところに表示されていないのだ。この図は、区民小ホールの入り口だが、貼り紙は目立つが肝心の「小ホール」の表示が見当たらない。事務所と間違う人があるのか、目立つ貼り紙の一つが次の図だ。 おそらくホールや集会室を借りにこられた方が、この入り口から入ろうとしたのだろうが、この入り口は小ホールが使用されている時しか出入りが出来ない。こんな所でも迷う人が、おられるのだろう。 それにしても、せっかくの美しい施設が台無しだ。このような目障りな貼り紙がやたらと多いのが、この住吉区の複合庁舎の特徴でもある。以下に、その典型例の画像を幾つか掲載していく。最初は、区民ホール棟の横の壁面だが、「これでもか!」と言わんばかりに多数の貼り紙が貼られている。3ヶ所にまとまって(図は2ヵ所)何枚かの貼り紙が等間隔で貼られているのが、せめてもの美的センスなのだろうか。 次は図書館棟の横にある貼り紙だが、1ヵ所に貼られている枚数が多すぎて、かえって注意喚起が目立たない。内容を見れば、区民のマナーの悪さが浮き彫りになる。同じ区民として恥ずかしい限りだが、マナーの悪い方々にとっては、おそらく貼り紙の効果は、あまり上がらないだろう。 これらの貼り紙の右端のものを次図に示すが、集会室などの場所案内なのだが、この貼り紙が貼られてかなり期間が経過しているが、今でも集会室の場所がわかり辛いのなら、そろそろ正規の案内板を設置すべきだろう。 最後に、住吉区の大ホールの入り口のそばにある柱に貼られている貼り紙を見ていただこう。一部愛犬家?のマナーの悪さと、区役所のセンスの悪さが、さらしものになっている。どちらも、住吉区民の皆さんには、ありがたくない話だ。せっかく市の予算を使って建てられた、素晴らしい新庁舎の価値が下がってしまう。早く何とかしていただきたいものだ。エッセイは、次のページでいろいろ掲載しています。遊邑エッセイ↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.22
コメント(0)
-

こどものあそびのための町づくり:ニュースに見るあそび
【小中学生が児童館に求めていること。「それは日常的に来やすく、居心地のいい場所。そして自分を受け止め、話を聞いてくれ、信頼できる『地域の大人』の存在です」と、ある職員は言う。 児童館に限らない。子どもが生き生き過ごせる場、遊びの環境を、地域にどうつくり出せるか。西公園(青葉区)でプレーパークを運営する市民団体が、「子どもの遊び環境学習会」を続けている。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/河北新報:2009年8月19日) この記事のように、こどもたちのあそびに関して、児童館やプレーパークの活動をはじめとして、様々な自治体や市民ボランティアなどの取り組みがある。その一方で、物騒な世相を反映してか、有料の屋内あそび場(商業施設)が急激に増えつつある。 こうした取り組みや営業は、それなりの存在意義があるだろう。しかし、これらの取り組み・営業が必要になったのも、元を正せば町、時には村までもが、こどもたちのあそびには不向きな方向に、発展したきた結果でもある。「外あそび」や「集団あそび」を、おとなが口を酸っぱくして説いても、肝心のそうしたあそびができる場所が、少なくなったのだ。 昔は、都市部でもトンボ・メダカ・トカゲなどの小動物が捕れたし、ジュズダマ・オナモミ・タンポポを摘んであそべた。日々のお小遣い程度で、その日十分に楽しめた駄菓子屋さんが、あちこちにあった。紙飛行機や凧で、安心してあそべる、広い空き地や原っぱもあった。ケンパ(石けり)やビー玉あそびが出来る、土の路地があった。 昔のあそびは豊かだったと懐かしむ、おとなの皆さん方も多いと思うが、そのあそびの豊かさは、こどもたちのあそびを無視同然にした町づくりが、奪ったと言えよう。だから、これからの町づくりは、こどもたちのあそびを大事にする町づくりであって欲しい。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.21
コメント(0)
-

何故、区役所で迷うのか?:シリーズ自治体の愚策/28
迷う人が続出する住吉区の複合庁舎群には、昨日に指摘したように、迷う理由として、入り口の設計段階からの変更が考えられるが、その事を少しだけ詳しく見ていく。 複合庁舎群には、「ガレリア」と称される雨避けの大きな屋根が設置されているのだ。そして、この「ガレリア」からは、ほぼ全ての庁舎に行く事が出来るようになっている。来庁者は「ガレリア」まで来れば、そこからは雨に濡れずに目的の庁舎に行けるし、庁舎間の移動も雨の心配が無い。そして、「ガレリア」の下を通れば、区役所だけでなく、その奥にある保健福祉センター・水道局サービスステーションへも行く事が可能なのだ。 要するに、「ガレリア」が複合庁舎群のセンターとして、本来のガレリアの役割を果たせるように設計されていたのだ。それが、通行止めや余計な入り口の設置をしたために、複合庁舎群が全体としてまとまりの無い、バラバラに近い庁舎群となってしまったと想像できる。 上の案内図を見れば、西エントランスと表記されている、区役所のメイン入り口が、デザイン上も変な位置に突出している感じに見て取れる。それに比べて、私が本来の区役所のメイン入り口と推定している入り口が、次の図だが見た目に開放的で、前日の図のような圧迫感も狭苦しさも無く、来庁者にとっては入りやすい入り口となる。(図はかなり以前のもので、現在は右手の扉は開放されている。これで、少しは庁舎間の移動がスムーズとなった。) 住吉区の新庁舎建設において、諸事情で工事途中で設計変更があったと聞き及ぶが、それがどの部分なのかは定かではないが、少なくとも完成後の庁舎群の運用は、当初の設計・デザイン通りでは無いことは、これまでこのブログで指摘してきたように、通行止め・閉鎖などにより、いたる所に「開かずの扉」「行けずの場所」が存在する事でも明らかだ。そして、この事が原因の一つとなって、未だに区役所で迷う方々が後を絶たないのだ。エッセイは、次のページでいろいろ掲載しています。遊邑エッセイ↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.20
コメント(0)
-

区民ホールのエントランスにて(続):シリーズ自治体の愚策/27
先日、区民ホールのエントランスでの、こどもたちのトレーディングカードゲームの様子を紹介したが。実は、その同じ日にこんな経験もしたのだ。それは、エントランスの椅子で休んでいると、新たに入ってこられた区民の方に、区役所の4階へ行く方法を尋ねられたのだが、どうも区役所棟と区民センター棟とを間違われていたのだ。 この区民ホールのあるのは区民センター棟で、区役所棟は向かいにあるが、区役所の入り口よりこの区民ホールの入り口の方が目立つのだろう。全く同じ経験は二度目で、同じ新複合庁舎の敷地内で、区役所自体を尋ねられた事は、これまでに二度や三度ではない。それほどまでに、新庁舎群はわかりづらいのだ。 簡単に新庁舎について説明をしておくと、この複合庁舎群には、大きく分けて三つの庁舎棟がある。区役所棟・区民ホール棟・図書館棟の三つだ。そして、さらに複雑なのは、区民センターとされているのは、大小二つの区民ホールと、集会室などを指し、後者の集会室などは図書館棟の二階にあって、同じ区民センターに属する施設が二箇所に別れているのだ。これでもかなり複雑だが、さらに区役所棟の奥には、保健福祉センターと水道局サービスステーションがあるといった有様だ。 この様な、各庁舎が別れている役所は珍しいことではないが、この住吉区の新庁舎のように、出来てから1年半以上も経過しても、未だに迷う人が相次いでいるのは、それなりに理由が考えられる。それは、それぞれの庁舎の入り口が別れているにも拘らず、それぞれが何処の入り口なのかがわかり辛くなっているのだ。 まずは、昨年一月の開庁当初の区役所のメイン?入り口を見ていただく。誰が、この状態を見て、大きな区役所のメインの入り口と理解できるだろうか。次図の状態のように改善されるまでは、この入り口の直ぐ前で、区役所を尋ねられた事もあり、区役所の入り口を探す来庁者が相次いだ。 この新しく設置された庁舎名の表示だが、建設後の対応処置なので、ご覧の通りやや文字が小さく、遠めには解かりづらい。しかも、二つ施設名の併記だから、「住吉区役所にある住吉区保健福祉センター」と勘違いされやすい。だから、「区役所の本庁舎」を探して、今だに迷う人がおられるのだろう。 そもそもこの入り口とされている場所そのものが、区庁舎のメイン入り口とは言い難い、大きな壁面に突如として付け足されたような、奇妙な構造になっているのだ。このブログでも以前に指摘した私の推測だが、本来の設計(デザイン)上は、別の場所がそもそものメイン入り口だったと思われるのだ。(続く)エッセイは、次のページでいろいろ掲載しています。遊邑エッセイ↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.19
コメント(0)
-

『ホオズキ笛』:ニュースに見るあそび
【通勤途中の花屋の店先に、ホオズキの鉢植えが並んだ。先のとがった赤い袋が五つ六つ。ガクが成長して、紙風船のように変形した姿だそうだ。子を守る親のように、赤い果実を優しく包み込む▼子どものころ、果実の中身をもみ出して口に含み、キュッキュッと音を鳴らして遊んだ。不器用なたちで、皮だけをきれいに残すことができず、兄や同級生にからかわれたのを思い出す▼既に11世紀の「栄花物語」にこの遊びの記述がある。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/河北新報:2009年8月13日) 全くと言っていいほど見かけなくなった、「ホオズキ笛」の記事だが、実は団塊の世代の私も、こどもの頃に本物の「ホオズキ笛」であそんだ記憶は無い。かろうじて、学童保育の指導員だった頃、先輩指導員から伝授してもらって、作って吹いた事はある。 上に「本物」と書いたのは、ゴム製の「ホオズキ笛」では、あそんだ事があるからだ。駄菓子屋さんで、当時1つ1円くらいだったと記憶しているが、ゴム風船を「ホオズキ笛」のように加工したものが売られていた。私は何とか吹いて音を鳴らす事が出来たが、結構これが難しいのだ。 さらに、本物のホオズキ(鬼灯)を使って笛を作るのは、おとなの私が挑戦してもかなりの難しさだった。あせると必ず失敗するので、かなり慎重に根気良く、中身をほじくり出さなくてはならない。作るのも吹くのも難しい「ホオズキ笛」、例え身近にホオズキがあっても、今の時代「ホオズキ笛」であそぶ子が、はたしているのだろうか。 さて、この「ホオズキ笛」もさることながら、身近な植物を使ってあそぶ事は、全くと言っていいほど、今のこどもたちの、少なくとも日々のあそびからは、姿を消してしまった。そうしたあそびに使える植物が、身近から消えた事にも原因があるが、例えあったとしても、あそぶことを期待できない理由もありそうだ・・・「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.18
コメント(0)
-

空々しい『政党のCM』
なお、この記事は都合上、削除(コメントも含む)する可能性があります。よりまして、コメントはご辞退申し上げます。 今、誰が決めたのか「政権」を争うと言われる二つの政党のCMが、連日のように垂れ流されている。その最も空々しいCMの一つが、「こどもの夢」「青年の希望」「高齢者の安心」をテーマにした政党CMだ。そうした「夢・希望・安心」が実現される事には、誰しもが賛成するだろう。 もし、これらの「夢・希望・安心」が奪われている(危うい)のが今の世の中だとすれば、では一体、そうした世の中にしてしまった政権を、担っていた政党はどこなのだろうか。もちろん、そうした世の中がたった一期の政権で出来上がったわけではない。 歴代の政権が主権者を蔑ろにしてきた結果、「夢・希望・安心」が脆くも崩れ去ってしまったのだ。そうした歴代の政権に、与党として関った政党や議員は、国民の「夢・希望・安心」をぶち壊した反省の弁から始めるのが、主権者への正しい政党CMのあり方だろう。 最も多く政党助成金を国民から受け取る二大政党が、連日テレビジャック同然に政党CMを垂れ流す。時には、少数意見が正しい事が有り得るのは、戦前・戦中の日本の政治が証明している。そんな時代において、少数意見が多数意見に転化し得なかったのは、マスコミが時の政権にジャックされたことにも大きな原因がある。 今の、金を使った(その金は、後で必ず何らかの手段をもって回収されるのだが)CMの氾濫は、ある意味では少数意見が多数意見に転化し難い条件をつくり出している。多数決は、少数意見も十分に国民が知り得る条件があってはじめて、その民主主義的特質を発揮する。 莫大な額の政党助成金よりも、政見放送にもっと予算をつける事こそ、選挙の民主主義や、政党政治を、豊かなものにする本道となるだろう。もちろん、巨大政党・金持ち政党がCM枠を牛耳ることの無いように、政党CMも禁止にすべきだろう。放送は公営・民間を問わず本来、政治的に中立でなければならないのだから。エッセイは、次のページでいろいろ掲載しています。遊邑エッセイ↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.17
コメント(0)
-

区民ホールのエントランスにて:今時のあそび場
所用で近くの区民ホールに行った。そこで出くわしたのが次の画像のこどもたちだ。10時少し回った頃に入ってきたこどもたちは、直ぐに空いていたテーブルに陣取り、それぞれ自分のトレーディングカード(トレカ)を取り出しゲームを始めたのだ。こどもたちがトレカゲームであそぶ光景は珍しくも無いが、「何故、こんな場所で!」と思うのがこの画像だ(画像は処理をしております)。 考えれば、この区民ホールのエントランスは、一日中冷房がきいており、テーブルに椅子まである。しばしカードゲームをするには最も適した?場所だと言える。もちろん、区民ホールと言う場所柄、いつもこの場所が確保できるとは限らないが、このこどもたちの慣れた振る舞いは、おそらく常連なのだろう。 私が所用を済ませて帰るまでにおよそ2時間ぐらい経ったが、まだ熱心にあそんでいた。今時のこどもたちはマイボトルに飲み物まで持参してきており、用意周到だ。つくづく感心する一方で、夏休みでも暑さに負けず外で、あそび回った世代のものとしては、やはり違和感がある。 ところで、あそんでいるトレカを詳細に見ると、1枚1枚のカードが保護のための専用のプラパックに入れられているのだ。確かに、あそんでいる間に傷や汚れが着き、レア物のカードの価値?も下がるので、そうしたパックも必要なのだろう。 カード1枚でも数十円もする、レアカードはさらに高くなるようだ。その他、専用ケースなどの付属グッズを揃えると、同じ紙物玩具である昔の面子(めんこ)と比べると、その値段は雲泥の差となる。さらに、次々と新しいカードが発売され、へたをすればトレカゲームで楽しむよりも、レアカードや新種カードだけに気が向いてしまう恐れもある。まだ、画像のこどもたちのように、熱心にバトルを楽しむのは、まだマシな方と考えなければならないのかも知れない。エッセイは、次のページでいろいろ掲載しています。遊邑エッセイ↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.16
コメント(0)
-

『あそびと会話』あそびと会話/その2:ニュースに見るあそび
(その1からの続き、引用記事は再掲)【クラスで、友達と話し合って物事を決める場の「学級会」。学校現場でいま、この学級会がコミュニケーション力を高める時間として注目を集めている。自分の感情や意見を超えて他の意見と折り合う経験を積み重ねることが、国語などの教科の理解やいじめ防止につながるという。(中略)なぜ、学級会がこれほど注目を集めるのか。同小で特別活動のあり方を研究してきた松川浩之教諭(39)は「塾や習い事で、集団で遊ぶ機会が減り、子供同士で話し合ったり、物事を決めたりする経験に乏しくなっている」とその背景を指摘。「同年代より大人と話す方が得意な子供が増えている」という。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/北海道新聞:2009年8月12日) 引用記事後半にある教諭の言葉、「同年代より大人と話す方が得意な子供が増えている」は、青年のタメ口を考慮して考えれば、若干ではるが、正確さに欠ける指摘だと思われるのだ。異年齢・同年齢を問わず、こども同士での会話の機会が減り、相対的におとなとの会話の比率が増えたように見えるだけなのだ。 さらに危惧するのは、テレビ・ゲーム機・パソコン(インターネット)・携帯などにドップリと浸かり、その結果こども同士の会話だけでなく、おとなも含めた人との会話全般が減ってきてはいないだろうか、と言うことだ。こうなれば、「コミュニケーション力」を、実践的に身につける機会さえ貧弱なものにする。こうしたこともあって、記事のような「学級会」での「コミュニケーション力を高める」取り組みとなるのだろう。 しかし、この「学級会」での取り組みで、気をつけなければならないのは、「学級会」はあくまでも教師などが見守っている(時には、監視している)状況下での「話し合い」なのだ。こうした場合、辛らつな言葉遣いや、相手を侮辱する言葉などは、抑制される傾向にある。下手すれば、「みんな良い子の?」の「話し合い」となりかねない。 こどもたちの会話は、おとなが心配するように、相手に容赦をしない言葉が飛び交う事は、ごく普通に見られる。また、一般社会でも一部のおとなたちは、往々にして相手を思いやらない言葉を投げかける。こどもたちが逞しい「コミュニケーション力」を身につけるには、こうした厳しくも冷たくもある言葉をも、経験する事も一定程度必要となる。 こどもたちの関係は、容赦しない関係でもあるので、そうした関係の中から生まれた、慰め・励ましなどの思いやりのある言葉は本物となり、その言葉を受け取るこどもたちも、大きな感激をもって心に留めおくだろう。ここに、作られた「話し合い」には稀な、心温まる「コミュニケーション力」を育む土壌があるのだ。 「学級会」での「話し合い」も大切だが、こどもたちが自然に自らの力だけで、「コミュニケーション力」を育むには、「集団で遊ぶ機会」を増やすことが大切だ。教師の皆さんは、こどもたちの保護者の皆さんと一緒になって、そのための取り組みに、もっと力を入れていただきたいものだ。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.15
コメント(0)
-

『あそびと会話』あそびと会話/その1:ニュースに見るあそび
【クラスで、友達と話し合って物事を決める場の「学級会」。学校現場でいま、この学級会がコミュニケーション力を高める時間として注目を集めている。自分の感情や意見を超えて他の意見と折り合う経験を積み重ねることが、国語などの教科の理解やいじめ防止につながるという。(中略)なぜ、学級会がこれほど注目を集めるのか。同小で特別活動のあり方を研究してきた松川浩之教諭(39)は「塾や習い事で、集団で遊ぶ機会が減り、子供同士で話し合ったり、物事を決めたりする経験に乏しくなっている」とその背景を指摘。「同年代より大人と話す方が得意な子供が増えている」という。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/北海道新聞:2009年8月12日) 最近、気になっている事がある。おとなのような(おとなでも出来そうも無いくらいに優秀な)言葉遣いのこどもたちが増えていると思えるのだ。中でも、「さんまのスーパーからくりTV」に出てくるこどもたちは、大人顔負けの丁寧な言葉遣いをする子が多い。これも、上記引用記事にある「同年代より大人と話す方が得意な子供が増えている」ことのあらわれなのだろうか。 また、反対に職場の上司やかなり年上の方に対して、タメ口(ぐち)を平気で使う青年たちが増えている。これは、どうも同年代の仲間内だけの人間関係だけで、育ってきたことによるのだろうか。実は、これもこども同士で話す事の経験が、歪(いびつ)になっているからと思われる。異年齢のこどもたちと、話す機会の極端な減少が見られるからだ。 こども同士でも年齢が違えば、同年齢のような話し方は許されない。おとなの上下関係のように、敬語や謙譲語が飛び交うわけではないが、同年齢のこどもたちと、年上のこどもたちとでは、話し方が微妙に違っていた。もちろん、反対に年上から話しかけられる、言葉も違っていたのは言うまでも無い。 この異年齢のこどもたち同士の関係は、特に集団あそびのなかで最も密となる。勝ち負けのあるチーム対戦型のあそびでは、年上のこどもから、過激な言葉を浴びせられる事もあるが、その反対に年長のこどもから、思いやりのある慰めの言葉もある。今のこどもたちの言葉遣いの変化は、こうしたあそびにおける、生きた会話の減少が大きく影を落としていたのだ。(続く)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.14
コメント(0)
-

こどものあそびとおとな/その2:ニュースに見るあそび
こどもたちのあそびへの、首を傾げたくなる、おとなの関わり方の例としての、二つ目の記事を次に掲げる。「泥団子?づくり」の記事だ。【「光る泥の団子づくり」が、夏休みの子どもたちの人気を集めた。 団子作りは、摩擦で光るしっくいの性質と町伝統の左官の技術を遊びに応用。土とわらと水で作った泥団子に、アクリル絵の具と石灰クリームを混ぜた赤や青など5色の塗料をフィルムケースの口で3回塗り、瓶の口で磨いた。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/朝日新聞:2009年8月11日) この記事を見れば「泥団子」に「?」を付記した意味を理解していただけるだろう。この取り組みを計画し、こどもたちを楽しませようとされた皆さん方のご努力は、たいへん尊いもので頭が下がる。しかし、これを「光る泥の団子づくり」と銘打つのは、一抹の疑問が残る。「光る泥団子」の普及に真剣にご努力されておられる「日本泥だんご科学協会」の皆さん方は、きっと不快に思われるだろう。 また、日本古来の土壁の材料である「土とわらと水」を、泥扱いするのも感心できない。「アクリル絵の具と石灰クリーム」まで使用するとなると、「団子づくり」と言うよりも綺麗な球体づくりだ。本物の光る泥団子を作るには、かなりの工夫と努力が必要だ。それが、簡単に作れるようでは、その醍醐味の大部分を台無しにしてしまう。 例え本物の「光る泥団子」であっても、おとなたちがその方法を、事細かくそして丁寧に教えるよりも、おとなが作った光り輝く泥団子を見せてあげるだけでいい。そして、「君たちも努力すれば必ずできるよ!」と一言付け加えれば、多くのこどもたちは、光る泥団子づくりに挑戦するだろう。 もちろん、マニュアルが無い分、失敗も多く、時には途中で挫折することもあるだろう。それでいいのではないだろうか。世の中は決して甘くはないのだから。泥団子作りでの経験は、きっとこどもたちの人生の中で生きてくるだろう。あるいは、素晴らしい新種の泥団子を発明するかもしれない。もし、自分の力だけで光る泥団子を作った時には、それこそ誰にも負けないくらいの大きな感激も作れるのだ。 なお、知人の経験で言えば、例え本などで光る泥団子づくりの方法やコツを見たとしても、かなりの苦労が必要だそうだ。これと、誰でも作れる「光る泥団子?」とは大きな違いがあるのは、誰でも理解できる。こどものあそびに、おとなが口を出したり、手を貸したりするのは、せめてこれくらいに止めるのが、こどもたちを本当に楽しませることとなるだろう。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.13
コメント(0)
-

こどものあそびとおとな/その1:ニュースに見るあそび
私はこのブログでも、こどものあそびへのおとなの適切な関わり方について私見を紹介してきたが。おとなのこどものあそびへの好ましくない関わり方見本が、ネットニュース検索で二つヒットした。それについて書いていく。まず、一つ目は次の記事だ。【4歳から遊べる「●●●●ゲームブック」(●●●●)は、小遣いをやりくりしながら買い物を楽しむ「おこづかいゲーム」がセットになっている。ゲームの基本はすごろくと同じ。サイコロを振って出た目の数だけ駒を進め、止まったマスに書いてあるカードをめくる。 カードは3種類。「●●●●カード」をめくれば、そこに描かれている文房具や日用品などを買わなければならない。一方、「●●●●カード」は、おもちゃや菓子など必ずしも必要でないものが描いてあり、限られた小遣いのなかで買うかどうかを自分で判断する。遊びながら、必要なものと欲しいものとの違いや、お金の使い方が自然と身につくという。(中略)「おこづかいゲーム」の考案者で、子どもの金銭教育に取り組む「●●●●」代表理事の●●●●さんは、「お金についての正しい知識は子どもの頃から身につけることが重要。ゲームをきっかけにお金への興味を持ってほしい」と話す。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/大手小町:2009年8月11日、注:●●●●にはそれぞれ違った製品名・会社名などの固有名詞が入る。) このゲームで「お金についての正しい知識」が身につくと、ゲーム考案者は本気にお考えなのだろうか。このゲームの最大の問題点は、「お金」の一側面、それも極めて偏った面しか取り上げておらず、「お金についての正しい知識」を育めるようにはなっていないと思われるのだ。 似たような事は、証券会社などがこどもたちに株取引を疑似体験させるような活動にも見られるが、これらは「お金」の価値を商品(サービス提供などの無形の商品や金融商品などを含む)との交換のみに偏って捉える危険性が高い。「お金」の価値のもう一つの側面である、労働により生み出される事への理解が無いと、「お金についての正しい知識」は極めて歪(いびつ)な知識になってしまうだろう。 この労働によるお金の価値は、額に汗して一所懸命に働いてみて初めて、正確につかめる。こどもたちは、せいぜい親や保護者たちが自分たちのために働く姿を、見聞きして間接的に、労働が生み出すお金の価値を、身につけるしかない。 そして、何よりもこうしたゲームに頼らずとも、このゲーム程度の事は、実際の生活のなかで十分に出来る事だ。自分で計算できる金額で、自分が貰える限度内の金額で、自分のお小遣いを自分の力で、実際にやりくりする事こそ、こどもたちの素晴らしい「金銭教育」となる。 その最も典型的な例が、昔の駄菓子屋さんだ。駄菓子屋さんには、消費税も無く、日々のお小遣いで、何点かの駄菓子や駄玩具を買えたので、まさに駄菓子屋さんは、「金銭教育」そして生きた「算数」を学べる場でもあった。こどもたちが「お金についての正しい知識」を身に付けるには、昔のような駄菓子屋さんを私はお勧めする。(続く)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.12
コメント(0)
-

『生物の多様性』:ニュースに見るあそび
【ある識者によると生物多様性を語るうえで最も適した生き物はトンボ。幼虫は水中、成虫になれば空中で暮らし、水陸に豊かな環境を要するからだ。幼き日の昆虫採集でトンボに魅せられ70年近い日本蜻蛉(せいれい)学会員の高崎保郎さん(75)=名古屋市名東区=の案内により今月5日、愛・地球博記念公園(愛知県長久手町)でトンボの“多様ぶり”を考察した。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/中日新聞:2009年8月10日) 記事の「愛・地球博記念公園」には、「44種類のトンボ」が確認されているそうだが、うらやましい生物の多様性だ。ちなみに、我が町(大阪市住吉区)では、赤トンボだけしかお目にかかっていない。近くの大和川の土手に出ても、バッタさえ見つけるのが難しい。公園にいるセミはクマゼミのみ、飛んでくる蝶は多くて2・3種類。こんな有様では、多様性の足元にも及ばない。 考えれば、同じ大阪市でもその昔、私がこどもだった頃(1950年代)の西淀川区では、トンボ(糸トンボを除く)でも数種類は確実にいた。バッタ・蝶も同様だ。セミは少なくてアブラゼミ・クマゼミ・ニイニイゼミくらいだった。公害で有名だった西淀川区ですら、昆虫だけとっても、これだけの多様性をもっていた。さらに、今の住吉区で全くと言っていいほどお目にかかれない、ゲンゴロウ・ミズカマキリ・ミズスマシなどの水生昆虫もいたのだ。 今の大阪市(住吉区)から昆虫の多様性が奪われたのは、こどもたちが昆虫たちを捕り尽くした結果ではない。生物の多様性を無視した都市開発を、進めたおとなたちにその責任がある。そして、再び大阪市の全ての地域に、生物の多様性を取り戻す事が、できるのもおとなたちなのだ。 カードやゲーム機の中で、昆虫を集めるよりも、自分たちの住んでいる町で、覚えきらないくらいに種類豊かな、昆虫たちを、汗水を流しながら追いかけて、やっとの思いでお目当ての虫たちを捕る事の方が、ずっと楽しいに違いが無い。生物の多様性は、こどもたちのあそびをも変え得る条件を備えているのだ。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.11
コメント(0)
-

『作る楽しさ』:ニュースに見るあそび
【電器街には、工作の部品を探しに来る人たちが大勢いた。ラジコンカーや真空管ラジオがはやれば、子供が何時間も自転車をこいで部品を買いに来た。 しかし、安価な電気製品やおもちゃが出回るにつれて工作熱は冷め、1990年代に150以上あった電器関係の店は、不況などもあって70店ほどに。子供の姿もない。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/読売新聞:2009年8月8日) 記事は、大阪市の「秋葉原」にあたる日本橋電気屋街の話だ。秋葉原もそうであるように、日本橋も大きく様変わりした。その一つが電気部品を扱う店が激減した事だ。「工作熱」に象徴される「作る楽しさ」が、人々から疎遠となりつつあるようだ。昔はどんな小さな町にもあった模型店やプラモデル店も同じだ。 この様な、工作や模型作りなどの、専用の部品や材料を購入して「作る楽しさ」の減少もさることながら、日常身の周りの、ありあわせの材料を使い「作る楽しさ」を満喫するあそびも少なくなっている。最もありふれた折り紙飛行機でさえ、知らないこどもたちも増えてきている。 昔に比べて、ダンボール・発泡スチロール・ペットボトル・紙パックなど、簡単に手に入る「作る楽しさ」の材料は多彩・豊富になってきているにも拘らず、それらを使ってあそぶ事は、イベントやこども団体の行事などで、時折「作る楽しさ」に接する機会は増えても、日常のあそびからは、どんどん「作る楽しさ」が急速に減りつつある。これも、今のこどもたちの悲しいあそびの一つの現状だ。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.10
コメント(0)
-

『遅寝、早起き』/その2:ニュースに見るあそび
(その1からの続き、引用記事は再掲)【起床、就寝時間は、「午前8時前に起床」が93・5%で第1回より15%増え、「午後9時前に就寝」は41・7%で23・8%減った。同センターは「夜型化と、睡眠時間の短縮傾向が表れている」と分析する。 食習慣については、「朝食を毎日食べる」が90・1%で4・3%の微増だった。 1日の平均的な屋外での遊び時間は、1時間未満が全体の6割近くを占めた。1時間以上は35・9%で、第1回より1割以上減った。外遊びをしない理由は「通園や習い事で時間がない」が370人でトップで、「安全な遊び場所がない」(192人)「遊び相手がいない」(172人)が続いた。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/静岡新聞:2009年8月5日) この記事で、もっと驚いた点がある。それは、「外遊び」の少なさもさることながら、その理由に挙げられている「通園や習い事で時間がない」だ。通園先が幼稚園や保育園なら、保育として「外遊び」をしているわけで、その分の「外遊び」時間が全体の「外遊び」時間に含まれていれば問題があるが、そうでないなら心配は少ない。ただ、3歳という低年齢で、「習い事」により「外遊び」が難しくなるほど忙しいのは極めて問題が大きい。 こどもたちは身体が疲れれば、放っておいても直ぐに眠るのが普通の姿で、3歳なら当然寝入るのもかなり早いはずだ。それが、夜9時を過ぎても寝入らないのは、やはり昼間の疲れが少なすぎるからだ。「外遊び」の少なさが、こどもたちの睡眠に大きな影響を与えているのだろう。これは、調査結果にあるように、朝の起床時間が早くなっても、夜の就寝時間が早くならない理由なのかも知れない。 文部科学省は、全国協議会まで設立して、「早寝早起き朝ごはん」を呼びかけているが、3歳児でこの様な状況では、当然小学校からの取り組みでは遅すぎるだろう。厚生労働省や経済産業省なども含めた、政府全体で取り組む必要があるだろう。もちろん、そうした取り組みも、こどもたちの保護者の努力が無ければ、改善は難しいが、保護者たちをこうした状況に駆り立てている原因を取り除く、国や自治体の抜本的な取り組みが望まれる。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.09
コメント(0)
-

『遅寝、早起き』/その1:ニュースに見るあそび
【起床、就寝時間は、「午前8時前に起床」が93・5%で第1回より15%増え、「午後9時前に就寝」は41・7%で23・8%減った。同センターは「夜型化と、睡眠時間の短縮傾向が表れている」と分析する。 食習慣については、「朝食を毎日食べる」が90・1%で4・3%の微増だった。 1日の平均的な屋外での遊び時間は、1時間未満が全体の6割近くを占めた。1時間以上は35・9%で、第1回より1割以上減った。外遊びをしない理由は「通園や習い事で時間がない」が370人でトップで、「安全な遊び場所がない」(192人)「遊び相手がいない」(172人)が続いた。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/静岡新聞:2009年8月5日) 今のこどもたちの生活習慣の調査で、この数字にはあまり驚かない方も多いと思われる。しかし、引用部分はあえて調査対象となった年齢掲載部分ををカットしたが、実はこの調査は「3歳児健診の対象となった幼児の保護者」に対しての調査だ。あらためて今のこどもたちの憂うべき生活実態が明かになったと言える。 ところで、記事の見出しの中には「遅寝、早起き」とあったが、確かに午後9時以降に就寝が、6割近いので「遅寝」は理解できるが、「午前8時前に起床」でひとくくりでは大雑把過ぎるので「早起き」とは即断できないだろう。「午前7時前」「午前6時前」なども是非知りたいところだ。ともかく、「夜型化と、睡眠時間の短縮傾向が表れている」のは間違いが無い。 今のこどもたちの「夜型・睡眠不足」については、このブログで度々触れたきたが、3歳児ですでにこの有様なので、こどもたちの「夜型・睡眠不足」は、極めて深刻な状況になっていると言える。記事には、昼寝(午睡)については触れられていなかったが、こどもには大事な睡眠なので、知りたいところだ。(続く)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.08
コメント(0)
-

時を見るから風を見るへ!:シリーズ自治体の愚策/27
諸事情により完成当初から色々姿を変える?住吉区の新複合庁舎だが、その意味が全くわからない模様替えがある。まずは、その衣替えの前の姿を見せておく。少しわかり辛いが、ポール先端の丸い大きな時計に被い(カバー)がかけられているのだ。このような姿で長期間放置されていた。故障したが修理できなかった(しなかった)のだろうか。 実は、この時計も新庁舎が開庁された直後には無かったもので、その後数ヶ月ほど経ってから設置されたのだ。ともかく、必要性があったから設置されたのだろうが、故障して何ヶ月も放置するようでは、その当初の必要性も疑わしくなる。その疑いが決定的になったのが次の図だ。 何と、ポールの先端が変わっていたのだ。それも、今は珍しい風見鶏に変身していたのだ。時計はまだしも、この場所に風見鶏を設置する意味があるのだろうか。しかも、このポールは普通のポールではないのだ。以前あった時計のための電気配線がされているのだ。 どう見ても風見鶏は電気動力で動く仕組みにはなってはいないようだし、電気動力で動く風見鶏では意味をなさない。ただの、ポールだけではみっともないので、とりあえず風見鶏をわざわざ設置しているのだろうか。このように、行き当たりばったりの模様替えは、貴重な住吉区(大阪市)財政の無駄遣いとなる。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.07
コメント(0)
-

不親切な案内表示:シリーズ自治体の愚策/26
住吉区の新複合庁舎のデザインが、極めてお粗末なものである事は、これまでにも幾たびか紹介してきた。今日も、その一つを紹介しよう。複合庁舎には、貼り紙がやたらと目に付くが、大ホールと小ホールの間にあるトイレにこんな貼り紙を見つけた。真新しい施設だけに、手作りの貼り紙は違和感がある。 近寄ってみると、下図のような具合だ。実は、この貼り紙は親切な貼り紙なのだ。おそらく、この貼り紙が無かった時には、男女間違って入りかける来庁者が多かったのだろう。それにしても、何故そのような状況が起きたのだろうか。それは、考えるまでも無く、要するに男女別を案内する掲示・表示に問題があったからだ。 もう一度、最初の図を見ていただければわかるが、トイレへ行く通路には正面から見て、男女別の表示が見当たらないのだ。そして、その見当たらない案内表示は、こんな所にあったのだ。どなたが、デザインされたのかわからないが、人が移動する経路(動線)や視線の方向を考慮すれば、こんな見えにくいところに男女別表示をするわけがない。 ともかく、急ごしらえの貼り紙は、不親切な案内表示を補う意味では親切な貼り紙だが、それは新庁舎のお粗末なデザインを周知せしめる貼り紙となっている。この貼り紙はいずれ見やすい案内表示に付け替えられるだろうが、そのツケは結局区民が支払う事となる。ああ、勿体無い!「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.06
コメント(0)
-

意外なところで面子(めんこ)が!:ニュースに見るあそび
【ロッテ立花龍司ヘッドコンディショニングコーチ(45)が、野球選手の肩、ひじを強化するためのオリジナル「めんこ」を販売する。めんこ遊びが肩、ひじを強化できることに着目し、00年から練習に導入。(中略)商品化にあたり、大きさ、重さなど試作を重ねたという。2625円で4日に販売開始する。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/日刊スポーツ:2009年8月4日) 日本の伝統的なあそびが、最新のスポーツトレーニングに活用される、興味深い取り組みだ。考えれば、「めんこ」に限らず昔のあそびには、「鬼ごっこ」や「どろけい(探偵ごっこ)」などの集団あそびはもちろんの事、ビー玉・コマ回し・ゴムとび・馬とび・お手玉など、身体の全部や各部を使ったあそびが多い。 そして、そのどれもが全身と手足・指先などの各部分の動かし方に独自性があり、違ったあそびをする事により、多彩な運動能力を育んでくれていたのだ。特に大事な点は、ただ単に筋力を強化するだけでなく、力の入れ加減や、しなやかな身体と手足の動き、器用な指先の動きなどを、こどもたちが楽しく獲得していけた事だ。 ところで、記事のトレーニングに活用される「めんこ」のやり方は、地面や床の上にある「めんこ」を、他の「めんこ」を投げつけて裏返すと言うやり方だが、「めんこ」のあそび方には他にもあって、台の上から特定の「めんこ」だけを落とすあそび方は、多くの場合、力加減が勝負の決め手となり、この方が奥が深いあそび方だった。 トレーニング用に商品化されたものは、2625円もするので、野球選手や選手志望のこどもたちには、いいかも知れないが、一般のこどもたちにとっては、ごく普通の「めんこ」であそぶに越した事は無い。ただ、その普通の「めんこ」も、意外と手に入れ難くなってしまっている。本当に残念な事だ。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.05
コメント(0)
-

『健康遊具ブーム??』の一つの実態-その2:『公園の遊具』論/3
しかし、この健康遊具、製造元のサイトなどで、その価格を調べてみると、思ったよりも高額だった。掲載写真から推定した、製造元と思われるサイトより、前記遊具の価格を紹介しておく。前回のブログ記事にある画像の左の「昇降運動遊具」で200,000円、同右の「腹筋遊具」で330,000円だった。そして、右図の遊具の価格は、何と420,000円もするのだ。 しかも、「消費税、運賃、基礎工事費、組立費は別途」と言う具合だから、如何に健康遊具の価格が高額かがわかる。ちなみに、同公園にある4人用ブランコ(昨日の画像参照)と同等遊具の価格は270,000円だから、遊具の価格は見た目ではわからない。もちろん、こども用も複合遊具となると小規模のものでも200~300万円もする。 以前にも、このブログで指摘したが、最近の公園には健康(高齢者)遊具と複合遊具という、極めて高価な遊具が、次から次へと設置され続けている。これは、新手の「箱物行政」の実例になりかねない。さらに、遊具そのものに財政をかけ過ぎて、その遊具の点検・整備が行き届かなくなる状況も、起きているのではないかと、大きな疑問も起こる。 健康遊具の導入は、地方財政がひっ迫しているおりでもあるので、ブーム?に流される事無く、慎重にする必要があるだろう。ブランコ・鉄棒・ジャングルジムなどの既存の遊具(対象年齢が限られた複合遊具を除く)でも、高齢者の健康維持のための活用も十分に可能だ。 こどもから高齢者まで、共にあそぶことのできる遊具が、低価格に出来れば一番いい。身体にハンディをもった方々とも、ともにあそぶ事が出来れば、もっと素晴らしい。おそらく、そんな遊具には、最もシンプルな遊具も含まれるだろうと思っている。素朴な遊具は、ユニバーサルなのかも知れない。エッセイは、次のページでいろいろ掲載しています。遊邑エッセイ↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.04
コメント(0)
-

『健康遊具ブーム??』の一つの実態-その1:『公園の遊具』論/3
これまで、遊具の対象年齢表示について見てきたが、対象年齢が限定された遊具のひとつとも考えられる、全国的にブーム?になりつつある健康遊具(高齢者遊具)について見ていく。右図は、近くの公園にある最近にわかに増えつつある、健康遊具あるいは高齢者遊具と呼ばれる一群の遊具の例だ。これらの遊具を含めて、この公園には6種類の健康遊具が設置されている。 我が家から、近くのスーパーマーケットまでの途中にあり、ほぼ毎日のようにこの場所を通るが、この遊具で運動をされている方を見かける日は極めて少ない。特に、梅雨時や真夏では、おそらく早朝・夜間の時を除いて、利用する人はもっと少なくなるだろう。同公園内にある、こども用遊具の利用頻度とは比べるに値しないほどの低利用率だ。 この利用率の、低さとその原因が想像できるのが左図だ。この遊具は、前図と同一のものだが、わずかの期間でこのような有様だ。要するに、雑草が直ぐに生えてくるような場所に設置されているのと、それに見合った草刈などのメンテナンスが、行われていないのだ。なお、遊具が頻繁に利用されているなら、雑草もこれほど伸びきらないだろう。 次のベンチの例でもそうだが、これを見ると、本来ベンチや遊具を設置するための場所として、設計・デザインされていた場所に、設置されたのではないと想像さえ出来る。空いた場所に、余った予算で、あまり必要性の無い健康遊具が、設置されたのではないかの、疑問がわき起こる。ともかく、健康遊具を設置して終わりという事ではなく、利用促進の取り組みや、快適な利用のためのメンテナンスも必要だ。(続く)エッセイは、次のページでいろいろ掲載しています。遊邑エッセイ↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.03
コメント(0)
-

遊具の対象年齢-その3:『公園の遊具』論/2
次に、遊具の対象年齢表示の運用上の問題点について見ていく。公園と言う不特定多数の人たち、とりわけ知識・分別も自己コントロールも未熟なこどもたちが、訪れる場所にある遊具は、たとえ対象年齢表示があったとしても、監視員などがいなければ、利用者にそれを確実に守らせることは不可能だ。 その行為の善悪はともかくとして、年齢表示や基本的な使用方法を守らない事は、こどものみならずおとなにもよく見られる事だ。例えば、一般的なブランコ(右上図)の基本的な使用方法は、座板に座って鎖を両手で持って乗る事になっているが、実際には二人乗り、立ちこぎなどは普通に見られ、幼児を膝の上に抱いて大人が乗っているのも自然である。 ところが、この一般的ブランコには、「社団法人日本公園施設事業協会」の「6~12歳」(左図参照)の対象年齢表示がある。当然、中学生以上のこどもたちやおとなはダメで、おとなが幼児を膝の上で抱いて使用するのは、もってのほかの事となる。昔は、そうした使用方法で概ね問題がなかったのだが、今のブランコはその程度の使用に耐えられないほど、ブランコの材質が昔より悪くなったのだろうか。 この様な状況では、公園の遊具の楽しみ方が制限され、ひいてはこどもたちが公園で思い切り楽しむことを萎縮させかねない。公園の遊具は、様々な人たちがそれぞれの能力・ハンディに応じて、自己の責任で遊具の選択と遊具のあそび方を決めれるようにするのがいい。そのために、構造上の欠陥や点検・整備上の不備を限りなく無くす事こそが大切なのだ。エッセイは、次のページでいろいろ掲載しています。遊邑エッセイ↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.02
コメント(0)
-

遊具の対象年齢-その2:『公園の遊具』論/2
本来、公園などの不特定多数が利用する遊具は、構造上・品質上・整備上などの、遊具に起因する原因を除いて、利用者の自己責任で使用されるのが原則だ。(対象年齢表示があっても同様) それは、こども自身の自己責任もあれば、付き添いの保護者や指導者などの保護者(監督者)責任の場合もある。 当然、その遊具が利用者の体力・技術などの身体的能力に適合しているかの判断も求められる。小学生以上のこどもたちには、自分の身の丈を知って、高すぎる危険な遊具には登らないような判断力が、育っていなければならないし、少なくとも昔のこどもたちには育っていた。もし、今の小学生にその能力が育っていなければ、その事こそ遊具事故防止で克服すべき課題となる。 なまじっか対象年齢シールがあると、自分で観察して判断するよりも、安易にシール表示に頼ってしまいかねない。そうなると、遊具の対象年齢表示は不必要であるばかりではなく、かえって遊具の危険性を判断する力をこどもたちに育む上での悪条件ともなりかねない。 考えれば、これまでの遊具による重大事故の大半は、対象年齢を逸脱した使用による事故ではなく、遊具の点検・整備不良に起因したり、もともと遊具にあった構造・材質上の問題に起因する事故なのだ。要するに、遊具の製造・設置・運用・管理の問題に起因した重大事故が多いのだ。 それは、そうした遊具の欠陥による事故が、大丈夫だと思って安心している時に、全く予期せずに起きる事が特徴となっているからだ。この不意という事態は、事故を死亡を含む重大な状態へと導く。反対に、危険だと認識して「うんてい」などの上に、よじ登って落下しても、落下地点にコンクリートなどの構造物がなければ、軽傷ですむ場合が多い。危険の事前認識は、こどもたちに、遊具利用の慎重さを必然的に促し、ひいては万が一の時の対処をも想定させるのだ。(前記の「うんてい」からの落下も想定内となる。)(続く)エッセイは、次のページでいろいろ掲載しています。遊邑エッセイ↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
2009.08.01
コメント(1)
全31件 (31件中 1-31件目)
1










