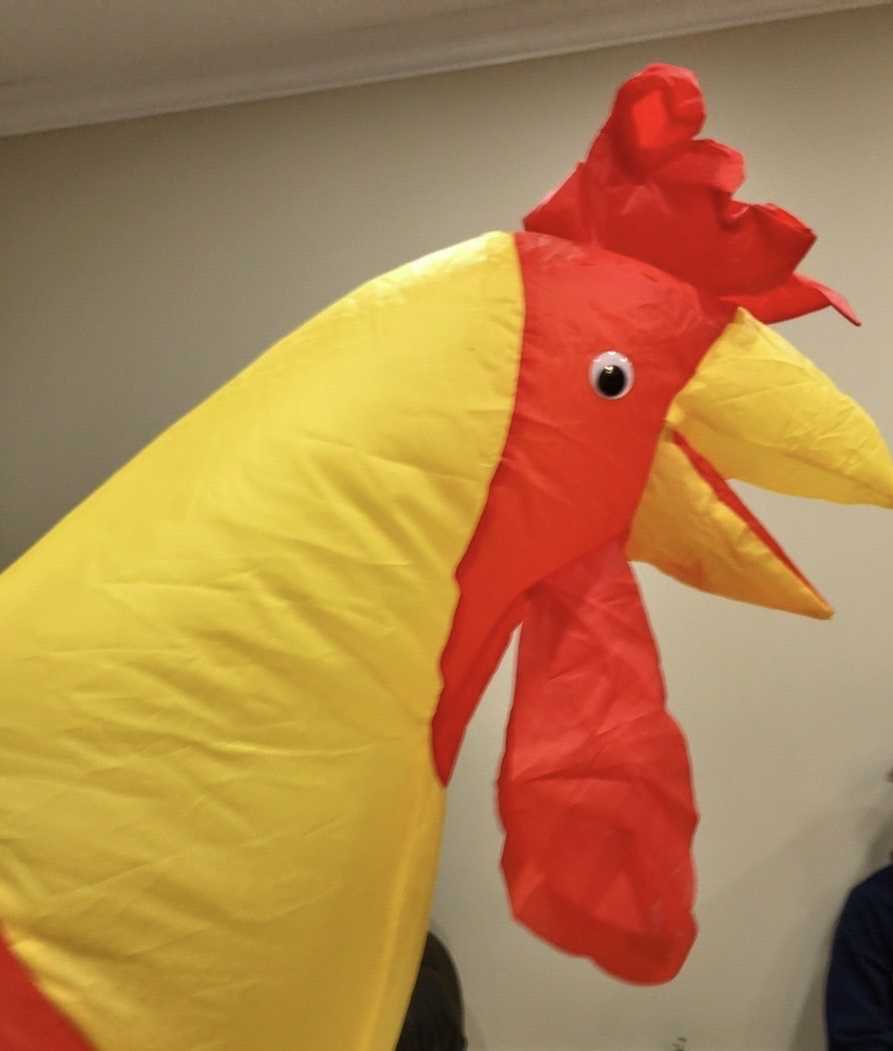2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年01月の記事
全32件 (32件中 1-32件目)
1
-

けん玉について:ニュースに見るあそび
いつものようにネットニュース検索をしていたら、次の記事がヒットした。【中国新聞社は29日、小中学生と家族向けの「ちゅーピー子ども新聞」冬号を発行した。(中略)1面は、今も人気を誇る広島発祥のけん玉を詳しく紹介。小中学生と保護者、祖父母を対象に行った3世代アンケートの結果も伝え、おはじきからテレビゲームまで、各世代にとって幼いころに親しんだ遊びが分かる。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/中国新聞:2008年1月30日) 上記記事の中で目に留まったのは、「広島発祥のけん玉」という個所だ。けん玉の発祥は日本ではないと思っていたので、いろいろネット検索をしてわかったことは、日本けん玉協会公認けん玉に代表される、大皿・中皿・小皿のある一般的な形の木製けん玉の発祥地が広島県の廿日市市と言うことだった。 もちろん、けん玉協会の公認けん玉のように洗練された形ではないが、基本的構造はこの廿日市市のけん玉が発祥とされているのだ。また、その発祥の年代が大正時代に溯るそうで、およそ90年たっている。その後、各地で同じ形のけん玉が作られたようで、私もこどもの頃に奈良へ行ったおりのお土産に買ってもらったけん玉も同じ形だった。 だから、少なくとも現在の形のけん玉を使ったあそびは、高々90年の歴史でしかないのだ。しかも、こどもがあそびで使うおもちゃとしては価格が高く、駄菓子屋さんなどには置いていなかったように記憶している。そうしたこともあり、昔ですら、こどもたちが日常的にけん玉であそぶことは少なかったように思う。その点では、お手玉やコマ回しとは違ったあそばれ方だった。 それが、全国各地にこどもから高齢者まで大勢の愛好家が生まれるようになったのは、けん玉協会などによるスポーツとしてのけん玉が普及してからと思われる。私も、本格的にけん玉をするようになったのは、学童保育所に勤めてからだった。そして、けん玉の奥深さに触れたのもその頃だった。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.31
コメント(0)
-
端切れとお手玉:ニュースに見るあそび
まずは、ネットニュースに配信されていた「お手玉」の記事から。【京都府与謝野町のNPO法人(特定非営利活動法人)「丹後の自然を守る会」がこのほど、ちりめんの端切れを縫い合わせたお手玉450個を同町教委に寄贈した。お手玉は町内の全9小学校に50個ずつ配られる。 同会の蒲田充弘理事長が会の活動紹介で小学校を訪れた際、地場産業の丹後ちりめんについて知らない子どもが多いことを知り、昨年4月にちりめんのお手玉を企画。端切れが捨てられて燃やされると二酸化炭素も生じるため、その削減の意味も込めた。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/京都新聞:2008年1月29日) 私もこどもの頃(1950年代)に、お手玉を手作りで作ったことがある。その時にも記事にある「端切れ(はぎれ)」を使った。この「端切れ」と言う言葉は、今のこどもたちの多くは耳にしたことが無いかも知れない。昔は、着物などを各家庭で縫う事も多かったので、自然と各家庭には「端切れ」が蓄えられていた。今、ほとんどの衣類は買う家庭が多いので、「端切れ」が全く無い家庭も少なくないだろう。 そういった状況の一方で、思わぬところで「端切れ」に出会った。それは、最大手の100円ショップにあったのだが、男の身でありながら、思わず衝動買いをしてしまった。それは、お手玉に仕上げれば、丁度いい柄の「端切れ」だった。今も時折、町の露店などで「端切れ」を売っているのを見かけるが、昔に比べずっとその機会は減っているので、以前から適当な「端切れ」を探していたのだ。 近々、それを使ってお手玉を作ろうと思っているが、皆さんもこどもたちと一緒に手作りしたお手玉で、あそんでみては如何だろうか。ちなみに、昔のお手玉には小豆を入れたりもしていたが、私は学童保育所でこどもたちと作った時は、中にBB弾(エアーガンの弾)と小石を入れて、適当な重さにしていた。 このお手玉の利点は、汚れてもそのまま洗濯できる点と、材料が比較的安価でしかも手に入り易いと言うことだ。出来れば、中に小さな鈴を入れると、音的にも良い感じになる。なお、小さな鈴も100円ショップで手に入れることが出来るので、手作りお手玉の参考となればと思っている。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.30
コメント(0)
-
『検査報告怠れば刑事告発』:ニュースに見るあそび
エレベーターやジェットコースターの痛ましい事故が相次いだ事への、国(国土交通省)の一つの対応策が出されるようだ。【国土交通省は27日、劇場やデパートといった建物、エレベーターなどの設備の所有者らが、建築基準法で義務付けられている定期検査の報告を故意に怠るなど悪質な場合、都道府県などに刑事告発を検討するよう求める指針を作ることを決めた。(中略)建築基準法には、報告を怠ったり虚偽報告をした場合、罰金100万円以下の罰則規定があるが、国交省によるとこれまでに適用された例はない。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/MSN産経ニュース:2008年1月27日) 引用記事の後半を見れば、国土交通省や自治体が罰則適用を怠っていたから、「定期検査の報告を故意に怠るなど悪質な」所有者を許していたと言うことにもなる。その点で考えれば、今回の国土交通省の指針の作成は遅すぎたと言わざるを得ないが、それでも今後定期検査の不備による事故が減るなら早く自治体に徹底させていただきたい。 ただ、罰則として「罰金100万円以下」では、遊園地の遊具が大型化・高速化している現在、一旦事故が起こると甚大で痛ましい人的被害が想定されるような実情には合っているとは言えないだろう。そもそも、劇場などの「特殊建築物」から、エレベーターやジェットコースターなどの遊技施設を含む「昇降機」、さらには空調設備など「建築設備」まで、一律の規定である事も不合理だ。 特に、このブログでも過去に指摘したように、エレベーターと絶叫型ジェットコースターを同じ「昇降機」として扱う事は、全く現状からかけ離れた法律規定になっている。これでは、罰則強化や刑事告発をしても、根本の検査規定が不確かなので、実効性に乏しいものになる恐れがある。 なお、本日付のネットニュースには以下の記事があった。【国土交通省は、高層ビルのエレベーターやジェットコースターなどの安全装置について、第三者機関の性能評価を受けて大臣認定を義務付ける方針を決めた。 遊戯施設などで重大事故が相次いだため、これまでの建築確認審査のほかに、安全面で新たなハードルを設けることにした。同省では、具体的な認定基準を詰め、早ければ年内にも建築基準法の施行令などを改正する。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/読売新聞:2008年1月29日) エキスポランドでの悲惨な事故があってからかなりの期間が経っていて、「早ければ年内」というような進捗具合では、やるべき仕事を怠っているのは、やはり肝心要の国土交通省だったと言わざるを得ない。もちろん、国土交通省全体の責任ではなく担当部署の責任だが、そうした担当部署に指揮命令できる立場にある担当大臣や幹部官僚には、是非反省してほしいものだ。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.29
コメント(0)
-
『外で遊ばない子ども』:ニュースに見るあそび
衛星利用測位システム(GPS)が、思わぬところで活用されていた。【衛星利用測位システム(GPS)を使って滋賀県長浜市内の小学生約460人の放課後の行動を調べたところ、6割が屋内で過ごしていたことが分かった。GPSの携帯端末を子どもに持たせて全行動を追った全国的にも珍しい調査法で、外で遊ばない子が増えているとの傾向を裏付ける結果となった。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/中日新聞:2008年1月27日) このGPSによる調査と共にアンケートを実施したそうだが、外あそびをしているかどうかは直接こどもたちに聞けばわかるにもかかわらずGPSを利用したのは、あそんでいる具体的な場所が時間をおって特定できることにあるのだろう。記事にも、外あそびの場所として、「公園や路地、家の庭」などがあげられ、屋内では「友人宅のほか、商店や塾」となっている。 こうしたことは、今までにも数多くの報告もあるが、放課後のこどもたちの様子を実際にこどもたちが動き回った動線として調査したことがユニークなところだろう。その同じ時間帯にこどもたちが何をしていたかは、同時実施のアンケートで調査したそうだが、記事によると【遊び仲間は2、3人程度。高学年になるにつれ、ゲーム機で遊ぶ比率が増えた。】(同上記事より引用)とあり、これは目新しいものではない。 ただ、この調査は「都市計画の研究の一環として」行われたそうなので、この結果を受けてどのような都市計画の提案がでるのか楽しみでもある。特に、調査にあたった宗本順三教授の「都市計画は、子ども中心に考えるべき」という視点には大いに賛同したい。 少子化の時代にある現在、少子化の住環境における一つの背景として、こどもの成長を脇に置いた都市の発展があったことを考えれば、この記事のように都市計画の中心に「子ども」を置くことは極めて大事な視点だろう。そして、その子ども中心の都市計画に沿った町づくりが実際に広がることを願ってやまない。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.28
コメント(0)
-
不発だった!緊急地震速報:風のつぶやき/その2
【震度5弱以上の揺れが予測される場合、直前に予想震度を放送などで広報する気象庁の「緊急地震速報」が昨年10月、運用を開始したが、26日に石川県で震度5弱となった地震では「予想震度4」と低く見積もったため、速報は出なかった。速報発表の基準に達した地震は運用開始後、今回が初めて。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/日刊スポーツ:2008年1月26日) 我が家は難視聴対策のためケーブルテレビになっているが、最近その接続会社から、二度ほど「緊急地震速報システム」の契約を勧誘された。しかし、この「緊急地震速報」については、現在のところ余り信用していない。新幹線や原子力発電所などはともかくとして、個人の住宅には現在のレベルでは必要性を感じていない。そうした思いの裏付けが上記引用記事に端的に示されている。 要するに、現在のシステム水準では震度にして1段階程度の誤差があるので、今回のような「緊急地震速報」を出すべき地域にその速報が出されていなかったのだ。その誤差が生まれる理由として、各地域の地質や地盤の状況に、「緊急地震速報」の判定が左右されることがあげられる。場合によっては、その地質・地盤の違いにより、震源に近い地域より遠い地域で震度が大きくなる場合もあるそうだ。 新幹線の路線や原発の地下は、地質・地盤調査が綿密に行われているので、「緊急地震速報」の精度は高いと思われるが、一般住宅下の地質・地盤調査はほとんど未調査、あるいは調査レベルが低いので、「緊急地震速報」の精度は相対的に低くなっているだろう。 また、老朽住宅はともかくとして、普通の住宅が倒壊するケースは、地震の特徴により一般的に震源からの距離が近い所となる。その時は、「緊急地震速報」が出てから極めて僅かな時間で地震の揺れが襲う。倒壊する危険が高いほど、「緊急地震速報」から地震到達までの時間が短いのだ。 そうした状況に、「震度予想」の精度の悪さが加わると、ますます「緊急地震速報」は怪しくなってくる。だから、一般住宅においては、「緊急地震速報システム」を整備するのも大事だが、少なくとも震度6には十分耐えられるような耐震補強をする方が懸命な選択だと思っている。エッセイは、次のページでいろいろ掲載しています。遊邑エッセイ
2008.01.27
コメント(0)
-
『ご迷惑』と『お騒がせ』:風のつぶやき/その1
昨年を象徴する言葉は「偽」だった。当然、その「偽」の数ほどの「謝」があった。そして、その「謝」のほとんどで登場するのが、「ご迷惑」と「お騒がせ」だ。政治家・プロボクサー・老舗料理屋・製紙会社などなど、そのほとんどの会見で「ご迷惑」と「お騒がせ」が乱発される。 多大な実害を伴っていて、「ご迷惑」や「お騒がせ」どころですまない重大な事例ですら、それらの言葉が使われる。また、「ご迷惑」をかけただけや「お騒がせ」しただけの事例でも、どうしてそうなったかの原因や理由に全く触れない場合も多い。これらは謝罪そのものが「偽」となるだろう。それは、事の起こりから謝罪までが、偽装に終始した事になり、結果として謝罪が無かったことに等しい。 だから、どこぞやの老舗料理屋の事件では、偽装の根本原因の一つとなっている役員が居座り続けている。「ご迷惑」と「お騒がせ」だけですます偽装謝罪の氾濫は、あらたな偽装を生み出す土壌ともなっている。こうした状況を変えるには、「ご迷惑」と「お騒がせ」だけの謝罪を許さない風潮をつくっていくことが、ジャーナリズムだけでなく国民一人一人に望まれているのだろう。エッセイは、次のページでいろいろ掲載しています。遊邑エッセイ
2008.01.26
コメント(0)
-
『命を見る目』:ニュースに見るあそび
考えさせられる記事がネットニュースにあった。【92年に小学1、2年に導入された生活科では、ザリガニやウサギにえさを与える様子が載っている。東京書籍の担当者は「生活科は、生き物に愛情を注ぎ命を大切にすることに焦点を当てている」という。(中略)「自然の中で遊ぶ機会が減り、昆虫や鳥の種類の見分けがつかない子が多い。身の回りにいるコオロギやバッタ、野鳥を見つけて観察し、命を見る目を養ってほしい」と石田さんは話す。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/朝日新聞:2008年1月24日) 引用部分は、この間の小学校教科書の変遷にまつわる記事の一節だが、「生活科」が「命を大切にすることに焦点を当てている」ということだが、最近のこどもたちの状況は、「命を大切にする」点では後退している事を暗示する事件があいついでいる。これでは、せっかくの「生活科」の意図は成功しているとは言えないだろう。 また、引用後半部は、帝京科学大学の石田(おさむ)教授の言だが、前記のようなこどもたちの状況では、確かに「命を見る目」を養う事は極めて大事なことだろう。しかし、少なくとも都市部では、残念ながら「コオロギやバッタ、野鳥」ですら激減しており、「命を見る目」を養う機会は貧弱なものになっている。 まさに、この点に、今のこどもたちの「命を大切にする」ことの弱さの一つの背景がある。学校の生活科で時たま習うより、日常的に動物たちに接し、その生・死や子育て・成長に対峙することにより、命の実像を豊かにつかみとっていく。 今、都会では目に付く動物で最も多いのが人間で、目に付く他の動物の総数をはるかに超える地域も少なくない。昔は、都会でさえ虫、魚、鳥、コウモリ、カエル、トカゲなどなど数限りない命があふれ、人間以外にもっともっと多くの生命が満ち溢れているなかでこどもたちは育ったのだ。 こうした環境こそ「命を見る目」を育んでいく。生活科での学習も大切だが、多種多様の生命に満ちあふれた環境を構築していくことが大切だろう。その点で、全国各地の学校で、「ビオトープ」づくりが広まっているが、学校内だけでなくもっと地域全体に広げていくことが大切だ。大きな公園にはすぐにでも「ビオトープ」をつくってほしいものだ。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.25
コメント(0)
-
『演出効果機能付きテレビ紙芝居』:ニュースに見るあそび
【マイクを兼ねたコントローラーをテレビに接続すれば内蔵の9作品が楽しめるほか、新しい作品もパソコンを通じてネットからダウンロードできる。登場人物に合わせて声色が自動的に変わるため、朗読が苦手な人でも上手に読み聞かせができる仕組みだ。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/MSN産経ニュース:2008年1月22日) これは、「読み聞かせ」がこどもたちに人気があるからと、あるメーカーが販売する「テレビ紙芝居」と銘打たれた製品の紹介記事だが、どことなくスッキリしない記事だ。元々、テレビは「電気紙芝居」とも呼ばれていたりもするので、「テレビ紙芝居」とは「電気紙芝居紙芝居」となりはしないか。 あるテレビのバラエティーショーでも、この製品を取り上げていたが、確かにテレビ画面の中で紙芝居そっくりに絵が変わっていた。しかし、親や先生などの読み手がマイクを通して、テレビ画面の中の絵を見て読むので、要するに紙芝居の絵を引いて変えるのを自動化したに過ぎない。 また、「登場人物に合わせて声色が自動的に変わる」のも、簡易なボイスチェンジャー機能で、「朗読が苦手な人でも上手に読み聞かせができる」というのは少し誇張があるように思う。声色を変えるのも「上手」と言えるのかもしれないが、「読み聞かせ」が上手だと言われているのは、感情豊かで生き生きとした読み方をしているからだろう。 そして、大事なのは「読み聞かせ」は、わざわざ「紙芝居」を買わずとも、絵本を読んであげることで十分にその目的を達することが出来る。そして、「読み聞かせ」が上手か下手かは大きな問題ではない。こどもたちの喜ぶ笑顔が見たいと言う読み手の心があれば、それだけで十分であり、子育て(教育)には大切なスタンスなのだ。 さらに、この「テレビ紙芝居」のキャッチコピーに「演出効果機能付き」とあるが、「声色が変わる」だけで「演出」に喩えるのは、多くの演出家を侮辱することにもなるだろう。この「テレビ紙芝居」、それはそれとしていろんな活用の仕方があると思う。過剰な宣伝文句は、かえって「テレビ紙芝居」の存在意義さえも小さくしているのではないだろうか。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.24
コメント(0)
-
漢字あそび:なつかしのあの風景
こどもたちは学校で習ったことをあそびに発展させることも多い。私のこどもの頃にも、国語で漢字の部首を習った後には、「ごんべん」の付く漢字をどれだけ多く書けるか(適当に組み合わせてもだめで、読めて意味を知っていないとだめだった。)競争しあったりした。 また、地面に掘って書いて、その上に砂を被せて隠した漢字を当てる「字掘り」もあった。これは、高学年になるにしたがって漢字も難しくなっていく。これらの漢字あそびによって、こどもたちは学校での勉強だけでなく、あそびの中でも漢字の予習・復習をしていたことにもなる。 最近では、そうした「漢字あそび」を教材として市販されているようだが、そうした「教材」は教材として使用するのがいいだろう。できれば勉強としてではなく楽しくあそぶ方がいいだろう。とかく、こどものあそびは長続きするが、勉強は長続きしないのが世の常で、教材としての意図があからさまでは効果が半減するだろう。 教材例101漢字カルタ98部首カルタ「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.23
コメント(0)
-
理科と科学とこどものあそび:ニュースに見るあそび
こどもや学生の理科離れが、大きな関心になっているが、理科離れ克服の取り組みも始まっているようだ。【ロボットを操縦して缶詰取りに挑戦する男の子 遊びの中で、モノを作る喜びや科学の楽しさを体験してもらう「第11回八代こども科学フェア」(八代市など主催)が19日、八代市新町のやつしろハーモニーホールで開かれ、親子連れらでにぎわった。20日まで。 開会式で、坂田孝志市長は「モノが豊かになり、情報のあふれる時代だが、多くの子供たちはモノにふれる機会が少ない。体験を通じて理科や科学に興味をもってほしい」と呼びかけた。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/西日本新聞:2008年1月16日) 最近、テレビなどでおなじみの「米村でんじろう先生」をはじめとした、おもしろ科学実験などのショーも、理科や科学をこどもたち(おとなにも)によく知ってもらおうとする取り組みだ。そうした、取り組みも今後も旺盛に取り組んでいただくことも大切だが、記事にあるように「遊びの中で、モノを作る喜びや科学の楽しさを体験してもらう」事ももっと大切だ。 ただ、記事や「でんじろう先生」なども取り上げておられる「科学遊び」は、本来のこどものあそびと少しニュアンスが違う様に思われる。どちらかと言えば、こどもたちが理科や科学に興味を惹くように予め(おとなによって)準備された活動だ。もちろん、それをこどもたちが十分に消化して「あそび」に発展させることはあるだろう。 そもそも、昔のことで言えば、このような「理科あそび」や「おもしろ科学あそび」が今ほど盛んではなかったにも拘らず、こどもたちの「理科離れ」は、言葉そのものも存在していなかった。だから、「理科離れ」を克服する入り口として、記事のような取り組みは大切だが、もっと根本的なことに眼を向ける必要がある。 こどものあそびには直接に理科や科学に関心を育むあそびも多いが、それよりもあそびを通して経験・体験・実践した事で、後に理科や科学(自然科学だけでなく人文科学)を体系的に学習する上での、大きく貴重なバックグランドを形成させることが重要なのだ。 その具体的な例は、すでにこのブログの中で幾つか(下記参考記事)紹介しているので、ここでは割愛させていただく。*参考記事折り紙と算数:幾何学的認識のひとつのバックグランドとしてのあそび回して楽しむあそび(その1):『回り』の不思議と魅力『科学遊び』と『知育遊び』:遊びと科学(その1)あそびと学習:遊びと科学(その2)あそびと科学法則の、一つの微妙な関係「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.22
コメント(0)
-

区役所は新しくなったのに:シリーズ自治体の愚策/6
近くの公園のブランコが、事故後の市内総点検で支柱だけになって、その上スプリング遊具までが撤去されて、ついに年を越してしまった。その新年早々、住吉区では新しい区役所の総合庁舎がオープンした。その真新しい豪華新庁舎をうらめしそうに見ながら、支柱だけになったブランコが佇んでいる。まさに、自治体の愚策を絵に描いたような光景だ。 なお、今日公園を通りかかると、ブランコが戻ってきていた、おそらく一昨日か昨日に再設置されたのだろうが、それでも撤去後まる三ヶ月以上も経過しており、さらに1月13日の撮影時点で、新庁舎を背景とした写真の状態がほぼ2週間続いていたことは事実だ。また、現在もなおスプリング遊具は撤去されたままである。 ついでだが、この遊具撤去を前後して、全国的にも注目された新しい市長も誕生した。新市長は、この様な事態(知りうる限りでは、市内全域で同様な事態になっている。)を知っていて放置していたのか、こうした公園の遊具再設置の今後の見通しは、この間市民には知らされていなかった。 この様な全市的な事態を知らないような市長は、少なくともこどもたちの味方ではないだろう。知っていて、放置されているなら、市長はもはやこどもたちの敵と言われても仕方がないだろう。もちろん、市の担当部署の幹部が市長に知らせていないなら、そんな幹部は大阪市には必要がない。 なお、ブランコが再設置されるまでに、三ヶ月間も野ざらしで放置されていたが、支柱にある吊り下げ部の点検がキチンと行われたのかどうかも不明だ。ブランコの鎖は以前の物の再使用だと思われるので点検済みなのだろう。吊り下げ金具は新しいものと交換が行われたと見受けられるが、その吊り下げ金具を吊り下げる部分の点検が不十分であれば、再び事故が起きかねない。はたして、これで大丈夫なのだろうか、一抹の不安は残る。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.21
コメント(0)
-

亀とおもちゃと創造と:なつかしのあの風景
「親亀の上に子亀をのせて、子亀の上に孫亀のせて、孫亀の上にひ孫亀のせて、親亀こけたら、子亀孫亀ひ孫亀こけた。」と言う早口言葉があったが、これには後半部を「親亀こけたら、皆こけた。」と言う落ちまでついていた。亀は、多くの爬虫類の中で、最もこどもたちの身近にいて親しみを持つ種類だろう。夜店や縁日の露店にもよく売られていたり、大阪市内の川にも棲んでいて、家で飼っているこどもたちも多かった。 そんな亀には、心を和ませるおもちゃが多いのは、きっとそのゆったりとした動きがそうさせるのだろう。最近、にわかにブームになりつつあるおもちゃ「ウォーキービッツ」も、そんな亀の持つ心和ませる雰囲気が受けているのかもしれない。コミパル ウォーキービッツ スイーツカルピス 上記のような亀のおもちゃは手作りが難しいが、私のこどもの頃に縁日や夜店で売っていた、粘土製の動く亀のおもちゃは、糸巻きと輪ゴム・凧糸・紙箱などがあれば、似たような物が自作できる。亀の背中の真ん中ぐらいから出ている糸を、引き伸ばし適当なところで糸を緩めると亀が前に走り出す。簡単な仕組みだが、面白いおもちゃだった。 最近のおもちゃは仕掛けが複雑になりすぎて、それはそれで面白いのだが、手ごろな材料で簡単に自作できない弱点がある。こどもながらに自分で模倣して作ってみようという気が起きるおもちゃも、幾つかはこどもたちに与えるのも、子育ての一つの工夫かもしれない。適度な仕掛けのあるおもちゃは、こどもたちに創造する意欲も与えることも多いのだ。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.20
コメント(0)
-
『影絵あそび』:ニュースに見るあそび
【岩沢さんは25歳のころ、「娯楽が少ない戦後の時代に子どもたちを楽しませたい」と人形劇を始めた。その後、仲間を集めて、公民館で影絵をしたり、紙芝居をしたり。テレビやおもちゃの普及とともに活動は下火になったが、たった1人になっても図書館で人形劇を続けていた。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/西日本新聞:2008年1月16日) 記事のようなショー的な影絵は別にして、今のこどもたちはどれほど、影絵あそびをしているのだろうか。「鳩」や「狼」・「狐」など手だけを使った影絵は、昔のこどもなら大概は知っていた。私が学童保育の指導員をやっていた10年あまり前には、これらの影絵を作れるこどもたちはすでにほとんどいない状況だった。 それには、テレビやゲーム機に象徴されるあそびの変化だけでなく、光環境の変化が関係しているように思われる。それは、白熱電灯から蛍光灯への変化が大きい。蛍光灯の証明のある部屋で試しに影絵をやってみればわかる。壁などに手を近付けないと、ハッキリとした影絵が映らないのだ。 これは、光源が平面的な広がりを持っているからだ。それに比べて、昔の白熱電灯はほぼ点光源に近いので、簡単にハッキリとした影絵をつくることができる。また、壁から手を離すことにより、影自体は薄くはなるが映った絵は大きくなるのだ。 もちろん、天然の点光源である太陽で塀などに影絵をつくることができる。ただ、真昼間に影絵あそびをするのもいいが、やはり暗くなった部屋から、障子越しに見る影絵は、雰囲気としては最高だろう。そして、明かりがロウソクや行灯だけであった時代の影絵は、さらにこどもたちを楽しませたことだろう。 いや、こどもたちだけでなく、今では想像できないぐらいに、江戸時代ではおとなも大いに楽しんだものだ。それは、江戸の書物を見れば明らかで、載せられている「影絵」の種類の多さには驚かされる。一人でやるだけでなく、二人以上でやる大作すらあるのだ。 ペープサートなどの本格的影絵も面白いが、保育園や学童保育所などで、夜のお泊り保育(行事)の際は、白熱電灯でやる昔ながらの影絵を楽しむのも、きっとこどもたちに新鮮な感動をもたらせてくれるかも知れない。もちろん、家の蛍光灯を一時的に白熱電灯に替えて、家庭でこどもたちに見せてあげるのもいいだろう。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.19
コメント(0)
-
『あそび』と『能動性』:ニュースに見るあそび
ゲーム機の動向を報じるネットニュース記事を見ていて、あることに気付かされた。その記事の一節は次の通りだ。【遊ばなくなった理由としては、ほとんどのゲーム機が「やりたいゲームソフトの種類が少ない」がトップとなっているが、「ニンテンドーDS」だけは「遊ぶ時間がなくなった」という回答がもっとも多いのが印象的だ。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/日経プレスリリース:2008年1月17日) 「遊ばなくなった理由」として「やりたいゲームソフトの種類が少ない」が挙げられているのは、これだけゲーム機が氾濫している世の中にあって、こどもたちの多様な個性に見合うソフトの種類がないということだろう。それはともかくとして、これを「あそび」一般に置き換えて見ると、「やりたいあそびの種類が少ないからあそばなくなった。」となりそうだが、ゲーム機などソフトに依存するあそびと、そうでないこれまでのあそびとは明らかに違った様相になっている事に気付かされる。 ゲーム機以前の多くののあそびには、こどもたち自身でやりたいあそびを新たに創りだすことで生まれたあそびも多い。その反対にゲーム機でのあそびは、やりたいあそび(ゲームソフト)はこどもたち自身では創りだせず、こどもたちはゲームソフトメーカーが、自分のやりたいソフトを作ってくれることをただ待つしかない。 考えれば、ゲーム機以前の多くのあそびは、こどもたちが創意工夫しながら創り出し、改良もしてきたのだ。それが、本来のこどものあそびの姿なのだろう。こどもたちは「あそび」に受身としてだけ関わるのではなく、「あそび」そのものを能動的にリードしてきたのだ。 もちろん、これまでにも本や一部の玩具などに見られる様に、おとなや企業がこどもたちのあそびをリードする事もあるにはあった。しかし、テレビの普及さらにはゲーム機の出現と、それらであそぶ時間の増大が、こどもたちがあそびに能動的に関わることを極端に減少させたしまったのだ。 「外あそび」「身体を使ったあそび」が減少した影響もさることながら、能動的なあそびの減少により、こどもたちの成長に大きな影響があらわれるのは自然の成り行きだろう。かつて青年が無気力だと言われた時代があったが、今後、こどもたちはひょっとすれば「受身人間」と言われる時代が来る、そんな危惧が全くの思い過ごしであることを願う。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.18
コメント(0)
-
ユニークな町づくり:ニュースに見るあそび
こどものあそびと関わっての、ユニークな町づくりをネットニュース記事からひろってみた。【(社)町田青年会議所(寺田雄久理事長)と町田市が昨年10月に共催して行った「町田わいわいミーティング~まちだ市民討議会」の報告書が1月8日、町田市に提出された。討議テーマである「遊びの視点からのひとづくり・まちづくり」から得られた「子どもの群れ遊びの空間・機会をつくろう」「地域の『遊ばせ力』を養おう」など3つの提言にまとめられた。 10月に行われた市民討議会は、同青年会議所が主導して行われたもので、無作為抽出により選出した市民1000人に案内を郵送し、そのうち参加を承諾した市民34人が出席して実施された。無作為抽出のため年齢、職業、地域などさまざまな市民が参加することで幅広い意見が集約できる利点があり、このような形式での市民討議会は全国で広がりを見せている。町田市内での実施は今回が初めて。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/タウンニュース:2008年1月16日) 前半部分は、すでにこのブログでも紹介済みだが、まとめられた「3つの提言」(引用部以外の提言は、同上記事の別の個所に「みんなの思いやり溢れるまちをつくろう」とある。)は、町田市だけの課題ではないだろう。是非、多くの町や村でもこの提言にあるような「町(村)づくり」をしていただきたい。 次に後半部にある、「無作為抽出のため年齢、職業、地域などさまざまな市民が参加すること」には、賛同のエールをおくりたい。今までのこうした「町づくり」会議は、いわゆる有識者(専門家)や町の名士だけの会議が多く、時には住民の願いと乖離した提言が出されることも少なくなかった。 もちろん、専門家などの助言は、素人の考えの及ばないことを提示する点では大切だが、同上記事の他の一節にあるように、住民の「幅広い意見が集約できる」点では、記事のような「無作為抽出」の住民参加の会議が望ましいだろう。こうした動きが「全国で広がりを見せている」という事だが、私の知り得る範囲ではあるが、残念ながら大阪市では見聞きしたことが無い。もしそうならば、大阪市でも実現して欲しいものだ。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.17
コメント(0)
-
『びゅんびゅんごま』と『あそびの指導』:ニュースに見るあそび
コマには水平に回る物と垂直に回る物がある。ヨーヨーやディアボロのように垂直に回すコマに「びゅんびゅんごま(ぶんぶんゴマ)」がある。【浜松市中区北寺島町の浜松科学館で14日、身近な物で簡単にできる工作教室「つくり隊!あそび隊!」が開かれた。来館した子どもたちが、回ると色が変わる「びゅんびゅんごま」作りを楽しんだ。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/静岡新聞:2008年1月15日) この「ぶんぶんゴマ」は、厚紙を丸く切って糸を通すだけで簡単に作れる。また、大き目のボタンや牛乳キャップを代用しても作れる。作るのはかなり簡単だが、回し始めるには少しコツがいるし、続けて何回も「ビュンビュン」と音をさせて回し続けるには、さらにコツがいる。 かつて勤めていた学童保育のこどもたちに初めて教えてあげた時の事だが、回すことは比較的に早くできるのだが、回し続けることに苦労していた。糸を引っ張ったり緩めたりするタイミングが難しいのだ。しかし、私は敢えてそのコツを教えなかった。ただ、私が「ビュンビュン」と回し続けることを見せ続けるようにした。 それは、「ぶんぶんゴマ」を回し続けるタイミングは、自らの力でつかみとる事が大切で、そのためには見本である私の回し方をよく観察させたかったからだ。「ぶんぶんゴマ」もそうだが、普通のコマを回すのでも、私たちのこどもの頃は、誰かに教えられるよりも、上手な子の回し方を見て、コツをつかむのが普通だった。 その点、「ぶんぶんゴマ」は、比較的短時間に回し続けるコツを会得するので、学童保育のこどもたちもすぐに会得した。この様に、こどもたちにあそびを教える際に、手取り足取り教えすぎないようにすることも大切だ。できれば、時間が有れば一切教えなくてもいい。ただ、見本だけは十分に見せてあげる必要がある。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.16
コメント(2)
-
公園の『高齢者遊具』広まる兆し:ニュースに見るあそび
昨日のブログ記事のように、こどもたちの「外で遊ぶ場所」が減少傾向にある中で、次のネットニュース記事のような事も進行中だ。【愛知県東浦町が公園に高齢者向け木製遊具を設置したところ、人気を集めている。全国の自治体、福祉関係者が視察に訪れ、各地に広まる兆しも。遊びながらストレッチや筋力強化が図れ、注意力を向上させる仕掛けもある。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/時事通信:2008年1月11日) 公園への高齢者向け遊具の設置は、高齢化社会に突入し高齢者の健康の維持と促進にとって大いに意義のある事だろう。その一方で、高齢化社会の裏返しである「少子化」を防ぎとめる意味では、こどもたちのために、安心して外であそべる場所の確保も重要だ。 実際にも、私の地域の多くの公園には幼児から高齢者まで訪れている。そうした公園の少なくないところで、元気で活発なこどもたちと四阿(あずまや)でくつろぐ高齢者の方との、トラブルも起こっている。こどもたちにとっては球技が出来ず、高齢者にとっては安心して憩えないという状況が、少なからずあるのだ。 それは、小さな公園に緻密な設計・デザイン無しに、余りにも多くの目的・機能を、安易に持たせすぎた事から起こっている。小さな公園は、ここはこどもたちだけ、あそこは高齢者と幼児などと、適当な棲み分けも必要だろう。また、大きな公園でも、こどもたちがあそびまわるオープンスペースと高齢者が憩う場所を分離することも大切だ。できれば、高齢者がこどもたちの元気な姿を見れる位置で、その安全が確保できるような設計が望ましい。 また、オープンスペースが少ない、こどもから高齢者まで安全にあそべる遊具、そういった遊具だけがあるような個性的な公園が、地域に一つくらいあってもいいだろう。要するに、適当に公園をつくり、適当に遊具を配置するのでなく、地域住民の意見をよく聞いていただいて、大きな視野(地理的な意味でも)に立った公園行政が望まれるのだ。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.15
コメント(0)
-
『外で遊ぶ場所と友人が減少傾向』:ニュースに見るあそび
【3歳から8歳までの子どもを対象に調査したもので、川口会長は外で遊ぶ時間や場所、友人が減少傾向にある現状を説明。「体を動かすことは心を育てることにもつながる」と、幼児期から運動やスポーツに取り組む重要性を力説した。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/神奈川新聞:2008年1月11日) 記事は、神奈川県の事で、記事にある会長とは県スポーツ振興審議会の川口千代京都女子大教授の事だ。その内容は、これまでにも多くの報告があることで目新しくはない。その改善方法の一つとして幼児期からの「運動やスポーツ」を、「川口会長」は提案されておられるが、疑問に思う点がある。 その一つは、現在のこどもたちの状況で言えば、昔に比べ幼稚園や保育園に就園するこどもたちの割合が高くなり、そういった施設において「運動やスポーツ」の機会は増えている。さらに、スイミングや体操教室など幼児向けの「習い事」も増加傾向で、今のこどもたちの「運動やスポーツ」が貧弱には決してなっていないだろう。 だから、こどもたちの「外で遊ぶ時間や場所、友人が減少傾向」という状況を改善するには、幼児期からの「運動やスポーツ」よりも、ずばり「外遊び(外あそび)」と「友人(仲間)」を増やす事を真っ向から取り組むことだろう。外あそびやあそび仲間が減った原因を解明し、その原因を一つずつ丁寧に解決することが大切だ。 そうした事無しに、幼児期からさらに一層「運動やスポーツ」を取り組めば、かえって「あそび」をする時間を減らすことにもなり、「あそび」を介して生まれる多くの「あそび仲間」も減らすことにもなりかねない。なお、「運動やスポーツ」と「あそび」には大した違いが無いと言う意見もあるが、そうでないことはこのブログの多くの記事で私見を書いているので、ここでは割愛させていただく事とする。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.14
コメント(0)
-

地図帳であそぶ:なつかしのあの風景
今の小学生は何年生になると地図帳をもらうのだろうか。私のこどもの頃(1950年代)には、担任の先生から真新しい地図帳をもらい、初めてそのページをめくった時、何故かワクワクドキドキした記憶がある。それほど、その時代には日本全国や世界の詳細な地図は珍しかったのかも知れない。 私は生まれも育ちも大阪だが、こどもの頃は近畿地方から外への旅行はほんの僅かな回数だった。だから、まだ見知らぬ地方のことを地図帳で探しながら想像するのもけっこうな楽しみだった。それは、私だけでなく多くのこどもたちも同じだった。 だからかも知れないが、地図帳を使ったあそびが結構流行ったものだ。自分や友達の姓と同じ地名を地図帳で見つけて自慢しあったり、愉快な地名を探す競争も面白くあそんだ。中でも、巻末の地名索引を使わずに、適当なページから相手が出題する地名を探す競争などは、授業の合間によくやった。 今なら、ネット地図では地名検索でいとも簡単に目的地が見つかるが、地図帳の中から目的の地名を探すのは一苦労だ。しかし、結果として目的地だけでなく、その周りを含めてよく観察することになる。だから、今ふりかえれば、そうした地図帳を使ったあそびは、地理的な関係、地形的な認識を育む上での大きな土台になったように思う。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.13
コメント(0)
-
『ジャングルジム下に衝撃緩和マット』:ニュースに見るあそび
【京都市内の小学校で、ジャングルジム型遊具の下に、落下時の衝撃を緩和するマットを設ける動きが広がっている。落下による大けがを防ぐのが目的で、この5年間に約8割の小学校がマットを敷設している。 マットの設置が進むのは、高さ約3メートルのジャングルジムに、滑り台や滑り棒、ろくぼくなどを備えた総合遊具で、市内のすべての小学校に置かれている。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/京都新聞:2008年1月10日) 最近、小学校や公園に設置してある遊具も大型化し、記事のように高さが3メートル以上あるものも少なくない。こうなると、最高部からの落下を想定した対策も必要となってくるかも知れない。そうした一環として、遊具の下に衝撃緩和マットなどを敷設しているところも多いのだろう。 ただ、そもそも学校や公園などに設置する遊具に、「衝撃緩和マット」が必要となるぐらいに、高さのある遊具が望ましいのだろうか。特別な施設の遊具はともかく、土の地面でも大けがをしない程度の遊具の高さで十分ではないだろうか。 仮に教育上、高い位置まで登る訓練として、そうした高さのある遊具が必要だとしても、落下面がはじめから安全である(落ちてもあまり痛くない)ようでは、その効果も少し疑問となってくる。落ちると危険だ(痛い)から、高所に登る能力と気構えなどが育つのだろう。 同上記事に掲載の写真で気になった点がある。地面と「衝撃緩和マット」の段差があり、けつまずくと遊具に顔などをぶつける危険性が感じられた。さらに、遊具からそんなに離れていない所に、コンクリートで囲われた鉄製蓋付マンホールがあった。落下した弾みでそこに転倒する可能性も大きい。 「衝撃緩和マット」が規格品かも知れないが、遊具設置場所の状況に応じた設置や設置方法を考慮する必要があるだろう。せっかくの、危険防止対策が功を奏さないことにもなりかねない。また、遊具の下や傍が固い材質であるにも関わらず、「衝撃緩和」処置がされていない遊具もまだ残されているかもしれない。 要するに、遊具を設置する場合において、設置する場所、使用目的、使用者などの違いにより、遊具の設置方法や安全対策は違ってくる。そうした、違いを十分に考慮して設置される事が大事なのだ。それには、当然ながら、遊具の設置依頼者や設置工事者に、そうした点を考慮できる能力が必要なのは言うまでもない。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.12
コメント(0)
-

『カルタ取り』に思う:ニュースに見るあそび
【新春百人一首カルタ大会が8日、小城市小城町の小城高校(西岡強校長、786人)であった。同校の年初の恒例行事で、生徒らは読み手が読み上げる和歌に耳を澄ませながら、下の句が書かれた札を取り合った。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/佐賀新聞:2008年1月7日) 記事は「歌ガルタ」とも呼ばれる「百人一首カルタ」だが、この「カルタ」にはその他に「いろは(犬棒)カルタ」「ウンスンカルタ」「花カルタ(花札)」などがある。このうち、一般的に「カルタ取り」と呼ばれているのは、「百人一首カルタ」と「いろはガルタ」だ。絵札を取るか字札を取るかの違いがあるが、ともに読み札を読んで、それと同じ札を取るあそびだ。 この「カルタ取り」、反射神経がその勝敗を決するあそびで、その事は例年テレビなどで放映される「百人一首カルタ」取り名人(クィーン)を決める大会の様子を見れば一目瞭然だ。しかし、そのような名人戦での勝敗は確かに反射神経がものをいうが、それより少しレベルが低い段階では、記憶力がものをいうのだ。(なお、名人戦級では記憶力は当然の前提だ。) 「一字決まり」「二字決まり」などの特殊な札を覚え、さらに並べられた取り札の配置を覚えることが、「百人一首カルタ」の勝利には欠かせないのだ。この記憶力は、初心者より少しレベルの高い「いろはカルタ」でも、勝敗を大きく左右する。 そして興味深いのは、「カルタ取り」の初心者同士の対戦においては、記憶力や反射神経よりも、目的の札を目で探す力が、勝敗の分かれ目となる場合が多い事だ。だから、こどもたちの「カルタ取り」は、「眼力(めじから)」のある方が勝利に大きく近付く。 この「カルタ取り」での「眼力」を鍛えるには、それを鍛える?ゲーム機ソフトに頼る事でもある程度可能かも知れないが、やはり「カルタ取り」の実戦に勝るものは無いだろう。何故なら、「カルタ取り」では、取り札が床に広く散らばっているので、視野を広くし遠近の調節も必要となってくるからだ。 遠い将来のゲーム機ならどうかはわからないが、少なくとも今のゲーム機では、「カルタ取り」をそのままでは再現できない。だから、実際の生活でも大いに役に立つ「眼力」は、意外とこの素朴な「カルタ取り」が鍛えてくれることがわかる。 ただ、「カルタ取り」は少なくとも三人のあそび仲間が必要だ。出来れば、取り手が数人だともっとエキサイティングになる。今のこどもたちは、同じ時間に一緒にあそべる友達が少ないと言われているが、できれば多くの友達と「カルタ取り」を楽しんで欲しい。「カルタ取り大会」もいいが、気の合う友達や家族と一緒に、「カルタ取り」をあそんで欲しいと思っている。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.11
コメント(0)
-
『新テロ対策特措法』の再可決を糾弾する!
新テロ対策特措法が、さきほど衆議院本会議で再可決された。【インド洋での海上自衛隊の給油活動を再開するための新テロ対策特別措置法は、11日午前の参院本会議での法案否決を受け、同日午後の衆院本会議で、憲法59条の規定に基づき、衆院議席の3分の2以上の多数で再可決、成立した。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/読売新聞:2008年1月11日) 「旧テロ対策特措法」により米軍等の艦船への補給を中心とした、自衛隊艦船による活動が展開されたにも拘らず、アフガニスタン情勢はさらに深刻さを増し、隣国パキスタンの混迷も悪化の一途をたどっている。要するに、法律そのものの存在意義が根本から問われているのだ。 しかも、「新テロ対策特措法」を是としない政党・議員が直近の参議院選挙で多数を占め、国民の意思として「新テロ対策特措法」に対して「No!」を突きつけた。だから、本来は再度の会期延長をするまでもなく、「旧テロ対策特措法」の自然消滅で決着すべきだった。 そうした主権者である国民の意思を無視した、今回の衆議院による再可決は断じて許されないだろう。そもそも、今回の「再可決」の憲法上の規定は、以下のようになっている。第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 もし、国民の意思とは別に、国会の意思を決するなら、当然議論が尽くされなければならないだろう。二院制である国会の一つの院が「新テロ対策特措法」を否決した場合、議論を尽くすには憲法59条の3項に基づき、「両議院の協議会」を開催し、それでも意見が分かれた時は、あらためて衆議院で再論議して後に再可決に至るのが本筋だ。 そういった手だてを全く採らず、参議院の否決した当日に再可決を強行するのは、議会制民主主義から極めて逸脱した愚行であると言わざるを得ない。ここで、あらためて「テロ対策」の名目で、アフガニスタン・パキスタン、そして事実上イラクを含む、多くのこどもたちをはじめとした罪無き人々の殺戮に手を貸す「新テロ対策特措法」を糾弾して、私見のまとめとする。(この記事につきましては、一切のコメントをご辞退させていただきます。)エッセイは、次のページでいろいろ掲載しています。遊邑エッセイ
2008.01.11
コメント(0)
-

『福笑い』からの思いつき:ニュースに見るあそび
全国各地で「お正月」にちなんだイベントが行われている。【年明け最初の週末、昔ながらの正月遊びを体験するイベントや真剣勝負の競技かるた大会が県内各地で開かれた。かるたや福笑い、こま回しなどがあり、参加した子どもたちは目を輝かせて熱中していた。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/信濃毎日新聞:2008年1月7日) 正月にふさわしいあそびはたくさんあるが、「福笑い」は数少ない目隠しをして楽しむあそびだ。目を瞑(つぶ)るとか、目隠しをするあそびには、その他の代表的なものには、「かくれんぼ」「目隠し鬼ごっこ」「スイカ割り」などがある。 目隠しをするなどして、わざわざ視覚を遮るあそびでは、普段では余り意識しない視覚以外の感覚が、俄然その力を発揮する。例えば、「かくれんぼ」の鬼になって、目を瞑ると隠れ手の動きを耳で探ることになる。逃げる方向や距離を聴覚だけで判断をするのだ。しかも、幼児でもそれをいとも簡単にやってのける。 記事の「福笑い」は、指先の触覚に頼ることも多い。「スイカ割り」では、足裏の感覚や時には、頬に当たる風の感覚さえ、こどもたちは動員する。この様に、視覚を遮るあそびは、視覚以外の他の感覚を普段以上に使うことをこどもたちに要求する。そして、こどもたちはそれらのあそびでの新たな感覚をも、楽しんでいることも多い。 さらに重要だと思うのは、視覚を遮ったあそびは、視覚にハンディを持った方々の事を、自らの擬似的な体験として、理解する上でも大きな意味を持っている。もちろん、そのことにより視覚障害者の方が置かれている立場をすべて理解できるわけでないのは言うまでもない。 この様に、目隠しをして楽しむあそびには、あそびそのものの楽しさの他に、いろいろ意義もあるからといって、その事をこどもたちに仕向けることや、その意義を説明することも必要が無い。ただ、無邪気にそれらのあそびを本当に楽しむだけでいい。あそびの教育的効果は、知らず知らずのうちに効いてくるものなのだ。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.10
コメント(0)
-
お年玉の使い道はゲームソフト:ニュースに見るあそび
ネットニュースに掲載されていた、「お年玉の使い道」の調査結果は、「やはりそうだった」と言える内容だった。【小学館(本社・東京都)が昨年、全国の小学生を対象に実施したアンケートでは、お年玉の平均金額は2万5293円。使い道の1位は「ゲームソフトを買う」(38・6%)、2位は「すべて貯金する」(31・7%)だった。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/紀伊民報:2008年1月8日) 結果は、「ゲーム」と「貯金」が二分している感じだが、昔からお年玉の使い道として「貯金」があったので、今風といえば「ゲームソフト」がトップになっている点だろう。昔の子どもたちは「どんなおもちゃを買おうか」と悩んだが、今の子どもたちは「どんなソフトを買おうか」と悩むのだろう。 ところで、ゲームソフトを買うと言うことは、当たり前のことながらすでにゲーム機を持っていることを意味する。しかも、性別に関係ない調査なので、女の子を含めて如何にゲーム機が普及しているかがわかる。少し前までは、ゲーム機は男の子が主だったが、今でもその傾向はあるかとは思うが、急速に性別に関係なくゲーム機が普及しているようだ。 また、この正月にゲームソフトを買うまでに、すでにゲームソフトを持っていることもまた当然と言えば当然だが、今のこどもたちはどれくらいの数のゲームソフトを持っているのだろうか。私の身近なところでは、姪の子は小学校高学年の男の子であるが、携帯ゲーム機のソフトを常にケースに3種類携帯している。家に置いてあるソフトの数がどれだけかわからないが、あと何種類か持っていそうだ。 この例は、ひょっとしたら少ない方かも知れない。考えれば、こどもたちが高価な「おもちゃ?」をこれだけ多く所有している事は、最近のこどもたちのひとつの特徴となっているようだ。私のこどもの頃(1950年代)にも、高価なおもちゃをたくさん持っていたこどもが、いなかったわけではないが極少数だった。 だから、今の時代はこどものあそびに使われるお金の額が、極めて高額になっている事にもなる。しかも、それが大都会のこどもたちだけの事ではなく、離島のような所のこどもたちであっても、その事情には大差がなくなっている。この地域差が無いのも、今時の特徴的なこどものあそび事情なのだろう。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.09
コメント(0)
-
『登下校見守りシステム』:ニュースに見るあそび
【最先端の情報技術(IT)を使い、広島市安芸区の矢野南小で進められていた登下校見守りシステムの実証実験が昨年十二月で終了した。「子どもの位置が分かり安心」といった評価がある一方、通学路を外れた児童への即時対応がしにくいなど課題も浮かび上がった。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/中国新聞:2008年1月5日) 今の世の日本のこどもたちは、自由と引き換えに「安全」を確保しなければならなくなるようだ。記事のような固定ICタグによる位置監視システムや、GPS付携帯電話などで、こどもたちは常に「監視」されることを親や保護者から余儀なくされる。今の物騒なご時世だから仕方がないのかも知れないが、こどもたちは歴史上最も不自由な時代に入ったことは間違いがないだろう。 さて、こうしたICタグやGPSで監視されることをこどもたちに強いたおとなは、逆にそうした監視体制に置かれたなら、はたしてそれを甘受できるだろうか。おそらく、多くのおとなはそうした監視に耐えられなくなるだろう。少なくとも、私には到底耐えられない。 そうしたITに頼る方法よりも、現在全国各地で取り組まれている、「見守り隊」などの地域の人々の献身的な善意による方法の方が、こどもたちに安全だけでなく、人々への信頼や敬意を育んでくれるだろう。こうした事態で浮き彫りになった「人を信じられなくなった世の中」だからこそ、そうした人の温もりのある対策が望まれる。 こどもの安全で言えば、通り魔などによる犠牲になるこどもたちの数よりも、交通事故それも無謀運転により犠牲になるこどもたちの数はずっとずっと多い。また、不幸にも虐待で命を奪われたり、悲しくも自らの命を絶つこどもたちの数も少なくない。 はたして、それらのこどもたちの生命を脅かす事態への対策は、「登下校時の見守り」のように熱心に取り組まれているだろうか。通学路の交通安全さえ後回しになっている所も少なくない。登下校時に通行禁止道路を平気で進入する車が後を絶たない。その点では、地域の有志の方による「見守り」は、その点をもカバーしている。 こどもの虐待で言えば、未だに法的な整備が遅れているし、実際にこどもたちを守るための人的整備も遅れている。こどもの虐待はITや機械では防げないし、虐待されたこどもたちに優しく寄り添って癒せるのは「人」だけだろう。人に裏切られた心は、人が癒すことで、人への信頼が再び蘇生するのだ。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.08
コメント(0)
-
『公園の遊具に耐用年数明記』:ニュースに見るあそび
今まで、次の記事にあるような安全基準が無かったのが不思議だ。【遊具メーカーの業界団体「日本公園施設業協会」(東京)は五日までに、ブランコなど公園遊具の設計、点検方法を定めた基準「遊具の安全に関する規準」を初めて見直し、新たに遊具の耐用年数を明記することを決めた。(中略)四月に耐用年数を盛り込んだ新基準を公表する予定。法的拘束力はないが、子どもの安全を守るため公園設置者の市町村などは順守を求められる。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/東京新聞:2008年1月6日) 遅きに失した感は否(いな)めないが、一歩前進には違いがないだろう。しかし、ジェットコースターなどの遊園地遊具のJIS基準もそうだが、新基準には「法的拘束力」が無いのは、その基準の有効性が問われるだろう。 また、新基準がどのように「耐用年数」を決めているかどうかはわからないが、「耐用年数」はその設置場所の環境条件にも大きく左右される。さらに、犬の排泄物による腐食などによる外的条件も「耐用年数」に変動をもたらせる。 こうした二次的条件を全て網羅し、それらに見合った「耐用年数」を完全に新基準に盛り込むのは出来ないだろう。そうなれば、遊具設置後の点検・整備の有り方がより重要になってくる。また、実際の事故でも、その点検・整備の不十分さに起因する事故が少なくない。遊具の「耐用年数」に頼りすぎると、結果として点検・整備がおろそかにもなりかねない。 だから、遊具事故を防ぐには、このブログでも度々強調しているように、如何に早く、しかも的確に遊具の不良個所を発見できるような点検体制の確立と、その後の迅速な整備・補修・撤去などの処置体制の確立が、最重要課題になっている。そして、それらの体制に「法的拘束力」を付加することが望まれる。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.07
コメント(2)
-

『すごろく』徒然話
お正月の遊びとして、少なくなったとはいえ、今でも比較的よくあそばれているのが「すごろく」あそびだろう。毎年の新版が出る「人生ゲーム」や将棋の駒を使った「回り将棋(ひょこまわり)」などの「すごろく」変形ゲームを含めると、もっとたくさんのこどもたちが「すごろく」であそんでいるだろう。 ところで、「すごろく」は本来サイコロを2個使ってあそぶから「双六」と呼ばれてきたのだ。しかし今では、サイコロ1つやルーレットもどきであそぶ事が多くなっているようだ。出来れば「すごろく」はサイコロ2個であそんで欲しいと思っている。 サイコロ2個であそぶと、当然2個のサイコロの目を加える必要に迫られる。小学校低学年や就学前の幼児にとっては、楽しみの中で「足し算」を実践的に学べる貴重なあそびなのだ。サイコロの目の合計の最大が12になり、それが「両手では少し足りない数」となるのが微妙で面白いのだ。一桁と一桁の足し算で、ほとんどが答えも一桁だが、稀に足し算の答えが二桁になる。この微妙なバランスが面白いと思っている。 また、小学校高学年や中学生にとっては、「確率」を理解するための一つの下地を作ってくれるだろう。原理は解からなくても、実践的に「7」の目が出易く、「2」や「12」は出にくいことを学びとる。その事が、後に「確率」を学習するときに生きてくるだろう。 お正月の時期を前後して「すごろく」あそびをする機会も増えるだろう。せっかくの機会だから、「すごろく」の原点に戻って、サイコロ2つであそぶ「双六」を楽しんでいただきたい。そして、こどもたちに「なぜ、『すごろく』と言うか知っているか?」と、由来を聞かせてあげるのも、こどもたちの好奇心をくすぐって面白い。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.06
コメント(0)
-
おとなもやってみたいな!『ふわふわ遊具』:ニュースに見るあそび
イベント会場などに最近よく見かけるのが、「ふわふわ遊具」だ。【空気で膨らませた巨大遊具をナゴヤドーム(名古屋市東区)に集めた「ふわふわワールドinドーム2008」(中日新聞社など主催)の入場者が3日、5万人に達した。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/中日新聞:2008年1月4日) 記事はその集大成とも言える大イベントだが、こんなに大きなイベントでなくても小さな会場でも、「ふわふわ遊具」の中ではいつもこどもたちが、元気にそして本当に楽しそうに飛び跳ねている姿を見ることが出来る。 それも、いわば巨大風船ともいえる遊具の素材自体の開発と送風技術の進歩のなせる業(わざ)だ。遊具の素材自体は、やわらかい素材なので比較的安全な遊具の一つだろう。しかも、その遊具の外形がこどもたちに人気の動物・乗り物・キャラクターが多いのも、こどもたちに視覚的な魅力をもたらせる。 さらに、実際に遊具の中に入って飛び跳ねたときのあの浮遊感と爽快感は、おとなもやってみたくなるような大きな魅力を持っている。しかも、何人ものこどもたちが一斉に飛び跳ねるのだから、楽しさは倍増する。他の子の楽しい表情・歓声が相乗効果をもたらせるのだ。 ただ、遊具自体が軽いため強風に吹き飛ばされての事故も起きている。厳重に固定することが大切だ。また、送風機にこどもたちが誤って手を突っ込まないように、安全管理も欠かせない。それと、中であそぶ人数が多すぎるのも衝突などが起こりうる。それらに、良く注意すれば、最近の大型遊具では珍しいこどもらしい遊具といえるだろう。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.05
コメント(0)
-
『ミニカー』雑感:ニュースに見るあそび
【玩具メーカー「タカラトミー」のミニカー「トミカ」を集めた「トミカ博」が二日、札幌市中央区のSTVスピカで始まった。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/北海道新聞:2008年1月3日)とかく男の子、ともすれば男のおとなも車のおもちゃが大好きなようだ。車のおもちゃにもいろいろあるが、ミニチュアカーの「ミニカー」はラジオコントロールカー(ラジコンカー)とは違った面白さがあるようだ。 その魅力の一つが小さいと言う特徴から来る。「おもちゃ」という言葉が「手でもてあそぶ」からきていることからして、ミニカーはまさに手でもてあそぶには適した大きさなのだ。こどもたちにとって、その小さな手にも十分に小さいのが魅力となっているのだろう。 そうしたあそび方の一つの手で持ってミニカーを走らせるあそび方には、ラジコンカーと違った面白みと意外な効果がある。ミニカーはラジコンカーよりも確実に自分の思い通りに操縦できる。どんな複雑な障害物でも巧みに避けて走行させることが出来る。時には、空を飛ぶ事だって可能なのだ。 そのようなあそび方をしている時のこどもたちの指先や手首は、様々な格好をとる。そうした複雑な、指先や手首の運動は、こどもたちの手の運動能力を楽しみの中で育んでくれる。それは、ラジコンカーのコントローラーの操作だけでは、決して得られないものだ。 だから、おとなのようにミニカーをコレクションとして眺めて楽しむより、こどもたちはミニカーを思う存分、手でもてあそんで欲しい。両手で2台のミニカーを走らせるのもいいだろう。古くなったら、家から飛び出して、本物のオフロードで走らせるのも面白い。土とミニカーを心行くまで「もてあそんで」ほしい!「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.04
コメント(0)
-
『遊戯』の不思議
言葉には、その意味を厳格に規定しているものもあれば、その意味にある一定の広がりをもっているものもある。「遊戯」という言葉もその一つだ。まずは、ネット辞書からその意味を見てみる。【(1)遊びたわむれること。あそびごと。 (2)幼稚園や小学校などで、運動と娯楽を兼ね、集団内での役割を自覚させることなどを目的として一定の方法に従って行う遊び。自由遊戯と組織的遊戯とがある。】(【】内はインフォシーク辞書/三省堂から引用) 上記(1)が本来の意味で、(2)が特定の状況下での使用上の意味と考えられる。ただ、実際にはもっとニュアンスの幅のは広いようだ。パチンコやゲームセンターや遊園地などを総称して「遊戯場」や「遊戯施設」と言う場合の「遊戯」。保育所などにある「遊戯室」における「遊戯」。幼稚園での「お遊戯」における「遊戯」。 それぞれ、微妙なニュアンスの違いがある。特に、「お遊戯」には、音楽や舞踊の要素が加味されているので、単に「運動と娯楽を兼ね」るだけに留まらず、この場合の「遊戯」には情操教育としての意味合いも感じとられる。 こうした、「遊戯」の意味合いの幅広さは、「遊」の字もさることながら、「戯」の字の方にその幅広さが集中しているようだ。同上ネット辞書から拾った「戯」の字の読みの主なものを次に紹介する。【戯る】(あざる)、【戯ける】(おどける)、【戯れる】(ざれる)、【戯る】(そぼる)、【戯ける】(たわける)、【戯れる】(たわむれる)、【戯る】(たわる) 送り仮名が同一でも、その読みに違いがあるのは、如何に「戯」の字が多くの意味合いを含んでいる証拠だろう。実際の意味合いの違いは、辞書で調べてみると面白い。ところで、「戯」という字にこれほどの読みの違いがあることから、あらためて日本語の繊細さが感じとられて興味深い。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.03
コメント(0)
-
急がれる『高速走行遊具の事故対策』:ニュースに見るあそび
エキスポランドでの痛ましい事故以後、高速走行遊具などの事故防止とその前提となる整備点検に関する法的整備が遅れている中で、幸い重大な人的被害が無かったものの、また遊園地の遊具で事故が起こってしまった。【三十一日午後一時四十分ごろ、北九州市八幡東区東田四のテーマパーク「スペースワールド」で、ジェットコースター「タイタンV」(六両編成)が走行中、三両目と四両目の連結が外れ、ホームに到着する手前で前の三両に後ろの三両が高速のまま追突した。乗客十三人が首や腰の痛みなどを訴え、市内の病院で手当てを受けたが、いずれも軽傷。(中略)スペースワールドによると、三両目と四両目の連結ボルトを留めるナットが脱落していた。もともと装着されていなかったのか、連結が外れた際に脱落したのかは不明。三日から二十一日にかけての定期点検で、二両目と三両目の車両を交換した際、問題の連結部をいったん外し、再びつないでいた。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース/東京新聞:2008年1月1日) 正確な事故原因は今後の調査によらなければならないが、少なくとも該当のナットが脱落し易い状況であった事は間違いがないだろう。ナットやボルトの欠陥か装着ミスかはともかくとして、脱落し易い状態を点検時に発見できなかった事が直前の原因と考えていい。 また、他のサイトの記事などを考慮すると、この連結部のボルトは直径2.5cm程度で、ナットは直径4cm程度だそうだが、高速走行遊具の車両連結部としては、そのボルト細さが意外だった。しかも、補助チェーンが有るとは言え、たった1本の鋼材で連結されているのも、素人の感想だが理解できない。 おそらく、強度的には十分な設計だとは思うが、少なくとも走行途中のナット脱落であるので、脱落防止装置の設置や、チェーンのような補助連結装置ではなく、連結装置を二重にするような設計も必要ではないだろうか。そうした点では、高速走行遊具の安全基準も罰則も含めた法的整備の確立も急がれるだろう。 エキスポランド事故後、すでに8ヶ月近く経過している中での、今回の事故は該当遊園地の責任も重大だ。しかし、国民の安全を守る国や自治体の対策の遅れ、特に高速走行遊具に関しては国土交通省の対策の遅れも、この様な不届きな遊園地運営会社を出さないためにも、厳しく批判されなければならないだろう。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.02
コメント(0)
-
『建築物事故情報ホットライン』(その2):ニュースに見るあそび
(その1からの続き) また、この「情報通報」がほとんどなかった結果を受け、国土交通省は「定期検査時に不具合情報の報告をメーカーや保守管理業者に義務付ける」という事だが、これは事故が起きるまでに当然なされていなければならない事だ。 「定期検査時」に発見された不具合を報告しなくてもいいなら、「定期検査」そのものを無視する企業も出かねない。実際に、エキスポランドで死亡事故が起こったではないか。その事故ですら、もう8ヶ月近く前になるにも拘らず、今回の記事のような事態になって「定期検査時の不具合情報の報告」を義務付けるとは、全く国民の命をないがしろにした態度だと言える。 この間、「消えた年金(正確には、消された年金)」問題で所管官庁やその職員の責任が追求されているが、この国土交通省の建築物事故に関わる責任も同様に、単に官庁や職員だけの責任の問題ではない。その官庁や職員を指揮・監督する大臣も重大な責任を負っているだろう。 もちろん、国家機関は巨大組織であるので、全ての業務を監督はできないが、少なくともある程度の問題や事故・事件が世に知られるようになって以後は、その監督大臣としての責任は免れないだろう。さらに、そうした不適格な大臣を任命した首相にも責任の一端があるだろう。年金問題では、同様に当時の歴代首相も猛省していただきたい。「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト
2008.01.01
コメント(0)
全32件 (32件中 1-32件目)
1