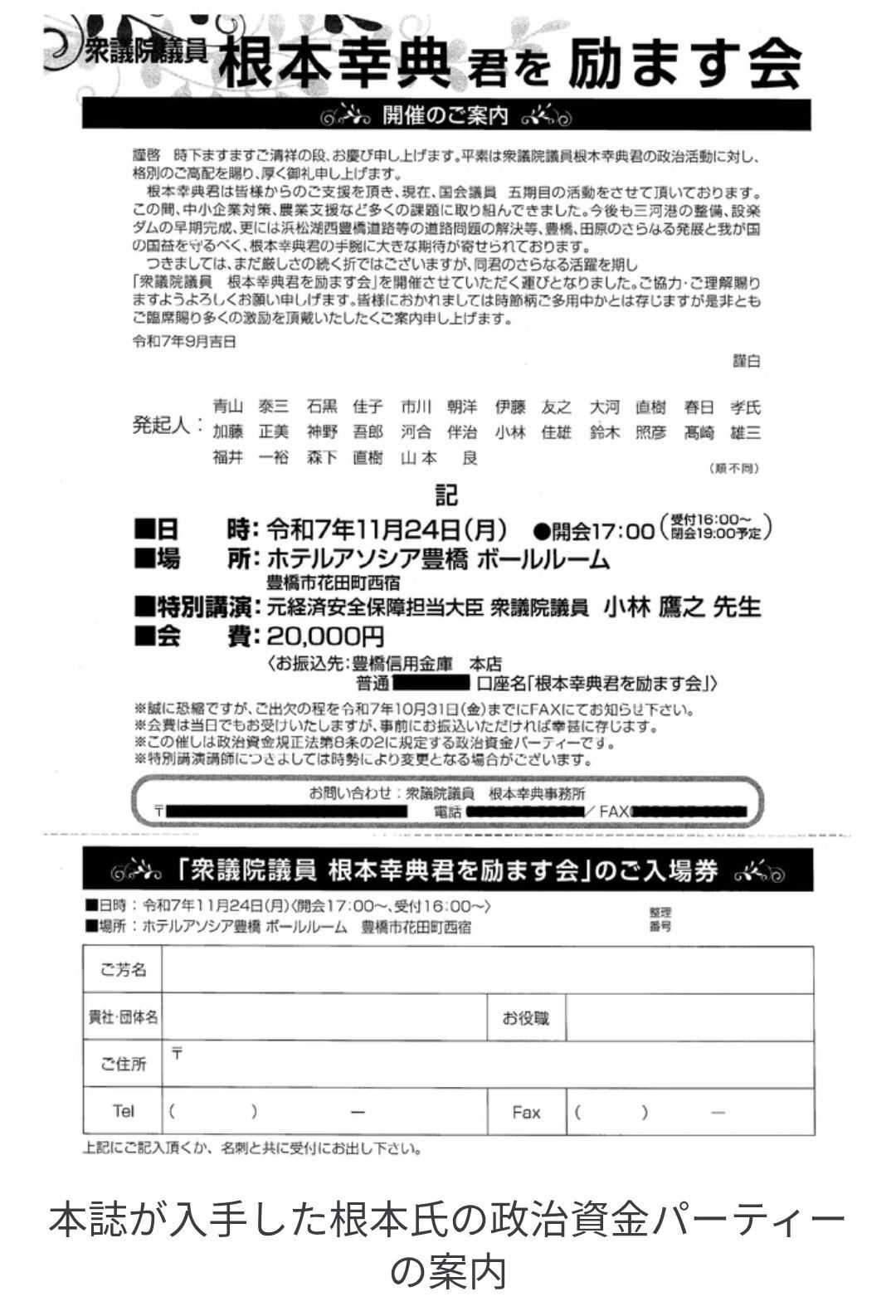2005年10月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
プレイステーションがソニーを凋落させた?
先日の日経新聞コラムで山根さんが、本来のソニー精神が失われた原因の一つにプレイステーションのゲーム機を取り上げていた。私も同感だ。確かに3G技術など最先端かも知れないが、何のためにこのようなゲーム機を作っているのかと考えると、疑問に思わざるを得ない。特に過激なゲームソフトは子供達にどのような影響を与えたことだろう。IBM,東芝と組んで素晴らしいLSIを作ったのはさすがと感心するが、その素晴らしい技術が将来のある子供達にとってはたして良いことなのかどうかと考えると、技術者達も心を痛めることがあるのではないかと思う。私もLSI技術者だったが、パソコンはじめデジカメ、携帯電話、デジタルテレビ、DVD、自動車、産業機器、ロボットなど、あらゆる業界の役にたってきたと自負している。しかし、企業として生き残るためにはパチンコ機器やゲーム機器にも頼らざるを得ないことは理解しているが、将来のある子供達への影響を考えると時々考えさせられた。特に携帯電話が普及し始めた頃は、これで誰もがユビキタス、便利な世の中になると思っていたが、その反面、女子高生たちの援助交際に利用されていることなど、負の面が広がっていくのを見ると、心が痛む。また、家電業界は価格下落が激しく、1個何百円という値段で売られているのをみるとがっかりしてしまう。現在は、1ミクロン以下の技術でLSIは作られているのだ。これを作るためには膨大な設備投資が必要になっている。同時に信頼性や歩留まりを上げるために、血の滲む努力をしている。技術者の気持ちとしては、自分の設計した製品が世の中の役に立つことで報われるのだ。1年もしないでモデルチェンジしていくのと同じような感じで技術者達が使い捨てにされていると感じるようになってしまっては、若者達が離れていくことにもなる。同じ苦労をするのなら、人間として世の中の役にたっているという充実感をもてる仕事をしていきたいものだ。私が入社したころは、大型コンピューターという世の中への貢献が具体的にはっきり見えていた製品だった。またIBMという巨人に対抗するという目標も明確だった。今振り返ってみると、世の中が便利になるのは本当に良いことなのかと思ってしまうこともある。便利になったインターネットもウィルスとのいたちごっこという感じだ。膨大な無駄をしていることになる。なんだか暗い話になってしまったが、今後の人間のあり方含めてもう一度生きる幸せを実感できる技術の方向をみんなで考えていく必要があるように思う。世の中をただ忙しく殺伐としていくのだけは御免だ。
2005.10.10
コメント(0)
-
運動会順延
きょうは息子の中学運動会が雨のためあしたに順延となった。天気予報によれば、あしたも雨がふるみたいなので、危ない。去年も丁度今頃雨が続き結局中止になったので、今年はなんとか運動会をさせてあげたい。もう息子には見に来るなと言われているが、、、、、
2005.10.09
コメント(0)
-
ミニ株奮戦記051004
医療関連の二プロを100株購入した。以前からテレビCMに好感を持っていたのだが、やはりこれからの高齢化社会においては、益々重要になる分野だと思い、長期投資として購入してみた。単元株になるまでじっくり買い増していくつもりだ。社長の顔も大変穏やかなお爺さんという感じで好感が持てた。スーパーを経営しているとは知らなかったが、健康を第一に考えた安全な食品を提供していってほしい。
2005.10.05
コメント(0)
-
ブログ開設1年を経過しての想い
1年が経過したが、タイトルを変えようかと思っている。この1年でアクセス数が2400程度にしかならなかった。これでは自分の自己満足で続けているに過ぎない。やはり、毎日100アクセスぐらいないと、ブログ管理者に対しても申し訳ない。『セカンドライフ』という人生の黄昏みたいなタイトルが魅力の無い原因の一つだと思う。そもそも人生は1回しかないもので、セカンドもサードも無いのだ。考え方を変えねばいけない。人生はホップ、ステップ、ジャンプと考えることも出来る。今までの沢山の経験を生かして、大きく飛躍することを考えるべきだ。色々なしがらみに囚われて、今ひとつ自由に動けないサラリーマン生活とは違う人生がこの先にはあるのだ。本当の自分を取り戻し、尚且つ今までの経験を生かして更に新しいことにチャレンジしていく心構えが必要だと思う。さて、タイトルをどうしようか。
2005.10.03
コメント(0)
-
株の上昇はいつまで続くのか?
ものすごい勢いで株価が上昇している。海外からの資金が流入しているそうだ。それに乗り遅れないようにということで、国内の機関投資家や資産家、それに一般個人まで巻き込んで、株に踊っているようだ。もし私にも自分で動かせるお金が何百万でもあれば、一緒に踊っていたかも知れない。幸いミニ株で奮戦している程度なのだが、それでも上がりすぎてもう手が出ない。ここまで上がるなんて思っていなかったから、売値のときより高い買値では悔しくてとても買う気にはなれない。下がるまでじっと待っているつもりだが、このままどんどん上がっていく気配だ。それでも、じっと見渡してみるとそんなに上がっていない株もある。上がっているのは資源関連と鉄鋼などだ。化学も上がっているが、原料の石油が高騰しているのに何故なのだろう。電力だって影響を受けるはずだ。さわかみファンドではないが、長期投資で自分を信じていくのが一番だ。三菱商事と昭和シェル石油はそのまま持っていれば良かったと悔やまれる。買ったときは長期保有のつもりだったのに。そういう意味では私も株に踊らされていたということだ。さわかみさんはエライ!!
2005.10.02
コメント(0)
-
気になる言葉づかいについて
きのうの日経新聞『NIKKEIプラス1』で、気になる言葉づかいをテーマにした記事が掲載されていた。読者アンケートで、気になる言葉となった一番は『○○でよろしかったでしょうか』だそうだ。私も変な言葉づかいだなと思っていたが、やはりみんな同じに感じていたということがわかり、ほっとした。私がこの言葉を聞いたのは1年くらい前になるが、1箇所の店ではなかったのでマニュアル化の弊害だと思っていたが、そうではないらしい。誰かが接客応対で使ったのを真似したのが、いわゆる口コミの要領で広がったらしい。NHKが時間を言うときに、『3時10分』を『さんじじっぷん』と言っているのに違和感をもったことがあるが、これはNHKが公に決めたらしい。言葉は生き物であるから、時代とともに変化していくのに目くじらたてることは無いとは思うが、NHKとか何とか審議会とかで一方的に決めてしまうのには少し抵抗がある。もう一つの問題に、差別用語についての自主規制がある。会社においても、差別用語は使わないように、との教育を受けたことがある。放送関係や新聞、出版関係でもだいぶ気を遣っているらしい。そのときの私の印象は、これは言葉狩りではないかということだ。途中で一言いいたかったが、講師は会社の総務の人で、質問されても困るという顔をしていたので、黙って聞いていた。”片手落ち”や”帚”も駄目だそうだ。”帚”が駄目だなんて誰が言ったのだろうか?それこそ差別意識の塊ではないだろうか?私は言葉を規制しても差別はなくならないと思う。むしろ事実から目を背け、逆にますます差別を意識させ助長するのではないかと思う。事実から逃げても何の解決にもならない。問題は、そういう差別があったときにきちんと注意できるかどうかだ。そのためには、そういう境遇の人や、差別された人の気持ちを考えることが出来るように、実際の体験機会を増やしていくことも教育の一つだと思う。文学作品に言葉の制約をかけるなどということは問題外だ。
2005.10.02
コメント(0)
-
女王の教室が問いかけたもの
だいぶ遅れてしまいましたが、一言残しておきたいのでブログにアップします。***********************************ドラマの評価は別にして、毎回もらい泣きしながら観ていました。このドラマは、先生だけでなく親達も含めてもう一度原点に返って考えねばならないテーマを色々と与えてくれたと思う。文部省や日教組をはじめとして、各地区の教育委員会、先生達それに父兄達、様々な立場の人達によって、それこそ子供達のためと言って進められてきた教育改革は間違っていなかったのか?実は子供達のためではなく、本当はそれぞれの立場の大人達のためではなかったのか?『自分さえよければいいのよ。』と言う女王先生の言葉に反発した人は多いと思うが、もう一度素直な気持ちで問い直してみると、大きな声で反論できる人はあまりいないのではないだろうか。そこが人間の弱さだと思う。そういう大人達の弱さや嘘を子供達は見抜いていて、結局大人達の考えたようには教育改革は効果を発揮せず、逆に色々な問題を曝け出してしまってきたのではないだろうか。不安や不信感を子供達に感じさせてしまったことが、学級崩壊ほかいろいろと問題をおこすことになってしまったのではないだろうか?はっきり言って大人の都合でいじり過ぎたのはないだろうか?子供達からすれば先生はやはり先生なのだ。多くのことを教わりたいのだ。毅然としていてもらいたいのだ。子供達のことを思って本気で怒ってもいいのだ。思わず手が出たっていいではないか。昔はそういう先生がいたし、卒業してからも記憶に残っているのだ。私が企業社会で若い人達に接しながら感じるのは、大きな壁を乗り越えようと努力する覇気に少し欠けているのではないか、ということだ。イッパシの理屈は言えるが、実際の問題を解決してくには何度も失敗しながら地道な試行錯誤が必要だ。それを継続して次のステップへいくまでの粘りづよい根気が少ないように思う。つまり、生きる力というか、覇気が少し弱く先行きが不安だ。社会全体がそうなのかも知れないが、少なくても学校においては先生が大きな壁となって、子供達を真正面から見据えてほしい。自分の狭い理屈の中に閉じ込めないでほしい。想定外のことが起きたときに、子供達と一緒に悩み考え、理解し合ってほしい。先生も人間だから、生徒にも好き嫌いがあるだろう。それでも先生であるからにはすべての生徒に言葉をかけてほしい。女王の先生の、『いろいろな階層の子供がいる公立だからこそ遣り甲斐がある。』と言う言葉は、やはり現状への一つの問いかけである。結局、人間は壁を乗り越えていく経験を通して成長していくということだ。壁から逃げていては成長は止まってしまうのだ。
2005.10.01
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1