2011年01月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
冬のさるすべり
落葉樹の剪定はたいがい 冬場にするらしい 冬晴れの一日 さるすべりの剪定をすることにした 瘤状になった枝先から 何本もの小枝が密生している その小枝を一本一本切り取ると 樹間から見上げる青空も ずいぶん広くなった 猿も滑るという 白い樹幹はすでに 直径20センチもあろうか 燃える夏ともなれば さるすべりの花冠もまた 真っ赤に燃えることだろう
2011.01.21
コメント(0)
-
雪は・・・
ニッケルの時計とまりぬ寒き夜半 漱石 流竄の旅のすえ はるばる 天から降りてきた 雪は ようやくにして 地上に安息の処を得たのだ そして 一夜さを一期とし 暁の星座の下 燃えるアセチレンのように ただ 蒼く冷たい炎となって 尽き果てることだろう
2011.01.18
コメント(0)
-
今は久しき
大学の受験シーズンがまたやってきた 日本史のテストに こんな問題が出たらどうしようか [問題] 文中の誤りを訂正せよ 今井宗及は戦国時代の堺の茶人で織田信長に仕え 名物松島の茶壷を信長に献上したことで知られる が・・・云々 戦国時代を舞台とした小説を読むのは楽しい。 織田信長・豊臣秀吉の時代を通じて登場してくる茶人に 千利休も有名であるが、いまいそうきゅう・つだそうきゅう もまた有名である。しかしこの二人姓こそ違え名前が似てい ることに加えて、いずれも堺の豪商であったこと、信長の 茶頭をつとめたことなど、共通点が多くまぎらわしい。 いまいそうきゅうは今井宗久であり、つだそうきゅうは 津田宗及であるから、問題の「及」一字は「久」に訂正しな ければならない。 今井宗久は、納屋を名乗り、堺五ヶ庄の代官職や生野銀山の 経営、鉄砲鍛冶の差配など多くの権益を与えられた。 (1520~1593) 津田宗及は、天王寺屋を名乗り、畿内の武将や本願寺坊官の 下間氏などと関係が深く、入洛した織田信長と結び付いて活 躍し、所領の管理、年貢の販売、物資の調達など、広く畿内 から九州に及ぶ商業活動を行った政商であった。 天正2年4月の相国寺の茶会では、利休とともに、正倉院の 蘭奢待を与えられたという。(?~1591) そこで、両者を区別し記憶するために、 「今は久しき 津に及ぶ」と憶えることにしている。 しかし、こんな問題は、大学入試にはまず出ないだろう。
2011.01.17
コメント(0)
-
とくとく徳利
東町のご住職は よく 明け方 すたすたと 南西の方に 歩いて行かっしゃった ほかでもない 八十吉っつぁんの 窯出しの日なのだ とはいっても ご住職も八十吉っつぁんも 先先代の話じゃがな 「これちょっとおもろいなあ」 「うん できそこないじゃが よかったらもっていかっしゃい」 たいがい こんなやりとりがあったことだろうて 窯出しのたんびに ご住職は 徳利や猪口の一つ二つを 後生大事に ふところにしのばせて いそいそと 帰らはったもんじゃそうな 箱書きもないそんな逸物が いまでも東町のお寺さんには いくつもあるんじゃそうな その一つが まわりまわって ここにある ほれ この徳利 お隣の呑ん平が 遊びに来ては 譲ってほしいと言ってきかない 譲るといっても 早い話 ただで呉れろということ 瓢型の胴の中程が ほどよくくびれていて うっすらと 灰緑色の釉薬がかかった下から 朱色の梅鉢紋が浮き出ている 見たとおり 派手さはないが地味でもない 「酒を注いだとき とくとくとくと 小気味のいい音をたてる これが何ともたまらんなあ」と 呑ん平はのたまうのだが いまのところ譲る気はない わしにとっても一期一会 まして 呑ん平ちゅうもんは えてしてそそっかしい 万一落としでもして 毀してしもうたら せっかくの徳利に 申し訳けがないからな
2011.01.08
コメント(0)
-
冬の街
遠い海鳴りをつれて 街には 雪が降っていた でも その夜紡いだ 追憶のキルトは 少しだけ 暖かかった
2011.01.08
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
-

- 戦闘機の写真を撮るのが好き!
- 三沢基地航空祭2025.09.21
- (2025-11-21 06:30:09)
-
-
-
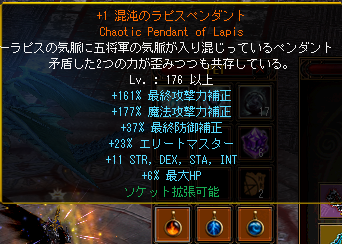
- 『眠らない大陸クロノス』について語…
- 権力
- (2025-11-13 03:11:27)
-
-
-

- 鉄道
- 【2025/10/30】小田急江ノ島線 3275…
- (2025-11-21 04:22:19)
-







