2010年01月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
ゴキブリなホイホイハイム
戀という字を分析すれば 糸し 糸しと 言う 心 ゴキブリのごきは蜚と書く 虫にもあらぬわる(非)い虫 ゴキブリのぶりは虫偏に廉と書く 虫のなかでもやす(廉)い虫 つまり ゴキブリとは虫偏に非と廉 もともと虫族のなかでは とるにたらぬ存在らしい しかし人間にとっては 憎々しい存在だから 人間はゴキブリホイホイなるものを発明した ゴキブリがホイホイ集合するハイムなのだ ハイムが単なる紙の箱だったら ゴキブリたちはなかなか集合してくれないし 捕獲もできない そこで 紙の箱の底にべっとり接着剤 ゴキブリの好きな匂いのご馳走も用意した 人間はさすがに 虫よりは知能指数ははるかに上だった しかし これは虫との比較においてにしか過ぎない 人間は人間の社会においても ゴキブリの教訓に学ぶことを忘れていたのか コンクリートのはこものばっかり作って 接着剤と匂いのご馳走のことまで知恵が回らなかったらしい つわものどもが夢の跡 無人のコンクリートの箱が いまや累々と屍を曝している つまり箱には箱のソフトウエアが伴わないと ただただコストの浪費に終わるのだということ ゴキブリは反面教師なのだ
2010.01.26
コメント(0)
-
べつに どっちでも
昨日の衆議院予算委員会でのこと 与野党のやりとりの一幕 自民党の茂木敏充議員が 鳩山総理に質問した 「朝三暮四」という言葉をご存知ですか」と 「朝決めたことが夜すぐに変わるという意味で 物事をあっさり変えてしまうことです」 というのが総理の答えだった 対して茂木議員は 「それは朝令暮改です」と総理の誤りを指摘した 「朝三暮四」(出典=列子) 中国の春秋時代 宗の狙公が飼っている猿にトチの実を与えるのに 朝三つ暮四つとしたところ 猿たちは少ないといって怒ったのだという それではと 朝四つ暮三つにしたところ 猿たちは大いに喜んだ という故事からきた言葉である 目前の違いにばかりこだわって 同じ結果となるのに気がつかないことを意味する 「朝礼暮改」(出典=漢書) 命令や方針がたえず改められてあてにならないこと 茂木議員の質問は 政府が第一次補正予算を凍結した財源を 第二次補正予算にも盛り込んだことに対するものだった 首相の答えが100パーセント間違いともいえないし 茂木議員の引用句が100パーセント適切だったともいえない 漢字検定四字熟語の部 両者いたみわけ
2010.01.23
コメント(0)
-
言霊汚染列島
啓蟄はまだまだ先だというのに 土中から湧き出る地虫のように 穢くて、紛らわしくて、煩わしくて 無評価で、無価値で、愚かしい 仮面を冠った言葉の行列が這いずりまわっている いわく 「いけめん」「ぶす」 「東大」「京大」「えりーと」「きゃりあ」「のんきゃりあ」 「ますこみ」「めでぃあ」「とぅいったー」 「げーにん」「おわらい」「たれんと」 「まんが」「あにめ」「こみっく」 「ぶっくおふ」「ぶらんどおふ」「くりあらんす」 「どうしゅうせい」「ちほうしゅけん」etc なかでも特に気になるのは「とくそう」だ そのむかし 平清盛は謀をめぐらし 十四、五歳の少年300人を集め 髪をかぶろ(おかっぱ)に切り 赤い直垂(ひたたれ)を着せ 洛中くまなく往き来させては いかなる陰口をも報告させた そして 平家の悪口を言うものは すぐにきびしく処分された 平成のいま 黒いコート 黒いスーツに身を包んだ 強面の一団が あたりを恫喝するように 暗黒と恐怖を撒き散らしている これをして「とくそう」というらしい しかし いかにも正義の味方めかしてはいるが 衣の下に鎧をまとった偽善 また さながらマル暴関係○○組のように 眼に映るではないか 言霊のさきおう国を汚染するのは誰だ一体!
2010.01.21
コメント(0)
-
乱世
なにも書く気がしない なにを言ってもむなしい気がする せめて乱世を眺めようではないか 『あのくたらさんみゃくさんぼだい』 歴史をふりかえるとき 平清盛 源頼朝 足利尊氏 織田信長 毀誉褒貶いろいろあろうが 乱世には 乱世を収束せんものと われこそはと 梟雄が名乗りをあげるもの それが善であったか悪であったか 後世 誰が評価を独り占めし得ようか まして現在においてをや ともあれ いま乱世であることは間違いない
2010.01.17
コメント(0)
-
鬱の鐘
ひとはだれしも 胸の奥に 憂悶の根を秘めている それは 活断層に潜む炬(かがり)のようでもあり 海底に沈む鐘のようでもある 炬はときに業火となって燃え 鐘はときにウオーオーンと哭くのだ 己を哭き 人を哭き 世を哭く 隠々滅々 水面に伝わる声は 鬱の鐘とでも呼ぶに相応しい
2010.01.14
コメント(0)
-
『知』のロジスティクセンター
書店は「知」のロジスティクセンターです 「図書館だってそうでしょう」 「ちょっと違うね」 (お召し上がりですか) (お持ち帰りですか) と問われれば やっぱり持ち帰りたいのです 「知」を発信・流通させる力のあるのは書店です 図書館はいうならば「知」の倉庫です (お持ち帰り)ではなくて(店内でお召し上がり)です でも お互いに補完関係にあることは間違いない 例えば万葉集について知りたいと思っても 万葉集についての万巻の書を 購入するわけにはゆかない 置く場所がない 購入するお金もないし 書店に古今の研究書が完璧に揃っていることもない 第一その道の研究者ならいざしらず 万巻の書に通暁することもない 座右の名著を数冊 時々ひもときながら 疑問の箇所は 図書館で 専門書の知恵を借りればよい とはいうものの 座右の書たるもの 教養の一端として必要不可欠なのです それを求めるのが書店です これは自分に対する最低限の投資です さてさて IT アイティーというけれど 電車に乗っている客で・・・ ケータイ (そもそもこの言葉自体あまり好きじゃない) 携帯の本来の意味は ポータブル(portable)ということでしょう 携帯電話もなるほどポータブルには違いないが きょうび 猫ちゃんのケージだって トイレも テレビも パソコンも 携帯可能なものは世の中に溢れている なのに なんで電話だけを特定して ケータイというのか 携帯電話と正確にいえばいい こんなご時世だから日本語が乱れてくる はてさて困ったものだ 詩を書こうと思ったのに いつのまにか意地悪おじさんの繰言になってしまった どだいテーマそのものに無理があったか ところで 話は電車の中だった 乗客のうちで 携帯電話をいじくっている客約三割 何もしないでぼんやりしている客約三割 隣同士しゃべくっている客約二割 本を読んでいる客約二割 わたしはこの後の二割の人があるかぎり 日本は少しは健康だと安心する 図書館や書店で 子供たちが 目を輝かして 絵本に見入っている姿を見ると ほっと安心するのです この日本も まだ見捨てたものではないなと 「知」のロジスティクセンターが機能している限りはと
2010.01.14
コメント(0)
-
冬の虹
昨年暮れの帰省列車 大阪発11時12分 雷鳥17号 席は通路左側の窓際だった 車中 発売間もない五木寛之の「親鸞」下巻を読んでいた 上巻はすでに読み終えていた 列車が近江坂本あたりに差し掛かると 窓越しに比叡の山並みが見えてくる 麓にひろがる平野部に いっとき冬の日差しが射し ほのかに虹がかかっていた 座席からは虹の立ち上がり部分 それも ほんの少ししか見えなかった 列車が進行するにつれ 近江高島あたりでは 山並みは比良連峰へととってかわる 虹の橋はようやく 左半分ぐらいを現した 右半分はおそらく琵琶湖にかかっているのだろうが この席からは右側の景色は見えない 琵琶湖も見えないのだった 『行きずりの 湖国に顕(た)てる 冬の虹』 親鸞と比叡と冬の虹 この偶然の符合は 何かの啓示を彷彿させた 何の啓示・または暗示なのだろう いつまでも 胸のうちでつぶやいていた
2010.01.06
コメント(0)
-
鰆は鯖ではなかったのだろうか
芥川龍之介が、友人室生犀星の肝煎りで犀星の郷里金沢を 訪れたのは、大正13年の5月若葉の季節であった。金沢か ら大阪を経て、5月23日には、龍之介は東京田端の居宅に 帰ったのだが・・・。 旅の途中龍之介は、金沢の銘菓「長生殿」を滝井孝作、志 賀直哉、薄田泣菫宛送る手配を済ませていた。ところが、そ れが宛先へすんなり着かないといって「怪しからんものは落 雁屋の番頭なり」と憤慨しているのが面白い。因みにこの落 雁「長生殿」なる銘菓も、老舗の果舗も今もそのまま存続し ている。 さて、5月28日付の犀星宛の手紙の中に「お国産を沢山 ありがとう。お隣りの香取先生や下島先生にもお裾分けした」 とある。 昭和10年岩波書店発行の芥川龍之介全集短歌の巻に、次 のような一首が載っている。 香取先生に 金沢の鰆(さわら)のすしは日をへなば あぶらや浮かむただに食(お)し給へ というのである。香取先生というのは龍之介の短歌の道での 師であった香取秀真のこと。香取秀真は著名な金工作家とし て知られている。 加賀の地では5月の春祭りに各家庭で押し鮨を作る慣わし がある。魚を薄味の酢じめにし、上にひじき等をあしらった 押し鮨で、その淡白な味わいと素材の色感が、ほのぼのとし た春の余情をかもし出すのである。 この押し鮨に使われる魚は大抵「鯖」か「しいら」か「皮 鯨」だった記憶がある。 しかし、季節は春、魚偏に春と書く「鰆(さわら)」は春 の語感としてはぴったりではある。 今一歩の推理として、 鯖という字を崩して書けばどうなるか。 鰆という字に見えないことはない。 とすれば、これは鯖の誤読ではなかろうかと。 ところで、昭和52年岩波書店発行の芥川龍之介全集書簡 の巻に次のような一首が掲載されているのである。 香取先生へ たてまつるかぶらのすしは日をへなば あぶらや浮かむただに食(お)したまへ 金沢の冬の味覚「かぶら鮨」は鰤(ぶり)を使う。 鯖でも鰆でもないが、麹で漬け込んだこの鮨は、今では、 急いで食べなくても結構日保ちする。のであるが・・・・ このかぶらのすしの一首といい、鰆のすしの一首といい、 これは同一の歌なのか、別の歌なのか、また鰆は鯖なのでは ないのか、春風駘蕩として確かめようがない。
2010.01.04
コメント(0)
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
-

- アニメ・コミック・ゲームにまつわる…
- 風次とシン工藤の平成ゲーム研究所 #…
- (2025-11-20 20:00:14)
-
-
-

- アニメ・特撮・ゲーム
- 209
- (2025-11-20 22:06:06)
-
-
-
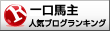
- 一口馬主について
- 所有馬近況更新(25.11.20)ハンベル…
- (2025-11-20 21:34:54)
-







