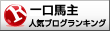2009年01月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
濫読・直近の30冊
詩と関わりのある本は少ないが・・・ 伝説 柳田國男 (岩波新書) 魚へん漢字講座 江戸家猫八 ( 新潮文庫) 黙契 佐伯泰英 (講談社文庫) 百寺巡礼2~5 五木寛之 (講談社文庫) 壊れる日本人 柳田邦男 (新潮社) 国際法の解説 (一橋出版) 三国志1~5 吉川英治 (講談社文庫) 戦後日本は戦争をしてきた 姜尚中・小森陽一 (角川新書) 密謀 上下 藤澤周平 (新潮文庫) 宣告 佐伯泰英 (祥伝社文庫) 我輩は猫である 夏目漱石 (岩波文庫) 読めない漢字1000字 (青志社) 西条八十 筒井清忠 (中公文庫) 想像力の地球旅行 荒俣宏 (角川文庫) 照葉の露 佐伯泰英 (双葉文庫) 花神(上中下) 司馬遼太郎 (新潮文庫) 闇の穴 藤澤周平 (新潮文庫) 乾山晩愁 葉室麟 (角川文庫) 草原からの使者 浅田次郎 (徳間文庫) 戦国の忍び 司馬遼太郎 (PHP文庫) 唐代伝奇 陳舜臣 (中公文庫) シーボルトの眼 ねじめ正一 (集英社文庫) 私の好きな日本人 石原慎太郎 (幻冬舎) 自らの身は顧みず 田母神俊雄 (WAC) 松林図屏風 萩耿介 (日経新聞社) ロシア、闇と魂の国家 亀山郁夫 佐藤優 (文春文庫) 詩歌の森へ 芳賀徹 (中公文庫) 詩の力 吉本隆明 (新潮文庫) 以上
2009.01.30
コメント(0)
-
虫的な宇宙
ごきぶりとががんぼは どっちが偉いのだろう こがね虫はてんとう虫より 金持ちなんだろうな 蟻社会や蜂社会には 女王様や兵隊がいたりして 大統領や首相はいないらしいけど 厳然たる格差社会じゃないのか しかし 蝉なんか世にでるのが 遅れっちまって ついに 頭角をあらわすことができないってのも かあいそうなもんだ 蛍にしても 闇夜に光明をもたらしたのに さてさて 虫世界の大半は 昼の舞台が主流だからして 功績の割りには評価されないのだ マチネー マチネー 源氏も平家も復権を賭けてはいるけどね ところで 蛇とか蝸牛とか蚯蚓とか 蜆や田螺や蛤なんぞ虫であるわけないのに 虫の片割れを掲げているのは ちょっと おこがましいけど まあいいか 番外虫のおかげで まっとうな虫の序列がさ 相対的にすこしずつアップしたというのなら 外道の虫も歓迎ってところ かくかくしかじか 考えてみると 虫的小宇宙というものも 案外 世俗的でつまらない ある意味 意味がないのよ 何故って? たとえば 音楽奏でたり 美しく着飾ったりする虫はいるけど 文芸を独創する虫はいないでしょう というわけで ファーブル先生解ったかしら?
2009.01.26
コメント(0)
-
挨拶のうた
I have a dreame. 慈しみの果実たわわに稔らせて 地上に愛の雫こぼるる キング師の遺志茫々と四十年 自由の旗幟は夢のまにまに 中宙(なかぞら)に平和の鳩の翔けるとき Yes we can 叫ぶひとあり Cange! ギアーも アクセルも ブレーキも いま ハンドルは世界の手に委ねられてある アメリカに アジアに イスラムに
2009.01.22
コメント(0)
-
歌舞伎の「らくだ」
「カンカンノウ」は 「看看口下送奴個九連環」という 中国清朝時代の音楽「清楽」が元歌で 長崎の出島から伝来したらしい そもそも、映画にしても音楽にしても予備知識なしで鑑賞するのが 王道かもしれない。しかし、あまりにもその周辺の知識、情報にう とくて理解できないどころか誤解してしまうというのも困りものだ。 余談だが、フランスのサルコジ大統領は日本の国技である大相撲の フランス興行に冷淡な関心しか示さなかった。メタボな男たちの裸 の格闘技などおよそ文化に程遠い蛮行そのものだと、生理的な嫌悪 を抱いたのだろう。大相撲に秘められた文化の伝統を知れば「食わ ず嫌い」も治るだろうに残念なことである。 『らくだ事典』 シネマ歌舞伎「らくだ」を見た後、いくつかの疑問に逢着した。 「らくだ」に関わるこれは予備知識ではなくて事後知識である。 *「らくだ」って歌舞伎だったの? ずっと以前、喜劇俳優エノケン主演の「らくだの馬さん」という 映画をみたことがある。以来すっかりらくだファンになってしま ったが、「らくだ」の原作は落語だとばかり思っていた。「らく だ」のルーツはこうらしい。 明治の頃、上方落語に「らくだの葬礼」というのがあった。 この外題を4代目桂文吾から譲られた3代目柳屋小さんが東京に 持ち込んだ。大正に入ってからのことである。以来「らくだ」に 看板は変った。以後、8代目三笑亭可楽、6代目笑福亭松鶴など 古今東西「らくだ」の名演は数多い。 落語の「らくだ」を題材にして劇化したのは、岡鬼太郎という人。 岡鬼太郎(1872~1943)は劇作家、劇批評家、東京の人。 慶応大卒、市川左団次らと演劇改良に努めた。洋画家岡鹿之助は その子。 岡鬼太郎によって劇化された「らくだ」は、初世中村吉右衛門の 久六、5世中村七三郎の馬太郎、13世守田勘弥の半次ほかの配 役で東京本郷座において初演された。昭和3年のことである。 落語と歌舞伎、二つの「らくだ」の違い。 落語では、最後まで死んだままの「らくだ」(=馬太郎)が歌舞 伎では大活躍すること。 兄貴分(=半次)とくず屋の久六が「らくだ」の死骸を大家の家 に持ち込んで「かんかんのう」を踊らせる。 この場面、落語ではものの数分で終わるのに、歌舞伎では死骸と 大家の抱腹絶倒の追っかけっこが延々と続くのである。 ・・・昨夜 馬公がフグを食って今朝方死んだんだ・・・ ことから始まるこの話、シネマ歌舞伎に仕立て上げられて見所満 載なのである。 (つづく)
2009.01.19
コメント(0)
-
100%のやさしさ
やさしさに100%ってあるだろうか あるところに 娘がひとりありまして 恵まれないこどもたちに 絵本の童話を読み聞かせていました ある日は「あかいふうせん」のはなしを ある日は「グリとグラ」のはなしを こどもたちは 瞳を輝かせてきいてくれましたが あるとき娘は考えました いったいお話でお腹はふくれるだろうか きっとお腹を空かしている子もいる筈だわ 娘はこどもたちの好きな クッキーをたくさん焼いて こどもたちに与えました こどもたちは歓声をあげて 食べてくれました でも でも きっとこどもたちは 親の愛にも飢えているに違いない どうすればいいのだろう とても一人一人のこどもたちの パパやママにはなり切れないわ わたしはヘレン・ケラーにはなれないし 「ねむの木学園」をつくる力もないし 100%のやさしさなんてできっこないないわ 娘は考えました こどもたちの望む100%はできなくても せめてわたしのできる100%をしようと
2009.01.17
コメント(0)
-
赤い風船・白い馬
詩に饒舌と寡黙があるように 映像が詩そのものではないにしても 饒舌で散文的な映像と 寡黙でも詩的な映像がある できれば 映像にも詩的抒情性がほしい .....人間と人間でないものの共生..... 例えば日本製アニメ「もののけ姫」 詩的にみれば饒舌型か もののけ姫の顔に歌舞伎調の隈取を化粧するのは何故だろう ほんの一端にすぎないが ことはここから始まる 装飾過多 表現としての饒舌 隈取なくしてもののけの本意を体現するのが詩であろう フランス映画 「赤い風船・白い馬」を見て ふと そう思った ここには説明がない 表現過多がない あるのは自然な余情とファンタジー ラストシーン 風船に包まれて空高く舞い上がってゆく少年 白い馬とともに波間に消えてゆく少年 あるのは寡黙ではあっても シャンソン的な 余情にみちた詩である * 白い馬=1953年(モノクロ)、赤い風船=1956年(カラー) アルベール・ラモリス監督・脚本で制作された。 2007年デジタル・マスターの手によって復活し、2008年に 多くの人達の要望により日本でも上映されるに至った。
2009.01.15
コメント(0)
-
シネマ歌舞伎のこと
「シネマ歌舞伎」と銘打った映画を三作品見た。 1; 人情噺「文七元結」 山田洋次監督作品 2; 眠駱駝物語「らくだ」 榎本滋民演出 3; 「蓮獅子」 山田洋次監督作品 人情噺「文七元結」は明治時代に三遊亭円朝が口演した落語である。 これをもとに榎戸賢治が脚色し明治35年(1902)に五世尾上菊五郎が 歌舞伎座で初演した、笑いあり、涙ありの人情劇である。 山田監督は古今亭志ん生や三遊亭円生の口演を参考に、歌舞伎の台本を補綴 し演出したという。 山田監督の次の言葉には全く納得できる。 『円朝はまったく天才だが、その天才の数ある傑作のなかでも 「文七元結」のストーリーは群を抜いて素晴らしく、神の業 かと思うくらい感心させられる。最近の芝居や映画は物語と は云えないささやかで日常的な身辺の出来事を淡々と描いた ものが流行のようだが、それが現代だというような大それた ことではなくて単に力強い物語を構築する力が今の作り手に 欠けているだけのことではないだろうか。「文七元結」のよ うな古典から、、ぼくたち映画や演劇の作り手が学ぶことは 多い』 主な出演者 左官長兵衛 中村勘三郎 女房お兼 中村扇雀 和泉屋手代文七 中村勘太郎 (つづく)
2009.01.08
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1