2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年02月の記事
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-
宝くじ
23日、台湾の大ロト宝くじの抽選会で、な、なんと、7億2600万元(25億円ぐらい?)を当てた人がいたらしい。前二回は、的中者がいなかったので、今回に持ち越され、台湾宝くじ史上二番目の高額になったとか。ちょっと、すごくないですか!?私はこっちで宝くじを買ったことはないのですが、もしこんな高額の宝くじが当たったら?と、しばし妄想にふけってしまいました。まずは、今奉仕している愛家教会の会堂を建てるね。あと、日本の私たちの教団の国外宣教委員会に、何億か献げましょう。そして、日本に帰った時にお世話になっている西大寺教会のチャーチスクールの土地を買って、校舎を建ててあげましょう!ついでに宣教師館なんて建てたりして。そうそう、主人と私のそれぞれの母教会、それに亀田教会もね。と、どこまでも妄想がふくらみ続ける私。最後、主人に「で、うちにはいくら残す?」主人曰く、「一ヶ月分の給与ぐらいあれば。」私、「うっそ~。一千万ぐらいは残そうよ。ほら、子どもの教育資金や老後や・・・。」主人の白い目。そ、そうよね。もしもの話はもうやめましょう。聞いた話によると、台湾で大口を宝くじを当てた人、平均して7年以内に使い切ってるんだって!そりゃ、勤労意欲も失うだろうし、人生変わるでしょ。今回大口当てた人、これからの人生どうなっていくんだろうな?
2007.02.28
-
親子丼
昨日の晩ごはんは、時間も食材もなく、「親子丼」ですませました。「親子丼」で思い出す二人の人がいます。一人は青年の男性。新潟で主人が牧師をしていたときのこと。洗礼準備会の時間が遅くなり、お昼にかかったので、親子丼を作って、3人いっしょに食べました。彼は、母一人、子一人で長く暮らし、いつも夕飯は、母親からもらった500円で、お弁当を買ってすませていたそうです。彼は、出された親子丼を本当においしそうに食べていました。聞けば、親子丼を食べたのは初めてだったとのこと。今ごろどうしてるかな?親子丼を食べる度に彼のことを思い出します。そして、もう一人は、その当時4歳だった男の子。お父さんは、牧師になるための神学校で勉強し、家族で、遠くから毎週私たちの教会に通っていました。そして、教会でお昼がないときには、我が家でお昼をとることが多かったのです。そんなある日、いっしょに食べたのが、やっぱり「親子丼」。食欲旺盛なコロコロした男の子でした。彼は、本当に嬉しそうに食べてくれて、その嬉しい気持ちをどう表現していいのかわからなかったらしく、いきなり、こう叫んだのです。「ち○こ先生を食べちゃいたいぐらいおいしい!」一瞬沈黙の後、大爆笑でした!作った私への感謝を表したかったようですが、かなり、うけました!その子は、お父さんに「変なこと言うんじゃない!」と叱られてましたが・・・。実は、うちの子どもたちは、そろいもそろって、学校に上がる前ぐらいまでは、みんな卵アレルギーでしたので、家でアレルゲンの卵や鶏肉を使うことは滅多にありませんでした。親子丼など、もってのほかです。だから、こんなに印象深くおぼえているのでしょう。「親子丼」を食べるたびにこの二つのエピソードを思い出します。
2007.02.27
-
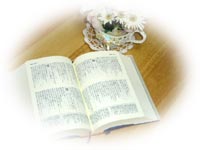
エサウ、ヤコブの誕生
イサクがパダン・アラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻に娶った時は、40歳であった。イサクは自分の妻のために祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに答えられた。それで彼の妻リベカは身ごもった。子どもたちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったとき、彼女は、「こんなことでは、いったいどうなるのでしょう。私は。」と言った。そして主のみこころを求めに行った。すると主は彼女に仰せられた。「二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから別れ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。」出産の時が満ちると、見よ、双子が体内にいた。最初に出て来た子は、赤くて、全身毛衣のようであった。それでその子をイサクと名付けた。その後で弟が出て来たが、その手はエサウのかかとをつかんでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを生んだとき60歳であった。創世記25:19~26~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~まるで絵に描いたような出会いをしたイサクとリベカ、しかし、結婚生活は必ずしも順調とは言えなかったのかもしれない。当時、不妊は不名誉であった時代、子を産めないリベカへの風当たりはかなり強かったことだろう。そんな中、イサクはリベカに子が与えられるように熱心に祈る。祈り続けること、なんと20年!イサクは、そんな人だった。地道にコツコツ信仰の灯火を消すことなく祈り続けるイサク。そんな彼の祈りだからこそ、主は答えてくださったのであろう。リベカ懐妊!どんなに嬉しかったことか!リベカは、お腹の子どもが双子であると、生まれるまで知らなかったように思える。初産だというだけで神経質になっていたであろうリベカは、お腹の中でぶつかり合うまだ見ぬ子に不安を抱く。そんなリベカに神さまは、彼女から二つの国民が別れ出ること、兄が弟に仕えることなどを語られるが、恐らくリベカは、何のことだかわからなかったことだろう。神さまのことばとは、時にそのようなもの。その時にはわからなくてもいい。時間をかけてゆっくりと、日々の営みの中で、そのみことばの意味が明らかにされていく、みことばが、自分の血となり肉となる、そんな時がきっと訪れるはずだから。だからその時のために、今はわからなくとも耳を傾けていたい。神さまのみことば、聖書のことばに。「兄が弟に仕える」神さまは、そうおっしゃった。なぜ兄のエサウではなく、ヤコブが?確かに聖書の中には選びの不思議がたくさん出てくる。私たちだってそう。どうしてクリスチャンの家庭に生まれたの?どうしてあの日、あの時、クリスチャンの友だちに出会ったの?どうして聖書を手にとって読もうと思った?私たちがふさわしかったから?いいえ、すべては、神さまの恵み、あわれみ。
2007.02.25
-
水族館
うちには、きれいな水槽があって、水草だってちゃんとあって、金魚ちゃんだっています。一匹だけど。知り合いで、植物系、お魚系が好きな方がいらっしゃって、その方が、水槽とその付属品もくれて、水草や、石やそういったものまで、キレイに置いてくれて、はじめはたくさん金魚さんもたくさんいたのです。でも、なぜかうまく飼えなくて、どんどん死んでしまって、とうとう一匹に・・・。だけど、そのお友だち、懲りずに、また子どもたちを連れて、きのう金魚を買いに行ってくれました。6匹買って来てくれて、今、水槽はにぎやかです。背びれのないぷっくりしたのや、赤や黒や・・・、(こんな貧しい表現しかできない自分が情けないけど。)今度はみんな元気で育ってしいです。ところで。台湾というところは、実は熱帯魚天国で、熱帯魚好きの人にはたまらない国なのですよ。街のあちこちに「水族館」があります。この「水族館」、日本とは違って、熱帯魚、金魚専門のペットショップのこと。水族館通りみたいなのもあって、通り沿いみんな「水族館」!しかも、お店の中はすごいのです。一面にキレイな水槽、色とりどりの魚たち。さながら日本で言う「水族館」のよう!日本で見られないような珍しい熱帯魚もたくさんあるらしいですよ。店内でお魚ちゃんたちを見ていると癒されますよ。ホント。しかも、日本に比べるとめちゃめちゃ安い!その方面に興味のある方は、一見の価値ありです!それしてもうちの金魚ちゃん、実は黒いのが一匹弱ってるのよね。さっき主人が水槽に手を置いて祈ってたけど。もちなおしてほしいな。
2007.02.24
-
蟻との共存
台湾に一年中生息する迷惑なもの。蚊、蟻、ゴキブリ。この中で共存可能なのは、アリちゃんだけ。まさかゴキブリとは共存できんでしょ。蚊も困ります。かゆいですから。台湾に来た当初は、アリもダメでした。台湾のアリさんは、夏だけではなくて、一年中とにかく働き者。うちは11階に住んでいるのに、少し油断するとすぐに大量発生。砂糖入れなどは、すべて冷蔵庫行き。それでも行列を作って歩いているのを見かける。聞けばマンションの21階に住む友だちも、アリには悩まされているらしい。「アリの巣ころり」を使ったり、アリの通り道に酢を塗ったり、殺虫剤を使ったり。アリ絶滅のために、随分戦ってきました。でも、最近すっかりアリに慣れてしまっている自分を発見!アリが流し台の上を歩いていても、驚きもしない。発見した段階で邪魔なものは指でプチッ!もっぱら対処療法で、アリを根絶しようとは思わなくなってしまっている。悪さしていなければ、放っておくこともできるようになったかな。考えてみれば、アリがいることによって、食べものを出しっぱなしにしておくことはしないし、食べかすなどもいつも掃除しておくようにする。台所がいつもキレイかも。いいこともあるってことか・・・。とにかくここにいる限り、アリとうまく共存していくしかなさそうですね。
2007.02.22
-
離散家族
台湾は今、経済的には中国なしにはやっていけません。聞けば、今や百万人もの人が、仕事の関係で大陸に行っているとか。そして、多くの場合、家族はバラバラに暮らしています。奥さんと子どもをおいて、大陸で仕事をしているわけです。教会の中にも、ご主人が大陸で仕事をしている人が、何人かいます。これは、大きな問題です。家族をおいて大陸に行った多くの男性は、娯楽の少ない環境、孤独の中で、女性に走ります。台湾と中国、同じ北京語を使っていますから、心を通わせるようになるまでに時間はかかりません。そして、最近一人の友だちが、そう言った理由で離婚となりました。聞けば15年も大陸で一人の女性とくらしており、子どもまでいたとか。このような例は珍しくありません。今や社会問題です。家族は一緒にいた方がいい。夫婦は一緒にいた方がいい。
2007.02.19
-
湖の上を歩いて
イエスさまは、強いて弟子たちを船に乗り込ませ、向こう岸に行かせた。イエスさまは一人残り、人々を解散させ、お一人で山に行き祈っていた。イエスさまは、弟子たちが向かい風のために、漕ぎあぐねているのをご覧になったので、湖の上を歩いて弟子たちに近づいて行かれた。すると弟子たち、湖を歩くイエスさまを幽霊だと勘違いして、叫び声を上げ、すっかりおびえてしまった。イエスさまはそんな弟子たちに話しかける。「しっかりしなさい。わたしだ。恐れることはない。」そして船に乗り込まれると、風が止んだ。弟子たちは非常に驚いた。彼らは、パンの奇跡からまだ悟っていなかったからだ。(マルコ6:45~52からあらすじ)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~弟子たちはイエスさまに強いられて船に乗り込みます。イエスさまの導きで踏み出したのだから、きっと平安で何の問題もだいだろう、私たちはそう思うでしょうか。けれどもそのような期待は間違っていると言わざるを得ません。たとえ、私たちがイエスさまの導きで踏み出したとしても、困難や闘いはあるのです。いいえ、イエスさまの導きで踏み出したからこそ起こる困難や闘いだってあるはず。けれども、恐れる必要はないのです。なぜなら、困難の中にあっても、私たちを見守るイエスさまのまなざしがそこにあるからです。イエスさまは遠くにいて、自分たちの近くにはいないと思っていた弟子たち。しかし、イエスさまは、遠くにあっても、弟子たちをご覧になっていました。そして、弟子たちがいよいよ困っているのを見ると、湖の上を歩いて渡り、弟子たちに近づいて行かれたのです。そして、そんなイエスさまを幽霊だと勘違いし、おびえる弟子たちのために、イエスさまは、ついには船にまで乗り込み、「しっかりしなさい!」と声をかけられたのです。「しっかりしなさい」とのイエスさまの声かけは、新約聖書の中で6回出て来ます。それは、どれも信仰者に対しての励ましでした。苦しみや戦いの中にある信仰者に、語りかけられているのです。私たちも忘れてはいけません。イエスさまは遠くにはおられません。私たちが苦しみの中にあるときも、イエスさまは私たちをご覧になり、近くに来て下さり、励まして下さるお方なのです。それにしても弟子たちは、なぜ、湖の上を渡って来られたお方が、イエスさまだと気づかなかったのでしょう。聖書はこう語ります。「彼らはパンのことから悟るところがなく、その心は堅く閉じていたからである。」五つのパンと二匹の魚でもって、五千人以上もの人々にお腹いっぱい食べさせたイエスさま。そんな力あるお優しいイエスさまなら、湖などものともせず、自分たちを救うために来て下さると、彼らは悟るべきだった。彼らの問題はそこにあったのです。実は私たちも神さまの恵みをたくさん見たり聞いたり、経験したりしているのではありませんか?そんな時「よかったね」で終わらせないで、ぜひ、神さまのすばらしさを学んでほしい。そのご人格の豊かさを知ってほしい。そうすれば、主の守りはいつも私たちの近くにあることを知ることができるでしょう。
2007.02.18
-

年菜!
今日は除夕!子どもの中国語の先生のご家庭、林家に招かれて、「年菜」なるものをいただいて参りました。聞きしにまさる豪華でおいしいお食事でした。一番手前の大きなお皿が「大根餅」その右が「アワビ」、左が「からすみ」、その他にも牛肉、鶏肉、豚肉、おいしいスープに煮物、野菜炒め、腸詰など、盛りだくさんでした。私は腸詰はちょっと苦手なのですが、他はどれも大好き!!子どもたちも何度もごはんをおかわりしながら、たくさん食べていました。おもしろかったのは、食事の途中、何回も乾杯すること。「新年快楽!」と誰かが言うと、それぞれの杯やコップを持って、互いにあいさつを交わし合います。食事の後は、居間に移動。みんなでお茶を飲んでおしゃべり・・・と思いきや、時代は変わり、今日はコーヒーをたててくれました。その場で豆を挽くところから初めて、おいしいコーヒーを入れてくれましたよ。何とかつたない中国語でおしゃべりをし、楽しいひとときを過ごしました。中国人はみんな「好客」だとよく聞きますが、本当にその通りで、こんな特別関係のあるわけでもない外国人を本当に気持ちよくおもてなししてくれました。おみやげに果物やおいしいお茶、からすみを持たせてくださり、子どもたちにいたっては、「紅包」(お年玉)までいただいてしまいました。楽しい除夕のひととき、林家の皆さん、ありがとうございました!本当に楽しい、思い出に残る一夜でした。
2007.02.17
-

明日は除夕!
明日は、旧暦の大晦日。こちらでは除夕(チューシー)と呼ばれています。ですからこの一週間ほどは、街中どこも忙しない雰囲気です。日本と同じで、年末は大掃除をします。確かにゴミ収集車が来る回数もいつもより頻度が高い。また、この時を機会に家具なども買い換える人が多く、あちこちにの家の前に粗大ゴミが出されています。大きい買い物をしている人もよく見かけますね。家具屋さんは、かき入れ時!どこも赤札を出して、お客を呼び込んでいるようです。正月の飾り付けもします。こんな出店があちこちで見られます。やっぱり、赤と金が好きでしょ?そして、日本で言うお歳暮のような習慣もあります。うちもなぜか、あちこちからいろいろと頂き物をしました。こんな時はお返しするべきなのだろうか・・・。こちらの習慣が今一わからない私たち。あと、服!!春節、つまりお正月は、上から下まで新しい服を着る習慣があるようです。ですから、服を売っているお店も大繁盛ですね!さて、除夕の食べ物。大陸の北部から来た人は、水餃子を食べるようですが、台湾人の多くは、「大根餅」や「年ガオ」(お餅)、その他の「年菜」を食べるようです。ふふふっ。実は明日、お友達のおばあちゃんの家にお呼ばれしていて、その「年菜」なる物を初めていただくことになります。ドキドキ!そうそう、台湾の家族親戚そろってのごちそうは、お正月ではなくて、大晦日の夜だそうです。家族親戚が集まる中に、私たち家族が入っていっていいのかなとも思うのだけれど、お友達曰く、中国人は、にぎやかなのが好き。全然「没関係(メイグアンシー)」訳「大丈夫!気にしない!」ということです。では、遠慮なく!!
2007.02.16
-
中国人が一番好きなもの
教会の婦人会で、絵当てクイズをしたことがありました。代表の人を立て、その人は、ある単語を見せられる。その単語を絵で表現して、みんなに当てさせるというもの。ところが、そのご婦人、絵が苦手で、始め二重丸を描いただけで、手が止まってしまう。誰も分からない。煮詰まってしまった彼女はとうとう口を開いてしまう。 「中国人が一番好きなもの!」みんな一斉に「わかった~!」「金」きんちなみに始めに描いた二重丸は、金の指輪だったらしい。
2007.02.14
-
五つのパンと二匹の魚
イエスは、船からあがられると、多くの群衆をご覧になった。そして彼らが、羊飼いのいない羊のようであるのを深くあわれみ、いろいろと教え始められた。 そのうち、もう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来て言った。「ここはへんぴな所で、時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして、近くの部落や村に行って何か食べる物をめいめいで買うようにさせてください。」 すると、彼らに答えて言った。「あなたがたで、あの人たちに何か食べるものを上げなさい。」そこで弟子たちは言った。「私たちが出かけて行って、二百デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるように、ということでしょうか。」 するとイエスは彼らに言われた。「パンはどれぐらいありますか。行って見てきなさい。」彼らは確かめて言った。「五つです。それと魚が二匹です。」 イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう、弟子たちにお命じになった。そこで人々は、百人、五十人と固まって席に着いた。 するとイエスは、五つのパンと二匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられた。また、二匹の魚も皆に分けられた。人々は食べて満腹した。そして、パン切れを十二のかごにいっぱい取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは、男が五千人であった。(マルコ6:24~44)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~イエスさまと弟子たちは、休むために寂しいところに退こうとしたのでした。ところが、多くの群衆が先回りをして、イエスさまの到着を待っていた。そんな群衆をイエスさまは見られ、羊飼いのない羊のようだとおっしゃったのでした。臆病で弱い羊は、羊飼いがいなければ生きていけません。そんな迷える姿に、イエスさまの心はあわれみでいっぱいになるのでした。あわれみでいっぱいになったイエスさまは、群衆に対し、何を始めたのか。それは、神の言葉、つまり聖書をもって教えることでした。神のことばは、迷える人を助け、支え、養う力があります。毎日聖書を読み、毎週礼拝でみことばを聞くときに、私たちの心は豊かに養われていくのです。イエスさまの教えに耳を傾ける群衆は、時がたつのも忘れ、一心に聞き入っていました。気がつくと、飲まず食わずで随分と時間がたっていたのです。弟子たちはイエスさまに提案します。「みんなを解散させ、それぞれで食べ物を買わせましょう。」と。しかし、イエスさまは言うのです。「あなた方で、あの人たちに何か食べるものを上げなさい。」原語を見ると、それはきっぱりとした命令だったようです。弟子たちはどう思ったでしょう。「そんなの無理だ。」そう思ったかもしれません。そう、私たちはいつもそう思う。自分の力のなさ、限界、貧しさを見て、「ダメだ。無理に決まってる。」そう決めつけるのです。でも、逃げてはいけません。イエスさまは、私たちにチャレンジしているのです。それは私たちに期待しているから。貧しくてもいい。自分の持つ五つのパンと二匹の魚をイエスさまに差し出してみよう。差し出せる物は必ずあるはず。神さまの奇跡は、自分の持てるものを差し出すところから始まるのです。私たちが、差し出したときに、それは、神さまの御手の中で満ちあふれ、5000人以上の人のお腹を満たしたように、私たちが期待する以上のものがそこから生まれるのです!さて、このイエスさまと弟子たちとのやり取り、群衆の知らないところでなされていました。群衆は、どんな展開がなされていたのか知らなかった。知っていたのは、五つのパンと二匹の魚を差し出した弟子たちだけ。同じように、実は世界中で神さまは奇跡を起こしている。でも、多くの人は知らないのです。知っているのは、自分の持てるものを、神さまに差し出したその人だけ。その貧しさ、弱さ、力のなさを知りつつ、イエスさまにそのすべてを差し出したその人だけ。私たちも、「無理だ」と嘆く前に、神さまの御前に持てるものを差し出してみよう。そうすればきっと、神さまの奇跡が見られる事でしょう!
2007.02.11
-

ウォータースタンド
これは、最新のウォータースタンド。要するに、水を売っているスタンド。このお店には4種類あります。一番左から純粋二番目がアルカリイオン水、3番目が、ミネラルウォーター、一番右が、竹炭水、竹炭を通した水ということかしら?値段は、純粋が1リットル1元(3,5円)その他が1リットル2元(7円)です。台湾の水道水は飲めません。うちには、備え付けの水を浄化する装置があって、一応は飲めるのですが、ピロリ菌で胃を悪くした経験のある主人は、それも信用できず、今は、ここのお水を愛用!ちなみに主人のお気に入りは、竹炭水です。いつも5リットルのタンクを持って行っては、給油じゃない、給水してます。日本でもこんなスタンドがあったら、結構流行るかも?
2007.02.08
-
子どもの古着
うちは子どもが4人いるので、当然のことながら、古着も多い。まだきれいで、思い入れが強い服は、お友達や親戚の甥っ子姪っ子にもらってもらう。そんなに思い入れはないが、きれいな服は、バザーに出すためにストックしてある。困るのは着古して、とっても人には使ってもらえないような古着。そんな古着は、子どものお気に入りで、いつも着ていた物だから、捨てるときは、大げさでなく、断腸の思い。でも、「地上では旅人寄留者」の宣教師家庭。シンプルライフを自負する私としては、いつまでもタンスの肥やしにしておくわけにもいかない。しかも節約、倹約家の私。ただで捨てるのももったいない。リフォームするには技術がない。行き着く先は、チョキチョキ小さく切って、台所などで、油や汚れを拭くために使うという利用法。でも・・・。切れない!その服を目の前にすると、その頃の子どもの姿が思い浮かんで、手が止まってしまう・・・。うっ・・・、だめだぁ~!そこで考えた。長女のアルバイト!!スーパーの袋一ついくらと決めて、切ってもらう。そうしたら長女、切るわ切るわ、容赦なく、惜しげもなく、チョキチョキと次から次へと切ってくれる。みるみるはぎれの山!はぁ、これで処分できる。と思いきや・・・、さっ、油を拭こうとはぎれ取り出すと、あ~ん、マイマイの使ってたパジャマ!!ちょっと、躊躇するときもあるのです。みなさん、どうしてるんでしょね。子どもの古着。
2007.02.05
-
イサクは待っていた
「イサクは夕暮れ近く、野に散歩に出かけた。彼がふと目を見上げ、見ると、らくだが近づいて来た。リベカも目を見上げ、イサクを見ると、らくだから降り、そしてしもべに尋ねた。『野を歩いてこちらの方に、私たちを迎えに来るあの人は誰ですか。』しもべは答えた。『あの方が私の主人です。』そこでリベカはベールを取って身をおおった。しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに告げた。イサクは、その母の天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは、母の亡き後、慰めを得た。」創世記24:63~67~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~なんて美しい光景!目を閉じて、この場面を想像してみる。夕日で赤く染まった広い荒野。静かな出会いのシーン。お互い遠くにいるときにその人と気づき、歩み寄って行く二人。家族を離れ、見ず知らずの相手、土地であるにもかかわらず、信仰を持ってやってきたリベカ。かたや、神さまのみこころの人をひたすら待ち続けていたイサク。「待つ」そんな「受け身」姿勢のイサクに頼りなさを感じるだろうか。しかし、こと結婚に関しては、この「待つ」ということが、どんなに大切か!なぜなら、結婚は、人のわざではなく、神さまのわざだから。そう、結婚相手を備えてくださるのは神さま。人のあせりや勇みは禁物。結婚はたいてい、若くて未熟なときの決断。経験を生かすということもできない。だからこそ、よく祈って、神さまの答えを待つことが大切。イサクを見てみよう。しもべの話に黙って耳を傾け、確かに神さまの導きであることを確かめている。待つこと、祈ること、それこそ結婚への確かな備え。「彼は彼女の妻となった。彼は彼女を愛した。」結婚した後に本当の愛が生まれる。恋愛と愛は違う。お互いが好きで好きでたまらなくて結婚しても、そのような恋愛感情は長くは続かないかもしれない。しかし愛は、結婚と同時に始まり、一緒に苦労し、助け合う中で、育っていくもの。神さまからお互いが愛を注がれ、満たされ、その愛でお互いを愛するとき、助け合って生きていくことができる。日々の生活の困難を乗り越える力も、子どもを育てる力も与えられていく。「結婚は人のわざではなく、神のわざ。」「祈ること、待つことの大切さ」幸せな結婚をするために、子どもたちには是非知っていてほしい。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~主人は私と結婚するために2年祈って待っていたという。ひとりで祈って一年。結婚を申し込んで一年。後半の一年は、毎週一通の手紙を書いてくれていたような。私はと言うと、その気もないのに気を持たせては悪いと、ただの一度も返事を書かなかったような。そして、いろいろあって、彼があきらめざるを得ない状況になったとき、一度、結婚のことを神さまに明け渡したという。実際に「あきらめます」との手紙も受け取った。ところがそんなとき、私の気持ちがいきなり、どういうわけか変わり、彼と結婚しようと思った。いや、そういう思いが上から与えられた、そう言った方がいいのかもしれない。そして、3ヶ月後にはめでたく結婚!結婚は人のわざにあらず!祈って、待って与えられるもの。今日の主人の説教には、実感がこもってました。
2007.02.04
-
娘の誕生日
うちの子どもは、なぜか兄弟同士、二文字の繰り返しで呼び合っている。みんみんケンケンコーコーマイマイそして今日はコーコーの九歳の誕生日!四人兄弟の三番目って、結構「穴」で、なかなか目が行き届かなかったりするかも。一番目は、やっぱりはじめての子だからね。二番目は、黒一点男の子だし。四番目はまだ小さいしね~。というわけで、気を付けてはいるけど、この三番目、いつも元気で朗らか、しかもいい子で、しっかり者、要するに手がかからないのです。もちろん四人とも同じように関心を向けて、かわいがってるつもりなんだけど、気を付けないと、やっぱり穴になってるかな~?だから、こういう特別な日には、うんと特別扱いして、楽しい一日を演出してあげるのです!今日の食事はコーコーのリクエストを準備。ケーキも手作りをリクエストされたので、時間をかけて手作り。プレゼントも主人と一緒にコーコーの喜びそうな物を考える。バースデーカードは、家族みんなで寄せ書き。思い出に残るお誕生日を演出できたかな?コーコーの九歳が、さらに輝いた一年になりますように。
2007.02.02
全15件 (15件中 1-15件目)
1










