2023年02月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-

ハイラックスの歌
先日、高知県室戸市にある「むろと廃校水族館」が更新したTwitter、ご覧になられました?展示の不備に対する「お詫び」のツイートなんですが、その内容が...「お詫び。 朝からアカイカさんがスミを吐いてしまいました。午前中は(水の)透明度が...大急ぎで水の入れ替えをおこなっています。すみません」(笑)テンジクネズミ(天竺鼠)と云う生き物がいます。名前の通り、ネズミのような形態をした生き物ですが、生物分類学上の分類ではヤマアラシの分岐したものとする説が有力ですね。このテンジクネズミ族でもっとも有名なのはモルモットです。名前に反して、テンジクネズミの一族は南米に分布していて「天竺」には生息していません。このテンジクネズミの「祖先」と云う生き物がいます。ハイラックス。ハイラックスの属名「Procavia」が「テンジクネズミの祖先」と云うイミなんです。ところがフランスの博物学者で解剖学者ジョルジュ・キュビエが、歯と足の特徴を調べた結果、原始的な有蹄動物だと分かったのです。足の裏側が、足底の全体を地面につける構造のゾウと同じ構造になっている、つまりゾウに近い生き物だったのです。しかも上顎の臼歯は馬の仲間のサイに、下顎の臼歯は牛の仲間のカバに似た特徴があり、全身の骨格はサイを小型にしたような特徴を持ちながら、前足の骨はゾウに類似しています。なおかつ胃の構造は馬に似ているそうです。って、馬の胃がどんな構造なのか見当もつかへん(笑)ハイラックスは大きな牙をもっています。人間の親指の爪くらいの長さの三角形に尖った牙が2本。それも上の前歯2本だけが牙になっています。この牙は一生伸び続けるのですね。牙は下の2本の前歯で毎日研がれているのでナイフみたいな形になっています。ただ外敵と闘うほどの武器にはならず、オスどおしの群れの闘争に役立つ程度です。ハイラックスの体格は、大人でも体長30~58cm 、体高が20~30cm 、体重は3~4.3kg くらいのずんぐりむっくりした体です。体のいたるところに6~8cm の長い感覚毛が生えてて、岩の裂け目など暗い場所で体の向きや距離感を計っているのですね。背中にはニオイを出す臭腺があります。足裏の柔らかい肉質クッションは、その摩擦力を利用して垂直の岩肌や木々を登るのに使ってるのですね。ちなみに、頭が入る穴であれば、体をすり抜けることが出来ます。オスのハイラックスは、岩の上にとまり、きしむ音を立て、チャックを鳴らし、歌をつぶやきます。 人間の耳には、ハイエナの鳴き声と黒板を引っかく音を足して2で割ったように聞こえます。しかし、ハイラックスのメスにとっては、それぞれのコーラスが渓谷に響き渡るバラードなんですね。そして、オスが安定したリズムを維持すればするほど、メスはうっとりするらしい。研究者たちは、これらの歌の音程が驚くほど複雑であることを発見しました。それは生息地域によって異なります。つまり、方言によって異なることはあっても、ハイラックスは歌うのです。Hyrax Singing on a Rock
Feb 28, 2023
コメント(6)
-

天正遣欧少年使節が持ち帰ったもの
長崎空港へ向かう大村市の箕島大橋の手前に、4人の少年像が建っています。この子たちは九州の大友宗麟、長崎港を開港した大村純忠、その甥の有馬晴信らキリシタン大名の名代として1582年(天正10年)ローマへ派遣された少年たちです。下の画像左から、日向国都於郡出身で大友宗麟の縁者"伊東マンショ"、大村純忠の甥で、有馬晴信の従兄弟でもあった"千々石ミゲル"、波佐見の出身で大村純忠の家臣の子"原マルティーノ"、中浦の出身の"中浦ジュリアン"。この4人は有馬晴信の本拠、島原半島の南部「有馬(現在の南島原市北有馬町、南有馬町)」に設立された日本最初のセミナリオ(イエズス会の初等教育学校)で学んでた少年です。セミナリオにいたカトリック教会の司祭アレッサンドロ・ヴァリニャーノが、日本での布教をローマ教皇に支援してもらおうと使節団派遣を計画します。そうして4人の少年が選ばれるワケですが、ヴァリニャーノは同時に日本の少年にヨーロッパを見せることで、キリスト教の栄光と偉大さを知らせ、その証人とすることも考えてたのですね。4名の少年たちのうち、伊東マンショと千々石ミゲルが正使、原マルティーノと中浦ジュリアンが副使の役割です。1568年(永禄11年)生まれの中浦ジュリアンが当時14歳の最年長で、原マルティノが最年少と云われてます。いづれにしても少年たちの年齢は12~14歳だったと推測されてます。彼らはマカオを皮切りに、マラッカ、インドのコチンを経てナポレオン幽閉の地として知られる南大西洋に浮かぶセントヘレナ島へと船を進め、ポルトガルの首都リスボンに上陸するのです。ここからスペイン、ローマへとヨーロッパを旅し、また帰国してきたのですから、いくらイタリア人のサポートがついたと云っても、この時代(1582年=天正10年)にタイヘンな偉業をなしたワケです。1585年(天正13年)、ついにローマ教皇グレゴリオ13世の謁見がバチカン宮殿「帝王の間」で許されます。ところが副使の中浦ジュリアンが熱病のためにここまで来ながら謁見できませんでした。ところが教皇は少し回復した中浦ジュリアンと別に単独謁見してくださり、教皇から特別な祝福をいただきました。しかしグレゴリオ13世は謁見の18日後に急死してしまうのです。グレゴリオ13世は最後の病床にあっても、ジュリアンの病気を心配されていたと伝えられています。下の画像はローマ教皇グレゴリオ13世に謁見した場面を描いた19世紀のフレスコ画です。このフレスコ画は、ローマにある同教皇の子孫宅で見つかったものです。1586年にドイツのアウグスブルグで印刷された天正遣欧使節の肖像画が残ってます。タイトルには「日本島からのニュース」と書かれています。ローマ教皇グレゴリオ13世の後を継いだ新教皇シクストゥス5世も、即位2日後に少年たちと会い、前教皇と同様に寵遇することを約束。聖ペトロ大聖堂で執り行われた戴冠式にも招待し、伊東マンショは、ミサで教皇が手をすすぐ際の補佐をする役を務めました。その後、ラテラノ教会へ行幸する新教皇の行列に、4人の使節も騎乗して参加しました。そのラテラノ教会へ向かう少年たちの絵が「ラテラノ教会行幸図」としてバチカン図書館シスト5世の間に残されています。イタリアの各地を見学した後、ふたたびリスボンに戻り、少年たちは帰国の途につきます。リスボンを出港したのは1586年(天正14年)。往路以上に長く困難な船旅でした。帰国の途上、彼らは信じがたいニュースに接します。少年たちを派遣した大名が次々と亡くなったのです。大友宗麟は1588年、チフスにかかり病死します。大村純忠は1587年に咽頭癌と肺結核で病死。悲惨だったのは有馬晴信で、「岡本大八事件」と云う朱印状偽造事件に関連して家康から切腹を命じられます。しかし、キリシタンであった晴信は自害を選ばず、妻たちの見守る中で家臣に首を切り落とさせたそうです。もっとショックだったのは織田信長の政策を継承し、キリスト教布教を容認していた豊臣秀吉が発令した「バテレン追放令」です。キリスト教宣教と南蛮貿易が禁制になってしまった。少年たちはインド国王の使節ということで何とか入国を許されたのが1590年(天正18年)。実に8年と5ヶ月の長い旅でした。出発したとき12歳の少年だった最年少の原マルチノも、もう20歳を超える青年となっていたのです。ど~云うワケかキリスト教禁止令を出した当の秀吉がローマから帰った少年たちに大変興味を持ったようです。聚楽第に少年たちを招き、熱心にヨーロッパの話を聞きました。そして使節の正使である伊東マンショに家来にならないかと勧めたと云います。彼は秀吉の申し出を丁重に断りました。少年たちは秀吉にあるモノを見せ、秀吉を喜ばせました。楽器です。かれらはスペインの貴族からクラヴィコードという楽器をプレゼントされてました。今のチェンバロに近いもので、ピアノの前身ともいうべき楽器です。クラヴィコードは音量が極めて小さく、楽器のそばにいる数人にしか聞こえない程度のものでしたが、秀吉はこの楽器がとても気に入り、何度も繰り返し演奏させました。これが功を奏して、上機嫌になった秀吉は使節の一行が日本に留まってもよいと許可を与えたのです。天正遣欧少年使節が持ち帰ったもうひとつは、もっと重要なものでした。「グーテンベルクの印刷機」、活版印刷機です。これによって日本語書物の活版印刷が初めて行われ、キリシタン版と呼ばれたのですね。他にも西洋絵画や海図、そして大型西洋馬であるアラビア馬1頭も連れてきました。この馬は聚楽第で秀吉に拝謁後献上されてます。伊東マンショは司祭になり、神学校で教えていましたが、1612年(慶長17年)に病死しています。千々石ミゲルは1603年にキリスト教の信仰を捨て大村家の家臣となって切支丹迫害に手を貸します。原マルチノは最年少でしたが、語学に長け、ローマからの帰途のゴアでラテン語の演説を行い有名になった人物です。彼は日本がいつか自由にキリスト教を伝えられるようになることを期待して1614年(慶長19年)国外に追放されることを選び、マカオで死んでしまいます。ローマで熱をだし、一度は教皇に謁見できなかった中浦ジュリアン。キリスト教禁止令のなか、司祭になって厳しい弾圧にもめげず1613年から20年間も潜伏して切支丹を励まし続けました。ついに小倉でとらえられ逆さ吊りという厳しい拷問にも屈せずに壮烈な殉教を遂げます。彼は苦しい刑罰のとき「われこそは日本人として始めてローマに赴き教皇から祝福をうけた中浦ジュリアンなり」と絶叫して死んだと云われてます。中浦ジュリアンは「肥前国中浦領主の中浦甚五郎の息子」と記録があります。当時の肥前国中浦城の城主だった小佐々兵部少輔甚五郎純吉が「中浦殿」と呼ばれていたことから、中浦ジュリアンはその息子の小佐々甚吾であると云う説があります。歴史にタラねばは禁物ですが、時代の歯車がチョット狂ってたら、彼らは困難な航海を乗り切って帰国したヒーローだったのに、時は彼らに味方しなかったのです。
Feb 27, 2023
コメント(4)
-

Z世代のジャズ
タレントのカズレーザーは「Z世代」という言葉は年配者が作った言葉で、Z世代と云う表現そのものが今時の価値観ではないと提唱してます。「今の価値観にアップデートしたいんだったらこう云う言葉は使わないほうがいい、古臭く見られます...絶対“Z世代”なんてダサい言葉使わないでください。昭和だと思われます」。確かに日本でこの言葉使いだした芝浦工大の原田教授も1977年生まれ、バリバリの昭和生まれやもんなぁ。と、云うワケできょうのタイトルが早くもダメ出しの対象に(笑)Z世代と云うのは、生まれた時からデジタル機器やインターネットが当たり前のように存在し、ウェブを日常風景の一部として利用している世代ですね。PCよりもスマホを日常的に使いこなし、生活の一部となっていて、ビデオ通話のZoomを多用することから「ズーマーズ(Zoomers)」とも呼ばれています。老害がZ世代と呼ぶ人たちは、2020年時点で世界人口の約1/3を占めてるそうです。で、このZ世代(まだ云ってる!)にとって音楽のジャズはどんなに映ってるのでしょう?ジャズの本場アメリカでは近年になってジャズが高級芸術と化し、ジャズ本来の自由な発想で音楽を追い求めるアーティストたちは、凝り固まったイメージとの格闘を強いられてるそうです。そんな...元々ジャズのルーツは、西アフリカの文化と音楽的表現、そしてアフリカ系アメリカ人の音楽の伝統にあるのに。ジャズの元祖、ニューオリンズ・ジャズなんて、ブラスバンドのマーチ、20世紀初頭にアメリカで流行したラグタイムやブルースなんかの即興演奏を組み合わせたものです。まぁ、そんなことはいいか。そんな硬直化したアメリカのジャズをあざ笑うかのように素晴らしいジャズ・デュオが登場してます。2000年生まれのフランス人鍵盤奏者ドミと、2003年生まれのテキサス州はダラス生まれのドラマーJD・ベックです。弱冠23歳と20歳ですよ~それで、このテクニックとクリエイティブさは何としたことでしょう!Nord Live Sessions: DOMi & JD Beck - Sniff彼女たちは1939年にニューヨークで創設されたジャズ専門のレコード会社で、ジャズ界屈指の名門レーベル「ブルーノート」からデビューしました。ドミはフランス国立高等音楽院やボストンのバークリー音楽大学で学んだ鍵盤の秀才です。一方、JD・ベックは10歳からドラムの演奏活動を、12歳でプロデューサーとして経験を積んできた早熟のドラマー。たちまちハービー・ハンコックやアンダーソン・パーク、サンダーキャット、フライング・ロータス、ルイス・コール、ザ・ルーツなど名だたるアーティストと共演。中でも2020年に開催された音楽、コメディなど何でもありのバーチャル・グローバル・イベント「Adult Swim Festival(直訳すると"大人の水泳大会")で、アリアナ・グランデやサンダーキャットとプレイした「Them Changes」や、ブルーノ・マーズ&アンダーソン・パークによるシルク・ソニックのシングル「Skate」を共作したことが大きな話題を呼びました。ニューヨーク・タイムズはこのデュオを「このふたりは、新しい音楽を私たちに届けるために地球に不時着した宇宙人かもしれない。彼らの音楽は、異常なほど複雑で超絶技巧であるが、"難しい"音楽ではない。キラキラしていて、執拗なまでにメロディックだ」と絶賛してます。今年2月6日に開催されたグラミー賞では、最優秀新人賞を含む2部門にノミネートされました。まぁ、音楽に小難しい理屈はいらんワケで、私は純粋にこのふたりの演奏が好きですね。私のようにZ世代以前の「Y世代」や「ミレニアル世代」とも違い、「X世代」よりまだ以前の世代で、もうワケ分からん世代の人間でもいいものはいい。私らノンベンダラリと生きてきたのと違って、今の世代の方がコスパやタムパ(タイムパフォーマンス=費やした時間に対する満足度)の悪いお金の使い方を嫌う代わり、自身が価値を感じるものや心を動かされるものに対してお金を惜しまない現実的な生き方をしてますしね。それに環境問題や人種差別問題に対する関心も私ら世代より強いしね。
Feb 26, 2023
コメント(5)
-

腕木通信
18世紀半ば~19世紀にかけて起こった産業革命は、技術力の驚異的な進歩とともに社会構造の変革をもたらしました。イギリスで最初の産業革命がおこり、これが近代とそれ以前との分水嶺になったのですね。これを皮切りにベルギー、フランス、アメリカ、ドイツ、ロシア、日本と次々に産業革命が波及していったのです。この産業革命によって、新たな情報技術が生み出されると云ったら、可能性がもっとも高かったのは本家のイギリスのハズでした。ところが近代的な情報技術はフランスから出てきたのです。それはクロード・シャップと云うフランスの発明家によってもたらされました。彼はもともと聖職者だったのですが、フランス革命が勃発すると、身分階級だった聖職者への弾圧が厳しくなったのですね。それで職を捨てて故郷に戻るワケですが、もともと興味あった物理学の知識を仕事に結びつけようとしたのです。そうしてシャップは、1794年に人間の視覚にたよる新しい通信技術を発明するのです。それが「腕木通信」と呼ばれるもので、19世紀半ばまでにフランス政府が整備した腕木通信のネットワークは5,769km にも及びました。イギリスでも腕木通信に倣って同種の通信技術を開発し、双方の通信網は北欧諸国、プロイセン、ロシア、スペイン、ポルトガル、アルジェリア、インドなど世界中で1万4,000km を超える規模へと発展したのです。腕木通信に電気は使いません。と、云うより使いようがなかった。なぜならシャップが腕木通信を発明した当時、最初の電池「ボルタ電池」はまだ発明されてなかったからです。腕木通信の通信方法は手旗信号とよく似ています。腕木通信機と呼ぶ3本の腕木からなる装置を建物の屋上に設置して利用するのですね。建物の屋上には4~5m の1本の柱が立ってます。その柱の先端に「調整器」と呼ばれる4m 程度の腕木が中央で固定されてます。この調整器は可動式で、縦横斜めと指せます。調整器の両端には、「指示器」と呼ばれる長さ2m 程度で可動式の腕木の片端が固定されています。指示器は、7ヶ所の位置を指せるようになってるのです。つまり、この調整器による水平・垂直の2ヶ所と指示器の7ヶ所の指す位置によって信号を作り出し、これを遠隔地から観察して情報のやりとりをする仕組みなんですね。そのため、腕木通信の基地は約10km ごとに設置して、望遠鏡で離れた腕木通信機の信号を読み取ってました。そして、その情報をまた先の基地に転送するのですね。フランス通信社の創業者シャルル=ルイ・アヴァスは腕木通信のメッセージを解読して、どこよりも早い新聞の速報記事を出すことでフランス通信社を発展させました。アレクサンドル・デュマの小説「モンテ・クリスト伯」の中では、策謀もくろむ主人公が腕木通信の通信塔を訪れ、通信士を買収して捏造情報を送信させるシーンがあります。しかし、腕木通信で最も有名なのはナポレオンとの関係でしょう。1799年のナポレオン・ボナパルトが総裁政府を打倒した「ブリュメール18日のクーデター」では、腕木通信網全線へナポレオンのメッセージが流されました。フランス革命戦争(ナポレオン戦争)期間中の1801年に、フランス東部の都市リュネヴィルでフランスとオーストリアが締結した講和条約「リュネヴィル講和条約」のときは、リュネヴィルへの通信回線増設のナポレオン命令に対し、シャップはこれを2週間で完成させました。ナポレオンがイタリアを支配するようになると、アルプス山脈を越えるリヨン-ヴェネツィア間の通信網が2年あまり費やして完成します。そしてライプツィヒの戦いに敗れたナポレオンが、1815年に流刑地のエルバ島を脱出しフランスへ上陸すると、その行動が腕木通信で即日パリへ通報されました。腕木通信が衰退した原因は、電信の発明です。情報技術が変わるときは先ず否定的な意見が支配します。スマホが登場したとき、携帯電話で用足りるやんか!でしたが、今ではスマホなくして生活が成り立たない。電話が登場したときは、「話をするための機械なんて、そんなものは役に立たない」と反対意見。そして電信が登場したときは、「電信なんて電線が切られたらどうするんだ」と批判する人が。しかし、腕木通信は電信に駆逐されていったのです。経営学者のドラッカーは、イノベーションを実現するうえで予想もしてなかった成功に注目すべきと説いてます。インターネットが登場したとき、現在のインターネットの普及をどれだけの人が予見したでしょう。そして電信の普及はフランスではなく、イギリスが先んじていました。当時、イギリス資本の電信線は世界全体の70%に上ったのです。1884年にベトナム領有を巡るフランスと清との争い「清仏戦争」が勃発しました。この戦争で最終的にはフランスが領土領有を達成したためフランスの勝利と考えられていますが、ベトナム北東部、中国国境の町ランソンでは、平静な判断力を失ったフランス軍がランソンを自ら捨てて敗走する事態が発生しました。フランス軍部隊は最低限の物資しか持ち出さず、我先に逃げ出していったと云います。このとき、フランス軍の敗走をフランス政府よりもイギリスが先に知ったのですね。それが電信の効用でした。ロンドンが金融の先端になったのも、情報が一番早く集まるようになっていたからです。電信を英語で「テレグラフ(telegraph)」と云いますが、テレグラフと云う言葉、もともとは腕木通信に対して使われてたのです。意味はギリシャ語の「テレ・グラーフェン(遠くに書くこと)」と云う言葉に由来しています。現在、腕木通信のことは「セマフォア(semaphore)」と呼ばれるようになりましたが、この言葉は視覚通信機の固有名詞だったものが変化したものです。セマフォア、聞いたことりません?鉄道の信号機をセマフォアと呼ぶのです。鉄道の信号機自体が、なんか腕木通信機の構造と似てますね。シャップが腕木通信の機構開発するとき、腕木機構の複雑な動作を可能にするため天才的な時計師(アブラアム=ルイ)ブレゲが協力してたのですね。あのトゥールビヨン機構を有した超高級腕時計のブレゲです。
Feb 25, 2023
コメント(3)
-

シクロビア
南アメリカ大陸で唯一、太平洋と大西洋、2つの大洋に面した国「コロンビア」。どんな印象をお持ちですか?私にはとにかく麻薬と殺人の国って印象しかない。それにはリュック・ベッソンが監督して2011年に公開した映画「コロンビアーナ」もたぶん影響してると思います。映画はコロンビアの首都ボゴタでマフィアの幹部である父が、別のマフィアに殺されて、命からがら逃亡した少女が成人して殺し屋になり、父を殺したマフィアに復讐すると云うストーリー。この作品を観ると、コロンビアなんて警察の手が及ばないマフィアだらけで、とても出歩くことができない。いつ、事件に巻き込まれるか知れたものぢゃない危険極まりない国の印象。事実、コロンビアの麻薬テロリスト「メデジン・カルテル」の創設者にして、アメリカで自身の組織した麻薬カルテルによるコカインの取引を独占したパブロ・エスコバルを生んだ国です。彼は麻薬のみならず、住民はおろか、警官、裁判官、政治家の殺人や暗殺にまで手を染め、コロンビアを殺人が跋扈する国へと変えた張本人です。そしてアメリカに持ち込んだ麻薬によって、推定640億$(約8兆5,700億円)の資産を蓄え、史上最も裕福な犯罪者と云われた人物です。エスコバルは、首都ボゴタに次ぐ第2の都市、故郷のメデジンでコロンビア国家警察率いる特殊作戦部隊と銃撃戦をおこない射殺されました。エスコバルの死に伴い、メデジン・カルテルは崩壊しましたが、コカイン市場は敵対していたカリ・カルテルが代わって独占するようになりました。コロンビアの麻薬戦争は80年代~90年代にかけてですが、それ以前は政府軍、左翼ゲリラ、極右民兵の三つ巴内戦が50年以上も続きました。世界で最も危険な国の1つだったのですね。ところが21世紀になって、政府の抜本的なテコ入れが功を奏して、劇的な治安の回復に成功したのです。いまではアメリカ大陸における主要国と位置づけられているほどに。それでも郊外や、観光地が少ない地域に行くとゲリラ集団が活動しているとこがまだ存在してます。それに加えて、隣国ベネズエラの経済危機で、コロンビアへ逃れてくるベネズエラ難民が急増。その数は100万人単位にもなります。このベネズエラ難民による犯罪が新たな社会問題となってきてるのですね。そんなコロンビアの首都ボゴタは、平日には160万台の自家用車、5万台のタクシー、9,000台のバスがごった返す騒々しい街です。ところが、日曜日と祝日になると様変わりするのですね。午前7時~午後2時まで、ボゴタの大通りとハイウェイが広範囲にわたり人々に開放されるのです。自転車、ローラースケート、キックスケーター、車椅子、スケートボードなど、動力を使わない乗り物が自由に行き来できる街に変貌します。この取り組みは「シクロビア(自転車道)」と呼ばれ、推進したのは1994年に選出されたアンタナス・モックス元市長の下で市民文化を担当したポール・ブロムバーグと云う人物です。封鎖された道路を自転車で走るだけでなく、道路脇で起こなわれるレクリエーションも重視される、穏やかな「自転車天国」を目指したのです。これはモックス元市長の施策の一環でした。市長は街を変えるには市民ひとりひとりが変わっていく必要があると考え、まず交通マナーの遵守を訴えました。モックス元市長はピエロを街に送り、マナーを守った人に白いカード、守らなかった人に赤いカードを渡すという変わったPRを行ったのです。最初は懐疑的だった市民も、やがてモックスの愚直な訴えに耳を貸すようになります。さらにレストランの深夜営業の禁止、家庭内暴力をなくそうという運動、市民の武装解除などを進めていったのです。モックス元市長の施策により、水の使用量が40%減少し、7,000のコミュニティセキュリティグループが形成され、殺人率が70%減少。交通事故死者は50%以上減少し、飲料水がすべての家に提供されました。そして下水道は全家庭の95%に整備されたのです。後をついだ1997年に選出されたエンリケ・ペニャロサ市長は、モックス元市長の思想をさらに発展させ、スタッフに多くの民間人を登用して新交通システムの導入を始め、自転車道の拡充、そして公園や図書館の整備を強力に推進したのです。こうしてボゴタを機能的な都市に変えていくと同時に、交通事故による死者や殺人事件の犠牲者を大幅に減少させることによって、ボゴタの街を変貌させたのですね。エンリケ・ペニャロサはこう発言してます。「途上国の都市における移動の課題は、お金や技術の問題というよりも、平等性・公平性の問題なのです」「80人が乗ったバスは、1人乗りの車より80倍も道路を利用する権利があります。100人乗りのバスは、1台の車の100倍の道路使用権があるのです」「私たちはバスのスペースだけのために戦ったのでなく、人間のスペースのために戦ったのです」「魚が泳いだり 鳥が飛んだり、鹿が走ったりするように、人間にも歩く必要があります」「先進的と後進的な都市の本当の違いを生み出すのは、高速道路や地下鉄ではなく、歩道の設備がちゃんとなされているかどうかなのです」「人々が人間としての尊厳を保てるような場所を作るため、30$の自転車に乗っている市民は、30,000$の車に乗っている人と等しく平等なんです」「我々は70km の自転車専用道を、世界でも有数の過密都市で造ることができたのです」「とても貧しい近隣地域の1つに、豪華な自転車歩行者専用道路があります」「非常にローコストでシンプルに、数百km のバス・自転車・歩行者道も含めての通りを作ろうと云うものです」「築き上げていく都市は、未来の数百万の人々の生活の質さらには幸せを決めるものになります」つまり、ふたりの市長は「民主的平等」のために尽力したのですね。休日になるとシクロビアに変わる道路は全長120km 余り。日曜日には150万人ものボゴタ市民が自転車などで街に繰り出すと云います。食べるのも自由、踊るのも自由、人間観察するのも自由。シクロビアのあちこちに「レクロビア」と呼ばれるレクリエーション・スペースがあり、ほぼ毎週、ズンバ(コロンビアのダンス・エクササイズ)のレッスンの後、サルサバンドの素晴らしい演奏が始まります。「最も重要なのは、シクロビアを利用する人々が生み出す社会構造です」と、シクロビア・プログラムの運営に携わったサルミエントは話します。「シクロビアは自動車が人に道を譲る時間です。私たちの目的は、街の公共空間を市民のものにすることです」。今では世界中の都市計画者や先進的な政治家がシクロビアを取り入れようとしています。しかし、何十年も内戦が続き、都市の規律を欠く国の首都から、どのようにしてこのアイデアが生まれたのでしょう?1976年、富裕層が暮らす地域では、歩道に乗り上げて駐車する人が大勢いました。信号機にいたっては、無視するのが当たり前のような状態だったのです。そんな時代に、ある市民グループが日曜日の自転車道という前例のない試みを提案しロビー活動を行ったのですね。「自転車はそれまで、薬の配達くらいにしか使われない乗り物でした」とブロムバーグ。「しかし、日曜日の自転車道が提案されたとき、ちょうど健康意識が高まるとともに、若者層が台頭しつつありました。だから、このアイデアが受け入れられたのです」。「コロンビアは階級社会だが、シクロビアは平等主義だ」とサルミエント。「着ている服や社会階級など誰も気に掛けていません。すべての人が歓迎されて、すべての人が平等です」「止められた自転車を見れば、それがよくわかる。さび付いたガタガタの自転車と、高級そうな自転車が並んでいる」「都市の概念を変えたのです」。
Feb 24, 2023
コメント(5)
-

アードウルフ
きょうは日本であまり馴染みない生き物を紹介しましょう。小さなオオカミ「アードウルフ」です。別名「ツチオオカミ」。オオカミと云っても、分類としてはハイエナと同じ系統のハイエナ科に属します。(と云っても、他のハイエナ類とは大きく異なった形態や生態をもつ小型のハイエナです)アードウルフという名前は、アフリカーンス語とオランダ語で「大地のオオカミ」を意味します。それらは主にアンゴラやウガンダ、エチオピア、南アフリカ、モザンビークなどアフリカ東部および南部の低木地に生息しています。実際のアードウルフを見ていただきましょうかね。なかなかカワイイお顔してます。ツチオオカミの別名は、この生き物が夜行性で、日中は地中の巣穴で眠り、夜になると餌を探しに出てくるからです。そして面白いことに、巣穴を掘るのは自分ではなく、ツチブタやトビウサギが掘って放棄された巣穴を利用しているのですね。大人のアードウルフは長さ (尾を含めて) 約55cm ~80cm 、身長は40cm ~50cm で、体重は7kg ~10kg ですから、小型の生き物の部類です。そして歯が貧弱で隙間も大きく、成獣では24本まで抜け落ちることも多々あるそうです。野生の生き物で歯が貧弱ってのは致命傷では?ところがアードウルフの主食はシロアリなんです。シロアリが採食する音を頼りに探し、兵隊アリが発する化学物質も感知して、非常に長くて粘着性のある舌を使って1晩に最大20万匹のシロアリを食べるのです。生後3ヶ月でシロアリを食べられるようになるそうです。アードウルフは終生、一夫一婦制をつらぬきます。一生同じパートナーと付き合うと云うことです。赤ちゃんが生まれると、例えば母親がご飯食べに巣穴を離れると父親が巣穴に残ると云う習性もってます。ありがたいことに、個体数は現時点で非常に安定しているのですね。国際自然保護連合(IUCN)によって「最も懸念されていない」と評価されています。地球には、私たちがまだまだ知らない生き物がワンサカいますが、少なくとも人間の手で絶滅なんてことないよう自然のままの環境を残しておかなくてはね。もう、人類は折れて曲がるほど他の生き物を絶滅させてきたのですから。
Feb 23, 2023
コメント(6)
-

天皇陛下のインターフォン
昔々、叔父がとってもチッチャなブラウン管TVを持っていました。まだアナログ時代も真っ盛り、モノクロ放送の時代のことです。それは1960年にSONYが開発した、世界初のポータブルトランジスタテレビでした。叔父がこのTVを買った時期は不明ですが、60年代初頭に間違いないでしょう。このTVが発売されて5ヶ月後にはTVのカラー本放送が東京ではNHK、日テレ、ラジオ東京(TBS)、大阪ではNHK、読売TV、朝日放送で開始されました。「日本レコード大賞」がまだ第2回目の年に発売されたTVです。そのTVの名称は「TVB-301」。このTVの画面サイズは8インチですから、今だったら小型のタブレットにほぼ近いですね。このTVの開発でSONYの技術力が一気に世界に認められたワケです。なんですが...売れませんでした。なにしろTVと云えば、茶の間に据え置くことが常識で、とにかく大型が良しとされた時代。だいたい14インチ~20インチTVがもてはやされた頃です。さっぱり売れなかったSONY「TVB-301」。それから2年後にTVB-301よりさらに小さい5インチのマイクロテレビ「TV5-303」をSONYは発売します。いちど小型TVは市場がないと分かってるのに、さらにバージョンアップして勝負を仕掛けてきたワケです。この時代のSONYは技術力もさることながら、開発意欲旺盛だったのですね。このTV5-303には数々の逸話が残されてます。TV5-303の開発は極めて秘密裏に他社に情報が漏れぬよう最新の注意が払われてました。いよいよTV5-303の完成間近と迫った1962年3月、昭和天皇、皇后両陛下のSONY工場見学が決まったのです。この工場見学で、まだ秘密のベールに覆われているマイクロテレビ「TV5-303」を両陛下にお見せしたのですね。そのときSONY側から「これは、まだ世の中に出ていませんから...」と申し上げたのが、後になって週刊誌の記事になりました。「天皇に口どめ」という見出しで。同年4月に工場見学した歌手フランク・シナトラは、このTVをたいへん気に入って「ぜひ譲ってほしい」と申し入れましたが、アメリカと日本ではTVの周波数が違います。「アメリカチャンネルのものができたら、必ずお届けします」と約束し、10月にアメリカでも発売が決まるとパラマウントの撮影所を訪れてシナトラと会い、この約束をはたしました。アメリカでのTV5-303発売に先駆けて、SONYはニューヨークのマンハッタン5番街にショールームを開設します。そして1日7,000人以上の人たちがこのショールームを訪れTV5-303を目にしたのです。10月の発売と同時に、それこそアッという間もなく売り切れてしまい、アメリカからのオーダーに応えるために、東京では出来るそばから船積みしても、焼け石に水の状態が続いたのです。ついにSONYは大型輸送機をチャーターして、このTVをアメリカへ空輸するまでになりました。TVは茶の間に据えておくのが常識の時代に、パーソナル使用を打ち出した先進的なTV5-303。このSONYの先駆性はなにもTVに限ったものではありませんね。1950年(昭和25年)には日本初のテープレコーダーを開発し、1955年(昭和30年)には日本初のトランジスタラジオを発売しています。1961年(昭和36年)になると世界初のVTR(ビデオテープレコーダー)を発売し、1979年(昭和54年)には携帯型カセットプレイヤー「ウォークマン」を発売するのです。ウォークマンは1995年度に生産累計が1億5,000万台に達してます。そんな先駆的なSONY、今では想像すらできない商品開発も行っていたのですね。戦艦ミズーリで日本が降伏文書に調印して第2次大戦が終結した1945年(昭和20年)、この大混乱の年に当時「東京通信工業」と呼ばれてたSONYは記念すべき失敗作第1号を開発したのです。ちなみに1945年の1月1日元旦には、アメリカのモンタナ州に日本軍が放った「風船(気球)爆弾」が落下してます。1945年にSONYが開発したのは何と「電気炊飯器」です。終戦の年に電気炊飯器の開発をやってたなんて信じがたいですよね。第一、この時期は食糧難で日本人はお米そのものが手に入りづらいのに。この炊飯器、木のおひつにアルミニウムの電極を張り合わせただけのものです。米軍の爆撃でインフラ破壊が激しく電力の安定供給がないし、水加減やコメの種類によって芯ができたりお粥のようになったり。みごとな失敗作で、発売には至りませんでした。終戦の翌年(1946年)に発売されたのは「電気ざぶとん」。これは大成功作だったのですが、SONYの創業者"井深 大"は東京通信工業の名前で売るのがためらわれて「銀座ネッスル(熱する)商会」と云う名称で売り出されたものです。この商品は終戦直後の物価高騰で社員の生活が苦しくなり、現金収入を得ようと開発された苦肉の商品なんです。温度調節機能もない簡単な構造で、今から見たらとても電熱マットとは云い難いのですが、これが売れに売れたのですね。社員の家族総出でミシンがけなどの下請け作業をしなければならないほどだったと云います。こんどはSONYのイメージからは想像できないもの。「鉄道模型」です。1960年代に「Nゲージ」と云うレール間隔(軌間)が9mm の鉄道模型規格が入ってきました。日本でもこの規格の鉄道模型を製品化しようとするメーカーが現れてきたのですね。1964年ごろにオモチャメーカーの「タカラトミー」が「高級電気玩具 OOO(スリーオー)ゲージ 新幹線 夢の超特急セット」を発売したのが最初ですが、これだけで立ち消えになりました。続いてSONYが鉄道模型専門の子会社「マイクロトレーン」を設立し、エレクトロニクス技術を生かした鉄道模型の量産を計画したのです。モデルになったのは、ED75形交流用電気機関車で、当時、最新鋭の機関車でした。真鍮製の車体、スハ43系客車2両に線路、パワーパック、レイアウトマットなど一式がセットになっていたました。が、コストがかかり過ぎて、試作品のみ約200台作られただけで、発売に至らず「幻の鉄道模型」として知られるようになった商品です。マイクロトレーン社は1965年に解散しました。そして最後に今日のタイトル「天皇陛下のインターフォン」について。1961年(昭和36年)、東京通信工業(SONY)は宮内庁から「(昭和)天皇皇后両陛下と侍従、女官を結ぶ使いやすいインターフォンを」と依頼を受けます。その背景には、世界で最も新しい機器を作ることができるのはSONYだからと宮内庁の信頼が古くからあったからです。これに携わったのはSONY創成期の基礎技術を確立させ、後にソニー専務になった技術者 木原信敏。インターフォンはハウリングを起こしやすく、ハウリング防止のためボタンを押してる間だけ通話可能なプッシュトーク方式を採用。全トランジスタ式で、3ヶ月程度で完成して吹上御所に向かい、両陛下の寝所に自身の手で設置しました。木原の開発した製品はいくつも献上されており、1950年に日本初のテープレコーダー「G型」、1957年には皇太子殿下(現 上皇)に「TC-552」ステレオレコーダーも献上されています。
Feb 22, 2023
コメント(6)
-

環境保護団体とは
以前、ユニセフ(国連児童基金)に寄付したら、追加の寄付依頼の手紙が繰り返し届くようになりました。寄付は強要されるものではないし、ウザといなぁと思ってたら、例の悲惨な子どもたちを映し出したTV CM放映しだして...あのCM見せられて、いい気持ちの人は皆無でしょう。なんか感覚が違うのですよね。ユニセフは紛れもない国連の補助機関だし、毎月1,000円の「マンスリーサポート」CMに登場する子どもたちも実在してるらしい。ユニセフで受領した寄付のうち、ユニセフ本部に送られるのが82.6%、広告など広報宣伝活動費にあてられるのが17.4%。つまり毎月1,000円寄付したら、そのうちの174円は次の寄付をつのるための広告費用にまわされるのです。この配分が是か非かは寄附者が判断するところ。私が疑問に思ってる「マンスリーサポートCMに、なにも悲惨な境遇の子どもたちを登場させなくっても」と云う考えも、受けとる人それぞれですからね。例えば「国境なき医師団」の活動は自ら危険地域にまで赴いて医療活動をおこなっており、まったく尊敬に値する行為なんですが、この活動によってウクライナ侵攻がとまることはないですね。それは政治の世界だからです。ユニセフの活動も、今、このとき悲惨な境遇の子供をひとりでも救う尊い活動ですが、あくまで一過性であって、その国の政治体制が根本的に変わらない限り同じことの繰り返し。それでも見過ごすことできないから、活動を続けてるワケですが、これとは別にもっと大局的にその国の体制を変える努力と両輪ではたさないとイミないワケです。それをやれるのは国連しかないワケですが、国連にしても、例えばシリアのアサドが国民を大量虐殺し、680万人もの国内避難民だしていても、内政干渉になるから経済封鎖くらいしか打つ手がない。だいたい各国の国連派遣員は自己保身ばかり気にしてる役人だらけで、こんな人たちではちゃんと機能するワケないと、昔、知り合いだった国連に派遣された人から聞きました。厄介なのは、こうしたボランティア組織を騙る詐欺行為が多いってこと。コロナ絶頂期には「○〇円払えば優先してワクチン接種が受けられる」なんてニセ ユニセフサイトまで出現しました。実際に日本ユニセフ協会を名乗った偽アカウントも存在するそうですから、寄付を志す方はよくよく見極めることが必須なんですね。環境保護団体で見ると、捕鯨問題で有名な「グリーンピース」がありますね。グリーンピースは目的達成のために直接行動を行う組織として有名で、その過剰な運動に対してエコテロリズムと批判されることも多々あります。しかし、主義主張のために暴力もいとわないのはグリーンピースの専売特許ではなく、例えばトランプ支持者による連邦議会議事堂襲撃や直近では“ブラジルのトランプ”と呼ばれるボルソナロ前大統領の支持者による連邦議会や大統領府の襲撃事件などもその部類です。日本でも60年代の全学連を中心にした学生運動でも暴力がまかり通ってました。もっと大きく云うなら、世界中で起こってる反政府組織による破壊活動の中にはこの部類のものも多くあるワケですね。そもそもグリーンピースの成り立ちは1971年にアリューシャン列島のアムチトカ島で行おうとしているアメリカの地下核実験に反対するために設立されたものです。それが捕鯨問題を含む地球環境保全まで発展したのは、バンクーバーのグリーンピースに接近した鯨類学者のポール・スポングがクジラをめぐる問題について注意喚起を行ったときからです。メンバーのポール・ワトソンらが主力になり、1975年から捕鯨船の目の前に高速ゴムボートを繰り出して捕鯨に反対するキャンペーンを開始したのです。その後、毛皮を目的にしたアザラシの乱獲問題などにも手を広げていったのですね。ところが行動の率先役ポール・ワトソンは、「グリーンピースは軟弱に過ぎる」と1977年に袂を分かち、エコテロリスト(環境テロ団体)の筆頭格「シーシェパード」を設立してしまったのです。発行部数がヨーロッパで最も多いニュース週刊誌、ドイツの「デア・シュピーゲル」は、グリーンピースの意思決定が「グリーンピース世界会議」の12人の大選挙人に握られており、一般メンバーは運営の意思決定に関わることはできない。収入の24%以上を上納できる資金力のある支部代表のみが意思決定を行っていると報道してます。グリーンピース・ノルウェーの会長を2年務めた後、追放されたビヨルン・オカーンは「グリーンピースの金が環境のために使われていると考えるのは間違っています。幹部たちはファーストクラスに乗って旅行し、最高級のレストランで食事し、優雅なエコ・セレブの生活をしている。クジラで大騒ぎをするのは、それが儲かるからにほかならない」と主張してます。グリーンピース創設メンバーの1人で、15年間会長をつとめたパトリック・ムーアは、後に別の団体「グリーンスピリット」を興して原発に賛同する立場になりました。グリーンピースの本来主張が原発反対なのに、180度の転換です。ムーアによれば、「ロックフェラー財団など50の基金が、原発に賛同する一方で環境保護に関心ありと云うポーズのためにグリーンピース本部に資金援助していると。アイスランドのジャーナリスト、マグヌス・グドムンドソンは「グリーンピースは環境保護団体のような顔をしているが、実態は政治権力と金を追求する多国籍企業です」と述べています。さらに資金の使い道は、一般会員には全く知らされていないのですね。年次会計報告がされてないのです。つまり、どんな組織も大きくなれば大きくなるほど、構成する人間によって趣旨が歪められていく。もっとも卑近な例が宗教組織に関わる問題ですね。このように組織の名目と実態がかけ離れてる例は枚挙にいとまがないのですね。例えば最も有名な「世界自然保護基金(WWF)」。アフリカの野生生物を絶滅の危機から救うため発足した団体ですが、今ではモンサントやコカコーラ、シェブロンなど世界的な多国籍企業から巨額の資金援助を受けており、それらの大企業の利益のために、自然保護よりもむしろ自然破壊に関与していると告発までされる始末です。また、WWFは一般市民や企業からの寄付金の使途について、その8%を管理費用に使い、他の多くの部分を活動費に使用していると述べてます。ところが、この「活動費」の中には、スタッフの人件費が隠されているのですね。WWFは5,000人もいる正規スタッフへの給与だけで寄付金の50%を食いつぶしており、最高幹部クラスの報酬にいたってはアメリカ大統領の俸給40万$(約4,200万円)を上回る50万5,000$(約6,000万円)にのぼる給与を受け取ってます。世界には「国際自然保護連合(IUCN)」「グリーンクロスインターナショナル(GCI)」「ナショナルトラスト」「ウォーターエイド」などさまざまな自然保護団体がありますが、こうした団体が本来趣旨を曲げず地道に活動してくれないと、せっかくの寄付が生かされないことになります。それは「アムネスティインターナショナル」や「セーブ・ザ・チルドレン」のような人権保護団体でも同じこと。そのためには寄付側も公式HPなどしっかり確認して「信頼できるか団体か否か」を判断することが大切ですね。
Feb 21, 2023
コメント(6)
-

アメリカ人とプール
2020年に公開されたウィル・スミス主演の映画「バッドボーイズ フォー・ライフ」にウィル・スミスが相棒のデカ"マーカス(マーティン・ローレンス)"の家にいって、マーカスの安物のプールでくつろぐシーンがでてきます。安物のプールと云うのは、よく映画なんかに登場する典型的なアメリカ家庭の「家+プール」ではなく、庭に置いた「ビニールプール」なんです。アメリカの1戸建て用プールには「イン・グラウンド(in-ground)プール」と「アボーブ・グラウンド(Above ground)プール」があります。要するに地面の「上」か、「下」かってこと。私たちがアメリカの家庭でイメージするのはイン・グラウンドプールですが、実はアボーブ・グラウンドプールを設置してる家庭も結構多いらしい。なんか私たちは地面に置くプールと云うと、お子ちゃま用のビニールプールを連想しがちですが、アボーブ・グラウンドにはかなり大きなプールもあるらしい。遠い昔、私がロスに行ったとき、到着日だけはダウンタウンではなく空港周辺に用事があって、空港のヒルトンに泊まりました。部屋は狭いし、日本のビジネスホテルに毛が生えたようなホテルです。そんなチンケなホテルにも、ちっちゃいながらもプールがあります。見たら、フメリカ人がすずなりで日光浴してる。誰も泳がず、ただ漫然とプールのデッキチェアーに寝そべってるだけ。性質的にアメリカ人は買い物が好きで、欲しいものは待たずに買う人が多い国民性です。背景にはクレジットカード社会のため大きな買い物はリボ払いで払う文化があるからです。教育費などでもローンを組む傾向があります。反面、アメリカ人は安物が好きで、勢いに任せてなんて買い物はしませんね。日本に来るアメリカ人観光客のサイフも固いハズです。100均で買い物するアメリカ人もよく見かけますね。私が見たロスのヒルトンのアメリカ人たちも、日光浴が好きってこと以上に、タダのプールだったらムダなお金を使わないで過ごせることの方が大きかったように思います。なんとなくアメリカ人=プールってイメージ強いですよね。それも公共のプールではなく、自宅にプール設置してる家庭が多い。アメリカは大して金持ちじゃない家にもプールがよくあります。自宅にプールの価値基準が日本人と違うので、とやかく云えませんが、日本人だったら公共のプールに行った方が自宅プールの管理費や掃除のこと考えたら合理的だと考えるのに、そうではないんですね。アメリカのプール設置業者の広告を見ると自宅にプールを持つメリットをこう表現してます。・プールサイドでの誕生日パーティー、家族の集まり、特別な行事など、一生の思い出に残るものが可能です。・プールは家の価値を高めることができます。・公共のプールに行くときは、荷物をまとめ、食べ物を準備し、忘れ物がないことを確認してから、車で行かなければならない。ドアのすぐ外にプールがある場合は、何かを忘れた場合でも、車で家に帰る必要はありません。これには掃除のことなど、これっぽっちも触れられてませんな。アメリカに駐在して、プールつきの家をレンタルした日本人によると「プール掃除は週1で、それを怠るとすぐにため池状態。薬が入ってるので蚊の発生は無いけど、周りの木の葉っぱとか、虫の死骸とかゴミがどんどん落ちてくる。鯉や金魚をここで泳がせようか?と真面目に思った」(笑)ど~やらアメリカ人も夏は泳ぎますが、その外の季節はただ眺めるだけのようです。そしてプールを持つと、メンテナンスが大変。水を入れるのに丸1日水を出しっぱなしにするので、水の取替えは1年に1回位。昔は、水は定額制だったので使っても使わなくても同じ料金でしたが、今はメーターで使った分だけの水道料金を請求される町が多いそうな。掃除などは前述の通りですが、お金持ちはメンテナンスを業者にやらせているようですね。プールのメンテナンス業者の広告を見ると「フルクリーニングサービス」から「化学物質のテスト」「設備機器のモニタリング」「壁、階段、ベンチのブラッシング」など多岐に渡ってます。もうひとつのナゾは、なぜアメリカ人はプールで浸かっているだけで泳がないのか?浸かるならまだしも、プールサイドで日光浴だけって人もワンサカ居る。アメリカでは、こんがり日焼けした肌は健康的、裕福というイメージが根付いているのですね。白人が、日焼けしていると云うことはそこそこの稼ぎがあり、リゾート地へ行き肌を焼くだけの余裕がある。つまり人生楽しんでいる富裕層という見方らしい。そして太陽にあたるとビタミンDが体内で生成されるので、積極的に太陽をあびることで健康を維持しようとしているらしい。それって、紫外線の過剰摂取で前がん症が発症するってことを無視してる?だいたい黒いのがよいなら、黒人みんなOKぢゃないか!
Feb 20, 2023
コメント(6)
-

あなたのキスを数えましょう
小柳ゆき、昔、大ヒットしましたなぁ。別に根拠がないのに私の中では小柳ゆき と 久保田利伸ってのは同列なんですね。小柳の「あなたのキスを数えましょう」ヒットしたのが1999年(平成11年)。一方、久保田がナオミ・キャンベルとコラボした「LA・LA・LA LOVE SONG」のリリースは1996年(平成8年)。確かに同じ時代には変わりないけど、別にふたりが音楽で交流あったって話も聞かないのに、私にはなぜか同列。小柳って、今年で41歳ですが、まだ独身で現役を続けてます。あれだけ大ヒットしたのに、突然のように消えたのは2005年の渡英が影響してるのですね。しかしロンドンで過ごしたのはたった4ヶ月。仕事もせずコンサートばかり行ってたとか。彼女をハーフと云う人がいますが、完全なガセです。埼玉は大宮出身の純粋な日本人。中学校時代、剣道部に所属してて、ソウルフルな発声の基礎はここで鍛えられたと云います。45週連続チャートインするというロングヒットを記録した「あなたのキスを数えましょう」はデビュー曲なんですね。その後もシングル「愛情/can't hold me back」や「be alive」が大ヒット。2nd オリジナルアルバム「EXPANSION」はミリオンセラーになったけど、やっぱ小柳と云うと「あなたのキスを...」のイメージが強すぎる。あなたのキスを数えましょう~You were mine~ 小柳ゆき♪散らかった床の上 うずくまり膝を抱いた守れない約束がカレンダー汚してる...この曲、失恋がテーマですが、実際に小柳が失恋直後にレコーディングしたらしいですね。作詞は中島美嘉の「LIFE」などを作詞した高柳恋。作曲と編曲は稲垣潤一の「Misty Blue」や今井美樹の「頬に風」の中崎英也。この曲は祖父がイギリス人で、5歳のときボストンに移住、香港に戻った後、女優や歌手、番組プロデューサーをやってる陳慧珊によって広東語でカバーされました。こっちのタイトルは「我還記得我是誰」。ちなみに久保田利伸もああ見えて純粋な日本人ですよ~ただ家族そろってファンキーなキャラクターで、八百屋さん営んでる父親はお客さんが来るとフィンガーチップス鳴らしながら「らっしゃい」と云ってたそうです。久保田の音楽の原点は中学から高校時代にかけて毎日聴いていたスティーヴィー・ワンダーなんですな。歌手の"JUJU"とはニューヨーク在住時代からの知り合いだそうです。私が通ってるリハビリ施設の女性スタッフに久保田を知ってるか?と問うたら「知らない。名前も聞いたことない」。「え~90年代後半からヒット飛ばした歌手やでぇ~」「あのう...私、2001年生まれなんです」(笑)
Feb 19, 2023
コメント(5)
-

シーフードいろいろ
魚を生で食べる国ってのは日本以外では、中国や台湾、オランダ、ハワイ、フィリピンなどがあるし、イタリアの「カルパッチョ」や韓国の「フェ」まで加えると結構な国々があります。バンコクのシーフードレストランへ知り合いのタイ人に連れて行ってもらったとき、生牡蠣が出されました。おそらく岩牡蠣でしょうが、サスガに衛生状態の悪い国だけに恐々で食べて...なんともありませんでした(笑)タイには生海老のサラダもあります。これは絶品!同行した息子も美味しい美味しいと3回もおかわりしたほどです。でも、これも衛生状態考えると...まぁ、こんときは私も息子もお腹壊しませんでしたけど。タイにはブイヤベース、ふかひれスープと並んで世界三大スープの1つとされる「トムヤムクン」がありますが、これだって云ってみればシーフード。観光客向けぢゃなくて、現地人が食べるトムヤムクンは辛いなんてモンちゃいます。食べたことない日本人は想像できない辛さ。昔は私も平気で食べてましたが、今は絶対ムリですね。国連の調査では、マグロが世界で最も食べられてる魚らしい。しかし、他の民間調査ではサーモンと云う説も。どっちにしても、このマグロとサーモンが2大巨塔らしい。それに続いてタラが登場しますが、こっちはもっぱらスープなんかにするのでしょうね。日本ではあまり馴染みがありませんが、アフリカと中近東原産の"ティラピア"と云う淡水魚も世界中でよく食べられてます。今では世界135カ国以上で養殖されてますが、この魚の最大の生産国は中国です。アメリカ人のイチバン好きなシーフードは「エビ」です。アメリカ人は、年間合計12億7,000万ポンドのエビを食べています。これは1人あたり約4.1ポンド(約1.9kg )に相当します。シーフードにはフランスの「プラトー・ドゥ・フリュイ・ドゥ・メール(Plateaux de fruits de mer)」みたいに、すぐに食べられるよう調理してある甲殻類や貝類の盛り合わせをクラッシュした氷の大皿に盛り付けた素朴な料理が多いですね。プラトー・ドゥ・フリュイ・ドゥ・メールに使われる魚介類は、エビ、ムール貝、ロブスター、カニ、アサリ、カキなどで調理済みか生のいずれかです。これにレモンとミニョネット・ソース、マスタード・ソース、カクテル・ソースなどさまざまなソースが添えられます。サンフ訪れたとき、ご多分に漏れず「フィッシャーマンズ・ワーフ」の「ピア39」にも行きました。そして、これまたご多分に漏れず「ボイル蟹」をいただいたワケですが、味は?昔のことなので忘れました。忘れるくらい、普通に茹でた蟹だったのでしょう(笑)世界で最も魚介を食べるのはダントツにアイスランドです。日本は食べてるようで意外に世界14位。そんだけ日本の食事は多様化してて、魚以外でも食べるものが豊富にあるって証拠でもあるんですけどね。逆に、ボリビア人はあまりにも魚を消費しないことで国連が危惧しています。国連の発表によると、年間魚をこれくらい消費したほうが良いという基準の半分ほどしかボリビア人は魚を食べてないそうです。ヨーロッパでも、ポルトガルやスペイン辺りは日本と同じくらい食べてますし、フランスやイタリアなども結構食べますが、ドイツなんかは海の近くの人は食べても、内陸の人はまったく食べない人たちも結構いるようです。そのためヨウ素が欠乏するので、塩と粉ミルクにヨウ素の添加が義務付けられている国も多いですね。スペインのバルセロナでスペイン料理の定番として有名な小皿料理「パパス」を楽しむ人は、「サーモンのエスカベッシュ(スペイン風南蛮漬け)」とか「牡蠣のガーリックオイル漬け」なんかを頼みますが、ダントツにオーダーの多いのは「イワシの唐揚げ」。「ボケロネス・フリートス(Boquerones Fritos)」と呼ばれる、オリーブオイルで揚げたカタクチイワシの唐揚げですね。これはザックリと塩味だけで、レモンをぎゅっと絞っていただきます。スペインのアンダルシア地方、地中海に面しているエスペトスはとりわけ焼きイワシ料理「エスペトス・サルディネス(Espetos Sardines)」が盛んです。サルディネスはスペイン語でイワシの意味です。この地方では19世紀後半ごろから、漁師は砂の上で余ったイワシを串に刺して炭火グリルしていました。今は6匹のイワシを1本の串に刺し、海塩で味付けしてから、オリーブの木の直火で焼きます。イワシが焼けて外側が黄金色になったら、オリーブオイルとレモン汁をまぶします。アンダルシアのリゾート地「マラガ」のビーチ・バーでは、ビールやサングリア、ティント・デ・ベラノと云う赤ワインをベースにしたカクテルとこのイワシ焼きがセットで提供されるのですね。街を歩いていると屋台でも売られてます。イワシのグリルは、ポルトガルの首都リスボンのレストランでも定番料理ですね。「サルディーニャス・アサーダス (Sardinha assada)」。こっちもイワシを丸ごとグリルし、塩とオリーブオイルで味付けするだけです。シーズンの夏には多くのレストランが店先にグリルを出し、炭火でイワシを焼いている光景にでくわします。エスペトスではカタクチイワシのマリネ「ボケロネス・エン・ビナグレ(Boquerones en Vinagre)」も盛んに作られてます。材料はいたってシンプル。お酢(もしくはワインビネガー)、塩、オリーブオイル、ニンニク、パセリなどでマリネしただけ。この料理は素朴ですが、お酢とニンニクがよくきいて、お酒のおつまみにぴったりなんですな。世界の伝統的な料理の体験型旅行ガイドサイト「テイスト・アトラス(TasteAtla)」が発表した「世界で最もおいしい料理」で今年は日本のカレーが1位を獲得しましたが、このテイスト・アトラスには10,000近くの料理、飲み物、食材、そして9,000のレストラン掲載されてます。日本料理だとお刺し身や握り寿司、牡蠣フライなどに混ざって、屋台の「いか焼き」なども紹介されてます。このテイスト・アトラスに取り上げられてるシーフード料理で、例えばスモークサーモンやスパゲティ・ボンゴレ、イングランドのフィッシュアンドチップスみたいによく知られてる料理以外で、これはと思う料理をご紹介しましょう。震災のキズ生々しいトルコには「ミディエ・タヴァ(Midye tava)」と云うムール貝料理があります。ムール貝に衣をつけて揚げた料理です。食べるときに、ほんの少しの塩とディップ用のピリッとしたタラトールソースを添えるだけで充分なんです。ノリとしては日本の牡蠣フライですな。ポルトガルに「ポルボ・ア・ラガレイロ(Polvo a Lagareiro)」ってタコ料理があります。ラガレイロってのは「搾油所の職人」という意味で、10月の終わりごろにその年の新しいオリーブオイルが出来ます。ポルトガル中部ベイラス地方でこのオリーブオイル工場の窯を使って作られたのが始まりの料理なんですな。調理法はいろんな種類がありますが、通常はタコを茹でてから切り分けて焼き、オリーブオイルを塗ってからあわせて、ニンニク、コリアンダー、レモン汁、塩なんかでドレッシングされたものです。スペイン料理の「アロス・マリネロ(Arroz Marinero)」はシーフードライスですが、パエリアと違って煮込むタイプの料理です。どっちか云うと「魚介のおじや」のような。主な具材は魚介と玉ねぎ、ピーマン、トマト、ニンニクなどのソテーした野菜と、さまざまなスパイスや調味料を加えて、ストック(シーフードまたは魚のストック)で煮込むのが一般的です。「フリット・ミスト・ディ・ペッシェ(Fritto misto di pesce)」はイタリアのメイン料理で、簡単に云うと魚介のミックスフライのことです。食材としては、エビやイカ、カタクチイワシ、イワシ、子サバ、ボラなんかを使います。地域によっては衣で揚げることもありますが、最も簡単な調理方法は、小麦粉で軽くコーティングし、きれいな黄金色の皮が形成されるまですばやく揚げることなんですね。中国の潮州市と福建省が発祥の「牡蠣のオムレツ」は、今や台湾、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピンなんかに暮らす福建人の代表的な料理ですね。この料理は、片栗粉と卵の生地を混ぜたものに小さなカキを加えただけ。台湾の台南市は最高の牡蠣オムレツを提供しているため、非公式にスナックシティとさえ呼ばれています。古典的なギリシャ料理「カラマラキア・ティガニータ(Καλαμαράκια τηγανητά)」はギリシャのイカフライです。レストランの定番料理で、パセリのみじん切りで飾られます。今回はアメリカのシーフードをワザと取り上げませんでした。なにしろ味オンチの国民ですからね(笑)メインデッシュに「シーフードとステーキ」なんてのが60年代からずっと人気なんですから。メリーランド州を代表する料理に「メリーランドクラブケーキ」ってのがありますが、ワタリガニの肉と、マヨネーズ、卵、パン粉、牛乳なんかが材料で、シーフードなのに別の料理に変貌。これはイギリス人入植者によってもたらされたものです。ど~りで美味しくなさそうな。
Feb 18, 2023
コメント(6)
-

仙台駄菓子
京都に日本で唯一の「金平糖」専門店がありますな。「緑寿庵清水」。今では東京なんかまで進出してて、ここのボンボニエール(ボンボン菓子入れ)に入った金平糖は皇室の引出物としても使われてます。しかし、云っちゃ悪いけど、たかが金平糖ですよ。べっ甲飴やボンタンアメ、紋次郎いか、酢昆布、うまい棒、ハッカパイプなんかと同じ駄菓子のひとつ。それが緑寿庵清水の清水焼の器に入った金平糖、6種セットなんて23,100円もする。これが京都独特の商売なんですな。駄菓子の起源は江戸時代に高価な砂糖を使って作られた上菓子とは違い、安い黒砂糖を使って作られた雑菓子が元祖だったとか。それのバリエーションで雑穀や水飴などでも作られて「一文菓子」と呼ばれていたものですな。昔はどこの町内にもオバチャンが営む駄菓子屋があって、私ら子供のころはここが集合場所。今みたいにスーパーや菓子専門チェーン店などで売ってるのと違って、お店のオバチャンとお話するのが日課でした。こうした「駄菓子」の概念とは違う、昔ながらの製法の駄菓子が残ってる地域があるんですね。私は若いころ個人旅行や仕事で日本各地巡ったのですが、なぜか東京以北、具体的に云うと埼玉から北にも東にも行ったことないんです。北はこうした地域飛び越えて、北海道の経験あるだけです。なので西武ライオンズのファンなのに所沢にあるベルーナドームも行ったことないし、日光東照宮も見たことありません。そんな空白の地に仙台もあります。遠縁の親戚に仙台出身の方がいたのですが、出身と云うだけで東京住まいだったので縁がなかったのですね。その仙台に「仙台駄菓子」と云う、ちょうど岐阜県高山の「飛騨駄菓子」みたいな位置づけのお菓子があったのです。上のお店の画像見ると、普通にイメージしてる駄菓子屋とは大違いですね。京都のどっか老舗のお店みたいな。戦前戦後の屋台や飯屋などでは、客が出て行く時に汚れた手先を暖簾で拭いていくので「暖簾が汚れているほど繁盛している店」という目安になっていたけど、このお店の暖簾はキレイですね。そりゃあ、食品を扱うお店なんだから清潔第一ですよね。置いてる商品のバリエーション見ても、こりゃあ私たちがイメージする駄菓子とは大違い。ところで「御菓子司」の読み方ってご存知でした?正解は「おんかしつかさ」ですね。これは、昔はお菓子を今で云う国家公務員が作っていたのです。それで今でもお菓子を「御菓子」、つまり尊い物を作ると云うイミ。「司」は宮中に仕える者の職位です。江戸時代に創業して、大正末に廃業した宮城の「越後屋」と云うお菓子屋さんがありました。この越後屋が開発した黒砂糖を米粉に練り合わせたお菓子で「南京糖」と云う看板商品があります。櫛型には和三盆をかけ、輪型には砂糖をかけたそうです。この輪型の南京糖が仙台でも作られて代表的な駄菓子になったのですね。一方、櫛型の南京糖は「石橋屋」で粳米を主原料にきなこを用いた「きなこねじり」として受け継がれてます。「兎玉」は新潟県弥彦村にある弥彦神社近くの菓子屋で作られている、ウサギの形の落雁と違って、仙台駄菓子では、赤餡(赤練り餡)に米飴、黒糖、餅粉を加えて練ったものに、白すり蜜をまぶした丸い形の菓子です。大坂などでは「松露」と呼ばれるお菓子ですね。仙台駄菓子の「兎落雁(めんこい)」こそ、弥彦神社の兎玉と同じで、ウサギ形の落雁ですね。私は落雁に興味ないけど、形はホント「めんこい」ですね。仙台駄菓子に「梅子」と云うのがあります。小麦粉を麦芽水飴で練って皮を作り、中に黄粉で作ったお菓子ですから柔らかですね。しかし、どれをとっても「駄菓子」と云うより「和菓子」ってなネーミング多いですね。ひとつには伊達政宗が、兵糧の改良増産にも力を入れたことから始まるのですね。「仙台糒(ほしいい)」と云うのは非常食で有名な「アルファ米」のことです。伊達政宗が兵糧にするため、道明寺糒を参考に作らせたのが始まりです。「糒」の歴史は古くって、平安時代の在原業平が「枯飯(かれいひ)」の上に涙をこぼしてふやけてしまったと云う有名な話しがあるほどです。江戸時代には仙台の特産品のひとつとして知らた仙台糒。この仙台糒で作った「おこし」をきなこと蜜の薄い皮で巻いたのが仙台駄菓子の「干切」です。飴そのものの歴史も古いですね。平安時代の延喜式(法典)には「京都に飴屋ができた」とあります。「ささら飴」は青竹を細く割いて串状にした先に、手まりのような可愛らしい飴を刺したものですね。昭和38年には昭和天皇行幸の際、仙台みやげとしてお買い上げになられたほど仙台のささら飴は有名だったのですが、今は肝心の青竹の串「ささら」の作り手がいないそうです。宮城県塩竈(しおがま)市のお菓子で「志ほがま」と云うのがあります。もち米に砂糖、塩、水あめ、青じそなどを混ぜ、型押しして作るお菓子です。同市に多くの初詣客が集まることで有名な「鹽竈(しおがま)神社」があるのですが、鹽竈神社の門前町 宮町にある「丹六園」は、江戸中期から志ほがまを作っているお店です。こうした和菓子と見間違いそうな仙台駄菓子ですが、いかにも駄菓子然としたお菓子もあります。「味噌パン」と云うのは普通の蒸しパン生地に味噌を練りこんで蒸し上げた蒸しパンタイプと、水分が少なめの生地に味噌を練りこんで、風味を付け、焼き上げた「菓子パンタイプ」があります。仙台駄菓子の味噌パンは後者の菓子パンタイプのものです。「仙臺まころん」はマカロンをベースにしたお菓子のように思えますが、製法は通常のクッキーよりも食感が軽いメレンゲ菓子の一種イタリアのアマレッティに近いです。泡立てた卵白に落花生かアーモンド、砂糖、小麦粉を加えて小球形に焼いたもので、昔の日本ではアーモンドが入手困難だったため、落花生を用いるようになったそうです。「きなこねじり」ってのは日本全国にありますね。このお菓子の元祖は江戸時代初期に京都で作られたものです。作るのが簡単な「きなこねじり」。なんせ材料は、きな粉と水飴だけですからね。水飴を熱して柔らかくなったところにきな粉を混ぜて生地を作り、それを平らに延ばして適切な大きさに切り分け、それをねじれば出来上がりなんですから。ねじられているのは元々しめ縄の形を表現したもので、縁起物とされていたからです。と、まぁ、仙台駄菓子と云うのは一般的な駄菓子の概念とは違い、ほとんど和菓子。地元でどんだけ浸透してるのでしょう?とりわけお菓子は和より西洋のものが好まれる傾向ありますからね。ただ、こう云った文化は継承してほしいですね。
Feb 17, 2023
コメント(6)
-

エルヴィン・ジョーンズとケイコ・ジョーンズ
昨年の9月、マンハッタンはセントラルパーク・ウエストのマンションで脳卒中のため亡くなった(奥谷)けい子ジョーンズ。享年85歳。私は不思議な縁で、このケイコ・ジョーンズと、 2004年に先に逝った彼女の夫エルヴィン・ジョーンズ(享年76歳)ととても親しかったのですね。エルヴィン・ジョーンズは知る人ぞ知る伝説のジャズ・ドラマーです。マイルス・デイヴィスやソニー・ロリンズ、チャールズ・ミンガスらと共演した後、モダンジャズを代表するサックスプレーヤーで、20世紀ジャズの巨人として有名なジョン・コルトレーンのカルテットに参加して一世を風靡しました。ジョン・コルトレーンのグループでは、ベーシストのジミー・ギャリソン、ピアニストのマッコイ・タイナーと共にカルテットを形成。複雑なリズムを難なく叩き、ドラミングの技術には定評がありました。1960年代にはブルーノート・レーベルを中心にウェイン・ショーターやグラント・グリーン、ラリー・ヤングらのレコーディングに参加。歴史的名盤を数多く残しています。ジョーンズ夫妻には子供がいませんでした。しかし夫妻が逝くとき、傍には継子のエルヴィン・ネイサン・ジョーンズが立ち会ってました。そしてエルヴィンとケイコの長年の友人だったドラマーのアルヴィン・クイーンも。"けい子"は長崎出身です。1937年に履物商の娘として生まれた けい子はクラシック・ピアノを学ぶ一方、ジャズを愛する父の影響を強く受けました。そして1966年、アート・ブレイキー、トニー・ウィリアムス、エルヴィン・ジョーンズをヘッドライナーに迎えたツアーの企画に参加するのです。この仕事でふたりは出会い、恋に落ち、1967年初頭、彼女はエルヴィンを追うようにニューヨークに渡り、1971年に結婚。生活をともにするようになるのです。この、ふたりが出会うきっかけとなったツアー企画にはジャズ関係者には有名な話があります。1966年11月、東京大手町産経ホールで幕を開けた「ザ・センショーナル・ドラム・バトル」の出演者の1人がバス・ドラムの中に隠し持っていたドラッグが摘発されるのです。麻薬取締官の尋問を受けた3人のドラマーのうちエルヴィン・ジョーンズが「そのドラムは俺のものだ」と名乗り出て現行犯逮捕。エルヴィンが将来性のある若いトニー・ウィリアムスの罪を自ら被ったのです。不憫に思った関係者が嘆願書を書いてエルヴィンを釈放させ、当時長崎でジャズ喫茶を経営していた けい子を呼び寄せ、エルヴィンの面倒を見させたのが縁なんですね。強制送還されたエルヴィンの再起を図るため、けい子はエルビンが送還された翌月ニューヨークにエルヴィンを追ったのです。その後、エルヴィン・ジョーンズは再入国が認められ、なんども日本に来日。自ら主催する「エルビン・ジョーンズ・ジャズマシーン」バンドで日本全国のツアーを決行しました。ジャズ・ドラムスの神様と評されるジョージ川口と親しくなったのもこのころですね。ジョージ川口とドラムバトルなんかをしてました。ケイコはどこに行くにも、エルヴィンと一緒でした。ただ奥様然としていたのではなく、常にマネージャーとして働き、エルビンがステージにあがる何時間も前からドラムをセットアップしたりしてたのです。エルヴィンがステージに立ってるときでさえ、ケイコは楽屋から離れることはありません。お茶を飲みながら、夫の音楽を楽しんでいたのです。ある日本人のプレーヤーがエルビンのマンションへ夕食に招かれたとき、「魚のあら炊き」がでてきたと云います。エルビンの健康を思いやって、肉食を控えるようにしてたのです。私がふたりと知り合ったのも、エルヴィンの再入国が認められてからです。勤めてた会社の若いスタッフが発したちょっとした言葉がエルヴィンを怒らしてしまったのです。エルヴィンは他の黒人と同じように、本国で悪意に満ちた差別に耐えてきました。そのスタッフに他意はなかったのですが、発した言葉が黒人差別と誤解を生んでしまったのですね。で、私が応対して話し合った結果、誤解も解け、それ以来とても仲良くなったと云うワケです。ジョン・コルトレーンの死直後に自らのグループで作成された未発表ライヴ音源「リヴァイヴァル:ライヴ・アット・プーキーズ・パブ」のオープニングは「ケイコズ・バースデー・マーチ」から始まります。プーキーズ・パブと云うのは、ロウワー・マンハッタンにある小さなパブらしいですが、エルビンはここに頻繁に出演したそうです。2008年にジャズ・ドラマー鬼束大我がエルヴィン邸を訪れたときの写真が残されてます。大我は9歳のときギネスブックに「世界最年少プロドラマー」として認定された天才です。7歳でニューヨークに渡り、「エルビン・ジョーンズの再来」「アート・ブレーキーの生まれ変わり」と絶賛された人物なんですね。日本より、むしろニューヨークの大物ジャズメンの間で知られる存在となったジャズ・ドラマーなんです。この大我がエルヴィン邸を訪れたとき、彼はまだ幼いころで、エルビンは既に帰らぬ人でした。部屋のあちこちには、エルヴィンの写真や肖像画が掛けられ、ファンからの贈り物だという人形や装飾品が所狭しと飾ってあったそうです。このときも、ケイコが大我に手料理を振る舞ってくれたそうです。
Feb 16, 2023
コメント(4)
-

フェアチャイルドの航空カメラ
昨年、カナダ・ユーコン準州ルカニア山で古いカメラが発見されました。それは1937年に2人の著名な登山家によって放棄されたカメラでした。登山家の名前はブラッドフォード・ウォッシュバーンとロバート・ベイツ。ふたりはルカニア山の初登を目指して登頂にアタック。そのとき悪天候に見舞われ、身軽になって生き延びるために、ほとんどの装備を置いていかざるを得なかったのですね。発見されたのは、そのときに手放したウォッシュバーン所有の米フェアチャイルド社製F-8型航空カメラだったのです。フォーカルプレーンシャッターのフェアチャイルドF-8には、ドイツの名門レンズメーカー「シュナイダー」のXenar240mm f/8レンズが装着されていました。このカメラは第2次大戦中にアメリカの「ウォレンサック」と云う総合映像機器メーカーの375mm f/5.6レンズを装着して航空写真に使用されてたものです。ウォッシュバーンはアメリカの山岳撮影したことでよく知られており、カメラと自分自身を飛行機に固定するために飛行機のドアを取り外すことがよくありました。簡単にドアを取り外すと行っても、とりわけ冬は非常に暖かい衣服が必要でタイヘンだったでしょうね。そもそも航空カメラと云うのは、普通のカメラと違って常識はずれの大きさです。フイルムや今だったらデジタルのセンサーを巨大にして、高い高度からでも繊細な画像をとらえないと測量なんかに使えないですから。現在のデジタル航空カメラとしてはアメリカの「ベクセル」社や「インターグラフ」社、そしてスイス東部に拠点を置く「ライカジオシステムズ」社のカメラがよく使われてますが、いずれも巨大なものです。形も私たちがイメージするカメラとは異質のものですね。現在の測量用航空カメラの標準仕様は写真画面の大きさが23cm ×23cm 、レンズの直径は300mm で、間隔調整器によってシャッター作動はすべて飛行機の速度に対応した自動装置でできるようになってます。飛行機から撮影された最初の航空写真は、1909年にライト兄弟の兄"ウィルバー・ライト"によって撮影されました。撮影当時、彼はイタリアでイタリア政府に飛行機売り込みをしていたのですね。そのテモンストレーションのとき、ローマ近くのチェントチェリで軍事施設の撮影をしたのです。本格的な航空カメラの歴史は第1次大戦まで遡ります。それ以前の航空からの観察記録は、航空観測者によるスケッチだったのですが、それがカメラの発達でたちまちスケッチに取って代わったのです。協商国(連合国)、ドイツ帝国・オーストリア=ハンガリー帝国・オスマン帝国・ブルガリア王国の中央同盟国、両陣営が使用する戦闘地図は航空写真から作成され、終戦まで両陣営は前線全体を少なくとも 1日に2回撮影してました。このために航空機用に特別に設計された熱赤外線検出器を装備するカメラが製造されてましたが、まだまだ安定性とシャッター速度は依然として充分な域に達していなかったのです。終戦に向けてフェアチャイルドはレンズ内にシャッターを配置したカメラを開発しました。この設計により画質が大幅に向上し、その後50年間にわたって航空カメラの標準となったのです。2002年に経営破綻したフェアチャイルドという会社、いまでこそ航空機メーカーと云う印象が強いですが、もともとは航空カメラの設計製作が主だったのですね。日本海軍の六桜社 (現コニカミノルタ)製 手持式航空写真機はフェアチャイルド製の航空写真機を元に大正14年頃~昭和13年に渡って生産されました。第2次大戦中に撮影された兵員が持ってる巨大なカメラ。カメラに取り付けられてるのは長さ約60cm の巨大な610mm f/6レンズです。このカメラはフェアチャイルドのK-17(コダックK-24とする説もありますが、それは誤認)。K-17は、9.1/2インチ(約241mm )幅のロールフィルムで9×9インチ (22.86cm 四方) の写真を撮影できるカメラで、6インチ、12インチ、24インチのレンズがあり、それぞれ絞り値はf/6.3、f/5、f/6でした。とにかくデカイカメラです。このカメラを手持ちで撮影するのは尋常ぢゃない体力ないとできませんな。24インチのレンズを装着すると、重量は75ポンド(約34kg )近くになったそうです。普通は航空機のマウントに固定されていましたが、手持ち操作用に1対のハンドルとビューファインダーを取り付けることができたのです。上の画像でフェアチャイルドK-17をコダックK-24と間違った人がいると述べましたが、コダックと云うのはアメリカのイーストマン・コダックのことです。コダックはフイルムや安価な初心者用カメラメーカーと思われがちですが、世界で最初にデジタルカメラを製造した会社で、プロ用デジタルカメラも数多く生産してます。コダックK-24はイギリスのF-24航空カメラを改良したもので、第2次大戦中に9千台近くが連合軍側に配備されました。テーマと外れますが、コダックK-24が手本にしたイギリスのF-24航空カメラについても触れておきましょう。F-24カメラは、1920年代~1950年代半ばまでイギリスと連合軍が空中偵察に使用したカメラです。F-24の基本設計は、1925年にイングランド南部ファーンバラにある英国王立航空会社によって行われました。このカメラはローラーブラインド・フォーカルプレーンシャッター付きボディ、ギアボックス、フィルムマガジン、レンズコーンで構成されていました。フィルムは幅5インチ(約12cm )のロール フィルムで、 マガジンひとつで最大250枚撮れる構造です。シャッター速度は1/100秒~1/1,000秒ですから、当時の普通のカメラと一緒ですね。1940年頃までにF-24には、8インチ口径、f/2.9のダルマイヤー・ペンタックレンズが導入され、1940年後半に20インチ(f/5.6)レンズ、1942年には36インチレンズとどんどん大きなレンズに変わっていって、大きな画像により非常に高い高度からより詳細な画像が得られました。第2次大戦中にF-24が搭載された航空機には、アベンジャーやコルセア、ヘルキャット、ハリケーン、モスキート、ムスタング、スピットファイアなど英米の著名な戦闘機や爆撃機があります。ロシアによるウクライナ侵攻で両軍が使ってるドローンによる偵察など、軍事偵察もどんどん様変わりしてきてますね。ドローンやヘリコプターはその巨大な羽音で敵に気づかれやすいのが難点でしたが、アメリカではその羽音そのものを軽減する特殊な羽(ブレード)を開発したらしいし、同じくアメリカで1,000機以上のドローンをAIでお互いにぶつかることなく集中使用できる技術を開発中とか。先日から世間を賑わしてる中国の偵察用気球の追跡にアメリカの「U-2」偵察機が使われてたのには驚きました。U-2の初号機が登場したの1955年ですよ。まさに米ソ冷戦のおとし子。それが改良に改良重ねて、今でも現役だったのです。なにしろU-2ほど高硬度を飛べる航空機は他にありませんからね。U-2は旅客機の約2倍、高度21,212m 以上の成層圏を飛行することができるのです。
Feb 15, 2023
コメント(6)
-

フィヨルドが残したもの
ノルウェーはフィヨルドの奥に形成された国からか奇岩が多いです。なかでも有名な崖と岩が3つ。観光客がワンサカ訪れる場所が。先ずは南西部にあるリーセフィヨルドの崖の1つ「プレーケストーレン」から。リーセフィヨルドはノルウェー語で「光のフィヨルド」のイミ。フィヨルドを形成する花崗岩が光る性質を持つことからこの名がついたらしい。そのリーセフィヨルドの水面から垂直に600m 上に「プレーケストーレン」と呼ばれる崖があります。プレーケストーレン(Preikestolen)はフィンランド語で「演説台」。なぜそう呼ばれてるかは下の画像を見れば一目瞭然。崖の頂上が、約25m 四方の正方形なんです。日本だったら絶対、崖の縁に柵を設けて事故防止ってとこですが、ノルウェー政府はそんな無粋なことしません。防護柵がなく、スリルを味わうことが出来るのですが、あくまで自己責任と云うことで。国内3の都市ノルウェー西海岸のスタヴァンゲルから訪れる、リーセフィヨルド観光スポットの中でもとりわけ人気のある場所のひとつなんですが、実はこの崖にたどり着くまでに試練が待ってるのです。それは...とにかく急峻で岩ゴロゴロの山道をひたすら登らなくてはならないってこと。もう、この時点で、私は脱落ですなぁ。冬の期間は雪が降って地面が凍り、滑りやすいためトレッキングは禁止されてるそうです。だいたいこんな急峻な道、冬に登るとなると冬山登山の装備いりますがな。リーセフィヨルドにはもうひとつ有名な観光地が。水面からほぼ垂直に1000m 以上伸びる絶壁に挟まった奇跡の岩「シェラーグボルテン」です。約5m の氷河堆積物シェラーグボルテンは、絶妙なバランスを保ちながら挟まってるのですね。この岩は最後の氷河期が終わり温暖化に転じると、海面が上昇しフィヨルドを氾濫させて水没した位置にあります。そして、再び水位が下がって岩が取り残されたのですね。とにかく、この岩を訪れる人は数多く、岩に乗る待ち時間は時には1時間近くかかることもあるそうです。プレーケストーレンやシェラーグボルテンのあるリーセフィヨルドのある区域は法的にベースジャンピングが許可されるとこです。なので、ベースジャンパーの聖地としても知られるのですね。リーセフィヨルドでのベースジャンピングの様子はYouTube 動画でど~ぞ。動画冒頭で雄大なリーセフィヨルドそのものが楽しめます。B.A.S.E Jumping Norway 2018最後にハルダンゲル・フィヨルドから分岐するソーフィヨルデン・フィヨルドにある「トロルトゥンガ(Trolltunga」。英語名は「トロールの舌(The Troll's tongue)」と呼ばれる高さ約700m の崖から水平に突き出た岩です。ここに登るには、首都オスロに次ぐ大都市ベルゲン市から高速道路を使っておよそ190km の距離を走り、ダム近くの海抜443m にある駐車場で車を停めます。そこから最初の1.5km の急峻な登山道を今は運転されていないトロリーカーの山上駅まで登って、さらに宙に浮いている軌道面を登り、出発点から4km 地点の海抜1,183m まで行きます。そこからさらに330m 登ってやっと到着。ここを往復するだけで、8時間~10時間要します。ここの崖も自然の美しさを損なわないようにとの配慮から手すりはついてません。
Feb 14, 2023
コメント(6)
-

メッセンジャーバッグとメールバッグ
私が普段使いするバッグはトートバッグとボディバッグ、そしてメッセンジャーバッグですね。ウエストポーチは持ってないし、使うことはありません。バックパックは非常持ち出し袋に使ってるくらいで、普段使いに私には容量が大きすぎて却って使いづらい。逆にサコッシュは小さすぎて、かと云ってスマホだけ入れるには大きいし、帯に短し襷に長しで持ってません。ショルダーバッグ、以前、グレゴリー(GREGORY)のお高いショルダー持ってたのに、久しく使わなかったら、皮部分にカビはえてました(泣)まぁ、カビはえるくらい使ってないってことは、一生使わないってことですね。「バック」と「バッグ」、どっちが正しい云い方?そりゃあ「バッグ(bag)」ですよね。「バック(back)」だと「戻る」とか「裏」になりますもの(笑)なかでも、もっとも重宝してるのがメッセンジャーバッグ。ショルダーバッグと違って、斜め掛けのベルトを調節して身体にフィットさせるようになってるので歩いててもバッグがズレてこない。これはメッセンジャーバッグの成り立ちが、マンハッタンの交通渋滞を縫うように駆け回る「メッセンジャー」と呼ばれる自転車配達員向けにデザインされたものだからですね。メッセンジャーバッグは、1860年代にアメリカのミズーリ州セントジョゼフからカリフォルニア州サクラメントまでの郵便速達サービスをやってた「ポニー・エクスプレス(Pony Express)」のスタッフが使ってた袋が起源とされています。それが現在のような形になったのは1950年代です。電話架線工事をする人が電柱に登って作業するときに使いやすいよう、ニューヨーク「グローブキャンバス社」の創始者フランク・デ・マルティーニという人物が考案したのですね。メッセンジャーバッグとよく似た機能のバッグに「メールバッグ(mail bag)」がありました。メールバッグってのは、郵便配達の人が各家庭に郵便物をとどけるのに使うバッグから、局内や鉄道・トラック・飛行機なんかで運搬するためのものまでの総称なんですね。個人宅に届ける前に、大量のメールを運ぶ目的で使用されるメールバッグで「メールサック」と云うものがありました。メールサックはセキュリティがほとんど必要ないため、鍵のかかったバッグではありません。郵便局間で軍事郵便など機密性の高い郵便物や書留郵便を入れるため、バッグの上部にロック機構がついた「メールポーチ」と違って、メールサックにはこの機能がないのですね。19世紀には前述のポニー・エクスプレスが馬の鞍にかぶせる取り外し可能な軽量の革製のカバー「モチラ (mochila)」を使ってました。これは普通の鞍にかぶせるサドルバッグでは、アメリカを横断するポニー・エクスプレスのように、マウント・ステーションで数分以内に新しい馬にすばやく交換するためには手間がかかるために考案されたものです。1860年に実用化したポニー・エクスプレスのモチラは、高速郵便配達システムの開発に大きく貢献しました。モチラにはカンティーナと呼ばれる4つのポケットがあり、小さな南京錠でロックできました。ポケットで運ばれる書類は油を塗った絹で覆われ、水や汗から保護されます。ポニー・エクスプレスの郵便サービスは0.5オンス(約14g )あたり1$~5$と、当時としては非常に高額で、企業だけが支払うことができる天文学的な金額でした。19世紀~20世紀初頭にかけて鉄道郵便が使ってたメールバッグに「キャッチャーポーチ(catcher pouch)」と云うのがあります。キャッチャーポーチは停車駅以外の駅で、列車間と受け渡しするメールバッグです。キャッチャーポーチの受け渡しは手ではおこないません。通過する列車をゆっくりと減速させ、貨物列車に備えられたキャッチャー・アームと呼ばれる装置によって掴まれ、それを列車内の係員が回収するものです。列車内の係員がキャッチャー アームでメールバッグを引っ掛けた後、そのメールバッグを列車内に投げ出さなければなりません。でないと、列車の下にメールバッグが挟まって破裂し、手紙が飛び散る可能性があったからです。この事故を係員は「吹雪」と呼んでたようです。キャッチャーポーチのイメージはなかなか伝わりにくいと思いますのでYouTube 動画でど~ぞ。動画はサイレントです。Train Taking Up Mail Bag from a Mailcraneアメリカでは、1913年に小包郵便が登場したのですが、発足当時、なんと小包で子供を送る人が続出したのです。例えば自宅から、おばあちゃん宅まで子供を送り届ける場合、小包の体重制限が50ポンド(約23kg )だったので、これより軽い子供だと鉄道料金を支払うより郵送する方がはるかに安かったのですね。で、これはあまりと、1920年に小包による子どもの送付が禁止になりました。と、まぁ、メッセンジャーバッグの原型、メールバッグにはさまざまなバリエーションがあったのですね。どのバッグも機能優先。その精神がメッセンジャーバッグまで受け継がれてるワケです。
Feb 13, 2023
コメント(6)
-
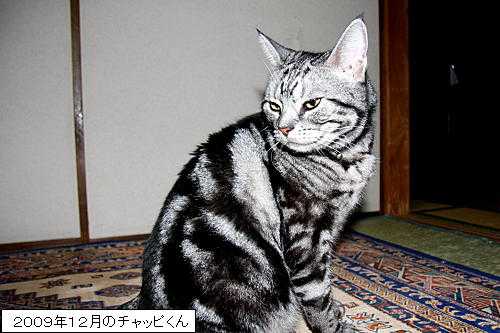
嵐の大地
太平洋戦争戦争のとき、ブーゲンビル島上空で戦死した山本五十六(海軍大将)は、日露戦争当時、少尉候補生のまま装甲巡洋艦「日進」配属となり、日本海海戦に参加します。この海戦で五十六は、左手の人差指と中指を欠損、左大腿部に重傷を負うのですね。その五十六が乗艦していた「日進」と、同型艦「春日」。巡洋艦と云う名前ですが、戦艦と同等の戦力があったそうです。そのため日露戦争では黄海海戦や日本海海戦の主力として活躍しました。この「日進」と「春日」、もともとは日本の船ではありませんでした。隣国チリと国境紛争が勃発しそうになったアルゼンチンが、イタリアの造船所に発注した「モレノ」「リバダビア」と云う2隻の巡洋艦だったのです。ところが国境紛争そのものが、ローマ法王が出てきて一挙に国境線を決めてくれたので、この船が必要なくなったのですね。で、アルゼンチンが発注した2隻の巡洋艦「モレノ」「リバダビア」を、当時ロシアのバルチック艦隊との戦いを迫られていた日本が買い取ろうとしたのですが、実はロシアも購入すべく画策していたのです。なんですが、移民の国アルゼンチンが白人のロシアに味方せず、有色人種の日本に味方したのですね。それとともに日本の同盟国であったイギリスの仲介もあって日本側に売却されたのです。ブエノスアイレスのアルゼンチン海軍大学の正面には東郷元帥の、横須賀の防衛大学にはアルゼンチン独立の父サンマーチン将軍の銅像が立っています。それではアルゼンチンとチリがあわや戦争直前までいった国境紛争の地とはどこでしょう?それは秘境とも云える地「パタゴニア」です。現在、アルゼンチンの人口は4,600万人くらいですが、パタゴニアに暮らしている人はアルゼンチン総人口の4.5%くらいしかいません。人口密度で云うと1平方km あたり1人以下なんですな。地球上で人類がまだ手をつけていない最後の土地と云えます。なにしろ南端は南極にほど近い。パタゴニアのことは先日放映されたTBSの「日立世界ふしぎ発見!」でも特集されてましたので、興味ある方はバックナンバーをご覧になってください。パタゴニアを発見したヨーロッパ人はスペインのマゼランです。パタゴニアの地名はマゼランが、住んでいた先住民「パタゴン族」の住む土地から命名したのです。「パタ」はスペイン語で「足」。パタゴン族は"大足"だったことからきてるのですが、本当に足が大きかったのではなく、ラマの一種「グアナコ」の毛皮ブーツを履いていたからだと云われてます。マゼラン遠征隊の生き残りの1人アントニオ・ピガフェッタは、そこで出会った先住民は普通の2倍の背丈だったと報告しています。しかし18世紀のマリーアントワネットの身長が150cm もなかったとか、モーツァルトも150cm 台と云いますから、昔のヨーロッパ人そのものが低身長だったのですね。パタゴン族は現在のパタゴニアからチリ中南部に住む先住民族「テウェルチェ族」だと考えられてます。テウェルチェ族も、他の中南米の部族と同じように、ヨーロッパ人が大陸から持ち込んだ天然痘やチフス、麻疹など免疫を持たなかった伝染病でいちじるしく減少したのと、リオ・ロカ将軍によるインディオ討伐によって自立した民族としては壊滅してしまいました。今では、日本の2倍強にあたる広大な面積のパタゴニアにテウェルチェ族は200人程度しか残ってません。パタゴニアと云うと、とにかく年間を通じて低温で風が強いですね。パタゴニアの代名詞とも云われてる風の強さ。最大風速が60m/sを超えることも珍しくないらしい。なのでアルゼンチンは世界一風の強い国と云われるのですね。人間は25m/sを超えると風に向かって歩けず、40m/sを超えると踏みとどまることも難しくなり、飛ばされることもあると云います。イギリスの登山家エリック・シプトンはパタゴニアを「嵐の大地」と呼びました。同じパタゴニアでも、チリ側は北西からの強い偏西風がアンデス山脈にぶつかって雨の多い地域です。ところがアルゼンチン側は南極を周回する南極還流がアンデス山脈に一旦さえぎられた後、南米大陸の南端に衝突することで台風クラスの風がいつも吹いているのです。パタゴニアには、もうひとつ特徴ありますね。氷河。南パタゴニア氷原から連なる氷河の数は大小50以上あると云われており、規模は南極、グリーンランドに次ぐ量と云われてます。ここの氷河は年平均100m ~200m 移動する動きの激しい氷河です。
Feb 12, 2023
コメント(5)
-

EMTの残響装置
ヴィルヘルム・フランツと云うドイツ人を知らなくても、彼が創業した「EMT」は古いオーディオ・マニアだったら懐かしさとともに、羨望の目を隠せないでしょう。EMTが創業したのは1938年(昭和13年)で、当初は無線や通信用の特別な制御、測定装置専門の製造会社でした。戦後、EMTはレコードプレーヤーなんかの製造を始め、これが古参のオーディオ愛好家の知るところとなったのです。EMTの製造する音響機器は業務用に徹していたため、思いきし質実剛健です。下に「EMT-927」と云うEMTを代表するレコードプレーヤーの画像を載せますが、前面のパネルを取り外した画像ではないんです。モーターむき出しのこの画像が製品そのものなんですね。ところが、このプレーヤーがとびきり音がいい。その秘密はとてもレコードプレーヤーとは思えない徹底したサスペンションによる制震構造だったのです。で、世界中のスタジオやラジオ局がこぞって採用したのですね。他にもEMTは、フォノカートリッジやトーンアームなどレコード再生に必要な機器の製造をしてましたが、どれもとび切り性能がよくて、かつ高価だったのです。それでも熱心なオーディオ愛好家は自宅に据え付けるの憚れる外観もお構いなしに、こうしたEMTの業務用機器を購入した人が多かったです。EMTは現在も健在で、形こそ民生用機器に近づきましたが、それでもEMTならではのこだわりもった製品ばかりです。下の2枚の画像、上は近々発売予定のレコードプレーヤーですが、音の濁りを防ぐためバッテリーで動きます。バッテリーがいちばん純粋な電源になるワケですが、充電が伴うのでいつでも聞くと云うワケにはいきません。このプレーヤーで連続3時間動いて、それを過ぎると充電のために休止しなくちゃなりません。下の画像はフォノカートリッジで拾った微細な音をアンプに導くためのフォノイコライザーと云う機器で、こっちは音のために特別仕様の真空管を使ってます。しかし、こうしたオーディオ機器の開発はEMTにとって、片手間仕事だったのですね。彼らが最も力を入れてたのは、レコーディング機器の製作です。EMTで最も有名なのは「EMT-140」と云うリバーブの機械です。リバーブは残響装置とも呼ばれますが、要するにカラオケスナックなんかでオッチャンが歌ってるとき、歌を上手にみせるためのエコー装置と同じです。自然界で残響音がない音は存在しなくって、普段生活しているときに聴こえる音には、必ずどこかに跳ね返った音も一緒に混ざって聴こえてきます。声やシンセサイザーの音のみでは違和感を感じてしまうのですね。とは云っても、カラオケのエコーは効かせすぎで、全員が(石原)裕次郎が唄てっるような違和感が(笑)レコーディングでは使ってるか分からない程度にリバーブをかけます。現在はカラオケもレコーディングでも、ほとんどが「電子リバーブ」を使ってます。今どきのレコーディング現場では、PCを使用して音楽を製作編集するのが常識なので、そこに使われるソフトとしてリバーブも有るのですね。リバーブには昔の家庭用ステレオなんかに装備されてた「スプリングリバーブ」と云うのもあります。金属製バネを使用した装置です。しかしノイズを拾いやすく、バネで振動を伝えるため特有の共振特性があって、あまり良い音とは云えませんでした。現在ではこの「バネっぽさ」が逆に独特のサウンドキャラクターとしてギターアンプに使われてます。スプリングリバーブと違って、「EMT-140」はとても家庭に持ち込めるようなものではありません。なんせ大きさが2.4m ×1.2m ×0.3m もある巨大な装置だからです。ダブルベッドのサイズが1.95m ×1.40m ですから、これの大きさとほぼ一緒ってことです。レコーディング用語に「チェンバー」と云うのがあります。チェンバーは特定の目的で使われる部屋のことです。この部屋は残響が発生しやすい部屋にスピーカーとマイクを立てて録音することでリバーブ状態を作り出しているのですね。そして、このとき得られるリバーブはとても自然な音がします。EMT-140はチェンバーに似た非常に自然なリバーブが得られることで有名です。構造は「プレートリバーブ」と云い、薄い大きな「鉄板」を振動させてリバーブが得られるように作られてます。リバーブを得る方法はシンプルで、鉄板の一方の端にスピーカーのようなデバイスがあり、もう一方にマイクがあって、スピーカーから出た音が鉄板を伝わってマイクに届く信号を拾ってるワケです。初期反射が大きく、音の立ち上がりも早いのが特徴で、「濃い、深い、温かい」などのイメージを抱くレコーディングエンジニアが多くいます。この機材は主にボーカル用のエフェクトとして利用されています。EMT-140は、それ自身が振動に弱いので、スタジオの外に防音室を設置して格納します。そしてスタジオのコントロールルームにリモートのコントローラーが設置してあり、それを使用してダンパー(鉄板の振動を抑える装置)を動かし、響きの長さを調節するのです。1950年代後半にEMT-140は、ビートルズやピンク・フロイドなどの録音を手掛けたロンドンの「アビー・ロード・スタジオ」に4台納品されました。1976年までに、さらに3台が設置され、合計7台のEMT-140が稼働してました。EMT-140が発売されたのは1957年(昭和32年)なのでとてつもなく古い機器です。その後もEMTは改良型を投入してきましたが、今はプレートリバーブのリバーブ装置は製造してません。それでも、世界中の多くのスタジオにこのシステムは残っていて、現役で稼働してます。歌物収録時はもちろん、バンド録音からストリングス録音、ミックスダウンなど多くの場面で使われており、特に「演歌」ではリバーブにこの機器しか使わないエンジニアが多くいます。
Feb 11, 2023
コメント(4)
-
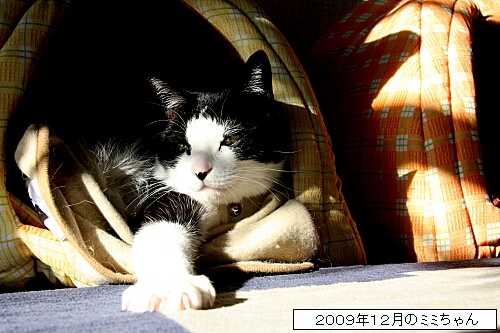
カンボジアの料理
1世紀~7世紀にかけて現在のカンボジアやベトナム南部からチャオプラヤー川デルタにかけて栄えた国で「扶南国(ふなんこく)」と云うのがありました。扶南をたてた人物は諸説あって、どの説もインド出身と述べてます。その根拠は扶南が仏教とともにヒンドゥー教の国家だったからかも知れません。その扶南国も628年にラオス南部からカンボジア東部にあった「真臘」と云う国に滅ぼされたのですね。この扶南をたてた民族が、クメール人(カンボジア人)なんです。私は一度もカンボジアに行ったことがありません。なんとしても有名なアンコール遺跡があるので見たいのですが、現在のカンボジアは治安が悪すぎます。コロナ以前でも日本人観光客の犯罪被害は、ひったくりから始まってスリ、強盗と枚挙がないくらいあがっています。だいたいカンボジア政府そのものがアジアでもダントツの汚職の巣。世界経済フォーラムが公表した資料では、カンボジアは世界で5番目に腐敗してる国と認定されてます。それより私がタイに居住してた時代はベトナム戦争の真っ最中だったので、例え隣国と云えど気軽には旅行できないし、ベトナム戦争が終わったらポル・ポトが政権略奪して、大量虐殺で100万人~200万人以上もの死者を出した国です。今でこそ日本地雷処理を支援する会(JMAS)などの活動で都市部は比較的安全になりましたが、カンボジア内戦直後なんてどこもかしこも地雷のオンパレードです。ダイアナ妃がアンゴラやボスニア・ヘルツェゴビナの地雷原に足を踏み入れて「地雷廃絶運動」の旗手として活躍したにも関わらず、ウクライナではまたしてもロシア軍が多数の地雷をウクライナの土地に埋没させてますね。さて、きょうの表題は「カンボジア料理」。そもそもカンボジアの町の様子をYouTube なんかで観ると、タイの田舎町と見間違えるくらいそっくりです。言葉こそタイ語とクメール語(カンボジア語)の違いはあるものの、タイと隣接しているだけに文化そのものは近いのでしょうね。今のカンボジア政権はラオスと同じで、中国にベッタリです。カンボジア料理に白身魚のココナッツカレー「アモック」と云うのがあって、観光客にイチバン馴染みあるのですが、実際のカンボジア郷土料理と云えば「サムラーカコ(Samlar kako)」ですね。カンボジアのレストラン始め、道端の屋台、家庭でもよく見かけます。ナマズと豚バラ肉から作られたボリュームのあるスープで、トーストした米でとろみをつけてます。「ナム バンチョク(Num banhchok)」と云うのは東南アジアご用達のビーフン料理です。食べ方もスープ麺、スープ無し麺とこれまた東南アジア独特のもの。汁なし麺は日本のつけ麺と違って、麺の上に好みのソースをかけていただくものです。オモロイのは東南アジアどこにでもある焼きそば風が見当たらなかったですね。カンボジア風生春巻きにも、この麺が使われてました。カンボジアにもカレー料理があります。代表的なのが「フィッシュアモック」。クメール帝国時代のクメール王室料理だった一品です。この料理はハゼ、ライギョ、ナマズなどの魚かカタツムリのどちらかで作られていましたが、今では鶏肉を使ったバージョンも見かけるようです。やや甘めのカレーで、バナナ葉のボウルで提供されるのが普通です。ライギョやナマズを使うのは、海に面してる地域が限られるので、国境を接してるラオス料理と同じなんでしょうね。なんか見ていても、特別 食指が動くようなお料理はないですね。どっちか云うとラオス料理に似た料理が多いです。隣接してるベトナム風ではないですね。最後にカンボジアの屋台を動画で。この動画観ると、バンコクの中華街あたりの屋台と変わりありません。Most Famous Place for Spring Rolls, Yellow Pancake, Noodles & Fried Wonton - Cambodian Street Food
Feb 10, 2023
コメント(5)
-
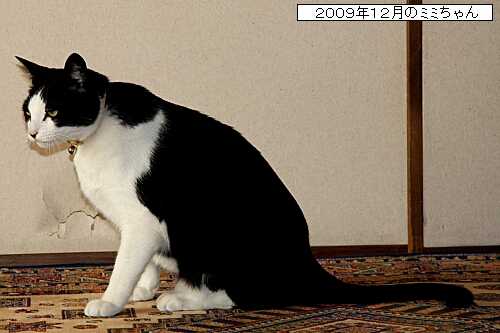
NeXT STEPライクな
話は1985年(昭和60年)に遡ります。まだPCにWindows が登場してなく(最初の実用的なWindows 3.0は1990年=平成2年まで待たなければなりません)、マイクロソフトが1985年に発売したのはWindows 1.0と云うDOS(Windows 以前のオペレーティングシステム)上で動作するものでした。TVによるCMもあり、発売前から大きな話題となっていたWindows 1.0でしたが、性能はよくなく評判は最低でした。この年の日本のPCの状況は云うと、NECのP98シリーズ全盛の時代で(OSはDOSのNEC仕様)、PC-98XAとPC-9801U2が販売された年ですが、どっちにしても今のPCから見たらオモチャみたいな代物でした。そんな時代の話です。大阪の長堀にキャノン(カメラのキャノンです)のショールームがあったのですが、そこでとてつもないPCを見たのです。それは当時、キャノンが出資していたアメリカのPCだったのです。今、思えば、私がWindows のようなGUI(今では当たり前のウィンドウやアイコン、ボタン、プルダウンメニューと、マウスなどで操作できるインターフェース)を見た最初でした。それが「NeXT cube」。私が見たのは1980年代後半だと思います。NeXT cube を製造、販売してたのがアップルのスティーブ・ジョブズです。彼が、アップル共同創業者の1人だったジョン・スカリーとの社内抗争に敗れ、同僚5人をひきつれてアップルを離れ「NeXT社」を立ち上げたのが1985年だったのです。そして最初のマシンNeXT cube が発売されたのが1988年(昭和63年)。ここから1993年(平成5年)までNeXTのマシンは販売されるのですが、スーパー・パーソナル・ワークステーションと云う名の通り、性能はバツグンだけど個人が買うにはあまりに高すぎて、1990年時点で月間わずか500台しか売れなかったのです。そんなNeXT cube に搭載されてたのがWindows でもなければ、Mac OSでもありません。NeXT STEPと云う、1960年代中頃マサチューセッツ工科大学、ベル研究所、GEが開発開始した「UNIX」と云うOSを改良したものでした。NeXT cube は商業的に成功しなかったものの、明らかに時代を先取りしたPCでした。NeXT STEPの特徴的なウィジェットがWindows95のシェルデザインの原型になったほどです。そして2000年にアップルのCEOに返り咲いたスティーブ・ジョブズは、アップル社内でのOS開発が暗礁に乗り上げている状況を見て、NeXT STEPを新しいアップルOSのベースにすることを決心します。こうして出来上がったのが、現在の「macOS」の基礎となったのです。つまり現在のMac のOSはUNIXベースなんですね。それと同時にアップルが「マッキントッシュ(Macintosh)」時代に外部から買い入れてたOSがあります。「BeOS」発表当時、PowerPC(昔、Mac で採用されてたマイクロプロセッサ)で動くMac OSよりも遥かに高速に動作し「PowerPCの真価を発揮した」とユーザーを驚かせたOSです。つまり、スティーブ・ジョブズは、NeXT STEPとBeOSのいいとこどりをしてmacOSを完成させたのですね。しかしBeOSを運営していたBe社の経営状況は悪化していって、2001年に解散してしまいます。それによってBeOSの歴史は終わりをとげたのです。しかしBeOSには熱烈なファンも多く、2002年以降、オープンソース(誰もが自由に利用、表示、変更、配布できるコード)プロジェクトがBeOS再構築のために動き出します。先ずドイツの会社が「ZETA」と云う名前でBeOSベースで開発したOSが登場しました。これはオープンソースではなく、商用でしたが、後にオープンソースに変更になります。ところがZETAがBeOSの海賊版であると訴えがあったため、これ以降、開発が取りやめになりました。代わって登場したのが「Haiku(ハイク)」プロジェクトです。Haiku は完全なオープンソースなので無料です。名前から察せる通り、名称は「俳句」からきてますが、それ以上の理由はないみたいです。Haiku の特徴は古いハードウエアでも高速なのに、複雑な用途にも適用できるぐらい高性能らしい。なんせインテルが1997年に発売したマイクロプロセッサPentium Ⅱ、メモリ256MB以上で動くし、OSのインストールに使用するHDDの空き容量は最低3GBしか要求しないのですから。Haiku のプロジェクトが発足したのが2001年ですが、いまだに正式リリースされていないのですね。それでも消滅することなく開発が続けられています。こんなにリリースが遅いのは、プロジェクトに参加してる人数が少ないのでしょう。Haiku は実用性よりも、懐かしさを楽しんでる人に支持されてるようですが、なんせマイナー中のマイナーOSだけに、対応するアプリも数少ないです。なのにBluetooth とかも対応してるし、不思議なOSです。で、遊んでるデスクトップPCがあるので、Haiku をインストールして立ち上げてみました。こんなOSインストールしようなんて酔狂な方はおられないでしょうから、インストール方法は割愛しますが、すんなりインストールできて立ち上がりました。サスガに立ち上がりはものスゴく早い。なんですが、使い勝手が悪いですね~文字入力こそGoogle が開発したLinux(リナックス)用日本語入力のMozc が使えますが、デスクトップ環境が特異すぎて使いづらいったらありゃしない。まぁ、これも慣れでしょうが、対応するソフトもまだまだって感じだし、こりゃあ将来を待つしかないか。なんとなくNeXT STEPの雰囲気だけ味わった気分でお仕舞い。
Feb 9, 2023
コメント(6)
-

言葉の世界
タイに在住してたころ、神戸生まれで神戸育ちのチャイニーズの知り合いがいました。この人、日本語はもちろん、中国語(どこの方言か記憶にありません)、英語、フランス語、タイ語と5カ国語の会話ができたのですが、それぞれの言葉が喋る言語によって、その国のネイティブと間違われるくらい達者だったのです。中国語はご存知のように土地土地で話す言葉も違えば、漢字も違うことが多いので、いきおい中国人は耳がいいからだと聞きましたが真意のほどは?中国の人口は約14億人ですから、中国語を母国語としてる人が世界で最も多いと思いがちですが、統計によっては英語がトップで、中国語は第2位ってのも結構見受けられます。これは一口に中国語と云っても、中国7大言語と呼ばれる北京語、広東語、福建語(台湾も)、江浙語、湖南語、江西語、客家語 以外に各地方地方で独特の言葉(方言)が存在し、「中国語」と云うジャンルでひとくくりにできないからだと思います。特に広東語と上海語なんて、北京語とイントネーションが全く違っているので、中国人同士でも聞き取れないことが多々あります。欧州の人は多言語をあやつる人が多いですね。なんせスイスみたいに自国の中でさえドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語(スイスのグラウビュンデン州のごく限られた地域でしか話されていない)と4つの言語が混在してるのですから。フランス人みたいに、英語が理解できてもフランス語しか話せないフリするのもいるし(笑)私が親しくなったドイツ人もドイツ語以外に、英語とスペイン語、そしてポルトガル語を話していました。スイスは上の画像の通り「スイス語」なるものは存在しないワケです。とは云え、スイスで話されるドイツ語、フランス語、イタリア語もみんなドイツ、フランス、イタリアとは微妙に違うのですね。例えば「スイスドイツ語」はドイツ語の方言で、アレマン語(ドイツ南西部の方言)に属する高地アレマン語が核になってます。ところが同じスイスドイツ語でも、ベルン方言、チューリッヒ方言、ウーリ方言、ツーク方言、ザンクトガレン方言など、これまた言葉に微妙に違いがある。つまるところ日本で云うと同じ東北弁でも、青森や秋田で使われる北奥羽方言と宮城や福島で使われる南奥羽方言があるみたいなものです。もはや人口世界一の中国に、人口で追いつき追い越せの勢いあるインドはご存知のようにヒンディー語が公用語ですが、ぢゃあ世界で使われてる言語の順位はと云うと3,4位に甘んじてる。なんせインド国内には数千の言語が混じり合って使用されているのですから、ヒンディー語だけ見たらこんな順位になるのですな。その代わり準公用語に英語があるから、違う地方の人でも英語で会話することができるワケです。シンガポールみたいに「シンガポール語」そのものが無くて、マレー語、イギリス英語、香港台湾式中国語、タミール語と多言語を混用して使ってる国ってのも多いですね。実は「国」という単位と「言語」という単位とが一致しないということは、世界ではごく普通のことです。さらに自国の言語のほかに英語を公用語、準公用語としている国も数多くあります。ヨーロッパではアイルランドはもちろん、EU(欧州連合)全体がそうですし、アメリカ大陸だとカナダ、ジャマイカ、バハマ、トリニダード・トバゴなど。アジアで云えば、先程述べたシンガポールやインドの他にスリランカ、フィリピン、香港もそうですね。アフリカは、ウガンダ、カメルーン、ガーナ、ケニア、タンザニア、南アフリカなんかがそうです。オセアニアだってオーストラリアとニュージーランド以外に、パプアニューギニアやパラオなどもそうです。英語を公用語、準公用語としているのは、実に50近い国や地域にのぼるのです。そう云うイミで、世界で最も話者が多い言語は前述の通り13億4,800人の英語です。続いて「北方言語の語彙」と「北京官話」の発音をベースに人工的に作られた標準中国語で、11億2,000万人。次がヒンディー語とスペイン語の約6億万人、5位にフスハーと呼ばれる現代標準アラビア語が2億7,400万人と続きます。では日本語は?そんなん独特のムツカシイ言語だから日本人以外ほとんど居ないでしょう。と、思いますよね。確かに世界の中ではマイナー言語ですが、日本の人口が1億257万人(2021年)ですから、これだけで世界の中で話されている言語の中でも10位前後に位置してるのです。そこいくと、韓国の人口は5,174万人(2021年)ですが、世界的に見たら8,800万人で世界20位。日本より人口が少ないから、世界的に見たら健闘してるワケですが、韓国の場合は中国と同じでアメリカなんかへの移民数が多いこともあげられます。アジア系アメリカ人の人口比率を見ると、韓国系は5番目に多い人数なんです。学者によって数え方に違いがあるのですが、世界の言語の百科事典とも云える「エスノローグ(Ethnologue)」によると、現在、世界には6,912の言語があると云われてます。それが言語学者によって世界の言語数が3,000~7,000と、開きが大きいのは「言語」と「方言」を区別する基準が存在しないからです。エスノローグの分類だって、例えば日本語でも「琉球諸語」と云う奄美語、国頭語、宮古語など方言も個別に数えてるので、日本だけで15の言語が存在するとしているのですから。それがヨーロッパだと東ヨーロッパだけで、ウクライナ語、ロシア語、ベラルーシ語、チェコ語、スロバキア語、ハンガリー語、クロアチア語、ルーマニア語、アルメニア語とあり、北ヨーロッパはグリーンランド語、アイスランド語、ノルウェー語、スウェーデン語、フィンランド語、エストニア語、ラトビア語、エストニア語、デンマーク語。西ヨーロッパはイギリス英語、ドイツ語、フランス語、オランダ語、ロマンシュ語。南ヨーロッパはスペイン語、ポルトガル語、カタルーニャ語、イタリア語、ラテン語、マルタ語、スロベニア語、クロアチア語、ボスニア語、セルビア語、アルバニア語、ギリシャ語、ブルガリア語、モンテネグロ語、マケドニア語とあって、それぞれに地域による方言が存在するのですから数え方も一筋縄でいかないワケですね。どっちにしても方言は方言として尊重すべきですよね。私がNHKを毛嫌いするのは、どんな地方局のアナウンサーも土地の言葉で喋らなくて、画一的に標準語を使おうとするからです。
Feb 8, 2023
コメント(5)
-
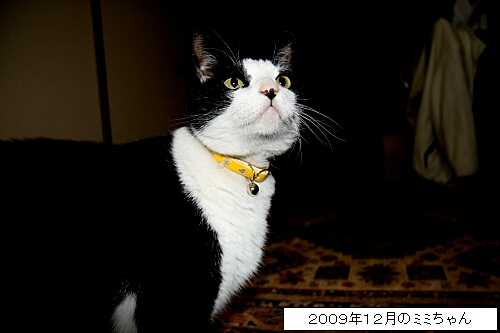
ビル・エヴァンスとモニカ・ゼタールンド
カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞したカトリーヌ・ドヌーヴ主演のミュージカル映画「シェルブールの雨傘」で音楽を担当したミシェル・ルグランが作曲した「Once Upon A Summertime(ワンス・アポン・ア・サマータイム)」。ミシェル・ルグランは「シェルブールの雨傘」以外にも同じドヌーヴ主演の「ロシュフォールの恋人たち」やスティーブ・マックイーンとフェイ・ダナウェイが主演した「華麗なる賭け」など数々の映画音楽を担当しましたね。「Once Upon A Summertime」の原曲は1954年にルグラン自身が創唱したシャンソン「La Valse des Lilas(リラのワルツ)」です。「Once Upon A Summertime」ってタイトル通り今の季節感ではなく、夏の終わりに聴く曲ですが、なんとなくYouTube 探してたらビル・エヴァンスのピアノでスウェーデンの歌姫モニカ・ゼタールンドが歌ってる動画が見つかりました。ビル・エヴァンスと云えば60年代~70年代を代表するモダン・ジャズのピアニスト。ジャズ演奏家としては少数派の白人ですが、彼が作った曲の多くが、後続のジャズ・ミュージシャン多くにカバーされるスタンダード・ナンバーとなっています。共演のモニカ・ゼタールンド。生まれはスウェーデンですが、幼いころからビリー・ホリデイやエラ・フィッツジェラルド、サラ・ヴォーンなど一流ジャズシンガーの曲を聞いて育ったほどジャズにベッタリの生活。穏当で、はかなげで、詩的と云った、彼女ならではのサウンドを引き出し、北欧ジャズの顔と言える存在でした。スウェーデン人女性シンガーでは最高の一人となりましたが、2005年にストックホルムの自宅マンションで発生した火事で悲劇的な最後を遂げました。それではビル・エヴァンスとモニカ・ゼタールンドの「Once Upon A Summertime」お聞きいただきましょうかね。Bill Evans & Monica Zetterlund - Once Upon a Summertime「Once Upon A Summertime」は名曲なので、他のプレーヤーも数多くカバーしてます。ウエストコースト・ジャズの代表的トランペッター"チェット・ベイカー"や西ドイツ生まれのジャズ・トランペッター"ティル・ブレナー"も演奏してますが、私は他の歌手ではスウェーデンのジャズ・アカペラグループ「ザ・リアル・グループ」でソプラノ担当していたマルガリータ・ベンクトソンがいいですね。なんだ!好みの歌手がジャズシンガーなのにふたりとも奇しくもスウェーデンの歌手(笑)まぁ、作曲のミシェル・ルグランもフランス人だし、ヨーロッパ系でかためたってことですかね。Once upon a summertime - Margareta Bengtson
Feb 7, 2023
コメント(5)
-

外国人アーティストとサントリーCM
先日とりあげたバド・パウエルの名曲「クレオパトラの夢」はサッポロビールのCMに使われてたことがありました。お酒のCMに海外の音楽を使うのはよくありますね。「いいちこ」みたいな焼酎のCMでさえ、1986年にはポルトガルの歌手"アマリア・ロドリゲス"の「Flor de lua(ムーンフラワー)」を使ってました。サントリーのCMで云えば、2015年に佐藤健が出演したウイスキー「知多」CMに、アニメ「銀河鉄道999」の曲をスウェーデンのジャズ・ミュージシャンがヨーロピアン・ジャズに再構築した曲を使ってました。古くは1973年に放映されたサントリーホワイトCMに"サミー・デイヴィスJr."が出演して、カンヌ国際広告祭でグランプリを受賞しましたね。サミー・デイヴィスJr.は1988年の「モンカフェ」CMにも登場してました。1988年にはブラジル出身のジャズ・ピアニストでボーカリスト"イリアーヌ・イリアス"が歌うヒット曲「コンチネンタル(The Continental)」、そして1989年には"マット・モンロー"の「慕情」が流されましたが、これらはみんなバックで歌ってるだけで、ご本人は登場してないです。同じ1989年にレイ・チャールズの有名なサントリー・ホワイトCM「いとしのエリー」が流されましたが、これも前半はブリキのレイ・チャールズ人形。後半になってやっとチョット顔のぞかせるだけ。レイ・チャールズは後に最初からちゃんと登場してるサントリー・ホワイトCMが流されましたね。アメリカのフュージョン・グループ"ガッド・ギャング"がそのまま登場してるサントリー・ホワイトCM「HOTで行こう」が流されたこともあります。リーダーのスティーヴ・ガッドを始め、リチャード・ティー、コーネル・デュプリー、エディ・ゴメスと結成時のメンバーが勢ぞろいしたCMでした。まぁ、しかし私にとってサントリーのCMと云うと、この人がイチバン印象深い。"ロン・カーター"。アメリカのジャズ・ベースシストですね。最初はクラシックのコントラバス奏者を目指して猛練習したのに、人種差別の壁にはばまれてオーケストラ入りできない。それで止むなくジャズベーシストとして活動を開始した人物です。マイルス・デイヴィスに抜擢され、60年代マイルス・ミュージックの屋台骨を支える重要な役割を果たします。来日回数もとても多いミュージッシャンですね。大の親日家。そしてロン・カーターが出演したサントリー・ホワイトのCMがこちら。RON CARTER SUNTORY WHITE TV-CM 1ロン・カーターは第一生命の「リード21」や「タリーズコーヒー」のCMにも登場してたことあります。また姿は写してないけどジャズ・ピアニスト"ハービー・ハンコック"のサントリー・ホワイトCMにドラムのトニー・ウィリアムスとともに、演奏で参加してたこともあります。では最後にロン・カーターとギタリストのジム・ホールが演奏している「枯れ葉」でもお聞きいただきましょうか。Jim Hall & Ron Carter - Autumn Leaves
Feb 6, 2023
コメント(5)
-

ヤマアラシの顔
アメリカのテレビ司会者にジミー・ファロンと云う人がいます。アメリカ3大ネットワークのひとつNBCの深夜トーク番組「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」の司会を務めている人物です。もともとは映画俳優で、コメディ映画「あの頃ペニー・レインと」なんかに出演してました。そのファロンが司会を務める「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」にイギリスの博物学者クリス・パッカムが登場したときのこと。パッカムがアフリカ クレステッド ヤマアラシと云う大型のヤマアラシを連れてきました。そしたら番組の途中でパッカムがファロンに「ヤマアラシのニオイ嗅いでごらん」。最初はイヤな顔するファロン。でも、仕方ないからこわごわニオイ嗅いだら「なんと云うこともないね」。案外、いいニオイだったらしい。そしたら今度は巨大で有毒なミズオオトカゲをパッカムが登場させた!そしてヤマアラシと同じように「ニオイ嗅いでごらん」。「遠慮しときます!」(笑)いくら人になれやすい性質のミズオオトカゲでも、そりゃあニオイ嗅ぎたくないですよね。このやり取りがYouTube で公開されてます。この動画、とにかくパッカムとファロンの掛け合いがオモシロ過ぎる。動画の中程からミズオオトカゲが登場するので、爬虫類ニガテな人はご注意を...Chris Packham and Jimmy Sniff an African Porcupine身体に鋭い針毛をもってるヤマアラシ。この針は、もちろん外敵から身を守るためのものですが、ヤマアラシは、むしろ積極的に外敵に攻撃をしかける攻撃的な性質をもってるのですね。肉食獣などに出会うと、相手を威嚇するだけでなく、背中の針を逆立てて、相手に対し後ろ向きに突進します。針毛は硬く、その強度はゴムの長靴を貫くほどらしい。また肉食獣に捕食された場合でも、針が相手の柔らかい口内や内臓を突き破り感染症や疾患を引き起こさせ、ときとして死亡させるほど。要するにやられたらやり返すのを忘れない。ヤマアラシにイタズラ仕掛けたワンちゃんの末路が下の画像。「ヤマアラシのジレンマ」と云うドイツの哲学者ショーペンハウアーの寓話に由来する哲学用語があります。寒空にいるヤマアラシが互いに身を寄せ合って暖め合いたいのですが、針が刺さるので近づけないと云うことから、「自己の自立」と「相手との一体感」という2つの欲求に対するジレンマを表したものです。実際のヤマアラシは、針のない頭部を寄せ合って体温を保ったり、睡眠をとったりしているそうですよ。しかし、ヤマアラシってのは、よく見るとカワイイ顔してますね~とくに赤ちゃんヤマアラシのカワイイことったら。ヤマアラシと同居するのはど~なんでしょう?絶滅危惧種ではないので、同居は可能らしいけど、ほとんど売ってないらしい。たまに売ってるのを見かけても、価格は50万円ほどはするらしい。だいいち同居してて具合悪くなったら、その辺の動物病院では対処できないでしょうしね。それに体長が大きいので、広い飼育スペースが必要になります。屋外で飼育することもできますが、冬場は暖房を入れてやる必要もあってなかなか手ごわい。やはり動物園で眺めておくのがいいみたい。
Feb 5, 2023
コメント(6)
-

バド・パウエルと云う天才
1986年にジャズ・サックス奏者のデクスター・ゴードンが主演したアメリカ・フランス合作の映画があります。この映画の音楽担当は、60年代以降から現在までジャズ・シーンをリードするジャズの第一人者"ハービー・ハンコック"が担当なんです。映画のタイトルは「ラウンド・ミッドナイト」。ストーリーはパリを舞台に、ジャズ・テナーサックス奏者のデイル・ターナー(デクスター・ゴードン)と、デイルの音楽を愛しサポートする青年フランシス(フランソワ・クリュゼ)の友情を描いたものです。この作品にはディカプリオが主演した映画「ギャング・オブ・ニューヨーク」の監督" マーティン・スコセッシ"が興行師役で俳優として出演してます。この映画の主役はテナーサックス奏者を主役にしていますが、実は実在のアメリカ人ジャズ・ピアニスト"バド・パウエル"がパリで活動していた時期の実話が元になっているんですね。同時に青年フランシスのモデルも実在のフランス人デザイナーでした。1960年代初頭、アメリカにジャズ不況が訪れ、多くのジャズメンがヨーロッパに活動の場を移した時期です。パウエルもまたフランスに渡って活動を続けたのです。パウエルは、40年代後半~50年代初頭にかけてジャズメンとしての最盛期を迎えますが、50年代中期以降は麻薬やアルコールの中毒に苦しみ、精神障害まで負います。その環境を変えるイミでもフランス行きは良かったのでしょうか、フランスに渡ったパウエルは麻薬依存から脱却したのです。しかし、すでに身体はボロボロで、1966年にアメリカに帰った後、結核、栄養失調、アルコール中毒が原因で死去しました。パウエルは、唸るような「ジャングル・スタイル」と呼ばれるトランペット奏法で知られる"クーティ・ウィリアムス"のバンドで1943年にデビューします。やがて彼はジャズピアノにおけるビバップスタイルのパイオニアとして知られるようになるとともに、クラシックを思わせるような完成された芸術性と、音からリズムを感じるような力強くキレのある演奏で、多くのジャズミュージシャン憧れの存在になっていくのです。まさにパウエルは、天才でした。右手でシングル・トーン、左手でコードを弾き、ベース、ギター、ドラムスのどれか伴ったピアノ・トリオでジャズを聴かせるというスタイルを定着させた偉人です。彼の技巧的なピアノ・プレイにより「ピアノのチャーリー・パーカー」と呼ばれたのです。1963年に発売されたテナーサックスの"デクスター・ゴードン"の名盤として人気の高い「アワ・マン・イン・パリ(Our Man in Paris)」。ロス出身の彼もまたフランスやデンマークを拠点に活動してた時期です。この「アワ・マン・イン・パリ」に当時フランス在住してたパウエルも参加しています。そして、やはりフランスに拠点を移してたニューヨーク出身のジャズ・ドラマー"ケニー・クラーク"も。ぶっきら棒なテナー、ドラムはせわしなく落ち着かず、パウエルのピアノは何故か弱々しい。実はこのアルバム、デクスター・ゴードンは当初、全曲自分のオリジナル曲で制作するつもりでしたが、体調がすぐれないパウエルが新しい曲を弾くのを嫌がったのですね。すったもんだしている間に、パウエルがお酒を飲みだしたので、泥酔する前にレコーでイングしなければならなくなったのです。結局、パウエルが演奏し慣れたスタンダードナンバーを、ほとんどワンテイクで録音したのだと云う話です。デクスター・ゴードン「アワ・マン・イン・パリ」Dexter Gordon - Scrapple From The Appleブルーノート、ルーレット・レコードなどのレーベルに名演奏を残すバド・パウエル。彼のアルバム代表作には「バド・パウエルの芸術」「アメイジング・バド・パウエル」「ジャズ・ジャイアント」「ザ・シーン・チェンジス」「バド!」など。そして数多くの作曲もしてます。バド・パウエルが作曲し演奏した1959年リリースの「クレオパトラの夢(Cleopatra's Dream)」。もう日本人のジャズファンだったら、この曲しかないでしょう。とにかく日本で圧倒的な人気を誇ってる曲ですね。医師で音楽ジャーナリストの小川隆夫は「かつてジャズ喫茶全盛のころ、この曲がかからなかった日はなかったほどヒットしたものだ」と。収録アルバム「ザ・シーン・チェンジズ」のジャケット写真でパウエルの右側から顔をのぞかせてるのは、当時3歳の愛息アール・ダグラス・ジョン・パウエルです。では最後にパウエルの演奏で「クレオパトラの夢」、お聞きいただきましょう。Cleopatra's Dream
Feb 4, 2023
コメント(5)
-

町工場の挑戦
神奈川県茅ヶ崎市に由紀精密と云う航空宇宙事業や医療といった先端分野の精密部品の切削加工をする会社があります。私も知らなかった社員40人くらいの会社だったのですが、ある製品でいちやく有名になった会社なんです。単なる部品メーカーの由紀精密がこれまで一度も手掛けたこと無い製品でしたが、これまでの常識を覆す画期的な製品だったのです。それは「AP-0」と名付けられた「レコードプレーヤー」です。このレコードプレーヤー、何が画期的かと云うとプラッター(レコードを乗せて回転させる部分)から、それを支えるシャフトまでの回転部が最下部の球1点のみで接触し、回り続けるコマのような構造になってることです。そのシャフトはマグネットで浮かせたセラミックスの点接触で受けて、ベアリングノイズのない静粛な回転が実現されてるのですね。さらにプラッターを回転させるのに、普通はモーターから1点でベルトや糸を使って動力を伝えてるのに、AP-0はモーター側とは反対方向にもシャフトがあって、この2本のシャフトでドライブ糸から受けるテンションバランスを取っているのです。トーンアームはカートリッジのバランスを保ち、適切な針圧でレコードの音を正確にトレースする装置ですが、これも由紀精密オリジナルです。材質はステンレス。あえてストレートのトーンアームにしたのは、カートリッジのカンチレバーの延長線上にアーム支点があって、プラッターの回転で針先が引っ張られるとき、カンチレバーに不要な横方向の屈曲力を掛けさせないためです。要するにアームに無駄な首振りをさせないことを重視したのですね。このプロジェクトを推し進めたのは現在、由紀精密の社長をやってる永松 純が事業部長だった時代です。当時の社長から裁量の範囲でリソースを任されていたので、自由にモノが作れたのですね。そして永松はオーディオとクラシックに没頭するマニアだったのです。永松は考えました「小さな会社が同じ事業を続けていては、国内のマーケットの縮小もあって、やがては下降線をたどる」と。「常に新しい挑戦をしていかなければ成長は望めない」とも。そうして発足したプロジェクトは20代~30代の若手エンジニア3人をスカウトして発足しました。ところがメンバーの反応がイマイチ。そりゃあそうですね、彼らはレコードを知らない世代なんですから。それで永松は自宅に招いて自慢のレコードコレクションを披露、自分のオーディオを聴かせたのです。「みんなびっくりしていました。レコードって、こんなにクリアな音がするんですね!」で、これをやろうと云うことになってプロジェクトは始動し始めたのです。ところが、このプロジェクトはなぜか社長に極秘で進行していったのですね。プロジェクト発足から1年が経った2018年、試作品ができあがり、ついに当時の社長にお披露目することとなりました。社長の反応は...「そう来たか!」。思いもよらぬプロジェクトでしたが、社長は大喜び。晴れて社長公認のプロジェクトとなったオーディオ開発。プロジェクト発足から都合2年半かけて完成したのが「AP-0」と云うワケです。普段、自社製品がどこでどのように使われてるか知る由もない切削加工会社の社員。それが初めて、自分たちで作り上げたものが製品そのものと云う喜びを味わったワケです。永松の狙いはそこでした。社員のモチベーションを上げることが最も重要な目的だったのです。いまやAP-0は国内のみならず海外からの問い合わせも多くなってます。お値段は高いですよ~200万円です!そうそう売れる価格帯ではないので、受注生産品です。
Feb 3, 2023
コメント(7)
-

アルゼンチン料理
アルゼンチンの料理と云うと"牛肉"ってイメージ強いですね。実際、アルゼンチンの牛肉年間消費量は1人当たり平均100kg に及びます。なかでも有名なのが「アサード(アルゼンチンのバーベキュー)」。ブラジルのシュハスコみたいに、火が立つ炭火で炙るように焼くのと違い、火も弱まった熾火の熱で部位そのままのブロック肉を燻すように焼きますね。それで、焼き上がりまで1時間ほどの長時間を要します。アサードはアルゼンチン以外でもチリやパラグアイ、ウルグアイなんかでも食されてますが、味付けは基本的に岩塩のみです。質実剛健そのものみたいなお料理ですね。アサードで加熱調理した「チョリソ」ソーセージをパンで挟んだ「チョリパン」は、安くて美味しいストリートフードです。このチョリパンにはオレガノ、パセリ、ニンニク、唐辛子、赤ワイン酢を混ぜて作った辛口ソース「チミチュリ」やトマト、タマネギ、パプリカで作った辛口のソース「サルサ・クリオージャ」をたっぷりかけて食べるのが定番です。まぁしかし、画像が見事に肉々しいですね(笑)アルゼンチンでよく食べられるお肉に「リャマ」もあります。リャマ。そうラクダ科のカワイイお顔の生き物ですが、アルゼンチン北西部ではリャマのステーキが普通に食されています。リャマの肉は牛肉に比べ、素朴な味で土臭さは有るそうですが、脂肪分が少ないため牛肉よりは健康的なんですな。ステーキやシチューに入れるのが普通ですが、カルパッチョやタルタルステーキにしても食べられてるそうです。アルゼンチンのストリートフードでチョリパンとともに有名なのが「エンパナーダ」。エンパナーダは、パン生地を折りたたんで具を包んだ食べ物ですね。エンパナーダは「パンで包む」という意味で、焼いたり、揚げたり調理法は問いません。また包む具によって野菜料理にもなれば肉料理にもなります。一般に具として使用されるのは鶏肉、チーズ、ハム、スイートコーン、カプレーゼ、ブルーチーズなどですが、牛肉も細切れ、薄切りともに具としてよく使用されるし、先程でてきたリャマの肉もエンパナーダの具材として使用されます。「トンカツ」に似た料理もあります。「ミラネーサ」。要するに、肉に衣をつけて揚げたものですね。ミラネーサのもとになったのはイタリアのミラノ料理「コトレッタ・アラ・ミラネーゼ」だと云われてます。ミラネーサ、通常は牛肉のもも外側の部分「シルバーサイド」か鶏の胸肉ですが、仔牛肉が使われることもあります。ミラネーサに目玉焼き、チーズとトマトソース、グリエルチーズなどのトッピングが一般的ですね。まぁ、しかし、どのお料理も日本料理のような繊細さが微塵も感じられませんな(笑)だいたいアルゼンチン料理ってのはイタリア系、スペイン系移民の影響を強く受けてますからね。それに北西部のアンデス地方や南部パタゴニアで採れた食材も使うらしいです。アルゼンチンのピザ、見た目はナポリのピザにやや似ていますが、似ているのは見た目だけです。クラストの表面に塗られるトマトソースの量は控えめなんですが、その上に乗っかってるアルゼンチン風モツァレラチーズの量がハンパないのです。名前そのものが「ムッツアレラ」と云うモッツアレラチーズを使ったピザが下の画像。「フガセッタ」ってピザも有名です。こっちはモッツァレラチーズとともに、タマネギもふんだんに使ったピザです。これにハムをトッピングしたり、お店によってバリエーションは豊富。他にはルッコラと生ハムがトッピングされた「ルクラ・イ・ハモン・クルード」とか4色チーズピザ「クアトロ・ケソ」とか、ピザの種類は豊富ですが、元がナポリピッツァなので生地が厚め。クリスピーなミラノピッツァの方が好きな私には、生地の厚いのはかなり重いですね。イタリア北部パダーナ高原などで生産されるセミ・ハードタイプのチーズ「プロヴォローネチーズ」のアルゼンチン版「プロボレタ」は、そのまま食べるとかなり淡泊な食感です。ところがグリルで焼くと、とろりとしたおいしい料理に様変わりするのですね。焼いてから、オレガノをトッピングします。外はややカリカリ、中はとろり。これは見ているだけで美味しそうだけど、ピザとともにカロリーがハンパないでしょうね。アルゼンチンだけでなく、ペルーからボリビア、エクアドル、コロンビア南部で国民食の1つが「ロクロ」と云うシチューのような料理。アルゼンチンでは5月革命記念日の5月25日によく食べられる料理です。牛肉か豚肉に牛か豚の胃袋、白トウモロコシ、赤チョリソ、白豆、ジャガイモかカボチャなどの野菜と一緒に煮込み、クミンとベイリーフで味付けをした料理です。と、まぁアルゼンチンのお肉とチーズ料理中心にご紹介しましたが、アルゼンチンって魚介食べないのかしら?それが近年になって健康志向の富裕層に大人気の食材にかわってきてるらしい。原因は「スシ(鮨)」です。レストランの人気投票でも日本食レストランが上位を占めてます。ところがアルゼンチンのスシは、例えば高級志向のスーパーで買っても、驚くほど不味いらしい。そもそもネタが貧素すぎるし、しかもチョ~高いときてる。海沿いの地域を除いて、ど~やらアルゼンチンでお魚は期待できないらしいです。きのうご紹介した新しいオープンリールデッキ「T-RX」の動画をYouTube で見つけました。説明では欧州のオーディオメーカー22社がこのプロジェクトに参加していたみたいです。T-RXは専用のバッテリーで駆動できるくらい省エネらしい。とにかく素晴らしい外観です。Metaxas Tourbillon T-RX
Feb 2, 2023
コメント(5)
-

2トラ38の逆襲
レコードの人気復活はすさまじいもので、昨年のレコード売上数量が1億3,430万枚、金額で1,528億円。対するCDはストリーミング・サービスが主流になってきたため減少の一途。昨年の実績ではCDシングルの売上数量は4,336万枚、金額で362億円と完全にレコードに逆転されたワケです。レコードの復活とともに「ミュージックカセット」も世界的に復活しています。それもカセットに馴染んでた世代だけでなく、カセットテープに初めて触れる若年層にも、新鮮なメディアとして受け入れられているのです。さらに歌姫アリアナ・グランデなど現代の海外アーティストもCDと同時にカセットでも新作を発表する場面が増えてます。そしたら、今度はオープンリールデッキ人気も世界的に再燃しているらしい。それも昔、高級オーディオファイルと呼ばれてた人たちが使ってた「2トラ38」と云う最高性能のオープンリールデッキが。今の方はご存知ない方が多いでしょうからオープンリールデッキを簡単に説明しますと、オープンリールデッキは巻いた状態の磁気テープを、空のリールに巻き取りながら、その間にテープに記録された音楽を読み取る装置です。これはレコード盤と同じく、完全にアナログの世界。「2トラ38」とはステレオの2チャンネルを1本のテープ幅で録音する方式です。別に「4トラック」と云うのもあって、ステレオ録音を往復で行う方式と、4チャンネル録音を片方向で行う方式があります。つまり2トラと同じテープ幅で4チャンネル録音するので、1チャンネルあたりのテープ幅が2トラの半分になるため、音質的には2トラの方がダンゼンいいワケです。「38」はテープスピードの単位で、安いデッキは19cm /秒ですが、高級機は38cm /秒で走行します。早いほうが音がいいのですね。一般にオープンリールの方がレコードより音質的に優れていると云われます。理由は情報量(ダイナミックレンジ)がレコードよりも広いためです。なのでレコードのように収録するときに、低域と高域の一部をカットする必要がありません。かつてオープンリールデッキのメーカーはアメリカの「アンペックス(Ampex)」やスイスの「スチューダー(Studer)」と同等、いやそれ以上に日本メーカーの独壇場でした。「アカイ(AKAI)」の「GX-747」とさらにその上を行く「PRO-1000」、「ティアック(TEAC)」の「A-6010」、「テクニクス(Technics=パナソニック)」の「RS-1800」、そしてプロ機器メーカー「オタリ(OTARI)」の「MX-5050」シリーズなど銘機ぞろいです。ティアックの「TASCAM 80-8」と云う、1/2インチテープを使用した8トラックオープンリールレコーダーは、1977年に公開されたスターウォーズ第1作「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」で、R2-D2やC3-P0の音声録音に使われました。しかし、日本を含むこうしたメーカーは全てオープンリールデッキ市場から撤退しており、今オープンリールデッキを買おうと思ったら、中古市場から比較的状態のよい製品を探すしかありません。ただテープデッキと云うのは、テープに記録された情報を読取る「ヘッド」やベルト、ピンチローラ、ブレーキドラムなどテープ走行系で摩耗してることが多く、補修部品もなかなか入手し辛いものです。話しは変わりますが、スイスの精密機器メーカーに「トーレンス(Thorens)」と云う会社があります。主にレコードプレーヤーを製造している会社ですが、元々はオルゴール製造の会社で、オイルライターやハーモニカなんかも製造していました。トーレンスの代表作と云えばレコードプレーヤーの「リファレンス(Reference)」。1979年に発売されて100台しか売れてません。理由は価格。なんと現在の中古価格でも600万円は優にします。そのトーレンスが2018年にオープンリールデッキを新発売したのです。ベルギーのオーディオショップでの販売価格は11,999ユーロ(約150万円)とやはり高価です。このデッキは再生、早送り、巻き戻しと3つのモーターを備えており、片手操作用の編集機能を搭載を搭載してます。また干渉を防ぐために、電源は外部に別に用意してます。この辺は単に懐古的なデッキ作りに走らず、新しい技術はどんどん取り入れてるのですね。ところがオープンリールデッキを新規に製造してるのはトーレンスだけではないのです。ドイツの「バルフィンガー(BALLFINGER)」もそのひとつ。元々は卓上ランプや高級腕時計を製造していた変りダネです。こっちはオープンリールデッキ全盛期には考えられなかったリモコンまでついてます。価格は200万円~400万円。他にもフランスの「アナログオーディオデザイン(Analog Audio Design)」のオープンリールデッキ「TR-1000」や、アムステルダム在住のデザイナー"Kostas Metaxas"が手掛けるポータブルタイプ オープンリールデッキ「T-RX」と新らしいオープンリールデッキの開発が進んでます。日本ではTEAC(ティアック)だけが修理を受け付けてただけですから、はたして日本で2トラ38が復活するのか?何よりもオープンリールデッキで再生する音楽ソースが数少ないですし、見つけてもものすごく高価ですからね。それでも徐々に新しいミュージックテープが販売され出しました。
Feb 1, 2023
コメント(6)
全28件 (28件中 1-28件目)
1










