2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年10月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-

名古屋でも食い倒れる その11 ~ パステルのなめらかプリン
ケーキショップで購入する洋菓子をコンビニで買うのが当たり前になったのは、私の主観で1990年代後半からだと思います。 カップ入りデザート、特にプリンは「プッチンプリン」から「クリームブリュレ」へ変化して行きました。 脂の味を覚えたということでしょうか(^^;)。 最近のプリンは、濃厚で滑らかな食感を持つものが多く、共同乳業のプリンの「隠れ家レストラン・代官山 加賀田京子シェフ」が手軽に体験できる濃厚な味だと思います。 市販プリンのレベルとしてはかなり高いものです。 パステルは北名古屋市の「チタカ・インターナショナルフーズ株式会社」という総合外食産業が展開するブランドの一つで、主力商品はプリンです。 名古屋を中心に中部、関西、関東へ進出しており、三層に分かれた濃厚なプリンはたくさんのファンによって支えられています。 パステルは持ち帰り専用(洋菓子専門)の店舗と、レストラン形式(パスタ、ピザ、グラタンを中心とした軽食)の2種類があります。 JR名古屋駅に近い場所で、前者はJR名古屋駅に隣接する高島屋の地下1階、後者はJR名古屋駅桜通りの「ユニモール地下街」にあります。 パステルのプリンの特徴は、以下の点にあります。 ・クリームブリュレのような、濃厚で滑らかな食感。 ・三層に分かれ、違う食感と味が楽しめる。 ・豊富な種類。月代わり商品、季節限定商品が多数。 1個の価格は294円~400円弱まで、種類により異なります。 パステルは初めてなので、定番と思われる「なめらかプリン」と「なめらか抹茶プリン」を購入することにしました。 1個あたりの重量は重く、食べ応えがありそうな予感がします。 横から見ると、なにやら層というかグラデーションになっています。 なめらかプリンは、薄いクリーム色をしています。 なめらか抹茶プリンは、抹茶色は薄く上品な色をしています。 頂いてみると、クリームブリュレよりはしっかりしていますが、プリンのようなぷるぷる、しっかり感はありません。 高脂肪生クリームベースのカスタード生地で、卵黄のみで固めたような感じでしょうか、油の粒が形を保っているのみという印象です。 食感は滑らかで、甘さは程よく、食べ進むにつれて卵の味が濃くなり、最後はカラメルの層が現れます。 油脂と砂糖のバランスがよく、何といってもクリーミーなので、食べて大満足です。 最近の市販プリンを食べ慣れていれば、取り立てて感動するものではありませんが、多種多様なプリンやその他のデザートが、月代わりで飽きさせないように販売されているのが特色なのかなと思いました。 また名古屋へ行くことがあれば、新しい味わいのデザートを頂きたいです(^^)。 検索すると、なんとパステルのなめらかプリンの作り方がありました。 これは是非試してみたいです。 さらに、ネット通販「パステルネットショップ」があり、なめらかプリンは輸送中に崩れるため販売はされていませんが、窯出しなめらかプリンという輸送に耐えうるプリンを販売しています。
2006年10月29日
コメント(4)
-
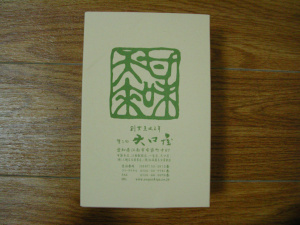
名古屋でも食い倒れる その10 ~ 大口屋の餡麩三喜羅
JR名古屋駅構内のお土産ショップへ行くと、広島とは比べ物にならない程の多彩なお土産があります。(正直なところ意外でした、、、) どのお土産を見ても、地方のお土産レベルを飛び越えたあかぬけたものばかりで、選択に困る程においしそうです。 青柳・大須ういろう、ゆかり、うなぎパイといった定番中の定番はショップで売っています。 カエルまんじゅうはどこででも売っているとは言い難いですが、地下街や高島屋で普通に入手できます。 このようなショップで売られていなく、わずかな売り場でしか見ることが無いため気軽に買いにくい、しかし全国的に知名度が高く、洗練されたお菓子があります。大口屋の餡麩三喜羅(あんぷさんきら)という麩まんじゅうです。 売り場がこれだけですので、一番気軽に買うことができる店舗が、JR名古屋駅に隣接する百貨店「松坂屋」の1階の売り場です。 夕方の4~5時には売り切れるようです。 日曜日の夕方4時に行った時は、前の女性が50個買って帰られたので焦ったことがあります(^^;)。 さらに翌週名古屋へ行った時は、神戸から来られた様子の女性2人が70個買って帰られたので、呆然としました。 広い年齢層から強い支持を得ている渋いお土産なのです。 大口屋がある江南市は、名古屋市の北20kmに位置する都市で、名古屋のベッドタウンであり、工業都市でもあり、岐阜県に近い場所のため、麩を使ったお菓子をよく食べる地域なのだそうです。 創業は1818年と老舗の和菓子屋さんですが、餡麩三喜羅が発売されたのは1973年と比較的最近で、今では大口屋の看板商品になっています。 いきさつはこちらにあります。 箱を開けてみると、このような感じで入っています。 小ぶりなサイズで、サルトリイバラの葉は丸くカットされています。 広島で昔よく見た、柏餅の葉っぱだな~と思いました。 香りは独特の香気で、懐かしい感じがします。 葉っぱはきれいにはがれます。 薄く灰色というかベージュがかった生地は柔らかく、ふよふよとした手触りです。 パンを手作りされる方ならお分かりになると思いますが、1次発酵後にガス抜きしたパン生地の感触と同じです。 餡麩三喜羅は生麩のまんじゅうで、生麩とは、強力粉のグルテンに餅米の粉を混ぜて蒸し、またはゆでたものですので、強力粉のグルテンで共通したパン生地と感触が似ているのは当然と言えます。 食べてみると、ふよふよと柔らかい生地はよく伸びてふんわり、麩まんじゅうにありがちなもっちりした歯ごたえはありません。 1次発酵後にガス抜きした生地の感触そのままで、火が通っているだけという不思議な食感です。 麩まんじゅうといえば、柔らかくてももっちりした抵抗感があるのに、それが皆無なので、ふわふわした食感と言われるのだと思います。 これはグルテンの量がかなり多いからではないかと思います。 中の漉し餡は柔らかくて緩く、ふよふよした生地に緩い漉し餡が何とも頼りない食感で、するするとのどを通っていきます。 生地は少し塩気が強く、グルテン独特の小麦臭が少しありますが、上品な漉し餡と合わさると、京都の茶菓子のような洗練された味とは違う、ひなびた郷愁を誘う懐かしい味がします。 上品だけどよそ行きぶっていない、ほっとする味です。 後味がすっきりなので、一度に3個ぐらい食べたくなります(^^;)。 つるつるもちもちが特色の麩まんじゅうの中で、ふよふよふんわりな餡麩三喜羅は異色だと思いました。 地元ではお遣い物として法事にもよく使うとのことです。 全国にファンが多いのも納得です。 さらに、餡麩三喜羅は冷凍できますので、ジップロックに入れて冷凍、自然解凍で食べることができます。 柳絲花紅、尾州芭沙羅も買ってみたところ、どちらも雑味が無い味で、大変おいしかったです。 柳絲花紅は甘くてもっちりしたりんごの蜜煮に白あんが入っていて、1個で大満足です。 尾州芭沙羅は薄いシナモン風味の黄身餡が珍しく、お茶によく合いました。 いろいろ食べた感想として、甘いところは甘く、控えるところは控えて、上品だけど洗練され過ぎていないお菓子だと思いました。 商品開発力が素晴らしいです。 広島の和菓子屋は完敗だと思いました、、、 ぜひ広島の百貨店に出展して頂きたいです。 餡麩三喜羅は日持ちがしませんが、なんとネットショップを運営されています。 他の様々な商品も販売しているとのことです。 先日、広島市内の友達にこちらのネットショップより餡麩三喜羅を送ったところ、珍しいと大変喜ばれました。 次は自分用に50個注文しなければ(^^;) 大口屋 大口屋オンラインショッピング
2006年10月22日
コメント(4)
-

名古屋でも食い倒れる その9 ~ ういろう
名古屋のお土産と聞くと、 ・エビフライ ・ゆかり(えびせんべい) ・みそかつ ・手羽先 ・ういろうが浮かびますが、その一つである「ういろう(外郎)」は、一度は食べたことがありますよね。 ういろうとは、「米または蕨(山口市)の粉に砂糖を加え、蒸して作る。黒砂糖で味を付けるのが基本であるが、白砂糖が用いられたり、抹茶、小豆、柚子、桜等が加えられることもある。粉や水分の調整、蒸し具合により、味わいは様々に異なる。」とあります。 名古屋名物の一つでありますが、全国の各地でお土産として作られています。 広島では山口県の「豆子郎」が有名で、頂くとうれしいお土産の一つです。 純然たる和菓子のういろうですが、最近は洋風にアレンジしたういろうが販売されていて、新しい名古屋土産の定番になっています。 名古屋へ行ったら、必ず買って帰りたいういろう2種類をご紹介します。・虎屋のういろう 虎屋は三重県伊勢市の老舗和菓子屋で、現在はういろう専門店になっています。 伊勢の名物ですが、事実上名古屋土産の定番になっています。 青柳や大須ういろう以上におすすめな理由は、 ・生ういろうと呼ばれる日持ちしないういろう。 ・もそもそした食感でなく、もっちりとした食感。温度により歯切れのよさやねっとり感が加わる。 ・程よい甘さで後味がすっきりしている。香りは全体的に薄い。 ・種類が豊富で見た目が美しく、楽しい(季節限定品あり)。と、これまでのういろうの印象を変えること必至です。 ようかん(羊羹)と似ていますが、ういろうと羊羹を比較すると、味の純粋さと濃さで、ようかんの圧勝と思います。 ういろうは米粉を多く使うため、それが食感の特徴である反面、具の味がどうしても米粉に支配されてしまうという構造的な問題があるからです。 ういろうは家庭のおやつとして、ほっとするようなおいしさがあり、それが支持されてきたのではないでしょうか。 虎屋はこの賞味期限が短いういろうを、なんとネット通販しています。 今日初めて知ったのがくやしい(^^;)、是非取り寄せをしなければ!・クレーム・ド・ラトリアの洋風生ういろう ういろうは米粉で作る蒸し菓子なのですが、これを洋風にアレンジしたういろうが「洋風生ういろう」です。 クレーム・ド・ラトリアはコーヒーポーションの「スジャータ」で有名な、めいらくグループの会社で、めいらく = 名古屋製酪株式会社、なんと名古屋の地場企業だったのです(^^;)。 名古屋では地元に就職する人が多いと聞きます。 名古屋にはめいらくの他に、カゴメ、ノリタケなど、インフラ系企業(電力、ガス、銀行など)以外の製造業系が異常に強いのです。 濃尾平野と豊富な水源のためでしょうか、県内に優良企業がたくさんあるというのは、同じく製造業系が強い(?)広島として、うらやましい限りです。 名古屋の独特な気質は、「名古屋みゃーみゃー通信」で読むことができます。 以前、名古屋学という本を購入して読んだ(大変面白かったです)が、紛失してしまったので探さなければ、、、 名古屋を知ることは、江戸時代に変わってしまった日本人の気質を調べることに通じるのです。 話を戻して、洋風生ういろうは、クッキー生地のようなごま入りタルト生地の上にバタークリームを塗り、その上にもっちりした洋風生ういろうが載っています。 このういろう部分は生クリームが練りこんであるらしく、もっちりしていながらこくがあるので、油の味を覚えた現代人向けのういろうと言えます。 味はチョコ、抹茶オレ、小倉、チーズ、キャラメルの5種類あり、どれも特徴があっておいしいです。 JR名古屋駅の高島屋地下で販売しています。 夕方には売り切れていることが多く、人気商品です。 ネット通販して頂けないかと思うのですが、、、 洋風生ういろうは冷凍できます! 名古屋へ行くことがあれば、是非試してみて下さい。
2006年10月15日
コメント(2)
-

名古屋でも食い倒れる その8 ~ 伊勢神宮(内宮、おかげ横丁)
伊勢神宮の内宮は、外宮から5kmほど離れた場所にあります。 そのため、移動はバスを使うのが便利なのですが、7月末の伊勢市は死ぬ程暑く、バスの本数が1時間に2本程度と少ないため、ここは楽に行きたい!と奮発してタクシーを利用しました。 タクシーの運転手さんは大変親切で、いろいろと地元のお話を伺うことができました。 内宮への道がいつも大変混雑すること、道の途中に大きなイオンがあり、地元の人はみんなイオンへ行くようになった、駐車場は平面で無料でなければ行く気にならない(^^)、呉の地元民と同じなんだなぁと納得しました。 内宮付近で下車すると、すぐ近くに「おかげ横丁」が見えます。 たくさんの人でにぎわっています。 お昼時なので、まずは食事に行きました。 海鮮で有名な「海老丸」で、名物の漁師汁を頂きました。 赤出汁の中にはワタリガニ、野菜などがたくさん入っていて、臭みが無い海鮮味噌汁といった感じです。 ご飯とよくあっていて、あっという間に平らげました。 一緒に出てきた伊勢茶の番茶がおいしい! 香ばしくて自然な甘みがあり、入れ方が上手なので渋みがありません。 伊勢茶は知名度が無いために安い価格なのだそうですが、味はかなりいいです。 私は「伊勢 丸中製茶」で、3年前から狭山かおり、無農薬くき茶(かりがね)、極上ほうじ茶を購入しています。 価格の安さからは考えられないくらいにおいしくて、緑茶は変なだし風味が皆無でおすすめです。 お土産を購入するのは後にして、先に内宮へ行きました。 標識に従って進むと、大きな松の木と鳥居が見えます。 内宮へ渡るために、大きな宇治橋を渡りました。 大きな川で、深い山の間に広がっています。 橋を渡ると広い参道があります。 周りにはきれいに手入れされた木があり、人がたくさん歩いています。 しばらく歩いて下ると、五十鈴川の「御手洗場」があります。 流れる水に手を入れると、ひんやりとした力強い流れの水に驚きました。 海は毎日見ているのですが、水の「鼓動」を直接感じる機会がないので、感動しました。 森の中に神社があるので、市内と比較すると少し涼しいのではないかと思います。 しかし、7月末の伊勢は暑かった、、、 湿度が広島より高いので、体力が落ちていくのを感じました(^^;)。 頑張って歩いて行きました。 一通り見終わり、出口付近まで戻ると、冷房が効いた休憩所があります。 伊藤園の「冷梅」(期間限定品)を一気飲みしてしまいました(^^;)。 梅の香りがさわやかで甘さはさっぱり、うちで作る梅サワー(サワー=酢 ^^;)より飲みやすかったです。 休憩所を出ると、伊勢神宮で暮らしている神々しい鶏が散策していました。 内宮を出て、おかげ横丁へ戻りました。 ここで食い倒れるぞ!と、抹茶ソフトクリーム、松坂牛の串(脂身がさっぱりとよい香り、赤みは柔らかくて絶品)などあれこれ食べました。 お土産には虎屋のういろうを買いました。 JR名古屋高島屋でも売っているのですけれどね(^^;)。 赤福の本店で、赤福氷を食べて行こうと思い寄ると、店先にはあふれんばかりのお客さんで一杯でした。 名古屋に戻って高島屋の赤福へ行こうか~!と思い、暑くて体力がなくなった私達は、再度タクシーで伊勢市駅まで戻り、近鉄で名古屋駅へ戻ったのでした。 朝9時過ぎに名古屋駅を出発し、午後3時過ぎには名古屋駅へ戻ってしまいました(^^;)。 目指すは高島屋の赤福!と行くと、10人以上の待ち行列が、、、 赤福氷を食べることなく、広島へ戻ってしまったのでありました。
2006年10月08日
コメント(2)
-

名古屋でも食い倒れる その7 ~ 伊勢神宮(外宮)
伊勢神宮とは三重県伊勢市にある神社で、全国の神社の頂点に立つ神社なのだそうです。 正式名称は神宮です。 伊勢神宮は名古屋から割と近く、近鉄やJRで行くことができます。 名古屋から本数が多い近鉄を使って行くことにしました。 JR名古屋駅から地下道経由で、近鉄名古屋駅を探しながら歩いて行きました。 駅に到着して切符を購入し、出発まで時間があったので、構内を歩いていました。 広島では見る機会があまり無い終点が! 見たことが無い車両がいろいろとあります。 路面電車以外に私鉄が無い広島では、見ることが無い景色です。 JR呉線には103系と115系しか走っていないので、さながら動体博物館状態であります。 こんなかっこいい車両が来て欲しい~! 時間になったので、特急を探して乗車、指定席なので座席を探して着席。 すごくしゃれた感じの内装ではないですか。 走り始めると、線路からの振動が少なくて社内はかなり静かです。 スピードもあまり出ていないような、、、騒音対策でしょうか。 JR呉線はかなりがたがたと揺れますが、これがデフォルトではないのですね、、、がっくり。 列車は快適でらくちんだねぇ~と車窓の景色を堪能しました。 地理の授業でしか見たことの無い地名を見て、津だ四日市だと大喜びです。 伊勢市駅で下車しました。 伊勢神宮は外宮(げくう)と内宮(ないくう)という2つに分かれていて、2つは5kmほど離れています。 最初に、伊勢市駅から徒歩で行くことができる外宮へ行くことにしました。 道は標識があるので分かりやすく、案内に従って歩くと、森が見えてきました。 入ると左手にトイレの案内があります。 のぞいてみると非水洗のようです。 伊勢神宮へ行くときは、トイレに気をつける必要があります。 7月の伊勢市は死ぬ程暑く、歩いているとかなり消耗します。 伊勢神宮内に入ると、森のために気温が数度低いのでしょうか、過ごしやすい感じがします。 背の高い木が多く、神々しい感じがします。 中にはこんなに立派な木がたくさんあります。 道の途中に神社のような場所が数箇所あります。 立ち止まっては中を眺めて、参道を歩きます。 外宮は内宮より人が少ないそうです。内宮の近くには「おかげ横丁」というお土産・飲食店街があるからかなと思いました。 そのため、ゆっくり見て回ることができます。 中には勾玉池というきれいな池があり、座るところがたくさんあったので、池を眺めながら一休みしました。 一休みしたら、内宮へ行くことにします。
2006年10月08日
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1










