[読書(フィクション)] カテゴリの記事
全54件 (54件中 1-50件目)
-

『ガールズ・ブルー』17歳の君へ
『カールズ・ブルー』あさのあつこ 文春文庫文庫解説の金原端人が「80年代、ヤングアダルト小説は振るわなかった。なぜならそれに代わるものとしてマンガがあったからだ。」という意味のことを言って大島弓子、岡崎京子、吉田秋生、山岸涼子、岡野玲子、吉野朔実、川原泉、水野英子、内田善美の名をあげている。どうしてこれらの名の中に萩尾望都、清原なつみ、三原順の名が無いのか、疑問ではあるが、確かに昔の少女漫画には輝きがあった。(どのようにあったのかはここでは立ち入らない。)一方、ヤングアダルト小説なるものを私は読まなかった。ワンパターンの恋愛小説だと思っていたからである。金原端人によると、90年代からその様相が逆転したらしい。江口香織、三浦しをん、角田光代、梨木香歩、藤野千夜、野中柊、梨屋アリエ、森絵都、佐藤多佳子らの名があげられ、(何人かは直木賞作家になっている)「もうマンガではすくい取れなくなってしまった若者たちを驚くほどたくみに細やかにすくいあげているのだ」と評価する。その中でひときわ輝いてるのが、あさのあつこだというのだ。確かに、これらの作家のほとんどを私は読んでいないが、あさのあつこの中には吉田秋生や三浦順的世界が確かにあるのを私も感じる。この本の感想をメモしていた土曜日の朝、私はマクドナルドにいた。4人くらいの17歳ぐらいの男の子がどやどやと入ってきて、店全体に響き渡るような声でおしゃべりを始めた。いや、4人がではない。よく聞くと、大きな声は一人のみ。一時間ほど聞いていると、この男のがどんな子なのか分かるくらいあけすけに思ったことをそのまましゃべっているという感じである。そういう性格なのだろう。もてるらしい。女の子たちはこの男の子をどうしようもない、と思いながら、でも良いところが忘れられずに付き合っているのかもしれない。なんか、そんなことまで分かるくらい彼はいろいろなことを喋り出した。彼の言うには、たくさんの女の子と付き合ってきて桃子のことが一番好きだったこと。今の彼女とは上手くいっていなくて別れたいこと。理科のテストで一番を取ったこと。3ヶ月の子どもを堕ろしたこと。3回浮気して許してもらったけど、彼女の一回の浮気が許せないこと。そういう彼に対して、一人の男の子は浮気なんて考えられない、と自分の彼女の話をする。一人の男の子はぼそぼそと一言二言話す。声の大きい男の子は「まじめな話‥」と言い出すと、隣の男の子はすぐに「お前が言うとまじめだと思えない」と返す。でもその男の子も本気で怒っているわけではない。「だって遊びたい年頃なんだもん。今すぐカラオケに行って何時間でも歌いたいんだよ。」といって彼らは店を飛び出していった。そのあと、店を出ようとした中学生の女の子が、テーブルの上に片付けられていない紙コップを見て鼻で笑って出て行った。この小説は「落ちこぼれ高校」に通う女の子、男の子が出てきて、小説的には「リアルワールド」みたいな事件は一切起こらない。大半は彼らのおしゃべりで埋まっている。けれども、そこからは17歳の世界が、いかにりりしく、強く、反対に弱いかを何とか掬い上げている。子どもを堕ろすような「悪い子」は出てこない。けれども、すこしずつ危うい。あるいは頼もしい。微妙な世界をあさのあつこはよくもこうもリアルに書けるものだと感心する。先のマクドナルドの男のたち、いつか君たちとじっくりお話ししたいものです。
2006年12月27日
コメント(0)
-
男の贈り物「セントメリーのリボン」
今年のベストワンです。テーマは「男の贈り物」。ハードボイルド短編集です。もちろん、男にも読んでもらいたいけど、女性にはもっと読んでもらいたい。私からのクリスマスプレゼントだと思ってもらって「まあ、今頃紹介されても遅いじゃない」と拗ねていただいたら、嬉しい。「セント・メリーのリボン」稲見一良 光文社文庫「死を怖れ、怯えてただとり乱すことと、死ぬ覚悟を決めた上で息のある限り生きようと足掻くことは別だ。」「麦畑のミッション」という短編の中で、B17爆撃機をイギリス田舎の水路に不時着させようとする直前、ジェイムス大尉はいつか見た罠にかかった雄ギツネのことを思い出す。「信じられないことが時には起こるもんだ。絶対にありえないと言えることなど、世の中には何もない。」大尉は息子にそんな風に話を聞かせてもいた。そして、この水路の近くにいる息子にいつかこのB17Fジーン・ハロー号を見せてあげるとも約束していた。稲見一良のことはまったく知らなかった。今回「この文庫が凄い」で06年度第二位になったことで読んでみた。結果、ずーと手元においておきたい一冊になった。値段は税込み500円。本の厚さからいって100円ほどサービスしているような気がする。稲見一良の文章を広めようとして、遺族・出版社ともに儲け部分を削ったのだろうか。そう、稲見一良はすでに故人だ。活躍期間は89年から94年の5年間のみ。5冊の本が残された。処女長編「ダブルオー・バック」を刊行した時点で、医師から余命半年と宣告されていたと言う。ガンはいつの間にか特別な病気ではなくなった。ガンを克服する人は多い。ガンで亡くなる人はさらに多い。ガンを告知されて、余命を延ばしながら素晴らしい仕事を成し遂げた人も枚挙にいとまない。例えば、余命は延ばさなかったが、「一年有半」の中江兆民、近くは約一年と少しで五冊の著書と旺盛な講演活動をした考古学者佐原真、今現在闘っている辺見庸。みんなに共通しているのは、死を見つめていない、ということだ。死は見つめなくとも目の前にある。だとしたら、見つめるのはそこからしか見えない生の世界だ。とくに稲見一良はその人柄か、本当にやさしく見つめている。中篇「セントメリーのリボン」で少女は犬専門のこわもての探偵、竜門卓に言う。「無愛想に見えて、気配りのある優しいお人やから。」「わたしがか?」「とぼけてもだめ。自分でもわかっているはずや‥‥‥」
2006年12月25日
コメント(4)
-

「リアルワールド」リアルを自覚するとは
私の長くない人生の中で、友達とつるんでいたという状況の中で、時と場所と人がすべて違っていたのに、同じ言葉を、おそらく三度ほど聞いたことがある。その言葉とは次のような、仲間に同意を促す台詞である。「それにしてもなあ、俺たちほど個性的な人間が、こんなにひとつ処に集まるなんてめずらしいよなあ。」バカか、お前は。と、私はそのたびごとに心の中で思った。ちょっと変わった趣味があるぐらいで、秘密の企てをしているぐらいで、中学生のときは四人の性格が単に違っているに過ぎなかったぐらいで、「めずらしい」もくそも無いもんだ、と。その時やはり自分は自覚していなかったのだと思う。自分では否定していたが、自分だけはこのような「ひと山いくら」のサルの群れの中には入らない、と自惚れていたのだ。小説は四人の少女と、一人の少年の独白形式で話が進む。少年は母親を殺して逃走した。少女たちは興味半分に少年の逃走を助けてしまう。ケータイで結ばれる彼女たち。自分だけは、「特別な自分」を見事に「友達」の少女たちに隠しとおせると思っている彼女たち。その一方で、「本当の自分」を分かってくれる「誰か」を探している。桐野作品だから当然のように物語は悲劇に向って進んでいく。いまどきの若者の覗き見はそれなりにスリルがあって楽しい。でも「柔らかな頬」(上)(下)「OUT」や「玉蘭」のように、私の心は引き裂かれない。若者たちの悩みはすでに私からはあまりにも遠いところにある。けれども、自分だけは人より特別だ、自分のことだけを誰か知っておいて欲しい、という欲望だけは今も健在だ。この高校生たちはバカだ、と笑いきれないのもそこら辺りにある。高校生を持つ親なら、この五人の独白小説を読んで背筋が寒くなるだろうと思う。
2006年12月21日
コメント(2)
-

次回の旅ではこの小説の舞台めぐりをしようと思う
2006年9月10日午後4時ごろ、私は韓国の水原駅からソウルに向かう電車の切符を買った。1400W。日本円にすると180円くらい。ゼロをひとつ間違えてはいないだろうか。私は唖然とした。釜山から長い旅をして10日目、私はいつの間にかソウルにそんなにまで近づいていたというのだろうか。電車は一号線を北上していく。客車も対面式の椅子である。木曜日の夕方、学生や会社員が増えていき、五時を過ぎて九老という大きな駅まで来ると客車はいっぱいになる。隅の椅子に座っていた私は、前の主婦があまりにも私のことを睨むので、おかしいなあと思っていたら老人専用の椅子であった。逃げるように席を離れると、私より少し歳のいった初老の方が優雅にあとを腰掛けた。夕染めの街を電車は走り、工場労働者と学生がどっと入ってくる。恋人は電車に入っても二人だけの世界を濃密に作る。彼らは隣りにはむすっとした冴えない中年がいるが無視する。もはや私は旅人ではない。一人の冴えない異邦人に過ぎない。私は新吉という駅で2号線に乗り換える。もうここからは地下鉄だ。すでに電車は大都会のソウルの中心地に入ろうとしていた。新吉駅のひとつ手前に永登浦駅というのがあった。今から思えば、あの電車から見た景色は、申京淑が16歳の頃鬱屈した思いを抱きながら毎日見ていた景色の一部だったのだろう。「離れ部屋」申京淑著 訳:安宇植 集英社 長い前振りで申し訳ない。21世紀のソウルの郊外の下町が、小説を読みながらしだいと私の中で26年前のソウルと重なってきたので、少し旅の思い出も書いてみた。この小説は田舎からやってきた16歳の少女が、九老工業団地で働きながら、永登浦夜間女子高校に通った四年間を自伝的に描いたものである。時代は1978年から81年。朴正煕大統領の暗殺、80年光州事件があり、徹底的な労組敵視会社運営、それに対する激しい闘争があった。しかし小説の視点はつねに『16歳の私』『17歳の‥‥‥』というものである。文章は散文、あるいは詩的。たった22日間の旅では見えないものがここにある。韓国人のイメージは常に前向き、声が大きいというものなのだが、この主人公は恥ずかしがり屋であまり声をださない。いろんな時代、いろんな生活、いろんな韓国人がある。当たり前のことではある。法律を無視して労組つぶしをする会社を見ていると、昔の日本を見ているようであり、現代の日本を見ているような気もする。肌のにおいがするような文章を読んで、私は次の旅では必ず永登浦駅と九老工団駅で途中下車しようと心に決めたのであった。
2006年10月31日
コメント(4)
-

「ふしぎな笛ふき猫」
「不思議な笛ふき猫」北村薫・文 山口マオ・絵 教育画劇民話「かげゆどんとねこ」より。千葉県千倉町の民話。しょうやのかげゆどんは、おこめができなかったとし、ねこのしろがしょうぐんさまのところでもんぜんのこぞうよろしく、かげゆどんをまねてふえをふいて、しょうぐんさまにきにいらました。それでねんぐをへらしてほしいというと、しょうぐんさまはいいよ、といいました。----てな感じのお話。すこしSFチックになっています。北村薫の本はすべて読むという私のポリシーのために一応読んでおきました。千葉県っていいなあ。小作人のことを思いやる庄屋もいるし、殿様は一応馬鹿じゃないし。でも、埼玉県人の北村薫がなぜに千葉県?
2006年08月21日
コメント(2)
-

『街の灯』ころがり落ちているのか
『街の灯』文春文庫 北村薫 最近『坂の上の雲』を読んだ方の映画『バルトの楽園』評を聞いた。日露戦争(1904)で発生した浮虜(捕虜)を当時の日本政府は非常に丁寧に遇したらしい。『バルトの楽園』は第一次世界大戦で捕虜になったドイツ兵の1914年以降の話。久留米の浮虜収容所では不潔な住居に住まわせ、暴力が日常になっていた。だからこそ、松平健扮する松江所長の坂東収容所が特別であって映画になったのだろう。件の方は、『日露戦争以降、日本は転げ落ちるように品格も何も無くなっていった、司馬遼太郎は書いている。私もその通りだと思う。」という。そしてこの作品の時代は1932年(昭和7年)、東京の上流家庭の女学生、花村英子となぞの運転士、別宮みつ子ことベッキーさんが、日常の謎、小さな事件を解いていく物語である。北村薫なので、日常生活を細やかに描いているが、時代と舞台が違う。昭和7年の上流家庭が見た東京の描写が見もの。この景色は、ものが溢れ、文化華やかしいまの庶民の生活と重なるところがある。1904年から30年間で、日本は転げ落ちるように『決定的なところ』までいったということは、いまなら高校生くらいなら教科書片手に説明くらいは出来るだろう。では、バブル崩壊から約15年間で、日本は転げ落ちるようにのっぴきならぬところまでいったのではないか、というような想いが私の頭から離れなかった。昭和7年の上流生活を垣間見る。微かに聞こえる軍靴の響き。日常描写を愛し、本格推理を愛する北村薫ファンからすれば、異端の読み方ではある。申し訳ない。
2006年08月19日
コメント(2)
-

『バッテリー5』映画化に期待
『バッテリー5』角川文庫 あさのあつこ毎回楽しみにしている今回の表紙絵は、早春の新田東の野原に座り込んでいる青波でした。退院直後だからなのか、少し痩せて見える。それとも少し背が伸びたからかもしれない。豪とケンカをして、仲直りをしたあとのりんごを持っているのかもしれない。このシリーズは、少年野球物としてもすこぶる面白いのだけども、それよりも「このひとって、どういう人なんだろう」という一見すぐ結論がつきそうなことを延々この五巻に渡って(たぶんこのあともずっと)追い求めている不器用な小説なのだ。私は人にしても作品にしても『不器用な』ものは好きだ。原田巧は自信過剰の我がまま天才タイプ。永倉豪は気配り優しさいっぱいの努力家。青波は素直で直観力優れた可愛い弟。端垣俊二は天才スラッガー門脇に嫉妬しつつもプライドは高い戦術家タイプ。門脇秀吾は単純明快努力家天才タイプ。……というような人間観察を、『そうとは言い切れないかもしれない……』とつぎつぎと壊していく。相手が分からない、自分のことさえ分からない、けれどもみんな野球が好きだ。だからぶつからざるをえない。『人におもねる必要はない。馴れ合う必要はない。卑屈に従うことも、自分の想いを押さえ込んでしまう必要もない。しかし、人を拒んでは野球はやれない。人を愛しいと知って、初めて、本当の野球が出来るのだ。』そうだよ、洋三おじいさん。あなたの心配は的を得ていると私も思う。けれどもそんなことはきっと言葉では伝わらない。2007年春、映画化。新田東は岡山県県北で撮影されている。岡山にも、フィルムコミッションというものが出来て、ロケ地誘致に成功したのだなあ、と感心していまHPを見たら、全然情報が載っていない。岡山県ロケが実現していないわけではない。検索したら、今現在やはり新見市で撮影中だという。『釣りバカ日誌』みたいに『バッテリー』が観光映画になってもらったら困るけど、撮影情報はしっかりと宣伝してもらいたい。岡山県は本来、日本映画の名作によく使われた場所でもあるのだ。私的にはもっともベストなのは、小津安二郎『東京物語』で笠智衆と原節子が穏やかな海を眺めるシーン。あれは物語的には尾道なのだが、海の景色の撮影は笠岡市の神島の南の先端でおこなわれている。今でもちゃんとベンチが置かれている。隠れたデートコースだといっていい。そうやって名作できちんと撮影されることで、観光以上の効果を生むはずなのだ。県の物産課よ、もっとしっかりして欲しいなあ。話がずれた。ということで、この作品の映画化、期待している。
2006年08月17日
コメント(5)
-

「野火」あるいは叔父の墓
無言館の戦没画学生には、フィリピン・ルソン島で戦死している学生が少なからずいる。たとえば山之井龍郎「昭和16年に出征し、シンガポール、サイゴンなどを転戦したのち、一時帰国するが、すぐに再び出征、20年5月フィリピンルソン島で24歳で戦死」。日本の自然や可憐な少女を描き、人一倍「美しさ」を感じ取ることの出来た精神が、ルソン島の中でどんな地獄を見たのか、どのように精神が変容していったのか、わたしは大岡昇平の「野火」を読みながら、さまざまな若い命のことを考えていた。お盆なので墓参りにいった。山の上の墓場に行くと、墓地の一等地にずらりと墓石のてっぺんが尖がっている墓が並んでいる。全て「名誉の戦死」をした人たちの墓である。当時の政府から多額の慰霊金が出るのでこのような墓になっているのだと知ったのはつい最近のことだ。そこに私の母の兄の墓もある。母はそのとき、13歳だった。もう一人の兄も戦地にいる。家事の一切と畑仕事をするのは、母の仕事だ。幼い妹を叱り、病弱の父と母を助け、病気がちの身体に鞭をうって、朝から晩まで働いていた。そのとき兄の戦死の報が届けられる。「昭和20年8月23日ビルマにおいて没する」墓にはそう記してある。「本当に賢いお兄さんだった。優しくて……」いつだったか、そのような母のつぶやきを聞いた気がする。母の兄がどのような死に方をしたのか、とうとう母からは聞かず仕舞いだった。戦後、父親はショックのせいか、すぐ死に、もう一人の兄がシベリアから帰ってくるのは、ずいぶんと後のことになった。その母も17年前56歳で死に、シベリア帰還の叔父も今年の6月に亡くなった。戦争とはなんだったのか、それを考えることの出来る記録文学、評論、映画、ドキュメンタリーは幸いなことに多数ある。けれども、数の問題ではない。何かが足りない。それは「自分と関係のあることなのだ」という実感をもてるかどうかということなのだろう。母の兄がどのような地獄を送ったのか。賢くて優しかった兄が、地獄の中でどのように変貌し、生きて死んでいったのか、その想像のよすががこの作品の中にはある。食料はとうに尽きていたが、私が飢えていたかどうかはわからなかった。いつも先に死がいた。肉体の中で、後頭部だけが、上ずったように目醒めていた。死ぬまでの時間を、思うままにすごすことが出来るという、無意味な自由だけが私の所有物であった。携行した一個の手榴弾により、死もまた私の自由な選択の範囲に入っていたが、私はただそのときを延期していた。この作品の主人公は高学歴の人間だ。ベルグソンの言ったことがすらすらと頭の中から出てきたりする。また彼はクリスチャンか、あるいはその信仰を持っている人間でもある。聖書の詩句が彼の頭の中にある。しかし、信仰はどうやら彼の救いにはならなかったようだ。しかし死の前にどうかすると病人を訪れることのある、あの意識の鮮明な瞬間、彼は警官のような澄んだ目で、私を見凝めていた。「なんだ、お前まだいたのかい。可哀そうに。俺が死んだら、ここを食べてもいいよ」彼はのろのろと痩せた左手を挙げ、右手でその上膊部を叩いた。この薄い文庫本を読み終えるのに、二年かかった。一文節たりとも、おろそかにできない文章が続く。「戦争とは何か」を突きつけてくるだけではなく、「人間とは何か」を突きつけてくる。当たり前だろう。戦争とはそういうものだから。
2006年08月15日
コメント(2)
-

ジャーナリストの初心「クライマーズ・ハイ」
明日の夕方、21年目のあの事故の日がやってくる。あの時は、私は気の合う者たちだけで、一週間のドライブ旅行をして白浜温泉で休んでいた。ふと見上げると、テレビに「日航機、埼玉・長野県境でレーダーから消える」というテロップが流れた、のを覚えている。今日はこの一冊をオススメする。『クライマーズ・ハイ』文春文庫 横山秀夫1985年8月12日、御巣鷹山に日航機墜落事故発生。群馬県の地元紙の遊軍記者、そして急遽全権デスクになった悠木和夫はひそかに『長野県に落ちてくれ……』と願っていた。『世界最大の航空機事故』という見出しが躍るに違いないこの事件のために、初めてのデスク体験に『クライマーズ・ハイ』に陥ることを無意識のうちに恐れていたからかもしれない。クライマーズ・ハイとは登山者の興奮状態が極限まで達し、恐怖感が麻痺し、ドンドン登ってしまうこと。事実悠木は上司と対立し、特ダネの記事を逃し、ひとり登っていく。著者は。この事件当時地元群馬の上毛新聞の記者であった。この作品は著者最初の長編新聞記者小説である。新聞記者をリアルに描いたものにほかには高村薫『レディー・ジョーカー』がある。今まではこれが新聞記者小説ではピカイチだった。けれどもこれは新聞記者のみが主人公ではない。今度からは新聞記者小説といえば『クライマーズ・ハイ』が筆頭に上がるだろう。記事の基本は『足で書く』だ。私も大学新聞を作っていたときに、徹底的に叩き込まれた。だから本物の事故現場を見た記者の滝沢が「現場を見たものだけが書ける記事があるのだ」と叫び、デスクの悠木と対立するのは名場面の一つである。あと三つ、この作品には『ヤマ』がある。(事件もヤマといい、作品の昂揚部分もヤマという。墜落現場はもちろん山だ。日本語とは不思議なものだ。)紙面会議で悠木は、局長社長と大喧嘩をしながら、どの新聞よりも愚直に詳報に徹すること決心する。遺族が社屋にまで新聞を買いに来たことで、地元紙の存在理由を知ったためである。大事件が起きた後、一般紙は次第と日常記事にシフトしていくのであるが、悠木の新聞のみはつねに日航機事故をどの新聞よりも詳しく載せ続ける。阪神大震災のとき、神戸新聞や地元のラジオはまさにこれをした。御巣鷹山より10年後のことである。これが一つのヤマ。裏がはっきり取れていない大スクープを果たして載せるべきか悠木は迷う。「(記事は)断定していない。大丈夫だ。うてる。だが……」真実を一番知りたがっているのは、世の中ではなく、遺族なのだ、と悠木は思うのだ。こが一つのヤマ。そして最後のヤマ。これで悠木は一つの決心をする。ずーとむかし、大学新聞を作っていたとき、新聞の見方だけではなく、世の中の見方も学んだ気がしている。「足で書く」とは理論をこねくり回す前に現場に足を向けることだ。現場にある無数の事実の中から、一番主張したい事実を拾い上げ、その事実を磨き上げることだ。しかし、新聞作りは記事のみが大切なのではない。どういう割付をするか。何を選び、何を外すか。も、重要な新聞つくりである。だからデスク悠木の役割は決定的だ。そして、どういう視点で新聞を作っていくか、これがもっとも大切でもっとも悩むところなのである。大新聞である朝日の視点の定まらない姿勢については、何度も、何度も、書いた。この小説に関していえば、ジャーナリズムに関心のあるもの、ジャーナリストを目指すもの、ジャーナリストの初心を忘れている全ての人にぜひ読んでもらいたい。
2006年08月11日
コメント(8)
-

「東京八景」と「純情きらり」
ふと思い至って新潮文庫版「走れメロス」を買う。420円。いまどき、これほど充実した内容で、この値段は珍しい。私はまだ一度も「太宰かぶれ」をしたことがない。中学生のとき一応は読んだけれども、すっと横を通り過ぎただけだった。クラスの隣にのちにボクシングチャンピオンになる奴がいたのに、悪ガキがいたとしか記憶していないことと少し似ている。(私の知り合いに辰吉の同級生がいるが、そういって悔しがっていた)この年になって昭和13年から18年にかけての短編を読み返す。なんか一瞬「かぶれ」てしまうような気になる。太宰の孤独は私なら理解できる、というような気さえしてくる。おやおや……。実はこの一ヶ月テレビを見ていない、8年間電源をつけっぱなしにしていたテレビのブラウン管が、ついに真っ黒になったためである。いまどきテレビなぞなくても、新聞とインターネットさえあれば、世の中の動きから取り残されることはない。一つか二つ残念なことといえば、NHKスペシャルの幾つかの番組と「純情きらり」を見ることができなかったことだ。もっともNHK受信料をいまだかってはらったことのない私が自慢げに言うことぢゃあない。すみません。いつものことだけど、回りくどい書き方をしています。実はこの「走れメロス」の短編の中に「純情きらり」の桜子を見つけたということを報告したかっただけなのです。この短編集の中に「東京八景」というのがある。津軽の大地主の家に生まれ、東大に入学するも、授業には出ず、左翼運動にかかわり、数度の自殺を試み、実家に無心をし、借金を重ね、薬物中毒におちいり、妻と別れ、心機一転作家として立ち直り、結婚をした半生を振返った自叙伝小説である。その小説の最後にまるで付け加えたように、ひとつのエピソードがある。小説で要約なんて野暮ではあるが、要約して紹介したい。再婚した妻の妹には婚約者のT君がいる。「はきはきした。上品な青年」であるが、ついに戦地に出発することになった。妹から速達が来る。「明朝9時に、芝公園に来てください。兄上からTへ、私の気持ちをうまく伝えてやってください。私はばかですから、Tには何も言っていないのです。」それから二時間もたたないうちにまた速達が来る。「よく考えてみましたら、先刻のお願いは、蓮っ葉なことだと気がつきました。Tには何もおっしゃらなくてもいいのです。ただ、お見送りだけ、してください。」これには太宰も妻も噴き出した。ひとりでてんてこ舞いしている様が、良く分かるから。当日太宰は妹に聞く。「どうだ、落ちついているか?」「なんでもないさ」妹は陽気に笑って見せた。「どうしてこうなんでしょう」妻は顔をしかめた。「そんなに、げらげら笑って」太宰はT君に「珍しく、ちっとも笑わずに言」う。「あとのことは心配ないんだ。妹はこんなばかですが、でも女の一番大事な心がけは知っているはずなんだ。少しも心配ないんだ。私たちみなで引き受けます。」妹=桜子はドラマよりはずいぶんと大人しい。大人しいけど、この小説でも妹の芯の強さと可愛らしさは伝わってきた。「純情きらり」は津島佑子の「火の山ー山猿記」を原案とする作品で、西島秀俊演じる冬吾さんは太宰がモデルらしい。ほとんどそれだけの情報でこのような思い込みの記事を書いているというわけだ。果たして「純情きらり」でもこのような場面はあったのだろうか。テレビはあと一週間ほどしてやってくる。宮崎あおいのあの大きな瞳は今は何を見つめているのだろう。驚くのは、「東京八景」は昭和16年に発表されているということだ。太平洋戦争が始まる年である。転向する作家や、筆を絶った作家や、投獄された作家が続出する中で、戦争を賛美する言葉が一つも出ていないのは素晴らしい。だから戦後すぐに作品を発表することが出来た。太宰の小説の中に出てくるアイデンティティを捜し求める青年の姿はそのまま現代青年の課題でもある。左翼運動に挫折し、自殺を重ねる、この昭和のはじめごろの青年の姿が、現代と重なるような気がするのは私だけか。「走れメロス」を久しぶりに読んで、少し思うこともあったのだが、それはまた次の機会に。
2006年08月08日
コメント(5)
-

面白い題材ではあるが「海の伽耶琴」(下)
「海の伽耶琴」(下)講談社文庫 神坂次郎秀吉の朝鮮出兵時、当初秀吉軍の中にいて、その後朝鮮側についた一群の武将がいた。彼らは鉄砲の技術を持ち、そのためそれまでの戦況を大きく覆すことに成功する。その武将の名前は「沙也可」と伝えられている。この小説はその武将を、紀州雑賀衆の大将鈴木孫市の若大将「小源太」として描いた歴史小説である。と、上巻の段階で分かっていたのであるが、下巻を読んだ後ここに感想を書くのを忘れていた。「孤将」を書いた後に思い出したので、一言二言感想を記す。調べたら、単行本は徳間書店からの発行であったが、文庫版が出ていたようだ。文庫版のほうも絶版になっているようで、「沙也可」の話はあまり日本には知られていない。何故小源太は寝返ったのか、秀吉に妻が殺されたのがきっかけとなっているのだが、そうだとすると、鉄砲集団である雑賀衆の行動原理としては弱い。しかも、一番肝になるべき朝鮮出兵の場面がほとんど描かれていない。この小説を書くにあたっての資料がほとんど日本の歴史書によっているのだから仕方ない。題材自体は面白いので、ほかの小説家が取り上げることを切に期待したい。今までのパターンからすると、韓国側から傑作が出てくる可能性は充分にあるのであるが。(たとえば、力道山みたいに映画で描かれるとか。)
2006年08月08日
コメント(4)
-

李舜臣の小説の意外な切り口『孤将』
以前コメント欄で在日さんより『あの豊臣秀吉軍と戦った朝鮮の英雄 李舜臣将軍をテーマにした小説ですが、戦争の無意味さを良く感じさせてくれます。訳者は、拉致され帰国された蓮池薫さんです。是非読んでみてください。』といって推薦された『孤将』をやっと読むことができました。『孤将』新潮社 金薫(キム・フン) 蓮池薫訳著者のはしがきはこのように始まっている。「2000年秋、再び田舎に戻った。正義感に溢れる者たちの世界と別れを告げたのだ。この時代のいかなる価値をも肯定できなかった。私は思った。君たちは希望の力で生きているのか。君たちと共有すべき希望も信念も、私にはない。自らの誤謬を持ちかかえたまま、私は一人で生きていくだろう。」著者は幾つかの小説も書いているジャーナリストであったが、ある時のインタビュー記事で批判されて、野に下ったのだという。この書は著者20年来の取材をもとに描いた秀吉の「朝鮮出兵」時の英雄・李舜臣(イ・スンシン)の小説である。しかしちょっと文章に触れて分かるように、英雄小説とは程遠い。この虚無主義、耽美主義的な世界観は、ちょっと日本に見出すことは難しい。何故かということはあとで述べる。しかしこれが、50万部を越えるベストセラーになっているのだから、やはり注目しておくべきなのだろう。この小説が現代日本小説から著しく違うところは、虚無主義でも耽美主義でもなく、その肉食人種的描写による。例えば、王から贈られた牛肉をこのように描写する。「つぶしたばかりの牛の肉は、今なお筋肉がぷるぷるっと摩擦でも起こすかのように新鮮だった。切り口には切り分ける途中、包丁の歯が一度とまったような跡が残っていた。切り口の面には筋肉と毛細血管の複雑な模様が浮き出ている。赤い肉の筋がどことなくすべってつながっていた。包丁の刃が通りすぎていった生命体の内面にはまだこのような模様が残っていたのだ。私が敵の刃、もしくは王の刀にきられたときも、果たしてその断面はこうなるのだろうか。」日常から祝いごとがあると牛をつぶし、食べてきた民族の描写だけではない。すぐ身近に朝鮮戦争で近親、同じ民族殺しあってきて、つい十数年前までは民主化弾圧の中でで拷問死に脅えなければならなかった人々の記憶が、このような描写を可能にしているのである。英雄譚ではない。王によってと投獄され、王の敵(秀吉)によってその軍事技術の必要性から生かされ、敵によって死地に赴く。これは民主化闘争を闘った現代知識人の心情も代弁しているかもしない。確かに『戦うことの無意味さ』を自分の血肉によって表現している。ここの登場人物は、王にしても、百姓にしても、主人公にしても、みんなよく泣く。泣くことで忠誠を誓わせ、泣くことで忠誠を表現し、泣くことで愛情を表現するのである。日本に対する歴史理解には疑問符はつく。秀吉軍のことを一貫して『日本は』と表現したり、「阿部順一」という捕虜になった『下級武士』(足軽にそんな名前はありえない)を登場させたりする。瑕として残らないのは、その捕虜を殺すときにも、李舜臣はきりきりとした痛みを持っていたのである。
2006年08月07日
コメント(2)
-

横山秀夫の隠れた名作『平和の芽』
今日は広島に原爆が投下された日。ということで今日はこの一冊を紹介。『平和の芽』講談社 横山秀夫いまや出す作品全てが売れまくる横山秀夫であるが、彼が新聞記者を辞めて91年『ルパンの消息』でサントリーミステリー大賞をとった後、98年ごろの「陰の季節」まで長い潜伏期間があった事は一応知られている。『小年マガジン』などの原作も手がけていたそうだ。しかし95年に小年少女読み物で『語りつぐ原爆・沼田鈴子ものがたり平和の芽』という本を執筆していたことを知る人は少ないだろう。また、のちの警察小説を読む人には『平和読み物』と聞いてそのギャップに驚くだろう。おそらく自ら提案した企画ではなく、被爆50年を記念しての講談社からの依頼だったのに違いない。でも読んでみると、ここには実に真摯に当時の政治、世相を取材し、青春の真っ只中で被爆し片足を無くした沼田鈴子さんを聖人視することなく心のひだまでを描こうとする「小説家」横山秀夫の生まれようとする姿がある。『黒い雨』や『鍋の中』など原爆のときやその後の一時を切り取った文芸作品は有るが、昭和初期からの一人の少女の日常を描き、原爆にあい、どのようなその後の人生を送ったかを描き、さらに80年代の10フィート運動で原爆の語りベとして目覚め、さらにはその後の語りベとしての成長までを描くというそんな小説は他には無い。原爆小説として他には無いタイプの秀作である。近辺では「ガキ大将」だった鈴子。おてんばっぷりの描写は平和運動家が書く「平和よみもの」とは一味もふた味も違います。軍都広島の描写も私たちが今イメージするヒロシマとは180度違います。鈴子は兵隊さんを見れば「かっこいい~」とうっとりと見とれ、軍国少女になっていきますが、鈴子は図画の時間、アイロンの絵を描こうとして灰色や銀色ではなく真っ赤なアイロンを描いてしまう。「それは鈴子の生まれ持った能力でした。他の人がどう思おうと自分が感じたままを素直に信じる力です。やはり鈴子は見ぬいていたに違いありません。教えられた戦争と、本当の戦争でおこっている出来事との大きな隔たりを」そのように、一人の少女の気持ちの中まで入り込む。『よみもの』ではなく、私はやはりこれを『小説』と呼びたい。
2006年08月06日
コメント(4)
-

戦争は静かに始まる『となり町戦争』
図書館でこれを借りるのに一年待ちました。『となり町戦争』集英社 三崎亜紀第17回小説すばる新人賞受賞作。普通に暮らしていた会社員の僕の元に届いた町の広報。町民税の納期や下水道フェアの告知とともに、そこには、となり町との開戦のお知らせが書かれてあった一点どうしても不思議なところがあり、なかなかこの小説の世界に入っていけなかった。主人公はずーとこの異常な世界に住んでいるはずなのに、なぜか一人称でかたられる彼の言葉は現代の一般市民の感覚なのだ。「ぼくたちの世代というのは、戦争というものの実体験もないまま、自己の中に戦争に対する主義主張を確立する必然もないまま、教わるままに戦争=絶対悪として思考停止に陥りがちだ。」と主人公はつぶやく。この小説の設定は近未来ではない。戦争が一つの『公共事業』にまで発展したパラレルワールドなのである。少なくとも100年以上前には戦時立法が成立していて、隣国との戦争を記念して植えた木々が立派な森になってそこを訪れるのが学生の情操教育の一環として位置づけられているようなこの町で、主人公のような感覚はありえない。そんな教育をしていたら、戦争など出来るはずもない。情報戦、あるいはスパイ活動の為に主人公はかなりやばい仕事をすることになるのであるが、それが『人海戦術』なのである。戦争はもっとも技術の発展を要請する『事業』なのであるが、あんな人海戦術などで話を進められたら、リアリティなど吹っ飛んでしまう。言いたいことは良く分かる。現代一般市民は、いくら戦争の危機が近づいていても、その一歩手前まで来ても、決して気がつかないだろう。その雰囲気を出したいのだろう。市役所窓口に勤める『香西さん』は主人公とともに業務として『偵察活動』という名の夫婦生活を送る。彼女は『業務としての戦争の仕組み』をさすがに主人公以上に理解している。けれども諦めきっている。(弟が戦争に志願して戦死しても、政略結婚で隣町の町長の息子と結婚することになっても、それを受け入れている。)その雰囲気は出ている。けれども私には受け入れがたい。小説は映画とは文法は違う。ひとつの大きなウソをつくためにほかの部分を緊密にリアリティを持って描く必要はないのかもしれない。けれどもこんな人物像は受け入れ難い。既に現実の役所は戦争準備を進めている。国民はそのことを知っているのだろうか。去年の県段階の国民保護計画作成に従い、現在では、市町村レベルで作成が進められている。3/31に書いたことの一部を再掲してみる。現在市町村は、野村、三菱総合研究所や外資系のコンサルタントに委託して策定作業を進めているという。政令指定都市では、京都・広島以外はそのための予算を計上している。ちなみに表があったので、この『再出発日記』を読んでくださている人に関係するような政令指定都市の18年度予算『国民保護計画策定費』を列挙する。札幌市3000万円。さいたま市843万円。千葉市1210万円。大阪市920万円。きちんと読んでいけば『お役所仕事としての戦争』が見えてくるかもしれない。コンサルタントに依頼して計画を進めているところとかは、この作品の中でも描かれている。さすが作者は長いこと公務員をやっていただけのことはある。作者は作者なりに『戦争の現実』を想像して、それが主人公たちにどう映るのかを書いているみたいだ。だから小説に書いてある部分以外のエピソードは相当あると思う。けれども、私の読む限りでは、それでも作者の想像する『戦争の現実』はまだまだ甘い、と思う。教育、情報戦の甘さについては既に述べたが、それ以外にももっともっとありそうだ。作者は1970年生まれの36歳。『ガンダム』世代である。アニメの中に『戦争のリアリティ』があった世代だ。そのことも関係していないとはいえないだろう。さて、この作品は映画化されることになり現在撮影が進められている。映画の場合は要求するぞ。「一つの大きなウソをつくために、それ以外はリアリティを持ってつくること。」「となり町戦争」江口&知世が初共演来春、渡辺謙作監督作品として公開される。配給が角川なので、ものすごく不安。この前新作の『戦国自衛隊』をDVDで見たが、なんと言うか、金儲けのことしか考えていないのかな、と思った。
2006年08月03日
コメント(1)
-

仕事とはなんだろう『深追い』
『深追い』実業之日本社 横山秀夫郊外にあるその警察署は五階建ての庁舎の裏に家族宿舎と独身寮まで建てている住職一体の「村」である。三つ鐘警察署を舞台とする連作短編集。交通課。鑑識課。盗犯一係。警務課。警察署次長。会計課。警察小説であるが、その登場人物は多様を極めている。ミステリの体裁を持ちながらそのなかの組織の中のさまざまな生き方を浮かび上がらせる。横山秀夫の短編にはほとんどはずれが無い。藤沢周平が出てきたときとよく似ている。彼も中年を過ぎて小説を書きだし、自らの鬱屈を吐き出していった。警察周りの新聞記者を辞めて、長い潜伏期間を経て、書き始められた横山秀夫の中にもきっと書かずにいられないことが有るのだろう。例えば『訳あり』。警務課の滝沢は、気の進まない仕事を頼まれる。本部の二課課長によからぬ女ができたらしい。「お守り役」二課次長が所轄で同期の滝沢に調べてほしいという。一度左遷させられた滝沢にはかっこうの本部帰省のための材料だった。キャリア課長の失態を未然に防ぐための探偵のようなその仕事は、滝沢の思う警察官の仕事とは程遠いだろう。「席をたつなら今だろうと思った。」しかし引きうける。単行本の奥付けは2002年12月15日初版。その一ヵ月後2003年1月15日には4刷を数えている。どんな人たちがこの本を買い求めたのだろう。年末も押し迫って残業を抱える仕事人間が駅地下の本屋でふと買い求める。読んでみて、妻にも言えない屈辱的な自分の仕事の一断面を思い出す。(滝沢は一体どうなってしまうのだろう‥)彼にとっては人ごとではない。結局小説は『筋を通した』結果に終わる。仕事人間はホッとする。(そうだよ、そうでなくちゃ。でも俺には妻も子供もいるし、第一この男のように機転も利かないし、かっこいい言葉も出ないし‥)(俺がもし失業したら、もう年間200万円くらいしか稼げるような仕事しか残っていないだろう。家族のためには、家族のためだけに、屈辱的な仕事もしていこう。)ほとんどのサラリーマンはそう思い、せめて横山秀夫の小説を読むことで憂さを晴らしていたのかもしれない。でも思うのだ。一年のうち一回ぐらいは、たいしたことで無ければやってみても良いかな、と。他には『又聞き』の最後の一行にやられた。
2006年08月01日
コメント(0)
-

マスコミの行方「ルポ改憲潮流」
昨日の続きです。今年3~5月にかけて、共謀罪が国会にかけられそうになり、実際にかけられ、審議され、一般的な観測ではそのまま強行採決されそうになっていたとき、東京新聞等一部を除くほとんどの新聞は「沈黙」を守っていた。特に、朝日新聞は教育基本法や国民投票法は国会に上程される何ヶ月も前から系統的に報道しており、共謀罪報道との差異にわたしは驚きと憤りと、諦めを感じていた。何故なのか、ということがいまだに疑問なのであるが、私はこの本を読んで、「そうか私はまだまだ朝日はそれでも反権力を守っている、と思っていたのだが、間違いだった」ということに思い至ったのではある。斉藤貴男は「NHK番組改変事件」を巡る朝日新聞の対応は「21世紀の「白虹事件」ではないのか」といっている。白虹事件によって、ほかの新聞も雪崩をうって翼賛新聞に変わっていくのではある。ちなみに、白虹事件により、当時の朝日社長、長谷川如是閑、大山郁夫等の論説委員の辞任とともに、「編集綱領」を発表し、戦争に協力することを誓うのであるが、このとき史上初めて「不偏不党」の文言が新聞の編集方針に登場する。ということもあって、私は「不偏不党」を言うジャーナリストを信じない。2005年5月9日、朝日の秋山社長が謝罪をした。しかし、これはあくまでも内部資料が他社のジャーナリストにすっぱ抜かれたことに対してではあった。しかし、斉藤は「朝日は土下座したとのみ、世間は受け止めた。いや、朝日新聞社として、あえてそう受け止められるように仕向けたのではないか、という疑念がわたしにはどうしても払拭できない」という。さて、秋山社長は謝罪の後、さらに2006年3月、35歳になる長男が大麻の所持で逮捕された事件で、よりいっそうの窮地に陥った。(これが朝日が共謀罪報道に不熱心だった真相ではないかと私は考えている。時期も一致する。もしそうだったとしたら、社長からデスクまでの一組織としての朝日新聞社にジャーナリズム精神はもはやない。)一方、安倍、中川両氏がNHK番組に介入した事実をスクープした社会部の記者は四月の人事で「アスパラクラブ」に異動している。彼に近しい記者たちも編集局を外れ、或いは全国に散っていったそうだ。NHKもまた、事件を契機に自らを立て直す好機にはせず、自民党との心中を選んでいるのは周知のこと。この新書には、読売新聞の朝倉敏夫論説委員長と朝日新聞の若宮啓文論説主幹のインタビューが載っている。朝倉氏の話は予想の範囲内である。「(自民党憲法草案について、読売との考え方とは)ほとんど変わらない。」そうでしょうね。ただ、憲法は国家権力を制限するものだという考え方については「憲法学者というのは、伝統的に現行憲法のファンであってね。逆に言えば、ある時期まで、そうでなければあの世界で生きていけなかった。ギルド社会の話ですよ。そこもわが社が変えたと自負するものです。」……ここまでいうか!と思いました。若宮主幹のインタビューについては、少しは期待していた分、よけいに落胆したかもしれない。「憲法ですが、非軍事を主体にし、平和主義を貫こうとする我々の基本的な考え方については変わりはありません。(略)(この10年の間に)9条に自衛隊を明確に位置づける考え方も一つの選択肢に入れたほうが良いのでは、と。社説にはそこまでピシッと書いていませんが、そういう趣旨に読めるよう、少し膨らみを持たせて軌道修正している。」「健全な保守層とも一緒に戦列を組んでいかないと、狭い護憲論だけで闘っていくと、危険な右傾化路線を利するだけではないだろうか。何も朝日新聞が売れるとか、売れないとかいうことではなくてね。」……なくてね、とは言うけれども、それ以外の何が軌道修正の原因だったのかは書いていない。というか、読者の支持のことしか書いていない。同じような理由で、「自衛隊が働くためのルールをつくっておく必要」を求めて、有事法制には賛成している。では自民党の憲法草案については、「いや、少なくともダメだとは考えています。(略)「軍」と謳ってしまえば、戦前の軍との違いに無頓着になるでしょう。ましてÅ級戦犯の何が悪いのか、といった風潮がある中で、それは良くない。またアメリカとの同盟関係は一気に深まりますね。集団的自衛権に歯止めがなくなると、アメリカが自衛の名の下に行うかもしれない先制攻撃まで付き合わされる可能性さえもある。」……前半部分と後半部分の論理の整合性が、このインタビューを読む限りではぜんぜんわからない。論説主幹でさえ、こうなのだから、朝日はその時々の勢いで社説はどうにでも変わるだろう。
2006年07月19日
コメント(6)
-

昔の「未来」から現代を見る「トワイライト」
文庫版のためのあとがきで、重松清はこんなことを書いている。「小学一年生のときに、アポロが月に行った。翌年には大阪で万博が開かれた。ぼくたちのー少なくともぼくの「未来」に対する希望は、その二つにの出来事に象徴される。21世紀には月面ステーションが出来上がっていて、ロボットが街を歩いているはずだと信じている少年だったのだ、ぼくは。一方で、ノストラダムスの予言が当たれば、1999年7月に人類は滅亡し、オイルショックのころの言説を信じるなら石油はあと数十年で枯渇してしまい、そんな先を待つまでもなく、アメリカやソ連が核戦争を始めたらボタン一つで地球は滅んでしまう。それをどこまでリアルな危機として実感していたかはともかく「未来」には確かに影もあった。」少し年代はずれるが、私の「未来」もみごとに同じようなものだった。小学館の学習雑誌にはばら色の未来が特集されていた。働くのは週三日だけ。きれいな家。食事は全自動でできるし、買い物をしなくても専用箱から飛び出てくる。テレビ電話は標準装備だ。絶望的な「未来」もあった。当時私の家から見える水島の工業地帯の煙突の煙は、公害問題の象徴だった。やがてここには住めなくなると本気で心配した。核戦争が勃発して家族と一緒に死を待つ自分もよく想像した。未来である現代はどうなっているのか。リストラされている人々たち。精神を病んでいる人々たち。レトルトという全自動食品を食べ、アマゾンで本を買い、携帯電話を持つ現代。煤煙公害はなくなったが、石綿被害という戦後最大の公害が始まろうとしている。そして、真綿で締め付けられるように、戦争の時代がやってこようとしている。内容(「BOOK」データベースより)小学校の卒業記念に埋めたタイムカプセルを開封するために、26年ぶりに母校で再会した同級生たち。夢と希望に満ちていたあのころ、未来が未来として輝いていたあの時代―しかし、大人になった彼らにとって、夢はしょせん夢に終わり、厳しい現実が立ちはだかる。人生の黄昏に生きる彼らの幸せへの問いかけとは。( 以上引用終わり)このタイムカプセルを提案した白石先生はその後不倫相手に殺される。タイムカプセルには白石先生の手紙が入っており、自らの未来の悲劇を予測した後、40歳を目前にした同窓生たちに呼びかける。「みなさんの40歳はどうですか?あなたたちはいま、幸せですか?」リストラされた克也、仕事が上手くいかなくなりDVを繰り返す徹夫とその度に子供をほっといて家出を繰り返す真理子、もと「マドンナ」として一世を風靡したが今は売れなくなった独身塾講師の淳子、四人を中心に物語がつづられる。「あなたたちはいま、幸せですか?」なかなかズルイ問いかけである。死にゆく人間が、遺言のようにそんな問いかけをする。大人なのに大人として自信がない四人は、いやほとんどの大人はその問いの前に佇んでしまう。いま子供の雑誌で未来論は特集されているのだろうか。悲劇は先送りされているかのように思える。ばら色の未来機器は、実現してみると当然のことながら汚れは着くし、副作用もある。どうすればいいのだろう。自信のない大人としては「分からない」。
2006年07月17日
コメント(5)
-

重松清の小説の構図「小さき者へ」
重松清の家族小説短編集。とはいっても重松清は基本的に家族小説しか書かない。私は彼によって、いじめやリストラ、離婚や、「負け続けること」や、一般家庭におきるさまざまなことを学んだような気になっている。文庫が出たら無条件に買う作家のひとりである。今回の文庫、最後にドキリとする文章がある。やはりそうだよね、彼にも書けない家族小説というものはある。(一番後で述べます)冒頭の「海まで」同じように頑固な老人を抱えているものにとって、ちょっと身につまされる短編。夏休み。主人公は一人息子。いなかに帰る。父親も死に、一人で暮らしている母。母親はまるで子供に帰ったように、主人公の二人の息子(つまり母にとっては孫)のうち、次男をひいきにし、長男に「姑いびり」のように接する。むかしは優しい母だったのに、主人公が東京に行くのを一人親族からかばってくれたのに。周りの人が死んでいき、身体にガタが来ている。主人公は思いつき、四時間かけて10年ぶりに母親の実家に墓参りに行こうとする。しかし、母親は途中でへばってしまう。主人公は慰める。「今度はもっと大きな車を借りるから、墓参りはまたにしよう。」母は膝をさすりながら呟く。「クーラーの効いているところにおったなら、すく痛うなる。」「今度いうて、いつになるんなら。」母は泣き出す。「なあ、いつ連れてってくれるんな。いつ帰ってくれるんな」「痛い痛い痛い、ほんま痛い、痛い痛い痛い」張り詰めていたものが切れる。裸の感情と向き合う、つらさ。最後は少しだけ目頭が熱くなるエピソードがある。けれども解決は無い。表題作の「小さき者へ」登校拒否におちいり、家族に暴力を振るうようになった一人息子に対して、リストラ危機にいる父親が、夜遅く、渡すあてのない息子宛の手紙を書く。自分が14歳だったころを思い出しながら。「親は、どんなときもベスト盤を子供のために、良かれと思って選んでしまうものなんだな。そして子供の本当に聴きたい曲に限ってベスト盤には入っていないんだな。」終わり近くのその一言が、作者の意図を超えて、私の心に響く。どの短編も涙ぐんだ。重松清の小説にはたいてい「弱くてぐずぐずしている男の子」「惨めな姿をさらす父親」「女の子はいつも強くてがんばっている」という構図がある。例えば反対に同じ世代の宮部みゆきは「少年もの」というパターンがある。少年が主人公になると、たいてい勇気があって賢い男の子が出てくる。男と女の「差」なのかもしれない。この文庫の一番最後に「作文家」という肩書きで、中学三年生(今現在はたぶん高1)の華恵さんが「解説」を書いている。読書感想文ではない。れっきとした解説である。彼女はそういう重松清の小説の構造を当然のことながら見破っている。そうして「重松さんに願うこと」を書く。「女の子は最後に颯爽と歩いていく姿が多い。だからこそ、読んでいると元気が出るし、がんばるぞ、と思える。でも……もし、それが出来なかったら?トモのような女の子が中・高生になって、強がりもできなくなって、力尽きてがんばれなくなってしまったら?「小さき者へ」の主人公の息子ように、一歩も踏み出せなくなってしまったら?ぐしゃっと押しつぶされて、壊れて……出口が見えないような惨めな姿になった娘を、見てくれますか。それでも応援し続けますか。徹底的に壊れた女の子の姿を、いつか描いて欲しい。」重松清なら必ず応援し続けるだろう。理想的な父親としてではなく、でもボロボロになりながらもそういう物語は書くことが出来るだろう。と私は思う。けれども重松清に「徹底的に壊れた女の子の姿」を書く勇気があるだろうか。と、ついつい彼の気持ちになってしまう。ホント、女の子というのは怖いことを言うものだ。
2006年07月15日
コメント(6)
-

七夕の夜に
気がつけば、今日は七夕。ミサイルの話もいいが、こっちのお空のお話をしておかないと一日が終わったような気がしないので一言。「銀河鉄道の夜」の冒頭場面である。「ではみなさんは、そういうふうに川だと言われたり、乳の流れたあとだと言われたりしていた、このぼんやりと白いものがほんとうは何かご承知ですか」先生は、黒板につるした大きな黒い星座の図の、上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながら、みんなに問いをかけました。 カムパネルラが手をあげました。それから四、五人手をあげました。ジョバンニも手をあげようとして、急いでそのままやめました。たしかにあれがみんな星だと、いつか雑誌で読んだのでしたが、このごろはジョバンニはまるで毎日教室でもねむく、本を読むひまも読む本もないので、なんだかどんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。 ところが先生は早くもそれを見つけたのでした。「ジョバンニさん。あなたはわかっているのでしょう」 ジョバンニは勢いよく立ちあがりましたが、立ってみるともうはっきりとそれを答えることができないのでした。ザネリが前の席からふりかえって、ジョバンニを見てくすっとわらいました。ジョバンニはもうどぎまぎしてまっ赤になってしまいました。先生がまた言いました。「大きな望遠鏡で銀河をよっく調べると銀河はだいたい何でしょう」 やっぱり星だとジョバンニは思いましたが、こんどもすぐに答えることができませんでした。 先生はしばらく困ったようすでしたが、眼をカムパネルラの方へ向けて、「ではカムパネルラさん」と名指しました。 するとあんなに元気に手をあげたカムパネルラが、やはりもじもじ立ち上がったままやはり答えができませんでした。むかしは、普通に読んでいたこの冒頭場面、今は涙で文字が霞んでしまう。お父さんの仕送りはとっくの昔に途切れている。ジョバンニは思いつめた様にアルバイトしている。だから眠くて、うっかりしていて、本当は答えることができるのにできなかったのだ。これはつらい。よくある経験だけど、本人はつらい。生活も苦しいけど、「本当はお父さんは監獄に入っているのではないか……」こっちの心配のほうが実は大きかったりする。未来が見えないジョバンニが可哀そうでならない。そして、カムパネルラの優しさ。角川文庫版では、最終近くに「ブルカニロ博士編」が載っている。賢治は後の推敲でこの挿話を削ってしまう。説教臭いと感じたのだろうか。それとも削ることが賢治の「決意」の表れだったのだろうか。ジョバンニは、はっと思って涙をはらってそっちをふり向きました、さっきまでカムパネルラのすわっていた席に黒い大きな帽子をかぶった青白い顔のやせた大人が、やさしくわらって大きな一冊の本をもっていました。「おまえのともだちがどこかへ行ったのだろう。あのひとはね、ほんとうにこんや遠くへ行ったのだ。おまえはもうカムパネルラをさがしてもむだだ」「ああ、どうしてなんですか。ぼくはカムパネルラといっしょにまっすぐに行こうと言ったんです」「ああ、そうだ。みんながそう考える。けれどもいっしょに行けない。そしてみんながカムパネルラだ。おまえがあうどんなひとでも、みんな何べんもおまえといっしょに苹果をたべたり汽車に乗ったりしたのだ。だからやっぱりおまえはさっき考えたように、あらゆるひとのいちばんの幸福をさがし、みんなといっしょに早くそこに行くがいい、そこでばかりおまえはほんとうにカムパネルラといつまでもいっしょに行けるのだ」「ああぼくはきっとそうします。ぼくはどうしてそれをもとめたらいいでしょう」「ああわたくしもそれをもとめている。おまえはおまえの切符をしっかりもっておいで。そして一しんに勉強しなけぁいけない。おまえは化学をならったろう、水は酸素と水素からできているということを知っている。いまはたれだってそれを疑やしない。実験してみるとほんとうにそうなんだから。けれども昔はそれを水銀と塩でできていると言ったり、水銀と硫黄でできていると言ったりいろいろ議論したのだ。みんながめいめいじぶんの神さまがほんとうの神さまだというだろう、けれどもお互いほかの神さまを信ずる人たちのしたことでも涙がこぼれるだろう。それからぼくたちの心がいいとかわるいとか議論するだろう。そして勝負がつかないだろう。けれども、もしおまえがほんとうに勉強して実験でちゃんとほんとうの考えと、うその考えとを分けてしまえば、その実験の方法さえきまれば、もう信仰も化学と同じようになる。(略)「さあいいか。だからおまえの実験は、このきれぎれの考えのはじめから終わりすべてにわたるようでなければいけない。それがむずかしいことなのだ。けれども、もちろんそのときだけのでもいいのだ。ああごらん、あすこにプレシオスが見える。おまえはあのプレシオスの鎖を解かなければならない」 そのときまっくらな地平線の向こうから青じろいのろしが、まるでひるまのようにうちあげられ、汽車の中はすっかり明るくなりました。そしてのろしは高くそらにかかって光りつづけました。「ああマジェランの星雲だ。さあもうきっと僕は僕のために、僕のお母さんのために、カムパネルラのために、みんなのために、ほんとうのほんとうの幸福をさがすぞ」 ジョバンニは唇を噛んで、そのマジェランの星雲をのぞんで立ちました。そのいちばん幸福なそのひとのために!「さあ、切符をしっかり持っておいで。お前はもう夢の鉄道の中でなしにほんとうの世界の火やはげしい波の中を大股にまっすぐに歩いて行かなければいけない。天の川のなかでたった一つの、ほんとうのその切符を決しておまえはなくしてはいけない」 あのセロのような声がしたと思うとジョバンニは、あの天の川がもうまるで遠く遠くなって風が吹き自分はまっすぐに草の丘に立っているのを見、また遠くからあのブルカニロ博士の足おとのしずかに近づいて来るのをききました。「ありがとう。私はたいへんいい実験をした。私はこんなしずかな場所で遠くから私の考えを人に伝える実験をしたいとさっき考えていた。お前の言った語はみんな私の手帳にとってある。さあ帰っておやすみ。お前は夢の中で決心したとおりまっすぐに進んで行くがいい。そしてこれからなんでもいつでも私のとこへ相談においでなさい」「僕きっとまっすぐに進みます。きっとほんとうの幸福を求めます」ジョバンニは力強く言いました。今よく読めば、この「セロのような声」をした人の言い分は、なんだかあらかじめ結論をもっている説教臭い大人のようにみえる。ジョバンニの旅も結局ブルカニロ博士の「実験」だったのかよ、と言うような批判も聞こえてきそうだ。賢治が削った理由も分かるような気がする。けれども、それでも私はこの挿話が好きなのだ。小学校のとき、一番最初に読んだ本にこの挿話が載っていたから、だけではないような気がする。夢から醒める前、心配事を抱えていた場合、全て夢の中では分かったような気になることが無いだろうか。素晴らしいことを発見した、何もかもこれで解決した、そう思って眼をが醒めて、もう一回思い返そうとするのだけど、どうしても思い出せない。そんな経験は無いだろうか。プレシオスの鎖を解くために、マゼェラン星雲に立ち向かっている自分をかっこいいーと思った瞬間に目が醒めたりしないだろうか。私にはある。そして、最愛の妹としこが死んだ後、そんなふうにして花巻の旧屋で目覚めたあとにしばらくぼおっとしている賢治の姿が、私には見える。(「ぼくはとし子といっしょにまっすぐに行こうと言ったんです」「ああ、そうだ。みんながそう考える。けれどもいっしょに行けない。そしてみんながとし子だ。」)「きっと本当の幸福を求めます」と決心したその自分の声の響きだけを追い求めて、やがて家を出て「野原ノ林ノ影ノ小サナカヤブキ小屋ニ」住む様になる賢治の姿が見える。そんなきれい事を言って、親の金で家を建て清貧生活を送る、弱くて強い賢治が見える。そして、限りなく愛しい。銀河鉄道の夜は「星祭」の夜の出来事であった。織姫、彦星だけではなくて、ジョバンニとカムパネルラの最後の旅が、今夜の厚い雲の上で再現されているのかもしれない。
2006年07月07日
コメント(8)
-

リハビリ打ち切り反対署名あるいは「聖」
今年の春、桜の咲きかけのころ、「狐の嫁入り」という記事のところで、「そのあと漫画喫茶なみに漫画をそろえているカレー屋で、山本おさむ「聖」を読んで感銘を受けるのであるが、これはまた別の機会に。」と書いてそのまますっかり忘れていました。今日ドラエモンのポケットみたいな私の財布の中を整理していたら、そのときのメモが入っていました。またどこかに行ってしまわないうちに書いておきます。村山聖。「手をのばせば届くところにある」ところまで名人位に切迫しながら、小さい頃から患っていた腎ネフローゼその他の難病の為に29歳で急逝した将棋の棋士です。その生涯を漫画化した作品に山本おさむ著「聖」があります。今回はその漫画について、ではない。第六巻のあとがきで、聖のお母さん、村山トミ子さんが寄稿しています。その内容についてです。知人から聖書を貰った聖は、大阪の前田アパートで大切に読み込みます。ある日、体調を崩して寝込み、広島からトミ子さんが上阪してきたとき、聖は言うのです。「お母さん、あのね、淀川で人が溺れ死んだのに誰も助けに行かなかった。ぼくならすぐ助けて飛び込んだのに。」と涙ながらに言ったそうです。「でもあなたでは泳げないでしょう。命を捨てることになってそれは駄目よ。」とお母さんは答える。「キリスト教はそんな教えは説いていないはずだ。協会ではっきり聞いてきてくれ。」お母さんは大阪・福島区のキリスト教会を訪ね、いろいろ牧師さんに聞き、それを聖に伝える。「聖は黙って聞いていましたが、納得していないようでした。」(どういう内容かは書いていないのでわからないが、文章の流れからはやはり飛び込んでは駄目だということだったのだろう)17歳の夏のことだったという。聖はプロになって言う。「プロになって勝っても、嬉しくない。相手を殺さねば、自分が生きていけない世界に自分は耐えられない。」けれども皮肉にも聖の唯一の生きる支えは将棋だった。知っている方もおられると思いますが、将棋の世界はほんの数人だけが勝ちあがる弱肉強食、本当に厳しい世界です。その世界で、聖は将棋の頂点一歩手前まで行く。ものすごい才能、ものすごい修羅の道だったに違いない。プロで得た給料の余分はすべてアフリカの子供たちへのフォスタープラン協会への寄付になっていったという。小説でも、漫画にも書かれていなかったエピソードです。わたしはうーむ、とうなされました。まるで宮沢賢治「よだかの星」です。私は、よだかの様に自分が生きるためにほかのものを犠牲にしていくことに気がつく度に泣く事はできません。でもやはり私も「星にはなれない」よだかの一人なのです。まるでとってつけた様に署名のお願いです。でも今、自分が淀川に飛び込んで濡れなくても出来る事です。昨日の記事で、hekomiimoさんから「リハビリテーション医療の打ち切りに反対する署名」のお願いがありました。6月24日署名集約打ち切りだそうです。詳しいことはまだよく学習していないのでわからない。けれども確実に何人かは溺れかかっている。私は臆病なので、人の助けを呼ぶことにした。リハビリテーション医療の打ち切りに反対する署名←このサイトでネット署名ができますと、ここまで書いた後、ネットにつなげると、既にUTSが署名の呼びかけをしていた。まあ、なんという素晴らしく速い情報の、人の、繋がり方だろう。私はこんな回りくどい言い方でしか、呼びかけは出来ませんでした。まあ、これも私の個性だと思って許してください。
2006年06月15日
コメント(10)
-

老人たちの覚悟あるいは「いのちのかたち」
新・ちくま文学の森(6)「いのちのかたち」という本の中にはさまざまな命の形が収められている。ロバート・フロスト 川本こうじ・訳『雪の夜、森のそばに足をとめて』この森の持ち主がだれなのか、おおかた見当はついている。もっとも彼の家は村のなかだから、私がこんなところに足をとめ、彼の森が雪で一杯になるのを眺めているとは気がつくまい。略森はまことに美しく、暗く、そして深い。だがわたしにはまだ、果たすべき約束があり、眠る前に、何マイルもの道のりがある。眠る前に、何マイルもの道のりがある。わたしが思うにその森は、死期が近い人だけに見える「何か」なのだろう。この作品集には他に、老いを意識し始めた女と男の金と欲がからんだ会話劇を描いた林芙美子の『晩菊』、終末医療の患者の心理をありありと描いた耕治人の『そうかもしれない』、「ウォー、ウォー」と叫びながら凄絶に死にゆくリツ子の臨終を描いた壇一雄の『終わりの火』、『「じゃあおれはもう死んじゃうよ」と何の表情もない、穏やかな目であった。わたしにも特別の感動も涙も無かった。別れだと知った。「はい」と一ト言。別れすらが終わったのであった。』謹厳、静かな父親の死を書いた幸田文の『終焉』。等々がある。あとがきで編者の鶴見俊輔は意外にもこんなことを書いていた。「二月ほどまえ、癌の告知を受けたとき、医者との会話がとぎれず、気分として普通の状態が続いた。ところが、そのすぐあとで看護婦が血圧と脈をはかりに来たときの記録によると、血圧は153-91、脈は99で、ふだん(その日の朝には血圧122-95、脈85)よりやや高く、わたしのからだはこどものころよりにぶくなったなりに、告知にこたえていた。」「なぜ生きるかの理論は、なぜ自殺しないかの理論と背中あわせである。」この本の発行は1995年。だとすれば、鶴見の癌は何とか転移を免れたのだろう。去年九条の会の事務局長小森陽一氏が講演でこんなうち明け話をした。九条の会の一周年を記念しての講演会の打ち合わせで鶴見俊輔がこういったという。「だれか一人はくたばるかと思ったけど、なんとかもったね」そのブラックジョークにわたし一人が笑ってしまって会場の失笑を買ったのである。だけどこのあとがきを読んで、鶴見俊輔はほとんど本気で言ったのだと思った。そしてわたしたちは本気で彼らの覚悟を知らなくてはいけない。6月10日、九条の会・全国交流集会があり、全国から1500人の人が集まり活発な交流が図られたという。九条の会は全国でざっと5000以上にまで達しているという。9条守ろう! ブロガーズ・リンクで、集会の内容をしっかりレポートしてくれている。思うに、今のところ、最も詳しいレポートなのではないだろうか。そこで、鶴見俊輔はこういうことを言っていた。「戦争を起こす文明に、耄碌人として反対する」三木睦子さんにいたっては「私たち九人は、もうそろそろ、力つきます(笑い)。いあ、実はそうでもないんですよ(笑い)。 私たちに、平和をもたらすのは、私たちの心からです。やさしくて、楽しい世界にしようではありませんか。みんなが楽しみを持てる世界にしようではありませんか」本当に彼らは命がけで戦っている。彼らの思いを引き継ぐ若者がもっともっと育たないと、この運動はジリ貧になってしまう。全国集会には案外若者が参加していたそうだ。今回は会場制限で人数が限られたし、日程も一日だけだったが、来年は憲法共同センターなどの力を利用してもっと大きい会場で、2日がかりぐらいで交流集会をしたらどうだろう。年寄りはともかく、若者は「刺激」を貰うと大きく化ける。全国の経験の交流を聞くだけ、あるいは自分で発言することで、大きく成長するだろう。そして加藤周一の言うように、「老人と若者の連帯」も、リアル世界で顔をつき合わせて2日ぐらい話をすると、大きく進展するかもしれない。今から来年に向けて準備していってはどうだろうか。
2006年06月14日
コメント(8)
-

W杯開幕 国連も夢見る
アナン国連事務総長が、W杯に「かこつけて」各国主要紙に投稿している。日本の場合は10日つけ朝日新聞の投稿欄に載った。非常にいい文章なのだが、ネット配信している記事ではないので、自力タイプで紹介したい。(誤字があったらごめん)私も9日深夜、ドイツVSコスタリカ戦を見ながら、(9.11の映像も確かに世界中が注視したけど、それに負けず劣らない目が今現在この映像を見ているのだ)と考えながら、『人類に希望はある』と感じたのでした。『W杯開幕 人々の熱気国連も夢見る』コフィ・アナン(国連事務総長)国連事務総長がワールドカップ(W杯)について書くなんて、読者は奇妙に思うかもしれない。しかし、国連から見ると、W杯は実際うらやましい限りなのだ。地球上のすべての国・地域の人々が競い合う国際試合の最高峰。国連もW杯同様、国際交流の場であるが、読者には『W杯は国連以上だ』といわれそうだ。何しろ国際サッカー連盟の加盟国・地域は207。われわれ国連は191カ国だからだ。私がうらやましいというのは、以下の理由による。第一の理由は、W杯の人気である。自国チームの順位がどうで、いかにして本戦出場を決めたか、誰がミスし、誰がペナルティーキックを防いだか、誰もがよく知っている。我々国連もその種の競い合いがあればいいと思う。世界中が見つめる中、「人権」という”競技”各国が堂々とトップを目指して競い合い、幼児死亡率の”低下競技”や教育を受けられる子供たちの数で競い合う。第二は話題性。ブエノスアイレスの街角から北京の喫茶店まで、地球上のいたるところで、人々は自国チームのゲーム展開に口角泡を飛ばす。話題は相手チーム、他国チームへと広がる。普段は口数の少ない10代の若者が、W杯の話になると、突然、雄弁家に変身する。国連もそのくらい世界中で話題になれば、と思う。「人間開発指数」(保健水準、教育水準、所得水準に基づく国の開発指数)や排ガス規制やエイズ問題に、自国がどれだけ熱心に取り組んでいるか、ホットな話題になればいいと願う。第三は、平等な参加の機会。W杯は才能とチームワークがあれば、どの国のチームにも本戦出場できる機会が与えられている。国連も、もっと機会の平等性を持っていて、各国が国際舞台でその力を発揮できればいいと思う。第四は、人種間、国家間の交流。いまや多くの国家チームが他国から監督を招くようになり、新しいサッカー観が導入されている。普段は外国のチームで活躍し、その国でヒーローになり、国家間交流に大きな役割を演じている選手も多い。そしてW杯の際にはその経験を自国チームに生かしている。国際社会でも移住者が、移住者自身と母国と受入国の三者にとって、ともに利益になればいいと私は願う。生活、経済、社会、文化の交流と深化を通じて。W杯出場は国家の誇りに深くかかわる。私の母国ガーナのように、初出場国にとっては名誉の架け橋である。アンゴラのように長年内戦にあえいだ国にとっては、国家再生の大きな踏み台にもなろう。内戦で分裂状態にあるコードジボワールのような国にとっては、国家統合の象徴的存在であるナショナルチームは国家再生の希望である。我々国連にとってもっともうらやましいと思うのは、W杯は到達すべき目標がはっきりと見えることである。私は何もゴールのことだけを指しているのではない。国家と人間による大きな地球家族の一員として、共通の人間性をたたえる場であること。それこそが最も重要なゴールではないか。わがガーナが12日にイタリアと対戦する際、私はそのことを思い返してみようと思う。その通りになるかどうか、約束できないけれど。
2006年06月10日
コメント(2)
-

怪物の誕生物語『山椒魚戦争』
昨日の続きです。さて、この小説の大まかな筋はこうである。一商船の船長が、インドネシア方面の海中で、山椒魚に似た奇妙な動物を発見する。彼は、この動物が人になれるうえに利口なことを知って、真珠採取に利用することを思いつく。そして、この仕事の企業化を、ある実業家にもちかける。山椒魚は、まず単純な海中作業に利用されるが、やがて、人間はさまざまな技術を教え、言葉までさずけて、彼らを高度な仕事につけはじめる。知識と技術を獲得した山椒魚はいろいろな権利を主張しはじめる。やがて彼らは自分たちの住処を確保するために地球の湾岸の大改造に取り組む。どんな軍事力も彼らには適わなかった。やがてほとんどの陸地が海に沈む。世間話、奇談、学術論文、等々さまざまな体裁をとりながら話が進んでいく。一つ一つのエピソードは独立していて、壮大な大河小説のように読むことも出来るし、単なる人間社会への風刺のように読むことも出来る。たとえば、山椒魚がしゃべり始めると当然『マスコミ』は殺到する。そのときこういうエピソードがある。ロンドン動物園のアンディは、「天気からはじまって経済危機や政治情勢に及ぶあらゆる話題で、彼と言葉をかわそうとする人々に取り巻かれた。ところが、彼は、そういう訪問者からチョコレートとか、ボンボンをたくさんもらったのがたたって、重い胃腸カタルにかかった。」結局アンディは「人気があだになって身を滅ぼした。名声というものは、山椒魚さえ堕落させるものなのである。」もちろん人類社会を皮肉っているのは明らかである。山椒魚の最初の『使用価値』は湾岸労働力ではなく、彼らが真珠を探してくる能力であった。山椒魚たちはナイフと「交換」して相当数の真珠を船長と資本家が立ち上げた会社に渡していく。やがてその事業に陰りが見え始めると、資本家は『山椒魚シンジケート』という新しい会社を立ち上げる。株主からそのアイディアを誉められた資本家は山椒魚とは一体どんな生き物なのかと聞かれてこう答えるのである。「それは、わたしも申し上げられませんよ、ヴァイスベルゲルさん。山椒魚がどんなものか、この私に分かるものですか。それにどうして、そんなことを知っていなければならないんです?山椒魚がどんな格好をしているか、といったことまで、神経を使う暇が、いったい、このわたしにありますか?」このくだりを読んで思いだすのは、「資本論」だったか、最初は人間のかわいい子供として味方として生まれ落ちた「お金」であるが、やがて人間を脅かす『怪物』に育っていくというくだりである。(白土三平の『サバンナ』がこのくだりを見事に劇画化しています。)始めペットみたいに可愛かった山椒魚なのであるが、資本家はついにはその正体を知ることなく、育て上げてしまう。それが『怪物』に育ってしまうまで、その正体に気がつくことは無い。この作品のテーマはだからといって資本経済批判なのではない。チャペックの意図はそこにもあったかもしないが、現代の私たちが読むとき、それは当時は無かった『核兵器』のことにも感じるし、『環境破壊』にも、あるいは未来の『情報社会』のことにも感じる。私たちもいつの間にか、その本当の姿を知ることなく、最初は奴隷として、やがてペットとして、いつの間にか私たちを脅かす『怪物』として何かを育てているのではないだろうか。(例えば、小泉、安倍)『山椒魚戦争』は1936年に出版され、チャペックは1938年チェコで死亡している。チェコがミュンヘン協定をへてドイツ軍のために全土を占領されたのはその翌年1939年のことであった。
2006年06月09日
コメント(0)
-

70年前の予言の書『山椒魚戦争』
UTSの今週の御題は本についてらしい。ちっょと協賛。「山椒魚戦争」岩波文庫 カペル・チャペック 栗栖継訳古代の進化からとり残されていた大山椒魚たちは、20世紀の始め、野心家の資本家の手により「利用」されることにより、急激な「進化」を始める。物語は、ドラマ、世間話、奇談、学術論文、新聞記事、等々のさまざまな体裁を取りながら、山椒魚族と人間との奇妙な戦争、文明の滅亡、さらには山椒魚族の滅亡まで取り上げる。実際の原作を読んだ人は少ないと思う。今はどの本屋でも見かけないし。私も96年岩波文庫で増刷されたときに買ってからずっとつんどく状態のままであった。ところが読みだすとこれがまた面白い。話のエッセンス的には手塚治虫「鳥人大系」だと思っていれば間違い無い。手塚は間違い無くこの作品を換骨奪体した。もちろん手塚は手塚なりの味付けをしている。しかし面白さの点ではさすがにこの原作には及んではいないようである。私が約10年前に読了に失敗したのは、話が動き出すまでに時間がかかったのと、そのときの主要人物であるボンディ船長はつい解説を読むとその後は全然登場しないと書いてあったので、何だかしらけてしまったためである。ところが実はこの船長が登場しなくなったあとがすこぶる面白くなるのである。これから読む人はその辺りまでは何とか我慢して読んでもらいたい。カペル・チャペックはその主著「R・U・R」で「ロボット」という人造人間を始めて登場させ、ロボットの名づけ親になったということでも有名である。(ロボットとは労働するという意味らしい)が、どうもそれだけに収まりきれないチェコ・スロヴアキアを代表する凄い文豪だったみたいだ。この本を読んで、とても1936年(昭和11年)の作品とは思えない。訳が良いのか文体は丸きり現代文。ここで書かれている世界情勢、この70年間いったい人類は進歩してきたのかと疑いたくなるくらい違和感が無い。ルイジアナで大地震が起こり、ニューオリンズが津波等の被害で海に沈んだ。それは山椒魚族が自分たちの住処を拡大するために起こした地殻変動で、ルイジアナ知事は山椒魚の長から「人名の損失を出したこと遺憾にたえず」という電報を受け取っていたが、いたずらだと思い無視していた。しかし、これはその後の「戦争」のほんの前触れに過ぎなかったのである。と、いうエピソードが中盤にある。---これですぐ思いだすのは昨年の台風カトリーナ。これってもしかしたら「予言の書」かと思ってしまう。そういえばスマトラの西沖には山椒魚揺籃の地(タナ・マサ島)が有ることになっている。ここが大震災の震源の地であると決めたのは果たして偶然なのか。あるいは、山椒魚との交渉でまったく進まない国際会議。つまらないことしか決まらないために返って事態は深刻になっていくさまは最近の中東問題、北朝鮮問題だ。長くなったので続きは明日
2006年06月08日
コメント(8)
-

茨木のり子「女の子のマーチ」
Under the Sun の今週のコラムは「好きな詩」というものらしい。ちょっと賛同しようと思って、好きな人の詩を眺めていた。最初は、今の情勢を考えて石垣りんの「雪崩のとき」にしようかと思っていたのだが、華氏451度さんがコメントで「もっと希望の熾火をかきたててくれる、元気の出る詩にすりゃーよかったな」と書かれていて、そうだよなー、と思ったので方向転換。茨木のり子さんの詩です。「女の子のマーチ」男の子をいじめるのは好き男の子をキイキイいわせるのは好き今日も学校で二郎の頭を殴ってやった二郎はキャンといって尻尾をまいて逃げてった 二郎の頭は石頭 べんとう箱がへっ込んだパパはいう お医者のパパはいう女の子は暴れちゃいけないからだの中に大事な部屋があるんだから静かにしておいで やさしくしておいで そんな部屋どこにあるの 今夜探検してみようおばあちゃまは怒る 梅干ばあちゃま魚をきれいに食べない子は追いだされますお嫁に行っても三日ともたず返されます頭と尻尾だけを残し あとはきれいに食べなさい お嫁になんかいかないから 魚の骸骨みたくないパン屋のおじさんが叫んでいた強くなったは女と靴下 女と靴下ァパンかかえ奥さんたちが笑ってたあったりまえ それにはそれの理由(わけ)があるのよ あたしも強くなろうっと! あしたはどの子を泣かせてやろうか私としては、双子の姪のこととか、幾人かの女の子のことを思い浮かべています。彼女たちの「大事な部屋」を壊さないように、いつまでも健康であるように、私を泣かすぐらい強い子であってくれるように、おじさんとしては少し元気を出さなくちゃなあ、と思っています。
2006年05月03日
コメント(8)
-

「第3探検隊」あるいは失われた幸せ
2000年4月、第3探検隊は火星に降り立つ。『希薄ですが、安全な大気のある小さな町です。隊長。』『地球の町にそっくりの小さな町だ。』と、考古学者のヒンクストンが言った。合理主義者で、80歳のベテランパイロットの隊長はなぜこのようなことが火星で起きるのかいぶかしみ慎重に探検を始めるのだが、つぎつぎと死んだはずの肉親が穏やかに暮らしているのに出会い、隊員たちは隊を離れていく。隊長でさえも、19歳で死に別れた兄に出会うと理性をなくしてしまう。『ママが待っているよ』『ママが?』『パパも待っている』『パパが?』隊長は硬い凶器で殴られでもしたように、あやうくたおれそうになった。きごちなく、ふらふらと歩き出した。『ママもパパも生きているのかい。どこに?』『オークル・アベニューの昔の家だ。』『昔の家』隊長は驚喜して目を見張った。『ママ、パパ!』隊長は子供のように階段を駆け上がった。 ブラッドベリ『火星年代記』「第3探検隊」より昨日は法事だった。気の置けない親戚同士で、これまでのこと、これからのことなどを話し合った。昔は良かった。正直そう思う。山田洋次の「息子」という映画の最後、父親役の三国連太郎は雪で玄関が埋るぐらいに積もった誰もいない家に帰ったとき、ふと貧しかったが家族団らんがあった昔の幻想を見る。帰りたいものならあの日に帰りたい。この映画が作られたのはもう十数年前だが、厳しい労働の実態と、次に発作があれば死んでしまうだろう父親の未来と、微かにだか確実に残っている親子の繋がりを描いて、忘れられない作品だった。「火星年代記」でも、一応なぜあのようなことが起きるのか、説明はしているが、作者はそんなことを描きたかったのではないだろう。失われた繋がりと幸せーそれが未来に向かって感じられない現実。 共謀罪が通ってしまうと「萎縮社会」がやってくる。教育基本法が通ってしまうと「愛国社会」がやってくる。市場化テスト法は成立したので「民間社会」は進む。、介護保険等の社会保険はさらに改悪され「自立支援社会」に変わる。憲法が改悪されると……。
2006年04月30日
コメント(2)
-

優しい小説『ラッシュ・ライフ』
『ラッシュ・ライフ』新潮文庫 伊坂幸太郎おそらくこの本を読んだ人間の10人に一人はやってみるに違いない。ここに出てくる四人の主要登場人物(黒沢、河原崎、京子、豊田)を時系列の表にして落とし、各人が何処で交錯しているのか、確かめてみる作業である。おそらく10人に9人は、そんなめんどくさいことしなくても、気がついている。この小説はあのエッシャーの騙し絵の構造になっていることを。この絵を少し見てもらいたい。(小さくてごめんなさい)兵士が歩いているお城の上の階段は現実にはありえない構造である。この小説も一点だけ現実にはありえない構造がある。その点を見つけるのがこの本の最大の楽しみになっているのだろう。ただ、表を作ってみてびっくりしたのは、それ以外は実に論理的に構成されているということである。まるでエッシャーの絵のように。伊坂はやさしい。(以下ネタバレあり。反転してね。)金で全てが解決するという男には鉄槌を。リストラされて無職の中年男には億単位の当たりくじを。神を求める青年には考える時間と空間を。我がまま女には、人生の苦味を。まるで人生の高みから眺めるように、まるで未来が分かってしまう『カカシ』のように、小説を作ってしまう。一方伊坂は、金持ちを憎んでもいないし、格差社会をどうこうしたいとも思っていないし、神は信じようともしていないし、タカビー女は嫌いだろうが、ほんとに好きな女のタイプのことは(おそらく)描こうとしない。彼はなぜ小説を書いているのだろう。そのこが気になってもう少しこの作家の本を読んでいこうと思う。この人の作品はキャラクターが作品を飛び越えて登場するのが特徴なのだが、まさかバルザックの『人間喜劇』を目指してはいないだろうね。もしそうなら人間の描き方が軽すぎる。付録。気に入ったセリフ。『リブート?電源を入れなおすことか?』『そう。再起動することだよ。パソコンを使っているとね、メモリという場所にいろいろな作業用の情報が残ったりして快適に動かないことがあるんだ。そういう時は再起動してあげれば、クリアされてまた動作がスムーズになる。』『なるほど』『わたしはね、今日ここでリブートした気分だよ。人生を再起動した。』
2006年04月21日
コメント(4)
-

神はなぜ戦争を許したまうか「神のふたつの貌」
昨日のエントリーでは「神と戦争の関係」まではたどり着くことが出来なかったのですが、今日紹介する作者は神様のことをしっかりと勉強してかかれたみたいで、この小説を手がかりにして、私は無理にそこまで話を持っていこうとしています。『神のふたつの貌』文芸春秋 貫井敏郎一応ミステリなので、仕掛けが有る。でもミステリとしてはお勧めではない。ちなみに一番最後は漫画版『デビルマン』の最後の場面をフィーチャーしている。神をテーマにした小説だからそれでもいいのだが、ちょっとした遊びごごろだろう。一章で、教会の牧師の12歳の息子早乙女(非常に早熟な考えを持った子供)と青年部のリーダー久永と神についての問答が有る。ここの教会はプロテスタントなので、清教徒であるブッシュの論理とは少し違うかもしないが、日本人にとってはあの穏やかなキリスト教徒たちが何故歴史的にも戦争を繰り返すのか、ひとつの回答になっていると思うので、長くなるが要約してその問答を再現したい。久永は早乙女の疑問を要約する。「神様が人間のことを愛しているなら、どうして戦争が絶えなかったり、辛い思いをする人がいつまでもいなくならなかったりするのか、不思議なんだろう。それは神様なんていないか、いても人間のことを見捨てたせいじゃないか。そう考えたんだろう?」そうだ、と早乙女は応える。自分も神はいると思う。正確にいうなら、造物主だ。神は世界を創りたもうた。だが、神の御業はそこまでのことだ。神は自ら創り上げた世界に、徹底的に不干渉の方針を貫いている。その態度は、見捨てたので無ければ、冷徹な傍観者のそれだ。まるで飼育箱の中のマウスを観察するような視線、それが人間に向ける神の目ではないだろうか。「違うんだ。そうじゃない。神は最初からずっと、人間に期待を寄せているんだよ。不完全な人間が、神の放つ波動をきちんと受け止められるようになることを、長い間ずっと期待しているんだ。」しかし、人間を不完全に創ったのはやはり神だ。それなら最初から完全な存在に創ればよかったのに。「完璧な存在ならわざわざ創り出す必要が無いじゃないか。人間は不完全だからこそ、神に近づこうと努力するんだ。完全だったら努力なんて無意味だ。人間を愛するのは、人間が努力するからなんだよ。」久永は零細スーパーの主人。このような真面目なキリスト教徒は無数にいるだろう。「人間はもともと神の放つ波動(神からの愛、人間からの祈り)を受け取ることが出来た。でも人間は神を裏切り、楽園を追放された。」これは創世記に記載されているアダムの原罪のことである。蛇から知恵の実のことを教えてもらい、食べる。そして楽園を追放されるのである。原罪は「人殺すことなかれ」等の10戒とはレベルが違う。神と波動の交換が出来なくなること。人間が自ら善悪の判断が出来るようになるということ、なのである。早乙女は質問する。神は裏切られたとき、見捨てることにしたのではないか。「いや、地球上の生物で神と波動の交換が出来るのは人間だけだ。そのように神は人間を作ったんだ。そのような特別な存在を神は見捨てはしない。たとえ不完全であろうと、波動の交換をやめはしなかった。だからおれたちは、神が存在していることを知っているんだよ」「そこで早乙女君のいう疑問だ。何故この世に悲惨なことが満ちているのか。その答えは、人間が不完全だからという一点に尽きる。いつか人間は、かってのように神が放つ波動を100%受け止められるようになると思う。そのときはこの世から全ての不幸が無くなっているはずだ。俺はそう信じている。」えっ!と無神論者の私は思う。じゃあ、神様から100点満点をもらうまでは、この世に戦争は無くならないということ?戦争が起きるのも、人間の信仰が足りないからなの?そんな疑問はよそに、早乙女は久永に質問する。それならば神はただ傍観しているだけでないのか。どうして導いてくれないんだ。「神は万能だ。だからこの世の不幸を全てなくすことも出来る。けれどもそれは人間が自分の力で実現しなくちゃいけない。そうしなけば、波動を浮け止めることが出来るようにならないんだ。」「人間は肉体と霊のふたつで出来ている。人間は生まれる前は霊だけで存在している。そのときに、どんな人間でも神と契約を結んでいるんだよ。人間はその契約は忘れてしまうけど、この契約にそむくことは出来ない。神との約束は、それだけ絶対のことなんだ。だから不幸に陥る人はそれは神との約束だからだ。」それは納得できない。早乙女は初めて首を振った。「そうだろうね。誰だって肉体を持つ身ではそう考えるはずだ。でも霊だけのときには、あえてわが身に不幸を与えてほしいと望むことだってあるはずだよ。だってそのほうが、より真摯な祈りを神にささげられるし、その結果、より美しい波動が得られるようになるからだ。人間の本質である霊にとって、肉体の寿命はほんの一瞬のことだ。そんな一瞬の不幸よりも、より恒久的な神の波動を望むのも当然だろう。」早乙女はこの後、神を理解したいがために幾つかの行動を起こす。その中には殺人も含まれている。物語はそうなのであるが、私は何故ブッシュが戦争を起こして何万人ものイラクの民を殺しても罪の意識を覚えないのか、その『仕組み』を理解したように思えた。自然の中で人間は唯一神と波動の交換が出来る特別な存在である。人間には原罪がある。『人を殺すこと無かれ』という道徳律より原罪を償う方が優先される人間と神の間には契約がある。この契約の善悪は人間には判断できない。肉体時の不幸は一瞬、神との生活は恒久的である。ということは、もしイラクとの戦争が『正義』ならば、殺人は許されるし、自分が戦死するのも契約のうちということになる。神と波動の交換が出来ないイラクの民や私たちは「不幸な民」なのだろう。貫井敏郎はもちろん無神論者である。その立場からこの小説を書いている。彼なりに殺人とはどういうことなのか極めたかったのだろう。相当勉強の跡がうかがわれた。神の声を聞くために、何でもする主人公を配して、罪とは何なのかを考えさせる力作である。一方貫井は戦争論まで広げていない。広げたのは私である。キリスト教に詳しい方から反論があれば嬉しいと思う。
2006年04月19日
コメント(22)
-

神とはなんだろう「神狩り2リッパー」
この間、神様の聖地で人殺しが延々と続いている「ミュンヘン」という映画を観たり、9.11の影響が延々と続いているさまを眺めているうち、「神とはなんだろう」という疑問がむくむくとわいてきた。そんな気持ちもあって、久しぶりに山田正紀の「神狩り2リッパー」というのを図書館で借りてきた。この本を借りたとき、一応前作からそのままつながっているみたいなので、先ずは前作を読もうと本屋で探して『神狩り』(ハヤカワ文庫)を買って読んだ。昔読んだのを思い出した。一応あらすじはこうである。若き天才情報工学者、島津圭助は、神戸市で調査中の遺跡、花崗岩石室内壁に、ある『文字』を見せられる。十三重に入り組んだ関係代名詞と、二つの論理記号のみの文字。論理では解くことのできないその世界の言葉を執拗に追うある組織は、島津の卓越した頭脳に、この文字を通じて『神』の実在を証明することを強要する。……30年前の山田正紀のデビュー作である。あの頃、半村良やら、小松左京やら、平井正和やら、星新一やら、日本SFを図書館で借りまくっていた。物語はつぎつぎと仲間がやられていって、一人残った島津が神に向かって「お前の正体を暴くぞ」と宣言するところで終わる。まるで平井和正の「幻魔大戦」ですね。なかなか面白かった。スーパーコンピューターがまだ電子計算機で、特権人種しか使えなかったころの話である。さて、30年後満を持して続きを書いたところ、どうなるのだろうか。『神狩り2リッパー』徳間書店 山田正紀期待して読んだ。謎は解けるのだろうか。この30年間、山田正紀はこのような小説しか書いてきていなかったのか。これは『濃密な描写』ではない。単なる原稿の増す目潰しである。日本SF大賞をとった『最後の敵』も、推理小説でいろいろ賞をとった『ミステリ・オペラ』も私は読んでいない。だからほとんど25年ぶりの邂逅である。『この世は神が創造した。それならば、神は人々を裁いてもそれを善い社会にするはずじゃあねえか。にもかかわらず、神は動かない。裁かない。』『人間が何をしようと、しまいが神は勝手に動く。』『神はアリバイが必要だった。そのアリバイを保つために「神」はやむおえずイエスを忙殺する必要があったわけなのさ』ちょっとわけが分かんない説明で申し訳ない。そもそも山田正紀は人類の秘密の一端をSFという「かっこいい」小説によってみせるということに主眼を置いてきたはずだ。そこはこの間も変わってきていない。しかし、壮大なテーマを前にして、この25年間、前作以上の仕掛けを提示することが出来なかった。こんなにも何も進歩が無かったとは思わなかった。よって、私は次の小説に手をかけることになる。
2006年04月18日
コメント(4)
-

精神科医の眼「症例A」
「症例A」多島斗志之 角川文庫推理小説の中には、謎解きそのものに重きをおく作品と、謎解きは話を面白くするツールであって、その背景説明の部分が一番書きたいところであるところの作品と二種類有る。松本清長の作品は後者であって、死かも社会背景を描くことに重きを置いている。しかし、後者はそれだけではない。哲学的なことに重きを置いたり、この作品のように、哲学ではなく、心理学の説明に重きをおく作品も有りうるだろう。もちろん、謎解きにも重きを置いて、『衝撃のエンターテイメント』を描くことも可能であろうが、心理学という分かったようで実はよく分かっていない世界を描くことも、北村薫のいう『ドキドキするような発見の喜び』があり、私はこれも充分「本格」だと思う。小説だとどういうことが可能になるのかというと、まるで自分が精神科の医者になったかのように、同じ目で病を得ている人の「症例」を見ていくことが出来るのである。一人の人の病の診断がいかに難しいものなのかをこういう本を読むとつくづく感じる。鬱病なのか、分裂病なのか、境界性人格障害なのか、それとも乖離性同一性障害すなわち多重人格なのか、専門家が見てもその判断がいかに難しいかを読む人間は知るのである。医者でも人間だ。間違いも有るだろう。それでも主人公の榊医師は覚悟を持って真面目にそれに対処していくのである。エンターテイメントではないが、読んだ後の充実感は非常にあった。
2006年04月17日
コメント(2)
-

春の季節の向こうにあるもの『博士の愛した数式』
『博士の愛した数式』新潮文庫 小川洋子春はこの小説を読むのにちょうどいい季節である。春はこの小説を読むのにとても残酷な季節である。春の季節の向こうにあるものは、近づいているのか、遠ざかっているのか。博士とルートの問答で、印象に残ったことの一つ。続きの奇数が二つとも素数なのが双子素数という。17、19とか41、43とかである。素数が無限にあるのように双子素数が無限に有るかどうかは分からない。「数が無限にあるんだから、双子だっていくらでも生まれるはずだよ」「そうだね。ルートの予想は健全だ。でも100を過ぎて一万、百万、千万、と大きくなると、素数が全然出てこない砂漠地帯に迷いこんでしまうこともあるんだよ」「砂漠?」ああ、そうだと博士は答える。それでもあきらめずにいくと、地平線の向こうに澄んだ水をたたえた、素数という名のオアシスが見えてくるという。それはまるで人類がいつか体験する宇宙への旅のように私には感じられた。映画が博士と未亡人の関係が重要なテーマになっているとしたら、この小説は博士とルートの関係が重要なテーマになっている。「彼はルートを素数と同じように扱った。素数が全ての自然数を成り立たせる素になっているように、子供を自分たち大人にとって必要不可欠な原子と考えた。自分が今ここに存在できるのは、子供たちのおかげだと信じていた。」子供は身近にいるようで、実は砂漠の向こうのオアシスのように貴重なものであることに気がつかされる。気がつくということは自分の中の素数を思い出す過程でもある。この本を読んでも結局オイラーの公式を構成するeやiやπの解釈は出来なかった。『神は存在する。何故なら数学が無矛盾だから。そして悪魔も存在する。何故ならそれを証明することは出来ないから。』どこかの「難しい名前の数学者」の言葉のように、このやさしさに満ちた小説の背後にはこのような恐ろしい『真実らしき』ものが横たわっている。だからこそ何度も何度も宇宙の砂漠をさまよい歩いた冒険者である博士が地球に舞いおりたときお手伝い親子にみせる優しさが私には心に堪える。
2006年04月15日
コメント(8)
-

最後の一行『99%の誘拐』
『99%の誘拐』講談社文庫 岡嶋二人「この文庫がすごい!」の05年度一位ということで読ませてもらった。700円というと韓国の一本映画鑑賞代である。その値段で約5時間、ノンストップのエンターテイメント映画を見た気分である。読み終わったのは、午前4時。その日の一日の生活がちょっと怖かった。あらすじ末期ガンに冒された男が、病床で綴った手記を遺して生涯を終えた。そこには八年前、息子をさらわれた時の記憶が書かれていた。そして十二年後、かつての事件に端を発する新たな誘拐が行われる。その犯行はコンピュータによって制御され、前代未聞の完全犯罪が幕を開ける。ただし、あー面白かった、で終わるタイプの作品でもある。登場人物たちの深い掘り下げは冒頭の生駒洋一郎以外には無い。トリックも面白いがそれほどではない。ハイテクをテーマにした犯罪である。TVシリーズ「24」では10分で犯人が割れてしまうような仕掛けなのではあるが、88年の日本だから成立はする。この当時確か私はパソコンなんて思ってもいなくて、初めてワープロを買って文章を打ち始めた。パソコンによる完全遠隔操作アリバイトリックはこの時代にあっては最先端の情報だった。時代劇の捕物帖が江戸時代だけに成立するように、このミステリも80年代後半だけに成立する歴史ミステリなのかもしない。などということの感想を持ちながら、最終ページの奥付けを見て私はびっくりする。「1988年徳間書店より発行される。」トリックとか筋立てより何よりも一番驚いたのはこの『最後の一行』である。
2006年04月06日
コメント(4)
-

「8号古墳に消えて」推理小説の考古学ネタ
「8号古墳に消えて」創元推理文庫 黒川博行私はもともと考古学ネタは推理小説になる、と思っている。考古学というのは物証の学問である。ブツが無ければ、一歩も進まない。しかも、たった一個の魚の小骨から、当時の食生活から、流通経路まで推理するのが考古学という学問なのだ。(「環境考古学への招待」参照)ところが推理小説のなかに考古学ネタがあまりに少ない。というところで、ふとこの本に行き当たった。うーむ、本心はがっかりである。作者はよく勉強していると思う。いやいや全然発掘作業に詳しくない私なので、えらそうなことは言えるはずも無いのであるが、私の本心としてはやはり考古学者が探偵役になってほしかった。この大阪府警の黒まめコンビはシリーズ物らしく、「地どり」の最中にも喫茶店にたむろしてはサボる描写など全然推理小説の主人公らしくなくて面白い。ただ、結局トリックにしろ、考古学的遺物に語らせる部分がほとんど無くて、絶対考古学でないとだめということでなかった。民俗学者の八雲が探偵の主人公として活躍するくらいだから、ぜひ考古学者も主人公になるシリーズ誰か作ってくれないだろうか。
2006年04月05日
コメント(5)
-
今から一年前の
2005年4月、スタンダール氏はアッシャー邸という名前の建物を立てた。工事責任者のピジェローはこの名前の由来を尋ねた。スタンダールはエドガー・アラン・ポーという名前を知らないかと聞く。ピジェローは首を横に振る。スタンダール氏は困惑と侮辱の入り混じった調子で言った。「あの有名なポー氏を知っているだろうと思うほうが無理だったんだろうな?ずっと前に死んだんだもの。リンカーンより前にね。彼の本は全部、あの大焚書で焼かれたんだ。30年前ーー1975年だ。」「あー」と、ピジェローはしたり気で言った。「あの時のひとりですか?」「そう、あの時のひとりなんだよ。かれも、ラヴクラフトも、ホーソーンも、アンブローズ・ピアスも、あらゆる恐怖と幻想の物語はみんな、だから当然、未来の物語というのもみんな、焼かれたんだ。無情にも、ね。かれらは、法律を通した。ああ、最初は、小さなことから始まった。1950年や60年頃には、一粒の小さな砂に過ぎなかった。かれらは、まず、漫画の本の統制からはじめた、それから探偵小説の統制、もちろん映画にも及んだ、いろんなやり方で、つぎつぎとね、政治的偏見もあれば、宗教的偏見もあり、組合の圧力というのもあった。つねに何かを恐れている少数者がいたし、暗黒を、未来を、過去を、現在を、じぶんじしんを、じぶんじしんの影を恐れている大多数の者がいたんだ。」ところで、この会話がなされているのは、火星の上です。すみません、「四月バカ」をやってみました(^^;)出典はレイ・ブラッドベリ「火星年代記」の中の短編「2005年4月第二のアッシャー邸」の一節です。1950年の発表です。数行でも騙された方がおられたら本望です。1999年火星に着陸した人類は、地球とあまり変わらない環境と火星人の自滅のおかげて急激に火星を植民地化していく。いろんな夢を火星に持ってくる地球の人たち。さまざまなエピソードを詰め込んだ連作短編集です。地球は2005年11月に全面核戦争が始まり、ほぼ滅びてしまいます。以下は「2001年6月月は今でも明るいが」より。「われわれは火星を損じはしないよ。」と、隊長は言った。「火星は大きすぎるし、善良すぎる。」「そう思いますか?大きい美しいものを損なうことにかけては、わたしたち地球人は天才的なのですよ。」
2006年04月01日
コメント(4)
-

あさのあつこのデビュー作「ほたる館物語」
「ほたる館物語」あさのあつこ「バッテリー」つながりでもう一冊。あさのあつこデビュー作である。「じゃりん子チエ」のチエちゃんにきちんとして両親がいたら、一子ちゃんみたいになるのではないか、と思わせるキャラクター。旅館経営の難しいことはおかあちゃんやおばあちゃんに任してはいるけど、やっぱり気になる小学校5年生から見た大人と子供の世界。一本義の一子は筋を通してがんばる。大人の世界をきれいごとで描かない、ひとつ二つほろりとさせる、デビュー作からなかなか魅せる。
2006年03月29日
コメント(0)
-

表紙も良し「バッテリー(4)」
中学生野球小説というよりか、現代の「次郎物語」「あすなろ物語」「バッテリー(4)」角川文庫 あさのあつこ四巻目、好きだな、と思った。一巻目の驚きも、二巻目の衝撃も、三巻目のわくわく感もないけど、横手中学校の天才スラッガー門脇と五番の端垣が、みごと巧と豪のあわせ鏡となる。「可能性」の前に二人は素直になる。若いんだもの。自分の力量のせいで巧のボールが打ち込まれたあとの豪の呆然とした後ろ姿を切り取った表紙の絵も好きだな。それと岡山在住の作家なので(彼女は岡山県九条の会の呼びかけ人)、新田の地のモデルは明らかに新見市であることがわかる。岡山の県北、津山と並ぶ二番目の盆地の町である。いろいろとイメージしながら読むことができる。10月の終わり朝はいつも霧で真っ白になったり、セイタカアワダチソウに初雪がふりだすと冬になるという季節感。三月にはアテツマンサクの黄色い花が咲いただろうか。
2006年03月28日
コメント(0)
-
宿題提出します「23分間の奇跡」
「23分間の奇跡」集英社 ジェームズ・クラベル 青島幸男訳短い本である。でも感想がどうもまとまらない。なぜなのだろうか。去年の10月、私のこの「再出発日記」がめでたく一万ヒットを迎えた。それを踏んで頂いたのが、碧落さんである。住所を聞いて記念品を贈るわけにもいかず、好きな本の書評を書かせてもらう、と申し出たところ、ものすごく喜んでもらい、この本の書評を書くことを約束した。…………ところが紆余曲折があったあとこの本を探して読んだところ、(「絵本」形式なのであっという間に読める。)どこから手をつけていいのかわからなくなってしまった。ちょっと読んだだけでは、この著者は愛国心を持て、とでもいいだげである。ところがそうではないというのはすぐわかった。この著者はどういう人なのだろう。調べてもどうも取り留めのない人だ。…………そういうわけでどうも取り留めのない話になりそうだ。ものすごく待たせたのに、(宿題がこんなに遅くなったのはもちろん私の人生で初めてです)こんなので申し訳ない。碧落さんは中学三年。ものすごくしっかりしているお嬢さんです。試験はもう一段落ついたよね。いい春が来てますように。話はそう難しくは無い。ある日のアメリカの小学校の話。どうやらアメリカはどこかの国に戦争かなにかで負けたらしい。授業が始まると、突然先生の交代があると知らされる。新しい先生は若い女の先生だ。この先生、不安がる女の子に歌を歌ってあげたり、あらかじめ机の位置で子供たちの名前を覚えていたりしてあっという間にほとんどの教室の子供たちの気持ちをつかんでしまう。ジョニーはまだ反発している。お父さんが戦勝国に連れ去られているからである。さて授業を始めようとして、先生は最初の「こっきにちゅうせいをちかう」というところで、「ちょっと待って」という。「このことはどういうことなのかしら。」みんな答えることが出来ない。意味なんて教えてもらっていなかったのだから。「ちゅうせいというのはね、こっきのためにつくすって、約束することなのよ。そして国旗というものは、とても大事なのね。だからみんなは、国旗がみんなの命よりだいじですって、そのちかいのなかでいっているのよ。でも国旗がのほうが、人の命より大事だなんて、そんなことあるのかしら。」難しい問いかけである。ところが先生、生徒が答える前に解決策を出してしまう。「国旗をみんな好きなら、この国旗を少しずつ皆で分けたらどうかしら。」そうやって国旗を切り刻んでしまう。ジョニーはまだ納得しない。「私たち負けたの?それとも勝ったの?」誰かが質問する。「わたしたち、つまり、わたしも、みんなも、どちらも勝ったのよ。」「へえー」みんなは安心する。ジョニーは爆発する。「僕のお父さんをどうした。どこへやった。」先生は「お父さんは間違った考え」を直すために学校に行っていると説明する。「勘違いしないでね。悪い考えと間違った考えは違うでしょ。だから、学習が終わったら帰ってくるわ。」ジョニーは父さんが帰ってくると聞いて安心する。先生は合宿の計画も打ち明ける。生徒が質問する。「ねるまえには、おいのりをするんでしょ」先生は巧妙に「お祈りしても役に立たない」ということを「これは秘密よ」といって教えてあげる。みんなは納得する。ジョニーはいまや、先生にすっかりうちとけていた。「この先生はうそをつかないで、何でも本当のことを言うからだ」授業が始まって23分間が過ぎていた。以上が「23分間の奇跡」の大まかな筋である。「スーパーサイズミー」という映画が有る。一ヶ月間、マクドナルドのみ食べつづけると、どういう変化があるか、監督自身が人体実験した映画である。この国の食生活の貧しさを単的に示した映画である。この映画を見るとBSE問題に無関心であるという米国の消費者意識が透けて見える。いや、そんなことはどうでもよくて、この映画のなかで、マクドナルドのCMが子供の心にどれほどまで植えつけられているか示すためのエピソードとして、「忠誠の言葉を言ってみて」といわれてつい詰まってしまう20代の女性に「マクドナルドの歌を歌ってみて」と聞いたら、すらすらと歌えた、というのが有る。問題はこの女性の反応だ。「恥じよ、これは恥じだわ。」私は知らなかったのであるが、アメリカ国民というのは、小学校時毎日国家に忠誠の言葉を発しているらしい。日本の公務員も、その最初の入所式には日本国憲法に忠誠を誓う。しかし、アメリカの場合、憲法に対してではなく、国旗に対して忠誠を誓っているらしい。TVシリーズ「24」にしても、法律よりも、国家に対する忠誠のほうが優先されている。アメリカにとって、愛国心は9.11があったから突然沸きあがったものではないのだろう。では、この本は愛国心を自分のものとして消化していないアメリカを批判した書物なのだろうか。実は若い女先生のほうは、最後のところで「うまくいった」と安心している。「ここまでのやり方は、全て教えられた通りに運んだまでのことだ。」先生は「この土地の全ての男や女たちが、同じ信念を持って、同じような手順の元に、教育されていくであろう」ことを思うと胸が熱くなるのである。先生の国はどうやらソ連を想定しているみたいである。(原本は1981年発行。)著者はもう一つのモデルである、国家ではなく指導者に忠誠を使う国、神を信じない国(ソ連のことだろう。ただしステレオタイプ的な認識ではある。)に対しても明確に批判的に見ているのである。では、どうすればいいというのだろう。私が小学校4年のときに担任になった鈴木先生は、授業の始めに歌を歌うということを始めた。後にも先にもそんなことをしたはその先生だけだった。歌は「ドナドナ」である。牛が殺されるためにつれていかれる悲しそうな歌である。名曲である。後に中学生のとき音楽の時間でも習ったから、純粋に情操教育のためだったのかもしれない。と、つい最近まで思っていた。しかし、今突然思う。あの時代、ベトナム戦争の終結直後だったではないか。この歌はジョーン・バエズの持ち歌だった。当時、この歌は反戦歌として歌われていたのである。そのことを知らなくても、私はこの歌を時々口ずさむ。そして悲しくなる。そんな持ち歌を持てて私の人生は少し有益だった。子供のときに教育は大切だ。たとえ、「きみがよ」の意味は知らなくても、もし毎日君が代を授業のたびに歌うようなことが有れば、その子供の人生に大きな影響を及ぼすだろうと思う。じゃあ反対に、日本人の場合は、日本国憲法前文を毎日授業の前に暗唱するべきだろうか。私はたとえ、憲法前文が国歌になっても、するべきではないという意見であるが、みんなはどうであろう。やはり予想とおり取りとめの無い感想になってしまった。アメリカの「忠誠の言葉」自体にはアメリカの歴史が有るから、私からなにも言えるはずも無い。この本の著者はアメリカ映画界の「アカ狩り」で追われた「大脱走」の脚本家ジェームズ・クラベルである。しかし、その後の著作を見ても彼が共産主義者であった形跡は無い。ただ「同じ信念を持って、同じような手順の元に、教育されていく」ことに厳しく異議申し立てをしてるのだということは感じられた。この本の原題は「The Children’s Story but not just for children」である。中学生よりもどちらかというと大人が読むべき本なのだろう。
2006年03月02日
コメント(6)
-

「晴子情歌」ある女の一生
「晴子情歌」新潮社 高村薫東北政治家の名門の家の傍系の娘・晴子は突然自分の娘の頃からのことを、東大を出ながらも遠洋漁業に従事する船乗りになった息子に宛てて、300日の間手紙100通も書き送る。大正生まれで、東京の教養主義の雰囲気で育ち、東北の厳しい労働のなかで青春を送ったあと、東北政治家の弟の元に強制的に嫁がされ、政治家の外子をはらむ。それでも、そのなかで、みずみずしい少女はいたし、凛々しい女性はいたし、したたかな女はいたのである。晴子は1919年生まれ。私の母は1934年生まれで、この当時の15年違いというのは現代の2~3倍の開きがあるし、東北資産家の遠縁と水呑百姓の娘とでは、天と地ほどの開きがあるから比べるなんて出来ないのではあるが、この小説を読んでいる間、ずっと55歳で死んでしまった母のことを考えていた。影之がこの手紙に出会ってはじめて母親のいろんな面と昭和という時代を感じたように、私は母の死に出会って初めて彼女に青春があったことを知った。戦中戦後にかけての彼女の悲しみと喜び。初めて父が語る母の若い頃のほんの一言か二言で、私は長い長い活動写真のように彼女の人生が見えてしまった。高村薫もこの小説を書く前に肉親が次々と死んでいる。しかし、書いたのは決して彼女の母親の半生ではない。しかしそういう形でしか、亡くなった者に対して決着をつけることが出来ない。という作家の「業」というものはなんとなく分かる。
2006年02月11日
コメント(0)
-
17年が経った
昨日2月9日は大切な人の命日であった。そのことを私はその日が過ぎたあとに気が付いた。と、いうかその人の命日はずっと10日ばかりだと思っていた(^^ ;)。1989年2月9日、そのころ私は10日ほど実家から会社に通っていた。その20日ほど前に母親を亡くしていたので、霊前への「おかんき」をする必要があったためである。家に帰ると妹が開口一番「手塚治虫が死んだわよ」といった。その後暫くは何をしていたか記憶がない。気がついたら深夜テレビ番組を見ていた。その後一週間ほどは昼間にわけも無く涙が流れた。こんなことは母親のときでもなかった。(たぶん涙の種類が違うのでしょう)誰かが天皇が死んで「自分の中から何かがすっぽり無くなっていった」といっていて、こんな人までそんなこというのかと思っていたが、手塚が死んで実感した。最初のおぼえている本は手塚の「ジャングル大帝」。カラーのおそらく二回目の書き直しの版だと思う。ねずみが船の中で幼いレオにミルクをあげるためにストローを継ぎ足していくのを何度も飽きずに眺めていた。近所の駄菓子屋で、10円四個のたこ焼きを食いながら、サンデー連載の「どろろ」を順番かまわず読んでいた。「火の鳥未来編」を真似て「大氷河時代」という漫画を書き、地球の未来を憂える作品をものにしようとしたが、失敗した。本屋で立ち読みすることを覚えて手塚作品は全て読みきった。と、思っていたらいつの間にか青年誌に書いていて、「奇子」によって戦後史に闇があることを知った。日本テレビの24時間番組で、手塚のアニメが復権したときは素直に嬉しかった。NHKで「手塚治虫漫画の秘密」というのをやり、24時間働いてそれでも「僕には漫画のアイディアだけはバーゲンセールが出来るぐらいあるんだ。」といったとき、正直初めて漫画家になる夢を諦めることができた。精神的には手塚の漫画とともに育ってきた。ぽっかり穴が開いても、当然である。あれから一体何年経ったのだろうか。えっ、17年!?と、いうことは手塚治虫を歴史上の人間としか思えない人がもう二十歳以上になっているということ?アトムはまだ誕生していないけど、21世紀のコンピュータ社会になっても、下駄履きのヒゲ親父みたいな中年はごろごろしていることが証明された。「ガラスのような地球」はさらなる危機に喘いでいる。手塚が警告したクローンの問題はさらに精鋭化している。戦争はその後大きいのが四回も起きた。生と死の問題は全然解決されていない。あれから17年間、人類は何をやってきたのだろう。一方漫画雑誌は次々と衰退している。手塚がいた頃から既にわかっていたことだ。問題は技術ではない。何を訴えるかだ。特に子供に。手塚ならその媒体は漫画でなくてもいい、というだろう。ゲームでもいい。けれども、市場に手塚作品に匹敵する「良品」はあるのだろうか。あれから17年……。信じられない。
2006年02月10日
コメント(7)
-

グローバリズムに攘夷を「吉田松陰と現代」
「吉田松陰と現代」鴨川ブックレット 加藤周一加藤周一が今の時代に吉田松陰を評価している。彼のほかの著作で、松陰を現代的に評価しているものはないからこれは加藤周一の初めての吉田松陰論である。かつて加藤は「日本文学史序説」の中で松陰をこのように言及していた。「吉田松陰という現象は、まさに詩人の政治家であった。」「吉田松陰の思想には独創性がなく、計画には現実性がなかった。しかし「狂愚誠に愛すべし」といった青年詩人は、体制が割り当てた役割を超えて、歴史に直接に参加するという感覚を、いわばその一身に肉体化していた。その感覚こそは、1860年代に若い下級武士層を意思の社会変化に向かって動員した力である。」私はそのことには同意する。厳密に作られた理論はなかったが、あの時代にホッブスやモンステキュー、ルソーがいたならもっと別の展開があったかもしれないが、日本は見事に国際化の波の中で「日本の独立」だけは確保する。それを可能にしたのは理論よりも「詩」であっただろう。今回の講演の中で、加藤は「詩人の特性」については多くを言及せず、現代の問題と関連させてこのように松陰を評価する。「松陰の立場は下層武士の思想で、幕府を倒してでも能率的な政府を作り、外からの脅威に対抗しようということだったと思います。」「これは水戸学派の観念論的なイデオロギーからは遠い立場です。また幕府の要人の暗殺や外国人の襲撃を内容とするテロリズムからも遠い考え方です。彼らと比べて松陰ははるかに現実的でした。」どうやら歴史相対的に現実性を持っている、と意見を修正したみたいだ。現在グローバリゼーションという言葉で「開国」を迫られている日本に今こそ松陰の精神を、と加藤はいうわけです。まずは「主権の独立」を図れ、松陰の時代でいうと「譲夷」ですね。そしてそのためにはまず個人の独立が必要だという。松陰の時代でいうと「尊王」です。あの時代にあつては「尊王」は革新的な個人の精神の表現だったのです。松陰の思想はそれだけ現実を直視ししていたと加藤は評価している。加藤は意見を変えたわけではなかった。過去の「松陰」という遺産を現代に活かす道を囁いたのである。しかしそれはあくまで「囁いた」に過ぎない。本格的に論ずる人が出てきてほしい、という願望があるのではないか。心ある人はもう一度そういう目で、松陰の著作を読むべきだろう。
2006年02月01日
コメント(0)
-

読む愉しさ『オーデュボンの祈り』
『オーデュボンの祈り』新潮文庫 伊坂幸太郎読み始めは、いつも『逃げている』ばかりの主人公が描写されている。そうか、事件の真相を明らかにする過程で主人公が成長するという物語になるのだな、とある程度この物語を予見をした。ところが、そんなありきたりの物語になってはいない。『弱気なギャングが地球をまわす』という作品のあとがきに著者は次ぎのようなことを書いたらしい。「現実世界とつながっているように見えながらも、実はつながっておらず、また、寓話のように感じられるかもしれませんが、寓意はこめられていない。そういうお話になりました。」(本書解説より)それはそっくりこのデビュー作にも当てはまる。この人を食ったような構造がとても快く感じられる。『読む愉しさ』を教えてくれる小説家である。読んでいる最中、謎がくるくると廻っているが、読後は実はそのときのことをよく覚えていない。あとにはいくつかの『感情』だけが残るのである。まるで良質の音楽会に行って来たときのように。初めて、この人の作品を読んだが、次も読んでみようかという気にさせる作家である。
2006年01月28日
コメント(6)
-

「模倣犯」読書日記(5)
「模倣犯」(5)新潮文庫 宮部みゆき古河鞠子の遺族である有馬義男はほかの殺人事件で自分を責めている塚田真一少年にいう。「あんたら若い人は、よくそういうものの言い方をするね?」「自分には何々する資格はないとかさ。自分は何々だと思ってコレコレのことをしてきたけど、本当はそれは偽りで、自分の心の底にはコレコレしたいシカジカの動機が隠されていたのだから、あれは間違いだったんだ、とかよ」「私なんざ、不思議でしょうがないよ。」「悪あがきでいい。そんなことははなからわかっているんだもの。私のやることなんざ、全部悪あがきだもんな。だって鞠子は帰ってこないし、真知子は正気に戻らん。そうだろう?」「そんでも私は、悪あがきをしたいんだよ。何かをしたいんだ。」「今となっては私には、大切なのは結果じゃないんだ。結果は理不尽で、ぜんぜん納得がいかないよ。それは充分わかっているんだ。だけど、そこまでいくあいだのことが大切なんだ。もう受身でいるのはまっぴらなんだよ」有馬の塚田少年に向けてのこの十数ページにわたる言葉(引用は物凄くはしょりました)は、この長い物語の(私にとっての)クライマックスであった。塚田少年が前を向くきっかけになった言葉の数々である。犯人たちの心の内は、とりあえず私には重要ではない。運命が人を襲ったときに、人はどのように立ち直るのか、そのひとつの物語を示してくれたということで、この「模倣犯」は意義があった。それにしても宮部の小説において主人公は多くの場合少年とおじさんである。この小説も結局そうなった。ピースの心の内面は一応描いてはいる。しかし、全面的に描いてはいない。この小説の中で、その心の内面へ探索していくかぎはいくつも残されているので、読者はもう一度読み返しながらそこに旅していけばいいのだろう。2006.01.20読了。結局最後はあっという間に読んでしまった。おそらく全部読み終えるのに、合計30時間以上は使った(浸かった)と思う。まあ、それでもさらさらっと読めてしまうのは宮部みゆきの才能だろう。「晴子情歌」の高村薫ならこうはいかない。読み終える前後、ライブドア事件が進行していた。ひとつの意見は「模倣犯」読書日記(2)で述べた。これは劇場型事件ではないが、事件はまるで劇場のような展開を示している。もし誰かがピースのように「これは僕のオリジナルだ」といいながら脚本を書いているのだとしたら、その場合犯人「役」はホリエモンではないだろう。真犯人Xは「真犯人Xは別にいる」とアドバルーンを揚げるだろうか。真犯人Xは決してそのような墓穴を掘るような真似はしないだろう。
2006年01月25日
コメント(2)
-

「模倣犯」読書日記(4)
「模倣犯」(4)新潮文庫 宮部みゆき4巻の主な登場人物は高井由美子と前畑滋子である。高井由美子は加害者の遺族がどのような状況になるかを体現し、前畑滋子は「事件の真相を描いてもどこまで描ききれるのだろう‥」という宮部自身の迷いを反映した内容になっている。この作品は力作であるが冗漫すぎる、という批判は本が上梓された直後からアマゾンコムなどで飛び交っていた。最初の構想から二倍もの量になったというのは、宮部の迷いが反映してのことだろう。しかし最後まで読むとその迷いはふっ切ったみたいだ。そして単なる連続殺人事件の真相に主題をおかず、事件をめぐる人物群像に主題をおいていることが読み終えてくっきりわかる構想になっている。時々勘違いをしている人がいるが、宮部みゆきは決して「社会派」の作家ではない。「火車」も決してそういう読まれ方は望んでいない。あまりにもいろんな事が見えてしまうから、そしてそれを言葉で表現できる類まれな才能を持っているから、この本を読むと連続殺人事件の本質を知ったような気になるが、彼女が描きたかったのはただ一点「人の心」のみなのである。p196の前畑の若者論、p208以降の由美子の遺族の気持ち、あるいは塚田真一の「自分が殺してしまった」という自責の気持ち、まるであわせ鏡のように、何度も何度も違う形で立ち現れて読者の私たちに考えるきっかけを与えようとしている。人の心の中はまるでひとつの宇宙である。宮部みゆきは常にそう云ってきた。2006.01.19読了。そして(5)をすぐ読み始める。三日前に観た「疾走」がひどかっただけに、殺人にいたる、残される遺族の気持ちにいろいろ考えてしまう。
2006年01月24日
コメント(0)
-

「模倣犯」読書日記(3)
「模倣犯」(3)新潮文庫 宮部みゆき三巻目はいわば前半のクライマックスである。ヒロミとピースと高井和明三人の対決が行われる。さて、この作品、そのあまりにものリアルさにいつの間にか本を読んでいる我々さえも、この小説の中に取り込まれてしまう。例えばーーやがては古川鞠子の悲劇を二度と起こさないよう、いろんな意見がブログで書かれた。無数の記事と無数のTBと無数のコメントがネットの上を飛び交った。「KUMA0504さんコメントありがとうございました。私も一応独身女性(^^;)ですから、駅から家に着くまで10分間がとても怖くなりました。」「栃木さん気をつけてくださいね。日本の警察は優秀ですから、きっと容疑者は既に相当絞られているはずです」云々。そして一連のそういう反応をヒロミとピースは嗤っていた。というような文章がこの作品のどこかに挟まっていても決して不思議ではないだろう。長い物語にする必然性は例えばこういうところにもあるのかもしれない。遺族を悼むコメントをしながら、犯人像をコメントしながら、巨大なネット上で井戸端会議をすることで、かえって犯人たちを喜ばしているという矛盾。劇場型犯罪に対して、私たちはまだ有効な対処の仕方を知らないのではないだろうか。この作品の重要人物なのに、なかなか叙述の語り手にならない人物がいる。ヒロミとピースの幼友達の高井和明である。和明がヒロミを説得しようとする言葉の一つ一つにこの作品の、作者の願いがこめられている。最後の最後で和明は叙述の語り手となる。和明の真意がヒロミに届きそうになった直後、運命は訪れる。2006.01.12
2006年01月23日
コメント(0)
-

「模倣犯」読書日記(2)
「模倣犯」(2)新潮文庫 宮部みゆき栃木の幼女誘拐殺人事件の犯人はまだ捕まらない。被害者の家族の心痛は想像できないが、小説という形をとってそれを追体験することが少しは出来るかもしれない。あるいは県警の努力、マスコミの犯罪分析……それぞれの立場に立てば全く違った景色が見えてくる。宮部みゆきの最初の長編小説は、「犬」の立場から見た犯罪小説だった。彼女の小説の魅力はまるきり登場人物の主観にたって物語を紡ぐことが出来るところである。これは簡単なようで難しい。宮部は特別な経験をして作家になったわけではない。その彼女が、苦労を重ねて老成した豆腐屋の主人になったり、熟練の刑事になったり、エンコー女子高生になりきるのである。宮部は生来のカメラアイとも言える類まれな記憶力を活かして、誰もがすぐに忘れるそのときの景色や風の色までも見事に文章の中に写し取るのである。だからおそらく普段から人を観察していて、おじさんの目線がどこを見ていて、そのときどういう景色だったか、心の箪笥の中にきちんと整理されているのだろう。まだ二巻目までしか読んでいないが、彼女はその才能を活かして今度は誰もがいい加減な描写で済ます連続殺人事件の犯人の心の中に入っていこうとしているように見える。まずは栗橋浩美(ヒロミ)側からの描写から入っている。ヒロミはトラウマがあって、病的で、自己中心的で、プータロウである。その後、外から見えるヒロミが一般的に言ってエリートっぽい人物に扱われていたことに少なからず驚く。外見と心の中、同じものを見ていてもいかに見える景色か違うのか、読者は体験する。栃木の犯人はまだ捕まらない。その異常性とは裏腹に、犯人の外見はきちんとしたエリートなのかもしれないし、万が一彼の心の中を覗いてみたら、つい私たちは「哀しい」と思ってしまうような心情さえ見つけてしまうのかもしれない。果たしてそのような感想を持つ私たちとはなんなのだろう。……というようなことは映画を観たときには思わなかった。これがこの小説の力である。2006.01.06読了。01.22追加ライブドアのもと副社長が自殺したのか殺されたのかネット上ではいろんな意見が出ているらしい。そういう方はぜひこの本を読んで頭を冷やしてもらいたい。確かにあれが自殺ではなく、殺しであったなら、日本の経済界を揺るがす大問題になるので騒ぎたい気持ちは分かる。しかし単に新聞やテレビから得られる情報で「憶測」で物事を書いても事態の進展には何の益もない、警察の動きを変える事は出来ない、ということをわれわれは知るべきだし、もちろんわれわれの想像をはるかに超える情報を警察は握っていることも知るべきだろう。「模倣犯」の犯人がこの騒ぎを利用したら簡単にわれわれは操作されちゃうよ。
2006年01月22日
コメント(2)
-

「模倣犯」読書日記(1)
「模倣犯」(1)新潮文庫 宮部みゆき宮部の著書は全部読む、というのが私のポリシーである。というような変なことで威張る小市民の私であるが、彼女はその小市民を描くのが天才的に上手い作家だ。「未曾有の連続誘拐殺人事件を重層的に描いた現代ミステリの金字塔、いよいよ開幕」ということだし、映画にもなったので、ある程度の筋はみんな知っているし、リンクつきのバナーを貼っておくのでそこを見ると大体のその巻のあらすじを書いてると思うので参照してもらいたい。文庫(1)は、事件の被害者側、捜査側のほうの視点で物語が進む。宮部みゆきは次々と代わる視点に少しも描写の上で妥協はしない。被害者の不安とやりきれなさと怒りと悲しみ、振り回される刑事と犯人との知能比べが綿密に描かれていて、読ませる。そして事件がとりあえずの結末を迎える。(まだ一巻目なのに?)ところが私は知っている。これがこの物語のマクラに過ぎないことを。映画「模倣犯」は大失敗作だった。見た時点で原作の筋など全然知らなかったが、あまりにも薄っぺらい主犯(仲居正弘)の演技に、まるで職人のように映画つくりをした監督の姿勢にがっかりした覚えがある。だからポリシーではあるが、一巻目二巻目を読んで読む気がうせたら止めようと思っていた。心配は杞憂だった。そして新たな心配が……。私はこの本を読むために何時間を費やしてしまうのだろう……。2006.01.03読了
2006年01月21日
コメント(4)
-
「海の伽耶琴」(上)あるいは朝鮮に寝返った男
「海の伽耶琴」徳間書店 神坂次郎秀吉の朝鮮出兵時、当初秀吉軍の中にいて、その後朝鮮側についた一群の武将がいた。彼らは鉄砲の技術を持ち、そのためそれまでの戦況を大きく覆すことに成功する。その武将の名前は「沙也可」と伝えられている。この小説はその武将を、紀州雑賀衆の大将鈴木孫市の若大将「小源太」として描いた歴史小説である。なぜ彼は朝鮮軍に「寝返った」のか。また、雑賀衆は戦国時代、一向宗に味方し、信長と戦い、ついに信長は彼らをつぶすことができなかった非常に優秀な技術集団でもある。その後も、秀吉軍と戦っているはずである。なぜ敵側である秀吉軍の中にいたのか。それは教科書では教えない歴史であり、(朝鮮の教科書には「沙也可」の名前は出てきているらしい)その秘密の中に戦争とは何か、ということが描かれているかもしれないと思い、紐解いてみた。信長は敵側を皆殺しにする日本歴史上稀有な独裁者であった。(比叡山焼き討ち、一向一揆・本願寺宗徒の壊滅)それと真っ向から対する雑賀衆もまた命知らずの鉄砲集団で、戦国の世を生きていく。彼らが戦死を恐れないのは当然だとは思うが、それぞれの「戦い」についてあまりにも疑問を抱いていないのは、不思議に思う。まだ後半はこれから読むのではあるが、私の最初の疑問は上巻ではぜんぜん解明できなかった。
2005年09月29日
コメント(2)
-
『対話の回路』(新曜社)小熊 英二 (著)を読んで
村上龍、島田雅彦、網野善彦、谷川健一、赤坂憲雄、上野千鶴子、姜尚中、今沢裕の八氏との対談集である。いろいろ刺激をもらう本なのではあるが、今回は現代の改憲論の中のナショナリズムについて考えるヒントをもらったので、書いてみたい。島田雅彦との対談に先立ち、小熊は『戦後ナショナリズムのスパイラル』と題し、『のナショナリズム』(慶応義塾大学出版会)の中身を要約してみせる。それをさらに要約するとこうなる。戦後のナショナリズムを概観するとこのように単純化できるという。対米従属によりアメリカに対する不満が蓄積する。(石原慎太郎や「つくる会」)(しかし面と向かってアメリカに文句は言えない)その代償行為として自衛隊増強や改憲、あるいは歴史問題が噴出する。その結果として(改憲の地盤が出来ることでアメリカの要求は強まり、歴史問題でアジアの反発は強まるので)ますます対米従属が強まる。これにはなるほどと思った。私は今まで改憲論者の『気持ち』が理解できなかったが、もしかしたら改憲論者も自分の気持ちが理解できず、ずっと「悪循環」のなかにはまり込んでいるのかもしれないと思ったからである。もちろん単純化による間違いは多々ある。もっともよく批判されるのは「代償行為」等、ナショナリズムをあまりにも「心情」として理解しすぎているということだ。それを踏まえたうえで読むなら、私は示唆に富む分析だと思う。これに9.11後を考えて小熊はこう問題提起する。(この対談はアフガン侵略直後)今度自衛隊に犠牲が出たときナショナリズムはどのように反応するだろうか。最悪の場合、日本でテロが起きたときナショナリズムはどのように反応するだろう。最悪の場合、世界から孤立して自滅するのではないか。小熊の解決策はこうである。『本当は冷戦が終わった今となっては、対米従属さえしていれば国際関係が乗りきれると言う路線そのものが限界に来ているはずなのです。アジア諸国はもうアメリカの言いなりに動いてはいない。アジア諸国から反発があるたびに対米関係に依存を深めるというは、日本ナショナリズムの悪循環をもたらすだけです。この状況を打開するためには、アジア諸国との間で戦後補償問題と歴史問題を解決して、日本が対米従属から開放されてもアジアのなかで信頼を醸成していくしかない』私はほぼこの説に賛成である。今やっと議論されてきた『東北アジア共同体』『アジア共同体』構想はその延長線上にあるはずだ。ただ、この対談では小熊の先に書いた大きな見通しは見事なのだが、具体的な話になると、「皇室が憲法尊守を宣言してしまえばいいんだ。」等、(素人の私でさえ分かる)政治力学が全然分かっていない話で最後まで通してしまった。自衛隊に犠牲が出たときやテロが起きた時どうなるかも展開されずじまいだった。結局思想史の学者の話なのである。民主党の前原代表がどういう理論でもって九条改憲を言っているのか、しっかり検討しなくてはならない。民主党の改憲案は国連主導の自衛隊活用なのであるが、彼が今の国際力学のなかでそれはつまりアメリカ追従と同じことだと分かった上で言っているのか、それとも反米ナショナリズムを目指して言っているのかで対応の仕方が変わるからである。
2005年09月19日
コメント(4)
-
指紋発見のルーツに大森貝塚
「指紋を発見した男」主婦の友社 コリン・ビーヴァン 茂木健訳スコットランド人医者ヘンリーフォールズは、宣教師として日本に滞在中、友人モースを手伝い大森貝塚の発掘に携わっているときに、土器に付いている指のあとの筋から『指紋が犯罪捜査に使えないか』と発想する。指紋が犯罪捜査に与えた役割はとてつもなく大きいものがあったが、それが証拠として採用されるまでにはいろいろなドラマがあった。また、指紋発見者としてフォールズが評価されるにも、紆余曲折があったのである。科学的な犯罪捜査が始まるまでの警察の歴史が読み物風になっており、なかなか面白い。特にヴィクトル・ユゴーの「ああ無情」のモデルになったというヴィドックを扱った『悪党を捕まえる悪党』の一章など、波乱万丈。また、マーク・トゥエンの「ミシシッピの生活」の第三十一章に影響を与えたかもしれないというくだりを北村薫辺りが読んだなら、早速推理小説のアンソロジーに入れたりするかもしれない。この本には『本格』の香りがする。ただ、指紋発見のエピソードに日本の大森貝塚が入ってくることに、(日本人としては嬉しいのだが)私は危惧を覚える。縄文土器をよく見た人ならすぐ気が付くのであるが、たとえ土器に指のあとがあったとしても、目の荒い土器には決して指紋のしの字も付かないのである。この著者は日本に来ることなくこの本を書いているが、変な伝説が一人歩きしないことを祈りたい。
2005年08月31日
コメント(0)
-
終わりが見えない「ドリームバスター2」宮部みゆき
前の本の続き。異次元世界「テーラ」から時空の穴を抜けて逃げ出した凶悪犯人を追って、ドリームバスターのシェンとマエストロは地球の日本という国の夢の中に降り立つ。そういう世界観だけで出来上がった物語かと思っていたら、前作のラストで少し変化があった。さあ、それでは「2」ではそこが展開されたり、解決するのかな、と思っていたら……これはないんではないか(怒)これはまだ物語が始まってもいないということなのか。宮部みゆきの作品は最近は特に長く長くなっているが、この作品の終わりが見えない。まさか田中某みたいに全10巻ぐらいを考えているのではないでしょうね。それなら、一年に二作ぐらいのハイスピードで書いてほしい。これだと一体終わるのに何年かかることやら。「ブレイブストーリー」はアニメ映画化される。この作品、もしアニメ化されるのなら、絶対テレビの連載アニメのほうがよい。なんだかこの作品はアニメ化を狙っているような気がしてならない。
2005年08月21日
コメント(2)
全54件 (54件中 1-50件目)
-
-

- 今日読んだマンガは??
- 【マンガ】DQ3 HD‐2Dリメイク記念 ダ…
- (2024-11-12 18:00:09)
-
-
-
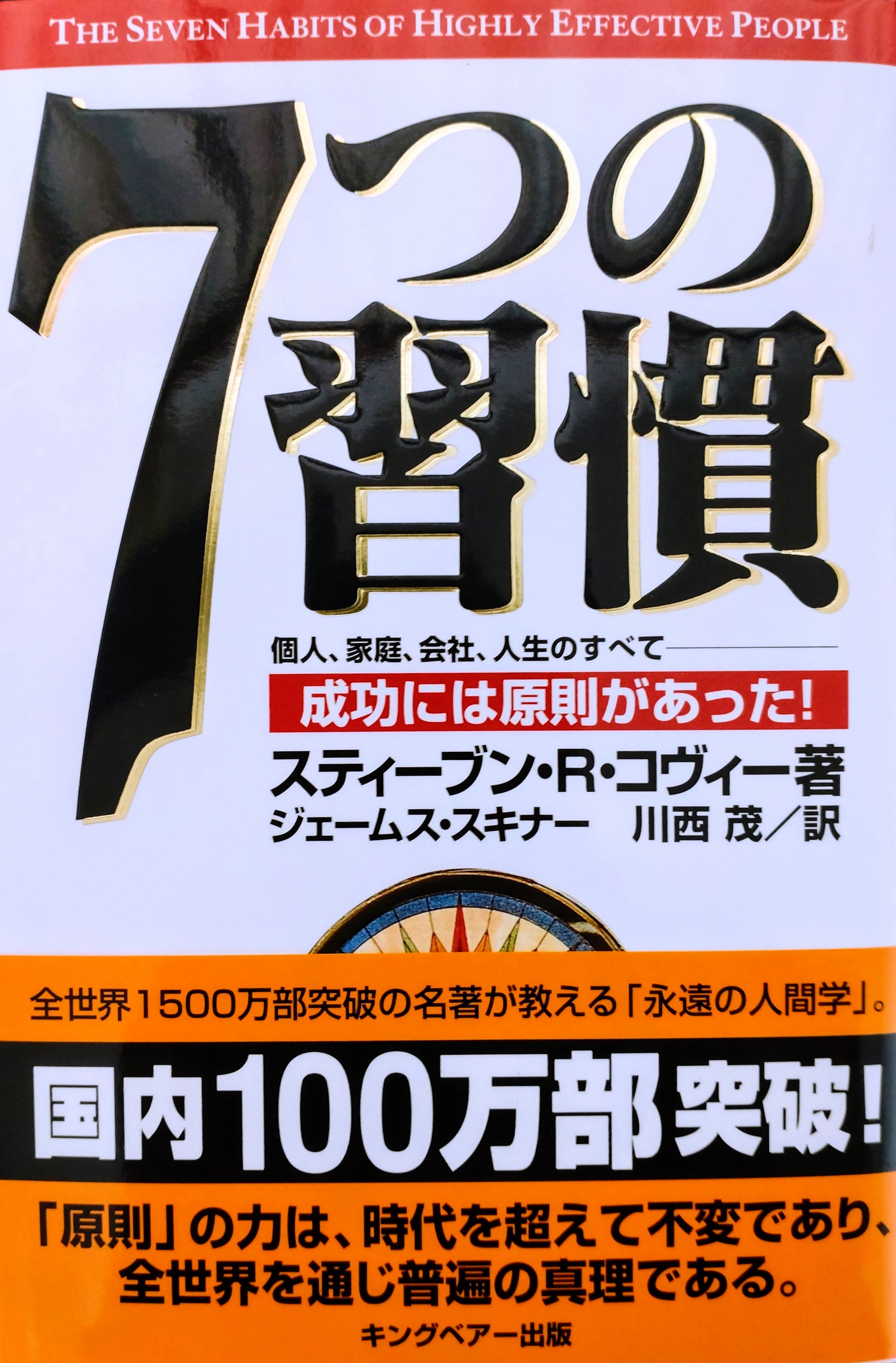
- 今日どんな本をよみましたか?
- 第一の習慣「主体性を発揮する」(「…
- (2024-11-13 00:00:25)
-
-
-

- 最近、読んだ本を教えて!
- 死はすぐそばに アンソニー・ホロヴ…
- (2024-11-11 19:50:46)
-








