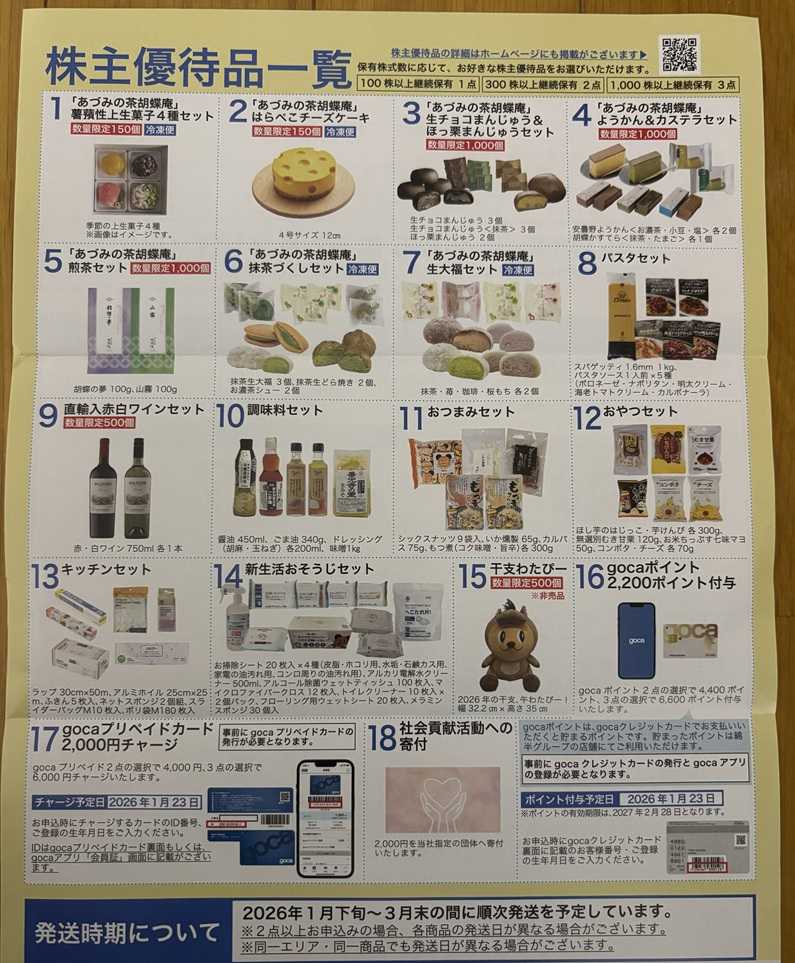2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年02月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
テレビで見た日本映画
1月にwowowなどで見た日本映画を、忘れないうちにメモしておかなければ。よかったと思う順に書きます。『カミユなんて知らない』 2006/柳町光男監督最近見た日本映画の中で、抜群だった。『メゾン・ド・ヒミコ』 2005/犬童一心監督田中民(←字が出ません)さんの存在感にびっくり。『同じ月を見ている』 2005/深作健太『ニワトリはハダシだ』2003/森崎東
2007.02.24
コメント(6)
-
ブログについての覚書(4)
FOR BEGINNERS 101 「ハンナ・アーレント」 文●杉浦敏子 イラスト●ふなびきかずこ (現代書館)2006/12異質な他者との共生を唱え、全体主義の苛烈な批判者であり、かつ、大衆社会を批判し、多様性を徹底的に擁護する。生誕100年、混迷の現代を撃つ。のキャッチフレーズ。これはとてもわかりやすい、ハンナ・アーレント入門書だと思う。品性と知性あるイラストがまたよきナビゲーターになっていて、親しみやすい。私のような初心者にはありがたかった。ここからもネットの世界に対応していると思われる点を、一部分だが抜書き。○インターネットの普及は個人の匿名性を前提としており、誰も語っていることに責任を問われない。そこには公的空間がない。政治には匿名性ではなく、各行為主体の個別性の承認が必要とされる。何(What)ではなく誰(Who)が問われるのだ。政治的に活動するということは可視的になること、自らの事績が他者によって認められ、判断されることを意味する。一つの意見や選好が客観的なものに変わるのは、複数の人々の対話と行為からなる公的空間にそれが現れるからである。 p.163○次に「活動」の不可予言性はもともと二重の意味をもつ。第1 にそれは「人間精神の暗闇」から生まれている。人間が自分自身を頼ることができない、あるいは完全に信ずることができないということは、人間が自由に対して払う代償といえる。第2 に人間は行為の結果について予め知ることができず、未来に頼ることができないというのは、多数性に対して払う代償であり、万人の存在によって各人にそのリアリティーが保証されている世界の中で、他人と共生する喜びに対して払う代償である。そして約束する能力の機能は、人間事象の暗闇を克服する。個人の衝動と意図が予測不可能であろうとも、人々の間にある世界で形成される合意は、「人間精神の暗闇」を取り払い、より永続的で信頼しうるもの、つまり権利を承認し、人々を守る法律や制度を樹立することを可能にする。 p.111○さらに重要なことは「活動」の持つ公的性格である。それは具体的には「公開性」と「世界性」を意味する。私的体験はそれが他人に見られ、かつ聞かれ得る形に変形されない限り公的なものとはなりえない、というのが「公開性」の意味である。また「世界性」については「世界において共に住むということは、本質的には世界がそれを共通に保持している人々の間に存在するということである」(『人間の条件』)と述べ、世界は人々を結びつける共通の場であり、公的事柄への関わりを通じて共に活動する場なのである。 p.112このあたりを読むとき、寺山修司のいう「……この場合の運動というのはあくまで政治--ポリティーク--の領域のそれであって、私は芸術運動というものは信じない。」の言葉が思い出されるのだった。アーレント言うところの「労働」「仕事」「活動」については、次の機会に書いておきたいと思う。西洋哲学というものを理解できない頭の持ち主の私であったが、アーレントの著作だけには胸を熱くさせられた。理解できているとは決して言えないにもかかわらず、アーレントを知らないまま死ななくてよかった、と、思うのである。
2007.02.21
コメント(6)
-
ブログについての覚書(3)
「ウェブ進化論」--本当の大変化はこれから始まる--梅田望夫 ちくま新書 2006/2から、浅学にして乱暴な抜書き。○チープ革命 ○知の世界の秩序再編 グーグル世界政府 プロフェッショナルとは何か プロフェッショナルを認定する権威とは誰なのか○Web2.0 ウェブサービスAPI公開○インターネットの可能性の本質 *不特定多数無限大の人々 *放っておけば消えて失われていってしまうはずの価値、 つまりわずかな金やわずかな時間の断片といった無に近いものを、 無限大に限りなく近い対象から、ゼロに限りなく近いコストで 集積できたら何が起こるか。○群衆の叡智 マス・コラボレーション バーチャル経済圏○ネット世界とリアル世界の価値観の融合はあるのか○オープンソース 過激な少数意見から時の常識に○ネット世界の三大法則 第一、神の視点からの世界理解(全体を俯瞰する視点) 第二、ネット上に作った人間の分身が金を稼いでくれる新しい経済圏 第三、(≒無限大)×(≒ゼロ)=Something あるいは消えて失われていったはずの価値の集積○グーグルアース 全地球上で何が起きているかを全部閲覧できるシステムへと○言語間の壁を取り払う 自動翻訳技術の開発○知の世界の秩序を再編成 ウェブ上での民主主義 「世界中に散在し日に日に増殖する無数のウェブサイトが ある知についてどう評価するか」 ページランク・アルゴリズム リンクという民意、インターネットの意志○ロングテール派 「80:20」の法則 あらゆる物事において重要なのは少数であり、大多数は取るに足らぬもの 取るに足らぬ80%→ロングテール○総表現社会の1000万人 暇人で能動的な目的意識を持った人たち 「連帯の構築」 社会合意形成の連帯 フツーなふーん意識の再確認 総表現社会=チープ革命×検索エンジン×自動秩序形成システム プロフェッショナルをプロフェッショナルであると認定する権威が 既存メディアからグーグルをはじめとするテクノロジーに移行する○信用創造装置、舞台装置としてのブログ 知的成長の場 ポートフォリオ ブログという舞台の上で知的成長の過程を公開することで その人を取り巻く個と個の信頼関係が生まれる○知的生産の道具 ソーシャルブックマーク、はてなブックマーク 集合知の成果:ウィキペディア○「コストゼロ」・「そこそこの信頼性」・「完璧」ではない○ソーシャル・ネットワーキング 人間関係マップ→人のランキング→人間検索エンジン○予測市場 「不特定多数の集約」という新しい芽○個人としての国際競争力*日用品化*層の薄い分野の発見*異質なものと異質なものの組み合わせ*不特定多数無限大への信頼胸騒ぎを覚えるほどの怖さもある、グーグル革命といわれる一端を垣間見たようだ。私などには予測不能な変化の気配に、本書からはワクワクする新しさと同時に、人間社会の本質は変わらないものがあるのではないか、とも、思った。だがことはすでに、知らない間に、始まっているのだ。踊っている(あるいは20%に踊らされている?)80%の私としては、少し居住まいを正したほうがいいのかも知れない。
2007.02.19
コメント(6)
-
ブログについての覚書(2)
「ブログ進化論」--なぜ人は日記を晒すのか--岡部敬史 講談社+α新書 2006/4より、好き勝手に抜書き。○生活に割り込むことなく日常を知る。覗き見 生活に割り込まれない程度に、日常を晒す。○簡便、安易○玉石混交 便所の落書きの楽しさ面白さ○情報発信としてのツール○ビジネス戦略としてのツール○コミュニケーションと広がり○ブログという目的 自分の立ち居地、自己主張と情報のバランス、自己構築○独自のテキスト文化 ネット用語○炎上 反対の意見を知る。議論の応酬。○フツーの人が発信すること 情報価値の変化、マスの無効化○自分に近い意見だけを追いかけることもできる。 細分化○メディアを監視する力と独自発信の力○自己PRメディア、コンテンツでなく才能○ポッドキャスティングとソーシャルブックマーク 音声ブログ、動画ブログ○アフィリエイトと賞金制度*リアクションのダイレクト感、手ごたえ*理屈はない*人間関係の継続維持*不特定多数の人との出会い*発信せずにはいられない人間の、根源的な欲求を満たす*嬉しさと便利さの積み重ねこれらは、ネットに少しでもかかわっている人なら、誰もが認識していることだと思う。
2007.02.18
コメント(4)
-
ブログについての覚書(1)
「戦後詩」--ユリシーズの不在--寺山修司(ちくま文庫)1993/5 (1965年11/25 紀伊国屋書店より刊行)同人誌批判として書かれた章から、自分勝手に引用。○相互慰藉 *感傷の福祉団体 *みすぼらしい人生を報告しあう *報告を芸術であるかのように誤解することによって、 辛うじて生き甲斐と言う免罪符を受け取る。 彼らには「救済」へのはげしい願望もなければ、 「変革」のための身をよじるような苦悩もない。 *幸福号 *経済的な事情による合宿 *つまらない人生は存在しなくても、つまらない詩は存在する。○無人島からの音信○事柄の連帯はできるが、感情や欲望の連帯はできない。○日常報告記録 メモリアリズム○備忘録○アンデパンダン展 自主独立・無審査・無賞○黄昏のヒューマニズムよりも真昼のエゴイズムを。 細胞の狂宴(オージイ) エゴイズムもまた人間復権の動機となる。 自白・告白○キャッチボールと性の解放。○多くの場合同人雑誌は個の確認の場としてのみ、利用され続けてきた。それは「孤独」の土地へ飛ぶためのパスポートであり、自分がひとりであることを悟るための予備群衆なのであった。だからルームメートは誰でもよかったのかも知れない。インターネットのなかった時代に書かれた、詩歌の同人誌に対する批判だが、現在の総表現者時代、ブログの世界に通じている事柄だと思われる点を、抜書きしてみた。実際の本の内容からは外れているが、ブログの内容を考えるとき、その差異をも含めて私の拠り所になってくれるように思う。
2007.02.18
コメント(0)
-
おーい、ニッポン
4日日曜日は、NHK BS-2 で「おーい、ニッポン~私の・好きな・徳島県」6時間放送を全部観てしまった。なんといっても、自分の生まれ育った土地は懐かしい。特に吉野川となると、もうこれは理屈抜きで吸い込まれる。私にとっては精神風土といった趣だ。ゲストの坂東さんは、徳島商業の投手だった頃から馴染み深い。「なっちゃんの写真館」の星野さんは、新潟生まれで、「花遍路」の早坂さんは愛媛生まれだ。三好和義さんは吉野川の源流を遡る写真集や、四国八十八箇所の写真集も出されている。中高生の頃から有名だった。非常に盛りだくさんで、アナウンサーやゲストも多彩だったが、地元に生活する人々のたたずまいや言葉や仕草のほうが、断然勝っていたと思う。三番叟が復活していることに驚いたのと、今年100歳になるお鯉さんの「よしこの」は圧巻だった。早坂さんの辛口な意見も興味深く聞いた。故郷喪失感とか故郷への屈折した思いとか、私たちの下の世代にはあまり存在しないのかもしれない。まっすぐでうらやましい。故郷・故里・古里・フルサトふるさとも時代の変遷を受けて、読み直され作り変えられていくものらしかった。
2007.02.06
コメント(8)
-
情熱大陸
先週の日曜日放送の『情熱大陸』でフィリピンの小さな村で働く助産師さん、富田江里子(39才)さんが取り上げられていました。この番組のことは、友人のお嬢さんである看護学生さんから教えてもらいました。調べたらブログもお持ちなので「フィリピン、貧しい母子のためのクリニック」または富田江里子さんで、ぜひ検索してみてください。自然にそった待つお産を広められていて、とりあげた赤ちゃんは159人にのぼるそうです。ここで撮影されたお産のシーンが、まったくあっけらかんと撮影されていて、姉御肌でさばさばしたお人柄が魅力的でした。私の目がもっとも引き付けられたのは、胎盤を手に持って、「これがへその緒、この袋の中に赤ちゃんが入っているのよ」とそれはそれは自然体で説明されていた、その手つきのさわやかさでした。初めて胞衣(えな)というものを見て、感動しました。日本では後産などはケガレやタブーのイメージがあったのに、光の下でどうどうとテレビカメラに撮影されて放映されたことに、時代の変化を感じました。それはまた大学病院で出産した私の、学生たちの教材となっていたのではないかという、暗いわだかまりを吹き飛ばしてくれる、始原の出産の姿でもありました。遠いフィリピンで二人のお嬢さんを育てながら、ご夫婦で活動しているこのような方もいらっしゃることを、教えてくれた看護学生のSちゃん、ありがとう!
2007.02.04
コメント(4)
-
工事その他
☆ 1月11日から始まっていた、築18年になるアパートの外装工事が、2月1日で終了した。ほぼ毎日職人さんたちの出入りがあり、細胞は活性化したけれど、終わってみると気疲れも出て、脱力状態。でもアパートは屋根から外壁、外階段の防水まで、ピカピカに生まれ変わった。これで10年は大丈夫かな?☆私の数少ない年賀状のやり取りの中でも、今年は胸を撃たれることが多かった。** 十歳年下の友人が、乳がんの手術をしたこと。** 同級生の友人も、早期発見で乳がんを退治したこと。** 30代で子宮がんの手術をした友人からは、60歳を無事に迎えられることが、信じられないよ! と。** 今年定年退職する友人は、某新興宗教へ帰依したことを。** 孫が3人になったと書いてくれたK君は、今でも白髪を染めているかな?** 中学時代の恩師からは、昨年12月、長女を亡くされたことを。すぐに返す言葉が見つからない分、逢って話したい気持ちがふつふつとするのだが、まだ何ひとつ出来ていない。また、これらと一緒に、今は亡き友人や恩師の年賀状も届いている。そんな気配が増えていく。☆私の禁煙生活も一ヶ月を経過した。煙草を吸わなくなったから体調が良くなった、ということも格別感じない。予想通りに便秘がちになってきたので、そちらの対策を考えているところ。けれどもなんとかともかく、禁煙続行中です。息子に「禁煙してるから、あなたも止めなさいよ。昔、お母さんが止めたら俺も止めるって言ったでしょ。」と誘惑したのですが、速攻「無理だよ」と、却下されました。この無理だよというのは、私(母)が禁煙を完遂するのが無理だよ、ということなのです。彼自身は、仕事が忙しいので喫煙数は減っているそうです。癪なので、今のところ、こらえております。
2007.02.03
コメント(4)
全8件 (8件中 1-8件目)
1