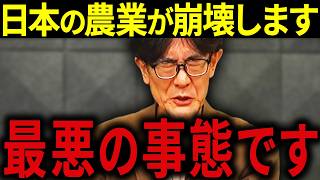2013年02月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
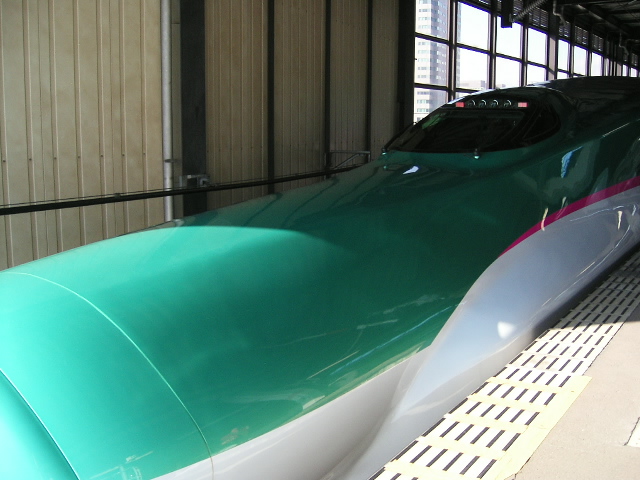
相模原から札幌までJRで行く~しかも函館で途中下車して市内観光も
年始は、実家のある相模原市の相模大野駅から札幌まで汽車を乗り継ぐと云う、短気な人間が発狂しそうな行程を愉しんだ。しかも、函館で下車して市内観光もしたのである。よく一日で札幌へ着けたなと今でも不思議に思う。それにしても、東北新幹線の鼻の長さが撮影者泣かせだった。新青森で在来線に乗り換えたのがお昼どき。駅で菓子パンと珈琲を買い込んでおいた。銀世界の中を進む車内で食べる菓子パンの味は格別だ。これぞ「ゲミュートリッヒ」と云うべきか。函館市内は銀世界。既に夕方になりかけていたので、急いであちこち歩き回った。函館市公会堂は、館内も見学する。ハリストス正教会も見た。銀世界なのに建物も白い。世界はモノトーンでしか無い。の建物を見て、広島の旧産業奨励館を連想した。拙者はまだ広島に行ったことが無い。北海道で広島と云えば、北広島市のことを指す。札幌行の汽車に乗ったのは夕方。イカに味ご飯が詰め込まれた弁当「いかめし」を買った。こんなに美味しいものだとは思わなかった。そして札幌に住む彼女にメールを打つ。今年もよろしく・・・。
2013.02.24
-
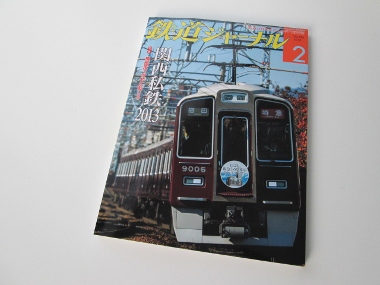
阪急電車は「ことごとく梅田への道?」~鉄道ジャーナル2月号より
鉄道ジャーナル2月号の表紙を飾っていたのは、マルーンの塗装が美しい阪急電車。「関西私鉄2013~積極策で攻めに転じる」と云う題を見て、迷わず買った。拙者は現在札幌市在住。阪急電車に揺られて学校へ通っていたのは随分過去の話だが、映画「阪急電車」のヒット、阪急百貨店うめだ本店のリニュアルオープンと、阪急にまつわるニュースは遠く北海道の地でも聞こえてくる。耳を澄ましているのは拙者だけかもしれないが・・・。大阪百貨店戦争は阪急うめだ本店の一人勝ち? 建て替え前後で大きく変わる鉄道ジャーナル2月号では、昨年11にリニュアルオープンを果たした阪急うめだ本店にまつわるエピソードに、かなりの誌面を割いていた。小林一三先生が日本で初めて電車駅ターミナルに百貨店を建設した話に始まり、増築に次ぐ増築、そして全面建て替えに至った経緯・・・懐かしい写真も楽しめたが、阪急うめだ本店の強みとは何か~鉄道雑誌を超えて流通界にも踏み込んだ内容に息を呑んだ。えらい気合が入った誌面である。聴こえてくるニュースを整理すると、とにかく阪急うめだ本店が圧倒的な勢いであり、JR三越伊勢丹は惨敗を喫したということだ。拙者なりの私見はと云うと、確かに大阪の百貨店戦争は熾烈だが、おかげで大阪への一極集中が加速しているのではないか、と云うこと。その見本が阪急百貨店である。神戸阪急を閉店しただけでなく、長らく京都側ターミナルであった河原町阪急まで閉店してしまった。経営資源をうめだへ集中させているのがみえみえである。百貨店を閉めることは、もはや阪急にとってターミナルとしての役割を終えたことを意味する。阪急京都線のダイヤに関する記事を読んで、河原町駅が「梅田行電車の出発駅」だけの存在になってしまったことをより強く感じた。「梅田への道」~えらく的を得たコトバかつて阪急京都線と云えば、2扉クロスシートの特急がノンストップで京阪間を快走していた。ところが、新生JR西日本が時速130キロの新快速をデビューさせたことで、都市間連絡列車としての競争から脱落、かつての京都線のクィーン的存在だった6300系電車は、嵐山線で寂しく余生を送っている。嵐山線で余生を送るかつての京都線特急車~車体はピカピカだ阪急に残された選択肢は、沿線住民を確実に拾って行くことしか無かった。練りに練ったであろうダイヤ改定の積み重ねの結果が、「沿線住民を確実に梅田へ運ぶ」と云う「梅田への道」の完成である。それは、阪急百貨店うめだ本店への集中と表裏を成すところが味わい深い。誌面上の「梅田への道」と云う指摘は、まさにドンピシャと云えよう。関西の鉄道があまりにも便利で快適であるが故に、大阪への一極集中を助ける結果になったのではないだろうか。厳しさを増す関西経済、JR西日本との競合~阪急電車を取り巻く環境は相変わらず厳しい。しかしながら、誌面から強く読み取れたのは、私鉄のトップブランドとして君臨してきた色艶は、未だに色あせていないことだ。ここでしか見られない、独特の上品さ、格好良さは、これからもしっかりと継承して行って欲しいと思う。最後に、松尾大社に参拝し、嵐山まで行った時の寫眞などを御覧くださいませ。
2013.02.11
全2件 (2件中 1-2件目)
1