2013年09月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

本と共に~『いないいないばあ』
いないいないばあ [ 松谷みよ子 ]「絵本選び」でこの本を目にしないことはまずないでしょう。それほどの定番中の定番、ですが。内容は、ネコ、クマ、ネズミ、キツネ、最後にのんちゃんが、それぞれ「いないいない」「ばぁ」をする、というもの。ページをめくらせるタイミングと絵が秀逸な作品です。だいたい読む時は、ネコ(普通)、クマ(低め)、ネズミ(高め)、キツネ(しゃがれ声)という感じで声色を使って読んで、最後、のんちゃんの後に、本人にやってもらうようにしています。本人も面白そうです。やはり、多くの人が薦める絵本だけあるなぁ、という作品です。
September 14, 2013
コメント(0)
-
in『魔法の美術館』@明石市立文化博物館
メディアアート、というと小難しく聞こえますが、私自身は「触れたり、作品に関わったり、体験したりして楽しむことが出来る、ちょっとデジタルな作品」のことだと理解しています。さて、明石市立文化博物館では初のメディアアートの展覧会ということで、子供が楽しめる展示だと良いな、と期待しながら行ってきました。----------最初の作品は、アトリエオモヤによる「光であそぶ」。これが秀逸で、白い布にビー玉をたくさん載せて、上から光を当てている、という作品なのですが、下の空間が、ちょうど子供の背が届く高さで、ジャンプしてこのビー玉を散らせるわけですね。すると、音と共にビー玉が広がって、カラフルな影が散らばります。シンプルなだけに、楽しくて美しい作品。----------影を使った「Kage's Nest」「Glimmer Forest」は共にプラプラックスの作品。前者は、丸い光の空間に足を踏み入れると、自分の影とは別に、飛行機や鳥やサルなどの影が生まれて動いていく、という作品。後者は、立木のオブジェにある光のスポットに手をかざして影で隠すと、そこから「何か」の影が生まれる、という作品…なのですが、自分の影で、いまいち何が生まれたのかが見えないままなのは残念でした。----------鳥の羽を使った一連のオブジェは、小松宏誠さんの作品。真っ白な羽を組み合わせたオブジェが、風にくるくると回り続ける様は、本当に美しいですし、孔雀の羽を使った時計も美しい。----------パーフェクトロンの「inside-out」は、この1月に東京駅ステーションギャラリーで見た電車の作品に引き続いての出会いとなります。真っ暗な部屋の中、ミニチュアの都市を、小さな電球をつけた車が走り抜けます。電球に照らされて現れる街、それ以上に、それによって生み出される影の変容と動きのダイナミックさ、それでいて静謐に流れる時間、素晴らしい作品で、ずっと見ていたい気にさせられます。うーん、でも、正直に言いますと、ステーションギャラリーの作品の方がダイナミックで面白かったな、と。----------真鍋大度/比嘉了氏による「happy halloween!」は、顔認識をうまく利用した作品。椅子に座ると、大きなスクリーンに自分の顔が映し出されます。すると、その顔に、不思議なマスクがかかるのです。顔を一度隠すと、別なマスクが。自分の顔が、次々と少し怖い顔に変身します。自分の顔の変身に来館の子供たちも大喜びしていました。なのですが、この時期になぜ、ハロウィンなのか、と。アイデア自体は面白いのに、マスクも「思い付き」のレベルですし、季節の選び方も含め、今一つ洗練されていない感じは否めませんでした。----------この、多分、今回一番人気だっただろう作品に見られるように、展示数にしても、内容にしても、雰囲気にしても、洗練されていない感じが残念。本当は、子供も楽しめる、とても楽しい展覧会でした、とまとめたいですし、それはそれで間違いないのですけれど…子供向けのとっつきやすさ、と言えばそうなのですが、ICCの展覧会が好きだった身からすると、子供にこそ「本物」のスタイリッシュさを感じてもらいたい、というのが正直な気持ちです。(岩井俊雄先生の作品とか)まぁ、子供が楽しんでいたから良かったっちゃ良かったんですけどね。----------同時期にICCもキッズプログラムだったのですね。いつか体験させてやりたいなぁ。http://www.ntticc.or.jp/Archive/2013/KidsProgram2013/index_j.html急ぐ必要はない、と思いつつも、自分ではさせてあげられない、こういうハッとする体験って、どこかで…というのは言い訳ですね。本当は子供をだしに、自分が行ってみたいのです。==========『博物館が大変身!光の魔法とあそぼう 魔法の美術館』展 @明石市立文化博物館 (兵庫・明石) http://www.akashibunpaku.com/[会期]2013.07/13~09/01 [休館]会期中無休[料金] 大人 : 800 大高生 : 500 中学生以下 : 無料作者:パーフェクトロン他
September 13, 2013
コメント(0)
-

本と共に~『ねんね』
ねんね [ さえぐさひろこ ]この本も一目ぼれ、でした。まず、この表紙の「眠りリス」の写真からして可愛すぎでしょう。中も、カンガルー、キツネ、ライオン、ゴリラ、キリン、カバ、等々、様々な動物の赤ちゃんの可愛らしい寝姿が、次から次へと出てきます。そして、それぞれの写真に添えられた文章も、実にリズミカルで心地よい。何度見ても、何度読んでも飽きない、本当に楽しい写真集であり、散文集です。最後のページに、写真が貼れるようになっているのも、とても素敵な工夫です。子供自身の寝姿を貼ることで、一緒に寝る気持ちになってくれれば…という感じですね。うーん。ま、なかなかそんな思惑通りにはいきませんけれど、ね。
September 12, 2013
コメント(0)
-

秋の訪れ。
先日、兵庫県の北の方に位置する、ハチ高原まで行ってきました。やはり、ここより涼しいのか、ススキが銀色に輝いていました。同行した息子は、トンボやコオロギを捕まえて、野原を満喫していました。トンボはその場で逃がしましたが、コオロギは連れて帰り、しばらく飼うことにしました。このあたりでも、虫の声が聞こえるようになっていましたが、家の中から聞こえるというのは、また別の風情があります。まぁ、遠くに連れてこられたコオロギ達にとっては受難ではありますが…。今まで「虫の声だよ」と教えながらも、「どんな虫か」を見せてやることが出来ていなかったので、良い経験が出来たかなと思います。
September 11, 2013
コメント(0)
-

本と共に~『もこもこもこ』
もこもこもこ谷川俊太郎作/元永定正絵この作品は、説明も何もなく、全編オノマトペ(音言葉)だけで書かれています。----------何もない大地から、「何か」が生まれ成長し、別の「何か」を食べてしまいます。そして食べたことからさらに別の「何か」が生まれ、成長し、すべてがはじけ飛びます。元の静かな大地に戻ったところで、再び「何か」が生まれ、物語は永遠のループを暗示して幕を閉じます。----------嗚呼。こうやって「あらすじ」を書いてみれば、「言葉」のなんと不自由なことよ。この物語を、谷川先生は、「音」だけで綴るのです。改めて、先生は本当に天才なのだな、と思います。そして、この物語を彩るのは、元永先生の絵。これがまた、豊かで見事な色彩で、「音」を「絵」に昇華しているのです。読む度に、年齢に応じて、物語の見え方、楽しみ方が違ってくるのも面白いところ。本当に奇跡的な作品と言って良いと思います。==========ちなみに、母が読み聞かせ教室(講師は永田萌さんと黒井健さん!)で聞いてきたのですが、この題名、「もこっもこもこ」と読む方が良いよ、と。題名を見ると、確かに、最初の「こ」の字がはねています。なるほど、と納得しました。==========大人はどうしても「意味」を考えてしまいますが、そうではなく絵を見て「感じる」、という、現代美術の鑑賞にもつながる、何か根源的な楽しみを与えてくれる名作です。
September 10, 2013
コメント(0)
-
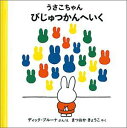
本と共に~「うさこちゃん びじゅつかんへいく」
「うさこちゃん びじゅつかんへいく」(福音館書店版)(または「ミッフィーのたのしい美術館」(講談社版))同じ内容で、2種類あるわけですが、ご存知の方はご存知のように、ミッフィー」「うさこちゃん」の名称は、版権の関係。なので、どちらの名前で知っているかで、世代が分かるそうです。ちなみに、私は「ミッフィー」派。今は、福音館書店版の「うさこちゃん」が主流ですね。実は、この「ミッフィー」という名は、アメリカでの呼称。ブルーナ氏の本国オランダでは、つまり、原作では、「ナインチェ」という名前で、これは「うさぎちゃん」という意味になるそうなので、本来的にはこちらが正しいのかな?福音館版と、講談社版では訳者も違うので、見比べると面白い発見があります。-----閑話休題(それはさておき)。姫路市立美術館での『美術館に行こう! ディック・ブルーナに学ぶモダン・アートの楽しみ方』展に備えて、この本を買って「予習」をしました。「現代美術(モダン・アート)」に対して難しいイメージを持っている人は多いかと思うのですが、基本的には、「自由に表現する」アートだということです。だから、見る側も素直に自由に鑑賞すれば良い。この本の「うさこちゃん」は、写実の絵画を見て、「ほんものそっくり」と言い、抽象画を見て「これならわたしにだってかける」と思います。あるいは「ほんとうにきれい」と思いながら「ほんとうはよくわからない」と呟きます。「何を描いているか」が問題なのではなく、「どう感じるか」が観る側に委ねられているのが現代美術だ、ということが出来るでしょう。何より、たくさんの「素敵」に出合う機会を持つことが、豊かな感性につながるのかな、と思います。本の感想というより、美術論になってしまいましたが(苦笑)まぁ、ここは本来、美術系blogなので、ということでご容赦ください。
September 8, 2013
コメント(0)
-

in『美術館に行こう! ディック・ブルーナに学ぶ(以下略)』@姫路市立美術館
夏休み&開館30周年特別企画で、姫路市立美術館では『美術館に行こう! ディック・ブルーナに学ぶモダン・アートの楽しみ方』展が開催されていました。これは姫路市立美術館デビューに良い機会と、息子を連れて美術館に行ってきました。姫路という街は、本当に面白い街で、現在、姫路城こそベールに覆われていますが、この「国宝」兼「世界遺産」のみならず、お城の裏手には、丹下さん設計の県立歴史博物館や、安藤さん設計の姫路文学館があったりします。この美術館自体、レンガ造りのとても美しい設計で、地元ではお城撮影スポットの一つとしても有名です。(写真は昔の。現在、姫路城は覆いをかけられている状態です)てか、ま、ここで月一回ボランティア(時々サボる)させて頂いているわけですが。===================さて、内容は、と言いますと、ディック・ブルーナ氏の「うさこちゃん びじゅつかんへいく」(福音館書店版)(または「ミッフィーのたのしい美術館」(講談社版))をもとに、現代美術(モダン・アート)を展示して、子供たちに楽しんでもらおうという企画展。結構いろいろなところを巡回しているようで、私自身、今はない大阪天保山サントリーミュージアムで、同名の展覧会に行ったことがあります。その時の感想はこちら。うーん。昔の方がしっかり書いているなぁ。正直、比較するのは酷だなぁ、と思うのですが…規模が違ってるのでねぇ。姫路美術館は、日本屈指のベルギー美術作品を擁し、兵庫県東播地域出身の作家を中心としたコレクションも非常に充実した素晴らしい美術館なのですが、では、それらの所蔵作品を並べれば、この美術展の趣旨と合った展覧会内容になるのか、と言うと、なかなか難しいものがあります。最後の「つくってみよう」のコーナーや、ブルーナ氏の作品が置いてある読書コーナーで、目いっぱい楽しんでいたから良いかな、美術館デビューも出来たし、というところですね。義理もございますので、歯切れの悪いレビューになってしまいましたが。子連れでなく、一人で行っていたら、このページにこの作品を充てるのか、というような楽しみ方も出来たのだろうな、と思います。==========『美術館に行こう! ディック・ブルーナに学ぶモダン・アートの楽しみ方』展 @姫路市立美術館 (兵庫・姫路) http://www.city.himeji.lg.jp/art/[会期]2013.06/22~09/01 [休館]月曜[料金] 大人 : 900 大高 : 500 中小 : 100作者:ディック・ブルーナ 他
September 6, 2013
コメント(0)
-
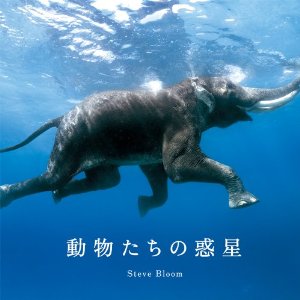
本と共に~『動物たちの惑星』
幼児向けの動物絵本というのは、たくさんあって、それぞれ可愛らしかったりします。動物園でも本物の動物を見ることが出来ます。図鑑でも、様々な種類の動物の様々な生態を知ることが出来ます。でも、ですよ。確かに、どれも素晴らしい体験だと思うのですが、本当に自然の中で生きている動物って、もっとダイナミックで過酷で美しい「生」を送っているわけです。そのことを子供に伝えてあげたいなぁ、テレビではなく、本の形で、と思っている時に、この本に出会いました。もうね、ひとめぼれですよ。この表紙の写真の美しさ、意外性からして魅力的ですし、中身も、ゾウのみならず、カバやサイ、ダチョウ、アルパカ、パンダ、ツル、ワシ、シロクマ、ペンギン等26種類もの動物たちの美しい写真が収められています。写真集としても美しく、大きさも手頃で、眺めていて飽きない。子供だけのものにするにはもったいない、素晴らしい本だと思います。「切り取られた自然」として動物を認識するのではなく「大自然の一部」として動物を感じてもらえれば、というのは、ちょっと早い高望みでしょうが。==========もう、楽天ブックスでは手に入らないようなので…紀伊國屋書店
September 4, 2013
コメント(0)
-
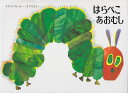
本と共に~『はらぺこあおむし』他
はらぺこあおむし [ エリック・カール ]小さなあおむしの、大きな冒険の物語。誰もが(読んだことはなくても)見たことのある絵本だと思います。改めて読んで、数と曜日と、あおむしがサナギになってチョウになることまで、お話の中に盛り込まれていることにびっくり。『はらぺこあおむし』には、様々なバージョンがありますし、世界中で読まれています。知り合いの大学教授の先生が、各国語、様々なサイズの『はらぺこあおむし』をコレクションされていたことを思い出します。妹に勧められて、「えほんうた」も聞かせてもらいました。エリック・カール絵本うた【CD】歌、というよりミュージカル仕立ての感じで、子供には難しいかな、と思ったのですが、何のことはない、難しいと思っているのは大人の方で、子供の方が素直にすぐに歌を覚えてしまいました。この「えほんうた」には、同じくエリック・カール氏の『できるかな?』『月ようびはなにたべる?』も収録されているので、今度はこれらの本も買って歌を覚えたいなと思います。できるかな? [ エリック・カール ]月ようびはなにたべる? [ エリック・カール ]
September 3, 2013
コメント(4)
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
-
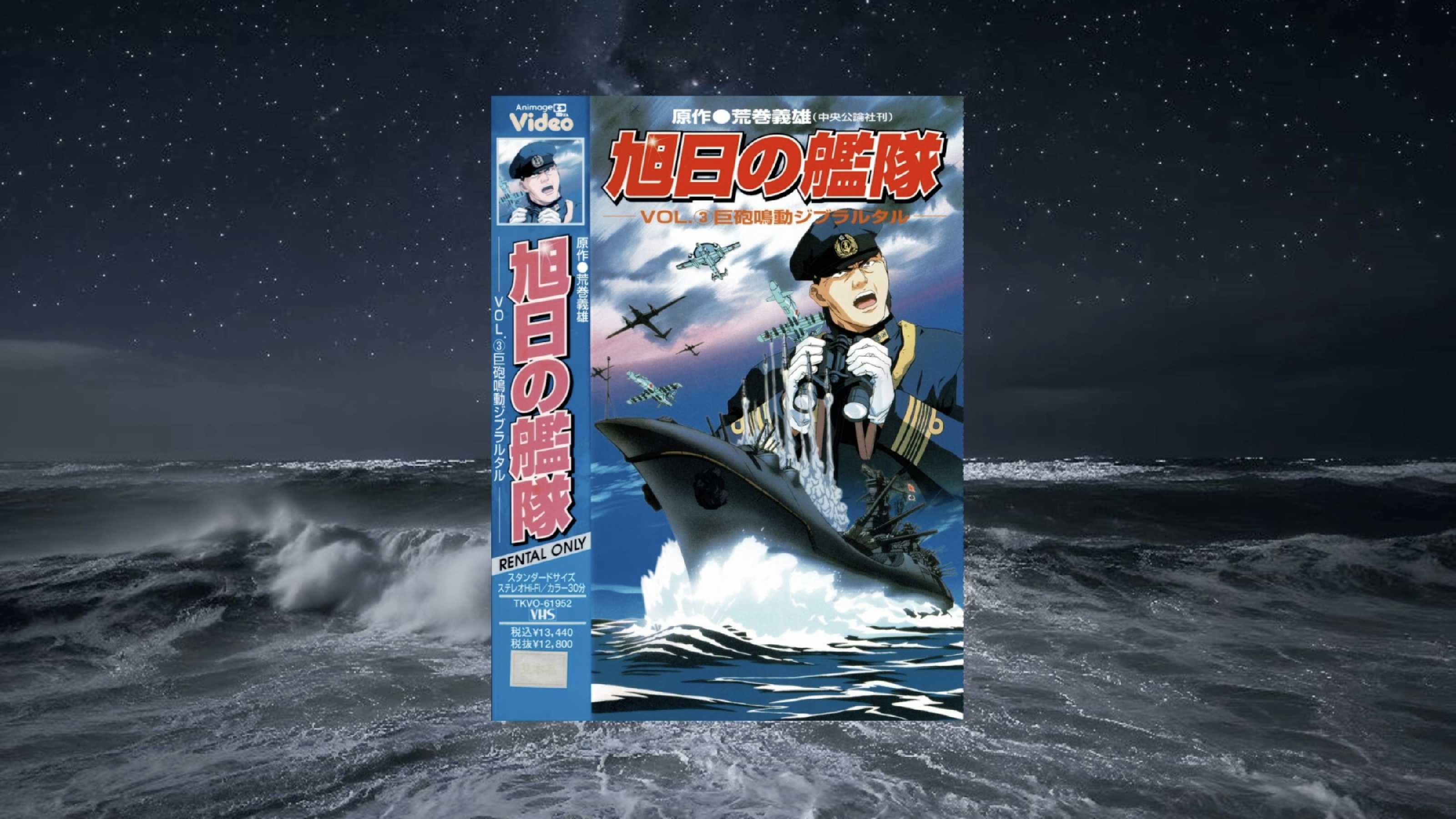
- アニメあれこれ
- お知らせ:YouTubeに アニメ「旭日…
- (2025-11-20 12:04:47)
-
-
-

- 懐かしのTV番組
- 塔馬教授の天才推理2 湯殿山麓ミイ…
- (2025-11-20 15:41:05)
-
-
-

- 映画作品紹介(楽天エンタメナビ)
- 【映画】 ニンジャバットマン対ヤク…
- (2025-11-18 17:00:07)
-






