2013年10月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-

in「愛の儀式」by大宮エリー@大阪
大宮エリーさんの名前は、NHKらしからぬNHK番組「サラリーマンNEO」の脚本家として知っていました。大阪の中之島を川沿いに歩いている途中、ふと目にした展覧会の看板。脚本家、だよね?というクエスチョンを頭に載せつつ、ふらりと立ち寄ってみることにしました。----------「愛の儀式」と銘打って、赤・青・緑それぞれの色のイメージを詩に書いて、それぞれのイメージとコラボレーションした部屋をプロデュースする、空間演出とでも言うべき作品。赤の部屋は、マグマのイメージ。生命力あふれる大地の営み。青の部屋は、海底のイメージ。生命が発生する母なる海。緑の部屋は、ジャングルのイメージ。生命を癒す森の空間。詩の言葉がそれぞれに力強く、生命力を感じさせられますそれぞれの照明に彩られた空間に足を踏み入れると、流れているそれぞれの音楽の雰囲気と相まって、不思議と落ち着いた気持ちにさせてくれます。題名の通り、何かの儀式が今にも始まりそうな、狭い部屋がワクワクする無限の空間へと広がりを見せるような感覚。 ----------非常に面白い空間表現ではあったのですが、この「答え」はあまりにストレートで、何か新しい視座を得られるというより、なるほどね、と納得する感じで、空間演出・空間デザインとしては美しいけれど、現代美術として観てしまうと、意外性、面白さには欠ける、かなぁ、と。その意味では、正しく「デザイン」の範疇なのかな、と思いました。----------緑の部屋が、カフェと一体となっていて、カフェ自体の演出になっていたのは、とても面白く、ちょっと混んでいたのと時間がなかったので、写真も含めて遠慮しましたが、ここでお茶でもしていれば、また違う感想を持てたのかもしれません。----------現代美術的な視座での感想を述べはしましたが、とても居心地が良い空間で、作家さんの「生」を感じられる、面白い展覧会でした。この展覧会は終わってしまいましたが、年内、同じく大阪は難波の「dddギャラリー」で「大宮エリー展」が開催されるそうです。==========『愛の儀式』 @中之島デザインミュージアム (大阪・中之島) http://designde.jp/[会期]2013.09/20~10/20 [休館]会期中無休[料金] 大人 : 300作者:大宮エリー==========『「大宮エリー展」-7年のOL時代と、7年間の今-』 @dddギャラリー(大阪・難波) http://www.dnp.co.jp/gallery/ddd/[会期]2013.11/05~12/20 [料金]入場料無料作者:大宮エリー※大宮エリー公式サイト http://ellie-office.com/生きるコント [ 大宮エリー ]
October 28, 2013
コメント(0)
-
星に願いを☆
10/21はオリオン座流星群が極大になる、ということで、夜、ベランダに出ました。明るい月がオリオン座の方角に眩しいくらい輝いていて、流れ星が見えないのは、そのせいかと思うくらい。なかなか見つけられないまま時間が過ぎ、でもせっかくだし1つだけでも見たいなぁ、と思っていたら、月明かりをものともしない明るい一筋の流れ星。あまりにも突然、あまりにも一瞬で、願いをかける余裕はありませんでした。もっと見たい気持ちはありましたが、寒くなってきたので、お部屋に退散。ぐっすり寝ている我が子を見ながら、いつか一緒に天体観測出来たら良いなと思った秋の夜でした。
October 23, 2013
コメント(0)
-
10/19は「イクメンの日」
なのだそうです。私自身も、そう呼んで頂くことも多いのですが、しかし、この言葉、私自身はあまり好きではありません。父親も育児を楽しもう、というコンセプト自体は理解できるし、賛同もするのですが、共働き家庭も多い現在、本来的には、育児うんぬん以前に、夫婦間の家事分担比率の問題ではないかと思うのです。なので、「育児だけ」に重点を置いてしまうと、問題の本質がずれてしまうのではないか、と。==========現実に「家庭内労働」としては、子育てのみならず、料理、洗い物、掃除、洗濯、ゴミ出し、お風呂の用意、近所づきあい等々、いろいろあるわけです。もちろん、それを全部一方に押し付けて「我関せず」というのは、昔の世代ならいざ知らず、今どきの世代の人間であれば、論外と思いますが、家事負担の分担の話を飛ばして、「育児しているかどうか」を判断基準みたいにしてしまうのはどうなのか、と。==========私自身は、一人暮らしで自炊もしていましたから、我流ではありますが、一通りの家事は可能ですし、時間のある時は出来る手伝いをやっています。子供と遊んだり、「育児」的なこともしますが、それ以上に、「育児」と直接関係しない、これらの手伝いこそが、「育児」への一番のサポートなのだと思っています。平たく言うと、「オムツを替えた回数」よりも「食器片づけて洗い物をした回数」の方が、母親にとって価値がある場合もあるのではないか、ということです。あくまでも、夫婦間の価値観の問題なので、どっちが正解、というのはないですが。==========正直、私が危惧しているのは、真面目な人ほど、仕事もして、育児参加もして、と自分を追い詰めかねないのではないか、ということです。男性の「育児ノイローゼ」、いや「イクメンノイローゼ」が増える日が近いという気がします。だって、男性で家事が出来ない、苦手な人もいるでしょう。あるいは、仕事の関係で、疲れて帰って、時間的・肉体的に無理な人もいるでしょう。そこに、「子育てに参加しないあなたはイクメンじゃない」というレッテル貼りをされたら、逃げ場をなくしてしまいかねません。==========本来、他人の家庭と比較する問題でなく、あくまで夫婦間の家事分担、労働分担の話し合いの問題のはずが、言葉が一人歩きして、「非イクメン」狩りに向かってしまっている気がするのです。プライベートなことであるが故に、二人がちゃんとしっかり納得していれば、どんな分担比率であろうが、他人が(アドバイスは出来ても)とやかく言うことではないはず。==========まぁ、とはいえ、今回のお話自体、「家事を手伝う気がある男性」という性善説に基づいた話で、「そうは言っても何も手伝おうとしない男性」であるとか、「暴力で相手を従わせようとする男性」とかについては、文字通り「論外」なのですけどね。
October 19, 2013
コメント(0)
-
7分間のプロポーズ
さて、昨日、ラジオに投稿したお話をさせて頂きました。(こちら)「お芝居」をテーマに、NHKラジオ「すっぴん」に送った内容が下記になります。==========学生の頃、「お芝居」をしていて、舞台に立ったこともある私。プロポーズに際し、自分にしかできないことをしようと頭をひねり、プロポーズの文面を手書きの手紙に書いて渡し、彼女が見ている前で暗唱して見せることにしました。心を込めて書いた手紙、時間にして7分。たった一人の観客の前での「お芝居」は、大勢の観客の前で「お芝居」するよりもずっと緊張しました。なんとか最後まで演じ切り、花束を渡して(指輪は要らないということだったので)、頂いた返事はイエス。文字通り、一世一代の大芝居でした。花束を渡した時、彼女は泣いていました、と言うと、高橋先生から「それも演技だよ」とツッコまれるかもですが(笑)==========「すっぴん」の高橋源一郎先生、藤井アナウンサーからは、「僕もされたい」「かっこいい」「どんな手紙か知りたい」との有難いお言葉を頂きました。---------まぁ、でも、難しいです。自己満足、自己演出と言われたらそれまで。相手が喜んでくれてこそのサプライズだし、プロポーズ。「指輪不要」と言われて、必死に演出を考えたらこうなった、というだけですし。---------え? どんな手紙か知りたい、ですって?リクエストにお応えしたいところですが、時間となってしまいました。残念ですが、今日はこの辺で。See You!
October 19, 2013
コメント(0)
-
ラジオ投稿顛末記。
小学生の頃、朝食の時はラジオを聞いていた。今思えば、母が時計がわりにしていたのだろう。----------関西ではメジャーな「ありがとう浜村淳です」が好きで、浜村さんの声や諜り方、また、映画以上に面白く、オチまでバラすこともしばしばの過剰で素敵な映画解説から受けた影響は大きい。http://www.mbs1179.com/arigato/----------中学に入って、ラジオを聞くことはなくなリ、大学からはテレビ中心になった。社会人になっても、東京にいる間は聞くことはなかったけれど、兵庫に帰り、車移動が増えて、また聞くようになった。----------午前中はNHK、午後・夜はKissFMというのが、だいたいのパターン。時々、地元FMのBanBanラジオをかける。移動の時間は大体決まっているので、聞く番組も決まってくる。http://www.nhk.or.jp/r1/http://www.kiss-fm.co.jp/http://www.banban.jp/radio/----------朝のNHKのニュースの声を聴いて、アナウンサーをしている後輩が大阪支局に来ていることを知った。時々TVでも顔を見る。----------「すっぴん」を聞くのは、月曜か金曜だ。月曜日、フィフィさんの元気さも良かったが、今の松田悟志さんも、爽やかで良いな、と思う。金曜日は、高橋源一郎先生。知的で隠やかで、時に皮肉な語り口が楽しい。「源ちゃんの現代国語」のコーナーは、聞ける機会こそ少ないが、小川洋子さんの「パナソニックメロディアスライブラリ」と合わせて、僕の読書指針の一つだ。http://www.nhk.or.jp/suppin/http://www.tfm.co.jp/ml/==========さて、今日のお話をしよう。投稿のテーマは「お芝居」だった。----------「お芝居をする」=「演技する」というのは、日常ではあまり良い意味に使われない。ラジオから流れてくるのは、そんなマイナスイメージの「お芝居」の話ばかりで、だから僕は投稿したくなった。----------運転中に文面を考えていたので、仕事の合間にさくっと打って投稿。再び仕事に戻って車で移動。ちょうど目的地到達前に、「今日は最後にもう一通お便りを」という形で紹介してもらった。----------内容からして、たぶん読まれるだろうと思っていたが、読まれるまで緊張感は独特だな、と思う。そして、文面も、藤井アナウンサーに読んで頂くと、自分の文章という感じがしない。実際に僕の書いた内容は、また後日。----------高橋先生のツッコミも予期して予防線を張っていたのだが、意外にも、「かっこいいよ」「その涙は本物だよ」と褒められた。って、内容を飛ばしたら分からないか(苦笑)----------自分の書いた文章が、プロのアナウンサーに読まれて、全国に届いていると思うと、やはりなんか不思議な気分。本来なら遠い存在の、藤井アナウンサーが、高橋先生が、すごく身近に感じられるのも、ラジオの魅力だなと思う。なるほど、投稿者の方々って、この感覚に中毒になるのか、と少し分かった気がした、NHKラジオ初投稿体験であった。
October 18, 2013
コメント(0)
-

★芝居★ 劇団ここから 『春の遭難者』
久しぶりのお芝居は、劇団ここからさんの本公演。チラシの説明で、題材が重いことは知っていたのですが、役者さんの上手さのおかげで、一層ズシンと心に刺さるお芝居でした。題材が題材だけに、不愉快な表現も混じるかもしれませんが、ご理解ご容赦ください。============舞台は、性犯罪の被害を受けた経験を持つ4人の女性が共同生活を送る山奥のロッジ。そこにオーナーの孫娘であり、実家の雑貨屋を手伝う女性が訪ねてきますが、生憎の雪で帰れなくなってしまいます。折悪しく、メンバーの一人は、裁判を終えて帰ってきたところ、しかも、裁判結果が思わしくなかった上に、裁判員の一人が知り合いであったことに傷ついていました。語られる現在の裁判制度の欠陥、加害者の背負う罰の軽さ、被害者の人権への無配慮。そんな中、一人の男性遭難者が、寒さに凍え、身動きも取れない状態で、助けを求めて訪ねてきます。遭難者を助けるのが当然と思っている雑貨屋の娘の前で、何もしようとはしない4人。あまつさえ、遭難者を見殺しにしかねない状況の中、雑貨屋の娘は4人の説得を試みますが、助けて欲しい時に助けてもらえなかったそれぞれの心の痛みが、それを邪魔します。膠着する「議論」の中、雑貨屋の娘はある行動に出ます。その行動は、その後の彼女達の人生を変えていくきっかけとなっていくのでした。============とまぁ、あらすじを書いたわけですが、いや、本当に重いお芝居でした。明るさの見えるラストの展開に希望を見ることは可能ですが、とはいえ「午後からまた新しい人が来る」という、リアルな重さも同時に描かれるわけで。作品の中でも言及されますが、「男性社会」の中で積み上げられてきた法律体系の下では、被害者、特に性犯罪被害者の人権に配慮しきれていない部分があるのは当然なのかな、とも思います。----------先日、どこぞの野球選手が、殺人の被害にあった女子高生を揶揄して「自業自得」と呟いて炎上したそうですが、相手の同意なくそのような写真を流出させるのこと自体が言語道断ですし、バラ撒くことを脅し文句にするのは立派な恐喝であって、殺した方、脅した方、バラ撒いた方が悪いのは、自明の理。例えば、被害者を自分の彼女に置き換えて、元カレが写真をバラ撒いたとしたら…この選手は、まぁ、それを理由に別れるか、彼女に対して暴力を振るうのでしょうね。元カレを糾弾するのではなく。選手として何流なのかは存じませんが、人としてはそのレベルだと言うことです。恐ろしいのは、この選手の考えに共感するような人間が少なからずいること。彼女の脇の甘さはあったのかもしれません。それでも、殺される謂れはない。そして、この話は、殺人を媒介にしているからこそ公に語られていますが、性犯罪の被害は、もっと陰湿で危険、悪質なものに他なりません。痴漢の冤罪事案や、女性車両の導入を指して、逆差別等を堂々とのたまう輩もいますが、被害者の気持ちへの配慮、サイレントマジョリティに「思いをいたす」ことの出来ないそういう考え方には、正直、怖さを感じます。----------さて、肝心のお芝居のことですが、何より、役者さん達に、心からお疲れ様と言いたい。役を演じるのは、ただでさえエネルギーのいる行為ですが、今回のお芝居は、それぞれの役が「重い過去」を背負っている以上、そこまで背負う必要があります。話を聞くだけでもつらい内容なのに、それを自分の口で、自分の体験として語る。演じててつらかったろうな、と思います。(ただ一人、そこまでの重い「過去」を背負わない守永さんは、方言指導入ってましたし(笑))そして、さすがの斉藤さん。唯一の男性役で、ほとんどセリフがないにも関わらず、その存在感、「復活」してからのセリフの冴えは本当に見事。男性出演者は斉藤さん一人ですが、演出も、男性が演出するからこそ難しい部分は多々あったのだろうな、と。----------そして、ホールはアラベスクホール。コンサート主体の、船底みたいな天井が特徴のホールですが、声の響きに微妙な反響があって聞きにくい部分があったのが残念。音楽ホールは芝居用ではないのだなぁ、と思いました。以前見たのは音楽とか子供のミュージカルとかだったからなぁ。しかし、こんなホールだからこそ、ほとんど音響を使わず、澤田さんによるギターの生演奏を幕間に挟む演出が活き、暗くて重い物語の幕間に、温かな演奏が心を和ませてくれました。============いろいろ考えさせられる、本当に「社会派」なお芝居でした。正直、次は、カラッと明るいコメディが観たいです。(アンケートでは「推理劇」に○しましたけど。)============劇団ここから 第28回公演 『春の遭難者』 @アラベスクホール (兵庫・加古川)2013/10/13(日) 作;滝本祥生 演出;戸野本和久 出演;守永知世 / 田口陽子 / 冨田京子 / 橘美恵子 / 井川瑛美 / 斉藤宰(フリー)ギター;澤田繁一
October 13, 2013
コメント(2)
-

本と共に~『ちびはち』
ちびはち [ エドワード・ギブス ]表紙であり、題名にもなっている「ちびはち」が、何かから逃げているようです。「なんでにげるの?」という問いかけに、その次のページに逃げる理由となっている生き物が描かれます。それぞれの生き物が、追われ、追いかけ、円環を形作る。食物連鎖、という概念とは少し外れてはいますが、その入り口になっています。訳が谷川俊太郎さん。動物の名前を正確に、というよりも、オノマトペとしての動物への呼びかけを大切にして訳されています。本来、絵本の動物の絵も、それが動物として「正しい」のか、というと違うわけで(だから、私は動物の写真集を買って見せることでバランスを取っているつもりです)、動物の名前を正しく覚える、ということよりも、楽しくリズムよく読むことに重点が置かれていることが、この独特の絵とマッチして面白い。読み終わると、裏表紙の円環の絵の意味が分かります。子供は終わった後で、裏表紙で遊んでいました。非常に楽しい本でした。
October 8, 2013
コメント(0)
-

本と共に~『ついておいでよ』
『ついておいでよ』 [ 松田素子 ]子供の想像力って、面白いなぁ、と思うのです。例えば絵本。文字が読めない分、自分の聞いた話を再現しようとしたり、あるいは絵から受けるイメージで新しいストーリーを作ったり。===============お父さん、お母さんに本を読んでもらえなかった主人公の女の子は、ぬいぐるみのネズミと、お友達であるネコと一緒に本を読むことにします。表紙のウサギさん、カメさんと一緒に本の中で「おさんぽ」するうちに、おサルさんやクマさん、ライオンさん、ゾウさん達と出合い、みんなで一緒に森の音楽会に向かいます。。===============この、本の中に入っていく、メタフィクション的な作りが面白い。そして、「現実」に戻ってからラストへの持って行き方がとても素敵です。子供なら、主人公に共感する部分は大きいんじゃないかなぁ。とても楽しく読ませて頂きました。
October 5, 2013
コメント(0)
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
-

- パク・ヨンハくん!
- 500記事目の記念に寄せて ― ヨンハへ…
- (2025-11-19 16:29:25)
-
-
-

- 芸能ニュース
- 草間リチャード脱退 Aぇ!groupメン…
- (2025-11-21 17:45:20)
-
-
-
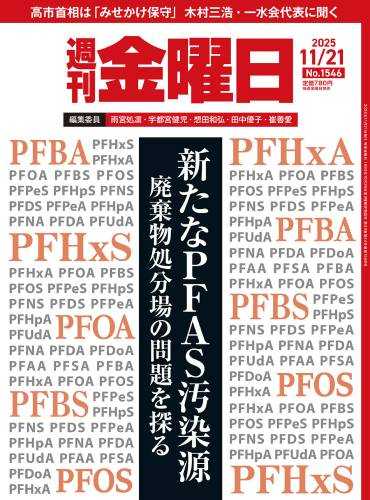
- 【演劇】何か見に行きますか? 行き…
- 劇評:劇団温泉ドラゴン『まだおとず…
- (2025-11-21 13:22:46)
-






