2013年11月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-

難しい料理
「カブトエビ」という生き物をご存じだろうか。田んぼなどにいる、形は「カブトガニ」に似た、小さな生き物である。(wikiでの説明はこちら下記写真もwikiより)小学生の頃、学校からの帰り道、田んぼを覗いては、飽かず眺めたりしていたことを思い出す。捕まえて飼おうとかは思わなかったけれど。----------さて、先日のことである。台所にレシピカードが置いてあった。目に留まったのは、何か違和感を感じたからだ。そう、そこには、こう書いてあったのだ。「かぶとえびのあっさり煮」…絶句した。食べるところはなさそうなのに、いや、干しエビやちりめんみたいに使うのだろうか、つまり一部の地方では食べる風習があるのか、それにしても旬は冬ではないだろう…一瞬の間にそんなことを考えて、はたと気づいた。そう、これは「蕪と海老のあっさり煮」なのだと。これならば、普通に美味しそうである。材料もシンプルで、料理としても簡単そうだし、体も温まりそうだ。----------なお、うちの食卓には、まだどちらの料理ものぼっていない。
November 27, 2013
コメント(0)
-

in『会田誠展:天才でごめんなさい』@森美術館
11月1日、たまたまお昼についていた「笑っていいとも!」のテレフォンショッキングで、会田誠氏が登場していました。文章で書けば、さらっと一言ですが、正直「お昼の番組に、この人を出してはいかんだろう」と目を丸くしてしまいました。一般的な「いいとも」視聴者層への認知度が高いとは思えないし、展覧会はとっくに終わっているし、何が目的の、どんなアートテロなのか。番組自体はタモリさんが上手く転がして、放送事故になることもなく無事に終了していましたが、(最後の会場アンケートで、微乳フェチを公言した挙句「ノーブラの人」の人数を聞き、それにタモリさんが悪乗りをして「ノーパンの人」の人数を聞いたのは、お昼の番組としてはギリギリな感じでしたが)、見ているこちらが妙な緊張感を味わいました。==========会田誠氏は、現代の美術のアカデミズムに対して、鋭く容赦ない批判を作品で投げかけている一人です。5年以上も前、「ぴあ」に載っていた、「美味ちゃん」シリーズの展覧会紹介記事を見た時の衝撃、「雪月花」シリーズをパルコで見た時の衝撃は忘れられません。会田誠氏が「現代日本美術」を語る上で、無視できない作家であることに間違いはないでしょう。紺洲堂主人さんは、彼の画集(私も持ってますが)を本屋で買って、サインをもらったと仰ってました。会田誠天才でごめんなさい [ 会田誠 ](画集がなかったので展覧会関連の書籍リンクです)=========さて、過去の話になりますが、会田誠氏の展覧会が森美術館で行われているというので観てきました。そもそも、「天才でごめんなさい」という題名からして、拒否感を覚える人も多いことだろうと思いますし、そして、その拒否感に違わず、良識のある美術好きには、苦痛でしかないだろう作品が、これでもかと展示されている展覧会でした。という書き方をすると、まるで会田誠氏の作品を嫌悪しているかのようですが、しかし、これは決してマイナスの批判ではありません。----------「美しい絵」が描けてしまうからこそ、テーマ性とのギャップによる「毒」が生まれます。そして、その「毒」は、我々の「良識」をあざ笑い、揺さぶります。それこそが会田誠氏の作品の真骨頂であり、我々自身の「下劣さ」、社会が蓋をしている「臭いモノ」を鮮やかにえぐり出すことで、見事な現代批評となっているのです。=========一面の金屏風に、精緻なタッチで実物大のゴキブリを一匹だけ描いた作品。----------日頃、金屏風の作品を有難がって見ている自分がいます。その作品に対する評価を決めるのは自分自身であって良い、という美術を楽しむ上での根本をどこかに置いて、権威主義的な見方をしている部分は、決してゼロではありません。----------だからこそ、超絶技巧で描かれるゴキブリが、凝り固まったモノの見方をほぐしてくれるのです。=========巨大で美しい瀧の絵を背景に、スクール水着姿の女子高生が何十人と水と戯れる姿が描かれるかと思えば、一見、数人の女子高生をテンポ良く画面に配しただけに見えて、良く見るとエグい「腹切女子高生」という、題名通りの作品もあります。=========また、小学生が学校で描かされるいわゆる「標語絵画」に大人として、子供風のタッチで挑んだ連作は、その偽善性を容赦なく暴きます。----------無批判に、「標語絵画」を微笑ましく見ていた自分がいます。しかし、関西に帰ってきた時に見て、ぞっとさせられた関西電力による、少女を起用した原発礼賛のCMと、「標語絵画」にいかほどの差異があるのか。----------福島以降なくなりましたが、原発CM自体を否定するつもりはありません。大人が自己責任で原発を礼賛し、推進することについては、議論の余地こそあれ、表現の自由、思想の自由の範囲内でしょう。CMへの出演についても然りです。自分で納得して、推進のCMに出ることに問題はないでしょう。しかし、大人がお金を貰って、納得した上で作られるものと、知識もない少女に「CO2を出しません!」と礼賛させるものとは、根本的に意味が違います。次世代(=少女自身)に禍根を残す可能性があるものに対して、その是非の判断も出来ないいたいけな子供に礼賛させるその無神経ぶりに、吐き気すら覚える悪夢のようなCMでした。----------そんな「思想の押しつけ」が「標語絵画」には潜んでいるのです。もちろん、その多くは、清らかな善意で成り立ってはいるのでしょう。しかし、一歩間違えると「中学生によるヘイトスピーチ」のような歪んだ何かに結びついてしまいかねない、ということを忘れてはなりません。=========さらに18禁指定されている部屋に展示されているのは、「雪月花」をはじめ、残虐性と反社会性を感じさせるとんでもない作品群。----------「雪月花」や「美味ちゃん」を見た時、美しいと思ってしまった自分がいます。そして、美しいと思った後に気付かされるのです。それを美しいと思ってしまう感性の中に秘められた自分自身の中にある残虐性や下劣な気持ちに。これは、本当に嫌な体験ですし、あまりしたくもない告白でもあります。=========これら「考えさせられる」ことを通じて、自分自身を、社会を見つめなおすきっかけを得られる、それが会田誠氏の作品の凄さなのです。観に行った甲斐のある、素晴らしい展覧会でした。「いいとも」の次は「徹子の部屋」ですかね?黒柳さん相手に下ネタってありなのかなぁ?どう考えてもアートテロだよなぁ。==========『会田誠展:天才でごめんなさい』 @森美術館 http://www.mori.art.museum/jp/index.html[会期]2012.11/17~2013.3/31[休館]会期中無休[料金]一般 1,500円/学生 1,000円/子供(4歳-中学生) 500円作者:会田誠
November 8, 2013
コメント(0)
-

in「坂口恭平 新政府展」@ワタリウム美術館
blogの更新を怠っていた間、アート的な世界から少し遠ざかっていたとは言え、何も見ざる言わざる聞かざるだったわけではもちろんなく。先日、文庫化された坂口恭平氏の『TOKYO一坪遺産』を読みました。(この本の感想については後日。)TOKYO一坪遺産 [ 坂口恭平 ]世の中の音を聞く耳を持っているかどうかが一流アーティストの証ならば、会田誠氏や、坂口恭平氏は、間違いなくそれを聞き、作品にする力を持っています。----------この本を手に取ったのは、氏の名前を知っていたこともありますが、何よりもこの1月にワタリウム美術館で行われていた「坂口恭平 新政府展」に行ったからです。それにしても、この1月のタイミングで、坂口氏をアーティストとして呼んでアートさせる、ワタリウム美術館のキュレーション能力の高さには、心から脱帽です。==========さて、展覧会のお話。坂口恭平氏は『独立国家の作り方』の作者として、ご存知の方も多いかと思います。独立国家のつくりかた [ 坂口恭平 ]坂口氏は福島の原発事故を受けて、故郷熊本にゼロ円で避難所を作り、たくさんの人を受入れ、その過程で、「政府」の在り方に疑問を持ち、「独立国家」宣言をしたわけですが、この展覧会では、その思想の根底を垣間見ることが出来、更にはその思想が展開していく過程、未来の一端に触れることが出来る、そんな展覧会でした。----------ドローイングについては、この展覧会の関連出版である『思考都市』を参照ください。思想家としてではなく、アーティストとしての坂口氏の作品を覗き見ることが出来ます。思考都市 [ 坂口恭平 ]絶妙なバランスで聳え立つ、脳から飛び出してきたかのような、「思考都市」の数々。(上の本の表紙のイメージです)妹尾河童先生の絵を思い出させる、細密で精密な記録画群。ラフな筆致で描かれたスケッチも、そのテーマ性、切り取り方に個性が表れています。----------そして、4階に「展示」されているのは、坂口氏の思考をそのままマッピングしたイメージマップ。横溢する言葉とイメージが、線でつながれ、次の関連を呼び、さらに展開されていく過程を見ることで、我々は坂口氏の思考をトレースし、思考の一端を追体験することが出来ます。同時に、このトレース作業によって、自分自身の考えも新たに呼び覚まされ、このマップは無限の展開を見せていくことになるのです。----------さらに、今回の展覧会で秀逸なのは、ワタリウム美術館の裏手(青山の一等地!)にゼロ円で住宅改装して共同生活を営んでいること。もちろん訪問可能です(参加も可能)。私が行った時はちょうど鍋をしている最中で、食べていけと勧めて頂きました。なんだか、何かが温かい。そして、この温かさこそが、経済成長の過程で我々の失ってしまったものだったのではないかと考えさせられます。==========教育の方向は捻じ曲げられ、マネーゲームを基準に経済が騙られ、「人を殺せる国へ」の政治が罷り通り、奇しくも大臣の仰った通り「ナチスに学ぶ」五輪の開催発表が行われ、庶民の幸福感とも経世済民とも程遠い所で政治が行われる、そんなとてもステキな現在に対する、強烈なアンチテーゼと言える展覧会。頭の中に「返り咲き」のお花を咲かして、勝手に国民から白紙委任状を取り付けた気で好き勝手している思い上がった政治家どもよりも、よっぽど人間らしく真っ当な価値観が、ここにはあります。----------「人間」あるいは「身体」の延長線上に手の届く範囲で生きる、という等身大の生き方の提示は、真の意味でのパラダイム・シフトと言えるのではないでしょうか。経済を数字のゲームから解き放ち、経済成長の源泉に教育の敷衍による選択可能性の拡大を置いた、ノーベル経済学者アマルティア・セン博士の思想にも通じると私は思います。我々は、経済の先でも、政治の先でもなく、思考の先に、人間らしい生き方を取り戻すことが出来るのかもしれない、そんなかすかな未来への希望を抱かせてもらえる、ディープな展覧会でした。==========「坂口恭平 新政府展」 @ワタリウム美術館 http://www.watarium.co.jp[会期]2012.11/17~2013.2/3[休館]月曜[料金]一般 1000円 / 学生(25歳以下) 800円 (会期中何度でも入場可)作者:坂口恭平 http://www.0yenhouse.com/
November 7, 2013
コメント(0)
-
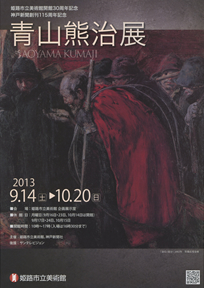
in『青山熊治展』@姫路市立美術館
兵庫県の中西部に、生野という、かって銀山として栄えた街あります。現在は朝来市生野町と呼ばれていますが、この街出身の「生野の三画伯」と呼ばれる画家がいます。明治末期に活躍した、白瀧幾之助・和田三造・青山熊治の三人です。----------お名前をご存じない方も、明治期を扱った現代美術の展覧会等で、知らず知らずの間に出会っているはず。----------姫路市立美術館では、2010年に没後50年「白瀧幾之助展」、2009年には「和田三造展」を行っていますので、今回の「青山熊治展」で、平成20年代の三画伯の美術展は一巡することになります。(三画伯について詳しくはこちら)==========展覧会は、青山熊治の画業を年代順に振り返る、オーソドックスな構成。初期作品については、画壇デビュー作の「老坑夫」、「アイヌ」等、一種プロレタリア的な重厚なテーマの取り方と、それに呼応する、暗い中に人物像を浮かび上がらせるレンブラント調の光の扱い、力強い描き方が印象的。----------1914年、シベリア鉄道経由でパリを目指した青山は、第一次世界大戦勃発の煽りを受け、ロシアで足止めをくらい、モスクワやペトログラードの美術館で模写をしながら勉強を重ね、スウェーデン、ノルウェーを経て、ロンドン、そしてようやく1915年、パリへ。パリを中心にフランスに長期滞在し、イタリア、スペインへも足を伸ばしたりしながら、1922年に帰国します。この時期の作品については、原画と比較しながら、模写作品が展示されているのですが、ルノワールやドラクロア、歴史叙事大作など、それぞれの画風をしっかりと学び取っている姿が浮かんできます。それとあわせて展示されている、風景画や人物画などの作品群からも、しっかりと何かを吸収してきた姿が垣間見えてきます。----------しかし、日本画壇への本格復帰は、1926年の「高原」を待たねばなりませんでした。帝展に出品されたこの作品は、当時の最高賞を受賞。少し遠く湖を望む高原に、服を脱ぎ、微睡み佇む裸婦たち。3mにも及ぶ画面の大きさ、弓なりの全体構図、裸婦が自然に溶け込んでしまうような淡く不思議な色彩感覚、思わず足が止められてしまう独特の雰囲気が、この作品にはあります。これと並んで展示されている、翌年の帝展に出品された「雨後」も、不思議な作品です。キャンパスの中心に、重なり合って描かれる、力強い馬たち。おそらく、小さな作品であれば、ごちゃっとした感じになってしまうのでしょうが、大作であるが故に、それがのびのびとした感じになるのは、構成の妙ということでしょう。「淡いが力強い」この色彩感覚は、初期の作品と同一人物とは思えない程です。----------何より大作が似合う作風という感じが強い展示のされ方から一転、次のコーナーでは肖像画、静物画に焦点が当てられます。この中では、「老婦人像」が秀逸。「いるよね」と思わせる、雰囲気の捉え方が本当に上手い。また、静物画の「上手い」を狙うのではなく、雰囲気を活写する描き方は、セザンヌの静物画に通じるものがあります。----------後半では、九州大学工学部の壁画や「九十九里」など、大作を描くに当たって描かれた習作、下絵が展示されています。パーツ毎それぞれの人物像や、構図を描いた下絵など、一つの作品それぞれにかけられたエネルギーを感じることが出来ます。どれだけの試行錯誤があって、「作品」に至るのかを思うと、良い作品を作りたいという作家の「業」を見ているような気がします。----------最後のコーナーは自画像。これらを見ると、厳しくも優しそうな画家像が見て取れます。==========それにしても、この画業にして46歳での死はあまりにも早く若い。最初から最後まで、作品の迫力に圧倒された展覧会でした。==========青山熊治展 @姫路市立美術館(兵庫・姫路) http://www.city.himeji.lg.jp/art/[会期]2013.09/14~10/20 [休館]月曜[料金]一般 800円/学生 500円/小中学生 200円作者:青山熊治
November 2, 2013
コメント(0)
-

♪movie♪「清須会議」
(C)2013 フジテレビ 東宝映画「清須会議」この作品情報を楽天エンタメナビで見る公開前なので、映画はまだ見ていないのですが、原作を読みました。清須会議 [ 三谷幸喜 ]本屋で流れてた映画紹介のDVDで、三谷幸喜さんが、映画は本と違うアプローチだから見てね、って言ってました。それにしても、豊臣秀吉役に大泉洋さんというキャスティングには、ちょっと唸らされます。人懐っこくて、憎めなくて、でも、どこか何か企んでいる、そんな役を説得力を持って演じられるのは、まさに人徳でしょう。そもそも、キャストが贅沢すぎ。私からすると、キャスト表を見ているだけでも幸せな気分になれる映画です。==========さて、小説版の物語は、「本能寺の変」における、織田信長の独白から始まり、それから15日後、柴田勝家が本能寺を訪れるシーンへとつながっていきます。この15日の間に、豊臣秀吉が毛利との戦いを切り上げて戻ってきて、丹羽長秀の軍勢と合流し、山崎の合戦にて明智軍を打ち破っていました。明智討伐に加われなかった柴田勝家は、丹羽長秀からの助言を得て、織田家の後継者と領地の再分配を決める「清須会議」の開催を織田家の宿老達に提案します。ここからが物語の始まりです。----------織田家の誰が後継者を担い、それを支えるのは誰になるのか。織田家後継候補たちのそれぞれの思惑。信長の妹、美貌のお市の方の思い。軍師黒田官兵衛の活躍。そして開催されるイノシシ狩り。それを受けて変わる情勢。前哨戦の3日間を経て、いざ会議という名の戦場へ!誰が誰につき、誰が最後に笑うのか。会話劇では描き切れない、それぞれの思惑を活字にすることで、駆け引きの裏側まで見せて楽しませながら、思いもかけない展開をみせる物語は、まさに言葉のジェットコースター。さらに、会議という「戦」の後の駆け引きも、ハラハラドキドキと楽しませてくれます。そして我々は、「それはまた別の話」ではあるものの、豊臣秀吉が柴田勝家を破り、天下人となるという、その後の展開を知っているわけで。だからこそ、ラストには少しのほろ苦さと、切なさを感じてしまいます。==========全文、「現代口語文」で書かれているのが、展開の面白さを引き立たせています。本来、時代劇は「見てきたような嘘を言い」の世界で、あくまで「お約束」として、それっぽいセリフ回しで進んでいくわけで、本当に当時の言葉のままが使われる時代劇なんて、あり得ない。でも、どうせ見てきたような嘘を言うのなら、このような「現代口語文」で、心情に踏み込んでも構わないわけです。舞台の世界では、違和感なく行われてきた手法ですが、小説やドラマ(時代劇)にすると、斬新な感じになりますね。---------- また、戦国時代、というアクション満載の時代を背景にしながら、「会議」という舞台設定なのも、面白い点です。 今回映画で柴田勝家役を演じられる役所広司さんが宮本武蔵を、益岡徹さんが佐々木小次郎を演じられた、三谷幸喜脚本の抱腹絶倒の舞台『巌流島』も、決戦前夜の宿を舞台にした会話劇で、巌流島という題名にも関わらず、決戦のシーンを描かないという、驚きの展開だったのを思い出します。あるいは、三谷幸喜さんの代表作から引用するなら、映画化もされた『十二人の優しい日本人』や『笑の大学』の密室会話劇を連想する方が正しいのかもしれません。12人の優しい日本人 【HDリマスター版】笑の大学 スタンダード・エディション会議室という「密室」からくる緊張感が、戦国時代という舞台を背景にしたことで、より高められ、「笑い」以上に「言葉」の密度が高い、良い意味で様々な期待を裏切ってくれる、小気味よい作品です。----------文庫本のペリー荻野さんの解説が、非常に上手に上記の点を指摘されていて、わが意を得たりだったので、そこから展開させたような感想になってしまいましたが。----------さてさて、映画はどうなりますことやら。豪華キャストによる演技対決、楽しみにしたいものです。
November 1, 2013
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
-

- Youtubeで見つけたイチオシ動画
- 12.5 全国公開「みらいのうた」予告…
- (2025-11-20 09:49:17)
-
-
-

- NHKおはよう日本 まちかど情報室
- 【 中学・高校生用 】お弁当の作り方…
- (2024-05-07 10:19:14)
-
-
-
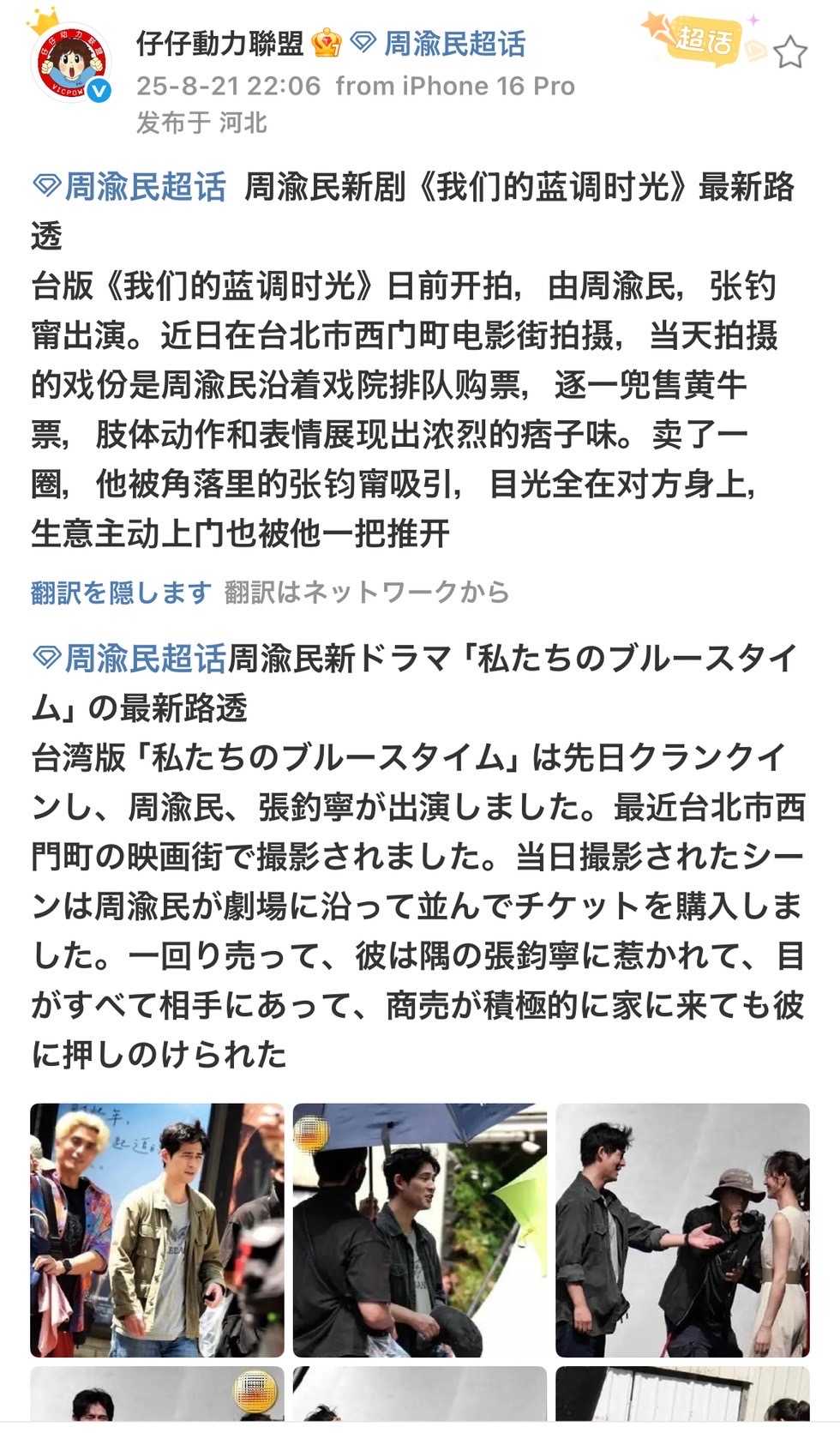
- 台湾ドラマ☆タレント
- 2025/08/21 『我們的藍調時光』撮影…
- (2025-08-26 19:17:32)
-






