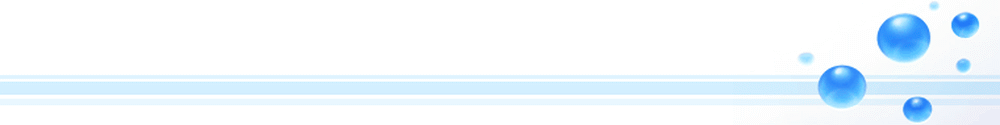2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2009年08月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
「褒めること」と「自慢すること」は似て非なるもの
「傷つきやすい性格」というのは、実は持って生まれた性格ではなく、幼少時に褒められることなく、叱られてばかりいたことが原因だと話しました。今回はその続きです。子供を「褒めること」と「自慢すること」は、どちらも子供を評価してるように見えますが、これは似て非なるものです。「褒めること」は子供に意識を向けた、子供に対する言葉です。この時に大切なことは昨日の自分よりも成長した、今日の自分を褒めてあげることです。しかし、「自慢すること」は違います。たとえば「自慢の息子(娘)」という場合、親の意識は我が子ではなく、世間に向けられた、人目を意識した言葉です。他の子供と比較して我が子を褒めるのも、これと同じです。世間体を意識した親の言葉、他の子供と比較した親の言葉は、自慢すればするほど、その言葉は子供にとってプレッシャーとなります。人目に適った自分だから、他の子供より優れた自分だから、親は自分を評価してくれているだけだと。人目に適わない自分になってしまったら、他の子供より優れた自分でなくなってしまったら、親はもう自分を認めてくれない。ありのままの自分を親は認めてくれているわけではないと。これもやはり褒められたことなく、叱られてばかりいたのと同じ結果をもたらします。自己否定の心を生み、「傷つきやすい性格」を作ってしまうのです。
2009年08月26日
-
伐採
数年前、教室の裏にいつの間にか木が生えました。みるみると大きくなり、枯れ葉が秋になるとたくさん落ちます。そこで思い立って、伐採することにしました。
2009年08月25日
-
ちょっとおバカになってみませんか?
おかやんさんの国際交流イベントでした。講師はインド出身名古屋在住32年のサクセナ氏。イギリスの植民地支配が、どれだけ今日までインド人の心に影響しているのか。カースト制にIT分野が存在しないから、インドのITが飛躍した話など、彼の話は国際的な視点を開かせてくれる機知に富んだものでした。
2009年08月22日
-
傷つきやすい性格
世の中には自称「傷つきやすい性格」の人が大勢います。皆さんはいかがですか?そういう人たちの大半は幼少期に親から叱られてばかりで、褒められた経験がほとんどありません。お心当たりはありませんか?もちろん親たちは我が子にきちんと育って欲しいという思いから叱るのですが、褒めることもしないとバランス的に良くありません。子供は褒められることなく叱られてばかりだと、「自分は親から否定されている」という思いがどんどん増していきます。すると親以外の誰かにちょっと指摘されただけでも、自分の存在自体が否定されたように感じてしまうのです。厳しく叱責しても、いずれ大きくなればそこに込められた親の愛情はきっと分かると信じている親もいますが、大きくなる前に自己否定の心に歪んでしまっては大変です。過ちを指摘したときに、それを重く受け止めて傷つくタイプと、全く気にせずにケロッとしているタイプがいます。だから生徒や部下の教育上、いずれのタイプかを見極めて接しなければいけないとはよく聞く話です。実はそれは持って生まれた彼らの性格のように思われがちですが、そうではありません。幼少期に褒められずに叱られたばかりいた人たちは、ちょっと指摘されただけでも「自分の存在自体が否定された」と過敏に反応してしまうのです。一方、きちんと褒められた経験もある人たちは、指摘されたことを分別して受け止めることができるのです。指摘されたのは自分の改めるべき言動に対してであって、自分の存在が否定されたのではないと。あるいは「あの言い方は厳しいなあ、恐いなあ」と思うことはあっても、自分の存在までもが否定されたとはまったく感じないので、傷つくことはありません。もし自分は「傷つきやすい性格」という自覚のある方は、自分が幼少期に褒められたことがあったかどうかを、振り返ってみてください。そしてそれは持って生まれた性格ではなく、後天的な理由からきていることを理解してください。このことを今後自分が傷つくたびに思い出して、理性的に自分の心を分析します。「自分が否定された」と過敏に反応してしまうのは、相手のせいではなく自分の幼少期からのトラウマだと理解するように心がけます。そうすることで「傷つきやすい意識」は次第に克服できます。
2009年08月19日
-
ちょっと自慢させてください
何気なくネットサーフィンをしていたら、自分が書いた懐かしい文章を見つけました。「開襟シャツとサマータイム制」というタイトルの文です。日付から見てこれは私がたぶん2002年の夏にメルマガで配信したものです。それをどなたかが私の呼びかけに応えて、コピーしてくれたようです。それから3年後に国はクールビズ政策を始めました。今でこそ国会議員が夏にノーネクタイは珍しくありませんが、「開襟シャツとサマータイム制」を執筆した当時は、およそ考えられないことでした。この呼びかけがきっかけで、クールビズが実現したとはさすがに思いませんが、先見性ということで言えば、ちょっと自慢ですもうすぐ選挙ですが、クールビズだけではなく、これからの日本に提言したい政策は他にも沢山あります。 ~開襟シャツとサマータイム制~ 今年の夏もまた記録的な暑さが続いています。 科学文明の生み出した地球温暖化の影響で、 年々、都会の暑さは異常性を増しています。 街に出るとサラリーマンたちは、うだる暑さの中でさえ、 背広にネクタイ姿で、アスファルトの照り返しに耐えながら歩いています。 また、外は倒れるほどの暑さだというのに、 会社内ではOLたちが、体を冷やしてクーラー病にかかりながら、 膝掛けをし、カーディガンを着て仕事をしています。 人間の手によって自然の摂理が破壊されつつある今日、 その報いを我が身が受けることを恐れながらも、 私たちはまるで自分たちにはどうすることも出来ないかのように、 世間の常識の言いなりとなって、この異常な生活に耐えています。 後は誰かがこの悪循環を解決してくれることを、 ただ受け身になって、じっと待っているのみです。 本当はこの問題の解決はとても簡単なはずです。 難しくしているのは、 今までの世間の常識に呪縛されてしまった私たちの心です。 解決策の一つは、男性がどのような場であっても、 熱帯の国々と同じように、 また昔の日本がそうであったように、 夏は背広にネクタイではなくて、開襟シャツにすることです。 ただこれだけでも、計り知れない効果があるではないですか。 営業でお客様に会う時に、 それではこちらの誠意が示せないというのなら、会社のスローガンとして、 「地球温暖化防止のために当社は開襟シャツです」と、 それを逆手にとって、環境問題を考える良識的な企業であることを、 アピールすれば良いのです。 またもし開襟シャツでフォーマル性が表せないというのなら、 新しい開襟シャツをどんどんデザインすれば良いのです。 新しい文化とはそうやって創出されていくものです。 もう一つの解決策は、サマータイム制を本気で導入することです。 本来、人は日の出と共に働き、日の入りと共に休みました。 自然の摂理に合わせて生きてきたのです。 そして、自然と調和して生きることこそが、 生き物にとっての、本当の幸せな姿ではないでしょうか。 一時間だけでも太陽に合わせて、一日の時間を早めるだけで、 これもやはり計り知れない効果があるのではないでしょうか。 今の地球は、 そんなことは無理だ、などと理屈を言っている事態ではないはずです。 一番良いのは国策として、この2つを本気で取り組むことです。 国会も開襟シャツでやれば良いのです。 TV局のアナウンサーも、茶髪を許すくらいの寛容性があるのなら、 開襟シャツでニュースを読めば良いのです。 もしこれを実行すれば、 はっきりとその効果が数字として表れるはずです。 なのに、なぜそれが出来ないのか。 それはこれまでに人々が作り出してしまった世間の常識に、 私たちの心が完全に縛られている以外のなにものでもありません。 しかし日本の風土を考えれば、 この常識の方がよほど理不尽なものです。 一歩外から見れば、 サウナのような環境で、ネクタイに背広を着て仕事をすることも、 真夏にエアコンをかけて、寒いからと服を着込むことも、 異常であることは容易にわかるはずです。 国やマスコミにそれが出来ないのなら、そういう世論を作ることです。 そして、その世論を作り出すのが、私たち一人一人の気持ちと、 受け身ではない行動力です。 今はインターネットの時代です。 もし共感していただけるなら、 どうぞこの内容をコピーして、お知り合いに送ってあげて下さい。 ヒーリングスペースTatsu 宮本 辰彦
2009年08月10日
-
お盆は意識改革の儀式
お盆にはお墓参りをするという風習が日本にはあります。多くの人たちは、これを形式的な行事として済ませています。しかし、日本人にとってお盆はお正月と共に、生まれ変わりのきっかけを与えてくれる重要な儀式です。人が心機一転、生まれ変わりたいと願っても、そこには条件があります。それは謙虚な気持ちを持たずして、人は新たに生まれ変わることは出来ないということです。日頃、忘れてしまいがな先祖に思いを寄せて、今自分がこうしてあるのも、先祖の存在があったお陰と思うことが出来たとき、人は謙虚な気持ちになれます。すると新たな気持ちで下半期を始めることができるのです。これが意識改革をもたらすコツです。日本にはお盆と正月。半期に一度、生まれ変わりを起こすための、国民的行事があるのです。
2009年08月06日
-
今朝、嬉しい夢を見ました!
出版社に来ています。書店から「瞑想力」の注文がFAXで入りました。何と570部も!これからこの調子でどんどん注文が入るといいですね、と出版社の方と喜び合っています
2009年08月01日
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
-

- ウォーキングダイエット日記
- ばんぶーさんの朝散記録 〜2025秋本…
- (2025-11-16 06:30:06)
-
-
-

- 新型コロナウイルス
- まさかのコロナ感染2回目!バトンツ…
- (2025-11-20 21:00:50)
-
-
-

- ダイエット日記
- ダイエット食事日記3112日、声楽…
- (2025-11-21 01:14:14)
-