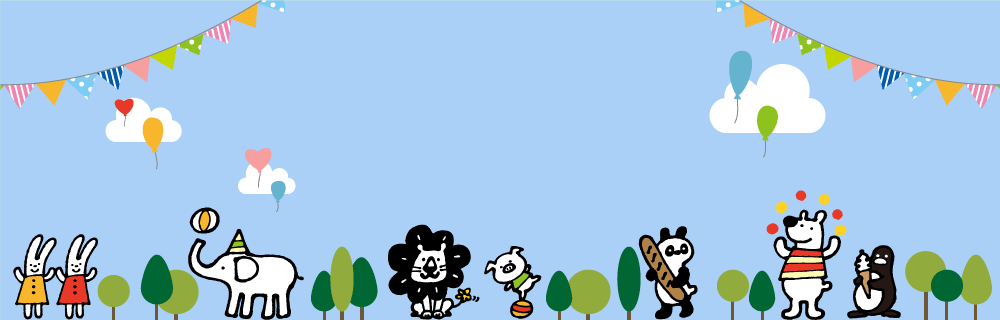2016年06月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
『風と共に去りぬ』誕生 30日の日記
クロニクル 『風と共に去りぬ』誕生1936(昭和11)年6月30日80年前、1936年は2,26事件の年です。その年の今日、アメリカジョージア州アトランタで生まれ育った、マーガレット・ミッチェル女史の大河小説『風と共に去りぬ』が出版されました。1900年生まれのミッチェル女史は、母方の伯母を通じて南北戦争の目撃談を詳しく教えられ、そうした記憶を下に、長い時間をかけて、この作品を書いたと言われます。作品は大ベストセラーとなり、3年後の1939年には映画化されました。ヴィヴィアン・リー、クラーク・ゲーブル主演の映画は、3時間を大きく超える長編でしたが、大変な人気を博し、評判が評判を呼んで大ヒットとなりました。日本での初公開は戦後の1952年でした。私が映画館で見たのは、1960年代のリバイバル上映だったように思います。
2016.06.30
コメント(18)
-
日本オリンピクに初参加 29日の日記
クロニクル 日本オリンピクに初参加1912(明治45)年6月29日、104年前のこの日、第5回オリンピック、ストックホルム大会の開会式が行なわれました。会場となったストックホルム競技場には、3万人の観衆が詰め掛け,大変な人気振りでした。この開会式に、五輪初参加の日本の代表団の姿もありました。面白いことに、この頃のオリンピックは、開会式後すぐに競技が始まるのではなく、競技は7月6日~14日の9日間で行なわれました。大会には28ヶ国から3282人が参加、日本もこの大会に初めて2人の選手を派遣していました。陸上短距離の三島弥彦選手と、マラソンの金栗四三(しぞう)選手です。またIOC委員として、東京高等師範学校校長、柔道の大家嘉納治五郎氏が参加しています。短距離の三島選手は、100mと200mは予選落ち、400mは準決勝に進出しましたが、負傷棄権となり、マラソンの金栗選手は、猛暑にやられ、25km附近で落伍してしまいました。まさに日本の初参加は、「参加した事に意義がある」の大会となったのでした。因みに、日本選手が最初にメダルを獲得したのは、次の第7回アントワープ五輪におけるテニス競技です。ダブルスの熊谷一弥・柏尾誠一郎組が銀メダルを獲得、余勢をかって熊谷選手はシングルスでも銀メダルを獲得したのです。何故、次の大会が第7回なのかというと、第6回大会は、第一次世界大戦のため、開かれなかったのです。第二次世界大戦では東京大会が中止になっていますが、それ以前にも中止となった大会があったのですね。
2016.06.29
コメント(16)
-
平和五原則発表 28日の日記
クロニクル 平和五原則発表1954(昭和29)年6月28日62年前のこの日、インドを訪問中の中国の周恩来首相は、デリーでインドのネルー首相と共に共同声明を発表、その中で平和五原則を提唱しました。インドと中国の間には、マクマホンラインを鋏んで未確定の国境問題があり、緊張関係にありましたが、この年4月に一定の合意に達していました。この日両国の親善を深めると同時に、4月の合意をより確実なものとするために、インド側の招きで訪印中の、中国の周恩来首相は、演説の中で五原則に言及、この精神で世界平和を推進しようと、アピールしました。ネルー首相もただちに賛同の意を示し、共同声明では単に2国間だけではなく、世界平和の推進に向けた原則であることが強調されました。五原則の内容は、1、主権の尊重 2、相互不可侵 3、内政不干渉4、平等互恵 5、平和共存 の5項目でした。大国意識丸出しに、意に染まぬ国の国家主権は無視して、平気で内政干渉に走りるいくつかの国には今一度この宣言を噛み締めてもらいたいものですね。と同時に、特に今の中国には、建国の指導者の発したこの宣言の精神を反芻し、インドと共に世界平和に貢献してもらいたいものです。
2016.06.28
コメント(16)
-
世界最初のATM設置 27日の日記
クロニクル 世界最初のATM設置1967(昭和42)年6月27日49年も前のことなのですね。この日イギリスのバークレー銀行が、ロンドン支店に、世界で始めてのATMを設置しました。随分速かったのですね。日本での設置は、数年遅れたのでしょうか。当時日本育英会の奨学金は、住友銀行への振込みでしたが、まだ店内にATMはなく、引き出しには相当時間、店内で待つ覚悟で出かけなければならず、かなりの不自由を感じたものでした。ATMがあれば、あんな思いはしなくて済んだのですがねぇ…。
2016.06.27
コメント(16)
-
ハーメルンの子どもたち 集団で失踪 26日の日記
クロニクル ハーメルンの子どもたち 集団で失踪 1284年6月26日中世ドイツの話です。日本では鎌倉時代に当ります。良く知られる史実を紹介すれば、2度にわたる蒙古襲来が、1274年と81年のことになります。ですから、2度目の蒙古襲来から3年後に当ります。この日の数日前のことです。ドイツのハーメルン市に、「ネズミ捕り」と名乗る1人の男がやってきます。男は一定の報酬で市内のネズミを駆除しないかと持ちかけ、約束を取り付けます。男は笛を鳴らしてネズミたちを誘い出し、市内を流れるヴェーザー川に誘導して、ネズミたちを全て溺死させます。ネズミ退治は見事に成功したのですが、あまりに簡単に成功したことから、ハーメルンの人びとは、報酬を出すことを拒否したのです。すっかり怒った男は、一度はハーメルンの町を後にするのですが、6月26日の午前中に再びハーメルンの町に現れ、住民たちが教会にいる間に、再び笛を吹き鳴らして、今度は市内の子どもたち130人を街から連れ去ったのです。130人の子どもたちは、笛を吹き鳴らす男の後について、洞窟の中に消え、二度と戻ってこなかったというのです。有名な『ハーメルンの笛吹き男』の話は、この実話に基づいて作られました。なお、6月26日は、聖ヨハネと聖パウロの記念日とされています。この話は、ハーメルン市の新門にあるラテン語の碑文に記されており、また全てのハーメルン市の記録は、この子どもたちの失踪事件から始められていますので、信謬性の高い話と受け止められています。参考 阿部謹也『ハーメルンの笛吹き男』(平凡社)
2016.06.26
コメント(12)
-
雪印集団食中毒事件発生 後日談
雪印集団食中毒事件発生 後日談遅くなりました。昨日のクロニクルでお約束した後日談です。本日のクロニクルは夜にでも…食中毒の原因について、会社側は7月1日になってようやく開いた記者会見で、「大阪工場の逆流防止弁の洗浄不足による汚染」によるものと発表しました。大阪保健所もそれ以上の追及はしませんでした。しかし、大阪府警は、逆流防止弁の洗浄不足のみが原因とは限らないと考え、その後も調査を継続しました。その結果、大阪府警は、大阪工場の製品の原料にあたる脱脂粉乳を製造していた、北海道大樹工場の汚染が原因であることを突き止めたのです。大樹工場では、同年3月31日に氷柱の落下によって3時間の停電が発生、病原性黄色ブドウ球菌が増殖して毒素が発生していたのです。電源回復後、大樹工場では生産再開を急ぐあまり、食品加工工場に必要な、ラインの衛生検査を行なわずに、生産を続けていたのです。これが真の原因でした。大阪保健所には、北海道の工場に検査に入る権限はありません。しかし大企業である雪印乳業には、大阪工場の製品による食中毒事件であっても、大阪工場の最終製品に関連する施設、さらには同社の全工場での、衛生状態を点検して安全を確認する程度のことは、企業の社会的責任として実行するぐらいのことは、なすべきことでした。しかし、同社の経営陣には、食品会社として当然のことを指摘し、実践する経営陣が居なかったのです。これが同社の不幸でした。大阪府警の活躍で原因が特定された結果、雪印グループ各社の全生産工場の操業は全面的に停止されました。雪印のブランドイメージは大きく傷つき、全国のスーパーや小売店から、雪印の製品は一斉に撤去されました。 消費者の雪印への抗議は、それだけ強かったのです。経営者が対応を誤った結果でした。トップは素早くマスコミに登場し、不明を詫びると共に、全社一丸となって食の安全と再発防止に取り組む姿勢を見せるべきだったのです。それをせず、ひたすらマスコミを避けようとしたトップの姿勢も、厳しく糾弾されました。こうした雪印グループの姿勢が、2年後にはBSE問題に絡んでのグループ会社「雪印食品」の牛肉偽装事件として表面化する事態に繋がりました。こうして雪印グループは無惨に解体され、今日に至ることになります。トップに人を得ない企業が、ブランドだけで生き残れる時代は、既に終っているのですね。最近では東芝や三菱自動車が同じようなミスを犯していますね。
2016.06.25
コメント(8)
-
雪印集団食中毒事件発生 25日の日記
クロニクル 雪印集団食中毒事件発生2000(平成12)年6月25日16年前のことですから、御記憶の方も多いと思います。この日雪印乳業(当時)の大阪工場で製造された「雪印低脂肪乳」を飲んだ子どもが、嘔吐や下痢などの食中毒症状を起こしました。これが近畿地方中心に、認定患者数14,780人を記録した、戦後最大の食中毒事件のプロローグでした。2日後の27日、大阪市内の病院から、市の保健所に食中毒の疑いが通報されました。調査の結果、市の保健所が大阪工場に製品の回収を指導したのは、30日になってのことでした。27日頃からは、兵庫県や和歌山県などからも、続々と食中毒発生の報が寄せられてきたのですが、雪印側の対応は遅く、マスコミ発表と自主回収の動きは、ようやく29日になってのことでした。マスコミの報道後、被害の申告は爆発的に増え、最終的には14,780人が被害に会うという、記録的な被害となりました。比較的症状が軽かったのが、不幸中の幸いだったのですが、雪印乳業の対応の遅さ、食品会社としての社会的使命の自覚の欠如という、企業モラルの喪失という欠陥が、浮き彫りになった事件でした。この話には、後日談があります。その点は後ほど…
2016.06.25
コメント(12)
-
壬申の乱始まる 24日の日記
クロニクル 壬申の乱始まる672(天武元)年6月24日趣向を変えて、今日のクロニクルは古代史から。 西暦645年の大化の改新を「ムシゴロシ」とゴロ合わせをして、覚えた方もいらっしゃるでしょう。この時の立役者の1人、中臣鎌足は後に藤原の姓を下賜され、藤原氏を名乗ります。平安朝中期の摂関政治の主役となる藤原氏の始祖はこの人なんです。 もう1人の主役が中大兄皇子,後の天智天皇です。大化のクーデタ後、彼は皇太子のまま実質的に政治を担当しますが、中国の新興国家、隋王朝を倒した唐と結んだ新羅に敗れ、命運の尽きかけた百済救援の軍を派遣し、白村江(はくすきのえ)の戦いで、唐・新羅の連合艦隊に惨敗を決します。 日本古代史における未曾有の危機の時代の到来でした。当時の政府当局者は、唐・新羅連合軍が勢いに乗って日本(大和朝廷)攻略軍を起こすのではないかと心配し、当時大阪難波宮にあった朝廷を、琵琶湖のほとりの大津宮に移したほどでした。 というわけで、壬申乱当時の朝廷は大津にありました。天智天皇は、この大津で即位したのですが、前年671年(天智10年)に亡くなり、天智の子、大友皇子が太政大臣のまま、政治を担当していたのです。 この時、後の天武天皇、大海人皇子は、闘病中の天智天皇の意中の人物が子息の大友の皇子であることを知り、剃髪して仏門に入り、吉野に脱出したのです。671年10月の出来事です。大津にいたのでは、いつ刺客を向けられるか分からない。飛鳥から大和一帯なら、自分の支持者も居て身の安全を確保しやすいと考えたのです。天智は12月に亡くなりました。この時代、頼朝・義経兄弟をとってもそうですが、名門の家柄では兄弟といえども、乳母・傅役が違いますから、親しい肉親の情などというものは、互いに持ち合わせておりません。 そこには食うか食われるかの権力闘争が存在するケースが多いのです。この場合がまさにそうでした。天智は家臣の信望を集める弟大海人の存在が、息子にとって極めて危険であることを知っていました。大海人の正妻、後の持統天皇は天智の娘で大友皇子の母違いの姉ですが、両者に姉弟の情は見られません。息子の草壁皇子を皇位につけることを考える母は、何としても夫を守り夫に皇位に就いてもらいたいと、弟の追い落としに積極的に協力していくのです。さて、吉野に隠棲しながら、大津宮の情報収集に怠りのなかった大海人らは、次第に吉野も安全と言いきれないと考え、支持者の多い、東国(東海地方)に下って兵を集め、挙兵する腹を固めます。大津の朝廷でも、大海人側の情勢を探っていますから、この脱出策を把握するのですが、事が漏れたことを察知した大海人側は、この日、決死の覚悟で、替え馬の用意もないままに、吉野の離宮を出発。敵側の伊賀越えを敢行して、伊勢に出、鈴鹿と不破の関を占領して、東海・東山地方の兵を集め、美濃に本営を設けます。こうした一連の出来事から、この日6月24日が壬申の乱の始まった日とされているのです。 大海人の挙兵を知り、大海人を慕う武人の多くは、大海人軍に馳せ参じます。最後は決断と人望が勝敗を分けたというべきでしょうか。戦いは大海人側の圧勝に終ります。 近江、大和で敗れた大友が、自害して果てたのは、7月23日のことでした。朝廷と地方の有力者を2つに割った内乱は、こうして僅か1ヶ月で、大海人(後の天武天皇)側の勝利に終ったのです。ところで、壬申の乱の記述は、戦前の国史教科書には、全く記述がありません。天皇家の諍い、それもむき出しの権力闘争が存在したなどと、国民に知られては、天皇家のイメージが崩れる危険が高いと判断され、南北朝の争いと共に、教科書から抹殺されていたのです。
2016.06.24
コメント(16)
-
家永教科書訴訟第2段始まる 23日の日記
クロニクル 家永教科書訴訟第2段始まる1967(昭和42)年6月23日この日、東京教育大学(現在の筑波大学です)の家永三郎教授は、ご自身がお一人で執筆された三省堂版の日本史教科書『新日本史』が、不合格処分を受けたことに関して、この日、「不合格処分の取り消し」を求める行政訴訟を起こしました。1965(昭和40)年6月の第1次訴訟は、教科書検定を違憲として訴え、国に賠償を求める「国家賠償請求」で、教科書検定は憲法に違反する検閲にあたり、違憲であることを訴えた民事訴訟でした。そちらは、賠償請求を勝ち取ることで、教科書検定の違憲性を浮かび上がらせようという絡め手作戦だったのに対し、こちらは正面から違憲判決の獲得を狙ったものでした。こうして、家永教科書訴訟は、2つの裁判が平行して進められることになったのですが、この裁判は、歴史に限らず教科書にしては珍しい、数名の著者による共同執筆ではない、家永氏1人による単独執筆であったこと、出版社である三省堂が、文部省による嫌がらせや、右翼による妨害をものともせず、敢然と著者に協力して、背後から訴訟を支えたことの2点に支えられていたことを、ここでは指摘しておきたいと思います。
2016.06.23
コメント(12)
-
有権者1億人突破 22日の日記
クロニクル 有権者1億人突破2000(平成12)年6月22日16年前のことです。この日、第42回衆院選が行なわれました。与党は後退しましたが、多数を確保し、他方で民主党も議席数を伸ばしました。しかし、この選挙で特筆すべきことは、選挙人名簿の確定の結果、名簿に登載された20歳以上の有権者数が、初めて1億人を超えたという事実です。総人口は1億2千万人台でしたから、いかに少子化が進んでいたかが分かりますね。それから16年、少子化対策という言葉は良く耳にしますが、掛け声ばかりで有効な手が打たれていない現実が、浮かび上がります。
2016.06.22
コメント(18)
-
新党さきがけ結成 21日の日記
クロニクル 新党さきがけ結成1993(平成5)年6月21日あれから23年ですか。この日の3日前に、自民党から造反議員が出た結果、野党提出の宮沢内閣不信任案が可決成立しました。6月18日のことでした。宮沢首相は、ただちに衆議院を解散し、国民の信を問うたのです。自民党の造反組が、新党を結成するのは、当然視されていたのですが、この日、小沢新党にまさに先駆ける形で、武村正義議員を代表とする新党さきがけが結成されたのです。小沢新党とも言える「新生党」の結成は2日後の23日のことになります。さて、この「新党さきがけ」の結成に参加した議員の中に、はとぽっぽさんとスッカラカンさんのお2人も加わっていました。それだけではありません。前原誠司、玄葉光一郎、枝野幸男、荒井聰らの各氏の名も記されていますから、かつての民主党の反小沢グループの幹部のほとんどは、さきがけ出身ということになります。 現在の民進党の岡田代表は、労組票を手放したくないらしく、旧社民党寄りの姿勢をとっていますから、さきがけ出身の皆さんは、自民党内の保守穏健派と組んで、戦争政策を推進するグループと対峙する路線をとった方が、議席も伸ばせると思うのですが、そちらにも踏みきれないようですね。彼らも泣かず飛ばずで、かつての熱気というか勢いが感じられないのが、残念です。 、
2016.06.21
コメント(18)
-
GHQ第一次追放解除を指令 20日の日記
クロニクル GHQ第一次追放解除を指令1951(昭和26)年6月20日65年前のことです。この日、GHQの指示を受けてた吉田内閣は、第一次追放解除を発令しました。ここに、戦犯として公職を追放されていた石橋湛山、三木武吉ら政財界人2,958人が、公職に復帰できることになりました。GHQは当初、憲法の前文にある如く、日本が再び軍事大国化を目指す事がないようにすることを目的に、日本の民主化を徹底したのですが、中国の社会主義化と、1950(昭和25)年6月の朝鮮戦争の勃発で方針を転換、日本を社会主義封じ込めの最前線とするべく、再軍備を奨励し、同時に戦犯の追放解除を示唆し、喜んだ政府がただちにそれに応じた結果が,この日の解除となったのでした。このうち、石橋湛山氏は、鳩山一郎氏に続く、第2代の自民党総裁になりました。総裁選で優勢だった岸信介氏を決選投票で逆転して総裁に就任したのですが、病に倒れて病床から退陣を表明、岸氏に首相を譲りました。引き際の見事さの目だった、爽やかな政治家でした。平和主義者だっただけに、戦犯だったことがとても意外でした。三木武吉翁は、鳩山側近として、自由党の大野伴睦と共に保守合同を影で支えた黒子役でした。
2016.06.20
コメント(14)
-
丹那トンネル貫通 19日の日記
クロニクル 丹那トンネル貫通1934(昭和9)年6月19日静岡県の熱海駅と函南駅の間を通る丹那トンネル。ご存知ですよね。この丹那トンネルが貫通したのが、82年前の今日でした。難工事で完成が遅れたため、清水トンネルが先に完成していましたから、延べキロ数は国内第2位となりました。貫通後は、速やかに利用されるようになりますが、丹那トンネルの開通まで、東海道線は、現在の御殿場線の線路を使って、沼津に出ていました。そのため、経費の面でも、時間の面でも、大いに助かったと言われています。なお、トンネル内で排気が出来ないため、トンネル内については、蒸気機関車ではなく、電気機関車がこの時代から使用されたそうです。
2016.06.19
コメント(14)
-
大森貝塚発見者モース博士来日 18日の日記
クロニクル 大森貝塚発見者モース博士来日1877(明治10)年6月18日139年も前になるのですね。この日、日本滞在中に大森貝塚を発見することになる、米国人の動物学者エドワード・モース博士が、助手や学生たちと共に来日しました。日本の貝類の研究が主目的でした。飛行機のない時代ですから、到着は当然ながら横浜港になります。モース博士は、横浜に滞在中の2日後の20日に文部省顧問で旧知のマレー氏を訪ねるため、横浜から汽車で新橋に向かいます。その途中、汽車は大森海岸を通ります。車窓から日本の風物に見入っていたモース博士は、白っぽい崖を発見、そこが貝塚であるに違いないと直感したのでした。この日、面会した旧知のマレー氏等からモース博士は、全く予期していなかった東京大学教授への就任を依頼されます。当時の日本の大学には、雇われ外国人が多く、彼等の尽力で西洋の学問を吸収、次第に成長していくのが、一般的でしたから、モース博士もその1人に選ばれたというところでしょうか。博士はしばしの塾考の後、申し出を受諾します。東大教授となれば、文部省の後援を得て大森での発掘がやりやすくなると考えたことは、大いにありえるだろうと、私は想像しています。博士の東大での初講義は、9月の12日に行なわれ、その4日後16日の日曜日には、はれて学生たちと大森海岸を訪れ、そこが貝塚に間違いないことを確認します。モース博士の報告は,大変なセンセーショナルを呼び、大森海岸の名は一躍全国に知れ渡ります。ここに、日本の考古学がはじめて産声を上げました。新しい学問が誕生したのです。モース博士は2年後の1879年に東大を退職、米国に帰りますが、それまで精力的に日本各地を調査して歩き、日本の考古学と人類学の揺籃期に大きな足跡を残しました。
2016.06.18
コメント(12)
-
中国水爆実験に成功 17日の日記
クロニクル 中国水爆実験に成功1967(昭和42)年6月17日49年前のこの日、中国政府は水爆実験を実施、成功した旨を発表しました。前年8月に始まった文化大革命が、益々激しくなっている最中の出来事でした。こうして中国は米ソに続く核大国への道を、フランスと共に走り出しました。核の連鎖どこまで続くのでしょうね。
2016.06.17
コメント(16)
-
工場の就業時間制限撤廃 16日の日記
クロニクル 工場の就業時間制限撤廃1943(昭和18)年6月16日73年前のことになります。アジア・太平洋戦争中の出来事です。この日、政府は、女性や子どもに対する工場労働の保護制限規定を撤廃しました。激化し、悪化する一方の戦局に対応して、青年男性を兵士として戦場に送り出した結果、労働人口の減少に悩んだ政府は、19世紀に始まる子どもや女性に対する労働制限法、すなわち子供や子を産む存在である母体の保護を目指した就業時間の制限を廃止し、同時に女性や子どもに対する作業規定を見直し、従来は禁じていた作業に従事することも認めました。このことにによって、女性や子どもが、鉱山での坑内作業を行うことが解禁されたのですが、これは明らかに、労働者保護という世界的な労働行政の流れに逆行する、明白な後退を意味していました。冷静な判断ができる政府なら、この時点で戦いをやめていたのでしょうね。その判断すら出来ない政府だったわけですが、戦後70年にして、そんな政府が出てくるかもしれないなと、そんな怖さを最近感じるようになりました。
2016.06.16
コメント(18)
-
暑中見舞い葉書発売 15日の日記
クロニクル 暑中見舞い葉書発売1950(昭和25)年6月15日66年前のこの日、郵政省は初めて暑中見舞い葉書を発売しました。当時の葉書は1枚5円でした。もちろんどんな図案の葉書だったか、小学校2年生だった私が知る由もありませんでした。書中見舞い葉書の売れ行きは、当初は散々だったそうですが、その後の日本経済の成長と共に、次第に広がって行きました。それでも、年賀はがきに比べると、はるかに少ないようですが… 年賀はがきの販売も、年々縮小しているメール全盛の今日、暑中見舞いはがき、いつまで持つのでしょうね。
2016.06.15
コメント(16)
-
ドイツ軍パリ占領 14日の日記
クロニクル ドイツ軍パリ占領1940(昭和15)年6月14日76年前のこの日、ドイツ軍はパリに無血入場を果たし、フランスの首都パリを占領しました。ヒトラー体制下のドイツは、前年1939年の9月1日に、全軍をあげてポーランドに侵攻、ここにイギリスとフランスも対独開戦を決意、9月3日に宣戦を布告、第二次世界大戦が始まりました。英・仏はすぐにもドイツとの戦端が開かれるものと、勢い込んでいましたが、ヒトラーは巧みなジラし戦法に出て、ポーランドから、北欧・中欧・南欧の攻略を優先し、翌40年春までは、いっこうに西部戦線のドイツ軍を動かそうとせず、巧みに英仏連合軍の気勢を削ぐ作戦を取りました。宣戦布告後、すぐにも独軍との戦闘が始まると受け止めていた英仏軍は、次第にこの戦争を「奇妙な戦争」と呼び、無意識の内に士気は緩んでいたのです。このため、5月に入って、突如ベネルックス3国に侵攻したドイツ軍が、進撃の速度を緩めずに、対仏国境を越えると、士気の緩んだ英仏連合軍は、そのスピードについて行けず、30万人の大部隊は敗走を重ねて、遂にダンケルクに包囲されたのです。ここで、到着した英海軍船に、辛うじて救出されたのです。緒戦は見事な敗北に終ったのです。勢いに乗ったドイツ軍は、ベルギー国境からフランスに進出。この日、無血でのパリ占領となったのです。それにしても、英仏連合軍、なぜ攻めてこないドイツ軍に付き合って、自ら仕掛けなかったのでしょうね。 敵が攻めてこなければ、何か攻められない事情があるに違いないと、自ら仕掛けるのが普通です。攻めていれば、指揮が緩むこともなかったでしょう。英仏連合軍の緒戦の敗退は、将軍達の無能に寄る所が大きかったように思います。 フランス軍で、積極攻撃を主張したのは、まだ若かったドゴール大佐(開戦時の肩書き)ただ1人でした。
2016.06.14
コメント(16)
-
金融ビッグバン最終答申出る 13日の日記
クロニクル 金融ビッグバン最終答申出る1997(平成9)年6月13日19年前のことです。この日、証券取引審議会・金融制度調査会・保険審議会は、金融制度の抜本的改革「日本版金融ビッグバン」を最終答申しました。 「日本版金融ビッグバン」の口火を切ったのは、当時の橋本首相の諮問機関だった経済審議会の行動計画委員会ワーキンググループでした。同グループは「2000年3月までに金融の規制を撤廃し、利用者本意の金融システム」を作ることを提言したのです。 幅広い競争を実現する、資産取引を自由化する、規制・監督体制を見直すの3点の目標も示されました。橋本首相は、この提言を受け、銀行・証券・保険の相互参入の促進や、株式売買手数料の自由化など、金融分野全般にわたる規制緩和策を、2001年までに実施するよう指示しました。この日の答申は、この首相指示を受けてのものでした。しかし、この指示と答申には、次ぎのような限界がありました。第1に、不良債権処理の仕組みが明示されていないこと、第2に、肥大化する公的金融や財政投融資は蚊帳の外におかれていたこと、第3に、税制の問題が棚上げされていたこと、です。 果せるかな、多額の不良債権を抱えた金融機関の破綻が相次ぎ、日本版ビッグバンは、多難な船出を迎え、最終的に実現する時期は少し遅れますが、現在では、政府系金融の整理も一応進行し、財政投融資も整理されつつあります。 なお、NYやロンドンの市場には見劣りがしますが、答申から19年の節目で見ると、変化はゆっくりとしか進まない日本にしては、途中まではまずまずのペースで進んでいたようにも思えます。郵政民営化が交代してからおかしくなっていますが…バブルの崩壊と、どうしようもない財政の窮状が政治家や官僚、そして金融関係者の背中を押し続けたことは確かなのですが…。
2016.06.13
コメント(10)
-
エリツィンロシア大統領に 12日の日記
クロニクル エリツィンロシア大統領に1991(平成3)年6月12日25年前になります。まだソ連邦が存在した時期です。そのソ連邦に属するロシア共和国でも、大統領制が敷かれることになり、この日選挙の結果、エリツィンが初代大統領となることが決まりました。この年8月19日、クリミア半島の別荘で休暇を楽しんでいたゴルバチョフソ連大統領が、反対派のクーデタで、別荘に幽閉される事件が起きたとき、ロシア市民と軍部の前でクーデタ派を糾弾する大演説を行い、世論を見方にゴルバチョフを救出したのが、エリツィンでした。ここに両者の力関係は逆転し、年末のソ連邦解体に繋がっていったのは、記憶に新しい所です。
2016.06.12
コメント(16)
-
日本列島改造論発表 11日の日記
クロニクル 日本列島改造論発表1972(昭和 47)年6月11日44年前のこの日、田中角栄通産大臣が、持論の日本列島改造論をまとめて発表しました。 沖縄返還を花道に総理・総裁の辞任を表明していた佐藤栄作首相の後継総裁を決める総裁選へ望む、角栄流の事実上の政策発表でもありました。 この公約を引っさげて、田中角栄は7月5日の総裁選に勝ち、7日に第一次田中内閣が誕生する運びとなります。さて「日本列島改造計画」の内容ですが、当時一般に伝えられた通りで、およそ次ぎの3点にまとめることができるように思います。 (1)人口の過密と過疎を同時に解消するために、工業地帯を再配置する (2)地方に25万人の都市を建設する (3)全国に新幹線・高速道路・情報網を整備するこの3点を柱として、農村と都市、太平洋側と日本海側の格差を是正しようという壮大なビジョンでした。雪国出身の政治家ならではの発想といえましょうか。国内の格差はいまだ埋まらず、地方の悲鳴は、当時よりむしろ切実で悲痛なものとなっているのは、構想は理解出来ても、実現に向けての手法に大きな問題があり、その時受けた大きな傷がいまだに癒されないままに、現在まで引きづっているからと、言えなくもありません。 当時彼の構想を実現するには、「ペルシャ湾のホルムズ海峡から、延々日本まで原油を運ぶタンカーの行列が続くほどに、大量の原油輸入が必要になるが、果してそれは可能なのか」という至極まっとうな批判がありました。それは世界の原油消費のバランス、世界の経済秩序を意識した批判だったのですが、この懸念は翌年秋、第一次オイルショックの発生によって、現実のものになりました。72年当時の原油価格の平均は、1バーレル3ドル以下でしたから、列島改造計画そのものが、原油は無尽蔵であり、安価でいつまでも輸入出きるという、幻想の上に立っていたということになります。夢破れた後に、この失敗を反省しての、全く別の構想がを牽引する政治家が現れず、彼の構想の一部つまみ食いだけが、今に至るもチマチマと続けられていますね。これでは日本経済と日本の元気の再構築は出来そうもないですね。オイルショックの結果、この計画は、地方を含む土地価格の急騰、物価の急騰とインフレを誘発しただけで、実現不可能となりました。とりわけ、地方の工業化計画に淡い期待を抱いた地方に、大きな爪あとを残したのです。この地方の傷が、85年以降のバブル期に、「あの時やれなかったことを、今なら」という雰囲気を醸し出し、今度は工業都市ではなく、リゾート計画として、再び過大な投資を促して、再度の大きな傷を残すことになりました。 現在の地方の困難は、この2度の誤算によって増幅された結果であるように思います。
2016.06.11
コメント(14)
-
ペルー大統領にフジモリ氏 10日の日記
クロニクル ペルー大統領にフジモリ氏1990(平成2)年6月10日26年前のこの日、南米のペルーで行なわれた大統領選挙で、日系人のアルベルト・フジモリ前国立農科大学長が、下馬評を覆して当選しました。日系人が、その移住先の国で、政治上のトップの地位につくことは、近代日本にとって、初めての事でした。この年の選挙で、本命視されていた候補者は、クリオーリョ(現地化した白人)層の地主と利害を共有し、社会の多数を占める貧農層の要求を、無視し続けていたのです。当初、前評判の高くなかったフジモリ氏は、土地改革を公約に掲げて、貧農の支持を受け、下馬評を覆して、当選しました。その後、2000年11月まで、10年間大統領の任にありましたが、退任後在職時の強権的な行動が批判され、現在は獄中にあります。先週ペルーでは大統領選の決選投票が行われ、フジモリ氏の令嬢ケイコ・フジモリ氏が、稀に見るデッドヒートを展開中ですが、最終結果が出るまで、なおしばらく時間がかかりそうですね。地方の貧困層にフジモリ支持が高いようなので、結果は最終結果発表までもつれそうです。
2016.06.10
コメント(12)
-
有島武郎心中死 9日の日記
クロニクル 有島武郎心中死1923(大正12)年6月9日93年前のこの日、白樺派に属した作家の有島武郎が、婦人公論記者の波多野秋子と、軽井沢の有島の別荘で心中しました。時に有島46才、波多野30才でした。有島は『白樺』の同人で、『カインの末裔』や『生まれいずる悩み』で、文壇にデビュー。『或る女』や随想風の評論『惜しみなく愛は奪ふ』などで、多くの読者に親しまれていました。そこに、第一次世界大戦後の不況と相俟って、社会運動が高まり、知識人への批判が高まる中で、有産階級の知識人の苦悩を『宣言一つ』として発表し、北海道の有島農場を小作人に開放するなど、人道的な社会主義者として注目を集めていました。有島と波多野は、共に配偶者がいたのですが、作家と編集者の立場を超えて、互いに惹かれ合うようになり、愛人関係となったのです。それを知った波多野の夫が、2人の心中の前日、有島に金銭を要求、人道主義者の有島に出来ない事を知りながら、金で妻を売ると有島に迫りました。これがきっかけとなり、前途を悲観した2人は、発見の遅れる場所をと、有島の別荘に逃避、そこで心中に至りました。2人の死体の発見は、およそ1ヶ月後の7月7日でした。涼しい軽井沢とはいえ腐乱し、変わり果てた姿だったと報じられています。これがおそらく、谷崎や佐藤春夫であったなら、大喜びで金を払い、妻と離別して堂々と再婚していたのでしょうね。人道主義者の悲劇がここにあったように感じられてなりません。
2016.06.09
コメント(24)
-
大鳴門橋開通 8日の日記
クロニクル 大鳴門橋開通1985(昭和60)年6月8日31年前のこの日、大鳴門橋が開通しました。本州四国連絡橋の3本のうちの1本、神戸ー鳴門ルートのうち、淡路島と徳島県鳴門市を結ぶ、鳴門海峡をまたぐ橋でした。大鳴門橋の開通で、橋上から鳴門の渦潮を見ることが出来るようになり、明石海峡大橋も完成すると、徳島の皆さんが関西に出る上では、格段に利便性が向上しました。私は5月に2度、8月に1度の3度この橋を通っているのですが、残念ながら橋上から鳴門の渦を見ることは出来ませんでした。3度のうち5月の2度は快晴だったのですが、そのために水蒸気が吸い上げられ、海面上は白濁してしまっていたのです。8月は土砂降りでの通過でした。ついてないですね。
2016.06.08
コメント(16)
-
衣笠選手2000試合連続出場 7日の日記
クロニクル 衣笠選手2000試合連続出場1986(昭和61)年6月7日30年前のことです。この日広島東洋カープの衣笠衣祥雄選手が、日本プロ野球史上初の2千試合連続出場を達成しました。衣笠選手は、京都の平安高校を卒業、1965年に広島カープに入団。4年後の1969年のシーズンからレギュラーに定着、背番号の28番から、人気漫画『鉄人28号』にひっかけて、鉄人のニックネームで親しまれるようになったのですが、連続試合出場を続けるうちに、本当の鉄人として意識されるようになりました。衣笠選手の連続試合出場の危機は、1979(昭和54)年8月1日の巨人戦で、西本聖投手のシュートボールが左肩を直撃、左の肩甲骨を骨折する重傷を負った時でした。しかし衣笠選手は、翌日の試合に代打として出場、江川投手の速球勝負に振るスイングで対抗、3級三振したのです。スタンドからは、巨人ファンを含めて、大きな声援が寄せられました。この時から衣笠選手は、本当の意味で鉄人と称されるようになりました。因みに衣笠選手の連続出場の最初の1試合目は、1970(昭和45)年10月19日の巨人戦でした。2千試合連続出場は通過点で、彼の記録はさらに伸び、1987(昭和62)年6月13日の中日ドラゴンズ戦で、ルー・ゲーリック選手の持つ米大リーグの連続出場記録を更新する、2131試合連続出場の世界新記録を達成、この年10月22日の年度最終試合での現役引退まで、2215試合連続出場という、輝かしい記録を残しました。衣笠選手の通算安打数は2543本、本塁打数は504本と、選手としての記録も立派です。私はというと、頭髪の薄くなった現役晩年の衣笠選手が、アートネイチャーのCMに出演していた姿に、大変親近感を持ちました。
2016.06.07
コメント(10)
-
大正池誕生 6日の日記
クロニクル 大正池誕生1915(大正4)年6月6日101年前の出来事です。この日活火山である焼岳が噴火し、流れ出した泥流が梓川の清流をせき止めました。こうして誕生した池は、大正池と名付けられました。池には噴火によって立ち枯れた木々が残る、珍しい景観が生まれ、そこから、13年後の1928(昭和3)年、大正池のある「上高地」は、「名勝及ビ天然紀念物」に指定されました。下流には、東京電力の霞沢水力発電所があり、大正池を発電所の調整池として利用していることから、上流から流入する土砂は、現在も毎年、冬場を利用して、発電事業者の東京電力が一定量(1万立方メートル~3万立方メートル)を浚渫しています。東電が浚渫をやめると、10年足らずで大正池は土砂で埋まり、姿を消すことになるのだそうです。
2016.06.06
コメント(18)
-
第3次中東戦争始まる 5日の日記
クロニクル 第3次中東戦争始まる1967(昭和42)年6月5日59年前のこの日、午前8時45分、イスラエル空軍がエジプト空軍の全ての基地を奇襲、滑走路を破壊し、空軍機を破壊し尽くしました。素早い隠密行動にあって、エジプト空軍機は一機も応戦に飛び立つことが出来ないままに、なすすべなくイスラエル軍機の攻撃に晒されたのでした。遮るもののない地域では、制空権を握った側が大勝するのは自然なことです。この戦争では僅か6日間の間に、イスラエルはエジプト領シナイ半島に、エジプトが実効支配していたガザを、東エルサレムを含むヨルダン領のヨルダン川西岸地域を、さらにシリア領ゴラン高原までも占領することに成功します。まさにイスラエルの大勝利でした。エジプトの指導者ナセルは、自慢の空軍が一戦も交えずになすすべもなく、敗れ去ったことにショックを受け、一時は辞意を表明するほどに落ち込んだのですが、アラブの危機とパレスチナ難民問題の深刻さを認めて、翻意する一幕もありました。しかし、この戦争は大量のパレスティナ難民を生みます。この時難民となった人達は、先祖伝来の地をイスラエルに奪われて難民となり、以来現在まで、自分の郷里の地に帰ることも出来ずに、難民としての生活を送っています。そうした彼等、彼女等が苦心の末に築き上げたのがパレスティナ解放機構(PLO)だったのです。 その後、イスラエルは、国連決議で、第3次中東戦争での占領地の一切を関係各国に返還するよう命じられながらも、それを無視し続け、僅かにイスラエルとの関係を改善したエジプトにシナイ半島を返還したのみで、今日まで占領地域に居座り続けています。現在では国際世論に配慮したのか、ガザとヨルダン河西岸にパレスティナ人の自治区の存在を認めていますが、それはどことも自由往来ができない、不自由極まりない世界に留まっています。 これでは、中東地域に平和が訪れるわけがありません。中東地域は、イラクやシリアも含めて、きなくさい状態がなお続きそうです。
2016.06.05
コメント(14)
-
張作霖爆殺 4日の日記
クロニクル 張作霖爆殺1928(昭和3)年6月4日88年前のこの日、関東軍(日本の満州派遣軍は、当時こう呼ばれていました)の河本大作大佐らは、満州軍閥の張作霖を奉天(現瀋陽)郊外で爆殺しました。この年5月、蒋介石の率いる国民革命軍による北伐は勢いを増し、北京解放を間近に控える勢いを示していました。ここにおいて、日本の田中義一内閣は、戦火が満州に飛火し、東三省(奉天、吉林、黒竜江の3省)における日本の権益が内戦に脅かされることを嫌い、張作霖に戦いを避けて満州に避難する事を勧めました。張作霖は、迷った末に勧告を受け入れ、前日3日の早暁に北京を経ったのです。河本らは、張を爆殺することで生じるであろう混乱を利用して、関東軍を出動させ、満州を占領しようと企んだのでした。しかし、予想された混乱はおきず、関東軍は出撃のチャンスを掴むことは出来ませんでした。この計画は失敗しました。 日本の田中内閣は、事件の真相を国民に隠し、「満州某重大事件」としか発表しませんでした。こうした事なかれ主義が、軍部をつけ上がらせ、3年後の満州事変をはじめ、その後の軍部の大暴走に繋がりました。暴走に繋がるかもしれない芽は、早いうちに摘んでおくことが大事ですね。
2016.06.04
コメント(16)
-
国連環境会議開幕 3日の日記
クロニクル 国連環境会議開幕1992(平成4)年6月3日今では環境問題は、誰もが重視するテーマの一つとなっています。この環境問題が大きく取り上げられるようになったのは、24年前の今日開幕した「環境と開発に関する国連会議」(通称国連環境会議、地球サミットとも呼ばれます)がきっかけでした。この会議はブラジルのリオデジャネイロで、「人類共有の持続可能な発展」をテーマに、14日まで12日間に及びました。そこでは「かけがえのない地球」を合言葉に、地球温暖化対策を中心に地球環境の改善が話し合われました。その後も会議は続けられ、1997年12月の京都会議で、温室効果ガスの削減目標を盛り込んだ、「京都議定書」が採択されました。これが今でも話題になる「京都議定書」ですが、温室効果ガスを大量に撒き散らしている米国が、自国の都合でこの議定書を批准せず、現在も有効な方策が取られているとは言えない状況にあります。 結局人間の身勝手が、地球を壊してしまうのかもしれませんね。
2016.06.03
コメント(12)
-
竹下内閣総辞職 2日の日記
クロニクル 竹下内閣総辞職1989(平成元)年6月2日27年前のこの日、竹下内閣が総辞職し、後継として宇野宗佑内閣が成立しました。内閣の交代と言う点では、確かに27年前の今日の話なのですが、実を言うと、竹下首相がリクルート事件等で、高まった政治不信の責任をとって、辞意を表明したのは、1ヶ月以上も前の、4月25日のことだったのです。1ヶ月以上も後継首相が決まらなかったのは、後継候補であるべき派閥の領袖クラスが、皆リクルート事件の関係者だったために、次期総裁の候補から外れ、清廉でこの人ならと言われた伊東正義元官房長官や、後藤田正春元官房長官らは、総裁と首相の椅子を望まず、最後に総裁候補とは言えなかった宇野宗佑議員が漁夫の利を得たのでした。しかし、宇野は女性問題をマスコミにたたかれ、7月の参院選に大敗、7月24日に責任を負って、退陣を表明しました。この間2ヶ月足らずという超短命内閣となりました。
2016.06.02
コメント(12)
-
片山内閣の誕生 1日の日記
クロニクル 片山内閣の誕生1947(昭和22)年6月1日69年前といえば、近代日本がはじめて戦争に敗れて2年弱。敗戦後の混乱期でした。前年4月10日に、日本女性がはじめて参政権を行使した衆議院選挙が行なわれて、僅かに1年でしたが、この年4月25日に再度の総選挙が行なわれ、日本社会党が143議席を得て第1党の地位を獲得しました。しかし、衆議院の過半数には遠く、第2党の自由党との連立を模索したのですが、合意に達しませんでした。そこで、民主党、国民協同党の2党に、参議院の緑風会(参議院に無所属で当選した58人の議員が結成し、後92人にまで増加した、参議院の最大会派でした)も加えた3党1会派の連立内閣が、この日発足しました。首相には第1党の党首だった、日本社会党の片山哲が就任しました。日本で初めて社会主義者が首相となったのが、69年前の今日でした。そして片山首相は、社会主義者であると同時に、熱心なクリスチャンでもありました。その意味で片山はキリスト教的ヒューマニズムに基礎をおく、人道主義的社会主義者でした。クリスチャンの首相もまた日本でははじめてのことでした。こうして誕生した片山内閣でしたが、日本の再建の為にと、賃金と物価の抑制策をとって、労働組合の反発を買い、また党内の左右両派の対立の調停にも失敗、翌年2月10日、在任8ヶ月強で総辞職することになりました。今はない社会党が元気だった時期、日本の戦後政治史の一齣でした。
2016.06.01
コメント(16)
全31件 (31件中 1-31件目)
1