2022年02月の記事
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-

ザ・イヤー・オブ・1981(その161)
『アンチゴーヌ』が名作とされるのは、その登場人物の内面深くに迫っているからです。単純に善(レジスタンス)と悪(ナチス)の戦いではないんですね。クレオンを批判しているわけではなく、アンチゴーヌを批判しているわけでもない。淡々と、登場人物の心の中の葛藤やジレンマを描いています。つまり、クレオンの心情やアンチゴーヌの心の奥にも深く分け入って分析しているから面白い作品に仕上がったわけです。 このようにアヌイの作品の優れた点は、人物の掘り下げの深さにあります。アヌイが知っていたかどうかは別にして、彼の分析力は、八卦を使った分析に非常に近いものがあります。実際に彼の持って生まれた性質を易で読み解くと、面白い結果が出ます。 彼は戌年生まれですから火(離)の魂を持っています。物書きなどの表現者の魂ですね。先祖からは直感力や集中力を示す水(坎)の性質・運命を受け継ぎました。環境は風(巽)ですから、比較的自由に自分の人生を選択できたのではないかと思います。そして全体の運命がやはり水(坎)です。水は、オタク的な性格を表わすのと同時に、深く掘り下げることが彼の運命であったことを示しています。そして、まさにそのように作品の中の登場人物たちを深く掘り下げて、彼らの心の奥底にある潜在意識まで突き詰めて、物語に仕上げたわけです。易の達人であったかのような印象を受けます。彼が自分の作品を、バラ色(喜劇)、黒色(悲劇)などと色で分類しているのも非常に易的です。少なくても、易的な八つの分類があることには気づいていたのではないでしょうか。さて、『アンチゴーヌ』の成功で劇作家として不動の地位を得たアヌイは戦後、戯曲『ベケット、または神の名誉(Becket ou L’Honneur de Dieu)』(1959年初演)を書き上げます。この戯曲は1964年に『ベケット』として映画化され、大成功を収めます。ヘンリー2世をピーター・オトゥール、トマス・ベケットをリチャード・バートンが演じています。こちらがその映画のDVDです。 この作品はカンタベリーのケント大学とも関係があるので、少し詳しく取り上げましょう。何と言っても、歴史的にも有名なカンタベリー大司教の暗殺事件(1170年)を題材にした戯曲ですからね。 (続く)
2022.02.28
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その160)
スイスの心理学者カール・グスタフ・ユングがいみじくも感じ取ったように、神話の中には人類が普遍的に持つ葛藤や対極の対立、ジレンマなどがしみ込んだ「原型」が詰まっています。原型はまさに易の八卦の要素でもあります。 原型は八卦に置き換えられるんですね。ここで一つだけ断っておきますが、アヌイの戯曲からパリ市民が感じ取った解釈は、人間のある一面を見ているにすぎません。おそらくパリ市民はナチスに対する抵抗劇とみてアンチゴーヌに感情移入したにちがいありませんが、それによってクレオンを間違いだとして断罪することもできないんですね。そこには人間の二面性のバランス、易の対極のバランスの問題があるからです。どちらにも偏り過ぎてはいけないんです。アヌイもそのことに気づいていて、後期の作品ではアンチゴーヌ的生き方がもたらす弊害や問題点も炙り出しています。それについては、後で詳しくみてゆきましょう。 ではまず、アヌイの『アンチゴーヌ』を易的な観点から読み解いてゆきます。 アヌイが描くクレオンは基本的に、政治的な妥協点を広く探る、いわば受容力・包容力をもつ坤(大地)の要素(性質)を強く持っています。ですから、アンチゴーヌの言い分にも耳を傾けつつも、法(艮の性質)と制度・組織(震の性質)を守らなければならない王(乾の性質)として、妥協点をなんとか見つけようとあの手この手でアンチゴーヌを説得しようとするわけです。 これに対して、アンチゴーヌは王と法に抵抗する自由(巽の性質)の代弁者として描かれています。しかしながら、その自由に寄り添うように持っているのが、兄を埋葬したいという、人間関係や家族を尊ぶ性質(震の性質)です。つまり、法律とも近い関係にある家族制度を重視するというジレンマをかかえていることになります。完全に自由ならば、兄の埋葬にもこだわらないはずですからね。心の中で、法や制度を重んじる性質があるから、クレオンに説得されそうになるわけです。 最終的にアンチゴーヌが選んだ決断は、クレオンが持つ「乾」や「坤」、「艮」の性質ではなく、ある意味「震」とも決別する「巽」の性質でした。もし彼女が「震」を貫いたら、伯父であるクレオンの顔を立てたはずですからね。「巽」は人を自由にしますが、反面タガが外れて暴走する性質もあります。制度や法を拒絶して暴走したアンチゴーヌは、自分の意志で死を選びます。これによって彼女が築いた人間関係は次々と崩壊します。おそらくアンチゴーヌは、魂として持っていた性質は「巽」、先祖から与えられた性質は「震」、環境がもたらした性質は「艮」で、運命全体ではやはり「巽」(あるいは「震」)だったのではないかと思われます。 一方、「坤」と「乾」の性質を持つクレオンは、彼の包容力が容認する妥協の産物が法の遵守であるわけです。「乾」の象徴である王として法を守らなければ示しが付きませんからね。同時に人間関係も場合によっては、法のために後回しにしなければならなくなります。彼がアンチゴーヌに見せた心情を酌むと、彼にもやはり人間関係や家族制度を重視する「震」の気質があったように思われます。 しかしながら、彼は「震」を捨て、「艮」と「乾」を優先させました。それによって、彼もまた人間関係が壊れてボロボロになるわけですが、元はと言えば、彼の「坤」の性質がもたらした結果でもありました。というのも、「坤」には、受容力・包容力がある反面、矛盾するものを受け入れる傾向があるため、内部崩壊しやすくなるんですね。アンチゴーヌのような“矛盾”が出現すると、たちどころにほころび始めます。おそらくクレオンは、魂がもっていた運命が「坤」(もしくは「震」)、先祖がもたらした性質が「乾」、環境がもたらした性質が「艮」で、運命全体では「震」(もしくは「坤」)だったのではないでしょうか。 (続く)
2022.02.27
コメント(0)
-
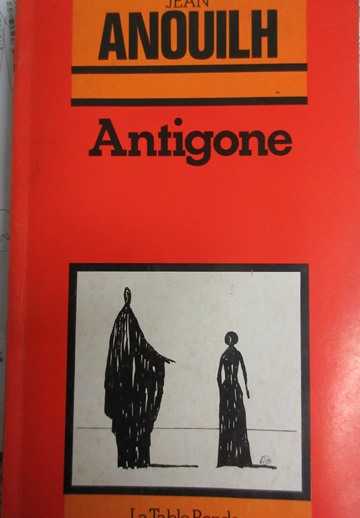
ザ・イヤー・オブ・1981(その159)
『アンチゴーヌ(Antigone)』は、古代ギリシャの三大悲劇詩人のひとりソフォクレスが紀元前5世紀に書いた『アンチゴネ』をアヌイが翻案した戯曲です。1944年にナチス占領下のパリで上演されました。 事件自体は、ソフォクレスが書いたとおりに展開します。ただしアヌイは登場人物の心の内を掘り下げて、対極にある二つの性質を浮かび上がらせているんですね。易でいうならば、それは7(山)と8(大地)という対極の対立・葛藤であり、2(沢)と4(木)の対立・葛藤であるということができます。こちらが当時購入した本。1・85ポンド(約925円)で購入しました。 物語は次の通りです。 アンチゴーヌの父オイディプスの死後、オイディプスの二人の王子(アンチゴネの兄)はテーバイを1年交替で統治するはずだったのですが、政権の独占を狙って対立、戦って相打ちとなり二人とも死んでしまいます。そこで彼女の伯父のクレオンが王となりますが、二人の兄弟のうち結果的に祖国を攻撃した形になったポリニスの遺骸を、国の法律に従って野ざらしにします。それを見て兄ポリニスを不憫に思いアンチゴーヌは、国法を破って遺骸に土をかけます。 国法を犯したアンチゴーヌは衛兵に捕まります。国法を犯した者は死罪です。クレオンは姪を死罪にしたくないので、捉えた衛兵の口を封じてまで救おうとしますが、伯父の説得にもかかわらずアンチゴーヌはポリニスの埋葬を主張して譲りません。仕方なく伯父は死罪を宣告、アンチゴーヌは地下墓地の幽閉先で自害します。それを知った彼女の婚約者であったクレオンの息子エモンも自害、クレオンの妻も絶望して自殺します。 以上ですが、どうしてこれが占領下のパリで熱狂的に支持されたかと言うと、パリの人々は死をかけて純粋な生き様を貫こうとするアンチゴーヌにレジスタンスの戦いを重ね、現実と妥協して生きて行くことを選ぶクレオンに対独協調派のペタンの姿を見出したからです。 しかしながら、この劇は単なる政治劇ではないんですね。先ほども指摘したように、対極のジレンマという人類普遍のテーマを浮き彫りにしているところが面白いのです。 (続く)
2022.02.26
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その158)
1910年という同じ戌年生まれのアヌイとジュネという二人のジャン。フランス近代文学史に偉大な足跡を残した二人の劇作家が、まったく異なる作品を書き続けて同時期を生き抜いたというのは、非常に興味深いことです。そこには相違点があるだけでなく、共通点も存在するからです。易を使って比較対照するにはもってこいですね。 まずはジャン・アヌイからみてゆきましょう。 アヌイは1910年6月21日、フランス・ボルドー近郊の小さな村セリゾール(Cérisole)に生まれました。バスク人の血を引いており、父親は仕立屋で母親はヴァイオリニストでした。8歳でパリに移り、親類が支配人をしている劇場に10歳のころから入り浸るようになります。演劇熱が高じて家で劇を上演するほど熱中します。まさに魂に、易でいうところの「火」を持った少年だったわけですね。 そのような演劇好き少年の人生を決定的にしたのは、名優・演出家で知られるルイ・ジュヴェ(Louis Jouvet)の演出により1928年に初演された『ジークフリード』(ジャン・ジロドゥ作)を見て感激したからだとされています。そのころ彼は、ソルボンヌ大学の法学生になったばかりのころだったのですが、経済的に行き詰まり18カ月で中退、広告会社のコピーライターとして働き始めます。彼はこの仕事が気に入ったらしく、下世話なキャッチコピーを作りながらも言葉の簡潔さと的確さを学んだと自ら皮肉交じりに話しています。確かに彼の戯曲を読むと、歴史上の偉人・貴人でも卑近な言葉を使って描いています。彼の戯曲の特色でもあります。 アヌイは31年に女優と結婚、34年には娘が生まれます。そのころ彼は、収入の足しにしようと戯曲を書き始めますが、作品はパッとせずに貧困に苦しみます。25歳のときには、青年期にあこがれた名優兼演出家のジュヴェの秘書として雇われましたが、あまり馬が合わず、やがて袂を分かちます。 劇作が成功するようになったのは、1937年に書いた『荷物無き旅行者(La voyageur sans bagage)』からです。そしてナチスドイツのフランス占領下で書かれた、古典を題材とした戯曲『アンチゴーヌ(Antigone)』によって前衛的な劇作家としての地位を不動のものとします。1944年に占領末期のパリで上演されると、抵抗劇としてパリ市民に圧倒的に支持されました。 次回は、ケント大学の授業でも取り上げたこの『アンチゴーヌ』を解説しましょう。 (続く)
2022.02.25
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その157)
1月7日。レント・ターム(Lent Term)が始まりました。3月19日までの10週間にわたって授業が行われます。日本では冬学期ですが、こちらで訳すとすると春学期でしょうか。登録したコースは一年を通したコースですから、改めてコース登録をする必要はありません。そうすることによって、一つのコースを幅広くかつ深く勉強することができるわけです。 新しい学期になって、特に勉強の仕方が変わるわけではありませんでしたが、私が専攻した現代ヨーロッパ演劇のコースは、セミナーをブラドゥビー講師(Lecturer)とクライヴ・ウェイク助教授(Reader)のグループに分けられることになりました。人数を少人数にするためだとの説明がありました。私は後者のウェイク助教授のグループに入りました。 ところで、イギリスの大学の肩書は、一番上がProfessor(教授)、次が Reader(助教授)、そして Senior Lecturer(上級講師)、 Lecturer(講師)です。コースの責任者は、ブラドゥビー講師なのですが、考え方が偏らないようにするために助教授が付いているようでした。結果的にこれが私にとっては、大変な吉とでます。というのも、ウェイク助教授にはそれ以降、ベケットの論文作成などで非常にお世話になるからです。ブラドゥビー講師は当時、新進気鋭の研究者でしたが、彼だと、これほど面倒見は良くなかったであろうと推測されます。ウェイク助教授はとても教え方が上手でした。 その新学期には、何を読んで何を勉強したのでしょうか。ジェームズ・ジョイスの『ユリシーズ』を取り上げたことは既に話しましたね。ところが残念なことに『ユリシーズ』をはじめとする春学期に読んだはずの本がほとんど見つからないんですね。私は捨てるはずがないので、引っ越しの最中に仕舞ったまま、どこかの箱の底のほうに埋まっているのだと思われます。転勤や引っ越しが多かったですからね。致し方ありません。 それでも何とか探し出せたのは、次の本でした。 ジャン・アヌイ(Jean Anouilh)の『アンチゴーヌ(Antigone)』ジャン・ジュネ(Jean Genet)の『 黒んぼたち(Les Nègres) 』 2人とも同じ1910年生まれのフランス出身の作家・劇作家です。奇しくも同じ年生まれの作家の著作がたまたま私の手元に残っていたことになります。 次回からは、この二人の作品と人生について紹介することにいたしましょう。 (続く)
2022.02.24
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その156)
新学期が始まる前夜の寮の食堂は、まるで同窓会のパーティーのような状態。ほぼ一か月ぶりに顔を合わせるので、皆「どうやってクリスマスや冬休みを過ごしたか」を聞いたり話したりするのに大忙しです。笑い声が絶えることはありません。たった一か月弱の休みで、これだけ盛り上がれるのですから凄いですよね。 私も聞かれたので、「冬休み中は、スイスのジュネーブからフランスのボルドーまで、雪の中ヒッチハイクをしながらフランスを旅していた」と答えると、皆、目を丸くして驚いていました。もちろん私よりも破天荒な冬休みを過ごした学生もいたかもしれませんが、私の冒険旅行もかなり一般の学生から見たら「ぶっ飛んでいた」と思います。 多くの学生は親元に帰って、ゆっくりと過ごしたようでした。ただ、私のように海の向こうのはるか彼方から来ている留学生の多くは、寮に留まって静かに過ごしていたようです。私の部屋のご近所のマラウィから来た留学生も寮で過ごしたと言っていました。「静かで良かったよ」と言っていましたから、のんびりと思索にふけるには、休み期間中に寮で過ごすのもいいかもしれませんね。 アジアからの留学生は、お金に余裕のある人は母国に帰り、余裕のない人は寮に残ったりイギリスの友人宅を渡り歩いたりしていました。アメリカからの留学生は、帰国する人もいましたが、むしろこの機会にヨーロッパを旅している人も多かったと思います。 その一人が以前紹介した、後に画家になった米国人女性ジョイスです。彼女は、冬休み期間中はずっとギリシャで過ごしたそうです。特にクレタ島がお気に入りで、大勢の友達ができたとか。「次の休み(春休み)にはクレタ島を再訪するから、時間が合えば友達を紹介し、島を案内するわ」と言って、クレタ島の拠点としている住所を書いてくれました。 まさにその瞬間です。私の中にあるギリシャの過去生の部分が“化学反応”を起こします。 「ギリシャに行かなくては」という考えが浮かびます。それも、クノッソス宮殿のあるクレタ島へ。 ジョイスとは何かあるんですね。初めて紹介されたとき、ジョイスという名前を聞いた私は「ジェームズ・ジョイスのジョイス?」と、思わず聞き返していました。人によっては気を悪くする人もいるかもしれませんが、彼女は「そうよ、そのジョイスよ。よくそう言われるわ」と笑って返してくれました。 私が研究するアイルランド文学を代表する作家の名前を持つジョイスが、ギリシャを紹介してくれたわけです。これが意味のない偶然であるはずがありませんね。 (続く)
2022.02.23
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その155)
たった5日間のパリ滞在でしたが、およそ150年分の文学・芸術史が詰まったパリを堪能しました。そして、1月6日の朝。イギリスに戻る日がやってきました。窓から春を思わせる柔らかな朝の光が差し込んできます。お世話になった「19世紀の部屋」ともお別れです。四角い窓からは、いつものように、パズルのピースのように切り取られた空が見えていました。 その後二回パリを訪れましたが、常に根底にあったのはこの1981年のパリの5日間です。私の中のパリの基準点となり、ここからどこの時代にも飛んでゆけるようになっています。 パリを発つのは名残惜しくありましたが、何と言っても、翌7日からは授業が始まりますからね。そんな感傷に浸っている暇も余裕もありません。早く戻って、授業の予習をしなければなりません。 宿屋の女主人にお礼と別れを告げて、今や第二の故郷となったイギリスへと向かいます。ボルドーからカンタベリーまでのチケットを使って電車でカレーまで出ます。そこからフェリーに乗り換えて、イギリス人がドーヴァー海峡と呼ぶカレー海峡(Pas de Calais)を渡ります。やがてはっきりと見えてくるのは、ドーヴァーの白亜の壁「ホワイト・クリフ(White Cliffs of Dover)」です。イギリスを侵略から守ってきた、自然の防璧ですね。高さ110メートルにも達する断崖絶壁になっています。その断崖が途切れた場所にあるのがドーヴァーです。ドーヴァーから後は、いつも通りのルートですね。カンタベリーの駅からケント大学のダーウィン・カレッジまで近道を早歩きして20分ほどです。 午後4時までには寮に到着していたと思います。預けていたスーツケースを受け取り、再入寮の手続きをして、自室に戻ります。 一か月近くに及ぶ長い旅が終わりました。ぎっしりと体験の詰まった旅でした。その疲れを癒すため、シャワーを浴びてベッドで夕寝することに決めました。午後6時の夕食にはまだ時間があります。それまでは、しばしの休息をとることにいたしましょう。そして、いつものように、まどろむ間もなく、深い眠りに落ちておりました。 (続く)
2022.02.22
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その154)
1月3日か4日の夜にイオネスコの『椅子』を観劇したほかは、4泊5日のパリ滞在中に何をやったか、詳らかには記憶しておりません。覚えているのは、観劇後は夜も深まって人通りが少なくなるので、安ホテルに帰る道が結構暗くて怖かったことです。もちろん、お金が残り少なくなっていたので、交通費を節約するため、行き帰りとも徒歩でした。 日中も同様でした。お金のかかる所は避けて、ひたすらパリの街を歩いていたように思います。観光客が訪れるような「ムーランルージュ」やセーヌ川の遊覧船なども当然、論外なわけです。 それでも、19世紀の佇まいがあちらこちらに残るパリを歩くだけで、私自身は結構、満足しておりました。厳冬の侘しいパリであっても、あるいはそうであるからこそ、その雰囲気は大いに楽しめました。灰色で重たいパリの空の下、何か自分自身が貧乏作家や貧乏画家になったような気分を味わっていました。 大島渚監督の映画『愛のコリーダ』を見に行ったのも覚えています。フランス語のタイトルは『L'Empire des sens(官能の帝国)』です。日本語で上映されフランス語の字幕が出ます。日本語を仏訳するとこうなるのかと随分と勉強になりました。 で、その肝心の「官能の帝国」ですが、かなり刺激が強かったです。1976年に公開された映画で、1936年5月18日に起きた有名な阿部定事件を題材にしたポルノ的な芸術作品として論争を巻き起こしました。日本では検閲に引っかかりぼかしなどで修正されましたが、フランスやイギリスでは無修正。評価も真二つに割れました。 とくに露骨な性描写は論議を呼び、私が見たパリの映画館でも性描写が映し出されると、退出する観客が相次いだので驚きました。公開から4年以上経っていましたから、すでにそれほど大勢の観客がいたわけではありませんが、全体の4分の1(約10人)くらいの人が上映中に映画館を後にしました。 後でケント大学の友人に聞いて知ったのですが、ケント大学でも私が留学する1年前に構内の映画館でこの映画を上映したことがあったのだと言います。英文タイトルは『In the Realm of the Senses (官能の王国にて)』。この時も、この映画を見た学生の半分近くが席を立って映画館を出ていったそうです。大学でも物議を醸した映画だったわけですね。 私の感想ですが、確かにポルノ映画のような描写が続きます。それでも、ちゃんと時代背景を描いていた点で、歴史の一断面を伝える映画として優れていると思いました。安倍定事件という狂気の性的猟奇事件が起きた1936年と言えば、陸軍皇道派のクーデターである2・26事件が発生、結果的に軍部の政治支配力が著しく強化され、戦争という狂気に国民が突き進んでゆく時代でもありました。雪が降りしきる中を行軍する青年将校らの狂気と、その真逆の方向に性愛のために走る被害者・吉蔵の狂気の対比が見事でした。 40年以上前に一度だけ見た映画なのに、今でもその場面を思い出せるということは、やはりそれなりに優れた、記憶に残る映画だったのだと考えています。 (続く)
2022.02.21
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その153)
私はイオネスコの『椅子』に、バランスが崩れて崩壊する8つの易の性質を見出すことができます。それがイオネスコの意識の深層にあったものです。 まず「坎」(集中力、潜在能力)を表わす主人公の老人。彼は深く掘り下げていって発見をする性質の代表です。彼は門番として人生を全うして、多くの事象を見出しました。ところが、彼にはその「発見」を表に出す「兌」(コミュニケーション力)や「離」(表現力)のような性質がなかったわけです。だから彼の「発見」には弁士という「兌」や、派手な発表会という「離」が必要となったわけですね。その弁士も発表会も、語るべき肝心の発見者(主人公)が身投げしてしまったわけですから、活躍の場や意味を喪失してしまいます。当然、老人の「発見」も水泡に帰します。 また、門番であった老人は野心があったら偉くなったかのような口ぶりで述懐します。野心はすなわち、リーダーシップを表わす「乾」が欠如していたことを示します。だから、老夫婦は皇帝が来訪してくれたことを喜ぶわけです。 しかし、その「乾」を象徴する皇帝も、治めるべき確かな国や伝統・文化を持っていないように見えます。というのも、「艮」を表わす「パリにあった古代文明」はとっくに(40万年前に)失われているからですね。偉大な文明を持たない「形だけの皇帝」でしょうか。 「坤」を表わす老婆は、夫である老人の嘆きを母親のように受け止める受容性を持っています。来客を受け入れるために次から次へと椅子を運び込む老婆は、まさに坤の性質(受容力・包容力)そのものです。ところが、あまりにも受容してしまったため、部屋は身動きが取れないほど混雑して、夫とも部屋の端と端で離ればなれになってしまいます。 「震」を象徴する椅子や列席した招待客は、人間関係や身分制度・組織を表わすシンボルです。身動きのできないほど混雑した部屋は、まさに組織や人間関係が行き詰まり、崩壊寸前であることを示していますね。そして、部屋の主人である老夫婦が身投げすることによって、完全に崩壊します。 「巽」の風を象徴する窓は、本来なら自由を表します。確かに身投げはある意味、肉体からの解放であると解釈する人もいるかもしれませんが、自殺はあくまでも逃避。死への束縛を意味しますから、自由とは根本的に違うモノです。その意味で、窓は本来の意味を喪失しています。 このように『椅子』には、イオネスコが易を知っていたかどうかにかかわらず、八卦の要素が詰まっています。 バランスを崩して8つの性質が崩壊するというテーマを描いたバランスの良さが、実はこの劇の完成度を高めているんですね。皇帝や椅子、窓など八卦の要素が一つでも欠けていたら、この戯曲のバランスが崩れるからです。今日においても『椅子』が傑作とされるのはそのためです。 (続く)
2022.02.20
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その152)
私も当時、イオネスコが何を言いたいのか、わからずにいました。不条理演劇は一体何を私たちに語り掛けているのか。それはまさに、そのとき私が書こうとしていた卒論のテーマでした。 わからないままに、当時私は、『椅子』を観劇して何かを感じ取っていました。たとえば目に見えない世界と目に見える世界の存在や、遠い昔に滅んだ文明の存在に思いを馳せていました。それからリズムのような周期性でしょうか。椅子がドンドン増え続け、最盛期を迎えたと思うと、最後は主人公不在となった虚しい部屋(廃墟)だけが残されます。希望と絶望、栄光と挫折(失意)、繁栄と崩壊。一つの文明の崩壊がテーマになっているようにも感じますね。実は人生はそのようなモノなのだと言っているようにも解釈できます。 実は、イオネスコは、すべての文明あるいは人生に普遍的に存在する一つのパターンを我々に提示しているのではないかと思われたんですね。これはベケットの卒論を書く上での大きなヒントになりました。人間の本質ひいては宇宙の本質には、ある種のパターンや法則があるんですね。それを明かそうとしたのではないかという考えが浮かんだわけです。 今から考えても、まあいい線は行っていたかな、と思います。もちろん当時はオカルト的なことに関しては半信半疑でしたから、それ以上は踏み込めなかったのも事実です。 で、現在の私からイオネスコの劇を見ると、宇宙の法則から読み解くことができるわけです。もちろんオカルトを使わなくても、イオネスコの主張はある程度わかります。増え続ける椅子は、期待と同時に不安の増大を意味しますね。皇帝は「自我の極致」の象徴でしょうか。不幸や死が突然訪れるという人間の人生の不条理性にも言及されていますね。 しかし、オカルト的に見ると、ちょっと違った見方ができます。たとえば八つの卦の性質で見ると、それぞれが何を象徴しているかがわかるんですね。 皇帝は1の天です。易で言うと乾。リーダーシップの象徴ですね。翁はこの場合、皺を深く刻んだ6の水で、坎と見ました。老婆は8の大地で坤、弁士は2の沢で兌、老夫婦が積み重ねてきた人生の歴史とパリの古代文明が7の山で艮、椅子は人間関係を表わす4の木で震、部屋の窓とその下を流れる川は5の風で巽、そして老人が見つけた「新発見」の発表会が3の火で離です。 物語で語られるそれぞれの性質をみてゆくことによって、イオネスコの潜在意識に眠る深層に迫ることができるのです。 (続く)
2022.02.19
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その151)
ウジェヌ・イオネスコ(Eugène Ionesco)は、ベケットやアルチュール・アダモフ(Arthur Adamov)とともに「反演劇」や「不条理劇」で一世を風靡したフランスの劇作家です。1909年(1912年説もありますが、本人が意図的にルーマニアの著名劇作家の没年に合わせたようです)のルーマニア生まれ。母親はフランス人で幼少時からフランスで教育を受けたため、フランス語を母国語として育ちました。1948年ごろに英語を習おうとした際、教則本の中に「天上は上にあり、床は下にある(the ceiling is up and the floor is down)」という当たり前のことが厳かに書かれている滑稽さから劇作を思い立ったといわれています。「This is a pen.」から哲学者が生まれるようなものですね。 イオネスコの作品は当初、パリの批評家や観客からあまり受け入れられませんでしたが、ベケットやアダモフの不条理劇が認知され好評を博するようになると、次第にイオネスコも脚光を浴びるようになります。そのきっかけとなった一つが、1952年に書かれ、56年にパリで再演された『椅子(Les Chaises)』でした 。この作品は、94歳の老婆とその夫の95歳の老人が暮らしている部屋が舞台となります。半円形の部屋で10カ所に扉があり、老夫婦だけがそこにいます。彼らの話に耳を傾けると、パリはどうやら40万年前に滅びているようです。そしてこの日が、老人が発見したモノを世間に明らかにする晴れの日であることもわかります。その新発見を「弁士」が来て、招待客の前で発表することになっているようです。 二人は、目には見えない招待客を次から次へと椅子へと案内します。その間に二人は、見えない招待客に対して自分の人生、嬉しかったことや後悔の念について、それぞれの立場から語ります。招待客はドンドン増えて、老婆はそのたびに椅子を運び込みますが、やがて舞台いっぱいに椅子が並びます。まさに身動きが取れない、すし詰め状態。姿が見えない招待客で部屋が溢れかえったので、老夫婦は部屋の中で別々の端のほうへと引き離されてしまいます。そこへとうとう、目に見えない皇帝陛下まで到着し、老夫婦は感動してむせび泣きます。 しかしながら、老人の新発見を発表するはずの肝心の弁士が現れません。いらだつ皇帝を鎮めようと老夫婦はあの手この手でなだめます。ようやく、待ちに待った「弁士」が老夫婦以外の第三の登場人物として現れます。今や「新発見」が認められ栄光の中にいると信じた老夫婦は、群衆の頭越しに別れの挨拶を交わしたかと思うと、それぞれの近くの窓から川に身を投げて自殺してしまいます。 ところが、舞台に残された弁士がいざ話を始めようとすると、目に見えない群衆と観劇に来た人たちは、彼が唖者(口がきけない人)であることに気づいて、終わります。 物語の設定から展開、幕引きまで奇抜な発想が満載ですね。イオネスコはこの劇で何を言おうとしたのでしょうか。 (続く)
2022.02.18
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その150)
ジョイスとベケットの人生と彼らの作品については後日、私が1982年に書いたベケットの卒論の関連で再び詳しく取り上げるとして、話をカルティエ・ラタンに戻します。おそらく1981年1月3日、私はここでイオネスコの不条理劇『椅子』のチケットを購入しました。その日か翌日の夜の上演だったように思います。『椅子』は、イオネスコが1951年に書いた「悲劇的笑劇」で、場所はカルティエ・ラタンにある小劇場であること以外に覚えていません。 同じカルティエ・ラタンには「ユシェット座(Théâtre de la Huchette)」というイオネスコ専門の劇場があります。1957年以来、イオネスコの初期の作品である「La Leçon」と「 La Cantatrice chauve」を二本立てで上演しているという非常に変わった劇場です。私が観た演目は『椅子』でしたから、必ずしもユシェット座で観劇したわけではないかもしれません。いずれにしても、1月初旬に上演しているイオネスコの劇は、私が知る限り『椅子』だけでした。 夜の部の上演でしたから、それに間に合うようにホテルを出て、テクテクと歩いてカルティエ・ラタンに到着しました。午後6時ごろだったでしょうか、もうすっかり暗くなっていました。どこの広場かは忘れましたが、その広場には大勢の人が集まっていて、大道芸人らがそれぞれの技を披露しておりました。カーニバルの真最中のような人ごみです。 その中でも、今でも忘れられない光景があります。群衆の間を縫うようにして、若い女性が物乞いをしていたんですね。年齢は私と同じくらいの20歳前後。学生なのでしょうか。あるいは失業者か。彼女は道行く人、誰彼に関係なく手を出して、「Un franc pour manger.(食べるために1フランちょうだい)」と懇願して歩き回っていました。 私も似たり寄ったりの境遇でしたから、身に染みる光景です。それでも私の場合は、貧乏学生とはいえ、場末の小劇場で観劇ができるくらい裕福なわけです。ふと不朽の名作とされる仏映画『Les enfants du Paradis(邦題『天井桟敷の人々』)を思い出しました。「天井桟敷」とは、劇場で後方最上階の天井(天国)に近い場所にある観客席のことですね。観にくいので、安い料金に設定されます。映画では、ここに最下層の民衆が詰めかけ、子供のように無邪気に声援やヤジを飛ばすことから、彼らは「Les enfants du Paradis(天国の子供たち)」と呼ばれていました。学生時代の私も「天国の子供たち」の一人だったわけです。 次回は、その晩に観たイオネスコの『椅子』について説明しましょう。 (続く)
2022.02.17
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その149)
閉じた円環ではなく、螺旋状に上昇する円環であることに気づくことは、非常に重要なことです。始めに出会ったAは、終わりに出会ったAではないわけです。A≠A。オカルトの世界では、今あるAは次の瞬間に存在するAとは同じではないのです。 実はこれが、オカルトと現代の科学が根本的に異なる点です。その相違点は理系と文系の違いにも当てはまることがあります。 最近読んだ朝日新聞のEduA2月号の特集記事「文理の壁を壊す」で、母校ICUの学長である岩切正一郎氏(奇しくも私と同じフランス文学が専門)が次のように書いていました。 「文理融合という時に、何を融合させるかです。それぞれの学問は、知ることへの関心の向け方が分野ごとに異なります。自然科学はエビデンスベースで、同じ条件なら誰が実験しても同じ結果が再現されることを求められます。社会科学もエビデンスを必要としますが、人間や社会を相手にする時は個別的な要素があり、ものを相手にするのと同じというわけにはいきません。思想や芸術などの人文科学も自然科学とは違います。芸術は一度しか出現しない出来事の集積といった一面を持っていますし、人間が生きていく意味を問います。」 これは結構、オカルトと現代科学の関係をも言い当てています。現代科学では、同じ条件なら誰が実験しても同じ結果が再現されることを求められます。これに対してオカルトの世界では、ある人がスプーンを“念力”で曲げたとしても、他の人が同じ条件でスプーンを曲げようとしても曲がりません。そればかりか、スプーンを曲げた人が同じ条件で同じスプーン曲げ実験をやったとしても、同じ結果にならないんですね。曲がったり曲がらなかったりする。というのも、オカルトの世界では、その時の心の状態が物質に影響を与えるからです。極端な例では10年に1度だけ、何月何日にこういう人が、こういう条件で、どこどこの場所で心から祈ればスプーンは曲がるというようなことが平気で起こります。 それは確かに芸術のようでもあります。岩切学長が言うように「一度しか出現しない出来事の集積」がオカルトだからです。確かに、芸術とオカルトは似ています。芸術家や作家の中には完全なオカルティストがたくさんいます。端的に言えば、優れた芸術家や作家は間違いなくオカルトの実践者です。一生に一度しか出現しない出来事でも、心の状態を変化・調整することによって、かなりの高確率で呼び寄せる、あるいは引き寄せることができるからです。それは呪術とか超能力と呼ばれることがあります。ジョイスやベケットがスプーンを曲げるような超能力者だったとは思いませんが、オカルトの世界が存在することをよく知っていたからこそ、あのような作品を残せたのではないでしょうか。 (続く)
2022.02.16
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その148)
「20世紀の文学史上、最も有名な遭遇」とも称されるベケットとジョイスの出会いは、「骰子一擲」の最たる例です。ダブリンとチューリッヒという別々の場所で二つのサイコロが投げられ、パリという場所で同じ時に出会うという「目」が出たとしたら、それはもはや「意味のない偶然」とは言えませんね。 ジョイスは1920年、支援者であるエズラ・パウンドの招待で一週間くらいの予定でパリを訪問したはずだったのですが、結局その後20年間をパリで過ごすことになります。そして、先述したように書店「シェイクスピア・アンド・カンパニー」から『ユリシーズ』を出版しました。 一方、ベケットはダブリンのトリニティ・カレッジで英語、フランス語、イタリア語などを学んだ後の1928年、パリの高等師範学校で英語講師の職を得ます。ベケットはおよそ2年間そこで働くのですが、まるで必然のように同郷の先輩ジョイスに出会うわけです。 1882年生まれのジョイスと、1906年生まれのベケット。年齢差は24歳。親子ほどの離れた関係ですね。実は二人とも同じ午年に生まれ、巳年に亡くなっています。アイルランドの歴史の重みと深さを知る二人は、おそらく出会った瞬間に、お互いに同じ魂の血が流れていることを敏感に感じ取ったに違いありません。私も、同じ干支生まれの人に自分と同じような性質を見ることがよくあります。 ベケットは、目がよく見えなくなったジョイスを助け、口述筆記や複写を手伝いました。そのようにして完成したのが、ジョイスの“オカルト文学”の極致とも言える『フィネガンズ・ウェイク』です。ベケットら多くの人の支援を受けて、1939年に出版されました。もちろんオカルト文学というのは、私が勝手に名付けただけで、オカルトを知らないと決して理解できない文学という意味です。 この作品は、おそらく普通の人が読み解くことは不可能です。言語学、シンボル学、易学などを熟知していないと読めないでしょう。もちろん私にも読み解けません。それでも、オカルトを知っている分、理解することはできます。 たとえばジョイスは、ワイルド並みの語学力や言語学、古典の知識を駆使して、広範な言語を結集させた、多言語間による語呂合わせを頻繁に使っていますが、シンクロニシティで説明した「同じ響きや意味は時空を超えて共鳴すること」を知っていると、なぜジョイスがそのような語呂合わせを重視したかがわかりますね。同じ意味や音、響き、形、シンボルは、場所(宇)と時間(宙)を超えて、それは音楽の倍音のように響き合うものなのです。 またジョイスは、あえて本の最初と最後の言葉を一つにつなげて円環を作っていますが、これも宇宙の三大法則を知っていると、よくわかります。 宇宙の非対称性の法則で説明しましたが、同じ一つの文章であっても、本の始めと終わりでは、意味が違ってくるわけです。それゆえに、たとえ円環状に閉じているように見えても螺旋状に発展してゆくことができるということです。 同じ3ピンと7ピンでも、易を知った後の3ピンと7ピンでは意味が違ってくるのと同じです。知るたびに何層も意味が変わって来る。オカルトとはそういうモノなのです。 (続く)
2022.02.15
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その147)
ヴェルレーヌの詩の音のように、時間や空間を超えて響き合う異界都市パリ。実はジョイスやベケットに代表されるアイルランド文学とパリは、奇妙なことに響き合う関係にあります。最初にパリに心を奪われたアイルランドの著名な詩人・作家は、オスカー・ワイルド(1854~1900年)です。童話『幸福な王子』、戯曲『サロメ』小説『ドリアン・グレイの肖像』などの作品で知られていますね。 ワイルドは、1878年に長詩『ラヴェンナ』を上梓、ダブリンのトリニティ・カレッジからオックスフォード大学に進み、同大学を主席で卒業しています。古典語を含む語学の達人で、学生時代から奇抜なファッションと機知に富んだユニークな発言で有名となります。1883年にはアメリカでの芸術論の講演で得た収入を使ってパリに滞在しますが、その時はパリでは変わり者として受け入れられなかったようです。 しかしその後、1884年に結婚してからは、出版・執筆活動や一風変わったファッションのリーダーもしくは有名人としてロンドンの社交界で頭角を現します。1890年に『ドリアン・グレイの肖像』を出版、1891年10月にパリを再訪すると、今度は有能な作家として、マラルメをはじめとするパリの文壇に受け入れられます。パリ滞在中のある晩、『聖書』に出てくるバプテスマのヨハネの首を所望した、ユダヤ王ヘロデの姪サロメについて着想を得ると、一気にフランス語で戯曲『サロメ』を書き上げました。その年のクリスマス前にロンドンに戻ったワイルドの元に、パリでの上演に向けた準備が始まった旨が伝えられます。ただし上演はすぐには認められず、結局仏文の『サロメ』が出版されたのは、1893年、その英訳は1894年でした。 その後ワイルドは、同性愛に絡む訴訟に巻き込まれて敗訴。投獄され、破産に追い込まれます。1897年に釈放されたワイルドは、事実上追放されるようにしてフランスに渡り、親しい友人らとヨーロッパを放浪しながら作家生活を続けますが、やがて困窮のうちにパリの「オテル・ダルザス(Hôtel d'Alsace)」という安ホテルで下宿生活を始めます。しかし、ほどなく持病の頭痛が悪化、1900年11月30日にこのホテルの食堂で寂しく息を引き取ったとされています。死因は脳髄膜炎でした。 このワイルド最期の住処となるホテルが、やはりこのカルティエ・ラタンにあります。有名な国立美術学校「エコール・デ・ボザール(École des Beaux-Arts)」のそばの狭いボザール通り(Rue des Beaux-Arts)に位置していますが、今ではワイルドが亡くなったことで有名な「L'Hotel(ロテル)」という名の小さな高級ホテルになっています。 ワイルドの死から約30年後、ワイルドを引き寄せたパリは、今度はジョイスとベケットというアイルランドを代表する二人の作家をも引き合わせます。まるでワイルドが呼び寄せたかのように、それは起こりました。 (続く)
2022.02.14
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その146)
ウディ・アレンの映画でも取り上げられた米国の小説家ヘミングウェイは、実際に1920年代のパリでフリーの特派員として過ごして、最初の結婚をしています。カルティエ・ラタンの中心街でもあるデカルト通り(Rue Descartes)39番地のアパルトマンに部屋を借りて、そこで執筆していたといわれています。彼は実際に従軍した体験をもとに、『日はまた昇る』『武器よさらば』などの名作を20年代に書いていますね。ハードボイルド小説の先駆者で、ICUの一年生の英語コースで最初の一週間に読まされる英文本が彼の『老人と海(The Old Man and the Sea)』でした。 同じアパルトマンの一室では、それより前の1896年、フランスを代表する象徴派の詩人ポール・ヴェルレーヌ(Paul Marie Verlaine)が没しています。隣説するレストラン「La Maison de Verlaine」の上にはヴェルレーヌに関する記念プレートが架けられています。ヘミングウェイもきっと、19世紀の偉大な詩人に思いを馳せたはずですね。こうして「死せる詩人の魂」は世代を超えて受け継がれていくわけです。 そのヴェルレーヌの詩の中から、「秋の日のヴィオロンの」で始まる上田敏訳で有名な「秋の歌(Chanson d’automne)」を紹介しましょう。同じ秋を歌った詩でも、ボードレールとは一味も二味も違います。 「Chanson d’automne」 Les sanglots longs Des violons De l’automne Blessent mon coeur D’une langueur Monotone. Tout suffocant Et blême, quand Sonne l’heure, Je me souviens Des jours anciens Et je pleure; Et je m’en vais Au vent mauvais Qui m’emporte Deçà, delà, Pareil à la Feuille morte. 私も訳せますが、上田敏の訳にはかないません。彼は「秋の歌」を「落葉」として訳しています。 落葉(詩:ポール・ヴェルレーヌ/訳:上田敏) 秋の日の ヴィオロンの ためいきの 身にしみて ひたぶるに うら悲し。 鐘のおとに 胸ふたぎ 色かへて 涙ぐむ 過ぎし日の おもひでや。 げにわれは うらぶれて ここかしこ さだめなく とび散らふ 落葉かな。 上田敏訳が優れているのは、この詩は言葉の意味よりも、音のほうが非常に深い意味があるからです。フランス語の持つ独特の音霊が見事な作品に仕上げられています。それを忠実に訳すと、日本語では五七調か5音で切って訳すしかなくなります。上田敏訳はそれを見事に成し遂げていますね。古語調でなく現代文調に訳すと、なかなかこうは行きません。 ヴィオロンとはヴァイオリンのことですね。ヴァイオリンよりヴィオロンのほうが、響きがいいです。秋風の悲しげな音がヴィオロンのように聞こえたのでしょう。加えて「オン(on)」とか「アン(an)」というフランス語の鼻音には、楽器のような音響効果があります。あえて簡単に説明すると、英語の詩がリズムや抑揚、切れ味の鋭さが特徴だとすると、フランス語の詩は音の響き具合が生命線になっているように思われます。 (続く)
2022.02.13
コメント(0)
-

ザ・イヤー・オブ・1981(その145)
「ユリシーズ」的世界に関連して、私にはもう一つの仮説があります。ジョイスはオデュッセウスの20年間の放浪人生を、ダブリンでのブルームの人生の1日に集約してみせたわけですが、そういうことが現実世界でも実際に起こるのではないかという仮説です。 たとえば、私が1980年夏~81年夏の人生日記を今ここで再現しようとしている理由の一つは、その1年間に私の人生のすべての要素が集約されている気がするからです。少なくとも人生を決定づける出来事が、その1年の間に次から次へと起こりました。おそらく誰もが、そのような1年、そのような1か月、そのような1週間、そのような1日、そのような1時間、そのような1分、そのような1秒を持っているはずです。そして、それがさらに集約されると、易となり、その八卦のシンボルとなります。だからこそ、「骰子の一擲」である生年月日や没年月日で、その人の運命とその人生の結果がわかるわけです。極小の数字から極大の人生や宇宙までが占えるのです。極大と極小は、同質のモノ同士が響き合う「無限の入れ子」のような状態になっているわけですね。 もう一つの面白い要素は、パリです。皆さんお気づきのように、この私の人生の旅日記では、パリに来てから時間と場所が目まぐるしく変わり、一段と激しい展開になりました。これも偶然ではないんですね。少なくとも私を含む多くの人にとっては、パリはそういう場所なのです。 ジョイスも『ユリシーズ』のほとんどをチューリッヒ(スイス)やトリエステ(イタリア)で書いていますが、既にご紹介したように、仕上げはこのパリでやっています。本当に面白い場所を“偶然に”選びました。 パリは実に不思議な場所で、変な話ですけれど、時空を往来しやすい場所なんですね。19世紀の面影が今でも残っており、ボーっとしているとその時代に引き込まれてゆくような錯覚に襲われます。そうした過去にトリップするようなパリの雰囲気を映画にしたのが、ウディ・アレンが監督した『ミッドナイト・イン・パリ(Midnight in Paris)』でした。映画のあらすじは次の通りです。 小説家を目指してパリにやってきたハリウッドの映画脚本家ギルが真夜中に一人で酔ってパリを歩いていると、目の前に古めかしい車が出現、誘われてその車に乗ると、1920ン年代のパリにタイムスリップ。そこでヘミングウェイやフィッツジェラルド、ガートルード・スタインといった米国の著名どころの小説家たちと遭遇します。明け方までには元の時代に戻ってくるのですが、それから毎晩のように過去のパリを訪れるようになります。彼らから刺激を受け、小説や自分の人生のヒントをもらったギルは、意見が合わなくなった米国人の婚約者と別れ、新しく出会った恋人とパリに残ることを決心します。 とまあ、他愛のない物語ではありますが、映画に描かれている1920年代のパリの雰囲気が実にいいんですね。脚本と監督を務めたウディ・アレンの気持ちがよくわかります。タイムスリップが可能に思えるのがパリなわけです。 (続く)
2022.02.12
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その144)
宇宙の謎を突き詰めて行こうとすると、最後には数字や図形といった共通のシンボルに突き当たるのはなぜか――。その謎は、おそらく次のような考えによって、ある程度説明できます。 たとえば、打ち寄せる大海の波が砂に模様を刻むように、ある性質を持ったパターンが形をつくります。繰り返すことによって形が生まれ、性質が固まり、その性質が繰り返されることによって、一つの形がある世界がつくられることになります。言い換えると、火の性質が三角形をつくるわけです。逆に三角形によって火の性質が生まれるようなことが起こります。その数字は3となり、表現力や飾る力、情熱、感情と結びつくわけです。方角は南で色は赤です。 その対極の北にあるのは、表面ではなく内面を深く掘り下げて、潜在能力を限りなく探り出そうとする水の力です。「涓滴(けんてき)岩を穿つ」と言いますが、わずかな水のしずくも、絶えず落ちていれば岩に穴をあけます。これが水の力です。努力や集中力、潜在能力の性質が凹みという形を作ります。深い穴ですから色は黒。理由はわかりませんが、数字は6が当てられます。「穴」から「六」が当てられた可能性もあります。 同様に、積み重ねる力、伝統や歴史を重んじる力は、山の形である凸を作ります。山の形をした積まれたところには、そのような性質の人たちが集まります。数字は7で、方角は北東、色は藍色ですね。5の風は波の形を作り、色は紫。4の震は枝分かれする系図や雷のようなギザギザ形や長方形を作り、色は緑・青です。1の天は丸・球で灰色、2の沢は三日月で金・白色、8の大地は正方形でオレンジ・ピンクです。 前方後円墳は、八卦の最初に出てくる1の円の天(乾)と最後に出てくる8の正方形の地(坤)とを組み合わせたことになりますね。「乾坤一擲」の運命を掛けた大勝負は、「骰子一擲」と同質のモノであったことがここでもわかります。 こうして同じパターン・性質同士は、同じパターン・性質同士で同じようなシンボルの下に集まる(引き寄せ合う)ようになるわけです。もちろん八卦の一つ一つが単独に存在することはありませんから、同じパターンを持つ者同士が集まる一方で、異なる性質を持ったグループ同士との組み合わせも小さな渦巻きのようなパターンとして刻まれ、その調合具合で自分が学べるパターンの世界を形成することになります。そのもっとも基本的な組み合わせのパターンが8×8の64卦あるわけです。 その調合された組み合わせもまた、大きな同質の渦巻きのようなパターンを世界にもたらします。これは輪廻転生も同じで、カルマとも呼ばれます。まず同質の者同士が集まり、次にそのグループと異なる性質のいくつかのグループが融合して組み合わさり渦巻きをつくります。その渦巻きのかき混ぜ具合あるいは性質の調合され具合によって一つのパターン(たとえば『オデュッセイア』のような物語のパターン)を生み出します。 その生み出されたパターンは時間と場所を超えて、現代のダブリンでも繰り返されます。それがジョイスの『ユリシーズ』です。ただし、同じパターンのように見えても、微妙に調合具合(対称性)が異なります。それによって現代に変換されたパターンは、似てはいても、異なる回転や展開を始めます。最初の渦巻きから脱出することができるんですね。まさにそれが、輪廻転生を含む宇宙の法則であり、シンクロニシティの本質でもあるわけです。 ですからどんなに複雑な物語も、その組み合わせがどのようになっているかをひも解いて行くと、パターン同士の組み合わせとなり、さらにその調合されたパターンの原材料を見てゆくと、64卦が現れて、最後は8卦とそれに付属する形や数字やシンボルに突き当たる――そのようになっているのではないでしょうか。まあ、一つの仮説ですけどね。(続く)
2022.02.11
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その143)
宇宙にある三大法則をうまく言い表していることのほかに、『ユリシーズ』で私が注目しているのは、ジョイスのシンボルの使い方です。とにかく彼は自分の誕生日の数字にこだわったことがわかります。自ら自分の40歳の誕生日までに完成させると決めて、校正に3か月かけ、1922年2月2日の誕生日にパリの「シェイクスピア・アンド・カンパニー」から出版させました。数字がもつ力を知っていたということですね。 本の中で「ダブリンの一日」に定められた日にち(1904年6月16日)にも意味があります。ジョイスが後に自分の妻となるノーラ・バーナクル(Nora Barnacle)と初めてデートした日なんですね。人生のターニング・ポイントとなる運命の日でもありました。 同時に彼は、物語を18章(18のエピソード)に分けましたが、それぞれの章を異なる文体で書いた上に、それぞれ異なるシンボル・象徴やテーマを挿入しています。非常に易経的でしょ。易経を知っていたとは思いませんが、彼は少なくとも何らかの数秘術を知っていたのだと思われます。 たとえば、第四章のブルームの家族を描く家の場面では、オレンジの色彩が重視され、7という数字や経済学、ニンフが象徴として配置されています。第7章の新聞社の場面では、赤色がイメージとして挿入され、修辞学というテーマや3という数字が入り込みます。第6章の墓地の場面では、当然黒のイメージが挿入され、宗教学というテーマが扱われています。 それぞれのエピソードについて、易経的に解釈していくことも可能ですが、ここでは彼が選んだ誕生日兼出版記念日である1922年2月2日と、初デートの日である1904年6月16日がどういう意味があったかだけを簡単に見てみましょう。 1922年は戌年ですから、まさに3の火の年です。つまり表面を飾ること(ファッション)や薄いモノに意味を与えること(出版や映画、絵画)に適した年であったと言えます。彼が意識した2は「兌」の沢。これは発信力・コミュニケーション力を強める数字ですね。同時に金運も強めます。出版して自分の作品を世に流通させるにはちょうどいいですね。全体としては7の山ですから、これまで積み上げてきたモノ(たとえば歴史)が重視されることを意味します。ジョイスの場合は、これまで書き溜めてきた原稿が出版という形で実現したことを指します。確かに彼は、『ユリシーズ』のよって西洋文学史に金字塔を打ち立てました。 1904年は辰年ですから5の風の年です。つまり自由になる機運が高まる時期ということですね。初デートは、まさに親の束縛から自由になることの始まりと解釈できます。6は集中力や直感力・霊感を表わす坎で、水が象徴です。彼がこの日にちを選んだということは、この時に何らかの『ユリシーズ』の霊感を得たのだと思われます。8がありますから、寛容性や受容力が高まった出来事もあったのではないでしょうか。全体としては3の火ですから、文筆家としての将来が定まったことを意味している可能性が高いです。 おそらく当時のジョイスには、たいていの人がそうであるように、そうした年月日の意味など分からなかったはずです。でも、あらゆる現象を突き詰めて行くと、宇宙共通言語としてシンボルがあることに思い至るものなのです。そうでなければ、あれほど数字にこだわらなかったはずですよね。ではなぜ、数字や図形などのシンボルが共通の宇宙言語になりうるのかという問題があります。 (続く)
2022.02.10
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その142)
ジョイスは『ユリシーズ』を書くにあたって、ホメロスの『オデュッセイア』を克明に調べ、その構成や登場人物、事件を現代(当時)のダブリンに持ち込み、ダブリンの「ユリシーズ物語」として描きました。オデュッセウスの20年の放浪の旅がダブリンの1日に置き換えられ、人物や環境の設定も異なりますが、父の不在と親子関係、恨みや嫉妬が渦巻く仕事の問題、家への帰還と妻の浮気など、共通する同じような人間関係や問題が時代と場所を超えて取り上げられています。 人物の対応としては、最初に出てくる作家志望の青年スティーブン・ディーダラスがオデュッセウスとその妻ペネロペとの間に生まれた息子テレマコスに対応します。そして途中から登場する38歳のハンガリー系ユダヤ人で広告取りを仕事とするレオポルド・ブルームがオデュッセウスで、その妻モリーがペネロペです。それぞれ「ユリシーズ」と同じような人生の問題を抱えています。 オカルト的に面白いのは、輪廻転生をしたら十分にありうるような人物関係が展開されることです。登場人物(すなわち私たち)はどの時代でも同じようなカルマを背負い、同じような人間関係や環境が自分の近くに現れてしまうわけですね。そして同じような問題に直面して悩み、同じような解決策を見つけ出そうとする。 これが宇宙の第一の法則である「繰り返し」です。歴史は繰り返すと言いますが、古代ギリシャと同じような物語が現代においても展開されるわけです。 そして、その物語に集まる人間たちも同じような性質を持って、転生してきます。意味や環境、パターンが同じ「似たモノ同士」は、共鳴し合い引き寄せ合うからです。これが宇宙第二の法則である「同質結集」です。だから転生しても同じような人間関係や問題が繰り返されているわけです。 でも、これだけだといつまでも同じことを繰り返すだけになってしまいますね。ただの円環、つまり永遠に同じ円を描いていなければならなくなります。これではシジフォスの苦役になってしまいます。 そこで働くのが宇宙第三の法則である「非対称性」です。全く同じに見えても、ちょっと異なるのがこの宇宙です。この宇宙の非対称性(対称性のゆらぎ)によって、同じ繰り返しに見えても、円環ではなく螺旋状に発展・展開していくことが可能になるのです。 ジョイスがこの三つの法則を知っていたかどうかにかかわらず、彼はこの三つの法則を見事に二つの作品を対応させることによって描いていると思います。 彼のオカルト的なところは、ほかにもたくさんあります。それがシンボルの使い方です。 (続く)
2022.02.09
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その141)
1980年12月から81年1月にかけての1か月弱わたるフランス旅行の期間中、実は私のリュックの中には一つの分厚い本が仕舞われていました。それが奇しくも「シェイクスピア・アンド・カンパニー」が版元になったジェームズ・ジョイスの『ユリシーズ』だったんですね。何という偶然! これも神の采配ですね。 どうしてこの本をリュックの中に入れたかと言うと、次の春学期(Lent term)のヨーロッパ劇文学コースの課題図書になっていたからです。ものすごく分厚い本(ペーパーバックで、厚さ約5センチ以上)で、とても一週間では読めないのは明白です。それで、冬休み中に読んでおこうと考えたわけです。 ところが最初の20ページほど読んだ時点で、とても旅の合間に簡単に読める代物ではないことが判明。同時にフランスの冬の旅が予想以上に過酷で、日々を生きるので必死だったこともあり、ほとんど手つかず状態でリュックの中で眠っておりました。結局、この本はざっと読んだだけで読み切れず、春学期の授業でもチンプンカンプンだったことを覚えています。 でも読み切れなかった学生は私だけでなく、他の学生も結構読んでいなかったことが後から判明しました。それほど長大で大変な作品ということですね。でも、英文学専攻の学生にとっては必読書の一つとなっています。日本文学専攻生の『源氏物語』のようなものでしょうかね。それがジョイスの『ユリシーズ』です。 当時完読したとしても、作者の意図やその意味をほとんど理解できなかったと思いますが、オカルトを体験して知った今なら、おそらく理解できるように思います。全部読んだわけではありませんが、私なりに『ユリシーズ』を解説してみましょう。 タイトルの「ユリシーズ」はギリシャの古伝説に登場するイタカ王で、長編叙事詩『オデュッセイア』の主人公オデュッセウスのラテン名ウリッセースの英語読みです。叙事詩の中で彼は、トロイの木馬の発案者とされていて、トロイア戦争に功を上げました。 ジョイスは『オデュッセイア』と対応する形で、ダブリンでのある一日(1904年6月16日)を多種多様な文体や意識の流れの技法を駆使して、描いています。 あの長編叙事詩をダブリンの一日で描いてしまうところが凄いです。次回はもうちょっと詳しくみてゆきましょう。 (続く)
2022.02.08
コメント(0)
-

ザ・イヤー・オブ・1981(その140)
ボードレールが青春時代を過ごした館を後にして先に進みましょう。シュリー橋を渡って、セーヌ川の左岸に渡った後、川に沿って右に進むと、右手のセーヌ川の中にシテ島のノートル・ダム大聖堂をはっきりと見ることができます。 ノートル・ダム大聖堂は、ヴィクトル・ユーゴーが1831年に書いた小説『ノートル・ダム・ド・パリ(Notre-Dame de Paris)』(邦名「ノートル・ダムのせむし男」)の舞台となったので一躍有名になりました。この小説を読んだ当時の人々は、ノートル・ダム大聖堂の歴史的・芸術的価値を再発見し、フランス革命の余波によって廃墟と化した大聖堂の復興運動が始まったんですね。その精神は今も引き継がれ、3年前の大火災後も再建作業が続けられています。ちなみにノートル・ダムとはフランス語で「我らが貴婦人」すなわち聖母マリアのことを指します。 シテ島の大聖堂が良く見えるセーヌ川左岸のこの辺りは、既にカルティエ・ラタン(ラテン街)と呼ばれる地域です。ここには有名な「シェイクスピア・アンド・カンパニー」という書店があります。パリにおける英米文学の中心地です。 何しろこの書店は、後で説明しますが、ジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』の版元でもありました。1919年に開業後、41年にはナチスドイツによるパリ占領で閉店を余儀なくされましたが、第二次大戦後、別の書店が名前を引き継いで二代目「シェイクスピア・アンド・カンパニー」として営業を再開、現在に至っています。 実は1981年当時はそのようなことも知らずに、引き寄せられるようにこの書店に入りました。そして、そのとき購入したのがこちら。 シェイクスピア全作品のフランス語版です。1961年版です。シェイクスピアの作品には親しんでおり、数々の名言を既に知っていましたから、それをフランス語でどう表現するのか知りたかったわけです。仏訳のタイトルだけでも結構楽しめました。ただし、全部はとても読み切れませんでした。 そして読み切れなかったといえば、ほかにも苦い思い出もあります。 (続く)
2022.02.07
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(番外)
前日はボードレールの運命を易で読み解きました。すると今朝ネットを見ていたら、たまたま竹内睦泰氏の生年月日と死亡年月日が目に飛び込んできました。何か「意味がある偶然」かもしれないので、2年前に亡くなった竹内氏の追悼の意味を込めて、竹内氏の人生を易占で偲んでみることにしましょう。竹内氏の生まれたのは、1966年12月17日で、亡くなったのは2020年1月13日です。彼の直霊が望んだ運命は7の山。伝統や歴史を重んじる役割を生まれながらにして持っていたことがわかります。これに対して先祖が彼にもたらした運命は4の震(木)。人間関係を大事にするように求める運命です。環境がもたらした運命は1の天。リーダーシップを発揮するように周囲に求められたはずです。そして人生全体のテーマとなる運命は、先祖がもたした運命と同じの4の木で、木に象徴される家系、すなわち竹内一族を含む人間関係を大切にすることでした。彼の魂は元々、歴史や伝統を重視したかったわけですから、先祖の竹内家の要望である第73世武内宿禰として伝統を引き継ぐことは、まったく矛盾しなかったわけです。実際に彼は正統竹内家の秘儀・口伝を継承するとともに、予備校の講師として教え子たちを非常に大事にしていました。そうした仕事(環境)から求められたのは「1のリーダーシップ」ですから、自分たちを引っ張ってくれる先生であり、竹内家の秘儀・秘伝を守る責任者としての武内宿禰であったわけです。その大きな流れの中で竹内氏は、既に出来上がった制度を含む人間関係を大切にして、ほぼ与えられた運命通りに生き抜く決心をしたのだと思います。で、それが最終的にどうなったかというと、歴史や伝統を重んじたくて生まれた魂(直霊)は、リーダーシップを重視する「1の天」に目覚めています。これに対して、先祖もリーダーシップを発揮するように求めるようになりました。その結果、環境が「5の風」に変わります。つまり「自由であれ」「自由になれ」という環境が自然と出来上がったんですね。ここに矛盾が生じます。実はリーダーシップを象徴する1と、自由を象徴する5は対極にあるからです。彼は正統竹内家の棟梁・武内宿禰として秘儀・秘伝を守らなければなりません。でも歴史は、語られなければ消えてしまいますね。もし棟梁として責任を持てというなら、自由にさせてくれという気持ちになったのかもしれません。知るべき歴史が埋没・抹殺されてしまうのは何としても避けたかった。それで彼なりのリーダーシップを発揮して、秘儀・秘伝を部分的に公開することに踏み切ったのではないでしょうか。そして、彼の人生として成し遂げた運命が、死亡年月日に「7の山」として記録されています。つまり「正統竹内文書の日本史」を、部分的であるにせよ、公にして歴史に刻み込んだということになります。4が7に変貌しました。4の人間関係を重視することによって、7の歴史が生まれたのだとも読めます。私がこの易占で驚いたのは、文筆家と関係がある3の火(表現力)や、先生や講師に関係がある2の沢(コミュニケーション力)がまったく入っていないことです。意外と文章を書くことや、講釈することに、本当はそれほど興味を持っていなかったのかなとも思えてきます。お付きの者たちにやらせていたのかもしれませんね。あるいはお神酒の力に頼っていたか、今となっても謎です。このように易占でその人の持って生まれた運命と、成し遂げた運命をある程度振り返ることができます。そして、こうして竹内氏のことを易占で偲ぶことができるのも、「骰子一擲」すなわち神の采配の賜物なのではないかと思っています。(了)
2022.02.06
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その139)
ところで、書き忘れていましたが、オカルトとカルトについて語っておきましょう。何しろオカルトと聞いただけで、オウム真理教事件を思い浮かべ拒絶反応を示す人が多いですからね。オウム真理教事件はオカルトではなく、ただのカルトによる凶悪犯罪事件です。 オカルトとカルトはまったく違います。両者はむしろ対極にあるモノです。すべてについて先入観を持たずに宇宙の法則をあるがままに受け入れる(理解する)のがオカルトであるとすると、カルトは過度に偏って妄信・狂信することです。科学至上主義も私から見ればただのカルトです。宇宙のすべてに存在する神秘性、すなわちオカルトを闇雲に否定していますからね。 そういった思い込みや偏見、我欲を一切排除して偶然に委ねた時、神の采配による「サイコロの一振り」がオカルトの神髄だと思ってください。宇宙的構造を持つ「偉大なる作品」によって世界を究極的に解明することを目指したマラルメが、最後に辿り着いた作品が「骰子一擲」だったことは偶然ではないのです。偶然が神の采配であることを知らなければ、オカルトはもちろん、この宇宙を理解することもできません。 それに気づくと、人間には森羅万象の中から「意味ある偶然」を検知する自動検索機能があらかじめ備わっているということがわかってきます。それを再認識させてくれるのが、詩人たちであり、オカルティストと呼ばれる人たちです。 サン・ルイ島のローザン館に別れを告げるために、最後にボードレールがたどった四つの運命を、神の采配である易で見てみましょう。 シャルル・ボードレール(1821年4月9日生まれ) 生まれ持った魂(直霊)が望んだ運命は、6の直感力・霊感力・集中力を高めることです。 先祖がもたらした運命は、4の人間関係力を強めること。人間関係を大事にしろということですね。 これに対して環境がもたらした運命は、1のリーダーシップ・指導力を発揮させることです。 そして彼の生涯にわたるテーマとなる運命は、3の愛情運や、詩作などの創作表現に磨きをかける、あるいは極めることです。 3と6は対極にありますから、自分の中で葛藤が生じていたでしょうね。本来の自分の魂は、何かを外に向かって表現するよりも、自室に籠って何かに集中するだけで満足だったわけです。ところが先祖や環境がそれを許しません。先祖は人間関係を築くように促す一方、環境は率先してリーダーシップを発揮しろと迫るわけです。生前に発表した詩集が『悪の華』だけだったのも納得が行きます。詩集を出して公に活動するよりも穴蔵や「大麻の巣窟」に籠って詩作に耽るほうが、彼にとっては重要だった(心地よかった)わけです。 そして時代(環境)は彼に、詩壇や文芸界を引っ張っていくリーダーシップを求めました。事実彼は、象徴主義の先駆者になりましたね。そして何よりも人生のテーマである運命が優先されますから、表現者として数々の名作を生み出しました。愛情面では黒人混血女ジャンヌ・デュヴァル(Jeanne Duval)との恋愛関係が知られています。 心(魂)はオタク的生活を望む一方で、家族関係や恋愛関係に巻き込まれ、詩壇を背負うように求められたボードレールは、結局うまくバランスを取ることができなかったようです。42歳で梅毒によって体に不調を感じるようになり、43歳で負債に追われて母親に金の無心をするようになります。それでも最後まで詩作を続け、批評家として論陣を張りますが、病が進行。最期は脳神経もやられて、46歳で亡くなります。1867年8月31日のことでした。遺体はカルティエ・ラタンに近いモンパルナス墓地に葬られます。 この亡くなった日にちからは、ボードレールの「運命(人生)の通信簿」がわかります。穴蔵で孤独に何かに集中することを求めていた彼の直霊は、晩年は人間関係を重視する4の「震(木)」に変貌しています。病床のボードレールは、結局母を頼るしか他に方法がありませんでしたからね。親と子の人間関係に感謝したと思います。言い換えると、先祖からの求められた運命(人間関係)を受け入れたことになります。それが受容力を表わす8の大地に現れています。で、リーダーシップを求められた環境に対して彼が成し遂げたものが、7の山である歴史として残ったわけです。フランス文学史に金字塔を打ち立てていますからね。そして人生全体では、やはり同じ3の詩人としての生涯を全うしたことが刻まれています。 (続く)
2022.02.05
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その138)
象徴主義の先駆者とされるボードレールの詩でオカルトとの対比に言及したついでに、オカルト的現象の中核をなすシンクロニシティと詩歌・西洋詩との関係について触れましょう。 実は、詩や歌はシンクロニシティのことを知らないと理解できません。極論すると、詩歌・西洋詩の神髄は、シンクロニシティを理解するために生まれたようなものです。 たとえば、英語やフランス語では脚韻や頭韻を踏みます。ボードレールの「秋の歌」でいうと、「ténèbres(暗闇)」と「funèbres(葬式の、陰鬱な)」、「courts(短い)」と「cours(中庭)」ですね。その結果、この詩を読んだときにどのようなことが起こるかと言うと、funèbres(葬式の)という言葉を読んだときに、二行前のténèbres(暗闇)と響き合う現象が起こります。連想、すなわちイメージの連鎖ですね。この場合、暗闇と葬式が響き合います。同様にcours(中庭)という言葉を読んだときにcourts(短い)という語と響き合います。「中庭」と「短い」というイメージが重なるような現象が起きるわけです。いわゆる洒落や地口の世界に近いです。漢詩にも同じような韻がありますね。 その共鳴現象をさらに進めて一体化・融合させたのが和歌です。 有名な小野小町の和歌を見てみましょう。 花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに 現代訳:桜の花は、春の長雨が降る間に、むなしく色あせてしまった。私の容姿も、長雨を眺めるようにぼんやりと人生の物思いにふけっている間に、すっかり衰えてしまった。 桜の花と自分の容姿を同化させ、「長雨」と「眺め」を融合して「ながめ」と歌っています。雨が「降る」と時が「経る」も「ふる」に融合していますね。 和歌を作った人はおそらく、こうしたシンクロニシティ現象が頻繁に起こることに気づいていたのです。 似たモノ同士は、引き寄せあうだけでなく、共に響き合う、つまり共鳴し合うのです。それも時空を超えて響き合います。 百人一首のカルタも同様です。 上の句と下の句がシンクロニシティを引き起こすものがどれかを当てろ、と言っているようなものです。一種のシンクロ当てゲームです。シンクロニシティに気づくための教材だったのかもしれません。 現実界の現象も実は、シンクロニシティによって引き起こされることが非常に多いのです。「笑う門には福来る」とか、「泣きっ面に蜂」のようことが良く起こります。古今東西、「類は友を呼ぶ」と言います。 それはどうしてかと言うと、シンクロニシティには、同じ状態、性質、意味、パターンのモノ同士は引き寄せ合い、響き合うという、目に見えない力が働くからです。 このシンクロニシティ現象を利用して生まれたのが、易経です。 「今ある状態は、易の64卦が言うところの、いったいどの状態とシンクロを起こしているのでしょうか」という質問に対する答えが返ってくるのが易占だからです。 (続く)
2022.02.04
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その137)
サン・ルイ島のローザン館で生まれたと言っても過言ではないボードレールの『悪の華』――。1857年に出版されると、公序良俗に反するとして摘発、治安裁判で6篇を削除されたうえに罰金を科されます。それでも1861年には35篇を追加した『悪の華』(第二版)を出版します。 その第二版に収録されたボードレールの詩の一部(冒頭のみ)を紹介しましょう。私の好きな詩で「秋の歌(Chant d’automne)」のタイトルが付いています。アポリネールの「ミラボー橋」と同様に、私が今でも空で口ずさめる一節です。 Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres ; Adieu, vive clarté de nos étés trop courts ! J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres Le bois retentissant sur le pavé des cours. (訳) やがて我々は凍えるような暗闇の中に落ちて行く。 さらばだ! あまりにも短い我々の夏、あの生き生きとした明るい夏よ! 早くも聞こえてくるのは、あの薪をくべる音だ。 中庭の敷石の上に落下した薪が、陰鬱な衝撃音とともに断末魔の叫びを鳴り響かせている。 いかがでしょうか。かなり主観的な詩であることがすぐにわかりますね。象徴主義の特徴です。これを客観的に書くと、「ああ、夏が終わったので、日の短い寒い日がやって来るね。中庭ではもう薪をくべる音がしているよ」です。 これに内面の心の動きを加えることで、こうまでもドラマチックにしてしまうわけですね。夏は長かったはずなのに主観では「短く」なります。日照時間が短くなり温度が下がるだけなのに、「凍えるような暗闇に落ちてゆく」と彼は感じるわけです。しかもここでは夏に対して「adieu(アデュー)」という別れの言葉を使っています。アデューは、普通のサヨナラを意味する「au revoir」と違って、長期間の別れ、それも二度と会うことはないと覚悟するような別れを意味します。また来年巡って来る夏に対してかなり大げさですが、主観としてはそれほど夏との別れを惜しんでいることがわかります。「陰鬱な衝撃」の「陰鬱な」という形容詞に「funèbre」を使っていますが、葬式を連想させる言葉です。薪をくべることは、生気をもっていた樹木の最期を意味することが連想されます。ボードレールはそこに樹木の「断末魔の叫び」を聞いたわけです。 (続く)
2022.02.03
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その136)
フランス文学を専攻する学生が避けて通れない詩人が、19世紀半ばに登場し、フランス詩に革命をもたらしたとされるシャルル=ピエール・ボードレール(Charles-Pierre Baudelaire)です。 ボードレールの詩は、それ以降のフランス詩がボードレールから派生したとされるほどフランス詩に大きなインパクトを与えたとされています。そのことから、彼は「近代詩の父」と称されているんですね。その詩作の特徴は、何と言っても19世紀の後半に台頭した「象徴主義(symbolisme:サンボリスム)」です。 象徴主義は内面の世界を象徴的に表現する芸術の潮流で、ボードレールはその先駆者であったとみなされています。当然、写実的な表現を重んじる客観主義よりも、想念の世界を象徴的に表現する主観主義が全面に打ち出されます。現代の科学とオカルトの関係にちょっと似ていますね。 さらに簡単に言ってしまうと、ボードレール以前の詩は、みてくれが重視されたため、文章も演出がかっており、本心よりも建前の美しさを表現することが主流だったように思われます。しかし、ボードレールはその姿勢に真っ向から挑み、内面性をこの世界のすべてであるととらえ、醜さや悪を含む人間の本当の姿を表現しようとしたと言えるのではないかと思います。 で、サン・ルイ島には、オルレアン河岸に「ローザン館(Hôtel de Lauzàn)」という、17世紀の建築家ルイ・ル・ヴォー(Louis Le Vau)によって1657年に建てられた美しい邸宅があります。まさにこの館に部屋を借りて、ボードレールは青春の一時代を過ごしました。 館自体は、室内装飾もヴェルサイユ宮殿に引けを取らない豪華さで、本来ならボードレールはここに暮らすことはできなかったはずですが、20歳になったときに亡き父の遺産を相続。その大金をつぎ込んで、22歳から24歳ごろまでの約2年間、実質的に資金が底をつくまでここで暮らしました。 その2年間、この館でボードレールは、女流作家ジョルジュ・サンド(George Sand)らと怪しげな麻薬パーティーを頻繁に開催。文豪バルザックやヴィクトル・ユーゴー、詩人テオフィル・ゴーティエ、作家サント・ブーヴらが通う『ハシシュ(大麻)・クラブ』の会合場所にもなっていました。 まさに「悪の華」の香りが漂う館です。実際、この2年間の館生活の体験とここで生まれた詩作が、彼が36歳となった1857年に出版された不朽の名作『悪の華』として結実しました。 (続く)
2022.02.02
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1981(その135)
易占いのついでに、秋山氏に教えてもらった「易による四柱推命」を使って、マラルメがたどった「運命」を占ってみましょう。これはまだ本に書いていないので、詳しいやり方はお教えできませんが、マラルメの誕生日である1842年3月18日から4つの運命がわかります。4つの運命とは、自分の魂(直霊)が選んだ運命、先祖が望んでいる(先祖の因縁がもたらした)運命、環境がもたらす運命、そして今生(今回の人生)において自分が学ぶことになっている運命です。マラルメの場合、自分の魂が選んだ運命が3の火(表現力・愛情運)です。先祖が望んでいる運命も3の火。環境がもたらす運命は2の沢(金運・コミュニケーション力)で、今生のテーマとなる運命が8の大地(包容力・受容力)となっています。具体的にみると、マラルメの魂がやりたがっていることが、詩や文章を書くという表現力を極めることだったわけです。マラルメの先祖が望んでいることも同じ。ただし、環境がもたらす運命はそれを許さず、金運を高めるために多くの人に言葉を発信して伝えるというコミュニケーション力を磨くことが求められました。すなわちマラルメの場合は生計のために英語教師として学校で教えるという運命が、もたらされたことになります。最後に人生で学ぶことになるマラルメの運命的なテーマは、受容力です。矛盾するもの(たとえば教職と詩作)をいかに包容するかが彼の人生のテーマでありました。同時に、彼の詩にあらゆる要素が詰め込まれて包容されていくのも、その運命がもたらした技法であったのではないかと思われます。このように「易による四柱推命」を使うと、不思議なことに大体その人の運命がわかってしまうんですね。非常によくできています。まさにサイコロの一振りによってもたらされた数字のマジックのようなモノでしょうか。さて、偶然のサイコロの一振りが「神の采配」であることをわかってもらえたでしょうか。それがわかれば怖いものなしです。実際、オカルトのことがわかれば、一生解けないと思っていた超難解詩でも、無理なく理解できてしまうんですからね。マラルメの超難解詩「UN COUP DE DÉS」の完訳はいつか取り組むとして、先に話を進めましょう。振り返ると、セーヌ川を渡る辺りから、アポリネールの「ミラボー橋」に話が飛び、キュービスム、シュールレアリスム、そしてマラルメと、次から次へと近代フランス文学史の連想が続いたわけですが、実は宿屋からカルティエ・ラタンを目指してセーヌ川を渡るときに通ったサン・ルイ島にも、紹介したい話があります。マラルメに多大な影響を与えたとされる詩人シャルル・ボードレールが青春時代を過ごした怪しげな館があった所だからです。(続く)
2022.02.01
コメント(0)
-

紅梅
今日は遅くなったので写真だけ。1月27日撮影した紅梅です。陽当たりの良い場所の梅は満開に近づいていました。
2022.02.01
コメント(0)
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
-

- ニュース
- ヨーロッパ国際デザイン賞グランプリ…
- (2025-12-04 11:44:12)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- お買い物マラソンで「レビューめんど…
- (2025-12-03 20:30:06)
-
-
-

- 株主優待コレクション
- 都築電気:明光ネットワーク:カーブ…
- (2025-12-04 12:53:06)
-







