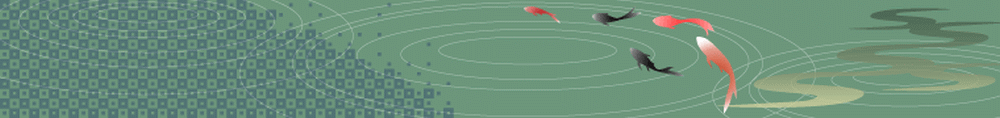カテゴリ: 映画
今日は雨が小雨がじとじと降りしきるあいにくの天気だった。
午後研究室に行くと、研究室仲間のD(ドイツ人)が「今から映画に行かないか」という。まだ昼間だぜ、というとその映画は昼間しかやっていないのだという。彼が行きたいと行った映画はかなり(僕としては)「ハズレ」の場合が多いのだが、今回はトーマス・マンの「魔の山(Der Zauberberg)」の映画化だというので大ハズレはしないだろうと思い、行くことにした。といっても僕は「魔の山」は読んだことが無い。マンの小説は短編をいくつか読んで大体の傾向は知っていたのだが。
その場に居たK君とDの彼女であるCも見に来た。上にも書いたが、この顔ぶれで何度か映画に行ったが、Dの好みに引きずられるせいか「何だこれ」という映画に当たることが多い。一番最近では「Silentium」というオーストリア映画、「Hero」(邦題・ラヴァーズ)という中国映画、「Agata und der Sturm」というイタリア映画などがそうだった。ちなみにこの「魔の山」は1982年西ドイツ映画、ハンス・ガイセンデルファー監督作品である。

物語は主人公の23歳の青年ハンス・カストルップ(クリストフ・アイヒホルン)がアルプス山中のサナトリウム(結核療養所)に軍人の従兄弟を見舞うところから始まる。ところがハンス自身が結核と診断され入院することになってしまう。全員が結核患者であるという以外はヨーロッパ上流社会の社交界の縮図のようなそのサナトリウムには、一癖も二癖もあるような人々が居て、暇にあかせて哲学談義をしていた。ハンスもその奇妙な世界に巻き込まれていく。フランス女性への恋慕(というか欲情)、従兄弟の死などのエピソードがあるが、最後に戦争が勃発してサナトリウムが閉鎖され、入院中の人々が戸惑うところで物語は終わる。
・・・とこうして書くとまあまともに見えるが、かなりしんどい映画だった。隣りの席で見ていたK君は途中で寝息を立てていたので肘でつついて起こした。Cも「居眠りはしなかったが何度も意識が遠のいた」と見終わった後で言っていた。なんというか話が唐突に展開してなんだか訳が分からないのである。小説ならその辺は丁寧に説明されるのだろうが。だからこの映画は原作を読んでいない人は見るべきではない。また原作を読んだ人ももしかしたらこのような映像化されたものは見ないほうがいいのかもしれない。主人公ハンスが吹雪の中、山小屋に向かうシーンがあって、原作では吹雪の様子や恍惚状態になるハンスの描写が素晴らしいらしいのだが、この映画では突然ハンスが雪山の中を歩くシーンになるので気でも狂ったのかと思うし訳が分からない。
「気でも狂ったのか」といえば、出てくる人物は周りも気にせず大声で議論したり叫んだりしたりしておかしいんじゃないのかという人ばかりである。原作ではこれが高尚な哲学論議とかになっていて、「魔の山」は「教養小説」というジャンルの棹尾を飾る作品とされているらしいのだが(筒井康隆の「文学部唯野教授」は物語中で主人公が文学論の授業をしたりするから、傾向としては似ているかもしれないが)、映画ではそこまで描きこめないので変人が次から次に出てくるようにしか見えない。映画の後でDが僕に向かって「ヨーロッパ人というのは皆頭がおかしいと思ったか?」と冗談混じりに聞いてきた。実ところこの映画に出てくる人物はドイツでは実際にその辺に居そうなところがまたすごいのだが。
(タビウサギさんのご教示により訂正:「教養小説」というのはBildungsromanの訳で、内容が教養的というのではなく、主人公の成長を描くジャンルのことらしい。したがって「唯野教授」は「教養小説」ではない)
そんな僕にもよく分かったのはハンスがフランス人女性に恋慕というか欲情するところだけだった(その口説き方もまたマンの小説によく出てくるタイプの変人みたいだったのだが)。というか結核で療養しているはずのハンスがえらく元気そうだったのがやはりまずかったのかもしれない。おいらにはこういう映画は難しいや。
40年近く政権の座にあったエヤデマ大統領の死後、大統領位の継承をめぐる政情不安が続く西アフリカのトーゴで、首都ロメにあるゲーテ・インスティテュート(半官のドイツ文化センター及びドイツ語教育機関)が武装した暴徒に焼き討ちされるという事件が起こった。所蔵されていた8000冊の書籍やコンピューターが焼失したという。
さらに首都ロメでは「ドイツ大使はナチスの過去がある。ドイツでは毎日我々アフリカ人がネオナチのリンチで殺されている」という扇動のビラも撒かれているという。このビラではギュンター・グローマン大使が1943年にナチス親衛隊に入ったと主張しているが、そうすると大使はとうに停年を迎えているはずであり得ない話である。なにかというとすぐにナチスと結び付けられてしまうドイツも大変ですな。また政府の意を汲んだ暴徒云々というのは最近どこかで見たような気もする。
ちなみにトーゴは1884年から1919年までドイツの植民地となっていた。第1次世界大戦後フランスの委任統治となり、1960年に独立している。1967年の軍事クーデタから政権の座にあったエヤデマ大統領が死んだ2月以来、政情不安と治安の悪化により3000人以上が隣国ベニンに逃げたという。またトーゴにはドイツ人300人がおり、ドイツのフィッシャー外相はトーゴの旧宗主国フランスなどと対応を協議している。
午後研究室に行くと、研究室仲間のD(ドイツ人)が「今から映画に行かないか」という。まだ昼間だぜ、というとその映画は昼間しかやっていないのだという。彼が行きたいと行った映画はかなり(僕としては)「ハズレ」の場合が多いのだが、今回はトーマス・マンの「魔の山(Der Zauberberg)」の映画化だというので大ハズレはしないだろうと思い、行くことにした。といっても僕は「魔の山」は読んだことが無い。マンの小説は短編をいくつか読んで大体の傾向は知っていたのだが。
その場に居たK君とDの彼女であるCも見に来た。上にも書いたが、この顔ぶれで何度か映画に行ったが、Dの好みに引きずられるせいか「何だこれ」という映画に当たることが多い。一番最近では「Silentium」というオーストリア映画、「Hero」(邦題・ラヴァーズ)という中国映画、「Agata und der Sturm」というイタリア映画などがそうだった。ちなみにこの「魔の山」は1982年西ドイツ映画、ハンス・ガイセンデルファー監督作品である。

物語は主人公の23歳の青年ハンス・カストルップ(クリストフ・アイヒホルン)がアルプス山中のサナトリウム(結核療養所)に軍人の従兄弟を見舞うところから始まる。ところがハンス自身が結核と診断され入院することになってしまう。全員が結核患者であるという以外はヨーロッパ上流社会の社交界の縮図のようなそのサナトリウムには、一癖も二癖もあるような人々が居て、暇にあかせて哲学談義をしていた。ハンスもその奇妙な世界に巻き込まれていく。フランス女性への恋慕(というか欲情)、従兄弟の死などのエピソードがあるが、最後に戦争が勃発してサナトリウムが閉鎖され、入院中の人々が戸惑うところで物語は終わる。
・・・とこうして書くとまあまともに見えるが、かなりしんどい映画だった。隣りの席で見ていたK君は途中で寝息を立てていたので肘でつついて起こした。Cも「居眠りはしなかったが何度も意識が遠のいた」と見終わった後で言っていた。なんというか話が唐突に展開してなんだか訳が分からないのである。小説ならその辺は丁寧に説明されるのだろうが。だからこの映画は原作を読んでいない人は見るべきではない。また原作を読んだ人ももしかしたらこのような映像化されたものは見ないほうがいいのかもしれない。主人公ハンスが吹雪の中、山小屋に向かうシーンがあって、原作では吹雪の様子や恍惚状態になるハンスの描写が素晴らしいらしいのだが、この映画では突然ハンスが雪山の中を歩くシーンになるので気でも狂ったのかと思うし訳が分からない。
「気でも狂ったのか」といえば、出てくる人物は周りも気にせず大声で議論したり叫んだりしたりしておかしいんじゃないのかという人ばかりである。原作ではこれが高尚な哲学論議とかになっていて、「魔の山」は「教養小説」というジャンルの棹尾を飾る作品とされているらしいのだが(筒井康隆の「文学部唯野教授」は物語中で主人公が文学論の授業をしたりするから、傾向としては似ているかもしれないが)、映画ではそこまで描きこめないので変人が次から次に出てくるようにしか見えない。映画の後でDが僕に向かって「ヨーロッパ人というのは皆頭がおかしいと思ったか?」と冗談混じりに聞いてきた。実ところこの映画に出てくる人物はドイツでは実際にその辺に居そうなところがまたすごいのだが。
(タビウサギさんのご教示により訂正:「教養小説」というのはBildungsromanの訳で、内容が教養的というのではなく、主人公の成長を描くジャンルのことらしい。したがって「唯野教授」は「教養小説」ではない)
そんな僕にもよく分かったのはハンスがフランス人女性に恋慕というか欲情するところだけだった(その口説き方もまたマンの小説によく出てくるタイプの変人みたいだったのだが)。というか結核で療養しているはずのハンスがえらく元気そうだったのがやはりまずかったのかもしれない。おいらにはこういう映画は難しいや。
40年近く政権の座にあったエヤデマ大統領の死後、大統領位の継承をめぐる政情不安が続く西アフリカのトーゴで、首都ロメにあるゲーテ・インスティテュート(半官のドイツ文化センター及びドイツ語教育機関)が武装した暴徒に焼き討ちされるという事件が起こった。所蔵されていた8000冊の書籍やコンピューターが焼失したという。
さらに首都ロメでは「ドイツ大使はナチスの過去がある。ドイツでは毎日我々アフリカ人がネオナチのリンチで殺されている」という扇動のビラも撒かれているという。このビラではギュンター・グローマン大使が1943年にナチス親衛隊に入ったと主張しているが、そうすると大使はとうに停年を迎えているはずであり得ない話である。なにかというとすぐにナチスと結び付けられてしまうドイツも大変ですな。また政府の意を汲んだ暴徒云々というのは最近どこかで見たような気もする。
ちなみにトーゴは1884年から1919年までドイツの植民地となっていた。第1次世界大戦後フランスの委任統治となり、1960年に独立している。1967年の軍事クーデタから政権の座にあったエヤデマ大統領が死んだ2月以来、政情不安と治安の悪化により3000人以上が隣国ベニンに逃げたという。またトーゴにはドイツ人300人がおり、ドイツのフィッシャー外相はトーゴの旧宗主国フランスなどと対応を協議している。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[映画] カテゴリの最新記事
教養小説
タビウサギ さん
えーと、ここでははじめまして、かな?(笑)
ドイツの「教養小説 Bildungsroman」というのは、内容が教養的ということではないのです。主人公の人間的成長(sich bileden)の過程が描かれているものをいいます。日本語に訳されたときに妙なことになっちゃったわけですね。
したがって、『文学部唯野教授』は教養小説とはいえませぬ。日本文学であんまり良い例が思いつかないけど、五木寛之の『青春の門』とか? (2005年04月30日 19時46分11秒)
ドイツの「教養小説 Bildungsroman」というのは、内容が教養的ということではないのです。主人公の人間的成長(sich bileden)の過程が描かれているものをいいます。日本語に訳されたときに妙なことになっちゃったわけですね。
したがって、『文学部唯野教授』は教養小説とはいえませぬ。日本文学であんまり良い例が思いつかないけど、五木寛之の『青春の門』とか? (2005年04月30日 19時46分11秒)
Re:教養小説(04/29)
>タビウサギさん
>えーと、ここでははじめまして、かな?(笑)
初めてだと思います。なんだか初めてじゃない気がするのは何でですかね?(笑)。
>ドイツの「教養小説 Bildungsroman」というのは、内容が教養的ということではないのです。主人公の人間的成長(sich bileden)の過程が描かれているものをいいます。日本語に訳されたときに妙なことになっちゃったわけですね。
なるほどBildungromanの訳ですか。それを教養小説と訳しちゃいかんですな。「成長小説」のほうが適当かも。ドイツ文学には全く疎いので日本語の字面だけで判断してしまいました。
>したがって、『文学部唯野教授』は教養小説とはいえませぬ。日本文学であんまり良い例が思いつかないけど、五木寛之の『青春の門』とか?
「教養小説」が適当な訳で無いなら「唯野教授」が教養小説にならないのは自明ですね。「魔の山」は読んだ事無いが「青春の門」は読んだぞい。自伝的という点では井上靖の「しろばんば」とかもそうなるのかな。
読んだこと無いけど池田大作の「人間革命」は小説じゃなくてただの自伝・自慢か(冷笑)。 (2005年05月01日 02時23分00秒)
>えーと、ここでははじめまして、かな?(笑)
初めてだと思います。なんだか初めてじゃない気がするのは何でですかね?(笑)。
>ドイツの「教養小説 Bildungsroman」というのは、内容が教養的ということではないのです。主人公の人間的成長(sich bileden)の過程が描かれているものをいいます。日本語に訳されたときに妙なことになっちゃったわけですね。
なるほどBildungromanの訳ですか。それを教養小説と訳しちゃいかんですな。「成長小説」のほうが適当かも。ドイツ文学には全く疎いので日本語の字面だけで判断してしまいました。
>したがって、『文学部唯野教授』は教養小説とはいえませぬ。日本文学であんまり良い例が思いつかないけど、五木寛之の『青春の門』とか?
「教養小説」が適当な訳で無いなら「唯野教授」が教養小説にならないのは自明ですね。「魔の山」は読んだ事無いが「青春の門」は読んだぞい。自伝的という点では井上靖の「しろばんば」とかもそうなるのかな。
読んだこと無いけど池田大作の「人間革命」は小説じゃなくてただの自伝・自慢か(冷笑)。 (2005年05月01日 02時23分00秒)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
フリーページ
Vortrag 18.6.2003

Einfuehrung

Yayoi-Zeit

3/4 Jhdt. n. Chr.

5/6. Jhdt. n.Chr.

7. Jhdt. n. Chr.

日本語版
過去の日記

考古学・歴史日記03年

考古学・歴史日記02年後半

考古学・歴史日記02年中頃

考古学・歴史日記02年前半

考古学・歴史日記01年
各国史

EU-25/2004(南欧)

EU-25/2004(中欧)

EU-25/2004(東欧)

EFTA諸国

ヨーロッパのミニ国家

EU加盟候補国

西アジア

アメリカ史(上) 建国

アメリカ史(中) 大国

アメリカ史(下) 超大国

カフカス諸国

バルカン半島(非EU)

EU加盟国(北欧)

スペイン史(1) 前近代

スペイン史(2) 近現代

EU-27/2007

中央アジア
ヘロドトス「歴史」を読む

その2

その3
「太平記」を読んで…
 New!
七詩さん
New!
七詩さん
復刻記事「韓国記事… alex99さん
不法滞在は即刻強制… シャルドネ。さん
北海道2023(その7) Leadcoreさん
Leadcoreさん
絨毯屋へようこそ … mihriさん
 New!
七詩さん
New!
七詩さん復刻記事「韓国記事… alex99さん
不法滞在は即刻強制… シャルドネ。さん
北海道2023(その7)
 Leadcoreさん
Leadcoreさん絨毯屋へようこそ … mihriさん
コメント新着
© Rakuten Group, Inc.