2011年06月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-

レグルスとエリダヌス 15
その衝撃にはっとする間もなく、怒涛のように、一連の記憶が押し寄せてきた。 深夜のリュキア神殿の、長く暗い廊下。 ひんやりと静まり返った礼拝堂。 その祭壇の前に、目覚めることのない深い眠りについた、闇の色の長い髪をした戦士。 苦い後悔。 自責と悲しみ。 呪わしい毒針を仕掛けた罠。 ケンタウロス。 迷宮。 城跡。 ゾーハルの酒場。 リュキア軍に敵意を抱く、生意気な、しかし凄腕の剣士。 名は、アンタレス。 私の片意地と油断によって見殺しにしてしまった、誠実な案内人! ――― こんな重大なことを、今まですっかり忘れていて、思い出しもしなかったとは! 背筋の凍りつくような驚愕に、レグルスは我を忘れて立ち上がった。 「思い出したぞ! 何もかも思い出した! こんな大変なことを、今までなぜ忘れていたのだろう! いや、それを考えるより先に、このことを早くベテルギウスにも知らせなくては! ああ・・・、彼の懸念こそが正しかったのだ!」 そのまま部屋を飛び出そうとしたレグルスに、エリダヌスが必死の面持ちですがりついた。 「お待ちくださいませ、レグルスさま! ご混乱はよくわかりますが、今、そのような恐ろしいお顔であの方のところへ飛んで行ったりなさってはいけません! お2人の記憶から消されたその事件、思い出されればベテルギウスさまもさぞや驚かれ、取り乱されるは必定。 お2人が万一暴走でもなさったら、御身に危険が及びかねません。 少なくともあなたさまご自身がいま少し落ち着かれてから、ベテルギウスさまに静かに事実を告げ、慎重に御対処なさるべきと思います。 どうか、冷静な御判断を!」 レグルスははっと足を止め、一瞬その存在すら忘れていた、この謎めいた布教師の顔を、まじまじと見下ろした。 エリダヌスの、その端正な面貌からは、明らかな配意以外、何も読み取ることはできなかった。 あたりの景色が、急にくらくらと渦を巻いて回転し始めたような気がして、レグルスは、こみ上げてくる吐き気を押さえながら、ようやく、かすれた声をしぼり出した。 「・・・エリダヌス、お前は何者だ? お前は、何を知っているのだ? 何のために、ここに来た?」
2011.06.30
コメント(2)
-

レグルスとエリダヌス 14
この返答に、レグルスは一瞬ぽかんと口を開け、それから、くすくす笑い始めた。 「・・・これは驚いた! 神官も冗談を言うことがあるのか? だが、エリダヌス、冗談とはそのように真面目な顔をして言ってはいけない。 バルドーラ相手に冗談を言うときは顔も笑え。 でないとそれが冗談であることが相手に伝わらず、話が混乱する」 が、エリダヌスはやはりにこりともせず、真剣極まりない表情のままじっと考え込み、それからまた、思い切ったように言った。 「・・・レグルスさま、私、以前から気になってしかたがないことが一つあるのですが、あなたさまの髪をいつも飾っているその髪飾り、それはどういったいわくのものなのですか? もしお差し支えなければ、この折に、近くでよく拝見させていただけないでしょうか」 この言葉にレグルスはまたまた唖然として、思わず自分の頭に手を伸ばした。 が、もちろんレグルスは髪飾りなんかつけたことはない。 「エリダヌス、ジャムルビーは皆そういうおかしくもない冗談で人を煙にまこうとするのか? ならば気をつけたほうがいい。 バルドーラ族にとって、身体の最上位に位置する頭は不可侵の尊厳を体現するところ。 忠誠の誓いのとき、相手の前にひざまずいて自分の頭に触れさせる、あの儀式も、あなたを君主としてこの頭上に戴き、わたしの心も命も捧げます、という表明だ。 さほどに大事な頭なれば、それに関する冗談は、バルドーラには口にせぬほうが安全だ。 髪飾りをつけているなどと笑ったら、ものも言わず殴りかかってくる短気なやつもいるぞ。 もっとも、その大事な頭も、中味に関しては、それほど神経質になることはないが。 たとえば、おまえの鈍い頭が回転し始めるのを待っていたら日が暮れてしまうとか、空っぽな頭を風に飛ばされないように用心しろとか、パピトたちがよく口にする軽口だが、その手の戯言なら、本気で怒り出す者もまず居るまい。 考えてみれば、同族ながら奇妙な習性だ」 エリダヌスは、冗談のつもりではなかったのですが、と、困ったように足もとに目を落とし、それから、また顔をあげて言った。 「では、その・・・、モノ、を、私が取ってもかまいませんでしょうか?」 たぶん、私の髪にゴミでもついているのだろう、とレグルスは考えた。 ゴミがついている、などと言ったら怒られるのではないかと、それを恐れて、髪飾り、などと妙な表現をしたのだろう。 レグルスは、こともあろうにジャムルビー族に頭を触らせるなんて、一生ぬぐいがたい恥辱になるんじゃないかと迷い、でも、ゴミを取ってもらうだけなんだから、床屋に髪を切ってもらうのと同じ、と考え直し、それにここは自分のプライベートな部屋、人に見られる気づかいもない、と、自分に言い聞かせて、さんざん迷ってからやっと、決心してエリダヌスの前にひざまずいた。 「ゴミだろう? 取ってくれ。 早くしろ。 私に恥をかかせるな」 言いながら、しかし、こわごわレグルスの頭に伸ばしてきたエリダヌスの華奢な白い手は、決してレグルスを不快な気持ちにはさせなかった。 それは、木陰を吹き抜ける夏の風のように、よどみなく優しく、涼しげに、レグルスの髪を心地よくくすぐり、レグルスはほとんどうっとりして、祝福とはこんな感じのするものだろうか、と考えた。 そのとき、エリダヌスの手がレグルスの頭を、ふっ、と離れた。 と同時に、エリダヌスが問う。 「アンタレス、って、誰ですか?」 ――― 一瞬、ぐらり、と大きく地面がかしいだような気がした。
2011.06.29
コメント(0)
-

レグルスとエリダヌス 13
レグルスの願いもむなしく、時は容赦なく過ぎて、エリダヌスは繕い物を終え、レグルスには信じがたい優雅で器用なやり方で、部屋着を羽織ったまま素肌をまったくさらすことなくもとどおり神衣を身につけるという技巧の秘技をやってのけ、あっという間に身支度を整えた。 レグルスの部屋着をきちんとたたむ、その手つきを眺めながら、レグルスは、その部屋着をたたみ終えたらエリダヌスが帰ってしまうことに突然思い至り、1分でもそれを遅らせようと懸命に話題を探し、しかし2人の間に共通の話題などほとんどないことに思い当たるとますますあせって、苦し紛れに、なにげなく視線を向けたベテルギウスの机に助けを求めた。 「・・・エリダヌス、お前に無礼な口を利いたベテルギウス少尉を覚えているな? 彼は私の一番の親友で、この部屋で寝起きをともにしているのだ」 エリダヌスは、ちょっと部屋の中を見回して、あまり興味なさそうに感想を述べた。 「・・・そうでしたか。 とても清潔な、すてきなお部屋ですね。 特に、窓がすてきですね。 私たちの宿坊に、窓はありませんから、憧れます。 ・・・でも、祭壇があればもっとすてきなのに」 レグルスはちょっと困って考え込み、エリダヌスが部屋着をたたむ作業を再開しようとすると、また、それを妨げるように言った。 「エリダヌス、あのときの少尉の無礼な態度を、どうか悪く思わないで欲しい。 少尉はただ、私の評判を心配するあまり、神経質になりすぎているだけなのだ。 本当はあんな礼儀を欠いたやつではないのに、このごろなんだか急に人が変わったようになって・・・病気ではないかと私も心配しているところなのだが」 エリダヌスが、はっとしたように顔を上げた。 「このごろ急にお変わりになった・・・? それは、いつごろからですか? どのようにお変わりになったのですか? レグルスさまは大丈夫ですか?」 思いがけないエリダヌスの反応に、レグルスは目をしばたたきながら応えた。 「私は大丈夫だ。 うつるような病気でもあるまい。 ・・・いつごろから? さて、はっきりと覚えてはおらぬが、お前がここに派遣されてくる少し前かな。 どのように・・・そうだな、沈み込んで何か考え事をしていることが多くなった。 何か大切なことを忘れているような気がする、と言って、その原因を神殿に求めているようだ。 それで、お前にも何らかの疑念を抱いているらしい。 一時的な病だと思うのだが」 エリダヌスは、息をつめてレグルスの言葉に聞き入り、長いこと何か考え込んでいるふうだったが、やがて、畳み掛けの部屋着を脇にどけ、決心したように口を開いた。 「いいえ、レグルスさま、私は、ベテルギウスさまがご病気とは思いません。 なぜなら、レグルスさま、あなたとベテルギウスさまのお2人は、あの晩、確かに、リュキア神殿においでになりましたから」
2011.06.28
コメント(0)
-

レグルスとエリダヌス 12
レグルスの部屋で、沈み込んだ様子のエリダヌスの口は重たかったが、タムタムの一方的な話によれば、おおよその事情はこういうことらしい。 タムタムは、エリダヌスが好きで、何とかして仲良くなりたいと思っているのに、エリダヌスは一向にそれに応えてくれない。 どころか、その態度は日増しに冷たくなるいっぽうだ。 このごろでは、タムタムから逃げ回っているようにさえ見える。 レグルスやレグルス隊の戦士たちは、そんなタムタムの様子を目にするたび、軽い気持ちで笑い者にしていたが、それは、タムタムの身になってみれば、つらいことだったに違いない。 これといった理由もないのに、邪険に自分を扱い、皆の笑い者の種にするエリダヌスが憎らしく思えることもあっただろう。 この日もエリダヌスは、訓練場の門をくぐったとたん、出迎えに駆けつけるタムタムの姿に気づくとあいさつもなしに急いで逃げ出そうとしたのだそうだ。 この態度にショックを受けたタムタムは、腹立ちまぎれにエリダヌスをちょっと困らせてやろうと思った。 クローバーが剣を折った話から思いついて、代わりの剣を武器庫から借りて来いとレグルスが命じた、と、エリダヌスを欺き、武器庫に向かわせた。 その際、エリダヌスの身を守る錫杖と楯を預かったのは、単純に、クローバーの重い剣を運ぶ邪魔になると考えたからで他意はなかった、と、タムタムは涙ながらに訴えた。 ただちょっとエリダヌスの困った顔が見たかっただけなのだと。 確かに、タムタムの目には、普段レグルスの戦士たちにまじって武芸訓練を受けているエリダヌスは、バルドーラ戦士たちと同格に映っていたことだろう。 武器庫に入って訓練用の剣を借りる ――― 戦士なら誰でも普通にやっている、見慣れた光景だ。 軽い悪戯のつもりだったに違いない。 あるいは、勝手がわからずにもたつくエリダヌスを助けてやって恩を着せようとか、かりに、エリダヌスにいちゃもんをつける輩が現れたとしても、常日頃、昼休みの食堂で休憩中の戦士たちの姿しか知らないタムタムには、そんなものは取るに足らない相手、得意の毒舌攻撃で自分が悪漢を追い払って、エリダヌスにいいところを見せ付けてやろうとか、そんな下心もあったかもしれない。 しかし、事はそう単純ではなかった。 バルドーラ族とジャムルビー族の間には、外から見ただけではなかなかわからない、深い溝が横たわっている。 あたりまえのバルドーラ戦士なら、自分たちの聖域ともいうべき武器庫に、ジャムルビー族がのこのこ入り込んでくるのを黙って見逃すはずがない。 もし逆の立場で表現するなら、それは、ジャムルビー神殿に土足で入り込んだバルドーラ戦士が、祭壇の上に胡坐をかいて見せるようなもの。 激怒して問答無用と襲いかかるのは当然の成り行きだ。 その現場に至って初めて、タムタムは事の重大さに気づき、レグルスに助けを求めてきた、ということらしかった。 身をよじって号泣しながら、馬鹿なことをしたと自分を責め、エリダヌスに許しを請うタムタムに、これ以上の説教も無用だろうと仕事に戻らせると、レグルスは、次にエリダヌスのほうを見やった。 エリダヌスは、さきほどレグルスが着せかけてやった部屋着を羽織って、窓辺の椅子に腰を下ろし、破けた神衣を繕っていた。 窓から差し込むやわらかな斜光の中で、エリダヌスには大きすぎる、レグルスの真紅の部屋着がゆるやかなドレープを作り、神衣を繕う白いたおやかな指先が、なめらかな動きで針を進めている。 手もとを見つめるエリダヌスの、うつむき加減の横顔は真剣で、その頬にかかった髪が、絹のような光沢を放っている。 ――― 美しい、と思った。 まるで、一服の絵画のようだ。 エリダヌスを、手放したくない、と、不意に、そう思った。 このまま、永遠に時が止まってしまえばいいのに!
2011.06.27
コメント(2)
-

レグルスとエリダヌス 11
するとこのとき、忘我の境のレグルスを押しのけて、タムタムが、2人の間に割り込んできた。 タムタムは、エリダヌスの喜びを我が事のように喜んで顔を上気させ、どさくさにまぎれてなれなれしくその肩を叩き、手を取ってぎゅっと握りしめた。 「凄えぞ、エリダヌス、おまえ、やるなあ! あんなでっかいやつを指先一本で吹っ飛ばすことができるなんて、そんな技を持ってるなら、いつまでも埒の明かない布教師なんかやってくすぶってることないだろう。 いっそ神兵になれよ! リュキア軍に正式入隊して、レグルスの部隊に入れてもらっちゃえ!」 無骨なレグルスには、羨望を覚えるほど、まっすぐで情熱的な言祝ぎに聞こえたが、エリダヌスのほうは、なぜか急に表情を固くして、タムタムの手を乱暴に振り払った。 「布教のお役目は、神さまが私にお与えくださった大切な修行のひとつです! 私は、くすぶっているのでもなければ軍への入隊を望んでいるわけでもありません! おかしなことをおっしゃらないでください」 常日頃から、うるさくしつこくつきまとうタムタムに辟易している様子のエリダヌスだが、これはまた、いつにもまして剣のある言い方だ。 さらに驚いたことに、いつもならこのていどのあしらいは柳に風と受け流して、もっと過激な冗談を返してくるはずのタムタムのほうも、今日はまるで青菜に塩、しょんぼりとうなだれて、哀れっぽい声であっさりとエリダヌスに謝罪したのだ。 「あ・・・そうだよな。 よけいなこと言って、ごめん。 ・・・ああ、それじゃ、エリダヌス、その服の破けたところ、俺が繕ってやるから、医務室に来なよ。 俺、繕い物得意なんだ。 お針子さんになればよかったのに、って、よく人に言われるんだぜ」 が、おもねるように笑ったタムタムのこの言葉も、エリダヌスはぴしりとはねつけた。 「けっこうです! 繕い物なら、私も得意ですから、あなたの手を煩わせるまでもありません」 「じゃ裁縫道具だけでも医務室から・・・」 「裁縫道具も持っていますからお構いなく!」 それきり、エリダヌスとタムタムは互いに目をそらし、ぎこちなく黙り込んだ。 2人の間に何かあったな、と感じたレグルスは、厳然とした口調で2人に命じた。「エリダヌス、タムタム、2人とも、ちょっと私の部屋に来い。 エリダヌスがなぜひとりで武器庫にいるのか、錫杖はどこに置いてきてしまったのか、なぜタムタムがいち早く異変を知って私を呼びに来るにいたったのか、この騒動の一部始終をとっくりと聞かせてもらうぞ。 2人とも、いいかげんな説明で私をごまかそうとするなよ」
2011.06.26
コメント(0)
-

レグルスとエリダヌス 10
レグルスの、常になくうわついた声の調子に、エリダヌスも、はっと我にかえったように顔を赤らめ、破けた神衣の胸もとをあわてて掻きあわせた。 「・・・あ、ありません」 頬を桜色に染めてうつむいたエリダヌスに、ためらいながら手を差し伸べようとしたとき、エリダヌスが、不意にその表情をこわばらせた。 ついで、エリダヌスの細いたおやかな腕が、突然、差し伸べたレグルスの手を避けるように、荒々しく前方に伸びる。 と同時に、その美しい唇から、思いがけないほど激しい気合が発せられた。 「Ψ→ヒムス壱ファルドーシャ!《蜂》Ψ」 そのせつな、レグルスの顔のすぐ横を、目には見えない、しかしとてつもなく重たいものが、猛スピードで、ざっ、と駆け抜けて行ったのを感じた。 とっさに身構えたレグルスの髪を衝撃波で巻き上げながら、後方に通過していったそれが、何かに激しく衝突してけたたましい音を立てた。 同時に、あちこちから上がった武器管理官たちの、わわっ、とか、ひゃー、とかいうしまりのない悲鳴。 振り向いたレグルスの目に映ったのは、さきほど退散していったばかりの下級戦士が、武具の並べられた棚のひとつにしたたか叩きつけられ、その勢いで外れ落ちた棚から、兜や短剣などの武具が、ガラガラとけたたましい音を立てて床に散乱した場面だった。 頭上に崩れ落ちてくる棚板や武具の下敷きになって、昏倒したその下級戦士の手には、不恰好な大型の剣が、抜き身のまま握りしめられていた。 レグルスに怒鳴りつけられ、赤っ恥かかされて、くやしまぎれに意趣返しをしてやろうと考えた下級戦士が、こっそりレグルスの背後に忍び寄り、襲いかかろうとしたものと推察できた。 いちはやくそれに気づいたエリダヌスが、レグルスを守ろうとして、何かしたらしい、ことも察しがついたが、さて、目の前のこの非力なエリダヌスが、どうやってあの大きなバルドーラ戦士を、一瞬のうちにはるか向こうの棚までも投げ飛ばしたのかは、レグルスには見当もつかないことだった。 「・・・エリダヌス、今の技は、いったい・・・?」 信じられない思いが先にたって、たずねるともなく声に出したレグルスだったが、どういうわけか、エリダヌス自身もまた、信じられない、といった表情で、自分の手や腕を不思議そうに眺め回している。 「・・・できた! 『燕』の呪法その1『神罰』!」 エリダヌスの顔に、会心の笑みが、ぱーっと広がった。 大きな喜びの波に押し流されるように、息を弾ませて立ち上がったエリダヌスが、レグルスの手を取り、声を上げて笑い、今にも抱きつかんばかり、興奮した様子で天に向かって叫んだ。 「ああ、神さま、感謝します! 私にも、とうとう『法力』の御技をお授けくださったのですね!」 なおもはじけるエリダヌスの歓喜の声は、レグルスにも向けられた。 「レグルスさま、ありがとうございます! あなたさまのおかげで、私は、長い間授からなかった法力を、今初めて、授かることができました! すべてレグルスさまのおかげです! なんとお礼を申し上げたらいいのでしょう、あきらめず練習を積んできて、本当によかった!」 ともかく、ジャムルビー神官たちの操る法力とやらを使うとこんな不思議なことができるらしい、そして今までそれのできなかったエリダヌスが、今初めてその技に成功したらしい、ということだけはおぼろげに理解でき、その嬉しさはレグルスにもよく理解できるところだったので、それを一緒に喜んでやろうか、それとも、その前に、軍の武器庫に無断で侵入したことを叱責するべきか、レグルスは迷いに迷ったあげく、結局は、自分の手をしっかり握りしめたエリダヌスの柔らかな手の感触がすばらしく心地良く、輝くその笑顔がこの上なく嬉しく、ただ、深い幸福感と、鼻をくすぐる優しい髪の香りに包まれて恍惚としているだけなのだった。
2011.06.25
コメント(6)
-

レグルスとエリダヌス 9
「レグルスさま!」 もがきながら泣き叫ぶエリダヌスを見て、レグルスは仰天した。 エリダヌスが、まったくの丸腰 ――― その手にはいつも持っている錫杖さえなかったからだ。 怒りが突き上げてきた。 このようなところを丸腰でうろつくエリダヌスのうかつさと、その丸腰の神官に容赦手加減なく襲いかかる戦士の粗暴さの、双方に、同じくらい腹を立てて、レグルスは、無言でいきなり、訓練用の木剣ではなく愛用の武太刀サーバルキャットを抜き放った。 ぶん、と、重たいうなりを上げて、サーバルキャットが舞う。 はっと振り返った下級戦士の鼻先をかすめて、振り上げたサーバルキャットが、レグルスの頭上でもう一度、ひらりと舞う。 重量のある武太刀を、両の手で、大上段に持ち替えて、さらに一歩、大きく足を踏み出した。 怒りをむき出したレグルスの、掛け値なし正真正銘真剣勝負の気迫に、殺気すら覚えたか、下級戦士があわててエリダヌスから離れた。 迎え撃つべく腰を落として剣に手をかけた下級戦士の肩に、渾身の力を込めたサーバルキャットが、容赦なく襲いかかる。 「レグルス軍曹! おやめください!」 「武器庫にての乱闘は御法度! なにとぞ剣をおおさめください!」 騒ぎを聞きつけて飛んできた武器管理官たちに押しとどめられて、かろうじて自制を取り戻したレグルスの前から、命拾いした下級戦士が、悔しげな面持ちで退散していった。 大きく息を吐き出し、息を整えながら荒ぶる衝動を押さえ込むレグルスに、武器管理官たちが、ほっとしたようにその場を離れ、床に散乱した武具を片付けはじめた。 太刀を鞘におさめるとレグルスは、まだ隅で震えているエリダヌスを眼光鋭く睨んだ。 入室はおろか近づくことも禁じていた武器倉庫に、しかも丸腰で入り込んだ愚かさを、きつく戒めなければと思ったからだが、その怒りは、ショックを受けて怯えきったエリダヌスの姿を見るなり、急速にしぼんでしまった。 フードが脱げて、白い肩まであらわになったエリダヌスの、血の気の失せた顔が、真っ直ぐにレグルスを見上げていた。 涙を湛えて大きく見開かれた、その瞳は、日の光のように明るい、澄んだ銀色をしていた。 あの、悪夢のような砂漠の夜、たった一度見たきり、どうしても思い出すことのできなかった瞳の色だ。 絹糸のようになめらかな白銀の髪は、レグルスが初めて見たときより少し伸びて細い肩先にまで達し、小窓から差し込む外光を受けて、きらきら、細かく震えている。 さらに、エリダヌスの、破けた神衣の胸元から、目にしみるほど白い、大理石のようにすべすべした肌が、まぶしくレグルスの目を射るにいたって、レグルスは突然、どぎまぎとうろたえ、赤面して、あわててそこから目をそらした。 「・・・エリダヌス、怪我はなかったであろうな?」 きつく叱りつけようと思っていたのに、妙にうわずった、かすれた声しか出なかった。
2011.06.24
コメント(4)
-

レグルスとエリダヌス 8
アーモンドも、窓の外の、通用門のほうを見やってくすくす笑い出した。 「ほんとだ。 あいつ、またエリダヌスさんのところに飛んで行っちゃったんですね。 エリダヌスさんにあんなに嫌われちゃってるというのに、よく懲りないもんだなあ」 「それがタムタムのいいところだろう。 もしあいつが、冷たくされて傷つくようなデリケートな神経の持ち主なら、エリダヌスもああまでタムタムを冷淡に扱うことはできまいからな。 ・・・ではアーモンド、お前は一足先に訓練場へ行って、皆に自主訓練を始めさせてくれ。 私は、このクローバーの手が生き返るのを見届けてから行くから。 エリダヌスの指南役を争って、喧嘩なんかさせるなよ」 「了解しました、軍曹殿!」 折り目正しい敬礼をして、アーモンドが出て行ってしまうと、レグルスは、クローバーと2人で遅い昼食をとり始めた。 ところが昼食は、またしても、どたばたと駆け込んできたタムタムの叫び声で中断させられた。 「レグルス、助けてくれ! 早く来てくれ! エリダヌスが、殺されちゃう!」 「何だって? 今、喧嘩するなと言ったばかりなのに、いったい何事だ!」 びっくりして立ち上がったレグルスの手を、タムタムが、泣きながら引っ張る。 「わけなんかどうでもいいから、早く来て! 武器倉庫だ! エリダヌスが、よその隊の下級戦士に、インネンつけられてるんだよ! 早く早く! 急いで!」 「武器倉庫? なぜエリダヌスがそんなところに・・・」 半信半疑ながらも、ただならぬタムタムの様子に、あわてて武器倉庫に駆けつけると、廊下の中ほどまで来たところで、まさしく、突き当りの武器庫の中から、エリダヌスの鋭い悲鳴と、それに重なって、知らない戦士たちの、エリダヌスを罵倒する声が聞こえてきた。 口汚くエリダヌスを罵る下級戦士たちの粗暴さと、あれほど固く禁じた武器庫に足を踏み入れたエリダヌスのうかつさと、双方に対する怒りに青ざめて、レグルスは武器倉庫の中へ飛び込んだ。 「静まれ! 何の騒ぎだ!」 倉庫の隅で、身づくろいもだらしない下級戦士が、3人がかりでエリダヌスを壁に追いつめ、悪態をつきながら今にも暴行に及ぼうとしていた。 レグルスの、雷神もかくやの怒声に、3人のうちの2人はぎょっと身をすくめ、エリダヌスから離れたが、あとの1人は、レグルスの声が聞こえなかったのか、それとも、聞こえないふりをしているのか、エリダヌスの細い首を締め上げた手にますます力を込め、怒鳴り続けている。 「・・・ちゃんと答えてみろよ、ええ? ジャムルビー風情が、いったい何をしに、リュキア・バルドーラ軍の武器庫に忍び込んだのかと、聞いているんだ! 俺らの魂の武器に、呪いをかけて俺らを戦えなくするためか? それとも、盗み出して反乱でも起こす気か? ジャムルビーは、ジャムルビーらしく、穴ぐら神殿の中にひっこんでおとなしくしてりゃいいものを、図々しくこんなところまで入り込んでくるとどんな目にあうか、ちょうどいい、お前を見せしめにして、広場でさらしものにしてやる!」
2011.06.23
コメント(0)
-

レグルスとエリダヌス 7
そのとき、救急箱を手に戻って来たアーモンドが、真っ青になってがたがた震えているクローバーを見、びっくりしたように叫んだ。 「クローバー、どうしたんだ! 死人のような顔色だぞ! 気をしっかり持て!」 それを聞くと、クローバーはわっと泣き伏して、涙ながらにアーモンドに言った。 「アーモンド伍長殿! 長い間、お世話になりました。 俺は、最後までレグルス軍曹とあなたのために戦うことができなくて、残念でなりません! ああ、無念で、いっそこのまま死んでしまいてえ!」 アーモンドが、目を丸くして、クローバーからレグルスに、視線を移した。 レグルスはなおも笑いをこらえて、涙に暮れるクローバーの肩を、両手でがしっとつかみ、言った。 「だが、まだあきらめるのは早いぞ、クローバー。 お前の手がまだ動くなら、今のうちに、早く手当てをすれば助かるかもしれぬ!」 ぱっと顔を上げて、クローバーがレグルスにすがりついた。 「ほんとですか?! 軍曹殿、お願いです! お願いですから、俺の左手を助けてください! ほら、まだ動いてますもん! 今のうちに、こいつが死んだことに気がつく前に、早く! 早くっ!」 「もちろんだ! 早くこっちに手を出せ! 急げっ!」 「はいっ!」 もう血は止まっていた。 レグルスは笑いをこらえて、神妙な顔で血止めの布を取り去り、傷口の消毒を始めた。 消毒液をつけたとたん、クローバーが、痛えっ!と悲鳴をあげ、反射的に手を引っ込めた。 レグルスは、すかさずその手をつかまえて叫んだ。 「よしっ! 生き返ったぞ! もう大丈夫だ!」 クローバーの顔が、痛みと安堵とで、泣き笑いになった。 「タムタム、救急箱から傷薬を取ってくれ」 レグルスが命じると、タムタムはあわててかじりかけのきゅうりを口の中に押し込み、傷薬の蓋を開けてレグルスの前に差し出しながら、クローバーに言った。 「クラーヴァー、カナカシャラワ、シャウィルジャー!(クローバー、この薬はしみるぞぉ)」 クローバーは、涙を浮かべて、俺の手が死なずにすむならなんだって我慢する、と言い返した。 アーモンドが、さっきからずっと下を向いたままひと言もしゃべらないのは、笑いをこらえているからだ。 傷薬を塗り終わると、タムタムが救急箱から包帯を取り出し、レグルスに差し出した。 タムタムが、使い終わった傷薬にしっかり蓋を閉め、救急箱に戻すのを横目で確かめながら、レグルスは、クローバーの腕に念入りに包帯を巻きつけた。 「よし、これで手当ては完了だ。 たぶん、これでお前の左手は一命を取りとめた、と思う」 クローバーが、情けない顔でレグルスを見上げた。 「・・・と思う? 思う、だけですか? 軍曹殿、言ってくださいよ、俺の手はもとどおりになるって!」 「私は、いいかげんな気休めは言わぬ。 一度は死にかけたこの手が、もとどおりになるかどうかはまだわからない。 少なくともあと2時間ほどは様子を見なければ。 2時間たってもちゃんと動くようなら、もう大丈夫だろう。 きっと午後の訓練には出られる。 ・・・おい、タムタム、包帯を巻き終わった。 はさみを取ってくれ」 クローバーは、あと2時間か!と嘆息してつぶやいたが、タムタムからは何の返事もなかった。 振り返ると、タムタムの姿はいつのまにか消え失せ、かわりにアーモンドが、はさみを差し出しながら笑った。 「タムタムのやつ、また雲隠れしちゃったようですね。 まったく、あいつときたら最後までちゃんと仕事をしたことが一度もないんだから」 アーモンドの手からはさみを受け取りながら、なにげなく窓の外に目をやって、レグルスは思わず吹き出した。 「いや、タムタムにはもっと大事な用事ができたようだぞ。 外を見てみろ。 エリダヌスが来た」
2011.06.22
コメント(0)
-

レグルスとエリダヌス 6
レグルスは、ほとんどあきれ返りながら、急いで自分の懐から取り出した布で、血止めを始めた。 「大した怪我じゃない、だと? お前は本当に、この傷で、訓練を続けられると思っているのか? あきれたやつだな。 だいたい、痛くないのか?」 「痛くないこたありませんけど。 でも動かないことはない。 剣くらい持てます」 レグルスは、傍らに立っているアーモンドに、医務室から救急箱を取ってくるように命じると、難しい顔つきでクローバーに言った。 「そうか。 大して痛くなさそうな顔だな。 では、お前の左手は、きっともう死んでしまったのだろう」 クローバーの目が、まんまるになった。 「俺の手が、死んじまった? ・・・そんな馬鹿なことがあるもんですか! ほら、指だってちゃんと動く」 言って、クローバーが、ひらひらと指を動かして見せる。 レグルスは、不思議そうな表情を作ってその指の動くのをまじまじと見た。 「おや、本当だ。 おかしいな。 この筋を切ってしまうと、手首から先は死んでしまうはずなのだが。 ・・・ああ! それではきっと、お前の左手は、人より少々鈍いのだろう。 まだ自分が死んでしまったことに気づいていないのだ」 クローバーの顔が、ちょっと曇り始めた。 「ま、まさか! 手だけ死んじまう、なんて、聞いたこともない! 脅かそうったってだめですよ、軍曹」 レグルスは、真剣極まりない顔で首を横に振った。 「いや、クローバー、手だけ死んでしまうことだって、例は少ないが、あるのだ。 もう少し待ってみればわかる。 きっと、この手は、自分の死んだことに気づいて動かなくなるはずだ。 まちがいない」 クローバーの後ろで、タムタムが、片手にかじりかけのきゅうりを持ったまま、赤くなって笑いをこらえている。 クローバーが、不安そうに自分の左手を見下ろした。 「そ、そしたらどうなるんですか?」 レグルスも、笑いをこらえるために思い切り顔をしかめて答えた。 「もちろん、動かなくなってしまえばただの肉。 まもなく腐り始めるに決まっているだろう。 そうなると臭くて困るぞ。 すっかり骨だけになってしまうまでの間、しばらく鼻をつまんで暮らさなくてはならないな。 不便なことだ」 クローバーの顔が、すーっと青くなった。 レグルスは、そ知らぬ顔で続けた。 「わが軍では、片手が骨だけの戦士を戦闘員に加えてはならぬという規則があるから、クローバー、残念だがお前には引退してもらわなければならない。 私も、お前のような有能な戦士を失うのは悲しいが、軍規によりやむを得まい。 せめてものはなむけに、引退後のお前の身のふりかたを一緒に考えさせてくれ。 さて、片手が骨だけでもできる仕事というと、どんなものがあろうかな。 皆もいっしょに考えてくれ」
2011.06.21
コメント(2)
-

レグルスとエリダヌス 5
午前中の訓練が少し早く終わったその日、まだ人の姿もまばらな食堂でレグルスが昼食を食べ始めたとき、アーモンドが、いつにない思案顔で現れて、レグルスにこう言った。 「軍曹、お食事中に失礼します。 今、うちのクローバー2等戦士が、どういうはずみか、うっかり剣を折ってしまったんです。 クローバーは、今エリダヌス師の武芸指導に当たっていますから昼休みの自主訓練はどうしても休みたくない、代わりの剣を軍の武器庫から借り受ける許可を、レグルス軍曹にもらいたいと言ってきかないんですが、どうしましょうか?」 「剣を折った? そんなこと、いちいち私にお伺いを立てなくても、さっさと自分で武器庫へ行って借りればいいだろう? いつもそうしているじゃないか。 ・・・でも、まあいいや、可愛い部下の要望だ、今日のところは私が武器庫へ行って、適当な剣をみつくろってきてやろう。 クローバーの得物は、長剣だな?」 スプーンを置いて立ち上がろうとしたレグルスを、アーモンドが急いで止めた。 「いえ、軍曹、そうではなくて、クローバーは・・・」 言いかけたその時、当のクローバーがほかの戦士たちに取り囲まれるようにして食堂に入って来た。 その一行を得意そうな顔で先導してくるのは、雑用係のタムタムだ。 見ればクローバーは顔面蒼白。 左手の手の手首の辺りを白い布でしっかり押さえ、その布が、みるみるうちに血の色に染まっていくのが遠目にも見て取れる。 「クローバー、怪我をしたのか?!」 驚いて吹っ飛んで行ったレグルスに、タムタムが、クローバーの背中を小突いて言った。 「レグルスよ、この頑固な兄ちゃんは、どうしても医務室に行こうとしやがらねえんだ。 このまま自主訓練に出るの一点張り。 ともかく手当てを頼むぜ。 それと、説教も」 クローバーが足の先でタムタムを追い払って、面目なさげにレグルスを見上げた。 「いや、医務室に連れて行かれるような大した怪我じゃないんです。 折れた剣のかけらが飛び散って、小さい破片が刺さっただけなんですよ。 破片はもう自分で引っこ抜いたし、血も、昼飯を食ってる間に止まるでしょう。 だから、先に、剣を借りる許可証を書いていただけませんか? 今俺が行っても、この怪我を理由に貸してくれないかもしれないですもん」 「当たり前だ。 怪我人に剣なんか貸してくれるもんか。 もし喧嘩による怪我だったら、さらに大事件を引き起こす可能性があるだろう? ・・・ともかく手当てをしなければ。 クローバー、ここに手を出して見せろ」 近くのテーブルに座らせようとすると、クローバーはあわてて、怪我した手を背中に隠し、口答えした。 「いや、ほんとに、怪我なんていうほどのもんじゃないんですよ。 俺、ふだんから、血の気が多いとか言われてるんですから。 血なんか少し流れ出して減ったほうが、身軽になって動きも敏捷になるかも・・・」 「いいから、黙ってここに手を出せ。 命令だぞ、クローバー。 手当てを受けないうちは許可証も与えない」 それを聞くと、クローバーはしぶしぶレグルスの前の椅子に腰を下ろし、既に真っ赤にぬれている布に包まれた左手を、テーブルの上に乗せた。 「ほんとに、大した怪我じゃないんです。 お願いですから、この傷では午後からの訓練は受けられないなんて、言わないでくださいよね」 「それは傷によって判断することだ。 おまえは少し口を閉じていろと命じたぞ、クローバー」 言いながら、汚れた布を取り去って、レグルスは目を丸くした。 クローバーの手の、手首より少し上のあたりがざっくりと大きく裂けて、そこから、どくどくと真っ赤な血が流れ出していたからだ。
2011.06.20
コメント(0)
-

レグルスとエリダヌス 4
リゲルの机の本立てには、とても入りきらないほどのさまざまな本が乱雑に積み上げられ、そのあちこちから、無造作に折り込んだページの端がはみ出していた。 開きっぱなしの本も何冊も放り出され、それらのページには小さな字でぎっしり書き込みがしてある。 机の上には、何か書き込んだ紙やいたずら書きをした紙、まだ何も書かれていない白い紙など、紙類がこれ以上並べようがないほどごちゃごちゃと並んで、ほとんど机が見えないくらいだし、そこに乗りきらなかった書きなぐりの紙は机の下まで占領している。 しかも、そういった紙類は机の引き出しからも顔をのぞかせ、そのために、ちゃんと閉まらない引き出しはどれも半開きのままだ。 大混乱の中にあるのは紙だけではない。 何本もの羽ペン。 蓋を開け放したままのインク壺。 ここではほとんど何の役にも立っていないだろうと思われる文鎮。 止めピン。 ペーパーナイフ。 コンパス。 メジャー。 糸巻き。 虫の標本。 ペンキ。 はさみ。 砂時計。 ありとあらゆるものが放り出されている。 やれやれ、これではまるで、物入れの中の物を全部机の上にぶちまけたようだ、と、机の下の物入れに目を移せば、案の定、物入れの蓋はぱっくりと口をあけたまま、中には、無造作に突っ込んだブラシとか磨き粉の袋、砂袋、地図、手紙類などと一緒に、なんと、ここからも、机の上と同様の紙類が顔をのぞかせていた。 もちろん、その前に置くのが決まりの靴も、右と左がはるか遠くに喧嘩別れしたまま、どちらもふてくされたようにそっぽを向いて転がっている。 その惨状に、ひとり苦笑をもらしていると、リゲルが、2人分のお茶を手に再び姿を見せた。 リゲルは、普通の訓練生たちとはおよそ異なる、上等な絹のローブを無造作に着こなして、これも南天舎の大食堂で出されるお茶とは天と地ほども違う、甘い香りがたちのぼる高級そうなお茶を、レグルスの前に置いて言った。 「さあ、軍曹、どうぞ召し上がってみてください。 家の自慢のお茶なんですよ。 もしお気に召したら、今度軍曹のお部屋にも一箱お届けします」 レグルスは思わず吹き出しながら、カップを手に取った。 「おやおや、リゲルはいつの間にお茶屋になったんだろう! 私相手に商売か? だが、残念ながら私は、こんな高価そうなお茶を毎日飲むような金持ちではないぞ。 ときどきお前にこうしてご馳走してもらうのを、あてにするより他ないな。 ・・・そんなことより、リゲル、お前の話というのを聞かせてくれ。 チェリーのことで、何かわかったのか?」 リゲルが、ちょっとびっくりしたように目をぱちくりさせてから、しょんぼりと椅子に腰を下ろした。 「ああ、チェリー一等戦士殿のことですか・・・。 それが実は、なかなか外出許可が下りなくて、調査に出られないんですよ。 ほかの戦士の方々にも、それとなく聞き込みはしているんですけど、なんだかみんな口が堅くて。 外出許可は一応3日後にもらったのですが、もし、それでは間に合わないのなら、今夜にもさっそく・・・」 今度はレグルスが、目をしばたたいてリゲルの話をさえぎった。 「いや、それは別に急いでいないからいつでもよいといっておいたはずだぞ。 それなら、リゲル、チェリーのことでないなら、おまえの話というのは、何だ?」 リゲルの目がますます丸くなった。 「へっ? 話? 私の話、って、何のことでしょう?」 「おかしなやつだな、リゲル。 お前が話があると言うから、私はここに来たんだぞ」 リゲルは天井を見上げて考え込み、それから、レグルスにぺこりと頭を下げた。 「すみません、軍曹。 別に話なんかなかったんです。 ただ、軍曹においしいお茶をご馳走したかっただけなんです。 嘘をつくつもりはなかったんですけど・・・でも、このお茶、本当においしかったでしょ? 来て損はなかったでしょ? 今度軍曹のお部屋にも届けますよ! お金なんかいりません!」 その、けろりとした物言いに、レグルスも思わず吹きだした。 きっと、ベテルギウスに腹を立てて目をつりあげていたに違いない自分を見て、軽率な真似をするなと言いたくて強引に引っ張って来たのだな、と思った。 リゲルが、可愛い、と思った。 レグルスは、重々しくうなずいて、答えた。 「確かに、美味なお茶であった。 ではリゲル、私に嘘をついた罰として、お前の分のお茶を半分、手土産として今私によこせ。 後でわざわざ新しいものを届けるには及ばぬ」 リゲルが、ぱっと顔を輝かせ、お茶を取りに飛んで行った。
2011.06.19
コメント(4)
-

レグルスとエリダヌス 3
リゲルの言うことにも一理あると思った。 このごろのベテルギウスの様子ときたら、ぼんやりして返事もしないと思えば、突然、激昂してエリダヌスや神殿を誹謗し始めたり、確かに、リゲルの言うとおり、今あの状態でベテルギウスをひとりにしておいたら、どんな妄想にとりつかれて、どんな無茶をしでかすかわからない。 やはり、多少の不快には目をつぶって、ベテルギウスがますますおかしな方向に暴走しないように、今は自分が見守ってやらなければならないときかもしれない。 もしも、リゲルの言うように、病気のためにベテルギウスがおかしな妄想にとりつかれたのならば、その病気さえなおればベテルギウスは、もとの、冷静沈着な頼もしいベテルギウスに戻ってくれるだろう。 そう考えると、あれほど高ぶっていた憤りも、しだいに、病気の親友に対するおおらかな思いやりの気持ちへと変わっていって、レグルスは、この、適切な忠告をくれたリゲルに、素直に感謝の目を向けた。 「お前の言うとおりかもしれない、リゲル。 私は少尉殿に、頭が変になったんじゃないかなどと言いながら、まさか本当に少尉の心が病んでいるなどとは考えず、感情的になりすぎていたかもしれない。 ・・・そうだな、個室に移ることを願い出るのは、ひとまずやめて、今はおまえの忠告に従い、少尉の病気がどのくらい悪いのか、しばらく様子を見ることにしよう。 あまり度が過ぎるようなら、ブロイリング医師に相談する。 おまえに話をしてみてよかった、リゲル」 リゲルが嬉しそうにうなずき、自分の部屋のドアを開けて、レグルスを招き入れた。 「よかった! レグルス軍曹、ベテルギウス少尉は、あなたにとって大切な方ですよ。 養成学校時代から、いつも、一途に突っ走ろうとなさるあなたに、冷静な判断力を取り戻してくれる、頼もしい参謀だったではありませんか。 今は御病気だったとしても、あの方と仲たがいなんかなさるべきではありません。 ・・・あ、軍曹、今、とっておきのお茶をご馳走しますから、ちょっとそこにかけて待っててくださいね! まず服を着換えてまいりますので、ちょっと失礼します」 リゲルが、着替えのために、カーテンの向こうに姿を消すと、レグルスは、部屋の隅に置かれた小さなテーブルセットの椅子に腰を下ろして、リゲルの部屋を、見るともなく見回した。 この部屋は、レグルスとベテルギウスの部屋と同様、リゲルとアルタイルの2人部屋で、内装もほぼ同じだ。 部屋の左右に、それぞれのベッドが作りつけられてあり、その足もとの方に簡素なロッカー、頭の方の壁には大きな窓がひとつあって、その下に、2人の机が並んでいる。 アルタイルの机は、レグルスやベテルギウスのものと同じように、小さな本立てやインク瓶やペン立てが少し並んでいるだけで、ほこりひとつなく、きちんと片付いている。 机の下の小さな物入れも、きちんと奥のほうに押し込んであり、その前に、アルタイルの、少し細めのスマートな靴が、ぴかぴかに光って並んでいるのも同様だ。 だが、その隣のリゲルの机は、まるで乱闘中の部隊、これ以上散らかしようがないほどとり散らかっていた。
2011.06.18
コメント(3)
-

レグルスとエリダヌス 2
レグルスは、可愛い後輩、リゲルには、本音を吐いてうなずいた。 「まあ、そういうことになる。 ベテルギウス少尉は、今布教に来ている神官に何か疑念を抱いていて、あの者が私に接近することにひどく神経質になっている。 私のため、と少尉は言うが、ひとの任務について度を過ぎた口出し、かえって迷惑だ。 今日も少尉は、レグルス小隊の自主訓練の見学という口実でやって来て、戦士たちの前で布教師を中傷した。 あんなことをされては不愉快極まりない」 リゲルは、ちょっと考え込んでからうなずいた。 「・・・確かに、自分を思っての忠告と頭ではわかっていても、あんまり口うるさく言われると腹立たしく感じますよね。 軍曹のお気持ち、リゲルもよくわかります。 でも、ベテルギウス少尉にとっては、それは軍曹のお立場を思うが故の御苦言。 ならば、そのために部屋まで変えてもらうなんて、少尉の御厚意に対して失礼に当たりませんか? どちらにとっても、あまり名誉な話ではないように思えますけど」 リゲルがこんなふうに考えるのももっともだと思われたので、レグルスは、顔をしかめながら言った。 「もちろん、良いことだとは思っていない。 が、最近のベテルギウス少尉の考えは、私の理解の域を超えているのだ。 リュキア神殿が、何か良からぬ目論見を抱いてわが軍に布教師を送り込んでくる、とか、エリダヌスは私の行動を監視する目的で私の小隊にばかり張り付いているのだ、とか、あるいはエリダヌスに、単身でベテルギウス小隊に布教に来ることを強要するなど、あれではまるで、エリダヌスと下級戦士たちとの間にいらぬ揉め事を引き起こし、私の任務を妨げようとするようなもの。 だから私は、ベテルギウス少尉への礼儀よりは、任務に支障を来たさないほうを優先した」 リゲルがまた、ちょっとびっくりしたように目をしばたたいてレグルスを見上げた。 「へええ! ベテルギウス少尉が、そこまで? ・・・ふーん、なかなか鋭いんだね、あのひと。 ・・・あっ、いや、その、えへん、ベテルギウス少尉は、なぜそんなことを考えついたんでしょうね。 少尉って、もともと、ジャムルビー族に対して、それほど偏見を持っておられない方と思っていましたけど」 レグルスは、ちょっと迷ってから答えた。 「こんなことをおまえに打ち明けていいものかどうか・・・少尉の名誉のため、口外しないでほしいのだが、実は、少尉は、このごろ急にリュキア神殿を敵視するようなことを口走るようになったのだ。 何を根拠にそんなことを考えついたのかわからぬが、少尉と私がリュキア神殿で何か重大な秘密でも目撃したかのように思い込んで、しかもその内容をすっかり忘れてしまっていると、固く信じ込んでいる。 だが、そのことを思い悩んでいるほかには、おかしなところはまったくないので、ブロイリング医師に相談しようかどうか、正直、私も迷っているところなのだ」 リゲルは、うーむ、とうなったきり、長いこと何か考え込んでいたが、やがて、笑顔に戻って言った。 「・・・そりゃ確かにおかしいですよね。 そんなおかしなことを考え出すなんて、確かにあの方らしくないことだ。 だったら、軍曹はますます、個室になんかお移りになるべきじゃないですよ。 こんなことを申し上げては失礼かもしれませんけど、ベテルギウス少尉は、一時的な、心のご病気のようなものにかかっておいでなのではないでしょうか。 だとすると、その方を今おひとりにするのはとっても危険なことですよ。 リュキア神殿に対して、そんな妄想を抱いているなら、軍曹が目を離したすきに、何をしでかすか・・・おっと、いや、まさかあの方に限ってとは思いますけど、ともかく今は、あの方から目を離さないほうがいいという気がします。 少なくとも、そのご病気が治って、おかしなことを口走らなくなるまでは」
2011.06.17
コメント(4)
-

レグルスとエリダヌス
その日の夕方、レグルスは、訓練を終えて南天舎の部屋に戻ると、着替えもそこそこに、リヒト教官の部屋をたずねた。 用向きは、ベテルギウスと共用ではない自分ひとりの個室をもらうことだ。 ベテルギウスには、つくづく失望した。 あんなふうに、陰鬱な顔つきで連日連夜、レグルスの新しい任務にけちをつけ、口出しされるのは、もう辛抱できない。 ひとりになって、少し頭を冷やすための個室が欲しい。 その思いでいっぱいだった。 が、リヒト少佐の部屋へ行ってみると、少佐はまだ訓練から戻っていなかった。 やむなくレグルスは、そのまま廊下で、リヒト少佐の帰りを待つことにした。 おっつけ、ベテルギウスも訓練から戻ってくるはずだと思うと、部屋に戻る気がしなかったのだ。 顔を合わせればまた口論になってしまうのは分かりきっている。 口論になれば、また、ベテルギウスの口から次々と飛び出してくるはずの、エリダヌスへの謂れない中傷を、いやでも聞かなければならない。 それが苦痛だった。 レグルスは、いらいらと足踏みをし、いないとわかっているリヒト少佐の部屋のドアを、もう一度乱暴にノックし、返事のないドアの前を言ったり来たり、うろうろと歩き回り、そしてとうとう、これ以上じっと待っていることに耐えられなくなって、まだ訓練中かもしれないリヒト少佐を迎えに行こうと、南天舎の階段を下りはじめた。 階段の中ほどまで来たとき、リゲルが、鼻歌まじりに階段を上がって来るのに出会った。 今訓練を終えたところなのだろう、リゲルは、砂だらけの戦闘衣のまま、元気よく2段おきに階段を駆け上がってきて、レグルスに気づくと、びっくりしたように足を止め、目を見開いた。 「・・・レグルス軍曹! どうかなさったのですか?! なんだか、ずいぶん怖いお顔をしておられますね!」 レグルスは、顔をしかめてうなずいた 「うむ。 すこぶる不快だ。 あまりにも不愉快なので、私は個室に移ることを願い出ようと思っている。 リゲル、リヒト少佐を、どこかでお見かけしなかったか?」 リゲルはますます大きく目を見開いて、レグルスの顔をまじまじと見つめ、それから、ちょっと考え込んで答えた。 「リヒト少佐は、今、北辰館の大浴場でご入浴中ですよ。 ・・・それなら、レグルス軍曹、リヒト少佐が部屋にお戻りになるまでの間、私の部屋でお待ちになりませんか? あの先生、長風呂だし、私も、レグルス軍曹に少しお話ししたいことがあるし・・・、ねっ、行きましょ!」 リゲルの話といえば、先日レグルスが調べてくれと頼んでおいた、チェリー一等戦士の住まいのことだろう、とすぐに察しがついたので、レグルスはうなずいて、リゲルと肩を並べて歩き始めた。 リゲルが、いつもと変わらぬ人なつこい笑みを浮かべて、レグルスを見上げる。 「軍曹、御不快というと、ベテルギウス少尉と何かあったんですか? 少尉とご同室なさるのがお嫌で、個室のご申請に、ということ?」
2011.06.16
コメント(0)
-

楽園 13
アルデバランの傍らに立てかけられた、奇妙な形の武器を見下ろして、ヴェガが言った。 「その弓矢は、デネブから譲り受けたものだな。 ニンゲン族の弓矢は、バルドーラ族のものと違って、小型で、狙いも正確、威力もあると聞いた」 黙ってうなずいたアルデバランの手を、傍らに座ったヴェガが優しく止める。 「だが、アンタレスを倒すには、それでも十分じゃないかもしれない。 アンタレスは既に、ミラから魔力を授かって、リシャーナの戦士の力を得たかもしれないんだ。 当たり前の弓では、リシャーナの戦士は倒せない。 目には見えない『リシャーナの鎧』を身にまとっているからな。 俺たちのリシャーナ・ローブにかかっている“保護”系魔法の、最上級の魔法だ。 鋼鉄製の箱の中にいるのと同じだよ。 どんな武器も撥ね返してしまう」 はっと顔を上げたアルデバランの手から、ヴェガが、そっと矢を取り上げた。 「“猫目石のかんざし”をミラとアンタレスに奪われてから、俺もいろいろ調べたんだ。 リシャーナの戦士にふさわしくないものがその力を得てしまったとき、どうやったらその力を再び取り上げることができるか」 ヴェガの手の中で、矢が、次第に、暗い鈍色に変わり始めた。 「そして、やっと見つけた。 “リシャーナの魔法返し”。 相手の使った魔法と、相反する力を呼ぶ魔法だ。 相手の魔力が大きければ大きいほど効果は絶大だぞ。 たとえば矢にこの魔法をかけると、矢が“リシャーナの鎧”に触れた瞬間、鎧とは逆の力が働いて、双方の力が相殺されてしまう。 矢の触れた部分だけ、鎧が消えちゃうということだな。 鎧の魔法を飲み込んで、魔法返しの魔法も消える。 矢だけが残る。 魔法の鎧を貫通する、魔法の矢というわけだ。 これがあれば、相手がどんな強力な魔力を持ったリシャーナの戦士でも、倒すことができる。 もちろん、魔力のない相手でも」 不気味な闇の色に変色した矢を、ヴェガが、アルデバランの手に、そっと返した。 「ただし、使えるのは一本だけだ。 いっぺんに何本も持ってると、その一本一本が互いの力を殺しあって、ぜんぶ普通の矢に戻っちまう。 だから、絶対に狙いをはずすな」 固く唇を引き結んでうなずいたアルデバランに、ヴェガが、弓を手渡す。 「それと、やつのそばには決して絶対近づくなよ。 あいつの剣は、たとえリシャーナの戦士になっていなかったとしても、恐ろしい殺人剣だ。 普通の、のろまなバルドーラ族にはない、悪魔のようなスピードがある。 小刀を投げつけるという隠し技も持ってる。 狙うのは、やつの弱点、背中だ。 そこを、やつに気取られないくらい、できる限り遠くから狙え。 それから、やつの近くには、ミラもいるかもしれない。 ミラに邪魔されないように、周囲に十分気を配ることも忘れるなよ」 うなずいて、アルデバランが、立ち上がった。 「アルデバラン!」 叫んだプロキオンを、アルデバランは優しく抱きしめ、ちょっと笑って見せた。 「プロキオン、心配しないで待ってて。 今、俺を動かすのは、恨みや怒りじゃない。 あなたへの愛だ。 “猫目石のかんざし”を手に入れて、この森で、きっとあなたを幸せにする」 こうしてアルデバランは森を出て行った。 その後ろ姿を見送ってから、プロキオンはちょっとヴェガを睨んで言った。 「ヴェガ、うそついたでしょ?」 「へっ? な、なんのことだろう?」 そそくさと逃げ出そうとしたヴェガの袖を捕まえて、プロキオンはさらに怖い顔でヴェガを睨んだ。 「アルデバランのお兄さんのお金、盗んだのヴェガでしょ? このごろヴェガはお金持ち、って、カラスたちの間でうわさの花になってるよ。 そういうことだったのね」 「いや、あの、そんなことは、・・・まあ、ちょっと借りたりはしたかも・・・」 しどろもどろと答えるヴェガの顔を覗き込んで、プロキオンは言った。 「パンセに頼まれてぼくの様子を見に来たっていうのも嘘だよね。 本当は長老に頼まれて、アルデバランに、リシャーナ族になるための試練を与えに来たんでしょ」 「いや、その、別に長老に頼まれたってわけじゃないけどさ、リシャーナの戦士は一人いればいいのよ。 ふたりもいたらトラブルのもとだもん。 それにふさわしい人選も、また、森の番人の仕事のうち、ってことさ」 プロキオンの手をそうっとはずしてから、ヴェガはおおいそぎで、茂みの向こうに逃げて行った。 いずれにしても、これでアルデバランに、リシャーナ族の一員として認められるための試練が与えられたということだ。 優れた狩人で、兄を思う優しい心と、プロキオンを愛する強い心を持ったアルデバランは、きっとすぐにこの試練を乗り越えて、森に帰ってきてくれるだろう。 アルデバランが、“猫目石のかんざし”を持って帰ってきたら、すぐにリシャーナの戦士になる魔力を授けてあげよう。 そして、豊かなこの森で、アルデバランとふたり、いつまでも幸せに暮らそう。 ひとり取り残されたプロキオンの、胸の奥の、どこか深いところに、今まで知らなかった、静かな、あたたかい、満ち足りた幸せが、小さく息づいていた。
2011.06.14
コメント(2)
-

楽園 12
リシャーナの小径を、アルデバランが、矢のような勢いで疾走する。 それは、いつもの優しいアルデバランとはまるで別人のよう。 激しい怒りの炎が、全身から燃え上がっているのが、目に見えるようだ。 いつもならアルデバランを楽々振り切るプロキオンも、今日は、疾駆するアルデバランを見失わないように、追いかけていくのがやっとだ。 やっぱりアルデバランは、特別な人、パピト族ともバルドーラ族とも違う、ヴェガの言ったように、この森を守るためにリシャーナの戦士となる運命に、生まれついたひとなのだ、必死で追いかけながら、そう実感した。 リシャーナの泉まで来ると、アルデバランはちょっと足をとめ、あたりを見回してから、泉から少し離れた茂みの中に入りこんで行った。 そういえばアルデバランは、泉の近くに自分の家を作ってあるんだと言っていたっけ。 そこで一緒に暮らそうと、プロキオンも何度も誘われた。 アルデバランの後を追って茂みの中に入り込んでいくと、アルデバランの言ったとおり、背の高い草に隠れるようにして小さな小屋が建っていた。 おそるおそる、小屋の中をのぞくと、中でアルデバランは、奇妙な形をした木の枝を取り出して、それに取り付けられた細い糸を、引っ張ったり、叩いたりしなから、調整しているように見えた。 それが、武器だということはすぐに気がついた。 小屋の中には、動物の血の匂いが、強くこもっていたからだ。 傍らに立てられた細長い入れ物に何本も突っ込んであるのが、動物たちを殺す、矢だということも、すぐにわかった。 アルデバランがその矢を手にとって、注意深く何か塗りつけようとしている、それが、一瞬にして生き物の命を奪う猛毒だということもわかった。 アルデバランは、狩人なのだ。 今まで、考えたこともなかったけれど、この泉でアルデバランと出会ったあの瞬間から、わかっていたような気もした。 リシャーナの戦士は、森の守護神。 深い叡智で、動物たちを守ると同時に、荒々しい狩りをすることも、森から許されているのだ。 プロキオンの後ろで、茂みをかき分ける柔らかな音がして、振り返ると、ヴェガが、ふたりの後を追って、やってきたところだった。 ヴェガが、プロキオンの頭を優しく一回なでてから、小屋の中に入り、アルデバランに近づいていく。 「アルデバラン、プロキオンの“猫目石のかんざし”を取り返しに、アンタレスのところへ行くんだな」 何本もの矢に、丁寧に毒を塗りつけながら、アルデバランが黙ってうなずいた。 引き締まったその横顔に、迷いの色はなかった。
2011.06.13
コメント(0)
-

楽園 11
アルデバランも、不安そうな顔をヴェガに向けた。 「アンタレスというのは、そんなに悪い人なんですか? 兄ちゃんはずいぶん信頼していたようでしたけど・・・」 激しく頭を振ったヴェガが、強い口調で答える。 「アルクトゥールスは、ずっと、アンタレスにだまされてたんだ。 アルクトゥールスも、小狡いようで純なところがあったから、可愛い弟のお前に面差しがよく似たアンタレスを、もうひとりの弟みたいに感じてたんじゃないだろうか。 だが、アンタレスのほうはそうじゃなかった。 あいつはただ、金を稼げるお前の兄ちゃんを利用しただけさ。 お前の兄ちゃんが二人で何か始めるために貯めていた金も、アンタレスは全部ひとりで持ち逃げして、どこかに行方をくらましちまったんだ。 だが、お前の兄ちゃんは、それでも一途にアンタレスを信じてた。 いなくなったアンタレスの身を案じて、毎日毎日、ろくな食事もとらず、寝る暇も惜しんで、街中走り回って、アンタレスを探していたようだったよ」 真っ青になったアルデバランの体が、ふるふると細かく震え始めた。 それを痛ましげに見ながら、ヴェガが続ける。 「アンタレスは、俺のミラもそうやってだましたんだ。 誰よりも強くなりたい、そう望んでいたアンタレスは、ミラの魔法の、馬鹿にならない威力を目の当たりにして、自分もそんな魔力が欲しくなったんじゃないだろうか。 剣技と魔力、ふたつながら自分のものになれば、もう誰も太刀打ちできないもんな。 誰も自分に逆らえない、世界は俺のもの、とでも思ったんだろうぜ。 それで、ミラを口説き落として“猫目石のかんざし”を盗み出させた」 「・・・ひどい! ヴェガ、そんなやつに魔力を授けてリシャーナの戦士にさせたりしたら、絶対だめだよ!」 憤慨するプロキオンに、ヴェガがさらに重々しくうなずいて言った。 「だろ? しかもあいつは今までに、数え切れないほど人を殺してるんだ。 ゾーハルの酒場の常連だった、アルゴスというバルドーラの仲間を何十人も殺したんだぜ。 悪魔のような殺人鬼として、あいつの顔は、すでに街中に知れ渡ってる。 人の命なんか、あいつは虫けらのようにしか思わないんだ。 アルデバラン、お前にこんな話を聞かせるのは心苦しいんだけど、あの迷宮で兄ちゃんの身に危険が迫った時だって、アンタレスは、ちゃんと兄ちゃんを守ろうとしたことなんか一度もなかったんだぞ。 いつも自分の都合ばかり考えやがって、バジリスクオオトカゲに石にされかけたときも、クロコッタ狼に食われそうになったときも、キマイラ獅子に焼き殺されそうになったときも、あいつは、へらへら薄笑いを浮かべてやがるだけで、俺たちのためになんか、なんにもしてくれなかった」 ふん、と荒い鼻息をひとつ吐いて、ヴェガが、とどめをさすように言う。 「言いたくないけど、あの大鏡の間で、アルクトゥールスが鏡に誘い込まれたのだって、アンタレスのせいだと俺は思ってるんだ。 信頼していたアンタレスに裏切られた、その大きな深い心の傷を、あの、魔の鏡に攻撃されたのよ。 だからアルクトゥールスは悲しみの沼から這い上がることができなかった。 俺、アルクトゥールスが沼に足をとられながら、何度もアンタレスの名前を呼ぶのを聞いたもん。 まるで、その沼の向こうにアンタレスがいる、そう信じてるみたいに、自分から、沼の深みに踏み込んで行ったんだ。 アンタレスの裏切りさえなかったら、アルクトゥールスも鏡の攻撃なんか受けなかったのにと思うと、俺もう悔しくて悔しくて!」 呆然としたように立ち尽くしていたアルデバランが、突然、疾風のような勢いでユキヤナギの茂みを飛び出して行った。 「アルデバラン! どこへ行くの?!」 プロキオンはびっくりして、アルデバランの後を追って茂みを飛び出した。 ふたりの後ろ姿を見送って、ヴェガが、ふっ、と小さく笑った。
2011.06.12
コメント(4)
-

楽園 10
「その秘石は、今もどこかにあるの? 大昔の偉い魔法使いは、どうやってそれをつくったの?」 俄然身を乗り出したプロキオンに、ヴェガがちょっと困ったように、がりがり頭をかいた。 「“血の石”が今もあるのかどうか、それは俺にもわからない。 新しく作るのも、俺たちの力ではとても無理だ。 人の生死に関わる秘石だぞ。 桁違いに強い魔力が必要なんだ」 がっくりと肩を落としたプロキオンに、ヴェガが続ける。 「でも、リシャーナの戦士なら、つくれるかもしれない。 リシャーナの戦士には、村で一番強力な魔法使いの長老より、もっとすごい魔力があるんだ」 「その、リシャーナの戦士、って何なの?」 その問いには答えず、ヴェガが、プロキオンの目をじーっと見つめて言った。 「プロキオン、俺、お前にも謝らなきゃならないんだけど、実は俺、その『大鏡の間』で、 “猫目石のかんざし”という秘宝を手に入れたんだよ。 それを手にしたとき俺はすぐに、これはプロキオンが使うものだと、そこまでは気がついたんだけど、そのときはまだ、それが何のために使うものなのか、知らなかった。 だから、ついのんびり構えてて、ずっと俺の家に置きっぱなしになってたんだよね。 そしたらあれは、眠っているリシャーナの戦士の力を、覚醒させるための秘宝だったと、後になって知って・・・。 あれは、今、お前が、このアルデバランをリシャーナの戦士にするために使うものだったんだよな」 今度はアルデバランが、ヴェガに、つかみかからんばかりに身を乗り出した。 「では、その“猫目石のかんざし”という秘宝があれば、プロキオンが俺のためにそれを使ってくれれば、俺はその、リシャーナの戦士というのになれるんですね?! 俺が自分で“血の石”というその秘石を磨いて、兄ちゃんを生き返らせることができるんですね? この森で、リシャーナ族の一人として認められ、堂々と、プロキオンと一緒に暮らすことができるんですね?」 プロキオンは、本当にヴェガにつかみかかって叫んだ。 「もう、ヴェガってば、何のんびりしてんのよ、それを早く言ってよ! その“猫目石のかんざし” 早くちょうだい! 使い方もちゃんとわかってるんでしょうねっ?!」 つかみかかったプロキオンの手を逃れて、ヴェガが、がばっと2人の足もとにひれ伏した。 「プロキオン、アルデバラン、ごめん! 実はそれ、もう俺の手もとにないんだよ。 俺より先にその使い道に気づいたミラに、持ち逃げされちゃったんだ。 ・・・本当に面目ないっ!」 「ミラが? なんで、そんなことを・・・!」 愕然としてつぶやいたプロキオンに、ヴェガが重々しくうなずいた。 「それなんだよ。 ミラはあの時、アンタレスのために“猫目石のかんざし”を使うと言った。 あいつ、アンタレスをリシャーナの戦士にするつもりなんだ。 それは由々しいことだぞ。 そもそもリシャーナの戦士というのは、この森が危険にさらされた時に限って、森を守るために現れる、戦う大魔法使いなんだ。 強い力と、大きな魔力とともに、この森の生き物たちに対する確かな愛と、深い叡智をも兼ね備えた、人格者でないといけねえ。 それをおまえ、アンタレスのような血も涙もない極悪人が、リシャーナの戦士の力を得て森に入り込んできてみろ、この森はたいへんなことになっちまう。 恐ろしい猛獣と醜い化け物がはびこって森の生き物たちを根こそぎ食い殺し、群れなす不可視の毒虫が得体の知れない病を運び込み、真っ黒な悪意に日の光もさえぎられて木も草も枯れ果て、森はあっという間に滅びちまうだろう。 この森の番人として、俺は何としても、それを阻止しなきゃならないのだっ!」
2011.06.11
コメント(0)
-

楽園 9
はたと動きを止めたヴェガが、片眉を上げて、じろりとアルデバランを見上げた。 「・・・別の仕事? アルクトゥールスとアンタレスが、2人で?」 「いえ、俺も、兄ちゃんが何を考えているのか、詳しいことはわかりませんけど、確かそんなようなことを。 まさか兄ちゃん、ほんとうに砂漠の盗賊になったりは・・・?」 抜け目なさそうなヴェガの目が、すっと細くなった。 「・・・砂漠の盗賊? ふーん、そうだったんだ。 あいつ、俺をのけ者にして、アンタレスと2人だけで国を出ようとか考えてたのね」 不機嫌そうにつぶやいて、ヴェガは何かしきりに考え込んでいたが、やがて、言葉を選ぶように、アルデバランに言い聞かせるように、ゆっくり、ゆっくり、言った。 「・・・あのね、アルデバラン、驚かないで聞いて欲しいんだけど、お前の兄ちゃんは、アルクトゥールスは、死んだんだよ。 迷宮の『大鏡の間』で、魔の鏡に誘い込まれちまったんだ。 あれは、人の心の一番弱いところに喰らいついて命を奪う、魔の鏡だ。 俺も何とかしてやつを助けようとしたんだが、俺には、鏡の向こう側に行くことがどうしてもできなかった。 鏡の向こう側で、あいつが深い沼に飲み込まれていくのを、鏡のこっち側でただ見てるしかなかったんだ。 かわいそうで、悔しくて、悲しくて、体がじりじり焼け焦げそうだったが、どうにも、手の施しようがなかった」 小さく息を飲んだアルデバランの顔が、みるみるうちに青ざめていく。 「・・・死んだ? だって、リュキア神殿で御祈祷を頼めば死んだ人も生き返ることができるんでしょ? 前にも兄ちゃんはそうやって御祈祷で生き返ったんです。 アンタレスという、その友達が助けてくれたんです。 うんとお金がかかるというけど、兄ちゃんは今、あのころよりもっとたくさんお金を貯め込んでいるはずだ」 ヴェガが、目に涙をいっぱい浮かべて、アルデバランの手を取り、ぎゅっと握り締めながら、首を横に振った。 「アルデバラン、落ち着いて、よく聞くんだよ。 アルクトゥールスは、鏡の向こうで、沼に飲み込まれちまったんだ。 神殿といえど、遺体がなくては御祈祷のしようがないんだよ。 あいつはもう、俺たちのいるこの世界には帰って来れない。 アルデバラン、すぐ目の前にいたのに、アルクトゥールスを助けてやれなかった俺を、どうか許してくれ!」 あまりにもつらい話に耳をふさぎたくなったプロキオンの隣で、アルデバランが、急に力を失ったようにへなへなとその場にくずおれた。 「もう、帰って来れない・・・そんな! 兄ちゃん!」 プロキオンは、そのアルデバランをあわてて支えながらヴェガに言った。 「ヴェガ、アルデバランの兄さんを、助けることは、もうできないの? リシャーナの魔法に、そういうのはないの?」 プロキオンを見返したヴェガの、大きな緑色の瞳が、きらりと光った。 「うん。 実は一つだけ、方法が、なくもないんだ。 俺も詳しくは知らないんだけど、大昔、偉い魔法使いが磨き上げた“血の石”という秘宝があれば、体が残っていなくても人を生き返らせることが出来るそうだ。 もっとも今は、そんなものをつくれるようなパワーを持った魔法使いはいないんだけど・・・」
2011.06.10
コメント(4)
-

楽園 8
いつもの調子で元気よくユキヤナギの茂みに入ってきたヴェガだったが、なぜか、アルデバランの顔を見るなり、ぎょっとしたように顔を引きつらせて叫んだ。 「うわっ! アンタレス、なんでおまえがここにいるのよ!?」 悲鳴のような声を上げて、そのまま表に逃げ出そうとした、そのとたん、ヴェガは、出入り口のところに置いてあったプロキオンの水瓶につまづいて、ばしゃんと派手な水音とともにすっ転んだ。 ひっくり返った水瓶の水を頭から被って、びしょぬれになったヴェガが、真っ青な顔をアルデバランに向ける。 「ご、誤解すんなよ! アルクトゥールスがあんなことになったのは、俺のせいじゃないからねっ! お前のせいだぞ、アンタレス、全部お前が悪いんだからねっ!」 ヴェガの必死の形相に面食らいながら、プロキオンは、ヴェガと、アルデバランの顔を見比べて言った。 「ヴェガ、アルデバランを知ってるの?」 アルデバランも、はっとしたようにヴェガの顔を見た。 「今、アルクトゥールスって言いましたか? 兄ちゃんを知ってるの? もしかして、あなたが、兄ちゃんの友達の、ヴェガさん?」 するとヴェガも、髪の毛からぽたぽた水を滴らせながら、あっけにとられたような顔になって、きょとんとアルデバランを見上げた。 「えっ?・・・お前、アンタレスじゃないの? ・・・アルデバラン? えっ、お前がアルデバラン? アルクトゥールスの弟の、アルデバラン?」 ぷるぷると頭を振って、髪の毛の水をはじき飛ばしてから、ヴェガが、大きな目でまじまじとアルデバランを見つめた。 「・・・驚いた! 確かに、アンタレスじゃないな、剣を持ってないもん。 体つきも小柄だし、よく見れば、顔も、あいつみたいにひねくれて偉ぶってないし。 明るくて、素直そうで、まあ、可愛いこと!」 感に堪えないといった顔で、ヴェガがさらにしげしげと、頭のてっぺんから足の先まで、アルデバランの全身を眺めまわした。 「・・・それにしても、本当に、アンタレスによく似てやがる。 アルクトゥールスの弟っていうより、アンタレスの弟みたいだ。 ああ、きっとアルクトゥールスのやつも、この顔のせいでアンタレスみたいな冷血漢に、ついうっかり、気を許しちまったんだなあ。 アルクトゥールスはしっかりしたやつだったけど、可愛い弟にそっくりな仲間だ、自分を裏切って金盗んで行方くらますなんて、思ってもみなかったんだろう。 気の毒なことだったわ、まったく」 なんとなく、おぼろげに、話が読めてきたような気がして、不安を感じ始めたプロキオンのほうに、ふと、不審げなヴェガの視線が移った。 「で、プロキオン、なぜお前が、そのアルデバランと仲良く一緒に・・・?」 言いかけて、ヴェガが、何かに気づいたように、はっと2人を見比べた。 「・・・そうか、『リシャーナの戦士』か! アルデバラン、なんと、お前が、『リシャーナの戦士』だったのか! これから、秘宝“猫目石のかんざし”の力を借りて、プロキオンに魔力を授かるはずだったんだな!」 これは、プロキオンにはよくわからない独り言をつぶやいて、ヴェガが自分の頭をぽかぽか叩いた。 「ああっ、それなのに、俺ときたら、その大事な秘宝を、ミラとアンタレスに・・・! ええい、この、酔っぱらいの、大間抜けの、からっぽ頭め!」 頭をかきむしるヴェガに、アルデバランが、おずおずと遠慮がちに声をかけた。 「あのう、ヴェガさん、俺の兄ちゃんに何かあったんでしょうか。 兄ちゃんは、俺のためのお金がいらなくなったから、もう迷宮に行くのはやめたんですよね? その、アンタレスという友達と2人で、何か別の仕事を始めたんですよね?」
2011.06.09
コメント(0)
-

楽園 7
こうして、そのひとは、プロキオンのユキヤナギの茂みで、一緒に暮らすようになった。 幸福だった。 朝、目覚めると隣に彼がいた。 朝の光の中でまどろむ、彼の寝顔は、幼い子どものように、無防備でいとおしかった。 ユキヤナギの狭い茂みの中で、肩を寄せ合って食べる苺。 際限なく続く、楽しいおしゃべり。 小鳥のようなキス。 手をつないで歩く森の小径。 抱き合って眠る、夜の闇の甘いときめき。 野生の動物のように美しく、力強い、その人の名は、アルデバラン、といった。 『魔法使いの森の、こんな奥に、よそ者が住み着いたことを、もしリシャーナの誰かに見つかったら、あなたが叱られるかもしれない』 そう言って、アルデバランは、何度も出て行こうとしたけれど、プロキオンはもう彼を放したくなかった。 『では、リシャーナの泉の近くの、俺の家で一緒に暮らそう』 そんなふうにも言われたけれど、プロキオンは承知しなかった。 リシャーナの村の長老のところへ彼を連れて行って、私の最愛の人、と紹介するつもりだから。 そして、リシャーナの村で、リシャーナとして一緒に暮らすつもりだから。 できれば魔力も授けてあげたい。 心の広い長老は、きっと彼を村に受け入れてくれると思う。 アルデバランも、喜んでうなずいてくれた。 『俺もあなたを放したくない。 この森で、ずっと一緒に暮らそう』 そう言ってプロキオンを抱きしめ、永遠の愛を誓ってくれた。 でも、他の種族が本当にリシャーナ族の仲間になるのは、長老の許しが出たあとも、ちょっとたいへんだ。 ミラと師弟関係を結んだのに、今まったくミラに無視されているデネブのように。 あるいは、最近リシャーナの村に現れて、長老の館でひそかに特訓を受けている謎の神官、カノープスのように。 長老は、きっとアルデバランにも何か試練を与えると思う。 だから今は、あと少しだけ、彼とふたりの甘い時間を味わっていたい。 でも、その夢のような日々は、ほんの数日間で終わってしまった。 ある日の午後、このごろ村に顔を出さないプロキオンの様子を見に、『森の番人』ヴェガが、ユキヤナギの茂みにずかずかと入り込んできたのだ。 「おーい、プロキオン、生きてるか? パンセが、最近プロキオンが顔見せないって、心配してたぞ。 誰よりも真面目なおまえが学校休むなんて、何かあったのか?」
2011.06.08
コメント(0)
-

楽園 6
プロキオンにつられたように、その人も小さく笑った。 「知ってる。 リシャーナ族の足跡の見つけ方は、デネブに教わったんだ。 その、“木隠れ”という魔法を使うとき、リシャーナたちは一瞬爪先立ちになる。 普通は足跡なんか絶対残さない彼らだけど、“木隠れ”の、つま先立ちの足跡だけはどうしても残っちゃう。 その足跡をみつけたら、足跡の一番近くの木の様子をよく覚えておいて、その周囲の木々の中から、その木と同じような感じの木を見つけ出す。 見つかったら、その木の下を探すと、きっと、また同じ足跡が見つかるはず。 リシャーナの足跡は、そうやってたどるんだ、って。 地面だけ探しても足跡はたどれない、って」 なるほど、と、思った。 デネブ、というのは、リシャーナの村はずれに住んでいる、魔法使い志願のニンゲン族だ。 プロキオンも、この人とは顔見知りで、何度か、いっしょにお茶を飲みながらおしゃべりしたことがある。 いつもにこにこしていて、とても優しい人だ。 あのデネブの知り合いなら、と、また少し気を許したプロキオンを、その人は優しい笑顔でじっと見つめた。 「・・・でも、本当は、あなたの後をつけるのに、足跡なんか捜す必要はなかった」 その人が、身を乗り出して、プロキオンに顔を近づける。 「あなたは、花のように、とても甘い、いい匂いがするんだ。 目を閉じて、風の運んでくる匂いだけを頼りに、あなたの姿を探しても、見つけられそうなくらい」 ほんの一瞬、身を引きそうになったけれど、プロキオンはじっとしていた。 いや、動けなかった。 夢にまで見た、そのひとの顔が、今、こんなに近くに! つややかな黒い髪。 少し憂いを秘めた、神秘的な赤い瞳。 すっと真っ直ぐに通った形のいい鼻筋。 なめらかな白い頬。 甘く優しい言葉をつむぎだす、苺のような唇。 間近に見ると、その美しさがいっそう際立って感じられた。 何か知らない魔法にかけられたみたいに、胸がどきどきして、体中、甘いハチミツになっちゃったみたいな気がした。 甘い、いい匂いがするのは、君のほう! と思ったけど、何も言えなかった。 胸のどこか奥のほうから、今まで知らなかった不思議な、熱い、甘酸っぱい感情があふれ出してきて、なんだか、じわっと涙がにじんできた。 今まで知らなかった幸福感に陶然としたプロキオンに、その人が、温かく大きな手を、そうっと、こわれものに触るようにこわごわ、伸ばしてきた。 「あなたの髪に、触ってもいい?」 その人の手が、そよ風より優しく、プロキオンの髪をなでる。 あふれる涙もそのままに、プロキオンはそっと、その人の熱い胸に体を預けた。 一瞬ためらってから、力強い腕が、プロキオンの体をぎゅっと抱きしめた。 そのひとの体からは、かすかに、動物の血の匂いがした。
2011.06.07
コメント(3)
-

楽園 5
いつものようにユキヤナギの茂みの中にもぐりこんでいこうとして、プロキオンは、はっと足を止めた。 プロキオンのねぐらの、入り口の真ん前に、あの人が腰を下ろして、にこにこ、プロキオンを見上げていた。 先回りして、僕を待ってた?! びっくりして、また逃げ出そうとしたプロキオンに、そのひとは、春の日差しみたいにおだやかな声で言った。 「お願いだから、逃げないで。 本当に、少し話がしたいだけ。 足跡をつけて来たりして、ごめんなさい。 俺、あんなふうに、あなたに誤解されたままで、帰れなかったんです」 うっとりするような、甘い声。 心がとろけてしまいそうな、優しい微笑。 どんな警戒心も恐怖心も、いっぺんに解けてしまう。 それに、逃げても、ここはもう僕の家の前。 この人の言うとおり、ちゃんと話をしないと、この人も僕も、いつまでも家に帰れない。 心を決めて、うなずくと、プロキオンは、その人の背後の茂みを指差して言った。 「その茂みの奥が僕のねぐら。 じゃ、はやく中に入って。 こんな森の奥深くまで、よそ者が入り込んできたのを、村の大人に見つかったらたいへんだよ!」 その人は、嬉しそうにぱっと顔を輝かせてうなずいた。 笑うと、子どものような可愛い顔になった。 急いで茂みの奥にもぐりこんで行く、その人の後に続きながら、プロキオンはなんだか胸がわくわくしてきた。 「森の外に住むバルドーラやパピトたちはみんな、リシャーナの森に入り込んで来るのをとても怖がっているよ。 悪戯な魔法使いに化かされて、骨抜きにされてしまうから、って。 君は、魔法使いの森の、こんな奥まで入り込んできちゃって、怖くないの?」 プロキオンのねぐらの、ふかふかのわらの床に腰を下ろして、その人が、ほっとしたように明るい目を上げた。 「怖いよ! あなたの足跡を探しながら、深い森の、狭い小径をたどって、ここにつくまでの間、生きた心地もしなかった! いつ、リシャーナの誰かに見つかるか、見つかったらどんな目に合わされるか、って。 でも、どうしてもあなたにもう一度会いたくて、会って話をしたくて、気持ちが抑えきれなかったんだ。 こんなふうに、足跡をつけてくるなんて、失礼なやつだと怒ってる?」 とうとう、くすくす笑い出しながら、プロキオンは頭を振った。 「怒ってないけど、思い切ったことするなあ、って 驚いた。 それに、よく、僕の足跡なんか見つけられたなあ、って。 リシャーナたちはみんな、森の中を移動するとき、“木隠れ”という魔法を使うんだよ。 地面に足跡なんか残さないのに」
2011.06.06
コメント(2)
-

楽園 4
薬草の森で、プロキオンが初めてその若者を見たとき、そのひとは、ひとりで泣いていた。 そのひとの、端正な白い横顔が、青ざめて、ゆがんで、あんまり悲しそうだったので、どうしてもそのまま通り過ぎることができなくて、そうっと近づいてみた。 プロキオンに気づいて、驚いたように顔を上げたそのひとは、息をのむほど整った、でも、とても優しそうな顔をしていた。 泣き腫らした悲しい目をしていたけれど、その赤い瞳はどこまでも清らかに澄みきって、穏やかで思慮深いパンセの瞳に、ちょっとだけ似ていた。 バルドーラのように精悍で、黒豹のように機敏で、リシャーナのように優美な姿。 パピト族ともバルドーラ族ともリシャーナ族とも違う、プロキオンのまだ知らない生き物だと思った。 強く惹かれて、その日から、プロキオンの頭の中からは、その人の面影が片時も離れなくなった。 どこの誰だかわからない人。 名前も、住むところも、種族も、未知の人。 でも、きっともう一度会える、と、思っていた。 そのひとと、不思議な、強い運命の糸で結ばれていることを、かたく信じていた。 だけど、――― よりによって水浴びしてる最中に現れる、って、どういうこと?! びっくりして逃げ出したけれど、その人が自分の後を追いかけてくるのに気づいたとき、すごく嬉しかった。 嬉しくて、わざと“木隠れ”しなかった。 木々の間を縫って、木漏れ日に揺れる森の小径を、その人に見えるように、わざと、ゆっくり逃げた。 でも、一生懸命走って追いかけてくるそのひとは、街の生き物。 リシャーナのように自由奔放に森の中を飛び回ることはできないから、つまらないくらい簡単に振り切ってしまった。 足を止め、後ろを振り向いてみたら、もう若者は、はるか彼方に取り残されて、途方にくれたようにたたずんでいた。 その姿は、木々の間に見え隠れする、若い雄鹿のように力強く、美しく見えた。 立ち止まって、ちょっと考えてから、プロキオンはこっそり、道を引き返し始めた。 その人の様子をもっとよく見たい。 目に焼きついて離れない、あの涼やかな、優しげな、匂い立つような面差しを、もっと近くで見たい。 熱い思いが、どうしても、抑えられない。 木の陰からそうっと様子を窺うと、そのひとは、一生懸命周りを見回していた。 見失っちゃったと思って、僕を探してる?! そう思ったら、また嬉しくなった。 胸を高鳴らせながら、さらに足を踏み出したとき、その人がプロキオンに気づいて、ぱっとこっちを向いた。 目が合ったら、急に恥ずかしくなって、ぱあっと顔に血が上った。 思わずうろたえて、また逃げ出した。 でも今度は、ちょっとあわてて、早く走りすぎたみたい。 はたと気がついて、足を止めて振り返ったら、そのひとの姿はもうそこになかった。 ――― もう追いかけっこに飽きて、帰っちゃったのかなあ。 がっかりした。 もう一度道を引き返して、泉まで戻ってみた。 でも、そこにも、もう誰もいなかった。 しょんぼり肩を落として、プロキオンは、とぼとぼ、魔法使いの森の、ユキヤナギのねぐらに帰って行った。
2011.06.05
コメント(2)
-

楽園 3
夢の中のようにおぼろな、その姿をもっとよく見たい。 現実のものと、確かめたい。 その思いに突き動かされて、われ知らず一歩前に踏み出しかけた足が、枯れ枝を踏んで、がさっと大きな音を立てた。 アルデバランがはっと息を止めたと同時に、泉から聞こえていた歌声もぴたりとやんだ。 覗き魔の出現に驚いたそのひとが、びっくりして泉から飛び出し、岸辺の木の枝にかかっていたローブを引っつかんで逃げ出す。 「待って!」 あわてて、アルデバランはその後を追いかけた。 追いかけたりしたらよけい怖がらせてしまう、とわかっていたけれど、覗き趣味の変質者みたいに思われたくなかった。 どうしても、釈明したい! 「待って! 俺、別に、覗き見してたわけじゃありません! どうか誤解しないで! 偶然あなたの姿を見てしまって、俺もびっくりして動けなくなって・・・」 しどろもどろ、叫びながら追いかけたが、そのひとは蝶々のように身軽だった。 どんどん距離が離れていく。 とても追いつかない。 大きな木の陰に逃げ込んだ、そのひとを追って、アルデバランも、息せき切って木の陰に駆け込んだ。 が、そこには、もう誰もいなかった。 あたりを見回しても、木々の枝が静かに揺れているばかり。 生き物の気配はなかった。 ――― ああ、見失っちゃった! アルデバランはなおもしばらくあたりを見回していたが、いくら目を凝らして見回しても、あの人の通って行った痕跡は何も見つからなかった。 がっくり肩を落として、帰ろうとしたとき、少し離れた木の向こう側から、その人が、ひょい、と、いたずらっ子みたいな顔を見せた。 ・・・引き返してきてくれた?! そう思ったら、俄然嬉しくなって、目の前がぱーっと明るくなった。 その美しくも愛らしい表情は、水浴びしているところを見られたから、ちょっと恥ずかしそうな、ちょっと怒っているような、ふうにも見えたけれど、同時にまた、突然目の前に現れたアルデバランに興味津々、子どものようにあどけない表情にも見えた。 一度は驚いて逃げ出したものの、こうしてまた顔を見せてくれたということは、アルデバランの言い分にも耳を傾けてやろうという気があるということだろうか? 思わず頬を緩めて、そのひとのほうに歩き出そうとしたとたん、そのひとはまた、ぱっと身をひるがえして逃げ出した。 「待って! お願いだから逃げないで! 俺の話を聞いて! ・・・いや、聞かなくてもいいから、君の言いたいことを何でも言って! 俺を思い切り罵り倒していいから、逃げないで」 あわてて追いかけた。 でも、その足の速さときたら、ウサギより小鹿より俊足。 まるで鳥が舞うように、ほとんど地面に足が着かないくらい軽々と、低木を飛び越し、蔓の下を潜り抜け、太い木々の間を縫って走る、走る。 いくら必死で追いかけても、どんどん引き離されていく。 走りにくい草むらの、地を這う蔓に足をもつれさせて転んだアルデバランが、再び顔を上げたとき、そのひとの姿はもうどこにも見えなかった。 深い森の奥に、明るい緑の木漏れ日がちらちら揺れているだけだった。
2011.06.04
コメント(0)
-

楽園 2
いつのまにか、うとうとしていた。 どこか遠いところで、鳥が歌っている。 歌うような、透き通った、長く美しいさえずり ――― ヒバリだろうか。 昔どこかで、こんなきれいな鳥の声を聞いたことがあった。 あれはどこだったか・・・胸の奥に刻み込まれた深い悲しみの記憶を呼び覚ますような、それでいて同時に、甘い不思議なときめきをかきたてるような・・・ はっとして目を開けた。 いや、ヒバリではない。 思い出した。 あれは、ヤップの墓の前で聞いた、不思議な歌声だ。 ヤップの記憶をなくした喪失感に茫然としていた時、頭の上から降り注いできた、ヒバリのさえずりそっくりの歌声。 底抜けに明るく澄んだ空に輝くばかり、どこまでも透明に響き渡って、どんな悲しみをも払拭してくれるような、美しい歌声。 今、アルデバランの耳に聞こえてくるのは、確かに、あのときのあの歌声だ。 その歌声の持ち主の優しい面影は、アルデバランの脳裏にしっかりと焼きついていた。 甘い花の香りのする、大輪の花のようなひと。 ミューズが、ヤップと呼んだ美しいひと。 いたずらっ子みたいに、アルデバランの頭から忘却の種を取り去って、ヤップの記憶を永遠に奪ってしまったひと。 では、あのひとが、この近くにいるのだろうか?! がばっと跳ね起きて、アルデバランは家の外に飛び出した。 濃い緑の茂みの向こう、明るい陽光を反射してきらめく、リシャーナの泉の方から、その歌声は聞こえていた。 アルデバランは、そうっと、足音を忍ばせて、泉のほうに歩き出した。 歌声が、近づいてくる。 胸がどきどき、高鳴った。 歌声と一緒に、小さな水音も聞こえてくる。 茂みの間から、こっそり、顔だけ出して、泉のほうを透かし見た。 ――― いた! 泉の浅瀬に膝のあたりまで浸かって、そのひとは、楽しそうに歌いながら、水浴びをしていた。 それは、とても不思議な眺めだった。 その白いほっそりとした姿は、ちょうど濃い霧の向こうの人影を見るように、そのひとの周りだけ、ぼうっとやわらかくかすんで見えた。 まるで、澄んだ泉の水が、空気に溶け込んで、濃い霧になって立ちのぼり、きらきら輝きながらそのひとの体を包み込んで、不思議な光の雨で全身を洗い清めている、みたいに。 はっとした。 あの人知を超えた神秘的な姿は、謎に包まれた魔法使いの森の、リシャーナ族! あのひとは、魔法使いの一族だ!
2011.06.03
コメント(2)
-

楽園
気配に気づいた一頭の鹿が、はっと顔を上げた。 そのせつな、張りつめた弓の糸を、ぱっと放つ。 ひゅん、とうなりを上げて、重たい矢が空を切り裂く。 命中! 首の真ん中に、毒塗りの矢を受けて、どう、と倒れた仲間に驚いた、他の鹿たちがいっせいに、ぱっと地面を蹴って逃げ出す。 手にした弓を下ろして、ほっと緊張の糸を緩めたアルデバランに、後ろでこの様子を見ていたデネブが、拍手を送った。 「お見事! アルデバラン、わずかの間に、本当に弓の腕を上げたね!」 「ありがとうございます、デネブ。 みな、あなたの御指導のおかげです」 深々と頭を下げたアルデバランに、デネブが照れたように頭をかいた。 「いや、僕なんか、カストールやポルックスの言うとおりに、君の練習を見ていただけだよ。 君の腕がここまで上達したのは、持って生まれた君の資質だと思う。 まるで生まれつきの狩人みたいに、君は、教わった以上のことをどんどんその体で吸収していくんだもの。 僕のほうがいつも驚かされた。 僕にはもう、これ以上君に教えられることはひとつもないよ。 本当によくがんばったね、アルデバラン」 料理人になりたい、その一心で家を飛び出して料理人の門を叩き、狩りのできないやつは弟子にしないと冷たく追い払われて、ふらふらと森の奥まで入り込んではきたものの、狩りなんて、やったことはもちろん見たこともないのに、何をどうしていいのかわからず、途方にくれてたたずんでいたアルデバランを、偶然見かけて声をかけてくれたのが、この、ニンゲン族のデネブだった。 ニンゲン族だけれど魔法使いになりたくてリシャーナ族に弟子入りしたというデネブは、パピト族だけれどバルドーラ族のように狩りをしたいアルデバランの気持ちをよく理解してくれて、自分では狩りも肉食も禁じられているけれど、道具なら提供してあげられると、アルデバランのために友人からこの大きな弓を貰い受けてくれて、その使い方も教えてくれたのだった。 さらにデネブは、狩りが得意だというその友人たちにアルデバランの指導を頼み、自らも丁寧に練習を見てくれて、アルデバランを一人前の狩人に育て上げてくれた。 アルデバランの恩人だ。 リシャーナの泉の近くの茂みの奥に、隠れるように建てた小さな自分の家に戻ってくると、アルデバランはごろんと床に寝転がって、草葺の天井を見上げた。 狩りは、まだまだ手際よくとはいかないけれど、どうにかできるようになった。 たぶん、街に戻って、再びあの料理人の門を叩けば、今度は弟子にしてくれるだろう。 アルデバランが街に帰ったら、兄のアルクトゥールスも、どんなに喜んでくれることだろう。 あの家で、独りぼっちになってしまった兄が、今ごろどんな食事をしているだろうかと考えると、胸がしくしく痛む。 それでもアルデバランは、すぐに街に戻ることをせず、この隠れ家のような小屋で、いつまでも迷っていた。 はたして自分はこういうものを求めて料理人になろうとしていたのだろうか。 パピトの広場の仲間たち、かっぱらい横丁の仲間たち、ラムの畑の仲間たち、みんなでわいわい楽しく食べた料理の、あの極上の味は、こんなふうに、ただがむしゃらに突っ走って作り出すものだったろうか。 俺は、まるで見当はずれなことをしている、その思いがどうしてもぬぐえない。 ――― 悶々とした日々を、アルデバランは送っていた。
2011.06.02
コメント(2)
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-15 02:35:31)
-
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- 生きがいの見つけ方
- (2025-11-16 10:51:00)
-
-
-
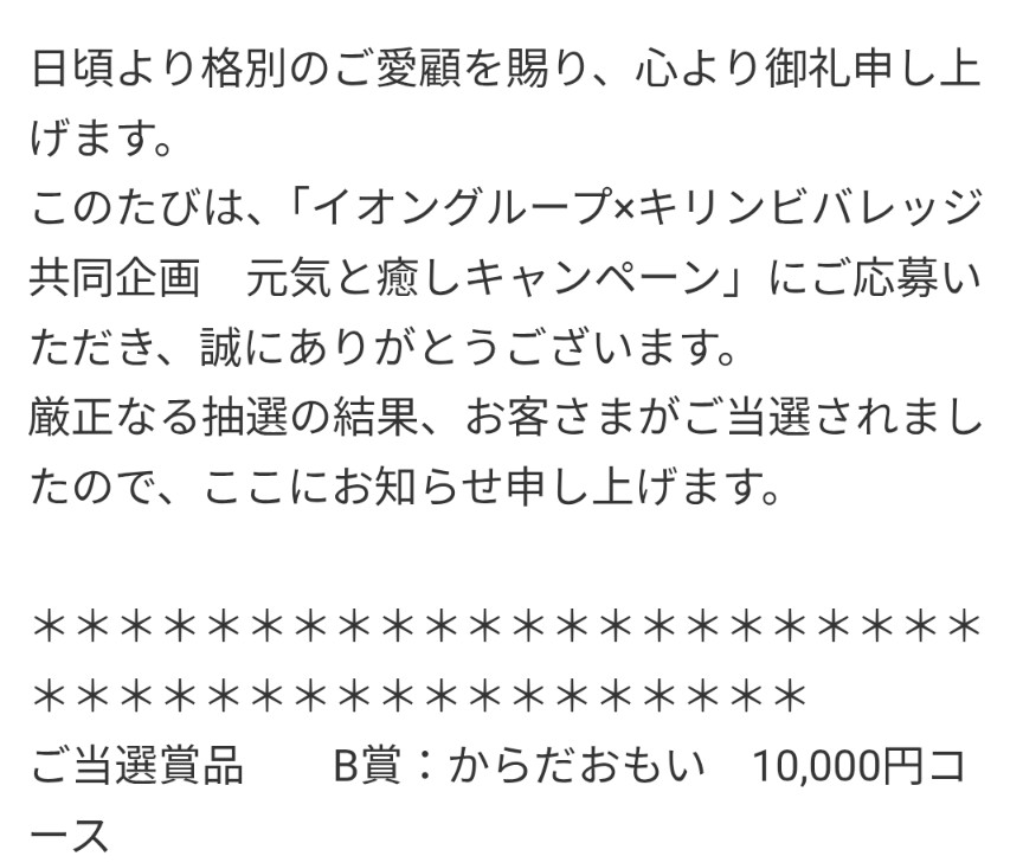
- 懸賞フリーク♪
- からだおもいデジタルカタログギフト
- (2025-11-16 00:56:51)
-







