2011年08月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
リュキア伝説 最終章 8
長い物語を罪の告解のように静かに語りながら、ゴルギアスは、その表情を、万華鏡のようにくるくると変化させる。 険悪な恨みの相から、ひとを苦しめる魔王の顔へ、汚れのない真っ白な恋をする乙女の顔から、独占欲に駆られる夜叉の顔へ、そして、苦い悔恨のそれへ――― 「・・・セルヴィウスもまた、この世に2度とあらわれてくれませんでした。 私の子として生きることを、拒否したのです。 そのとき初めて私は気がつきました。 お后さまが、どんなにセルヴィウスをいつくしんで育ててくださったかということに。 お后さまには御自分のお子さまがたも大勢いらしたのに、後継者として王さまが選んだのは妾妃の子。 どれほど私を憎んだかわからないのに、その不満を少しも外に表すことなく、私の子も御自分のお子たちと同じ、広いお心で愛し、未来の王として教育してくださったのに違いありません。 だからこそセルヴィウスも、お后さまを本当の母と固く信じ、そのお后さまを殺した私を、深く恨んだのです。 セルヴィウスから幸せを奪い、苦難の道を歩ませてしまったのは、ほかのだれでもない、私自身だった。 セルヴィウスも、もう一度生まれ変わるなら、やはりお后さまの子として、そう望んだのでしょう。 それに気がついた時、私はようやく、千年の憎しみから解放されました」 長いまつげの影を落として、ゴルギアスが悲しげに目を伏せる。 「私には、長い間どうしても解けなかった謎が、ひとつ、ありました。 ミラとして成長しながら、私は、なぜリシャーナたちは一日数粒の苺だけで、元気に生きていけるのか、いつも不思議でなりませんでした。 いいえ、リシャーナの子どもに限らず、苺という食物に限らず、この、ゴルギアスホローの子どもたちは皆、飢えに苦しむこともなく、流行り病に侵されることもなく、大人になって自らここを出てゆくまでの間、総じて伸び伸びと健康に育っていきます。 栄養価の高い、バランスの取れた食物、質のいい衣類、よく効く薬、そういったものが、なぜ、形を変え手段を変え、過不足なく、やすやすと、私たちの手に入るのか。 考えて、ようやくその答えに行き当たりました。 それらはひとつ残らずすべて、母たちの、涙だったのです。 リュキアに残された母たちが、底なしの沼に呼ばれて姿を消したわが子の身を案じ、どうか無事で生きていてくれますようにと泣きながら祈る涙の、飢えることなく病に苦しむことなく暮らしていてくれますようにと日々捧げる供物の、その悲痛な母の願いが、形となってちゃんとここまで届いていたからなのです。 千年もの長きにわたって累々と、母たちは、消えた子どもたちのために涙を流し続け、ここの子どもたちはその涙によって育てられ、守られていたのです。 それに思い至ったとき私は、いまさらながら、自分の罪の深さに慄然としました。 私は、なんという愚かな、罪深い母だったことでしょう!」 神殿はまだ燃え続けていたが、大通りには、焼け出された人や怪我人を保護する兵士たちのきびきびとした動きが目立つようになり、その指示の下で、人々も次第に落ち着きを取り戻していくように見えた。 深いため息とともにその光景を見渡してから、ゴルギアスが、再びアルデバランに視線を戻した。 「子どもたちは大人になるときが近づくと、恋をして、二人手に手を取ってこの国を出て行きます。 けれどアルデバラン、あなたは、この国の中で、初めて、プロキオンとの愛を成就させました。 それによって私の邪悪な呪いはなかば解け、リュキアの子どもたちがゴルギアスホローに落ちてくることは2度となくなりました。 本当は、私が、今生で、ミラとして、アンタレスと2人、それをしたかったのかもしれない。 でも、アンタレスはそれを望みませんでした。 前世にあっては、彼の保護者であり支配者であったに違いない私の、遠い記憶が、彼の中に残っていたのかもしれませんね。 ・・・いずれにせよ、あとは、ゴルギアスホローというこの檻を、世界から孤立した砂漠から、緑なす懐かしいリュキアの地に戻せば、呪いは完全に消えてなくなります。 あの、開かずの大城門を開くと、その道はリュキアにつながります。 さあ、アルデバラン、今こそ、あなたに預けた鍵で、大城門を開けて、子どもたちを、ゴルギアスホローの檻から解き放って、母たちの、父たちの、手に返してやってください」
2011.08.31
コメント(2)
-
リュキア伝説 最終章 7
炎上する神殿の照り返しに、赤く染まったゴルギアスの横顔が、苦しげにゆがんでいる。 「・・・数年後、セルヴィウスは私のもとに帰ってきました。 でもそれは、私の愛する息子としてではなく、父母を惨殺した憎い敵として、私を討つためでした。 ・・・私は心底、うちのめされました。 実の母を仇敵と思い込んで、憎しみの中で成長するなんて、私のセルヴィウスになんというつらい運命を背負わせたのだろうと思うと、もうとっくの昔に亡くなったお后さまが、憎くて、憎くて、・・・当たりどころのない激しい憤りに私は正気を失い、おそろしい呪いの言葉を吐いてしまったのです。 王の一族、王妃の一族、そして、それに加担したすべての者の、母から、未来永劫、子を奪い続け、私と同じ苦しみを与え続けてやる、と」 地獄のような炎の色に照らし出されて、悲鳴とも怒声ともつかない声を上げながら、人々が通りを逃げ惑っていた。 その様子を悲しげに見やって、ゴルギアスが続ける。 「今リュキアと呼ばれているこの城内は、母親たちから奪った子どもたちを閉じ込めておく、世界から隔絶された大きな檻です。 リュキアの子どもたちはある年齢に達すると、“狂気の森”の底なしの沼に呼ばれて、一瞬でこのゴルギアスホローという穴の中の、“つめ草の野原”に“現し身”されますが、実際には、ここは、本来のリュキアの地からは遠く離れたところ。 山を隔て、海を隔てた彼方の、広い砂漠の中央に位置しています。 子どもたちは、ここから逃げ出すことはできません。 母たちが探しに来ることも不可能です。 もっともこのごろでは呪いの力も弱まったのか、強い愛情で沼を渡って子どもを捜しに来る親がいたり、リシャーナの森の奥が本来のリュキアの地とつながっていたり、あちこちにほころびが生じてきたようですが」 そのゴルギアスホローは、今、混乱の渦の中にあった。 燃え落ちる神殿に手を差し伸べて泣き叫ぶ者、ひざまずいて神に祈りを捧げるもの、救護に駆けつけてくる兵隊たち・・・。 ある者は若者に見え、ある者は年寄りに見える。 が、彼らはみな、父母の記憶を失った、呪われた子どもたちなのだ。 いずれは大人になり、見も知らぬ故郷へ帰る日が来るのかもしれない。 立ち尽くすゴルギアスの視線は、しかし、それらを素通りしてどこか遠いところをさまよっているように見えた。 「・・・セルヴィウスの歩んできた、長い、つらい道のりを思うと、私は、黙ってその恨みの刃をこの胸に受けるしかありませんでしたが、それでもなお、もう一度セルヴィウスと人生をやり直したいという思いは、どうしても捨てることができなかった。 もう一度、赤ちゃんのセルヴィウスをこの腕に抱いて、この手で育てたい。 もう一度。 初めから。 来世では必ず。 そう願って、セルヴィウスと私自身のために、よみがえりの秘宝『血の石』をふたつ、アンタレスに託したのでしたが・・・」 ふと顔を上げたゴルギアスの表情が、一瞬、普通の、リシャーナ族の愛らしい少女のそれに変わった。 くりくりとした輝く瞳は清らかに澄み切って、胸がつまるほど初々しい。 が、はっとする間もなくその表情は消え、悄然と肩を落としたゴルギアスが言った。 「・・・でも、私は、今生でゴルギアスとして目覚める前に、ミラという無垢な少女としてアンタレスと出会い、彼に恋をしてしまいました。 だから、セルヴィウスのための“血の石”を、アンタレスを目覚めさせるために使ってしまったのです」 「では、ゴルギアスさまご自身のための、もうひとつの“血の石”は?」 思わず身を乗りだしてたずねたアルデバランに、ゴルギアスが、優しい少女の顔で微笑みかけた。 「デネブにあげてしまいました。 レダの命を救うために、私と真の友情を結ぼうと懸命の努力していたデネブに、正面からちゃんと応えてやらなかった、不誠実な友ミラからの、せめてもの謝罪です。 それを持ってデネブはさきほど、カストールとポルックスとともに、自分のフネに帰りました。 わたしのムラ気のせいで獲得できなかった魔力のかわりに、デネブは、あの石を使ってレダを目覚めさせることでしょう。 ・・・アルデバラン、 あなたが、“血の石”の力でアルクトゥールスを蘇らせたいと願っている事は知っています。 でも、アルクトゥールスは、もうこの世界に戻ることは望んでいないと思います。 あなたを育てるためにここに生を受けたアルクトゥールスです。 あなたが自分の足で歩き始めようとしている今は、心の平安を得て静かに眠っているはず。 もし目覚めれば、また、強すぎる愛情であなたを支配しようとして、結局は自滅することになってしまう。 それはどちらにとっても不幸なことだと、賢明に悟ったのです」
2011.08.30
コメント(2)
-
リュキア伝説 最終章 6
その瞳に、深い苦悩の色を浮かべて、ゴルギアスの物語は続く。 「でも、私は反乱なんか起こしたくなかった。 ただ、セルヴィウスのことがどうしてもあきらめられなくて、王さまが狩りにいらした時、ひそかに王さまに近づいて、もう一度、私の子を返してくださいとお願いしたのです。 かわいいセルヴィウスが帰ってきたら、父もきっと反乱を思いとどまってくれる、そう思ったからですが、王さまはやはりそれをお認めくださいませんでした。 強く、賢く、美しいセルヴィウスは王家の後継者にふさわしい子、もう、リュキアの国の皇子であって、おまえ一人の子ではない、そのかわりリシャーナ一族も、王家の親族として手厚く処遇することを約束する、おまえも城に戻ってくれ、と。 そして、口論になってしまいました」 ゴルギアスの瞳が、深い慈愛と悲しみの入り混じった不思議な色をたたえて、アルデバランを見た。 「そのときです。 草むらから一頭の黒豹が飛び出してきて、いきなり王さまに襲いかかったのは。 驚いた王さまはとっさに剣を抜き、黒豹を一刀のもとに斬り殺してしまいました。 すると、今黒豹の飛び出してきたその草むらから、その後を追うように小さな子どもの黒豹が2匹、よちよちと駆け出してきて、稚い声で鳴きながら、死んだ黒豹のまわりをうろつき始めたのです。 この様子を見て、王さまも私も、ようやく、私たちの口論の声に驚いた母豹が、子どもたちを守ろうとして襲いかかってきたのだということに気がつきました。 王さまはこれを哀れと思し召し、母豹を丁寧に弔い、子どもたちは城に連れ帰って母豹の代わりに大切に育てるよう、私にお命じになりました」 そのときの子豹たちが、アンタレスとあなたです、と、ゴルギアスが優しく微笑んだ。 「・・・けれど、王さまはそのときすでに、黒豹の爪から受けた毒に蝕まれておられ、私がお城にお送りする途中、馬車の中で息を引き取ってしまわれました。 そのとき私は初めて、王さまの剣から、霊石『慈悲の涙』が抜き取られていることに気づき、お后さまの策略に思い至りました。 前々から、王さまの愛情を独占する私に嫉妬していたお后さまは、王さまが狩りに行くことを知って、私と会うことを予測し、おそらくは口論になることも見越して、王さま自ら私を斬り捨てるように願をかけ、剣から霊石を抜き取ってその慈悲心を奪ったのにちがいない、と」 ゴルギアスの瞳が、再び、妖しく激しい憎悪の色に燃え上がった。 「私は、そのとき、鬼になりました。 私からセルヴィウスを奪い、王さまの命をも奪った、お后さまへの恨み、抑えがたく、父の戦士たちを率いて城に攻め入り、お后さまとそのお子たちをとらえて塔に押し込め、王さまの忘れ形見セルヴィウスを奪還しようとしました。 が、セルヴィウスはそのときすでにどこか別のところに隠されて、城にはいませんでした。 私は何とかしてお后さまからセルヴィウスの居所を聞きだそうとしましたが、お后さまはついに口を閉ざしたまま、塔から飛び降りて自殺してしまわれました」 ゴルギアスの口から、痛恨とも悲哀ともつかない、深いため息が漏れる。 「・・・結局、セルヴィウスの行方はわからぬまま、私は、成り行きでリシャーナ一族の長となり国王に担ぎ上げられて、国政の実権を握ったのですが、私にとっては、そんなものはどうでもよく、施政はすべて父とその近臣たちにまかせきり、いつかセルヴィウスが私のもとに帰ってきてくれるというはかない望みだけを頼りに、城内にこもり、自暴自棄の日々を送っていました。 民の幸せなんて、考えたこともありませんでした。 国は乱れ、民の心は病み、私はリュキア国民から、呪詛をこめて破壊王ゴルギアスと呼ばれるようになりました」
2011.08.29
コメント(4)
-
リュキア伝説 最終章 5
大城門から、ひらりと飛び降りたアルデバランの背中に、静かな声をかける者があった。 「・・・アルデバラン、とうとう、アンタレス兄さんを殺してしまったのね」 どこかで聞いたことのある声。 遥かな昔、遠い記憶の中の、母にも似た優しい声。 「・・・ゴルギアスさま?!」 振り返ったところに立っていたのは、ひとりの小さなリシャーナだった。 その顔に見覚えはなかったが、そのひとは、前世ではよく見知った人、アルデバランが母と慕った人に間違いなかった。 寂しげな微笑を浮かべたそのひとが、小さくうなずいた。 「そうです。 前世で私は人々に、憎しみを込めて、その名で呼ばれていました。 現生では、ミラ、という名で呼ばれていましたが、その名も、今は捨てました」 その、不思議な色の瞳は、いま、涙で赤く潤んでいた。 「・・・猛々しく美しい獣だった前世にあっても、あなたとアンタレスとは水と油、小さなころから本当に仲が悪くて、けんかばかりしていましたね。 穏やかなあなたと違って、アンタレスは、荒々しい野生むき出しの性格で、見るもの触れるもの動くものなら何でもすぐに飛びかかって殺してしまう。 私もずいぶん叱りつけたり罰を与えたりして直そうとしましたが、おとなになってもその性格は少しも変わることがありませんでした。 それで私は、お別れの時、彼の罪が少しでも軽くなるよう、彼に命を奪われた者が再びこの世に蘇ってその生をまっとうできるように、秘宝“血の石”を持たせたのです。 アンタレスもあなたも、同じように、私にとっては可愛い息子たち。 奪い去られた本当の息子のかわりに、どんなに私の心を慰め、癒してくれたことでしょう」 まるで性格の違う2頭の黒豹兄弟に、わけへだてなく、惜しみない愛情を注いでくれたこの人の笑顔が、いつもどこか寂しげに翳っていたのが、アルデバランの記憶の中にも確かに、強く焼きついていた。 その、さびしい笑顔で、ゴルギアスが、今では忘れ去られた古いリュキアの伝説の、真実を語り始めた。 「リュキア王さまと私は、アルデバラン、ちょうどあなたとプロキオンのように、リシャーナの森で出会い、恋に落ちました。 王さまは、気高くまばゆい、太陽のような方で、私はひと目見るなり彼に夢中になってしまいました。 王さまも、すでにお后さまがおいででしたが、そのお后さま以上に、私を深く愛してくださいました。 リシャーナ族の長老であった私の父は、私が第2妃として王宮に上がることに猛反対しましたが、私にはもう何も聞こえませんでした。 一途に王さまをお慕い申し上げ、着の身着のままでお城に上がり、王さまの愛を独占して、お子までなしました。 それがセルヴィウス皇子 ――― リュキア王の長子です」 その瞬間、ゴルギアスの瞳に、暗い憎悪の炎が燃え上がったように見えた。 「けれど、セルヴィウスが生まれると、王さまは私からその子をお取り上げになってしまいました。 セルヴィウスは、王の後継者。 正室のもとで育てなければならない、と。 私はどんなに王さまを恨んだことでしょう! どんなにお后さまを憎んだことでしょう! セルヴィウスを返してと、昼夜の別なく泣き叫び、あまり泣き騒ぐので、私は近臣たちにお城から追い出されてしまいました。 泣き疲れて恨み疲れて、生きる気力も失って、リシャーナの森を出たとき同様着の身着のままで、ふらふらと村に戻った私を見ると、父は烈火のごとく怒り、すぐに村人を集め、王に反旗をひるがえす支度をはじめました」
2011.08.28
コメント(0)
-
リュキア伝説 最終章 4
エリダヌスの手をしっかりと握りしめたまま、レグルスが、窓の下に向かって叫んだ。 「アンタレス! 無茶をするな! なぜ私がここにいるとわかった?」 夜空に向かって燃え上がる火柱の、目もくらむような光と、強風に渦を巻く火の粉の中、90度に屹立する塔の外壁を登ってくるアンタレスは、吹きつける熱風にあおられて今にも壁から引き剥がされそうだ。 レグルスを見上げて、アンタレスが答えた。 「『夢幻の香炉』だ! そこに『夢幻の香炉』があるはずだぞ。 アナルケルが、塔の最上階に納めたと言っていた、それを探せ。 それは、おまえが真の王になるために必要な、3つの秘宝のうちのひとつだ。 その香炉と、この前手に入れたハンマーと、それからもうひとつ、ケンタウロスが保管している『王妃の宝石箱』。 この3つを持って迷宮の、グリュプスのところへ・・・」 レグルスが、窓から身を乗り出して、アンタレスのほうに手を差し伸べた。 「アンタレス、今我々に必要なのは、この窓から外に脱出するための、長いロープだ。 この塔には呪いがかかっていて、この窓以外に出口がない」 「呪い・・・ゴルギアスの魔法か」 レグルスが伸ばした手に、アンタレスがつかまろうとしたそのとき、どこからともなく飛んできた太い矢が、アンタレスの無防備な背中に、ドスッといやな音を立てて突き刺さった。 凄まじい衝撃に、アンタレスの細いからだが一瞬、弓なりに反り返る。 つかんでいた壁から、その手が離れて、宙に舞った。 「アンタレス!」 間髪をいれずレグルスが窓から大きく身を乗り出し、アンタレスの手をがっしとつかんだ。 渾身の力で窓に引き上げるレグルスに、アンタレスが苦しげな声を絞り出した。 「矢を、・・・背中の矢を、抜いて、・・・」 一瞬息を飲んでから、レグルスがうなずいた。 「矢を、抜くんだな?」 レグルスが手を伸ばして、アンタレスの背中に深々と突き刺さった矢をつかんだ。 「抜くぞ!」 咆哮にも似たレグルスの声と、アンタレスの苦悶の声が重なる。 地獄のような一瞬のあと、アンタレスが、ぐったりと血の気の失せた顔で、レグルスの手から、血染めの矢を取った。 「・・・レグルス、さすがは未来の王だ。 ちゃんと救いの矢が飛んできた。 この矢には、リシャーナの“魔法返し”がかかってる。 俺の“リシャーナの鎧”を打ち抜くためにかけたのだろうが、俺は“リシャーナの鎧”をつけていなかった。 だから“魔法返し”はまだ有効。 これを使って、この塔にかけられた呪いの魔法を、解いてやる」 言って、アンタレスは、レグルスの手を振りほどき、窓枠を蹴ったその勢いで、矢を、塔のてっぺんに向かって投げつけた。 「止めろ、アンタレス!」 レグルスがあわててアンタレスをつかまえようとしたが、遅かった。 「レグルス、迷宮への案内はヴェガに・・・」 言い残して、力を失ったアンタレスが、ぼろ人形のように、闇の底へ落下していく。 塔のてっぺんに突き刺さった矢が、一瞬、白色に輝き、次いで塔全体が白い光に包まれて、オレンジ色に燃えあがる神殿と、鮮やかな対をなした。
2011.08.27
コメント(2)
-
リュキア伝説 最終章 3
ジャムルビーたちの頑迷さに歯噛みしながら、リゲルは、後から応援に駆けつけてきたバルドーラ兵たちに向かって怒鳴った。 「伝令! 緊急出動命令を! リュキア全軍に非常召集をかけて神殿の救援に出動するよう、直接ヘルメス将軍に言え! 後は俺が全責任を取るから、俺の名前で、そのまま、土足で北辰館2階の将軍の寝所に踏み込んで行っていい! 指揮は・・・、あのじいさまじゃだめだな、ジューラ大佐にやらせろ! あの人なら24時間武器管理室に詰めてる。 ・・・なに、リザード中将閣下? だめだめ、あいつは、夜まで軍舎に残っていたことなんかないもん」 バルドーラ兵たちがどたばた走り去っていくのを見送って、カノープスが驚嘆したようにリゲルを見上げた。 「・・・あなたは、いったい、何者・・・?」 肩をすくめて、リゲルが答える。 「俺はリゲル。 ただの訓練生だ。 なんの権限もない。 だけど、こんな非常時にいちいちお偉い方々の御裁可なんかお伺いに行く暇はないだろ? 俺の采配が悪かったら後で俺が一人で罪を被る。 とにかく今は、俺にできることを全部する。 それだけのことだ」 そのとき、もうひとりの神官、スピカが、塔の上のほうを指差して叫んだ。 「あっ! 誰かこの塔の外壁を上っていく人がいますよ! 何者だろう! 早いなあ!」 びっくりして、その指差す先を見れば、なるほど、塔の外側を、てっぺんの窓に向かってすごい勢いで登っていく人影がひとつ、炎上する神殿の炎の色に照らされて、はっきり浮かび上がって見える。 炎の熱に煽られてなびく、闇の色の長い髪に、ほっそりとしなやかな体つき。 あの人影、どこかで見覚えがある、と考え込んでいると、スピカが、今度は、大城門のほうを指差して叫んだ。 「あっ! 大城門の上にも、誰か登って来ようとしている!」 はっとそちらに目をやれば、見上げるほど高い、大城門の上にも、今、誰かが登りきって、すっくと立ち上がったところだった。 神殿の炎に照らし出されたその姿は、なんとこちらもまた、闇の色の長い髪に、ほっそりした体つき。 塔を上っていく人影と、瓜二つ、まるで鏡像、まるで、2頭の黒豹だ。 このときやっとリゲルは、確かに見覚えのあるその人影が誰なのか、思い出した。 今年の入隊審査でトップの成績をおさめ、にもかかわらずそれ以後ふっつりと姿を見せることのなかった、今では伝説となった勇士、アンタレスだ。 一方、大城門に登って来た人影のほうは、剣を佩いていなかった。 そのかわり、狩人たちの持つ大きな弓を背負っていて、大城門のてっぺんで、それを肩から下ろし、矢筒から太い矢を一本抜き取って弓につがえた。 定めた標的は、まばゆい光に照らし出されて、塔を登って行くアンタレスの背中。 「・・・あ、あいつ、何をする気だ・・・!」 なすすべなく見上げるリゲルの頭の上で、大城門の射手が、力の限り引きしぼった矢を、ぱっと放った。
2011.08.26
コメント(2)
-
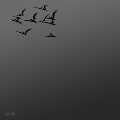
リュキア伝説 最終章 2
門番が少し不安げに、それでもおとなしく剣をおさめると、リゲルは、異国の神官の顔をものめずらしげにじろじろ見ながら言った。 「訓練場の外の砂漠に出たい、と言ったな? 急いでるんだな? よし、それも俺の責任において柵を開けてやろう。 ただ、手短でいいから事情を説明してくれ。 おまえは、わが軍に派遣されていた布教師に縁故のある者だな? エリダヌス師拉致の件で動いてるんだろ?」 「ありがとうございます! 仰せのとおりです」 柵に向かって駆け出したリゲルの後を、機敏な動きで追いながら、神官が答えた。 「私たちは、法力をもって遠くはなれた仲間と会話することができますが、今日昼ごろ、突然エリダヌスとの連絡が途絶えてしまいました。 心配になり、リシャーナの長老にお願いして、モミの木の森のカラスたちを総動員して捜索に当たらせたところ、夕方になってようやく、南大城門の外の、塔の最上階の窓に、エリダヌスの姿を発見したという知らせが返ってきました。 ただ、どうやってそこまで行ったのかがわからない。 塔は城壁の外にあって、城壁の外には、この軍訓練場を通らなければ出られないのですから。 でも、この国に到着した夜、あの塔の足もとに、砂に埋もれかかった小さな出入り口がひとつだけあったことは記憶にありましたので、あの戸をこじ開けて塔の中に入ろうと、それで、こちらから砂漠に出していただくためにまいりました。 私の後からもう一人、弟神官のスピカが、塔の出入り口の鍵を開けるため、パピトの街から腕のいい鍵開け職人を連れて、こちらに向かっています。 おっつけ到着すると思います」 「あの塔は、砂漠にも出入り口があったのか!」 リゲルは目を丸くして、カノープスというこの神官の顔を振り向き、それから、おろおろと2人の後を追ってくる門番に言った。 「門番! 今の聞いてたね? じゃ、急いで北辰館に走って、今日の夜勤担当の兵長にこの事情を一言一句もらさずに伝えよ。 それから夜勤兵の半数で応援部隊を編成して、南天舎の食料庫に向かわせる。 いいね、食料庫だよ。 そこに待機している料理人たちに案内させて、地下通路を南に進攻するんだ。 すると、どんづまりは塔の入り口。 そこでアルタイルが待っているから、以後はアルタイルの指示で動け、と。 それから、砂漠の、俺たちリゲル隊の方にも応援兵を何人かよこすように。 ・・・了解?」 命令を復唱してから、門番が、カチッと靴のかかとを鳴らして敬礼した。 「了解しました! エリダヌスさんの救出ですね? 俺たちも、全力で当たります!」 柵の戸を開けて、踏み出した砂漠は、すでに夜の帳が下りて、物音ひとつない、果てしなく暗い水底のようだ。 白い砂を蹴って大城門のほうに走っていくと、カノープスの言うとおり、見張りの塔の足もとには、砂に半ば埋もれて、小さな戸がひとつあった。 後から追いついてきたスピカという神官と、彼が連れてきた、腕のいい鍵開け職人だというパピトたちがさっそくランタンの灯りを頼りに、錆びついたその錠前を調べ始める。 そのとき、突然、あたり一面、ぱーっとまばゆいオレンジ色に染まった。 「な、なんだ?!」 振り向くと、城壁の中、競技場の先のあたりに、巨大な火柱が上がっていた。 まぶしそうに片手で顔を覆いながら、カノープスが答える。 「リュキア神殿が炎上します。 通常の火と異なり、消すことは不可能だと聞いています。 が、火が放たれてから炎上までには少し時間の余裕がありましたので、神官たちはみな外に避難しました。 ご病気の方、眠っておられる方なども、全員退避させることができたということです」 「なんと! そんな大事故が起きているのに、神殿はなぜわが軍に救援を要請してこないのか?!」
2011.08.25
コメント(0)
-
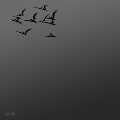
リュキア伝説 最終章 1
「レグルス!」 目の前で閉ざされた重い扉に飛びついて絶叫したベテルギウスは、しかしすぐにリゲルを振り返って言った。 「リゲル、ここの鍵は、アナルケル少佐が持っておられると言ったな? では、アナルケル少佐に、鍵を借りてくる!」 身をひるがえして通路を駆け戻るベテルギウスの背中に、リゲルは急いで声をかけた。 「アナルケル少佐は、今休暇を取っておられます! 神殿で、重篤な怪我人の治療に専念しておられるとか。 ここの鍵も、きっと神殿に持って帰っておいでのはず。」 猛スピードで走り去りながら、ベテルギウスが手を振って答えた。 「了解した! 直接神殿に向かう」 その後ろ姿を見送って、リゲルは、今度はアルタイルに言った。 「アルタイル、俺はいったん兵舎に帰って応援を呼んでくる。 大勢でこの扉をぶち破れば、あるいは鍵も壊せるかもしれない。 アルタイル、おまえはここで、この扉を見張っていてくれ。 レグルス軍曹が入ったらひとりで閉まった扉だ。 一定時間が過ぎたら、またひとりで開く、という可能性もある」 アルタイルが、期待に輝く目を、扉に向けてうなずいた。 「たしかにそうだな。 よし、俺ここでしっかり見張ってて、扉が開いたらすぐにレグルス軍曹の後を追うぞ!」 北辰館の戦士たちに非常召集をかけに南天舎を出たとき、訓練場通用門からひとりの小柄な神官が、息せき切って駆け込んでくるのが目に入った。 リゲルの姿に目をとめた神官が、真っ直ぐこちらに向かって駆けて来る。 詰所からあわてて駆け出してきた門番が、大声で停止を命じながらその後を追う。 ――― とても急いでいて、門番に来意を告げる暇もない、そんな様子に見えた。 ジャムルビーとは思えない軽やかな身のこなしで、飛ぶようにリゲルに駆け寄ってきた神官が、フードを取り去るのももどかしげに言った。 「御無礼いたします。 士官学校の方とお見受けいたします。 わたくしはリュキア神殿の客神官で、今はリシャーナの村に派遣されております、カノープスと申します。 どうか、急ぎあの柵を開けてくださいませ! 私たちが砂漠に出るお許しを、今すぐに!」 まだ若い、硬質で繊細なガラス細工を思わせる、整った風貌の神官だ。 言葉遣いは丁寧だが、有無を言わせぬ語気で、神官が指差したのは、訓練場と砂漠を区切る、盗賊避けのための高い金網の柵。 その外の砂漠に出ることは、特別な事情のない限り、一般人には許されていないのだ。 追いついてきた門番が、真っ赤になってその神官につかみかかった。 「こらっ! 許可なく勝手に軍施設内に入ると半年間の禁固刑だぞ! こっちへ来い!」 その腕を引っつかんだとたん、門番の手に、ピシッと小さな音を立てて青白い火花が散った。 「いててっ!!」 飛び退った門番に、神官が深々と頭を下げた。 「申し訳ありません、緊急の事態なのです! 御処分は後で何でも受けますから、今は、しばらくの御猶予を!」 なおも剣を振りかざして乱入者を取り押さえようとする門番を制して、リゲルは言った。 「良い。 この者の門内への立ち入り、俺の責任において許可する。 剣をおさめよ」
2011.08.24
コメント(2)
-
続 ゴルギアスの塔 5
「レグルスさま!」 駆け寄ったエリダヌスを、レグルスの腕がしっかりと抱きとめた。 なんと、あたたかく、力強い腕だろう! これで救われたというわけでは決してないのに、その瞬間、全身からいっぺんに力が抜けていくほど、深く、深く、安堵した。 「エリダヌス!」 激しい力でエリダヌスをかき抱く、レグルスの熱い胸から、トク、トク、と確かな心臓の鼓動が伝わってくる。 その音が嬉しくて、どっと涙があふれてきた。 レグルスが、両手でエリダヌスの肩をつかみ、自分の胸から引っぺがして顔を覗き込んだ。 「エリダヌス、大丈夫か? 怪我はないか?」 レグルスの、明るい琥珀色の瞳にも、同じ、安堵の涙がいっぱいたまっていた。 その涙を隠そうとするように、レグルスがまた、荒々しくエリダヌスを抱きすくめる。 「・・・おまえが拉致されたと聞いて、生きた心地もしなかった。 おまえの身にもしものことがあったら、と思うと、私は・・・」 嬉しいのか悲しいのか、突き上げてくる熱い感情に声を詰まらせながら、エリダヌスはようやく言った。 「レグルスさま、申し訳ありません! 命を狙われたのは私ではなく、レグルスさまなのです。 私は、あなたさまをここまでおびき寄せるためのエサ、そしてここは、一度入り込んだら脱出の手だてがないゴルギアスの牢獄なのだそうです。 ここを出るには、あの高窓から遥かな地上に身を投げるより他に方法が・・・」 すでに、夜の闇に閉ざされた窓の外を指差して、エリダヌスはまた、声を詰まらせた。 「なに? 外に出られない? そんな馬鹿な。 だって私は今何の支障もなくすいすいとここまで・・・」 言いながら、戸の方を振り向いて、レグルスも、はっとしたように声を途切らせた。 たった今、レグルスが飛びこんできた戸は、いつのまにか固く閉ざされていた。 戸に飛びついたレグルスが、押したり、引いたり、叩いたり蹴飛ばしたり、渾身の力を込めて試みるも、それはびくとも動かなかった。 エリダヌスは絶望に打ちひしがれながら告げた。 「たった一つしかないその鍵は、アナルケルという神官が持っていたそうですが、そのアナルケルも神殿の地下で落命したと、フォーマルハウトは言っていました」 「アナルケルが、落命・・・? あの、アナルケルが?」 不思議そうにレグルスがつぶやいた時、すでに闇に沈んでいた窓の外が突然、ぱーっとオレンジ色に燃え上がった。 ぎょっと顔を上げ、窓際に駆け寄った二人の目に映ったのは、天をも焦がすと思われる巨大な火柱。 「ああ、リュキア神殿が・・・!」 足もとが崩れ去るような気がしてふらふらと倒れかけたエリダヌスを、しっかりと支えながら、レグルスがその巨大な火柱の底部を覗き込んだ。 「なぜ神殿が炎上を? 火をかけたのは誰だ? 中の神官たちは、避難できたのか?」 真昼のようにまばゆくあたりを照らし出すオレンジ色の光の中、窓から身を乗り出したレグルスが、眼下を見おろしてさらに驚愕の声を上げた。 「誰かこの塔の外壁をのぼってくる! すごい速さだ!」
2011.08.22
コメント(0)
-
続 ゴルギアスの塔 4
窓の外の四角い空は、すでに夕暮れの色も消えて、夜の色に染まろうとしていたが、塔の中は、暗くなるということがなく、昼も夜も、常にほんのりとうす明るかった。 窓がなければ時の移ろいさえわからない、永劫の幽暗地獄。 その薄闇の中、ひっそり横たわったフォーマルハウトの死に顔は、とても美しかった。 どんな法力も魔法もその効力を現さない、この不思議な塔の内部では、ゴルギアス千年の呪いさえも、効力を失うのだろうか。 それとも、この国の神官たちは、死んだときやっと、ゴルギアスの呪いから解放されて、生きている時にはついに一度も見ることのできなかった、本来の自分の顔を取り戻すということなのだろうか。 いずれにしても、なんというむごい呪いだろう。 フォーマルハウトの、砂に汚れた顔をきれいにぬぐい、乱れた髪をといてやりながら、エリダヌスは、不思議な思いで、今初めて見るフォーマルハウトの、美しい顔に話しかけた。 「・・・フォーマルハウト、あなたは、こんなにきれいな顔をしていたのね」 フォーマルハウトが、エリダヌスの声に静かに耳を傾けていてくれるような気がした。 「ねえ、フォーマルハウト、美しさ、って、何なのでしょう。 奇妙なことを言うとお思いかもしれませんけど、私、あなたと親しくおつきあいさせていただいている間ずっと、あなたのお顔が、ご自分でおっしゃるほど醜いとかおそろしいとか思ったことは一度もありませんでしたよ。 それは呪いをかけられた身でなければそのつらさがわからないからだ、と、あなたはおっしゃるのかもしれませんけど、私にとってあなたはずっと、カノープスやスピカや、ハザディルに残してきた弟妹たちとどこも変わることのない、かけがえなく愛しい、大切な存在でした。 それは、あなたの心が、あの子たちと同じように、まっさらで、純粋で、美しかったから、と、私は今も信じているんですよ。 あなたが初めて私の目の前に現れて、私が一生の間にいただく分の幸福を、全部このかたにお譲りしたいと神さまにお願いした、あのときの、慈愛に満ちた、気高く清らかな、天使のような、あのフォーマルハウトのままだと、私、今も信じているんです」 耳の奥に、フォーマルハウトの、無邪気な笑い声が蘇る。 2人で過ごした時間の、楽しいことばかりが思い出された。 「フォーマルハウト、思い出してください。 レグルスさまが私にお心を開いてくださったのも、決して私の容姿なんかのせいではなかったでしょう? 毎日毎晩、落ち込んで顔も上げられないボロ雑巾みたいな私といっしょに、悩んで苦しんであれこれ方策をひねり出して私を強力に後押ししてくださった、あなたの奮励が実を結んだからではありませんか。 半分以上、あなたのご功績ですよ。 いっしょに喜んでくれるとばかり思っていたのに、それは私の思い上がりだったのですか? ならばその苦しみ、なぜ私にも分けてくださらなかったのですか? あなたにとって私は、そんなに頼りにならない姉でしたか?」 その心の闇を知ってしまった今も、また、別人のように変容しても、なお、フォーマルハウトはやっぱり、エリダヌスのよく見知った、慎み深く、柔和で、敬虔な、可愛い弟の一人、あのフォーマルハウト以外の何者にも見えなかった。 その遺体に取りすがって嗚咽を洩らす、エリダヌスの耳に、そのとき、階段を一足飛びに駆け上がってくる音が、聞こえてきた。 はっと顔を上げたエリダヌスの目の前で、石室の戸が、ばん、と、勢いよく開いて、全身から金色のオーラを発する太陽のように、輝ける若きレグルスが飛び込んできた。 「エリダヌス、無事かっ!」
2011.08.21
コメント(0)
-
続 ゴルギアスの塔 3
はっと顔を上げたエリダヌスの前で、アードウルフが、崩れるように床に倒れこんだ。 「ア、ギーラ・・・?」 混乱しながら、思わず駆け寄ったエリダヌスを見上げて、アードウルフが薄く笑った。 「ああ・・・まだ、その名前で俺を呼んでくれるんですか、エリダヌスさま」 その瞳は明るく、くもりひとつなく澄み切っていた。 「・・・この魔剣は諸刃の剣、人を斬り殺せば自分も同じ目に遭う。 あなたを斬った時には、あなたが生き返ってくださったから、俺も命拾いできた。 でも今度は、とうとう俺にも相応の天罰が下されるようです」 すでに夕暮れの迫る砂漠の空の色を映して、アードウルフの瞳が悲しげに曇る。 「・・・エリダヌスさま、今までずっとあなたをだましていてすみませんでした。 だけど、俺はどうしても、あなたの命を本当に狙っている正体不明の敵から、あなたを守りたかった。 非道な行いをした、その償いをしなければいけないと、ケンタウロス先生に、あの『偽りのガラス玉』をいただいたときから、俺は、この薄汚い命を、エリダヌスさまに捧げるためにだけ、生きてきたんです。 やっと敵の正体をつかんで、その息の根をとめることができた今、俺、あなたに多少なりとも償いのまねごとができたでしょうか」 「何を言うんです、アギーラ!」 エリダヌスは思わず、アードウルフの、傷だらけの手を握りしめた。 ああ、この人は今まで、一人でどんなに苦しんでいたことだろう、と思うと、胸がつぶれるような気がした。 エリダヌスが、あのおそろしい事件を早く忘れてしまおうと努力奮闘している間、この人はひとりで、ずっと自分の罪に向き合い、まっすぐエリダヌスを見つめ続けていたのだ。 誰にもその心の内を明かすことなく、ただ無言のままで。 それは、どんなにつらいことだっただろう! すすり泣きながら、エリダヌスも自分の思いを吐露した。 「・・・私は、あなたがあの盗賊団の首領だということは知らなかったけれど、最初は、あなたが怖くてしかたがありませんでした。 毎日私の部屋に来て、ただ黙々と用を足してくれるあなたに、感謝しなければと思いながら、わけもなく気味が悪くておそろしくて、なかなかあなたに心を開くことができなかった。 でも、あなたは、そんな私を怖がらせないように、いつも心を砕いてくれていましたね。 近づきすぎず、かといって離れもせず、いつも絶妙の距離を保って、しっかりと私に寄り添い、支えていてくれました」 かいがいしくエリダヌスの世話をしてくれるアギーラの、孤独な後姿が脳裏に蘇って、その心中を思うと、あわれで、痛ましくて、涙が止まらなかった。 憎む気持ちは、少しも起きなかった。 「・・・知らない国の、知らない神殿で、知らない人たちに囲まれて、心細い思いをしている私のそばに、いつもそっと立って気遣ってくれるひとがいる、それはどんなに心強いことだったでしょう! だんだんあなたに心を許すようになって、いろいろなおしゃべりをするようになると、ますます、私の中であなたの存在は大きくなっていきました。 あなたがよその国から来たことを知っていたわけではないのに、不思議にもあなたは、私にとっていつも、同じ異邦人、さびしい同胞、でした。 思えば、私がつらい修行に耐えることができたのも、弟たちに会えない寂しさを紛らすことができたのも、あなたがいつもそばにいてくれたからでした。 あなたは、私にとって、なくてはならないひと。 私の同胞で、私の親友の、アギーラでしょう? どうか、これからも私を守って、助けてください!」 「・・・エリダヌスさま!」 エリダヌスを見上げるアギーラの瞳から、大粒の涙がこぼれ落ちた。 「そんなふうに言ってもらえるなんて・・・俺、幸せだ」 微笑んで、アギーラが、静かに目を閉じる。 「・・・俺、なんとかしてこの塔から、・・・エリダヌスさまを、お出しくださいと、・・・神さまに、お願いに・・・行って、きますから・・・」 「だめ! アギーラ! ああ、死なないで! 目を開けて!」 エリダヌスの嗚咽が、むなしく石壁に反響した。
2011.08.20
コメント(2)
-
続 ゴルギアスの塔 2
小さく頭を振ってから、フォーマルハウトがまた、アードウルフの顔をしげしげと珍しげに見下ろした。 「・・・それにしても、アギーラ、神殿の下働きに、よく化けたものですね! 今まで誰一人として正体に気づかなかったとは! 私の得意とする『虚言』の呪法をもってしても、ここまで完璧に人をだますことはできません。 いったいどんな魔法を使ったんです?」 アギーラが、唇をゆがめて笑い、懐から、透き通ったちいさなマリのようなものを取り出した。 「『偽りのガラス玉』――― お前の『虚言』と同じ効果で、今までずっと俺の正体を隠してくれていた秘宝だ」 真っ青になって震え続けるエリダヌスを、悲しげな瞳で見やって、アギーラが、そのガラス玉を、邪悪な秘宝の並ぶ棚の上に置いた。 「・・・ エリダヌスさまに俺の正体を明かした今、これはもういらなくなった。 この先誰も使うことのねえよう、ここに納めておくのがいいだろう」 そのガラス玉から手を放したとたん、アギーラは、正真正銘、見た目も恐ろしい、あの砂漠の盗賊団の頭領、アードウルフに変貌した。 その、凶悪な狼のように無慈悲な相貌に、さすがのフォーマルハウトも、思わず一歩後退る。 「アギーラ、お前は、何のためにそこまでしてエリダヌスに近づこうと・・・?」 アードウルフが、にやり、と凄みのある笑みを浮かべた。 「しれたことよ、俺を使ってエリダヌスさまを殺そうとしたやつを突き止めて、そいつに引導を渡すためさ」 アギーラが、ばっ、と、音を立てて、勢いよく神衣を脱ぎ捨てる。 神衣姿の下には、武装した砂漠の盗賊団頭領、アードウルフの姿があった。 窓から吹き込んだ一陣の熱風が、アードウルフの乾いた砂色の髪を、ざっ、とかきあげる。 アードウルフが、黒光りする『人斬りの魔剣』を、すらりと抜くがはやいか、その長い刀身を、真っ直ぐフォーマルハウトの胸に突き出した。 「よく見ろ、これが『人斬りの魔剣』だ! お前が、大芝居打って俺の手につかませた、殺戮剣だ! やっとお前に返すときがきたぜ! さあ、それを持って、さっさと地獄に落ちやがれ! 神さまの楯も、祝福も、ここでは効かねえんだ!」 魔剣の刃が、ぬめりと不気味に一閃して、フォーマルハウトの胸に、吸い込まれるように深々と沈みこむ。 「ああ、やめて! そんなことをしてはだめ!」 たまらず両手で顔を覆ったエリダヌスの悲鳴と、フォーマルハウトの断末魔の絶叫が、呪いの塔の中に陰々とこだまする。 それに、アードウルフの怒声が重なった。 「けっ、天馬を呼んで、ひとりでここから逃げ出す、だと? おい、フォーマルハウト、地獄への土産話にもうひとつ教えてやる。 天馬は、お前がいくら呼んでも、もうこのあたりには近づかねえんだ。 お前に酷使されたあげく飛ぶ力を奪われた、かわいそうなあの天馬が、親切な人に助けられてまた飛べるようになり、天馬の国に帰って仲間に知らせたからさ。 ゴルギアスホローの空には決して近づくな、悪魔のような神官につかまって翼をもぎとられてしまうから、と。 その日から後、ここの空を天馬が飛ぶことはなくなったんだ。 フォーマルハウト、てめえのことしか考えないおまえは、そんなことにも気がつかなかったんだなあ!」 かかと笑った、アードウルフの声が、不意に途切れた。
2011.08.19
コメント(4)
-
続 ゴルギアスの塔
「なるほどねえ、フォーマルハウト、お前はそんなことを考えていたのか」あるはずのない不気味な笑い声に、フォーマルハウトがぎょっと振り向いた、そのすきに、エリダヌスは急いでフォーマルハウトの手を振りほどき、窓枠から飛び退いた。 が、フォーマルハウトの視線の先に立っている人影を見ると、エリダヌスは、再びその場に凍りついた。 フォーマルハウトも、驚愕の表情を浮かべている。 「・・・アギーラ?! おまえ、声が・・・!」 四方の石壁に不気味な笑い声を響かせて、アギーラが、これまで、深く下ろして一度もとったことのないフードを、勢いよく、ばっ、と脱ぎ去る。 その顔には、見るも恐ろしい傷跡が、無数についていた。 「フォーマルハウト、お前にこの顔は見覚えがないんだろうな。 お前はいつも高みから見下ろしているばかりだもんな。 汚い仕事には決して自分で手を下さねえ」 ――― エリダヌスには、見覚えがあった。 忘れることのできない恐ろしい顔、恐ろしい声。 あの、悪夢のような砂漠の夜、エリダヌスの胸に、黒光りする長い剣を深々と突き立てて、命を奪おうとした、凶悪な盗賊。 「・・・アードウルフ!」 悲鳴のような声で叫んで、そのまま恐怖に凍りついて身動きできなくなったエリダヌスを、アードウルフが、いや、アギーラが、いや、アードウルフが、苦しげな表情でちらりと見やってから、また、フォーマルハウトに向かって、憎々しげに、牙をむき出した。 「フォーマルハウト、お前は、俺に、エリダヌスさまを襲わせるために、その数日前にあらかじめ、にせものの3人組の旅の修行者を襲わせたな。 旅の修行者は見た目に似合わず宝をたくさん持ち歩いていて、それを奪うのも簡単、割のいい仕事だ、と俺に思い込ませ、エリダヌスさまの一行を見つけたらすぐに襲いかからせるためだ。 加えてもうひとつ、手にすれば誰でも人殺しをしたくなる魔剣を俺に持たせるためだ。 悪知恵の働くやつめ、お前は、エリダヌスさまをリュキア神殿に受け入れたくなかったから、俺を使って、途中でその命を奪おうとしたのか」 「手にすれば誰でも人殺しをしたくなる魔剣・・・!」 ぬめぬめと黒光りする、あの恐ろしい剣の、胸に食い込む冷たい感触が蘇って、身体が、がたがたと激しく震え始めた。 両手でしっかり自分の身体を抱きしめて、耐えようとしたが、震えはおさまらなかった。 そのエリダヌスに、フォーマルハウトが、冷ややかな視線をちらりと投げかけ、肩をすくめる。 「本当に、エリダヌスには気の毒なことをしてしまいました。 でも、あのときはまだ、命まで奪おうとしたわけじゃないんですよ、本当に。 アナルケルの言いつけどおり、レグルスの気を引くために、少しだけ派手な怪我をさせるにはどうしたらいいかと、考えあぐねた結果だったんです。 レグルスは、ジャムルビー族を毛嫌いしていますから、少しばかりの傷を負ってみせたくらいで気を許すはずがないし、そもそもパピト族の盗賊たちは、金品を盗むだけで武器を振り回すようなことはめったにしないものだ。 かといってバルドーラの盗賊になんか襲わせたら、3人とも、あっという間に滅多切りにされるか、あるいはさらわれて人買いに売り飛ばされてしまうかもしれない。 そんなことになったら、私の手に負えなくなってしまいます。 それでは困りますから、やむなく『人斬りの魔剣』を持ち出すにいたったんです。 まさか、あれほどの強い霊力があるとは、私も思いませんでした」
2011.08.18
コメント(0)
-
わかれみち 11
ミラの脳天を直撃すると思われた剣は、ぎりぎりのところでぴたりと動きを止めていた。 おそるおそる見上げたアンタレスの、ルビー色の美しい瞳は、今、大きく見開かれて、ミラの顔でもない、剣でもない、虚空を見つめていた。 その白い顔がだんだん赤く染まっていく。 びくとも動かなくなった剣を、腕を、体を、渾身の力をこめて動かそうとしているのだ。 でも、それは不可能だ。 たぶん、今、アンタレスの立っているのは、岩のように重たい、底なしの闇の中。 何も見えない。 何も聞こえない。 声も出ない。 指一本動かせない。 助けを求めることもできない。 ミラがすぐそばにいるのもわからない。 アンタレスの手から、剣が床に滑り落ちて、ごとん、と重たい音を立てた。 その瞳から、涙が一粒、ぽろりとこぼれ落ちた。 ああ、かわいそうなアンタレス、そこはどんなに怖いだろう! 今、君を苦しめているものは何だろう! 続いてもうひと粒、あふれた涙がその頬を伝い落ちるのを見たとき、ミラは、これ以上アンタレスが苦しんでいるのを見ていられなくなった。 ミラの欲しいものは、アンタレスの優しい微笑だ。 手を差し伸べると、やれやれ、という顔をして、笑って抱き上げてくれる、あたたかい大きな腕だ。 部屋が明るすぎるとか暗すぎるとか、鎧を着るとか着ないとか、他愛無いおしゃべりをして二人で過ごす、甘い穏やかな時間だ。 ミラの命じることを何でもするけど、2度と微笑んでくれない、話しかけてもくれない、そんな操り人形が欲しいわけじゃない。 ――― アンタレスは、アンタレスのままでいて欲しい。 たとえミラを憎むようになっても! ミラは、すすり泣きながら、アンタレスを“狂気”の魔法から解放した。 石のように固くこわばっていたアンタレスの全身の筋肉が、ふっと緩んで、それからアンタレスは、崩れ落ちるようにその場に座り込み、うずくまった。 ベッドの縁をしっかりつかんで、あえぐように大きく息を吸い込んだあと、急にぶるぶる激しく震え出した。 震えながら、あたりを見回す、怯えた目。 蒼白の顔。 乱れた髪。 涙を浮かべた瞳。 喉から漏れ出す、声にならない悲鳴。 途切れ途切れの、あえぎ。 その表情は、自分自身が作り出す幻影の恐怖の中で、アンタレスがどんなに苦しんでいたか、無言で語っていた。 ミラにはほんの数分でも、アンタレスにとっては、終わりのない地獄の時間だったろう。 ミラは、本を読んだだけでちゃんと理解もしていなかった、おそろしい魔法を使ってしまったことを深く後悔した。 落ち着きなく部屋のあちこちをさまようアンタレスの視線は、完全にミラを素通りしている。 その視界の中に、もうミラは存在しない。 ようやくアンタレスの視線が止まったのは、床に落ちた剣の上だった。 いまだ震えのおさまらない手で、アンタレスが剣を拾い上げ、苦労しながら鞘におさめる。 よろよろと立ち上がったアンタレスが、戸口に向かう。 その背中に、思わず声をかけた。 「アンタレス・・・!」 すでに“電撃”効果も切れた戸にもたれかかって、ちょっと立ち止まったアンタレスが、どんな感情もこもっていない、寒々と凍てつくような声でミラに答えた。 「・・・帰れ。 2度と俺の前に現れるな」 一度もミラを振り返ることなく、アンタレスはふらふらと森を出て行った。 主のいなくなったユーカリ樹の小屋で、ミラはただ泣き崩れるしかなかった。 「・・・アンタレス、行っちゃだめだ!」
2011.08.17
コメント(3)
-
わかれみち 10
振り下ろした剣を、ミラの頭上すれすれのところで寸止めした、そのとき、突然体が動かなくなった。 びっくりして、目を開けた。 真っ暗だった。 ミラがあかりを消したのか? いや、ちがう。 これは何かの魔法だ。 目を見開いて、暗闇の向こうに意識を集中した。 青白いボールがかすかに見えていた。 剣の下から、まるで顔色をうかがうように、そろそろと逃げていく。 渾身の力を込めて、剣を振り下ろそうとした。 が、いくら力を込めようと、腕はびくとも動かなかった。 まるで、岩の中に閉じ込められたようだ。 青白いボールがそろそろと遠ざかっていって、すっかり見えなくなると、あたりは真の暗闇になった。 もう、いくら目を凝らしても何も見えない。 全身を押し包む岩のような空気が、ゆっくりと重さを増していく。 重たくて、胸に空気を吸い込む隙間がつくれない。 苦しい。 「ミラ、どこに隠れた! 早くこの魔法を解け!」 怒鳴ろうとしたが、声が出ない。 息ができない。 体にかかる重みが増していく。 このままでは、闇に押しつぶされてしまう! 「ミラ、ここから出してくれ!」 懇願しようとしたが、口も動かない。 音も、光もない世界。 体にのしかかる重圧だけが、じりじりと増していく。 そのとき、後ろでかすかな物音がした。 はっとして、振り向こうとした。 が、体は動かない。 ――― ちょろちょろと忙しく床を駆け回る小さな足音。 時おり立ち止まっては、カリカリと何かを齧る音。 ねずみがいる! 心臓が縮み上がった。 アンタレスはねずみが大嫌いだ。 昔から、近くにその気配を感じただけで背筋がそそけだった。 部屋の隅をちょろっと駆け抜けたのに気づいたりしたら、それだけで悲鳴をあげて逃げ出してしまう。 情けない。 なんでこんなものが怖いのか、自分でも腹立たしくなるが、怖いものは怖いのだからしかたがない。 この場所に住居を決めた理由も、この一帯にやつらが一匹もいないことを発見したからだ。 なのに、なぜ、いま、この、動きの取れないのっぴきならない状態の時に、現れる?! しかも、音から察するに、相手は一匹だけではないようだ。 あっちにも、こっちにも、うようよ、いるみたいだ。 長い尾を引きながら、やつらが、部屋の中を我が物顔にちょろちょろ走り回る。 ベッドの陰から、テーブルの下へ。 椅子の足もとから、鎧の中へ。 何匹も、何十匹も、足もとをちょろちょろ走り回る、その光景を思い描いただけで、冷や汗が出てきた。 「ミラ、助けてくれ! こいつらを追っ払ってくれ!」 声を限りに叫んだ。 ような気がしたが、やっぱり声は出なかった。 足もとを走り回っていたうちの一匹が、アンタレスの足を駆け上り、背中に飛びついた。 「やめてくれ!!」 たまらず泣き叫びながら、両腕を振り回した。 ような気がしたが、腕はやっぱりぴくりとも動かなかった。 肩までよじ登ってきたやつが、ふっ、ふっ、と小さく忙しい息を吐きながら、顔の周りを嗅ぎ回る。 その細い頬髯の動きまで、皮膚に感じ取れる。 いつのまにか、アンタレスの力の源、ダイダロスの剣も、手から消えていた。 それに気づいたときが、我慢の限界だった。 何も考えられなくなった。 自分でもわけのわからないことをわめきながら、ただ狂ったように泣き叫んだ。
2011.08.16
コメント(2)
-
わかれみち 9
驚愕した。 まばゆい光に耐えられなくなったのか、アンタレスはずっと目を閉じたまま。 なのに、その小刀は、正確にミラの位置をつかんでいるのだ。 どこに逃げても、小刀は必ずミラのからだのどこかにぶつかり、そのたびに、カン、と音を立て火花を散らす。 リシャーナの鎧で守られていることがわかっていても、その音から逃れられない恐怖が、徐々にミラを追いつめる。 そして、アンタレスが剣を抜いた時、ミラの恐怖は臨界点に達した。 冷たく鋭い、ただならぬ光を放つ、アンタレスの剣が、怖い! 逃げなくちゃ、と思うのに、アンタレスのベッドの後ろにぺったり座り込んだまま、腰が抜けて、どうしても立てなくなった。 アンタレスの剣が、ミラの頭上に高々と振り上げられ、脳天めがけて振り下ろされる。 すくみあがりながら、ミラは、無我夢中で呪文を唱えた。 「《ヴァイドメタヴァイドカルーラールールーケッジャードルーノワリグルー》!!!」 唱えながら、失敗した!と思った。 相手の動きを封じる“暗闇”、いや、相手は手強いアンタレスだから、もう一段階上の恐怖を加えた“重圧”をかける、つもりが、動転して、血迷って、パニクって、さらにその一段階上級の、“狂気”の呪文を唱えてしまったのだ。 “隠遁”から発展したこの一連の魔法は、高い知性を持った霊長類にだけしか効かない魔法で、 “暗闇”の魔法だけだったら、相手は真っ暗闇の中で動けなくなるだけだけれど、それに“重圧”が加わると、動けなくなった体がさらに狭い空間に押し込められてつぶされるような感覚を味わうことになる。 この恐怖によってたいていの相手は降伏させ従わせることができる、と魔法書にあったので、今、ミラはその呪文を唱えようとしたのに、あわてて唱えてしまったのは、そのひとつ先“狂気”の呪文。 これは、“重圧”の恐怖に加えて、相手の心の中から、最も恐れているものの幻を引き出し、その心を破壊して操り人形に変えてしまう、禁断の魔法だ。 もちろん恐怖の対象は人それぞれなので、その頭の中にあるものまではわからない。 が、たとえば、虫とか小動物とか猛獣とか、揺れるものとかとんがったものとか刃物とか、高いところとか狭いところとか、おばけとか魔法使いとか人間とか、その人がいちばん怖いと思うもの、どんな自制心も自尊心も一瞬のうちに吹っ飛んで悲鳴をあげて逃げ出してしまうもの、あるいはトラウマ、根源的な恐怖。 ・・・もしもそんなものが、身動きも取れない暗闇の中で、あとからあとから自分に襲いかかってくるとしたら、それはどんなにおそろしいことだろう! その恐怖から逃れるために相手の言うとおりにしようなんていう、理性すらどこかに吹っ飛んでしまうに違いない。 これはただ相手を従わせるために使うんじゃない。 相手の尊厳を踏みにじり、ずたずたに心を引き裂き、2度と立ち直れないように破壊したうえで、操り人形のように体を操る、そのための非道な魔法だ。 こんなもの、使う気はなかったのに。 魔法書によれば、この、終わりのない恐怖に耐えられる者はいない、相手はじきに正気を失って、そうしたらもうもとには戻せなくなってしまうから、もし、本当に相手を操り人形にする気がないなら、この魔法を唱えたら5分以内に解除して、恐怖から解放してやらなければならない、とあった。 でも ――― 解放したら、すぐさまアンタレスは森を出て行ってしまう。 こんなひどいことをしたミラのもとへは、もう2度と帰ってきてくれない。 ――― どうする?
2011.08.15
コメント(0)
-
わかれみち 8
こんな抵抗に遭うなんて、思ってもみなかった。 目もくらむような光の中、完全に姿を消したミラの、“炎”が、立て続けに飛んできて炸裂する。 体のどこかをかすめるたびに、焼けつくような痛みを引き起こす、容赦のない“炎”。 そして、その合い間を縫って、隙をうかがうように、じりっ、と襲いかかってくる、ゆっくりとした奇妙な攻撃の気。 こんなふうに、ただ“炎”から逃げ回っているばかりでは、いずれ疲れて動けなくなる。 ミラはそれを待っているのだろう。 なんとかしてミラをつかまえなければ、と思った。 手が使えなければ魔法も使えないはずだ。 “炎”の飛んできた方向に向かって小刀を投げる。 こんなものをいくら投げてもミラを傷つける心配はないから、“炎”の飛び出してきた位置に見当がついたら即座に、遠慮会釈なく投げつける。 たいていの場合、ミラはもう位置を変えていて、小刀はその後ろの壁にむなしく突き刺さるだけだったが、時に、逃げ遅れたミラに当たると、カン、と、明瞭な音を立て、その位置を知らせてくれた。 が、今、アンタレスにできるのはそれだけだ。 このままでは埒が明かない。 なすすべなく、“炎”と『光明』の織り成す閃光にひりひり痛む目を閉じた時、不意に、まぶたの裏の闇に、ミラの姿がはっきりと浮かび上がって見えた。 まるで、闇の中で青白く揺れ動く、ボールのようだ。 迷わず、闇の中のそのボールめがけて小刀を投げた。 カン、と、大きな、確かな音がした。 そのとき、青白いボールが、一瞬、きらりとオレンジ色に輝いた。 “炎”だ。 闇の中に、オレンジ色の光が、鮮やかな光跡を描いて飛んでくる。 これなら避けるのは簡単だ。 なんなく身をかわす。 天井近くまで舞い上がった青白いボールめがけて、小刀を投げつける。 カン、と、鋭い音。 青白いボールがまた、オレンジ色に、2回光って、テーブルの下に逃げ込んだ。 2本のオレンジ色の光跡を、余裕をもってかいくぐり、青白いボールを追ってテーブルに駆け寄る。 カップや使いかけの薬瓶や砥石やはさみなど、細々としたものが雑然と乗ったテーブルを、力まかせにひっくり返した。 ガラガラとけたたましい音を立てて床に物が散乱し、ひっくり返ったテーブルの下からあわてて転げ出した青白いボールが、今度は、部屋の隅のベッドの後ろに逃げ込んだ。 一足飛びにその後を追いながら、ダイダロスの剣を抜いた。 ベッドの向こうで、青白いボールが、ふるふると小さく震えている。 ミラは、俺を恐れている、と思った。 いや、恐れているのは、剣か? ダイダロスの剣は、リシャーナの鎧を斬れるのか? 真っ直ぐベッドに駆け上り、青白いボールめがけて、振り上げた。
2011.08.14
コメント(2)
-
わかれみち 7
レグルスなんてやつのところへ、絶対、行かせない、と思った。 バルドーラの仲間になんか、アンタレスを返さない。 ずっと、リシャーナの森にいてもらうんだ、と。 アンタレスが開けようとした戸に、“電撃”を流した。 子どもの魔法“稲妻”の、最高位の魔法。 鋭い痛みと痺れが全身に走り、一瞬の間動けなくなる。 “電撃”に触れて動きの止まったアンタレスの背中に、“眠り”を構えた。 が、呪文を唱え始めたとたん、アンタレスが、まるで、背後のミラの動きが見えたみたいに、大きく横へ跳んだ。 と同時に、ミラの“眠り”を構えた腕に、何かが飛んできて、カン、と鋭い音を立てて跳ね返った。 アンタレスが、ミラの魔法を封じようと、小刀を投げつけてきたのだ。 もちろん、ミラの全身はリシャーナの鎧で守られているから、そんなもの痛くも痒くもない。 でも、いきなり小刀を投げつけてくるなんて、ずいぶん荒っぽいことをする、と思った。 ミラの気持ちが通じないのが、悔しくて、悲しくて、そして、すごく腹が立った。 ――― こうなったら、意地でも、この家から外に出してやらない! 印を結んで、“透明”を唱えた。 再び戸口に向かおうとするアンタレスの、足もとめがけて、大きな“炎”を飛ばした。 ちょっときつい攻撃。 アンタレスが、激しい熱風にあおられて転倒する。 跳ね起きたアンタレスが、2本目の小刀を投げつけてきた。 あてずっぽうだ。 “透明”になったミラの姿は、アンタレスにはもう見えてない。 小刀は、とんでもない方向に飛んで行った。 鋭い視線を周囲に走らせるアンタレスに、もう一度、“眠り”をかけようとした。 でも、アンタレスはまた、ミラの動きが見えたように、大きく横に飛んだ。 激しく動き回るアンタレスには、どうしても、時間のかかる“眠り”がかけられない。 ちょっと悔しい。 小さく地団駄踏んで、もう一度、“炎”を飛ばした。 跳び退ってそれを避けたアンタレスの、肩の辺りめがけてさらにもうひとつ。 身をねじってそれをよけたアンタレスの背中めがけてもうひとつ。 床に伏せたアンタレスの横っ腹めがけてもうひとつ。 そして、回転しながら逃げ惑うアンタレスに、続けざまにいくつも“炎”を投げつけた。 が、しなやかな身のこなしで敏捷に動き回るアンタレスには、ひとつも命中しない。 いらいらしてきた。 ミラの執拗な“炎”攻撃を避けながら、アンタレスが、部屋の隅の暗がりに転げ込む。 と、たちまち闇に溶け込んで、アンタレスの姿が見えなくなった。 ――― 暗いところに逃げ込めば、僕が攻撃できないと思ってる。 そう思ったら腹が立ってきた。 顔をしかめて、ミラは『光明』を唱えた。 今度は、最大光量だ。 部屋の中が、いっぺんに、真昼のように明るくなった。 もう、ねずみ一匹隠れるほどの暗がりもない。 隠れ場所を失ったことを悟ったアンタレスが、悔しそうに片手で顔をかばいながら、立ち上がった。
2011.08.13
コメント(0)
-
わかれみち 6
気がつけばもう、あたりは薄暗くなり始めていた。 アンタレスは、ミラと過ごす楽しい時間の短さに驚きながら、約束どおり、『光明』のあかりを消させ、靴を手もとに引き寄せて履き始めた。 「ミラ、俺は出かけてくる。 おまえは、ここにいるか? それとも、ヴェガのところに帰るか?」 はっとしたように顔を上げた、ミラの表情が、少し険しくなった。 「どこへ行くの? まさか、君に迷宮の道案内をさせたうえ平気で見殺しにしようとした、戦士たちのところじゃないだろうね?」 アンタレスはちょっと驚いてミラの顔を見上げた。 「レグルスたちを知っていたのか? だが、レグルスは俺を見殺しにしようとしたわけじゃない。 毒針に刺されたのは俺の不注意だ」 「同じことだよ! そいつら、瀕死の君を神殿に預けっぱなしにしたまま、何もしてくれなかったじゃないか! ヴェガもだ! 僕もアルクトゥールスも、必死になって君の行方を捜していたんだよ!」 ミラの剣幕に少し戸惑いながら、アンタレスは言った。 「ミラ、おまえには感謝している。 だが、俺は今、そのレグルスにどうしても伝えなきゃならないことがあるんだ」 剣を手に立ち上がったアンタレスに、ミラが悲痛な声で叫んだ。 「行くな、アンタレス! ・・・レグルス、っていう、その戦士のところへ行ったら、君はもう森に戻って来ないつもりだろ? そいつに、バルドーラたちがよくやる忠誠の誓いとかいうものを立てて、一生、そいつの足もとにひざまずいて暮らす気なんだろ?」 戸口に向かった足が、ふと、止まった。 そうかもしれない、と思った。 リュキア軍になんか今も興味はない。 だが、レグルスは違う。 リュキア軍の戦士としてではなく、『君主の剣』を手に、リュキアの輝ける若き王として立つレグルスの姿を、アンタレスは見たい。 そのレグルスの足もとにひざまずいて、命を捧げてもいいと思う。 いや、それでこそ自分がこの世に生まれてきた甲斐がある、と思う。 ミラの言うとおり、今、レグルスのところへ行ったら、アンタレスはもう森には帰って来ないかもしれない。 森は、アンタレスにとって、いつも、人目をしのんで隠れひそむ場所だった。 今、アンタレスは確かに、レグルスという太陽の下で、堂々と、思うさま腕をふるいたいと、強く、激しく、望んでいるのだ。 それに気づいたら、逆に、心が決まった。 黙ってドアの取っ手に手をかけた。 手を触れたとたん、その取っ手が、ばちっと大きな音を立てて火花を散らした。 「痛てっ!」 思いがけない痛みと衝撃が、指先から全身を走りぬけた。 一瞬硬直して動けなくなったアンタレスに、ミラが言った。 「アンタレス、君はもうリシャーナの戦士になったんだ。 この森を守らなきゃいけないんだよ。 バルドーラの仲間になんか、絶対返さない!」 言いながら、ミラの手が動いた。 何か魔法を使おうとしているのだ。
2011.08.12
コメント(0)
-
わかれみち 5
アンタレスの額に当てたミラの指先から、ミラの力がゆっくりとアンタレスのほうに移り始めた。 アンタレスの顔の火傷を治した時とよく似た感覚。 でもこれは、“リシャーナの癒し”の魔法じゃない。 長老にしかできない“魔力授け”を、髪に挿した“猫目石のかんざし”の霊力を借りて行っているのだ。 何が起きているのかわからないのだろう、ぽかんとした顔つきのアンタレスに、ミラは笑って言った。 「アンタレス、君は今から魔法使いの仲間だよ。 僕の魔力を、君に分けてあげる。 僕は、アナルケルと戦ったおかげで、リシャーナの魔法だけじゃなくて、ジャムルビーの法力も少し使えるようになった。 ジャムルビーの法力は、リシャーナの魔法ほど荒々しくはないけど、洗練されてて効率がいいよ。 君は今、このふたつの力を同時に自分のものにするんだ。 世界最強の、リシャーナの戦士が、今誕生する。 ・・・ほら、ぽかんとしてないで、目を閉じて。 僕の手から君の体に流れ込んでいるこの力を、よく見て。 たくさんの、光の粒みたいなものが流れていくのが見えるだろ?」 「・・・ひゃあ、ほんとだ。 まるでホタルの集団脱走」 「ふざけないで。 厳粛な儀式なんだよ。 集中して、よく見てて。 まだ終わらない?」 「まだまだ。 あとからあとから、きりがないぞ。 いつまで続くんだ?」 もちろん“魔力授け”なんて、ミラにも初めての経験だが、たぶん、毎年何人もの子どもたちに魔力授けをする長老だって、こんなのは経験したことがないに違いない。 “癒し”を行ったときも驚かされたけれど、アンタレスの魔力の吸収力は、さらに荒々しくて貪欲で、まるで底なしだ。 しかも、やがてアンタレスの入れ物がいっぱいになったように、光の粒の流れ方がまばらになってきたと思ったら、今度は、光の粒が突然逆流を初めて、アンタレスからミラのほうに向かって流れ始めたのだ。 それはまるでミラのほうがリシャーナの癒しを受けているように、ぽかぽかと暖かくて気持ちが良くて、ミラはうっとりと目を閉じて、その流れに見入った。 この美しい光の流れを、ミラはいつまでも見ていたかったけれど、アンタレスのほうは、すぐに飽きてしまったみたいに言った。 「まだ終わらないのか? もういいだろ?」 確かに、このぶんでは、光は、あっちへ行ったり、こっちへ来たり、永久に流れ続けているかもしれない。 ミラは目を開け、今度はアンタレスの左手を右肩に当てさせて、言った。 「じゃあ、今度から、戦うときには必ずこうして左手を右肩に当てて、呪文《サフェールショーナモントワー》を唱えるんだよ。 リシャーナの“保護”の呪文だ。 これをするだけで、君の体はあの鎧に守られているのと同じになる。 重さは全然感じない。 練習を重ねると、この見えない鎧はどんどん強力になる。 効果も長く続くようになって、しまいには、いちいち呪文を唱えなくても24時間鎧をつけているのと同じになる。 ぐっすり眠っている時も、裸で水浴びしてる時もだよ。 便利でしょ?」 アンタレスがにやにやしながらうなずいた。 「へえぇ、それは便利。 《サフェールショーナモントワー》?」 全然信用してない。 ミラは、アンタレスがきちんと呪文を唱えたのを確認するといきなり、傍らの小テーブルの上に乗っていた小刀を取り上げてアンタレスの胸に突き立てた。 この不意打ちに、アンタレスはぎょっとしたように身をかわそうとしたが、小刀の刃はすでに、固い岩にでも突き立てたみたいに、途中からぽきんと折れてしまっていた。 アンタレスは目を丸くして、折れて床に転がった小刀の刃を見、それが今突き刺さったはずの自分の胸のあたりに触り、それからミラの顔を見た。 にやにや笑いはもう消え、真顔になっていた。 その顔に、ミラは満足して笑った。 「ね、うそじゃないでしょ? 僕がいなくても、いつでも、すぐにできるから、呪文、絶対忘れないでよ!」
2011.08.11
コメント(0)
-
わかれみち 4
アンタレスが家の中に入っても、ミラは、戸口のところで立ち止まったまま、こわごわと中を覗き込んでいるばかりで、なかなか入って来ようとしなかった。 「・・・アンタレス、家の中、暗いね。 ランプをつけて」 そうか、リシャーナは夜目が利かないんだった、と、思い出した。 ヴェガのやつも、迷宮に行くといつも、暗い、暗い、とぼやいていたっけ。 「あいにくだが、ここにはランプはない。 俺は夜目が利くからランプはいらないんだ」 「アンタレス・・・」 今にも泣き出しそうな顔で、ミラが、手探りでアンタレスの腕に触った。 本当に、暗いところが苦手らしい。 その手をつかんで部屋の中に引っ張り込み、抱きしめた。 そのまま床に腰を下ろすと、アンタレスの腕の中で、やわらかなミラの体が、小さく震えていた。 胸が高鳴って、ミラを抱きしめる手にさらに力がこもった時、ミラが顔を上げて言った。 「ねえ、あかりをつけてもいい? さっき神殿から盗んできたんだ。 ジャムルビーの法力『光明』の呪文。 あそこの壁、ランプもないのにいつもぼうっと薄明るいでしょ?」 「法力を盗む? ミラ、そんなことができるのか」 言いながら、その『光明』を唱えようとしたらしい、ミラの手を押さえ、重ねて言った。 「だが、あかりはだめだ。 外にあかりが漏れると、ここに小屋のあるのがわかってしまう」 ミラが、アンタレスの手を振りほどいて笑った。 「大丈夫だよ。 外のほうが明るいもの。 『光明』が洩れても、木漏れ日にしか見えない。 外が暗くなったら消すと、約束するから。 ねっ?」 その無邪気な笑顔を見たら、首を横に振ることはできなくなった。 「わかった。 外が明るい間だけならいい」 嬉しそうに笑って、ミラが両手を合わせ、何か呪文を唱えた。 そのとたん、あたりがふわっと明るくなった。 明るくなったといっても、小屋の外の深い葉陰と同じ程度だから、外から見えるほどではない。 うまい具合に調節できるものだ。 思わず笑みがこぼれた。 「ミラ、便利なやつだな」 声を上げて笑いながらアンタレスの膝の上から飛び降り、小屋の中をきょろきょろ見回し始めたミラが、隅に立てかけてあった古い鎧に目をとめて顔を輝かせた。 「アンタレス、鎧、持ってたんだね! かっこいい! どうして着ないの? 君があれを着たら、きっとすごくすてきなのに!」 「うん、俺もかっこいいと思って買ったけど、重くて、結局、着られなかった。 今は、鎧なんかないほうが動きやすくていい。 だから、ずっと置きっぱなしになってる」 「ふーん・・・」 ものめずらしげに鎧に触ってみていたミラが、急に、ふところから何か取り出し、髪に挿してアンタレスを振り返った。 「じゃあ、この着られない鎧のかわりに、僕が、君にリシャーナの鎧をあげる! 重さゼロ、着てるか着てないかわからない、だけどこんな鎧よりもっと頑丈な、鋼鉄の矢をも撥ね返す鎧だよ!」 ミラが髪に挿した、金色のかんざしが、猫の目のように妖しく色を変えながら、『光明』のあかりを反射してきらきら光っていた。
2011.08.10
コメント(2)
-
わかれみち 3
森の中を疾走するアンタレスは、野生の獣のようだ。 魔法が使えるわけでもないのに、リシャーナの“木隠れ”にも匹敵するスピードと軽さ。 もしこの彼がリシャーナの魔力を得たら、その力はどれほど大きくなることだろう! そう思うと、胸が高鳴った。 ミラのふところに大切にしまってある『猫目石のかんざし』を、髪に挿して魔力授けをしたら、アンタレスは、この世で最強の、リシャーナの戦士になる。 そうしたら、ミラの知っている魔法を、全部教えてやろうと思う。 嬉しくて、ひとりでに顔が緩んでしまう。 「着いたぜ、俺の家」 アンタレスの声に、ミラは、きょとんとあたりを見回した。 「・・・ここ? ここはリシャーナの泉じゃないか。 僕たちも毎日水浴びに来るところだ。 家なんかどこにもないよ?」 うなずいたアンタレスが、目を細めてまぶしい水面を見やる。 「昼間、リシャーナたちがここに水浴びに来るのは知っている。 ときどきバルドーラの猟師や茸採りのパピトも来る。 だけど俺は、昼間はずっと寝てる。 夜しか動かないから誰にも会わない」 そう言ってから、アンタレスは、少し離れたところに生えている、高いユーカリ樹のてっぺんを指差した。 「俺の家はあの木の上だ。 木の上に小屋を作ったが、葉が茂っているので下からは全然見えない」 アンタレスが近づいていく木を見上げて、ミラは思わず、あっと小さく声を上げた。 その一帯は、古くから、リシャーナの戦士の聖地と呼ばれていた。 リシャーナの戦士が住む場所だといわれている。 だから、他の生き物は一切足を踏み入れない。 特別な場所なのだ。 感動して、体が細かく震え始めた。 自覚はなくても、アンタレスはやっぱり、リシャーナの戦士だった! 昔話の通り、リシャーナの戦士は、ずっと前から、ちゃんと聖地にいたんじゃないか! アンタレスが、ミラにたずねた。 「のぼれるか?」 「だいじょうぶ、登るのは無理だけど、飛べるよ」 答えたミラに、アンタレスも笑ってうなずいた。 「そうか、飛べるのか」 アンタレスの腕から、ユーカリ樹の枝に、ふわりと飛び移った。 と、アンタレスが靴を脱いで、靴紐を口にくわえたと思ったら、ほとんど駆け上がるみたいにしてユーカリ樹を登り始めた。 すごいスピードだ。 こんな木の登り方をする生き物、見たことがない。 ミラの“木隠れ”でも、追いつくのが大変なくらいだ。 ユーカリ樹のほうも、こっそり、アンタレスの木登りを助けているみたいに見える。 ちゃんと靴を脱いで、ユーカリ樹の幹を傷つけないようにすばやく優しく登るアンタレスに、ユーカリ樹も愛情で答えているのだ。 この光景を見ると、ミラはまた嬉しくなった。 アンタレスは、だれにも教わらないのにちゃんと、森の木々とのつきあいかたを心得ている。
2011.08.09
コメント(0)
-

わかれみち 2
正直、ミラを自分の家に連れて行くのは気が進まなかった。 アンタレスの、ミラに対する思いは複雑だ。 万難排してアンタレスを救出してくれたことは、もちろん、言葉につくせぬほどありがたいことだし、妖精のように愛らしく、一途な思いをぶつけてくるミラを、愛しく思う気持ちもある。 腕に、胸に、首に、ミラのあたたかい体温を感じているのは夢の続きのように心地よくて、このままいつまでもミラを放したくない気持ちになったり、あるいはまた、愛しさのあまり、頭からばくりとかじりついて食べてしまいたい気持ちになったりする。 ミラの、小鳥のようなおしゃべり、めまぐるしく色を変える神秘的な瞳、やわらかい髪、すべすべした肌、果実のような甘い香り・・・つい惹き込まれて、荒々しい情熱に自らを制しきれなくなりそうな気がしたりする。 が、それでいて同時に、ミラの中に眠る底知れぬ力は、ひっそりと静やかに、アンタレスを恐怖させる。 ミラがヴェガの後を追って城跡に現れ、“炎”を飛ばしてアンタレスを驚愕させた、あのときと同じ質の恐怖だ。 相手にほとんど死を直視させんばかりの強烈な殺気。 そして、それとはうらはらに、飛んできたのは、ふざけたようなちっぽけな“炎”。 ミラは、天下無敵のこのアンタレスに向かって、明らかな手心を加えやがったのだ。 それは、これまで経験したことのない、圧倒的な力の差だった。 えたいのしれない力に対する恐怖は、今も大きくアンタレスを支配している。 いや、ミラが、単身神殿に乗り込んで手だれのジャムルビー神官を倒したことを知った今、その恐怖はますます重く、不気味に、アンタレスにのしかかっている。 ふたつの相反する思いに、アンタレスは戸惑っていた。 が、アンタレスが、今、家に帰るのをためらう一番の理由は、ミラではない。 時間が惜しいのだ。 ――― 早くレグルスに知らせなければ。 その思いに、気がはやる。 手にした者が王になるという『君主の剣』と、それを守るグリュプス。 そこに至る道にたちはだかる鏡と、それを割るハンマー。 『君主の剣』が正しく『君主の剣』であるための、霊石『慈悲の涙』と、その霊石の力を制御するための香炉。 レグルスの手は、もう『君主の剣』に届こうとしているのだ。 それを早くレグルスに教えたい。 が、さっきからしきりに胸騒ぎがしてならない。 『新王』レグルスが、のっぴきならない危機に直面しているような気がして、じっとしていられないのだ。 時間が惜しい。 それで、ひとまずミラを家に連れて行くことにした。 家を知ったら、満足してくれると思ったからだ。 家で、ミラが、アンタレスの出かけるのを笑って見送り、帰りを待っていてくれる。 心のどこかに、そんな、淡い期待もあった。
2011.08.08
コメント(0)
-
わかれみち
アンタレスが、微笑んでくれる。 他の誰でもなく、ミラに向かって、ミラひとりだけに向かって、優しい微笑を投げかけてくれる。 その白い頬には、赤みが差し、瞳は生き生きと、ルビーのように輝いている。 あの、獣のように強靭で美しいアンタレスが、今、再びミラのもとへ帰ってきてくれた。 幸せだった。 軽々と抱き上げてくれたアンタレスの腕から、ミラは、いつまでも降りたくなくて、その首にしっかりとしがみついて離れなかった。 アンタレスも、何も言わなかった。 ただ、優しく微笑んで、ミラを抱いたまま、歩き出した。 リュキア神殿の広々とした廊下を、闇色の長い髪をなびかせて傲然と行くアンタレスに、すれ違うジャムルビー神官たちがぎょっとしたように立ちすくむ。 神官たちは、まだ誰も、この神殿の頂点に君臨するアナルケル大僧正の死を知らない。 この神殿のもっとも深いところで、ひそかに、リシャーナの炎が燃え広がりつつあることも知らない。 数時間後にはその熱が神殿を覆いつくし、やがて一気に巨大な火柱が上がるころには、千年の歴史と威容を誇るこの美しい建物も、ぐにゃぐにゃに溶けて焼け爛れ、あっという間に崩れ落ちてしまうことだろう。 そうとも知らず今日で最後の鐘の音が、正午を告げて明るく閑々とふりそそぐ中、神殿から森に入ったアンタレスが、狩場を出たところで立ち止まり、腕に抱いていたミラを下ろそうとした。 「ミラ、おまえのおかげで一命を取りとめた。 救援を感謝する。 ・・・では、家に帰って少し休め。 ここからなら、もうひとりで帰れるだろう?」 降りようとしないミラに、アンタレスが苦笑して言った。 「家まで送れというのか? ・・・ヴェガに怒られそうだから嫌だなあ」 ミラは、アンタレスの首にしっかりしがみついたまま首を横に振った。 「ヴェガの家になんか帰らないよ! あいつは君を目のかたきにしてるもん。 デネブの家にも帰りたくない。 あいつは狩りをする種族の仲間だもん。 ・・・アンタレス、僕は君の家に行く。 連れて行ってよ」 一瞬、びっくりしたように押し黙ったアンタレスが、またミラを抱いて歩き始めた。 「・・・どうして俺の家になんか来たいんだ。 俺が怖くないのか? リシャーナ汁にして食っちまうかもしれないぞ」 がおー、と歯をむき出して見せたアンタレスに、ミラは笑って答えた。 「君はそんなことしないよ。 僕にはわかる。 君はバルドーラ族じゃないもの。 狩りもしなければ肉も食わない。 君はいつも花の匂いがする。 僕たちと同じ匂いだ。 住まいも、この森のどこかでしょ? だから、君の家に行ってみたい」 ちょっと傷ついたみたいに肩をすくめたアンタレスが、急に、ミラをつかまえた手に力を込めた。 「よし、じゃ、連れて行ってやる。 走るぞ、ミラ、振り落とされるなよ!」 だっ、と駆け出したアンタレスの首に、ミラは、きゃあ、とはしゃいだ悲鳴を上げてしがみついた。
2011.08.07
コメント(2)
-
ゴルギアスの塔 4
「待て、レグルス! どこへ行くんだ!」 あわててレグルスの後を追って駆け出したベテルギウスの肩越しに、レグルスが一目散に目指しているものが見えた。 通路の突き当りに、開けっ放しになった扉がひとつ。 扉の内部は暗くてよく見えないが、その入り口の、よく目立つところに、小型の楯と錫杖が立てかけてあるのだ。 神兵たちがよく手にしている武器だ。 レグルスはそこに向かっていた。 レグルスを追って走りながら、ベテルギウスがちょっとリゲルを振り返って言った。 「エリダヌスの錫杖と楯だ! 我々に居場所を知らせるために、エリダヌスが置いて行ったのだろう。 エリダヌスは、あの扉の向こうに連れ込まれたのだ。 追うぞ!」 アルタイルも、勢いづいてその後に続く。 「了解っ! 少尉、位置から考えて、あの扉は見張りの塔の入り口ですね。 だったら、彼らにもう逃げ場はない。 追いつめたも同然だ!」 「逃げ場のない、見張りの塔・・・?」 急に不安になって、リゲルは、資料室で見つけた古い図面を頭に思い浮かべた。 ――― 通常の地上路とは別に、リュキア城内に張り巡らされた、地下通路と空中回廊 ――― 王宮や神殿や戦士宿舎など、城内の主要な建物の内部と連結するその2つの通路は、そこに面したすべての出入り口に大きな鍵のマークが書き込まれていて、その鍵を全部閉めきった通常の状態では、たとえ外敵の侵入があっても、鍵がなくてはどこにも入れないことを示していた。 たった一つ、鍵のマークの書かれていなかったのが、見張り塔への出入り口だ。 そこに、鍵のかわりに書いてあったのが、塔に向かう太い矢印。 そして、その逆、塔から通路への矢印には、はっきりとした打ち消し線が描かれていた。 あれは、どういう意味だろう。 あの矢印は、入ったら出て来られない、一方通行を表すもの? まさか、あの塔には、内部連絡通路に侵入した敵を追いこむ、捕獲器みたいな役割が・・・? わざわざ扉が開け放してあるのは、獲物を誘い込むためか? リゲルは真っ青になって、通路の奥に駆け込んでいく皆の背中に声をかけた。 「止まれ! 罠だ! その扉の向こうに入っちゃだめだ!」 アルタイルがびっくりしたように急停止して振り返った。 その前を行くベテルギウスも不審げに足を止めた。 が、先頭のレグルスは、真っ直ぐ扉の向こうへと駆け込んで行った後だった。 ギギィ・・・と重たい音を立てて、レグルスを飲み込んだ扉が、ばたん、と閉まった。
2011.08.06
コメント(0)
-

ゴルギアスの塔 3
食料庫に入って、床を見るとリゲルは、やっぱり、とうなずき、レグルスを振り返った。 「ほら、軍曹、床に四角い穴が開いているように見えるでしょう? あの部分、床が沈んで出現する穴なんです。 あそこの床には普段から干し肉や粉類が山のように積み上げられていますから、誰もその下の床が出入り口だなんて思わない。 でも、あんなふうに、積み上げられた荷物ごと、床が沈んで、地下通路への出入り口が現れる仕掛けなんです。 だけど、開けっ放しで行っちゃったのは、なぜかなあ。 まるで、追って来いと言わんばかりだが・・・」 穴の底に積み上げられた形になった干し肉の山の上に飛び降りると、料理人たちが、青くなって穴を覗き込んだ。 「リゲルさま! 行くんですか!?」 「大丈夫?! あぶなくないの?」 「止めといたほうがいいんじゃ・・・」 心配顔の料理人たちに、リゲルは笑って答えた。 「みんな、僕たちが戻ってくるまで、この扉は、このまま、開けっ放しの状態にしておいてくれよ。 さっきも言ったとおり、僕たちは誰もこの扉の鍵を持っていない。 閉め出されたら、僕たちは死ぬまでこの地下通路の中をさまよう羽目になってしまう。 絶対閉めるなよ!」 地下通路は、照明らしきものもないのに、壁全体が発光しているようにほんのり明るかった。 リゲルを先頭に、その後ろにベテルギウスとレグルス、最後尾にアルタイル、と一列に並んで狭い通路を進んで行くと、やがて、まっすぐ東に伸びる通路が北と南の2方向に分かれる、T字路に出た。 分かれ道で足を止めて、リゲルは、レグルスを振り返った。 「このあたりはちょうど、訓練場の通用門の真下あたりになると思います。 通路は、北は神殿方面へ、南は競技場方面へ向かって伸びています。 神官らは、神殿方面へ行くならば、門から地上を直行したほうが早かったわけですから、ここは南へ曲がったものと推測します」 通路を南に、しばらく歩いていくと、やがて左手に、小さな扉がひとつ見えてきた。 リゲルはその扉の取っ手をちょっと引っ張ってみてから、レグルスを振り返って告げた。 「この扉の向こうは、競技場警備兵舎の武器倉庫です。 やはり鍵が閉まってますね。 神官らはもっと先まで行ったんでしょう。 図面によればこの南にあるのは、城壁内回廊への入り口階段、そして、そのさらに先が見張り塔だ。 さて、どっちへ行ったのかなあ・・・」 これより南には、リゲルもアルタイルも一度も行ったことがない。 薄暗い未知の通路に視線を向けたとき、リゲルの、全身の毛がそそけ立った。 いつのまにか隊列を離れたレグルスが、その未知の通路を猛スピードで、奥に向かって突っ走って行くのだ。 「エリダヌス!」 レグルスの咆哮が、通路にこだました。
2011.08.05
コメント(2)
-
ゴルギアスの塔 2
一瞬、顔を見合わせた料理人たちが、次の瞬間、いっせいに口を開いてしゃべり始めた。 「来ました来ました! 昼のゴミを出そうとして勝手口を開けたら、いきなり、神官が2人も、ずかずか入って来るんだもん、俺びっくりしちゃった!」 「アタシもびっくりしたわよ! 神官がこんなところに何の用事よ、ってさ」 「俺ら昼の大仕事が終わってほっと一息つこうとしてたところだったでしょ、そこに神さまのありがたいお話なんか始められたらよけい疲れると思って、お帰り願おうとしたら」 「布教じゃない、って言うんだよな。 ちょっと通らせてもらうだけですから気にしないで、とか言って、どんどん奥に行っちまう」 「だめも止まれもないのよ。 まるで自分ちみたいにさっさと入り込んで食料庫の中へ」 「食料庫ですぜ! 俺らみんなびっくりして、丸々1分もの間、開いた口がふさがらなかったよなあ」 「それから料理長が、食料庫の中に声かけて」 「もしもし、神官さま、どうなさったんですか、って、おそるおそる戸を開けたら」 「誰もいねえのよ! な? な?」 「そうなんだよ! 今確かに神官が2人入って行ったのに、煙のように消えちゃった!」 「もう、気味悪くてさ」 「あれから誰も食料庫のそばに近づかないんですよ」 「俺なんか、足りなくなった小麦粉、その食料庫に取りに入るのが嫌で、わざわざ北辰館まで借りに行っちゃった」 「アタシ、以前から思ってたんだけど、その食料庫、なんか気味悪いのよね」 「そうそう、ときどき、だれもいない夜中の間に、誰か入り込んだ形跡があったりするんだよな」 「そういえば俺も、ここの床で、俺たち料理人の靴じゃない足跡、何度も見た!」 「夜の夜中に、食料庫の中から気味の悪い話し声が聞こえてきたっていう話も聞いたことがありますよ」 「朝出勤して来たら、食料庫の床に、朝飯用のオカズの食い散らかしが落ちてたことも!」 「ねえねえ、リゲルさま、この食料庫、いったいどうなってるんです?」 「俺ら、気持ち悪くて我慢できねえから、どうせあんまり使ってない倉庫だし、取り壊してもらうように総務課に願い出ようかって話し合ってたところだったんですよ」 よしよし、わかったから静かに、と、リゲルは片手でみんなを制して言った。 「レグルス軍曹、それから料理人の皆も聞いてください。 この厨房の倉庫は、本当は倉庫じゃなくて、地下通路への入り口なんです。 その地下通路がどこに続いているのか、僕とアルタイルは、この南天舎と競技場の警備兵舎がつながっているところまでは確かめたんですけど、それ以上のことは調べられませんでした。 なぜならその鍵を持っているのが、アナルケル少佐おひとりだけで、合鍵がなかったからです。 そこで、やむなく、北辰館の軍資料室に忍び込んで、この訓練場の古い図面を探し出して調べてみますと、その地下通路、確かに古図面に書き込まれていて、この国の周りを囲む城壁の中に続いていることがわかりました。 その昔、リュキア城の城壁内部は空洞になっていて人が歩くことができた、という伝説は、本当だったんです。 当時、城壁内通路には窓がたくさんあって、美しい王宮や庭園を見下ろしながらぐるりと城を一周できる、空中回廊になっていたようです。 回廊の先にはさらに連絡路が延びて、大城門の外の、見張りの塔まで続いていることもわかりました。 今はすべての窓は塗りつぶされ、空中回廊も取り壊されてしまいましたが、地下通路のほうはきっと今も、すべて当時のままで残っているはずです。 2人の神官は、その地下通路を通って、どこかに行ったのだと思います。 レグルス軍曹、あとを追いましょう!」
2011.08.04
コメント(1)
-
ゴルギアスの塔
「レグルス軍曹! 今日はこちらでご夕食ですか! やや、ベテルギウス少尉もご一緒ですか? リゲルも? わぁ、僕もご一緒してもいいでしょうか?」 南天舎の食堂に入っていくと、今から夕食をとろうとしていたらしいアルタイルが、目ざとくレグルスを見つけて飛んできた。 リゲルは急いでそのアルタイルを制し、早口で告げた。 「アルタイル、緊急事態だ。 軍に派遣されていた布教師が謎の神官に連れ去られた模様。 南天舎の勝手口に入って行く神官2名を、門番が目撃していた」 アルタイルの顔にも、さっと緊張の色が走る。 「南天舎の勝手口、というと・・・!」 食堂の、厨房のほうを指差したアルタイルに、リゲルは大きくうなずいて答えた。 「うん、それしか考えられない。 だが、門番の口ぶりでは、布教師を連れ去った神官は、アナルケル少佐ではなく、どうも、軍に所属していない普通の神官らしいんだ。 あの鍵を持っているのは、アナルケル少佐だけのはずだが・・・」 話しながら厨房に向かって歩き出した2人に、レグルスがいらだたしげにたずねた。 「リゲル、2人で何の話をしている? エリダヌスがこの食堂に連れ込まれたとでも? なぜ食堂なのか? その根拠は?」 厨房の扉を押し開けながら、リゲルは、レグルスを振り返って答えた。 「私が説明するよりも、ご覧になればレグルス軍曹にもすぐにご納得いただけると思います。 アルタイルと私が偶然、この奥の食料倉庫で発見したものを」 ちょっと考えて、レグルスが言った。 「そういえば、いつだったかおまえたちは、夜中、腹が減って、南天舎の食料倉庫に忍び込んで、盗み食いをしたときに、何かを見つけた、というような話をしていたような気がするな。 あの時おまえは、何を見つけたと言ったっけ?」 「そうそう、あのときは、マルシリオのおしゃべりに話の腰を折られて、全部お話できなかったのでしたね。 これからそれをお話しします」 厨房に入ると、リゲルは、夕食を作り終えて一休みしていたパピトの料理人たちに声をかけた。 「皆、そのままでいいからちょっと話を聞いてくれ。 実は今日の昼過ぎ、神官が2名南天舎に入るところが目撃されたのだが、その神官たち、ここに入って来なかったか? この厨房の奥の、食料倉庫に。 見かけた者はいないか?」 「食料倉庫に・・・?」 リゲルの後ろで、レグルスとベテルギウスが、あっけに取られたように顔を見合わせた。
2011.08.03
コメント(0)
-
続々 アンタレスの夢 9
俺は死んだのかな、とアンタレスは考えた。 なんだか幸福だった。 ふわふわの毛布に包まって、まどろんでいるように心地よかった。 遥か遠い遠い昔の、淡いミルクの匂いにも似た思い出。 深い安堵と充足感。 死ぬ、って、こんなに気持ちのいいものなのか? アンタレスの右手を、あたたかい、やわらかいものが、優しく包み込んでいる。 その右手から、熱い、力強い何かが、体の中に流れ込んでくる感覚がある。 この感じは、前にも経験したことがある、と思った。 あれはなんだったろう、と、アンタレスは、その心地よさに身をまかせ、目を閉じたままうっとりと考えた。 そうだ、思い出したぞ。 ミラだ。 ミラが、火傷の傷を治してくれた時、あのときと同じ感覚だ。 ふと気がつくと、横たわった胸の上にも、あたたかな、心地よい、重みのあるものが乗っていた。 生暖かいしずくが、アンタレスの胸をぬらして、えりもとを伝って落ちていく。 それが何なのか、目を開けなくてももうわかっていた。 ミラだ。 ミラが、アンタレスの右手を握りしめ、胸に顔をうずめて、泣いているのだ。 蘇ったアンタレスのために。 ――― 静かに目を開けた。 そこはリュキア神殿の地下室だった。 広い地下室のあちこちで、ちろちろと小さな炎が上がっていた。 激しい争いの気の、残滓。 血の匂い。 いくつもの炎。 アンタレスを救うために、ミラが、たった一人、ここで命がけで戦ったことを悟った。 そして、勝利したことも。 顔の下に、ミラの、さらさらした緑色の髪があった。 左手を動かして、その髪にそっと触れた。 はっと息を飲んで、アンタレスの顔を見上げたミラの、透き通った大きな緑色の瞳から、また、新しい涙がぽろぽろとこぼれ出した。 起き上がって、ミラを抱き上げた。 ミラが、安堵に体を震わせながら、両手を伸ばしてアンタレスの首にしがみついてきた。 ミラの髪は、乾いた草の匂いがした。
2011.08.02
コメント(4)
-

続々 アンタレスの夢 8
闇のどこかで、さっきから、甲高く早口で聞き取りにくい、耳障りな声がいくつも響いていた。 「・・・えっ! 『夢幻の香炉』をですか? アナルケルさま」 「でもあれは、生きている者に対して使うものではないことが判明した、と、この前おっしゃっていたではありませんか」 「生きているものに対して使うと、その心を壊してしまうと。 ・・・それを、この“眠り人”に使う? なぜです?」 それに答えたのは、今の甲高い声とは違う、低い、くぐもった、不気味な声だ。 「『夢幻の香炉』は、君主が、『君主の剣』に、『王妃の宝石箱』から取り出した『慈悲の涙』をはめこむ際、荒れ狂うその石の霊力を鎮めるために用いるものでした。 この香炉を焚いて、石の力を封じておかないと、『慈悲の涙』は『君主の剣』におさまる前に、君主の体の中に入ってその命を奪ってしまうのです。 あの香炉は、人ではなく、石に働きかける香炉だった・・・ならば、この眠れる黒豹の体のどこかに隠された『血の石』も、あるいは、香炉の力に引き寄せられて自ら姿を現すという可能性もあるということです」 甲高い声が再び、ぺちゃくちゃと何事かしゃべり始めたとき、低い声の持ち主が、しっ、と鋭くそれを制した。 「『死体守り』たちよ、静かに。 神殿内に、何か不穏な気配が、侵入してきたようです。 ・・・あるいは、ゴルギアスの塔の最上階に納めた『夢幻の香炉』、取りに行くまでもないかもしれませんよ」 香炉・・・どこかで聞いたような言葉だ、と、アンタレスは深い眠りの中で考えた。 レグルスが、あの、輝くような笑顔をアンタレスに向けて、からからと小気味よさそうに笑っていた。 「コンロじゃない、香炉だよ、アンタレス。 いい匂いのする香を焚く、小さな器のことだ」 まだ若いレグルスには、軍の権威を知らずふりかざすような面があり、その高飛車な物言いは、いつもアンタレスの反発を誘って言い争いになったが、そのいっぽうでアンタレスは、レグルスとの口合戦を、楽しんでもいた。 すぐに熱くなって、怒ったり、喜んだり、恥じたり、傷ついたり、そんな感情を、ストレートに顔に表すレグルスは、好ましかった。 これまで誰にも感じたことのない親近感を覚えた。 同時に、レグルスの、高邁な使命感、一点の曇りもない潔癖さには、深い敬意を抱かずにはいられなかった。 レグルスはこの明るい笑顔のまま、思い描く未来に向かって、ひたすら前進させてやらなければならない、と思った。 たとえ今、どんな犠牲を払っても。 だから、レグルスが開かずの扉の鍵を手に入れ、どうしてもその扉を開けると頑張って譲らなかった時、アンタレスは、罠が仕掛けてあるかもしれないその扉を、レグルスに代わって開けることを即座に決めた。 それでも、アンタレスとしては、できるだけ注意深く調べてから、鍵を開けたつもりだったのだが、やはり、鍵開けのプロ、アルクトゥールスの腕には遠く及ばなかったようだ。 指先にちくりとトゲが刺さったのを感じたとき、毒針にやられた、と思った。 だが後悔はなかった。 ただ、毒針に刺されたのがレグルスでなくてよかった、と、心から思った。 突然、頭の中で、かちりと音を立ててパズルのピースがはまったような気がしたのは、レグルスの手にしたハンマーを見たときだった。 ――― がしゃん、と、澄んだ大きな音を響かせて、何か、大きな、光るものが、粉々に砕け散るヴィジョン ――― そうだ、レグルス、そのハンマーで、叩き壊せ! が、それを伝える前に、アンタレスは果てのない暗闇に落ちて行った。
2011.08.01
コメント(2)
全30件 (30件中 1-30件目)
1










