2016年07月の記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-

夏のご挨拶
暑さに負けずに頑張る 我が身と全ての方へ向日葵のパワーが届くことを願いつつ・・・iPhoneの壁紙も・・・大賀の郷の向日葵づくしです(o^^o)
2016.07.31
コメント(12)
-

今朝の富士
↑岡村公園から見た 今朝の富士2016.7.30 am.6:25・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・我が家の花壇の花たち↑↓トレニア↑サルビア コクネシア↑ 多分…鹿の子ユリかと…遅かった関東地方もようやく梅雨が明けました。今朝は久し振りに、富士山や丹沢山系もクッキリとした姿を見せてくれました。梅雨が明けた途端、昨日今日は、「猛暑」というオマケ付きの真っ青な青空が広がっています。もう一つオマケは、凄まじいばかりの蝉の大合唱です(≧∇≦)今年の花壇は、無駄な抵抗をやめて実生のサルビアコクネシアをセンターに、トレニアを周囲に植えてみました。たちまち地面を覆うくらい繁り、雑草取りの心配もいらず、結果は大正解!暑さにもめげず、まるで中に植えた百合を守るかのように咲き誇っています。
2016.07.30
コメント(4)
-
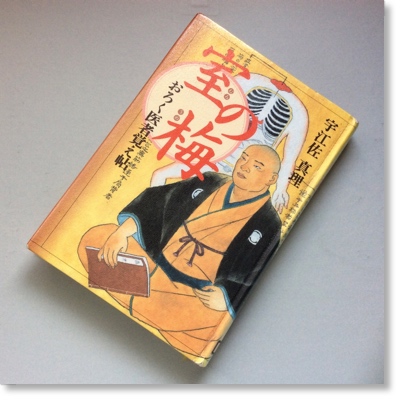
室の梅・宇江佐真理
☆室の梅(おろく医者覚え帖)・宇江佐真理・1998年8月20日 第1刷発行・発行所:講談社♣︎主な登場人物・美馬正哲=検屍役(人は「おろく医者」と呼ぶ) 1774年4月、江戸八丁堀の町医者、 美馬洞哲の三男として生まれる。36才。・お杏=産婆、正哲の女房・美馬玄哲=正哲の父、町医者。♧目次1.おろく医者2.おろく早見帖3.山くじら4.室の梅*注.おろくとは?「南無阿弥陀仏」の6文字から来ているが、市井の人は「死人」の意味に使っていた。・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本で最初に腑分けが行われたのは宝暦4年(1754)閏2月4日のことである。若狭小浜藩の藩医小杉玄適は、藩主の許しを得て初の腑分けを見学した。玄適の師、山脇東洋は、この時の玄適の話を元に『蔵志(ぞうし)』という観察記録を出版した。玄適の同僚、杉田玄白は機会があれば腑分けを観臓(見学)したいと望んでいた。だが、江戸にいた玄白にようやく機会が巡ってきたのは17年後(1771年)であった。小塚っ原で仕置された刑死体を使っての腑分けだった。見学する玄白の懐にあったのは蘭書『ターヘル・アナトミア』であったが、この時の玄白はオランダ語を一語も理解できず、掲載されている内臓の図だけが彼の手引きだった。それは一つの間違いもなく死人の内臓と一致した。これ以後、玄白は4人の仲間と共に「ターヘル・アナトミア」の翻訳に着手、刊行されたのは3年後だった。この年、江戸八丁堀の町医者、美馬家の三男として正哲は生まれた。長男、玄哲は姫路藩酒井家の藩医、次男、良哲は松前藩松前家お出入りの医者として勤めに従事していた。だが正哲だけは違い、若い頃医者の修行のために長崎に遊学したにもかかわらず、江戸に戻ってからは八丁堀の役人と組んで死人の検屍ばかりしていた。医者には違いないのだが、彼は一度も人の脈を取ったり、投薬をしたことがなかった。人は、彼をいつの頃からか「おろく医者(注*)」と呼んだ。お杏は、父親は行方知れずとなり母親がお杏を置いて再婚したあと、産婆をしていた祖母に育てられた。だが、その祖母はお杏が16才の時に急死。祖母の最後を世話した洞哲はお杏の身を案じ、正哲と一緒にならないかと勧め二人は結婚した。正哲のお役目は検屍役とはいえ、決して実入りの良い商売とはいえず、所帯を持ってからは産婆をしている妻のお杏の稼ぎを当てにしているところがあった。(町奉行所に「おろく医者」と称する検屍役の記述はなく、美馬正哲の存在は同心が抱える小者の扱いと同等のものになる)遡ること5年、紀伊の国の医者、華岡青洲は世界最初とも言うべき、麻酔剤による乳癌摘出手術をおえていた。その詳しい記述書を目にしていた正哲は、お杏の元に「おろく早見帖」を残し、遅くとも一月で帰ると言い置いて紀伊の国の華岡青洲の元へ旅立って行った。三月後、ようやく帰って来た正哲は「花岡先生がなかなか放してくれなくてな、美馬先生、美馬先生とうるせぇくらいだったのよ。おれな、麻沸散(麻酔剤)を使って実際に手術もしてきたぜ・・・」と得意そうに言った。さりとて、その後も正哲は出世を望む訳でもなく、正哲とお杏の暮らしは三月前と何も変わらない日々が続く・・・。おろく医者・美馬正哲と産婆・お杏。人の生と死に立ち会う夫婦の目を通して描かれた捕物帖。
2016.07.30
コメント(0)
-

上大岡・大賀の郷のひまわり畑 2016
☆ 上大岡・大賀の郷のひまわり畑 ☆撮影:2016.7.28ひまわりフェア開催期間 2016.7.21(木)~31(日)↑上大岡駅からの案内図今年は雨と低温が続いたため向日葵の開花が遅くて心配しましたが、ようやく、ほぼ咲き揃いました。このひまわり畑は、上大岡駅から徒歩で7~10分位、住宅地の真ん中にあります。期間限定のため、残念ながら今月一杯で終了します。興味のある方はお早めに・・・。☆下記の上大岡方面行きバスの場合 上3(汐見台循環)、上7(笹堀・泉谷循環)、133系統(上大岡行き) 64系統(港南台行き) 上大岡駅の一つ手前のバス停「千保(せんぼ)」下車、直進。 地図↑の中の、ファミリーマートと美容院のT字路を左折します。 ( 所要時間:3~4分)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆ 追記「大賀の郷」とは? 以前、気になって調べてみました。・・・古くは久良岐郡(くらきぐん)上大岡村といい、明治22年の市町村制施行の際、久保村、最戸村、別所村、中里村、弘明寺村、下大岡村、蒔田村、堀ノ内村、引越村、井土ケ谷村、永田村と合併して大岡川村となり、昭和2年、横浜市に編入して上大岡町となりました。古くは「大賀(おおが)郷」といい、これが「大岡」に転訛(てんか)したものでしょうか。・・・・・。(横浜市港南区の「町名の由来」参照)
2016.07.28
コメント(6)
-

食虫植物展・フラワーセンター大船植物園
☆ フラワーセンター大船植物園・3 ☆食虫植物展 ( 第2展示場 )うつぼかづらの仲間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・サラセニアの仲間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・モウセンゴケの仲間↑アデレー↑イトバモウセンゴケ↑ヤツマタモウセンゴケ ↑ヨツマタモウセンゴケ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ハエトリソウ第2展示場では、フラワーセンター大船植物園で栽培されている「食虫植物」が展示されていました。小学生の自由研究用に、虫を捕まえる仕組みも説明書きも添えられていました。( 入園口付近 )風船とうわた「おまけ」です。「風船とうわた」って、こんな花だったのですね!初めて知りました
2016.07.27
コメント(4)
-

百日紅&向日葵・フラワーセンター大船植物園
☆ フラワーセンター大船植物園・2 ☆( 百日紅園 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(芝生広場付近 )↑向日葵・バレンタイン↑モネの向日葵↑フロリスタン↑レモンエクレア↑マチスの向日葵↑ゴッホの向日葵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・↑ナツズイセン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・↑花トンネル今年もオキナワスズメウリなど、ヘチマや瓜尽くしでした。フラワーセンター大船植物園
2016.07.25
コメント(4)
-
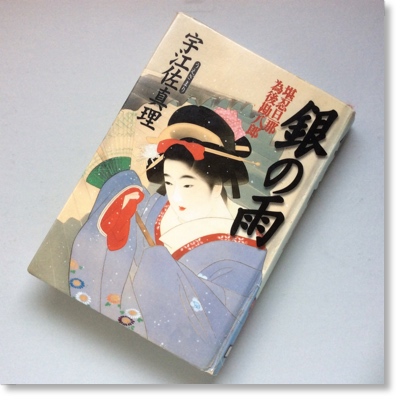
銀の雨・宇江佐真理
☆銀の雨(堪忍旦那 為後勘八郎)・宇江佐真理・発行所:幻冬舎・1998年4月15日 第1刷発行♣︎主な登場人物・為後勘八郎(ためご かんぱちろう) 北町奉行所定町廻り同心、36才。妻、雪江。 市中の人々から堪忍旦那と呼ばれている。・為後小夜=勘八郎の一人娘、17才。・岡部主水(もんど)=北町奉行所臨時廻り同心。・岡部主馬(しゅめ)=同心 岡部主水の嫡男で文武に優れた若者。18才。この小説は、「江戸北町奉行所定町廻り同心(じょうまちまわりどうしん)為後勘八郎は、市中の人々から「堪忍旦那」と呼ばれていた。下手人に対して寛容な姿勢を見せるからだろう・・・・・・・」という書き出しで始まる。勘八郎は、一人娘の小夜に、いずれ然るべき婿養子を迎えて跡を継がせるつもりであった。市井の人々には勘八郎の人気は高かったが、若い同心の中には面と向かって異を唱える者もいた。同じ北町奉行所の臨時廻り同心の嫡男、岡部主馬もその1人であった。主馬は文武に優れた若者で、彼の言うことは筋道が通っていて決して間違いがないのだが、その若さゆえの潔癖性が、勘八郎にとってはやり難いこと夥しいのであった。 主馬は岡部家の嫡男、小夜はいずれ婿を迎え、為後家を継ぐ身・・・。そんなお家の事情があるにもかかわらず、あろうことか小夜は密かに主馬を慕っていた。この小説は、「その角を曲がって」「犬嫌い」「魚棄てる女」「松風」「銀の雨」の五つの短編集の形をとっています。夫々の事件と、そこに登場する様々な人々を絡めて、小夜と主馬の恋の紆余曲折を描き、最後の「銀の雨」で完結する物語。勘八郎は定(町)廻り同心、主馬の父、岡部主水は臨時廻り同心・・・。違いが気になって調べてみました。☆同心とは?Wikipediaによりますと、「当初は、定廻り同心だけであったが、のちに、臨時廻り同心、隠密同心が加わり、三廻り同心と呼ばれた。人数は、北町奉行所、南町奉行、夫々に、定廻り同心6名、臨時廻り同心6名、隠密同心2名。合計28名。臨時廻りには定廻りを長年勤めた者が就き、定廻りの補佐・指導が主な役目である。隠密廻りは他の三廻とは違って変装して江戸市中を廻り、そこで集めた町の風説を町奉行に報告するなどの諜報活動を行った」のだそうです。上記は、Wikipedia 「三廻り」を参考、要約させて頂きました。
2016.07.24
コメント(0)
-

レンゲショウマ&ヤマユリ・フラワーセンター大船植物園
☆ フラワーセンター大船植物園・1 ☆( もみじ山付近 )↑レンゲショウマ・キンポウゲ科立て札には「日本特産の植物です。蓮華(=ハスの花)に似た花をうつむいて咲かせます」と書いてありました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・↑ヤマユリやカノコユリに混じって純白のユリが咲いていました。↓↑鹿の子百合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・↑純白花たまあじさい( 入園口〜花の築山付近 )↑天竺斑蓮(てんじくまだらはす)↑明美紅(めいびこう)↑紅翼(こうよく)↑千弁連(せんべんれん)花弁が多く、開きにくいため、花びらを折り返してあるそうです。↑友誼牡丹(ゆうぎぼたん)八重咲きで、まるで牡丹の花のようです。↑蓮池のハス↑クレオメ↑女郎花と白い花魁草↑ノリウツギ☆ つつじ しゃくなげ園 ☆↑ヤマユリこのところ、涼しいのを通り越して朝晩は肌寒い日が続いています。今日は久し振りに晴れたので、フラワーセンター大船植物園へ行ってきました。嬉しいことに、一度見たいと思っていた「レンゲショウマ」も見ることが出来ました*\(^o^)/*。今日、明日は「ハスの花の早朝開園日」だからでしょうか、入園口付近は珍しいハスの鉢がたくさん並んでいました。色とりどりの百日紅や向日葵のほか、つつじ 石楠花園のヤマユリが見頃でした。
2016.07.23
コメント(2)
-

エゴノネコアシ
* エゴノネコアシ *エゴノキに、丸い実と一緒に、バナナの房を小さくしたような「奇妙な物体」が付いていました。なんだろう?と思い、調べてみると、これは「エゴノネコアシ」といい、エゴノキにできる「虫こぶ」なのだそうです。エゴノネコアシアブラムシの幼虫がエゴノキの冬芽に寄生して作った物だとか・・・。名前の通り「猫の足」の様な、バナナの様な形をしています。初めて見ました。京都自然教室 → エゴノネコアシ散歩道さんのブログ → エゴノキの実?* エゴノキの花 *この2枚は、2016年5月7日に撮影したもので、エゴノネコアシが付いていたのと同じ、エゴノキの写真です。
2016.07.21
コメント(6)
-
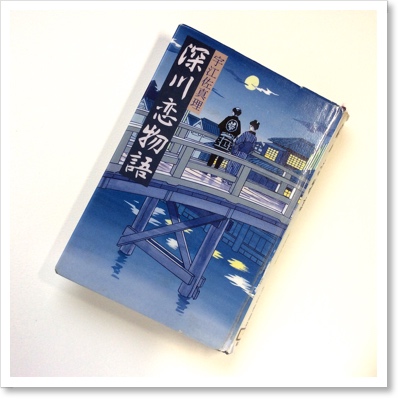
深川恋物語・宇江佐真理
☆深川恋物語・宇江佐真理・1997年9月30日 第1刷発行・発行所:(株)集英社・第21回吉川英治文学新人賞受賞作1.下駄屋おけい〈大店の娘、おけいの恋〉深川佐賀町で太物(*)を扱う大店、伊豆屋の娘‘おけい’は、伊豆屋のはす向かいに店を構える、小商いの履物屋「下駄清」の一人息子、巳之吉を「あんちゃん」といい慕っていた。その巳之吉が、女に騙されてお店の金を15両も持ち出して行方をくらました。けいは、巳之吉がいなくなって初めて自分の思いに気付いた。今更家にも戻れない巳之吉は、下駄清のベテラン職人、彦七の元で下駄作りの修行をしていた。それを知ったけいは、一旦承知した浅草の履物問屋との縁組を断り、これまでのように暮らしに余裕は無いのは承知で、巳之吉と生きる道を選んだ。(*太物=和服用の織物の呼称の一つで、絹に比ラベて糸の太い、木綿や麻織物のこと)2.がたくり橋は渡らない〈若い花火職人、信次の失恋〉年老いた母親のことが気がかりで返事を渋る‘おてる’を説き伏せ、信次はいずれ所帯をもつ約束をさせた。てるの母親が床につき、看病のため仕事を休みがちになり、月の実入りも少なくなった。薬代ばかり嵩み、おてるはついに、さる商家の主人の世話になることを決心した。諦めきれず、未練が若い信次を苦しめた。おてるを刺して自分も死のうと思い詰め、匕首を懐に忍ばせ、凍えるような寒さのなか、おてるの家の前で帰りを待っていた。そんな信次の気配を察した隣家の錺(かざり)職人夫婦は、彼を家に入れ、ただただ自分たちの身の上話を語った・・・。信次を諌めた訳でもない・・・。けれど、二人の優しさが信次の心を揺さぶり、我に返った信次の頭に、翌年打ち上げようと考えていた「虹色発光」のことが浮かんだ。大川の川開きの日。舟に載せた、打ち上げ花火の木筒の中には、信次が作った「虹色発光」の二尺玉が込められていた。「信、火を点けろ」の声に、火の点いた‘つけ木’を筒の中に放り入れ、艫先に身を寄せる。‘虎の尾’がうねうねと頭上に昇って弾けたが、そこからは開いた形が分からない。白い光が弾けた瞬間、紅の色が微かに見えただけだった彼の耳に、観衆が思わず上げた「おお」という感嘆の声が聞こえた。ざわざわと首から悪寒とも感動ともつかないものがせり上がった。「いただきやした・・・」思わず両の拳を胸元であわせ、静かに目の上まで差し上げた。信次、21才の夏だった。3.凧、凧、揚がれ凧師、末松は大の子供好き。凧づくりを教えた近所の子供達との長年の交流を描いた話。4.さびしい水音大工の佐吉。子供の頃から好きだった絵が評判を呼び、一時は売れっ子絵師になった女房おしん。子供に恵まれなかった夫婦の、出会いと別れ。5.仙台堀6.狐拳・竹次郎=材木問屋、信州屋の主・おりん=竹次郎の後妻、元深川の芸者鶴次・新助=竹次郎の連れ子・小扇(ふく)=吉原の半籬、大黒屋の振袖新造。・清二=竹次郎、おりんの息子*振袖新造=花魁の世話を焼く番頭新造の妹格の新造材木問屋、信州屋の後妻‘おりん’には、竹次郎の連れ子である新助と、二人の間に生まれた清二という2人の息子がいた。元深川の芸者だった おりんには、もう一人、芸者だった頃に生み、子のない夫婦に養女に出した‘おふく’という娘がいた。おりんが3才から愛情を注いで育てた新助が、吉原の振袖新造‘小扇’に惚れた。反対するおりんに、父親の竹次郎は、小扇を身請けして新助と一緒にさせるつもりだと告げた。商家の嫁になるには色々と覚えておかなければならないと、落籍させてからしばらくは間に入ってもらった鳶職の徳蔵の家に預けることにした。ところが、思いが叶って嬉しいはずの新助の表情が浮かない。問い詰めたおりんに、新助は「小扇は自分の女房になりたくない。女中か駄目なら妾にしてほしい」と言っていると答え、それ以上は何も喋らない・・・。怒りを胸に徳蔵の家を訪ね、小扇に会いに行ったおりんだったが、小扇がかつて自分が手放した娘の‘おふく’だったと知り、何もかも合点がいった。今頃は嫁に行って幸せに暮らしているものと思っていた、忘れたはずの娘だったのだ・・・。信州屋に嫁いでから、仲立ちをしてくれた人を訪れることもなく、おふくのその後を知らなかった・・・。おりんは頭の中が混乱したまま船着き場に向かったが、冷や汗が絶え間なく流れ、目まいも治らない。やっと信州屋の看板が見えた時、気を失って倒れた・・・。2日間眠り続け、やっと目を覚ましたおりんを、竹次郎は「何も心配しなくてよい」と優しく制した。そして、小扇は家にいて、ずっとおりんの看病をしていたのだと話した。何もかも承知の竹次郎は「小扇の祝言の衣装を任せるから、良いものを見繕ってやりなさい。これもご先祖様のお引き合わせだ」というと、仏間に入って行き、鉦を鳴らして手を合わせた。おふく(小扇)は、新助にはこちらに来てから初めて事情を話したと言う。ほんとにこのままで良いのかと問う おふくに、りんは「よろしいもよろしくないもお前次第さ。新助と上手くいかないとなったら、わっちと一緒にこの家を出るしかない。ただの嫁ではない。わっちの娘だもの・・・」涙に咽ぶおふくに「嫌だねぇ、泣き虫は・・・」というおりんの目にも膨れ上がるような涙が浮かんでいた。
2016.07.21
コメント(0)
-

きまぐれさんの枠をお借りして
↑紅筋ヤマユリ( フラワーセンター大船植物園 )↑ルリマツリ( 朝の散歩道 )時々きまぐれ(きまぐれさん)が、JTrimで作成された素敵な枠をお借りして、スマートフォン用アプリ、LINE Cameraを使って合成しました。きまぐれさん、ありがとうございました。1.枠=JTrimで作成(きまぐれさん)2.画像の合成=LINE Camera3.リサイズ、影をつける=バッチリサイズ2
2016.07.19
コメント(8)
-

アメリカリョウブ&ギボウシ
アメリカリョウブ我が家の近所には、大小取り混ぜて幾つもの公園があります。ラジオ体操の帰りに、その小さい公園のうちの一つ「笹堀第5公園」で、珍しい花が咲いているのを見つけました。ピンク色のリョウブという感じで、花だけ見ると以前掲載した「コバノズイナ」にも似ています。調べてみると、どうやら「アメリカリョウブ」だということが分かりました。写真では区別が付かないのですが、ピンクの色が濃いのが、アメリカリョウブ ‘ルビースパイス’、薄いのが‘ピンクスパイヤー’ という名前だと分かりました。花と緑の図鑑 → アメリカリョウブ園芸ネット → アメリカリョウブギボウシ今年はそろそろお終いですが、白とブルーの濃淡のアガパンサスがとても爽やかです。この公園は、シャガ、エゴノキ、ヤマボウシ、アガパンサス、ギボウシなど淡い色の花、意識して草花や花木の花の色を統一して植えられているように思えます。近所の峰公園はイングリッシュガーデン風ですし、バス停の近くのミニ公園は、桜の木をメインに、足元にはサツキのような低い緑を植え、花は色とりどりのクリスマスローズだけがいっぱい・・・。ミニ公園の全てではありませんが、気をつけてみていると素敵な公園が幾つかあり、そんな公園に出会うのも散歩の楽しみの一つです。
2016.07.17
コメント(6)
-

毬栗と散歩道の花たち
☆ 岡村公園 ☆↑早や イガグリがこんなに・・・↑紅白のサルビアコクネシア↑純白のペンタス☆ 散歩道の花たち ☆↑フロックス和名:おいらんそう(花魁草)、クサキョウチクトウ(草夾竹桃)子供の頃、夏になると、ゼニアオイやこの花が庭のあちらこちらに咲いていました。もう少し背が高くて、花の色はピンクや白の単色だったように思います。私は、祖母が呼んでいた「花魁草」という名前で覚えていたのですが、私の記憶違いかと思っていました。改めて調べてみると、ちゃんと「花魁草」は健在だと分かり、嬉しくなりました。出来れば品種改良された華やかな「フロックス」ではなくて、素朴な「花魁草」が欲しいです。・・・・・・・・・・↑↓ヘクソカズラ別名 :灸花」(やいとばな)オオイヌノフグリと同様、この花も可哀想な名前です。別名だけでも、もう少しお洒落な名前をつけてあげて欲しかった・・・。
2016.07.16
コメント(4)
-

我が家の野菜と花たち
↑↓こちらももう直ぐ収穫↑黄色いミニトマト↑ミニ菜園・1(ゴーヤ、インゲン、トマト、ピーマン、唐辛子類)↑ミニ菜園・2(胡瓜)↑トマトの初収穫昨日、初めて大玉のトマトを2個収穫しました。現在、我が家の菜園には、大玉のトマト、黄色いミニトマト、甘長唐辛子、ピーマン、タカノツメ、胡瓜、ゴーヤ1本、ツルインゲンが、すくすくと育っています。このうち、トマトと胡瓜の苗は、ご近所のYさんとMさんの両方から、ツルインゲンの苗は、Yさんから頂きました。お二方の凄いところは「苗」を購入するのでは無く「種」から育てていらっしゃることなのです。収穫した胡瓜やピーマン、インゲン、甘長唐辛子は、数知れず・・・。Yさんが「海老より美味しい」と言って苗を下さった「ツルインゲン」は、ゴーヤと一緒にネットに絡ませて、グリーンカーテンの仲間入り。このインゲンは、天ぷらにすると本当に美味しくて、もっぱら天ぷらにして頂きました。残念ながら暑くなって収穫は一休み・・・。涼しくなったらまた収穫できるらしいので、そのままにしてあります。この野菜たちは、全て主人の管轄。私は、時々トマトの脇芽を摘んだり、倒れない様に支柱に縛ったりする手伝いをするくらい・・・。感謝していただいています。↑ジギタリスのひこばえ種を採ろうと元の株をそのままにしていたら、根元から芽を出したひこばえが、元気に咲いています。↑オニユリ↑ヒメヒオウギズイセン↑実生のトレニアトレニアは、サルビアコクネシアと同じく、こぼれ種が毎年芽を出して育っています。赤いサルビアコクネシアも咲き出しました。
2016.07.14
コメント(12)
-
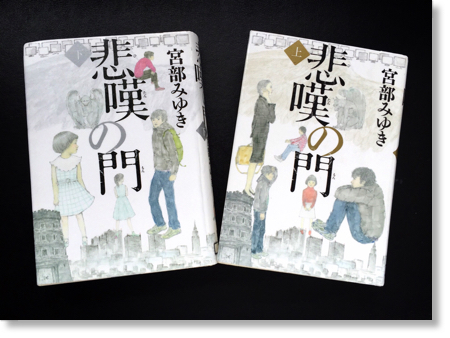
悲嘆の門 ・宮部みゆき
☆悲嘆の門 上下・宮部みゆき・発行所 :毎日新聞社・発行日:2015年1月20日☆ 主な登場人物とあらすじ♣︎三島孝太郎 都内にある大学の1年生。(株)クマーでアルバイトをしている。家族は、父と母、妹の一美(高校生)♣︎美香=隣の家に住む一美の友達(高校生)♣︎都築茂典=元警察官♣︎ガラ(女戦士)=始源の大鐘楼の守護戦士。*始源=言葉の生まれ出ずる領域(リージョン)*(株)クマー = サイバーパトロールをしている会社5才の女の子は、瀕死の母親と住むアパートの窓から、灯りの点かないビルの屋上にある怪物を見ていた。今は使われていないそのビルから、10mくらい離れた家に住む老婦人は、最近 その怪物が一夜明けると向きが変わっていると言う。調べて欲しいと頼まれた元刑事の都築が、そのビルの屋上に上がると、元々屋上に有った怪物(ガーゴイル)の像は粉々に壊されていた。そこにあったのは、異界の魔物「ガラ」が化けた別の怪物だった。老婦人が見ていたのは、夜な夜な飛び回り、昼は羽をたたみ怪物に化けて居座るガラの姿だった。ガラは、罪を犯して〈無名の地〉へ追放された息子を連れ戻そうとしていた。〈無名の地〉へ入るためには、〈悲嘆の門〉の門番を倒さなければならない。その為には、武器である大鎌を鍛えなければならない。大鎌は、人々の〈渇望〉を吸い込み、美しさと強度を増して進化する。ガラは自らの大鎌を鍛えるために、人間の世界へやってきたのだった。・・・・・中略・・・・・茶筒ビルの屋上に上がり込んだ幸太郎と都築は、ガラという魔物に遭遇して魅入られ、ガラの力を借りている積りが、いつの間にかガラに操られていた・・・。幸太郎は誘拐された美香を救うために、犯人を殺してしまった。罪を犯した自分はこの世で生きていけないと、彼はガラと共に無名の地へ行く道を選んだ。ガラは、自らの息子を救い出すために大鎌を鍛えただけで無く、息子の大罪を取り返す代償に、幸太郎を身代わりとして差し出した。幸太郎は騙されていたのだ。ガラは悲嘆の門の傍に佇み、我が息子、戦士オーゾの解放の時を待っていた。だが現れたオーゾは「あなたは欺瞞を操り、人の子をこの地に導いた。それは過ちです・・・」といい、「私がこの地で無になりましょう。自ら進んで、己の咎を負うのです。ほんのひととき外界を見た代償に・・・」といい、去っていった。〈無名の地〉に囚われた幸太郎は逃げ出そうともがくが、足が動かない。身体が動かない。手足の感覚がなく、もうぼんやりとしか感じない・・・。どこかで鎖が巻き上げられる音がして、唐突に終わりが来た。闇の中へ放り出された幸太郎は落ちていく。沈んで行く・・・。深い深い闇の中へ・・・。そして幸太郎は見た。悲嘆の門に不動の閂として固定されている、全身が石と化したガラの姿を・・・。現実の世界に放り出された幸太郎は、鼻血を出して公園のコンクリの上に倒れていた。意識が戻った幸太郎は、時間が戻っていることを知った。彼が罪を犯す前の時間に・・・。
2016.07.14
コメント(0)
-

フラワーセンター大船植物園・7月
☆ 入園口 〜 つばき園付近 ☆↑フイリセイヨウダンチク(斑入り西洋暖竹)斑入りの葉が、見るからに涼し気でした。↑↓クレオメが咲き始めました。遅ればせながら、フラワーセンター大船植物園で、7月6日に撮影した残りの写真を掲載します。この季節は、1週間で開花状況がガラリと変わっていることと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆ 芝生広場 ☆↑リアトリス↑ゴーギャンのひまわり・キク科↑花のトンネルこのトンネルに、おとぎの国のガーデナー(ティンカーベルさん)のブログで見た 黄色い「キングサリ(ラバーナム)」の花房が、藤の花の様に垂れ下がり、足元には 紫の「アリウム」が咲く風景を夢見ています。キングサリ(ラバーナム)の素晴らしいトンネルは、こちらをご覧下さい。↓おとぎの国のガーデナー ⇒ 2015.5.30 美しき‘らばーなむ’・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆ 温室の中庭 & 温室 ☆↑グレヴィレア ‘ロビンコードン’・やまもがし科温室の中庭(オーストリアゾーン)で咲いていました。↑カンガルーポー ・ハエモドラム科↑ヒシバデイゴ・マメ科別名を珊瑚刺桐(サンゴシトウ)といい、温室の前にありました。神奈川県立 フラワーセンター大船植物園
2016.07.11
コメント(8)
-

フラワーセンター大船植物園のヤマユリ
ヤマユリ( 逗子市桜山産 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ヤマユリと鹿の子ユリの交配種今年はフラワーセンターのヤマユリを見に行くのはやめようと思っていました。けれどどうしても紅筋ヤマユリに会いたくて、開花状況を問い合わせました。築山の紅筋ヤマユリは未だ咲いていないけれど、第二展示場裏のもみじ山で、ヤマユリがたくさん咲いています、と教えて下さいました。もみじ山のヤマユリは、これまで見た事がありません。気になって昨日(6日)の午後、行ってきました。ナント! 二種類のユリが群れて咲いていました*\(^o^)/*上のヤマユリには名札がありましたが、ピンクの筋が入ったユリの名札は見当たらず、気になって「園芸相談」の方に聞いてみました。フラワーセンター大船植物園で、山ユリと鹿の子ユリを交配して作出された品種で、固有の名前は付けられていないそうです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・紅筋ヤマユリ↑鉢植えの紅筋ヤマユリ(そろそろ終わりかけていました)↑花の築山の紅筋ヤマユリ( 蕾が色付いていました)フラワーセンター大船植物園
2016.07.07
コメント(6)
-

建長寺の山百合
☆ 建長寺 ☆半蔵坊付近↑↓ヤマユリ↑ヤブミョウガ(名前は、マルリッキーさんが教えて下さいました)今年は大船のフラワーセンターのヤマユリが期待できそうに無いので、昨日は、ずーっと前に行った三崎口駅近くのお寺へ行ってみようかと調べていました。思いがけず、気ままに(marboさん)が、6月28日の日記に、北鎌倉の長寿寺と建長寺の素晴らしいヤマユリの写真を掲載していらっしゃるのを見つけました。既に5日経っています。このところの暑さを思うと果たして間に合うかどうか・・・。居ても立っても居られなくて、午前中に行ってきました。北鎌倉は長男が通っていた高校があり、度々通った懐かしい場所です。どちらも、北鎌倉駅から10〜15分と近いお寺です。9時に北鎌倉駅到着。先に、遠い方の建長寺へ行くことにしました。総門→山門→仏殿→法堂→龍王殿と進み、更に奥の半蔵坊へ向かいました。ヤマユリは、半蔵坊へ登る階段の脇に咲いていました。半蔵坊まで登ると相模湾が一望できる筈なのですが、残念ながら、今日は霞んでよく見えませんでした。私はここからUターンしましたが、江東区から来たという小学生の親子連れは、天園のハイキングコースへ行くと、更に上へ登って行きました。↑建長寺 境内図クリック or タップで拡大画像が開きます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・↑↓天下門↑奥に見えるのは、総門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・龍王殿(方丈)↑龍王殿裏の庭園龍王殿の前や前庭には鉢植えのハスの花がたくさん飾られていましたが、流石にプラスチック容器では無くて、素敵な容器に植えてありました。色合いからすると、もしかしたら「銅製」?☆ 長寿寺・北鎌倉 ☆↑山門↑山門脇のヤマユリ残念ながらほとんど散っていました( ; ; )↑長寿寺横の「亀ケ谷切り通し」紫陽花が綺麗に咲いていました。
2016.07.03
コメント(12)
-

我が家のサルスベリ&サルビアコクネシア
↑サルビアコクネシア毎年、こぼれ種が芽を出して元気に咲いてくれます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・↑紅い百日紅↑↓今年はピンクの百日紅↑例年、薄紫の筈が・・・?何故か今年は淡いピンクの花が咲いています。2階のベランダから撮影矮性の百日紅の間で胡瓜が育っていますピンクは赤の種から育った子供です。今日の横浜の最高気温は30度、湿度は80パーセント以上。午前中、動き回っていると汗びっしょりになりました。もう直ぐ3時、2階の窓辺に座っていると、心地よい風が吹き抜けていきます。何といっても自然の涼風はクーラーに勝ります。
2016.07.02
コメント(4)
-

通りゃんせ・宇江佐真理
☆通りゃんせ・宇江佐真理(うえざ まり)・角川書店・平成22年10月5日 初版発行・初出/「野生時代」2008年6、9、12月号、2009年3、6、9、12月号北海道の大学を出た大森 連は、地元のスポーツ用品メーカーに就職。入社3年目に東京勤務となる。ある日、マウンテンバイクで小仏峠を越えたところで道に迷ってしまった。方向を見失った連は、明神滝の裏側に迷い込み、深い穴に落ちて気を失った。気がついたところは黴くさい匂いがする農家の様な家の中だった。台所の床は赤土の土間で、雑誌でしか見た事がない竃(かまど)が設えてあり、おまけに電灯らしき物も見当たらない・・・。そこは、江戸時代末期の武蔵国中郡中郡青畑村だった。明神滝に近い観音さまの社の樹の陰で倒れていたところを、 時次郎、さな兄妹に助けられたのだという。時は天明6年(西暦1786年)、その年の青畑村は梅雨が明けても雨が降り続き、川は氾濫、稲は実らず、年貢米を納められない百姓の中には、厳しい取り立てに田畑を捨てて逃げる者が続出した。連は、まさに天明の飢饉の最中にタイムスリップしたのだった・・・。(以下略)♣︎宇江佐真理1949年北海道函館市うまれ。函館大谷女子短期大学卒業。1995年「幻の声」でオール読物新人賞を受賞し、デビュー。2000年「深川恋物語」で吉川英治文学新人賞。2001年「余寒の雪」で中山義秀文学賞。人情味溢れる市井物を中心に幅広く時代小説を手がけている。2015年11月7日、死去(66歳)最後の作品は「うめ婆行状記」(朝日新聞連載)♧その他の作品Roadside Library( kyoshi 様)→ 宇江佐真理 著書リスト
2016.07.02
コメント(0)
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-
-

- みんなのレビュー
- 【レポ】内容違いで販売中「訳あり黒…
- (2025-11-15 20:12:44)
-
-
-

- ★つ・ぶ・や・き★
- 【北村晴男】話せる範囲でお話ししま…
- (2025-11-15 22:09:17)
-
-
-
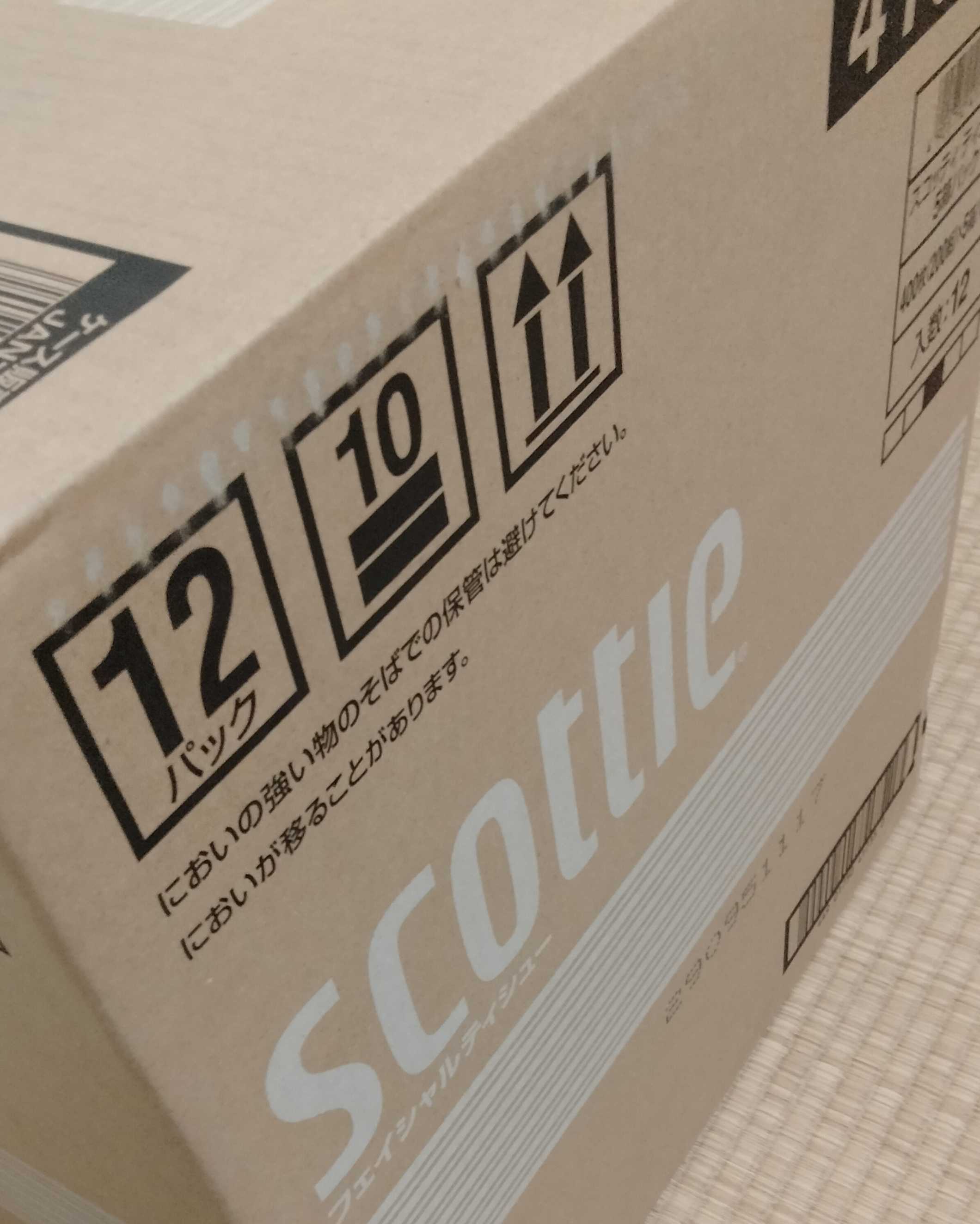
- 株主優待コレクション
- マツキヨココカラ:京都で:ノンアル…
- (2025-11-15 18:27:26)
-







