2022年03月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-

大岡川の桜を満喫
ー 大岡川プロムナードの桜 ー( 横浜市南区 )↑ 観音橋付近SUPに乗る人たちSUPとは?=スタンドアップ・パドルボード(Stand-Up-Paddleboard)の略称とっても気持ち良さそうでした(^∇^)・・・・・・・・・・・・・・・・・・↑ 神代曙(ジンダイアケボノ)染井吉野と比べると、ピンクの色が濃くみえます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日は、この近くに住む友人が誘ってくれ久し振りに友人4人で桜を堪能してきました。思えば、このメンバーと会うのは3年振りでした。一日中曇りの予報でしたが時折り青空が顔を見せてくれました。やはり桜は水辺がよく似合いますね。以前は桜の下に ずらりと並んでいた屋台の姿は見えず桜を堪能できました。
2022.03.30
コメント(10)
-

原種系チューリップが咲きましたが・・・
イギリスにお住いのブロ友さんの所で咲いていた「原種系チューリップ」に憧れてSのタネのオンラインショップで球根を買いました。当然のことながら、イギリス国内と同じ品種は見つからず「原種系」だけを頼りに選びました。↑こちらがサンプル画像原種系チューリップ・バイカラーミックス白と赤、白と黄色の球根が10ケずつ入ってましたが小さいこと (@_@)フリージアの球根くらいの大きさでした。全部一緒に植えれば良かったものを大きいプランターに各5ケ計10ケずつ植えたのが失敗のもと^_^;一度に咲いてくれればまだしも先ずは赤しか咲かず黄色はまだ小さい小さいつぼみのまんま。かくして、なんとも間抜けなことになりました。来年は、全部一緒に植えることにします。でも果たして2年目も咲いてくれるでしょうか ^_^;・・・・・・・・・・・・・・・・・・黄緑色の原種系のヘレボラス逞しいです。少しずつイメージ通りの、ヘレボラスコーナーになってきました (^_^)v↑ ダッチアイリス今年はずいぶん早い開花です。ダイソーのタネ(2つ100円)から育ったルピナス大きい株は、こんな状態です。雨の前の移植は大成功!なんとか根付いてくれました。
2022.03.29
コメント(14)
-

アーモンド & 散歩道の花たち
庭仕事も疲れ桜の追っかけも飽きて今日はどちらも小休止。アーモンドの花が咲いていたことを思い出しいつもの、東方面の散歩道を歩いてきました。↑↓ ニワザクラ(庭桜)歩道沿いの、この花壇はいつも花が絶えることなく咲いています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・帰り道、珍しい花を見つけました。グミとルッコラの花です。↑↓ グミ
2022.03.27
コメント(14)
-

横浜緋桜2022・本牧山頂公園
ー 観山広場(ひざくらの丘) ー広場の周囲を、ぐるりと取り囲む様に緋桜が植えてあります。↑↓ 横浜緋桜 & ソメイヨシノ大島桜(上) & 横浜緋桜(下)大島桜淡い緑がかった白い大島桜や薄ピンクのソメイヨシノと濃い紅色の緋桜の対比が美しいのです。同じ時期に咲くのは滅多になくて私がこのコラボに出会えたのは2回目。2〜3日後ならもっと美しかった筈ちょっと残念です。この広場には横浜市内在住の、桜愛好家(白井勲さん)が作出された横浜緋桜の原木があります。横浜市中区の区政70周年を記念して平成9年(1997年)11月に植樹されました。本牧山頂公園 − 公式サイト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日は雨の予報が出ていました。降り出す前にと、昨日は庭や花壇のあちらこちらで芽を出し咲き出したノースポールや虫取撫子の苗などなど居心地の良さそうな場所に植え替えてやりました。今日は午前中にルピナスを移植。ルピナスはダイソーで買った種から十数本育ちました。苗ポットではなくプランターに直播きしたため果たして根付いてくれるか不安で雨を待っていました。そんなこんなで昨日、今日は大忙しでした。予報通り、午後から本降りに。暖かい春の雨です。どうぞ上手く根付いてくれますように・・・。
2022.03.26
コメント(10)
-

新本牧公園〜本牧山頂公園へ
ー 本牧通り〜新本牧公園〜本牧神社へ ー横浜緋桜今日は午前中いっぱい庭仕事をして午後から、本牧山頂公園へ横浜緋桜を見に行ってきました。本当は週末が一番良かったのですが残念ながら週末の予報は雨と曇り・・・。月曜日も予定が入っています。本牧通りから新本牧公園を通り抜け本牧神社へ公園は地域の人々の憩いの場いつも子供達が自由に走り回っています。辛夷(コブシ)の大木が何本もあります。正面に見えるのが本牧神社神社の緋桜は、やっと咲き始めたばかり。社殿右手の階段を昇り本牧山頂公園へ山頂公園到着〜さくら広場へさくら広場のソメイヨシノは1〜2分咲きというところでしょうか一回りして観山広場(ひざくらの丘)へ途中に咲いていた桜(名前は不明)以前は名札が付いていました。心配した観山広場の横浜緋桜はちょうど見頃でした\(^^)/明日へ続きます。
2022.03.25
コメント(12)
-

夏みかんピール & ジャム
今年はどこからも夏みかんが頂けず諦めかけていたところ友人から「夏みかん要らない〜?」との嬉しいLINEが〜♪喜び勇んでもらってきました。皮はピールに、中の実はジャムに。おかげで今年もたくさん出来ました\(^^)/夏みかんの実だけで作ったジャムは私の一番好きなジャムです(^∇^)ピールは下準備から仕上げまで2日がかりでとても手間がかかります。毎年、もうやめようと思いつつ懲りずに毎年作っています(*^^*)夏みかんピールの作り方 → 夏みかんの皮の砂糖煮(ピール)↑ このレシピは、少量(2〜3個)を作る場合、途中から焦がす心配がない電子レンジを利用する方法で、鍋で作る「マロンさんのレシピ」のアレンジバージョンです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日の横浜は朝から冷たい雨が降ってます。最高気温は夜中に出たそうで日中は5度までしか上がらないとか。横浜地方気象台は、昨日(21日)横浜で桜が開花したと発表したとか。マルリッキーさんが教えて下さいました。近所のソメイヨシノは既に咲き始めています。けれど大半はまだ蕾・・・。この寒さでほころびかけた蕾が縮こまってしまいそうです。岡村公園のソメイヨシノ昨日の朝写しました。寿命がきたソメイヨシノの後継種として植えられている桜です。こちらも昨日の朝、近くの公園で写しました。木全体ではぽつぽつと咲いていました。
2022.03.22
コメント(18)
-
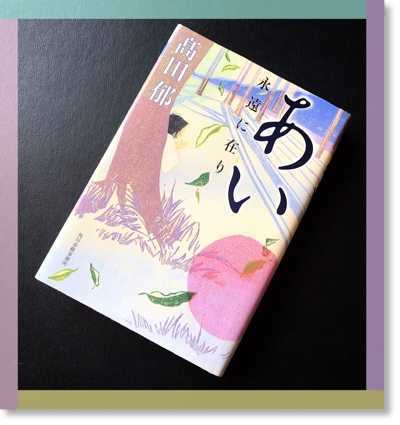
あい 永遠に在り・高田 郁
☆あい 永遠に在り・高田 郁・発行者:角川春樹・発行所:(株)角川春樹事務所・2013年1月8日 第1刷発行。♣︎君塚あい上総国山辺郡前之内村(千葉県東金市)の貧しい農家に生まれ、関寛斎(蘭方医)と結婚。幕末から明治を生き抜いた女性。8男4女を設けるも、6人を病気で亡くす。第1章 逢天保10年(1839年)上総国山辺郡前之内村。人の記憶がどこまで遡れるのか、あいが5歳の時に見た情景は、後々までもあいの心に残り、折に触れて思い出される。その後の記憶がごっそり抜け落ちているが、少年の哀しみと山桃の姿が、あいの胸に刻まれ消えることはなかった。のちに夫となる関寛斎(*1)、その人との出会いであった。第2章 藍嘉永6年(1853年)、水無月。江戸湾の浦賀沖に、ペリー率いる黒船が4隻姿を現した。佐倉順天堂で蘭医学を学んでいた関 寛斎は、前之内村に戻りあいと結婚。医院を開業するも、待てど暮らせど患者は来ない。ならばと、ときには佐倉順天堂まで6里の道を通い様々な外科手術に立ち会い、あるいは師に代わって執刀する事もあった。あとの日々は診察室に籠り、「順天堂外科実験」なる記録を認めて過ごした。あいは得意な機織りで家計を支えた。これだけ精進している寛斎が、前之内村にいる限り報われないことが残念でならなかった。同僚が長崎へ留学すると聞き、前之内村で開業したことを悔やんでいた寛斎は、何ごとにもくよくよしないあいの姿から学んだことがあるようだ。安政2年(1855年)、のちに安政江戸地震と呼ばれる大地震が起きた。寛斎は佐倉へ出向き怪我人の治療に専心した。幾日かのち師の佐藤泰然から呼び出しの文が届き、銚子で開業せよと、直々に勧められた。あいの願いが叶い、やっと家族3人で銚子で暮らせることになった。銚子は豊穣な海と、醤油醸造で大いに賑わい、利根川を利用しての大量の物資が運ばれる、「江戸の台所と称されるほど豊かな町である。「関医院」の看板をかけたその日から、次から次へと患者が訪れる。前之内村の頃が夢かと思われるほどの忙しさだった。あいは、朝餉の支度の合間、竹箒を手に表へ出た。日の出の刻を迎え、曙色に染まる東天は家々の瓦屋根を輝かせている。港の方からは威勢の良い声が響き、深く息を吸うと、塩と醤油の香りが胸一杯に流れ込む。郷里と異なる朝の光景に、あいは箒を手にしたまま、うっとりと見入った。ふと、脇に人の気配を感じで視線を向ければ、面長の穏やかな風貌の男が微笑みながらあいを眺めていた。濱口悟陵(*2)と名乗り、寛斎の評判は色々と耳に届いています。ぜひ一度ゆっくり話をしたい。ついては診察を終えた後にでも家の方にお運び頂くようにお伝えくださいと、4、5軒先の邸宅の屋根を指し示した。最初はお大尽から呼びつけられたと誤解した寛斎だったが、あいの勧めで出かけて行った。帰宅した寛斎は気持ちが高揚しているらしく、妻を相手にその夜のことを話し続けた。話が弾み、医学のこと、政のこと、西洋のこと、等々、悟陵との話は多岐に亘り、尽きることがなかったという。悟陵は37歳と若く、寛容で柔軟。歳が近い寛斎にしてみれば、より近しく思われるのかも知れない。いずれにしろ、移り住んだ町で良い出会いに恵まれたことを、あいは深く感謝した。銚子と佐倉は、およそ14里(56km)。それでも治療に疑問を覚えると、寛斎は躊躇うことなく佐倉まで足を運び、恩師泰然はじめ諸先輩に教えを乞う手間を厭わなかった。寛斎の誠実な姿勢は、患者の信頼をさらに厚いものとし、関医院は銚子の町にしっかりと根を下ろしつつあった。あいは、近隣の女性たちと親しく交わるようになり、あいはあいの方法で、この地に溶け込んでいった。貧しい者からは薬礼を取らず、質素な着物を纏い、雑穀混じりの米を口にして暮らしている。そんな夫妻の質実剛健な生き方は、銚子の人々に感動を持って受け止められた。安政5年台所の醤油が切れる頃になると、濱口家から新たな品が届く。そればかりではなく、最新の医療器具や医学書が頻繁に送られてくる。何かの形でお礼をしたいと、あいは刻を見つけて機を織った。寛斎より一回り小柄な悟陵に合わせた、美しい藍色の縞木綿であった。将軍家定逝去に伴い、紀州藩主だった家茂が14代将軍となった。長崎でコレラ患者が出た。腹を下し、吐き、コロリ、コロリと死んでゆく。抗いょうのない、恐ろしい病だった。今回は長崎で発症したのだ。蘭方医達が知恵を寄せ合い、事に当たるに違いないいう寛斎の言葉を聞き、あいはほっとする。 ところが、半月ほどあとのこと、飛脚が江戸にいる濱口梧陵からの手紙を、文字通り飛ぶようにして運んできた。文を持っ寛斎の手が戦慄いている。「あい、私は江戸へ行く」江戸でコレラ患者が出たという。行かないで欲しいとの懇願を妻が口にする前に、寛斎は頭を振って先に封じた。「齢4つで、生母と死に別れたが、のちに、適切な治療を受けてさえいれば助かる命だったと知った。そのとき、石に齧りついてでも、医学の道へ行こうと決めた。助かる命なら、どんなことをしてでも助けたいのだ」初めて知る、夫の胸のうちであった。魚を食べるとコロリにかかる、という噂が流れ、銚子の漁師の暮らしを直撃しかかった頃、寛斎が江戸から戻った。そして、コレラの予防法を書いた大きな紙を戸板に貼り、医院の前に立てた。錦絵を飾ることしか身を守る術を持たなかった人々は半信半疑ながらも実践してみることに決めたのだった。蓋を開けてみれば、江戸市中において死者はおよそ3万人とされるのに対し、銚子ではごく少数が罹患したのみだった。安政6年(1859年)、春の宵のこと。梧陵は、寛斎のお陰でこの地がコロリから救われたと、両手を畳について、深く頭を下げた。一方寛斎は、梧陵のお陰で、薬剤や医学書、資料など一切を揃えられたこと。また、優れた蘭方医の方々と親しく交わることが出来たことなど、どれだけ言葉を尽くしても感謝しきれないことを伝えた。梧陵から勧められた長崎留学の話を固辞し続けた寛斎だったが、あいから梧陵の真意を聞いた寛斎は、長崎留学の話を受けた。ポンペは、寛斎より一つ年上の33歳。4年前に来日し、以後、患者の治療と医学生の教育という二本柱を担い続けた。養生所には身分の違いによる差別は一切なく、どの患者も同じ扱いで、治療費は富めるものは銀6匁、貧しいものはその半分。極貧者は無料と決められていた。明けて、文久2年(1862)年1月に長崎を発った寛斎は、江戸に立ち寄り4月になってようやく銚子に戻った。梧陵から更なる長崎留学の提案があるも、寛斎は断った。そして、佐倉順天堂で共に学んだ友から推挙された阿波徳島藩主、蜂須賀公の国詰め侍医を受けることに決めた。寛斎は「更なる5年の留学を終えると39。その間、年老いた親の扶養や子等の養育を人の金で賄うことが私にはできない。これ以上は重すぎる恩義は耐え難い。こういう風にしか、私は生きられないのだ」と、声を振り絞り、あいに話した。濱口からの申し出を断ることは最初から決めていたことで、御典医の話はたまたま転がり込んだ口実に過ぎなかったのだ。第3章 哀家族と共に徳島へ向かった寛斎は、この地に蘭方医学を伝えるため、いかなる努力もしようとしていた。慶応2年(1866)11月、徳川慶喜公が大政奉還。慶応4年(1868年)寛斎の理解者だった蜂須賀公死去。第4章 愛明治32年(1899年)古希を迎えた寛斎は、あいに「息子のところへ身を寄せてほしい。ゆくゆくはこの家も土地も手放し、身一つになって、ただ1人徳島を出て、北海道に渡り、開拓に身を投じたい」寛斎は家督を息子に譲り、札幌農学校で学ぶ7男又市の住む樽川へ移住するつもりであったのだ。ー人たるものの本分は、眼前にあらずして、永遠にありー寛斎の父俊輔がそうであったように、夫は、昔から「私」よりも「公」を重んじる人だった。あいもこの目で、その緑なす大地を見てみたい。「連れていってくださいな。私も一緒に。きっとお役に立てますよ。田畑仕事は、先生よりも私の方が上手ですからね」作者はあとがきに、凡そ次のようなことを書いています。あいに関して今日に残るものは殆どありません。手織り木綿の布地がすこし、着物一枚、帯締め、家族写真数葉、現存するものはそれだけです。あとは「婆はわしより偉かった」等の寛斎の言葉が残るのみ。その言葉に着目して、あいの物語を構築しました。そして最後に、あいが夫に託した遺言は守られ、関寛斎、あい夫妻は今、陸別町を見渡せる小高い丘に一緒に眠っています」と。♣︎関 寛斎(*1)幼名・豊太郎、実在の人物。文政13年(1830年) - 大正13年(1830年)。82歳で没。幕末から明治時代の蘭方医。幼くして母を亡くし、生母の姉の嫁ぎ先である関家の養子となる。18歳で前之村を出て、佐倉に出来た蘭方の医学校(佐倉順天堂)に入り、蘭医学を学ぶ。あいと結婚。26歳のとき銚子で開業。豪商濱口梧陵の支援を受け、長崎でオランダ人医師ポンペに近代医学を学ぶ。銚子を去り、徳島藩蜂須賀家の御典医となる。戊辰戦争(1868年〜1869年)のときは、官軍の軍医となり敵味方なく治療に当たる。戦が終わったあと徳島に戻り、一町医者として庶民の診療、種痘接種に尽力し、慕われる。明治35年(1902年)、72歳。一念発起し北海道に渡り、陸別町の原野の開拓事業に全財産を投入し、広大な関牧場を拓く。のちにこの農地を小作人に解放することを望むも、家族に強く反対され、苦悩の末、大正元年(1912年)10月15日、82歳で没。服毒自殺。♣︎濱口悟陵(*2)濱口醤油醸造所当主。鷹に似た鋭い目の寛斎とはことなり、馬を思わせる黒目がちの優しい双眸のひと。紀州を大津波が襲った際、身を挺して稲むらにに火を放ち、闇を照らして高台へ逃げる道筋を示し、千人からの人を救った、その人である。☆高田 郁1959年生まれ。中央大学法学部卒。小説家、時代小説作家。主な作品出世花、みをつくし料理帖シリーズ、銀二貫、あきない世傳 金と銀シリーズ他
2022.03.21
コメント(0)
-

続・春爛漫の大船フラワーセンター
ー ツツジ 石楠花園〜芝生広場〜菖蒲園付近 ー↑左=カンレンボク(別名:喜樹)、右上=辛夷(コブシ)↑ 紫木蓮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・↑↓ 山茱萸(さんシュユ)↑ ユキワリイチゲ(サンシュユの根元で咲いていました)・・・・・・・・・・・・・・・・・・花も葉もラッパスイセンにそっくり花は小さくて、全体に細目でした。Googleアプリで検索するとキズイセン、イトズイセン、ジョンキルスイセンと、表示されました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・↑↓ スノーフレーク↑ 利休梅(リキュウバイ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー グリーンハウスの中 ー↑↓ ドンベア ティリアケア (アオイ科)原産地:東アフリカ・マダガスカルこの花木は以前からあった筈なのに咲いているのは初めて見たかも。・・・・・・・・・・・・・・・・・・↑↓ 金花茶(キンカチャ)ツバキ科ツバキ属(原産:中国・広西省南部)とても珍しい花木だそうです。・・・・・・・・・・・・・・・ー もみじ山〜ピクニックグラウンド付近 ー ↑↓ しゃくなげもどき (マンサク科)何年も通っていますが、この花も咲いているのを見たのは初めてでした。たしかに、名前の通り花も葉も石楠花に似てるといえば似ています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・↑ ボケ↑ゲンカイツツジ(花の築山)・・・・・・・・・・・・・・・・・・一昨日(3月17日)に行った大船フラワーセンターの続編です。昨日は早咲きの桜に絞って掲載しましたが今日は残りの花たちを掲載しました。この日は初夏の陽気でしたのに昨日は一転して冷たい雨が降る真冬の寒さでした。近くの公園のソメイヨシノがちらほらと咲き出しました。予想より早く開花宣言が出そうです。
2022.03.19
コメント(18)
-

早咲きの桜満開・大船フラワーセンター
ー 花の築山、玉縄桜広場付近 ー↑ 左から、玉縄桜、おかめ桜、春めき(足柄桜)↑ 春めき(足柄桜)後ろ=春めき(足柄桜)、手前=おかめ桜↑↓ 敬翁桜(けいおうざくら)↑ 玉縄桜すでに満開を過ぎていました。黒いハス桶が、ずらりと並んでいました。今年も花が咲くのがのが楽しみです〜♪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー ピクニックグラウンド〜シャクヤク園附近 ー↑ 敬翁桜↑ 春めき(足柄桜)↑↓ 玉縄桜・・・・・・・・・・・・・・・・・・↑ 大寒桜・・・・・・・・・・・・・・・・・・↑大寒桜の実生↑ 木に掛けられていた説明書き(原文のまま)一昨日は一日中庭仕事。昨日も続きをするつもりでした。ところがフラワーセンターのTwitterを見ると既に早咲きの桜が満開とのこと!今日から気温が急降下おまけに雨の予報が出ていました。急遽予定を変更!行ってきました。思えば久し振りのフラワーセンターでした。麗らかな春の日差しのもと勝手知ったる園内を歩き回り春を満喫してきました\(^^)/3月17日(昨日)の歩数=15,268歩久し振りによく歩きました。
2022.03.18
コメント(16)
-

残念なダイヤモンド富士
3月15日(火)岡村公園から見た日没時の富士山です。気象条件が良ければ、昨日はダイヤモンド富士が見えた筈でした。残念ながら、このところ霞(かすみ)? もや(靄)がかかっていてこれがやっとでした。3月14日(月)一昨日は富士山の稜線はクッキリでしたが太陽は山頂より左に沈みました。
2022.03.16
コメント(18)
-

我が家の庭の花たち・3月
ー クリスマスローズたちーヘレボラス オリエンタリス春咲きのクリスマスローズです。10年くらい前、クリスマスローズに目覚めた頃最初の頃に買った中の一つです。八重咲きなど珍しい品種はいつの間にか消えてしまいました。この花も、一度花が咲かなくなり諦めかけた株でした。思い切って、バッサリ株分けして植え替えたら元気になりました。ヘレボラス アーグチフォリウスこんなに花が咲きました(^∇^)度々登場する有茎種の、お気に入りの原種です。茎の先に、花を咲かせます。・・・・・・・・・・・・・・・・・我が家で自然交配一人で芽を出し育った良い子です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その他色々・古株たちろくな手入れもしてもらえないのにめげずに、毎年咲いてくれます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー その他 ー太神楽一旦咲き終わった早咲きの椿何故かまた咲き出しました。昨秋亡くなった友人からもらったプリムラ何年も姿を見せず、消えたと思っていました。3年前に突然咲き出し少しずつ株が大きくなりました。これも消えてしまったかと思っていたラッパ水仙今年は、植えた覚えのないところでも芽を出し健気に咲いています。細い葉は、ダッチアイリスです。ヒヨに突かれて茎だけにされていた小松菜に、花が咲きました。こうやって、改めて並べてみるとどれも手間いらずの丈夫な花ばかりでした(*^^*)
2022.03.15
コメント(17)
-

満開のオカメザクラ & 今日の雪割り桜
ー オカメザクラ ー通り抜け自由な通路沿いに4本我が家から徒歩で20分ほどのところにある病院の敷地内で咲いています。紅色の細長いハート形の花弁が可憐な桜です。自由に通り抜けられる通路沿いに4本関係者以外は入れない敷地内に3本白い建物に紅色の花が映えて、美しいです。最初、10日に見に行ったのですが、行った時間が早かったため花の半分が影になっていました。また、未だ5〜6分咲きと見ごろには早かったこともあり昨日の午後もう一度見に行ってきました。結果は大正解!昼下がりの穏やかな日差しのなか白い建物と青空に、紅色の花の色が映えて最高に美しかったです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆オカメザクライギリスの桜研究家コリングウッド・イングラムがカンヒザクラとマメザクラを交配して作出。名前は「おかめ」に由来するのだそうです。う〜む。おかめと言えば、私にはあのお面の「おかめ」しか思い浮かびません。「オカメザクラ」のイメージと「おかめ」のイメージが結びつかないんです。日本女性の一人である私からすると、いささか、複雑な気分でもあります。そう思うのは私だけ?ー 今日の「雪割り桜 ーまさに満開!美しいのを通り越して、モコモコ状態でした(@_@)
2022.03.13
コメント(20)
-

雪割り桜ほぼ満開・岡村公園
ー 岡村公園の雪割り桜 ー今年も、雪割り桜が咲きました。岡村公園には雪割り桜が2本あります。今年は開花が遅かったのですがこのところの暖かさで、一気に満開になりました。この桜は、正式には「ツバキカンザクラ(椿寒桜)」といいシナミザクラとカンザクラの交配種だそうです。高知県須崎市にある桑田山(ソウダヤマ)には1000本植わっているとか。見てみたいものです。雪割り桜の特徴は下記の3点だそうです。a.長くて目立つ蕊(シベ)b.花弁が内側に丸まっているc.小振りの花がまとまって咲く他では余り見たことが無いのですが、皆様の近くではどうでしょう?皇居の東御苑にもあるそうです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・例年より開花が遅れていた早咲きの桜がこのところの暖かさで、一気に開花しました。かくして、私は桜の追っかけで大忙しです。といっても近場の桜だけですが・・・。今日は、オカメザクラを撮りに行ってきました。おかめさんは、また明日・・・。実は「雪割り桜」の名前のことについて、以前調べたことがありました。以下は、2016年3月11日 の当ブログに掲載した文章のコピーです。♣︎青い山脈の「ユキワリザクラ」のこと青い山脈の歌詞に登場する「ユキワリザクラ」は、この「雪割り桜」のことだと思っていましたが、どうやら違っていた様です。レファレンス協同データベース(*注1)に『「青い山脈」に出てくる「雪割り桜」の写真ののった本はあるか?』と言う質問に対して、下記の回答が記載されていました。ほぼ同じ内容の回答が幾つか掲載されていましたが、その中の1つをご紹介します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『西條八十全集 9』(西條八十/国書刊行会/1996) p466~p467に以下のような記述あり。 「・・・後年筆者が名古屋の繁華街を歩いていると、桜草に似た淡紅色の花をつけた植物を売っている男が「青い山脈 雪割桜だよ。買ってらっしゃい」と口上を述べていた。 そこで八十にその植物の話をすると、「その植物は「雪割草」が正しい名前で、「雪割桜」と言うのは、僕の考えた新語だよ」との事だった。・・・」・『野草大百科』(北隆館/1992) ※p332【スハマソウ(ユキワリソウ)】あり。写真あり。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・*注1レファレンス協同データベース(レファ協)とは?国立国会図書館が全国の図書館等と協同 で構築する調べ物のための検索サービスのこと。参加館の質問・回答サービスの事例、 調べ方、コレクション情報など調査に役立つ情報を公開しています。詳しくはこちら ↓レファレンス協同データベース(レファ協)とは?レファレンス協同データベースに記載されていた回答のページここまで読んでくださった方、どうでも良い話にお付き合いいただき有難うございましたm(__)m
2022.03.12
コメント(18)
-

梅・思いのまま & 岡村梅林
ー 岡村天満宮 ー思いのまま桜が咲き始めると、すっかり梅のことを忘れてました。ブロ友さんのところで拝見して‘思いのまま’ のことを思い出し今朝、ラジオ体操の帰りに寄って見ました。朝の光の中では、色が綺麗に撮れず午後から出直しました。枝垂れた枝の花はピークを過ぎていましたが全体にはまだまだ綺麗でした。ー 岡村梅林 ー公園に隣接して作られた梅林です。東屋が作られていたり日本庭園風の作りになっていてなかなか風情があります。ところが、ここ数年、肝心の梅の花が年々減る一方でやっと疎らに咲いている状態…なんとも寂しい限りです。
2022.03.11
コメント(16)
-

万作 & 三椏の花が咲きました
万作(マンサク)の花この斜面の土地は、斜面の下に住む方が、草を刈り様々な花木や果樹を植えて手入れされています。梅、桃、柿、夏みかん、温州みかん、などなどその中に小さな「マンサク」見つけました。なんでも知り合いの方から貰い受けられたものだとか。嬉しくなって以来、春が来るたび眺めています。いつもパラパラとしか花が咲かなかったのですが未だ株の右半分の枝だけですがたくさん花を咲かせてくれました\(^o^)/左半分も蕾が付いています。自分の物でもないのに一人で喜んでいます〜♪・・・・・・・・・・・・・・・・・・三椏(ミツマタ)近所のAさんのミツマタが咲き始めました。未だ花が少ないのですが待ちきれなくて撮らせてもらいました。
2022.03.08
コメント(18)
-

河津桜満開・宝積寺
ー 宝積寺の河津桜 ー昨日の午後、友人3人と宝積寺の河津桜を見に行ってきました。我が家からだと徒歩で約30分ほど。根岸にある宝積寺の本堂裏手の高台で咲いています。見るには、墓地の中のジグザグの階段を登ります。かなりハードです。桜の咲く場所は、日当たり、眺望抜群!本数は10本ほど、既に満開でした。去年行ったは2月22日満開をすこし過ぎていました。今年は2週間近く遅いです。去年は4人で行きました。昨秋その内の1人が亡くなり今年は寂しい花見になりました。一番高台の見晴らしの良いベンチに座り三人三様あれを思い、これを思いしつつしばし、亡き友を偲びました。横浜市磯子区 → 明王山・宝積寺
2022.03.07
コメント(22)
-

ピンクの枝垂れ梅 & 海苔巻き
いつも花が少なくて、影が薄いご近所さんの枝垂れ梅です。今年はどうしたことか、見事に咲きました。こんなに咲いたのを見たのは初めてです。ー 海苔巻きー節分には海鮮巻きを作りました。やっぱり昔ながらの海苔巻きも食べたくて作りました。今回入れた具材は7種類干瓢、竹輪、卵焼き、ほうれん草高野豆腐、干し椎茸、甘い桜でんぶそのまま使えるのは、桜でんぶだけ。卵は味付けして焼くだけですが椎茸、干瓢、高野豆腐は、一旦、水なり湯で戻してから別々に味付けして煮る必要があります。海鮮巻きはただ巻くだけ。ところがこちらは数倍手間がかかりました^_^;
2022.03.04
コメント(18)
-

ミモザ & 公園のリス
ー 近所のミモザ ーご近所の I さんのミモザが咲き始めました。まん丸いポンポン玉のような可憐な花がいっぱい!明るい黄色が青空に映えて気持ちがパーっと明るくなりました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー 岡村公園のリス ー↑左のリスを、拡大すると手にドングリを持ってます。↓リスが岡村公園の中を駆け回っています。どうやら台湾リスのようです。リスを撮って来ると夫がカメラを持って出かけて行きました。枝から枝へ飛び移ったり木の幹を垂直にスルスルと登ります。すばしっこくて、撮るのは無理かと思っていたら拡大してみると、ちゃんと写ってました。当人も思っていたより良く撮れていたようで驚いていました(笑)
2022.03.02
コメント(16)
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 94歳の大村崑、人生初の骨折「こんな…
- (2025-11-15 20:00:04)
-
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-15 02:35:31)
-








