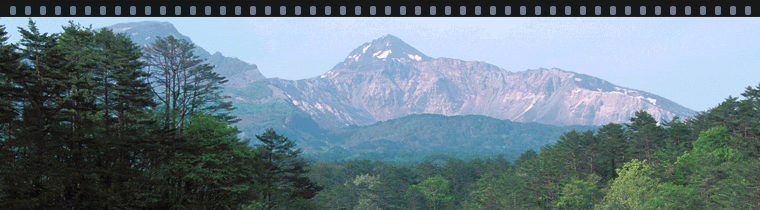2007年01月の記事
全39件 (39件中 1-39件目)
1
-
ミクシィ[mixi]で何ができるのか?
「ミクシィ[mixi]で何ができるのか?」 山崎秀夫 2007年01月 青春出版社 他の本を探しに行ったのだが、探しきれず、こちらの本を立ち読み。出会い頭にいろいろ読んではいるが、この本、2007年発行の本としては、このブログでは一冊目じゃないかな。やっぱり新しい本は新鮮でいいなぁ。 さて、またまたmixi本だが、私の生活は、趣味も仕事も、インフラとしては、mixiがあることを前提として成り立ち始めている。自宅においては部屋ごとにパソコンがあるし、外出時においてはケータイでチェックするようになってきた。もちろん、このブログもケータイでみているのだが、友人の中では、もう完全にケータイに移行している人もちらほらでてきている。 私もすっかりmixiにはまっている人間の一人だろうなぁ。そういえば、昨日、久しぶりに知り合いの事務員さんをmixiに招待した。だが、どうもまだうまく登録できていないらしく、気になって何度もチェックしている自分を、なんとも可笑しく感じる。 ネット上の常識(コモンズ)ができつつある。もっともっとしっかりしたコモンズがでてくるだろう。mixiに限らず、限定的なSNSもビジネス上で出来つつあるらしい。しかし、私も実験してみたが、他のSNSサービスは、まだまだ参加者が充実していないし、mixiではなくて、そちらを使う、という積極的な理由がない。 日記を書いて5分間レスがつかないと不安になる、なんてぇことはありえないが、でも、あんまり急にマイミクさんが増えると、mixi疲れがでてくるのも事実だなぁ。近々、「mixi動画」も開始とのことだし、またまた嵌りそう。みなさん、ほどほどのお付き合いをお願いします。
2007.01.31
コメント(0)
-
未来のアトム<4>
<3>より続く「未来のアトム」 田中伸和 2001/7 アスキー 構想から出版にいたるまで、2年を要したという本書であるだけに、実に多くのテーマが網羅されている。新書で言えば、10冊以上のテーマと量があるだろう。ともすれば散漫になってしまい、本来の中心的テーマがぼけてしまいがちだが、本書の成功は、タイトルに「未来のアトム」というものを持ってきたように、実に具体的であり、また多くの読者と容易に共有できるイメージを追いかけたところにある。そして、テーマ自体が、ロボットと作ることでも、科学や哲学の優位性を主張するところでもなく、人間そのものにたいする探究心を最後まで貫きとおしているところである。 コンピュータやAI(人工知能)が、今の原理のままで、どんなに高度化しても、「意識」や「心」を持つことはありえないだろう。それは明らかであるように私には思える。p600 ここが結論である。 結論からいえば、今のままのメタファー(暗喩)で考えられている限り、「鉄腕アトム」は実現しない。つまり、人間並みの知能、知覚、感情、意識、心を持ったヒューマノイドは実現しない。 もし、「鉄腕アトム」が実現するとしたならば、それは従来の「鉄腕アトム」というメタファーを超えたときである。p616 もし、今、あらたな質問として、22世紀ネコ型ロボット「ドラえもん」は実現可能か、と問われてば、即座に、「それは不可能だ」と断言してしまうことは可能だろう。だから、唐突に「鉄腕アトム」は実現可能か、と問われれれば、簡単に「不可能だ」と断言することは、できないわけではない。 しかし著者は、その質問をひとつの契機として、現代科学、思想哲学、宗教神秘主義について、広く思索する。そして、容易に想像できた結論に到達するわけだが、その結論自体は、人類に対して絶望感をもたらすものではない。 SF小説が好んで主題に取り上げるようには、ヒューマノイドに簡単に「意識」や「心」が発生することはありえないことは確実であるように私には思える。 このことは、逆にいうと、私たち人間が、誰しも、実に驚嘆すべき能力を宿しているということである。私たちは、自分たちが宿している驚嘆すべき能力について、あまりにも無知なのである。p600 本書は、私にとってはとても啓発的だった。大冊なので、読むのは、ちょっぴりしんどかったが、最後の最後まで、こちらのハートをわしづかみして離さない。ただおしいのは、この本は、2001年にでた本であることである。改定版の「第二版」が2003年にでているようであるので、そちらでは多少のデータ更新されているのだろうが、むしろ、最近「進化の『謎』を探れ!」という共著を出しているようなので、著者に対する興味関心や期待感を、そちらのほうに移していこうと思う。<5>につづく
2007.01.31
コメント(0)
-
心のマルチ・ネットワーク 岡野憲一郎
「心のマルチ・ネットワーク」 岡野憲一郎 2000/9 講談社現代新書 ちょっと古い本だが、タイトルからして気になっていたので、目を通してみた。やはり本には読むべき時期、読まれるべきタイミングというものがあり、情報や学問的成果としてはやや旧聞に属するものとなっていた。しかも、私の誤解は、人間間におけるネットワークをマルチにとらえるというイメージを最初に持っていたことだった。 もし、それを展開してくれるとするなら、それはシングラリティ・カテゴリで追いかけていたテーマであったが、この本は、あくまでも個人の心における、さまざまな要素のネットワークについて著者なりの理論を展開している。 後半部分において、景山民夫とみられる作家について論述している。久しぶりにこの直木賞作家について思い出した。割目すべき活躍のあと、新興宗教といわれる団体に属することで、人生の転機を迎え、1998年に事故で亡くなった。享年50歳。 この本で提示されている理論は、たぶんだが、現在においては、多くの研究者達によって、類似の理論が展開されているはずであり、その方向性は大きくは間違っていないだろうと思う。心理臨床家として、このような本を書くことにより、自らの立場を整理し、論理の整合性を図っていくことは、常に必要なことと思われる。真面目な本だ。
2007.01.30
コメント(0)
-
「神秘と超能力」の嘘
「『神秘と超能力』の嘘」 大槻義彦 1997/5 講談社 1994年から「噂の真相」に連載した記事を膨らませて一冊になったもの。火の玉教授が、いわゆる超能力者たちをまな板に上げている。対象となっているのは、宣保愛子、富田隆、タカツカヒカル、サイババ、青山圭秀、オウム、村上龍、矢追純一、織田無道、ライマ、X-ファイル、立花隆、などなど。 数日前、大槻教授の生家の近くをドライブした。例年になく雪の少ない霊峰からの吹き降ろしてくる涼しげな風の中の牧歌的な農村風景である。このような環境の中で、彼は火の玉を見たのだろうし、また真実探求の想いを強くしたのだろう。 村上龍は、山岸隆との共著「『超能力』から『能力』へ」を出したことを批評されている。その本が、こんな風に利用されているとすれば、かんがえものである。私も実はスピリチュアル・コンベンション(略称すぴこん)に行った時、一冊無料でもらった。 この本について、SNSの日記に書いたら、思わぬ人からメールが届いた。その人は、以前から「パパベル」(だったかな)とかいう商品の愛好者で、たいへん役に立ったという。ああ、そう、と相槌は打っておいたが、私はさっそくその書き込みを削除した記憶がある。 われらが世代の芥川賞作家・村上龍が、こっぴどく批判されているのは忍びないが、まぁ、このトンデモ商品の広告塔をさせられていることはまちがいない。この商品の開発者・2000年に亡くなっている。 最近の「あるある大辞典」での、納豆データ捏造事件での騒動は、番組そのものをみていないので、コメントを避けるが、私個人にとっては、納豆はダイエット効果あることはまちがいない。私がいままでいろいろ試したなかでは、一番の効果があった、ということはできる。 ただしいろいろ補足がある。もともと、僕は納豆が大嫌いだ。通常ならほとんど食べない。ところがダイエットしようと思い立った時になると、なぜか朝食の納豆がおいしく感じるのである。ある意味、納豆をおいしく食べられる、というのは、僕が健康に向かっているときの重要なサインだ。だから、鶏が先か、卵が先か、という論争になるが、すくなくとも、「僕が納豆をおいしく感じている時は、ダイエット効果が上がる方向に向かっている」という事実はある。 なんとか真理教、とか、なんとかの科学、などという団体もあるが、本当の真理や本当の科学はなかなか見極められるものではない。すくなくとも大槻教授のように「科学者」と自分を規定して世の中をぶった切り続けることはできないが、科学的な目でもって、常にものごとを観察し続ける姿勢は必要であろう。すくなくとも、データをいつわる、ということがあったのでは、それは、科学ではなくて、やはり詐欺としかいえない。
2007.01.30
コメント(0)
-
スピリチュアルメッセージ<3>愛することの真理
「スピリチュアルメッセージ(3)」愛することの真理 江原啓之 2003/12 この方の本を買ってまで読もうとする気はまったくないが、図書館の開架にちょこんとあれば、ちょっと手にとってみてみようかな、と思わせる、なにかの魅力がある。先日読んだシリーズにもそのような魅力は確かにある。 この本の著者は、正確に言うと、「私」であって「私」ではありません。前書と同じく、私の指導霊(ガイドスピリット)であり、良き助言者でもある昌清霊(まさきよれい)のメッセージを、私の肉体を通してお伝えしたものです。p2 なるほどそういうことだったのか。チャネリングや交霊、お筆先などは、私自身の体験から考えても一概に否定してしまうべきことでもない。その体験なり才能を伸ばすには、それなりの努力と機運、時間が必要となる。 本書は江原啓之氏とその指導霊(ガイドスピリット)である昌清霊(まさきよれい)との交霊会の記録をまとめたものです。指導霊とは、みなさんがよくご存知の守護霊のなかの独りで、職業や才能、趣味を指導します。 昌清霊(昌清之命マサキヨノミコト)は戦国の世に生き、もともと京都御所護衛の職にある武士で、のちに出家をし、修験道の行を積み、加持による治療に長けていた人でした。p4「本書を読まれる前に」 本書はシリーズの三冊目にあたる。前作でどのようなことが書かれていたか詳しくはないが、この「愛することの真理」に文字として書かれている内容は、特に抜書きしてメモしておく必要を感じるところはない。むしろ、文字面よりも、このようなメッセージを受け取るときに、必然的にその言葉に備わっている「説得力」というものを、どう感じるか、評価するか、ということがテーマになるであろう。-----------<1><2>は半年後に読んだ。
2007.01.28
コメント(0)
-
文明の憂鬱
「文明の憂鬱」 平野啓一郎 2006/1 新潮社 2000年から2005年にわたって、著者が雑誌に書いてきたエッセイを一冊にまとめたもので、もともとは2002年に著者最初のエッセイ集としてでたものをさらに増補して文庫本化されたものである。著者の作品は、いくつか読んだが、本来、小説家なのだから、小説をよまないで著者を考えるのは、まだ早いかも知れない。 1975年生まれということだから、1995年にようやく20歳になったということになる。芥川賞を受賞したのは23歳の時、当時最年少の受賞者であったということである。それこそ、新世代、新人類といわれるべき世代の代表者であるべきだが、他はさておいて、この一冊において、私は、老成した、むしろ保守的で、旧人類的な趣きさえ感じる。 本書は「Voice」誌に2000年1月に書いた「『玩具』と『ペット』」から始まっており、ソニーが1999年11月に25万円で売り出した家庭用子犬ロボット「AIBO」について書かれている。そしてまた、911のことは「既視感」で書いている。ひとつひとつが雑誌の連載で書かれたエッセイだから、全体的にこまぎれだ。ある意味、今でいうところのブログで書かれたものを、まとめたような感じさえする。 僕らの時代の芥川賞作家というと村上龍がいる。76年「限りなく透明に近いブルー」を「群像」で読んだ時は、僕は22歳。読んだ直後、僕はいよいよ、アレンギンズバーグの「吠える」日本語版がでた、という感想を持った。その翌年私はインドに渡って、あまり日本の出版のことなどわからなくなって、その後の村上龍の作品などほとんど読まなかった。 文学者とか小説家という職業は、それだけの才能と努力にささえられていることは当然のことであろうが、時代の目撃者としての位置もあるに違いない。私は村上龍どころか村上春樹もまともに読んではいないが、時代時代で、その世代の代表的な「語り部」を配置して、そのグランドマークと自分の位置の違いを確認しながら、人生を送っていく、というのも、文学の使い方のひとつであるにちがいない。 平野啓一郎、未知の可能性を秘めた新しき「語り部」として、たくましく、のびやかに、その使命を全うしてくれることを祈る。
2007.01.28
コメント(0)
-
Googleのすべて
「Googleのすべて」 検索しか使わないあなたは損している! ROAD TO WEB2.0 2006/8 インプレス 1994年に創刊され2006年5月に休刊した「インターネットマガジン」の最近の注目すべき記事を柱にしながら、ムック形式でGoogleを中心にまとめた一冊。この1994~2006という期間がなんともいい。そして「インターネット」を冠する雑誌が休刊した、ということに、Web1.0終焉の悲哀を見る。 そして、その残り火を「Goobleのすべて」にかける、というのだから、なんとも涙が流れるではないか。時代はひとつ、終わったのである。そして、次世代へとバトンタッチをしようとしている。Googleについては、このブログでもなんどか取り上げてきた。いまさら、内容について、どうのこうのと言ってもしょうがないだろう。 今「男はつらいよ」48作目をみながら、このエントリーを書いている。NHKBSで2年がかりで全作を放映してきたシリーズが今日で終わるのだ。これはこれで懐かしい。阪神淡路大震災でボランティア活動をしている寅が映っている。そうか95年は、「男はつらいよ」が終了した年でもあったのか。この年こそ日本におけるインターネット元年だった。ここで時代は切り替わっていたのだ。そして今、インフラとしてインターネットは当たり前の存在となり、時代はさらにWEb2.0へとシフトアップした。 Googleがけっしてやらない2つのこと Googleは、自らは取り組まないビジネスとして明言していることが2つある。「コンテンツを創り出すこと」と「それを保存すること」だ。あくまでも、他社によって生成された情報の体系化と検索性を高めること」が使命なのである。p035 本書はさまざまなGoogleの気になるサービスをさまざま紹介している。ひとつひとつは、もう僕には利用しきれないほど、いっぱいだ。「検索しか使わないあなたは損している!」なんて言われても困る。そういえばまもなくあと数日でWindows Vistaとやらが発売になるらしい。こちらも本当のことをいうと僕にはもう必要ないほどよけいなかざりがつきすぎている。いまだにWin2000で十分に感じている私がいる。「Google が発見した 10 の事実」ユーザーに焦点を絞れば、「結果」は自然に付いてくる。1 つのことを極めて本当にうまくやるのが一番。遅いより速い方がいい。ウェブでも民主主義は機能する。情報を探したくなるのは机に座っているときだけではない。悪事を働かなくても金儲けはできる。世の中の情報量は絶えず増え続けている。情報のニーズはすべての国境を越える。スーツがなくても真剣に仕事はできる。すばらしい、では足りない。 p074時代は刻々、未来へと続いている。
2007.01.27
コメント(0)
-
図説ユング 自己実現と救いの心理学
「図説ユング」 自己実現と救いの心理学 林道義・著 1998/6 河出書房 小さな本だが、前頁アート紙にカラー印刷された、とてもきれいな一冊。「ユング心理学の入門書や解説書は無数と言っていいほどに出ている」p126ということだが、ユングの人生を伝記のような形で読んだのは初めてだった。先日読んだ「瞑想とユング心理学」以来、どことなくユングのほうに引かれる。 無意識体験は、とくに神体験は、本人が望んでも望まなくても、まさに「向こうから現れて来る」ものだからである。「神はやって来る。思いもよらない姿で」ということこそ、ユングの無意識探求の結論であった。p53 フロイトの夢判断もそうであったが、ユングにおいても、夢は大きなテーマとして取り上げられている。特にユングの場合は、自分自身の夢そのものが大きな意味を持っていた。それを多くの図版として残している。一枚一枚が美しい。もともとはインドのリンガを連想するような突起物であったり髭を生やした老人と美少女だったりしたが、次第に、上下左右対称を多く用いた幾何学模様も多く描くようになった。ユング自身が科学的な探求者でもあったが、同時にまた神秘家でもあった。 ユングは心霊現象や超心理学現象に対して非常に強い好奇心を示し、それを科学的探究の対象にすることに野心を燃やしていた。ユングは狭い意味での医学の勉強よりも、こうした時代の関心事である非合理的な現象に興味を持ったのである。しかし、それを研究する方法はあくまでも合理的でなければならない、というのがユングの基本的な考え方であった。p24 フロイトと出あったのは、今年から丁度100年前、1907年、フロイトが51歳、ユングは32歳であった。年齢的な関係や、社会的な活動歴から、二人の間には、父と子、ともいうべき関係があったとされる。本人達もそういう意識を持っていた。フロイトは、ユングを自分の仕事の第一の後継者と考えて、それぞれに要職につけたが、兄弟子アドラーとフロイトの葛藤などを見ながら、フロイトには距離をおいて活動するようになっていった。 ユングについては、これからも何回か触れることもあるだろう。マンダラパターンや、インド哲学や、チベット密教、「死者の書」などについては、このブログでは不可避的みちゆきである。UFOなどについての積極的な取り組みもユングの魅力である。本書は、「図説」とあるだけに、図版がいっぱいあって、とてもカラフルにユングの伝記や業績に触れることのできる好著である。
2007.01.27
コメント(0)
-
スピノザ 「無神論者」は宗教を肯定できるか
「スピノザ」 シリーズ・哲学のエッセンス 「無神論者」は宗教を肯定できるか 上野修 2006/7 NHK出版 著者が前作「スピノザの世界・神あるいは自然」を執筆中に依頼され、同時に書いていたと言われる一冊。それぞれに個性はことなる。かたや講談社の現代新書の中の一冊、かたやNHK出版の「哲学のエッセンス」シリーズの中の一冊。おのずと性格は違うが、どちらかというと、こちらのほうがよりわかりやすい。私がだんだんとスピノザ的言辞に慣れてきたせいであろうか・・・? 『国家論』はスピノザが晩年になって書いていたもので、彼の死によって最後のほうの民主制論に入ったあたりで未完になっている。もう敬虔の文法の話ではなくて、国家を、それ自身の法則で何かができている一個の自然固体という観点から考察している。だから社会契約の話がでてこない。統治権は契約の文法によってではなく「群集の力」(multitudinis potenitia)によって定義されるのである。p73 ここでようやくマルチチュードという言葉がでてきた。いままで私が読んできた本のなかで、カタカナではなくて、アルファベットでこの単語がでてきたのは、初めてかも知れない。すでにネグリ&ハートの一連の著書によって注目を浴びている語彙であるがゆえに、説明ももう少し細かくされている。 スピノザはこういうふうにして各人の力との差として現れるアノニムな力を「群集の力」と呼び、人間集団がひとりひとりの人間に対して何かをさせるリアルな力として考える。「群集」のラテン語multitudoはちょっと訳しにくいが、多くのものの集まりという意味である。その際みんなが同じ意見で一致している必要はぜんぜんなくて、要するに同じものをそれぞれの理由で恐れたり期待したりしていればそれでよい。p75 このようにして、文脈の一部だけを、キーワードの説明するために切り出すことは、著者にとっても、スピノザにとっても不本意だろうが、まずは、このようにして、スピノザ的世界に近づこうとしている一人の読者がいるのだ、ということで許してもらおう。ここまで読んできて、まだまだそのレトリックやいわゆる本髄を理解しているわけではないが、スピノザが立っている位置は次第に明らかになりつつある。 最後の章のテーマはこのすれ違いである。ここにはきっと、西洋近代が解けずにいるいわば「スピノザ問題」とでもいったものがある。『神学・政治論』はあの時代、ほとんどだれにもまともに受け入れられることはなかった。その孤独は今も終わっていない気がする。p85 この「スピノザ問題」を継承する形で、ネグリ&ハートが提示した「マルチチュード」問題が、ネット社会の現出などの現実を見据えながら、より多くのリアリティを生み出すことを期待する。
2007.01.26
コメント(1)
-
顔のない裸体たち
「顔のない裸体たち」 平野啓一郎 2006/3 新潮社 今日も実は、エントリーを書いたあとに、アップする途中で失敗。せっかく書いた文章がパーになってしまった。もう同じことは書けない。もうこうなったら、箇条書き。1)最初、この本、私むきじゃないなと思った。2)もうどうでもいいこと書いてるなと思った。3)「ウェブ人間論」の対談者の片割れじゃなかったら、こんなの読むか、と思った。4)これが芥川賞作家かよ、と思った。5)だんだん猟奇的内容になってきた。なかなか止め時がない。6)だんだんわかってきた。作者は男も女も恋愛も書いているわけではないのだ。7)ネットにおけるエロスとタナトス。8)ネットがなかったら、このような集団的エロスが存在することもなかったかもな。9)でも、結局は、人間は原寸大を生きている。10)小品だから、最後まで読めた。提示されているテーマは重い。11)梅田望夫とは確かに対極の視点からネットを見ている。12)シンギュラリティと対極というか対をなす<マトリックス>のカテゴリの世界だ。13)平野啓一郎、あなどるべからず。
2007.01.24
コメント(0)
-
瞑想とユング心理学
「瞑想とユング心理学」 ウォルター・オダージンク原著 湯浅泰雄・監訳 安藤治・是垣正達・訳達 1997/11 創元社 原書1993 トランスパーソナルつながりで安藤治を検索したところ、図書蔵書リストにあったのでリクエストしていた本。ユングはいつかゆっくり読もうと思っていたが、こういう形でユングと遭遇するのも素晴らしい。監訳が湯浅泰雄となっており、このブログでも何冊か関連書籍を読んできたが、私にはこの系譜はなかなか適応しやすい流れであるようだ。 この本の著者オダージンクについては何もしらないが、極めて読みやすく、ああ、こういう本ならいいのに、と安心して読めた。ただ、必ずしも読書というものは、面白い、読みやすいというだけではあまり益がないことも多く、やや難解であったり、批判的心情を書き立てられたほうが、結局は自分に役立つことが多い。 この本、なぜ読みやすいのかなぁ、と考えてみたが、もともと原著が1993年に書かれている、ということがあるだろう。この辺までの流れは、私なりに把握できているということにもなるだろうし、時間が経過してコモンセンス化している、ということもあるだろう。でも、もし言うとするなら、1938年生まれのオダージンクはチューリッヒで訓練を受けたユング派分析家、という側面があるのかもしれない。 ニューヨークで開業している、ということだから、ある意味、アカデミズムの学者にありがちな融通の聞かない難解さを避けていることも幸いしているかもしれない。同じチューリッヒで訓練を受けた河合隼雄は1928年生まれだから、彼より10年若い。1993年オダージンク55歳の時の著書である。 本書においては、「黄金の華の秘密」が盛んに引き合いに出される。すぐさま私はモンジュの訳したOshoの「黄金の華の秘密」を思い出した。そういえば、この本もまだじっくりとは読んでいなかった。そういえば、abhiの書いた「魂の螺旋ダンス」の中に、「その源流は、神智学会によるインド思想再発見にあり(中略)ラジニーシもそれらの思想的達成を継承する形でp197」というような表現があり、ちょっと気になっていたのだが、いわゆるトランスパーソナルな流れが60年代あたりまでに形成されたとして、その流れをどのような位置でOshoが見ていたのか、関心のあるところだ。 また、Kヨタカの書いた本の中で、アジズは「Oshoはある小さな寺院で7年間、タントラの修行をして悟りを得た。」p87と言っている。私はそのことについては、確たる情報は何もないが、そのように想像することは年代的にも状況的にも難くない。21歳で大悟し、28歳まで何らかの磨きをかけた、ということは有りうる。ブッタの大悟にしても35歳と42歳の両説があり、なかなか興味深い。 1928年、ヴィルヘルムは『黄金の華の秘密』(原題は『太乙金華宗旨』)とい瞑想法の本をドイツ語に訳し、ユングに対して、心理学者の立場から解説してくれるよう依頼した。p274 この本は、西洋と東洋の瞑想を繋いだユングにとっても、かなりエポックメイキングな重要な一冊となっているようである。このオダージングの本が私にとって読みやすいのは、いわゆる東洋的瞑想に対する西洋人的理解がよりユング的であるからだろうと思われる。オダージングは、日本におけるいわゆるトランスパーソナル心理学の代表として紹介されるケン・ウィルバーには、ある一定程度の距離をおいている。 ウィルバーは、東洋の思想に対して共感的姿勢は取っている。だが、彼はみずからの西洋的無意識と元型的背景から抜け出せないでいる。彼はまた、心的統一性を組織し包括する一体性の元型にとらわれている。彼は思考タイプであるため、その元型が彼の理論上の概念を通して働いているのである。p218 このような批判が的を得た正しいものであるかどうかは分からないが、私は共感して、このような部分を読み進めることができる。トランスパーソナル心理学という括りは、日本においては80年代においてC+Fの吉副伸逸あたりを中心に紹介されてきたことが多かった。70年代においては、Oshoの本が翻訳され始まったが、グルジェフやクリシュナムルティとて、Oshoの本に引きづられるように翻訳が始まったという印象がぬぐえない。 吉福は1987年に出した月刊「アーガマ」編集長・松澤正博との共著「意識のターニングポイント」p139の中でこういっている。吉福---それと、やっぱりぼくは、「トランスパーソナル」というものが日本に入ってくるのは、ちょっと早かった、という気がしている。ぼく自身、ここのところ何年か、トランスパーソナル心理学を日本に紹介しようとしてきたわけだけど、やはり、アカデミックな視点からみると、やっとユング心理学が定着してきた状態だと思う。日本側のスピーカーの一人だった樋口先生の話でも、河合隼雄さんも実際には2,3年早すぎるといっていたというから。その点では同じ意見だね。p139 この対談集は、84~86年に阿含宗からでていた月刊「アーガマ」に連載されたものをまとめたものである。今でも続刊されているのかどうか知らないが、私は、もともとこの阿含宗(あるいは桐山靖雄ながれ)と吉福のつながりが気になるのである。77年に彼が編集長として出した月刊「メディテーション」という雑誌も桐山関連の平河出版からでている。 なにもセクト主義に陥る必要もないのだが、吉福を中心とした80年代の「グルイズム批判」というものが、もっぱら外来のOshoなどだけに向い、自らにとってもっと身近であったはずの桐山「管長」を故意に見逃し続けた罪は重いと、私は思う。90年代に起きたオウム事件も、麻原や早川をはじめ、桐山ながれの人物達によって起こされていることを忘れてはいけない。あの時、何故吉福や松澤は、同じ「グルイズム批判」を自らに向けなかったのか?、今でも不思議に思う。 そんな疑問がいまだにとけないので、私には吉福に対していまだに襟元をひろげる余裕がなく、また吉福が中心となって紹介したウィルバーは、周辺の挟雑物がじゃまになって今だに読めない本となっている。いつまでこのトラウマを抱え続けることになるのか、今の私には分からないが・・・。 さて、脱線につぐ脱線になってしまったが、「瞑想とユング心理学」この一冊はとても共感できる読みやすい本だ。オダージングの視点も優れて私向きだ。湯浅や安藤という訳者陣も私向きだった、ということができるのかも知れない。
2007.01.23
コメント(0)
-
裸のサイババ パンタ笛吹
「裸のサイババ」 ぼくたちの外側に「神」をみる時代は、終わった。 パンタ笛吹 VOICE 2000/12 先ほど読んだ平野啓一郎「本の読み方」ではスロー・リーディングの必要性を教わったばかりなのに、早速、ななめ読みしてしまう本がでてしまって、申し訳ない気分だ。先日から借りてきてストックとなっていたこの本の貸し出し期限が今日で終わる。読まないで返すか、再貸し出しをしてもらって、熟読するか、はたまた、とにかく今日、目をとおしてしまうか。今回は最後の方法を選んだ。 現在までの私の読書は、まずはブログありきで、ブログに書く材料を図書館に借りにいくというスタイルであった。そして、特にリクエストせずに、開架図書を閲覧していて、気になる本があったら、ランダムに借りてきて、出会い頭に読んでみる、というスタイルである。 この本も実はその一冊である。特に読まないで過ごしてしまっても特に問題はない。読んでおいても問題はないだろう、という程度である。以前は、図書館から借りてきた本はほぼ目を通し、ブログを書いていた。ところが、最近は、仕事がいそがしくなってきたせいもあるが、だんだん専門書や長編の大作に挑むことが多くなり、どうしても冊数を稼ぐことができない。そこで仕方がないので、残念ながら読まずに返却することも若干でてきてしまっている。 さて、この本、著者とは顔見知りである。70年代初半からの旅仲間である。当時から彼は、あの長身で、なおかつ好奇心に満ち、また不思議な一面をも持った人物だった。その彼と再開したのは、95年に彼が共著で「アガスティアの葉の秘密」を出したことによる。この本に著者がかつての70年代の私が属していたコミューン活動の記録を書いていたので、読者ハガキで連絡をとっておいたのだった。 翌年、アメリカ在住だった著者から電話があり、彼の講演会の主催を引き受けることになった。その経緯については、ネットのどこかに書いてあるので割愛するが、とにかく90年代中盤に日本に戻って、新たな話題を提供してくれたことは間違いない。 しかし、アガスティアの葉にせよ、サイババにせよ、あるいは、イギリスのミステリー・サークルにせよ、彼は、乗りつつ覚めている、あるいは、覚めつつ乗っている、ということができる人なのだなぁ、と改めて感心する。 彼はたしかどこかで、サイババについては痛く敬服したような表現をしていたのではなかっただろうか。たとえば、テレビに出演した時は、ミステリー・サークルの権威のような顔していたが、個人的に一対一で話してみると、「あれは人間がやってるんだよ」と静かに断言するような、きわめてクリアな男である。 私はサイババの存在は、Oshoの存在と同じくらい前から知っているが、ちっともサイババに惹かれたことがない。これは残念ながら申し訳ないがごめんなさい。だから、サイババがどういうトリックで、どのように人々に接していたのかは、コメントしようがない。ただ、何回かは、テレビで見た。ビブゥーティという白い粉を、誰かに現物を見せてもらったこともある。 しかし、サイババのシステムを私は最初から必要としていない。だから、あえて、この本のタイトルのように「ぼくたちの外側に『神』をみる時代は、終わった」と2000年当時に宣言されたとしても、私の目にも届かなかったし、耳にも入れる必要がなかったのであろう。 サイババの数々の所業については私はあまり関心がない。この本についてコメントするとすれば、最後部分にあたる「17章 グル時代の終焉と21世紀のニューエイジに向けて」というところである。内容すらもあまり私にとっては、引っかかるものがなかった。タイトルだけ言えば、この「グル時代」という単語を簡単に取り扱ってしまう姿勢。あるいは21世紀、ニューエイジ、といった紋切り型の言辞を弄するのは、2000年当時の流行だとしても、なんだか、薄ら寒いのだが、どうしてだろうか。 他の本を今は引用しないが、著者はたしか1999年の終末や、2000年問題(Y2K)について、自分のホームページでも大々的に問題視していたのではなかったか、と思う。いちいち言上げしないが、どうもそのような、さまざまなシーンが私の脳裏をかすめる。ひとりサイババばかりが批判されなくてならない、ということでもなさそうなのだが。 最近の私は、インド哲学の最深部とも言われるウパニシャッドを聞こうと思って、すこしづつ準備に入っているところである。いままでもそれに触れては来たのだが、どうやらこちらの自分に準備ができていなかった。これからはすこしづつ、体制を変えていこうと思っている。キーワードは、全体性、受容性、信頼性である。だから、読むべき本も、「出会い頭」もすこしづつ減ってくるし、「批判的」もすこし減ってくるだろう。好意的、というだけでもなく、ポジティブというだけでもない。 もし、サイババが、人々をそのウパニシャッドの最深部に招こうとして、ビブゥーティなどのテクニックを行使していたとしたら、そのテクニックが災いして、そこから人々はさらに深い部分へと進めないことになり、ちょっと残念だ。私はそのような挟雑物などがあるとすれば、注意深くそれらに足をとられないようにしながら、もうちょっとウパニシャッドの方へ、足を進めてみようと思っている。
2007.01.18
コメント(0)
-
本の読み方 スロー・リーディングの実践
「本の読み方」 スロー・リーディングの実践 平野啓一郎 2006/9 PHP新書 「ウェブ人間論」を手に取らなかったら、平野啓一郎という作家に目を停めることはなかっただろう。私は別に「速読」に関心があるわけでもなく、本が好きなわけでもない。しかし、ここに及んで「スロー・リーディング」という言い方に、それなりに共感を感じないわけでもない。 このブログの再スタートのきっかけにもなった梅田望夫「ウェブ進化論」については、一読だけでは不満で、一ヶ月ほどかけて、ゆっくりと私なりに「熟読」した。もちろん、それでこの本の内容を全部理解した、ということにはならないが、少なくとも「斜め読み」で済ましてしまうことのできないなにか凄いものを感じたから「熟読」したのであったと思う。 さてその続編ともいうべき「ウェブ人間論」は、読むには読んだのだが、今いち印象がうすいのは何故だろうと思った。梅田については「シリコンバレーは私をどう変えたか」などを読んで、すこし情報を補強したので、わりと人物のイメージができた。ところが、この平野啓一郎という作家については、ほとんどなにも知らないのであった。 そこで図書館に行ったのだが、10数冊ほどある蔵書のほとんどは貸し出し中であった。それだけ人気がある作家である、ともいえるだろう。ようやく私の番にまわってきたのが、この本と「顔のない裸体たち」である。この本も読み始めているところだが、先日読んだ「顔という知能」に対応していてなにやら可笑しい。 さて、私の読書のスタイルは、読みたい本があったら、1)タイトルを見、その種類を確かめ、2)前書きと目次を読み、3)気になるところがあったら、まずそのページを先取りして読んでしまい、4)後書きと著者プロフィールを読み、5)それからおもむろに本文を急ぎ足で読んでしまう、というものである。最近は、これに、6)気になるところには付箋をつけておき、7)その付箋の部分をもう一度読み返しては、2~3箇所についてブログにメモしておく、というスタイルになっている。 この私の読書方法は、速読でもなければ、熟読でもなく、ましてや著者のいうようなスロー・リーディングでもないだろう。まぁ平均的な読み方だとは思うが、この読み方は、新書本や研究書のようなものには向いているかもしれないが、小説やSF、ノンフィクションなどのストーリー性を重んじるような本には、向いていないようである。 現在も実は、最新のSFであり、このブログの重要カテゴリをタイトルに持つ「シンギュラリティ・スカイ」を平行して読んでいるところであるが、なかなか進まない。ひょっとすると挫折するかもしれない。そこで、訳者あとがきに用語解説が書いてあったので、忘れないうちに、こちらに転記しておく。 シンギュラリティとは特異点、つまりある基準のもとでその基準があてはまらない点のことで、重力に関する特異点はブラックホールを生じさせる。しかし本書では、SF作家ヴァーナー・ヴィンジが、本職の数学者として1993年に発表した論文「<特異点>とは何か?」(SFマガジン2005年12月号に向井淳訳で掲載)で提唱した、科学技術の幾何級数的進歩によって現在からは理解も予測もできない段階へと世界が到達する時点を指す(ブラックホールのほうのシンギュラリティは”特異点”と訳した)。多くのSF作家がポスト・シンギュラリティをテーマにした作品を執筆しているが、もっともまっこうからとりくんでいるのが本書の著者、チャールズ・ストロスだ。ストロスが、シンギュラリティの原動力になるはずのコンピュータの専門家であることが、その大きな理由になっているのだろう。ヴィンジは、シンギュラリティが起こるのは2005年から30年にかけてだろう予測していた。インターネットで検索すればたいていの専門用語の意味がわかるようになっている現状は、まさしくシンギュラリティの予兆と考えられないだろうか?「シンギュラリティ・スカイ」p541 ストロスの著者紹介では、「1964年生まれ。薬剤師として働いたが、大学に再入学しコンピュータ学科を学んだ。卒業後はプログラマーやテクニカル・ライターやLINUXとオープンソース・ソフトウェアを専門とするフリーライターとして働いた」というプロフィールを紹介している。ここまでの段階で私はこのSF小説にとても惹かれるのだが、いざ本文となるとなかなか読めない。現在70ページほど読んだところで中断中である。 本題に戻ろう。平野啓一郎のこのPHP本を読んだのは、必ずしも「スロー・リーディング」が私に新たなスタイルとして必要である、ということではなかったが、いみじくも好タイミングであった。なかなか示唆に富んだ内容である。しかし率直に言って1975年生まれの31歳の青年としては、すこし老成しすぎているような保守的なイメージさえある。この人がなぜに梅田望夫と「ウェブ人間論」を著わすことになったのか、私はちょっと首をかしげている。 平野のいうごとく、私はもう一度「ウェブ人間論」をそのうち読み直してみようと思っている。そして、平野のキャラクターがわかってきたら、もうすこし、その「人間論」とやらがわかってくることになるだろうか。ちなみに、今、読み始めている「顔のない裸体たち」は、まったく別なイメージである。
2007.01.18
コメント(0)
-
未来のアトム<3>
<2>より続く「未来のアトム」 たとえば、一つの脳に複数の身体が結びついたケースを考えてみよう。これは、つまり、身体は異なるものの、精神は同じである、共通である、というケースである。永嶋(史朗)氏はこれについて、こう述べる。 「そこで生じるものは、集合的無意識みたいなものかもしれませんね。地球全体が電子網で囲まれて、そこから、なんとなく意識のようなものが生じる可能性もないとはいえません。これからどういう方向に進化するかはわかりませんが、地球全体が”自意識の海”になる進化の方向がありうるような気がします」 心理学者のユングは、人類は、種族の違いを超えて、原始・未開の心性を共通に持つとした。それが、ユングがいう集合的無意識である。p150 ここで言われている「地球全体が”自意識の海”になる」という状態を、とりあえず私はシンギュラリティと名づけて、このブログのカテゴリとしている。完全に人間を離れた機械としての集合的無意識ではなくても、たとえば、人間の可能性をはるかに大きくしてくれた半人間半機械的存在、それをサイボーグというかもしれないが、とにかくそういう状態になりうる可能性は十分ある。 たとえば、人間より早く走るためには、かつてのアニメのエイトマンのように二足走行ではとても、新幹線を追い越すという構造では無理だろう。そこには、車輪なり、リニアモーターなりの発明が必要だ。 ライト兄弟が鳥のように飛びたいと考えたとして、羽ばたく鳥の羽の模倣をしていたら、最後まで飛行機は完成しなかった可能性もある。 私たちがいまインターネットで体験しているものは、まさに集合的無意識の実体化ではないか、とさえ思える。 「人工脳」を規模的に拡大していけば、「地球規模の『人工脳』を実現することだって原理的には可能です」と下原(勝憲)氏はいうが、地球規模の「人工脳」ができた場合、使い方次第では、恐ろしいことが起こりうるかもしれない。 テロリストとかが「人工脳」を悪用して、コンピュータを操作し、社会を大混乱におとしいれるといった自体も想定されうる。デガリス(・フーゴ)氏自身は、そうした危険性を念頭に置いて、「人工脳の研究には賛否両論あるだろう」と述べているとのことである。p160 このことはまさにWeb2.0でGoogleなどが直面し始めた問題である。別に「テロリスト」の手におちなくても、このようなシステムは、つねに人間個人個人の自由を奪ってしまう可能性は十分ある。「悪用はしない」というGoogleの誓いを信じるとしても、いつの間にか詐取されるという可能性はゼロではない。 そこで、広瀬(茂男)氏に「知と身体は切り離せると考えてよいのでしょうか?」と尋ねてみた。それに対する広瀬氏の答えは、「(切り離して)考えてもいいんじゃないかと思います」というものだった。 むろん、話がここまで進むと、今の段階では実証的な話ではなくなり、かなりSFの領域に入ってしまうのは避けられないが、私自身の考え方を述べれば、私自身は、「知と身体は切り離せない」と考えている。p175 人工知能とロボットは、互いの距離を測りながら、互いに進歩していく可能性があるだろうが、この段階で、私には、人工知能は近未来のうちに、人間から独立した新しい生命体になる、とは思えない。ただ、地球上の人間の意識を集合し、あたかも、一つの巨大な知能、巨大な意識のようなものとして繋いでくれる可能性は大きいと思う。いや、むしろそうなりつつあるのであり、その実用性を多いに活用すべき時代にきていると思う。 そして、その巨大な知能ができつつあるのなら、それに繋がったロボットは、良識ある新しい住民として、たとえば介護ロボットとか、交通整理ロボットとかのように、人間の管理下で働き続けることは可能になるだろうし、現在、ほぼ、科学はそこまで進歩してしまったように思われる。衛星システムとナビシステムのようなイメージで私はそう思う。 カントは、その主著『純粋理性批判』において、時間と空間は、人間に与えられた先験的な思惟形式にほかならず、人間の思惟はその枠組みを超えることはできないと断じた。 要するに、人間の思考の可能性と不可能性ーーその境界を見定めるというのが、カントのいう「批判」である。「批判精神」とは、カントにおいては思考の深さの別名である。 この本を書いている私の基本的なスタンスは、カント的な意味での、つまり、言葉の本質な意味での「批判」をなんとか展開したいということになる。 p176 私は著者のこの姿勢を諾とする。著者は科学をし、哲学をしている。そして、科学と哲学の間の領域において、なんらかの線引きをしようとしているかのようである。しかし、この段階において、著者は「瞑想」に触れることができていない。まだ「不可知」に向けた、「全体性」「受容性」「信頼性」に舵を取ることはできていないように思える。つづく
2007.01.17
コメント(0)
-
未来のアトム<2>
<1>よりつづく「未来のアトム」 ブログで数を稼いで多く読んで書いていくには、新書本くらいの軽い読みものが向いているようだが、これからは、全体性や信頼性、受容性ということをテーマとして読んでいくなら、気にいったものゆっくり、全部読んでいくという傾向になっていかざるを得ない。この「未来のアトム」も相当に面白い。本当にゆっくり読んでいくなら、凄く時間がかかりそうだ。 「生きる延びる」ことだけを目的としたサバイバルロボット(92p)というものが紹介されている。 サバイバルロボットは、太陽電池によってエネルギー供給を行い、動き回る。つまり、このサバイバルロボットが生き延びるためには、太陽電池が絶対に必要だということだ。 そのため、サバイバルロボットは、太陽電池に当たれる場所を常に捜し求めるということになる。太陽光を探し当てると、そこで充電する。そうすることによって、生き延びられるというわけだ。 キャタピラーが付いているから、障害物も乗り越えることができる。いくら探しても、太陽光を探し当てられない場合は、「夜だ」と判断して、サバイバルロボットはスリープモードになる。眠るのである。ムダに電力を消費することがなく、サバイバルしやすいようにできているのである。p92 まさに、サバイバルセンターに属する第一身体的ロボットというべきか。 「人間とは何か?」という問いは、人間永遠の問いであり、解答を手にした人は誰もいない。 そしてまた、「人間とは何か?」という問いは、必然的に「生命とは何か?」「心とは何か?」「意識とは何か?」「自分とは何か?」「自意識とは何か?」といった問いを、次から次へと派生させる。 哲学、心理学、生命科学といったあまたの学問、そして宗教も含め、人類のさまざまな営みは、いずれも、この問いに答えようと努力してきたわけだが、解答は得られていない。p118 これが原点であり、このためにこの本は書かれ、ロボットもその探求のために研究されていると、著者には見える。 「人間とは何か?」ということを考える上で、「死」は見落としてはならない重要かつ決定的なファクターである。 しかも、人間は自分が必ず死ぬということを自覚している。他の動物も、もちろん、すべていずれは死ぬが、「死の自覚」を認識のレベルでこれほど強固に持っている動物は、おそらく人間だけだろう。p121 この本におけるロボット学を通じての人間学には相当に深いものがある。もっと書きたいが、とりあえずお昼休み終わり。つづく
2007.01.17
コメント(0)
-
究極の錬金術<13>
<12>からつづく「究極の錬金術」 図書館から借りてきた本をいろいろ同不順で読み続けていると、Oshoの本はいろいろな点でユニークだ。まずは、その本は科学的探究でもないし、哲学的思索でもない。小説でもないしノンフィクションでもない。新書のように学者がとりあえず分かりやすく書いた入門書でもないし、もちろんベストセラーを狙った戦略的企画本でもない。 かといって、玉川信明さんがまとめたOshoのガイドブックは、なにか内容のダイジェストだけで、概略を「理解」することが出来るかもしれないが、その本を読んで自分が「変わる」という体験までいくか、というところが疑問だ。 この「究極の錬金術」一冊を読み始めてみると、幾通りにも読みすすめることができるようだ。最初は、とっくに一通り読んでしまっている。二度目は、細かく引っかかりながら読もうとしたら、これがどこまでも堂々巡りになってどうにも進まなくなり、一旦休止してしまった。これは3度目のチャレンジだ。私はこのOshoの声をどのように聞くのだろう。最初の聞き方は、論理を通してのものだー理知的二番目はフィーリングを通すものー感情的三番目は実存を通すものー実存的論理を通して聞く時、あなたは自己の実存の一部分を通して聞いている。フィーリングを通して聞いている時も、あなたは自己の実存の一部分を通して聞いている。三番目は最も深い、最も真性な「聞く」という次元は、自己の全体性ー肉体、マインド、精神ー 一つの全体として、また一体性を通して聞くというものだ。この三番目の聞き方を理解して初めて、ウパニシャッドの神秘に深く入っていくことができる。三番目の聞き方の伝統的な言い方は「信」だ。とすると、区別ができる。論理を通す聞き方は「疑い」だ。フィーリングを通す聞き方は「愛、交感」だ。実存を通す聞き方は「信、信頼」だ。 p12 いままでは、このブログでは、出会頭に、出会う本を一冊一冊読んできた。疑いというほどの疑いももたなかっただろうし、愛や交感というほど感性を全開にして聞いているわけでもない。さて、ここでのあらたなテーマは「信頼」だ。そして全体性である。全体性が働くのは、深い受容性の中だけだ。何一つ能動的ではない。全てが静かだ。あなたはなにもしていない。あなたはただここにあるーただの現存ーそして扉は開かれている。その時初めて、ウパニシャッドのメッセージが何であるかが理解できる。 p14さぁ、ここからは、信頼、全体性、受容性、などがテーマとなる。<14>につづく
2007.01.16
コメント(2)
-
未来のアトム<1>
「未来のアトム」 サイエンス・ノンフィクション 田中伸和 2001/7 アスキー 「ネット社会と未来」というカテゴリの次のステップとして、グローバル・ネットワークを大きな一つの超巨大なスーパーコンピュータとみたてて「シンギュラリティ」というカテゴリを掲げてみたが、その仮定や説の実証としてロボットや人工知能の世界を垣間見ることになった。ロボット関連の図書も一通り目を通して、それなりに納得する方向にきたので、そろそろ最後の1~2冊というところで、この本にであった。 「アトム」というタイトルからして、簡単に読み飛ばせるものと考えていたが、とてもとてもそのような本ではなかった。まず第一に分厚い。なんと636ページある。しかも文字は2段組みである。量的にも一晩で読めるようなものではなかった。二つ目に、本書の内容が実に説得力があり、分かりやすい。三つ目に共感する部分がとても多い。そういうことで、この本を読了するには、しばらく時間がかかりそうなので、とりあえず、なんどかに分けてエントリー記事を書いていこうと思う。 この本を好きになったのは、著者に親近感を感じたためともいえる。著者は私と同じ年代に生まれ、私の住んでいた市内にある大学で学んでいる。まだ66ページまでしか読んでいないので10分の一しか読んでいないことになるが、その論旨は極めて明瞭で納得共感できる。本文を引用すれば誤解もすくないのであるが、こころはとりあえず、暫定的に私が理解したことをメモしておくことにする。1)鉄腕アトム、は人間の手によって作られることはない。しかし、未来においては、別な形での鉄腕アトムが作らえる可能性はある。2)ロボットは人間を超えることはない。科学が進んでも、人間としての存在をこえることはない。ただし、人間の一部機能を超えて、より正確迅速大量に行なうことはできるようになる。3)人間の意識が解明されることはない。しかし、人間の意識を解明しようとする動きは永遠に続く。 いままで読んだところでは、そのようなことが書いてある。当たり前と言えば当たり前なのだが、この結論に達するには、それなりの調査や推論・議論さまざまな思惟活動が行なわれている。ロボット産業は、日本のお家芸である。日本政府が後押しをしている。アメリカは実利的でないので、ロボット産業に参入するのを戸惑っている。西欧においては、キリスト教の影響下にあるので、人間が新しい「生命」や「意識」を作り出す、ということに、神学的な躊躇がある。時には背信的匂いさえある。 しかしながら、知能や意識、感情、生命の探求が、その正しさを実証するにはロボット研究というものは欠かせない。この研究はどこまで続くのか、日本の本領が試されつつある。この本が書かれたのはすでに2001年であるから6年前ということになる。もっと最新の研究や報道によらなければ、より真実は見ることはできないだろうが、この著者のここまでのスタイルは、私にとっては、とても共感できる部分が多い。 既知→未知→不可知、という階層の中で、科学的な理性や、哲学的な感性を忘れず、なお、積極的な意味において神秘的な不可知性を認めようとする真摯な態度は、地球人スピリット探求者として、大いに学ばなくてはならない姿勢だと思う。つづく
2007.01.15
コメント(0)
-
電脳進化論 ギガ・テラ・ペタ
「電脳進化論」 ギガ・テラ・ペタ 立花隆 1993/2 朝日新聞社 出版されたのが世界的にインターネットが開花する以前である1993年。スーパーコンピュータを中心に論旨が展開する。立花隆のようなライターにだけ許されるような、カラー挿画やイラストがたくさんあって、非常にワクワクするような本。僕が読んだのは1996年12月にでた第3刷だが、かなり売れた本だったのだろう。このあと、立花隆は1997年12月に「インターネットはグローバル・ブレイン」を出す。こちらは、出版当時すぐ私も手にいれて読んだ。 私は、80年はじめのマイコンブームからコンピュータの展開する世界にには魅せられてきたが、あのまま世の中がコンピュータから、スーパーコンピュータへと展開していくなら、とてもとても手の届かない世界として、あきらめるしかなかっただろうと思う。この本のでた1993年当時もワープロやパソコンをもってはいたが、ハードディスクすらついておらず、電話線でたまに通話料金を気にしながらパソコン通信をやる程度だった。 1995年のインターネット爆発から、著者も、いままでのスーパーコンピュータ依存から、一気にインターネットへと視点を変換していった。そういった意味では、この「電脳進化論」はちょうど端境期に存在した記念碑的一冊と言えるかもしれない。 我が瞑想会のパートナーP君は、某国立大に3台しかないというスーパーコンピュータの保守管理をしているSEだ。ときおり、時間をみつけては、その世界のことを聞いてみるのだが、シロートの私にはそこでどんなことが行なわれているのか、想像もできないが、パソコンなら私にもイメージができそうだ。しかもそのパソコンがネットワークして「グローバル・ブレイン」となるというのだから、凄い。 2001年頃になると「立花隆先生、かなりヘンですよ」なんて本もでてきて、その「知的巨人」ぶりにややかげりがでてくるのだが、私などは立花隆的とんちんかんな楽観主義には実は多いに手を叩いていたほうだ。今後も私はシロート的悲しさで、あちこちの袋小路に入り込むことが多いことだろう。 科学者が絶対正しい、ってこともない。哲学者だけしかいけないって世界もないはずだ。瞑想者であるがゆえに理解されない個的な理解ってこともあるだろう。今後も試行錯誤しながらも、一人の地球人としてのスピリット探求は続く。
2007.01.14
コメント(0)
-
人間がサルやコンピューターと違うホントの理由
「人間がサルやコンピューターと違うホントの理由」 脳・意識・知能の正体に科学が迫る ジェームス・トレフィル著 家泰弘・訳 日本経済新聞社 1999/2 原著1997 なんだか、この長たらしいタイトルは草思社の一連の邦訳本を連想するが、もともとは「ARE WE UNIQUE?」私達は独創的なのか、というのが原題である。その答えはズバリこうなる。 かつて神秘であったものでも、その多くは科学の合理的思考の守備範囲に取り込まれてきている。意識の問題の最前線においても将来何が起こるかを推測するのは、私にとって、競馬を観戦していて馬券を買うときに、これまで出場したすべてのレースで勝った馬に投票すべきかどうか尋ねられるようなものだ。その馬が次のレースにも絶対勝つと証明することはできない。かといって、その馬に賭けないというのもまったく愚かなことだろう。p278 この本は、1999年に翻訳された本だが、原著は1997年にでている。まさに世界的にインターネットが爆発的につながりはじめた時代であり、まだ、この時点では、コンピュータチェスは、人間に勝つことができなかった。しかし、現在では、IBMのチェスコンピュータは、人間のチェスチャンピオンに勝利することができるようになって、何年も経ている時代である。ネットの進化も尋常ではない。はるかな変化を遂げてきている。 しかし、そのような変化を考えてみても、この本の姿勢は、誠実であり、今でも読む価値のある一冊のように思える。本書においては前半部で、生物学的考察やバイオテクノロジーについての言及に多くのスペースを割いている。私はこのブログをスタートするにあたってネット社会でつながる人間の意識はどうなるのか、というところに一番の関心をもっていたので、工学的な研究が主に視野にはいっていたのだが、ここに来て「マトリックス」というカテゴリ創設にからませて、これらのバイオの世界について学習しなくてはならないのだなぁ、と強く感じるようになった。 後半は比較的コンピュータ関連なので、読んでいて理解しやすかった。しかし、バイオテクノロジーなどが、実際に作られ得るのかどうかというのは、まだまだ五里霧中といっていいだろう。 コンピュータのような機械ははたして意識をもちうるのだろうか?(中略)人間が意識をもつのと同等の意味で意識を有する機械を作ることが可能ということになるかもしれない。あるいは、多くの人が「意識がある」と認めるような一連の属性をもつ機械でありながら、人間の脳とは似ていないもの(つまり、人間とは異質の意識をもつもの)を作ることが可能ということになるかもしれない。あるいはまた、そもそも意識や人間の脳を真似えうような機械を作ることは不可能という結末になるかもしれない。私が主張したいのは、それがまだ答えの見つかっていない問題だということだけである。p300 なんと誠実な解答であろう。千万語を費やしたあとの結論として、私はこの結論を諾とする。「それがまだ答えが見つかっていない問題だ」として、きちんと把握しつづけることは大切だ。科学的な探究心を失ってしまってはいけないし、怠惰になって哲学的な思索を怠ってもならない。そして、いたづらに神秘性を否定するところに走ってもならない。自分の二本の足で歩きながら、自分の頭で考え、自分とは誰かを瞑想しつづける、一人の地球人でありたい。巻末に参考文献リストがあったので、追記しておく。著者推薦『DNAに魂はあるか』フランシス・クリック 1995 原著1994『数学から超数学へ』エルンスト・ナーゲル 1968 原著1958『皇帝の新しい心』ロジャー・ベンローズ 1995 原著1989『言語を生みだす本能』スティーヴン・ピンカー1995 原著1994『人と話すサル「かんじ」』スー・サベージ・ランボー1997 原著1994『心は薬で変えられるか』スコット・ヴェッジバーグ 1998 原著1996訳者推薦『マインズ・アイ』ダグラス・ホフスタッター 1992 原著1981『コンピューターは考える』パメラ・マコーダック 1983 原著1979『クォークとジャガー』マレイ・ゲルマン 1997 原著1994
2007.01.14
コメント(0)
-
ロボットは心を持つか -サイバー意識論序説ー
「ロボットは心を持つか」 -サイバー意識論序説ー 喜多村直 共立出版 2000/11 工学の専門家が哲学の世界に切り込んでいくというスタイルの本書は、正直言って読解するのが難しい。テーマは非常に面白いが、工学と哲学における広範囲な知識を要求される。まして、発行されたのが2000年11月となっており、テーマから考えると、現在の2007年にいたるまでの経過の中で、さまざまな工学的&哲学的な進化があり、かならずしもアップデイトな話題になっていないのがおしい。 この著者の近書なら面白かろうとググッてみたが、どうやら寡作な研究家らしく、さらに遡ること5年、1995年に『人間と機械の共生』があることを確認したのみである。もし、近未来的にこの研究者が新たな書物を著すとしたら、注目に値すると思う。 『ロボットは心を持つか』というタイトルの割りには、極めて難解な抽象論を扱っている本である。むしろサブタイトルの「サイバー意識論序説」のほうがずばり内容を表している。デカルトの心身二元論に端を発する著者の遠大な試みは、哲学、心理学、神学、工学、社会学など学際領域への多岐にわたる言及が続くので、大学の講義などで数年間かけて学ぶ教科書としては面白かろう。しかし「序説」としては大いなる視点を与えてくれるだけで、必ずしも、科学として実証領域まで降りてきていないのが、おしいと言えばおしい。 著者もそこをわかっているので、200ページに渡る難解な論点を、「終章」として箇条書きにまとめている。その8つの箇条書きの結論の結論部分では、こう書いている。 ロボットは、人間の機能の延長として作られ、人間の機能や構造の一部を積極的に模倣して作られる。そのために、すべての人間機械論は論理的にトートロジーに陥る。一方、人間と機械の差異を素材の差異に還元する「反人間機械論」の主張はカテゴリミステイクに陥る。人間と機械は共進化するため、その差異は時代の技術に依存すると共に、機械を模範モデルとした人間理解は時代の技術に依存する。p198 結局は、あたりまえの結論ということができる。哲学が提起した「人間とはなにか」「私という意識とはなにか」「私とは誰か」といったテーマは、科学的技術的に証明され実証されるだろうが、技術が進化しないことには、人間とはなにかといった一連の哲学的テーマは解明されない、と言っているにすぎない。まさにトートロジーに陥っていると言える。 ここにおいては不可知なものの存在を予感させる素振りはあるものの、積極的に不可知なものを不可知として感知していこうという姿勢は、見られない。このブログにおいては、人間を取り巻く不可知な領域は無限大に広がっている、と想定する。そして、その領域において人類ははるか昔から哲学的な思索を続け、科学によって実証してきたとする。しかしながら、いまだに、圧倒的に不可知な部分がほとんどで、哲学が及ぶ範囲や、科学が到達した範囲など、ごくごく一部でしかない、という想定でいく。 なぜならば、不可知な部分がなく、ましてや未知なる部分に限界があるとすれば、いずれは哲学は終焉を迎えるのであり、科学もまた最終的にその進化を終えるということになってしまう。不可知な部分があればこそ、未知なるものの発見も続くわけだし、やがては既知なるものとして、我々人類は科学の生み出す豊かさを享受できるのである。 この本は、「シンギュラリティ」というカテゴリに分類するが、このブログにおいては、「マルチチュード」カテゴリに低通するテーマを抱えている。逆に、最近インターネット社会やオープンソース運動に共感を示しているマルチチュードの「哲学的」運動の潮流は、この本の提示するようなサイバー意識論へと、地下廊を通って、「シンギュラリティ」カテゴリへとやって来る可能性もある。 私のみるところ、「マルチチュード」にせよ「シンギュラリティ」にせよ、デカルト的心身二元論に端を発している限り、その人間理解には限界がかならずやってくるのである。では、それはどのように超えていくことができるのか、となれば不可知領域の「神秘性」をどのようにあつかっていくのか、にかかってくるだろう。本来このブログではそれを「アガルタ」カテゴリで扱おうと思っているのだが、まだ機は熟していない。 この本のテーマ「ロボットは心を持つか」について、心身二元論的言えば、ロボットはどこまでも進化して人間的な、より本質的な意味で人間的な身体をもつことになるだろうし、さらに人間の心理や意識も次第に解明されて、ソフトウエァのような形に置き換えられるものになるだろう。だから、将来的において、はるかに進化したハードウェアと、はるかに進化したソフトウェアが合体するということは有りうる。 そして、かつて人間の限界と思われていた行動や思考、たとえば超々長労働時間に耐えうるとか、遠大な計算を瞬時に処理してしまう、といったようないわゆるスーパーマン的な存在としては実現可能なのではないだろうか。その方向において、幾何級数的に進化しうると想定できる。でも、それは「人間」を超えたことにはならない。仮にいわゆる進化したロボットが「自立・自律」する存在になったとしても、人間を超えたということにはならないだろう。 なぜか。それはいずれは人類は不可知を受け入れざるを得ないからである。それはゼロの発見ともいえるし、無限大の発見ともいえる。その概念を受け入れないことには、ついには進化し続けることができなくなるからである。不可知な領域を受け入れながら、なお、未知なる探検と、既知なるものの実証をし続ける、そのこと総体を人間的活動ということになるからである。
2007.01.13
コメント(0)
-
顔という知能
「顔という知能」 -顔ロボットによる「人工感情」の創発ー artdificial emotion 原文雄・小林博・著 2004/8 共立出版 人工知能artificial intelligence、人工生命artificial life、とくれば、次は人工感情artificial emotionである。この人工artificialという接頭語は非常に便利なもののようだ。この調子でいけば、人工感性artificial feeling、人工精神artificial spirit、人工意識artificial conciousness、なんてでてくるのではないだろうかと思って、ググってみたら、やっぱりあるんだね。artificial heart。 顔ロボットの研究は、人造人間をつくる研究ではない。工学的には、知能機械システムと人間とのインターフェイスをどうつくるかという課題に対して、解答を見出そうとする研究であり、純粋科学としては、人間の知能を、人間とのインタラクションを介して、創発的方法論で合成的立場から明らかにしようとする研究である。p.iv 創発とは英語で"emergence"といい、システム理論や複雑系、生命科学の用語。システムを形成している個々の要素のレベルでは持っていない性質が、システム全体として振る舞う際に発現 emergeされることをいう(「≒部分は全体の総和以上である」)。近年ではネットワーク時代における組織論(コラボレーション論)やイノベーション論の文脈でメタファーとして用いられることが多い。 知性inteligenceに対峙する感情emotionということではなく、いわゆる総論的に人工知能と言われる中の情緒的インターフェイスを研究することによって、人間とはなにか、ということに最後は迫ろう、という研究、と解釈してもいいだろう。 ただ、情緒的なインターフェースと考えるなら、たとえば、アスキーアートのような「喜」(^o^)/「怒」(#`Д´)「哀」(T_T) 「楽」ヽ(´ー`)ノでも足りるだろうし、二足走行ロボットの顔面にディスプレイでも取り付けて、いろいろな表情がでるようにすればそれで足りるような感じもするが、どうやら、それだけでもなさそうだ。 たとえばソニーの犬型ロボットのアイボなどが、あまりに表現豊かになってしまっては、まさに人面犬ロボットになってしまい、ちょっと不気味さを通り越して、ゾンビ的な違和感を与えてしまうかもしれない。そういえば、犬の感情が分かる「バウリンガル」なんて商品があって、話題になったことがあった。 人間と人工物システムである機械との間で、バーチャル・コミュニケーションを実現するためにはAHI(Active Human Interface)の三つの機能を発現するインターフェースが必要であるが、そのインターフェイスは、ものごとの説明のための情報(説明的情報)と人の気持ちを伝える情報(感性的情報)とを取り扱い、それらの知覚と行動表現との対応付けである「高度知能」を持つものであろう。その人工的実現は、言い換えれば「人工の心理」、または「人工感情」の実現であり、工学と心理学との学際分野に「人工心理学」という大きな課題をなげかけている。p29 この本では、いわゆる顔ロボットに限定された研究が紹介されているが、実際は、非常におおきなテーマを抱えていることがわかる。つまりは、神秘学でいうところ7つの身体のうち、第一身体から第二、第三、第四身体へのステップアップの鍵を握っているのである。その研究は、端緒についたばかりと思われるので、今後の研究の進展に期待したい。 顔ロボットのような人工物システムが人間社会に導入されるとき、大きな問題がひとつ存在する。それは、従来からSFなどで物語られていることで、「人工感情」を持った「ロボット」と人間との共存をどう実現するかという問題である。「人工感情」はどうあるべきかは、その応用を考えるとき、重要な課題であり、工学のみならず、哲学、心理学、倫理学、社会学に携わる多くの学問が解決の道を探し求めることになるだろう。この問題は、人間がどうあるべきかに通じるところであり、数千年の学問活動を経ている現在でも、未だにその解を見出していない人間は、永遠にこの問題に悩むのであろうか。結局、顔ロボットの研究は、人工物システムをつくることから人間を知ることに繋がっているといえよう。p123 我が家にあるコンピュータミシンは、20年前に松田聖子がテレビで宣伝していた優れものだが、ちょっと困ったことがある。間違った操作をすると、音声で間違いを指摘してくれるのである。「押さえレバーを下げてください」「青いレバーを上げてください」。ちょっとした操作ミスをしただけで、毎回、この音声アドバイスに「叱られて」いる我が家の奥さんは、かえってイライラしているようだ。(#`Д´) あるいは、たとえばMS社のOfficeについているアシスタントは、秘書がでてきたり、イルカがでてきたりして、アイディアとしては面白いが、とてもうるさ過ぎて、すぐ消してしまう人がほとんどであろうと思われる。人間は感情の動物だ、などと言われるが、よく「感情的にならずに、ゆっくり話してみなさい」などとたしなめられるように、artificial emotionの実現&活用には、今後、さまざまな課題が待ち構えているようだ。
2007.01.12
コメント(0)
-
セレンディピティ・マシン 未知なる世界発見への航海
「セレンディピティ・マシン」 未知なる世界発見への航海 デビッド・グリーン著 羽山博・訳 2005/3 (原書2004) インプレス 最初、この本を読んでいて、あまり目新しいことも書いていないような感じがして、すこし退屈だなぁ、とあくびがでた。私の読書はもともと図書館の開架書庫に並べられている本を借り出してきて、目を通す、というものだから、情報としては必ずしも最新というものではない。時には20~30年前の本に手を出して読んでいることもしばしばだ。 この本は、2005年3月発行(原書2004)だから、その中にあっても比較的、あたらしい書物と言えるが、ドッグイアーと言われる技術革新の世界のこと、ほんの数年でも情報として陳腐になってしまったのだろうか、と思った。しかし、読み進めてみると、次第にその奥行きの深さがわかってきた。特に遺伝子工学などに触れた部分を読み始めたときは、これは、このブログ上のあたらしいカテゴリが必要かな、とさえ思った。 セレンディピティという言葉は、予期せぬ発見をもたらす幸運な偶然を表すものとして以前からよく使われている。これは、ホレス・ウォルポールという18世紀の英国人の小説家が造り出した言葉だが、もとは『セレンディップの三人の王子』という古いペルシアのおとぎ話が起源となっている(セレンディップは、現在のスリランカ)。そのおとぎ話は、主人公たちが世界を旅し、思いもかけないようなすばらしい発見をするというものだ。p4 この本は、現代の知的活動の広範囲について言及しているので、必ずしも特徴的にこの分野ということではないのだが、このブログで「シンギュラリティ」と対置的に考えている「マトリックス」というカテゴリについての足がかりを作ってくれているようである。 科学の歴史とは、自然を目の前にして人間がいかに小さい存在であるかということを人類が徐々に知る物語である。何世紀にもわたって、新たな発見がなされるたびに人間は宇宙の中心から遠ざかっていった。神の姿に似せて作られた存在から、最近になって進化したヒト科の動物であると考えられるようになったのである。その中で、動物や植物に備わる驚くべき能力の不思議さを知った。p192 まさに、既知→未知→不可知の途上にあると言える。この本は、まさにサブタイトルにあるように、未知の分野についての論述が多く、現在の情報工学や遺伝子工学の進化を踏まえながら、未知なる世界への挑戦について、多いに語る。 バイオテクノロジーはコンピュータとともに成長してきた科学である。遺伝子の配列とデータベースに記録された重要なデータを照合するという伝統的な方法は、初期の頃から確立されたものであった。このような活動は、バイオインフォマテッィクス(生命情報学・生体情報工学)と呼ばれるまったく新しい科学を生み出した。バイオインフォマティックスとは、分子生物学における情報の利用について理論研究や実験を行なう分野である。遺伝子の新しい配列を、関連するすべての配列と逐一比較していくことができるようになると、分子研究にまったく新しい次元が追加された。p228 かつて私達人類の探求というものは、ほとんどが宗教的な不可思議さで覆われていることが多かった。しかし、自己とはなにかという哲学的な探求がおこり、産業革命などを通じて科学的な目が、新しい発明品を生み出すことによって、不可思議な宗教的な世界がどんどん狭まれているように思われた時期もあった。現在、人類の知的な探求は、みずからの生命体としての「不思議」に挑戦しはじめている。 今や、子どもを持ちたい者はバイキング方式で精子を選ぶことができる。そこには、スポーツの有名選手やノーベル賞受賞者などの精子もある。だが、ヒトゲノムに関する構造と機能の知識が増えるにつれ、遺伝子工学により何が生み出されるか分からないという危険も増えてきた。当初から、胚の遺伝子検査についてはすでに多くの議論がなされている。つまり、胎児に異常がないかどうかを検査して確認できるということである。その意味はするところは、子供に異常があることを両親が知ると、中絶の道を選ぶかもしれないということだ。いつか、この倫理的な問題を完全に解決できるかもしれないが、ヒトの卵子や胚は、現在以上に選別され、遺伝子の強化を受けるかもしれない。p248 この部分は、まさにOshoの「受胎調節と遺伝子工学」についてのビジョンや言及を彷彿とさせる部分でもある。私には、にわかには何の判断もできない。しかし、このようなことがすでに可能になってきているということについて、古い「宗教的」倫理観で判断するのではなく、新しい「科学的」な実証的な判断が出来る時代が、そう遠くない時期にやってくるのではないか、と予想するのみである。 これまで、バーチャルリアリティを使ってコンピュータの中に現実の世界の一部を再現することがいかに有望であるかを見てきた。では、現実のシステム、たとえば地球そのものまでを、コンピュータの中に完全なモデルとして構築することが、どの程度実現可能なのであろうか。 (中略)現在のコンピュータのメモリ容量は、自然界のさまざまなシステムのサイズにほぼ匹敵するほどにまでなっている。たとえば、ヒトゲノムに含まれる全データも、多くの家庭で使われているコンピュータのハードディスクにも保存できるほどになっている。p279 最近のグーグル・アースなどのサービス提供のスタートを考えてみると、本当に地球全体をバーチャルにパソコンの中に見ることができる時代がやってくると思わわずにはいられない。また、もし、パソコンの中にヒトゲノムの全データを展開できるとしたら、シロート考えだが、それを操作してパソコンの中で生まれてくるべき子供の姿や成長過程をバーチャルに見ることができるに違いない。アニメや画像の自動生成ソフトを使えば可能だろう。あるいは、最新のロボット工学と連携したら、新しい生命体としてのサイボーグが生まれてくる、かも知れないのだ。 あえてこのような最新の、ともすれば思想錯誤にみちた意欲的な探求にも積極的な肯定観を持ち、未知なるものをどんどん既知なるものをしていく作業は限りなくつづくであろう。そして、さらにその向こうにある不可知なもの。この不可知なものについて探求や思索するのではなく、「瞑想」する、というところまでいけるかどうか、というのが、このブログに課せられた大きな使命である。
2007.01.12
コメント(0)
-
ブルックスの知能ロボット論
「ブルックスの知能ロボット論」 なぜMITのロボットは前進し続けるのか? MITコンピュータ科学・人工知能研究所長 Rodney A. Brooks著 五味隆志・訳 2006/1 オーム社 原書2002 著者は、原書がでた時点では、人工知能、あるいは知能ロボット論では、第一人者的なポジジョンを確保した人物と考えてもよいのだろうと思う。その思想の根幹は自ら創設したSA(サブサンクション・アーキテクチャ)理論にあると思われ、この20年間にわたって賛否両論を生み出してきたとされる。 その神経回路は十個ほどの簡単な演算素子からなり、センサ入力を駆動出力に繋いだ形になっていた。回路へは、入力から連続した信号が流れ込み、それに応じて途切れのない信号を出力側に送り出した。p70 この考え方は、人工知能(A.I.)から人工生命(A-Life)への発展の可能性を持ち、その途上において知能ロボットやサイボーグへの可能性を秘めている。 1986年に衝撃的な論文を発表したブルックスは、MITの一新米助教授に過ぎなかったが、その論文をめぐる激流の中で、87年に準教授、93年に人工知能研究所副所長と同正教授、97年に同研究所長、03年7月にMITコンピュータ科学・人工知能研究所(825名)の所長に就任したという。「米国とは言えども異例の出世を遂げた」ということだ。 ロボットにまつわる話題や研究は、多岐の領域にまたがっており、拡大する興味の範囲はつきない。しかしブルックスのロボット論は、極めて役に立つ理論であり、現実性の高い理論である。そのロボット観は、日本のアイボやアシモなどといったロボット群とはまた一線を画しているようだ。少なくとも、日本においてはブルックスの理論はほとんど研究されていないと言う。 それはなぜか。日本のロボットは、私の見るところ、神秘学的身体論の第一身体の完成を急いでいるかのように見える。それに対してブルックスの理論は、感性回路を拡大することによって、自立する生命体に向けて一歩歩みだしているところにあると感じられる。 さて、ここまでロボット論周辺を散歩していて思うことは、どうも私はロボット研究の成果物を利用することには多いに関心があるけど、開発するそのこと自体にはあまり関心がないのだなぁ、ということだ。既知→未知→不可知、という流れの中で、未知の領域から、しだいに科学が既知としてさまざまな発明品を生み出してくれるのはとてもありがたいと思う。しかしながら、結局、私は、未知→不可知の部分、特に不可知と呼ばれることになってしまう部分についてもっとも関心があるのだなぁ、と思う。 科学が物事を明らかにし、哲学がまだ私達が知らないことがあるとその見探検の領域を拡げながらも、結局、分かりえないもの。それは一体なにか、という魅力に取り付かれているのだと思う。それはともあれ、科学や哲学がどこまで進化しているのは、常に自分のセンサーを広げておきたいものだ。 話題は変わるが、小学生高学年の時、私は「鉄腕アトム」を少年サンデー(だったかな)で読んでいて、アトムの妹のウランちゃんが敵の罠にはまって、体を左右半分に断ち切られてしまうシーンが描かれていたの見た。そのシーンをあまりに魅力的に感じたのだった。しかも、その半身になってしまったウランちゃんの体の断面から泡が湧き出し、不足していた半身部分の形成してしまって、二つの体になってしまうのである。 私はこのシーンに異様に惹きつけられた。もっというなら、まだ射☆能力のなかった私の男☆器が☆起したことを思い出す。ウランちゃんがはいていたスカートが真っ二つに裂かれたことに興奮したのだろうか。いや、体の断面から泡が湧き出してくるというところに、むしろ☆的コーフンを感じたといっていいと思う。(楽天倫理規定による伏字あり) この性癖が昂じたら、私は、なんらかの猟奇事件にかかわった少年主人公になっていたかもしれない。幸いに、私はそうならなかったが、今でも強烈にあの漫画のシーンを覚えているのは何故だろう。そんなことをこのロボット論を読んでいて思い出した。 A.I.人工知能から、A-Life人工生命へと変遷していく過程で、機械人間→サイボーグ→新しき知的生命体という可能性が見えて来たとして、A.I.→A-Lifeのプロセスには、基本的な性理論が必要となるのではないだろうか。何故人間はセックスの快感に取り付かれるのか、なぜセックスは生命の誕生に深く関わっているのか。この点が、ロボット研究の周辺をうろつきまわっていて、まだ見つけることのできない領域だ。
2007.01.11
コメント(0)
-
人工知能のパラドックス コンピュータ世界の夢と現実
「人工知能のパラドックス」 コンピュータ世界の夢と現実 サム・ウィリアムズ著 本田成親 2004/12 工学図書 原書2002 原題は ARGUING A.I. The Battle for Twenty-first-Century Science 議論する人工知能 21世紀への戦い、という意味であろうか。A.I.とはartificial intelligence まさに人工知能。 ジョン、マッカーシーは「人工知能」(artificial intelligence )という用語を使いはじめたのがいつ頃からだったのか、いまでははっきり思い出すことはできないといっています。「人工知能」ちう言葉が科学専門用語として公式に認定されたのは、1956にダートマスで開催された人工知能に関するサマー・カンファレンスの場においてのことでした。マッカーシーはこの会議の幹事長でしたが、そのとき彼自身には、この用語の草案者が自分であったという明確な認識はなかったようなのです。p51 ということはすでに半世紀前にこの名称がでてきていたということになる。 マッカーシーは初めて「人工知能」という用語を使ったときの思いについて、「私はマストに旗印を高らかに掲げ、自分たちの研究目標が何であるのかを誰の目にもはっきりとわかるように示したかったのです」と語っています。p60 しかし当時は誰もが強い関心をもって応じたわけでもなかったし、どちらに転ぶかわからない「運まかせのクラップゲーム」のように不安を抱いていたのだと言う。1965年頃、MIT教授ドレイファスは「錬金術と人工知能」と題して、人工知能の批判研究報告書を書いたという。彼はいう かつての錬金術師たちの二の舞をえんじないためにも、私たちはいまこそ自らの立脚点を見極めなければなりません。人間の理性の働きというものを徹底的に分析して状況に左右されることのない明確かつ不安な諸要素にまで分割し、特定のルールに従ってそれらの要素を機械的に演算処理し復元をはかるなどということが可能なものでしょうか。 p69 そのようなA.I.批判を浴びながらも確実に科学は進歩し、21世紀になって、その成果が現れつつある。そのプロセスについてこの本に詳しい。 ハイテクの世界には宗教の世界とたいへんよく似たところがあります。ハイテク産業はその製品の売れ行きについて長期的な展望を立てることが困難であるという事情を抱えているため、この製品を絶対的に信頼し使い続けますという消費者の誓約をたくみに引き出すことによってその場をしのいでいくしかありません。そういうわけですから、あの手この手でユーザーの洗脳に努めたマッキントッシュの「販売促進伝道師」らの暗躍や、チャットを通じて「ウィンドウズ教」の聖なる教えの伝道に尽くしたマイクロソフト教会の宣教師らの忠誠ぶりにまつわる裏話には事欠きません。p93 この辺になると、半分笑い話としてきくこともできる。この本に展開されている歴史はパソコンの歴史と隣り合わせで同時進行してきたことがわかる。では、リナックスに対する記述がないかと思って探してみたらありました。映画『2001年宇宙の旅』を43回も見たというスタンフォード大学のストーク教授は、共同参画者を呼び込み、日常的な知恵の断片を寄せ集めそれらを普遍的な知識ベースにまとめあげることを目指している。 GNUイーマックス(Emacs)やリナックスのような人気のあるフリーソフトウェア・プロジェクトに啓発されたストークは、そのプロジェクトにでもできるだけ多くの人々に参加してもらいたいと考えているようです。 「私たちはできるかぎり多くの人々の知識を取り込み蓄積していかなければなりません。オープンソース・プロジェクトを検討してみるうちに、私は二つの重要な傾向があることに気づきました。プロジェクトごとの共同参画者の数は時を追うごとに増大しつづけています。1970年代のイーマックスの場合、共同参画者はおおよそ100人くらいでした。そして、リナックスの場合は一万人以上の研究協力者が集まりました。私は、将来的には一億人にも及ぶ共同参画者を集めることができるようなプロジェクトを遂行したいと考えています。」と彼は述べています。p205 ぶぶぶ、一億人の参加するプロジェクトとは凄い。でもすでにウィキペディアなどはそのようなものに近づいていく可能性はでてきたと言えるだろう。あるいは、限りなく1000万人に近づいているSNSもある現在である。一億人を魅了するプロジェクトがぜひでてきてくれることを願う。 ストークはいまひとつの傾向についても指摘しています。それは、共同参画者の数が増えるにしたがって、参加者一人ひとりの平均的な専門知識レヴェルが下がってきているという点です。ストークは、「20年代ほど前にフリーソフトウェアを作っていた人たちは真の意味でのハッカーでした。しかしながらいまからは誰もがその種の仕事に貢献することのできるようなシステムづくりが必要です。私たちがやらなければならないのは、できるだけ多くの数の人々を集め、彼らが容易に仕事に専念し貢献できるような環境をつくることなのです」とも語っています。p206この本はとても面白い内容だ。だが、なんだか読みにくい。何故だろう。予備知識がもうひとつ足らないこともあるだろう。人名や書名が錯綜していることもあるだろう。内容が抽象的なこともあるかもしれない。しかし敢えていうなら、既知→未知→不可知、という図式の中で、この本は、科学から哲学、そして宗教ともいえる部分にも、迫ろうとする姿勢があるからだろう。 「コンピュータ世界の夢と現実」という副タイトルをもつ本書は、まさに現実と夢の間をいったり来たりしているようだ。
2007.01.10
コメント(0)
-
Osho/gnu v0.01
某SNSのコミュで『 [OSHO mmp/gnu v0.0.1β]という名の宝石箱』というトピックを始めたのが、去年の3月、もう10ヶ月くらい前のことだ。その後、かならずしも急拡大にネットワークが広がっているわけでもないが、そのトピックの趣旨そのものについては、私の想いがますます強くなってきたのを感じる。 このブログが再スタートしたのと同時期のことだったので、本来は、このブログでは、このテーマを、もっと前面に押し出して展開するべきであったのかもしれないが、なかなか本筋にもどることができなかった。 ところが、本日、新年にあたって、新たな想いがつよくなってきた。前は「Meditation in the Market Place」というコミュにおいての展開だったので、その略称で、mmpという単語を入れておいたが、そのSNSを離れてもう少しシンプルに「Osho/gnu v0.01」という名前で、こちらのブログで展開できないか、と模索を始めることにした。 βをはずしたのは、特に意味はないが、すこし進めたほうがいいかな、という思いからである。本来、v1.0にならないと、本当のことがスタートしないのだろうが、はるかな目標地点に向けて、とりあえずのスタートを再宣言したいと思う。 そんなことを考えていたら、我がLinuxグル=セツのブログに「☆ [自由な世界] サニヤスのバザールとカテドラル(伽藍:がらん)」という文章が書いてあった。いつものシンクロがまたおきつつあるなぁ、と納得納得。 今年は、いよいよこのテーマでいろいろ展開ができるといいなぁ、と思う。
2007.01.10
コメント(0)
-
究極の錬金術<12>
<11>よりつづく「究極のの錬金術」 Oshoの新しい講話録「永久の哲学2」がでたようである。こちらを読み始めようとして、実は、まだ「究極の錬金術」をまだ書ききれていないことを思い出した。一時的にお休みをしていたのである。まずはこちらを読みすすめることが先決だと思う。 と、宿題を片付けるような気分でスタートしたのではあるが、必ずもそれに故がないわけではない。現在、「シンギュラリティ」というカテゴリで人工知能について考えてみているのだが、その文献を読み進めてみると、どうやら「人工知能」を考えたり作り出したりすることは「錬金術」のようだ、という表現によくぶつかるのである。それは、錬金術のように不可能なことに挑戦している、と読むこともできるし、錬金術を研究するように楽しいことである、と読むことができるである。 Oshoにおいての錬金術、ましてやこの本のような「究極の錬金術」と表現されることどもは、実はただ事ではない。それにコメントをつけようとして、実は前回は挫折した。今回は適当な章立てを区切りに、他の本を読みながら、それに関連付けながら、この本を読み解いていこうと思う。既知、未知、不可知という三つの言葉をまず最初に理解するように。というのも、ウパニシャッドは始まりのみが未知に関わっている。そして、ウパニシャッドは、不可知なるものを語ることで終わる。既知の領域は科学になり、未知の領域は哲学になる。そして不可知の領域は宗教に属する。哲学とは、既知と未知の間を、そして科学と宗教の間をつなぐものだ。哲学は全面的に未知に関わっている。何かが既知になると科学の一部になる。それはもう哲学の一部に留まらない。だから、科学が発達すればするほど、哲学は押し戻される。既知となったものは科学となり、哲学は科学と宗教をつなぐ。科学が発達すると、哲学は後退せざるを得ない。哲学は未知にだけ関わっているからだ。だが、哲学が先に進めば進むほど、宗教は押し戻される。なぜなら、宗教は基本的に、不可知に関わっているからだ。p9 最近「地球人スピリット・ジャーナル」を標榜するこのブログでの主たるテーマは、「人工知能」というところにやってきた。人間社会に現れたコンピュータ文化は、複雑に絡まりあうネットワークとして一つの有機的な知性を持ち始めているかのようである。この進化は留まるところを知らず、その成果はロボット製作などで実証され始まっている。まさにOshoのいうように、哲学は、科学の道筋を切り開き、科学の領域がまさにムーアの法則で加速度的に拡大しつづけている。 哲学は、ますます宗教の領域を切り開き、宗教はどんどん挟雑物を取り払われ、しだいしだいに純化され続けているかのようである。宗教は哲学に追いつかれ、そしてついには科学によって既知化されてしまうのか。 Oshoは、未知なるものは既知となるが、ついに不可知のままで残るものがあるという。あるいは、既知なる世界、未知なる世界が限りなく拡大しても、それでも在り続けるもの、それを不可知と名づけると言っている。<13>につづく
2007.01.09
コメント(0)
-
ネット社会の未来像 IT時代のジャーナリズム
「ネット社会の未来像」 IT時代のジャーナリズム 神保・宮台マル激トーク・オン・デマンド3 宮台真司・東浩紀・西垣通・神保哲生・水越伸・池田信夫 2006/1 春秋社 「ネット社会と未来」というこのブログのカテゴリを終了したと思っていたら、まさにその通りのタイトルの本があったのね、とちょっと本屋店頭で立ち読み。購入してじっくり読んだのであれば引用したいところもあるが、簡単に書きとめておく。 ただ、このブログでは「ネット社会」と人類の「未来」を対置的に考えてみたのであるが、この本では「ネット社会」の進化過程の「未来像」を読み解こうとしている。宮台真司は、私としては、あまり好みの学者ではないが、先進的な視点から挑発的な論陣を張る姿勢や、その彼の論調を支持する潮流の存在は、決して侮れない。 この本では「ネット社会の未来像」を「IT時代のジャーナリズム」というキーワードで読み解こうとする。 サイバー世界には何でもある。だけど、人の心だけはない。あいつぐ幼女殺害事件、子どもの安全を名目に着々と進む監視社会、テレビ局を飲み込むIT企業、不安に怯えて吠える都市の弱者たち、どこかで響く高笑いの声―サイバー・ネットワーク社会で、知らぬまに人の心を操るアーキテクチュラルな権力を読み解く。 カバー・コメント 私のブログにおいては「ネット社会」の進化過程として、必ずしもジャーナリズムやメディアというところに収斂させずに、「シンギュラリティ」と「マトリックス」にイメージを分散してみた。「シンギュラリティ」とは、ネット上のパソコンが全て有機的に繋がって、まさに一つの巨大な人工知能コンピュータとして機能し始めるイメージである。「マトリックス」とは、ビックバン以降、地球上の水分にあらゆる要素が溶け出して、前生命体であるスープ上の溶液が出来上がっていく過程のイメージである。 この本において、「サイバー世界には何でもある。だけど、人の心だけはない。」という極めて意味深なメッセージが書かれている。「人の心」とはなにか。どうもこの文脈では、道徳心のような、「心正しく生きる」というような用法で「心」がとらえれているようである。たとえば2ちゃんねるのようなコミュニティにおけるいわゆるネチケットの不備を嘆いているようにともとれる。 しかし、私は、このメッセージをネット社会というものの限界性として、「知性」と「胎性」は作れるけれど、「意識」はつくれない、と読み解こうと思う。あるいは、コンピュータやネット社会の進化によって、限りなく実現可能性が拡大し続けた時、ついに到達しえないものとして「意識」を定義づけてみようと思う。 「人工知能」は人間とロボットの合作から次第にロボットの限りない自立へ向けた過程の中で、その進化が実証されていくことだろう。あるいは「マトリックス」への試みは、バイオテクノロジーは、Googleなどの科学と医学のテクノロジーを融合させて、生物学と遺伝学の分野へ進出させる、という野心的な長期計画などで、達成されていく可能性が大きい。 だけど、「心」や「意識」は、今のところ、人間そのものがその「ネット社会」に組み込まれない限り達成はしえないのではないか、と想像する。ないしは、ロボットやコンピュータには作り出しえない最後の最後のものこそ、まさに地球人スピリットと呼ぶにふさわしいものではないか、と思う。そこにこそ、人間の存在価値があるのではないだろうか。
2007.01.09
コメント(0)
-
世界ロボット大図鑑
「世界ロボット大図鑑ROBOT」 ロバート・マローン著 2005/5 新樹社 いやぁ、実にカラフルな写真いっぱいのカラー図鑑です。ロボット大図鑑というべきか、お宝鑑定団カタログ集ともいうべき、マニア垂涎の一冊。いわゆるロボットいう言葉で連想する実在したロボット画像を一挙に掲載する。アニメやSFを加えたらさらにバリエーションは増えるだろうが、こちらはおもちゃのトイ・ロボットから、最近の人型ロボットまで網羅している。 さらに驚くのは、ロボットの世界においては、世界に先駆けて日本が圧倒的にリードしていること。純然たるトイ・ロボット第一号は、日本製のブリキのおもちゃ、リリパットとされている。1937年ごろに製造されたというから今から70年前、身長15センチと小ぶりながら、ゼンマイ式で、前進歩行した。 それから戦前・戦後を通じておもちゃロボットの世界は、70年代までメイドイン・ジャパンが圧倒する。80年代になると、アメリカから「組み立てロボット・キット」が出始める。バッテリーやマイコンまで搭載され、自分で動き、人間とのコミュニケーションもおこない、簡単な作業ならプログラミングすることもできたという。83年にでたトポは、マック・コンピュータでリモート・コントロールしたというから、時代の黎明期を感じる。 合体型ロボットや変形ロボットなどを経ながら、やっぱり現代の知能ロボットが世界的に話題になったのは、ソニーの犬型AIBOや本田技研のアシモの出た2000年前後となる。新世紀になると、デンマークからレゴ社から組み立て式のマインドストリームなどがでてくるが、いまや、各社が意欲的なロボットを思い思いに出して、まさに現在は「ロボット新世紀」という様相を呈している。 セキュリティ・ロボットやミリタリー・ロボット、手術用ロボットなど、さまざまな実用的なロボットが研究されているが、トヨタではパートナーロボットというコンセプトで、人の役にたつロボットの開発を進めている。ここまでくると、このブログの趣旨から外れていくので、深追いはしないが、ロボット研究がこのように人間社会に貢献することはすばらしいことだと思う。 何度も繰り返されていることだが、[アイザック・アシモフの作品に登場したロボット法三原則]を再掲しておく。1.A robot may not injure a human, or allow a human to be injured. 第一条 ロボットは人間に危害を加えてはならない。また何も手を下さずに人間が危害を受けるのを黙視していてはならない。2.A robot must follow any order given by a human that doesn't conflict with the First Law. 第二条 ロボットは人間の命令に従わなくてはならない。ただし第一条に反する命令はこの限りではない。3.A robot must protect itself unless that would conflict with the First or Second Laws.第三条 ロボットは自らの存在を護(まも)らなくてはならない。ただし、それは第一条、第二条に違反しない場合に限る。 シンギュラリティというカテゴリ・テーマから見ると、「役に立つロボット」はあまりに生活に近過ぎてどうもピンとこなくなるが、少なくとも、これだけ人類がロボットにかける夢は大きく、少なくともこういうものができるようになった現代というものはすごいなぁ、と思う。
2007.01.07
コメント(0)
-
知能の謎 認知発達ロボティクスの挑戦
「知能の謎」 認知発達ロボティクスの挑戦 けいはんな社会的知能発生学研究会・編 2004/12 講談社ブルーバックス 人工知能についての研究会の10人による共著であり、ロボットに対する哲学的・心理学的あるいは工学的な側面からの意欲的なアプローチ。 たぶん知能について考えるよい方法がふたつある。そのひとつが哲学の本をいろいろ読んでみることだ。AI(人工知能)やロボットの研究者には、哲学書をよく読んでいる人が多い。本章のメイン筆者である瀬名(秀明)も以前は哲学が苦手であったのだが、「知能」というキーワードを常に抱えながら読むと、哲学の本がすごく面白いことがわかってきた。いくつもの発見があるのである。例えば評論家の柄谷行人(1941~)が著書『探求2』の中で「単独性と特殊性を混同してはいけない」という話をしている。これは私達の知能を考えるうえでとても大切な本質を提示してくれていると思う。p14 ここまでは、ある意味、このブログがやってきたこと延長していくことで、どこかで接点を得ることができるようになるのは間違いない。 近年は遺伝子工学や再生医療の技術が発達したとはいえ、まだ人間そのもののシステムを理解する手段にはなり得ていない。生物科学の限界は、実際に自分の手でいのちをつくって検証してみることができない、ということに尽きる。 では、その限界を超えて、人間らしい賢さを研究するためにはどうすればよいのか? 先程、知能を考えるのにふたつのよい方法があると書いた。ひとつは哲学からヒントを得ることだったが、もひとつは何か? 私達にはロボットがある。p23 本書においては、ロボットを作ること自体は目的ではない。 知能に関する仮説を立て、ロボットを作って動かし、仮説を検証する。このようやり方を、従来の「分析的アプローチ」と区別する意味で、少し難しい言葉だが「構成論的アプローチ」と呼ぼう。構成論的なアプローチに基づいて認知発達ロボティクスという新しい方法論を確立することで、私たちは従来の科学の限界を超えて、人間の知能の本質に迫ることが可能なのだ。p26 ということで、「人間のような知能を持ったロボットを通して『知能』の研究がこれから始まる」ということである。この一冊は、あくまでロボットに対する「工学的」なアプローチではなく、「哲学」的アプローチを貫きながら、知能に迫るにはロボット製作が絶対に必要だ、と主張している。だから、当然のことながら、この、けいはんな社会的知能発生学研究会は、他の多くの学際的なグループとの連携なしには、成果を検証できないということになる。 にわかにロボットに目覚めた私には、なるほどこういうアプローチがあったかと、感動しきりで、かならずしも研究の途中経過であっても、その成果を十分に受け取ることはできない。しかし、このような視点があることを確認できただけで、今回は満足だ。 ここで単純に言っておけば、チベットタントラ密教などを中心に7つの身体論がある。サバイバル、意思、権力、ハート、創造、ビジョン、光明、と敢えて単純に言っておくとすると、現在のロボット工学はまずは第一身体であるサバイバル・レベルまでは作り得る自信を持ちえたのではないか。あるいは、意思、権力までは、なんとか作り得る可能性もほのかに見えてきているようだ。 しかし「知能」となると、一体、どういうことなのか。ロボットで検証可能かどうかはともかくとして、「知能」を探求するなら、第5身体のクリエイティブから、第6身体のビジョンまでは、いかなくてはならないだろう。科学の力は、いつかはこれらに達成することができるとしても、これらの研究の歩みを見る限り、そのゴールははるか遠くにさえ、見えてきてはいないようだ。
2007.01.07
コメント(0)
-
ロボットの文化誌
「ロボットの文化誌」 機械をめぐる想像力 馬場伸彦・編 2004/12 森話社 「ネット社会と未来」をテーマに108冊の本を読んでみたところ、その未来像として、二つのイメージが湧いてきた。一つは巨大な子宮や羊水を思わせるマトリックスの世界であり、もうひとつは、人工頭脳、人工知能という世界のイメージであった。ある意味「セックスから超意識へ」というOshoの本のタイトルを思い出したのだが、それはまぁ余談としても、そこから生まれてくるものとはなんだろうと思ったらロボットが思い出された。 そこでロボットをテーマとして本をさがしてみると、あるある、あれ~なんでこんなに隣にある本を見逃していたの、というくらい沢山の本がある。なるほどロボットか、と思ってこの本をめくってみると、まさに私が読みたいと思っていた内容をほぼまとめてくれていたような本だった。 映画『マトリックス』において印象的だったのは、仮想現実(マトリックス)と現実世界を接続させる配線や構造が剥き出しになった装置の類であった。あるいはまた重機械工業を思わせる地下都市のいかにも機械然とした古めかしい光景だった。それらは、複雑であるが、視覚的に理解しやすい「機械のある風景」であり、イメージに覆われた仮想のマトリックス世界をと比較して、優れて具体的で触覚的な世界であった。 P12 私のイメージはここでいうところの「イメージに覆われた仮想のマトリックス世界」なのだが、ロボットは「地下都市のいかにも機械然とした古めかしい光景」の延長線上に存在するマスコットのようなイメージがあった。しかしこの本は、そのような私のいままでの偏ったうえに限定的な私のロボット像をいとも簡単に破ってくれた。 『マトリックス』のなかで、仮想世界が機構を直接的に感覚することのできない現代都市に描かれ、現実世界が構造を剥き出しにした機械だらけだったことを思い出してほしい。基本的に仮想でしかない映画表現において、仮想世界と(映画内の)現実世界とを描き分けることは難しく、そのためリアリティと密接な関係にある「機械だらけの環境」を対置させることが、現実世界であることを観客に印象づけるために有効となる。機械とは実在であり、安定した物質世界を構成する一因子にほかならない。p16 『A.I』『未来との遭遇』『2001年宇宙の旅』などなどの映画作品がそのほか沢山登場する。 『ブレード・ランナー』を挙げるまでもなく、ロボットの<死>の問題は、人間の<死>の問題へと容易に転換される。つまり、ロボットの<死>の問題は人間の<死>への関心を招きよせる手がかり以上のものではない。どうやらキリスト教圏における、こうした問題に対する想像力は芽を出しこそすれ、成長する機会には恵まれていないようである。p226 漫画の鉄腕アトムが誕生したと言われる2003年までに、人類は、現実の「鉄腕アトム」を生み出すことはできなかったけど、ロボット研究は極めて速い速度で進行しているようだ。私が初めて本田技研の二足歩行のロボットを見たのは1998年だった。PTA役員をしていた中学校の生徒が本田のロボット研究所に手紙を書いたところ、そのロボットを4トントラックのコンテナにロボット一体を積んでやってきてくれたのだ。(生徒が手紙を書いたことになっているが、実は私達PTA役員の裏企画だったのだが) 当時はまだアシモという名前もついておらず、また、本体はもってきてくれたが、歩行はしなかった。当時はまだ本田技研も大々的に発表もしなかったので、本来はマスコミも呼びたかったが、それは本田との約束で出来なかった。でも、その研究過程のビデオを生徒全体の前で上映してくれたのだった。あれから日本のロボット文化は、はるかに進んでいる。 どこまで行っているのか、少し気になってきた。
2007.01.06
コメント(0)
-
SEの持つべき『思想』
「SEの持つべき『思想』」 できるSEは何を考え、どう動いているのか 秋月昭彦・瓜生聖 2003/1 すばる舎 このブログで、現代を象徴するような職業として、ジャーナリスト、カウンセラーと並んでプログラマを上げておいた。コンピュータ関連で食べている人たちを象徴的に言ってみたのだが、より専門的でクリエイティブな雰囲気がある。厳密に言えば、プログラマとSEとは、また違った職分だ。必要とされる技術も能力も違う。 この本では、さらにその職分を細分化して、●ソフトウェア知識、●プログラミング能力、●ハードウェア知識、●設計能力、●マネージメント能力、コミュニケーション能力、の6つの能力についてレーダーチャートで分析している。1)システムエンジニア(つまりSE) ほぼ満遍なく6つの能力が必要とされるが、ハードウェア知識については、やや劣っても構わないとされている。2)プログラマ こちらは、ソフトウェア知識とプログラミング能力は完璧を求められるが、そのほかハード知識がやや必要となる以外は、他の能力については特に求められない。3)システムアナリスト 設計能力とコミュニケーション能力を完璧に求められ、ソフトウェア知識、マネージメント能力も高いものを求められるが、他については、あまり問われない。4)プロダクトマネージャ マネージメント能力は完璧を求められるが、他はコミュニケーション能力とソフトウェア知識がそこそこあれば勤まるとされる。5)ネットワーク管理 ハードウェア知識がそこそこあれば、他についてのそこそこの能力があればよい、という評価だ。6)システム管理・保守 こちらは、6つの分野どれも高いものは求められないが、どれもほんの基礎的なものがあればよい。7)技術担当窓口 マネージメント能力とコミュニケーション能力があれば、他は高いものは求められない。8)コンピュータメンテナ ハードウェア知識、ソフトウェア知識があれば、他はあまりとわれない。 門外漢の私は、単純にコンピュータ関連と表現してしまうが、こまかく言えばこのような職分があるようである。そして、ソフトウェアのクリエイティブな面を象徴する職分としてプログラマは象徴的だが、本来はシステム・エンジニア(SE)となれば、外部との折衝など、一般の社会的なネットワーク能力が求められる。 つまりはSEが勤まるのであれば、他の職分は大体勤まるということになるのであるが、誰でもSEになれるわけではない。象徴的にはプログラマがより確立した職分なのだが、よりSE的な存在として万全な全人格的な存在になることを薦めているのが、この本の趣旨である。 必要最小限のコミュニケーションスキルの基本的な三つのポイントとして次のように列挙する。1)自分の考えを的確に言葉にする。2)相手が納得できる形を作る3)相手の立場に立つ p72 当たり前と言えば当たり前のことだ。これらのことが、SEに限らず、社会的生活には必要なことなのだが、これが、なかなか実行できないのが実際のところだ。「SEは『一生の仕事』にできるか、プログラマ30歳定年説」p33などを紹介しながら、読者層を20代のSE候補者たちに見立てて、さまざまなレクチャーが続く。 OSやアプリケーションの選定も同様だ。Windows嫌いのSEの中には、職場のマシンのクライアントのOSとしてLinuxを使っている人もいる。もちろんLinuxはすばらしいOSであるが、そのために他のすべてのWindowsユーザとのコミュニケーションが円滑にいかなくなっているのをたまに見かける。(中略) 自分だけの閉じた世界、自宅での趣味の世界であればそれは結構だが、自分が会社内で他ユーザのサポートをしなければならないのであれば、他のユーザが使っているOS、アプリケーションを選択するのは当然だろう。p59 この本はすでに4年前にでている本である。ドックイアーといわれるコンピュータの世界では、周囲の事情はどんどん変わっている。この言葉は、数年のうちに逆転する可能性もある。職場のマシンのクライエントがすべてLinuxに変わってしまったのに、Windowsを選択しようとするSEが残ってしまう可能性はある。時代はどんどん変わっている。 プログラマによく見られるのだが、自分の理想を「無愛想で変人、口は悪いけど腕は超一流」といったハッカー像に置く傾向が見られる。一般的に、無愛想であること、変人であること、そして口は悪いというのはデメリットだ。しかし、超一流の腕がそれらのデメリットを打ち消し、組織に「なくてはならない存在」と認識させられると考えているのだ。しかし、生粋のハッカーでもない限り、これはほとんどの場合「逃げ」にすぎない。p84 これは実はSEに限らず、一般的な専門職のすべてに言える。コミュニケーション能力やネットワーク能力を磨く努力を避けたい人が、専門職を選ぶ、という傾向もあるのだろうが、人間としては、どの職業、どの立場においても、人間としては磨かなくてはならない能力だと思う。 経験のないSEは、大抵システムやプログラムが「動いた」時点をゴールと見る。プログラムが正常に動作するのを確認したところで仕事が終わったと考えてしまうのだ。それに対して経験のあるSEは、プログラムが動いたという状態は、単に「システムの実現が可能であることを実証できた状態」という程度にしか判断しない。さらにそこから、連続稼動、エラーが起きたときの復旧のしやすさ、保守作業など、システムが稼動したずっと後のことまで考慮する。p114 これは、言葉を変えれば、販売の世界でのアフターサービスに対応するかもしれない。どの職分、どのサービスにおいても、キモに銘じたい言葉だ。「一度ひどい目に遭ったユーザが良い顧客となる」というところでは、次のように語る。 システムの構築で一度苦難を経験した顧客はそれなりの物差しができており、システムやSI会社に対する幻想も失われているので、比較的スムーズに仕事を進められることが多い。もし選ぶことができるならば、初めてのシステムを組む顧客よりは、一度システム構築に失敗している顧客をお勧めしたい。p151 この部分は、なんだか、恋愛問題を思い出して、笑った。まぁ、初恋は破れるもので、すこし傷つくことを体験したあとのほうが、深みのある恋愛の世界に入ることができるかも・・・・、なんちゃって。 コンピュータと人間、その両方を相手にしなければならないのがSEだ。SEとして働く限り、悩みがつきることはない。しかし、相手が人間であってもコンピュータであっても共通するのは、「何を求められているのか」という正しい目標の把握に尽きる。p165 職業であるかぎり、これはどの職業でもおなじことであろう。至言です。<頭を使う仕事は午前中に><可能な限り電話には出ない><打ち合わせは、頭の働きが鈍くなる午後にする><月曜日に打ち合わせはいれない><中だるみのする水曜日はいつもと違う仕事をする><いつでもメモを携帯する>などなど、大いに共感できる納得言が続く。「食わず嫌いは二流の証」ではこのようにある。 アンチマイクロソフト派の人にその理由を聞くと、「マイクロソフト社の戦略や体質が嫌いだから製品も嫌いだ」とか「一般にマイクロソフト製品を使っている人が多い、つまり初心者ユーザが多いから玄人の自分は嫌いなのだ」といった答えが返ってくることがある。しかし、そうした人たちは製品そのものを見て判断していない場合が多い。p194 この辺も、他山の石として、キモに銘じなければならないと思う。この本で言われる「思想」とは、なにか小難しい哲学や現代思想のように、論理をこねくり回して悦に入る、という意味での思想ではない。実際に職業・職分として働く人が気をつけるべき生活態度ともいうべきもののようである。それは、SEという専門分野を超えて、一般的な職業どれについても言えることだ。 SEへの敷居が低くなったこをプラスにとらえてもらいたい。今までなることすら難しかったSEにとりあえずはなれるのだ。そして、なったからには本物のSEを目指して欲しい。P206 プログラミングという技能と、それを職業として人間社会を生き抜いていくことには、次元の違いがある。やはり人間としての基本的な部分はそう変わるものでもあるまい。SEを、本人も周囲の人も、まれびと、として見ていた時代は終わりをつげつつある。
2007.01.06
コメント(0)
-
WEB of the YEAR 2006
「WEB of the YEAR 2006」 YAHOO!Japan Internet Guide 2007年2月号「2006年ユーザーに最も支持されたサイトは!? 」図書館にいったら、黒地に金箔の表紙がやたらと目立った。手にとったら、おおおという内容なので、ああこれは買わなきゃと書店に走って、残った一冊を買ってきた。やっぱり、WEBは楽しいなぁ。◆年間総合大賞 ウィキペディア日本語版 これは堂々の一位というべきか。もうすでに意識せずに日常のインフラとして使っている。集合知という意味ではまさにWeb2.0の王道を行っている感がある。最多得票を獲得というのもうなずける。◆ネットレイティングス賞 YouTube 年間で利用者がもっとも急増したという意味では、まず当然だろうと納得。統計を取っている世界各国の中でも、日本からの利用者がもっとも多い、というのはちょっと意外。でも、周囲をみても、友人の話題に上った件数を考えると、納得。◆話題賞 YouTube 利用者が急増したから話題になったのか、話題になったから利用者が増えたのかもともかくとして、YouTubeがここの入るのは当然か。mixiが3位なのに、どうどうの2位になったのは「やわらか戦車」だとか、こんなん知りません。なんか目新しいの一個みっけ。◆新人賞 イザ! こちらも知らなかった。なにやら「新聞2.0」をキャッチフレーズとするWeb2.0的なブログだとか。3位にYahoo!Daysが入っているが、いまいちmixiには追いつけない。SNSも2個3個登録しても、使い分けが大変。◆ウェブ情報源部門 ウィキペディア日本語版 こちらも当然か。ほぼ桁違いのぶっちぎりで堂々の1位。2位のAll Aboutってなに?3位のはてなブックマークも梅田望夫人気に便乗模様。ソーシャルブックマークってやつだね。◆コミュニティ部門 mixi 2位の2ちゃんねるの6連覇を阻止したのはmixiだった。というより、これまで2ちゃんねるががんばっていた、という事実に、私的にはびっくり。3位の価格.comは使ったことはないが、話題ではよく聞く。◆動画部門 YouTube これは急激に伸びたのだから当然、これからもますます独走の構え。2位のGyaOが今後善戦することがあるのか。3位Yahoo!動画、こちらは一回も使ったことなかった(汗◆音楽部門 iTune Store この分野に関して、私はお手上げ。昔はギターを弾いたり、コンサートなどもよくでかけたのだが、これほどまでに音楽と縁のない男だったかと、自分なりに半信半疑。いや、今の若者文化のほうが、極端に音楽に偏っているのではないか。もっとも、ミリオンヒットだけが目だってしまう昔の流行歌の世界よりは健全か。2位うたまっぷ、3位Yahoo!ミュージックが並ぶ。◆地図部門 Googleマップ 私は実際には2位のYahoo!地図情報を使うほうが多い。なんせ急いでいる時には周辺地図の拡大と、おおよその道のりがわかる道順の地図を2枚プリントアウトして駆け出す。慣れていないせいかGoogleマップはプリントアウトして使うのに向いてない。◆旅行部門 じゃらんnet 最近は出不精であまり遠出をしなかったが、秋にちょっと新幹線乗り換えの旅をした。その時、子供がいろいろなコースから情報をアレンジしてくれた。今は便利なものができたのだなぁ、と快適な旅に感謝。実際に旅にでなくても、シュミレーションだけでも面白いかな。◆ショッピング部門 Amazon.co.jp おお、Amazonが復活している。本以外の品揃えが増えたせいでもあるようだが、本の売り上げも復活しているのではないかな。すくなくとも、ネットが一巡した感があり、本は本で、楽しいという時代がめぐってきたかな?◆オンライン・フォト・ストレージ部門 Yahoo!フォト デジカメをがいぷでプリントアウトしてもらうというサービスなのかな。それだけクオリティの高い画質のものを必要としないので、利用することはないのだが、街角のDTPショップが次々と姿を消すのを見ているのも、どこか忍びない。◆ブログサービス Ameba by CyberAgent アメブロ アメブロという名前は聞いたことがあるが、なぜトップに輝いたかはわからず。「実録鬼嫁日記」などで話題になったせいかな。FC2ブログ、Yahoo!ブログにつづいて、わが楽天ブログは4位。ままの高位置をキープか。livedoorブログ、ヤブログ!、ココログ、ハテナダイアリー、gooブログ、エキサイトブログ、と続く。◆店舗検索 ぐるなび これも結構便利。いきなり検索するとぐるなびのページにでること多し。飲み会の幹事役などは、検索も告知も予約も楽になった。ホットペッパー.jp、iタウンページが続く。◆エンターテイメント ハンゲーム ゲーム話題は苦手じゃ。ハンゲームなどという名前はまったくしらない。2位のほぼ日刊イトイ新聞が今でも人気とは知らなかった。子供がこれで腹巻とかエプロンとか買っている。あ、4位のYahoo!ゲームみっけ。実は私、Yahoo!ゲームのオセロオタクです。レートは1500~1600を行ったり来たり。戦歴は9000回弱。ふ~、9000回もお世話になっておりました。感謝。◆コンピュータ部門 窓の杜 こちらもフリーウェアソフトやシェアウェアなど、いつもお世話になっております。ウェブ上ではインフラとして不可欠品ですね。◆オンライントレード イー・トレード証券 ネットトレードも一時期ほど話題にはならなくなったが、証券会社も投資家も一定程度の淘汰の荒波を経て、いまや、小康状態を迎えているというところか。私も口座をいくつか持っているが、投資するほどの手持ち金なし。シコシコ労働中。◆オンラインバンキング イーバンク銀行 地方銀行利用者としては、とにかくリアルな店舗が身近にあることが銀行選びの第一課題であろう。あとは、ネット上でのサービスだが、実行の差こそあれ、意外とすぐ他の銀行も同じサービスを始める。ネットオークションをやっていると、4位のジャパンネット銀行の利用者多し。7位の郵便貯金もお世話になってます。もっともオンラインではなくて、リアルな窓口で。送金額が一番やすい。ネット取引に最適。◆情報部門 Google はいはい、何も文句はいえません。もうほとんどGoogleを使っているという意識すら薄らいでいます。Yohoo!japan、Gooが続くが、使ってみれば、使い勝手は一目瞭然。◆ニュース部門 NIKKEI NET 最近は、あまり新聞をよまなくなった。テレビとネットのニュース。ニュースはmixiでもGoogleでも、どこでも見れる。このままでは、いままでのニュースのあり方が様変わりしてしまうのだろうなぁ、という予感。ホントは信憑性のある新聞社系のニュースで最終的に確認できないと、信用できないという性癖がある。◆スポーツ部門 スポーツナビ 相撲でも野球でも駅伝でも、千秋楽や優勝戦、最終ランナーにならないと、どうもスポーツには関心をもたない私には、あまり関係ないかも。往年の初代タイガーマスクの試合はYouTubeで見てるし・・・。◆プロバイダ部門 Yahoo!BB あれれ、私の使っているプロバイダは、10位のランクから落ちている。結構安価で安定していて新しいサービスも他に先んじて提供しているのに。まぁ、いいか、実際には使っていて文句なければ、もうプロバイダはどうでもいいや、という時代ではないかな? ちがうかな?◆ブログ賞 中川翔子 かわいい女優さんだが、なんぼアクセス数がおおいからと言って、私はわざわざ見にいくことはありません。しかしそれにしても、一日に最高70回の更新をする、というのはすごい。私は多くて4~5回。これでも友人のブログに比べたら多いと思っていたのに・・・。
2007.01.05
コメント(0)
-
Google誕生
「Google誕生」 ガレージで生まれたサーチ・モンスター デビッド・ヴァイス/マーク・マルシード・著 田村理香・翻訳 2006/6 イースト・プレス 原書2005★★★★★ 現代思想や哲学の流れを追っていくと、ネグリ&ハートの「マルチチュード」という言葉にであう。お互いに多様性を認めて受容しあう群集、という意味だが、それに対する、その一人ひとりの個性的な存在をシンギュラリティと呼ぶらしい。シングラリティともサングラリテとも言うらしい。いわゆるOnly Oneに近いニュアンスなのだが、語源も原語もわからないが、とりあえずカタカナでスタートする。 シンギュラリティで検索していくと「シンギュラリティ・スカイ」というSF作品もあるらしいし、別なサイトを見ると、どうやら人工頭脳の名前かもしれない、という予感さえしてきた。「この語は、数学者ジョン・フォン・ノイマンの造語らしい。」などと、ノイマンの名前まで飛び出すのだから、なんだか、怪しい魅力的なところへと地下回廊がつながっている雰囲気がある。 そこで、このブログの「ネット社会と未来」カテゴリも108エントリーに達してしまったので、その後継カテゴリを「シンギュラリティ」としてスタートすることにする。そもそも、このネットのつながりの先にあるのは一体なんなのか、ということになるのだが、それは一つの飛びぬけた超々スーパー人工頭脳になるのか、はたまた、マトリックスとして、何かを生み出す母胎になるのか、という二つのイメージが湧いてくる。あるいは、羊水に浮かぶ胎児の「意識」のようなものになるのか、想像を掻き立てられてしまう。 さてさて、その「シンギュラリティ」カテゴリのスタートの一冊としては、現在のところ、これ以上ふさわしい本はないだろうと言えるのが、この「Google誕生」である。類書は何冊か読んでいるが、2006年6月発行ということだから、比較的最新の本といっていいだろう。この470Pほどの本の中には、たくさんの情報が詰まっている。一体どのようにしてこのような本ができあがるのだろうと不思議になってくる。 本書は、150人以上の人たちへのインタビュー、ビデオや録音、出版された文書や私的な文書、インターネットの掲示板や電子メールを基に執筆された。p443 とある。さらには、もちろんGoogleの検索機能をフルに使って書かれているのである。「ワシントン・ポスト」の記者という立場も最大限利用されているに違いない。このような本は全部は読みきれないが、ただただ目を通すだけで、なんだか知的な興奮とポジティブな思考法がどんどん湧いてくるから不思議だ。 「ガレージで生まれたサーチ・モンスター」とはいうものの、ガレージから生まれさえすれば、どの企業でもモンスター的に成功するものではない。トラックの運ちゃんが全員エルビス・プレスリーになるとは限らないとと同じことだ。Googleがどのようなスタートをしたかはともかくとして、モンスター的に成功するポテンシャルは最初から持っていた。しかし、だからと言って、完全に保障されたものは何もなかったのである。創業者のラリーとサーゲイの才能と努力があったればこそである。 かつてマイクロソフトで働くのを夢見ていたエンジニアたちは、マイクロソフトのダース・ベイダーや闇の力(ダーク・フォース)、あるいはフェアプレイしない会社というイメージでとらえるようになっていた(*ダース・ベイダーは、映画の「スター・ウォーズ」に登場する悪役で、ダーク・フォースはダース・ベイダーズが使う力)。P150 グーグルを日常的に使うクリエィティブな人間はトゥルードだけではない。「マトリックス」三部作の視覚効果監督のジョン・ガエタも、グーグルの熱烈なファンであることを「ワイヤード」誌に明かしている。p225 う~む、どうやら先日から感じてはいることだが、Googleやネット社会の話題についていくには、どうしても常識的な「スター・ウォーズ」や「マトリックス」などの基礎知識は必要なようである。私にとっては、これからの課題だ。 「Gメール論争」p237などというところも興味深い。私はGメールには一年ほど前から登録はしているが、ちょっと様子見で、そちらに完全移行するということは今のところ考えていない。やはりプライバシーについては気になる。すっかり裸にされてしまうような危険性を感じる。もっとも、現在でも、どのルートを使おうとネットである限りプライバシーなんて本当はないのだが。 余談だが、私は、私はわずか500足らずのエントリーしか書いていないこのブログのどこに何を書いたかを検索する時には、すぐGoogleをつかう習慣になってしまっている。たとえば、「Bhavesh (本のタイトル)」を入れると、すぐ自分のブログを探してくれるから便利だ。勿論、著者名でもいいし、単に一つとか二つのキーワードでもよい。もちろん、他人のブログを検索するときもこのGoogle機能を使うようになっている。 「ポルノ・クッキー・ガイ」p255なんてところも面白い。かつてインターネットが爆発的に発展した陰には安価なあるいは無料のポルノグラフィの存在があったの半ば事実であろう。かつては、ビニ本と呼ばれた裏本は、すべて画像としてインターネットで公開されてしまった。いまや動画に完全に移行してしまった。現在、裏本ビジネスは完全に終焉したようである。「現在、裏本は発行されていません」というアナウンスがでるから可笑しい。 このポルノ問題は、今後のネット社会の大きなテーマになってくるのではないだろうかと思う。単に道徳的な面からだけではなく、ポルノから暴力性が落とされ、よりチベット密教的タントラ化して、さらに、マトリックス化するなんて、ありえるだろうか、なんて、一人で夢想する。 終章では「遺伝子をグーグルするーそして未来へ」p428というテーマで展開される。 「サーゲイ・ブリンとラリー・ペイジには、科学と医学のテクノロジーを融合させて、グーグルを生物学と遺伝学の分野へ進出させる、という野心的な長期計画がある。p428 GメールやYouTubeだけでもこれだけ物議をかもしているGoogleが、遺伝子工学にまで躍り出て、いままでになかった新しい動きを始めたら、さぁ、大変な大騒動になる可能性もある。見ものだ。私にも今のところ賛否はなにも言えない。 かつてOshoが「グルイズム」とか「物質主義的」とか批判されたが、さらに反対派をコーフンさせたものに、Oshoの「受胎調節と遺伝子工学」についてのビジョンや言及があった。この一つのビジョンでOshoにラベルを張り、その元を離れた者たちもいた。 私には、賛否をいうことができなかったし、今でもわからない。しかし、優れた人がいうことに対して、とにかくその真偽は分からないが、とにかく留意してみていようではないか、という姿勢は変わらない。これはかつて、70年代のアメリカのロック誌「クローダディ」の編集長ポール・ウィリアムス(20そこそこだったが)が、「優れたアーティストがやりだすことについては、理解できなくても、すぐこちらで判断せずに、どうなるかしばらく見ていようじゃないか」というような発言をしていたことが、10代からの私の判断基準となっていることが大きい。 このようなGoogleの切り開いた地平を契機として、わがシンギュラリティはスタートする。
2007.01.04
コメント(2)
-
魂の螺旋ダンス<5>
<4>よりつづく魂の螺旋ダンス<5> The Spiritual Spiral-dance はるかなる今ここへ 長澤靖浩 2004/10 第三書館 こちらの本も、大冊ではないにしろ、簡単に読む進めてしまうことができないことがわかってきた。少なくとも、簡単に読み進めてしまうことはもったいないと思う。巻末の「主要参考文献リスト」には、およそ100冊の興味深い書籍が列挙されている。 扱う領域は、この島の精神文化史全般であり、そこにはまた世界的な視野も取り入れなければならかなかった。そのため文献の読破に時間を取られる一方、精神文化の螺旋モデルの具体的な肉付けにも、産みの苦しみを味わった。「あとがき」p240 本文を読めばわかるが、この文献リスト以上の文献が読みこまれたことは想像に難くない。ここまで文献を読み込んで、著者は一体なにをしようとしたのだろうか。そう問うて見ると、今、遅ればせながら、この数ヶ月、私がこのブログでやろうとしていることは、すでにこの著者によって、行なわれてしまっているのではないだろうか、というデジャブのような既視感覚に陥った。 そうか、そうならば、この本の結論を読み込めば、それでよいはずだ。そのような安堵感がまずあった。そういう意味で再読してみれば、今後この書の意味はどんどん違った側面をみせてくれそうだ。著者が「超越性宗教」から「絶対性宗教」へ、そして更なる螺旋上に描くものを思うとき、私は、このブログで便宜上名づけた「地球人スピリット」を思う。 私には、アルファから始まってオメガで繋がる円環のイメージが大変居心地がいいし、時間的経過を考えるなら直線的に進むイメージが当然のように思える。それに対する著者の螺旋構造というものは、ケン・ウィルバーの意識変容論や、DNA構造を説明するときなどにも使われているようである。もし、そのような構造が、著者との接点になりえるのなら敢えて、そのようなものとして、とらえなおしてみようではないか。 私はこのブログを始めるにあたって、あまり古い文献とかは目に入れないで、新しいものだけを追いかけてみようという想いがあった。少なくとも、もう前世紀のことはよいではないか、というような切捨て感覚があった。でもそれはちょっと甘かった。表面的な潮流だけを追っていくなら、新刊本だけを眺めていればいいが、ちょっと立ち止まって考えてみようとすると、90年代や80年代どころか、19世紀や18世紀まで、時にはもっと中世や古代について想いを馳せなくてはならないことも分かってきた。 昨年は一定程度、新書本に触ってみたところで、今年は、すこしちょっと古めの文献にも目を通してみようと思う。特に、この著者・長澤が巻末にリストアップしたような文献は、他人が読んでくれたからそれでよい、とせずに、自分で可能な限り読み込んでみようと思う。少なくとも宮崎哲哉の「新書365冊」で葛藤しながら、自分の好みの本をより分けていくより、こちらの長澤リストのほうが、はるかに私にとっては有益なようである。 そういいながら、埃をかぶって乱雑に積み上げられている我が家の書庫の中に、まだ十分読み込まれていない書物が何冊かあることに気がついた。私はもともと精読家でもないし収集家でもない。その時々で自らのポケットの小銭を勘定しながら、その時々に関心のある本を買い集めているに過ぎない。しかしそれでも、「還相」の途上にあって、関連書籍を網羅したりすることもなかったし、「グルイズム」というラベルを貼られながらの「論敵」の文献を読み込むのも、あまり面白くもなかった。ましてやインターネット時代にあっては、より一層、書籍離れしたのも事実だった。 しかし皮肉なもので、インターネットに深く関わろうと思えば思うほど、書籍帰りが進むのだから、不思議なことだ。「非戦を旨とする地球人スピリットの探索」という、このブログのテーマはそのままにして、私の拙い読解力で、まずは前世紀後半に現れた書籍をすこしづつ読み込んでみようと思う。正月早々、そのような気分にさせてくれた、この「魂の螺旋ダンス」は、今、「往相」と「還相」という一つの小づくりな円環を閉じようとした私を、ちょっと一歩前に押しやってくれたようである。 私の「魂の螺旋ダンス」はここから、また始まるだろう。この書についての、とりあえずの感想は今回はこれくらいにしておいて、折に触れて、各章に言及することになるだろう。そういう意味で、私はこの書についても感謝したいし、友の仲間がいれば、この書が提示した叩き台で遊んでいきたいものだと思う。なにはともあれ、Thanks abhi。とりあえず、一旦終了。後日再読した。<6>につづく
2007.01.04
コメント(2)
-
さよなら、サイレント・ネイビー(3)
(2)よりつづく「さよなら、サイレント・ネイビー」 <3>地下鉄に乗った同級生 伊東 乾 いくら引っ張ったとしても、キリがないので、この本についての感想はこのエントリーでとりあえずの終了とすることにする。私にとっての一番の感心事は、前回のエントリーにおける「5)地球と人類の未来について」なのだが、オウム真理教や地下鉄サリン事件をどう弄り回しても、直接的には、ポジティブなエネルギーが湧き上がってこないのは残念である。 そうは言っても、たくさんの突っ込みどころはそのまま残ったままになってしまっている。以下はこの本の取り巻く環境のなかから、今後いつかは再発しそうなテーマをただ羅列だけしておく。1)この本が出ることになった「開高健ノンフィクション賞」の審査員の一人に佐野眞一がいることになるほどという新鮮な感動があった。「これほど知的興奮を覚えた作品は近頃珍しい」と評価している。2)「往相」と「還相」という言い方があるとするなら、Oshoとであった75年からOshoが肉体を離れた90年までの足掛け16年が、私自身の「往相」であった。90年以降の私は、言葉としても意識して「還相」の時代を生きてきた。詳細は省くとして、そういった「社会へ、人の中へ」という時代の中で出会った95年のオウム事件については、ひたすら違和感を感じざるを得なかった。あれからほぼ16年私の「還相」はある原点に指し戻ったような感覚がある。一つの円環が完結して、2007年、あらたな次元が始まる気配を感じる。3)オウム真理教について、いろいろな経緯の中で20世紀末の666、「偽マイトレーヤ」に仕立て上げられてしまった、という感慨をもつ。ほとんど自爆したに過ぎないのだが、社会が、キリスト教社会がこのような「偽マイトレーヤ」の出現を待ち望んでいたように思う。まんまと引っかかってしまったのが、松本一派であっただろう、というのが私の中の納得点である。4)地下鉄サリン事件とは何も関係もなかったのであるが、Oshoに対するマスメディアによる歪曲報道が展開されるに及んで、国内のメディアに関心あるサニヤシンたちとネットワークを張って、訂正要求を送り続けた。この時のトラウマが、ちょうど時代的に立ち上がってきたインターネットの必要性を私が強く感じ、参加していったきっかけになった。5)この時の、中沢新一や島田裕巳などの親オウム学者たちについては、ハッキリ言って強く批判したい気持ちで今も変わりはない。今でも彼らを許さない私がいるのであるが、彼らはほかにもいくらか「良い」仕事をやっているようだ。私はそろそろ頑なな気持ちを解いて、彼らの近年の仕事にも触れてみようかな、と思っている。ただ、言葉でいきている限り彼らの犯した誤謬は誤謬として記憶はされなくてはならない。6)オウム一派は、各地に自らのブランチをもっていた。私達の町にもあった。あったばかりか、当時の私達のオフィスのすぐ側にあった。側にあったというばかりではなく、住所は、ほんの数字の一文字が違っていただけであった。私達のオフィスも印刷物などで公表されていた住所だから、ひょっとすると、そのすぐ側を狙ってブランチ作りをしているのか、と疑いたくなるほどだった。80年代後半のことであるが、意図的ではなかったとしても、どうもこの辺のキモいシンクロ現象については、まだ解決できていない。7)オウム心理教の「教義」そのものは、実にごった煮の観を出ないのであるが、この中において「オウム」という「聖音」が、この事件を通じて、なにごとか他の意味合いを帯びてしまったのは、いかにも悲しいことだと、つねづね思っている。聖なる音として「オウム」の復権を願うものだ。そして、チベット密教タントラの真実なる復権と成長を願う。8)「さよなら、サイレント・ネービー」という言葉が、もし、著者・伊藤乾が、学生時代の親友・豊田亨に言った言葉であり、寡黙なまま死刑台に消えようとするのではなく、寡黙な海兵隊であることに、さよならを言え、という意味であったとするなら、私は私自身にこの言葉を言ってみようと思う。「雄弁は銀、沈黙は金」などという言葉に、どこかで共感する私がいる。9) 著者・伊藤は事件の再発をふせぐために、豊田よ語れ、と催促するが、私は必ずしも事件には関わりはない。むしろ、あの地点でとまってしまった、私自身のなかでの「人類の精神的成長の過程」への探求、というものがあったとすれば、もう一度、その地点に立ち戻ってみようと思うのである。10)長澤靖浩が「魂の螺旋ダンス」で書くように、スピリチュアルな成長過程が、円環状に繰り返すでもなく、直線的に進むでもないp1とするなら、私の螺旋ダンスは、一段次のステージに進むことになる。 <4>につづく
2007.01.04
コメント(0)
-
和尚(ラジニーシ)、聖典を語る <1>
「和尚(ラジニーシ)、聖典を語る」 エッセンス集 玉川信明・編著 社会評論社 2003/12 この一冊で、玉川ノートである「和尚ガイドブック」4冊を読み終えたことになる。貴重と言えば貴重と言えるシリーズであったと言える。玉川には「異説 親鸞・浄土真宗ノート」があるので、これを最後に読むことになるだろう。こちらは2004年4月発行ということなので、著者、最晩年の心境と言えるだろう。 もっとも親鸞については、この本の「あとがきに代えて」でも触れている。 仏教の中の仏教と言われる浄土真宗が再生するためには、現代人のボン・サンス(良識)に合わない部分をすべて切り取ることが必要とされるのである。現代人の普遍的思想と合わなければ、それにあわせなければならないのは旧宗教のほうである。 前書きがながくなったのは、それを見事にやり遂げてまったく新・宗教として現れてきたのが、和尚の宗教である。p301 やたらと批判されると、ちょっとやってらんないなぁとムキになってしまう自分がいるが、逆にこう持ち上げられても、別に反対する要素もないが、ちょっと照れてしまうような、居心地の悪さも本当はある。あなたの言うことはその通りだ。だからどうした?と、ちょっと皮肉を言いたくなってしまう。結局は批判しようが、共感しようが、自分自身、私自身が、どうなっているのかを理解しなければ、どんなにOshoが素晴らしかろうが、どうにもならないのだ。 著者が生存していたら、この「和尚ガイドブック・シリーズ」はもっと続いたのだろうか。どうもこの本の成り立ちからして、著者はここでストップをかけたような感じがする。まぁ、玉川的センスを理解するには、このくらいが丁度よい。これ以上、ながなが続くのであれば、もともとOshoの講話録そのものにあたったほうが早い。 この本は、前三部作と違って、Oshoの世界を網羅する形で原典を選び出し、ダイジェストをつなぎ合わせている。だから、一冊まるまんまを一気に読むのはちょっと不適当だ。すこし休み休み読まなくてはならない。だが、玉川ノート完結編だけに、Oshoの全体像が見やすい形には編集されている。この完結編のエッセンスを一言で言っているOshoの言葉があるとすれば、次の言葉となろう。 第一次元は科学の次元で、客観世界、対象、事物、他者の世界だ。第二次元は美学の次元で、音楽、詩、絵画、彫刻の世界で想像力の世界だ。そして第三次元は宗教、主観的な、内側の世界だ。これら三者の関係は科学と宗教は対極に位置する。中間には美学の世界がある。 そこで私は第四の道を提案する。真の人間はこれら三つの次元のすべてでなければいけない。真の人は科学者であり、芸術家であり、宗教者だ。私はこの第四の人間を「スピリチュアル、霊精神的」な人と呼ぶ。私はここのところで、アインシュタインやブッダやピカソ、彼ら全員と一線を画する。第四の人間の創造こそ、世界の希望だ。Osho p184 「第八章 存在はゆったりして自然である ティロパ『マハムドラーの詩』」は、「存在の詩」のダイジェストとなっている。まぁ、読まないよりはいいのだろうし、数センテンスだけを読むよりはいいのだろうが、「存在の詩」そのものを読むような感動は得ることはできない。私がOshoの言葉に触れたのは30数年前のこの本だったのだが、あの本だからこそ、あれだけの衝動を感じたのであって、ダイジェストを最初から読んだのであれば、また感想は違ったものになったかもしれない。 しかしまぁ、無謀なチャレンジをして、このような貴重な本を、しかも四冊も残された玉川さんには、私は感謝する。折にふれて、今後、このシリーズを紐解くことが多くなると思う。 <2>につづく
2007.01.03
コメント(1)
-
君が世界を見捨てても世界が君を見捨てない
「君が世界を見捨てても世界が君を見捨てない」 瀬戸しおり 2006/10 幻冬社 このような本が流通している事実に対し、私は本当のことを言うとちょっと疑問を感じる。地方の図書館の新着本の中にあり、また、たしか山口百恵の本も出したことのあるいわゆる一般的な出版社からでているのだから、どこかでどういう形でか話題になっている本のなのかもしれない。しかし、私はこの本の在り方に感心しない。 著者1981年生まれの女性ということだから、まだまだ未来のある若い女性だ。そして行政書士事務所を開設しているとのことだから、まだまだこれから社会的な活動の期待される人物である。ましてや、作文が得意で、中学校2年生の時に「内閣官房長官賞」までもらったp32ことのあるという彼女の文才はただごとではない。まさに鬼気迫るリアリティと説得力がある。 自己を開示するのは、TPOさえ間違っていなければ大歓迎だし、時には、自然と頭がさがり、開示してくれたことに感謝してしまうということも多い。ただこの本においては、関係者が実名らしき形で出てくる。本人達の了承を得ているのかもしれないが、ここまで書くか、と、とても違和感を持つ。執筆者のみならず編集者や出版社に猛省を望む。 いくら通っていた中学校の教師が、「ひどい暴力で有名であった」p33としても「翌年、教師を解雇された」p46としても、具体的な人物の存在をこのように書き出していいのか。しかもK(本文は苗字のみの漢字)という、実名らしい名称を何度も書き出すのはいかがなものだろうか。 この疑問は、大学生になって水商売を始め、キャバクラ嬢となって「そこのお客さんに、面倒見のいいT損保の課長のM(本文では苗字の漢字)さんが部下を連れてやってきた。」p128という表現にぶつかった時、ますます大きくなった。「人事の課長さんだから・・」という表現からすると、察しがつく人には察しがついてしまう。T損保とここでは会社名を書いていないが、ここでこのような配慮をするなら、学校名や他の登場人物についても、特段の配慮が必要なのではないだろうか? このような、一読者としての私には過剰とも思える周囲についての評価や書き出しは、自らの父親や母親への視線についても言える。いくら身内であったとしても、ここまで書いていいのか。カウンセラーとの面談としての自己開示と、文字となって一般出版社から刊行される本の文章となる自己開示での表現はおのずと明確に違ってしかるべきだ。 このような他者を見つめる激しい視線で、自らを見つめる時、彼女は彼女自身を痛めつけてしまうのではないだろうか。それは生まれながらの性格、あるいは体質、時には「病気」ということになるのであろうが、なんとも私には、かわいそうな悪循環のように思える。 彼女はブログを書いている。この本の出版されたのが昨年06年10月だが、この12月の本人の書き込みを見ると、現在、かならずしも精神的に安定している状態でもないようだ。私は自分のブログを棚にあげておいて他の方のブログなどを語っている場合ではないが、しかし、それにしても、自らの情報についてだけでなく、周囲の人々についての配慮がもうすこしあってもよいのではないか、と思う。 周囲の主治医やカウンセラーという立場の人々や出版社関係者についても、このような形での出版に至った過程について、私は猛省を促したい。書かれている内容そのものについては、とても貴重なレポートであると思う。もし小説と言う形や、もっと一歩引いた形でのノンフィクション的な表現であったなら、私はもっと、余計なことに気をとられずに、ことの本質に向かい合うことができたと思う。残念である。
2007.01.03
コメント(1)
-
和尚(ラジニーシ)、性愛を語る
「和尚(ラジニーシ)、性愛を語る」 エッセンス集 玉川信明・編著 2003/2 社会評論社 玉川信明の和尚ノート・シリーズ、「超宗教的世界」、「禅を語る 」に続く三冊目、この後「聖典を語る」で4冊で完結する。 いつであったか10数年前に、Oshoを紹介する新書本のようなものがあったらいいのにと感じたことがあった。出版関係者に提案したこともあったが、私の望むような形での本は出現しなかった。それにはいくつかの困難さがつきまとうので、それは当然のなりゆきであったとも思う。 さて、今回、この玉川ノート(と敢えて言っておこう)シリーズは2~3年ほど違和感があって、なかなか手にとって読むことはなかった。今回、だんだん読み進めてみて、ああ、これは私がかつて望んでいたものが、とりあえずこういう形で実体化したのだなぁ、と新ためて感じ入った。 そのサブタイトル「和尚ガイドブック」である。この本がどういう経緯で、どのような関係者の努力で出来上がったのか、私には詳しいことは分からない。しかし、このような形の本はありそうでなかった。ある意味、いままでのOsho本の成り立ちを知っている関係者なら、むしろ、こういう形では編集出版することはなかったであろう。 玉川信明は2005年に亡くなったが、彼は40年にわたる執筆活動を継続して行なっており、その著作にも触れてみた。ダダイスト辻潤にたいする思いや、ヤマギシ会の山岸巳代蔵の評伝、越中富山の薬売りの民俗学的著述などを読み進めていくにつれて、なるほど、この人なら、Oshoをどう読むのだろうと関心が湧いてくるし、ある程度の、「異例な振る舞い」は、この人になら許してもいいのかな(笑)という気分になってくる。 この本に対しては、私に不満がないわけではない。和尚のあちこちの著作を無際限に切り張りされており、その出典が「参考文献」として巻末に列挙されているが、どの部分がどのような形で引用されているのか、まったく分からない。また、些細なこととは言え、引用したものの誤字脱字校正ミスが複数見られるので、ちょっと白けてしまうところもある。 しかしながら、それもすべては「玉川ノート」として読むとすれば、それほど気にはならなくなる。むしろ、あえてこのシリーズを読むことによって、すでにほとんど読了しているOsho本について、また再読するような、楽しみが湧いてくるのも事実だ。特に、このようにOshoの「性愛」についての言及を一冊にまとめた本など、類書はない。 新人類を創造できるのは、タントラ以外にはない。p202 ものごとすべてにおいて最大表現するのはOshoの常だが、この本の本質、そしてOshoの本質は、この一行に込められていると言っても過言ではない。実際の技法や論及は、実際の書籍や指導者に譲るのでここでは触れない。 この本、「和尚ガイドブック」となっているが、今後はこの玉川ノートからOshoに触れていく人もこれからでてくるに違いない。そして何か感じるものがある人はぜひ原典(もちろん日本語訳でいいが)にあたって、その文脈の含蓄をもっと深く味わってもらいたいと思う。そのように使われるとするなら、この本の存在意義は大きい。 玉川ノート・シリーズについては、著作権の問題や、編集権の問題など、門外漢の私なりに気になることもある。関係している立場にある人たちは、この点についてどのように感じているのか、寡聞にして知らない。それぞれの立場からの意見も聞いてみたいと思う。<2>につづく
2007.01.03
コメント(0)
-
さよなら、サイレント・ネイビー(2)
(1)よりつづく「さよなら、サイレント・ネイビー」 <2> 地下鉄に乗った同級生 伊東 乾 何の因果か、正月元旦早々、この本の読書で今年がスタートすることになった。読みたいと思っていたものを、正月にまとめて読もうとストックしておいたのだから、仕方ないとして、なんと重い課題を持った一冊なのかと、ため息がでた。 私の読書は、本を正しく評価するというものでもなく、紹介するものでもなく、ましてやダイジェストを作ろうというものでもない。私自身がブログを続けるために、読んだ本に口火を切ってもらって、それに反応する自分を開示してみようという試みである。だから、この本に限ったことではないけれど、特にこの「さよなら、サイレント・ネイビー」のような本については、正しく引用できない可能性があるので、多くの方々が実際に手にとって読まれることを期待する。 「たとえどんな境遇にあっても、豊田は俺の生涯の親友だよ。昔も今も少しも変わらない」p183 この本のテーマは、この一行に表されている。地下鉄サリン事件の実行犯の一人となった豊田亨に対する友人としての著者の想いがこの本を作った。同内容について広く社会に問うことを意図したが、著者は通常の形での出版の機会をなかなか見つけることはできなかった。刊行はもはや不可能かと思われた時、「開高健ノンフィクション賞」にエントリーすることになり、それがしかも第四回の賞を受賞することによって、ようやく日の目をみた作品なのである。 だから、崔洋一のように、最有力の問題作とみなしながら、選考に反対した選考委員がいたことににも納得がいく。ノンフィクションという技法からは、やや外れた、自らの意見や解釈の多さや、小説を思わせるような会話などが続く。しかし、それは、かつて書かれたものを、応募のために書き直したせいであり、その混乱ともいえる不統一は、この本を飽きさせずに読ませ、その緊急性を読者に訴える良い結果も生んでいる。 私は、この小説を読んでいて、どうもこの本で書かれている内容と、私がいままでイメージしていた豊田亨という人物像がうまく重ならなかった。あらためて、Googleで検索してみて、ああ、この人だったか、とあらためてその顔を覚えなおした。どうやら、私は、別人である中川智正被告のちょっと太めでカエルが怒ってにらんでいるような(失礼!)人相を想像していたようだ。 2年後期の試験が近づき、友達のノートのコピーが出回るようになって、「豊田ノート」を初めて見たときの衝撃を今でも覚えている。きれいとか、完全という言葉では足りない、驚くべきノートだった。まず字がただ事でなくきれいだった。初めて聞く内容でも、ポイントをびっしり抑えて、明確にノートされている。p196 なるほど、この方の写真を見れば、このような表現をされるのも納得がいくような気がする。この本に共感なり、自分なりの思考の足がかりをつけるとすれば、いくつかのポイントに分けることができる。1)著者自身の生い立ちについて2)友人である豊田亨について3)オウム真理教について4)日本社会への言及について5)地球と人類の未来について 1)については、父親が満州へ学徒出陣し、シベリア抑留や復員後の廃人同様の病状を体験しつつ、40歳で結婚したものの、著者6歳の時に、肺癌で亡くなってしまったこと。著者が「戦争は、私にとって教科書上の歴史や人ごとではなく、小学生以来、毎日の生活にちりばめられたルサンチマンだった。」p67と書いている。これほどではなくても、私もまた、似たような経緯で父親を8歳の時になくしている。著者のルサンチマンの在り処に共感を感じる。 2)豊田亨本人については、彼が寡黙であることもあって、いまいちわからないことも沢山ある。しかし、「豊田自身による再発防止への呼びかけ -松本智津夫の死刑確定を受けて・・・2006年9月16日」p337という文章から察するに、まだまだ、彼の語り得るチャンスはあるという感じがする。本人は、いくら語っても理解してもらえないだろう、と考えているとするなら、それは思い直してもらいたい。少なくとも私は、この本の続編としてでるだろう、彼の実声を聞いてみたいと思う。 瞑想者としては、彼が今、拘留されつづけているとしても、その運命を乗り越える力を得てもらいたいと思う。単純に比較はできないが「<帝国>」や「マルチチュード」などを表しているアントニオ・ネグリなども、ながく収監されながら、その環境の中で、優れた業績を残している。 サイレント・ネイビーとは「あれこれ政治に口出しをする陸軍と違い、海軍は黙って任務を遂行し、失敗してもあれこれ言い訳せずに黙って責任を取る」p318というところに由来しているという。「さよなら」とは、著者がだれに向かっていった言葉なのだろうか。黙って死刑台に消えていく友人に別れを告げる言葉なのだろうか。いや、「男は黙って去る」と言った美学に、もし浸っているとすれば、豊田よ、その美学に別れを告げて、語れ。想いをぶちまけよ、と、友人として、無二の親友として呼びかけているのだろう。3)については、あまりに膨大なので、ここでは触れない。しかし、事件後11年を経て、直視する力をもつべきだと、いう必要性は感じる。このブログで、徐々に触れていくことになろう。4)オウム真理教と日本や日本人との相似形を語ることは、より多くの日本人の心情を揺り動かすかも知れないが、私はあまり歓迎しない。日本人や日本人の戦争責任は当然問い続けられるべきだと思うが、オウム真理教とは別個の問題だと思う。ここでニアミスしてしまうことは、むしろ松本たちの思う壺に嵌ってしまうのではないか。5)については、この本では、大きな展開はないと思ってよい。 村上春樹は、地下鉄サリン事件について着想をえた「アンダーグランド」というノンフィクションを書いている。著者は、この小説の各所に違和感をもっている。私はこれから読んでみるつもり。 ところで、本書で何箇所かでOshoの名前がでてくるのでドキッとする。著者は大学社会学の見田宗介の合宿ゼミでOshoの話に触れている。 バグワン・シュリ・ラジニーシの「ダイナミック・ヨーガ」の話も魅力的だった。1983~4年ごろのことだ。p229 半年のゼミでは、まず教室で、禅の「十牛図」や、バグワン・ラジニーシの「ダイナミック・ヨーガ」などの話題を扱った。ちょうど豊田が「オウム神仙の会」に通い始めたころ、私は大学のキャンパス内で、「社会学」という学問の枠と「自我論・間身体論」というテーマ設定がある中で、クンダリーニなどのヨーガの概念を知ることになったのだ。p231 こちらは1987年頃のこととされる。 この本、「第4章 欣求 -官能と禁忌の二重拘束ー」P101 では、クンダリーニや性愛エネルギーに語っているところも興味深い。 続く
2007.01.01
コメント(0)
全39件 (39件中 1-39件目)
1