2011年10月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
運動律エクササイズの薦め
今回は、「運動律エクササイズ(モダン出版、古瀬精一氏著)」という本を皆さんにお薦めします。 ブログ友だちのワルツ♪さんにご紹介いただいた良書「運動律エクササイズ」は、実にすばらしい内容が掲載されていました。ワルツ♪さん、有難うございました。 まだまだ使いこなすには時間がかかりそうですが、この本に出合えて最近の迷いが払拭されたようです。私にとっては少なくとも次のような知識を確認することができました。1.あらゆるのダンスの動きの基礎となるであろう「上体インナー・マッスルのローテーターカフ(棘上筋・棘下筋・肩甲下筋)」と大臀筋や腹側筋の補助を使って「下体インナー・マッスル(大腰筋)」のピストン運動との連動によるシンクロ(同調)が体験できるようになり、今後より深く習得し応用することで上達が期待される。 ※ 大腰筋をピストン運動のように動かす考え方は新たな知識で、また、大臀筋と大腰筋は 拮抗筋で逆の動きをすることも理解できたので、更に正確な動きができそうです。 ※ 立位で行うメレンゲアクションもこの動きの一種であること、インナー・マッスルとアウター ・マッスルの併用方法を理解することができました。2.コントロールできる筋肉とそうでない「身体の自然な随意運動」とがあり、後者の領域に意識的に入ってしまうと、不自然な動きや身体を痛めてしまったりしてしまうので、自分の意思でコントロールした後は、思い切って自然な動きに(不随意運動に)任せる意識が肝要なようです。 ※ 私の場合、不随意運動までをコントロールしようと試みていたために無理があり、身体を 痛めてしまうことがよくありました。3.ダンスしている最中、体幹と肩甲骨のあるべき姿は次のとおり。 (1) 背骨をS字にセットすること。 (2) 胸骨を持ち上げる(リブケージ・アップ)。 (3) 両肩をセットすること。
2011.10.29
コメント(2)
-
体幹と脊椎とダンスについて
今回は社交ダンスで重要な体幹と背骨について纏めてみました。1.体幹は、横隔膜より上の「胸腔」と下の「腹腔」とに分けられます。 体幹が重要な訳は、あらゆる姿勢や動作の出発点となるからです。木の幹から枝が生えている様に、手足や頭の動きはすべて体幹でコントロールする構造になっています。社交ダンスでは上半身と下半身をしなやかに連動させながら踊ることが大切となります。 (1)「胸腔」は、胸椎や肩甲骨や肋骨のフレーム及びインナー・マッスルが形成 します。 (2)「腹腔」は、腰椎の筋肉や骨盤底筋群や内臓全体を包む腹横筋等の骨や 内臓を保護するインナー・マッスルが活躍して身体の中のコルセットを形成 しています。丹田とか腹圧に関連します。 * 発声や息を吐いたりする事で「腹腔」に力が入って体幹が しっかりしますから、「よいしょ」と掛け声をかけて立ち上がる のは、身体の自然な行ないの一つです。 ※ 最も重い頭部と腕は胸で支え、横隔膜から下は大地を駈けるイメージで使い分けることが効果的なようです。別の言葉で「胸から下が脚であること」を意識しましょう。2.背骨は、上から「頸椎(7個)」「胸椎(12個)」「腰椎(5個)」で形成されています。 「頸椎」と「腰椎」は縦に良く動き、「胸椎」はあまり動きません。 一方、回転するのは「頸椎」と「胸椎」で「腰椎」はほとんど回りません。 (この構造に沿った動きをしていれば負担やケガが少なく、見た目もキレイに踊れます。) ※ 胸椎の最も下部の「12番」は、胸をそらす時も回転する時も重要なポイント となりますから、胸椎「12番」を起点に意識して練習しましょう。 (胸椎「12番」は、概ね、直立して両腕を下げた時の肘の高さに位置します。) ※ 胸椎「12番」は、横隔膜及び「腹腔」中の最も重要なインナー・マッスルの 大腰筋が付随する「上半身の要」となります。 ※ したがって、回転を伴うCBMやローテーションを行なう場合に胸椎「12番」が重要なポイントとなりますから、意識して練習しましょう。
2011.10.17
コメント(0)
-
ルンバの基礎・ポイント
以前、纏めかけてそのままになっていましたが大切なポイントとなるので掲載しておきます。一歩ずつ踏み出す度に意識しながら練習しましょう。 1. ストレッチ 2. ツイスト 3. 体重移動 ※ ルンバウォークで一歩ずつ踏み出す度にストレッチして、上体 とヒップがツイストしながら体重移動することを意識します。 一連の動きの中で、アクセントや変化を入れる事で魅力的なダンスとなります。逆に変化のないワンパターンのダンスは面白みの無いダンスとなるでしょう。 ・ スピードの変化 ・ インパルス * アクセントの、最初の動きにエネルギーを与える。 ・ インパクト * 動きの最後にアクセントを持って来る。 ※ 見せることが大切、そのためには気持ちを入れる事が重要。 ※ アクセントが大切。しかし多用するとうっとうしくなるので、これ らのコンビネーションが大切となります。
2011.10.10
コメント(0)
-
脊椎とダンスについて
本日、○○○ファンを読んでいたら目からうろこの知識に出会えたのでご紹介します。その知識とは次のとおり。 「頸椎」と「腰椎」は縦に良く動き、「胸椎」はあまり動きません。 一方、回転するのは「頸椎」と「胸椎」で「腰椎」はほとんど回りません。 * この構造に沿った動きをしていれば負担やケガが少なく、見た目もキレイに踊れます。 この二行を読んだ後、何だか嬉しくなってしまいました。ラテン、スタンダード共に、最近、ローテーションを伴う動きをする時どうも今一つ動きがスッキリしなかったのですが、今回の知識 “回転するのは「胸椎」で、「腰椎」はほとんど回らない。” が得られたおかげで解決しました。“「ローテーション」とは垂直な背骨の周りをヒップが回転する”と理解したため、腰椎の周りをヒップが回転と考えていましたが、実際は胸椎が回転することが解り、実際に動いてみると回転が実に軽くなりました。
2011.10.04
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-
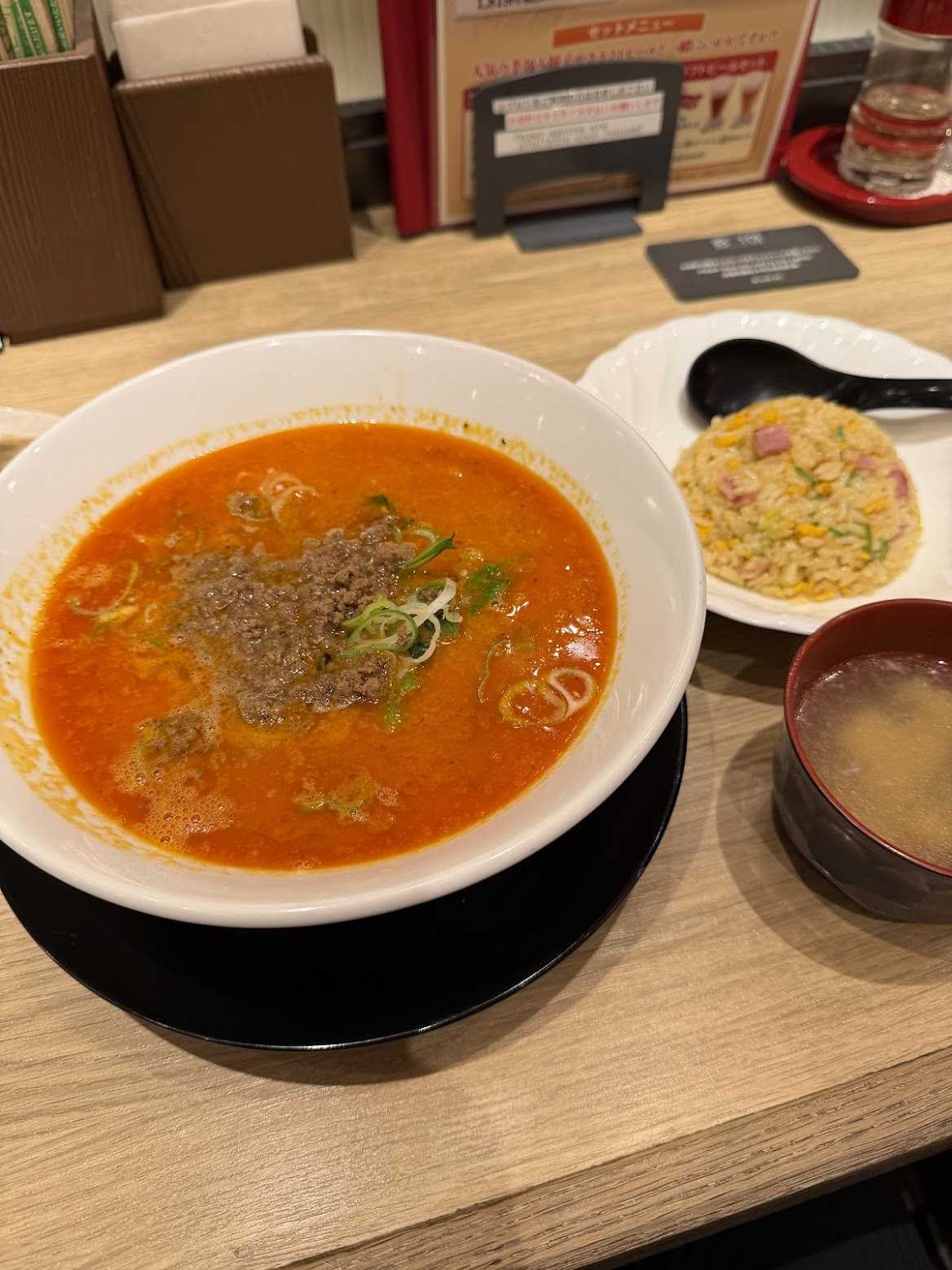
- 【金鷲】東北楽天ゴールデンイーグル…
- 育成1位は俊足巧打
- (2025-11-23 06:59:38)
-
-
-

- サッカーあれこれ
- Y.S.C.C.×大阪 葛飾×浜田 浜松×水戸 …
- (2025-11-24 21:24:14)
-








