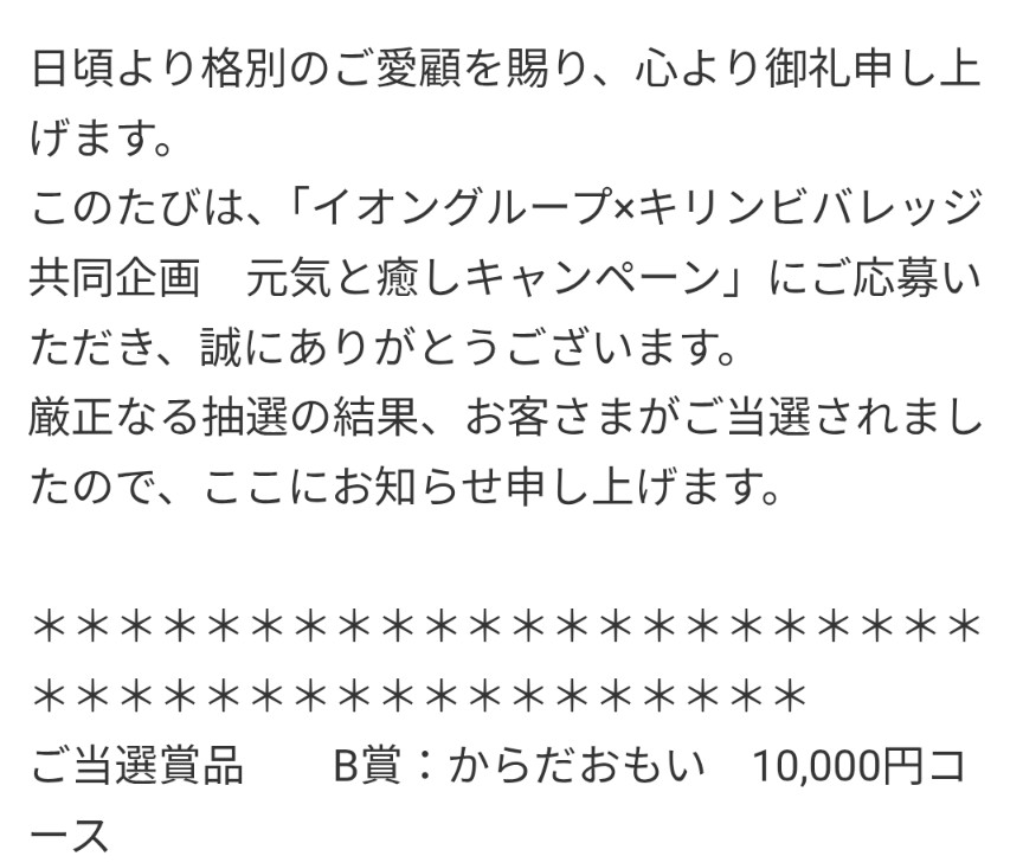全757件 (757件中 1-50件目)
-
本日の偶然「赤瀬川原平」
病院の待ち時間で赤瀬川原平翁の『ブータン目撃』を読んだ。その後、薬局の待ち時間で『からころ』という病院関連の無料雑誌を読む。 その雑誌の巻頭に「赤瀬川原平さん入院加療の為、休載」と出ていた。 知らなかった(>_
2014年01月21日
コメント(0)
-
表彰状を贈る
本年も物言わぬ「物」達に表彰状を贈る。 白黒斑の野良(?)猫殿。 貴殿は散歩中しばしば良く伴走(歩)し、病母を楽しませました。 特に身をくねらせながら柵を潜り潜り、また飛び降りては足元によるという仕草は、愛嬌と共に猫の不可解さまでも良く伝えました。 よって、その功績を称え、表彰します。 ゴーヤと蟷螂殿。 ゴーヤ殿は種植えが遅かったにも関わらず律儀に実をつけ、11月に入っても蕾をつけるという生命の粘り強さを身を以って示されました。 また蟷螂殿はゴーヤの蔓にじっと数日間居続けるのみならず、適宜蔓の上を移動し、秋口に日々の楽しみを与えました。 両者共に、生物は「死ぬまで生きている」という新鮮な感動をもたらしました。 よってここにその功績を称え、表彰します。 掃除用ウェットティッシュ殿。 貴殿は、想像以上の洗浄力で、よく掃除の任に堪えました。 特に台所の油汚れ落としは当初の予測を遥かに越える洗浄力で、「こういうの宣伝ほどには落ちないんだよね」という発言の使用者を深く恥じ入らせるばかりでした。 ここに貴殿の能力を高く称え、表彰します。 本年も皆様ご苦労様でした。来年も宜しくお願いいたします。 皆様も良いお年を。
2013年12月31日
コメント(2)
-
本日の偶然「財前」
テレビ欄(8チャンネル)を見たら、「財前」という名前が、同じ縦位置に間隔を空けて、三つ並んでいた。(その内、二つは「財前直見」さん。他はドラマの主役名) (「これを偶然とは言わない」とお考えになる方も多いと思います。しかし、偶然とは当人の意識と外界との関係の問題であると考えますので、「偶然と感じられたから偶然」としておきます。)
2013年11月08日
コメント(0)
-
本日の偶然「7777」
万歩計の数字を見たら「7777」歩。(「000」→「111」→「7777」。次はあるのか)
2013年10月18日
コメント(2)
-
本日の偶然「1時」
夜中、電子レンジのリセットボタンを押して時計表示にすると、表示時間が「1:11」。(前回の「本日の偶然『12時』」も0:00といえる)
2013年10月06日
コメント(0)
-
本日の偶然「12時」
時計の針が12時丁度で止まっていた。
2013年10月04日
コメント(0)
-
降旗康男監督『少年H』を観た(その1)
ステレオタイプ。力点の場所を間違えている。固形物ばかり喰うな。「相棒」役者発見祭り。 この映画は褒めないと“政治的”に正しくない事になりますよ。愛国運動も結構ですが、貶すと馬鹿と思われますよ(BYニポンリベラル)。以上感想終わり。 (以下、“政治的”に“良い子”の皆は読んじゃ駄目だよ) アホらしいのでだらだら書きます。 テレビで充分です。いつか必ず放送するでしょう。作っているのはテレ朝ですし。 水谷豊を観に行ったようなもんです(「相棒」好きだから、まぁいいか)。 想像以上に駄目でした。 まず原作。これが一部では有名な代物。妹尾河童の『少年H』。これが酷い、作者の人格が疑われるレベルと大評判(?)。 「自らの記憶と体験を元に書いた作品である」と言いながら、「お前は超能力者か!」のありえない記述のオンパレード。戦後明らかになった史実を何故か父親が知っていたり、参考にしたモト本『昭和二万日の全記録5巻・一億の「新体制」』の誤記を右から左に写していたりと、「何がどう、自らの記憶と体験なんだよ」の世界。 あんまりにあんまりな内容に、児童文学者の山中恒氏が『間違いだらけの少年H』という本を態々、病(癌、心筋梗塞)をおして著した程。『少年H』より『間違いだらけの少年H』の方がずっと分厚く興味深い本になりました(笑)。 念の為に書いておきますが山中氏は別にネトウヨ(笑)でも軍国主義者でも何でもない、強いて言えば寧ろ左翼の人です。「夥しい数の歴史的な齟齬と事実誤認」の出鱈目さが嫌なだけ(「年表と新聞の縮刷版をふくらませて作り上げたような作品」「戦争体験者の酒の席での与太話を小説風にまとめただけのもの」とは山中氏の評との事)。 なお山中氏は野間児童文学賞最終審査会でもオカシイ点を指摘したそうですが、ハイ無かった事にされました。出版社もグル。そして目出度く340万部のベストセラーになったとさ。 これはある意味戦前より酷いんじゃない?それともニポンリベラルなら言論弾圧と印象操作はスバラシイのか。せめてやるならスターリン並に徹底すべきでしょうね。左翼の人の批判なのでニポンリベラル大困惑の大混乱。 なお、この『間違いだらけの少年H』が発表されると、妹尾河童はこっそりと指摘された箇所を修正しています。 結局、“超能力”少年「H」クンの「ボクの一家はこんなに聡明で道徳的にスバラシイ一家でした。ドウダ。周りの人間は戦争賛美の馬鹿ばっか。だから僕達のような偉大なリベラル一家が迷惑するんだよね」という自慢話で、当然「ボクのような全知全能、道徳完全人間のリベラル人が、永久戦犯民族ニポン人を支配する。その為には、嘘に印象操作に隠蔽工作と、何をやっても許されるのさ」に繋がる訳です(ニポンリベラルというのは思想上の問題ではなく、ある種の人格異常者が自己の異常性を正当化する為の「オイシイ理屈」として所謂左翼思想を利用しているんでしょうね。〔もっとも「利用できてしまう、親和性がある」と言う事は結構大きい。フランス革命の時から左翼の歴史は言論弾圧、大量虐殺、強制収容所の歴史だからね〕)。 (関係ないけど、山中恒氏ってNHK少年ドラマシリーズの『とべたら本こ』『ぼくがぼくであること』の原作を書いた人だったんですね) しかし、原作がクソでも映画が素晴らしいと言う事はありえるしな(脚本は『三丁目の夕日』の古沢良太氏)。 それに、「盛られている思想がウ○チでも、映画としての評価は別」だしね(ナチの宣伝映画『意志の勝利』は冒頭の空撮から見せたものね)。 という訳で、観てきました。同行者は戦争体験者の老母(昔の事を思い出すのはとても良いそうだ)。 前半は当に上記の原作のノリ。“超能力少年H”の“超能力者”ぶりを遺憾なく発揮されております。「新聞で報道されているのは皆嘘だぁ」とかね、超能力で判るの(笑)。 ニポンリベラルのプロパガンダ。 プロパガンダでも別に構わないけど、台詞で主張(イデオロギー)を“説明”しちゃうというのは、映画として駄目なんじゃない。 以下、如何にもニポンリベラルが言いそうなエピソードの連続。所々に妹尾氏の“自慢”が入ります。 ステレオタイプのオンパレード。 横目で見たら、老母は寝てました。そりゃ寝るわな。 起こす鬼息子。 映画終了後、感想を尋ねたら一言「(主人公一家が)固形物ばかり食べている」。そこですか(笑)。 ここ、説明が要りますかね。当時、日本の都心部は食糧難でとても薄い雑炊(?)ふうの“何か”を食べているのが普通だった訳です(念の為、書いておくと、日本の全地域がそうだった訳ではないよ。地方の農村なんかでは、一番酷い時でも白米をお腹一杯食べていたという所もある。色々ね) ストーリーの展開上、“液状食品”を出せなかったのかも知れないが、“プロパガンダ”としてここは間違えていると思うよ。「戦争は悲惨だぁ~。だから反対だぁ」と言いたい訳でしょ。だったら、こういう点をリアルに描写しなきゃ。台詞で“説明”してどうすんの。 反戦物は細部描写が大事。 私も寝そう。 ここで映画評論の神、淀川長治の精神を思い出します(笑)(この人は凄かったね。「どんな映画でも必ず良い所がある」と必ず褒めるの。どうしようもないクソ映画でも「レストランのシーン。出て来たお皿の模様が素晴らしかったですね」(笑)スゴイよ) という訳で、「脳内『相棒』祭り」(笑)。 この映画、「相棒」でお馴染みの役者さんが結構出ているんですよ。君は何人見つけられるか。 「小野田官房長」の岸辺一徳さんは直ぐに判る。吉村役の国村隼さんは「劇場版2」に悪役の「長谷川警視庁副総監」で出てたね。他、錠剤大好き「大河内監察官」の神保悟志さんがチラリと出ていた(たぶん)。 「脳内『相棒』祭り」の最大の山場はこれ。 トリオ・ザ・捜一の一番若い「芹沢巡査」が「杉下右京」を拷問していた(笑)。鉛筆を指に挟んでグイグイ。いいのか、芹沢。イタミンならまだしも、芹沢が杉下右京に拷問かけるとは。芹沢、大きくなったな。ファンとして嬉しい(笑)。 本来なら特高警察は鬼畜のイメージ(ステレオタイプ)なんだけど、「芹沢巡査」のイメージが強すぎて、そんなに悪い人に見えないなぁ。 結局、この映画の最大の問題点は「鑑識の米沢さん」の六角精児さんと、「暇かっ」の「角田課長」山西惇さんが出ていない事にある、といえるだろう(なんかもう、「相棒」の役者さん観に来てる感じ)。(その2)に続くのかぁ。
2013年08月07日
コメント(2)
-
降旗康男監督『少年H』を観た(その2)
(その1)の続き。 後半は少しマシに。 ステレオタイプではなく、“人間”として父親が描かれる様に。 少年Hが、人格のマトモな軍事教練担当の軍人から、自分の教練射撃部に入部しないかと誘われた時の、父親のアドバイス。「それで配属将校から目をつけられなくなるなら、入ったほうが良い」。同様のアドバイスを母親にも与える。 また、少年Hが米国から来た絵葉書を友人に見せたばかりに、机に「スパイ」と落書きされる破目に。怒って少年Hは友人を詰問しに行こうとすると「その友人もお前に言われた通りの事を友達に喋っただけじゃないのかい。犯人探しなんて詰まらないからおやめよ」。 大人の優しさと知恵で諭す父親。水谷豊の演技もあって味わい深い。 こういう所を膨らますべきじゃないのか、この映画。力点の場所を間違えている。 イデオロギー宣伝に主力を注ぐと、“硬直”した平板な人間像しか描けなくなくなってしまう。それは、どこの時代のどの国、どの民族にも通じる、豊かな人間描写を放棄するという事なんだよね。 それに、時間も喰われちゃう(笑)。 後半は、折角“面白く”なって来たにも関わらず、詰め込み、端折り過ぎ。 終戦後、あの聡明で物静かだが強い意志を持った父親が気が抜けたような虚脱状態になる。 興味深いエピソードなのに、ここ説明不足。軍国主義者、国粋主義者が負けた為に放心するのは判る。しかし、父親はそれらと全く正反対の人物の筈。何故、虚脱状態になるのか。これは「ミシンが焼けて仕事が出来なくなった」だけでは説明がつかない。 少年Hが自殺を決意するまで悩む、というのも、描写が足りないせいで「なんじゃこりゃ」。唐突に始まり唐突にエピソードが終わる。 ホント端折りましたね。 ここをメインに描写しなきゃ駄目じゃない。 原田泰造演じる軍事教練教官が可笑しい。脚本家も監督も恐らく意図しない所で可笑しい。 戦前は少年Hをボコボコに殴る鬼畜野郎で、おぉ、原田泰造氏見事に好演。 で、戦後コロリと180度転向。共産党の演説集会なんかに出席している。 で、少年Hは「大人は信じられなぁ~い」と。 でも、そうは感じられない。 少年Hが転向を難詰すると、原田泰造、やたらと腰が低い。人の良い庶民という印象だけ。小狡さ、卑屈さが感じられない。 つまり戦争中という特殊な社会状況だったから、凶暴であっただけで、元々は小心で善良な人物。単に元に戻っただけ(これ演じた原田泰造氏の解釈か)という事。転向という感じではない(糅てて加えて時々テレビで観るお笑い芸人としての印象もあって、「原田泰造。許してやろうよ。根はいい奴だよ、たぶん」(笑)。 「大人は信じられなぁ~い」という話にするのなら、「腰が低い」では駄目。 『橋のない川』の住井すゑレベルのクソクズ人間を出さなきゃ駄目。 「戦争はありがたい。戦争は価値の標準を正しくしてくれる。そして人間の心に等しく豊かさを与えてくれる」「戦争はありがたい。あり余る物によって却って心を貧しくされがちな人間の弱点を追い払って、真に豊かなものを与えようとしていてくれる」 住井すゑ。このクソクズは戦争中散々、こうした戦争賛美の随筆や小説を書いていたのだが、戦後一転「戦犯天皇粉砕ぁ~い」の反戦反差別作家として出版、言論界で絶大の権勢を誇っていたのだ。 「そんな筈がある訳がない。ネトウヨには困ったもんだなぁ。ははは」と思ったでしょ(脊髄反射かい)。 これは朝日新聞社の雑誌『RONZA』(95年8月号)に特集を組まれていたもの(「朝日はネトウヨだぁ」か)。 あのアサピーですら、この住井すゑのクソクズっぷりに腹を据えかねたのだろう。 だが、それだけではない。 朝日の記者がこの件を突っ込むと、なんと住井すゑは「ほほほ・・・。何を書いたか、みんな忘れましたね」「書いたものにいちいち深い責任感じていたら、命がいくらあっても足りませんよ」と答えているのだ。 本当の人間のクズ。というより人格異常者だろう。正にこれが“ニポンリベラル”の正体。 (今、この“衣鉢”(笑)を継いでいるのが、大江健三郎。このクズも原発を容認していたくせに、なんの説明もなく口をぬぐって反原発の旗手サマに御転向で、一山当てました。さすが、独裁国家北朝鮮を賛美しているだけの事はあるよ) そう、このレベルの鬼畜、クソクズっぷりを出さなきゃ「大人って信じられなぁ~い」の説得力が出ない。原田泰造じゃあ、ただの「いい人に戻ってよかったね。目出度し目出度し」だ。 だが、クスクズは出せない。無理だ。何故か。 作者の妹尾河童も、“ニポンリベラル”だから(笑)。 モスクワ映画祭で受賞したのは“政治的”理由だろうな(地下資源がらみの問題でロシアは接近したがっているからね)。 いや、もっと情けないレベルで、そもそも「戦争中、日本人が大量虐殺されていた」という事に衝撃を受けたからかも知れない。 殆どの大都市は空襲で徹底的に破壊され、日本人非戦闘員が大量虐殺されていた(1945年3月10日の東京大空襲だけで死者10万人以上)。海外では、一流のジャーナリスト、インテリの類でさえ、こうした事実は全く知られていない。えっ!って驚くぐらい知られていない。 結論。 プロパガンダなら、プロパガンダでもいいけど、プロパガンダ映画としても三流。 出演俳優のファンだけ、テレビで見ればいい。 たぶん、ちゃんとした“反戦”映画を作りたいなら、第二次大戦に材を取ってはもう駄目なんじゃないでしょうか。ひょっとして角田課長出てた?
2013年08月06日
コメント(0)
-
本日の偶然「ピンクの安全ピン」
路上で安全ピンを拾う。長さ5センチ程の物。針を引っ掛ける部分はプラスチック製で色はピンク。 翌日、全く別の場所で同一製品を拾う。どちらも「LOCK R JAPAN」の文字。他、一方は「D-1」、もう一方は「MD-5」の文字も。
2013年08月05日
コメント(0)
-

鈴木一義著『からくり人形』を読んだ
豊富な写真。鯨発条の限界が残念。 からくり人形の写真が多数収録されています。からくり人形は美術品としても側面もあって目を楽しませます。 ただ惜しむらくは、どのような動きをするのか判り辛い点。分解写真のような図解が欲しい所です。 江戸時代、金属発条がそれ程普及していなかったのは残念な事です。鯨発条は金属発条に比べどうしても力が弱い。 メモ書き。p4 からくり儀右衛門こと田中久重の製作した「弓射り童子」の連続写真。的を見定める首の動きが大変素晴らしい。ほんの少しだけ首を傾げている。 この「弓射り童子」人形は個人向けの商品であった。お金持ちではあろうが、貴族や特権階級向けではなく庶民が買っていた物だったのだ。 この辺り当時の歌舞伎とオペラの客層の違いと似ている気がします。日本文化の特異性とは庶民文化の洗練に多く拠っているのでしょう。p74 「弓射り童子」の人形の表情。 「西洋のオートマタであれば、目や口が動くところであるが、『能』にみられるような極めて日本的な動きで、同じ動きであるのに、矢が当たったときはうれしさが、外れたときは悔しさが見事に伝わってくるのである。」 そういえば、現代のからくり人形とでも言うべき恐竜のロボットで、日米に差が見られたのは面白い事と感じた事がありました。米国製の恐竜ロボットは眉の辺りが動くのです(これは科学的にはオカシイよね)。これは恐竜の登場する子供向きのアニメなんかも同じですね。欧米人が作ると欧米人の“顔”をした恐竜になる。p22 「中国では時計でも、世界に先駆けて優れた機構を発明していた。11世紀、宋の時代に蘇頌(そしょう)、韓公廉(かんこうれん)らが水運儀象台なる天体観測機械を作っている。この機械は水を利用して動きの周期を決め、天球儀や時計などを自動運行していた。この機構が後に西洋に伝わり、機械時計の基になったとも言われている。」 中国の技術の多くは一部特権階級に貢献するだけのものだったのに対し、西洋は実用、生産の手段として発達させた、との事。どうして両者にこのような違いが生まれたのか(技術的には本来支那の方がずっと上位であった)。生産力と生産関係で政治体制や文化が決定されるとする唯物史観の観点からはどう説明されるのか、なんて考えると面白いかも知れません。p36 「遊女の愛したからくり」 吉野太夫「蟹の杯」。精巧な蟹の細工物。甲羅に杯を載せると、歩き出して客のもとに杯を運ぶ。見せてもらった滝沢馬琴が『著作堂一夕話』に記しているある。このからくりは現存している。 他に同種の現存するからくりとして亀もある(蛙や兎だったら(笑)。 この「蟹の杯」や茶運び人形のような給仕をする人形は西洋にはない。オートマタは完全に観賞用の人形。p42 「段返り人形」はしばしば失敗するという話(「段返り人形」とはとんぼ返りのような動きをしながら階段を下りていく人形。人形胴部に納められた水銀等の移動による)。 「綾渡りと同じように、失敗するから人気があったと思われる。西洋のオートマタで、失敗を売り物にしたものなど聞いた事もない。日本人独特の感覚から生まれたからくりである。」 「弓射り童子」には意図的に失敗する矢が混ぜられています。 演出上の効果としては日本の方が一枚上手。 ただ、もしからくりを自然の模倣、再現と捉えるなら、西洋と日本の自然観の違いが現れているのかも知れません。謂わば、最初に神様が螺子を巻けば後は自動的に間違いなく運行される“自然”と、その都度生成し変化する“自然”の違い。p76 江戸時代の日本は「無螺子文化」。 技術レベルは非常に高く、かつ「螺子」という概念を全く知らなかった訳でもないのに、普及しなかったのは何故だろう。p49 「幕末から明治初期に活躍した田中久重は現在の東芝の前進である芝浦製作所の創始者としても有名である。」からくり儀衛門が東芝を作ったのか。p108 「(幕府)天文方に文化八年(1811)設けられた蛮書和解御用係は後に、開成所を経て、東京大学の母体となっている。」東大のルーツは幕府天文方だったのか。p108 伊能忠敬が全国測量に使った器具を製作したのが、大野弥三郎規好。その息子の大野規周は文久二年(1862)、欧州に留学生として派遣されている。この当時から職人(技術者)を派遣していた訳だ。 彼の腕にはオランダ人技術者も驚嘆したという。p108 文政年間には大野規周らの他にも天文具司や測器師が現れる。それも幕府御用ではなく、一般庶民向けであった。 大隅源助を名乗る店の引き札(広告)が残っている。江戸時代から浅草茅町二丁目で営業され、眼鏡、望遠鏡、温度計、時計、幻灯機らしいものの広告がある。 凄いね、江戸時代。流石に子供が「望遠鏡、買って、買って」と店先で駄々を捏ねていたとは思いませんが、大店の道楽息子が買って帰り、太鼓持ちが「よ、若旦那、粋なご趣味でげすな」ぐらいは言っていたかもしれません。女の子にも、もてたんじゃないでしょうか。p110 からくり伊賀七の「酒買い人形」の話。 「茶運び人形」の様なものであろうか。筋向いの酒屋まで酒を買いに行ったという。酒の量を誤魔化した時には動かなかったという。 動力は何だったのであろうか。誇張された伝説のような気もします。p113 「からくりでは、まさに科学と技術の区別がない。目に見えるものが全てである。」 名言のような気がします。p86 1800年代には真鍮の手延べの発条が使用され始める(田中久重らが使用)。 金属加工の為の知識と技術は当時の最先端のもの。例えば、沖牙太郎は江戸時代は秋芸藩の銀細工師であったが、明治になってからは、その知識と技術を活かし、電信機などの製作を行い、現在の沖電気の創始者となったのである。 日本の電気メーカーの歴史を辿ると、江戸時代まで行き着くというのは興味深い事です。明治維新でいきなり近代化した訳ではないんですね。【からくり人形 弓ひき童子】自ら矢をとり、連射する脅威の機巧 学研大人の科学価格:8,900円(税込、送料別)
2013年07月09日
コメント(0)
-
本日の偶然「アガサ・クリスティ」
入浴中、有名な推理小説家の名前が思い出せなかった。 入浴後トイレで阿刀田高作の『こんな話を聞いた』を読むと、アガサ・クリスティの逸話が出ていた。 そう、アガサ・クリスティだ。エラリー・クイーンは直ぐに思い出せたのに。(「オリエント急行」のトリックはあひぁ~だったなぁ)
2013年06月22日
コメント(0)
-
ヤーロン・ジルバーマン監督『25年目の弦楽四重奏』を観た
傑作。カタルシスゼロの大人の味わい。たとえハーモニーは崩れるとも、人生は続く。 文句なく傑作だと思います。お勧めです。 ただし、若い方は感情移入が難しいかもしれませんね。 粗筋。 世界的に著名な弦楽四重奏団「フーガ」。記念すべき25周年に演奏するのは難曲ベートーベンの「弦楽四重奏第14番」。 ところが、リーダー的立場の老チェリストがパーキンソン病に蝕まれてしまう。引退を決意するチェリスト。友情以上の固い、しかし繊細な絆で結ばれていた弦楽四重奏団メンバーに動揺が生じる。 やがてその動揺は、メンバー達が当人達も気付かずに蓄積していった様々な葛藤を表面化させて行く。競争心、嫉妬、怒り、そして浮気。 果たして、25周年記念演奏会の幕が上がり、「弦楽四重奏第14番」は演奏されるのだろうか。 粗筋のみですと、他にも同工異曲の作品があるのではと、お思いになるかと思います。 私もロックバンドの話で観た事があるような気がします。仲のよかった仲間が、途中から仲間割れ。しかし、ある切欠から再び友情を取り戻し、ロックコンテストやらレコーディングやらに漕ぎ着け、目出度し、目出度し。こういった話。 ただ、思い出して欲しいのですが、貴方がご存知のこういった話、それは、「青春物」ではありませんでしたか。そして「青春物」に相応しく最後はハッピーエンドで、スカッと爽やか、カタルシスが感じられる映画だったのではないでしょうか。 この映画は違います。何しろ「25年目」ですから。全員、中高年(笑)。 簡単にやり直せるようにはなりません(というより、無理でしょう)。 “文芸映画(ここではこの語を褒めて使っています(笑)”なので、この辺り、娯楽色の強い、所謂“ハリウッド”映画とは違う展開です(所謂“ハリウッド”映画なら、絶対「年齢なんか関係ない。いつでもやり直せる。いつでも心は若者さ。若さバンザイ」という話になるのでしょう)。 その為、最後に、スカッと爽やかなカタルシスが観客に与えられる事はありません。ある意味、苦い映画なのです。 だが、最後の最後に、希望ならざる“希望”とでも言うべきものが立ち上がり、話は「解決が付かない」という“解決”をみる事になります。 逆説的な話です。 若者ではないから修復は不可能。しかしそれ故に、「人生にはそういう解決が付かない問題もあるのだ」という知恵を身につける事が可能になるのです。 ただ、最後の最後にメンバーに大きな変化があった後の演奏の音色、それはそれ以前に比べ、力強く、明るく、希望に満ちたような響が感じられます。 やっぱり、ハッピーエンドなんでしょうね。 ベートーベンの「弦楽四重奏第14番」を人生のメタファーに持ってきた本作品、着想の点で素晴らしいです。 ベートーベンの最高傑作の一つとも言われ、愛好家の多いこの楽曲は、全7楽章をアタッカ(楽章の境目を切れ目なく)で演奏する事が要求されます。約40分間弾きっぱなし。人生の様に止まることなく進むよりしょうがない。 たとえ演奏するに従って、楽器の音程が狂ってきたとしても、途中で調律は不可能。人生と同じように、元に戻って最初からという訳には行きません。 “ハーモニー”が徐々に失われていく中、どう“曲”を弾き続けるのか。 老チェリスト役にクリストファー・ウォーケン。私が最初に印象に残ったのは『デッドゾーン』でした。もうスッカリお爺ちゃんですね。最近だとテレビ東京『孤高のグルメ』シリーズでの飄々とした演技が印象的です(それ違う違う、松重豊さん)。 他、「冷静沈着の筈がやっぱりそりゃマズイよ」の第一ヴァイオリン奏者役にマーク・イヴァニール。「秘めた矜持」と「馬鹿やっちゃって」と「鉄拳」であがくの第二ヴァイオリン奏者役にフィリップ・シーモア・ホフマン。「妻、母、演奏家の全部は無理が露呈」のヴィオラ奏者役にキャサリン・キーナー。「意外とこの子が一番大人の判断を示したんじゃない」のヴィオラ奏者の娘役にイモージェン・プーツ。見ごたえばっちりの一流の役者さん達、演技の火花が散ります。 本作品、“欧米文化”というものも感じます(テーマは充分に普遍的なんですが)。 「あそこで、あんな直球で事を言わないだろう。やらないだろう。空気読むだろう」という気がするシーンもあって、でも当然の事ですが、そもそも“空気”に当たる概念が欧米にはないのでした。よって、即座に亀裂は表面化。 日本人だともっと隠微な展開になっていたかも知れません。文化の“チューニング”能力(これはこれで大変なんだけどね)。 ベートーベンの「弦楽四重奏第14番」は、バッと上がって、ポンッて感じで終わる印象。これはこれで幸福な人生かな。
2013年06月20日
コメント(2)
-
雀の雛を拾ったのだが
雀の雛が路上をうろうろしていた。車の通りが結構あり、雨も降っていたので、連れて帰る事にした。 薄めたポカリスエットなどをやったのだが、翌日、動かなくなっていた。 念の為動物病院に持って行ったがやはり死んでいた。 こういう場合、連れて帰らないという選択肢もあったと思う。 どうも最善の方法は、「新聞紙等を敷いた開いた箱に入れ、拾った場所付近の、猫の手の届かない場所に安置する事」らしい。 雀が飛んでいる姿を見ると、当分は思い出すのだろう。 猫は時々雀の子を獲って来ると聞く(わざわざ飼い主に見せに来るらしい)。そのような存在だから、そうしているだけだ。 人間はなんとも面倒くさい。 晩御飯のおかずは鶏肉だった。 “命”は語りえないものだから、“生物”についてのみ語るべきだと思う(目の前の鶏肉の元となった鶏と雀の雛は違うとしか言いようがない)。
2013年06月13日
コメント(0)
-
陳舜臣著『巷談 中国近代英傑列伝』を読んだ
意外と盲点だよね、近代中国史と日本。 近代中国の歴史的重要人物の多くは留学、亡命等、日本と関係が深い人物が多い。この辺り、今の中国ではどういった扱いなのでしょうか(たぶん党による隠蔽)。 一方日本では、「近代中国に於ける日本の影響」と言えば「兎に角、悪事しかしてこなかった。未来永劫永久に土下座謝罪です!」としか教えてはいけない事になっている(こちらもニポンサヨクによる隠蔽)。ニポンサヨクの紋切り型台詞「ニポン人は歴史を知らない」の“歴史”とは「特定歴史」とでも称すべきものなのでしょう。 有史以前からの両地域の密な交流関係(一方向的な関係じゃないよ)は、戦前まで脈々と続いていたのに、この認識は。 中国では共産党が独裁体制を敷き、日本ではニポンサヨクがヘゲモニーを握っている今が、一番両地域が疎遠になった時代なんじゃないでしょうか。皮肉と言えば皮肉、当然と言えば当然の話なのでしょう。 とはいえ、話題に挙がる中国史が古代(三国志とかね)にのみ偏っているとは言えそうです。「中国近代史と日本」というのはもっと語られて良いテーマでしょう。 (忙しいので今回は手抜きのメモ)p14「もっとも倭寇といっても、その八割は中国人だった。王朝交代期に前王朝の残存勢力で海にのがれた者、もともと戸籍をもたない者など、自分だけでは勢力にならない者が倭寇と称して海岸を荒らしたのです。」 八割!ならば殆ど“冤罪”ですね(他に朝鮮人もいたとすれば、更に日本人の割合は)。p122「1902年、魯迅は江南督練公所から派遣されて日本に留学します。1年後に魯迅は辮髪を切る。そして「私にはじめて満漢の区別をさとらせたのは、書物ではなく辮髪であった」と留学当初のころを回顧しています。(辮髪を切った為、帰郷すれば謀反人として殺される魯迅は、上海で2元で辮髪のカツラを買っているとの事)。」 恐るべし、辮髪!切れば死刑(あれ、トイレで誤ってウxxの上に垂らしちゃうなんていう事はないのかな)。p142 シンポ的知識人から見れば、“反動”であった王国維の人生の哀しさ(入水自殺っていうけど、意外と水深浅かったのね。湖底の泥による窒息死だったのか)。 中国史関連の本を読むと、しばしば妙な気分に襲われます。「あれ、何時代の話だったっけ」。時代の“ホワイトアウト”現象。時代の前後が一瞬混乱。 マルクスなぞは馬鹿にして「アジア的停滞」なんぞと言っておりますが、「中国は古代から進みすぎていた。進みすぎていたから後は特に変化(進歩)しようがない」と言えると思います。 でもこれ、逆に言えば、「現代でも“古代”“中世”」とも言える訳で。 現代中国の社会事情は時々日本人を面食らわせますが、あれ、所謂“近代”の感覚ではないからかもしれない。 「近代」は普遍的か。あるいは超地域的、超民族的なものか。
2013年05月26日
コメント(2)
-
本日の偶然「15%」
日経新聞5月9日朝刊第38面に「DV被害の支援センター 『即日保護必要』15%が経験」の見出し。 一方同第39面に福島避難区域で「事業再開わずか15%」の見出し。 当然、前者は「15%も」の意味で、後者は「15%しか」の意味だろう。 (しかし前者が後者の「わずか」の語に引っ張られてしまう印象)それはジュゴンだねぇ。
2013年05月09日
コメント(0)
-
私的連想のメモ
「ホルン」から「トリケラトプス」(逆も可) これは、明らかに形状が似ているので、誰でもそう連想するだろう。 「栗毛の馬」から「黒砂糖の味」 「黒砂糖」ではなく「黒砂糖の味」。色が関連している事も想像できるが、多々ある茶色の物の中で、何故「黒砂糖」なのか不明。なお、「黒砂糖」を口に含んでも、「栗毛の馬」のイメージは浮かんでこない。一方向的な連想。 「ミッキーマウス」から「ネギの臭い」 これも「ネギ」ではなく「ネギの臭い」。ここで連想される臭いは独特な不快臭。子供の頃から、ミッキーマウスの姿を見る度に、ネギ臭が感じられて困る。 何故かは不明。
2013年04月29日
コメント(0)
-
本日の偶然「焼き鳥」
焼き鳥をおかずに食事中、テレビで取り上げられていたのが「焼き鳥」。 「偶然の一致に気付くという事」つまり「それを何か意味のある一致と考えるという事」は、確かに私と私を取り巻く世界の“何か”を示していると思う。 とりあえず、焼き鳥は(スーパーの割引品は特に)、アツアツでないと美味しくないよね、という事は判った(笑)。
2013年04月12日
コメント(0)
-
英国人の日本人蔑視の一例
ロルフ・ハリス著『動物ウソ?ホントの話』を読んだ。 (本自体は頭の凝らない雑学本といった物だが、同じような話が多く、飽きる。「イルカが人を助けた話」と「犬が遠く離れた飼い主の所に戻った話」が幾つも) その中の記述(p178) 「メスのアヒル「ドナルド」は、第二次世界大戦中、第二ゴードン高地連隊兵たちのマスコットだった。 そのドナルドが日本軍につかまって、あわや殺されそうになったとき、スコットランド軍のウィリアム・グレイ伍長は、とっさに突拍子も無い嘘をでっちあげて、ドナルドの命を救っている。 日本の占領軍にむかって、スコットランド人はむかしからアヒルを信奉している民族だ、とのたまった!ドナルドは神聖な生き物だから、毎朝欠かさず日の出の時刻に、軍全体であがめたてまつらねばならない----と。 すると、迷信深い日本の兵隊達は、アヒルを殺す決定を中止して、おそるおそるドナルドを遠巻きにしながら歩いたものだ。 当のドナルドはというと、腹をすかせた戦争捕虜たちのために、それまでどおり卵を産み続け、終戦まで生き延びて、グレイ伍長と一緒に無事にスコットランドに帰っている。」 「迷信深い日本兵」(嘲) 「アジア人は劣っている」という植民地支配者根性丸出し。隠そうともしないね(「敵国である我々英国人の宗教まで日本兵は尊重してくれる」と英国兵が確信しているところがミソ。本当は「信奉しているのなら、是非とも殺さなきゃ」と敵国兵士なら考えてもおかしくない)。 単純に最初からアヒルを殺そうとも考えていなかっただけの話だろう(アヒル料理ってどんなのか想像出来る日本人が現代でさえどれほどいるか)。英国兵のペット飼育にまで配慮してやっているに過ぎない。 日露戦争時、ウラズオストク巡洋艦隊を攻撃した大日本帝国海軍第二艦隊司令官、上村彦之丞は海上に投げ出されたロシア兵600人以上を救出しているが、この時、ロシア兵の飼っていたカナリアまでも救助している(ロシアの教科書にも載っていたらしい)。 また第二次世界大戦時、スラバヤ沖海戦で大日本帝国海軍駆逐艦「雷」の工藤艦長が撃沈された敵国英国艦隊の将兵を、422名も救出している。「諸官は勇敢に戦われた。いまや諸官は日本海軍の名誉あるゲストである」とは工藤艦長の英国兵へのスピーチ(英国艦隊の潜水艦に攻撃される危険があった。救助は大変危険な行為)。 残念ながら、親切にされて感謝する人たちばかりとは限らない。逆に「日本人は馬鹿だから親切なのだ」と考える者も世界には大勢いるという話(念の為。感謝される為に親切にする訳ではない。それが善事だから為すべき事。しかし、「逆に馬鹿にされる可能性」を常に念頭に置くべき。“善人”と“愚者”は似て非なるもの)。 この本にも凄い話が載っている。英国人女性が日本人捕虜の前で平気で裸体をさらしていたという話。“動物”の前で裸を恥ずかしがる必要がないから。“餌”を投げ与えていたらしい。
2013年03月30日
コメント(0)
-
星新一訳『竹取物語』を読んだ
単なる訳本ではなかった。星氏の分析が面白い。 星新一氏の本は数冊を除いて全て読んでいると思いますが、この本はその例外中の一冊でした(因みに他は『生命のふしぎ』『黒い光』『天国からの道』)。 ただの翻訳だろうと敬遠していたのですね。流石に竹取物語なら話を知らない訳はありませんし。 しかし、読んでみると意外に面白いものでした。 章が変わるごとに「ちょっと、一息」と星新一独自の感想が入るのです。この部分が想像以上に長い。長くて得した気分。 主に創作者としての視点から、竹取物語の“工夫”と“仕掛け”について、星新一が解説していきます。 五人の求婚者のそれぞれの特徴分析など面白いなぁ。そもそも各々に性格的な違いがあると、考えた事もなかった(子安貝の人だけ若干違うかなと思った程度)。やはり、きちんと読まなければいけませんね(「有名な物語の不幸」というものはありますね。誰でも粗筋を知っているので、読んだ気になっちゃう。読む気になれない)。 また、性格に関する論評も星新一ならではのものが感じられます。例えば、騙す為、「玉の枝」の偽造を職人に命じて作らせ、延々とかぐや姫に冒険譚を語った求婚者。私の昔受けた印象では、悪知恵の働く汚い人物というものだったのですが、星新一は違います。 p50「計画の立て方もよかったし、それなりの努力もしている。」 p51「まったく、すごいやつさ。その着想、財力、努力、物語を作らせても天下一品。しかも、身分だっていい。普通だったら、理想的な人物と扱っていいと思う。」 ちょっと、ちょっと(笑)。しかし道徳訓ではないのだから、こういう評価で良いのでしょう(“アメリカンドライ”だね、星新一氏は)。 一方、子安貝を得るべく、律儀に燕の巣を探っているうちに落ちて死んでしまった人物。私の昔の印象では、まぁまともな人物というものでしたが、星新一の評は p88「この人物の特色は、他人の意見をつぎつぎに求め、よりよい意見があると、それを試みる。最後には、自分で確認しようとする。経営学のはじまりみたいだ。」 p89「この部分の物語の面白さは、自主性のない人物と、その部下の男達の、ドタバタにあるのは、すぐにわかる。」 とバッサリ。 天人がかぐや姫に着せる、羽衣の機能のアイディアが凄いと星新一。着用させると思考を一変させてしまうのです。確かにこれは凄い着想。空を飛ぶとか、百人力になるといった物理的なものは思いつくでしょうが。少なくとも10世紀以前にこのアイディアは凄い(これも指摘されて気付いたなぁ)。 なお、星氏はチベットにある竹取物語類似の民話との関係について、日本の竹取物語が伝わったものではないかと、述べています(自分の作品も良く翻訳されているので、そのうち自分の話も民話扱いになるのではないか、だって(笑)。巻末に原文も収録されていました。
2013年03月12日
コメント(2)
-
平松恵美子監督『ひまわりと子犬の7日間』を観た
必要なのは感傷ではなく考える事では。 う~ん。これで良いのかなぁ。 話の決着の付け方も、描き方も、これで良いのかなぁ。 でも、実話だそうだからなぁ。良いも悪いもないのか。 やっぱり犬の映画だと点が甘くなります。 パンフより粗筋。 保健所に収容された母犬と生まれたばかりの3匹の子犬。母犬は近寄る人全てに激しく吠え、懸命に我が子を守ろうとする。妻を亡くし男手一つで二人の子供を育てる保健所職員の主人公は、そんな母犬の姿に心を打たれ、彼らを助けようと奮闘する。だが、保健所が預かれる期間は7日間だけであった・・・。 主演は堺雅人。私の好きな俳優さんです。ご出身は宮崎県だそうで、本映画の宮崎弁は“ネイティブ”。 また本映画監督の平松恵美子女史は20年間山田洋次監督の助監督を務められた方だそうです。そういえば、山田洋次監督の後期作品に作風が似ている気がします。 犬の演技が素晴らしい(正確に言うと「調教師の宮忠臣さんが」でしょうが)。母犬を“演じた”柴犬は『マリと子犬の物語』でマリ役を務めた犬だそうです。2作も主役級を務めたというのは大スターですね(牙をむき出しにして威嚇しているアップのカットが数箇所あるが、あれは機械仕掛けのぬいぐるみなんではないだろうか。少しぎこちない気がする。機械仕掛けのぬいぐるみは一箇所も使っていないのなら、完全に脱帽)。 オードリーの若林正恭氏は本作品が映画初出演。 初出演なのに出るわ出るわ、完全に主要登場人物。出来は、う~ん「初めてにしては上手い方です」。 オードリーの若林氏って動きで笑わせる芸人ではないよなぁ。なんで抜擢したんだろうか。暇をもてあましてブラブラしている演技とか、こけて転ぶ演技とか、あんまり笑えるとは思わず。漫才コントの才能と喜劇俳優の才能は全く別のものだと改めて認識。 まぁ、演じた人物の人柄の良さは伝わったので、それで充分なのでしょう。 ここからネタバレ。 肩透かしを喰ったような気分です。 ストーリーとしては『ロレンツォのオイル』のような展開を期待していました。 つまり、「“感傷”を越えて、理知と人々の協力により解決“方法”を見つけ出す物語」という事ですね。 本映画、ハッピーエンドなんでしょうかね。 というより、ハッピーエンドにして良かったのか(そりゃ、実話だからこうなるんだと言われたら、終わりなんですが)。 たまたま、この犬が良い人に巡り合ったというだけですよね(身も蓋もない言い方ですが)。 収容施設の他の犬はどうなったんでしょうか。 (そもそも題名の「7日間」からして首を捻ります。だって最終的には保健所職員の方が引き取るんですよね。だったらさっさと初めから引き取って、自宅で7日間といわず一ヶ月でも一年でもたっぷり時間を掛けてこの犬の心を開けばいいじゃないですか。「この犬を第三者に引き取らせたい。しかしその為には人を噛む状態じゃ駄目だ。あぁ時間は7日間しかない」だと思いましたよ。「おぉ、この主人公の保健所職員は2頭も大型犬を飼っている。なるほど、これはこの人が新たに犬を飼えないという、伏線だな。上手い」なんて、そんな事も考えておりました(笑)。これもやっぱり「実話だからしょうがない」かなぁ) ここには(観客自身の問題でもあるという)普遍的な“方法”への“希求心”“意志”がない。普遍的な“方法”を求める心がなければ、(観客とは所詮関係のない)ただの“感傷”と“感想”が残るだけなんでは。 いや、別にいいんですけどね、映画だから。値段に見合う分だけ楽しんで、それで帰れば充分ですから(皮肉に非ず。映画は“商品”なり)。 ただ・・・。 「現在、日本では年間約8万7千頭の犬が保健所に収容され、そのうち約5万3千頭が殺処分されている」とはパンフの文章。 本作品、制作者サイドは所謂“社会的問題”の提起を願ったと思うのですが。 本作品では犬が大量殺処分されている原因を、犬を棄てた人間の“人格”にのみ求めています。つまり「世の中には悪人がいて、悪事を行う。何故悪人は悪事を働くかというとそれは彼らが悪人だから」という思考停止の循環論法。 そりゃ確かに犬をただの玩具だかアクセサリーだかの“物体”だと思っているクソ野郎もいますよ。 しかしそれで、殺処分されている5万3千頭の全てを説明できるんでしょうか。 典型例が本作品に登場した「老衰し恐らくは病気の大型犬」を保健所に引き取ってもらおうとした市民と保健所職員の問答のシークエンス(画面に市民は登場しません。オードリー若林氏演じる職員の報告という形)。 本映画では市民がただのクソ野郎という設定なのですが、現実の問題としてどうか。 仕事による転勤、飼い主の健康問題etc、様々な理由で犬が飼えなくなる、泣く泣く手放すという事があるのではないのか。 無論、通常引き取り手を探すわけですが、「老衰し病気の大型犬」を引き取っても良いという人がそう簡単に見つかるとは思えません(見つかった場合でも多くは「既に老衰し病気の大型犬を飼っている」ので更にもう一頭飼うのは難しいでしょう)。 どうすれば良いのでしょうか。 「どうすれば良いのか」と考えるべきなのであって、それを「悪人がいるからだぁ」で止めてしまってはイカンでしょう(もっと言えば、仮に「原因は全て飼い主の鬼畜人格」であったとしても、その「鬼畜人格の持主」にどう対応するかという問題がやはり出てくる筈です。でもこの映画では「犬を棄ててけしからん」と登場人物が悲憤慷慨して終わり。誰も登場人物は“考え”ようとしないのね)。 また本作品でしばしば「税金」という言葉が出てきます。主に“悪役”が発する言葉です。 “悪役”(市民)が、犬を保健所で引き取ってもらえる根拠として述べているのが「この制度は『税金』で運営されているから」であり、他の“悪役”(主人公の上司)が犬を7日間で処分しなければならない根拠として述べているのも「予算(『税金』)の制限があるから」です(救いは主人公の上司を演じているのがベテラン俳優小林稔侍氏である事。氏の演技のおかげで、“悪役”臭が消臭され、ある程度には良識的な響を持つ台詞となっています)。 恐らくこれ、制作者サイドの「金の問題はどうでもいいんだぁ~。命、命の問題だぁ~」という主張なのでしょうが、本当に犬の殺処分の問題を解決しようと考えるなら、この「金の問題」こそ真正面からまず考えなければならない問題の筈です(しかし映画では非難するのみのスタンス。ここでもだれも“考え”ない)。 本当はここにこそ大きな焦点を置くべきだったと思いますよ(上司をただ予算予算と煩く言うだけの人物として描くのではなく、きちんと上司の立場にも正当性があるのだと描けば、必然的にそこに主人公と上司の対決が生まれ、ドラマに奥行きが出来たと思うんですがね)。 更に言えば・・・。 実は行政側は欺瞞でもなんでもなしに、棄て犬を減らしたいと考えていると思いますよ(役所つまり国家即悪と考えたい人も多いでしょうが)。何故か。 だって、お金かかっちゃうから。仕事も増えるし。別に善意からでもなんでもないですが。 そう考えると、役所は敵でもなんでもない。寧ろ味方につくと考えるべきでしょうね、棄て犬を減らしたいと考える人に取っては。 「お金の為なら“善事”だってなんだってしちゃう」可能性を経済至上主義批判なり資本主義批判なりしている人はよく看過しがちです。 映画のラスト、ほんのおまけ程度に犬の譲渡会が開催されている様子が描かれていましたが、本当はこれこそちゃんと描くべきではなかったんではないでしょうか(ちゃんとここに重点を置いたのなら「“感傷”を越えて、理知と人々の協力により解決“方法”を見つけ出す物語」になった筈なのにね)。 また本映画では、この「7日間」規定による犬の殺処分を、主人公が服務規程違反を犯す事(黒板の数字を書き換えちゃう(笑)によってしばしば“解決”します。 良い人だと思うよ、主人公。だけどそれは別の問題を引き起こしていないかい。 もしかしたら犬の殺処分より、もっと怖い問題を引き起こすかも知れませんよ、こうした考えは。 結局、ある保健所に善い人がいたよね、という話で終わっちゃってます(実話としては良いのですが、映画としてはどうなんだ)。 少なくとも、私にとってはここに感動はなかったですね。(そりゃ、主人公が犬の前で泣く山場では涙腺を刺激されたけどね。そういうのを感動とは呼ばないのです)。感動というのは自分が信じている世界観を揺さぶられるものです。 もし、社会的問題を提起したいのなら感傷的に描いては駄目です。淡々とドキュメンタリータッチでやらないと。いや「タッチ」抜きで「ドキュメンタリー『殺処分』」が一番良いかもしれません(映画『ブタがいた教室』は結構よかったですね)。 “情緒”で人々を動かそうというのはデマゴーグのやる事。人々に“考えて”貰わなければ駄目です。 無論、一人一人が“考えて”出した結論が、自分の主張、支持している(主に政治的に)“正しい”答えと一致するとは限りません。しかし、それで善い筈です。 逆に言えば、民衆という“道具”を煽動して、権力を奪取、保持したい“政治的に正しい”人々は、必ず“情趣”で訴えますね。「ほぉ~ら、こんなに可哀想な人達がいるぞぉ~(そういう私は彼らの代弁者サマであるぞ)」。 かくして、神聖にして犯すべからざる最強権力者集団“弱者サマ”が生まれる訳です。 (因みに、こういう事を言うと「ヘイトスピーチ」認定をもれなく受ける事になりますね) 他雑感。 実話だから、実際に「痛くない、痛くない。ただ怖かっただけなんだよね」の「リアルナウシカ」行為(もしくはムツゴロウプレイ)をこの保健所の方は行ったんでしょうね。噛まれた時に、普通は反射的に腕を引っ込めてしまい、なかなか腕の力を抜くというのは出来ないものです。偉いものです(これ、映画の演出で実際には行っていない、なんて事ないよね。それなら「ナウシカのパクリ」だ。怒るよ)。 山田洋次監督の後期作品って私はあんまり評価していないと改めて認識。一昔、二昔前の所謂“進歩的”主張がもはや何の意味もなく、いや意味がないどころか反って物事を考える上で桎梏にすらなっている状況なのに、その事に気付いていない、というような“鈍感”さ。そんな感じを受けるからでしょうか(でも、“職人”としては、例えば寅さんシリーズは凄いと思います)。 「雲海」は旨い麦焼酎だと思う。協賛しているらしい。 犬食文化のある民族の方が見たら、どういう感想を持たれるのか、少し気になります(「殺処分された犬の肉を売って、その金で収容されている犬の生存期間を伸ばせば良いのでは」なんていうアイディアが出るのでは)。
2013年02月27日
コメント(0)
-
茶柱と呼んで良いのか
(大変尾籠な話で恐縮です。食事中の方、いや食事中でなくてもお読みにならない方がm(_ _)m 出涸らしのお茶の葉を炒って、ふりかけを作っています(七味唐辛子に醤油を少々足して)。 こういう事をするくらいなので、茶葉もそれなりのお徳用。かなり茎が混じっています。所謂、茶柱が立ち易いお茶。 最近はふりかけの供給が需要を上回り、かなりの在庫が。 先日、一挙に不良在庫を処分しようと、椀にこのふりかけを盛り上げ、お湯をかけて吸い物(正確には何だかわからない物)を作り、食べてみました。 茶葉に大量の茎が混じっている為、かなり咀嚼しなければなりませんでした。羊か山羊になった気分。が、食べられぬという程でもなく、まぁ、腹も膨れる物でした。 その翌日。 “小部屋”に行って“仕事”をして、驚きました。 水面に一面、大量の茎が「ぷかぷか」と(多少陽気にそうに)、浮いているのです。牛ならぬ我が身にとって彼らは“ただの通行客”なのでした。 そして、幾本かの茎は、見事に「立って」いたのでした。 これを「茶柱」と呼んで良いのか。幸“運”の前兆と捉えて良いのか。 (「茶」の中だから「茶柱」なら、「柱」なのか) そういえば昔、カクテルに使うブルーミントの原液を割りもせず、ちびりちびりとやった事がありました。翌日“それ”は美しいと言えるほどに「真っ青」でした。カマンベールチーズを食べ過ぎた時は、「ほぼ白」。トマトジュースを飲み過ぎた時は「赤」。 食べた物が“そのまま”というのは、逆に妙な気になります。 たから最初に書いたでしょ。カタツムリに色紙を喰わせると、その色のままの・・・。「探偵ナイトスクープ」でやっていましたね。
2013年02月20日
コメント(0)
-
沖田修一監督『横道世之介』を観た
『南極料理人』と同じ風合い。大人の為の80年代青春映画。 悪い映画じゃないです(う~ん、正直困った)。 原作は吉田修一氏の『横道世之介』。第23回柴田錬三郎賞、2010年本屋大賞3位を受賞した「青春小説の金字塔」と呼ばれる長編小説だそうです(未見)。 たぶん「青春物」というジャンルが私の好みじゃないからでしょうか。 同じ沖田修一監督作品の『南極料理人』の方がずっと私の好みには合いました。 ただ、この映画をご覧になった方で「時間と金を損した」と思う方はいないと思います。 興味が湧きましたならば、ご覧になってはいかがでしょうか。 (今気付きましたが、原作者と監督の名前がどちらも「修一」。名字もどちらにも「田」の字。御兄弟でしょうか・・・・オイオイ) 粗筋。 長崎の港町から上京した主人公、横道世之介と彼を巡る若者達の恋や出会いといった、愛おしい青春と、その後を描く。 主人公横道世之介の人物描写が秀逸。ユーモラスで思いやりがあり、しかし、少し頓珍漢。彼と巡り合った全ての人々に笑顔(失笑?)と爽やかな記憶を残していく。 高良健吾が好演。 緩やかな描写は同じ監督による『南極料理人』と同じ味わい。 もう少し余計な事を。 ネタバレではないと思うのですが、先入観なしで御覧になりたい方は御注意を(そもそも、「ネタバレで興を削ぐ」という事はズバリの推理物以外ないのでは、とも思いますが、一応ね)。 パンフ、公式HP等ではハッキリ書いてありませんが、舞台は80年代の東京。その世代の人々には懐かしい気がすると思います。 例えばファーストカットは斉藤由貴のカセットテープ!の街頭広告がバ~ンと(笑)。その他、主人公がVHSのビデオを見ていたり、友人がカセットのウォークマンを愛用していたり。 「人生の折り返し地点を迎えた全ての日本人に。もう一度懐かしいあの友、あの頃を思い出してみませんか」なんてキャッチコピーが付きそうな感じ。 ここは、この映画の一つの見所なんじゃないかと思うのですが、宣伝では強調されてません。 沖田監督自身はあまり80年代と言う事に関して意識していないという事ですので、その為でしょう。そして、「80年代を意識せずに制作した」という姿勢は正解だったと思います(意識したら、あざといものに堕した可能性がありますね)。 もっと書けば、“xx世代”“xx年代”(大抵マスコミでは「≒“流行”」)とやらが本当に“存在”するのか、という疑問がありますね。たぶん、私の気付かない、その当時流行っていたもの(流行っていたとされていたもの)が、まだあちこちのカットに登場しているのでしょう。デートシーンで登場する巨大ハンバーガー屋なども、たぶんそうなのでしょう(原宿か?)。当時の私の学生生活圏とは場所的にも時代的にも重なっているのですが、私は全くそういう事に関心がなく、今後もやっぱり関心がないと思います。 関心があった人は「あぁ、あの頃私は若かった」式のしみじみとした感傷に浸る事が出来るのかもしれません。 こういうのって、どちらが幸福なんでしょうね。「時代(≒流行)の変遷」をしみじみ感じる(それはつまり自己の加齢を感じるという事でも)人か、最初から「時代の変遷」とは無縁の人か。 私が唯一感じたのは、ここ。登場人物の一人、知的スノッブの人物の部屋に柄谷行人の本があったカットで失笑してしまいました(たぶん、ココ笑う所じゃない(笑)。おぉ、浅田彰の『構造と力』じゃないんだ。 登場人物の一人の下宿にビデオがありましたが、あれはお金持ちという設定なんでしょうね。 あぁ、そういえば、この頃ビデオが普及し始めたんでしたっけ。この「録画して観るというナウイ行為」に飛びついたテレビ局(フジテレビ?)が深夜に延々の長時間番組特集を組んだのを憶えています。確か一回目が浅田彰をメインに据えた「現代社会を分析する」的な番組。冒頭、浅田彰がタクシーの中からフランス現代思想っぽい(笑)事を述べたのでした(この頃はまだ祖母が健在で、この番組を観て「ようわからん」と感想を述べていましたっけ)。「録画」という行為が一般家庭に普及し始めた頃と浅田彰、いや“フランス現代思想”の“ブーム”は同時期だったなぁ、というどうでもいい話(この時期、評論家呉智英氏が「フランス現代思想などというが、北朝鮮の主体思想だって“現代”思想だ(爆笑)」と言っていたのを覚えています。ただの冗談のようですが、今考えると深い)。 そして、この特集企画のたぶん二回目は劇団夢の遊眠社の劇の一挙纏めての放送。ワーグナーの「ニーベルングの指輪」に材を取った劇でした。そういえば、この劇、観に行ったんだよね。やたら長かった記憶があって。円城寺あやさん、どうしてるのかな。 と、まぁ、まさに取りとめもなく、どうでも良い話が思い出されます。 映画を鑑賞している筈なのに、無関係な事を思い出す。という事は、この映画は駄目な映画か。 違うと思います。この映画は“スペクタクル(感覚への暴行)”とは無縁の映画だからでしょう。こういう映画も良いのです。喚起する為の映画。 もっと言えば、“芸術品”ではなくて“工芸品”の映画。 唯一、時代考証(笑)的におかしいと思ったのは、登場人物の一人が「違ぇ~よ」と言った点。当時こんな言い方は存在しません(因みに「なにげに」も「サクサク(物事が順調に進む形容で)」もありません)。 閑話休題。 この映画の構成、最初は少し面食らいました。『スローターハウス5』のようなアヴァンギャルドな(ナイナイ(笑)作品かと一瞬思った程です。 最初は80年代の主人公が上京し友人達との生活が始る所からスタート。時間軸は主人公に沿い、時間は80年代を流れます。 ところが唐突に時間は16年後に飛び、話の時間軸は16年後の主人公の友人達の上に立てられます。 時間が飛んだ瞬間が今の若い人は判らないんじゃないでしょうか。だって「茶髪の若者」のアップが出て判る仕掛けになっているのですから。 80年代に髪を染めている若者は東京でもミュージシャン(パンクス)といった特殊な人以外ほとんどいませんでした。 ここで16年後の主人公の友人達は主人公を思い出し、現在の生活の幸福を噛み締めつつ、笑顔と共にこの幸福を得るきっかけを作った主人公に思いを馳せるわけです。「あいつどうしているのかな」と。 で、また時間は突然80年代。主人公の視点でさっきの話の続き。で、また唐突に16年後にジャンプ。またまた友人が現在の幸福を噛み締めつつ・・・。 流石に二巡目からはこの映画の構成が判り、安心しました(笑)。 (ここからネタバレ) そして、三巡目の16年後で主人公が夭折した事がわかります(だからこの映画のキャッチコピーが「涙なんか流さずに笑いながら観てください。」なんだと、ここで得心しました)。 この夭折した原因の設定が上手い。ある事件が原因で亡くなるのですが、それが如何にも、この、人柄良い主人公ならでは、と納得がいくものなのです。しかもその事件、恐らく多くの日本人の記憶に残っているだろう、有名な事件なのです。 再び時間は80年代へ。ここから一挙に緊張感が私の内に沸きあがりました。主人公は相変わらずユーモラスで少し頓珍漢なんですけどね。 「なんでもないと思っていた日々が、どうしてこんなにも愛おしいんだろう---。」とはパンフのコピー。私も全く同じ感想。あぁ、この人、その後、あぁなっちゃうんだね。悲しいね。でも、そういう事と関係なしに一生懸命生きているんだね。なんて愛おしいんだろう。 仏陀の目にはあらゆる存在が、愛おしく可憐な存在に映るらしいですが(中島敦『悟浄歎異』)、主人公の生の有限性を知っている私は、プチ仏陀状態。 良い映画です。 だけど、何で劇中盤、三巡目から、なのか。冒頭から主人公の死を暗示していた方がよかったんじゃないでしょうか。 劇始って直ぐ(一巡目の冒頭80年代)は、私に取っては緊張感に欠けるように感じました。「拙くはないが、特筆するべき事も無い、よくある学園青春物」といった感想。 『南極料理人』と同じ味わいなのですが、南極と違い特殊な舞台設定でない分、緊張感に欠けるように感じたのでした(これ、テレビで観ていたら、消しちゃってそれっきりだったろうな。逆にいえば『南極料理人』は上手い。本当に良い映画でした。特殊な舞台設定だからこそ、緩やかな描写が絶妙な味わいを生み出していたと思います)。 死んだ人は大抵“善人”(と見なす)。これは社会の通念ですね。 通念だから自分の信じている世界観が揺らぐ訳ではない。つまり所謂“芸術”から来る“感動”はここにはない。 そして、これはそういう映画で良いのです。 ところで、「青春物」というジャンル、当の青春を現在送っている人たちは見たがるものなのでしょうか。 この映画、どういった方々が観に行ったのか。また現在青春期を送っている人が見たらどういう感想を持つのか。気になります。 (「クソ~、リア充め~」なんて僻んだら駄目だよ。「リア充」なんて“幻想”なんだから。だって“リアル”そのものが“幻想”だからね) なお横道世之介が実家で食べていたカステラは蝙蝠マークの福砂屋です。長崎なら当然。 創業寛永元年(1624年)、福砂屋のカステラは美味しいよ。 ここにオリジナルスクリーンセイバーもあります。福砂屋の「こうもり」マークが、マウスの動きを追いかけながら次々と登場してはヒラヒラと舞うのです。「ビバビバ」の景気の良い時代ではありました。
2013年02月05日
コメント(0)
-
伊藤明彦著『未来からの遺言』を読んだ(その1)
奇書にして名著。読むべし。異様な感動の「(非)被爆者」のドキュメンタリー。 凄い本です。読後、なんとも“奇妙”な感動に襲われます。 極めて真摯誠実なドキュメンタリーなのですが、映画や小説のように“どんでん返し”があり、最後に起きる悲劇は“物語の結末”めいた印象さえ読者に与えます。 ある“被爆者”の記録です(いや、そう見なしてあげるべき本なのでしょう。違うかも知れません。私は“文学的”判断を留保しておきます)。 世界苦の体現者のような人生を歩んだ話者に、読者は強烈な印象を受けると思います。特に原爆症での闘病生活中の姉との思い出は、読む者全てに鮮烈な心象を与えるでしょう。 しかし...。 ここまでこの拙文をお読みになった、意地の悪い、若しくは“ある種の政治的権力集団(私は彼らを「珍思考権力集団ニポンサヨク」と呼んでいます。≠まともな左翼)”のプロパガンダに辟易している方は、こう考えるかも知れません。「ハイハイ、カワイソな人を出して『核兵器反対、戦争反対だぁ~』って本ね」。 恐らく、そういう方はこの本の“どんでん返し”に衝撃を受けると思います(ドキュメンタリーなのに、どんでん返し)。 そして、かくも異様にして感動的なドキュメンタリーでありながら、“封印”されてしまっているのは、正にその“どんでん返し”の為なのでしょう。 ニポンサヨクにとって、このような記録は、“政治”的に存在してはならない事例であり、故にこの本は“存在しない本”なのでしょう。中国や北朝鮮のような一党独裁国家ではありふれた思考ですね。 ニポンサヨクのヘゲモニーが揺らぎ始めた今こそ、再評価されるべき本だと思います。 是非読んでください(復刊したらしいので、是非)。 著者の伊藤明彦氏は、1002人(!)の被爆者とのインタビュー、及び録音をした方。録音テープは950巻に及ぶそうです。しかも、この行為、全くの自費(p194さしあたりの生活において、自分より貧乏な被爆者にあったことが私にはありませんでした)。原爆の記録を後世に何としても残さないといけないという使命感に支えられた行為です。この事自体、驚嘆と敬意に価します。 また、この伊藤氏は(読んでみれば判りますが)極めて誠実な方のようです。安易な“政治的に正しい思考”を押し付けません(何よりも自分自身に対して)。ありのままの“どんでん返し”をそのまま記録し発表します。その為、この「“被爆者”の記録」を生み出す事が出来たのでしょう。 “粗筋”を知るのではなく、実際に読むと、相当衝撃を受けます。 是非読んで欲しいものです(2回書いちゃったね)。 以下、メモ書き。 1980年刊行。1971年11月13日より数年間にわたる、吉野啓二氏(仮名)へのインタビューを纏めた物。記録された時期はかなり古いのものですね(若干時代背景等に説明が必要なのかも知れません)。 なお、インタビューを受けた吉野氏は重度の吃音症の方でした。(p74)一年前に代々木病院を退院して、このアパートの三畳間に移り、生活保護を受けながら、自炊し、通院し、闘病し、活動し、好きな音楽を経済的に許される限りで鑑賞するのが、吉野さんの現状でした。(p74)(吉野さんの健康状態)病名は原子爆弾後障害による無気力症候群、自律神経失調症、再生不良性貧血によるアレルギー疾患、出血性素因、副腎皮質機能障害、慢性肝機能障害など、数えると24にもなり、80種類の薬を飲んでいる事。(p30)「吉野さんの話によれば、吉野さんに放射線障害の症状があらわれたのはそれからでした。鼻血・歯茎からの出血が最初のきざしでした。やがてはげしい下痢もはじまります。吉野さんの記憶では、それは被爆後三日目のことでした。」 映画、小説ならば本書の前半の山場。薄幸の姉弟の原爆症闘病生活記録。原爆症の悲惨さと印象深い姉弟愛の記述(感動的ですがそれは本書を読まないと。詳細は割愛)。(p83)吉野さんの話が最も具体的な情景に満ちているのは、いうまでもなく、その15年の入院生活についての部分です。(p83)ただひとり生き残って敗戦の日救護病院にかけつけてきた「姉さん」が、吉野さんの枕元に置かれた両親の遺骨にしがみついて泣いたシーン。 吉野さんには白いご飯を食べさせ、自分は芋を食べていた「姉さん」。 砂糖を買って来い、ミカンを買って来いという吉野さんの無理難題に、廊下で泣いていた「姉さん」。 窓の外の風景をみたくないといって、病室の窓にカーテンをつけさせながら、こっそり、外をのぞいて「姉さん」にみつかり笑われた吉野さん。 お土産のお菓子を目の前にぶら下げて、犬や猫をじゃらすように吉野さんをじゃらした「姉さん」。ベッドにに寝たまま、それにとびつこうとする吉野さん。 「姉さん」の具合が悪くなって、同じベッドに背中合わせに寝かされ、何ヶ月ものあいだ、ひとことも口をきかなかった思春期の姉弟。 見舞いの中学生が持ってきた果物を、自分でもよく説明できない気持ちから放り出してしまった吉野さん。そのとき、床に転がった果物や、枕元にとりだされた一匹の折鶴のイメージが、私にはくっきりと浮かんできます。 そして死の床にあっ、しきりに吉野さんの名前を呼んでいる「姉さん」と、その傍らに運ばれていった吉野さんが、手を伸ばして、「姉さん」に触れようとする、印象的なシーン。 それからまた、東大病院の病室のベッドから、布団をかかえては転げ落ち、床を這う練習をする吉野さん。 三人の看護婦に前後を支えられながら、歩行器にとりすがり、汗びっしょりになってはじめて5メートルを歩いた吉野さん。 15年の吉野さんの入院生活の物語は、数々の豊かなイメージを私にあたえてくれます。(p86)吉野さんの話の中で、最も印象的な登場人物はいうまでもなく、昭和28年に亡くなった吉野さんの「姉さん」です。吉野さんの話の中で、というより、被爆者に私がうかがった話の中に登場してくる、数千人以上の人々の中で、私にとって最も印象的な人物はこの「姉さん」です。 10代のはじめ、原子爆弾によって両親、兄、姉と家・財産の一切をなくし、ただ一人生き残った病弱でききわけのない弟の養育と看病に一身をなげうち、ついに自分も白血病に犯され孤独の内に死んだ「姉さん」。この少女くらい、無名戦士という称号にふさわしい存在はないのではないか、私はそう思いました。私はこの「姉さん」の生涯、その生と死に深く心を動かされました。(p53)「吉野さん、お姉さんの生涯を考えてみられて、いまどんなお気持ちをもたれるでしょうか?お姉さんはわずか13歳くらいのときに被爆して、ご両親、兄姉を亡くされ、寝たきりの弟さんひとりを残されたわけですね。勉強したい自分の望みは捨てて、一生懸命働いて、看病に明け暮れて、とうとう力尽きて、弟さんの行く末を案じながら、22歳の若さで亡くなってしまわれたわけですね?そのお葬式にきてもらえる肉親もいなかったわけですね?」吉野さんの顔は赤くなり、こめかみの血管はふくれました。広い額の下にひっこんでいた吉野さんの奥目は怒りに燃え、飛び出しそうになりました。(略)「もう、それをいわれることじたい、もう、ちょっと、僕にとっては残酷すぎますよね、ハッキリいうとですね。」 (その2)に続く。
2013年01月31日
コメント(0)
-
伊藤明彦著『未来からの遺言』を読んだ(その2)
(その1)の続き。 感動的な吉野さんの台詞。(p76)「吉野さんの現在の生き甲斐はなんでしょうか?(略)」「(略)生き甲斐といったら、それこそ社会を、政治をですね、変革するということになるんじゃないでしょうかねぇ。そのひとことだけで、いいきれるんじゃないかと思うんですよ。」(略)「将来に託せる希望といったら、いまいったように、社会を変革するということと、それからもうひとつは、自分がですね、もういちど社会に出て、本当にあの、人間らしい生活ができるということですね。というのはですねぇ、僕ですね、最近ですねぇ、この押入れの中にクモの巣ができていたんですね。小さなクモなんですよ。で、小さなクモの巣のところをちょっと手で触れて、網をひっかいたんですね。そしたらそれをですね、そのちっちゃいクモですらね、編み始めるんですね。一生懸命ですね。これをみてですねぇ、クモの巣がですね、クモが編んでゆくようなあの自力ですね、なんで僕が、それが出来ないんだろう、そう思ったですね。本当にそう思ったんですよ。本当に俺は、今まで人間らしい生活をやって来たんだろうか、そう思いましたですねぇ。」(p79)吉野さんが「生き甲斐は社会を変革する事だ」といいはなった瞬間、これこそが、言葉の正しい意味での「原子爆弾の効果(エフェクトオブアトミックボム)」だ、と直感しました。(p84)最後に、吉野さんが問わず語りに語ったクモの巣の話は、私を驚かせました。木賃アパートの三畳間の片隅で、破れた巣を一心につくろっている一匹の小さなクモ。そのクモの営みを見つめて、人間らしく生き抜こうという思いを、もう一度自分自身にたしかめている吉野さん。それは26年間にわたる吉野さんと原子爆弾との闘いの物語を締めくくるのに、もっともふさわしいシーンであるように私は感じました。(p95)原子爆弾が吉野さんから、人間らしく生き死にするために必要な条件を根本から奪うものだった、そのゆえに、吉野さんがその後も生き続け、人間らしく生き続け、自分の人間らしさを回復しようと努めたその営みのひとつひとつは、抜き差しならず、原子爆弾を否定し返す性質を持つほかなかったのだ、と。 その営みの二六年目の到達点として、私は「生き甲斐は社会を変革する事だ」という言葉を聞いたのです。(p97)最も根本的に自分の人間らしさを原子爆弾によって否定された吉野さんは、自分の人間らしさを最も根本的に取り返し、原子爆弾を否定し返す事の結論を、社会の変革にみいだすほかはなかったと思うのです。(p97)原子爆弾と吉野さんのこの関係を、原子爆弾=加害、吉野さん=被害者、という図式だけでとらえきれない事は明らかでしょう。私は吉野さんの話を聞き終わった時、もう、これから先どれだけの数の被爆者に会っても、これ以上の話にめぐり合う事はないのではないか、と感じました。豊かな感情、躍動する言葉、意外性とクッキリした情景に満ちた話には、これからまたいくらでもめぐりあう事が出来るでしょう。 しかし吉野さんより多く、原子爆弾から奪われる事はまずない以上、吉野さんより多く、原子爆弾から奪い返す事はありえない以上、その話の本質において、吉野さんの話を超えるものはないだろう、そう感じたのです。(p99)原子爆弾を廃絶させようとする被爆者の意思は、自分達の人間らしさを回復しようとする、被爆者の営みの到達点としてあります。 それは原子爆弾の使用が奪う事が出来なかった、被爆者の生命の力の、必然的な帰結でしょう。 自分達の体験が、同じ体験を人々にさせないうえで役立った、という事をつうじて、被爆者はその人間らしくない体験が、人間世界のなかで意味を回復し、自分達の人間らしさがすこしでも回復された、と感じる事ができるでしょう。 しかし時々インタビュアー伊藤氏が感じる小さな違和感(この辺り、小説、映画ならゾクリとする伏線に当たる)。例えば。(p68)(小さな疑問。当時の吉野さんの初任給が高すぎる事)ただ三日目に録音に訪れたとき、吉野さんが、「あの額はやはり、間違っていなかった。自分は全国金属という労組に手紙を書いて、昭和35年ころの工場労働者の初任給を問い合わせ、大体、自分が言った金額と同じくらいという答えを得た。」と、こう主張したことは私を驚かせました。鉄鋼労連ではなく全国金属だったわけもよく判りませんが、それはともかく、巨大な官僚組織でもある大きな労働組合が、こういう問い合わせに、すばやく返事をくれるものでしょうか。(略)これもまた、たいして意味のないエピソードかもしれません。(p80)傍らで私は、この話は本当だろうか、と思いました。その傍証が欲しいと思いました。(p80)私はまず、吉野さんの話に深い感銘をうけました。第一にこの話が、鮮やかな情景に満ちていることに感じ入りました。第二に、吉野さんの話の中の最も印象的な登場人物である、「姉さん」の生と死に、心からうたれました。第三にこの話の内容全体に--つまり原子爆弾から、人間らしく生き、人間らしく死んでゆくために必要な条件を徹底的に奪われた人間が、人間らしく生き抜くための営みのあげくとして、最も徹底的に原子爆弾を否定し返す、その高みにたどりついているという、吉野さんの半生そのものに、最大の感動を感じました。(p82)ただし被爆以前の生活や、直接の被爆体験そのものについては、吉野さんの話はけっして「第一級」のものとはいえません。この部分についての吉野さんの記憶は多少混乱しているように私には感じられました。ほかの人々の話をぬきんでている、具体性をもっているとも思えません。 段々と、インタビュアー伊藤氏の中で膨らむ疑念。(p110)吉野さんの話そのもののなかにも、細かい点では、よく判らない事がありました。 1935(昭和10)年の早生まれの人は、被爆した時国民学校の五年生のはずですが、吉野さんは四年生でした。 生き残った「姉さん」を除く、ほかの兄や姉の名前を、吉野さんが憶えていない事も一寸不思議でした。(p111)夏休み中の八月九日、生徒達を登校させていなかった事は、三年前、教頭先生から、直接うかがっていた事でした。これは吉野さんの記憶違いでしょうか。それとも生き残った先生方の気がつかない「史実」があったのでしょうか。(p111)爆心地から至近距離にあった長崎医科大学付属病院が被爆によって廃墟となり、その直後、組織的な救護・医療の活動をその場所では行えなかった事は、当時、長崎にいた誰もが知っている事です。長崎市や諌早市の病院、学校などを転々とした長崎医大が、被爆した坂本町の施設で病院を再開したのは1950(昭和25)年10月の事です。この間、多くの被爆者は長崎市内、諌早市、大村市などの病院を転々としました。あれほど印象深く語られた吉野さんの病院生活の中に、この時期の転院が語られていないのは何故でしょうか。(p112)被爆後20年以上もたってから被爆者を訪問し、その話の中の細かい矛盾を指摘する事自体、意味のない事であり、相手に対して失礼といわなければならないでしょう。かりに被爆者の記憶に曖昧な部分が生まれていたとしても、その責任は遅すぎた訪問者の方にあるのですから。私は「歴史家」として、歴史を編む為、被爆者に史実を質しているわけではありません。検察官として、被爆者を取り調べているわけでも勿論ありません。私は被爆者が正確な記憶を持っている事、それをそのままに語ってくれる事を期待はします。しかしそれを要求する筋合いではありません。被爆者がなにかの事情で事実を語らなかったり、粉飾や虚構をまじえてその体験を語ったとしたら、そのような人間の心、その心とその人が被爆した事の関係には、深い関心をいだきます。しかし、その事に私が苦情を述べる筋合いではないでしょう。(p112)自分の疑問を露骨に述べる事を私はためらいました。そして心の中で、吉野さんは自分で話しているよりも、実はもっと若いのかもしれない、つまりもっともっと子供のころ被爆した人なのかもしれない、と考えました。(p113)ただ、それにしても。 この話を正真の事実として第三者に紹介するという事になると、事情がかわってきます。(p113)この話が大筋では、一番大事な中心の部分では真実であるという、傍証が欲しいのです。吉野さんの話を人々に聞いてもらい、それが私の期待通りの波紋をよんでいるうちに、吉野さんの過去をよく知っている人が現れて、「この話の大筋は本当でない」といってくるようになっては困るのです。 私は長崎の友人に手紙を書きました。友人からは二度に分けて、返事がきました。「長崎市役所の吉野さんは大陸からの引揚者で、お母さんも現存している。東京の吉野さんのお兄さんである可能性は全くない。」「当時の城山国民学校の教頭先生には、その姓の生徒についての記憶はない。在校生の名簿は無論残っていない。」 印象深い衝撃的シーン。(p115)はじめて吉野さんにあった、その次の年の五月のある日、吉野さんが通院している目黒の診療所で、私は吉野さんと顔をあわせる機会がありました。その時、私は思い切って、本籍地から戸籍謄本をとってみてはどうか、と吉野さんに提案してみました。行方不明となったお兄さんやお姉さんの名前や正確な生年月日が判れば、長崎にいる友人達に頼んで、消息を調べてもらえると思う、私はそう説明しました。 その時の吉野さんの怒りを忘れられません。吉野さんはその時診療所のある部屋の椅子にすわっていたのですが、その椅子からとびあがりそうになって怒りました。「一体全体、それはどういう意味ですか!」黒い顔を真っ赤にして吉野さんは叫びました。吃音はいっそう激しくなりました。吉野さんの奥目は充血し、飛び出しそうになり、鼻の脇に、怒った犬のような皺がよりました。(p116)得ようとした傍証や裏付けは、得られませんでした。吉野さんは私にとって、あいかわらずニュールンベルクの孤児のような謎の存在でした。(p116)私は主としては、吉野さんを信じていました。被爆者がその被爆体験を語る、その行為のなかに、故意のいつわりが入り込む事ができる、と考える事自体が、私には憚られました。被爆者が偽りを語るかもしれない、という事を前提としては、私たちのこの作業は成り立ちません。話のウラをとる。これ自体がイヤな言葉です。(p117)吉野さんが日本共産党の熱心な支持者であった事が、私の信頼を深めた事も正直に告白しておかねばなりません。(その3)に続く。
2013年01月30日
コメント(0)
-
伊藤明彦著『未来からの遺言』を読んだ(その3)
(その2)の続き。 吉野氏の他のインタビューとの齟齬。国連提出の公式文書での詐称か。(p133)その年、1976年(昭和51)年の事です。八月でした。「核兵器全面禁止国際協定締結・核兵器使用禁止の諸措置の実現を国連に要請する国民代表団派遣中央実行委員会」という団体によって、「広島・長崎の原爆被害とその後遺--国連事務総長への報告--」という文章が作成されました。(p133)あとがきによればこの文章は、七人の専門家によって作成され、日本被団協、民医連、日本原水協などが協力したという事です。なにかの用事で東京の被爆者の会の事務所を訪れた時、20ページの小さなパンフレットに印刷されたこの報告書を私は手に入れました。そしてぱらぱらとページをめくって、「原爆被爆者の30年--事例研究」「事例四」として、「長崎・男・41歳 被爆当時・小学生・後遺に苦しむ」とある部分を一読して、文字通り、目をむきました。(以下、吉野氏が著者に語った内容とは食い違う話が報告されている)(p137)この文章を読んだ時の、私の驚きがお判りいただけるでしょうか。私は唖然として声をのみました。この文章の星野恵二さん(仮名)が、吉野啓二その人である事は99%、間違いありますまい。(略)吉野さんはこの通りのものとして、自分の過去を語ったのでしょう。それが「広島・長崎の原爆被害とその後遺」の一部として国連事務総長へ報告され、「原爆被害の実相と被害者の実情を国際的に普及するため」利用される事も承知だったに違いありません。 いったい、吉野さんはどういうつもりで、こんな話をしたのでしょう。 いや、この話が本当なのでしょうか。(p138)その時、私は考えました。いや、その方法を考えたのではなくて、被爆者が話したことの内容に一歩踏み込んで、その「真実性」を探求してよいものかどうかを考えました。(p139)被爆体験、被爆者体験は、全体としては大きな公的な体験、人類にとっての歴史的な体験です。しかしその部分ひとつひとつを構成する被爆者ひとりひとりの体験は、その時の職業や立場によって、部分的に公的な性格を持つことがあるにしても、概ねは、いわばプライバシーに属する個人的体験としての性格を持っています。それもほとんどの人にとっては、悲しい、苦悩に満ちた、好んでは触れたくない体験です。 そのプライバシー、個人的な体験が、全体としては、巨大な公的性格を持つことを被爆者が理解し、事実をありのままに語ってくれるよう、私は期待します。しかしそれを要求する筋合いではないでしょう。(p140)被爆者が事実を隠したり偽ったりする事があるとしても、その事実を追及したり、暴いたりする権利は、誰にもないでしょう。 しかしここで、その被爆者の話を、第三者に伝えるということになると、話はすこし違ってきます。その時、私には、その話が大筋においては事実に近い、少なくとも大きく事実をいつわったものではない、ということくらいは保証する責任が、生じるでしょう。(p140)厳密に言えば私が第三者に対して責任を持って報告できるのは、「被爆後20何年、30何年かたって、自分が被爆者にこのように質問したことに対して被爆者はこのように答えた」という、その事実だけです。(p142)二つの話のうちのどちらかは、明らかに故意の作り話でしかないのですが、いや、ふたつのうちのひとつは、必ず正真の事実であるという保証もないのですが、被爆者に対して、人間と原子爆弾との関係に対して、深い関心をいだいてきた私は、その作り話をした吉野さんの心と、吉野さんが被爆したことの関係に、異常に惹かれるものを感じました。そこに、人間と被爆との関係の秘密を解き明かす、ひとつの鍵がひそんでいるように感じたのです。 筆者は吉野氏の本籍地の役所に確認しに行きます。(p153)吉野さんのふた種類の身の上話と、この戸籍によって確かめられることとの関係を、次に私は考えてみました。 そしてこのように結論するほかありませんでした。 私に語った身の上話が正真の事実であれば、この身の上話を私に語ったあの人は、吉野啓二ではありえない、と。 もしあの人が間違いなく吉野啓二という人であれば、私に語った、あの被爆体験の重要な部分のほとんどが、虚構だ、作り話だ、と。(p154)(第一の仮定。筆者がインタビューした人物を「Xさん」とする)Xさんは私達には判らないなにかの事情で吉野啓二さんを名乗っているけれども、私にたいしては、Xさんとしての自分の、正真の身の上話を語ったということになります。 一方、「国連事務総長への報告」にたいしては、吉野啓二さんの戸籍上の身の上話とは矛盾しない被爆体験を作り出して、語ったことになります。(p154)Xさんはこのようにくわしく、吉野啓二さんの本籍地の番地や、母方の祖父の名前や、母の名、養母の娘の名、被爆前に幼い弟や妹が亡くなったこと、戦後に妹が生まれ、兄が現存していることまで知っているのですから、よくよく、吉野啓二さんの家族のことを知りうる立場にある人に違いありません。(p155)第二の仮定の場合--私にあの身の上話を語った人が、間違いなく、この戸籍謄本に記された、吉野啓二さんである場合の事を次に私は考えてみました。 その場合は、私に語ったあの身の上話の重要な部分のほとんどが、作り話だったということになります。 兄、姉がたくさんいた、ということも作り話なら、八月九日、壕の入り口で母が死んだというのも作り話ということになります。母は1955(昭和30)年まで生存していました。そして吉野さんは、母が死んだ時の情景についての作り話を、録音の二日目に、自分で希望して、もう一度したということになります。三菱造船幸町工場の焼跡で父の遺体が見つかった、それを父とは信じられなかった、今でも信じられない、というのも作り話という事になります。父は1959(昭和34)年まで生存していました。吉野さんはこの作り話を私に対して口で語っただけでなく、繰り返し、手紙にも書き記して私に送ってくれたことになります。 被爆によって多くの兄、姉が行方不明になったというのも作り話ということになります。兄はひとりしかいず、現存しており、姉はさいしょからひとりもいませんでした。(p156)この戸籍謄本をみて私が驚倒したのは、加藤家(吉野さんの生父)、佐川家(吉野さんの養母の嫁入り先)のいずれをさがしても私にとってあのように印象深い存在だった「姉さん」が、どこにもいないということでした。 「姉さん」もまた、吉野さんが作り出した虚構の存在なのでしょうか。 そうだとすると、吉野さんが語った、あの病院生活の印象深い情景のひとつひとつが、ことごとく作り話だったということになります。吉野さんは被爆直後の8月15日、「姉さん」が救護所にたずねてきて、自分の枕元においていた両親の遺骨箱にしがみついて泣いた、と語りました。そのとき、思わず涙声になりました。いたはずのない姉が、あったはずのない両親の遺骨箱にしがみつく光景を想像して、吉野さんは泣いたのでしょうか。 「姉さん」の生涯を振り返って、どんな気持ちを持つか、と私が質問したのにたいして、吉野さんは「その質問はあまりに残酷すぎます」といって、泣くまいとして声をふるわせながら、一身をなげうって自分をまもってくれた姉を亡くした胸の痛みを、わがままをいってその姉を苦しめた悔いを、かきくどくように語りました。吉野さんは空想上の「姉さん」の生涯を痛恨して、あのように感情を高ぶらせたのでしょうか。(p157)あの夕方、あの会場で、私のような男に会い、そのような要請を受けるということは、吉野さんはまったく予期していなかったと私は思います。吉野さんはその時とっさに、作り話を思いついたのでしょうか。そして私の三度の訪問に先立って、その日に話すべき作り話の筋や情景を考え、私の待ったのでしょうか。 それともこの作り話は、私の会うずっと以前から、吉野さんの心の中には作り上げられていたのでしょうか。(p159)この戸籍謄本をみて実に疑問に思ったのは、加藤家、佐川家、このふたつの家族の歴史には、これらの家族が長崎市に、長崎市の城山町に住んでいたらしいことを推定させる記事が、どこにも発見できないということです。(p161)----吉野さんのふたつの身の上話と、数通の戸籍謄本を材料にして、私は今いく通りかの可能性を考えてみました。 この文章を読んでくださっているあなたは、どの想像が、真実に近い、とお考えになりますか。それとも私が考えつかなかった、第四、第五の可能性を考えますか。 二種類の身の上話には共通している部分もあります。しかし、従ってその部分は真実だ、と判断できる材料もありません。二種類の身の上話のどちらかは、すべて真実だ、と考える根拠もありません。またどちらかはすべて作り話だ、と考える根拠もありません。(p162)私はさいごの疑問にたどりつかないわけにはいきません。 ----この話のいちばん大事なところ、つまりこの話のドマンナカは大丈夫だろうか。(その4)に続く。
2013年01月29日
コメント(0)
-
伊藤明彦著『未来からの遺言』を読んだ(その4)
(その3)の続き。「被爆太郎の誕生」(p166)被爆体験がいつわって語られることと、その人が被爆したこととの関係を考えただけではなく、被爆体験がいつわって語られることと、その人が被爆しなかったこととの関係を、考えました。(p166)いまはもう明らかです。(p166)吉野さんの養母(叔母)と義妹は小倉市にいます。ふたりの妹さんたちの居場所も判っています。東京の近県にはお兄さんがいます。 これらの人々、とくにお兄さんを訪ねれば、吉野さんが生まれて以来のことが、もっとも確実に判るでしょう。1945年8月9日、吉野さんと両親が、どこにいたか、吉野さんの両親の死と、その日長崎で起こった出来事の間にかかわりがあるかないか、話してもらうことが出来るでしょう。(p166)私は何ヶ月も、一年以上も考えました。 結局、それはしないことにしました。 自分のその行為が、人伝てに吉野さんの耳に入って、吉野さんの精神状態の均衡に危険を与える可能性を、私はまず怖れました。(p166)かつて「戸籍謄本をとりよせてはみてはどうか」と提案した時吉野さんが示した、あの跳びあがらんばかりの怒りが私には忘れられません。提案しただけであれほどの反応を示した吉野さんが、私の行為を知り、吉野さんのほんとうの身の上や、吉野さんの被爆体験の虚構に私が気付いたらしいことを知ったら、どれだけ感情をたかぶらせるでしょうか。(p168)それらの人々を訪ねてはゆくまい、と決めたもう一つの理由、最も大きな理由は、今度こそ私には、もうそんなことをする権利がない、目的がない、名分がない、と考えたからでした。 吉野さんの場合だけはタブーを破り、被爆者の話の内容に一歩踏み込んで、その「真実」性を私が検証しようとしたのはなぜでしょうか。いうまでもなく、吉野さんの話に深く心をゆり動かされ、将来、この話を沢山の人々にきいてもらいたい、自分の気持ちを多数の人々のものにしてほしい、と考えたからにほかありません。 そのためにも、この話が、その内容のの大筋においては正真の事実であるという確信を持ちたい。そのための傍証を得たい。それが私の行為の目的でした。 結果は出ました。「傍証はすこしも得られなかった。この話が正真の事実であるという確信はまったく持ち得ない。」 これが結論です。 これ以上、タブーの中にもう一歩踏み込む理由は自分にはもうない。私はそう考えました。私はもう、充分に、吉野さんの「過去を暴いて」しまいました。知る権利のないことを知ってしまいました。被爆とはなんの関係もない人々の個人生活まで覗き込む失礼をおかしてしまいました。(p172)その吉野さんが、私に語った、あの「幻」を作り出していく過程を空想してみました。 吉野さんは----長崎医大付属病院ではないかもしれませんか----どこかの病院に、長いこと入院していた人かもしれません。そうして別の被爆者、場合によっては複数の被爆者たちと、何年ものあいだ、隣り合わせのベッドに寝ていたのかもしれません。 そのような経験が、なんどか繰り返されたのかも知れません。 二年も三年も、隣り合わせのベッドで寝ていた被爆者が、亡くなっていくようなことを経験したかもしれません。 その人に、やさしい、被爆者の「姉さん」がいたことを私は空想してみました。 その「姉さん」が、吉野さんを可愛がってくれたことを空想してみました。 その「姉さん」が、亡くなったことを空想してみました。 それからまた、同室していた被爆者達が、繰り返し繰り返し、それぞれの身の上を語り合ったと私は空想してみました。人の体験と、自分の体験との区別がつかなくなるほどに。(p173)その過程で、不必要な部分はいつのまにか削り落とされ、必要な部分は事実をいっそう鋭く伝えるように作り変えられ、複数の人間の体験がひとりの人間の体験に凝縮され、しだいしだいに一個の「被爆太郎の話」が出来上がっていく過程を空想してみました。 「被爆太郎」は人間と原子爆弾との関係を、もっとも鋭く表現した存在として誕生します。 ありえないことですが、かりに原子爆弾が、人類がまだ文字を持たない時代に投下されたとしても、そして代々の権力者が、このような体験が記憶され、伝承されることを望まなかったとしても、それは人々の脳裏に深く刻まれ、口から口へ。祖父母の口から子供達や孫達へ、孫達からそのまた子や孫たちというふうに幾世代ののちまでも、必ず、伝えられていったに違いありません。 被爆体験とはそのような体験でした。(p174)このような口伝えの被爆体験は、それが幾世代にもわたって語り伝えられるあいだに、数え切れぬ、「被爆民話」を生み出したに違いありません。 「恐ろしい話」「悲しい話」「不思議な話」「ちょっとの偶然が運命を左右した話」「日ごろのよい行いが報われて生命が助かった話」「亡くなったお母さんが、娘の嫁入りの晩、箪笥を届けて来た話」「救護所の遺体の金歯を、夜毎ペンチで引き抜いてまわっていた鬼のような男の話」「野犬に食べられた赤ちゃんの話」「自分の身を棄てて、弟を守り抜いた気高い姉の話」「死んだ息子が観音様になって母親の夢枕にたち、人間の生き方を諭した話」「焼け死んだ美しい娘が夏の夜蛾になって、恋人の部屋を訪れた話」、こんな話がかぎりなく、生み出されたでしょう。 そこには軍人、高官、母親、兵士、中学生、大工、看護婦、機関士、娘、産婆、先生、泥棒、警察官、修道女、商人、農民、情深い人、強欲な人、およそありとあらゆる人々が登場してきたでしょう。 そのような「被爆太郎」の原型とでも呼びたい話を、私はいく十となく聞いていました。(p175)大和朝廷の発展期に、いくどか行われた熊襲や東夷を征服する戦争の民族的な記憶は、いつかヤマトタケルノミコトというひとりの英雄の物語を生み出しました。 複数の人々の集団的な体験、民族的な体験が、ひとりの人間の体験として抽象され集約されていった数多くの例を、私達はこの国の歴史の中にも、外国の歴史の中にも、いくらでも見つけ出すことがができると思います。 「被爆太郎」は数え切れぬ人々の集団的な体験、民族的な体験を、ひとりの身に凝縮した存在として、私達の前にたち現れます。 吉野さんによって私に語られたこの話は、被爆後二十数年の日本の戦後社会が、すでに「被爆民話」を生み出しつつあることの一つの証拠ではないか----私はそう、空想してみました。(p175)私は、またもうひとつの空想をしてみました。つまり吉野さんが被爆者でなかった、と空想してみるのです。(p175)そのうえで、被爆体験が偽って語られたことと、その人が被爆したこととの関係ではなくて、被爆体験が偽って語られたことと、その人が被爆しなかったこととの関係を、つくづく、考えてみました。 空想によって、被爆者でない吉野さんを直視するとき、それでも、どうしても否定することのできない悲運を負った存在としての吉野さんの姿が見えてきます。 吉野さんがきわめて病弱な人であるということはだれにも否定のしようがありません。 口やそぶりで病を詐っても医師や検査技師を騙す事は出来ません。二十四種類の病気を持ち、八十種類の薬を飲んでいるという吉野さんの姿は、かりに被爆はしなかったとしても残る吉野さんの現実です。(p176)もし人が、生まれながらにしてこのような条件を背負って人生を歩み始めたとしたら、その人はいったい、自分のその苦悩の意味づけを、どのようにして得ることができるでしょうか。 意味づけの得られない苦悩は、いっそう、耐え難い重みをますにちがいありません。 人間は自分の生と死の意味づけを求めて生きている。 その意味づけは、ただ、他とのかかわりのなかでだけ、得られる。 人間はしばしば、意味づけの得られない生よりも、意味づけの得られる死のほうを選ぶ。(p179)原子爆弾はそれを拒もうとする人間の行為に対して、実に不思議な意味づけの力をもっています。 それがあまりに残酷で、犯罪的で、人類の未来にたいして破滅的状況を与える不気味な可能性を持っているために、原子爆弾は、それに反対し、それを廃絶させ、使用を阻止させようとする人間の営みにたいして、限りなく大きな意味を付与するのです。 その残虐性や破壊力の巨大さとちょうど等量の大きさの意味を、その営みに対して与えるものです。 被爆者は自分の苦悩が、同じ苦悩を他の人々に味わわせないことに役立てられることをつうじて、自分の苦悩の意味づけを獲得し、その苦悩に耐える力を持つことができます。 核兵器が人類を破滅状態にさせうる破壊力を持っているために、被爆者の死と、その苦悩に満ちた生は、それが核兵器を再び使わせず、廃絶させることに役立てられる道をつうじて、人類史的な意味を獲得するのです。(p180)吉野さんが生まれながらに病弱な、吃音や恵まれぬ肉体的条件をもった人だと私は空想してみました。 吉野さんは、ひょっとすると久留米市で空襲にあった人かもしれない、とも空想してみました。 戦後のある時期、お兄さんといっしょに、長崎市の城山町に住んだことのある人かもしれない。そのとき、爆心地のようすをみたり、長崎大学医学部付属病院で治療を受ける機会があった人かもしれないと空想してみました。 生まれながらに意味づけを得られない苦悩を負って生きてきた吉野さんが、その時期にか、または別の機会にか、被爆者と縁をもつようになったことを私は空想してみました。(p181)私は多くの地方で被爆者に会い、被爆者の運動にふれる機会をもちました。 「あの人は実は被爆者ではないのではないか」 そんなふうに他の被爆者から噂される被爆者があることを、いちどだけでなく知らされました。それが、その地区の活動を代表するような被爆者であることを知って、おどろかされたこともありました。 しかし、それにもかかわらず、その人が献身的な活動を続け、被爆者としての活動が、その人の生活、というより、その人の人生の中心となっていることを知るときも、私は原子爆弾が人間の行為に対してもっている不思議な意味づけの力を感じ、戦後に被爆者が生まれていることを感じるのです。 最後に伊藤氏が知る悲劇的結末。(p191)「荒川で被爆者が自殺」 ×日午前十時ごろ、埼玉県秩父郡大滝村大滝の荒川右岸近くに男の死体があるのを近所の主婦が見つけ、秩父署に届け出た。同署で調べたところ、持っていた顔写真付きの診察券から東京都目黒区中町○○○○××荘内、無職、吉野啓二さん(44)とわかった。死後、一週間くらい(新聞記事より)。(p195)日本被団協事務局からの電話で、吉野さんの遺体が奥秩父の三峰山の山の中で見つかったことを私は報されました。(p201)そして吉野さんの生涯を思いました。 吉野さんが、長崎に原子爆弾が投下されたあの日どこにいた人か、吉野さんの「被爆者体験」がどのような過程をつうじて生成されていったのか、私には判りません。 私はただ、吉野さんの話の背後に、原子爆弾に被爆して亡くなった、無数の人々の声のない声を感ぜずにはいられません。その声が吉野さんを深くつき動かして、あのように、その被爆者体験を語らせたことを感ぜずにはいられません。もし亡くなった被爆者達の体験、その人々の声が、吉野さんの話のなかにとりいれられていたとするならば、死者達が生きている吉野さんの口をかりてその体験と怨念を私に語った、私の録音機をとおして限りない数の人々に語った、そう考えることは、それほど事実から遠くもなく、非科学的な表現でもないような気がします。虚構を語ることによって、その死者たちの怨念を身に負う重みにひしがれることが、吉野さんになかったでしょうか。それが不安定だった吉野さんの精神状態と、どこかで繋がっていることはなかったでしょうか。(その5)に続く。
2013年01月28日
コメント(0)
-
伊藤明彦著『未来からの遺言』を読んだ(その5)
(その4)の続き。 蛇足。 悲惨な話です。吉野氏が「ただの金銭や利権目当ての嘘つき野郎」ではなかった、という点が。 インタビューを行った伊藤明彦氏は(言葉の真の意味で)大変誠実な方ですね。それは吉野氏の虚偽に対する態度で良く判ります。真偽の裏づけをちゃんと取りつつ、しかし、吉野氏を“裁かない”。 ニポンサヨクであれば、どんな滅茶苦茶なつじつまが合わない内容でも“弱者”が語った事ならば、“自己脳内検閲”が働いて、疑問に思わないものでしょう(所謂従軍慰安婦問題の「疑う事自体、セカンドレイプ」なる理屈)。また「オカシイじゃないか」と感づく(または第三者に感づかれる)と、そのインタビュー自体、なかった事にするでしょう。 でも、先ずスタートラインに立たなきゃね。人間存在の奥深くには、このような心理があるのだと。“意味”への渇望。 これは普遍的な人間の欲望だと思います(そしてそれ故、人間は“欲深い”)。 また、俗に言う大文字で語られる“歴史的事件”といったものに、そうした“欲望”は根深く絡みつくものなのでしょう。これは“歴史的事件”を考察する際に忘れてはならない事だと思います。 (これは日本人だけに見られる問題ではないでしょう。1994年1月10日ドイツのザクセン・アンハルト州ハレ市で実際に起きた事件で、身体障碍者の少女がネオナチから暴行を受け、額にナイフでカギ十字を刻まれた、とされる事件がありました。一万人を超える大規模な抗議デモも起きたのですが、後にそれが虚偽と判明。四日後、自分で刻んだと捜査当局に自白したのです。これも一種の「ただの障碍者である事に耐えられない。意味が欲しい」という事なのでしょう。なお、一万人の抗議デモ参加者の誰一人として「ネオナチはケシカランが、この事件に関しては濡れ衣だったので謝罪しよう」と言う者はおらず、事件自体“なかった事”になったらしいですね。ドイツ版ニポンサヨク(笑)でしょうか。) 珍妙な所謂“従軍慰安婦”の証言(「従軍慰安婦の仲間がニポン軍人に首を切り落とされ、大鍋でグツグツ煮られ、そのスープを飲まされた」式の発言ね)も、こうした観点からの考察が必要なのでしょう(こっちは、単純に金銭的利益の側面が大きいのか)。 「意味づけの得られない苦悩は、いっそう、耐え難い重みを増す。」「人間はしばしば、意味づけの得られない生よりも、意味づけの得られる死のほうを選ぶ。」(この心理は日本ミステリー三大奇書の一つとも言われる傑作『虚無への供物』でも取り上げられていたような気がします。あやふや。あれ長いから読み直したくないの)(p85)著者のもとを訪問した「ある文芸雑誌の文学賞を受賞した長崎出身の被爆者」とは石田雅子さんか。 私の母も長崎で被爆していますが、ある日見知らぬ客が「私がその時その場に居た、と証言出来る人を御存知ありませんか」と訪ねて来たという事があったそうです。言外に「貴方に証言して欲しい」という意が見え隠れしたとの事(母は、偽証をするわけにもいかず、丁重に断りました)。 こういうのは判断が難しいですね。家族親族、友人知人が全滅に近い状態に置かれた大変不孝な方かも知れません。或は訪問してきたのは被爆とは関係なく、単に淋しいだけだったのかも知れません。或は、医療費の無料化を狙った詐欺師か(まず病気しなければならない(笑)から、あんまりウマミはないでしょうが)。 虚構は虚構(虚偽とはあえて言いませんが)。 (吉野氏の語ったような)“文学”が人間存在の本質を穿つという事はあるでしょう。しかしそれは個別の事象を超えたものである筈です。個別の事象の元に立ち現れる“ルール”の世界とごっちゃにしてはイカンです。(「“文学”で“裁く”」ニポンサヨク)。その“世界”を“求める”のはいいけど、その“世界”から“見下ろし”てはダメ。 このドキュメンタリー、映画化されないかな。周防監督あたりにやって欲しい。
2013年01月27日
コメント(0)
-
表彰状を贈る
本年も物言わぬ「物」達に表彰状を贈る。 タイのインスタントラーメン殿。 貴殿は日本製インスタントラーメンよりも遥かに安価であるにもかかわらず、異国情緒溢れる美味、しかも鍋さえ要らず、丼に熱湯を注いで蓋をするだけという簡便さをも併せ持ち、以って空腹時の求めに良く答えました。 ここにその栄誉を称え、以って表します。 芋虫殿。 貴殿は、病母との散歩途中に我々の方に這い進み、その虫とも思えぬ巨体のユーモラスな動きを以って、良く我々に微笑みと自然の喜びを与えました。 四季の移り変わりを体色の変化で文字通り身を以って示した蟷螂殿と共に、その功績をここに表します。 スーパーの身障者用トイレ殿。 貴殿は、病母の散歩時の懸念を一掃し、安心感、利便性と共に、母の健康維持に大きな貢献を成しました。 付き添いも入れる点、ほとんどのスーパーに設置されているという点も合わせて、ここにその功績を称え、以って表します。 龍角散殿。 貴殿は、予想を遥かに上回る効用と、漢方薬とは思えぬ即効性を以って、良く痰を切り、喉の不快感を和らげました。 江戸中期以降からの長い歴史と共に、その栄誉を称えます。 本年も皆様ご苦労様でした。来年も宜しくお願いいたします。 皆様も良いお年を。
2012年12月31日
コメント(0)
-
本日の偶然「シロクマ」3
書店に入ってクリスマスカードを眺めていたら、目に留まったのが「シロクマ」のクリスマスカード。「シロクマ」とは私にとって何なのか。
2012年12月17日
コメント(0)
-
本日の偶然「シロクマ」2
「本日の偶然『シロクマ』」を書き込んで、買い物に出たところ、途中でシロクマのキーホルダー(?)を見つける(柵の上に置いてあげたら、帰路には下に落ちていた。何故か紐がなくなっていた。汚れてもいるし、可愛そうなので拾って帰り、洗ってあげた)。
2012年12月16日
コメント(0)
-
本日の偶然「シロクマ」
テレビがマンガ『シロクマカフェ』を紹介していた時、手元のパソコンに「シロクマ」という名の製品が表示されていた。未読。可愛らしい話なのかな。
2012年12月14日
コメント(0)
-
杉浦日向子作『ごくらくちんみ』を読んだ
酒と珍味に沿って味わう大人の世界。滋味豊かな短編小説集。 あまり厚い本ではないのですが、短編が68篇も収録されていました。当然すべて短い。超短編集。 全編、つまみとしての「珍味」と酒が“舞台”として登場し、その上に人情の機微を表す話(多くは会話の形)が展開されていきます。 本当に短いです。短すぎる感じ。何か「もう一寸」という物足りなさ。 その物足りなさが見事に、酒のつまみの「珍味」の感じに相似ています(腹にたまって満足する「おかず」じゃないのね)。良く出来ています。 ぼけ始めた姉と呑む本醸造の酒と「からすみ」。若い男と同棲している女友達と呑む山廃純米古酒と「かぶら寿司」。墓を買った40過ぎ独身女性が友人との会話を思い出して呑むプロセッコと「このこ」・・・。 (一寸男女関係の話が多くて、それらは既読感があります。) ただ、惜しむらくは...。 名前も聞いた事のないような、知らない「つまみ」が多いんだよなぁ。あぁ、残念。話の世界が完全に理解できなくて残念だけれど、それ以上にその珍味を味わってみたくて残念。 味覚って言語化するのが一番難しい感覚だから、「旨そう」という雰囲気は充分に伝わるんですが、あぁ、もどかしい。 全編、登場する珍味の作者イラストが付いていて想像はいや増すのですが、あぁ、もどかしい。 「ふぐこぬかづけ」「うばい」「このこ」「鮭の酒びたし」「ふくしらこ」「にがうるか」「そばみそ」「ばくらい」「かつおへそ」「いぬごろし」「パルミジャーノ・レッジャーノ」「リエット」「ラルド」「黒いブーダン」「たてがみさしみ」・・・。 う~ん。どんなもんでしょうか。 (なんと巻末に親切にも手に入るお店とその電話番号が載っています。) また、合わせるお酒が、普通と違うのではないか。そういう気がします。純和風の珍味に洋酒を合わせたりしている。 「さなぎ(蚕)」と赤ワイン、「またたび」とカルバドス、「がん漬け」とテキーラ、「このこ」とプロセッコ、「ふなずし」とカルバドス、「とうふみそずけ」とシングルモルト、「しおなっとう」とテキーラ、「しおうに」とコニャック、「うみたけ」とテキーラ・・・。 合うのか。一般的なのか。これが通というものなのか。良く判りません。 だがもっと謎なのは、「黒豆」と大吟醸の取り合わせ。合うのか。甘いでしょ、黒豆。甘くていいのか。 更に、それよりもっと謎なのは、「きんつば」と本醸造の熱燗。良いのか、合うのか。本当に合うのか。あれ、甘いよ、相当(何故か読みながらコーフン)。 う~ん。 試してみた方が良いのでしょうか。 かつて私は、「安い冷凍物のピザ」と合成清酒の熱燗という取り合わせを試してみた事があります。 こみ上げてくるものがありました(泣)。 「しめ鯖」とブルーハワイという事もありました。若さ故の無謀さでした。 これは、かなりキマシタ。 出来れば、どなたか親切な方、「黒豆」や「きんつば」が日本酒と合うのかどうか、実験して教えてください。 もっとも最近私は「焼酎のココア割り」を飲んでいたりします(笑)(ポイントは安い焼酎で作る事です)。 なら、焼酎のつまみに「チョコレート」も可能なのか。 ダメでした。不思議。不思議。 「割る事」と「つまみ」はどうも違うらしい(私の場合は)。
2012年11月30日
コメント(2)
-
周防正行監督作品「終の信託」を観た
安易な救いを排除した恋愛ならざるラブストーリー。悪役大沢たかお大発見。 良い作品だと思います。ただ興行的にどうかといえば・・・(私も正直、現在のような状況下で見るのはツラカッタ)。 所謂「安楽死」「尊厳死」がテーマの作品ですからね。しかも、こういうテーマの場合、大抵、“明るく”“爽やか”に、救いのある話として制作されるのが常道だと思うのですが、この作品は違います。そういうハリウッド的ハッピーエンド、もしくは“すっきりとした結末”がありません。カタルシスなし。 無論、これは周防監督が「すっきりする問題じゃないから、すっきりしないで下さい」と意図的にそうしている訳です(これは「それでもボクはやってない」の場合と一緒)。 ただ、所謂サヨクの「社会の問題告発映画」的な、これ見よがしな無駄な重さ、陰惨さはありません。“清潔感”のある“端正”な描写。 構成は前半後半の二部構成。前半は重度の喘息患者と彼の担当女医の関係の深化について。女医が起こした自殺未遂事件を通じて、二人は人格的に深く共感しあいます。患者が女医に自分の安楽死を託す程に。 “明るい”というのは違う、“透明”とでも言うべき感覚で描写されています(これがなかったら、随分観るのがキツイ映画になっていたでしょう)。そしてプッチーニのオペラ「ジャンニ・スキッキ」の肩の力がふっと抜けるようなエピソード(「私のお父さん」の旋律の美しさに反して「ジャンニ・スキッキ」が喜劇だとご存知でしたか)。 重度の喘息という設定も生きています。何十年もずっと苦しんできて、しかも徐々に症状が重くなっている。患者の今に至るまでの人生にずっと安楽死の問題が影の様について来ていたんですね。 また、患者の幼少期に起きた事件もエピソードとして登場し、彼の死生観を理解する助けとなります。 前半はラブストーリーなんでしょうね。でも、ここまで極まると、所謂「ラブストーリー」とは全然違うものになっている。甘さ、幸福感は無論の事、高揚感も無い。「愛は惜しみなく奪う」とも「愛は惜しみなく与う」とも言いますが、どっちとも違う。ただ、人生の最後を任せる、任せられるという強い信頼関係があるだけ。 所謂「大人の恋」というのも違う(それは浅野忠信との関係ね)。強いて言えば「逝ける者の恋」か。 実際、「あぁ、恋なのだな」とはっきりと判る(恐らくは女医自身も自覚した)台詞は、たった一回だけ、患者が死んだその瞬間に発せられた台詞だけですからね。 患者役の役所広司さんの演技というか、“顔”が素晴らしい。本当にもう直ぐ死ぬ顔です(テレビCMのラーメン食べてる顔とギャップが大きい)。 また、空と地が一つに合わさる「“天空”に至る道」の撮影場所も素晴らしい選択です。平凡極まる東京の川縁の舗装された土手の道。空はいつでも灰色の曇り空。晴れてもいない。すっきりとした開放感もない。 だからこそ、逆に“説得力”があります。あぁ、この人の人生はずっとこんな感じだったんだなぁ。 後半は一転、密室劇となります(検事役の大沢たかおさんと女医役の草刈民代さんのほぼ二人っきりで、薄暗い検事室。これは圧迫感、閉塞感がキツイです)。女医は殺人罪で検事から厳しい追及を受けます。 ここはエグイ。“灰汁”が強くて飲み込み辛い。 検事役の大沢たかおさんの演技が素晴らしい。高圧的で老獪で、ぶん殴ってやろうかと思うほど、憎らしい。「大沢たかおの野郎、南方仁とか言いながら、草刈民代さんを苛めているじゃないか、はったおしてやる(もう滅茶苦茶)」というぐらいイヤな人物を好演。 日本映画史上に残る“悪役”なんじゃないでしょうか。 でもこれ、この検事が悪人である訳ではないんですね。寧ろ、“良い人”。能力があって職務に忠実で、しかも志気が高い。これは“良い人”“良い検事”でしょう。 しかし、不快な人物。観客は前半で、女医と患者の関係や、安楽死を決断した経緯なんかをしっかり感情移入しつつ観ているから、本当に嫌悪感を感じます。 つまりこの検事は、彼の人格とは関係なく、社会制度、法制度という抽象的存在としての“悪役”なのです(こういう悪役は日本映画では実は珍しい。日本の「社会告発もの」は大抵ただの人格攻撃で終わる)。 大沢たかおさんって、悪役をやっても凄みのある顔をお持ちなんですね。これは大発見です。「爽やかな好青年」顔だけじゃない。 机をバンッと叩いて威嚇するシーンなど、本当に憎悪を感じます。「大沢たかお、お前何にも知らないで。南方仁のくせに、エラそうに」。 今後是非、大沢たかおさんにはさらなる悪役に挑戦して頂きたいです(色悪ですね)。 この映画、救いがないといえば“無い”映画ですが、患者さんも女医さんも自分の決断を後悔していないでしょう。 人生を「幸、不幸」で計らない。人生には“意味”がある。どんな人生にも“意味”がある。 一人の人間の“魂”(とでもいうより仕方ないもの)に深く寄り添う事が出来た。その意味を女医さんは味わうだけで充分なのかもしれません。 最後に。 この映画、他人事ではないでしょうね。家族が倒れたらどうするか。さらに、自分が倒れたら・・・。 安楽死、尊厳死の問題、「一筆書いておけば全て解決」というような簡単な事では済まず、様々にクリアすべき問題があります。 本気で望んでいるのならば、残された人々に迷惑をかけないようにしておきたいものです。因みに草刈民代さん、実は冗談好きのかなり陽気な人のよう。『「Shallweダンス?」アメリカを行く』という周防監督の本に詳しい。
2012年11月01日
コメント(0)
-

サボテンの花
ベランダのサボテンの鉢の一つに花が咲きました。 「岩牡丹」だと思います。 全く世話らしい世話をしていないのにちゃんと咲いてくれました(葉の幾つかが赤茶けて変色しているのが気がかりです。世話をしていないからでしょう)。 季節は人の人生とかかわり無く、移って行くものですね。 年年歳歳花相似たり、歳歳年年人同じからず。 昔の風流な人は、菊の節句にちなんで盃に菊の花びらなどを酒盃に浮かべた様ですが、この花は止めておいた方が良いでしょう。 「烏羽玉」と同じく、このサボテン、幻覚作用があるようです。(一寸花を浮かべたぐらいだと関係ないけどね)。
2012年10月27日
コメント(3)
-
本日の偶然「名古屋」
呉智英氏の『真実の「名古屋論」』を読んだ数日後、NHKの歴史番組で名古屋を扱ったものを観た。その数日後、たまたま手に取って読んだ司馬遼太郎の本が『濃尾参州記』。名古屋が舞台のもの。 (所謂「偶然」という概念に当てはまらないかもしれないが、主観的には「何故か、名古屋が続いている」という印象。偶然とは主観と客観のあわいに現れるものだろうから、あえてここに記しておく)そういえば暫く食べていないなぁ。
2012年10月23日
コメント(0)
-
滝田洋二郎監督作品『天地明察』を観た
晴れ晴れと心が開かれる作品。とほほの忍者の謎。 事情により、今後当ブログ、以前にも増して走り書きになります(あんまり変わらんか)。(因みに見たのは一ヶ月程も前でしょうか。書く時間がないのです) 珍しく時間が空いたので、『天地明察』を観てきました。監督は滝田洋二郎氏。『おくりびと』の監督さんですね。その次の監督作品『釣りキチ三平』も淡々とした描写ながら晴れ晴れとしたした作品だったので、私は気に入りました。どうもこの監督の作風とは気が合うようです。 本作品も私は気に入りました。 事情があって鬱々とした日々を送っていたので、実に嬉しい映画でした(実は『プロメテウス』も観たのですが、こちらは反って・・・)。 ただ、後半全く首を捻るシーンもあって、「何故、『おくりびと』の監督がこのような」と妙な気持ちになったものです。 本作品は、江戸時代、天体の観測を通じて日本初の暦づくり(日食を正確に予測出来るレベル)に挑戦した実在の人物、安井算哲(渋川春海)の映画です。 前半部、主人公(岡田准一)や主人公を取り巻く人々の性格描写が清清しいです。高等数学の難問に夢中になって挑む主人公(高等数学を解くのが趣味という人々。江戸時代とはなんと豊かな時代であった事か)。嬉々として取り組んでいる姿がなんとも爽やかで、ほほえましくもあります。数学史上の“化け物”関孝和との接触。そして、その姿を温かく見つめる将来の妻との出会い。 なんとも晴れ晴れとした気分になります。 彼は天体観測と数学の才能から北極出地(北極星の高度計測による土地計測)任務の旅の一員となります。 この時巡りあう上司二人も、なんとも好ましい人物(笹野高史、岸辺一徳)。上司と部下という関係はきっちりしながら、主人公の才能と情熱に敬意も払っています。 そして、なんとも暢気な空気。移動距離を歩数で測るのですが、その時の歩いている格好が、大きく手足を振って、かわいい、かわいい。幼稚園児が遠足に出かけている姿を連想しちゃいました。 一緒に旅をする下働きの男達も気がよさそうです。 関孝和に挑んだ数学問題のエピソードも味わい深いものでした。主人公のミスで解が無数にある欠陥問題を制作してしまったのですが、上司二人はミスを指摘しつつも、にこやかに彼の学問の姿勢を褒めます。また、問題を受けた関孝和も「いままで見た設問の中で一番好きだな」と呟くのです。 世俗的な上下関係とは別に、同じ地平に立っている同士なんだな、と感じます(逆に言えばこうした関係が無ければ学問発達しないのでしょう)。 主人公の妻となる女性(宮崎あおい)も、考えてみれば妙な女性です。縁談を自分から断られるように仕向けたり、わざと離縁されるようにしたりして、主人公と結ばれる事を願います。しかし、障害はそれだけではなく、北極出地やら暦の制定やらの為、一年、また三年、また十年と、どんどんプロポーズ自体遅れていく訳です。でも、待ってるんですね。しかも、さして思い詰めてるふうでもなく、軽やかな感じで待っている。この、全く思い詰めていない、しかし主人公を信じている感じが、何か非常に明るい晴れ晴れとした気持ちを誘います。 最後に印象に残る人物を。水戸光圀(中井貴一)がそれ。政界の黒幕といった“怪人物”として登場します。和洋中ごちゃ混ぜの奇妙な部屋に住み、これまた妙な和洋中混合料理を所狭しと並べた食卓で主人公と相対します。ラーメンとか餃子とか食べてるんだよね(笑)(「水戸光圀とラーメン」の話は有名ですね)。 本作品の直接のテーマではないですが、日本も含めて非西洋圏の科学技術史はもっと注目されても良いと思います。第一、当の日本人が無知というのは、ご先祖様に申し訳ない(笑)。 この映画でもそうでしたが、東アジアの場合、近代以前まではやはり何といっても支那が中核となり、周辺地域は、その核の科学理論、中核技術とどう向き合うか、応用するか、という形から、それぞれ独自に科学技術を開花させていく訳です。これ、他にも江戸時代の言語学なんかもそうですね。 また、もっと大きな流れも考えられます。本映画でも他に比べて正確だと登場した元の授時暦、これはイスラムの優れた天体観測技術の影響が見られるとも言われています(元、つまりモンゴル帝国だから)。そして、イスラムの科学技術の源流をぐっと辿れば、ギリシャまで行きます。 地球を大きく取り巻き、流れ続けてきた、延々たる人類英知の営み。それは相応しい場所で繁殖し種子を飛ばす植物のように、彼方此方で花開いてきた訳です。 さて、この映画の難を言えば、まず渾天儀(天体観測所)。近代の天文台のように円形蛇腹式というのは違和感がありすぎるような気がします(当時の技術で可能なんですがね)。 また、京都の陰謀公家、宮栖川友麿があまりに判り易い図式的な悪役として性格づけさせられていた事。ただの保守的な人で良かったんじゃないでしょうか。寧ろ、日食予測で主人公の正しさが証明された時、「安井算哲はたいした男のよう」のような発言で最後を締めくくれば、後味がずっと良かったと思います。この映画に悪人は要らないですよ。 そして、最大の欠点。何ゆえ、謎の黒ずくめ放火集団が登場?お前等、忍者か!。 なんで、あの『おくりびと』の監督がこんなシーンを撮ったのか判りません。山崎闇斎、壮絶戦死(笑)。アクションシーン要らないでしょ(原作では脅迫状が届くだけらしい)。せめて、「放火の報を聞き、研究資料を持ち出そうとした山崎闇斎が焼死した事を暗示」ぐらいにして欲しかったです。 「安井算哲の測量殺法が闇を斬る」「敵か味方か、秘剣、行列剣法の謎の使い手、関和孝」いらない、いらない(笑)。 ごたごたした地上と対照的な、静謐で清らかで、どこまでも広がる満天の星空。 この映画の開放感は、背景の「満天の星空」から来ているのでしょう。
2012年10月15日
コメント(2)
-
鎌田東二著『現代神道論』を読んだ
題名不適切。ユニークな神道家による「3.11東日本大震災以降の神道」。 著者は大変ユニークな方です。なんと紹介して良いのか。宗教学者や、民俗学者、哲学者というので良いのでしょうか。神道家でしょうか(大学の先生でいいか)。 ご自身では「フリーランス神主」「神道ソングライター」と名のっている事もあるそうです(CDまで出していた(驚)。竜笛の演奏家というのは知っていたけどね) 本書の書名「現代神道論」も副題の「霊性と生態智の探究」も、若干不適切であると思います。 主な内容は「3.11東日本大震災後の日本を鎌田氏を始めとした神道家(宗教家)はどう見るか、どう活動しているか」というものです。「3.11東日本大震災」が題名にも副題にも入っていないのはイカンのではないでしょうか。 文章の口調は「論文」調なのかも知れませんが、内容は「論文」といった、何かの“論理”の展開が示されているというより、知見と活動の記録です。神道(宗教)を“内側”からを記述する試みというものでしょうか。“内側”からなので当然、文献がどうのこうのという話では全然ありません。 所謂「論文」ではないので、すらすら読めます。 先ず、神道家の方々が被災地で活動している、という話が興味深いですね。何故か、日本のマスコミは報道しません(しても、何故かキリスト教関係限定)。近接領域と思われる所謂「心のケア」の問題が比較的に取り上げられるのに比べると、残念な気がします。“心”となれば医療なのでしょうが、“魂”の問題もあるのではないでしょうか(“心”と“魂”。さて両者の違いは)。宗教家の使命も大きなものがある筈です(こちらも何故か医療方面からのタッチしか注目されない)。 また、この未曾有の大災害を神道家としてどう位置づけるか、という話も興味深いです。世界観自体の変化という極めて大きな問題。 著者はこれまで繰り返し「現代大中世論」という持論を展開してきたとの事。現代日本の情況を幕末に喩える人は多いのですが、中世とは(より大きなスパンで見ているというか)。日本の歴史は古代と近代、中世と現代が対応するのだそうです(古代の律令体制と近代の立憲君主制、等)。 p63「日本中世には律令体制が大きく崩れ、『征夷大将軍』という令外の官が権力の中心になって二重権力構造が生まれるに至るが、戦後の現代日本もまた米国という別種の『世界の警察』を自称する『征夷大将軍』に制圧され守護された二重権力構造の中にあるといえるだろう日本国憲法第一条に規定された象徴天皇制は、そうした二重権力的な中世的ねじれと対応すると思われる。」 ただの“お見立て”と言われそうですが、面白い着想だと思います。 日本の中世と言えば保元平治の乱等で世は乱れ、武士が台頭してくるのですね。「末法の世」などとも言われておりました。地震等の天災、飢饉も起きました。 p13「京都に住んで実感するのは、先が読めない天候だということ」 著者に拠れば京都の天気はイギリスやアイルランドや北方ヨーロッパと似ているそうです。彼の地に住む人々(例えばゲーテ)が「光の国」イタリアに憧れていたのは有名。で、熊野の天候はイタリアに似ているのだとか。「京都に住んでいると、なぜ後白河法皇や後鳥羽上皇が三十回前後も熊野行幸したのかわかるような気がする。」 p17「わたしは『神道』の真髄を誰にでもわかるように解き明かすとすれば、『むすんでひらいて』という童謡が適切であると以前より主張してきた。」「あるものとあるものとをむすぶ、そしてそのむすびからあるものごとをひらいていく、そして神前で拍手を打つように手を打って、またさらにそれらをむすびかため、またひらき、手を打って、天地神明に対し、手を上にして祈りの言葉を唱え、感謝と祈りの気持ちをあらわす。」 p42「神仏習合とは神神習合の一分枝(ブランチ)である」 「私は『神仏習合』という文化習合が練り上げられる遥か以前から、日本列島は四つの『プレート習合』の地で、そこに東西南北から四つの海流(黒潮、対馬海流、親潮、リマン海流)が流れてきて合流するという海流の十字路でもあり、そのプレートや海流の合流点に、さらにさまざまな『カミガミ』が合流してきて、そこに列島の『神神習合』の文化特性が出来てきたと考えている。」 p44「『神』と『仏』の原理的差異を三点に分けて説明してみたい」 「神は在るモノ/仏は成る者」「神は来るモノ/仏は往く者」「神は立つモノ/仏は座る者」 解り易い。 p55古事記と日本書紀「日本の神話と歴史を記述する同時代の書が二つもあること自体がダブルスタンダードであるが、この神話と歴史が相当異なっている点が奇怪である。(例えば冒頭神。古事記では天御中主神。日本書紀では国常立尊。しかも日本書紀には本文と異伝承が『一書に曰く』という形式で並列併記されている)このような『ダブルスタンダード』ならぬ『マルチスタンダード』の記述様式を国の最初の公式文書に置いたのが『八百万の神々』を伝え、生物多様性ならぬ『神仏多様性』を担保してきた日本という国柄なのである。」 (「一書に曰く」の並列併記スタイル)「世界中の神話を見ても、これほど奇妙な神話歴史書はまたとない。一つの神話素にABCDなどのヴァリエーションがあると言うのをそのまま載せているのだから」 「私はここに日本の習合思想の一つのあらわれを見る。」 p84エコロジーの神を祀る「空気神社」。 エコロジストの神道家によって(エコロジストでない神道家というのはありえるのか)、1988年に新しく「空気神社」という神社が創建された、という話が紹介されていました。 場所は山形県西村山郡朝日町。1973年の村の寄り合いでの白川千代雄翁による問題提起がきっかけだったそうです(『空気ものがたり---『空気神社』を創った男達』に詳しいとの事)。 ブナ林の中に建てられ、本殿は舞台のような形態で、五メートル四方のステンレス板が張られており、四方の四季折々の自然がそこに映し出されるそうです。風が吹けばブナの梢のそよぎが、夜になれば月や星がステンレスの鏡面に。また、本殿の祭壇は地下に納められていて、その前に十数個の甕が置かれ、風が吹くと共鳴するそうです。 なお、この空気神社の参拝方法も独特。「ニ拝.四拍手.仰ぎ.一拝」だそうです(四拍手は四季に対してとか)。 p86「正面から戦争に反対する『戦争メモリアル』を作るよりも、わたしとしてはこのような『空気神社』の創建の事例の方が平和構築や戦争廃絶への身近で等身大の道のりだと思っている」 p129神社周辺の森林のナラ枯れの問題。聖地霊場の存続基盤の衰退。 これはもっと神道家側からの積極的な発言が待たれる問題だと思います。 p158「浪分神社」の例(「浪分」=津波がここまで来たの意)。神社が防災ランドマークであった。先祖が残した津波という「場所の記憶」。 日本中で行政サイドが地名を訳の判らんモノに変える流れがありますが、地名はその土地の“記憶”です。事にこうした大震災の記録は重要です。 南方熊楠も述べていたと思いますが、神社とはその土地の歴史記念館でもある訳で、もっと産土神を祀っている神社、ひいては神道という“あり方”が注目されても良いと思います。 p182倒れなかった霊石、御神石等の話。 釣石神社の「釣石」(不安定そうな立ち上がった形の巨岩)等。別にこれは神秘と考える必要はないと思います。話は逆で、長い年月の間、倒れない場所にあったから御神木、御神石と祀られるようになったのでしょう(因みに「釣石」は無事なのですが、津波で入り口の茅の輪は折れまがり灯篭も崩れ落ちています)。 「釣石神社の上まで駆け上がって命が助かった人がいるとの事だった」「この釣石は1978年の宮城県沖地震にも耐えた」「民間信仰というのは大変面白い。人々の素朴な願望や安心を得るための身近な回路になっている。それだけでなく、ランドマークになったり、災害時の緊急避難所となるなど、具体的で実用的な機能も果たしている。」 p199(京都造形芸術大学教授の地球科学者、原田憲一氏の九州災害多発地域の地質研究の話)「災害多発地域にあっても神社が災害を免れていることが多い。ことを実証的に示している。神社に巨岩や巨木があることが多く、石神社や釣石神社の御神体がそうであるように、地震などでも崩れることのなく、長期的に安定した『杜』を維持してきているところが多い。ということは、そこが経験的に安定した地盤であり、その『鎮守の森』は生物多様性が保持されてきた生態学的センターであるために、いざという時の避難所にもなるということである。『災害』に対する伝統文化の拠点としての神社が持つメッセージ性とランドマーク性と警告はもっと注意されていい点であろう。」 鎌田東二先生は60歳を越えられたそうですが、バク転が出来るそうです。で、何故か聖地霊山の中で三回バク転を。 妙な人です。鎌田東二先生オフィシャルサイトオフィシャルサイトがあるんだ。
2012年09月09日
コメント(0)
-
くよくよダイエット法
家族の病気の為、一週間程、食事が満足に取れなかった。目が離せない為、食事時間が取れなかったのだが、そもそもストレスで食欲がない。 赤瀬川原平翁が命名したところの「くよくよダイエット」にチャレンジする事になった(「老人力」もそうだが、赤瀬川翁の発想の凄い所は価値観を全く転倒させてしまう事だ)。 一週間程で5キロ以上落とす事に成功した(これはまぁ予想出来る事だが)。 しかし、異常と言っても良い程、体が柔らかくなったのには吃驚。 下と上から手を背中にまわすと、指先の第二関節までがっちり握手できる。 片手でもう一方の手の親指を押しつつ手首を曲げると何の抵抗感も無く、親指が腕に着く。 前屈すれば、これまた全く何の抵抗感もなしにべったりと頭が膝頭に着く。 女座りをして、そのまま体を後に倒すと、膝頭を完全に閉じた状態で、背中がぺったりと床に着く。 全身の関節がもれなく柔らかくなった。 何だ、これは。 幸いに時間が取れたので、チェックを兼ねて献血に行った。 アルブミンの項が少し悪いくらいで、他は正常。コレステロール値も下がり、γ-GTPなど、今までで最も低い価であった。 恐るべし、くよくよダイエット法。 (尤も、家族の病気が小康状態に入ると、ぎっくり腰になった。ぎっくり腰がやや快方に向かったところで調べてみると、まだ体は柔らかい方であるが、以前ほどではない。)
2012年09月01日
コメント(0)
-
小野田博一著『論理パズル「出しっこ問題」傑作選』を読んだ
極短文章の問題集。羊を数える代わりに。 全問全て論理によって解くクイズ集です。「論理によって解く」とは完全に論理展開のみによって解くという事です。所謂引っ掛けとか言葉のダブルミーニング等が鍵の、トリッキーな問題は一問もありません。 しかも、質問一問一問が極端に短い。文字通り、文字数が少ないのです。論理展開のみによって解くのですから、必然と言えるでしょう。 この点でユニークと言えると思います。 ただ、強いて言えば、そこが難点かも知れませんね。一寸同じ料理が続いているという感じ。たぶん、一日で一挙に読み進めるというより、毎日一、二問ずつ楽しみながら解いていくという形が良いのでしょう。 質問自体が至極短いので、問題文を読んだ後、寝床に入り、目を瞑って問題を解くという楽しみ方も出来ますね。 60問ありますので2ヶ月は楽しめると思います。 本書から、私でも解けた問題の内、3問程。 p19「菜々がカゼをひいているとき、絵里香はカゼをひいていません。では、絵里香がカゼをひいているとき、菜々はカゼをひいていない、といえるのでしょうか?」 この問題は著者の娘さんが作った問題だそうです。単純ですが、多くの人が引っかかるとの事。 「絵里香がカゼをひいているとき菜々はカゼをひいていない、とはかぎらない」と考えた貴方、残念ながら間違ってます(笑)。 この問題は、何故これが不正解なのか説明を聞いても納得されない人が結構いるそうです。「菜々、絵里香」と「風邪ひき、風引きでない」の関係、全部で4パターンですね。その4パターンについて考えるのが一番簡単な方法だと思います。ある程度論理学に通じている人は、対偶命題を考えれば良いと直ぐに判りますね。 この問題、何故不正解の人が多いのか。著者は「現実生活では二人が同時に風邪をひくことはありうるから」という思い込みから間違うのではないか、と著者の方は憶測を述べられています。が、私は違うと思います。「ひく、ひかない」という選択肢が2つだけ、という情況が特異だからではないでしょうか。現実生活で選択肢が2つだけというのはあまり無いですからね(「風邪、風邪気味、風邪ではない」etc)。 選択肢が2つしかない、例えば性別の問題ではどうでしょう。例えば「一卵性双生児の片方が男でない場合、もう片方は男でないといえるか」という問題。間違える人はいないと思います。 p61きのう与之介、ひとみ、由香の3人はそれぞれ、鷲、鷹、モズの内2つ(2種類)を見ました。見た2つが同じ人はいません。 与之介「私は鷲を見ました」 ひとみ「私は鷹を見ました」 由香 「私はきのうハンバーグを食べました」 「ある鳥」を見た者の発言は偽で、見ていない者の発言は真実です。「ある鳥」とは何? この問題、勘の良い人なら瞬解するかも知れません。「ある鳥」を見た人は嘘つきという事は、「その鳥を見た」とは言えない筈ですね。 p67「あなたは寒がりでない。したがって『あなたが寒がりなら、あなたはペンギン』。この論理は正しいか?」 これは一寸意地が悪いかな。論理学の知識がなければ「何を出鱈目言っているんだ。正しい訳ないだろう」と何も考えずに誤答してしまうでしょう。 補足に「『豚である。したがって豚か羊である』の論理が正しい事がわかりますよね」とあります。つまり「あなたは寒がりでない。したがって『あなたは寒がりでない、あるいは、あなたはペンギン』」と同じという事になります。 純粋に論理のみで考える問題なので、そこが著者の意図せざる引っ掛けになっているのかも知れません。
2012年08月20日
コメント(0)
-
人間的な同居人たち
以前こんな事がありました(未だ書いていなかったようですね)。 暑い夏の日に帰宅して、いの一番に冷蔵庫からビールを出し、一旦テーブルの上に。そして、おもむろに取り上げて、グーッと飲み干し、やれやれ人心地ついたと、視線をテーブルに落とすと・・・。 いたんですね、ゴキブリが。しかも、逃げない。 テーブルの上の、ビールの缶に点いた水滴の輪に頭をつけている。水を飲んでいるのです。 あぁ、今日は暑かったからなぁ。こっちがビールをキューっとやっているのと同じように、水を飲んでいるのだろうな。逃げもせず、一心不乱に飲んでいる。 暫くゴキブリ氏に水を飲ませておきました(結局、叩き殺したんですけどね)。 また、似たような事があったんです。 帰宅して、放るように衣服を脱ぎ捨てて、扇風機に当たっていると・・・。 いたんですね、長椅子の背に。触覚を扇風機の風になびかせながら、のんびりと長椅子の背の“土手”を散策していました。ふかふかした夏草(長椅子の起毛)を踏み、夕涼みにそぞろ歩きに出たといった風情。 これがマハトマ・ガンジーやダライラマ猊下ならば「ようやく川風が吹いて涼しくなりましたね」などと、ゴキブリに声をかけ、共に命ある者同士の交歓に喜びを感じる所なのでしょうが、私はそれ程偉くない。 あたふたしながら、殺虫剤を振りかけ、ゴキブリ氏は猛スピードで遁走しました(現在に到るまで生死不明)。 のんびりと歩く風情は、明らかに涼んでいました。考えてみれば日中、暑い部屋にずっと籠もっていたんですからね。悪い事をしたかもしれません。 夏は昆虫達が自然の中で短い命を精一杯輝かせる季節です。そして、人間の住居だって、彼らにしてみれば“自然環境”なんでしょうね。 しかし、今度出てきたら必ず仕留めるからな。
2012年08月16日
コメント(2)
-
『ポケット・ジョーク グルメと笑い』を読んだ
文化の違いなのか。訳の問題か。これは憎まれ口なんでは 厚くない文庫本ですが、多くのジョークが載っています。一寸した気晴らしには良いのでは、というつもりで読んでみました。 う~ん、笑いの意図は理解できるんですが、笑いまでには行かない話が大部分。文化の違いのでしょうか(というより、この本は何なのだろう。翻訳された方のお名前はあるのですが、その原書の名前は一切無し。ジョークならば、やはり米国なのか)。 訳の問題なのかも知れません。「あとがき」には、ジョークと無関係な最近の野菜栽培の堕落ぶりを批判した文が載っていました。訳者の方は大変生真面目な方なのではないでしょうか。 この類の本で一番笑えるのは、江戸時代の小咄集であるというのは、私の嗜好のせいなのか。 未だに、「日本人はユーモアの欠けた劣等民族だ」式の発言をなさる方が“国際人(←何なんだろう)”さまにいらっしゃるようですが、民族に上下はないと思いますよ。単に「ユーモアの欠けた人」がいるだけだと思います(それが“国際人”だったりする)。 強いて言えば、欧米人はスベる事を恐れない、というか、そもそも他の事と同様、他人の反応をそれ程気にしていないのではないでしょうか。 (ユーモアのセンスの欠けた人の連発ジョークが常態化した社会。それはそれで・・・。) あぁ、でも「とにかく、バットを振れ」という考えはあって良いな。 この本で大量にそうしたジョークを読んで、そんな感想を持ちました。 ・レストランでウェイターに「君がここで働きはじめてどれくらいになる」「一年ほどです」「じゃ、僕の注文を取ったのは君じゃないな」 ・「これは何だい」「ビスケットよ。自分で焼いたの」「そうかい。なら自分で食べるといいよ」 総じて攻撃的な皮肉や憎まれ口が大半。欧米では知りませんが、日本社会では実際には使えません。嫌な奴だよね、単に。 よく「直接的に非難せず、ユーモアやウィットに包んで話す欧米人は素晴らしい」式の発言をする人がいますが、どうなんでしょう。余計に嫌な雰囲気になるだけだと思いますが(笑)。 「クレーム社会では皮肉と憎まれ口が発達する」というのはどうでしょうか(で、“国際人”がそれを「ユーモアのセンスが豊かな素晴らしい社会」と勘違いしてたりして)。 全く詰まらない話ばかりでもないので、一寸訳を私流に縮めて幾つか。 ・「『卵産みたて』って書いてあるけど、何時なの」「十分前に、私が書きました」(人工知能にありがちの問答) ・息子に葡萄を買いにやらせた婦人が、八百屋にクレーム「三ポンド買ってこさせたのに二ポンド五オンスしかないじゃない」「葡萄じゃなく息子さんを測って御覧なさい」 ・さる婦人があるベーカリーのクッキー作りを見学。そこのベーカリー店主は、自分の耳や肘、臍などで型を取ってクッキーを作っていた。「上手いもんでしょ。ドーナッツ作りも見学なさいますか」 ・某国首相の演説「私が首相になった時、我が国の経済は断崖絶壁に立っていた。私は、我が党が大胆な一歩を前に踏み出した事を大変誇りに思っている」(野田首相で可) ・「スープのなかで蠅が泳いでいる」「泳げるって、得意になって見せびらかしているんだな」(なんか蠅がかわいい) ・広告「当店でお食事をされた方は、二度とほかの店で食事をされる事はありません」(夏場は特に) ・今晩の夕食はチーズだけ。ポークチョップに火がついて、デザートの中に落っことし、しかたがないからスープで消したから。 ・料理が出来るのにしようとしない女房より始末におえないのは、料理が出来ないのにしようとする女房である(「福島原発国会事故調報告書」にあってもおかしくない台詞) ・「俺には動物を惹きつける不思議な力があるんだ」「ナイフとフォークを使うようになれば、そんなに寄って来るかしら」 ・「このウィルスには大量のオレンジジュースが良く効きます」「でも、どうやってそのウィルスにオレンジジュースを飲ませるんです?」 ・狼が菜食主義じゃないのに、羊が菜食主義を決議しても意味がない。 ・「レモンに足ってあったっけ?」「あるわけないだろう」「じゃあ、さっきウィスキーに絞ったのは、あんたのカナリヤだったんだ」 ・人食い人種の親子。子が飛行機を指差して「あれは何」「ロブスターみたいな物。殻は食べずに中身だけ食べるの」 「日本の笑い」って欧米で紹介されているんですかね。 アニメ、マンガ経由で結構知られているのかも知れません。
2012年07月26日
コメント(2)
-
赤瀬川原平著『健康半分』を読んだ
枕頭、病者の楽しみ。 お見舞いの差し入れに丁度良い本ではないでしょうか。薄く、活字も大きく、「ソーメンみたいにスルスル読める」(著者自身の弁)とは言いえて妙。病気の時には“重い”本は最初から手に取る気がしなくなるものです。また小さな活字を目で追う事も億劫。本の構成自体、内容にぴったり合っていると思います。 病院の待合室に置かれている無料の小雑誌『からころ』に連載されていたものです。著者のイラスト入り。 内容は、病気のありがたみ(「健康の」では無い)等について書かれた本です。流石は「老人力」の人です。病気は人生に深みを与える経験でもあるんじゃないかと気づかされます。病気の悩みは無くならなくとも、悩みそれ自体に悩む事は無くなるんじゃないでしょうか。 赤瀬川原平翁自身、最近入院されていたようですね。入院中、20回もスカイツリーに登らされたとの事(テレビでね)。「うんざり味わうのが入院生活」だそうです。テレビの劣化が激しい昨今、一番の被害者は身動きの取れない病者なのかも知れません。 という様な事を、赤瀬川原平翁のツイッターで知りました。 赤瀬川翁がツイッターをしているという事自体、私には驚きです。結びつきませんでした。
2012年07月04日
コメント(0)
-
スコット・ワウ、マイク・マッコイ監督『ネイビーシールズ』を観た
ドキュメンタリーを何故撮らなかったのか。ガジェット鑑賞映画。 パンフには「主演:米海軍特殊部隊<NAVY SEALS>」と大きく入っています。登場する各兵器、隊員全て本物との触れ込み。これが一番の呼び物なのでしょう。 ドキュメンタリータッチで淡々と訓練から作戦遂行の模様を描写するのかと期待しました。 ハズレ。 普通の娯楽映画。 そして普通の娯楽映画として見るなら、凡庸です。ベタ過ぎ。 戦闘シーンはそうでもないのですが(そりゃ本物の隊員が本物の兵器でアクションしている訳だから)、他はベタ過ぎる演出で制作者サイドの意図が見えすぎ。正直、脱力感まで漂います。 例えば冒頭、各隊員を一人一人ナレーションで説明しちゃうんですよね。米国三流映画でよくやる演出。しかも「良き家庭人、良き社会人」であるという事を態々印象付けたいんだな、と意図が見え見えの。 こういうのってさぁ、台詞や仕草で自然と人物像を浮かび上がらせるものじゃないの。 「大衆向けの娯楽映画にこそ、その国の国民性が表れる」というのが持論なんですが、この映画に表れているのは、「アメリカ人の“鈍さ”」なんじゃないでしょうか。一々、口で説明してやんなきゃ解らない。そして一々口で説明してくる(“鈍い”のであって“馬鹿”ではない)。 ストーリー、というよりその前提である世界観自体、完全に米国国内向け映画。米国人なら熱く盛り上がれるのかも知れませんが、外国人(である日本人)には「何だかなぁ」。 「外国人から見たら」という視点(或は普遍性)が欠如している。これもまた「米国一般大衆」の一面なのでしょうね。 結局「隊員を含め兵器等、登場するガジェットを鑑賞する映画」として楽しむべきなんでしょう。 強いて面白かったと言えるのは、密輸団のボスを尋問するシーン。喰えないボス相手に紳士的に対応するんですが、やんわり脅迫するやら、いきなり態度を豹変させるやら(でも暴力は振るわない)。プロの尋問の仕方だなと感心します(でも現実の米軍には“素人”が多いんでしょうね)。 戦闘シーンで女性と子供は見事に無視するシールズ隊員。嘘だよなぁ。撃つんじゃない、実際は。 といって、「米軍は平気で女子供を殺す鬼畜だぁ」と言いたい訳ではないのです。フェアに言って「女子供の方も平気で撃ってくるだろう」という訳です(正規兵同士の戦争じゃないからね)。 そもそも企画の段階で、この映画、違うんじゃないでしょうか(この点で非難しちゃぁ、映画評じゃなくなっちゃいますが)。 何故、ドキュメンタリーを撮らなかったのか。 折角、本物のネイビーシールズの協力を得られるのなら、訓練風景のドキュメンタリーの方がずっと良いのではないか。 自衛隊の広報施設に行って、訓練風景の短編映画を観た事があるんです(レンジャー部隊?)。極々短いドキュメンタリー映画でした。 でも、感じる所があったんですよね。 訓練の最後、自衛隊隊員は疲労困憊、ヨレヨレの状態で、それでも目的地に向かって行進して行く訳です。そして迎える人々。 少しジンと来ましたね。 「全てが本物」が売りならば、「本物」を直に描くのがベストだと思いますが、如何でしょうか。 (ミリタリーファンの方なら、尚更、「お芝居」は夾雑物と感じられたんじゃないでしょうか。もっと充分に隊員や兵器を見せて欲しいという感じ) 笑い事じゃないのでしょうが、思わずニヤニヤしちゃったのがコスタリカでのCIA救出シークエンス。米国は勝手に軍隊入れちゃって、勝手にゲリラとドンパチして、勝手にCIAを救出して、コスタリカの主権はどうなっているのかなぁ(笑)。いや、そもそもCIAを送り込んじゃって、それはいいのかなぁ。「何の恥ずかしげもなし」に(笑)。 (メキシコでのシークエンスではしっかりメキシコ政府側の人間が出てきて、作戦協力しておりました。つまり「了承の外交的手続きがあった」の描写)。 メキシコとコスタリカ、この差はどこから。 2010年コスタリカ議会は、米国海軍駐留を認める議決を行っております。米軍は自由にコスタリカ領内を移動し、必要とあればドンパチやって良いとのお墨付きを、コスタリカ政府は米軍に与えているのであります。 はい、「何の恥ずかしげもなし」でOK(えっ、本当に)。 あぁ、やっぱりコスタリカの主権は“どうなっているのかなぁ”。 コスタリカって“非武装中立”の“スバラシイ”理想国家だそうです。“スバラシイ”九条支持者の皆様が仰っておられましたから間違いなし。 その“スバラシさ”が少し理解できました(笑)。 あぁ、コスタリカって超“沖縄”なんだろうな。 あれ?“沖縄”“沖縄”と騒いでいる人たちが「コスタリカは理想国家だぁ」って言っていいのかな? (なお、どんなにスッゴイ兵器を保有していても「警察」「警備隊」と名前がつけば「軍隊」ではないので、コスタリカは“非武装”です。ははは) 最後に、重大な極秘情報を。 「ネイビーシールズはCanon製のカメラで敵地を撮影している」 やはり日本製。
2012年06月23日
コメント(0)
-
マイケル・スーシー監督『君への誓い』を観た
「恋愛」より「記憶とアイデンティティ」の方が興味深いのに 記憶喪失物のラブストーリーです。 新婚の奥さんが自己で記憶喪失に。過去の記憶はあるのですが、旦那さんと知り合って以降の記憶がさっぱり。実家に戻りたがる彼女、元の彼氏の出現。果たして二人は再び結びつくのでしょうか(実話に基づいているらしい)。 正直言って無茶苦茶多いですよね、記憶喪失物、日米共に。 何なんでしょうか。「記憶喪失出せば安全パイ」なる諺が映画界にはあるのか。しかもプロットまで似たような(大抵恋愛物)。 後は描写のテクニックの優劣ぐらいか。 本作品は恋愛物の“甘さ”に重点を置いていて、私の口には少々合いませんでした。ドリュー・バリモアの『50回目のファースト・キス』の方が良かったですね(悲劇なんだけど、バカっぽいユーモアがあって、そこが好き)。 あるいは渡辺謙主演の『明日の記憶』。こちらは若年性アルツハイマー病で記憶がどんどん消滅していく話ですが、この話の夫婦愛の方が胸に迫ります。 ドキュメンタリータッチで淡々と描写するか、悲劇をユーモアで包んで描写するか。甘い恋愛物に仕上げちゃうとどっちつかずになるというか。 そもそも「記憶とアイデンティティ」というテーマが充分に興味深いものと思います。もったいない。 この映画では偶然にも旦那さんと知り合って以降の記憶のみ消滅した訳ですが、もし仮に、もっと以前からの記憶が消滅したら、果たしてどうなるか。 言うまでもなく、恋愛感情とは、その人の人格に対しての感情の筈ですが、では、人格と記憶の関係は。自伝的記憶が消えてもそれによって形成されていた人格は変わらないのか、変わるのか。 更に言えば。 どの記憶喪失物物映画でも、記憶を何か脳内にある“物体”のように、取り扱っていますが、どうも記憶とはそのようなもの(正確には“事”)ではないようです。自伝的記憶は現在の自分が再構成した“事”なのです。 米国の心理学者エリザベス・ロフタスが行った興味深い「ショッピングモールの迷子」の記憶実験がありますね。被験者に「家族から聞いた子供時代の真実のエピソード」3つと「ショッピングモールで迷子になったというフィクション」1つを混ぜて話し、どう“思い出すか”という実験。 すると被験者の約25%は、「ショッピングモールで迷子になった」記憶をありありと詳細に“思い出しちゃった”そうです(「あれは嘘」って実験後教えると、その人たち「えぇ!」と驚いたらしい。そりゃ驚いたろうな。それにしても、この25%というのは、多いと見るべきなのか、少ないと見るべきなのか)。 さらに、他の実験の例。「小さい頃ピクルスが嫌いだった」という偽の記憶を“思い出しちゃった”被験者が、パーティー会場で、ピクルスに手を伸ばさなくなるという実験。つまりその記憶が正しかろうと間違いだろうと、その後の人の行動を左右しちゃうんですね。 よくサスペンス物で、偽の記憶を悪の組織に植えつけられちゃう主人公、なんていうのが出てきますが、そういう話以前に、そもそも記憶とはそういう“事”であるようです。 ならば、恋愛感情だって・・・。 永続的、固定的な実体を持った自我など存在しない。恋愛だって相手と自分に実体的な自我があると考える無明から起る執着。 羯諦羯諦、波羅羯諦、波羅僧羯諦、菩提薩婆訶.....(^人^)。 過去、自分がどういう人間で、その人とどういう関係であったか、ではなく、どういう人間を目指すのか、その人とどういう関係を築きたいのか、という事なんでしょうね。 記憶喪失の主人公が、悟っちゃって過去の自分探しをやめちゃうというような映画が出来てないかな。タイ辺りでどうでしょうか。
2012年06月01日
コメント(0)
-
キャメロン・クロウ監督『幸せへのキセキ』を観た
ウェットなアメリカ映画。家を買ったら突然ムツゴロウ。 半年前に最愛の妻を亡くした主人公が二人の子供と共に、過去を振り払うべく引越しを計るのだが、新居に入居する条件は、おんぼろ動物園を引き継ぐ事だった。 実話に基づいているとの事。主演はマット・デイモン。 そもそも「家に動物園が付いている」っていう時点で、敷地面積としてなんですが、ハイ、舞台は“アメリカ”です。クローゼットが六畳ぐらいあったりする国です。極普通の事です(ウソ。なお実際は英国での話です)。 筋は大体想像がつくでしょうね。紆余曲折の挙句、見事動物園を復活させ、新しい人間関係の中で、主人公家族が妻(母)の死を受け入れられるようになるというもの。 予定調和じゃないかと言えば、そうですが、実話だから仕方がないと言うべきか(実際は奥さんが亡くなる前に動物園購入を決意)。 アメリカ映画としては随分“ウエット”な作りです(「ウェット」なる日本語、訳しづらいですね(笑)でもこの場合ぴったり)。感傷的と言ってもいいです。 主人公が亡くなった奥さんの写真をじっと眺めて目を潤ませたりしていると、一寸私には辛いです。表現がストレート過ぎます。 深刻なテーマでも、笑いのうちに描写する、というのがハリウッド映画の美点だと私は思うのですが、残念ながら、本作品はユーモア控えめ。日本映画の作りに近い作品になっています。テンポも日本映画に近いですね。 脚本は『プラダを着た悪魔』のアライン・ブロッシュ・マッケンナとの事(「エッー」という感じ。全然感じが違うじゃない)。 近年の山田洋次監督作品なんかが好きな人であれば、向いているかも知れません(私の趣味ではない)。 アメリカに秘かに流れる“ウエット陰流”の発露といった感じです。 もっとも正確に言えば、こういう側面を所謂“国際人”が知らない、若しくは語りたがらないだけで、「秘か」でもなんでもないんだけどね(他にもよくいるじゃない、「アメリカ人は合理的で、日本人は感情的」とか未だに言っている奴。アメリカ人自身がそんな事言っている例が一例でもあるのか)。 例えばカントリーミュージックなんかの歌詞をみると、まるっきり演歌なんですよね。「おぉ、別れた妻よ、恋人よ~。もう一度会いたいよ~。泣く」みたいな(笑)。ウエット、感傷的。(どっちも長距離トラックの運転手さん御愛用という点も同じだね) 一番大きいのは個人差。次にその人物が属している“階級”差。さらにその次に所謂“国民性”“民族差”(この「民族」なる概念、相当疑ったほうが良いです。実体概念じゃないですよ。デオキシリボ核酸と無関係)。 というわけで、こういうストレートに“ウエット”な映画が好きな人が日米両国とも一定数いるんだろうな、という話。 ただ、“陳腐さ”という“悪癖”は各国、各民族で差異に富んでいるようです(陳腐なのは映画ではなく、私の予想ね。念の為)。 中で老衰した虎をどうするかというエピソードがあるのですが、これが肩透かしを喰らいました。 主人公は虎をなんとか無理やりにでも生かそうとするのですが、動物園スタッフと揉めます。 で、平均的日本人なら話の展開をこう想像するでしょう。 「なるほど、虎の死をきっかけに、どんな生にも終わりがある事を悟り、それが奥さんの死を受け入れる事に繋がるんだな。」(陳腐だけどね) そうなりません(笑)。なんかやられたって感じ(笑)。「虎の死」と「奥さんの死」をリンクさせないの。 テーマが「死」だけに、宗教的なバックボーンの問題なのでしょうね。あの人たちはキリスト教を始めとするセム族系宗教が主流派で、こっちは仏教系。意識しなくても自然と仏教的死生観が身についている。身についているが故の“陳腐さ”、をあらためて実感(たぶんタイ人やチベット人の映画好きも同じ筋展開を予想する筈)。 セム族系宗教的には「我々人間は神より動物の管理を託された存在」という事なんでしょうね(例えば南極のタロとジロ。ああした場合、欧米人だと躊躇無く殺しちゃうらしいですね。苦しませずに楽にしてやるべきだと)。 文化の“差異”というのは、“陳腐さ”の中に姿を現すのでしょう。 幼い娘役の子役マギー・エリザベス・ジョーンズが上手い。こましゃくれていて可愛い。 ↑原作本。大昔テレビで『ムツゴロウの結婚記』というのを観たが、あれは明るかったなぁ。同じ動物ワサワサでも、これから結婚するのと奥さん亡くなっちゃうのとでは正反対。今は凡作でも良いから明るい映画が観たいです。
2012年05月24日
コメント(0)
-
ピーター・バーグ監督『バトルシップ』を観た
実は米国人も結構気にしているんでは。 楽しめました。良く出来ている方だと思います。ユニバーサル映画100周年記念作品。 単純な娯楽映画です。一部韓国人が「ケシカラン映画だ」と問題視していたやに聞いていましたが、単に日本国旗が画面に多く登場するという、そんな理由なのでしょう。別に深い意味はないですね。 ハワイ沖で世界各国の海軍が合同演習中にエイリアン出現。米国海軍軍人の主人公と日本の自衛隊員が協力してエイリアンと戦うというもの。ま、ありがちな話です(「エイリアンもので海軍」というのが珍しいか)。文芸作品じゃないから筋は単純な方が良いのです。 相棒の日本護衛艦艦長を浅野忠信氏が好演。準主役級。割と好きな俳優さんなので満足。 ストーリーは、結構勘所を押さえたエピソードを上手く使っているといった感じです。 例えば相棒が日本海軍(自衛隊)というのは、太平洋戦争の「あぁ、恩讐を越えて」という事なのでしょうし、米国にしては珍しく老人集団がカッコ良く登場し、最後を戦艦ミズーリ(太平洋戦争時の日本の降伏調印式場ね)で締めるというのも上手い。 ただ、あくまで単純娯楽映画路線なので、そう深く掘り下げる事(所謂「涙腺を刺激する感動」という奴)なく、さらっと話が流れて行きます。 こういう映画は単純娯楽作品だからこそ、平均的米国人の自己像が今どうなっているか、知る資料になると思うんですね(インテリさん向け文芸作品を観たって参考にはならない。国民差、民族差より階級差の方が一般に大きい)。 (反米馬鹿の想定する「米国人自己像」の認識と逆に)米国の一般大衆って結構判って来ているんじゃないでしょうか。 自分達が未熟なアホのくせに、やたらリーダーぶって指導したがり、挙句の果てに大勢の人の命を犠牲にする、すごく迷惑な奴。こういう自己像。 実際、この映画の主人公が途中まで当にそれなんですよね(だから、若者の成長譚であると同時に、米国の“成長譚”でもあると思うのだ)。 で、今回の相棒役の日本の立場は、浅野忠信演じるナガタ艦長の次の台詞に集約されてます。 (感情的にイケイケ突撃をする主人公の艦を見て)「あのアホ!!おい、あいつを援護するぞ」。 あ~、日本人言いそうだわ。 (ハリウッド映画で米国人主人公がリーダーを外国人に譲るのって初めて見た。また日本人が指揮しちゃうというのも。これが欧州人だと米国一般大衆の拒絶反応は強いと思います。日本人だと無難) これ、米国人脚本家が米国の一般大衆にウケルように、筋や台詞を考えている訳で、という事は、米国一般大衆の自己像(及び日本を始めとする対外国像)にそういう側面、少なくとも“下地”はあるという事になるでしょう(まるっきり無かったら観客は拒絶反応のみ)。 結構、善い奴じゃない、米国人。かわいいじゃない(笑)。こういう所は欧州人には無いわな。気にしてるんだ。 某国や某某国の国民より数段マシだよな。 翻って、我が国マスコミの「米国像」を見ると・・・・。 アンフェアな気がします。 そういえば、今回襲来してくるエイリアン、それなりに紳士的(?)な奴なの。一応、無抵抗の人間は襲わない。 そこが、一寸笑える気がします。人類を頭っから無視するエイリアン。眼中に無し(笑)。あの態度はないよな。人類のプライドが傷つくよ。このエイリアン侵略者像は新しいかも(生身の人類は無視して戦艦戦車等機械のみに攻撃をかける、という合理性追及からの帰結なんでしょうけどね) やたら凶暴ではない、このエイリアン像も脚本家の気配りなんでしょうか。 エイリアンの攻撃艦の武器がレザー等ではなくて、変なピン状の砲弾でした。なんであんな変な武器なんだ。 という疑問はパンフを買って氷解。これは玩具メーカーとのタイアップ映画なんでした。懐かしの「ニューレーダー作戦ゲーム」。 だから、思いっきり「ピン」なんでした。これには爆笑。思いっきりベタ。 なお、ついでにパンフに拠ると、主役のテイラー・キッチュ氏は結構善い人みたい。アフリカの子供達のドキュメンタリーを撮ったそうです。 「実はホームレスだった頃の僕にベッドを貸してくれたのもピーター・バーグ監督だったんだ」「(ブリトー窃盗のシーン)僕が実際に警察に追いかけられた経験は活きているかもね」おいおい、何やっていたんだ(笑)ブリトーは盗んでいないとの事ですが。 我が家ルールでは、戦艦の上に戦艦、その上に更に戦艦を乗っけて配置するのもアリでした。
2012年05月05日
コメント(0)
-
エドワード・ゴーリー『題のない本』を読んだ
二度と読みたくないのに、何度も読んでしまう絵本。ユーモラスとグロテスクは表裏一体。 30頁程の大変短い絵本です。そしてユーモラスであると同時に不気味な本です。 作者エドワード・ゴーリーは有名な“大人の為の絵本”を数多く出している作家で、世界中に多くのファンが存在しています。 どの作品も、大変きめ細かい線で描かれたモノクローム線画で、登場する人物(生き物?)は皆とぼけたような造形。 そして、大抵は不気味。筋もしばしば不条理で残酷であったりします。 (「この“味わい”は間違いなく英国人」と思ったら、米国人でした) 実は私、この人の本を読むの、イヤなんですよね(笑)。気持ち悪いんですよ。何回読んでも気持ち悪い。 話の不気味さ、不条理さ、“非(「反」ではない)”道徳的展開はそれ程でもないのですが、絵がなんとも言えず、薄気味悪いやら気持ち悪いやら。 どこがどうと言えない薄気味の悪さ(「どこがどうと言えない」事自体がもう既に気持ち悪い)。 世の中には不気味な絵が多く存在しますが、そういった絵の「気持ち悪さ」とは違います。それらは恐怖や嫌悪感を意図して描かれている訳で、意図がある以上造形的に計算されていて、そういう意味では実は気持ち悪く“ない”。 この人の絵は違います。そういう「不気味さ志向、キンキー趣味(大抵は「肥大化した自意識」ちゃんの作品)」の意図が感じられない。寧ろ進んでユーモラスに描こうとしている。精魂を込めてユーモラスに、ニコニコと。 でも、薄気味悪い。 これ東洋人には出せない味わいの絵じゃないでしょうか。 何百年も前からある古びた石造りの館の、碌に日が射さない黴臭い部屋で、その館の主人から愛想良く勧められた紅茶。砂糖が入っているので甘いのですが、なにかくすんだ様な、変な味がする紅茶。そんな絵。 表面には出ていない所で、間違いなく、何か“発酵”しています。 発酵していて、時々表面に小さな泡がぷくり、ぷくりと...。 なんともイヤな感じです。 イヤなんですが...。 読んじゃう。読んでしまう(笑)。何回も読み直してしまう。 そして読み直す度に、「あぁ、この人の絵はやっぱりイヤだ、あぁ、やっぱり気持ちが悪い」と、再確認、再々確認。 くさやの干物とか納豆のような“魅力”なのでしょうか。 本作品に筋らしい筋はありません。不条理な世界で、ネタバレも何も無いだろうから書きます。 全頁、画面は全て固定された風景。庭木、茂みの描かれた庭に、右手、煉瓦造りの壁と窓。窓には子供らしき人物(一寸、吉田戦車の描く極端に簡素化された人物像に似ている)。 そして下に意味のない、呪文のような囃し言葉のような出鱈目アルファベット。 1頁進む毎に、この庭に生物らしき物が一匹ずつ登場していきます。 最初に蟻(?)が登場。子供の体ほどもあります。 手足を広げてポンッと飛び出したような姿。ユーモラスです。 でも、気持ちが悪いの。本物の蟻に比べ明らかに手足が長過ぎます。これが気持ち悪い。手足のバランスが気持ち悪い。そのバランスの悪い手足が絡んで描かれていて気持ち悪い。 次に蛙。 これも気持ち悪いの。本物に比べ妙に長細い身体つき。それがイヤなの。腹が白い所は本物と同じなんだけど、それも気持ち悪い。 その次に何だか判らない生き物。 蜥蜴の様だけど、菱形模様なの。その模様も気持ち悪いし、頭がバランス悪く大きいのも、目が点でしかないのも、皆、気持ち悪いの。 以下、よく訳の判らない生物状の“何か”が茂みから、地面から、上空から、登場していきます。 登場して何かしています。踊っているのでしょうか、組体操をしているのでしょうか。判りません。 判らなくて、これまた気持ち悪いです。 そして、その怪風景を見て手を叩いて喜ぶ子供(?)。 無表情で喜んで(?)います。 と、突然、上空を隕石の様に、生首(?)が通過。 怪生物達は、あわてて一匹、又一匹と姿を消していきます。 終わり(?)。 全編ユーモラスである分、逆に気持ちが悪いです。 「ユーモラス」と「グロテスク」、「笑い」と「恐怖」。 呼び方が違うだけで、本質は同じ物なんじゃないでしょうか。 うなされそうです。 助けてください。
2012年04月23日
コメント(0)
-
本木克英監督『おかえり、はやぶさ』を観た
三作品中、これが一番快活。懐かしさにじんわり。はやぶさ≒忠臣蔵 結局、「はやぶさ」三作品を全て見てしまいました(笑)。同じ題材で、三作品が同時期に制作、上映。こういうケースは今までもなかっただろうし、これからもないと思います。各作品、細かいエピソードなどの取り上げ方も含めて、相違点、共通点があり、「はやぶさ」という題材を離れても、なかなか興味深かったですね。 さて、しんがりを務めた本作品、3D作品で、三作品中、一番“明朗”な作品となっています。明白に家族向け。(監督は『釣りバカ日誌』を撮った人らしい。納得)制作者は特に科学少年、少女に見て欲しいと願っているのでしょう。オフィシャルサイトなんかも見ると一目瞭然です(ただ、“軽い”とも言えるんだよね)。これは主演を渡辺謙氏が務めた瀧本智行監督作品『はやぶさ 遥かなる帰還』と対照的。 科学少年少女向けという事で、その為、はやぶさの軌道や起死回生の姿勢制御の方法等、アニメを使って解り易く解説され、一寸した科学教育映画の要素もありました。他の二作品にはない特徴です。3Dである点も判り易さに貢献していたんじゃないでしょうか。 で、それを見ているうちに懐かしさが、じんわり。 あったよなぁ~、こういうの。子供の為の科学教育用の本やテレビ番組。今は妙にタレントなんか出して子供の興味を無理やり引き付けようとするんだけど、昔はシンプルに科学自体の面白さだけで説明してたんだよね。 特に思い出深いのはプラネタリウム。ドームの周りのホールに様々な展示物や写真が飾られていたっけ。そうだ、ボタンを押すと太陽の周りを惑星が回りだす装置があったなぁ。あれと全く同じ絵柄(そりゃ同じに決まってます)。 私が始終通っていたプラネタリウムは取り壊されてしまいました・・・。しみじみ。 という訳で、「子供はわくわく、お父さんはしみじみ」という作品なんじゃないでしょうか。 (ただ、もう少し“ぶっきらぼう”な説明スタイルの方が、逆に良かったんじゃないですかね。科学少年、少女って「子供向き」より逆に「大人向き」の方が喜ぶものです) しかし、これは映画本来の出来不出来とは関係ないですね。 どうも「はやぶさ」映画というものは、「映画」という事だけでは括れないレゾンデートルがあるようです。 純粋“平和”利用の衛星技術だったり、金銭的にはビンボーだったり、精神性を帯びているとさえいえる技術への情熱だったり、日本人の心の琴線に触れる要素が多々ありますね。 国民的“物語”。言ってみれば“「はやぶさ」忠臣蔵”(そういえば忠臣蔵に「はやぶさ」は似ている(笑)。艱難辛苦の挙句、目的を達するが、結局は切腹しちゃうのだ) 閑話休題。 家族向けを狙った為、プロットも縦糸にはやぶさ計画、横糸に二家族の情愛と葛藤を描いています。 ただ横糸の方、二つも家族は要らなかったんじゃないかな。「はやぶさ」に携わる主人公と失敗した「のぞみ」に携わっていた彼の父親との葛藤と和解に焦点を絞った方が良かったんじゃないでしょうか。入院する母親とその子供というのは少し陳腐。 音楽は誰でもわかる冨田勲。ありがちな選択ですが、やはり画面と合っていて、三作品中ではこれがBEST。 今回はリポビタンDの出番なし(笑)。川口淳一郎教授の神頼みシーンもなかったですね。 代わりに、「はやぶさ」の名前の由来が説明されていました。鳥の隼が獲物を取って巣に帰る行為に因んだのだそうです(この説明は合っているのか。てっきり、日本ロケット工学の父、糸川博士が設計した戦闘機「隼」から来ているとばかり思っていたが)。 他の二作品と違い、理学系と工学系の対立なんかも触れられていました。ここの所に興味を惹かれましたが、あまり深く掘り下げてくれず残念(一口に「科学技術」と言いますが、「科学」と「技術」の関係って歴史的に面白かったりするんです)。 ただ三作品とも見事に共通するのは「ビンボー」。本作品では直接的な描写こそありませんでしたが、繰り返し台詞(「予算はNASAの十分の一」)で語られていました。 ラストに「一番じゃなきゃダメなんです」と民主党の蓮舫議員への当て擦り(笑)も。皆さん、忘れかけていたのにね。 しかし、皮肉なものです。本映画でも大杉漣氏演じる川口淳一郎教授が「結果を出さなければ予算が下りない。結果を出さなければ意味がない」と力説していましたが、当に「結果を出した」からこそ、「このような事が二度とあってはならない」と民主党は「はやぶさ2」を叩き潰しにかかった訳ですし、マスコミもこの動きを「報道しない自由」で全力で隠蔽している訳です。 失敗したら予算がつかず、成功しても予算が下りない。 (「はやぶさ」プロジェクトサイト) http://www.hayabusa.isas.jaxa.jp/j/ 川口淳一郎教授の声明。予算削減への抗議と皆様への支持のお願い。 自由民主党も日本共産党も党員となるには日本国籍である事が条件ですが、民主党は違います(というより世界中探して民主党のような党則の政党が他にあるのか)。つまり現在の民主党代表(つまり首相)は外国人の方々の投票によって“も”決められている訳です(日本人の圧倒的大多数には代表を決める権限はない)。また多くの民主党閣僚が外国人“な”方々から多額の献金を貰っている事は皆さん御存知の通り。 民主党、ポンと韓国様に5兆円!もの通貨スワップ。 しかし、「はやぶさ2」の予算は必要予算の半分以下。 この“民主党と偉大な隣国人たち”からの“御命令”は果たして、地球人類の科学技術史に如何なる意味を残すのか(実際、劣悪な条件であったが故に特殊な科学技術が発達するという可能性もある訳です。科学技術史は奇妙な流れをしばしば見せます)。 P.K.ファイヤアーベント『方法への挑戦』(分厚いが面白い) 三作品全てを見た(笑)結論。 堤幸彦監督の『はやぶさ/HAYABUSA』が一番良かったんではないでしょうか。 音楽はこれがBEST。
2012年04月01日
コメント(0)
-
カイガラムシとダライラマ
カイガラムシ産業は有望かも。 庭木に毎年大量発生するカイガラムシを駆除する為(実は冬が駆除時期だったりする)、参考資料として伊澤宏毅著『カイガラムシ』を読んだところ、一寸面白い記載があった。 (p47)「塗料で『ラッカー』という言葉を聞いた事があると思う。この『ラッカー』の語源となったのがラックカイガラムシだ。ラック(Lac)とはサンスクリット語のラクシャ(Laksha、10万を意味する)に由来する。つまりそれほど多くのムシが集合するということから、この名が付いた。中国南部からインドにかけて約20種が生息し、そのうちの二種類が産業的には利用されている。雌が集団で寄生して分泌する多量の排出物(樹脂状の塊を形成)を集めて、分離精製し、シェラックと呼ばれる樹脂とラックダイという染料を取り出すのである。中国ではすでに紀元前2000年頃から使われ、漢方薬としても用いられた。染料としてはその後インドでも使われるようになり、今でもインドからタイ、チベットの山岳地帯にかけて住む諸民族が着る赤色や臙脂色の衣装の原料は、ラックダイである。」 という事はダライラマ猊下がお召しになっている臙脂色の法衣も、カイガラムシで染め上げた物なのだろうか。 「XXと言う食品の赤い色はムシから作られている」なぞと良く言われる豆知識(怪知識)の元は、このムシ由来のラック色素の事か、またはサボテンに付くコチニールカイガラムシ由来のコチニール色素の事。 コチニール色素は古くアステカ文明でも使用されていたと、この本の記述に記載されていた(現在では、ハム、ソーセージやケチャップ、洋酒、キャンディーと色々使われているらしい)。 ラックダイは2000年も前から人の口に入っていた物だから、人工着色料よりは余程安全だろう(無論、取り過ぎれば何だって毒だが)。 そういえば、家の庭木に大量発生するカイガラムシを駆除する際、カイガラムシの赤っぽい体液が服について困る事がある(基本的に農薬は使わず、手で掻き落としています)。あれで手染めなぞ出来るのであろうか(出来ても私は着ませんが)。 なおラックダイは精密機器の防錆剤、電気絶縁材、医薬品や食品のコーティング剤としても利用されており、一方、シェラックは、天然樹脂で唯一熱硬化性をもち、耐油性、電気絶縁性、無毒性に優れた特性を持っている為、石油系樹脂に代わる、環境に配慮した素材として注目されているとの事。 カイガラムシが明日の地球環境を担っちゃってるようだ。 ところで、インドやタイではどうやって生産しているのであろうか。カイガラムシ養殖場(?)。枝にびっしりとカイガラムシ(想像してしまった)。 会津の高級和蝋燭(煤が出ないのだ)の原料はイボタロウムシの分泌物。このムシもカイガラムシだ。この本によると、このイボタロウムシの分泌物は最近、高級化粧品の材料や、チョコレート等の食品のコーティング剤としても利用されているらしい。 我々はカイガラムシ由来成分を結構口にしているようである。 なお、欧米には、日本のように「カイガラムシ」と総称する表現はないと出ていた。分類によってそれぞれ違う呼び名で呼んでいるらしい。例えばコナカイガラムシ類(白い粉を吹いているような奴)はmealybugミーリーバグ、マルカイガラムシ類(硬くて丸い奴)はscale insectスケールインセクト、カタカイガラムシ類(蝋が固まったような奴)はsoft insectソフトインセクトといった次第。 何処かで使う機会が...無いな。素人にはカイガラムシの同定の段階で難しい。この本、カイガラムシの一覧と写真が欲しい。
2012年03月06日
コメント(0)
-
滝本智行監督『はやぶさ 遥かなる帰還』を観た
民主党の予算半減により2号機は。川口教授憤激。当然マスコミ取り上げず。 20世紀フォックス、堤幸彦監督の『はやぶさ/HAYABUSA』に続き、また、はやぶさ映画を観ちゃいました。当然、ストーリー(と言うより実話なんだが)は同じ。我ながら、好きですね「はやぶさ」。 こちらの方は川口淳一郎教授を演じる渡辺謙氏が主役の映画。比較してみるに、こちらの滝本智行監督版の方が、シリアスな演出(堤幸彦監督版の方はなにしろ『トリック』の監督さんによる物だから。両者比較すると堤監督版の軽やかさが改めて感じられます)。 言ってみれば堤監督版は青年、家族向き、こちら滝本監督版の方は中高年向きでしょうか。 実際、堤監督版に比べ、役者に対する観客の感情移入度は意図的に低くなるように描かれていると思います。その分観客は俯瞰的に人物群像の動きを見る事が可能になっている訳です。堤監督版と違って、うるっと来るシーンは意図的に回避。ラストのはやぶさに地球の写真を撮らせるシークエンスもさらりと描いています(これは暗に、仕事帰りの疲れた状態だと、睡魔が、という可能性がありますという・・・。あ、別に悪くはないですよ) ただ、若干、そのシリアスさの重みが、話の展開のスムーズさに響いてしまったか、という気がしますね。 我々ははやぶさの話を知っているので全く問題ないのですが、事情を知らない外国人や後世の子供達に見せるのなら、先ず堤監督版の『はやぶさ/HAYABUSA』を見せた方が良いでしょう。こちらの方が事件の流れが追い易いと思います。打ち上げ以前の事情なんかも触れていましたし。 ただ、どちらの『はやぶさ』も、日本の科学技術開発現場の財政的貧しさを強烈に告発しています。 日本は実はビンボーな国なのですね。 さてこちらの方では、川口淳一郎教授率いるJAXAスタッフだけでなく、もう一人の人物にも焦点が合わさります。名優山崎努演じる、町工場の職人気質の親父、はやぶさの部品を製造した人物です。 実は山崎努氏の演技がこの映画の味わいを決定付けているんじゃないでしょうか。この人がいなかったら他のはやぶさ二作品とに、味わいの違いを出せなかったと感じました。 山崎努氏の演技は過剰な情緒的演技から距離を置いています。べた付いてないんですね。特に、はやぶさが危機的な情況にある中、川口淳一郎教授がこの人物と会偶するシークエンス、この名優二人の演技がちょっと良かったですよ。 主役渡辺謙の演じる川口淳一郎教授の人物像もしっかり描かれています(この辺は堤監督版に比べ上手)。(現実の川口教授がどういう人柄の方か判りませんが)少し辛辣な皮肉を言ったりする人物。狷介な所もありそうな、喰えない複雑な面を持ち合わせています。こうした困難なプロジェクトを成功させる指導者は単純な理想主義者では無理という少し大人の味わい。 余計な、というより「嘘つけ」と言いたい人物も登場。朝日と思われる新聞社の科学面担当女性記者(狂言回し役)。テレ朝日と朝日新聞がこの映画に噛んでいるので、こうした人物が出てきます。 関連して「あれ?マスコミがそんなに注目してましたっけ」と言いたい。記者会見室は毎回満席で、熱気溢れる各テレビ局新聞社の取材があったかのような演出。恰もマスコミが最大の関心を払っていたかのように印象付けています。 この点では堤監督版の方が作為がなく正直。あちらは空席がチラホラありました。 皆さん思い出してくださいね。「はやぶさの帰還」、見事にどのテレビ局も無視していましたね。一社のテレビ局も中継しなかったのです。多くの天文ファンがテレビ局に中継の要望を出したにもかかわらずに、です。そして帰還後、鳥越俊太郎を初めとするテレビコメンテーターの冷笑的コメント(「そんな遠くに行って、地球の砂と同じだったらどうするんだろうね、フン」)。 “ニポンマスコミ”は不愉快で仕方がなかったんでしょう。何とか国民の目から隠したがった。「報道しない自由」です(無論、人類史的快挙を隠すのは無理に決まっていますが)。 掌返しで、マスコミは昔からはやぶさの応援をしてきたかのような印象操作を行っていますが、騙されちゃいけません。 現在もはやぶさに関して、日本のマスコミはニヤニヤしながら「報道しない自由」を満喫中です。 民主党により、はやぶさ2の予算は半減。まともな結果を出すなど絶望的な情況です。 川口淳一郎教授はJAXAドメインのブログで今回の予算削減の報道に触れ、民主党政府の「はやぶさ2計画に科学的な意義を見いだせない」という意見に対し、「まことに信じがたい」と憤激していらっしゃいました。 私も激怒しています。民主党は頭がオカシイのか、日本に対する“邪悪な意思”があるのか(それとも両方か)。 そして、あれほど掌返しで「はやぶさ、はやぶさ」と騒いで見せたマスコミは、不思議な事に--というより当然の事に--この件に関して「報道しない自由」行使、全く報じません(朝から晩まで韓流が流されている事と何か関係があるのかな(嘲)。 日本の抱える諸問題の多くは、こうした情報の“歪み”が正されれば、解決か、さもなくば大きく進展する筈です。 第四の権力者サマ“ニポンマスコミ”、諸悪の根源。 なんか、本題から離れた話になっちゃいましたね。 はやぶさに“帰還して”。 以前、堤監督版『はやぶさ/HAYABUSA』の観想で、「頻発する栄養ドリンクのショットは何」と書きましたが、大正製薬を初め、関係者の皆さん、済みませんでした。リポビタンDは、はやぶさファン公式(?)飲料と呼ばれる程、馴染みの深い栄養ドリンクなのだそうです。大正製薬の方が態々JAXAに寄贈したんですって(大正製薬のHPにも載せれば良いのにねぇ)。 これから、リポビタンDを贔屓しようかな。 ファイト、一ッ発ァッ~ツ\(`O´”)そういえば「鷲のマーク」だった。同じタカ目ね。
2012年02月12日
コメント(0)
全757件 (757件中 1-50件目)