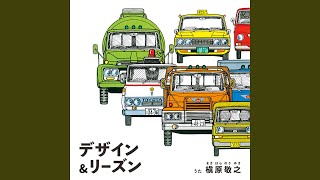2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2010年05月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-

第213回 中国の4月の経済統計
今日のまとめ 4月の経済統計はインフレ懸念を払しょく出来なかった 工業部門に陰りが見え始めている 成長を犠牲にせずに不動産価格をコントロールするのはムリ 更なる金融引締めの必要性を感じさせる4月の経済統計 中国の4月の経済統計が出揃いました。結論から言えば更なる金融引締めの必要性を感じさせる内容でした。 中でも4月の都市部の不動産価格が統計開始以来最大の+12.8%上昇し、3月の+11.7%を上回ったことは市場参加者をがっかりさせました。 物価 4月の消費者物価指数も市場予想を上回る+2.8%、同じく生産者物価指数も予想より高い+6.8%でした。 銀行融資 4月の銀行融資は7740億人民元で前年同期比+30%近い数字でした。人民銀行は単月ベースでは銀行融資を管理していませんが、まだブレーキをか ける必要のある数字だと言えます。 小売り売上高 4月の小売り売上高の数字は+18.5%で予想より若干強かったです。 鉱工業生産 4月の鉱工業生産は+17.8%と市場予想を下回りました。グラフからもわかるように頭打ちの傾向が明確になってきつつあります。 まとめると不動産価格は相変わらず急騰しており中国政府は金融引締めを継続する必要があります。その一方で昨日のレポートの中でも説明しましたが輸 入のペースは鈍化しており、また上に述べたように鉱工業生産にも伸び悩みが顕著になっています。 つまり或る程度成長を犠牲にせずに不動産価格をコントロールすることはもはやムリにな りつつあると考えるのが自然なのです。
2010年05月12日
-

第212回 中国の4月の貿易統計
今日のまとめ4月の貿易統計は無難な数字だった貿易黒字幅が恒常的に狭まるかに注目欧州向け輸出は今のところ好調だが、今後の変化に注意輸入のモメンタムが今後落ちるようだと再び下降サイクル入りも4月の貿易統計中国の4月の貿易統計が発表されています。輸出は1199億ドル、輸入は1182億ドルでした。貿易収支は再び黒字となり、16.8億ドルを記録しました。3月の貿易収支が過去6年で最初の赤字となり-72.4億ドルを記録した後ですので4月の数字の黒字への復帰は正直なところ中国ウォッチャーを安堵させています。上のグラフからも読み取れる事ですが以前は中国の輸出は輸入を軽々上回り、貿易黒字が定着していました。しかし最近では2つの線が重なってきています。まだ2カ月程度ではこれを新しいトレンドだという風に判断するのは早計だと思いますが、再び昔のような輸出が大幅に輸入を上回る構図に戻るかどうか、たいへん興味深い局面にさしかかってきていると言えます。先月のレポートで輸入が先行し、タイムラグを伴って輸出が回復する仕組みを説明しましたが、4月も基本的にはそのパターンを踏襲して輸出の伸びが輸入の伸びに追いついてきている様子が下のグラフからも読み取れます。このように過去数カ月を見る限りでは中国の貿易不均衡は改善したかのように見えます。これは人民元切り上げの政治的なプレッシャーが弱まることを意味します。このところ欧州ではPIIGS(ポルトガル、アイルランド、イタリア、スペイン、ギリシャの略)問題などの影響で景気の先行きが懸念されています。しかし貿易統計を見る限りでは1~4月のユーロ圏への輸出は前年同期比で30%成長しており、これはアメリカ向け輸出より早い拡大ペースです。今後も欧州向け輸出の成長ペースが維持できるかどうかに注目したいと思います。最後に前年同期比で見た輸入の伸び率が再び鈍化しているように上のグラフからは読み取れるのですが、これが再び中国の経済活動が下降サイクルへ入っていこうとしている前兆なのかどうかにも注意を払いたいと思います。
2010年05月11日
-

第211回 中国の工業セクターは鈍化しているのか?
今日のまとめ中国購買担当者指数は弱かった豪政府の資源超過利潤税導入は懸念材料中国の金融引締めは続く先行指標の役目を果たす株価は冴えない購買担当者指数日本がゴールデン・ウィークでお休みになっている間に海外市場では「中国の工業セクターが鈍化してきているのではないか?」という事が言われはじめました。これにはいくつかの理由付けがありますが、そのひとつが先日発表された香港上海銀行の出している中国購買担当者指数の数字が3月から4月にかけて下落したというニュースです。中国には政府が発表する購買担当者指数というのもあり、こちらの方は3月に比べて4月は下がっていません。このように調査によって食い違いが出るひとつの理由は政府の調査が専ら大企業を対象としているのに対して香港上海銀行はもう少し小さい企業も含まれているからだと説明されています。購買担当者指数は50を超えていれば「景気は拡大している」と解釈され、今回の香港上海銀行の調べによる購買担当者指数は55.4だった為、景気が拡大していることには違いはありません。ただ拡大のペースは去年の9月以来で最も低い数字だった点が問題にされているのです。豪政府による資源超過利潤税の導入さて、これとは別にオーストラリアが新しく資源超過利潤税を導入すると発表しました。実施は2012年7月ですからまだ先の話ですが、これは鉱山会社の新規プロジェクトへの投資意欲を減退させる可能性があります。また鉱山会社にとってコスト増になった分は顧客に転嫁されることも予想され、これは中国の工業セクターにとっては悪いニュースです。鉱業コモディティの需給関係という観点からはこれは強気材料だと思うのですが、それでも商品価格が反応しなかったところを見ると市場参加者はむしろ中国の工業セクターの減速の方を心配しているのかも知れません。相変わらず続く金融引締めその一方で中国では金融引締めが続いています。5月2日には中国人民銀行が再び銀行の預金準備率(貸出する際に中央銀行に留め置かれる準備金の比率のこと)を50ベーシス・ポイント引き上げると発表しました。先行指標としての株式こうした一連のニュースを受けて中国の工業セクターにとりわけ関係の深い世界の工業・素材関連の株は最近急落しています。先ずブラジルの鉄鉱石の会社、バーレ(ティッカー:VALE)です。次に同じく鉄鉱石の会社であり、バーレのライバルであるオーストラリアのBHPビリトン(ティッカー:BHP)です。次に世界最大の鉄鋼メーカーであるアセロール・ミッタル(ティッカー:MT)の株価も下がっています。銅はいろいろな工業コモディティの中でもとりわけ中国の鉱工業セクターとの関係が深いことで知られています。その代表銘柄は米国のフリーポート・マクモラン(ティッカー:FCX)です。最後にティッシュペーパーなどの原料となるマーケット・パルプのメーカーであるブラジルのファイブリア(ティッカー:FBR)です。これらの株式はいずれも変調を感じさせる動きになっています。今後、大きな変化がでないかどうか、引き続き注目してゆきたいと思います。
2010年05月06日
全3件 (3件中 1-3件目)
1