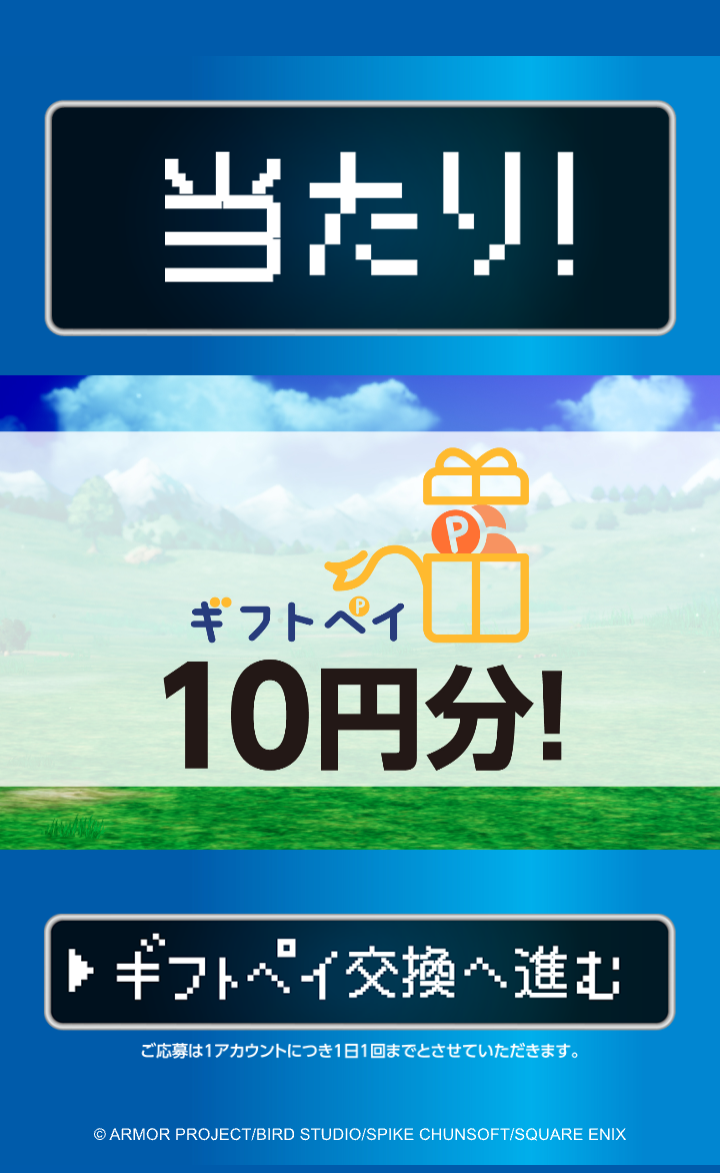2022年03月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-
最も嬉しいのは…
今週は新大学1年生が2名来塾してくれました。水海道一→茨城大学教育学部、水海道一→東京理科大理工学部。理科大の理工学部は隣町の野田にあるのですぐ近くです。正直、私も、卒塾3年後に進路が決まってようやくホッとできる、肩の荷が降りる感じなんですよ。ほんとに嬉しく思います。うちの卒塾生ではないのですが東工大に現役合格した人も岩井中→水海道一高のようです。今年の卒塾生も水海道一高へ多く進学しましたが「あたまいいわー」と感心させられることもしばしば、学力が平行移動すれば筑波大、千葉大くらいに、もし高校で伸びればさらに上位大学へ入れそうな可能性を持っています。頑張ってほしいところです。コロナでいろいろ制約されますが新生活を楽しんでください。
2022.03.31
コメント(0)
-
大学合格者数を味わう(2)興味深い早慶学部別
早大の入試も「国立受験者に易しく」、「現役生に優しく」といった方向に変化してきているようです。国立の肩慣らし及び滑り止めでかまわないのでぜひ一人でも多くの茨城県の高校生に受けてほしいと思っています。早稲田・慶應、それぞれ学部によって合格者を出している高校に違いがあるのはなかなか興味深いところです。各学部に最も多く合格者を出している高校早稲田大学政経学部 開成法学部 開成商学部 渋谷幕張文学部 女子学院教育学部 湘南社会科学部 都立青山、都立西、開成国際教養学部 頌栄女子学院文化構想学部 女子学院基幹理工学部 開成創造理工学部 開成先進理工学部 開成人間科学部 栄東スポーツ科学部 栄東女子学院というと慶應大学のイメージなのですが2つの学部で1位になっています。人間科学部では1位の栄東が26名、2位の渋谷幕張が15名、スポーツ科学部では1位の栄東が18名、2位の桐蔭学園と修猷館が8名なのでこの2学部に関しては栄東が他の追随を許しません。また教育学部で湘南、社会科学部で都立青山、都立西といった公立高校が最多合格者数を記録しています。慶應義塾大学経済学部 開成法学部 頌栄女子学院商学部 芝文学部 大宮開成理工学部 開成総合政策学部 開成環境情報学部 麻布看護医療学部 洗足学園薬学部 桜蔭医学部 開成私が受験生だった頃は湘南キャンパスができる前で、比較的入り易かったのが法学部だったように記憶しています。私が好きな巨人の高橋由伸元選手もそうですが野球部はだいたい法学部政治学科でした。いま全私立大学の中で文系では最難関なんですよね。時代は変わります。それと慶應法学部で驚くのが女子校の強さです。1位 頌栄女子学園 27名2位 女子学院 13名4位 白百合学園 10名8位 東洋英和 8名9位 雙葉 7名 フェリス女学院 7名 吉祥女子 7名これを見て法学部でなく文学部ぽいなあと感じるのもまた時代遅れなんでしょうね。全体としてみると早慶ともに女子学院と頌栄女子学院の強さが目立ちます。
2022.03.26
コメント(0)
-
大学合格者数を味わう(1) 女子の難関大合格力
私立・県立問わず進学実績は公表されるのが一般的です。しかし、男女の別について外部には明らかにされませんから女子がどのくらい頑張るのかは不明です。分かるのはせいぜい自分のお子さんが通われている高校くらいのものでしょう。そこでおおいに参考になるのが公立としては珍しく男子校・女子校制度を残している栃木県・群馬県の進学実績です。宇都宮高校(男子校)東大14、京大3、一橋大7、東工大7、東北大35。宇都宮女子校東大5、一橋大4、東北大16。栃木高校(男子校)東大2、東工大2、東北大10。栃木女子校京大2、東北大3。前橋高校(男子校)東大11、京大8、東工大3、東北大22。前橋女子東大3、京大1、東工大1、東北大8。高崎高校(男子校)東大11、京大4、一橋大2、東工大2、東北大22。高崎女子東大2、京大2、東北大7。(前橋・高崎間は10キロちょっとの距離。受験の制限はなく前橋市民が高崎の高校を受験することも高崎市民が前橋の高校を受験することも可能のよう。)各都市とも男女比はほぼ同じでしょうから、性差はあるといえばあるし、ないといえばない。それでも女子がこれだけ北関東から東大や京大別行っていることに驚かされます。何に驚かされるかというと頭の良さではなく体力なんです。難関大学の受験というのは体力的に相当にきついと思うんですよね。もしかしたら省力化する能力に長けているともいえるのかもしれません。最難関である東大理科3類(合格者97人)の出身高校も興味深いものがあります。1位 桜蔭(女)132位 灘(男) 103位 開成(男) 64位 久留米大付(男)45位 筑波大付(共) 3 駒場東邦(男) 3 栄光学園(男) 3 東海 (男) 3 ラサール (男) 3
2022.03.25
コメント(3)
-
進学校へ行く意味
早朝課外どころか朝のホームルームもなく午後は3時05分に解放されていた自分の高校時代を振り返ると、現在あちこちの学校で行われている1日8時間授業とかいったびっしりの日程に「自分ならついていけんわあ。」と慄きます。しかし、よくよく考えるとウチの塾の中学3年生も学校終了後に平日は1日1科目150分授業、土曜日は2科目230分授業だったのでそれ自体が「超ロング課外」になっていました。中学校は9教科を学ばなけばいけないので授業単位が50分なのは仕方がないのですが、自分の感覚では50分だと「何も身につけないうちに終わっちゃうな」というところです。話し合い学習をして、さらに演習までするなんて難しい。今年、卒業した3年生はどの科目についてもかなり深いところまでアクティブラーニングになっていました。太郎さんと花子さん的な人が多くてうちほど茨城県の指針に従っていたところはないと思います。高校が満足するところまで教えたいと考えたら確かに課外授業は必要なのかもしれません。昭和の時代の高校というのは「場の提供」であって「勉強はお前ら勝手にやってくれ」という感じでした。そのあたりは大きく変わったと思います。ただ進学校に行く意味というのはそう変わっていないと思います。第一に志の高い同級生や先輩に会うため。第二に優秀な先生に会うため。この二つに尽きます。大学入試は個人戦であるとともに団体戦です。一人では戦えません。東大が当たり前の首都圏私立の生徒、東北大が当たり前の東北地方公立進学校の生徒に比べると、茨城県の生徒はよくもわるくも高校進学時点での志望はぼやけているように思われます。「あいつも東大というなら自分も受けてみるか」、「あの先輩が受かったなら自分でもできるかも」という縦横のシナジー効果は軽視できません。また、旧帝以上に行くような生徒は自分が何をすべきかはわかっているはずです。高校のカリキュラムがどうこうのはほとんど関係ないでしょう。枠を嵌めるのは有害ですらあります。ですが難関大学を目指せば目指すほど悩みのレベルも高く、深い。そこで「ほんのちょっと」助けてくれる先生がいるかいないかの違いは大きいと思います。まず第一に。さまざまな高い志を持つ人と出会うため。東京の私立の場合ははじめから「東大へ行こう」という人が多いと思うのですが、地方の場合、もちろんそんな人もいる一方ではじめは特になんにも考えていない人も多く「あいつもそう言ってんなら自分も目指してみようか」とか「あの先輩が行けたのなら自分も行けるかもしれない」というのも少なくないでしょう。大学入試というのは高校入試以上に個人戦かつ団体戦なので東大、京大、国立医学部というのが変わったことではない、普通のことであるという環境に身を置くことはとてもたいせつに思います。「ほどほどでいい」と思ったら結果はほどです。2.質問できる先生に会うため。旧帝以上の生徒に無理やり学校のレールをはめる必要がないことは昨年度長期休校があったにもかかわらず大学進学実績が良かったことからも明らかです。このレベルになると自分が何をすることが必要かはわかってはいますがちょっとした悩みのレベルも高い。それにつきあってくれる先生がいるかどうかというのは大きな影響を与えるでしょう。
2022.03.19
コメント(0)
-
休校と学力
今年の中3生は休校期間が学習の重要期間と重ならなかったという点においてはラッキーだったと思います。休校となった中1の3月。数学で学習する「確率」は学習全体の流れの中では独立しています。あとからここだけ学んでもそう苦労しません。英語も2月までには重要な文法事項は学習済みでしたので教え残しは特になかったはずです。中2の4月、5月の数学も文字式の計算なので1年生の計算をしっかりと学習していた生徒にとっては学習指示だけで十分だったはずです。塾生も例年の中2生の4月、5月よりもむしろ学習速度は速く、こなした量も多かったように思います。仮に休校期間が三角形から平行四辺形へという流れの中とか1次関数とかそのあたりと重なったら日本全国の中学校で非常事態になっていたことと思われます。英語も旧の教科書だったため4月、5月はbe動詞の過去形と過去進行形、未来形でした。助動詞willも一年生のときに助動詞canを学習済みでしたから文の構造は同じです。文法練習的には単純なことの繰り返しなので休校被害は最小限に済んだといえるでしょう。「3単現」の肯定文と否定文と疑問文とか不定詞の3用法と動名詞とかだったらこちらもまた全国たいへんなことになっていたはずです。新指導要領への移行期ということで比較的コロナが鎮まっていた2年生末に受動態と現在完了まで学んでしまうこともできました。そんなわけで今年卒業した人たちは学習のヤマとなる時期と休校期間が被らず、長期間学校に行かなかったわりには学力は低くないはずです。新中3生は中学生としての学習開始時期が2ヶ月遅れました。英語は新指導要領に基づきこれまでの内容が半年前倒しされています。休校がなくとも厳しいのに。これから基礎復習できるかどうかでしょうね。数学は小学校6年間の内容をきちんと済ませ、区切りはついています。新中2は小5の終わりから小6ですよね。ここの算数抜けは全国的に深刻な被害を出すでしょう。反復練習と学習習慣の確立がたいせつなところなのに。茨城県は「オンライン先進県」と言われますがみなさんオンラインに期待し過ぎです。高校の進学実績が休校の影響を感じさせない、昨年度などはむしろ例年よりもよかったのはなんら不思議ではありません。難関大学を受けてもいいかなという生徒は地方の公立高校であっても高3の春になれば「何をするべきなのか」はわかっているはず。だけどなかなか時間が取れないのが現実。学習も作業的になりがちで自分自身納得がいくまでじっくりと考えられない。皮肉にもコロナ休校のおかげで学力を熟成できたということなのだと思います。でも導入は欠かせないからなあ…。特に地方の子の場合は。高校入学と休校が重なってしまった今度の高3生はどうなんでしょうね。ちょっと心配です。
2022.03.17
コメント(2)
-
2022 卒塾生進学先
今年の卒業生はスタディ・ポートにしてから第5期生になります。ほとんどが中1の初めにポンと集まってくれた生徒です。中1の3学期からマスクが外せなくなりました。学校行事が行われず何度か休校にもなり、いろいろと辛いことも多かったはずです。それでも明るさを失うことなく頑張ることができ素晴らしかったと思います。時間、空間、数学や英語の問題、その他もろもろの有形無形、塾がなにがしかを提供できたのだとしたら嬉しく思います。個性的なメンバーに私も鍛えられました。なお今年の当塾からの水海道一高進学者は揃ってかなりの高学力者です。あとは水海道一高の先生に宜しくお願いしたいところです。(2022 進学先)国立茨城高専 1名境高 2名常総学院 1名竹園高 1名土浦日大(学力特待)1名水海道一高 5名水海道ニ高 1名守谷高 1名(5年累計進学先)水海道一高 24名境高校 6名下妻一高 5名土浦日大 4名常総学院 3名水海道ニ高 2名竹園高 1名古河三高 1名守谷高 1名小山高専 1名茨城高専 1名
2022.03.14
コメント(2)
-
私立高チャンス到来!
水戸一や竹園など倍率が高かった県立上位校では、英語・国語が得意な人、さらにいうと英語・国語・数学が得意な人まで合格から漏れてしまっているようです。また点数の硬直性が強い生徒(問題が難しかろうが易しかろうが430点で動かないというような生徒)は全体点数が低くなった時の粘りは強いのですが、点数が軽くなった今回の問題に対しては不適でした。残念。(理科は良い問題だったと思うのですが、選択式試験のなんたるかを理解していたのが理科の先生だけだったというのがなんとも…。5教科それぞれでもっとはっきりと差がつく問題にしてほしかったですよね。国語!)しかし、私立高校にとってはチャンス到来なのではないでしょうか。大学入試って孤独ではあるのですが一人では戦えません。田舎の子の場合、はじまりは「あいつも京大って言ってんのかあ。俺もやってみっか。」てなところからです。そういう塊が10人、20人とできていくと大きな力になります。例年以上に県立入試に波乱があったと思われる今年は私立高校にも実力者や将来的可能性の大きな人が集まりそうです。最近、高校生も現実的になっているのか希望が小さい。学びのために勉強するのか、社会貢献のために勉強するのか、地位やお金のために勉強するのか、それは人それぞれだと思います。日本で学歴なんぼのもの?という主張も一理あるのですが可能であればできるだけ上位の大学で学んだ方がいい。私の大学の同級生も一部の人だけが偉くなるのだろうなとたかをくくっていたら、一部の人だけが偉くならなかったことに気づかされて呆然としています。茨城で塾を運営する程度なら寒い日も眠い日も毎朝3時半に起きてあれほど勉強することもなかったのですが、おおかたの人にとっては金銭的にも社会的地位にも努力した見返りというものらきちんとあるものだということを思い知らされます。全国に出たときには茨城の何高校なんて誰も知らないですから、今回、意図せずして私立高校に行くことになった人にはぜひ大学入試で頑張ってほしいものだと思います。
2022.03.14
コメント(0)
-
記述に備えたことが実となり
いくらよくできたと言われても「竹園の合格を確信して待てる」なんてことはこれまでなかったなと思うと、ほぼ正確に自己採点が可能な選択式の入試も悪くはないのかもしれません。巷間ささやかれるボーダー付近の場合、自分が何点取れたかはわかっているがゆえに「いったいどこまで大丈夫なんだろうか?」という苦悶の長さはこれまで以上なのでしょうけれども、合格したときの喜びはひとしお、不合格のときの悔しさもいっそうということです。入学試験というのは「合格した人にとっては良い試験」であって「不合格の人にとっては悪い試験」です。とはいえ…。今年は高得点を取れた生徒たちからも「もう少し書きたかった」という声が例外なく聞かれます。ここで以下重要なことを書きます。たしかに「直接的」には書くことについての努力が答案に反映されなかったかもしれませんけれども、どの科目も文章にまとめてみることで、より深く、より正確に理解できているのです。文章にしてみて「あれ、なんか変な文章になっちゃつたな」というときには、みなさん「どこが変なのか」を確認していましたよね。簡単なSVOの文型さえきちんと書くことは意外に難しいものです。語形変化問題なら間違うことのない過去形もついうっかり忘れてバツをもらって以後は間違わなくなる。簡単な単語もいざ書こうとしてスペルがあやふや、そこで単語集で確認する。その膨大な積み重ねはあなたの実になっています。私に「この問題はこういう視点から聞かれてるんだよ」とか「こういう聞かれ方をしたら答えにはこういう言葉を入れた方がいいよ。」とか「なるほど、あなたが書いたような考え方もあるね。」とか言われながら、一つ一つの問題を1年間考え続けたことが、結局のところ形式が変わっても点数に反映されているわけです。いやーそれにしても塾生の水海道一高受験者の得点が軒並み竹園を受けてもいいくらい高くなって驚きましたが、もともと偏差値65〜70の層なので、彼ら・彼女らにとっては順当なところです。 塾生だけでなく最終倍率が1.58倍(10人に6.5人しか受からない)と普通科では水戸一高に次いで高いなか、塾生以外の岩井中学校生の合格率も高いようです。(上位層の学力が例外的に高い学年でもあり。また、なぜか多くが下妻一でなく水海道一を受けている。)全体人数ではつくばエクスプレス沿線の生徒にかなわないと思うのですが、ぜひ成績上位層を形成してほしいです。結局のところボーダーもまあ順当といったところに落ち着いたようです。ただ来年「どうせ記号なんだし。」という勉強をしたときにどんな学力になるのか、さらに茨城県の実験は続きます。出題もバランスですよね。ロザンの宇治原氏が彼のYouTubeチャンネルで今回の茨城県立入試について取り上げています。私、これまで、この人のことを「芸人なのに高学歴しか食うネタがないのかよ」と軽蔑していたのですが、他所のことなのに素早く正確に問題の核心をとらえ、出題方針が一貫することの重要性や文章作成能力の重要性について相方の菅氏と興味深い議論を行なっています。(特に動画の後半部分でかなり重要なことを話しています。)京大法学部らしい頭の良さも伺えます。「あー、こういう人が京大法学部に行くんだ」ということもわかりますので興味のある方は「宇治原 採点ミス」で検索してご覧になってみてください。タイトルとは異なり採点ミス問題に関してというよりも、今年の茨城県の入試問題について「学力を測るとはなんなのか」についての議論になっています。私の意見も宇治原氏とほぼ同じです。それにしても、北関東の一県に過ぎない茨城県立入試、来年度も注目を集めることと思われます。「現在完了進行形」的に大きな問題になってきたものです。
2022.03.14
コメント(0)
-
萎縮せずに良い問題を望みます。
日付が変わって3月13日になりました。昨日は何も書かなかったにもかかわらずアクセス数が激増しておりました。おそらく新聞やネットで話題になっている作問ミス(※)に関して私が何を書くか興味を持たれているのかと推察します。うーん難しいですね。昨年の採点ミス発生からの一連の流れは日本社会の縮図のような気がしてなりません。ミスがあまりにも厳しく糾弾され、その結果、とにかく失敗を避けることが第一の目標となり、創発性も士気も失われ、高品質のものを生み出せなくなる。テレビカメラの前で深々と頭を下げる県教委幹部の姿も痛々しいのですが今回の件できつく叱責されるであろう現場を思うといたたまれません。来年度の出題委員が萎縮、硬直しないことを望みます。今回の問題が現場の高校の先生の指摘(大問1の(1)にしては誤答が多過ぎないかという珍妙なものであるにせよ)により明らかになったのはよかったと思います。来年度の社会や理科の問題から地図やグラフ、実験図がいっさいなくなり、全て一問一答式の問題になることばかりは避けてほしいです。問1.茨城県の県庁所在地はどこですか。次の4つのうちから選びなさい。ア、つくば市、イ茨城町、ウ、水戸市、エ、土浦市この連続で50問とか。今年の「文章どころか語句の記述も避ける」という受験生の方を全く見ていない守備徹底の態勢からすると冗談とも思えません。地理の出題ミスという細部にとらわれず5教科500点全体をよく振り返り生徒の学力が反映される良問が提供されることを期待します。※地理の出題について。「点の位置がブエノスアイレスにしては下(南)過ぎないか?」と気づいた生徒は少なくないかと思います。ただ問題文が「各国の首都」と限定しているわけではないのでブエノスアイレスでなくてもそれ自体は大丈夫なんですね。ブエノスアイレスの南の中都市バイアブランカならほぼ同じ気候なのでなんとか抗弁できるところなのですが、どう見てもサンマティアス湾の左側(西側)なので全く気候が異なります。というかこの点を打ったあたりは世界地理の問題として出せる都市がないうえに気候帯が入り組んでいて難しいですね。福島県会津と福島県磐城では気候が全く異なりますが、両都市を入試問題の世界地図に正確に打点するのはほぼ無理なような気がします。なお自分の都合を第一に考えるのは塾講師も同様でして、この問題で(たまたま当たったというにせよ)正解した人にとって騒ぎ立ては全く不要です。特に1点を争うというような深刻な場合、なおさらそうなります。自塾の生徒が全員模範解答と異なる場合を除けば何も言えません。
2022.03.13
コメント(0)
-

塾より教科書!
高校入試で1問も間違わなかった(ただし満点ではなかった)という話をすると「盛ってる!」と言われたものですが、今年の入試では生徒たちもその可能性があることを感じることができたでしょう。塾生に電話で話を聴いたところ、水海道一高受験者の中にも「水戸一高上位合格ペース」で午前中を終えられた人が少なくなかったようです。(実際の水戸一高受験者には午前中を300点満点またはそれに近い点数で折り返せた人も多いはず。)数学の各大問の(3)の健闘に驚きました。多少は役に立てたかなとホッとしました。理科は教科書学習のたいせつさを再認識させられました。学校ではプリント学習やグループ学習が授業の主流となっているようです。定期テストも業者ワークの繰り返しが求められます。その結果として教科書そのものは疎かになりがちです。今回の入試理科問題は中学校に対する警鐘でしょう。もちろん塾に対しても同じです。音の伝わり方、音の反射。ここ!大日本図書教科書中1理科。164ページ。このページには「鼓膜」が載っていますので、さらに感覚器官へつなげて物理・生物の融合問題にしてもおもしろかったかなと思います。他の問題も痛いところを…。文句のつけようがありません。理科だけは私のような性格の人が作ってしまった感じです。これまで教科書が蔑ろにされてきました。塾に行くよりも、学校のワークを繰り返すよりも、まず教科書を読み込むことがたいせつです。特に社会と理科はそう思います。最後に今年の全体的な難しさについていうと学校の実力テスト並みかなと感じました。なぜか点数構成は事前の予想通りにならないのは例年通りです。
2022.03.09
コメント(0)
-
理数系というよりは理科の試験
今日何人かの生徒や保護者の方と話をさせてもらいました。数学の大問3の(3)や大問6の(3)ができたとの報告は嬉しいかぎり。数学も点数も伸ばせる科目だったようです。(できた人は私のおかげでなくテキストのおかげ。テキストを処方したのは私ですけれど。)教え方の切れ味が鋭いのが外科的講師だとすれば自分は内科的講師です。薬と言ったら変なのですが、材料を選んで処方期間や処方回数を考えながらしつこくじわじわと各自に力をつけてもらう。そんなイメージです。今回、英国も易しかったといっても両方とも高得点で乗り切れる人は勉強の賜物。(書いた練習もいっけん役に立たなかったように思われますが実はそんなことは全くありません。)問ごとに1人1人を見て回るのは骨の折れる作業でしたが「こういう書き方はどうなんですか?」ときかれて「それはこちらの視点から質問しているんだからこう書いた方がいいんじゃないの。」とか「これが抜けてたら点もらえないよ。」ということの膨大な積み上げは文章を把握する力や考えるクセとなってあなたの地となり肉となっているはずです。テストでは1教科ごどに気持ちの区切りをつけるようにはしつこく言ったけれど、とはいえ、午前中をいい気分で終えられるに越したことはありません。試験順が理科、社会、数学、英語、国語とかでなくてほんとによかった。理科は完全に私の的が外れました。本当に申し訳ありませんでした。1年間、全国の入試問題に可能なかぎり目を配り、直近の近県入試をやって臨んでも掠らなかったというのが正直な実感です。恥ずかしながら大問は天体(太陽、月、正座)、人のカラダ(消化酵素、血液循環、器官)、ダニエル電池を予想していました。物理は1年生範囲と思いましたが音があのような問題で問われるとは思いもしませんでした。小問の細かなところでも意表をつかれました。今回は文系不利、理系有利などと言われていますが、理系というよりは「理科」の試験だったと思います。発表まで眠れない日が続きます。
2022.03.08
コメント(0)
-
すべてはあそこから…
昨年の12月初旬に今年度の茨城県立入試に関してNHKの取材を受けました。放送されたのは一部ですが記者の人と雑談を含めて1時間ほどあれやこれや議論しました。その際、「不合格答案の送付」についてどう思うか問われ、「絶対に反対です。」と答えました。全国に波及したら茨城県を起点にとんでもない騒動になってしまいますよとも。全ては昨年4月に第三者委員会が「不合格者全員の答案の開示・送付」を提案し、県教委がそれをありがたく頂戴したことから始まっています。記述問題に関しては「なぜ12点中8点ではなく6点なのか?」、「この問題はこういう見方もできるのではないか?」という抗議を受けつける必要は全くないと思います。それは学校ごとの裁量でかまわない、というよりも学校ごとの裁量にすべきです。(千葉県は予めそのことを明らかにしています。)完全な客観性を求めたら東大や京大の試験までマークシートにしなければなりませんし、オリンピックの採点競技は成り立ちません。解決するのは、あきらかな誤採点と点数集計のミスだけでよかったのではないかと思います。採点ミスはその多くが物理的に採点不可能な記述問題を作ってしまったことに起因しており、その修正に留めることで十分だったのではないでしょうか。公立中等の作問も県立高校入試の影響を受けたようですが公立中等なんてそれこそ「学力検査」ではなく「適性検査」なのですから、「発想がおもしろい」とか「文章が上手で意図が伝わりやすい」とか独自の基準で生徒を取ってもいっこうにかまわないような気がします。公立中学校の「学力検査」は法律で禁止されているわけですから。長いこと県立高校入試の問題を眺めてきて、今年の作問から直感的に感じるのは「脱力」と「脅え」です。塾講師にはけっして作ることのできない入試問題独特の「気合い」や「高揚感」が感じられません。各高校の現場で生じるであろう問題、県教委と各高校の幹部が回避したい責任を考えるとこういう作問しかできなくなってしまったのははやむをえないのかもしれません。ミスを起こさないのは厳命とはいえ…。第三者委員会の提言は東京と神奈川を参考になされたらしいですが東京の進学校の入試は国語・英語・数学が自校作成問題ですし、神奈川の進学校は別日を設けて特色試験を乗せますので茨城県にそのまま持ってくるのは適切といえません。茨城県も水戸一高や土浦一高は自校作成問題にするべきだと思ってきましたが不合格答案を返却するのだったら絶対に無理ですよね。水戸一高の立場としては…という見解が部外者にボコボコにされかねないわけですから。水戸一高や土浦一高の合否が共通テストの物理と生物で決まるようなことがあってはならないと思います。「県民の信頼」ってミスをしないことだけじゃないと思うのですよ。0地点に立っていて−(マイナス)にならなければ+(プラス)にならなくてもいいのか。萎縮と息苦しさ。この混乱の2年を経験した中学生って優秀な人ほど茨城県教員にならないような気がします。今年の漢字の書きを削られた国語の作問者が出した読みの3問は自分たちへの痛烈な皮肉だと推測します。(1)「険しい」山道。(けわしい)(2)「凡庸」な性格。(ぼんよう)(3)時の流れを遡る。(さかのぼる)自分たちの置かれた立場→険しい山道。平凡でとりえのない問題しか作れない無力感→凡庸。振り返り見れば良い時代もあった→時の流れを遡る。
2022.03.06
コメント(2)
-
茨城県立入試 2022(5) 来年への影響
入学試験は「学習指針」としての役割も持っています。だから昨年は県教委が自分たちで採点しきれないような無理な問題を作って自爆したにもかかわらず、今年の受験生はそれに対応すべく1年間努力してきたわけです。全問選択式の神奈川県の問題をやってみたところ形式はどうあれ「問題がきちんと作られていれば」学力は点数に正しく反映されるんだなということはわかっていました。けれどもあなたたちが無茶を求めるものだから生徒たちは黙々とそれに合わせようとしてきたのです。コロナの影響で楽しめない日々の中にあっても。県内、みなさん同じだと思います。予告なき急な方針変更のあとの予告なき急な方針変更ってなんなんだ?どこまで生徒を弄べば気が済みますか?今回の入試の出来不出来ということは生徒それぞれ異なるでしょうけれど仮に出来がよかったとしても「割り切れなさ」は全員に残ったのではないかと思います。誤りを改めたというよりは自分たちの保身のために曲げてはいけない志を曲げてしまった。教育者としてそのことを恥じる気持ちはないんでしょうか。矜持。生徒に対して仁義礼智信を欠くというのは採点ミス以上に罪深いことです。さて来年です。今年の入試が「誤った信号」にならないように祈ります。もちろん私は先々のことも考えて英作文も国語の記述も合同や相似の証明も社会や理科の記述もやっていきます。それが全国の趨勢でもあります。というか県教委は全国に先駆けたつもりだったはず。困ったことに学校実力テストというのは「ここまで模すのか」とあきれるほど県立入試を模してきます。結局、新3年生は「全く英作文を書くことなく」、「国語の記述をすることなく」、「漢字の書き取りをすることなく」、「数学の証明記述をすることなく」来年の県立入試に臨むことになりそうです。こういう極端なことにならないためにも各科目少しずつでも「文章を書く」ことを残さなくてはいけなかったと思います。もちろん学力はいくらでもマークシートで試すことはできます。それはそうなんですけれども一昨年、昨年、今年の一連の出題の不可解さについては採点ミス問題とは別に一県民として説明を求めたい気持ちでいっぱいです。そもそも自分たちの採点能力を測れてさえいれば避けられた問題なんですよ、これ。なにかの外部要因で起きているわけではないですからね。もう少し第三者委員会に対しても主張すべきは主張して生徒を守ってもよかったのではないかと思います。市販される県立入試過去問集はだいたい5年分、または6年分収録されますが、過去5年の問題を並べたときの連続性の無さはあまりに醜いものです。土浦一高も水戸一高も都立日比谷や県立浦和、横浜翠嵐といった公立進学校と伍していきたいわけでしょう。今年は英・国が没問になって理・社で決まってしまいそうですし。大学受験に向けて茨城県、それで大丈夫なんでしょうか。昨年も思いましたが入試の統括ディレクターのような人はいないんでしょうか。県教委は巨大組織ですからなかには優秀な人もいるはず。そういう人ってどこかに埋もれて燻っちゃうでしょうか。やれやれ、何をどうしたいんだか、私にはさっぱりわりません。県民のみなさんも同様だと思うのですが、そう言ってしまうのは私の思い上がりなのでしょうか。
2022.03.06
コメント(2)
-
茨城県立入試 2022(4)満点な人たち
今回の県立入試について県教委が総括し、大井川知事に上がるであろう報告を予想します。(採点ミス問題に関して)出題方法の工夫・改良、再発防止策の徹底により著しい改善が見られた。(平均点が大幅に上がるであろう学力検査結果に関して)コロナ禍にもかかわらず、県が主導したオンライン学習の効果もあり、生徒の学力に著しい向上が見られた。きっと有識者のみなさんからもお褒めの言葉が下賜されるでしょう。満点だ。めでたい。めでたすぎる。
2022.03.05
コメント(0)
-
茨城県立入試 2022(3)理科 社会
(理科について)理科は今年から学習内容に加えられた「ダニエル電池&イオン化傾向」が神奈川県、東京都と大問で出題され、千葉県、埼玉県でも小問で出題されていたので、茨城県でも出題されるのではないかと思ったのですが、イオンの「イ」の字もありませんでした。化学分野の大問は昨年に引き続き2年生内容の化学変化からでした。また地学分野の大問は4年連続して1年生の学習内容からでした。出題者は空が嫌いなものと思われます。物理分野の大問は1年生学習内容から「音」でした。生物分野の大問の食物連鎖は3年生内容なのですが、ここはもともと2年生で「動物」を学習したあと教科書に付加的に載っていたところなのでどうも違和感があります。学習学年による出題の偏りはひどいのですが、「点差がつきやすい」という点では理科かなと思います。選択肢の一つ一つについて正誤を判定できないと正解できないため知識の正確性が求められます。「計算が…」という人もいるようですが、この程度はできてほしいところです。(社会について)社会は「はぁ?」というような簡単な問題がいくつもあります。記述が消滅したことと相まって易化の印象を受けますし、平均点は上がるでしょう。しかし、けっこう嫌な感じのところも突かれてきています。大問1、地理の2(1)、今回は定番の択捉島ではなくて国後島の方を聞いてきています。しかも選択肢には「択捉島」が置かれています。「最北端が択捉島」と覚えておけばBはAより南だから択捉ではないな、さすがに淡路島や佐渡島ではありませんから消去法で「国後島」に辿り着けてはいると思うのですが。それから同じく地理の(3)、近畿2府、5県のデータ。和歌山県と三重県の見分けがつきにくいですよね。ここで気づいてほしいのが県庁所在地の選択肢、(ア)大津市、(イ)四日市市、(ウ)津市。たまにこういう洒落で和ましてほしいものです。こちらは簡単で、答えは津市なのですが、左隣の四日市市も三重県です。四日市といえば石油化学コンビナート、だとすると製造品出荷額も多いはず。そこから(エ)が三重県で(ア)が和歌山県だと判断できるかと思います。実際のところはホンダ鈴鹿関連の数値が大きいのだとは思いますが、「試験勘」としてはこういうアタマの働きもホント重要です。それから大問2の歴史。1の(1)。「ムハンマドがイスラム教をおこしたのは何世紀ですか。」と直接的に聞く問題が何年か前にあったのですが、今回はさらに「ムハンマドがイスラム教を起こした頃の日本の様子」の選択肢。これは正解率が低そうです。さらに2の(2)。享保改革と同じ世紀の出来事。答えは「ウ」のフランス革命。フランス革命は寛政の改革と同じ時期なのですが「世紀」で聞かれればどれも18世紀。塾でも特に江戸時代は日本史に世界史を並走させています。(世界の出来事が日本の開国につながっていきます。)大問3、公民。(1)首長は地方議会の解散権限があります。だから「エ」は誤答なのですがアと迷った末にエと書いた人はけっこういそうです。(6)の日本銀行の金融政策もその仕組みをきちんと勉強しているかどうか問われます。大問4、融合。(3)ドイツ帝国成立後の出来事並び替え。これもワイマール憲法どこだっけ?となるとなかなか難しいかもしれません。社会も全体としては易しく高得点が狙えます。また大きく崩れることも考えにくいです。しかし高い得点が必要な高校を受けた人は「どれだけ削らずにすんだか」ということになります。けっこうポロポロやっている人も少なくないはずです。
2022.03.05
コメント(0)
-
茨城県立入試 2022 (2) 国語
今年は長年続いてきた200字作文(10点)と漢字の書き(9点)が消滅しました。記述問題(6点×2問)もどこかへ行ってしまいました。まず作文についてはあまりにもパターン化していたので思い切って削ってよかったと思います。今年は不合格答案が返却されるので「これは10点中なぜ8点でなく7点なんですか?」とか「こういう視点からの書き方もあるじゃないですか?」と抗議されても高校側で受けきれないという事情もあると思います。漢字の書きも生徒それぞれ字のクセが強いので、4人の先生が集まってもマルにするかバツにするか結論を出せない事例が出てくることも容易に想像できます。これまで模試において自分の名前の漢字が出題されて、それを書いてバツになって返ってきたことが2度あります。名前は長い年月の間に独自の書き味になっていますのでそういうことも起こりがちです。漢字の採点は難しい。採点は時間的余裕もありませんから思い切ってカットしたものと思われます。漢字の書きが出ないというのは全国的にみても異例の事態なのですがやむをえません。浮いた得点は説明文と古文に回されました。せっかくなので、選択肢に難問を混ぜてもよかったと思うのですが満点になってしまった人も少なくないと思います。とはいえ全部正解するのはたいへんですが1問あたりの配点も例年に比べると小さいので大きく崩れたということはなかったのではないでしょうか。国語がけっして得意とはいえない人や中堅校を受験した人も意外と得点が伸びたかもしれません。漢字の読みで出題された「凡庸」と「遡る」が少し難しかったかもしれません。まあ1問2点なのでさしたる影響はないでしょう。英語同様に国語が得意な人にとっては差をつけることができない、差を詰められてしまうという点において、たいへん酷な試験になってしまいました。特に書くことが得意な人にとっては残念な出題内容だったと思われます。入学試験全体からみると国語そのものが没問といえるでしょう。都立日比谷はじめ都立の進学校は国語の自校問題を作っているくらいなのに。
2022.03.04
コメント(5)
-
茨城県立入試 2022(1)英語 数学
英語はひどい試験になってしまいました。ひどいというのは記述式が選択式に変わったことではありません。私個人としては、昨年までの「私は」、「私は」、「私は」という勝手な自己主張ばかりの自由英作文はやめるべきだと思っていました。選択式でも英語の読み書きの力を問うことは十分に可能なのですが今回の試験は全くそうなっていません。ひどい質です。英語の得意な人にとっては本当に酷な試験になってしまいました。うっかり勘違いをしなければ(drawnと takenとか)苦手な人でも容易に100点近い点数が取れます。上位者間どころか中位者と上位者の差もつかないように思います。ちょっと難しいとすれば大問3の(2)でしょうか。この文章並べ替えは英語の問題ではなく国語の問題ですね。数学も英語ほどではないにしろ、ひどい試験になってしまいました。塾生は大問6の(3)の紐回し問題をできた人も多かったと思います。(それまでの大問で時間を浪費しなければ。)大問6の(3)もそれほど時間をかけずに解くことは可能です。ただ大問6の(1)円錐の体積(4点)、(2)円錐の表面積(5点)は定期テストではないのだから入試ではどちらか1問、あるいは問題にもう少し工夫が必要に思います。ここで貴重な9点を浪費せずとも。中堅校以上の受験者の多くが(1)と(2)は正解、(3)は上位校受験者の多くも不正解という結果になったと思われます。また大問4も同様に(1)4点、(2)5点は普通の小学生でもできる問題ですが、(3)は上位校受験者でも撃沈してしまった人が少なくないと思われます。ここでも貴重な9点を浪費。大問3、4、6のそれぞれの(3)、そこだけ見ると良問なのですが、全体としての仕上がりが選抜のための試験としてはあまりにも拙劣に感じられます。英語と違ってすごくできる人は抜け出せたものの、それに続く層がやはり中間層に吸収されてしまっているように思われます。残念。長年、県立入試を見てきましたが、茨城県の先生方って作問能力がこんなに低かったかしら?というのを痛感しました。中等教育学校を含め県教委に対する不信感は拭えません。
2022.03.04
コメント(0)
-
首都圏入試を見て思うこと
今日は自由当塾でした。先週行われた埼玉県の社会(全問)と理科の一部(地学、生物)をやってみました。よい仕上がり具合だと思いますので、あとは問題文をよく読んで「何を答えるのか」に注意してください。最後に、入試は出題者と受験者と採点者の三者がいて成り立つものだという話をしました。問題を解くということは出題者と対話することです。またあなたの答案を読んでくれる人がいることをわすれないでください。首都圏入試を見て痛感するのは読解力、思考力、記述力がより強く求められるようになってきていることです。それと「生活の中の○○」です。○○には数学を入れても、物理を入れても、化学を入れても、地理を入れてもかまいません。よく中学生は「社会にでたら学校で習ったことなんか使わねえじゃん。」と文句を言うのですが完全に逆手にとられるようになってきました。また知識問題は少なくなってきてはいるのですが、知識問題を正解するために必要な知識の難易度は上がっているという印象を受けます。「非」知識の方に舵をきったのかというと必ずしもそんなことはありません。今日やってみた埼玉県の社会では。これまでなら、せいぜい「勘合貿易」「明」「倭寇と区別」程度、暗記していればよかったのですが、本日の問題では「勘合はどちらの国がどちらの国に与え、どのような役割を果たしたか書きなさい。」となっています。「勘合貿易」「勘合」という言葉は問題の前提であり、(問)としては聞かれないのですよね。また、これまでなら「廃藩置県」の4文字熟語を知っていれば得点できたところ「中央集権国家を確立するために行われたことを県令という語を用いて書きなさい。」となっています。戦前、現在の県知事にあたる地位は選挙で選ばれたのではなく「官選」だったのですよね。そんなわけで中学生の学力は低下しているにもかかわらず、課せられるもののたいへんさは年々増しています。全国の中学生がどれほど耐えられるか私にはよくわかりませんが標準を上げたということは学びたい生徒には幸せなことに思います。
2022.03.01
コメント(0)
全18件 (18件中 1-18件目)
1