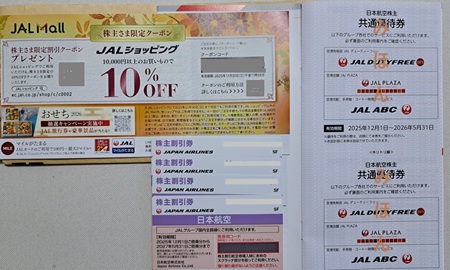2023年01月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
英語 仮定法の思い出
英語においては昨年度からいくつか高校の学習内容が中学に降りてきました。仮定法もその一つです。「もし私が鳥だったらあなたのもとへ飛んで行けるのに。」というやつですね。高校に入ってすぐ担任の先生から1年生のうちに高校英文法のテキスト(当時下妻一高で使っていたチャート式英文法)を読みきってしまうように言われていたので学校の授業とは別にとっつきやすそうな単元からコツコツノートにまとめていっていたのですが、仮定法は最後の最後まで残していました。「すごく難しそう。理解がたいへんそう。」という印象だったのですね。代表例文にあった「If I were a bird , I could fly to you.」というのに恐れ慄いてしまった。なんで 主語が「I」なのにbe動詞が「were」なん?なにこれ?あとにしといた方が良さそうだわ。ということで仮定法の単元は飛ばして他の単元をやってから最後に戻ってきました。それが中学生に来るとはねえ。感慨もひとしお?。中学で学習するのは仮定法過去(現在の事実に反する仮定)だけです。仮定法過去完了(過去の事実に反する仮定)は高校に行ってから学びます。だから、さして難しくありませんし、受動態や現在完了、動名詞、不定詞のように理解できないと読み書きに困るというものでもありません。語形変化や選択肢などのちょこっと問題でちょこっと問われるだけだろうなと思います。(実際、模試や実力テストでもそのような出題です。)原形不定詞を用いる使役動詞などもそうなのですが、なにゆえ高校英語の木々の一部からこれまた何本かの枝だけを中学生に移動させているのか。意図もよく分かりませんし中途半端ぶりがひどい。私にかぎらず現場の英語指導に携わっている人はみな不思議に思っているのではないでしょうか。それにしても人間も50年以上生きていると「仮定法過去完了」満ち満ちてきます。どんな生き方をしてきてもそうなのではないでしょうか。人生はアドベンチャー。何歳になっても進行形のアドベンチャーではありますけど戻れるなら19くらいからもう一度挑んでみたくもあります。(なぜ16、17でないかというとさすがにあんなに毎日早朝から勉強するのは無理だからです。)
2023.01.28
コメント(0)
-
お隣さんの内申点は???
茨城県立高校入試において、これだけは他県の入試制度に比べて優れていると思うのは「内申点」の扱いです。他の県だと通知表の評価が悪ければ悪いだけ入試当日のスタートラインが後ろに下がります。千葉県のように入試500点+内申135点=635点満点(※)というのはまだマシな方で学力検査と内申点の比が1対1でなおかつ内申点も5教科は素のままで技能教科を2倍して計算するとか全く意味不明なことをやっている県もあります。(※)東葛高校のように500点+67.5点=567.5点満点のような例外もあります。茨城県の場合、ご存じの通り偏差値50以上のほとんどの高校ではA群(内申順位が定員以内)であっても学力検査の順位が定員の上位8割に入れないと合格決定とはならず(B群送りとなり)、B群内は8割の人が学力検査の点数順に2割の人が内申点順に合格します。極端な話、制度上は水戸一高や土浦一高をオール1で受けにいっても当日の点数が良ければなんの不利も被らない仕組みになっています。(もちろん、そんな例は現実的にはないでしょう。仮にあったとしたら「特別の事由」に該当して入学を認めるか否か審議の対象になるでしょう。私が大嫌いな成田悠輔氏のように中学校不登校で東大首席のような人もいますから全くありえなくもないかな。)まあ、他の県だったら「この内申では土浦一高レベルは受けられないよな〜」とという人でも学力検査で点数を取って合格しているように思います。とはいえB群のうち2割は内申順に合格なので周りの人がどのくらいの内申点なのかは興味のあるところだと思います。内申点がどの程度なら学力検査の「保険」として機能するのか。これは難しい。その高校の元々の難易度に加えてその年の激戦度合いに大きく左右されそうです。またその年の試験問題の性質にもよるも思います。昨年の入試だと理科で点数を伸ばせた人は学力検査順が上にいったはずで国語の得意な人はかなり不利を受けました。一般的には内申点135点などという人は学力検査の点数も高くA群合格でどんどん抜けていってしまうと思われます。(ほんとにそうか?。けっこう本番では点数取れないもんだぞ、という声もありそうですけどね。)塾で見ていると成績優秀者の中にも「なんか嫌がらせを受けているのではないか?」、「意地悪なんじゃないの?」という感じで音楽や美術で点数を下げている人が少なくない一方で、がっちり5✖️9科目✖️3年間=135という人もけっこういます。中学校によっても評価の辛いところと甘いところがあります。(2013年の推薦入試廃止の理由の一つがこれだったはず。)ちょっと前まで千葉県は生徒の出身中学校別に内申点の加減調整というとんでもなくめんどうくさいことをやっていました。ちなみにうちの近くは比較的オール5が取りやすく思います。(これを住民誘致に使えばいいのに!)135満点だから135取っていたら必ず内申救済で合格されそうに思うのですがどうなんでしょう。土浦一高や水戸一高でも3年間で45、45、45という人は10人に1人もいない。(ように思われます。)3年間で43、43、44=130なんて人は多い。(ようです。)134とか133なら効いてくる場合があるかもしれません。125だと「並み」で、あとはもう115だろうが105だろうが同じ条件のように思います。下妻や水海道はどうなのかなあー。推薦入試があった時代下妻一高は定員42でほぼオール5じゃないと中学校内の審査に通らなかったように記憶しています。ということは受験者のうち40名程度はオール5がいたと推測されます。県西の「村」の子どもの場合、特定の「できる子」に対する評価は高くなりがちですから地域性もあるように思います。水海道一高は定員56でしたが塾生だと3年生の内申が42くらいで受けてけっこう受かっていました。英数国の独自試験もやっていて通知表との合計だったのですが下妻ほどは受験条件が厳しくなかったように思います。下妻一高も水海道一高も内申135や134の生徒の多くは学力検査で抜けていくでしょうから、内申救済点はそれなりに下がってくるような気もしますがB群の2割というのがいったいどこまでなのかは全くわかりません。ただ高校側がきちんと制度を守ると仮定するなら、135や134という生徒は他の生徒よりも余裕をもって受験できるということにはなります。(大昔のことなので真偽不明ですけれども、私が受験した頃の茨城県の制度では内申点が悪ければ悪いだけスタート位置が下げられていました。しかし、入学後に高校のある先生から聞いた話では「そんなめんどくさいことはしていない。入学試験の順番に上から並べて315(当時の定員)で切っておしまい」とのことでした。内申点が低かったため、合格を危惧した中学の担任が志願先変更期間の夜遅く突然家にやって来て大揉めになりましたが、点数順だったのならいったい何の騒ぎだったかとあとから思ったものです。当時の下妻一高って多くのことが他の県立高校と違っていたのでありえなくはない話ですが真偽は不明です。当時は点数開示がなかったので私は何点取れたかとか何位だったのかは知りません。ただ入学後すぐに模試を受けるので「あー、こんなもんなんだなあ。」ということはすぐにわかりました。水海道一高に行った弟は得点だけでなく順位を知っています。塾生の保護者の人でも「入試で何点で何位だった」と言う人がいてまあ昔はいろいろゆるかったもんだということを感じます。
2023.01.21
コメント(0)
-
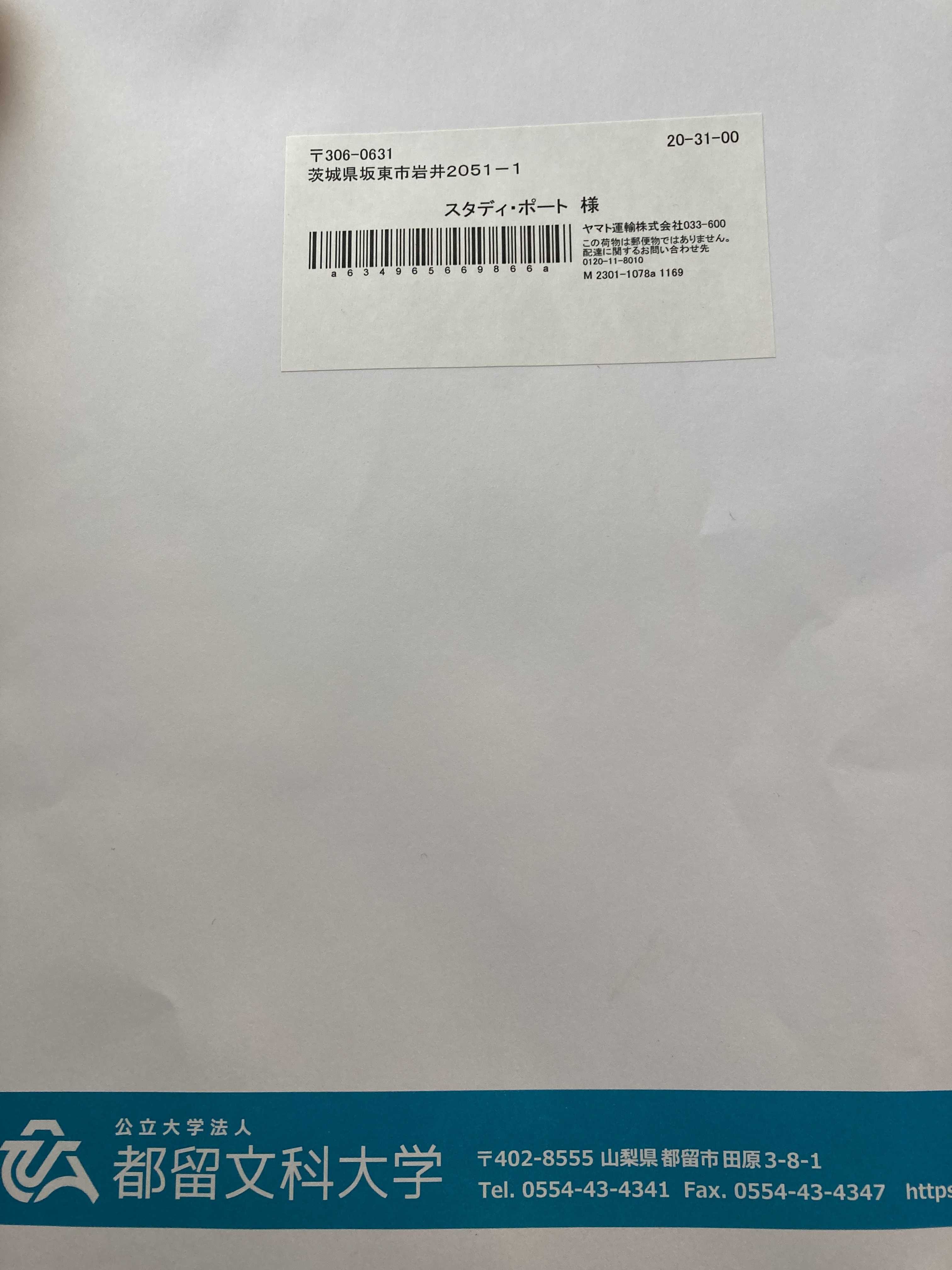
こんなところまで…
1980年代、この近隣の公立大学といえば図書館情報大(現筑波大)、高崎経済大、横浜市立大、それに都留文科大くらいのものでした。郵便ポストの中にその都留文化大からの封筒が。。What ?ということで開封してみたところ、「こんな素晴らしい大学だから学生を送ってください。」というご案内でした。私のところのような県外の小さな塾にまでこういった類いのものが届くとは驚きました。いわんや茨城県立高校においては。しかもなんとも絶妙な時期です。 都留文科大。山梨県の都留です。昔からあります。なるほど受けやすそう。教員志望者が多いと。学生は山梨県外出身者が85%とのこと。今回、案内を送ってきたこととは全く関係はありませんが、ここで大学時代に1年生のときに同じクラスだった友人が教授をしています。彼の磯子の自宅に遊びに行ったり、山下公園で夜を明かしたり、ボッタクリバーに引っ掛かったり、逗子に海水浴に行ったり、よく遊んでいたのですが卒業後は音信がなくなっていたので、偶然、このことを知った時には本当に驚きました。大学で教えていることには全く驚かないのですよ。では何に驚いたかというと「文学部英文学科」の教授で専門は「アメリカ演劇の研究」だということです。だって卒業したのは政治経済学部経済学科で学士号は経済学士、ゼミは「日本経済史」だったんですから。たしか大学受験も日本史選択だったはず。全然畑が違う。はじめは同姓同名かと思ったのですが、履歴が早稲田大学政治経済学部卒になっており、なにより写真で確認したら髪は薄くなっているものの紛れもなく本人でした。どうも早稲田の教育学研究科の大学院に行ってそれからの話のようです。大学時代、本人が読書している姿は全く記憶にないです。芝居や映画にかぶれてる友人はたくさんいましたが、そういうタイプでもありませんでした。ただ、印象に残っていることといえば彼の家が廊下や階段までお父さんまたはお母さんのものと思われる本、本、本で侵食されていたことです。私は家に本が一冊もない環境で育ちましたから、「うわー、こんな家もあるんだ。」と思ったことをよく覚えています。現在は教育以外に大学の運営にも携わっているようです。われわれそういう年齢です。早稲田とは違う大学の付属校からどうしても早稲田に入りたくて一浪して猛勉強、駿台1位の圧倒的な学力をひっさげて早稲田文系の全学部を受験し全部合格。そんな彼が地方の公立大学で「都留もいいとこだよ。こんなに受けやすいから受けに来てね。私大より公立だよ」というのも不思議な感じがします。松山とか大分とか暖かくて温泉のある町で国立大学の先生なんてのもいいかなと思ったのですが大学法人になって以降、「学の独立」どこへやら国の管理がきつく報酬もさほどでないようです。
2023.01.20
コメント(1)
-
2023年
2023年になりました。コロナの前の年末は毎年日本橋へ出かけ利久庵というところで年越し蕎麦を食べていたのですが今回の年越しも家でじっとしていました。正月も元旦に八坂神社に3日に國王神社(平将門)と大生郷天満宮(菅原道真)にお参りしてあとは家で入試問題を解いていました。毎年インフルエンザの予防接種も欠かしませんし私も受験前は医療従事者並みの厳重警戒なわけです。紅白は7、8分ほど観ました。佐野元春も67歳の学年なのかと驚愕し、私もこれまでの六角精児みたいな爺さんになりたいという生活態度を改めて今年は心身ともに若返りを図りたいと誓いました。年明けは3日から授業で土浦日大高校の数学、国語、英語と昨年の試験問題を解いて解説、復習してみました。特に数学はほどよい難しさで県立の準備としても良い問題が並んでいます。(県立のような資料問題はありませんが。)県立対策ばかりやっていると守備範囲というか守備態勢が硬直しがちなので頭の動きの良さ、キレを増すためにも数学は(土浦日大を受験しない人も)土浦日大の問題をやってみるのもいあかもしれません。それにしても今年度も相変わらず年末時点で筑波大22名と筑波大附属土浦日大高校といってもいいくらいの合格実績となっていて驚きです。
2023.01.06
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1