2015年10月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-

なぜ歌うのか、なぜ踊るのか、なぜ演奏するのか
なぜ歌うのか、なぜ踊るのか、なぜ演奏するのか。 太古の人間たちも現代の人間たちも本質は少しも変わってはいない。 この生命を与えてくれた神に対する感謝の気持ちであり、なぜ愛するものたちと死別があるのかこの世界に対する異議申し立てであり。 その本質を忘れてしまった音楽には意味はない。 もちろん神なんているわけがない。われわれは所詮偶然の産物でしかない。それでもなお、何らかの意味があるのだと信じたい。神は幻想であるが幻想こそがわれわれに意味を与えてくれる何かなのだ。 なぜ歌うのか、なぜ踊るのか、なぜ演奏するのか。
2015.10.20
-

Here comes another new day
Echoes in rainエンヤの最新作らしい。映像も詞も素晴らしい。まったく朝にこの音楽を聞いたら夕べに死すとも可なりである。映像もきわめて上品でエクセレントだし、詞が俳句のように極度に研ぎ澄まされた驚くほどシンプルな言葉で、この宇宙と我々の世界を余すところなくすべて表現しきっているように思われる。そして、アレルヤ、意味が分からないんだけどこの言葉がありとあらゆることを表現しているような気がする。こんな音楽に出会えるなんて生きていてよかった。本当に素晴らしい音楽とは創造への意欲を掻き立ててくれるものだ。いつの日にかこれらに負けないものを創りたい。
2015.10.20
-
三つのユーミン幻想 2
経る時 ティールームには僕一人 終了近くになると必ずかかる曲がある。 僕のリクエストだ ときどき僕はわからなくなる 彼女は僕ではないだろうか 僕は彼女ではないだろうか 同じ魂を求めて 永遠に生まれ変わりつづける さまよう魂に 涙が落ちる ティールームには彼女一人 窓の外を見ている 空から経る時が見える そこにはもう誰もいない
2015.10.19
-
映像が幽霊のようにやってくる話
どこかで読んだ記憶があるのだが、村上春樹がねじまき鳥クロニクルを書いていたとき、登場人物が映像として幽霊みたいに自分のもとにやってきてまとわりついた、ということを書いていた。たぶんほかの小説家たちもそういう状態というか、そういう経験はあるのではないかと思うが、そのことを書いてる小説家はほとんどいなかったと思う。かろうじてトルストイが同じことを言っていたような気がする。 これはすごいことだと思う。脳細胞がものすごい活動状態にあるときふとした瞬間にハイパーワールドの扉が開くのではないかと思う。残念ながら僕は文章を書いていてそういう経験はまだない。 昔大学に入ったとき剣道部にはいって合宿でマラソンやらコンパやらでめちゃめちゃ疲れてもうダメかなと思ったときすうっと何かが取れて楽になり大きな声が出るようになり稽古をしているときに相手が何を考えているかまるでテレパシーみたいに手に取るようにわかる状態になったことがあった。あえて言えばそれが一番近い経験かもしれない。本当に相手の考えていることがテレパシーのように伝わってきたのだ。 よく宇宙飛行士が何日が宇宙で暮らしているうちに相手が考えていることが手に取るようにわかる状態になったという話をしているのを読んだことがあるが、僕の経験から言ってもそれは本当のことなのだと思う。 たぶん酸素の濃度が通常より多い状態でその中に何日かいると脳細胞が活性化してそういう状態になるのではないかと思われる。 小説の中の登場人物たちが映像になって幽霊のようにやってきてまとわりつくとは、テレパシーの次元をはるかに超えている。まとわりついていったい作者に何を訴えたのだろう。 小説家はそんな状態になれたら本物なのではないかと思う。
2015.10.18
-
三つのユーミン幻想 1
永い時の涯てへ Glorious 何に身を隠したとしてもAll my previous きみに会うと信じていた 彼女のメッセージを胸に折りたたんで僕は僕の人生を生きている。 欠落した距離と時間をやさしく物語が包んでくれる。 今読んでいる本が「はじめての超ひも理論」河合光著。超ひも理論については何冊か読んだけど、この本が一番丁寧でわかりやすい。数式は一つも出てこないが、その根本にある概念をわかりやすく説明しようとしている。難解な数式をちらつかせて一般の読者を煙に巻く専門家が多い中でこの本の著者はとても好感が持てるし誠実な感じがする。そのせいか、なんだか超ひも理論って期待できそうな気がする。サイクリック宇宙論という最新の考えもおもしろい。それによると我々は50回目くらいの宇宙に住んでいるらしい。 マヤの人たちは天体を観測しているうちに、王国だの社会だのばからしくなって密林の彼方へ姿を消したのではないだろうか。 あるいは乗ってきた船にのってふるさとの星に帰って行ったのかもしれない。 そして、何百年か後のある日突然、僕らはこの星に取り残されたたった二人の孤児だったことに気づくのだ。オーロラの舞う平原手に手を取り走り出せばふるさとの遠い星まですぐ
2015.10.18
-
Family Affair
家族の事はあまり触れたくないものだ。家族こそが我々の精神に関するあらゆる問題の原因なのではないだろうかという気さえする。 工場で働いていたとき、僕はどちらかと言えば楽な仕事だったので、昔のことを際限なく思い出しては悲しい気持ちになっていた。美人の女性とつきあっていて結婚を望めば結婚もできたはずなのになぜかふみきれなかった。その根本にあった問題は僕が子供がほしくなかったということだった。なぜほしくないのか理由を考えたこともなかったしずっとわからないままでここまできた。 しかし現在実家に帰ってきて身内と一緒に暮らしているのだが、弟も僕と同じ深刻な精神の問題を抱えて苦しんでいた。僕はあまり話したくなかったのだが、弟はその問題をどうしても突き詰めて考えねばならない性分だった。 この前朝方近くまで酒を飲みながら話し合っていてどうも兄弟で同じような問題を抱えていることがわかった。結局僕が子供がほしくないということもつきつめると幼少期の家族の問題であり母に十分かまってもらえなかったということが原因なのかもしれない。僕と弟は幼少期曾祖母に育てられた。 僕はほとんど周りの人に影響を受けずに白紙のまま育ち後に宮沢賢治や吉本隆明の影響を受けたのでむしろよかったと思っているけど、子供がほしくないということは、いくら吉本さんに普通に生きるのが一番価値があるんだよと言われても、どうしようもなかった。 原因がわかったからと言ってもどうにもなるものでもない。家族や母を責める気持ちはさらさらないしむしろ育ててくれたことに感謝している。もともと家族というものは問題だらけなものだし、どこの家族も多かれ少なかれそうだということもわかっている。普通は大人になる段階でいつの間にかそういう問題は克服できるものなのだ。また、そうであるべきなのだ。 僕は文学を信奉しているので滅亡の民なのだと思っている。それでいいしそれ以上のことは考えたくない。しかし何も信奉するものがない弟は未だににっちもさっちもいかず苦しんでいる。残念ながらこれは人が助けてあげられるような問題ではない。 家族の問題は誰にとってもあまり触れたくない事柄だ。その根本的な原因は自分が思っている観念的な偉大さと家族から見た存在の卑小さの格差がありすぎるからだ。 いくら僕が人類がこれまで誰一人として知らなかった言語学上のある知識を発見した人間であったとしても弟にとっては兄らしいことを何一つしなかったしょうもない兄でしかないし母にとっては何一つ親孝行もしたことがないどうしようもない馬鹿息子でしかないのだ。 家族の問題は鬼門である。その意味で漱石は偉大だった。たとえ奥さんにしてみれば粗大ゴミみたいな亭主にすぎなかったとしても。
2015.10.15
-
エルム街の書店にて
エルム街のショッピングセンターで買い物をして帰ろうとしたら雨が降ってきたので、雨が止むまでショッピングセンター内の本屋で時間をつぶした。久しぶりに本屋に来てみると面白そうな本がたくさんあった。買おうかなと思って値段をみると1800円もする。面白そうだけど1800円の価値があるかなと考えて結局買わなかった。ここ何十年か日本はずっとデフレが続いているがなぜか本の値段は下がっていない。それどころか上がっているような気がする。雨もまだやまないので立ち読みで我慢することにした。 吉本さんの本がいくつか並んであった。いずれも目新しい本だ。亡くなった後も本が続々と出版されるとは、せっかく全部読んだつもりでいたのに困ったことだ。しかも新しい発見があった。それは村上春樹について詩を書いたことのある人じゃないかと言っていたことだった。僕が感じていたことと同じだったので驚いた。僕は昔、ねじまき鳥クロニクルの目次を見て、それらを並べるとまるで一片の詩のようだと書いたことがある。吉本さんの感性の鋭さそして正確さにあらためて驚いた。昔の左翼が書いたようないかめしく難解な文学はもはや嘘っぽくなってしまっているのだ。昔あった文学というものの価値が下降しつつある中でむしろ軽さの中にどう深みを見出せるかが文学の中心的なテーマになっている。そういう意味で現在の文学がどこにあるのか両村上氏を読めばわかるといった吉本さんの主張は全く正確だと思う。 感性を論理化する際に変なバイアスで捻じ曲げないでストレートにあるいは素直に論理に反映させることが肝要だ。ただバイアスがかかっている人は感性までゆがめてしまっているのかもしれない。正しく感じることそしてそれをストレートに言語化することが大切なことなのだ。 ストレートにとは簡単に思われるかもしれないが簡単ではない。一般の人々は多かれ少なかれ偏見や先入観、嫉妬や怨念によって観念の時空はゆがめられているものなのだ。孤独の中で自らの観念の誤謬を訂正したことがある人でないと本当は難しいことなのだ。 村上春樹をくそみそにけなしている人たちはいったいどれだけ嫉妬や怨念で感性をゆがめてしまっているんだろうと思わざるを得ない。そうでなければ文学などは全く理解不能な縁のない人たちだろうと思う。はたして蓮見重彦はどっちだろうか。 立ち読みにつかれて本屋をでると雨は止んでいた。大急ぎで家に帰った。
2015.10.12
-
今日の雑感
一通り表現したかったものを吐き出してしまったらもう書くことが何もなくなってしまった。今回僕がめざしたものは音楽と文学のクロスオーバーした表現であった。音楽の持つ深い象徴性や高度な抽象性にシンクロする文章を書いてみたかった。そしてできれば音楽の転調と同じ効果を文章で実現できないだろうかと考えていた。どの程度実現できたかは心もとないが感触はつかめたような気がしている。 表現されたものに我々の魂が乗り移るためにはそこにゲシュタルトが存在しなければならない。ゲシュタルトとは魂が宿るための形、構成、いわば家のようなものである。それは魂の遠近法、精神の幾何学によって作られている。 ゲシュタルトが存在しない表現には我々の魂は乗り移ることができない。そういう表現は我々はつまらないと感じたり空虚さにいたたまれなくなる。 ゲシュタルトの表出水準に至るためにはやはりカポーティが言ったように空の高みに登らなきゃならない。登ってしまえば後は楽だけど登る前がつらいのだ。 現実の世界で順応しそこで満足している人は表現する必要がない。ある意味では現実の世界で失ったものをあきらめた代償として表現が存在するのだといってよい。それは普通に生きることをあきらめて永遠に生きたいと願うことでもある。 文学は文学である。なぜわざわざ純をつけなきゃいけないのか。人々のレッテル思考には不快感を覚える。 純文学という言葉に嫌悪感を持たないような言葉に鈍感な人間が文学をやってるつもりになっているのはたちの悪いジョークのように思われる。
2015.10.11
-

最深度音楽探訪の旅 1
サティ:ジムノペディ第1番メロディとは発明であろうか。サティ:ジムノペディ第1番は人類へのとても大きな贈り物だったような気がする。サティがいなければこのメロディを我々は今日に至るまで知らなかったにちがいない。・・・リスト:ため息僕を捨てていった人が昔よく弾いていた曲だった。曲名が「ため息」であることを知ったのは最近だ。ため息をつきながらこの曲を聴いている。ドビュッシー:亜麻色の髪の乙女初恋は小学1年のときだったが、セカンドラブが本当の初恋だと思っている。相思相愛だと思っていたが、途中僕が別の人を好きになってしまい、それがなぜかばれて、彼女は僕を絶対許してくれなかった。その彼女が亜麻色の髪をしていた。初恋を失ってしまった苦さとともによみがえる彼女の面影をいつまでもこの曲の中に探し続けているシューマン:予言の鳥<森の情景より>予言する鳥は何を予言しているのだろう。それを知りたくてときどき聴いているが、さっぱりわからない。それでもなお、予言する鳥は何かを予言している気がする。バッハ:「目覚めよ、と呼ぶ声あり」確かにヨーロッパ人たちは目覚めた。アジアの人々はまだ目覚めていない。「目覚めよ、我々の共同幻想に」と叫ぶ声あり。 ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ僕もこの音楽を聴くと何か小説を書きたくなる。村上春樹のように。でもまだ書いていない。
2015.10.10
-

最終日の観光、帰郷、そしてさよなら
16日、本当は午前中で終わり帰る準備をしたいと思っていたのだが、そう思う人がほかにも何人かいて班長さんは最後ぐらいちゃんと終わりまでまっとうすればいいのにと憤慨していた。それで僕も休むに休まれなくなってしまった。ミス工場の姿はその日朝から見えなかった。今日まで仕事だと言っていたのに変だなと思っていたら、昼食を終えて寮の部屋に戻る途中、ばったり彼女とあってしまった。彼女は彼氏とおそろいの服で帰るところだった。 それにしてもなぜ彼女にこんなところでばったり出会うんだろう。できれば僕が知らないうちに帰ってくれたらよかったのに、まるで僕が昼食を終えて寮に戻る時間を見計らったようにジャストタイムで出会ってしまった。ひょっとして僕に彼氏を見せつけたいんだろうか。 まさか話しかけるわけにもいかず、そのまますれ違ってさよならとつぶやいた。 16日はほとんど掃除ばかりで僕のところは早く終わったので午後4時で仕事を終了した。僕は夏服しか持ってきていなかったので明日観光に行くとき着る服とズボンを買いに近くのスーパーストアに出かけた。そして寮に戻ってきたら、お風呂に出かけようとしている彼女の後姿を見かけた。長くて縮れた赤い髪は間違いなく彼女に違いなかった。でも彼氏と帰ったはずなのになぜここにいるのか不思議だった。それに彼女は女子寮に入っていたとは全く知らなかった。朝人材派遣会社のマイクロバスに乗ってどこかの寮からここに通っていると思っていた。それは朝7時40分ごろマイクロバスとともに彼女を見かけたことがあるからだった。ひょっとして髪の赤い別の人だったのかなと思って帰りの準備に取り掛かった。 17日、朝食を7時ごろ終えて食堂を出たら、またしても彼女に出会った。風呂道具を持って朝風呂にいくところだった。それにしても昨日といい今日といい、なぜ彼女とばったり出会うのか不思議だった。まさか行き会うタイミングを見計らっていたわけでもあるまいし、偶然が重なっただけだろうと思いなおして、それでも話しかけるべきなんだろうかと考えながら結局話しかけずにそのまますれ違った。いずれにしても今日が最終日で僕らは朝8時半にバスで出発の予定だった。電車で帰る人はその前にもう工場を後にしていた。僕の部屋もがらんとして何とも言えない寂しさが漂っていた。8時15分頃にはバスが来たので僕たちはバスに乗り込んで出発時間を待った。一緒に働いた社員の人たちや友達になった人材派遣で働きに来ていたフィリピン系の若い男のダンサーが見送りに来ていた。 出発の時間を過ぎたがまだ二人足りないということで僕たちは待たされた。僕たちは全員そろっていたので宮古班の誰かが遅れているようだった。一体何してんだろうと思っていたらやっとバスに乗り込んできた二人をみて驚いた。ミス工場と彼氏だった。そして彼女らは僕のひとつ前の席に座った。 そういうわけで結局最後の最後まで彼女らと観光をつきあいフェリーまで一緒に乗る羽目になった。縁があったのかなかったのかよくわからない。僕はなるべく見ないようにして仲間たちと観光を楽しんでいたけど、時々彼女と目が合ったりした。それにどういうわけか彼氏とも目が合った。なぜか僕を見ているような気がした。 フェリーは八戸港につくはずだったがチリ沖の地震のせいで青森港に朝5時半ごろついた。車の下船で1時間近くまたされやっと6時半ころ船を下りた。僕たちはターミナルゆきのバスに乗った。宮古ゆきのバスもすでに後ろに止まっていた。僕が乗っているバスを通り過ぎるとき彼女はちらりと僕を見た。
2015.10.04
-

ティファニーで昼食を
工場の中で働いているとまるでアンダーグランドの世界に迷い込んでいるような気がした。松橋さんは地獄の1丁目だと言っていた。様々な人生を抱えた男女が集まっていた。本当は暗くてつらい労働の日々になるはずだった。それがミス工場がここにいてくれたおかげでぱあっと花が咲いたように色彩をおびた日々となった。本当は休憩室で彼女を見ているだけで十分幸せな気分だったのだ。どうして話しかけようなんて思ったのだろうか。実は僕は混乱していた。はじめて出会ったときから彼女にY.S.さんの幻を見ていた。 あるとき休憩室に彼女はちょっと離れたところに座っていて、僕は同郷の班長さんと一緒に座って何か話していた。そのとき班長さんが僕に「おばけいる、おばけ」と言った。僕は一瞬何をいっているのかわからなくて聞こうと思ったけれど、たぶん彼女のことを言っているんじゃないかという気がして聞かずにおいた。津軽の人はこの世とあの世の中間に敏感な感覚を持っている。たぶん彼女にこの世ならぬ何かを感じていたのではないか。そのことがあってますますY.S.さんがここにきているという印象を強めることになった。 またあるときは、彼女は僕の隣に座っていて携帯を落としたふりをして拾おうとしてそのとき僕にちょっと触れたことがあった。なぜ僕に触れようとしたのだろう。本当に偶然だったのだろうか。 そういうことが重なって僕はいつの間にかY.S.さんが彼女の無意識を操って僕に会いに来ていると解釈するようになっていた。 しかし、実際彼女と言葉を交わしたときわかったことがあった。それは彼女はY.S.さんじゃなかったんだということだった。僕の全くしらない人だった。当たり前と言えば当たり前のことだけど、僕は再び困惑し混乱した。 Y.S.さんは僕に会いに来たはずなのに僕が彼女に話かけたときにはもうどこにもいなかったのだ。どうして?という謎をのこしたまま僕は再びこの世界に一人取り残されてしまった。 僕と松橋さんと中野さんの三人で一番後ろの席を確保して昼食を食べるようになっていた。彼女は僕たちのすぐ近くに座って食べていた。 それから僕は松橋さんたちと離れて一人で昼食を食べるようにした。もちろん向かいの席は空いている場所を選んだ。僕の向かいの空いてる席には同部屋の若い男が何も知らずに「やぁ、○○さん。」といって座ったり、しらないおばさんが座ったりした。 そして何日かした後、思った通りに彼女が座ってくれた。 いつ帰るのと聞いたら「16日まで仕事をして17日に彼氏と帰るの」と小さい声で答えた。彼女は隣に彼氏の席をジュースを置いて確保していた。「そうなんだ。」といって僕は席を後にした。 その日を境に僕は彼女を目でさがすのをやめた。いつの間にか夏は終わり色彩はすっかりあせて見えた。もう帰る日が迫っていた。
2015.10.02
-

僕には有り余る ロマンスが有り余る
休憩室で何回か一緒に居合わせた数日後、たまたま廊下で彼女とすれ違ったことがあった。彼女は僕を認識して目であいさつをするような動作をした。僕はまったく予想していなかったのでとっさに対応できずそのまま通り過ぎて「しまった。」と思った。こういう場合女性は自尊心を傷つけられて殻に閉じこもってしまうものだからだ。せっかく心を開いてくれようとしたのにそのチャンスをつぶしてしまった。大学時代同じようなことがあった。コンパでお酒を飲んで同級生の女性たちと盛り上がった次の日、キャンパスを歩いていたら、つかつかと女性が寄ってきて、あいさつしたのに無視するなんてひどいわと僕に食って掛かってきたのだ。僕は眼鏡をかけていなかったので本当にまったく気づいていなかったのだが、そのことを言ってお詫びをしたのだが、彼女は「もう、いい。」といってぷいと行ってしまったのである。それっきり彼女とは一度も話すこともなく大学を卒業してしまった。北海道の砂川出身の人だった。そういう場合なんて言ったらよかったのだろう。いまだにどう対応したらよかったのか僕にはわからない。案の定、彼女もそれ以降廊下ですれ違っても何の反応もしなくなってしまった。僕が悪いのだからひたすら耐えるしかない。あのときちゃんと反応して目で合図するなりしていれば本当はスムーズに話しかけられたはずだったのだ。ちょっと人見知りで突っ張ってしまったのでとても困った。結局松橋さんの力を借りるまで回復できなかった。 さて、話しかけてみようかななどと彼女にも聞こえるように言ってしまった手前、約束通り話しかけなければならなくなった。とはいえ話しかけるには隣か向かい合って座っているかでないと話しかけられない。なかなかそういうチャンスはなかったのだが、数日後彼女は冷蔵庫の横の椅子に腰かけて冷蔵庫の横に背をくっつけて休んでいた。ちょうど僕は冷蔵庫に飲み物を入れていたのでさりげなく冷蔵庫のそばに座って冷蔵庫を開けて飲み物を取り出して飲んだ。彼女はすぐ横にいた。今話しかけなきゃと思ったのだが、いざとなったら何を話しかけていいものかさっぱり思いつかなかった。でもとりあえず約束は果たさなきゃと思って話しかけた。「何時まで働いているの」と尋ねた。彼女は突然話しかけられてちょっとまごついた感じて「夜11時まで」と答えてもう一度丁寧に「朝の8時から11時まで」と答えてくれた。そこでもう少し話そうと思ったらそこに松橋さんが割り込んできて僕に話しかけたのでそこで彼女との会話は終わってしまった。まったく応援しているのか妨害しているのかわからない人である。でもとりあえずどういう形にせよ、話しかけるという約束はなんとか達成できた。彼女は近くの若い女の子たちと何か楽しそうにひそひそ話していた。
2015.10.01
-

松橋さんのこと
今回の仕事で松橋さんというご老人に仲良くしていただいた。一言お礼を申し上げておきたい。同郷の男たちはどの人もキャラが際立っていて興味深い人たちばかりだったが、その中でも強烈なキャラとして目立っていたのが松橋さんだった。仕事の初日にアイスクリームを20個ばかり買ってきて女の人たちに配っていたという話が仲間内で話題になっていた。まったく人見知りすることのない人で、全然知らない人でも昔からの友人のように人懐こく話しかけてくる人だった。僕も一瞬にして昔からの知り合いのような感覚で親しくなった。この人は男に対してもそうなのだが、女に対しても全く変わらない。知らない女性でも普通に躊躇することもなく話しかけていた。中でも全然言葉の通じないペルー人の女性たちにまで平然と話しかけていたのには、こちらもはずかしいやらあきれてしまうやらだった。しかし最初は全然相手にされていなかったのに最後近くになるとペルー人の女性たちも僕たちを見ると身振りや目であいさつを交わしてくれるようになっていた。松橋さんと一緒にいたおかげで僕も女性に話しかけやすい環境の中にいた。実はミス工場としょっちゅう休憩室で顔を合わせていたのだが、周りはオジサンおばさんばかりで何となく若い子に話しかけるのは気が引ける雰囲気だったし、管理者のT女子、僕たちは彼女をデビ婦人と呼んでいたが、その人が、ここのおとこたちが若い子に手を出させないように監視しているみたいに目を光らせていた。 松橋さんは夜食として会社からいただいたパンと牛乳を毎日デビ婦人にプレゼントしていた。デビ婦人は最初松橋さんに会ったとき愛嬌のある顔だわねと言っていた。まったくその通りで若かった頃はとてもハンサムボーイだったに違いない。どの女性に対しても分け隔てなく優しいし、一生懸命尽くす人だった。デビ婦人も最初はおちゃらけた軽い人だと思って全然相手にしていなかったのだが、毎日プレゼントをもらっておまけに愛してますと言われ続けているうちに、ほろっと来るようになっていた。 ある日そのことを松橋さんに話していると、突然真面目な顔になって、「女って怖いものだよ」と僕に言った。いつ話したのかは知らないけど、なんでもデビ婦人からセックスのお誘いを受けたそうだ。もうおばあさんに近い年なのにちょっと色気があってまだ現役らしいのだ。松橋さんは、ばあさんとなんかできるかよと平然と言い捨てた。毎日プレゼントして愛してますと言っていたのにである。まったく津軽人の典型を見ているような気がした。お茶らけている一方で、実は極めて冷めた目で物事を見ている人格が存在するのだ。たぶん太宰も津軽人のこういう気質を受け継いでいたんだろうなと思った。 そんなこんなでなかなかミス工場に話しかけられずにいたのだが、ある日休憩室に彼女が入ってきたときに、僕と松橋さんは一緒に並んで休憩していたのだが、そのとき松橋さんが彼女にも聞こえるような声で「おっ、きれいな人だな。おめばにらんでいたよ。気あるんでね、話しかけてみれば。おめもいい男だもな。」と僕に言った。それで僕も「えー、ほんと。じゃあ、はなしかけてみるかな。」と冗談っぽく松橋さんに返答した。たぶん彼女に聞こえていたかもしれない。その場にいた若い女の子たちが笑いながらひそひそと話し合っていた。 初日から大酒のみで落ち着きがなく誰かれなく話しかけるので仲間内からはうるさい人と敬遠されていたが、僕は松橋さんが大好きだった。最終日僕たちはバスで観光して帰る予定だったが、松橋さんは室蘭のいとこを訪ねるということで電車で帰る予定だった。僕は一緒にバスで観光しようと何度も言ったのだが、めったに会えないからということでやはり別々に帰ることになった。 みんなを明るくして元気にしてくれた松橋さんにもう一度会いたい。彼がいたおかげで僕たちはとてもハッピイだった。僕も何とかミス工場に話しかけることができたわけだし。
2015.10.01
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
-

- 福山雅治について
- 福山雅治PayPayドームライブ参戦
- (2025-09-29 12:53:35)
-
-
-
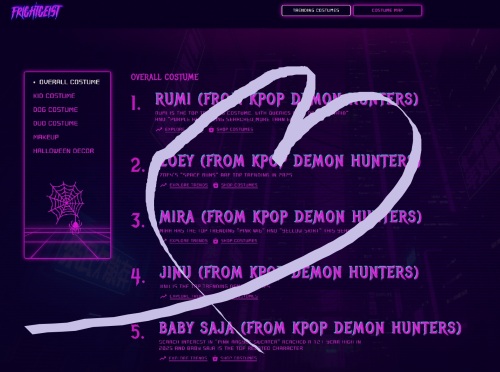
- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 영원히 깨질 수 없는
- (2025-11-11 06:13:39)
-
-
-

- X JAPAN!我ら運命共同体!
- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…
- (2024-07-25 18:16:12)
-







